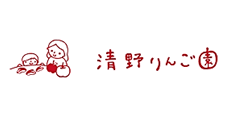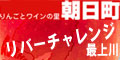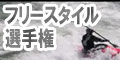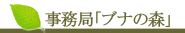少しずつだが、歴史はより自由で、より公平で、より開かれた社会に向かって進んでいる。私はそう信じている。ただ、その流れは一直線には進まない。しばしば揺り戻しが起き、時には逆流が生じる。アメリカのトランプ大統領の振る舞いは、歴史が激しい逆流の時代に入ったことを示しており、それは新しい戦争の時代の到来を告げるものになるかもしれない。

トランプ政権は産油国のベネズエラに軍事侵攻し、マドゥーロ大統領を拉致してアメリカに連行した。ニューヨークの連邦地裁で麻薬密輸罪などで裁くという。とんでもない行為である。日本のメディアは「国際法違反の疑い」などと報じたが、腰の引けた表現だ。国際法に反することは明白である。アメリカはかつて、北朝鮮やイランを「ならず者国家」と指弾したが、その言葉が自国に向かって発せられたら、果たして反論できるのか。
国際法の重要な規範の一つに「外交特権」というのがある。国家を代表して交渉にあたる外交官は、受け入れ国によって身柄を拘束されたり、刑事裁判にかけられたりすることはない。所得税などの課税も免除される。そうしなければ、国家間の紛争や摩擦を解決するための交渉を進めるのは困難、と各国が悟ったからだ。
外交特権は、戦争に明け暮れたヨーロッパ諸国の間で19世紀の初めに確立された合意で、第2次大戦後の1961年に外交関係に関するウィーン条約として成文化された。条約は「外交官の身体は不可侵とする。外交官はいかなる方法によっても抑留し又は拘禁することができない」(第29条)、「外交官は接受国の刑事裁判権からの免除を享有する」(第31条)と明記している。まともな国家で、この条約を無視したり、否定したりする国はない。
一人の外交官に対してすら、不逮捕や刑事免責の特権が認められている。国家を代表する大統領や首相をどのように遇するかについては、国際的な条約や協定はないが、外交特権の当然の帰結として、国家元首や首相、外相についても同様の特権と免責が与えられ、他の国が刑事責任を問うことはできない、と国際慣習法で広く認められている。
ベネズエラに軍隊を派遣して護衛を殺害し、マドゥーロ大統領夫妻の身柄を拘束して軍用機で連れ去るなど、どのような論理を使っても正当化できるものではない。ましてや、マドゥーロ大統領がコカインの密輸にどのように関わっていたかについての説明もなく、「ベネズエラの石油は今後、アメリカが管理する。利益の配分も決める」と言うに至っては、支離滅裂と言うしかない。
ただ、問題なのは、国際社会にも国連にもアメリカ大統領の責任を問う力も仕組みもないことである。国家間の紛争に対処するのは国連安全保障理事会の仕事だが、安保理で五つの常任理事国すべての賛成を得られなければ、国連は動くことができない。アメリカは常任理事国であり、拒否権を持つ。要するに、かつての「戦勝国」が何をしようと、国連は何もできないのである。
ヨーロッパが主戦場になった第1次大戦では戦場で毒ガスが多用され、戦後、毒ガスや細菌兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書(1925年)ができた。第2次大戦では捕虜の虐待や民間人の虐殺が相次ぎ、1949年に成立したジュネーブ諸条約で、そうしたことが禁止された。国際法とは、その時代の国際社会の「映し鏡」であり、その多くは各国が戦争の惨禍をくぐり抜けてたどり着いた「紳士協定」のようなものに過ぎない。
誰かがその鏡を打ち砕き、「条約や協定など紙くず」と言い始めたら、効力はなくなる。トランプ大統領やガザでの住民虐殺をいとわなかったイスラエルのネタニヤフ首相は、「国際法など紙くず」と言っているのである。彼らに道理を説いても通じることはないだろう。激しい逆流の時代に入った、と覚悟を固めて対処するしかない。
激しい逆流は、次の大きな戦争へとつながる可能性がある。では、次の戦争はどのような様相を呈するのか。すでに、ロシアによるウクライナ侵攻でその輪郭がおぼろげながら見え始めている。ドローンの大量投入に象徴される、ハイテクを使った無人兵器の使用である。人型ロボットの投入も、そう遠くないだろう。
戦争の帰趨を決めるのは「武器と情報」である。あまりメディアでは報じられないが、情報の世界でもすさまじい競争が起きている。とりわけ注目されるのが量子コンピューターの開発と実戦への応用である。
兵力面で劣勢と見られたウクライナが初期段階でロシア軍の侵攻を食い止めることができたのは、ロシアの侵攻作戦の概要がウクライナ側に筒抜けで、準備する時間が十分にあったから、と考えるのが自然である。
ウクライナ側も情報の収集に必死になっていただろうが、ウクライナの力だけではロシア軍の作戦全体を把握することは困難だったはずだ。アメリカがロシア軍部隊の動きを詳細につかみ、差しさわりのない範囲でウクライナ側に伝えた、と私は見ている。
その際、決定的な役割を果たしたのは量子コンピューターなのではないか。しばらく前のコラム「ロシアの暗号は解読されているか」(末尾にURL)でも指摘したが、ロシア側が電子コンピューターで組み立てた暗号を使い、「解読不能」と確信しているシステムを、アメリカは量子コンピューターで解析し、暗号の解読に成功している可能性がある。
量子力学の原理に基づく量子コンピューターは順列や確率の計算が得意とされ、現在のスーパーコンピューターだと1万年かかるような計算を3分ほどで解く、と伝えられている。暗号解読の世界で「パラダイム・シフト」が起きている可能性がある。そして、この分野にもっとも巨額の費用をつぎ込こんでいるのはアメリカである。
技術分析のコンサルタント会社アスタミューゼ(東京・神田錦町)のリポートによると、2018年までの10年間でアメリカは10億6000万ドルの研究開発費を投じたと推計される。以下、イギリスが8億3000万ドル、中国6億3000万ドル、オーストラリア3億ドル、日本2億3000万ドルと続く。
この順番と開発費の推計は、実に興味深い。アメリカとイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの5カ国は、情報収集と暗号の解読で「アングロサクソン連合」を組んでおり、その合計額は、彼らが新しい戦争の時代に備えて、量子コンピューターの研究開発をいかに重視しているかを示しているからだ。
その重要性を知る中国と日本も追いかけているが、5カ国連合の知の総合力と資金力には遠く及ばない。この研究開発費ランキングの上位にロシアが登場しないのも示唆的だ。石油収入に頼りきり、ほかに世界で闘える産業が見当たらないないロシアは、ハイテク時代の競争で置いてきぼりになっているのかもしれない。
とはいえ、この国もあなどれない。なにせ、ロシアはもともと国際法など気にかけていない。一方で、中東やアフリカではいまだに隠然たる影響力を保っている。どちらも、次の新しい戦争の主要な舞台になる、と考えられるからだ。トランプ大統領は、デンマーク領のグリーンランドや南米コロンビアへの関心を示しているが、アメリカが中東とアフリカの利権を虎視眈々と狙っているのは明らかだ。
第1次大戦後、ドイツは権威的な体制を廃し、ワイマール憲法の下で再出発した。自由と人権の保障をうたった「もっとも先進的な憲法」と評された。だが、ヒトラーはその憲法の枠内で選挙を通して権力を握り、戦争に突き進んでいった。ナチスの躍進を支えた突撃隊(SA)のスローガンは「すべてをドイツのために」だった。
アメリカの民主主義は、かつてのドイツよりはるかに強靭で復元力がある、と信じる。しかし、この国には先住民を力で追い払って土地を奪い、アフリカの黒人を奴隷として酷使して富を築いた、という暗い過去がある。それを正面から見つめ、自省しているか疑わしい。アメリカは「民主主義の旗手」であり、民主主義の破壊者になることはあり得ない、と誰が言い得るのか。
トランプ大統領のキャッチフレーズ「アメリカ・ファースト」は、時にナチス突撃隊の「すべてをドイツのために」という叫びと同じ響きをもって聞こえてくる。「安易なアナロジー(類推)」と一笑に付すことができれば、いいのだが。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2026年1月18日
≪参考文献&サイト≫
◎『国際法概説』(香西茂ら、有斐閣双書、1974年)
◎国家元首等の外国刑事管轄権からの免除(竹村仁美・愛知県立大学准教授)
◎外交関係に関するウィーン条約の全文(同志社大学のサイト)
◎ロシアの暗号は解読されているか(ハンター、2023年1月31日)
◎米英中豪日の量子コンピューター研究開発費の推計(アスタミューゼのサイト)
◎5カ国連合による情報収集については、2001年の欧州議会報告が詳しい
◎『暴露 スノーデンが私に託したファイル』(グレン・グリーンウッド、新潮社、2014年)
◎プリゴジンは中東とアフリカで何をしてきたのか(ハンター、2023年7月3日)
≪写真説明≫
◎米軍に拘束され、連行されるマドゥーロ大統領(トランプ大統領のSNSから)

トランプ政権は産油国のベネズエラに軍事侵攻し、マドゥーロ大統領を拉致してアメリカに連行した。ニューヨークの連邦地裁で麻薬密輸罪などで裁くという。とんでもない行為である。日本のメディアは「国際法違反の疑い」などと報じたが、腰の引けた表現だ。国際法に反することは明白である。アメリカはかつて、北朝鮮やイランを「ならず者国家」と指弾したが、その言葉が自国に向かって発せられたら、果たして反論できるのか。
国際法の重要な規範の一つに「外交特権」というのがある。国家を代表して交渉にあたる外交官は、受け入れ国によって身柄を拘束されたり、刑事裁判にかけられたりすることはない。所得税などの課税も免除される。そうしなければ、国家間の紛争や摩擦を解決するための交渉を進めるのは困難、と各国が悟ったからだ。
外交特権は、戦争に明け暮れたヨーロッパ諸国の間で19世紀の初めに確立された合意で、第2次大戦後の1961年に外交関係に関するウィーン条約として成文化された。条約は「外交官の身体は不可侵とする。外交官はいかなる方法によっても抑留し又は拘禁することができない」(第29条)、「外交官は接受国の刑事裁判権からの免除を享有する」(第31条)と明記している。まともな国家で、この条約を無視したり、否定したりする国はない。
一人の外交官に対してすら、不逮捕や刑事免責の特権が認められている。国家を代表する大統領や首相をどのように遇するかについては、国際的な条約や協定はないが、外交特権の当然の帰結として、国家元首や首相、外相についても同様の特権と免責が与えられ、他の国が刑事責任を問うことはできない、と国際慣習法で広く認められている。
ベネズエラに軍隊を派遣して護衛を殺害し、マドゥーロ大統領夫妻の身柄を拘束して軍用機で連れ去るなど、どのような論理を使っても正当化できるものではない。ましてや、マドゥーロ大統領がコカインの密輸にどのように関わっていたかについての説明もなく、「ベネズエラの石油は今後、アメリカが管理する。利益の配分も決める」と言うに至っては、支離滅裂と言うしかない。
ただ、問題なのは、国際社会にも国連にもアメリカ大統領の責任を問う力も仕組みもないことである。国家間の紛争に対処するのは国連安全保障理事会の仕事だが、安保理で五つの常任理事国すべての賛成を得られなければ、国連は動くことができない。アメリカは常任理事国であり、拒否権を持つ。要するに、かつての「戦勝国」が何をしようと、国連は何もできないのである。
ヨーロッパが主戦場になった第1次大戦では戦場で毒ガスが多用され、戦後、毒ガスや細菌兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書(1925年)ができた。第2次大戦では捕虜の虐待や民間人の虐殺が相次ぎ、1949年に成立したジュネーブ諸条約で、そうしたことが禁止された。国際法とは、その時代の国際社会の「映し鏡」であり、その多くは各国が戦争の惨禍をくぐり抜けてたどり着いた「紳士協定」のようなものに過ぎない。
誰かがその鏡を打ち砕き、「条約や協定など紙くず」と言い始めたら、効力はなくなる。トランプ大統領やガザでの住民虐殺をいとわなかったイスラエルのネタニヤフ首相は、「国際法など紙くず」と言っているのである。彼らに道理を説いても通じることはないだろう。激しい逆流の時代に入った、と覚悟を固めて対処するしかない。
激しい逆流は、次の大きな戦争へとつながる可能性がある。では、次の戦争はどのような様相を呈するのか。すでに、ロシアによるウクライナ侵攻でその輪郭がおぼろげながら見え始めている。ドローンの大量投入に象徴される、ハイテクを使った無人兵器の使用である。人型ロボットの投入も、そう遠くないだろう。
戦争の帰趨を決めるのは「武器と情報」である。あまりメディアでは報じられないが、情報の世界でもすさまじい競争が起きている。とりわけ注目されるのが量子コンピューターの開発と実戦への応用である。
兵力面で劣勢と見られたウクライナが初期段階でロシア軍の侵攻を食い止めることができたのは、ロシアの侵攻作戦の概要がウクライナ側に筒抜けで、準備する時間が十分にあったから、と考えるのが自然である。
ウクライナ側も情報の収集に必死になっていただろうが、ウクライナの力だけではロシア軍の作戦全体を把握することは困難だったはずだ。アメリカがロシア軍部隊の動きを詳細につかみ、差しさわりのない範囲でウクライナ側に伝えた、と私は見ている。
その際、決定的な役割を果たしたのは量子コンピューターなのではないか。しばらく前のコラム「ロシアの暗号は解読されているか」(末尾にURL)でも指摘したが、ロシア側が電子コンピューターで組み立てた暗号を使い、「解読不能」と確信しているシステムを、アメリカは量子コンピューターで解析し、暗号の解読に成功している可能性がある。
量子力学の原理に基づく量子コンピューターは順列や確率の計算が得意とされ、現在のスーパーコンピューターだと1万年かかるような計算を3分ほどで解く、と伝えられている。暗号解読の世界で「パラダイム・シフト」が起きている可能性がある。そして、この分野にもっとも巨額の費用をつぎ込こんでいるのはアメリカである。
技術分析のコンサルタント会社アスタミューゼ(東京・神田錦町)のリポートによると、2018年までの10年間でアメリカは10億6000万ドルの研究開発費を投じたと推計される。以下、イギリスが8億3000万ドル、中国6億3000万ドル、オーストラリア3億ドル、日本2億3000万ドルと続く。
この順番と開発費の推計は、実に興味深い。アメリカとイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの5カ国は、情報収集と暗号の解読で「アングロサクソン連合」を組んでおり、その合計額は、彼らが新しい戦争の時代に備えて、量子コンピューターの研究開発をいかに重視しているかを示しているからだ。
その重要性を知る中国と日本も追いかけているが、5カ国連合の知の総合力と資金力には遠く及ばない。この研究開発費ランキングの上位にロシアが登場しないのも示唆的だ。石油収入に頼りきり、ほかに世界で闘える産業が見当たらないないロシアは、ハイテク時代の競争で置いてきぼりになっているのかもしれない。
とはいえ、この国もあなどれない。なにせ、ロシアはもともと国際法など気にかけていない。一方で、中東やアフリカではいまだに隠然たる影響力を保っている。どちらも、次の新しい戦争の主要な舞台になる、と考えられるからだ。トランプ大統領は、デンマーク領のグリーンランドや南米コロンビアへの関心を示しているが、アメリカが中東とアフリカの利権を虎視眈々と狙っているのは明らかだ。
第1次大戦後、ドイツは権威的な体制を廃し、ワイマール憲法の下で再出発した。自由と人権の保障をうたった「もっとも先進的な憲法」と評された。だが、ヒトラーはその憲法の枠内で選挙を通して権力を握り、戦争に突き進んでいった。ナチスの躍進を支えた突撃隊(SA)のスローガンは「すべてをドイツのために」だった。
アメリカの民主主義は、かつてのドイツよりはるかに強靭で復元力がある、と信じる。しかし、この国には先住民を力で追い払って土地を奪い、アフリカの黒人を奴隷として酷使して富を築いた、という暗い過去がある。それを正面から見つめ、自省しているか疑わしい。アメリカは「民主主義の旗手」であり、民主主義の破壊者になることはあり得ない、と誰が言い得るのか。
トランプ大統領のキャッチフレーズ「アメリカ・ファースト」は、時にナチス突撃隊の「すべてをドイツのために」という叫びと同じ響きをもって聞こえてくる。「安易なアナロジー(類推)」と一笑に付すことができれば、いいのだが。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2026年1月18日
≪参考文献&サイト≫
◎『国際法概説』(香西茂ら、有斐閣双書、1974年)
◎国家元首等の外国刑事管轄権からの免除(竹村仁美・愛知県立大学准教授)
◎外交関係に関するウィーン条約の全文(同志社大学のサイト)
◎ロシアの暗号は解読されているか(ハンター、2023年1月31日)
◎米英中豪日の量子コンピューター研究開発費の推計(アスタミューゼのサイト)
◎5カ国連合による情報収集については、2001年の欧州議会報告が詳しい
◎『暴露 スノーデンが私に託したファイル』(グレン・グリーンウッド、新潮社、2014年)
◎プリゴジンは中東とアフリカで何をしてきたのか(ハンター、2023年7月3日)
≪写真説明≫
◎米軍に拘束され、連行されるマドゥーロ大統領(トランプ大統領のSNSから)
「遠山の金さん」こと遠山金四郎景元(かげもと)が北町奉行に就任したのは江戸時代の後期、天保11年(1840年)のことである。テレビドラマでは、お白洲に引き出された悪党どもがご託を並べると、「やかましいやい」と片肌を脱いで一喝し、「この桜吹雪に見覚えがねえとは言わせねえぜ」と啖呵を切って罪を認めさせ、一件落着となる。
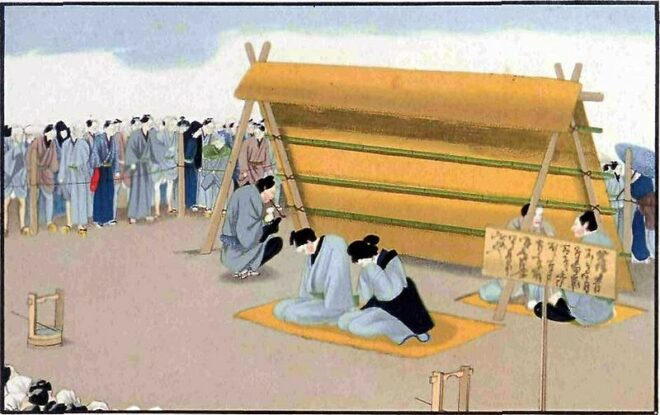
お家の事情が複雑で、遠山金四郎は若いころ悪所通いをして遊びほうけた。その時に刺青(いれずみ)を入れたのは事実のようだが、それが桜吹雪だったという記録はない。明治時代に書かれた伝記や歌舞伎の脚本には「刺青は口に紙片をくわえた女の生首だった」というものもあるという。刺青の図案については諸説あり、真偽は不明だが、よく考えてみれば、そもそも江戸時代の町奉行が公けの場で肌を見せて啖呵を切るということ自体、あり得ないことだろう。
刺青はともかく、遠山が庶民の暮らしぶりにも配慮し、人情味あふれる裁きをして人気があったのは間違いない。当時の老中首座、水野忠邦が幕政改革のために贅沢禁止令を出し、寄席や芝居小屋を次々に閉鎖したのに対して、「あまり行き過ぎては市中がさびれてしまう」と抵抗したのも遠山だった。庶民にとって水野は悪玉、遠山は善玉であり、後の人々は歌舞伎や伝記でその名奉行ぶりを褒めたたえたのである。
◇ ◇
江戸後期の全国の人口は3000万人前後、江戸の人口は100万人ほどと推定されている。和歌山大学教授などをつとめた関山直太郎によれば、身分ごとの比率は下図の通りで、農民や漁民・林業従事者を指す百姓が8割強、武士は6?7%、町人が5?6%、穢多(えた)・非人が1.6%程度だったと見られる。
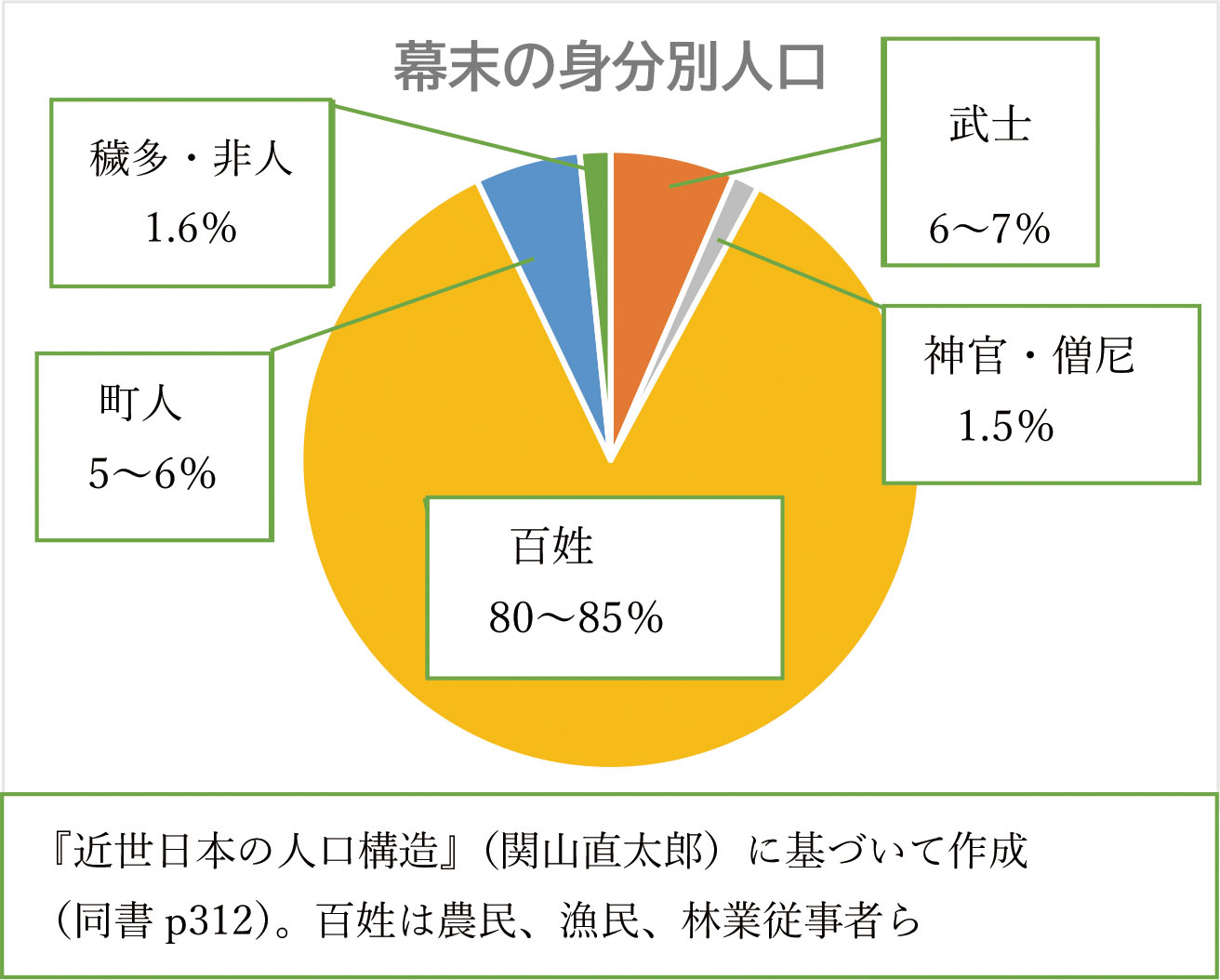
遠山が町奉行として裁いたのは、江戸の町人の事件やもめごとである。武士のもめごとは評定所、寺社がからめば寺社奉行が取り扱った。身分の区分が厳格な社会であり、裁きもまた身分ごとに行われた。
ただし、江戸で暮らしていながら、町奉行の裁きに服さない人々がいた。穢多と非人である。彼らは浅草に住む弾左衛門という穢多頭(えたがしら)の管轄下にあった。弾左衛門は江戸だけでなく、関東一円に住むすべての賤民の頭であり、彼らのもめごとを裁いた。約7万人が弾左衛門の支配下にあったとされる。
当時、穢多には処刑場での仕事や捕縛役の見返りとして、斃(へい)牛馬の解体と処理(牛皮や馬皮の加工)が独占的に認められていた。これは全国的なものだが、弾左衛門にはさらに、関東での灯芯(とうしん)の製造と販売の特権も与えられていた。配下の者たちがゴザや畳表の素材となるイグサから、その髄(ずい)を抜き取り、それでろうそくなどの芯を作って売っていた。当時、灯芯は生活必需品の一つであり、大きな収入源だった。
関東一円の穢多は灯芯や皮革製品を売り、利益の一部を上納金として弾左衛門に納めていた。物乞いの頭領である非人頭からの上納金もあった。その収入は巨額で、小大名あるいは旗本並みだったという。その資金で闇金融を営んでいたことも知られている。弾左衛門は浅草に広大な屋敷を構え、敷地内には牢屋まであった。
こうしたことから、江戸時代の賤民の中では穢多の方が非人より格上だったことが分かるが、「賤民から平民になるチャンスがある」という点では、非人の方が恵まれていた。道ならぬ恋の末に心中を試み、2人とも生き残った場合、彼らは3日間のさらし刑にされ、非人に落とされたが、条件が整えば、平民に戻る可能性が残されていた。穢多にはこうした余地はなかった。なぜそうした違いがあったのか、よく分かっていない。
穢多と非人には、もう一つ大きな違いがあった。それは穢多には全国的な人的ネットワークがあったが、非人にはそうしたものは見られない、という点である。徳川家康の江戸入府の際に取り立てられて関東一円の穢多頭になった弾左衛門は、幕末まで十三代続いた。その世継ぎが途絶えそうになった時、この人的なネットワークで後継者が選ばれている。
十一代の弾左衛門は安芸(広島)、十二代は信州(長野)、十三代目は摂津(兵庫県南部と大阪府の一部)の生まれで、いずれも養子縁組によって後を継いだ。彼らはどのようなプロセスを経て江戸の穢多頭に選ばれたのか。作家の塩見鮮一郎が『最後の弾左衛門 十三代の維新』で詳細に綴っている。
十二代の弾左衛門に世継ぎがなく、誰を後継者にするかをめぐって関東の有力な小頭(こがしら)の間でもめにもめ、収拾がつかなくなった。話はほどなく京都や大阪、広島の有力な穢多頭に伝わり、彼らが動き始める。白羽の矢が立てられたのは、摂津・住吉村の小太郎という若者だった。母親は「せん」という女性で、姉は広島の穢多頭に嫁いでいる。姉妹は京都・柳原の有力な人物の娘だった。
穢多とさげすまれた人たちの間にも階層があり、有力者の間で緊密なネットワークがあったことがうかがえる。弾左衛門の後継者に選ばれた摂津の聡明な若者は、数え17歳で江戸に入り、北町奉行の前で十三代襲名のお披露目をした。その時の奉行が冒頭に記した遠山金四郎景元である。
十三代目の弾左衛門は幕末の激動期を生きた。戊辰戦争では幕府に兵站用の人員の提供を申し出たり、野戦病院の建設費用として3000両の負担を約束したりしている。並行して、幕府に「天地の間に生を受けた人間に違いはない。人間としての交際もできないのは誠に嘆かわしい」との文書を出し、賤民身分からの解放を嘆願した。

崩壊直前の幕府はこれを認め、弾左衛門と配下の65人の手代を平民身分とすることを決めた。江戸時代の厳格な身分制度の一角が崩れたのである。明治新政府が賤称廃止の太政官布告を出した明治4年の3年前のことだが、このことに触れている歴史書はほとんどない。
◇ ◇
前回のコラム(連載14)の最後で、明治4年の賤称廃止の布告の後、非人の多くは庶民に融け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは激しい差別にさらされ続けた、と記した。その状況を人口統計に基づいて明らかにしたのは、大正から昭和にかけての歴史家で東京帝大教授の喜田貞吉である。
喜田は、大正8年(1919年)に発行した研究誌『民族と歴史』の「特殊部落研究号」に次のように記した。少し長くなるが、そのまま引用する(数字は洋数字に変換。ルビは一部、筆者が付した)。
「穢多と非人とどちらが多かったかと申すと、今日正確な数を知る事は出来ませぬが、少くとも京都付近では、非人の方が非常に多かった。正徳5年(今より204年前)の調べに、洛外の非人の数8506人に対して、穢多の数は僅かに2064人しかありません。しかるに、その後非人という方はだんだん減じまして、明治4年穢多非人解放の際には、全国で穢多28万311人、非人2万3480人、皮作等雑種7万9095人とあります。この皮作はやはり穢多の仲間です。これは維新前に於いて、既に多数の非人が消えてしまった、すなわち良民に混じてしまった証拠であります。維新後に於いても、非人という方は大抵解放されまして、もはや世人は彼らを特殊部落民であるとは考えなくなっているのが多いのであります」
「しかるに気の毒にももと穢多といわれた者だけは、明治4年の解放も実は単に新平民の名を得たのみであって、実際上にはその全部が永く後に取り残さるることになっております。これは穢多は穢(けが)れたものであるという思想と、『穢多』という同情なき文字とが累(わずら)いをなしているのであります。もちろん彼らが貧乏である、不潔である、品性の下等なものが多いという様なこと、特に密集して住んでいて、団結心強く、世間に反抗する思想を持っていると認められていることなども、その理由をなしているのでありましょうが、第一にはこの『穢多』という文字が悪いと思います。『穢多』と書くが故に特別に穢れたのだとの観念が去りにくい。(中略)そしてこれらの原因は、もとをただせば主として社会の圧迫にあるのであって、彼らのみを責めるのは残酷であります」
要するに「穢多」という呼称が災いしている、と言うのだが、非人が庶民に融け込んだのに穢多はそうならなかった理由の説明としては説得力に欠ける。
喜田はこう説いた後、古代の賎民制度に触れ、帰化人の末裔であるとか外国の捕虜の子孫であるといった様々な起源説に触れたうえで、それらの説をすべて否定し、「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するというようなことは、少くとも昔はありませんでした」と書いた。およそ、現実離れした見解と言うしかない。
結論として、喜田は「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」と記した。これが戦後の「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断するために政治的に作られたもの」という「近世政治起源説」へとつながっていく。
部落の起源に関するこうした学説は1980年代以降、中世や古代の賤民の研究が進むにつれて破綻し、今では見向きもされなくなったことは繰り返し、紹介してきた。ならば、そもそも「穢多」と呼ばれた人たちのルーツは何なのか。それについては、部落史の研究者の間でも混沌とした状況にある。
被差別部落の起源やルーツを考えるうえで、大きな手がかりとなるのは、穢多や長吏(ちょうり)あるいは「かわた」など様々に呼ばれた人たちの間には、かなり古くから「全国的な強い人的ネットワークがあった」という事実だろう。それは、彼らの間に「共通の記憶」あるいは「歴史の共有」といったものがあったから、と考えるのが自然ではないか。彼らが共有し続けたものとは何だったのか。探求の旅を続けたい。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*初出:調査報道サイト「ハンター」 連載15「彼らには全国的なネットワークがあった」(2025年9月29日)
≪参照≫
*連載14「賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった」(2025年9月10日)
≪写真と図の説明≫
◎心中未遂でさらし刑にされた男女(幕末に英国人が描いたもの)
J.M.W.Silber : Schetches of Japanese Manners & Custums, London 1867
https://mag.japaaan.com/archives/192899/2
◎十三代目の弾左衛門(新宿近世文書研究会のサイトから)
https://skomonjyo.blog.fc2.com/blog-entry-228.html
◎図 幕末の身分別人口=『近世日本の人口構造』に基づいて筆者が作成
≪参考文献&サイト≫
◎『遠山金四郎の時代』(藤田覚、校倉書房、1992年)
◎ウィキペディア「遠山の金さん」
◎『大江戸裁判事情』(戸部新十郎、廣済堂文庫、1998年)
◎『近世日本の人口構造』(関山直太郎、吉川弘文館、再版1969年)
◎『歴史人口学で読む江戸日本』(浜野潔、吉川弘文館、2011年)
◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)
◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫、2019年)=1919年発行の『民族と歴史』第2巻第1号「特殊部落研究号」を翻刻したもの
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)
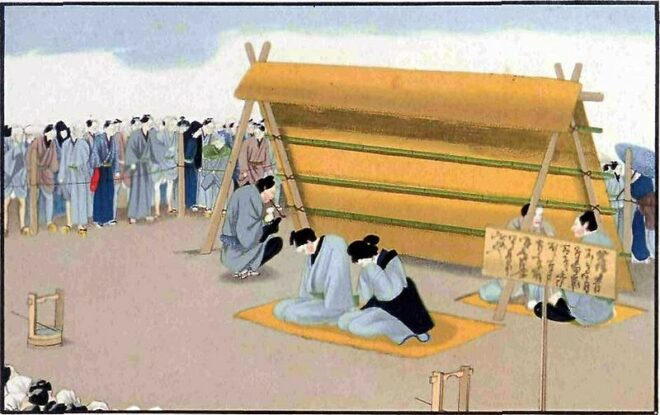
お家の事情が複雑で、遠山金四郎は若いころ悪所通いをして遊びほうけた。その時に刺青(いれずみ)を入れたのは事実のようだが、それが桜吹雪だったという記録はない。明治時代に書かれた伝記や歌舞伎の脚本には「刺青は口に紙片をくわえた女の生首だった」というものもあるという。刺青の図案については諸説あり、真偽は不明だが、よく考えてみれば、そもそも江戸時代の町奉行が公けの場で肌を見せて啖呵を切るということ自体、あり得ないことだろう。
刺青はともかく、遠山が庶民の暮らしぶりにも配慮し、人情味あふれる裁きをして人気があったのは間違いない。当時の老中首座、水野忠邦が幕政改革のために贅沢禁止令を出し、寄席や芝居小屋を次々に閉鎖したのに対して、「あまり行き過ぎては市中がさびれてしまう」と抵抗したのも遠山だった。庶民にとって水野は悪玉、遠山は善玉であり、後の人々は歌舞伎や伝記でその名奉行ぶりを褒めたたえたのである。
◇ ◇
江戸後期の全国の人口は3000万人前後、江戸の人口は100万人ほどと推定されている。和歌山大学教授などをつとめた関山直太郎によれば、身分ごとの比率は下図の通りで、農民や漁民・林業従事者を指す百姓が8割強、武士は6?7%、町人が5?6%、穢多(えた)・非人が1.6%程度だったと見られる。
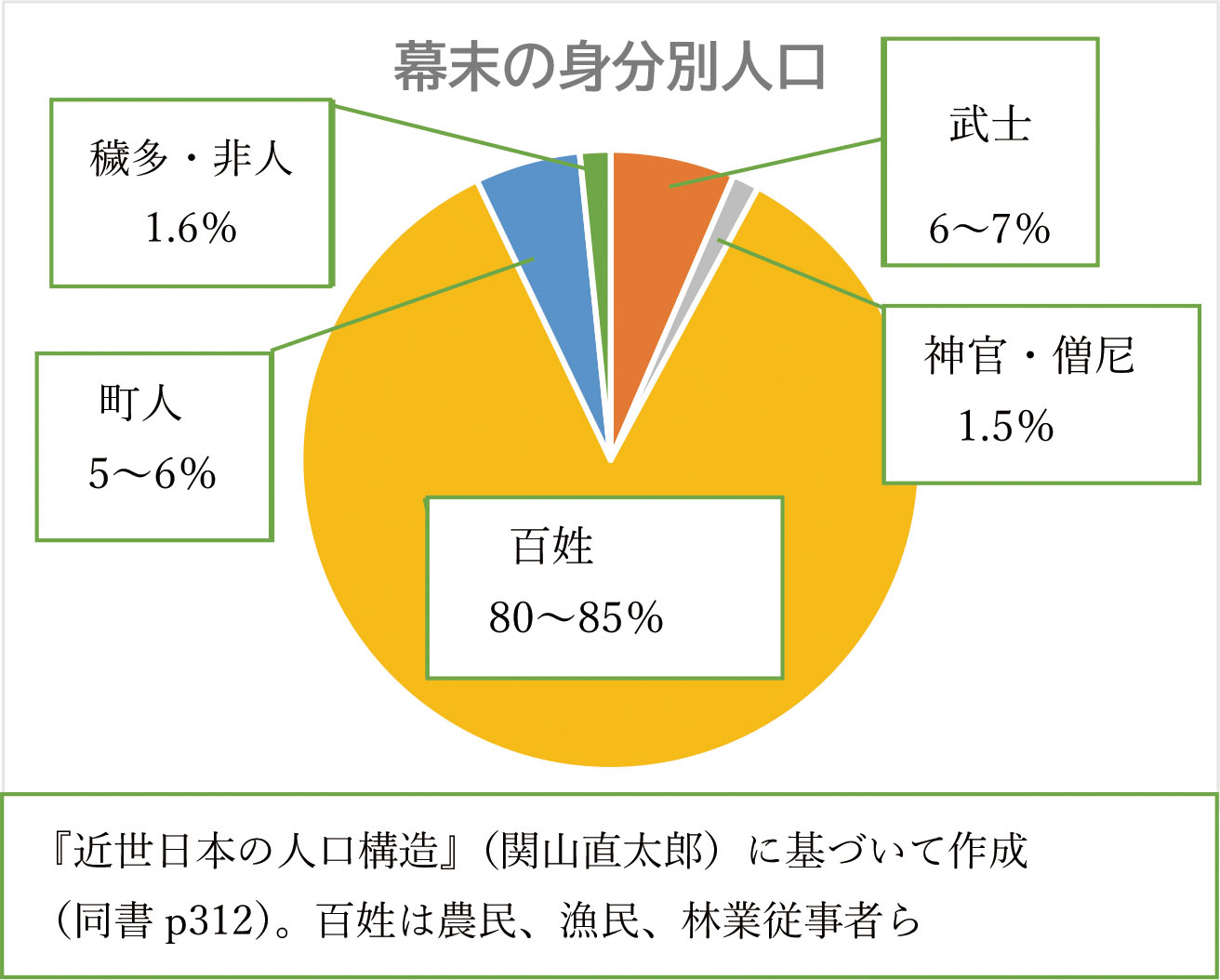
遠山が町奉行として裁いたのは、江戸の町人の事件やもめごとである。武士のもめごとは評定所、寺社がからめば寺社奉行が取り扱った。身分の区分が厳格な社会であり、裁きもまた身分ごとに行われた。
ただし、江戸で暮らしていながら、町奉行の裁きに服さない人々がいた。穢多と非人である。彼らは浅草に住む弾左衛門という穢多頭(えたがしら)の管轄下にあった。弾左衛門は江戸だけでなく、関東一円に住むすべての賤民の頭であり、彼らのもめごとを裁いた。約7万人が弾左衛門の支配下にあったとされる。
当時、穢多には処刑場での仕事や捕縛役の見返りとして、斃(へい)牛馬の解体と処理(牛皮や馬皮の加工)が独占的に認められていた。これは全国的なものだが、弾左衛門にはさらに、関東での灯芯(とうしん)の製造と販売の特権も与えられていた。配下の者たちがゴザや畳表の素材となるイグサから、その髄(ずい)を抜き取り、それでろうそくなどの芯を作って売っていた。当時、灯芯は生活必需品の一つであり、大きな収入源だった。
関東一円の穢多は灯芯や皮革製品を売り、利益の一部を上納金として弾左衛門に納めていた。物乞いの頭領である非人頭からの上納金もあった。その収入は巨額で、小大名あるいは旗本並みだったという。その資金で闇金融を営んでいたことも知られている。弾左衛門は浅草に広大な屋敷を構え、敷地内には牢屋まであった。
こうしたことから、江戸時代の賤民の中では穢多の方が非人より格上だったことが分かるが、「賤民から平民になるチャンスがある」という点では、非人の方が恵まれていた。道ならぬ恋の末に心中を試み、2人とも生き残った場合、彼らは3日間のさらし刑にされ、非人に落とされたが、条件が整えば、平民に戻る可能性が残されていた。穢多にはこうした余地はなかった。なぜそうした違いがあったのか、よく分かっていない。
穢多と非人には、もう一つ大きな違いがあった。それは穢多には全国的な人的ネットワークがあったが、非人にはそうしたものは見られない、という点である。徳川家康の江戸入府の際に取り立てられて関東一円の穢多頭になった弾左衛門は、幕末まで十三代続いた。その世継ぎが途絶えそうになった時、この人的なネットワークで後継者が選ばれている。
十一代の弾左衛門は安芸(広島)、十二代は信州(長野)、十三代目は摂津(兵庫県南部と大阪府の一部)の生まれで、いずれも養子縁組によって後を継いだ。彼らはどのようなプロセスを経て江戸の穢多頭に選ばれたのか。作家の塩見鮮一郎が『最後の弾左衛門 十三代の維新』で詳細に綴っている。
十二代の弾左衛門に世継ぎがなく、誰を後継者にするかをめぐって関東の有力な小頭(こがしら)の間でもめにもめ、収拾がつかなくなった。話はほどなく京都や大阪、広島の有力な穢多頭に伝わり、彼らが動き始める。白羽の矢が立てられたのは、摂津・住吉村の小太郎という若者だった。母親は「せん」という女性で、姉は広島の穢多頭に嫁いでいる。姉妹は京都・柳原の有力な人物の娘だった。
穢多とさげすまれた人たちの間にも階層があり、有力者の間で緊密なネットワークがあったことがうかがえる。弾左衛門の後継者に選ばれた摂津の聡明な若者は、数え17歳で江戸に入り、北町奉行の前で十三代襲名のお披露目をした。その時の奉行が冒頭に記した遠山金四郎景元である。
十三代目の弾左衛門は幕末の激動期を生きた。戊辰戦争では幕府に兵站用の人員の提供を申し出たり、野戦病院の建設費用として3000両の負担を約束したりしている。並行して、幕府に「天地の間に生を受けた人間に違いはない。人間としての交際もできないのは誠に嘆かわしい」との文書を出し、賤民身分からの解放を嘆願した。

崩壊直前の幕府はこれを認め、弾左衛門と配下の65人の手代を平民身分とすることを決めた。江戸時代の厳格な身分制度の一角が崩れたのである。明治新政府が賤称廃止の太政官布告を出した明治4年の3年前のことだが、このことに触れている歴史書はほとんどない。
◇ ◇
前回のコラム(連載14)の最後で、明治4年の賤称廃止の布告の後、非人の多くは庶民に融け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは激しい差別にさらされ続けた、と記した。その状況を人口統計に基づいて明らかにしたのは、大正から昭和にかけての歴史家で東京帝大教授の喜田貞吉である。
喜田は、大正8年(1919年)に発行した研究誌『民族と歴史』の「特殊部落研究号」に次のように記した。少し長くなるが、そのまま引用する(数字は洋数字に変換。ルビは一部、筆者が付した)。
「穢多と非人とどちらが多かったかと申すと、今日正確な数を知る事は出来ませぬが、少くとも京都付近では、非人の方が非常に多かった。正徳5年(今より204年前)の調べに、洛外の非人の数8506人に対して、穢多の数は僅かに2064人しかありません。しかるに、その後非人という方はだんだん減じまして、明治4年穢多非人解放の際には、全国で穢多28万311人、非人2万3480人、皮作等雑種7万9095人とあります。この皮作はやはり穢多の仲間です。これは維新前に於いて、既に多数の非人が消えてしまった、すなわち良民に混じてしまった証拠であります。維新後に於いても、非人という方は大抵解放されまして、もはや世人は彼らを特殊部落民であるとは考えなくなっているのが多いのであります」
「しかるに気の毒にももと穢多といわれた者だけは、明治4年の解放も実は単に新平民の名を得たのみであって、実際上にはその全部が永く後に取り残さるることになっております。これは穢多は穢(けが)れたものであるという思想と、『穢多』という同情なき文字とが累(わずら)いをなしているのであります。もちろん彼らが貧乏である、不潔である、品性の下等なものが多いという様なこと、特に密集して住んでいて、団結心強く、世間に反抗する思想を持っていると認められていることなども、その理由をなしているのでありましょうが、第一にはこの『穢多』という文字が悪いと思います。『穢多』と書くが故に特別に穢れたのだとの観念が去りにくい。(中略)そしてこれらの原因は、もとをただせば主として社会の圧迫にあるのであって、彼らのみを責めるのは残酷であります」
要するに「穢多」という呼称が災いしている、と言うのだが、非人が庶民に融け込んだのに穢多はそうならなかった理由の説明としては説得力に欠ける。
喜田はこう説いた後、古代の賎民制度に触れ、帰化人の末裔であるとか外国の捕虜の子孫であるといった様々な起源説に触れたうえで、それらの説をすべて否定し、「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するというようなことは、少くとも昔はありませんでした」と書いた。およそ、現実離れした見解と言うしかない。
結論として、喜田は「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」と記した。これが戦後の「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断するために政治的に作られたもの」という「近世政治起源説」へとつながっていく。
部落の起源に関するこうした学説は1980年代以降、中世や古代の賤民の研究が進むにつれて破綻し、今では見向きもされなくなったことは繰り返し、紹介してきた。ならば、そもそも「穢多」と呼ばれた人たちのルーツは何なのか。それについては、部落史の研究者の間でも混沌とした状況にある。
被差別部落の起源やルーツを考えるうえで、大きな手がかりとなるのは、穢多や長吏(ちょうり)あるいは「かわた」など様々に呼ばれた人たちの間には、かなり古くから「全国的な強い人的ネットワークがあった」という事実だろう。それは、彼らの間に「共通の記憶」あるいは「歴史の共有」といったものがあったから、と考えるのが自然ではないか。彼らが共有し続けたものとは何だったのか。探求の旅を続けたい。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*初出:調査報道サイト「ハンター」 連載15「彼らには全国的なネットワークがあった」(2025年9月29日)
≪参照≫
*連載14「賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった」(2025年9月10日)
≪写真と図の説明≫
◎心中未遂でさらし刑にされた男女(幕末に英国人が描いたもの)
J.M.W.Silber : Schetches of Japanese Manners & Custums, London 1867
https://mag.japaaan.com/archives/192899/2
◎十三代目の弾左衛門(新宿近世文書研究会のサイトから)
https://skomonjyo.blog.fc2.com/blog-entry-228.html
◎図 幕末の身分別人口=『近世日本の人口構造』に基づいて筆者が作成
≪参考文献&サイト≫
◎『遠山金四郎の時代』(藤田覚、校倉書房、1992年)
◎ウィキペディア「遠山の金さん」
◎『大江戸裁判事情』(戸部新十郎、廣済堂文庫、1998年)
◎『近世日本の人口構造』(関山直太郎、吉川弘文館、再版1969年)
◎『歴史人口学で読む江戸日本』(浜野潔、吉川弘文館、2011年)
◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)
◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫、2019年)=1919年発行の『民族と歴史』第2巻第1号「特殊部落研究号」を翻刻したもの
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)
明治新政府が発した五箇条の誓文は、「施政の基本方針」を示した文書である。それは封建社会から脱して、近代国家の建設をめざすものだった。
一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ
一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ
一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス
一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ
一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。
尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。
武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。
前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。
政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。
この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。
いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。
戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。
新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。
奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。
地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。
明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。
では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。
新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。
同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。
地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。
上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。
「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。
ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*メールマガジン「風切通信 134(2025年9月10日)
*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)
末尾に連載各回へのリンク
≪写真説明≫
◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)
https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html
≪参考文献&サイト≫
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)
◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)
◎江戸時代の税(国税庁のサイト)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm
◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)
◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)
◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)
◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)
◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)
https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html
◎ウィキペディア「伊勢暴動」
≪参照≫
【元右衛門の嘆願書の現代語訳】
一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ
一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ
一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス
一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ
一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。
尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。
武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。
前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。
政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。
この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。
いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。
戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。
新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。
奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。
地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。
明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。
では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。
新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。
同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。
地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。
上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。
「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。
ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*メールマガジン「風切通信 134(2025年9月10日)
*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)
末尾に連載各回へのリンク
≪写真説明≫
◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)
https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html
≪参考文献&サイト≫
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)
◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)
◎江戸時代の税(国税庁のサイト)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm
◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)
◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)
◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)
◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)
◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)
https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html
◎ウィキペディア「伊勢暴動」
≪参照≫
【元右衛門の嘆願書の現代語訳】
朝のラジオニュースで、鹿児島県の霧島市に大雨特別警報が出されたことを知った。線状降水帯が発生し、8月7日夕から8日朝までの12時間で495ミリの雨量を観測したという。495ミリの雨量とは、あたり一面に50センチ近い雨が降り注いだことを意味する。
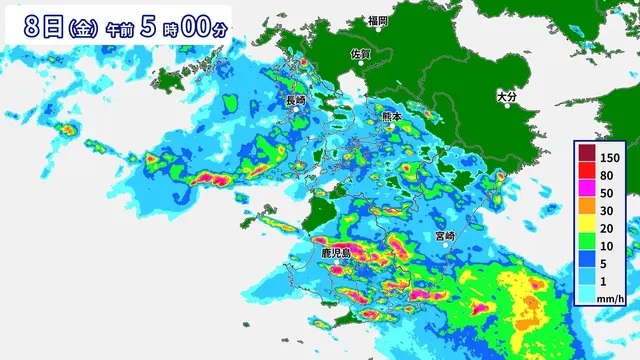
気象庁が「災害がすでに発生している可能性が極めて高い」と警鐘を鳴らしたのは当然のことで、災害報道に力を入れるNHKも、7時のニュースのトップでこの大雨特別警報のことを伝えた。これまた、当然の扱いだろう。
ところが、である。NHKが「現場からの報告」として伝えたのは鹿児島市内にある放送局の前からの記者のレポートだった。鹿児島市には大雨の特別警報は出ていない。放送時には雨もほとんど降っていなかった。トンチンカンな「現場からの報告」に唖然とした。
誰も霧島市内に行っていないのである。記者は「霧島市に通じる道路では落石や土砂崩れが発生しており、交通が規制されています」と伝えていた。ならば、せめて「行けるところまで行ってみました。通行はこのように規制されています」という映像があってもよさそうなのに、そうしたものすら放送されなかった。
霧島市は、大昔から火山活動が活発だった霧島連峰の南に広がる。火山灰などの噴出物が分厚く降り積もっており、地盤はきわめて軟弱だ。気象庁の指摘を待つまでもなく、すでに河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生していると考えられるのに、NHKは何の情報もキャッチできていなかった。
「霧島市内に住む人が被災の様子をスマホで撮影しているはず」と考え、チャンネルを民放に切り替えたところ、テレビ朝日が系列の地元局に視聴者から寄せられた動画を流していた。川が濁流となって家屋の土台を削っており、乗用車が流されていた。こうした被害が続発しており、霧島市役所なども混乱状態にある、と考えるのが自然だろう。
近年、事件や事故が起きると、記者がよく「私は安全なところからお伝えしています」と口にする。そんなことは映像を見れば分かるのに、必ずと言っていいほど付け加える。メディアとして、組織のコンプライアンス(法令遵守)にのっとって行動していることをアピールしたいのだろう。
もちろん、記者の命と健康も大事だ。会社として取材のルールを定めて動くのは当然のことである。1991年には雲仙岳の大火砕流で報道関係者を中心に43人が死亡・行方不明になる惨事があった。命をかけてまで取材することを求めるわけにはいかない。
だが、報道する者には可能な限り現場に肉薄し、自分の目で見たもの、知り得たことを伝える使命もある。リスクがあるからと言って近づかなければ、報道の使命を十分に果たすことはできない。要は、記者の命と健康を守ることと報道の使命の妥協点を探る努力を常に続けなければならない、ということだろう。
そうした努力がおざなりになり、メディアに「現場に肉薄する覚悟」が薄れてきたのは何時からか。私は、2011年の東日本大震災が転機だったと考えている。この時、福島原発の爆発事故と放射能の大量流出を受けて、政府は原発から半径30キロ圏内に立ち入らないよう規制した。
報道機関はこれにどう対処したか。東京の主な新聞とテレビの幹部が集まり、各社とも30キロ圏から記者やカメラマンを引き揚げ、立ち入らないことを決めた。その時、30キロ圏内には畜産農家や介護施設の入所者らがまだ多数残っていた。が、彼らの生活や苦悩を取材することを放棄したのである。
放射線量を考慮し、防護服を付けての短時間の取材なら命にかかわることは避けられたにもかかわらず、各社は談合して「原稿より健康が大事」と決め込んだ。そして、みんなでその取り決めを守った。「それはおかしい」と唱え、会社の指示にあらがった者はほとんどいなかった。
この取り決めは、その後の戦争報道や災害取材にも陰に陽に影響を及ぼした。記者とて危ないことはしたくない。会社の幹部も、無理をさせて責任を問われるようなことは避けたい。こうして、「命と使命の妥協点」をさぐる作業はズルズルと命の方に傾き、使命は少しずつ遠ざかっていった。
かくして、台風を取材するのにホテルの部屋からカメラを回し、「安全なところからお伝えしています」とうそぶく記者が登場するに至った。強い風を頬に受け、たたきつける雨に打たれることもない台風取材。それを「おかしい」とも思わないメディア。報道する者がその矜持を失った時、そのツケを払わせられるのは読者であり、視聴者であり、ひいては私たちの社会そのものである。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*メールマガジン風切通信 133 (2025年8月8日)
≪写真説明&Source≫
霧島市を襲った線状降水帯(Yahoo ニュースのサイトから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/af7666a304b470fc56d115392e185f7b3ee1bb8e
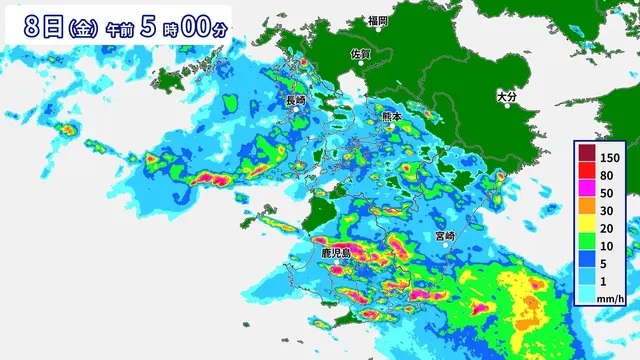
気象庁が「災害がすでに発生している可能性が極めて高い」と警鐘を鳴らしたのは当然のことで、災害報道に力を入れるNHKも、7時のニュースのトップでこの大雨特別警報のことを伝えた。これまた、当然の扱いだろう。
ところが、である。NHKが「現場からの報告」として伝えたのは鹿児島市内にある放送局の前からの記者のレポートだった。鹿児島市には大雨の特別警報は出ていない。放送時には雨もほとんど降っていなかった。トンチンカンな「現場からの報告」に唖然とした。
誰も霧島市内に行っていないのである。記者は「霧島市に通じる道路では落石や土砂崩れが発生しており、交通が規制されています」と伝えていた。ならば、せめて「行けるところまで行ってみました。通行はこのように規制されています」という映像があってもよさそうなのに、そうしたものすら放送されなかった。
霧島市は、大昔から火山活動が活発だった霧島連峰の南に広がる。火山灰などの噴出物が分厚く降り積もっており、地盤はきわめて軟弱だ。気象庁の指摘を待つまでもなく、すでに河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生していると考えられるのに、NHKは何の情報もキャッチできていなかった。
「霧島市内に住む人が被災の様子をスマホで撮影しているはず」と考え、チャンネルを民放に切り替えたところ、テレビ朝日が系列の地元局に視聴者から寄せられた動画を流していた。川が濁流となって家屋の土台を削っており、乗用車が流されていた。こうした被害が続発しており、霧島市役所なども混乱状態にある、と考えるのが自然だろう。
近年、事件や事故が起きると、記者がよく「私は安全なところからお伝えしています」と口にする。そんなことは映像を見れば分かるのに、必ずと言っていいほど付け加える。メディアとして、組織のコンプライアンス(法令遵守)にのっとって行動していることをアピールしたいのだろう。
もちろん、記者の命と健康も大事だ。会社として取材のルールを定めて動くのは当然のことである。1991年には雲仙岳の大火砕流で報道関係者を中心に43人が死亡・行方不明になる惨事があった。命をかけてまで取材することを求めるわけにはいかない。
だが、報道する者には可能な限り現場に肉薄し、自分の目で見たもの、知り得たことを伝える使命もある。リスクがあるからと言って近づかなければ、報道の使命を十分に果たすことはできない。要は、記者の命と健康を守ることと報道の使命の妥協点を探る努力を常に続けなければならない、ということだろう。
そうした努力がおざなりになり、メディアに「現場に肉薄する覚悟」が薄れてきたのは何時からか。私は、2011年の東日本大震災が転機だったと考えている。この時、福島原発の爆発事故と放射能の大量流出を受けて、政府は原発から半径30キロ圏内に立ち入らないよう規制した。
報道機関はこれにどう対処したか。東京の主な新聞とテレビの幹部が集まり、各社とも30キロ圏から記者やカメラマンを引き揚げ、立ち入らないことを決めた。その時、30キロ圏内には畜産農家や介護施設の入所者らがまだ多数残っていた。が、彼らの生活や苦悩を取材することを放棄したのである。
放射線量を考慮し、防護服を付けての短時間の取材なら命にかかわることは避けられたにもかかわらず、各社は談合して「原稿より健康が大事」と決め込んだ。そして、みんなでその取り決めを守った。「それはおかしい」と唱え、会社の指示にあらがった者はほとんどいなかった。
この取り決めは、その後の戦争報道や災害取材にも陰に陽に影響を及ぼした。記者とて危ないことはしたくない。会社の幹部も、無理をさせて責任を問われるようなことは避けたい。こうして、「命と使命の妥協点」をさぐる作業はズルズルと命の方に傾き、使命は少しずつ遠ざかっていった。
かくして、台風を取材するのにホテルの部屋からカメラを回し、「安全なところからお伝えしています」とうそぶく記者が登場するに至った。強い風を頬に受け、たたきつける雨に打たれることもない台風取材。それを「おかしい」とも思わないメディア。報道する者がその矜持を失った時、そのツケを払わせられるのは読者であり、視聴者であり、ひいては私たちの社会そのものである。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
*メールマガジン風切通信 133 (2025年8月8日)
≪写真説明&Source≫
霧島市を襲った線状降水帯(Yahoo ニュースのサイトから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/af7666a304b470fc56d115392e185f7b3ee1bb8e
2025年の第12回最上川縦断カヌー探訪は、7月26日に渇水状態の最上川を長井橋から朝日町の上郷ダムまで下り、27日は小国町の赤芝峡を周遊しました。参加者は1日目が34人、2日目が23人。猛暑の中、全員が元気に完漕しました。ご協力いただいたすべての皆様に深く感謝いたします。



≪真鍋賢一さんが撮影・編集した動画≫
▽7月26日(長井橋ー上郷ダム)
▽7月27日(赤芝峡)
≪出発&到着時刻≫
▽7月26日(土)最上川の長井橋から上郷ダムまで24キロ(参加34人)
7時 長井橋のたもとの河川緑地公園で受付、検艇
8時ー9時 参加者がマイカーで上郷ダムに移動、バスで長井橋に戻る
9時30分 長井橋の河川緑地公園の水路から出発



12時20分 黒滝橋手前の河川敷で昼食休憩
13時40分 昼食を終え、河川敷を出発

14時30分 白鷹ヤナ公園(あゆ茶屋)を通過




17時ー17時30分 上郷ダムに到着
▽7月27日(日) 小国町の赤芝峡を周遊(参加23人)
9時 小国町の荒川にある玉川口の駐車場で受付、検艇
9時50分 玉川口の駐車場から赤芝峡に漕ぎ出す
11時50分ー12時10分 玉川口に戻る




≪参加者≫2日間で38人(1日目34人、2日目23人)
▽7月26日(土) 参加34人(長井橋ー上郷ダムの24キロ)
石川毅(山形県村山市)、結城敏宏(山形県米沢市)、林和明(東京都足立区)、阿部明美(山形県天童市)、阿部俊裕(同)、伊東正則(福島県郡山市)、柏倉稔(山形県大江町)、安孫子笑美里(山形県寒河江市)、七海信夫(福島県郡山市)、伊藤隆久(山形市)、佐藤稔(福島県三春町)、佐竹博文(埼玉県戸田市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、鈴木雄也(山形県東根市)、今田飛呂志(同)、中沢崇(長野市)、安部幸男(宮城県柴田町)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、寒河江洋光(盛岡市)、岸浩(福島市)、宮城建夫(神奈川県厚木市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、川添廉介(岩手県北上市)、岩佐和時(東京都狛江市)、阿部悠子(岩手県北上市)、管慎太郎(山形県天童市)、内藤フィリップ邦夫(東京都町田市)、柴田尚宏(山形市)、矢萩剛(山形県村山市)、馬場先詩織(山形県東根市)

▽7月27日(日) 参加23人(1日目参加の34人のうち19人と2日目のみ参加の次の4人)小国町の赤芝峡
増川かな(山形県天童市)、増川舜基(同)、池田丈人(山形県酒田市)、渡辺政幸(山形県寒河江市)

*最年少は川添廉介さん(7歳、小学1年)、最ベテランは清水孝治さん(84歳)

≪参加者の地域別内訳≫
山形県内 18人(天童5人、東根3人、山形・村山・寒河江各2人、酒田・米沢・尾花沢・大江各1人)
県外 20人(福島4人、岩手・群馬・東京・神奈川各3人、宮城・栃木・埼玉・長野各1人)
≪第1回―第12回の参加者≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人
第10回(2022年)45人、第11回(2023年)37人、第12回(2025年)38人
≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、赤芝発電所、
長井市、朝日町、小国町
≪第12回カヌー探訪の記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 佐竹久▽佐竹恵子▽白田金之助▽長岡典巳▽長岡位久子▽長岡昇▽長岡佳子
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪写真撮影≫ 長岡典巳、寒河江洋光、佐竹久
≪動画提供≫
≪受付設営・交通案内板設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助、長岡昇・佳子
≪尾花沢スイカの提供≫斉藤栄司
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
≪カヌー探訪の歩み≫
・第1回 2012年7月28日 長井橋ー上郷ダム(朝日町)24キロ 24人(2日間で)
7月29日 朝日町ー長崎大橋(中山町)29キロ
*2013年は大雨のため開催中止
・第2回 2014年7月26日 朝日町雪谷ー長崎大橋(中山町) 28キロ 35人(同)
7月27日 長崎大橋ー村山市の碁点橋 20キロ
・第3回 2015年7月25日 朝日町雪谷ー長崎大橋 28キロ 30人(同)
7月26日 碁点橋ー大石田河岸(かし) 20キロ
・第4回 2016年7月30日 朝日町雪谷ー寒河江市ゆーチェリー 23キロ 31人(同)
7月31日 大石田ー猿羽根大橋(尾花沢市) 19キロ
・第5回 2017年7月29日 予定変更し、大江町ー長崎大橋(中山町) 10キロ 13人
7月30日 最上川が増水したため中止
・第6回 2018年7月28日 朝日町雪谷ー朝日町栗木沢 8キロ 26人(2日間で)
7月29日 猿羽根大橋(尾花沢市)ー新庄市本合海 20キロ
・第7回 2019年7月27日 新庄市本合海ー戸沢村古口 18キロ 35人
・第8回 2020年7月25日 戸沢村古口ーさみだれ大堰 ―庄内大橋 20キロ 45人
・第9回 2021年7月31日 庄内橋(庄内町)ー出羽大橋(酒田市) 13キロ 49人
・第10回 2022年7月30日 朝日町雪谷ー大江町おしん筏下りロケ地 15キロ
7月31日 長井ダム湖の三淵渓谷 45人(2日間で)
・第11回 2023年7月29日 村山市の碁点橋ー大石田河岸 20キロ
7月30日 寒河江ダムの月山湖 37人(2日間で)
*2024年は大雨のため開催中止
・第12回 2025年7月26日 長井橋ー上郷ダム(朝日町) 24キロ
7月27日 小国町の赤芝峡 38人(2日間で)



≪真鍋賢一さんが撮影・編集した動画≫
▽7月26日(長井橋ー上郷ダム)
▽7月27日(赤芝峡)
≪出発&到着時刻≫
▽7月26日(土)最上川の長井橋から上郷ダムまで24キロ(参加34人)
7時 長井橋のたもとの河川緑地公園で受付、検艇
8時ー9時 参加者がマイカーで上郷ダムに移動、バスで長井橋に戻る
9時30分 長井橋の河川緑地公園の水路から出発



12時20分 黒滝橋手前の河川敷で昼食休憩
13時40分 昼食を終え、河川敷を出発

14時30分 白鷹ヤナ公園(あゆ茶屋)を通過




17時ー17時30分 上郷ダムに到着
▽7月27日(日) 小国町の赤芝峡を周遊(参加23人)
9時 小国町の荒川にある玉川口の駐車場で受付、検艇
9時50分 玉川口の駐車場から赤芝峡に漕ぎ出す
11時50分ー12時10分 玉川口に戻る




≪参加者≫2日間で38人(1日目34人、2日目23人)
▽7月26日(土) 参加34人(長井橋ー上郷ダムの24キロ)
石川毅(山形県村山市)、結城敏宏(山形県米沢市)、林和明(東京都足立区)、阿部明美(山形県天童市)、阿部俊裕(同)、伊東正則(福島県郡山市)、柏倉稔(山形県大江町)、安孫子笑美里(山形県寒河江市)、七海信夫(福島県郡山市)、伊藤隆久(山形市)、佐藤稔(福島県三春町)、佐竹博文(埼玉県戸田市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、鈴木雄也(山形県東根市)、今田飛呂志(同)、中沢崇(長野市)、安部幸男(宮城県柴田町)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、寒河江洋光(盛岡市)、岸浩(福島市)、宮城建夫(神奈川県厚木市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、川添廉介(岩手県北上市)、岩佐和時(東京都狛江市)、阿部悠子(岩手県北上市)、管慎太郎(山形県天童市)、内藤フィリップ邦夫(東京都町田市)、柴田尚宏(山形市)、矢萩剛(山形県村山市)、馬場先詩織(山形県東根市)

▽7月27日(日) 参加23人(1日目参加の34人のうち19人と2日目のみ参加の次の4人)小国町の赤芝峡
増川かな(山形県天童市)、増川舜基(同)、池田丈人(山形県酒田市)、渡辺政幸(山形県寒河江市)

*最年少は川添廉介さん(7歳、小学1年)、最ベテランは清水孝治さん(84歳)

≪参加者の地域別内訳≫
山形県内 18人(天童5人、東根3人、山形・村山・寒河江各2人、酒田・米沢・尾花沢・大江各1人)
県外 20人(福島4人、岩手・群馬・東京・神奈川各3人、宮城・栃木・埼玉・長野各1人)
≪第1回―第12回の参加者≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人
第10回(2022年)45人、第11回(2023年)37人、第12回(2025年)38人
≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、赤芝発電所、
長井市、朝日町、小国町
≪第12回カヌー探訪の記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 佐竹久▽佐竹恵子▽白田金之助▽長岡典巳▽長岡位久子▽長岡昇▽長岡佳子
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪写真撮影≫ 長岡典巳、寒河江洋光、佐竹久
≪動画提供≫
≪受付設営・交通案内板設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助、長岡昇・佳子
≪尾花沢スイカの提供≫斉藤栄司
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
≪カヌー探訪の歩み≫
・第1回 2012年7月28日 長井橋ー上郷ダム(朝日町)24キロ 24人(2日間で)
7月29日 朝日町ー長崎大橋(中山町)29キロ
*2013年は大雨のため開催中止
・第2回 2014年7月26日 朝日町雪谷ー長崎大橋(中山町) 28キロ 35人(同)
7月27日 長崎大橋ー村山市の碁点橋 20キロ
・第3回 2015年7月25日 朝日町雪谷ー長崎大橋 28キロ 30人(同)
7月26日 碁点橋ー大石田河岸(かし) 20キロ
・第4回 2016年7月30日 朝日町雪谷ー寒河江市ゆーチェリー 23キロ 31人(同)
7月31日 大石田ー猿羽根大橋(尾花沢市) 19キロ
・第5回 2017年7月29日 予定変更し、大江町ー長崎大橋(中山町) 10キロ 13人
7月30日 最上川が増水したため中止
・第6回 2018年7月28日 朝日町雪谷ー朝日町栗木沢 8キロ 26人(2日間で)
7月29日 猿羽根大橋(尾花沢市)ー新庄市本合海 20キロ
・第7回 2019年7月27日 新庄市本合海ー戸沢村古口 18キロ 35人
・第8回 2020年7月25日 戸沢村古口ーさみだれ大堰 ―庄内大橋 20キロ 45人
・第9回 2021年7月31日 庄内橋(庄内町)ー出羽大橋(酒田市) 13キロ 49人
・第10回 2022年7月30日 朝日町雪谷ー大江町おしん筏下りロケ地 15キロ
7月31日 長井ダム湖の三淵渓谷 45人(2日間で)
・第11回 2023年7月29日 村山市の碁点橋ー大石田河岸 20キロ
7月30日 寒河江ダムの月山湖 37人(2日間で)
*2024年は大雨のため開催中止
・第12回 2025年7月26日 長井橋ー上郷ダム(朝日町) 24キロ
7月27日 小国町の赤芝峡 38人(2日間で)
令和の米騒動の報道が冴えない。冴えなくて当たり前なのかもしれない。主要メディアには「農林水産業を専門に取材する記者」は、今やほとんどいない。日頃きちんと取材していないから、急に米価が高騰し、政府備蓄米の売却が決まっても、「コメの流通って、そもそもどうなってるの」という初歩から取材を始めるしかないからだろう。

「コメの値段がこんなに上がっています」と現状を伝え、「備蓄米を放出したのに店頭に出てきません。値段はまだ上がっています」と、事態の推移をただ伝えるだけ。小泉進次郎氏が農水相になり、備蓄米を随意契約で売却した結果、すみやかにスーパーの店頭に並ぶと、それをパパラッチのように追いかけて映像を流す。毎日、そんな報道ばかりだ。
戦後の食糧管理制度の変遷と、その中で農業協同組合(JA)と農林水産省が果たしてきた役割を深く知る者なら、今回の米価高騰の元凶は「JAと農水省である」とズバリ指摘し、その核心にギリギリと迫っていくことができるのではないか。
私は農業問題の専門記者ではなかった。「深く知る者」とはとても言えないが、それでも「元凶はJAと農水省」という核心にたどり着くための手がかりくらいは示すことができる。
今回の米価高騰の発端は、昨年8月8日に気象庁が南海トラフ地震の臨時情報(巨大地震注意)を発表したことである。なにせ、被害想定は死者約30万人という大地震だ。それが差し迫っているかのような発表があったのだから、人々があわてふためいたのは当然だろう。
大地震に備えて、多くの人が食料の買いだめに走った。コメを置いているスーパーの棚はほどなく空っぽになった。その後、お盆前後に台風が相次いで襲来し、米作農家が打撃を受けた。「コメの需給が逼迫するのではないか」との観測が強まり、米価の高騰に拍車がかかった。
グラフ1は、2024年(令和6年)産米の相対(あいたい)取引の平均価格がどのように上がっていったかを示したものだ。コメの相対取引とは、JAなどの集荷業者が卸売業者に販売する取引で、玄米60キロ当たりの取引の平均価格を示している。棒グラフは月ごとの取引量である。
2023年(令和5年)産米の9月の相対取引価格は、平均で1万5291円だった。それがグラフに見るように、2024年9月には2万2700円と1.5倍になり、今年の4月には2万7102円とさらに高騰した。JAが卸売業者に販売したコメは二次卸、三次卸を経て小売店に並ぶ。その都度、マージンと流通経費が上乗せされ、小売に並ぶ段階では2倍の値段になってしまったのである。
グラフ2は、2012年(平成24年)産米から2024年(令和6年)産米の相対取引価格の推移を示している。これを見れば、2023年(令和5年)産米までは玄米60キロ当たり1万2000円から1万6000円前後で推移しており、年間を通して安定していたことが分かる。2024年産米だけが9月以降、異様な形で高騰したことがよりハッキリと見て取れる。
JAが収穫時期に農家から買い取る際の仕入れ価格は概算金と呼ばれ、米価が上がれば農家に追加金が支払われるが、それでも米作農家の手取りは2倍にはなっていない。スーパーを含めた小売り段階では競争が激しく、そのマージンは限られている。小売り段階で値段が跳ね上がることは考えられない。要するに、JAをはじめとする集荷業者と大手の卸売業者が「高値相場」を作り出し、しこたま利ザヤを稼いでいるのである。
政府が備蓄米を売却してこの高値が崩れたりしたら、JAも卸売業者も困る。そこで、江藤拓・前農水相は「備蓄米を買った業者は1年以内に同じ量を政府に戻さなければならない」という条件を付けて入札にかけた。こんな条件を付けたら、応札できるのはJAくらいしかない。
かつての食糧管理制度の下では、JAがほぼすべてのコメを集荷し、卸売業者に販売していた。食管制度が廃止になり、コメの流通は自由化されたが、それでもJAは今でもコメの全流通量の4割を扱っており、最大の集荷業者である。競争入札なら備蓄米を高値で落札して独占し、市場に流すのも遅らせれば、高値を維持できる。そうやって利ザヤを稼ぎ続けるつもりだったのだろう。農水省の官僚たちも「それで構わない」と考えたはずだ。なにせ、トップの大臣が「(コメを)買ったことがありません。支援者の方がたくさん下さるので」と平気で言う人物なのだから。
そこに、JAや農水省の思惑など気にしない小泉進次郎氏が登場し、「備蓄米を随意契約で売る」「コメが5キロ2000円で売られるようにする」と宣言し、実現してしまった。JAも農水省も心穏やかではいられない。今の高値が崩れれば、JAも卸売業者も大損する恐れがあるからだ。そうなると頼れるのは、自民党の農水族しかない。
さっそく、野村哲郎・元農水相が「(随意契約による備蓄米の売却は)自民党の了承を得ていない。ルールを覚えていただかなきゃいかん」と小泉氏に苦言を呈した。農水省出身の鈴木憲和・復興副大臣は「国がやるべきことは備蓄米の放出ではない。すべての国民に平等に行き渡るようにすることだ」と、トンチンカンな発言で随意契約による売却に異を唱えた。
普通の市民にとって、主食のコメが倍の値段になるということは大変なことだ。とりわけ、所得の低い人ほど打撃が大きい。こういう発言をする政治家はその切なさがまるで分かっていない。自分の支持母体であるJAとこれを支える農水省のことしか頭にないようだ。
その農水省の幹部も、コメを作っている農民のことやこれを食べる人たちのことなど気にしていない。農水省の本川一善・事務次官はJA全農の経営管理委員に天下った(2017年)。荒川隆・官房長も2020年にその後任として同じポストに就いた。「退職後にお世話になるところに不利なことなどできません」というのが本音だろう。
日本の農業の未来を見据え、この国の食糧安全保障に心を砕く官僚は農水省には一人もいないのか。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年6月5日)
https://news-hunter.org/?p=27099
≪注≫グラフ1、2はいずれも農水省のサイトから抜粋
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/aitaikakaku-392.pdf
≪写真説明≫
神奈川の備蓄倉庫を視察する小泉進次郎農水相(ロイター/アフロ)
https://www.j-cast.com/2025/06/02504848.html
≪参考サイト≫
◎『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し(三菱総合研究所、稲垣公雄)
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html
◎『令和のコメ騒動』(2)コメ価格の一般的な決まり方(同)
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311.html
◎農林水産省における天下りの実態調査報告
https://note.com/pure_skink5267/n/nc3974f015019

「コメの値段がこんなに上がっています」と現状を伝え、「備蓄米を放出したのに店頭に出てきません。値段はまだ上がっています」と、事態の推移をただ伝えるだけ。小泉進次郎氏が農水相になり、備蓄米を随意契約で売却した結果、すみやかにスーパーの店頭に並ぶと、それをパパラッチのように追いかけて映像を流す。毎日、そんな報道ばかりだ。
戦後の食糧管理制度の変遷と、その中で農業協同組合(JA)と農林水産省が果たしてきた役割を深く知る者なら、今回の米価高騰の元凶は「JAと農水省である」とズバリ指摘し、その核心にギリギリと迫っていくことができるのではないか。
私は農業問題の専門記者ではなかった。「深く知る者」とはとても言えないが、それでも「元凶はJAと農水省」という核心にたどり着くための手がかりくらいは示すことができる。
今回の米価高騰の発端は、昨年8月8日に気象庁が南海トラフ地震の臨時情報(巨大地震注意)を発表したことである。なにせ、被害想定は死者約30万人という大地震だ。それが差し迫っているかのような発表があったのだから、人々があわてふためいたのは当然だろう。
大地震に備えて、多くの人が食料の買いだめに走った。コメを置いているスーパーの棚はほどなく空っぽになった。その後、お盆前後に台風が相次いで襲来し、米作農家が打撃を受けた。「コメの需給が逼迫するのではないか」との観測が強まり、米価の高騰に拍車がかかった。
グラフ1は、2024年(令和6年)産米の相対(あいたい)取引の平均価格がどのように上がっていったかを示したものだ。コメの相対取引とは、JAなどの集荷業者が卸売業者に販売する取引で、玄米60キロ当たりの取引の平均価格を示している。棒グラフは月ごとの取引量である。
2023年(令和5年)産米の9月の相対取引価格は、平均で1万5291円だった。それがグラフに見るように、2024年9月には2万2700円と1.5倍になり、今年の4月には2万7102円とさらに高騰した。JAが卸売業者に販売したコメは二次卸、三次卸を経て小売店に並ぶ。その都度、マージンと流通経費が上乗せされ、小売に並ぶ段階では2倍の値段になってしまったのである。
グラフ2は、2012年(平成24年)産米から2024年(令和6年)産米の相対取引価格の推移を示している。これを見れば、2023年(令和5年)産米までは玄米60キロ当たり1万2000円から1万6000円前後で推移しており、年間を通して安定していたことが分かる。2024年産米だけが9月以降、異様な形で高騰したことがよりハッキリと見て取れる。
JAが収穫時期に農家から買い取る際の仕入れ価格は概算金と呼ばれ、米価が上がれば農家に追加金が支払われるが、それでも米作農家の手取りは2倍にはなっていない。スーパーを含めた小売り段階では競争が激しく、そのマージンは限られている。小売り段階で値段が跳ね上がることは考えられない。要するに、JAをはじめとする集荷業者と大手の卸売業者が「高値相場」を作り出し、しこたま利ザヤを稼いでいるのである。
政府が備蓄米を売却してこの高値が崩れたりしたら、JAも卸売業者も困る。そこで、江藤拓・前農水相は「備蓄米を買った業者は1年以内に同じ量を政府に戻さなければならない」という条件を付けて入札にかけた。こんな条件を付けたら、応札できるのはJAくらいしかない。
かつての食糧管理制度の下では、JAがほぼすべてのコメを集荷し、卸売業者に販売していた。食管制度が廃止になり、コメの流通は自由化されたが、それでもJAは今でもコメの全流通量の4割を扱っており、最大の集荷業者である。競争入札なら備蓄米を高値で落札して独占し、市場に流すのも遅らせれば、高値を維持できる。そうやって利ザヤを稼ぎ続けるつもりだったのだろう。農水省の官僚たちも「それで構わない」と考えたはずだ。なにせ、トップの大臣が「(コメを)買ったことがありません。支援者の方がたくさん下さるので」と平気で言う人物なのだから。
そこに、JAや農水省の思惑など気にしない小泉進次郎氏が登場し、「備蓄米を随意契約で売る」「コメが5キロ2000円で売られるようにする」と宣言し、実現してしまった。JAも農水省も心穏やかではいられない。今の高値が崩れれば、JAも卸売業者も大損する恐れがあるからだ。そうなると頼れるのは、自民党の農水族しかない。
さっそく、野村哲郎・元農水相が「(随意契約による備蓄米の売却は)自民党の了承を得ていない。ルールを覚えていただかなきゃいかん」と小泉氏に苦言を呈した。農水省出身の鈴木憲和・復興副大臣は「国がやるべきことは備蓄米の放出ではない。すべての国民に平等に行き渡るようにすることだ」と、トンチンカンな発言で随意契約による売却に異を唱えた。
普通の市民にとって、主食のコメが倍の値段になるということは大変なことだ。とりわけ、所得の低い人ほど打撃が大きい。こういう発言をする政治家はその切なさがまるで分かっていない。自分の支持母体であるJAとこれを支える農水省のことしか頭にないようだ。
その農水省の幹部も、コメを作っている農民のことやこれを食べる人たちのことなど気にしていない。農水省の本川一善・事務次官はJA全農の経営管理委員に天下った(2017年)。荒川隆・官房長も2020年にその後任として同じポストに就いた。「退職後にお世話になるところに不利なことなどできません」というのが本音だろう。
日本の農業の未来を見据え、この国の食糧安全保障に心を砕く官僚は農水省には一人もいないのか。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年6月5日)
https://news-hunter.org/?p=27099
≪注≫グラフ1、2はいずれも農水省のサイトから抜粋
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/aitaikakaku-392.pdf
≪写真説明≫
神奈川の備蓄倉庫を視察する小泉進次郎農水相(ロイター/アフロ)
https://www.j-cast.com/2025/06/02504848.html
≪参考サイト≫
◎『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し(三菱総合研究所、稲垣公雄)
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html
◎『令和のコメ騒動』(2)コメ価格の一般的な決まり方(同)
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311.html
◎農林水産省における天下りの実態調査報告
https://note.com/pure_skink5267/n/nc3974f015019
文は人なり、という。文章からは、それを書いた人の教養と学識に加えて、人柄や性格までにじみ出てくる。そうしたものが分からないように取りつくろい、ごまかそうとしても隠しきれるものではない。
そういう目で、前回のコラムで紹介した京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)が出した嘆願書を読んだ時、にじみ出てくるものは何か。明治維新を機に「穢多(えた)という名分をなくしていただきたい」と願い出たこの文書の随所に、私は「篤実さ」を感じる。

嘆願書は、幕末の激動から戊辰戦争を経て発足した新政府に対して、明治3年(1870年)の初めに提出されたものだ。蓮台野の人々のルーツについて「私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました」と記し、東北から西に連れてこられた祖先が応神天皇や安康天皇の時代をどう生き抜いたかについて叙述した冒頭部分は、極めて興味深い。
これを「史実を踏まえた祖先の苦難の物語」と見るか、それとも「天皇との結び付きの古さを印象づけるための創作・捏造」と捉えるか。この点については、前回も指摘したように見解が分かれるところだろうが、その点はひとまず置いて、嘆願書の内容を筆者の現代語訳を通してさらに紹介したい。第4段落は次のように続く。
古くから小法師(こぼし)として、私どもの村から常は二、三人、
用の多い時には八人まで、御所の掃除役を仰せつけられ、築地内に
部屋をいただいて日々出勤し、扶持もいただいておりました。年始
や八月一日には、未明から麻裃(あさがみしも)に御紋付きの箱提
灯を持ってご挨拶し、下され物がありました。奏者所では青緡(あお
ざし)銭三貫文、長橋局では白木綿一疋、台所では雑煮をいただき、
七日には七草餅、十五日には小豆粥、その他、五日、六日、十四日に
は穂長汁をいただきました。
「小法師」とは、普通は「若い僧侶」を意味する。福島県会津地方の民芸品「起き上がり小法師」がその例で、七転び八起きの縁起物として知られる。だが、ここでは「中世から近世にかけて、御所(ごしょ)の庭園の清掃や植栽をしていた賤民」を意味する。
京都の被差別部落の歴史に詳しい元京都文化短期大学教授の辻ミチ子によれば、蓮台野村の人たちは江戸時代には京都の奉行所の配下で働き、牢屋の番人もしていた。葬送や皮革の仕事に携わる人たちがいて、御所の掃除をする人たちもいた。
京都の御所には、正門の建礼門をはじめ六つの門がある。このうち、警護の武士や宮中に品物を納める業者が通ったのが西側の清所(せいしょ)門(冒頭の写真)で、蓮台野の人たちもこの門から出入りしていた。奏者所とは天皇への奏上を取り次ぐ部署、長橋局(つぼね)は女官長がいるところで、これらが小法師として働く人たちの窓口になった(図は御所の中央部分)。
次の第5段落には、新政府が発足して御所を京都から東京に移すことが決まり、それに伴って蓮台野の人たちも振り回されたことが記されている。
年頭に小法師より差し上げておりました藁箒(わらぼうき)は
例年、正月二日早朝に儀式があり、その飾り付けの一品でした。
これまでは年始と八朔(はっさく)に数家族が献上しておりま
した。昨年の巳年(明治二年)の春からたぶん廃止になるとの
ことでしたが、藁箒については旧例通り献上するようにとのご
沙汰がありましたので、そういたしております。昨年の冬のご
沙汰では、例年正月二日に差し上げていた藁箒のうち、天皇家
に献上いたします「七つの子」の祝いの分については東京に回
されるとのことですので、十二月十二日までに差し上げるよう
仰せつかり、期限通りに献納いたしました。
幕末の動乱から戊辰戦争へと至る過程で、倒幕の主力となったのは薩摩藩と長州藩である。薩摩の西郷隆盛と大久保利通(としみち)、長州の木戸孝允(たかよし)を「維新の三傑」と呼ぶのはそれを象徴するもので、これに土佐藩と肥前藩の有力者、尊王攘夷派の公家の岩倉具視(ともみ)や三条実美(さねとみ)らを加えた人たちが新政府の方針を決めていった。
慶応4年3月(旧暦)に「五箇条の誓文」の素案の一部を削り、「旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ」という項目を加えて成案にしたのは木戸孝允とされる。この時、孝明天皇の後を継いで即位したばかりの睦仁(むつひと)は満15歳。政治の流れを左右する力はなかった。公家たちの強硬な反対を押し切り、天皇の江戸への行幸と遷都を決めたのも薩長土肥の面々だった。
遷都への抵抗があまりにも大きかったため、新政府は遷都ではなく、「東京奠都(てんと)」という表現を使った。遷都となると、古い都は廃される。一方、奠都は「新しい都を定める」という意味で、「帝都は東京と京都の二つである」というニュアンスを持つ。遷都に反対する公家と京都府民を難しい言葉を使って、なだめたのである。
御所が京都から東京に移るとなれば、蓮台野村の人たちにとっては一大事である。御所に献納していた藁箒(わらぼうき)のことを長々と書いているのは、この間の混乱と先行きへの不安を示すものだろう。江戸の浅草には、関東一円の穢多・非人を支配する弾左衛門(だんざえもん)という頭領がいた。弾左衛門は江戸幕府が長州征伐に乗り出せば、これに協力した。鳥羽・伏見の戦いの後も幕府軍に兵糧を出したりしたが、江戸城明け渡しと決まった途端、官軍に寝返って生き残りを図った。
天皇が江戸城に移った後、その城の掃除役は誰が勤めるのか。蓮台野の人たちと弾左衛門の配下との間で激しい綱引きが繰り広げられたはずである。この段落の「藁箒」についての記述は、両者の間で綱引きがあったことを間接的に示すものだろう(その結末を知りたいところだが、それに触れた文献はまだ見ていない)。
嘆願書の最後の段落にも、被差別部落の起源に関わる重要な記述がある。
私どもの村々の者は多くが殺業に携わってきましたが、仏教が
国内に広まるにつれて世間は殺生を忌み嫌うようになり、足利
幕府の頃、誰とは分かりませんが、穢多(えた)という字を付
けるようになったとのことです。『閑田耕筆』には穢多と称する
のは「餌取(えと)り」のこととあり、また『和名抄』では
「屠者恵止利」と記し、人倫漁猟の部に加えています。そし
て、穢多というのは屠者で今の漁師のことなどともあります
が、穢多と言えば人外異物のようにいやしめられ、とりわけ
町との交際もだんだんとすたれていったのは実に残念なこと
だと、村々の者たちは悲観しております。
仏教が日本に伝わり、広まったのは6世紀ごろとされる。これは歴史学者の間であまり異論がない。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先は仏教が広まるにつれて忌み嫌われるようになり、室町時代には「穢多」という字を付けられ、賤視されるようになっていった、と記している。これは「被差別部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断統治するため政治的に作られたもの」とする近世政治起源説を真っ向から否定する内容である。
近世政治起源説を唱えた大学の教授たちがそろって、この元右衛門の嘆願書に触れようとせず黙殺し続けたのは、ある意味、当然だったのかもしれない。また、私がこの嘆願書の存在に気づくまで何年もかかってしまったのも理由のないことではなかった。
最後の段落には、蓮台野を含む差別にさらされ続けた人たちの切ないまでの思いがあふれている。
今般の王政復古はありがたくも庶民を慈しむことを第一に
されるとのこと、恐れ多いことと存じております。とりわけ
旧弊を一掃されるとのことで、私どもの村々の者に至るまで
神州の民となりました。穢多という名称があるのは何とも嘆
かわしいことです。獣類や皮革の品物を取り扱う仕事をして
いる者もありますけれども、これもまた国家の一端を担う仕
事であります。田舎では多くの者は農業だけで暮らしており、
右のような品物を取り扱っている者はございません。なにと
ぞ、昔からの穢多という名分をなくし、士民と同じように取
り扱ってくださるよう伏して嘆願いたします。
近世政治起源説を唱えた研究者の多くはマルクス主義に基づく革命理論を支えとし、「被差別部落の人たちは労働者や農民と共に変革に起ち上がるべきだ」という信念を抱いていた。そのためには「やっかいな天皇制と被差別部落の関わり」については避けて通りたい。「豊臣秀吉や徳川家康が部落を作ったのだ」と唱える方が分かりやすい。その方が差別の解消を求める部落解放同盟にとっても都合が良かった。
歴史と真摯に向き合うことを放棄し、自らが信じるイデオロギーのために学問を利用する――そのような者たちが打ち立てた学説が峻厳な歴史の審判に耐えられるはずもなかった。1980年代以降に中世史や古代史の研究が進むにつれて学説として破綻し、見向きもされなくなったのは当然の報いと言うべきだろう。
だが、小学校や中学校で推進された「同和教育」で部落の歴史を学んだ人たちの中には、今でも「部落は近世になってから支配階級が政治的に作り出したもの」と信じている人が少なくない。社会に出てから被差別部落のことを学び直す機会は滅多にないからだ。
同和対策事業の一環として公金を使って教材を作り、誤ったことを長年にわたって教え続けた罪は償いようもない。これから長い時間をかけて誤りを正し、まっとうなことを広めていくしかない。イデオロギーにからめとられることの怖さをあらためて思う。
(敬称略)
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年5月29日)
【元右衛門の嘆願書の現代語訳】
【元右衛門の嘆願書の原文】
【参照】
*蓮台野の元右衛門の嘆願書についての前回のコラム12(末尾に連載の各回へのリンク)
・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
≪写真&図の説明≫
◎京都御所の清所門(せいしょもん)=「旅と歴史」サイトから
https://blog.goo.ne.jp/ogino_2006/e/05cdb4c28cef5a746e1fc5f8231fe0d4
◎御所の中央部にある奏者所と長橋局(伊藤之雄『明治天皇』から複写)
≪参考文献&サイト≫
◎辻ミチ子「近世 蓮台野村の歴史 ―甚右衛門から元右衛門―」(2009年度部落史連続講座講演録<京都部落問題研究資料センター>所収)
http://shiryo.suishinkyoukai.jp/kouza/k_pdf/2009.pdf
◎『京都の部落史 2近現代』(京都部落史研究所、1991年)
◎『有識故実から学ぶ 年中行事百科』(八條忠基、淡交社、2022年)
◎『明治天皇』(伊藤之雄、ミネルヴァ書房、2006年)
◎『明治天皇の生涯(上)』(童門冬二、三笠書房、1991年)
◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)
そういう目で、前回のコラムで紹介した京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)が出した嘆願書を読んだ時、にじみ出てくるものは何か。明治維新を機に「穢多(えた)という名分をなくしていただきたい」と願い出たこの文書の随所に、私は「篤実さ」を感じる。

嘆願書は、幕末の激動から戊辰戦争を経て発足した新政府に対して、明治3年(1870年)の初めに提出されたものだ。蓮台野の人々のルーツについて「私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました」と記し、東北から西に連れてこられた祖先が応神天皇や安康天皇の時代をどう生き抜いたかについて叙述した冒頭部分は、極めて興味深い。
これを「史実を踏まえた祖先の苦難の物語」と見るか、それとも「天皇との結び付きの古さを印象づけるための創作・捏造」と捉えるか。この点については、前回も指摘したように見解が分かれるところだろうが、その点はひとまず置いて、嘆願書の内容を筆者の現代語訳を通してさらに紹介したい。第4段落は次のように続く。
古くから小法師(こぼし)として、私どもの村から常は二、三人、
用の多い時には八人まで、御所の掃除役を仰せつけられ、築地内に
部屋をいただいて日々出勤し、扶持もいただいておりました。年始
や八月一日には、未明から麻裃(あさがみしも)に御紋付きの箱提
灯を持ってご挨拶し、下され物がありました。奏者所では青緡(あお
ざし)銭三貫文、長橋局では白木綿一疋、台所では雑煮をいただき、
七日には七草餅、十五日には小豆粥、その他、五日、六日、十四日に
は穂長汁をいただきました。
「小法師」とは、普通は「若い僧侶」を意味する。福島県会津地方の民芸品「起き上がり小法師」がその例で、七転び八起きの縁起物として知られる。だが、ここでは「中世から近世にかけて、御所(ごしょ)の庭園の清掃や植栽をしていた賤民」を意味する。
京都の被差別部落の歴史に詳しい元京都文化短期大学教授の辻ミチ子によれば、蓮台野村の人たちは江戸時代には京都の奉行所の配下で働き、牢屋の番人もしていた。葬送や皮革の仕事に携わる人たちがいて、御所の掃除をする人たちもいた。
京都の御所には、正門の建礼門をはじめ六つの門がある。このうち、警護の武士や宮中に品物を納める業者が通ったのが西側の清所(せいしょ)門(冒頭の写真)で、蓮台野の人たちもこの門から出入りしていた。奏者所とは天皇への奏上を取り次ぐ部署、長橋局(つぼね)は女官長がいるところで、これらが小法師として働く人たちの窓口になった(図は御所の中央部分)。
次の第5段落には、新政府が発足して御所を京都から東京に移すことが決まり、それに伴って蓮台野の人たちも振り回されたことが記されている。
年頭に小法師より差し上げておりました藁箒(わらぼうき)は
例年、正月二日早朝に儀式があり、その飾り付けの一品でした。
これまでは年始と八朔(はっさく)に数家族が献上しておりま
した。昨年の巳年(明治二年)の春からたぶん廃止になるとの
ことでしたが、藁箒については旧例通り献上するようにとのご
沙汰がありましたので、そういたしております。昨年の冬のご
沙汰では、例年正月二日に差し上げていた藁箒のうち、天皇家
に献上いたします「七つの子」の祝いの分については東京に回
されるとのことですので、十二月十二日までに差し上げるよう
仰せつかり、期限通りに献納いたしました。
幕末の動乱から戊辰戦争へと至る過程で、倒幕の主力となったのは薩摩藩と長州藩である。薩摩の西郷隆盛と大久保利通(としみち)、長州の木戸孝允(たかよし)を「維新の三傑」と呼ぶのはそれを象徴するもので、これに土佐藩と肥前藩の有力者、尊王攘夷派の公家の岩倉具視(ともみ)や三条実美(さねとみ)らを加えた人たちが新政府の方針を決めていった。
慶応4年3月(旧暦)に「五箇条の誓文」の素案の一部を削り、「旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ」という項目を加えて成案にしたのは木戸孝允とされる。この時、孝明天皇の後を継いで即位したばかりの睦仁(むつひと)は満15歳。政治の流れを左右する力はなかった。公家たちの強硬な反対を押し切り、天皇の江戸への行幸と遷都を決めたのも薩長土肥の面々だった。
遷都への抵抗があまりにも大きかったため、新政府は遷都ではなく、「東京奠都(てんと)」という表現を使った。遷都となると、古い都は廃される。一方、奠都は「新しい都を定める」という意味で、「帝都は東京と京都の二つである」というニュアンスを持つ。遷都に反対する公家と京都府民を難しい言葉を使って、なだめたのである。
御所が京都から東京に移るとなれば、蓮台野村の人たちにとっては一大事である。御所に献納していた藁箒(わらぼうき)のことを長々と書いているのは、この間の混乱と先行きへの不安を示すものだろう。江戸の浅草には、関東一円の穢多・非人を支配する弾左衛門(だんざえもん)という頭領がいた。弾左衛門は江戸幕府が長州征伐に乗り出せば、これに協力した。鳥羽・伏見の戦いの後も幕府軍に兵糧を出したりしたが、江戸城明け渡しと決まった途端、官軍に寝返って生き残りを図った。
天皇が江戸城に移った後、その城の掃除役は誰が勤めるのか。蓮台野の人たちと弾左衛門の配下との間で激しい綱引きが繰り広げられたはずである。この段落の「藁箒」についての記述は、両者の間で綱引きがあったことを間接的に示すものだろう(その結末を知りたいところだが、それに触れた文献はまだ見ていない)。
嘆願書の最後の段落にも、被差別部落の起源に関わる重要な記述がある。
私どもの村々の者は多くが殺業に携わってきましたが、仏教が
国内に広まるにつれて世間は殺生を忌み嫌うようになり、足利
幕府の頃、誰とは分かりませんが、穢多(えた)という字を付
けるようになったとのことです。『閑田耕筆』には穢多と称する
のは「餌取(えと)り」のこととあり、また『和名抄』では
「屠者恵止利」と記し、人倫漁猟の部に加えています。そし
て、穢多というのは屠者で今の漁師のことなどともあります
が、穢多と言えば人外異物のようにいやしめられ、とりわけ
町との交際もだんだんとすたれていったのは実に残念なこと
だと、村々の者たちは悲観しております。
仏教が日本に伝わり、広まったのは6世紀ごろとされる。これは歴史学者の間であまり異論がない。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先は仏教が広まるにつれて忌み嫌われるようになり、室町時代には「穢多」という字を付けられ、賤視されるようになっていった、と記している。これは「被差別部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断統治するため政治的に作られたもの」とする近世政治起源説を真っ向から否定する内容である。
近世政治起源説を唱えた大学の教授たちがそろって、この元右衛門の嘆願書に触れようとせず黙殺し続けたのは、ある意味、当然だったのかもしれない。また、私がこの嘆願書の存在に気づくまで何年もかかってしまったのも理由のないことではなかった。
最後の段落には、蓮台野を含む差別にさらされ続けた人たちの切ないまでの思いがあふれている。
今般の王政復古はありがたくも庶民を慈しむことを第一に
されるとのこと、恐れ多いことと存じております。とりわけ
旧弊を一掃されるとのことで、私どもの村々の者に至るまで
神州の民となりました。穢多という名称があるのは何とも嘆
かわしいことです。獣類や皮革の品物を取り扱う仕事をして
いる者もありますけれども、これもまた国家の一端を担う仕
事であります。田舎では多くの者は農業だけで暮らしており、
右のような品物を取り扱っている者はございません。なにと
ぞ、昔からの穢多という名分をなくし、士民と同じように取
り扱ってくださるよう伏して嘆願いたします。
近世政治起源説を唱えた研究者の多くはマルクス主義に基づく革命理論を支えとし、「被差別部落の人たちは労働者や農民と共に変革に起ち上がるべきだ」という信念を抱いていた。そのためには「やっかいな天皇制と被差別部落の関わり」については避けて通りたい。「豊臣秀吉や徳川家康が部落を作ったのだ」と唱える方が分かりやすい。その方が差別の解消を求める部落解放同盟にとっても都合が良かった。
歴史と真摯に向き合うことを放棄し、自らが信じるイデオロギーのために学問を利用する――そのような者たちが打ち立てた学説が峻厳な歴史の審判に耐えられるはずもなかった。1980年代以降に中世史や古代史の研究が進むにつれて学説として破綻し、見向きもされなくなったのは当然の報いと言うべきだろう。
だが、小学校や中学校で推進された「同和教育」で部落の歴史を学んだ人たちの中には、今でも「部落は近世になってから支配階級が政治的に作り出したもの」と信じている人が少なくない。社会に出てから被差別部落のことを学び直す機会は滅多にないからだ。
同和対策事業の一環として公金を使って教材を作り、誤ったことを長年にわたって教え続けた罪は償いようもない。これから長い時間をかけて誤りを正し、まっとうなことを広めていくしかない。イデオロギーにからめとられることの怖さをあらためて思う。
(敬称略)
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年5月29日)
【元右衛門の嘆願書の現代語訳】
【元右衛門の嘆願書の原文】
【参照】
*蓮台野の元右衛門の嘆願書についての前回のコラム12(末尾に連載の各回へのリンク)
・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
≪写真&図の説明≫
◎京都御所の清所門(せいしょもん)=「旅と歴史」サイトから
https://blog.goo.ne.jp/ogino_2006/e/05cdb4c28cef5a746e1fc5f8231fe0d4
◎御所の中央部にある奏者所と長橋局(伊藤之雄『明治天皇』から複写)
≪参考文献&サイト≫
◎辻ミチ子「近世 蓮台野村の歴史 ―甚右衛門から元右衛門―」(2009年度部落史連続講座講演録<京都部落問題研究資料センター>所収)
http://shiryo.suishinkyoukai.jp/kouza/k_pdf/2009.pdf
◎『京都の部落史 2近現代』(京都部落史研究所、1991年)
◎『有識故実から学ぶ 年中行事百科』(八條忠基、淡交社、2022年)
◎『明治天皇』(伊藤之雄、ミネルヴァ書房、2006年)
◎『明治天皇の生涯(上)』(童門冬二、三笠書房、1991年)
◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)
森友学園では幼稚園児に毎朝、君が代を歌わせ、戦前の教育勅語を復唱させていた。安倍晋三首相の昭恵夫人が2014年春に訪問した際には、籠池(かごいけ)泰典理事長が「どんな首相ですか」と問い、園児が「日本を守ってくれる人」と答えると、昭恵夫人は「ちゃんと伝えます」と感涙にむせんだという。

その森友学園が小学校の建設を計画し、昭恵夫人は名誉校長を引き受けた。学園が9億円余りの国有地を格安で払い下げてもらったのは2016年、その疑惑が表面化したのは翌2017年の2月だった。メディアが「森友疑惑」と大々的に報道し、国会も大騒ぎになった。おさらいしておくと、一連の報道や調査で明らかになった事実は以下の通りである。
▽2015年9月3日 安倍首相が財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長と面会
9月4日 国会が安保法制の法案審議で紛糾する中、安倍首相は大阪に
出張し、公明党の冬柴鉄三・元国交相の次男でコンサルタント
会社を経営する冬柴大(ひろし)氏と会食(写真参照)

9月5日 明恵夫人が森本学園経営の塚本幼稚園で講演
▽2016年6月20日 国が森友学園と大阪府豊中市の国有地の売買契約を締結
▽2017年2月8日 木村真・豊中市議が国有地売却に関して情報公開を求める訴訟を
起こし、直後に記者会見。森友学園疑惑が表面化した
2月17日 衆議院予算委員会で安倍首相が「私や妻がこの国有地払い下げに
もし関わっていたのであれば、総理大臣をやめる」と言明
2月23日 安倍晋三事務所が森友学園に昭恵夫人の名誉校長辞任を伝える
2月24日 衆議院予算委員会で佐川宣寿理財局長が「記録は廃棄した」と
答弁。2月下旬から4月にかけて、財務省は関係文書を改竄
▽2018年3月2日 朝日新聞が「森友文書 書き換えの疑い」と報道
3月7日 国有地売却文書の改竄に関わった近畿財務局の赤木俊夫氏が自死
5月31日 大阪地検、背任罪などで告発された迫田、佐川両氏らを不起訴処分
▽2020年3月18日 妻の赤木雅子氏が国と佐川元理財局長を相手に損害賠償請求訴訟を
起こす
▽2021年12月15日 国側が請求を認め、損害賠償請求訴訟を終結させる
▽2023年9月14日 森友関連文書の改竄に関する行政文書の開示を求める訴訟で
大阪地裁は請求棄却の判決
▽2025年1月30日 大阪高裁は地裁の判決を覆し、関係文書の開示を命じる。石破
政権は最高裁に上告せず、開示を決定
こうした経過を振り返って、あらためて思うのは「安倍首相とその意を体して動き回った財務省の幹部たちは、何と姑息で卑劣なのか」ということだ。安倍首相は自らと妻の関与が明らかになっても、首相の座を退くことはなかった。「乗り切れる」と見ていたのだろう。
実際、財務官僚たちはあらゆる手を尽くして、疑惑が事件になるのを防いだ。財務省の佐川理財局長に至っては、自らの関与について国会で証言を求められると、「捜査に関わることなので答弁を控えさせていただきます」と証言を拒み通し、国税庁長官に栄転した。背任罪や虚偽公文書作成罪などで告発を受けた検察当局は、佐川氏を含む全員を「嫌疑不十分」あるいは「嫌疑なし」として不起訴処分にした。
確かに、財務省は不都合な文書を削除して、丸く収まるような文書に改竄しただけだ。「虚偽の内容の公文書」を作ったわけではない。背任罪に問うためには、「故意に国庫に損害を与えようとした」ということを立証しなければならない。これはハードルが極めて高いので、背任罪にも問えない。財務官僚たちは「法律のプロ中のプロ」である。どのように立ち回れば、犯罪にならないか、十分に検討したうえで対処している。
それでも、文書の改竄を命じられた末に命を絶った赤木俊夫さんの妻雅子さんはあきらめることなく、事実を明らかにするために闘い続けた。そして、今年の1月、森友疑惑の発覚から8年たって、ようやく関連文書の全面開示を勝ち取った。開示対象の文書は、紙の資料が17万枚以上、電子データファイルが数万件とされる。4月に第1弾として約2200枚が開示された。これから順次、残りの文書が公開される。
だが、闘いはまだまだ続く。第1弾の開示文書ですら、肝心の部分は欠落している。「なぜか」という問いに、財務省は「廃棄したためない」と答えた。すでに2018年の段階で、国会で「一部廃棄した」と答弁している。「廃棄しているため文書はない。従って公開できない」というわけだ。
法律の専門家に意見を求めたら、「ないんだから、どうしようもないね」という。自分たちに都合の悪い文書を廃棄しておいて、「公開できません」と開き直っても、とがめようがないという。これでは、情報公開制度の意義が著しく損なわれる。「公開請求されそうな文書は早めにシュレッダーにかけてしまえ」というのがまかり通ってしまうからだ。
「公務員が作った文書はすべて納税者のものであり、国家機密や外交、安全保障にかかわる機微な情報以外は、原則として公開しなければならない」という情報公開制度の根幹が崩れる。財務官僚たちの対応は天にツバする行為と言うしかない。
そういう許しがたい行為は「厳罰をもって臨むべし」と思うのだが、刑法などで処罰することはできないのだという。虚偽公文書作成罪や背任罪は上述のような理由で無理だ。公務員職権濫用罪もしくは公用文書等毀棄罪を適用できる「可能性」はあるが、どちらも3年から5年で公訴時効が成立する。
2018年の国会答弁で、財務省側は「関係文書の一部は破棄した」と明らかにしているので、どちらもとっくに時効が成立している。おそらく、この国会答弁も「時効の起算点」をはっきりさせておく、という意図があったのだろう。
「行政文書を適正に管理するため」という名目で、2009年に公文書管理法が制定されたが、この法律には罰則がない。「だめですよ」と懲戒処分を下せるだけだ。刑法も行政法も「官僚に優しく、官僚が使いやすいように」できている。
「公務員は全体の奉仕者である」という憲法15条も、「すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない」という国家公務員法96条もどこ吹く風。彼らの本音は「権力を握る者への奉仕者として、自分の利益のために勤務する」といったところか。
繰り言を重ねても意味はない。どんなに厳しい道でも、あきらめることなく、赤木雅子さんのように立ち上がり、「開かれた社会への道」を切り拓いていくしかない。官僚機構の中にも心ある人たちはいる、と信じたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 130」 2025年5月13日
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
≪写真説明とSource≫
◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人
◎2015年9月4日、大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)
≪参考記事&サイト≫
◎昭恵夫人が森友学園の幼稚園を訪ねた際のエピソード(産経新聞のサイト)
◎安倍首相、夫人が大阪の小学校の名誉校長を辞任(ロイター、2017年2月24日)
https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN16306R/
◎ウィキペディア「佐川宣寿(のぶひさ)」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%B7%9D%E5%AE%A3%E5%AF%BF
◎ウィキペディア「森友学園問題」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%95%8F%E9%A1%8C
◎大阪地検特捜部の不起訴処分についてのコメント(政府の公文書のあり方を問う弁護士・研究者の会)
https://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7679/
◎服務の根本基準(人事院のサイト)
https://www.jinji.go.jp/content/900018089.pdf
◎森友文書の不開示決定を取り消した大阪高裁判決の記事(2025年1月30日、日経電子版)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2721P0X20C25A1000000/
◎「森友開示文書に欠落」と報じた新聞各紙の記事(2025年5月10日付)

その森友学園が小学校の建設を計画し、昭恵夫人は名誉校長を引き受けた。学園が9億円余りの国有地を格安で払い下げてもらったのは2016年、その疑惑が表面化したのは翌2017年の2月だった。メディアが「森友疑惑」と大々的に報道し、国会も大騒ぎになった。おさらいしておくと、一連の報道や調査で明らかになった事実は以下の通りである。
▽2015年9月3日 安倍首相が財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長と面会
9月4日 国会が安保法制の法案審議で紛糾する中、安倍首相は大阪に
出張し、公明党の冬柴鉄三・元国交相の次男でコンサルタント
会社を経営する冬柴大(ひろし)氏と会食(写真参照)

9月5日 明恵夫人が森本学園経営の塚本幼稚園で講演
▽2016年6月20日 国が森友学園と大阪府豊中市の国有地の売買契約を締結
▽2017年2月8日 木村真・豊中市議が国有地売却に関して情報公開を求める訴訟を
起こし、直後に記者会見。森友学園疑惑が表面化した
2月17日 衆議院予算委員会で安倍首相が「私や妻がこの国有地払い下げに
もし関わっていたのであれば、総理大臣をやめる」と言明
2月23日 安倍晋三事務所が森友学園に昭恵夫人の名誉校長辞任を伝える
2月24日 衆議院予算委員会で佐川宣寿理財局長が「記録は廃棄した」と
答弁。2月下旬から4月にかけて、財務省は関係文書を改竄
▽2018年3月2日 朝日新聞が「森友文書 書き換えの疑い」と報道
3月7日 国有地売却文書の改竄に関わった近畿財務局の赤木俊夫氏が自死
5月31日 大阪地検、背任罪などで告発された迫田、佐川両氏らを不起訴処分
▽2020年3月18日 妻の赤木雅子氏が国と佐川元理財局長を相手に損害賠償請求訴訟を
起こす
▽2021年12月15日 国側が請求を認め、損害賠償請求訴訟を終結させる
▽2023年9月14日 森友関連文書の改竄に関する行政文書の開示を求める訴訟で
大阪地裁は請求棄却の判決
▽2025年1月30日 大阪高裁は地裁の判決を覆し、関係文書の開示を命じる。石破
政権は最高裁に上告せず、開示を決定
こうした経過を振り返って、あらためて思うのは「安倍首相とその意を体して動き回った財務省の幹部たちは、何と姑息で卑劣なのか」ということだ。安倍首相は自らと妻の関与が明らかになっても、首相の座を退くことはなかった。「乗り切れる」と見ていたのだろう。
実際、財務官僚たちはあらゆる手を尽くして、疑惑が事件になるのを防いだ。財務省の佐川理財局長に至っては、自らの関与について国会で証言を求められると、「捜査に関わることなので答弁を控えさせていただきます」と証言を拒み通し、国税庁長官に栄転した。背任罪や虚偽公文書作成罪などで告発を受けた検察当局は、佐川氏を含む全員を「嫌疑不十分」あるいは「嫌疑なし」として不起訴処分にした。
確かに、財務省は不都合な文書を削除して、丸く収まるような文書に改竄しただけだ。「虚偽の内容の公文書」を作ったわけではない。背任罪に問うためには、「故意に国庫に損害を与えようとした」ということを立証しなければならない。これはハードルが極めて高いので、背任罪にも問えない。財務官僚たちは「法律のプロ中のプロ」である。どのように立ち回れば、犯罪にならないか、十分に検討したうえで対処している。
それでも、文書の改竄を命じられた末に命を絶った赤木俊夫さんの妻雅子さんはあきらめることなく、事実を明らかにするために闘い続けた。そして、今年の1月、森友疑惑の発覚から8年たって、ようやく関連文書の全面開示を勝ち取った。開示対象の文書は、紙の資料が17万枚以上、電子データファイルが数万件とされる。4月に第1弾として約2200枚が開示された。これから順次、残りの文書が公開される。
だが、闘いはまだまだ続く。第1弾の開示文書ですら、肝心の部分は欠落している。「なぜか」という問いに、財務省は「廃棄したためない」と答えた。すでに2018年の段階で、国会で「一部廃棄した」と答弁している。「廃棄しているため文書はない。従って公開できない」というわけだ。
法律の専門家に意見を求めたら、「ないんだから、どうしようもないね」という。自分たちに都合の悪い文書を廃棄しておいて、「公開できません」と開き直っても、とがめようがないという。これでは、情報公開制度の意義が著しく損なわれる。「公開請求されそうな文書は早めにシュレッダーにかけてしまえ」というのがまかり通ってしまうからだ。
「公務員が作った文書はすべて納税者のものであり、国家機密や外交、安全保障にかかわる機微な情報以外は、原則として公開しなければならない」という情報公開制度の根幹が崩れる。財務官僚たちの対応は天にツバする行為と言うしかない。
そういう許しがたい行為は「厳罰をもって臨むべし」と思うのだが、刑法などで処罰することはできないのだという。虚偽公文書作成罪や背任罪は上述のような理由で無理だ。公務員職権濫用罪もしくは公用文書等毀棄罪を適用できる「可能性」はあるが、どちらも3年から5年で公訴時効が成立する。
2018年の国会答弁で、財務省側は「関係文書の一部は破棄した」と明らかにしているので、どちらもとっくに時効が成立している。おそらく、この国会答弁も「時効の起算点」をはっきりさせておく、という意図があったのだろう。
「行政文書を適正に管理するため」という名目で、2009年に公文書管理法が制定されたが、この法律には罰則がない。「だめですよ」と懲戒処分を下せるだけだ。刑法も行政法も「官僚に優しく、官僚が使いやすいように」できている。
「公務員は全体の奉仕者である」という憲法15条も、「すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない」という国家公務員法96条もどこ吹く風。彼らの本音は「権力を握る者への奉仕者として、自分の利益のために勤務する」といったところか。
繰り言を重ねても意味はない。どんなに厳しい道でも、あきらめることなく、赤木雅子さんのように立ち上がり、「開かれた社会への道」を切り拓いていくしかない。官僚機構の中にも心ある人たちはいる、と信じたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 130」 2025年5月13日
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
≪写真説明とSource≫
◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人
◎2015年9月4日、大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)
≪参考記事&サイト≫
◎昭恵夫人が森友学園の幼稚園を訪ねた際のエピソード(産経新聞のサイト)
◎安倍首相、夫人が大阪の小学校の名誉校長を辞任(ロイター、2017年2月24日)
https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN16306R/
◎ウィキペディア「佐川宣寿(のぶひさ)」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%B7%9D%E5%AE%A3%E5%AF%BF
◎ウィキペディア「森友学園問題」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%95%8F%E9%A1%8C
◎大阪地検特捜部の不起訴処分についてのコメント(政府の公文書のあり方を問う弁護士・研究者の会)
https://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7679/
◎服務の根本基準(人事院のサイト)
https://www.jinji.go.jp/content/900018089.pdf
◎森友文書の不開示決定を取り消した大阪高裁判決の記事(2025年1月30日、日経電子版)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2721P0X20C25A1000000/
◎「森友開示文書に欠落」と報じた新聞各紙の記事(2025年5月10日付)
新春の都大路を駆け抜ける京都女子駅伝は、とてもユニークな駅伝大会だ。都道府県ごとにチームを組み、9区間42.195キロでたすきをつなぐのだが、社会人や大学生のトップランナーだけでなく、中学生や高校生が走る区間がいくつもある。
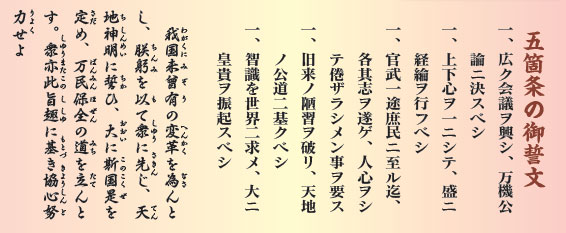
伸び盛りの選手に刺激を与え、その背中を押してあげたい、との思いが感じられる。2023年の大会では、岡山チームの中学3年生、ドルーリー朱瑛里(しぇり)が17人抜きの快走で区間新記録をマークし、「陸上界のニューヒロイン候補」と話題をさらった。
京都女子駅伝は西京極の陸上競技場からスタートし、西大路通を北上して衣笠校前でたすきをつなぐ。第2区のランナーは左手奥に金閣寺がある地点を過ぎると、右折して北大路通に入り、ほどなく千本通との交差点にさしかかる。この交差点の周辺が、かつて「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれた地域である。
「蓮台」とはハスの花をかたどった仏像の台座のことだ。極楽浄土に往生する者が身を託すもので、転じて葬送を意味する。平安の昔から、蓮台野は東の鳥辺野(とりべの)、西の化野(あだしの)とともに北の葬送地として知られていた。化野は庶民、鳥辺野は裕福な人たちが葬られたところ、そして蓮台野は皇族の葬送地であった。後冷泉天皇や近衛天皇の火葬塚が残っており、今も宮内庁書陵部の陵墓資料に記されている。
この地で蓮台野の人たちは代々、御所の庭園の手入れや清掃に加え、皇族の葬送の仕事を担ってきた。その西側に紙屋川が流れていることから、皮なめしを業とする人たちも暮らしていた。なめし作業には流れる水が欠かせないからだ。蓮台野村は同じ京都の天部(あまべ)村や六条村、大阪の渡辺村などとともに、畿内でよく知られた被差別部落の一つだった。
◇ ◇
長い間さげすまれ、虐げられてきた人々にとって、明治維新は「新しい夜明け」を感じさせる出来事であり、新政府に寄せる期待には並々ならぬものがあった。とりわけ、五箇条の誓文に盛り込まれた「旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」という言葉に目を見張った。差別から抜け出す道が開かれた、と受けとめたのである。
明治3年(1870年)、蓮台野村の年寄(取りまとめ役)、元右衛門(がんえもん)は新政府にあてて、賤称の廃止を求める嘆願書を出した。京都の被差別部落の人たちの総意を踏まえた嘆願と見ていいだろう。嘆願書は次のような文章で始まる。
乍恐奉歎願候口上書
一昨辰年八月 元右衛門より供奉願書奉差上候節
由緒有増奉申上候通り
私共類村義 在昔は奥羽之土民に御座候 尤其辺
総而被為称東夷 王化に不奉復者も有之
遂に日本武尊 御征伐被為在之 其御凱陣之砌
御連帰り扈従候處 伊勢神宮に被為留置
夫より当時之帝 御鳳闕左右に被為近候事
日本書紀とも御座候
漢文調の難解な文章である。この調子で最後まで続く(末尾に全文を添付)。3年前の秋、東京の国立国会図書館を訪ね、この嘆願書が採録されている本を閲覧して複写したが、漢文の素養のない私のような者には到底、読みこなせなかった。その後、京都の蓮台野を訪ね、地元の歴史に詳しい方々に教えを請うた。並行して日本書紀や古事記、関連する文献に目を通して、ようやく内容を理解できるようになった。冒頭部分の現代語訳は次の通りである。
恐れながら嘆願奉り候口上書
一昨年の辰年(慶応四年)八月に元右衛門より行幸に
お供させていただきたいとの願書を差し上げました際、
私どもの由緒につきましてあらまし申し上げました通り、
私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました。
もっとも、その辺りでは総じて東夷と称され、
天皇に従わない者もありましたが、日本武尊(やまと
たけるのみこと)が征伐なされ、凱旋の際に連れて
帰られ、これに付き従いましたところ、伊勢神宮に
留め置かれました。
その後、当時の帝が宮城の門の左右に配置なされた、と
日本書紀に記されています。
衝撃的な内容だった。「私たちの先祖は古代の東北で蝦夷(えみし)と呼ばれた土民です。日本武尊に征伐され、西に連れてこられた者たちです」と記しているのだ。日本書紀の巻7「景行天皇 40年の条」には、確かに日本武尊が陸奥に遠征し、捕虜にした蝦夷を伊勢神宮に献上した、と書いてある。
もちろん、研究者の多くが「日本書紀に記された初期の天皇についての事績は神話もしくは伝説であり、史実と受けとめるわけにはいかない」と解釈していることは承知している。では、何代目の天皇から実在したと考えるのか。これは難問のようで、(1)第10代の崇神天皇(約2000年前)以降、(2)第15代の応神天皇(3世紀)以降、(3)第26代の継体天皇(6世紀)以降、と見解が分かれ、いまだに決着がついていない。日本武尊についても、ほとんどの専門家は「何人かの事績を重ね合わせて創作した伝説上の人物」と見ている。
とはいえ、畿内の朝廷勢力が東北の蝦夷と「38年戦争」と呼ばれる長い戦争を繰り広げ、帰順した者や捕虜を多数、西に移送したことについては歴史家の間で異論がない(連載1参照)。自分たちのルーツについてしたためた嘆願書の冒頭部分は、日本武尊という固有名詞を除けば、史実を伝えている可能性がある。嘆願書の内容を以下、現代語訳で紹介していく。第2段落は次のように続く。
応神天皇が国境を定められた時、播磨国神崎郡瓦村崗のあたりで
川上から青菜が流れ下ってきたので、伊許自別命(いこじわけの
みこと)に調べさせたところ、(川上に住む者たちは)「日本武尊
に帰順した者たちです」との報告がありました。天皇は日本武尊の
功績を思われて、伊許自別命に佐伯の姓を下賜し、その地を治める
よう命じられた、と新撰姓氏録(しょうじろく)などにあります。
その時から(私どもは)佐伯部になったということです。
「新撰姓氏録」とは平安時代の初期、嵯峨天皇の時代に編纂された古代の氏族名鑑である。畿内に住む1,182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し、その祖先について叙述している。伊許自別命はその中に登場し、応神天皇に報告した内容についても詳しく書いてある。川上に住む者たちは「我らは日本武尊が東夷を平定した時に捕虜になった蝦夷の後裔です。針間(播磨)、阿芸(安芸)、阿波、讃岐、伊予などに散り散りに移され、今ここにいます」と答えたのだという。「佐伯部になった」とは、「佐伯の姓をたまわった伊許自別命の配下になった」ということだろう。
元右衛門の嘆願書の中で私がもっとも瞠目したのは、次の第3段落だ。安康天皇と次の雄略天皇の時代(5世紀)に皇位継承をめぐって血みどろの争いが繰り広げられた。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先がその争いに巻き込まれて「忠死した」と書いている。
仁徳天皇の時代に天皇の憎しみを被り、五カ国に散り散りになり
ました。その後、安康天皇の時代に私たちの祖先は(市辺押磐)
皇子の警護役である佐伯部仲子(なかちこ)に仕え、近江国
来田綿(くたわた)の蚊屋野(かやの)に付き従い、忠死した
者もおります。仁賢天皇の時には、国郡に散らばった佐伯部を
捜し求められたことも日本書紀に記されています。
この内容を読み解くために、私は日本書紀の関連部分を熟読した。「なんとすさまじい権力闘争であることか」と、うなってしまった。日本書紀に基づいて要約すれば、権力闘争は次のようなものだった。
安康天皇は大草香皇子の妹を大泊瀬皇子(おおはつせのみこ=のちの雄略天皇)に嫁がせようとし、大草香皇子はこれを承諾した。ところが、使いの者は大草香皇子が返礼として献上した宝物をわがものにしたうえで、「妹を差し出すことはできないと固辞した」とウソの報告をした。安康天皇は激怒し、大草香皇子を殺害してその妹を大泊瀬皇子に嫁がせた。しかも、寡婦となった大草香皇子の妻を宮中に入れて妃(きさき)にした。
妃には眉輪王(まよわのおおきみ)という連れ子(大草香皇子の実子)がいた。幼い眉輪王は自分の父親が罪なくして殺されたことを知り、酔って寝ている安康天皇を刺し殺してしまった。これを知った大泊瀬皇子は「自分の兄弟たちが背後にいるのではないか」と疑い、皇位継承でライバルになる可能性のある兄弟を眉輪王ともども次々に攻め殺した。
大泊瀬皇子はさらに、いとこで有力な後継候補だった市辺押磐皇子(いちのべのおしはのみこ)を狩りに誘い出し、近江の来田綿(くたわた)の蚊屋野という所で射殺してしまう。その際に、警護役を務めていた佐伯部仲子(なかちこ)と従者たちも皆殺しにした。嘆願書に「忠死」とあるのは、「殺された従者たちの中に私たちの祖先もいた」と言っているのである。
ライバルを一掃して、大泊瀬皇子は即位して雄略天皇になる。次いでその皇子が清寧天皇になるが、清寧天皇には子がなく、謀殺された市辺押磐皇子の息子が皇位を継いで顕宗(けんぞう)天皇となった。天皇は「雄略天皇の墓を壊し、遺骨を砕いて投げ散らしたい」と復讐に燃えるが、兄にいさめられて思いとどまる。その兄が次の仁賢天皇になり、各地に散らばって隠れていた佐伯部の人たちを捜し求めてねぎらった――壮絶な物語である。
嘆願書のこの段落には、もう一つ注目すべきことがある。蓮台野の祖先が「皇子の警護役に付き従い、忠死した」と記している点である。冒頭で書いたように、蓮台野の人たちは「御所の庭園の手入れや清掃」をしていたが、これは「平時の仕事」だろう。いったん事あれば、彼らは皇族を警護する舎人(とねり)の私兵として、武器を持って戦ったと考えるのが自然だ。「忠死」はそのことを意味しているのではないか。
朝廷勢力と長く戦い続けた古代東北の蝦夷は、戦闘力がきわめて高いことで知られた(連載3参照)。帰順した者や捕虜となった蝦夷の一部は、防人(さきもり)として大宰府や対馬などに配置されている。とするなら、畿内に移送された者の中にも、皇族や貴族の「私兵」として使われた者がいた、と考えるのが自然だ。蝦夷たちは権力を握る者たちにすがり、忠誠を誓って生き延びるしかなかったのだから。
◇ ◇
元右衛門の嘆願書は、自分たちのルーツについて叙述した後、祖先が御所でどのような役割を果たしてきたかを事細かく記している。そのうえで「今般の王政復古はありがたいことです」「私どもも神州の民となりました」「なにとぞ、穢多という名分をなくしてください」と結んでいる。
問題は、この嘆願書をどう見るかだ。史実を踏まえた信憑性の高い文書と考えるか。それとも、日本書紀や新撰姓氏録などの文献に造詣の深い者による「捏造文書」と捉えるのか。見方によって、この嘆願書の価値はまるで違ってくる。
戦前、戦後を通して、部落史の専門家の多くは「被差別部落は民衆を分断するため、近世になってから政治的に作られたもの」と唱え、この嘆願書の祖先に触れた部分に目を向けようとしなかった。嘆願書が史実に基づくものなら、彼らが唱えた「近世政治起源説」はたちまち瓦解してしまう。ゆえに、黙殺した。
部落の歴史や起源に関する本や資料をいくら読んでも元右衛門の嘆願書がなかなか出てこないのは当然のことで、この嘆願書にたどり着くまでずいぶん長くかかってしまった。
京都大学や立命館大学、大阪市立大学の教授たちが唱え、打ち固めていった近世政治起源説はその後、中世史や古代史の研究が進むにつれて揺らぎ、やがて破綻した。今では信じる者はほとんどいない(連載?参照)。被差別部落のルーツを古代東北の蝦夷と結びつけて考える説を「俗説」あるいは「妄説」として退けた彼らの説こそ「珍説」であり、検証に耐えられない代物だった。
これまでの学説に囚われず、曇りのない目でこの嘆願書を見つめ直せば、被差別部落のルーツについての新しい知見が得られるのではないか。次回以降、この嘆願書の持つ意味をさらに探っていきたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出 調査報道サイト「ハンター」 2025年5月8日
≪注≫元右衛門の嘆願書は、大和同志会の機関紙『明治之光』第2巻第7号(1913年7月15日発行)に採録、掲載された。新政府への提出の43年後である。『明治之光』の原本は散逸しており、1977年2月に兵庫部落問題研究所が『復刻・明治之光』(上中下3巻)を発行した。添付した原文はこの復刻版に基づく。現代語訳は『千本部落の歴史と解放への闘い』に掲載された現代語訳を参照しつつ、筆者が行った。
【元右衛門の嘆願書の現代語訳】l
【元右衛門の嘆願書の原文】
◇「古代東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の連載一覧
・1東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・2続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・3追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・4東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・5蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・6安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・7黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・8被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・9皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・10部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
・13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月30日)
・14 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった(2025年9月10日)
≪写真説明≫
◎五箇条の誓文=白山比咩(しらやまひめ)神社のサイトから
≪参考文献&サイト≫
◎『復刻・明治之光(上)』第2巻第7号(兵庫部落問題研究所、1977年)=国立国会図書館所蔵
◎『千本部落の歴史と解放への闘い』(部落解放同盟千本支部部落史研究会、1987年)=佛教大学図書館所蔵
◎2009年度部落史連続講座講演録(京都部落問題研究資料センター)
◎『死者たちの中世』(勝田至、吉川弘文館、2003年)
◎後冷泉天皇の火葬塚に関する資料(宮内庁書陵部のサイト)
◎『日本書紀(一)ー(五)』(坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫、1994?1995年)
◎『日本書紀(上)(下)全現代語訳』(宇治谷孟、講談社学術文庫、1988年)
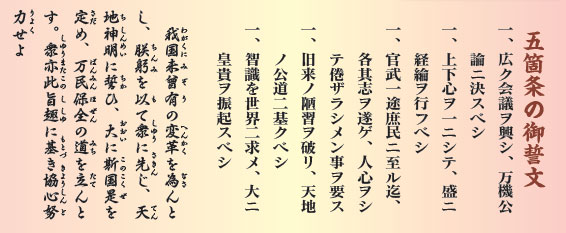
伸び盛りの選手に刺激を与え、その背中を押してあげたい、との思いが感じられる。2023年の大会では、岡山チームの中学3年生、ドルーリー朱瑛里(しぇり)が17人抜きの快走で区間新記録をマークし、「陸上界のニューヒロイン候補」と話題をさらった。
京都女子駅伝は西京極の陸上競技場からスタートし、西大路通を北上して衣笠校前でたすきをつなぐ。第2区のランナーは左手奥に金閣寺がある地点を過ぎると、右折して北大路通に入り、ほどなく千本通との交差点にさしかかる。この交差点の周辺が、かつて「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれた地域である。
「蓮台」とはハスの花をかたどった仏像の台座のことだ。極楽浄土に往生する者が身を託すもので、転じて葬送を意味する。平安の昔から、蓮台野は東の鳥辺野(とりべの)、西の化野(あだしの)とともに北の葬送地として知られていた。化野は庶民、鳥辺野は裕福な人たちが葬られたところ、そして蓮台野は皇族の葬送地であった。後冷泉天皇や近衛天皇の火葬塚が残っており、今も宮内庁書陵部の陵墓資料に記されている。
この地で蓮台野の人たちは代々、御所の庭園の手入れや清掃に加え、皇族の葬送の仕事を担ってきた。その西側に紙屋川が流れていることから、皮なめしを業とする人たちも暮らしていた。なめし作業には流れる水が欠かせないからだ。蓮台野村は同じ京都の天部(あまべ)村や六条村、大阪の渡辺村などとともに、畿内でよく知られた被差別部落の一つだった。
◇ ◇
長い間さげすまれ、虐げられてきた人々にとって、明治維新は「新しい夜明け」を感じさせる出来事であり、新政府に寄せる期待には並々ならぬものがあった。とりわけ、五箇条の誓文に盛り込まれた「旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」という言葉に目を見張った。差別から抜け出す道が開かれた、と受けとめたのである。
明治3年(1870年)、蓮台野村の年寄(取りまとめ役)、元右衛門(がんえもん)は新政府にあてて、賤称の廃止を求める嘆願書を出した。京都の被差別部落の人たちの総意を踏まえた嘆願と見ていいだろう。嘆願書は次のような文章で始まる。
乍恐奉歎願候口上書
一昨辰年八月 元右衛門より供奉願書奉差上候節
由緒有増奉申上候通り
私共類村義 在昔は奥羽之土民に御座候 尤其辺
総而被為称東夷 王化に不奉復者も有之
遂に日本武尊 御征伐被為在之 其御凱陣之砌
御連帰り扈従候處 伊勢神宮に被為留置
夫より当時之帝 御鳳闕左右に被為近候事
日本書紀とも御座候
漢文調の難解な文章である。この調子で最後まで続く(末尾に全文を添付)。3年前の秋、東京の国立国会図書館を訪ね、この嘆願書が採録されている本を閲覧して複写したが、漢文の素養のない私のような者には到底、読みこなせなかった。その後、京都の蓮台野を訪ね、地元の歴史に詳しい方々に教えを請うた。並行して日本書紀や古事記、関連する文献に目を通して、ようやく内容を理解できるようになった。冒頭部分の現代語訳は次の通りである。
恐れながら嘆願奉り候口上書
一昨年の辰年(慶応四年)八月に元右衛門より行幸に
お供させていただきたいとの願書を差し上げました際、
私どもの由緒につきましてあらまし申し上げました通り、
私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました。
もっとも、その辺りでは総じて東夷と称され、
天皇に従わない者もありましたが、日本武尊(やまと
たけるのみこと)が征伐なされ、凱旋の際に連れて
帰られ、これに付き従いましたところ、伊勢神宮に
留め置かれました。
その後、当時の帝が宮城の門の左右に配置なされた、と
日本書紀に記されています。
衝撃的な内容だった。「私たちの先祖は古代の東北で蝦夷(えみし)と呼ばれた土民です。日本武尊に征伐され、西に連れてこられた者たちです」と記しているのだ。日本書紀の巻7「景行天皇 40年の条」には、確かに日本武尊が陸奥に遠征し、捕虜にした蝦夷を伊勢神宮に献上した、と書いてある。
もちろん、研究者の多くが「日本書紀に記された初期の天皇についての事績は神話もしくは伝説であり、史実と受けとめるわけにはいかない」と解釈していることは承知している。では、何代目の天皇から実在したと考えるのか。これは難問のようで、(1)第10代の崇神天皇(約2000年前)以降、(2)第15代の応神天皇(3世紀)以降、(3)第26代の継体天皇(6世紀)以降、と見解が分かれ、いまだに決着がついていない。日本武尊についても、ほとんどの専門家は「何人かの事績を重ね合わせて創作した伝説上の人物」と見ている。
とはいえ、畿内の朝廷勢力が東北の蝦夷と「38年戦争」と呼ばれる長い戦争を繰り広げ、帰順した者や捕虜を多数、西に移送したことについては歴史家の間で異論がない(連載1参照)。自分たちのルーツについてしたためた嘆願書の冒頭部分は、日本武尊という固有名詞を除けば、史実を伝えている可能性がある。嘆願書の内容を以下、現代語訳で紹介していく。第2段落は次のように続く。
応神天皇が国境を定められた時、播磨国神崎郡瓦村崗のあたりで
川上から青菜が流れ下ってきたので、伊許自別命(いこじわけの
みこと)に調べさせたところ、(川上に住む者たちは)「日本武尊
に帰順した者たちです」との報告がありました。天皇は日本武尊の
功績を思われて、伊許自別命に佐伯の姓を下賜し、その地を治める
よう命じられた、と新撰姓氏録(しょうじろく)などにあります。
その時から(私どもは)佐伯部になったということです。
「新撰姓氏録」とは平安時代の初期、嵯峨天皇の時代に編纂された古代の氏族名鑑である。畿内に住む1,182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し、その祖先について叙述している。伊許自別命はその中に登場し、応神天皇に報告した内容についても詳しく書いてある。川上に住む者たちは「我らは日本武尊が東夷を平定した時に捕虜になった蝦夷の後裔です。針間(播磨)、阿芸(安芸)、阿波、讃岐、伊予などに散り散りに移され、今ここにいます」と答えたのだという。「佐伯部になった」とは、「佐伯の姓をたまわった伊許自別命の配下になった」ということだろう。
元右衛門の嘆願書の中で私がもっとも瞠目したのは、次の第3段落だ。安康天皇と次の雄略天皇の時代(5世紀)に皇位継承をめぐって血みどろの争いが繰り広げられた。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先がその争いに巻き込まれて「忠死した」と書いている。
仁徳天皇の時代に天皇の憎しみを被り、五カ国に散り散りになり
ました。その後、安康天皇の時代に私たちの祖先は(市辺押磐)
皇子の警護役である佐伯部仲子(なかちこ)に仕え、近江国
来田綿(くたわた)の蚊屋野(かやの)に付き従い、忠死した
者もおります。仁賢天皇の時には、国郡に散らばった佐伯部を
捜し求められたことも日本書紀に記されています。
この内容を読み解くために、私は日本書紀の関連部分を熟読した。「なんとすさまじい権力闘争であることか」と、うなってしまった。日本書紀に基づいて要約すれば、権力闘争は次のようなものだった。
安康天皇は大草香皇子の妹を大泊瀬皇子(おおはつせのみこ=のちの雄略天皇)に嫁がせようとし、大草香皇子はこれを承諾した。ところが、使いの者は大草香皇子が返礼として献上した宝物をわがものにしたうえで、「妹を差し出すことはできないと固辞した」とウソの報告をした。安康天皇は激怒し、大草香皇子を殺害してその妹を大泊瀬皇子に嫁がせた。しかも、寡婦となった大草香皇子の妻を宮中に入れて妃(きさき)にした。
妃には眉輪王(まよわのおおきみ)という連れ子(大草香皇子の実子)がいた。幼い眉輪王は自分の父親が罪なくして殺されたことを知り、酔って寝ている安康天皇を刺し殺してしまった。これを知った大泊瀬皇子は「自分の兄弟たちが背後にいるのではないか」と疑い、皇位継承でライバルになる可能性のある兄弟を眉輪王ともども次々に攻め殺した。
大泊瀬皇子はさらに、いとこで有力な後継候補だった市辺押磐皇子(いちのべのおしはのみこ)を狩りに誘い出し、近江の来田綿(くたわた)の蚊屋野という所で射殺してしまう。その際に、警護役を務めていた佐伯部仲子(なかちこ)と従者たちも皆殺しにした。嘆願書に「忠死」とあるのは、「殺された従者たちの中に私たちの祖先もいた」と言っているのである。
ライバルを一掃して、大泊瀬皇子は即位して雄略天皇になる。次いでその皇子が清寧天皇になるが、清寧天皇には子がなく、謀殺された市辺押磐皇子の息子が皇位を継いで顕宗(けんぞう)天皇となった。天皇は「雄略天皇の墓を壊し、遺骨を砕いて投げ散らしたい」と復讐に燃えるが、兄にいさめられて思いとどまる。その兄が次の仁賢天皇になり、各地に散らばって隠れていた佐伯部の人たちを捜し求めてねぎらった――壮絶な物語である。
嘆願書のこの段落には、もう一つ注目すべきことがある。蓮台野の祖先が「皇子の警護役に付き従い、忠死した」と記している点である。冒頭で書いたように、蓮台野の人たちは「御所の庭園の手入れや清掃」をしていたが、これは「平時の仕事」だろう。いったん事あれば、彼らは皇族を警護する舎人(とねり)の私兵として、武器を持って戦ったと考えるのが自然だ。「忠死」はそのことを意味しているのではないか。
朝廷勢力と長く戦い続けた古代東北の蝦夷は、戦闘力がきわめて高いことで知られた(連載3参照)。帰順した者や捕虜となった蝦夷の一部は、防人(さきもり)として大宰府や対馬などに配置されている。とするなら、畿内に移送された者の中にも、皇族や貴族の「私兵」として使われた者がいた、と考えるのが自然だ。蝦夷たちは権力を握る者たちにすがり、忠誠を誓って生き延びるしかなかったのだから。
◇ ◇
元右衛門の嘆願書は、自分たちのルーツについて叙述した後、祖先が御所でどのような役割を果たしてきたかを事細かく記している。そのうえで「今般の王政復古はありがたいことです」「私どもも神州の民となりました」「なにとぞ、穢多という名分をなくしてください」と結んでいる。
問題は、この嘆願書をどう見るかだ。史実を踏まえた信憑性の高い文書と考えるか。それとも、日本書紀や新撰姓氏録などの文献に造詣の深い者による「捏造文書」と捉えるのか。見方によって、この嘆願書の価値はまるで違ってくる。
戦前、戦後を通して、部落史の専門家の多くは「被差別部落は民衆を分断するため、近世になってから政治的に作られたもの」と唱え、この嘆願書の祖先に触れた部分に目を向けようとしなかった。嘆願書が史実に基づくものなら、彼らが唱えた「近世政治起源説」はたちまち瓦解してしまう。ゆえに、黙殺した。
部落の歴史や起源に関する本や資料をいくら読んでも元右衛門の嘆願書がなかなか出てこないのは当然のことで、この嘆願書にたどり着くまでずいぶん長くかかってしまった。
京都大学や立命館大学、大阪市立大学の教授たちが唱え、打ち固めていった近世政治起源説はその後、中世史や古代史の研究が進むにつれて揺らぎ、やがて破綻した。今では信じる者はほとんどいない(連載?参照)。被差別部落のルーツを古代東北の蝦夷と結びつけて考える説を「俗説」あるいは「妄説」として退けた彼らの説こそ「珍説」であり、検証に耐えられない代物だった。
これまでの学説に囚われず、曇りのない目でこの嘆願書を見つめ直せば、被差別部落のルーツについての新しい知見が得られるのではないか。次回以降、この嘆願書の持つ意味をさらに探っていきたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出 調査報道サイト「ハンター」 2025年5月8日
≪注≫元右衛門の嘆願書は、大和同志会の機関紙『明治之光』第2巻第7号(1913年7月15日発行)に採録、掲載された。新政府への提出の43年後である。『明治之光』の原本は散逸しており、1977年2月に兵庫部落問題研究所が『復刻・明治之光』(上中下3巻)を発行した。添付した原文はこの復刻版に基づく。現代語訳は『千本部落の歴史と解放への闘い』に掲載された現代語訳を参照しつつ、筆者が行った。
【元右衛門の嘆願書の現代語訳】l
【元右衛門の嘆願書の原文】
◇「古代東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の連載一覧
・1東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・2続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・3追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・4東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・5蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・6安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・7黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・8被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・9皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・10部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
・13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月30日)
・14 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった(2025年9月10日)
≪写真説明≫
◎五箇条の誓文=白山比咩(しらやまひめ)神社のサイトから
≪参考文献&サイト≫
◎『復刻・明治之光(上)』第2巻第7号(兵庫部落問題研究所、1977年)=国立国会図書館所蔵
◎『千本部落の歴史と解放への闘い』(部落解放同盟千本支部部落史研究会、1987年)=佛教大学図書館所蔵
◎2009年度部落史連続講座講演録(京都部落問題研究資料センター)
◎『死者たちの中世』(勝田至、吉川弘文館、2003年)
◎後冷泉天皇の火葬塚に関する資料(宮内庁書陵部のサイト)
◎『日本書紀(一)ー(五)』(坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫、1994?1995年)
◎『日本書紀(上)(下)全現代語訳』(宇治谷孟、講談社学術文庫、1988年)
パレスチナのガザ地区で朝日新聞の通信員として報道し続けてきたムハンマド・マンスール氏(29)が24日、イスラエル軍のミサイル攻撃を受けて死亡した。ガザ地区南部のハンユニスで家族と暮らしながら取材を続けていたが、避難していたテントが攻撃されたようだ。妻と子どもたちの安否は不明という。

イスラエルはイスラム組織ハマスとの停戦合意を破って、18日に攻撃を再開した。マンスール氏は死の直前、攻撃再開による惨状を伝えてきた。記事の中で、彼は「私の一日は攻撃を受けるのを避けながら、家族とともに飲料水や食料を集めることでほとんど終わってしまう」と綴っていた。
現役の記者だったころ、私もアフガニスタン戦争の取材に携わった。砲弾が飛び交う中で走り回ったこともある。取材中に死亡した顔見知りの記者もいた。だが、ガザ地区での取材は「普通の戦争取材」とはまるで異なる。自分の家族を守りながら戦争の実情を伝える――なんと過酷な取材であることか。壮絶な死、である。
国際NPO「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ、本部・ニューヨーク)は、イスラエル軍による24日の攻撃でマンスール氏と衛星放送局アルジャジーラのホサム・シャバト記者(23)が死亡したことを非難し、国際的な調査をするよう要求した。CPJによれば、2024年に殉職したジャーナリストは124人に上り、この30年で最多だった。その7割はイスラエルによる殺害と断じている。
イスラエルにも言い分はあるだろう。今回の戦争の発端は、2023年10月のハマスによる奇襲攻撃である。ハマスはイスラエルの市民を無差別で殺害し、しかも女性や子ども、高齢者を含む240人もの人質を取った。「ハマスを壊滅させるまで戦う」と宣言して、イスラエルは戦争を始めた。ハマスは住民に支えられて戦うゲリラであり、戦闘員と住民を区別するのは難しい。壮絶な戦争になることは当初から予想されていた。
とはいえ、どのような戦争であろうと、守るべき「ルール」はある。戦闘と無関係な市民を攻撃してはいけない。投降した捕虜を殺してはならない。病院や学校などの施設を攻撃することは避けなければならない。各国は数多くの戦争を経て、そうしたことを「ジュネーブ諸条約及び追加議定書」としてまとめ、これを守ろうとしてきた。イスラエルも「ジュネーブ諸条約」を締結、批准している。
「ハマスはテロ組織である。条約など気にしていない。ならば、我々も気にしない」と言うなら、イスラエルはもはや「まともな国家」とは言えない。国際的な取り決めを歯牙にもかけない国家を「ならずもの国家」と呼ぶなら、イスラエルももはや「ならずもの国家」の一つと言うしかない。
「ならずもの国家 Rogue state 」という言葉を初めて使ったのは1994年、アメリカのクリントン大統領である。イラクやイラン、北朝鮮、リビアなどを指して使ったものだが、ガザ地区で市民への無差別攻撃を続けるイスラエルを「全面的に支持、支援するアメリカ」は、今や「ならずもの国家」のお友達と言うべきだろう。
ウクライナに侵攻し、住民を虐殺したロシアは「ならずもの国家の典型」である。そのロシアとアメリカは、国連安保理の常任理事国として「拒否権」を持ち、特別な地位にある。プーチン大統領とトランプ大統領の振る舞いは「われわれは国際社会の顔役なのだ」と言わんばかりである。2人でウクライナ戦争の始末を付けるのだという。
「ならずもの国家」とその友達がわが物顔で跋扈(ばっこ)する、恐ろしい世の中になった。そこから抜け出す道がまるで見えてこないことが一層恐ろしい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 128」 2025年3月26日
≪写真≫
◎ムハンマド・マンスール氏(テレビ朝日のサイト)
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/900021301.html
≪参考記事&サイト≫
◎ムハンマド・マンスール氏の記事と彼の死を伝える朝日新聞の記事(2025年3月25日付、3月26日付)
◎NPO「ジャーナリスト保護委員会」のイスラエル非難声明(英語版)
https://cpj.org
◎ジュネーブ諸条約及び追加議定書について(日本外務省の公式サイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html
◎ジュネーブ諸条約の主な内容(同)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html

イスラエルはイスラム組織ハマスとの停戦合意を破って、18日に攻撃を再開した。マンスール氏は死の直前、攻撃再開による惨状を伝えてきた。記事の中で、彼は「私の一日は攻撃を受けるのを避けながら、家族とともに飲料水や食料を集めることでほとんど終わってしまう」と綴っていた。
現役の記者だったころ、私もアフガニスタン戦争の取材に携わった。砲弾が飛び交う中で走り回ったこともある。取材中に死亡した顔見知りの記者もいた。だが、ガザ地区での取材は「普通の戦争取材」とはまるで異なる。自分の家族を守りながら戦争の実情を伝える――なんと過酷な取材であることか。壮絶な死、である。
国際NPO「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ、本部・ニューヨーク)は、イスラエル軍による24日の攻撃でマンスール氏と衛星放送局アルジャジーラのホサム・シャバト記者(23)が死亡したことを非難し、国際的な調査をするよう要求した。CPJによれば、2024年に殉職したジャーナリストは124人に上り、この30年で最多だった。その7割はイスラエルによる殺害と断じている。
イスラエルにも言い分はあるだろう。今回の戦争の発端は、2023年10月のハマスによる奇襲攻撃である。ハマスはイスラエルの市民を無差別で殺害し、しかも女性や子ども、高齢者を含む240人もの人質を取った。「ハマスを壊滅させるまで戦う」と宣言して、イスラエルは戦争を始めた。ハマスは住民に支えられて戦うゲリラであり、戦闘員と住民を区別するのは難しい。壮絶な戦争になることは当初から予想されていた。
とはいえ、どのような戦争であろうと、守るべき「ルール」はある。戦闘と無関係な市民を攻撃してはいけない。投降した捕虜を殺してはならない。病院や学校などの施設を攻撃することは避けなければならない。各国は数多くの戦争を経て、そうしたことを「ジュネーブ諸条約及び追加議定書」としてまとめ、これを守ろうとしてきた。イスラエルも「ジュネーブ諸条約」を締結、批准している。
「ハマスはテロ組織である。条約など気にしていない。ならば、我々も気にしない」と言うなら、イスラエルはもはや「まともな国家」とは言えない。国際的な取り決めを歯牙にもかけない国家を「ならずもの国家」と呼ぶなら、イスラエルももはや「ならずもの国家」の一つと言うしかない。
「ならずもの国家 Rogue state 」という言葉を初めて使ったのは1994年、アメリカのクリントン大統領である。イラクやイラン、北朝鮮、リビアなどを指して使ったものだが、ガザ地区で市民への無差別攻撃を続けるイスラエルを「全面的に支持、支援するアメリカ」は、今や「ならずもの国家」のお友達と言うべきだろう。
ウクライナに侵攻し、住民を虐殺したロシアは「ならずもの国家の典型」である。そのロシアとアメリカは、国連安保理の常任理事国として「拒否権」を持ち、特別な地位にある。プーチン大統領とトランプ大統領の振る舞いは「われわれは国際社会の顔役なのだ」と言わんばかりである。2人でウクライナ戦争の始末を付けるのだという。
「ならずもの国家」とその友達がわが物顔で跋扈(ばっこ)する、恐ろしい世の中になった。そこから抜け出す道がまるで見えてこないことが一層恐ろしい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 128」 2025年3月26日
≪写真≫
◎ムハンマド・マンスール氏(テレビ朝日のサイト)
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/900021301.html
≪参考記事&サイト≫
◎ムハンマド・マンスール氏の記事と彼の死を伝える朝日新聞の記事(2025年3月25日付、3月26日付)
◎NPO「ジャーナリスト保護委員会」のイスラエル非難声明(英語版)
https://cpj.org
◎ジュネーブ諸条約及び追加議定書について(日本外務省の公式サイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html
◎ジュネーブ諸条約の主な内容(同)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html
心の底に沈み込み、癒やされることのない深い悲しみを「哀しみ」と呼ぶならば、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」の綱領からにじみ出てくるものは「哀しみ」ではないか。

AfDの綱領は次のような言葉で始まる。
「ドイツのために起(た)ち上がる勇気。私たちは臣民ではなく、自由な市民である」
続いて、綱領は次の3つの文章を掲げる。
「私たちはリベラルであり、かつ保守主義者である」
「私たちはわが国の自由な市民である」
「私たちは民主主義の堅固な支持者である」
そして、長い間、募る思いを胸に抱え込み、口に出すことをためらってきた人々に「今こそ起ち上がり、行動する時だ」と呼びかける。「正義と法の支配に反すること、立憲国家を破壊するようなことをこれ以上、見過ごすわけにはいかない」「健全な経済諸原則に違背する政治家たちの無責任な行動を見過ごすわけにはいかない」と記し、「だからこそ、私たちは真の政治的選択肢を提示する」と訴えている。
「立憲国家の破壊」「健全な経済諸原則への違背」とは、何を意味するのか。これは、この政党の生い立ちに深く関わる表現である。「ドイツのための選択肢(AfD)」は2013年、ギリシャ危機のさなかに結成された。でたらめな財政運営を重ね、「国家破綻」の危機に瀕したギリシャを救済するため、欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)が大規模な金融支援に乗り出した時期である。
ギリシャは、労働人口の4人に1人が公務員という「役人天国」だった。年金の支給は55歳から。しかも、年金は現役時代の給与の9割を支給するという大盤振る舞い。これでは国家として立ち行かなくなるのは当たり前だ。
そのギリシャに、EUとIMFは2010年の第一次金融支援で1,100億ユーロ、2012年の第二次金融支援では1,300億ユーロという巨費を投じることを決めた。緊縮財政への転換と経済改革の断行を条件にしたうえでの支援とはいえ、その負担はEU加盟国、とりわけその最大の資金拠出国であるドイツに重くのしかかってくる。
ドイツは、欧州連合(EU)の前身の欧州共同体(EC)の時代から、巨額の資金を拠出してその運営を支えてきた。少し乱暴に言えば、自動車や鉄鋼製品の輸出でドイツが稼いだ金でフランスなどに潤沢な農業補助金を回し、それらの国々を支えてきたという側面がある。誰も口に出しては言わないが、それは第2次大戦を引き起こしたドイツによる「隠れた戦後賠償」という性格も帯びていた。戦争に敗れ、ホロコーストで断罪されたドイツには、そうした配分に抗弁できるはずもなかった。
しかも、加盟国による拠出金の負担と補助金配分という受益の割合をどうするかは、EU本部のあるブリュッセルの官僚たちと各国の政治指導者による協議で決められる。主権者である国民には異議を差し挟む機会すらない(ドイツには国民投票の制度がない)。そうした不満が鬱積しているところに、「健全な経済諸原則」を踏み外したギリシャを救済する決定が下されたのだ。

2013年にAfDを立ち上げた時の創設者の1人は、ハンブルク大学のベルント・ルッケ教授(経済学)である。もともと共通通貨ユーロの導入について「歴史的な過ちである」と批判しており、ギリシャ救済についても「とんでもない災い」と非難した。高級紙フランクフルター・アルゲマイネの元編集者も創設に加わった。
ドイツにとって、欧州統合は国是とみなされてきた。その国是に「しかるべき見識を持つ人たち」が初めて、公然と反旗を翻した。「我慢に我慢を重ねてきたが、これ以上、負担ばかり押し付けられるのはごめんだ」という声が噴き出したのである。
そうした憤りを背に船出したAfDは、綱領にも「欧州連合(EU)を中央集権的な連邦国家にする考えに反対する。EUは各国をゆるやかに結びつける経済共同体に戻すべきだ。ヨーロッパ合衆国という構想も拒絶する」と記した。そして、根本的な改革がなされないならば、「ドイツのEUからの離脱、もしくはEUの解体を求める」と宣言した。それは、戦後のドイツと欧州の歩みに真っ向から挑戦するものであり、政治と経済の基盤を根底から揺さぶるものだった。
欧州統合の推進役を果たしてきたドイツが「統合推進か離脱か」で大揺れになるような事態になれば、その影響はドイツだけにとどまらず欧州全体、さらには世界経済にも及ぶ。とてつもない混乱が広がる恐れがある。
ドイツでは、主要政党のキリスト教民主同盟(CDU)や社会民主党(SPD)、緑の党なども欧州統合を進めることでは一致している。このため、たとえAfDが総選挙で躍進し、第一党になったとしても、単独で過半数の議席を確保しない限り、政権を担う可能性はない。EUからのドイツの離脱がすぐに現実的な政治課題になる可能性も極めて小さい。
とはいえ、ドイツの各種世論調査によれば、来年2月に繰り上げて実施される総選挙で、AfDはメルケル元首相の出身母体であるCDUに次いで第2党になる勢いを見せている。ショルツ首相が率いるSPDをしのぐことは間違いない情勢だ。ドイツのEU離脱というテーマは、いまや「一部の過激派の極端な主張」と言って済ませるわけにはいかない。どの政党も真剣に立ち向かわざるを得なくなるだろう。
欧州連合(EU)の本部があるブリュッセルでは、欧州委員会や閣僚理事会、欧州議会のスタッフら3万2000人の職員が働いている。加盟27カ国で使われる公用語は24。主要な会議の話し合いと議事録の作成には、それぞれ大勢の通訳が必要になる。EUの運営費は年々、膨らむ。AfDはそこにも鋭い視線を向け、「これらのシステムは非効率で市民の暮らしからかけ離れているにもかかわらず、肥大化している」と批判してやまない。
AfDの勢力拡大のもう一つの大きな要因は移民・難民政策である。AfDは、2015年の難民危機の際のメルケル首相(当時)の決断(困窮し、庇護を求める人はすべて受け入れるとの政策転換)を「完全な失敗だった」と弾劾する。法的な枠組みもないまま、庇護を求める人も出稼ぎ目的の人も一緒くたにして受け入れてしまった、という。
その結果、同年末にケルンで集団性暴行事件が起き、ハンブルクやシュツットガルト、ドルトムントなど各地で同じような事件が続発した。移民と難民による犯罪の多発はドイツ社会に深刻な影を落としており、「政策の大転換が必要だ」というAfDの訴えは、ますます説得力を増してきている。
ただ、どのように転換するかをめぐってはAfD内部でも意見が割れ、創設者の1人のベルント・ルッケら穏健派は離党した。穏健派が離れた後に改訂された現在の綱領は「信仰の自由は無条件で支持する」としながら、「ただし、私たちの法秩序やユダヤ教・キリスト教的な文化基盤に反するイスラム教の礼拝や習慣には断固反対する」という。つまり、アザーン(礼拝の呼びかけ)や公共の場でのヒジャブやニカブの着用は認めない。
綱領には「イスラム教はドイツに属するものではない。イスラム教徒の数が増え、広がることはわが国にとって危険なことだと考える」という、より直接的な表現もある。それらは、より過激な団体「西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者(ペギーダ)」の唱えるスローガンと重なる部分があり、主要政党が警戒の眼差しを向ける理由になっている。
AfDの綱領でもう一つ注目されるのは「ドイツに国民投票の制度を設けよ」と主張している点だ。ナチス時代の反省から、「扇動的な政治家が民衆をあおり立てて国家の根幹を変えてしまう恐れがある」として、ドイツは国民投票の制度を設けなかった。このため、ユーロの導入にしてもギリシャ救済にしても「一握りの政治エリートたちによって決められてしまった」と、AfDは非難する。
綱領は「ドイツは政治的な岐路に立っている」とし、「憲法の改正や重要な条約の発効については国民の投票による同意なしに行ってはならない」と唱える。とりわけ、「財政支出をともなう決定については国民投票にかけよ」と言う。ユーロ導入やギリシャ救済が国民の頭越しに決められたことを非難するもので、これも有権者の胸に響く主張だろう。
ドイツのEU離脱は、英国の離脱とは比べようもないほどのインパクトを持つ。「イスラム教徒とどのように向き合うか」という問題も、欧州全体に突き付けられた課題である。そうした重要な政治課題について、これほどドラスティックな転換を唱えたドイツの政党は今までになかった。

現在、「ドイツのための選択肢(AfD)」を率いるのはティノ・クルパラ(49)、アリス・ワイデル(45)という2人の共同党首である。クルパラ氏は旧東ドイツ生まれで、塗装工から建設会社のオーナーになった実業家。ワイデル氏は西部ノルトライン・ヴェストファーレン州出身。バイロイト大学で経済学を専攻し、ゴールドマンサックスや中国銀行に勤めた。出身地、経歴とも対照的で、男女の共同党首というのも現代的と言うべきか。
ドイツの有権者は来年2月の総選挙で、2人が率いるAfDにどのような審判を下すのか。選挙結果は、ドイツだけでなく欧州全体の未来を大きく左右するものになるだろう。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2024年11月28日
◇関連記事
(1)ドイツは「第4の大波」に耐えられるか
(2)ドイツの「封印された哀しみ」が噴き出している
(3)ドイツのEU離脱を求める政党の登場
≪写真≫
◎「ドイツのための選択肢(AfD)」の集会(オンライン・マガジンPolitical violence at a glance から)
◎AfDの創設者、ベルント・ルッケ教授(英語版ウィキペディアから)
◎AfDのティノ・クルパラ(左)、アリス・ワイデル(右)共同党首(独紙ベルリナー・モルゲンポストのサイトから)
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「ドイツの『封印された哀しみ』が噴き出している(2)」
◎「ドイツのための選択肢(AfD)」の綱領(英訳版)
◎「ギリシャ問題とユーロ圏の構造強化(内閣府の公式サイトから)
◎「変調するドイツ政治」(板橋拓己、国際問題No.660 2017年4月)
◎英語版ウィキペディア「ベルント・ルッケ Bernd Lucke」
◎「共通農業政策の財政と加盟国の農家経済」(石井圭一・東北大学大学院准教授)
◎「欧州理事会、閣僚会議、欧州委員会」(宮畑建志)
◎『超約 ドイツの歴史』(ジェームズ・ホーズ、東京書籍)

AfDの綱領は次のような言葉で始まる。
「ドイツのために起(た)ち上がる勇気。私たちは臣民ではなく、自由な市民である」
続いて、綱領は次の3つの文章を掲げる。
「私たちはリベラルであり、かつ保守主義者である」
「私たちはわが国の自由な市民である」
「私たちは民主主義の堅固な支持者である」
そして、長い間、募る思いを胸に抱え込み、口に出すことをためらってきた人々に「今こそ起ち上がり、行動する時だ」と呼びかける。「正義と法の支配に反すること、立憲国家を破壊するようなことをこれ以上、見過ごすわけにはいかない」「健全な経済諸原則に違背する政治家たちの無責任な行動を見過ごすわけにはいかない」と記し、「だからこそ、私たちは真の政治的選択肢を提示する」と訴えている。
「立憲国家の破壊」「健全な経済諸原則への違背」とは、何を意味するのか。これは、この政党の生い立ちに深く関わる表現である。「ドイツのための選択肢(AfD)」は2013年、ギリシャ危機のさなかに結成された。でたらめな財政運営を重ね、「国家破綻」の危機に瀕したギリシャを救済するため、欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)が大規模な金融支援に乗り出した時期である。
ギリシャは、労働人口の4人に1人が公務員という「役人天国」だった。年金の支給は55歳から。しかも、年金は現役時代の給与の9割を支給するという大盤振る舞い。これでは国家として立ち行かなくなるのは当たり前だ。
そのギリシャに、EUとIMFは2010年の第一次金融支援で1,100億ユーロ、2012年の第二次金融支援では1,300億ユーロという巨費を投じることを決めた。緊縮財政への転換と経済改革の断行を条件にしたうえでの支援とはいえ、その負担はEU加盟国、とりわけその最大の資金拠出国であるドイツに重くのしかかってくる。
ドイツは、欧州連合(EU)の前身の欧州共同体(EC)の時代から、巨額の資金を拠出してその運営を支えてきた。少し乱暴に言えば、自動車や鉄鋼製品の輸出でドイツが稼いだ金でフランスなどに潤沢な農業補助金を回し、それらの国々を支えてきたという側面がある。誰も口に出しては言わないが、それは第2次大戦を引き起こしたドイツによる「隠れた戦後賠償」という性格も帯びていた。戦争に敗れ、ホロコーストで断罪されたドイツには、そうした配分に抗弁できるはずもなかった。
しかも、加盟国による拠出金の負担と補助金配分という受益の割合をどうするかは、EU本部のあるブリュッセルの官僚たちと各国の政治指導者による協議で決められる。主権者である国民には異議を差し挟む機会すらない(ドイツには国民投票の制度がない)。そうした不満が鬱積しているところに、「健全な経済諸原則」を踏み外したギリシャを救済する決定が下されたのだ。

2013年にAfDを立ち上げた時の創設者の1人は、ハンブルク大学のベルント・ルッケ教授(経済学)である。もともと共通通貨ユーロの導入について「歴史的な過ちである」と批判しており、ギリシャ救済についても「とんでもない災い」と非難した。高級紙フランクフルター・アルゲマイネの元編集者も創設に加わった。
ドイツにとって、欧州統合は国是とみなされてきた。その国是に「しかるべき見識を持つ人たち」が初めて、公然と反旗を翻した。「我慢に我慢を重ねてきたが、これ以上、負担ばかり押し付けられるのはごめんだ」という声が噴き出したのである。
そうした憤りを背に船出したAfDは、綱領にも「欧州連合(EU)を中央集権的な連邦国家にする考えに反対する。EUは各国をゆるやかに結びつける経済共同体に戻すべきだ。ヨーロッパ合衆国という構想も拒絶する」と記した。そして、根本的な改革がなされないならば、「ドイツのEUからの離脱、もしくはEUの解体を求める」と宣言した。それは、戦後のドイツと欧州の歩みに真っ向から挑戦するものであり、政治と経済の基盤を根底から揺さぶるものだった。
欧州統合の推進役を果たしてきたドイツが「統合推進か離脱か」で大揺れになるような事態になれば、その影響はドイツだけにとどまらず欧州全体、さらには世界経済にも及ぶ。とてつもない混乱が広がる恐れがある。
ドイツでは、主要政党のキリスト教民主同盟(CDU)や社会民主党(SPD)、緑の党なども欧州統合を進めることでは一致している。このため、たとえAfDが総選挙で躍進し、第一党になったとしても、単独で過半数の議席を確保しない限り、政権を担う可能性はない。EUからのドイツの離脱がすぐに現実的な政治課題になる可能性も極めて小さい。
とはいえ、ドイツの各種世論調査によれば、来年2月に繰り上げて実施される総選挙で、AfDはメルケル元首相の出身母体であるCDUに次いで第2党になる勢いを見せている。ショルツ首相が率いるSPDをしのぐことは間違いない情勢だ。ドイツのEU離脱というテーマは、いまや「一部の過激派の極端な主張」と言って済ませるわけにはいかない。どの政党も真剣に立ち向かわざるを得なくなるだろう。
欧州連合(EU)の本部があるブリュッセルでは、欧州委員会や閣僚理事会、欧州議会のスタッフら3万2000人の職員が働いている。加盟27カ国で使われる公用語は24。主要な会議の話し合いと議事録の作成には、それぞれ大勢の通訳が必要になる。EUの運営費は年々、膨らむ。AfDはそこにも鋭い視線を向け、「これらのシステムは非効率で市民の暮らしからかけ離れているにもかかわらず、肥大化している」と批判してやまない。
AfDの勢力拡大のもう一つの大きな要因は移民・難民政策である。AfDは、2015年の難民危機の際のメルケル首相(当時)の決断(困窮し、庇護を求める人はすべて受け入れるとの政策転換)を「完全な失敗だった」と弾劾する。法的な枠組みもないまま、庇護を求める人も出稼ぎ目的の人も一緒くたにして受け入れてしまった、という。
その結果、同年末にケルンで集団性暴行事件が起き、ハンブルクやシュツットガルト、ドルトムントなど各地で同じような事件が続発した。移民と難民による犯罪の多発はドイツ社会に深刻な影を落としており、「政策の大転換が必要だ」というAfDの訴えは、ますます説得力を増してきている。
ただ、どのように転換するかをめぐってはAfD内部でも意見が割れ、創設者の1人のベルント・ルッケら穏健派は離党した。穏健派が離れた後に改訂された現在の綱領は「信仰の自由は無条件で支持する」としながら、「ただし、私たちの法秩序やユダヤ教・キリスト教的な文化基盤に反するイスラム教の礼拝や習慣には断固反対する」という。つまり、アザーン(礼拝の呼びかけ)や公共の場でのヒジャブやニカブの着用は認めない。
綱領には「イスラム教はドイツに属するものではない。イスラム教徒の数が増え、広がることはわが国にとって危険なことだと考える」という、より直接的な表現もある。それらは、より過激な団体「西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者(ペギーダ)」の唱えるスローガンと重なる部分があり、主要政党が警戒の眼差しを向ける理由になっている。
AfDの綱領でもう一つ注目されるのは「ドイツに国民投票の制度を設けよ」と主張している点だ。ナチス時代の反省から、「扇動的な政治家が民衆をあおり立てて国家の根幹を変えてしまう恐れがある」として、ドイツは国民投票の制度を設けなかった。このため、ユーロの導入にしてもギリシャ救済にしても「一握りの政治エリートたちによって決められてしまった」と、AfDは非難する。
綱領は「ドイツは政治的な岐路に立っている」とし、「憲法の改正や重要な条約の発効については国民の投票による同意なしに行ってはならない」と唱える。とりわけ、「財政支出をともなう決定については国民投票にかけよ」と言う。ユーロ導入やギリシャ救済が国民の頭越しに決められたことを非難するもので、これも有権者の胸に響く主張だろう。
ドイツのEU離脱は、英国の離脱とは比べようもないほどのインパクトを持つ。「イスラム教徒とどのように向き合うか」という問題も、欧州全体に突き付けられた課題である。そうした重要な政治課題について、これほどドラスティックな転換を唱えたドイツの政党は今までになかった。

現在、「ドイツのための選択肢(AfD)」を率いるのはティノ・クルパラ(49)、アリス・ワイデル(45)という2人の共同党首である。クルパラ氏は旧東ドイツ生まれで、塗装工から建設会社のオーナーになった実業家。ワイデル氏は西部ノルトライン・ヴェストファーレン州出身。バイロイト大学で経済学を専攻し、ゴールドマンサックスや中国銀行に勤めた。出身地、経歴とも対照的で、男女の共同党首というのも現代的と言うべきか。
ドイツの有権者は来年2月の総選挙で、2人が率いるAfDにどのような審判を下すのか。選挙結果は、ドイツだけでなく欧州全体の未来を大きく左右するものになるだろう。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2024年11月28日
◇関連記事
(1)ドイツは「第4の大波」に耐えられるか
(2)ドイツの「封印された哀しみ」が噴き出している
(3)ドイツのEU離脱を求める政党の登場
≪写真≫
◎「ドイツのための選択肢(AfD)」の集会(オンライン・マガジンPolitical violence at a glance から)
◎AfDの創設者、ベルント・ルッケ教授(英語版ウィキペディアから)
◎AfDのティノ・クルパラ(左)、アリス・ワイデル(右)共同党首(独紙ベルリナー・モルゲンポストのサイトから)
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「ドイツの『封印された哀しみ』が噴き出している(2)」
◎「ドイツのための選択肢(AfD)」の綱領(英訳版)
◎「ギリシャ問題とユーロ圏の構造強化(内閣府の公式サイトから)
◎「変調するドイツ政治」(板橋拓己、国際問題No.660 2017年4月)
◎英語版ウィキペディア「ベルント・ルッケ Bernd Lucke」
◎「共通農業政策の財政と加盟国の農家経済」(石井圭一・東北大学大学院准教授)
◎「欧州理事会、閣僚会議、欧州委員会」(宮畑建志)
◎『超約 ドイツの歴史』(ジェームズ・ホーズ、東京書籍)
政党の本部といえば、首都の中心部にあるのが相場だ。日本の自民党と立憲民主党の本部は千代田区永田町にある。大阪を拠点とする日本維新の会を除けば、ほかの政党も都心に近いところに本部を構えている。

ところが、ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」は違った。ベルリンの郊外、東京でいえば中野区か練馬区のはずれのようなところに党本部がある。最初、ネットで調べた時は「何かの間違いではないか」と首をかしげたが、AfDの公式サイトに載っているのもその住所だった。アポなしで訪ねることにした。
ベルリンの中心部、ブランデンブルク門の近くにあるホテルから地下鉄と近郊電車を乗り継いで30分ほど。最寄り駅のヴィッテナウに着いた。駅前で住所を示して尋ねたが、誰も知らない。9月の州議選で大躍進を遂げてドイツ政界を揺るがした、いま話題の政党なのに。
住所は「アイヒホルスター通り80番地」と分かっている。近所の住民なら知っているだろうと、片言のドイツ語で尋ね回ったが、これまた誰も知らない。さまよい歩いて30分、ようやく「80番地」にたどり着いた。ごく普通の5階建てのビルだ。党本部はその1階にあった。
インターホンのベルを押す。誰も出てこない。「みんなで昼食にでも行ったのか」と思い、ビルの玄関先でタバコをふかしながら20分ほど待った。党員か支持者とおぼしき若者が来たら、ドアが開いた。どうやら「いきなり訪ねてきた怪しげな男」を監視カメラで見ていたようだ。
「日本から来ました。元新聞記者です」と自己紹介すると、仕事をしていた職員が何人か奥のオフィスから出てきた。みんな興味津々といった顔つきだ。日本人が訪ねてきたのは初めてだという(帰国してからさらに調べたところ、都心にもう一つ、議員が陣取る本部があることが分かった)。
「なんでこんな遠いところに党本部を構えてるんですか。地元の人も誰も知らないので、探すのに苦労しました」と、素朴な疑問をぶつけてみた。すると、1人が「警戒する必要があるからです。左翼からの襲撃や破壊活動に備えなければなりません」と答えた。真顔だった。
「現在の問題は演説や多数決ではなく、鉄と血によってのみ解決される」と豪語したのはビスマルクである。19世紀の鉄血宰相の言葉を持ち出すまでもなく、ドイツの政治は血なまぐさい。20世紀前半には、ヒトラー率いるナチスが突撃隊という準軍事組織を使って政敵を武力でねじ伏せた。
ナチスは選挙で第1党になって政権を握り、当時のワイマール憲法の非常大権を使って独裁体制を築き、戦争に突き進んでいった。その苦い歴史を繰り返さないために、戦後つくられた西ドイツの基本法(憲法)は、国民に「自由と民主主義を守るために戦うこと」を義務づけた。戦後の西ドイツは「反ナチス」と「戦う民主主義」を掲げて再出発したのである。
中央政府には「連邦憲法擁護庁」という情報機関があり、憲法秩序に抵触する恐れのある政党や団体を監視して取り締まる権限が与えられている。極右政党のAfDは監視対象になっており、ナチスを称賛する言動をして罰金を科せられた幹部もいる。2013年の結党時から、主要政党もメディアも厳しい目を向けており、身構えざるを得ないのだろう。
私が「初めてドイツに来ました。フランクフルトから入り、ミュンヘンを回って」と言うと、「第一印象はどうですか」と尋ねられた。「こざっぱりして、システムがしっかりしていて規律正しい社会だと思う(a decent, well-organized and well-disciplined society)」と率直に答えると、失笑が漏れた。「それは昔のこと」と言うのだ。
鉄道や地下鉄が定刻通りに運行されていたのは昔のこと。今では遅延は日常茶飯事、突然の運休も珍しくない。街頭にはゴミが散らばっている――延々と愚痴が続いた後、1人が「日本では深夜でも女性が独り歩きできると聞いたが、本当か」と聞いてきた。
新宿の裏社会を描いて秀逸だった馳星周や大沢在昌の小説を読んで得た知識と、ささやかな実体験をもとに「日本のヤクザと中国人マフィアの抗争が激しい時期は治安も良くなかったが、新宿や池袋の主な盛り場を中国人マフィアが抑えてからは落ち着いている。深夜でも若い女性が平気で歩いている」と答えると、顔を見合わせながらうなずいた。
ドイツ国内の、とりわけ大都市の治安の悪化はかなり深刻なようだ。彼らが脳裏に思い浮かべたのは、2015年の大晦日にドイツ西部ケルンで起きた「集団性暴行事件」だったのではないか。事件が起きたのはケルン中央駅と大聖堂の間にある広場である。ここに集まった1000人余りの中東アフリカ系の群衆が新年を祝うお祭り騒ぎの中で、多数の女性に性的暴行を加え、強盗をはたらいた。強姦された女性までいた。
一夜明けた2016年元日、ケルン警察は「大晦日はおおむね平穏だった」というプレスリリースを出した。主要メディアは何も報じなかった。大規模な市民の抗議デモが起き、被害届が殺到した。ケルンの警察長官が記者会見を開いて、事件の概要を発表したのは1月4日のことである。それでも、公共放送のZDFはその日夜のニュースで「群衆の背景が不明」として、この事件を報じなかった。
警察発表の翌5日、ヘンリエッテ・レーカー市長は会見で記者に「女性はどうやって身を守ればいいのか」と問われ、「見知らぬ人々には近づかないこと。腕の長さ以上の距離を保つことは、いつだってできるでしょ」と答え、市民の怒りを増幅した。その後、逮捕された容疑者の中には、難民申請中の者が多数いることが確認された。
警察が事件の発表をためらい、市長がこのような発言をしたのはなぜか。この年、2015年の夏にメルケル首相は「すべての難民を受け入れる」「私たちはやり遂げる」と宣言し、ドイツの難民政策を大転換した。ケルンの市長は当時の政権与党、キリスト教民主同盟(CDU)や緑の党の支援を受ける女性政治家である。「メルケル政権の難民政策を後退させるわけにはいかない」という思いがあった、と見るのが自然だろう。
前回のコラムで、「ドイツには戦後、トルコ系移民と旧ユーゴスラビアからの難民、中東アフリカ系の難民、ウクライナからの難民と4つの大波があった」と記した。だが、実はドイツにはこの前に、もう一つの「語ることを許されなかった、より大きな移民の波」があった。旧ドイツ東部領土からの移民である。

第2次大戦後、ドイツは東プロイセンやポンメルンなど広大な領土を失い、ソ連とポーランドに奪われた。土地によっては数百年にわたってドイツ人が住んでいたところもあったが、いっさいお構いなく、ドイツ系の住民は補償もないまま追放された。混住を認めれば、将来、再び紛争の種になる。戦勝国側は「ドイツ人を一掃する」と宣言し、実行したのである。
ナチス占領下でユダヤ人を東の強制収容所に送り込んだ貨物列車が、今度は追放されたドイツ人を乗せて西へ向かった。荷馬車と徒歩で移動した人々もいた。被追放者の総数は1200万人とも1500万人とも言われる。
移動の途中で、被追放者はポーランド人やユダヤ人、チェコ人らから凄惨な報復を受けた。死者は推定で40万人ないし60万人。戦争によるドイツ本国の破壊と荒廃はすさまじく、旧領土からの移民のことまで手が回らなかったのだろう。その総数も報復による犠牲者の数も、いまだ推計すら定まらない。「旧ドイツ東部領土問題」と呼ばれる。
戦後のドイツは、多くの国民が飢餓線上をさまよう状況にあった。そこに追放された人々が移り住んだ時、どのような境遇に落ちていくか。彼らは「外国人」として疎外されないよう、自らが被追放者であることを隠し、劣悪な条件の下で生きていくしかなかった。
公けの場で追放の辛苦を語ることもできなかった。戦後、ドイツ人による600万人のユダヤ人虐殺や占領直後のポーランドやウクライナでの蛮行が次々に暴かれ、裁かれていったからだ。「被害者としてのドイツ」を語ることは、「加害者としてのドイツの歴史的な罪を中和することになる」と批判され、沈黙するしかなかった。
日本のメディアもこの問題を報じたことはほとんどなかったが、ドイツの旅から戻って間もない10月28日の夜、NHKは「映像の世紀 ドイツ さまよえる人々」というドキュメンタリーを流した。ポーランド兵による殺害と暴行、解放されたユダヤ人による報復の数々・・・。その映像のおぞましさに息をのんだ。
追放された移民たちが「被追放者連盟」を結成して、公然と語り始めたのは21世紀に入ってからである。その体験と哀しみを語るのに60年余りを要した。そのうえ、主要政党からもメディアからも厳しく批判された。60年たっても、周りは「敵だらけ」だった。
ドキュメンタリーは、自らも被追放者だった作家ギュンター・グラスの「ドイツの罪や後悔が長く喫緊の課題であったとはいえ、彼らの苦悩について沈黙してはならない。この問題を右翼に任せてはいけない」という言葉を伝え、最後も彼の「歴史は私たちに慰めを与えてはくれない。私たちはその歴史の中を歩き続けるのだ」という言葉で締めくくっている。
9月のドイツ東部3州での極右政党AfDの躍進は、こうした歴史的な経緯を抜きにして考えることはできない。「統一後も残る東西ドイツの経済格差への不満」という視点だけでは説明できないことが多すぎるのだ。旧西ドイツ地域でも、AfDは着実に支持を広げ続けている。
東部3州の州議選の結果をよく見ると、チューリンゲン州とザクセン州ではショルツ政権の与党、社会民主党(SPD)が惨敗した。ブランデンブルク州ではメルケル前政権の与党、キリスト教民主同盟(CDU)が第4党に転落した(グラフ参照)。
グラフが複雑になるので省略したが、注目されるのはチューリンゲン、ブランデンブルク両州で第3党になった「ザーラ・ワーゲンクネヒト同盟(BSW)」という新しい極左政党である。この政党は、難民政策に関しては「受け入れを制限すべきだ」と訴え、ロシアと戦い続けるウクライナへの武器供与の中止を求めて躍進した。
移民・難民政策とウクライナ戦争への対応では、極右のAfDと極左のBSWが同じような主張をして票を伸ばした。両党とも若者の支持率が高い点も共通している。つまり、戦後ドイツの政界のメインストリームとも言うべき社会民主党(中道左派)とCDU(中道右派)は、その支持基盤を両側から掘り崩されているのである。来年9月の総選挙でAfDはどこまで支持を伸ばすのか。社会民主党もCDUも戦略を練り直しているところだろう。
話をAfD党本部でのやり取りに戻す。彼らは、日本の移民・難民政策に強い関心を示した。難民申請をしても条件が極めて厳しく、なかなか難民として認めない日本の制度は「カナダと並んで、お手本(role model)なのです」とまで言う。
日本で移民と難民の問題を担当しているのは、法務省の外局の出入国在留管理庁である。その所管と名称からして、国際社会の基準から外れている。移民と難民を治安維持の観点から「管理する対象」と捉えているからである。昔ながらの「官尊民卑の感覚」と言える。
ドイツの場合、連邦移民難民庁は内務社会省の管轄下にあり、移民と難民を「困窮した人たちとどう向き合い、社会にどうやって受け入れていくか」という観点で捉えている。難民の申請受付と認定だけでなく、受け入れ後の語学教育や職業訓練まで総合的にカバーしている。要するに、移民も難民も「われわれと同じ人間」として向き合おうとしており、日本とは根本的に異なる。どちらがまともかは言うまでもない。
極右政党のAfDは連邦憲法擁護庁の「監視対象」になっていることを意識しており、移民の「排除」を要求してはいない。「受け入れの制限」を求めている。とはいえ、AfDの支持層は、より過激な団体「西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者(ペギーダ)」の支持層と重なっており、移民・難民政策をどうするかをめぐっては、党内で激しい議論が続いているようだ。
AfD党本部での対話は2時間たっても終わらない。そのうち、先方から「党の幹部に会ってみませんか。セットします」と提案された。私は「明日、ベルリンを離れるんです」と言って辞退したが、その日の夜には英語版で100ページ近い党綱領をメールで送ってきてくれた。
移民・難民問題と並んで、ドイツ政治の重要な課題の一つは「欧州連合(EU)とどう向き合うか」である。帰国してから、AfDの綱領をじっくり読んでみた。綱領には、ドイツ社会の根幹を揺さぶる政策が盛り込まれていた。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2024年11月11日
◇関連記事
(1)ドイツは「第4の大波」に耐えられるか
(2)ドイツの「封印された哀しみ」が噴き出している
(3)ドイツのEU離脱を求める政党の登場
【追記】
ショルツ連立政権は11月6日、与党の自由民主党が連立から離脱し、崩壊した。連立の主軸の社会民主党と緑の党が大規模な財政出動による景気刺激策を唱えたのに対し、財政規律を重視する自民党は反対していた。連立の崩壊に伴って、来年9月に予定されていた総選挙は前倒しされる見通しだ。
【注】
・ドイツのための選択肢(AfD= Alternative für Deutshlandの略称、アーエフデー)
・ナチス(国民社会主義ドイツ労働者党 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei の略称Nazi の複数形。国家社会主義ドイツ労働者党と訳す専門家もいる)
≪写真&地図≫
◎Wikipedia “Flight and expulsion of Germans (1944?1950)”
https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_and_expulsion_of_Germans_(1944%E2%80%931950)
◎ベルリン郊外にある「ドイツのための選択肢(AfD)」の党本部=2024年10月16日、筆者撮影
◎地図 ドイツが第2次大戦後に失った東部領土(英語版ウィキペディアから引用)
https://en.wikipedia.org/wiki/Former_eastern_territories_of_Germany
◎グラフ ドイツ東部3州の州議選の得票率(主要3党)=各州の公式サイトのデータを基に作成
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「ドイツは『第4の大波』に耐えられるか」
◎「支持を広げるドイツのための選択肢」(川畑大地、みずほリサーチ&テクノロジーズ、2024年9月24日)
https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/report/research/express/2024/express-eu240924.html/
◎極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)の公式サイト(ドイツ語だが、日本語や英語への自動翻訳機能付き)
◎ウィキペディア「ギュンター・グラス」
◎ウィキペディア「ケルン大晦日集団性暴行事件」
◎英語版ウィキペディア「2015-2016 New Year’s Eve sexual assaults in Germany」
◎ウィキペディア「旧ドイツ東部領土」
◎ウィキペディア「連邦憲法擁護庁」
◎ドイツ語版ウィキペディア「Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 」(ドイツ語だが、日本語や英語への自動翻訳機能付き)
◎ウィキペディア「西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者(ペギーダ)」
◎「ドイツ移民法・統合法成立の背景と動向」(ハンス・ゲオルク・マーセン、筑波ロー・ジャーナル2号 2007年12月)
https://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/pdf_kiyou/tlj-02/images/hansu.pdf
◎『包摂・共生の政治か、排除の政治か』(宮島喬、佐藤成基編、明石書店)

ところが、ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」は違った。ベルリンの郊外、東京でいえば中野区か練馬区のはずれのようなところに党本部がある。最初、ネットで調べた時は「何かの間違いではないか」と首をかしげたが、AfDの公式サイトに載っているのもその住所だった。アポなしで訪ねることにした。
ベルリンの中心部、ブランデンブルク門の近くにあるホテルから地下鉄と近郊電車を乗り継いで30分ほど。最寄り駅のヴィッテナウに着いた。駅前で住所を示して尋ねたが、誰も知らない。9月の州議選で大躍進を遂げてドイツ政界を揺るがした、いま話題の政党なのに。
住所は「アイヒホルスター通り80番地」と分かっている。近所の住民なら知っているだろうと、片言のドイツ語で尋ね回ったが、これまた誰も知らない。さまよい歩いて30分、ようやく「80番地」にたどり着いた。ごく普通の5階建てのビルだ。党本部はその1階にあった。
インターホンのベルを押す。誰も出てこない。「みんなで昼食にでも行ったのか」と思い、ビルの玄関先でタバコをふかしながら20分ほど待った。党員か支持者とおぼしき若者が来たら、ドアが開いた。どうやら「いきなり訪ねてきた怪しげな男」を監視カメラで見ていたようだ。
「日本から来ました。元新聞記者です」と自己紹介すると、仕事をしていた職員が何人か奥のオフィスから出てきた。みんな興味津々といった顔つきだ。日本人が訪ねてきたのは初めてだという(帰国してからさらに調べたところ、都心にもう一つ、議員が陣取る本部があることが分かった)。
「なんでこんな遠いところに党本部を構えてるんですか。地元の人も誰も知らないので、探すのに苦労しました」と、素朴な疑問をぶつけてみた。すると、1人が「警戒する必要があるからです。左翼からの襲撃や破壊活動に備えなければなりません」と答えた。真顔だった。
「現在の問題は演説や多数決ではなく、鉄と血によってのみ解決される」と豪語したのはビスマルクである。19世紀の鉄血宰相の言葉を持ち出すまでもなく、ドイツの政治は血なまぐさい。20世紀前半には、ヒトラー率いるナチスが突撃隊という準軍事組織を使って政敵を武力でねじ伏せた。
ナチスは選挙で第1党になって政権を握り、当時のワイマール憲法の非常大権を使って独裁体制を築き、戦争に突き進んでいった。その苦い歴史を繰り返さないために、戦後つくられた西ドイツの基本法(憲法)は、国民に「自由と民主主義を守るために戦うこと」を義務づけた。戦後の西ドイツは「反ナチス」と「戦う民主主義」を掲げて再出発したのである。
中央政府には「連邦憲法擁護庁」という情報機関があり、憲法秩序に抵触する恐れのある政党や団体を監視して取り締まる権限が与えられている。極右政党のAfDは監視対象になっており、ナチスを称賛する言動をして罰金を科せられた幹部もいる。2013年の結党時から、主要政党もメディアも厳しい目を向けており、身構えざるを得ないのだろう。
私が「初めてドイツに来ました。フランクフルトから入り、ミュンヘンを回って」と言うと、「第一印象はどうですか」と尋ねられた。「こざっぱりして、システムがしっかりしていて規律正しい社会だと思う(a decent, well-organized and well-disciplined society)」と率直に答えると、失笑が漏れた。「それは昔のこと」と言うのだ。
鉄道や地下鉄が定刻通りに運行されていたのは昔のこと。今では遅延は日常茶飯事、突然の運休も珍しくない。街頭にはゴミが散らばっている――延々と愚痴が続いた後、1人が「日本では深夜でも女性が独り歩きできると聞いたが、本当か」と聞いてきた。
新宿の裏社会を描いて秀逸だった馳星周や大沢在昌の小説を読んで得た知識と、ささやかな実体験をもとに「日本のヤクザと中国人マフィアの抗争が激しい時期は治安も良くなかったが、新宿や池袋の主な盛り場を中国人マフィアが抑えてからは落ち着いている。深夜でも若い女性が平気で歩いている」と答えると、顔を見合わせながらうなずいた。
ドイツ国内の、とりわけ大都市の治安の悪化はかなり深刻なようだ。彼らが脳裏に思い浮かべたのは、2015年の大晦日にドイツ西部ケルンで起きた「集団性暴行事件」だったのではないか。事件が起きたのはケルン中央駅と大聖堂の間にある広場である。ここに集まった1000人余りの中東アフリカ系の群衆が新年を祝うお祭り騒ぎの中で、多数の女性に性的暴行を加え、強盗をはたらいた。強姦された女性までいた。
一夜明けた2016年元日、ケルン警察は「大晦日はおおむね平穏だった」というプレスリリースを出した。主要メディアは何も報じなかった。大規模な市民の抗議デモが起き、被害届が殺到した。ケルンの警察長官が記者会見を開いて、事件の概要を発表したのは1月4日のことである。それでも、公共放送のZDFはその日夜のニュースで「群衆の背景が不明」として、この事件を報じなかった。
警察発表の翌5日、ヘンリエッテ・レーカー市長は会見で記者に「女性はどうやって身を守ればいいのか」と問われ、「見知らぬ人々には近づかないこと。腕の長さ以上の距離を保つことは、いつだってできるでしょ」と答え、市民の怒りを増幅した。その後、逮捕された容疑者の中には、難民申請中の者が多数いることが確認された。
警察が事件の発表をためらい、市長がこのような発言をしたのはなぜか。この年、2015年の夏にメルケル首相は「すべての難民を受け入れる」「私たちはやり遂げる」と宣言し、ドイツの難民政策を大転換した。ケルンの市長は当時の政権与党、キリスト教民主同盟(CDU)や緑の党の支援を受ける女性政治家である。「メルケル政権の難民政策を後退させるわけにはいかない」という思いがあった、と見るのが自然だろう。
前回のコラムで、「ドイツには戦後、トルコ系移民と旧ユーゴスラビアからの難民、中東アフリカ系の難民、ウクライナからの難民と4つの大波があった」と記した。だが、実はドイツにはこの前に、もう一つの「語ることを許されなかった、より大きな移民の波」があった。旧ドイツ東部領土からの移民である。

第2次大戦後、ドイツは東プロイセンやポンメルンなど広大な領土を失い、ソ連とポーランドに奪われた。土地によっては数百年にわたってドイツ人が住んでいたところもあったが、いっさいお構いなく、ドイツ系の住民は補償もないまま追放された。混住を認めれば、将来、再び紛争の種になる。戦勝国側は「ドイツ人を一掃する」と宣言し、実行したのである。
ナチス占領下でユダヤ人を東の強制収容所に送り込んだ貨物列車が、今度は追放されたドイツ人を乗せて西へ向かった。荷馬車と徒歩で移動した人々もいた。被追放者の総数は1200万人とも1500万人とも言われる。
移動の途中で、被追放者はポーランド人やユダヤ人、チェコ人らから凄惨な報復を受けた。死者は推定で40万人ないし60万人。戦争によるドイツ本国の破壊と荒廃はすさまじく、旧領土からの移民のことまで手が回らなかったのだろう。その総数も報復による犠牲者の数も、いまだ推計すら定まらない。「旧ドイツ東部領土問題」と呼ばれる。
戦後のドイツは、多くの国民が飢餓線上をさまよう状況にあった。そこに追放された人々が移り住んだ時、どのような境遇に落ちていくか。彼らは「外国人」として疎外されないよう、自らが被追放者であることを隠し、劣悪な条件の下で生きていくしかなかった。
公けの場で追放の辛苦を語ることもできなかった。戦後、ドイツ人による600万人のユダヤ人虐殺や占領直後のポーランドやウクライナでの蛮行が次々に暴かれ、裁かれていったからだ。「被害者としてのドイツ」を語ることは、「加害者としてのドイツの歴史的な罪を中和することになる」と批判され、沈黙するしかなかった。
日本のメディアもこの問題を報じたことはほとんどなかったが、ドイツの旅から戻って間もない10月28日の夜、NHKは「映像の世紀 ドイツ さまよえる人々」というドキュメンタリーを流した。ポーランド兵による殺害と暴行、解放されたユダヤ人による報復の数々・・・。その映像のおぞましさに息をのんだ。
追放された移民たちが「被追放者連盟」を結成して、公然と語り始めたのは21世紀に入ってからである。その体験と哀しみを語るのに60年余りを要した。そのうえ、主要政党からもメディアからも厳しく批判された。60年たっても、周りは「敵だらけ」だった。
ドキュメンタリーは、自らも被追放者だった作家ギュンター・グラスの「ドイツの罪や後悔が長く喫緊の課題であったとはいえ、彼らの苦悩について沈黙してはならない。この問題を右翼に任せてはいけない」という言葉を伝え、最後も彼の「歴史は私たちに慰めを与えてはくれない。私たちはその歴史の中を歩き続けるのだ」という言葉で締めくくっている。
9月のドイツ東部3州での極右政党AfDの躍進は、こうした歴史的な経緯を抜きにして考えることはできない。「統一後も残る東西ドイツの経済格差への不満」という視点だけでは説明できないことが多すぎるのだ。旧西ドイツ地域でも、AfDは着実に支持を広げ続けている。
東部3州の州議選の結果をよく見ると、チューリンゲン州とザクセン州ではショルツ政権の与党、社会民主党(SPD)が惨敗した。ブランデンブルク州ではメルケル前政権の与党、キリスト教民主同盟(CDU)が第4党に転落した(グラフ参照)。
グラフが複雑になるので省略したが、注目されるのはチューリンゲン、ブランデンブルク両州で第3党になった「ザーラ・ワーゲンクネヒト同盟(BSW)」という新しい極左政党である。この政党は、難民政策に関しては「受け入れを制限すべきだ」と訴え、ロシアと戦い続けるウクライナへの武器供与の中止を求めて躍進した。
移民・難民政策とウクライナ戦争への対応では、極右のAfDと極左のBSWが同じような主張をして票を伸ばした。両党とも若者の支持率が高い点も共通している。つまり、戦後ドイツの政界のメインストリームとも言うべき社会民主党(中道左派)とCDU(中道右派)は、その支持基盤を両側から掘り崩されているのである。来年9月の総選挙でAfDはどこまで支持を伸ばすのか。社会民主党もCDUも戦略を練り直しているところだろう。
話をAfD党本部でのやり取りに戻す。彼らは、日本の移民・難民政策に強い関心を示した。難民申請をしても条件が極めて厳しく、なかなか難民として認めない日本の制度は「カナダと並んで、お手本(role model)なのです」とまで言う。
日本で移民と難民の問題を担当しているのは、法務省の外局の出入国在留管理庁である。その所管と名称からして、国際社会の基準から外れている。移民と難民を治安維持の観点から「管理する対象」と捉えているからである。昔ながらの「官尊民卑の感覚」と言える。
ドイツの場合、連邦移民難民庁は内務社会省の管轄下にあり、移民と難民を「困窮した人たちとどう向き合い、社会にどうやって受け入れていくか」という観点で捉えている。難民の申請受付と認定だけでなく、受け入れ後の語学教育や職業訓練まで総合的にカバーしている。要するに、移民も難民も「われわれと同じ人間」として向き合おうとしており、日本とは根本的に異なる。どちらがまともかは言うまでもない。
極右政党のAfDは連邦憲法擁護庁の「監視対象」になっていることを意識しており、移民の「排除」を要求してはいない。「受け入れの制限」を求めている。とはいえ、AfDの支持層は、より過激な団体「西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者(ペギーダ)」の支持層と重なっており、移民・難民政策をどうするかをめぐっては、党内で激しい議論が続いているようだ。
AfD党本部での対話は2時間たっても終わらない。そのうち、先方から「党の幹部に会ってみませんか。セットします」と提案された。私は「明日、ベルリンを離れるんです」と言って辞退したが、その日の夜には英語版で100ページ近い党綱領をメールで送ってきてくれた。
移民・難民問題と並んで、ドイツ政治の重要な課題の一つは「欧州連合(EU)とどう向き合うか」である。帰国してから、AfDの綱領をじっくり読んでみた。綱領には、ドイツ社会の根幹を揺さぶる政策が盛り込まれていた。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2024年11月11日
◇関連記事
(1)ドイツは「第4の大波」に耐えられるか
(2)ドイツの「封印された哀しみ」が噴き出している
(3)ドイツのEU離脱を求める政党の登場
【追記】
ショルツ連立政権は11月6日、与党の自由民主党が連立から離脱し、崩壊した。連立の主軸の社会民主党と緑の党が大規模な財政出動による景気刺激策を唱えたのに対し、財政規律を重視する自民党は反対していた。連立の崩壊に伴って、来年9月に予定されていた総選挙は前倒しされる見通しだ。
【注】
・ドイツのための選択肢(AfD= Alternative für Deutshlandの略称、アーエフデー)
・ナチス(国民社会主義ドイツ労働者党 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei の略称Nazi の複数形。国家社会主義ドイツ労働者党と訳す専門家もいる)
≪写真&地図≫
◎Wikipedia “Flight and expulsion of Germans (1944?1950)”
https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_and_expulsion_of_Germans_(1944%E2%80%931950)
◎ベルリン郊外にある「ドイツのための選択肢(AfD)」の党本部=2024年10月16日、筆者撮影
◎地図 ドイツが第2次大戦後に失った東部領土(英語版ウィキペディアから引用)
https://en.wikipedia.org/wiki/Former_eastern_territories_of_Germany
◎グラフ ドイツ東部3州の州議選の得票率(主要3党)=各州の公式サイトのデータを基に作成
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「ドイツは『第4の大波』に耐えられるか」
◎「支持を広げるドイツのための選択肢」(川畑大地、みずほリサーチ&テクノロジーズ、2024年9月24日)
https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/report/research/express/2024/express-eu240924.html/
◎極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)の公式サイト(ドイツ語だが、日本語や英語への自動翻訳機能付き)
◎ウィキペディア「ギュンター・グラス」
◎ウィキペディア「ケルン大晦日集団性暴行事件」
◎英語版ウィキペディア「2015-2016 New Year’s Eve sexual assaults in Germany」
◎ウィキペディア「旧ドイツ東部領土」
◎ウィキペディア「連邦憲法擁護庁」
◎ドイツ語版ウィキペディア「Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 」(ドイツ語だが、日本語や英語への自動翻訳機能付き)
◎ウィキペディア「西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者(ペギーダ)」
◎「ドイツ移民法・統合法成立の背景と動向」(ハンス・ゲオルク・マーセン、筑波ロー・ジャーナル2号 2007年12月)
https://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/pdf_kiyou/tlj-02/images/hansu.pdf
◎『包摂・共生の政治か、排除の政治か』(宮島喬、佐藤成基編、明石書店)
新聞記者として長くアジアを担当したので、インドやパキスタン、アフガニスタンから東南アジアまで、この地域の国々はかなり頻繁に訪れた。石油をめぐる連載記事の取材で湾岸の産油国を回ったこともある。だが、「担当地域外」ということで、ヨーロッパの国々を取材する機会はほとんどなかった。
古稀を過ぎて、体力も気力も徐々に衰えてきた。「まだ余力があるうちに取材の空白域に足を運んでみたい」と思い、かねて訪ねてみたかったドイツに10日間の旅に出た。

10月上旬、空路、フランクフルトから入り、中央駅近くのホテルにチェックインした。フランクフルトの繁華街は、中央駅の前に「こぎれいな歌舞伎町」をドスンと置いたような風情だ。駅前から延びる街路にはそれぞれ警察官が配置され、角々には中東系とアフリカ系の若者がたむろしていた。
中央駅から数ブロック奥に入っただけで、あやしいネオンが光り輝き、辻々には街娼が立っている。小さな紙片を広げてコソコソ売買しているのは麻薬だろう。大都市らしい猥雑さだ。夜遅く、散策を終えて駅前のホテルに戻ったが、明け方までパトカーのサイレンがけたたましく鳴り響き、しばしば眠りを妨げられた。
翌朝、駅前のカフェに入った。店員の会話に耳を傾けていたら、「タシャクル」という言葉が聞こえてきた。アフガニスタンの共通語ダリ語(ペルシャ語方言)で「ありがとう」の意味だ。「私は日本から来た。あなたたちはアフガンから?」と英語で尋ねると、少し驚いたような表情で「そうです」と答えた。その店員はウズベク人だという。そこで、カウンターにいるもう1人の店員に「あなたはパシュトゥン人か」と問うと、ビンゴだった。
「なんで分かる」と聞くので、私は「元ジャーナリストで、アフガニスタンには取材で何度も行ったことがある」と答えた。パシュトゥンの若者は、首都カブール北方のパンジシール渓谷の近くで生まれたという。パンジシールと聞いてすぐに思い浮かぶのは、タジク人武装勢力の指導者、マスードである。
マスードが率いる勢力は1992年に社会主義政権を倒して権力を握ったが、4年後にはパシュトゥン人主体のタリバンに首都を追われた。マスードは拠点のパンジシール渓谷に立てこもってタリバンに抵抗し続けたが、2001年9月、アルカイダのメンバーと見られる男たちに自爆テロで殺害された。
当時、アフガニスタンを支配していたタリバンとその庇護下にあったアルカイダにとって、親欧米のマスードはアメリカとの戦争を始めるにあたって「障害になる人物」と見られていた。アメリカと手を組み、背後から攻めてくる恐れがあったからだ。
オサマ・ビン・ラディン率いるアルカイダのメンバーが旅客機を乗っ取り、世界貿易センターと米国防総省に突っ込んだのは、マスード暗殺の2日後、9月11日だった。「アメリカとの聖戦(ジハード)」を始める前に、彼らは「背後の敵」を始末したのである。
パシュトゥンの若者に「ドイツに来てどのくらいになる?」と尋ねた。「20年以上。タリバン政権になって逃げてきた」という。この感じならアフガン料理の店もあるはず、と思って探したら、すぐ近くにレストラン「カブール」があった。その日の夜、この店で羊肉と細切りニンジン、レーズンの炊き込みご飯「マヒチャ・パラウ」を食べた。懐かしい味がした。

戦火のアフガニスタンから逃れる人々の流れは、1979年のソ連のアフガン侵攻とその後の内戦、1990年代のタリバン政権成立前後の混乱、そして2001年9・11テロ後のアメリカとの戦争、と絶えることなく続いた。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によれば、隣国イランとパキスタンには今なお、合わせて500万人を超えるアフガン難民がいる。
隣国での苦しい生活から何とか抜け出したいと願うアフガン難民は、より良い暮らしを求めてヨーロッパを目指す。その中で、最も多くのアフガン難民を受け入れてきたのがドイツだ。連邦統計庁のデータによると、国内のアフガン人は2022年時点で42万人を上回る。ドイツでは、帰化した外国人やドイツ生まれで国籍を取得した子どもは統計上、外国人として扱われないので、アフガン系の人口はこれよりかなり多いと見ていい。
第2次大戦後、ドイツは労働力不足を補うため、トルコやイタリア、スペインなどから大量の移民を受け入れた。彼らは「ガスト・アルバイター(ゲスト労働者)」と呼ばれ、主に鉄鋼業や鉱業、農業部門などで働き、ドイツの戦後復興とその後の経済成長を底支えした。移民・難民のいわば「第1波」で、その数はトルコ人だけで約300万人とされる。
この移民政策は1973年の石油危機で景気が後退すると打ち切られたが、母国に帰らず、家族を呼び寄せて定住する者が多かった。イタリア人やスペイン人はあまり目立たず、社会に溶け込んでいったが、イスラム教徒のトルコ人は肩を寄せ合い、ドイツの中に「別のもう一つの社会」を形成していった。
ドイツは「資格社会」である。ほとんどの職業で公的な資格が必要とされ、一定の教育と職業訓練を経て資格を取らなければ、しかるべき職業に就けない。ドイツ語を覚え、ドイツの習慣に合わせるだけでも大変だ。それを乗り越えて、こうした資格を取るのは容易なことではない。多くのトルコ人は低賃金の仕事で糊口をしのぐしかなかった。
それはドイツ国内でも欧州各国でも広く知られたことだったが、ドイツ国内の「もう一つの社会」の問題にすぎないとして、声高に議論されることはなく、内外のメディアで取り上げられることも極めて少なかった。
ドイツの憲法である基本法には「政治的迫害を受ける者は庇護権を享有する」という条文がある。ナチス時代の圧政を繰り返さないために設けられた規定だ。これがあるため、「ドイツはずっと、難民に広く門戸を開いてきた」と受けとめられがちだが、必ずしもそうではない。国際的なルールに沿って粛々と難民として受け入れてきた、というのが実情だ。国内のトルコ人問題がトゲのように刺さったままであり、慎重な姿勢を保たざるを得なかったのだろう。
それでも、「難民鎖国」と批判される日本に比べれば、はるかに多くの移民と難民を受け入れてきた。アフガン難民に限らず、戦火に追われ困窮した人たちはドイツを目指した。1991年以降、旧ユーゴスラビアでの紛争が激しくなると、押し寄せる難民は急増し、翌1992年には40万人を超える難民がドイツに流れ込んだ。移民・難民の「第2の波」である。
そのピークが過ぎ、落ち着きを取り戻した頃、今度はシリアやイラク、スーダンなど中東アフリカ諸国からものすごい数の難民が押し寄せてきた。欧州連合(EU)には「最初に難民を受け入れた国が責任をもって対処する」というルールがあった。ダブリン規約と呼ばれるもので、特定の国に難民が集中するのを防ぐために定めたものだが、大波に直面したイタリアやギリシャ、オーストリアなどからは「負担に耐えきれない」と悲鳴が上がった。「2015年欧州難民危機」である。
混乱が深まる中で動いたのがドイツだった。当時のメルケル首相はダブリン規約にこだわることなく、「すべての難民を受け入れる」と宣言した。難民政策を大転換し、門戸を大きく広げたのである。国内から湧き上がった批判を、彼女は「私たちはやり遂げる」「困っている人たちに手を差し伸べたことで謝罪しなければならないというのなら、ドイツは私の国ではない」と一蹴した。その決断は、EUの境界周辺で立ち往生する難民たちを何よりも勇気づけるものだった。2015年から翌年にかけて、ドイツには100万人近くの難民が殺到した(グラフ参照)。
中東やアフリカから押し寄せた「第3の波」。ドイツは難民支援を担当する職員や関係施設の拡充に追われ、中央政府と州政府の予算も膨らんでいった。そこへ、2022年のロシアによるウクライナ侵攻である。戦争が激しくなるにつれて、ウクライナから「第4の波」が押し寄せた。ドイツが受け入れた難民はポーランドに次いで多く、100万人を上回った。
トルコからの移住者からウクライナ難民まで、人口約8500万人のドイツは約730万人(全体の8%)の外国人を抱えるに至った。欧州諸国の難民支援は手厚い。とりわけドイツは、難民として認定した人だけでなく、難民申請中の人にも住居を提供し、当面の生活費を支給する。申請した本人だけでなく、子どもや家族向けのドイツ語習得プログラムも充実している。
当然のことながら、移民と難民を支援する予算は膨らむ一方だ。豊かとはいえ、ドイツ経済にかつての勢いはない。国内では少子高齢化と地方の過疎化が進む。「難民ではなく、私たちのために税金を使え」という声が高まるのは避けられないことだった。
16年にわたってドイツを率いたメルケル元首相は、名宰相として今でも海外では高く評価されているが、ここ数年、国内では風向きが変わってきた。「いくら何でも、ここまで難民を受け入れる必要があったのか」「プーチンとツーカーの仲と言われていたのに、ロシアのウクライナ侵攻を止められなかったではないか」といった厳しい批判にさらされている。
こうした流れの中で、今年9月にドイツで行われたチューリンゲンの州議会選挙では、反EUと反移民を唱える極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が第1党に躍り出た。ザクセン州とブランデンブルク州でも躍進し、第2党になった。反ナチスを国是としてきたドイツで極右勢力がこれほど伸びたのは戦後初めてであり、衝撃的な結果だった。
多くのメディアは「東西ドイツの統一後も旧東ドイツ地域は経済的に立ち遅れたままだ。経済格差への不満が噴き出した」と分析したが、その底流に「難民政策への不満」があったことは間違いないだろう。旧東ドイツ地域以外でも確実に支持者を増やしているからだ。
「移民と難民の第4波」が打ち寄せるドイツで、何が起きているのか。ドイツは大波に耐えられるのか。ベルリンにある極右政党AfDの本部を訪れ、彼らの声に耳を傾けてみた。次のコラムで、ドイツ政治の底流を探ってみたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【初出】調査報道サイト「ハンター」 2024年11月1日
◇関連記事
(2)ドイツの「封印された哀しみ」が噴き出している
(3)ドイツのEU離脱を求める政党の登場
≪写真&グラフ≫
◎難民キャンプの子どもたち(著作権フリーの写真サイトPexelsから)
https://www.pexels.com/ja-jp/search/%E9%9B%A3%E6%B0%91/
◎フランクフルト中央駅の近くにあるアフガン料理店「カブール」
(ミュンヘナー通りとモーゼル通りの交差点近く=2024年10月10日、筆者撮影)
◎ドイツへの難民申請者数の推移(ドイツ連邦移民難民庁のデータを基に作成)
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「アフガニスタンの苦悩と誇り」
◎英語版ウィキペディア「Afghans in Germany」
◎「ドイツの『難民』問題とアフガン人の位置」(嶋田晴行、立命館国際研究2019年2月)
https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/31-3_02Shimada.pdf
◎「ドイツ在住トルコ系移民の社会的統合に向けて」(石川真作、立命館言語文化研究29巻1号)
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/kiyou/pdf_29-1/lcs_29_1_ishikawas.pdf
◎「ドイツの移民政策ー統合と選別」(前田直子、獨協大学大学院外国語学研究科)
https://iminseisaku.org/top/conference/090516ms1m.pdf
◎「ドイツはなぜ難民を受け入れるのか」(難民支援協会、2016年8月26日)
◎ドイツ語版ウィキペディア 連邦移民難民庁「Bundesamt für Migration und Flüchtlinge」
◎『移民・難民・外国人労働者と多文化共生―日本とドイツ/歴史と現状―』(増谷英樹編、有志舎)
古稀を過ぎて、体力も気力も徐々に衰えてきた。「まだ余力があるうちに取材の空白域に足を運んでみたい」と思い、かねて訪ねてみたかったドイツに10日間の旅に出た。

10月上旬、空路、フランクフルトから入り、中央駅近くのホテルにチェックインした。フランクフルトの繁華街は、中央駅の前に「こぎれいな歌舞伎町」をドスンと置いたような風情だ。駅前から延びる街路にはそれぞれ警察官が配置され、角々には中東系とアフリカ系の若者がたむろしていた。
中央駅から数ブロック奥に入っただけで、あやしいネオンが光り輝き、辻々には街娼が立っている。小さな紙片を広げてコソコソ売買しているのは麻薬だろう。大都市らしい猥雑さだ。夜遅く、散策を終えて駅前のホテルに戻ったが、明け方までパトカーのサイレンがけたたましく鳴り響き、しばしば眠りを妨げられた。
翌朝、駅前のカフェに入った。店員の会話に耳を傾けていたら、「タシャクル」という言葉が聞こえてきた。アフガニスタンの共通語ダリ語(ペルシャ語方言)で「ありがとう」の意味だ。「私は日本から来た。あなたたちはアフガンから?」と英語で尋ねると、少し驚いたような表情で「そうです」と答えた。その店員はウズベク人だという。そこで、カウンターにいるもう1人の店員に「あなたはパシュトゥン人か」と問うと、ビンゴだった。
「なんで分かる」と聞くので、私は「元ジャーナリストで、アフガニスタンには取材で何度も行ったことがある」と答えた。パシュトゥンの若者は、首都カブール北方のパンジシール渓谷の近くで生まれたという。パンジシールと聞いてすぐに思い浮かぶのは、タジク人武装勢力の指導者、マスードである。
マスードが率いる勢力は1992年に社会主義政権を倒して権力を握ったが、4年後にはパシュトゥン人主体のタリバンに首都を追われた。マスードは拠点のパンジシール渓谷に立てこもってタリバンに抵抗し続けたが、2001年9月、アルカイダのメンバーと見られる男たちに自爆テロで殺害された。
当時、アフガニスタンを支配していたタリバンとその庇護下にあったアルカイダにとって、親欧米のマスードはアメリカとの戦争を始めるにあたって「障害になる人物」と見られていた。アメリカと手を組み、背後から攻めてくる恐れがあったからだ。
オサマ・ビン・ラディン率いるアルカイダのメンバーが旅客機を乗っ取り、世界貿易センターと米国防総省に突っ込んだのは、マスード暗殺の2日後、9月11日だった。「アメリカとの聖戦(ジハード)」を始める前に、彼らは「背後の敵」を始末したのである。
パシュトゥンの若者に「ドイツに来てどのくらいになる?」と尋ねた。「20年以上。タリバン政権になって逃げてきた」という。この感じならアフガン料理の店もあるはず、と思って探したら、すぐ近くにレストラン「カブール」があった。その日の夜、この店で羊肉と細切りニンジン、レーズンの炊き込みご飯「マヒチャ・パラウ」を食べた。懐かしい味がした。

戦火のアフガニスタンから逃れる人々の流れは、1979年のソ連のアフガン侵攻とその後の内戦、1990年代のタリバン政権成立前後の混乱、そして2001年9・11テロ後のアメリカとの戦争、と絶えることなく続いた。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によれば、隣国イランとパキスタンには今なお、合わせて500万人を超えるアフガン難民がいる。
隣国での苦しい生活から何とか抜け出したいと願うアフガン難民は、より良い暮らしを求めてヨーロッパを目指す。その中で、最も多くのアフガン難民を受け入れてきたのがドイツだ。連邦統計庁のデータによると、国内のアフガン人は2022年時点で42万人を上回る。ドイツでは、帰化した外国人やドイツ生まれで国籍を取得した子どもは統計上、外国人として扱われないので、アフガン系の人口はこれよりかなり多いと見ていい。
第2次大戦後、ドイツは労働力不足を補うため、トルコやイタリア、スペインなどから大量の移民を受け入れた。彼らは「ガスト・アルバイター(ゲスト労働者)」と呼ばれ、主に鉄鋼業や鉱業、農業部門などで働き、ドイツの戦後復興とその後の経済成長を底支えした。移民・難民のいわば「第1波」で、その数はトルコ人だけで約300万人とされる。
この移民政策は1973年の石油危機で景気が後退すると打ち切られたが、母国に帰らず、家族を呼び寄せて定住する者が多かった。イタリア人やスペイン人はあまり目立たず、社会に溶け込んでいったが、イスラム教徒のトルコ人は肩を寄せ合い、ドイツの中に「別のもう一つの社会」を形成していった。
ドイツは「資格社会」である。ほとんどの職業で公的な資格が必要とされ、一定の教育と職業訓練を経て資格を取らなければ、しかるべき職業に就けない。ドイツ語を覚え、ドイツの習慣に合わせるだけでも大変だ。それを乗り越えて、こうした資格を取るのは容易なことではない。多くのトルコ人は低賃金の仕事で糊口をしのぐしかなかった。
それはドイツ国内でも欧州各国でも広く知られたことだったが、ドイツ国内の「もう一つの社会」の問題にすぎないとして、声高に議論されることはなく、内外のメディアで取り上げられることも極めて少なかった。
ドイツの憲法である基本法には「政治的迫害を受ける者は庇護権を享有する」という条文がある。ナチス時代の圧政を繰り返さないために設けられた規定だ。これがあるため、「ドイツはずっと、難民に広く門戸を開いてきた」と受けとめられがちだが、必ずしもそうではない。国際的なルールに沿って粛々と難民として受け入れてきた、というのが実情だ。国内のトルコ人問題がトゲのように刺さったままであり、慎重な姿勢を保たざるを得なかったのだろう。
それでも、「難民鎖国」と批判される日本に比べれば、はるかに多くの移民と難民を受け入れてきた。アフガン難民に限らず、戦火に追われ困窮した人たちはドイツを目指した。1991年以降、旧ユーゴスラビアでの紛争が激しくなると、押し寄せる難民は急増し、翌1992年には40万人を超える難民がドイツに流れ込んだ。移民・難民の「第2の波」である。
そのピークが過ぎ、落ち着きを取り戻した頃、今度はシリアやイラク、スーダンなど中東アフリカ諸国からものすごい数の難民が押し寄せてきた。欧州連合(EU)には「最初に難民を受け入れた国が責任をもって対処する」というルールがあった。ダブリン規約と呼ばれるもので、特定の国に難民が集中するのを防ぐために定めたものだが、大波に直面したイタリアやギリシャ、オーストリアなどからは「負担に耐えきれない」と悲鳴が上がった。「2015年欧州難民危機」である。
混乱が深まる中で動いたのがドイツだった。当時のメルケル首相はダブリン規約にこだわることなく、「すべての難民を受け入れる」と宣言した。難民政策を大転換し、門戸を大きく広げたのである。国内から湧き上がった批判を、彼女は「私たちはやり遂げる」「困っている人たちに手を差し伸べたことで謝罪しなければならないというのなら、ドイツは私の国ではない」と一蹴した。その決断は、EUの境界周辺で立ち往生する難民たちを何よりも勇気づけるものだった。2015年から翌年にかけて、ドイツには100万人近くの難民が殺到した(グラフ参照)。
中東やアフリカから押し寄せた「第3の波」。ドイツは難民支援を担当する職員や関係施設の拡充に追われ、中央政府と州政府の予算も膨らんでいった。そこへ、2022年のロシアによるウクライナ侵攻である。戦争が激しくなるにつれて、ウクライナから「第4の波」が押し寄せた。ドイツが受け入れた難民はポーランドに次いで多く、100万人を上回った。
トルコからの移住者からウクライナ難民まで、人口約8500万人のドイツは約730万人(全体の8%)の外国人を抱えるに至った。欧州諸国の難民支援は手厚い。とりわけドイツは、難民として認定した人だけでなく、難民申請中の人にも住居を提供し、当面の生活費を支給する。申請した本人だけでなく、子どもや家族向けのドイツ語習得プログラムも充実している。
当然のことながら、移民と難民を支援する予算は膨らむ一方だ。豊かとはいえ、ドイツ経済にかつての勢いはない。国内では少子高齢化と地方の過疎化が進む。「難民ではなく、私たちのために税金を使え」という声が高まるのは避けられないことだった。
16年にわたってドイツを率いたメルケル元首相は、名宰相として今でも海外では高く評価されているが、ここ数年、国内では風向きが変わってきた。「いくら何でも、ここまで難民を受け入れる必要があったのか」「プーチンとツーカーの仲と言われていたのに、ロシアのウクライナ侵攻を止められなかったではないか」といった厳しい批判にさらされている。
こうした流れの中で、今年9月にドイツで行われたチューリンゲンの州議会選挙では、反EUと反移民を唱える極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が第1党に躍り出た。ザクセン州とブランデンブルク州でも躍進し、第2党になった。反ナチスを国是としてきたドイツで極右勢力がこれほど伸びたのは戦後初めてであり、衝撃的な結果だった。
多くのメディアは「東西ドイツの統一後も旧東ドイツ地域は経済的に立ち遅れたままだ。経済格差への不満が噴き出した」と分析したが、その底流に「難民政策への不満」があったことは間違いないだろう。旧東ドイツ地域以外でも確実に支持者を増やしているからだ。
「移民と難民の第4波」が打ち寄せるドイツで、何が起きているのか。ドイツは大波に耐えられるのか。ベルリンにある極右政党AfDの本部を訪れ、彼らの声に耳を傾けてみた。次のコラムで、ドイツ政治の底流を探ってみたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【初出】調査報道サイト「ハンター」 2024年11月1日
◇関連記事
(2)ドイツの「封印された哀しみ」が噴き出している
(3)ドイツのEU離脱を求める政党の登場
≪写真&グラフ≫
◎難民キャンプの子どもたち(著作権フリーの写真サイトPexelsから)
https://www.pexels.com/ja-jp/search/%E9%9B%A3%E6%B0%91/
◎フランクフルト中央駅の近くにあるアフガン料理店「カブール」
(ミュンヘナー通りとモーゼル通りの交差点近く=2024年10月10日、筆者撮影)
◎ドイツへの難民申請者数の推移(ドイツ連邦移民難民庁のデータを基に作成)
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「アフガニスタンの苦悩と誇り」
◎英語版ウィキペディア「Afghans in Germany」
◎「ドイツの『難民』問題とアフガン人の位置」(嶋田晴行、立命館国際研究2019年2月)
https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/31-3_02Shimada.pdf
◎「ドイツ在住トルコ系移民の社会的統合に向けて」(石川真作、立命館言語文化研究29巻1号)
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/kiyou/pdf_29-1/lcs_29_1_ishikawas.pdf
◎「ドイツの移民政策ー統合と選別」(前田直子、獨協大学大学院外国語学研究科)
https://iminseisaku.org/top/conference/090516ms1m.pdf
◎「ドイツはなぜ難民を受け入れるのか」(難民支援協会、2016年8月26日)
◎ドイツ語版ウィキペディア 連邦移民難民庁「Bundesamt für Migration und Flüchtlinge」
◎『移民・難民・外国人労働者と多文化共生―日本とドイツ/歴史と現状―』(増谷英樹編、有志舎)
2012年から始まった最上川縦断カヌー探訪の記録を紹介し、併せて朝日町出身の民俗文化研究者、柴田謙吾氏(1912年?2010年)が作成した壮大な『最上川絵図』を一般公開するパネル展「最上川を見つめ直す」を、山形県朝日町の文化施設・創遊館で2024年9月17日(火)から9月29日(日)まで開催します(22日は臨時休館)。地域おこしのNPO「ブナの森」が主催します。

最上川をカヌーで下るイベント「最上川縦断カヌー探訪」は、毎年7月最後の週末に開催しています。2012年の第1回探訪の1日目は長井市を出発して、白鷹町から朝日町へと続く五百川(いもがわ)峡谷を下り、2日目は朝日町から中山町まで下りました(写真は五百川峡谷のタンの瀬)。
2013年は豪雨のため中止。2014年以降、少しずつ中流域から下流へと漕ぎ下り、2021年の第9回探訪で、ついに酒田市の最上川河口に到達して「縦断」を達成しました。2022年の第10回探訪からは、1日目は最上川、2日目は流域の湖や峡谷をめぐるツアーをしています(2024年は大雨のため中止)。
カヌー川下りで最上川に親しむ中で、私たちは最上川の民俗文化の研究に打ち込んだ柴田謙吾氏のことを知りました。柴田氏は朝日町の生まれで、会社を経営するかたわら、半世紀にわたって最上川の民俗文化の研究に力を注ぎ、著作物に加えて『最上川絵図』を残してくれました。長さ40メートル、幅60センチの壮大な絵巻物です。
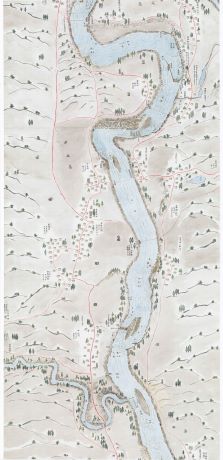
絵図には、流域の村々の名称と人口などが克明に記され、ダム建設で消える前に存在した簗場(やなば)や渡し船の船着場が丁寧に描かれています。舟運で栄えた、かつての最上川の姿を浮かび上がらせる貴重な文化遺産です。絵図が一般公開されるのは7年ぶりです。ぜひ、足をお運びください(上の図は朝日町周辺)。
このパネル展は、朝日町町制70周年記念事業として朝日町の補助金を得て開催するものです。創遊館でのパネル展のあと、10月1日からは朝日町の西部公民館、10月12日からは北部公民館で巡回展示される予定です。ただし、『最上川絵図』の実物が公開されるのは、創遊館ギャラリーだけです。公民館での巡回展示では、絵図の写真パネルの展示になります。
≪柴田謙吾氏の略歴≫
最上川の民俗文化研究者。明治45年(1912年)、桐材商兼農家の次男として山形県大谷村(戦後の合併で朝日町に統合)の栗木沢で生まれる。戦前、中国大陸に渡り、大連語学校を卒業、南満州鉄道に入社した。終戦間際に召集され、朝鮮半島の陸軍部隊に配属されたが、苦難の末、妻の待つ大連に戻った。昭和22年(1947年)に帰国し、山形市旅篭町で菓子原材料の卸売会社の「柴田原料」を創業した。

会社経営の傍ら、昭和30年(1955年)ごろから最上川の民俗調査に乗り出し、舟運の船頭や筏(いかだ)下りの職人たちを訪ね歩いた。川下りの難所や簗場(やなば)など流域の村々についても調査を進めた。昭和44年(1969年)から最上川絵図の作成に乗り出し、10年がかりで長さ40メートル、幅60センチの絵図を完成させた。俳画家としても知られ、著書『最上川小鵜飼船と船頭衆の生活』に多数のスケッチ画が収められている。平成元年(1989年)、山形県社会文化協会から第3回大衆文化賞を受賞。平成22年(2010年)、98歳で死去。

最上川をカヌーで下るイベント「最上川縦断カヌー探訪」は、毎年7月最後の週末に開催しています。2012年の第1回探訪の1日目は長井市を出発して、白鷹町から朝日町へと続く五百川(いもがわ)峡谷を下り、2日目は朝日町から中山町まで下りました(写真は五百川峡谷のタンの瀬)。
2013年は豪雨のため中止。2014年以降、少しずつ中流域から下流へと漕ぎ下り、2021年の第9回探訪で、ついに酒田市の最上川河口に到達して「縦断」を達成しました。2022年の第10回探訪からは、1日目は最上川、2日目は流域の湖や峡谷をめぐるツアーをしています(2024年は大雨のため中止)。
カヌー川下りで最上川に親しむ中で、私たちは最上川の民俗文化の研究に打ち込んだ柴田謙吾氏のことを知りました。柴田氏は朝日町の生まれで、会社を経営するかたわら、半世紀にわたって最上川の民俗文化の研究に力を注ぎ、著作物に加えて『最上川絵図』を残してくれました。長さ40メートル、幅60センチの壮大な絵巻物です。
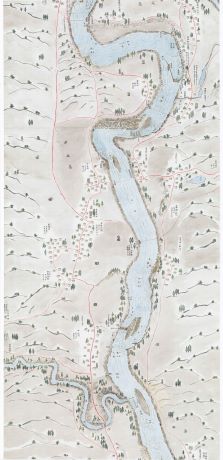
絵図には、流域の村々の名称と人口などが克明に記され、ダム建設で消える前に存在した簗場(やなば)や渡し船の船着場が丁寧に描かれています。舟運で栄えた、かつての最上川の姿を浮かび上がらせる貴重な文化遺産です。絵図が一般公開されるのは7年ぶりです。ぜひ、足をお運びください(上の図は朝日町周辺)。
このパネル展は、朝日町町制70周年記念事業として朝日町の補助金を得て開催するものです。創遊館でのパネル展のあと、10月1日からは朝日町の西部公民館、10月12日からは北部公民館で巡回展示される予定です。ただし、『最上川絵図』の実物が公開されるのは、創遊館ギャラリーだけです。公民館での巡回展示では、絵図の写真パネルの展示になります。
≪柴田謙吾氏の略歴≫
最上川の民俗文化研究者。明治45年(1912年)、桐材商兼農家の次男として山形県大谷村(戦後の合併で朝日町に統合)の栗木沢で生まれる。戦前、中国大陸に渡り、大連語学校を卒業、南満州鉄道に入社した。終戦間際に召集され、朝鮮半島の陸軍部隊に配属されたが、苦難の末、妻の待つ大連に戻った。昭和22年(1947年)に帰国し、山形市旅篭町で菓子原材料の卸売会社の「柴田原料」を創業した。

会社経営の傍ら、昭和30年(1955年)ごろから最上川の民俗調査に乗り出し、舟運の船頭や筏(いかだ)下りの職人たちを訪ね歩いた。川下りの難所や簗場(やなば)など流域の村々についても調査を進めた。昭和44年(1969年)から最上川絵図の作成に乗り出し、10年がかりで長さ40メートル、幅60センチの絵図を完成させた。俳画家としても知られ、著書『最上川小鵜飼船と船頭衆の生活』に多数のスケッチ画が収められている。平成元年(1989年)、山形県社会文化協会から第3回大衆文化賞を受賞。平成22年(2010年)、98歳で死去。
第12回の最上川縦断カヌー探訪は、2024年7月27日(土)、28日(日)の両日開催する予定でしたが、山形県内に25日、大雨が降り、最上川の水量が急増したため中止します。全国各地から50人を超えるカヌーイストが参加を申し込んでくださったのですが、天候の急変で中止のやむなきにいたりました。残念です。来年夏の再開に向けて準備を進めます。
開催要項にのっとり、振り込んでいただいた参加費は半額返金いたします。ブナの森あてに口座の名義と口座番号をお知らせください。よろしくお願いいたします。
開催要項にのっとり、振り込んでいただいた参加費は半額返金いたします。ブナの森あてに口座の名義と口座番号をお知らせください。よろしくお願いいたします。
世の中には、汗水たらして働くことを嫌い、他人をだまして金を儲けようとする輩がいる。そういう人間がIT(情報技術)に目を付けないわけがない。インターネットの世界でも、詐欺師どもが跳梁跋扈している。

彼らは「ITや金融の最先端の動き」に敏感である。対話型の人工知能(AI)であるChatGPTや外国為替保証金取引(FX)を持ち出し、言葉巧みに投資を呼びかけて金をだまし取る。すでに多くの詐欺被害者が発生し、警察が容疑者を逮捕した事件もあるが、ここ最近、とんでもない手口を使うグループが登場した。
朝日新聞や日経新聞、読売新聞のニュースサイトとそっくりの偽サイトを作って著名人を勝手に登場させ、「最先端技術を使って確実に資産を増やす方法がある」と投資を呼び掛けているのだ。最初は「3万5000円の投資で始めましょう」と敷居を低くし、その後、金額を膨らませて全額かすめ取る、という手口である。
12月下旬、Facebook に「著名な起業家のイ―ロン・マスク氏が革命的なAIプロジェクトに乗り出した」という記事を伝える投稿があった。クリックすると、朝日新聞デジタルとそっくりの画面が現れ、「スペシャルリポート」と銘打った記事が表示される。本物の朝日新聞デジタルと同じロゴを使い、サイトのバナーも同じだ(偽サイト1)。
記事では「イーロン・マスク氏が共同設立した企業がAIプロジェクトに数十億円を投資し、暗号通貨の取引を通じて富を生み出す技術を開発した」と伝え、ご丁寧にもマスク氏との独占インタビューなるものまで載せている。
マスク氏は「私たちの目的は、すべての人が自分の願望を手に入れられるようにすること」「世界中の銀行がこの新しいプラットフォームを快く思っておらず、サービスの閉鎖を試みている」と語ったのだという。
もちろん、サイトそのものが偽物で記事もすべてデタラメなのだが、一見しただけでは、朝日新聞の公式サイトと区別が付きにくく、「画期的な技術が開発され、投資のチャンスが到来した。乗り遅れてはいけない」と思い込んでしまう読者もいそうだ。
記事では続けて、「このトレーディング・プラットフォームの人気が急上昇しています」「利用可能な期間が限られている可能性がありますので、すぐに申し込むことを強くお勧めします」「現時点では(日本向けに)37名の枠が残っています」とたたみかけ、口座の開設とその口座への入金を促している。
実に巧みな手口だ。よく考えれば、世界的な起業家が日本の新聞にそのような重大なことを明かすはずもなく、怪しげな話だと分かる。が、このプロジェクトで資産を増やした、という東京の大場健さんやら京都の北澤繁樹さんやら(いずれも架空の人物と思われる)の「実例」が写真と利益額付きで紹介されている。読者の警戒心を緩める仕掛けも巧妙きわまりない。
同じ時期、Facebook には、日本経済新聞のニュースサイトが「トヨタ自動車の豊田章男会長がビットコイン(デジタル通貨)で2000億円の投資をして新しいプロジェクトに乗り出した」との記事が掲載された。こちらも、クリックすると日経の公式サイトと同じロゴを使った偽サイトにつながる(偽サイト2)。
初回に3万5000円を入金すれば、その金が「AIのプログラムで見る見るうちに増えていきます」との触れ込み。朝日新聞デジタルの偽サイトとまったく同じ手口で、同じように口座開設と入金を促すページに誘い込む仕掛けになっている。
Facebookには、読売新聞オンラインの偽サイトも登場した(偽サイト3)。こちらの登場人物は落語家の笑福亭鶴瓶で、ぐっと庶民的だ。鶴瓶が黒柳徹子の「徹子の部屋」に出演し、うっかり「お金持ちになるために働く必要はないんです。この(ビットコイン)プログラムは1日に何万円も稼いでくれるんです」との“秘密”をもらしてしまった、との仕立てだ。その後の投資勧誘の手口は、朝日新聞や日経新聞の偽サイトと変わらない。
この記事では「鶴瓶の発言で日銀が提訴」「放送中に日銀から番組の中断を求められた」などとなっているが、もとがデタラメなのだから、そのような事実もあるはずがない。
こうした罪深いものを掲載したFacebook はどう対応するのか。注視していたら、数日後にはどの偽サイトもFacebook からは消えていた。ただし、偽サイトそのものはネット上に残っているので、SNSで拡散される恐れは消えていない。
この手の話はSNSでアッと言う間に広まる。さっそく、Facebook には「投資詐欺にあいました」とのコメントが寄せられた。大金を失い、コメントを寄せる気力もない人もいることだろう。
そもそも、しかるべき人が見れば、一目でデマと分かる投稿や広告がなぜ、Facebook にはやすやすと載ってしまうのか。その運営方法に改善の余地があるのではないか。朝日新聞や読売新聞、日経新聞の本物のニュースサイトを見れば、デタラメな内容であると簡単に分かるのに・・・。偽サイトを作られ、利用された新聞社の方も、今回は「よくある投資詐欺の一種」と見過ごすべきではないだろう。
この投資詐欺グループは、口座を開いて入金した人にプログラムマネージャーを名乗る人物がしつこく、たどたどしい日本語で追加の投資を求めてくることで知られている。偽サイトの作成は日本人、電話での投資の勧誘は外国人と分業しているようで、かなりの人数がかかわっている、とみられる。
弁護士事務所には、この手の投資詐欺に遭った被害者からの相談が続々と寄せられているようだ。「当事務所には仮想通貨詐欺に強い弁護士がいます」などとうたった弁護士事務所のサイトがいくつもある。
詐欺師は、儲けより損失の方が大きいことを何より嫌う。関与した者たちを詐欺容疑で摘発し、厳罰に処すことが最善の解決策だろう。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【追記(12月25日)】
さらに調べたところ、10月27日にはネット上に「笑福亭鶴瓶の投資話はデマ」と注意を呼びかける投稿があった(下記のURL参照)。Facebook は2カ月近くも詐欺グループの偽サイトを掲載し続けていたことになる。
https://kawagopro.com/syoufukuteitsurube-rumor/
≪偽サイトの説明とURL≫
◎偽サイト1
Facebookに掲載された朝日新聞デジタルの偽サイト(2023年12月22日時点)
https://heilpraktiker-hamburg.com/products/wheres-my-catty-goodie-hoodie?promoted_link_id=kQ5dKQZGt8jbdN&adset_name=New%20Leads%20Ad%20Set%20-%20Copy7&fbclid=IwAR2PEdmtf-jx40FkEwANWTDI-o7a2-2eoMEVN_MoUJ623paFPOZAtSjjFpg
◎偽サイト2
Facebookに掲載された日本経済新聞の偽サイト(2023年12月22日時点)
https://growthopportunitiesforyou.com/products/1636-30728196-short-en-molleton-motif-tropical-west49-homme?fbclid=IwAR3jh18Tud2XTqD8aBcSddRYAX3KfqXuOCHYSIuf4mgHg8n2fnOhG5k6eUA
◎偽サイト3
Facebookに掲載された読売新聞オンラインの偽サイト(2023年12月22日時点)
https://etmirror.top/products/puma-palermo-og-sneakers-cobalt?utm_content=VahJwyb3DTLsmvN&adset_name=JP%20%E2%80%93%20Copy&fbclid=IwAR2YuQhzKCVpex5N-5s233YZQxQ55c09uTvsbMIC6mBcuVSjMCtNASGZcPs

彼らは「ITや金融の最先端の動き」に敏感である。対話型の人工知能(AI)であるChatGPTや外国為替保証金取引(FX)を持ち出し、言葉巧みに投資を呼びかけて金をだまし取る。すでに多くの詐欺被害者が発生し、警察が容疑者を逮捕した事件もあるが、ここ最近、とんでもない手口を使うグループが登場した。
朝日新聞や日経新聞、読売新聞のニュースサイトとそっくりの偽サイトを作って著名人を勝手に登場させ、「最先端技術を使って確実に資産を増やす方法がある」と投資を呼び掛けているのだ。最初は「3万5000円の投資で始めましょう」と敷居を低くし、その後、金額を膨らませて全額かすめ取る、という手口である。
12月下旬、Facebook に「著名な起業家のイ―ロン・マスク氏が革命的なAIプロジェクトに乗り出した」という記事を伝える投稿があった。クリックすると、朝日新聞デジタルとそっくりの画面が現れ、「スペシャルリポート」と銘打った記事が表示される。本物の朝日新聞デジタルと同じロゴを使い、サイトのバナーも同じだ(偽サイト1)。
記事では「イーロン・マスク氏が共同設立した企業がAIプロジェクトに数十億円を投資し、暗号通貨の取引を通じて富を生み出す技術を開発した」と伝え、ご丁寧にもマスク氏との独占インタビューなるものまで載せている。
マスク氏は「私たちの目的は、すべての人が自分の願望を手に入れられるようにすること」「世界中の銀行がこの新しいプラットフォームを快く思っておらず、サービスの閉鎖を試みている」と語ったのだという。
もちろん、サイトそのものが偽物で記事もすべてデタラメなのだが、一見しただけでは、朝日新聞の公式サイトと区別が付きにくく、「画期的な技術が開発され、投資のチャンスが到来した。乗り遅れてはいけない」と思い込んでしまう読者もいそうだ。
記事では続けて、「このトレーディング・プラットフォームの人気が急上昇しています」「利用可能な期間が限られている可能性がありますので、すぐに申し込むことを強くお勧めします」「現時点では(日本向けに)37名の枠が残っています」とたたみかけ、口座の開設とその口座への入金を促している。
実に巧みな手口だ。よく考えれば、世界的な起業家が日本の新聞にそのような重大なことを明かすはずもなく、怪しげな話だと分かる。が、このプロジェクトで資産を増やした、という東京の大場健さんやら京都の北澤繁樹さんやら(いずれも架空の人物と思われる)の「実例」が写真と利益額付きで紹介されている。読者の警戒心を緩める仕掛けも巧妙きわまりない。
同じ時期、Facebook には、日本経済新聞のニュースサイトが「トヨタ自動車の豊田章男会長がビットコイン(デジタル通貨)で2000億円の投資をして新しいプロジェクトに乗り出した」との記事が掲載された。こちらも、クリックすると日経の公式サイトと同じロゴを使った偽サイトにつながる(偽サイト2)。
初回に3万5000円を入金すれば、その金が「AIのプログラムで見る見るうちに増えていきます」との触れ込み。朝日新聞デジタルの偽サイトとまったく同じ手口で、同じように口座開設と入金を促すページに誘い込む仕掛けになっている。
Facebookには、読売新聞オンラインの偽サイトも登場した(偽サイト3)。こちらの登場人物は落語家の笑福亭鶴瓶で、ぐっと庶民的だ。鶴瓶が黒柳徹子の「徹子の部屋」に出演し、うっかり「お金持ちになるために働く必要はないんです。この(ビットコイン)プログラムは1日に何万円も稼いでくれるんです」との“秘密”をもらしてしまった、との仕立てだ。その後の投資勧誘の手口は、朝日新聞や日経新聞の偽サイトと変わらない。
この記事では「鶴瓶の発言で日銀が提訴」「放送中に日銀から番組の中断を求められた」などとなっているが、もとがデタラメなのだから、そのような事実もあるはずがない。
こうした罪深いものを掲載したFacebook はどう対応するのか。注視していたら、数日後にはどの偽サイトもFacebook からは消えていた。ただし、偽サイトそのものはネット上に残っているので、SNSで拡散される恐れは消えていない。
この手の話はSNSでアッと言う間に広まる。さっそく、Facebook には「投資詐欺にあいました」とのコメントが寄せられた。大金を失い、コメントを寄せる気力もない人もいることだろう。
そもそも、しかるべき人が見れば、一目でデマと分かる投稿や広告がなぜ、Facebook にはやすやすと載ってしまうのか。その運営方法に改善の余地があるのではないか。朝日新聞や読売新聞、日経新聞の本物のニュースサイトを見れば、デタラメな内容であると簡単に分かるのに・・・。偽サイトを作られ、利用された新聞社の方も、今回は「よくある投資詐欺の一種」と見過ごすべきではないだろう。
この投資詐欺グループは、口座を開いて入金した人にプログラムマネージャーを名乗る人物がしつこく、たどたどしい日本語で追加の投資を求めてくることで知られている。偽サイトの作成は日本人、電話での投資の勧誘は外国人と分業しているようで、かなりの人数がかかわっている、とみられる。
弁護士事務所には、この手の投資詐欺に遭った被害者からの相談が続々と寄せられているようだ。「当事務所には仮想通貨詐欺に強い弁護士がいます」などとうたった弁護士事務所のサイトがいくつもある。
詐欺師は、儲けより損失の方が大きいことを何より嫌う。関与した者たちを詐欺容疑で摘発し、厳罰に処すことが最善の解決策だろう。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【追記(12月25日)】
さらに調べたところ、10月27日にはネット上に「笑福亭鶴瓶の投資話はデマ」と注意を呼びかける投稿があった(下記のURL参照)。Facebook は2カ月近くも詐欺グループの偽サイトを掲載し続けていたことになる。
https://kawagopro.com/syoufukuteitsurube-rumor/
≪偽サイトの説明とURL≫
◎偽サイト1
Facebookに掲載された朝日新聞デジタルの偽サイト(2023年12月22日時点)
https://heilpraktiker-hamburg.com/products/wheres-my-catty-goodie-hoodie?promoted_link_id=kQ5dKQZGt8jbdN&adset_name=New%20Leads%20Ad%20Set%20-%20Copy7&fbclid=IwAR2PEdmtf-jx40FkEwANWTDI-o7a2-2eoMEVN_MoUJ623paFPOZAtSjjFpg
◎偽サイト2
Facebookに掲載された日本経済新聞の偽サイト(2023年12月22日時点)
https://growthopportunitiesforyou.com/products/1636-30728196-short-en-molleton-motif-tropical-west49-homme?fbclid=IwAR3jh18Tud2XTqD8aBcSddRYAX3KfqXuOCHYSIuf4mgHg8n2fnOhG5k6eUA
◎偽サイト3
Facebookに掲載された読売新聞オンラインの偽サイト(2023年12月22日時点)
https://etmirror.top/products/puma-palermo-og-sneakers-cobalt?utm_content=VahJwyb3DTLsmvN&adset_name=JP%20%E2%80%93%20Copy&fbclid=IwAR2YuQhzKCVpex5N-5s233YZQxQ55c09uTvsbMIC6mBcuVSjMCtNASGZcPs
山形県の戸沢(とざわ)村には「最上川舟下り」の会社がある。江戸時代に船番所があった場所に本社を構え、冬には和船にコタツをしつらえた「コタツ舟」を運航している。鍋をつつきながら熱燗を手に、雄大な最上峡の冬景色を楽しむことができる。
そんな戸沢村で最近、こんなことがあった。
その男性は夏でも冬でも、朝の4時半に散歩に行くことを日課にしている。夏なら薄明るくなっているが、冬が近づけば、4時半では真っ暗だ。

それでも、彼はいつも通り、4時半に散歩にでかけた。歩き慣れたコース。暗闇でも道に迷うことはない。が、街灯のあるところに差しかかったら前を行くものがいる。「誰だ」と思ってよく見たら、ツキノワグマが歩いていたという。
それを伝え聞いた人がひと言、「知らないうちに追い越さなくて、よかったね」。もし、暗がりですれ違ったりしていたら、こんな軽口はたたけなかっただろう。
熊にまつわる話なら、戸沢村を持ち出すまでもない。私が暮らしている山形・新潟県境沿いの朝日町では農作物、とりわけリンゴ農家が大打撃を受けている。
朝日町は「無袋(むたい)フジ 発祥の地」として知られる。かつて、リンゴ栽培では1個1個に袋をかけて栽培するのが普通だったが、その袋掛けをしないでフジリンゴを栽培する手法を編み出した町である。太陽の光をたっぷり浴びさせることで、糖分やビタミンを豊富に含むリンゴができる。
そのリンゴ栽培の名人の畑がこの秋、熊に荒らされた。人家から遠い、山あいの畑にある10本のリンゴの木が収穫寸前にすべて熊に食べられてしまったのだ。1頭で食べきれる量ではない。何頭もの熊が入れ代わり立ち代わりやって来たようだ。
1本のリンゴの木からは、約1000個のリンゴが収穫できる。全部で1万個前後。これほどの被害は初めてで、さすがの名人も肩を落としていたという。10本どころか、手塩にかけて育ててきたリンゴをほとんど食べられてしまった篤農家もいる。
今年は全国的に熊が人里に下りてきて人を襲う事例が相次いだ。北海道のヒグマはともかく、本州に生息するツキノワグマは体長1.5メートルほどで、元来、それほど戦闘的ではない。人里に出てきて人間に出くわし、驚いて攻撃してしまったというケースが多のではないか。
問題は「なぜ、人里に下りてくるようになったのか」である。専門家は「エサとなるドングリが今年は不作だから」と解説している。それも大きな理由のようだが、もっと根本的な理由もある。
それは、人間が里山にあまり出入りしなくなったことだ。熊は臭覚が鋭い。山の畑や森に人間が通い、働いていた時代は「人間の臭い」を敏感に嗅ぎ分け、「ここいらは人間の縄張りだ」と警戒して、あまり出入りしなかったと考えられる。
ところが、農業も林業もすたれ、山の畑は荒れ放題。山林も手入れが行き届かない。ツキノワグマにしてみれば、「誰も出入りしないなら、おいらの縄張りにしてしまえ」と決め込んだのではないか。同じリンゴ畑でも、人家の近くより山あいにあるリンゴ畑で被害が続発しているのは、熊が自分の縄張りとみなした結果だろう。
里山まで縄張りを広げた熊の一部は、さらに人家の近くや市街地にまで足を延ばしたと考えられる。柿も栗もリンゴも、人間がたくさん植えてくれた。熊は「格好のエサ場」とみなして、これを当てにする個体が増えた、と見るのが自然だ。
人間の暮らしの変容が熊の生態にも影響を及ぼし、両者の境界線がぼやけてしまった結果が「熊の出没多発となって表れた」と言えるのではないか。
熊に襲われて亡くなった方やけがをした方の多さを考えれば、市街地や人里に出てきた熊を殺害するのはやむを得ない。農作物の被害の甚大さも考え合せれば、「熊と人間が共存する道はないか」などと悠長に構えていられる状況ではない。熊に加えてイノシシの食害に苦しむ農家にとっては、死活問題になりつつある。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン風切通信 123 (2023年11月25日配信)
≪写真説明≫
◎ツキノワグマ(よこはま動物園のサイトから)
https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/animal/yamazato/JapaneseBlackBear/
≪参考サイト≫
◎「最上川芭蕉ライン舟下り」(山形県戸沢村)のサイト
https://www.blf.co.jp/
◎「山形 味の農園」のサイト
https://www.ajfarm.com/1916/
そんな戸沢村で最近、こんなことがあった。
その男性は夏でも冬でも、朝の4時半に散歩に行くことを日課にしている。夏なら薄明るくなっているが、冬が近づけば、4時半では真っ暗だ。

それでも、彼はいつも通り、4時半に散歩にでかけた。歩き慣れたコース。暗闇でも道に迷うことはない。が、街灯のあるところに差しかかったら前を行くものがいる。「誰だ」と思ってよく見たら、ツキノワグマが歩いていたという。
それを伝え聞いた人がひと言、「知らないうちに追い越さなくて、よかったね」。もし、暗がりですれ違ったりしていたら、こんな軽口はたたけなかっただろう。
熊にまつわる話なら、戸沢村を持ち出すまでもない。私が暮らしている山形・新潟県境沿いの朝日町では農作物、とりわけリンゴ農家が大打撃を受けている。
朝日町は「無袋(むたい)フジ 発祥の地」として知られる。かつて、リンゴ栽培では1個1個に袋をかけて栽培するのが普通だったが、その袋掛けをしないでフジリンゴを栽培する手法を編み出した町である。太陽の光をたっぷり浴びさせることで、糖分やビタミンを豊富に含むリンゴができる。
そのリンゴ栽培の名人の畑がこの秋、熊に荒らされた。人家から遠い、山あいの畑にある10本のリンゴの木が収穫寸前にすべて熊に食べられてしまったのだ。1頭で食べきれる量ではない。何頭もの熊が入れ代わり立ち代わりやって来たようだ。
1本のリンゴの木からは、約1000個のリンゴが収穫できる。全部で1万個前後。これほどの被害は初めてで、さすがの名人も肩を落としていたという。10本どころか、手塩にかけて育ててきたリンゴをほとんど食べられてしまった篤農家もいる。
今年は全国的に熊が人里に下りてきて人を襲う事例が相次いだ。北海道のヒグマはともかく、本州に生息するツキノワグマは体長1.5メートルほどで、元来、それほど戦闘的ではない。人里に出てきて人間に出くわし、驚いて攻撃してしまったというケースが多のではないか。
問題は「なぜ、人里に下りてくるようになったのか」である。専門家は「エサとなるドングリが今年は不作だから」と解説している。それも大きな理由のようだが、もっと根本的な理由もある。
それは、人間が里山にあまり出入りしなくなったことだ。熊は臭覚が鋭い。山の畑や森に人間が通い、働いていた時代は「人間の臭い」を敏感に嗅ぎ分け、「ここいらは人間の縄張りだ」と警戒して、あまり出入りしなかったと考えられる。
ところが、農業も林業もすたれ、山の畑は荒れ放題。山林も手入れが行き届かない。ツキノワグマにしてみれば、「誰も出入りしないなら、おいらの縄張りにしてしまえ」と決め込んだのではないか。同じリンゴ畑でも、人家の近くより山あいにあるリンゴ畑で被害が続発しているのは、熊が自分の縄張りとみなした結果だろう。
里山まで縄張りを広げた熊の一部は、さらに人家の近くや市街地にまで足を延ばしたと考えられる。柿も栗もリンゴも、人間がたくさん植えてくれた。熊は「格好のエサ場」とみなして、これを当てにする個体が増えた、と見るのが自然だ。
人間の暮らしの変容が熊の生態にも影響を及ぼし、両者の境界線がぼやけてしまった結果が「熊の出没多発となって表れた」と言えるのではないか。
熊に襲われて亡くなった方やけがをした方の多さを考えれば、市街地や人里に出てきた熊を殺害するのはやむを得ない。農作物の被害の甚大さも考え合せれば、「熊と人間が共存する道はないか」などと悠長に構えていられる状況ではない。熊に加えてイノシシの食害に苦しむ農家にとっては、死活問題になりつつある。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン風切通信 123 (2023年11月25日配信)
≪写真説明≫
◎ツキノワグマ(よこはま動物園のサイトから)
https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/animal/yamazato/JapaneseBlackBear/
≪参考サイト≫
◎「最上川芭蕉ライン舟下り」(山形県戸沢村)のサイト
https://www.blf.co.jp/
◎「山形 味の農園」のサイト
https://www.ajfarm.com/1916/
日本の新聞記者は入社すると警察担当、いわゆる「サツ回り」からキャリアをスタートさせることが多い。私もそうだった。最初の数日は「とにかく、刑事部屋にずっと座っていろ。デカの名前と顔を覚えろ。自分の名前も覚えてもらえ」と命じられた。

大学で多少、法律を勉強していてもほとんど役に立たない。なにせ、刑事たちは生の事件を扱っている。無愛想で取り付く島もない。刑事たちが何をしているのか、まるで分からないまま、数カ月が過ぎた。
ある日、読売新聞に抜かれた。翌日は毎日新聞に抜かれた。地元の静岡新聞も特ダネを放つ。他社の記者がどうやってスクープをものにするのか、まるで分からなかった。朝日新聞の当時の上司から、「記者に向いてないんじゃないか?(会社を)辞めたら」と叱責された。
悔しくて涙が出そうになったが、泣いているわけにもいかない。刑事たちがよく行く赤提灯の飲み屋を回り、彼らの自宅を夜回りしてネタ集めを続けた。そのうち、憐れんだ刑事の一人が手がけている事件についてヒントをくれた。それを手がかりにして、やっと小さな「特ダネ」を書き、一矢報いることができた。
他社に抜かれるたびに、先輩記者にこう諭(さと)された。「クヨクヨすんな!きちんと追いかけろ。読者は一つの新聞しかとってないんだ。お前が書かなければ、知るすべがないだろ」。その通りだと思った。どこに抜かれたのか。なぜ、抜かれたのか。読者にとって、そんなことはどうでもいいことだ。読者に届けるべきニュースかどうか。それがすべてだと知った。
週刊文春はこの1カ月、木原誠二・官房副長官の妻が2006年に当時夫だった男性の変死に関与した疑いがあり、2018年に警視庁が殺人事件として再捜査を進めたが、木原氏の圧力で事件捜査が潰された疑いがある、と連続して報じた。
その報道内容は詳細かつ具体的だ。証言や証拠は報道内容を裏付けるに十分で、調査報道のお手本のような報道だ。変死した元夫の遺族は警察に再捜査を求め、7月20日に記者会見を開いた。ついには、2018年当時、警視庁捜査一課の殺人担当の刑事だった佐藤誠・元警部補(昨年退職)が実名で捜査の実情と捜査終了に至った経緯を文春の記者に赤裸々に語り、記者会見まで開いた(7月28日)。
佐藤元警部補が告発に至ったきっかけは、警察のトップである露木康浩・警察庁長官が7月13日の記者会見で「警視庁において捜査等の結果、証拠上、事件性が認められない旨を明らかにしている」と述べたことだ。
佐藤氏ら現場の刑事たちは未解決になっていた事件を掘り起こし、真相を解明するために力を尽くした。なのに、警察のトップが「そもそも事件ではなかった」と全否定したのだ。現場にとっては許しがたいことである。義憤に駆られての証言、と言える。警察庁の長官と現場の刑事のどちらが本当のことを語っているのか。少しでも事件を担当したことのある新聞記者なら「現場の刑事にはウソを言う理由がない」と、確信をもって言えるはずだ。
では、全国紙やNHKを含むテレビ各局が週刊文春の報道を黙殺しているのはなぜか。権力にピタリと寄り添うのを旨とする読売新聞が静観するのはよく分かる。ある意味、一貫している。だが、常日頃、権力の監視役を自任する朝日新聞や毎日新聞はなぜ、きちんと報じようとしないのか。
「いや、報じている」と言うのかもしれない。確かに、両紙は「松野博一官房長官は『週刊文春の報道は事実無根』と木原氏から報告を受けたと語った」などとベタ記事で報じた(7月28日、29日)。こういうのを「アリバイ記事」という。「黙殺なんかしてないよ」と取り繕うための記事だからだ。
全国紙の事件記者たちは「警察が事件ではない、と言っているものを報道するわけにはいかない」と言いたいのかもしれない。「ふざけるな」と言いたい。何が事件で、何を報じるかは報道機関が自ら判断すべきことだ。こういう問題で権力に寄りかかって、どうするのか。
「警察が事件として扱わないものは報じない」などと言っていたら、1988年のリクルート事件の報道はあり得なかった。この事件は、リクルート社が子会社の未公開株を賄賂として政治家や官僚らにバラまいた汚職事件だが、神奈川県警は上からの圧力に負けて捜査を投げ出した。
それを朝日新聞横浜支局の記者たちが掘り起こし、最後には当時の竹下内閣を総辞職に追い込んだ。「事件かどうか」の判断を権力側にゆだねていたら、決して明るみに出ることはなかった。その貴重な教訓を忘れたのか。
リクルート事件で問われたのは「贈収賄」だった。つまり、金品のやり取りである。重い罪であることに変わりはないが、今回、週刊文春が追及しているのは「人の命を奪う殺人」というさらに重大な罪である。こういう犯罪についてまで、政治家が権力をふりかざし、捜査を潰すのを許していたら、社会はどうなるのか。「法の支配」どころではない。「人としての道義」がすたれてしまう。
どんな社会でも、権力を握る者たちは自分たちに都合がいいように事を運ぼうとする。だが、そこにもおのずから「節度」というものがあるはずだ。それすら見失ったら、社会は漂流し、あらぬ方向に走り出す。「節度」まで崩れようとする時、それを押しとどめるものは「心ある者たちの覚悟」しかない。
今回の週刊文春の報道は、今の日本社会で「心ある者たち」がどこにいるか、それを炙り出す結果になった。全国紙やテレビ各局はてんでダメだが、東京新聞や河北新報などのブロック紙は立ち上がりつつある。河北新報は7月28日付で「文春報道 木原副長官が苦境」と報じ、東京新聞は8月2日付の「こちら特報部」で、木原副長官が報道陣との会見を避け、外遊もやめて「公務に支障」が生じている、と伝えた。
殺人事件の再捜査の状況と捜査終了に至った経緯を証言した佐藤元警部補に対して、「地方公務員法に定められた守秘義務に違反しているのではないか」と追及する向きがある。確かに、条文に照らせば、守秘義務に触れる可能性はある。
だが、「人としての道に反することをしている人たち」がいる時に「おかしい」と声をあげることが法律違反に問われるとしたら、それはどんな社会なのか。私たちはそんな社会になることを望んでいるのか。断じて否、である。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:ウェブコラム「情報屋台」 2023年8月3日
http://www.johoyatai.com/6160
≪写真説明≫
◎木原誠二・官房副長官(時事通信のサイトから)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023073100648&g=pol
≪参考記事≫
◎『週刊文春』7月13日号、7月20日号、7月27日号、8月3日号、8月10日号
◎朝日新聞7月25日付、7月28日付
◎毎日新聞7月29日付、読売新聞7月29日付
◎河北新報7月28日付
◎東京新聞8月2日付
*東京新聞以外は、山形県で発行されている新聞の日付

大学で多少、法律を勉強していてもほとんど役に立たない。なにせ、刑事たちは生の事件を扱っている。無愛想で取り付く島もない。刑事たちが何をしているのか、まるで分からないまま、数カ月が過ぎた。
ある日、読売新聞に抜かれた。翌日は毎日新聞に抜かれた。地元の静岡新聞も特ダネを放つ。他社の記者がどうやってスクープをものにするのか、まるで分からなかった。朝日新聞の当時の上司から、「記者に向いてないんじゃないか?(会社を)辞めたら」と叱責された。
悔しくて涙が出そうになったが、泣いているわけにもいかない。刑事たちがよく行く赤提灯の飲み屋を回り、彼らの自宅を夜回りしてネタ集めを続けた。そのうち、憐れんだ刑事の一人が手がけている事件についてヒントをくれた。それを手がかりにして、やっと小さな「特ダネ」を書き、一矢報いることができた。
他社に抜かれるたびに、先輩記者にこう諭(さと)された。「クヨクヨすんな!きちんと追いかけろ。読者は一つの新聞しかとってないんだ。お前が書かなければ、知るすべがないだろ」。その通りだと思った。どこに抜かれたのか。なぜ、抜かれたのか。読者にとって、そんなことはどうでもいいことだ。読者に届けるべきニュースかどうか。それがすべてだと知った。
週刊文春はこの1カ月、木原誠二・官房副長官の妻が2006年に当時夫だった男性の変死に関与した疑いがあり、2018年に警視庁が殺人事件として再捜査を進めたが、木原氏の圧力で事件捜査が潰された疑いがある、と連続して報じた。
その報道内容は詳細かつ具体的だ。証言や証拠は報道内容を裏付けるに十分で、調査報道のお手本のような報道だ。変死した元夫の遺族は警察に再捜査を求め、7月20日に記者会見を開いた。ついには、2018年当時、警視庁捜査一課の殺人担当の刑事だった佐藤誠・元警部補(昨年退職)が実名で捜査の実情と捜査終了に至った経緯を文春の記者に赤裸々に語り、記者会見まで開いた(7月28日)。
佐藤元警部補が告発に至ったきっかけは、警察のトップである露木康浩・警察庁長官が7月13日の記者会見で「警視庁において捜査等の結果、証拠上、事件性が認められない旨を明らかにしている」と述べたことだ。
佐藤氏ら現場の刑事たちは未解決になっていた事件を掘り起こし、真相を解明するために力を尽くした。なのに、警察のトップが「そもそも事件ではなかった」と全否定したのだ。現場にとっては許しがたいことである。義憤に駆られての証言、と言える。警察庁の長官と現場の刑事のどちらが本当のことを語っているのか。少しでも事件を担当したことのある新聞記者なら「現場の刑事にはウソを言う理由がない」と、確信をもって言えるはずだ。
では、全国紙やNHKを含むテレビ各局が週刊文春の報道を黙殺しているのはなぜか。権力にピタリと寄り添うのを旨とする読売新聞が静観するのはよく分かる。ある意味、一貫している。だが、常日頃、権力の監視役を自任する朝日新聞や毎日新聞はなぜ、きちんと報じようとしないのか。
「いや、報じている」と言うのかもしれない。確かに、両紙は「松野博一官房長官は『週刊文春の報道は事実無根』と木原氏から報告を受けたと語った」などとベタ記事で報じた(7月28日、29日)。こういうのを「アリバイ記事」という。「黙殺なんかしてないよ」と取り繕うための記事だからだ。
全国紙の事件記者たちは「警察が事件ではない、と言っているものを報道するわけにはいかない」と言いたいのかもしれない。「ふざけるな」と言いたい。何が事件で、何を報じるかは報道機関が自ら判断すべきことだ。こういう問題で権力に寄りかかって、どうするのか。
「警察が事件として扱わないものは報じない」などと言っていたら、1988年のリクルート事件の報道はあり得なかった。この事件は、リクルート社が子会社の未公開株を賄賂として政治家や官僚らにバラまいた汚職事件だが、神奈川県警は上からの圧力に負けて捜査を投げ出した。
それを朝日新聞横浜支局の記者たちが掘り起こし、最後には当時の竹下内閣を総辞職に追い込んだ。「事件かどうか」の判断を権力側にゆだねていたら、決して明るみに出ることはなかった。その貴重な教訓を忘れたのか。
リクルート事件で問われたのは「贈収賄」だった。つまり、金品のやり取りである。重い罪であることに変わりはないが、今回、週刊文春が追及しているのは「人の命を奪う殺人」というさらに重大な罪である。こういう犯罪についてまで、政治家が権力をふりかざし、捜査を潰すのを許していたら、社会はどうなるのか。「法の支配」どころではない。「人としての道義」がすたれてしまう。
どんな社会でも、権力を握る者たちは自分たちに都合がいいように事を運ぼうとする。だが、そこにもおのずから「節度」というものがあるはずだ。それすら見失ったら、社会は漂流し、あらぬ方向に走り出す。「節度」まで崩れようとする時、それを押しとどめるものは「心ある者たちの覚悟」しかない。
今回の週刊文春の報道は、今の日本社会で「心ある者たち」がどこにいるか、それを炙り出す結果になった。全国紙やテレビ各局はてんでダメだが、東京新聞や河北新報などのブロック紙は立ち上がりつつある。河北新報は7月28日付で「文春報道 木原副長官が苦境」と報じ、東京新聞は8月2日付の「こちら特報部」で、木原副長官が報道陣との会見を避け、外遊もやめて「公務に支障」が生じている、と伝えた。
殺人事件の再捜査の状況と捜査終了に至った経緯を証言した佐藤元警部補に対して、「地方公務員法に定められた守秘義務に違反しているのではないか」と追及する向きがある。確かに、条文に照らせば、守秘義務に触れる可能性はある。
だが、「人としての道に反することをしている人たち」がいる時に「おかしい」と声をあげることが法律違反に問われるとしたら、それはどんな社会なのか。私たちはそんな社会になることを望んでいるのか。断じて否、である。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:ウェブコラム「情報屋台」 2023年8月3日
http://www.johoyatai.com/6160
≪写真説明≫
◎木原誠二・官房副長官(時事通信のサイトから)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023073100648&g=pol
≪参考記事≫
◎『週刊文春』7月13日号、7月20日号、7月27日号、8月3日号、8月10日号
◎朝日新聞7月25日付、7月28日付
◎毎日新聞7月29日付、読売新聞7月29日付
◎河北新報7月28日付
◎東京新聞8月2日付
*東京新聞以外は、山形県で発行されている新聞の日付
2023年の第11回最上川縦断カヌー探訪は7月29日(土)に村山市の碁点、三ケ瀬(みかのせ)、隼の瀬の三難所を下り、翌30日(日)に月山湖を周遊しました。テレビが「危険な暑さが続きます」と連呼する中でのカヌー行となりましたが、37人の参加者は全員、熱中症にもならず元気にカヌーを楽しみました。ご協力いただいたすべての皆様に深く感謝いたします。


≪出発&到着時刻≫
▽7月29日(土) 最上川三難所下り(参加32人)
午前7時 参加受付・検艇開始
8時 出発地の碁点橋のたもとからゴールの大石田河岸(かし)に
参加者が車で移動開始
8時半 大石田河岸からマイクロバスで碁点橋に戻る
9時15分 碁点橋のたもとから順次、出発




9時40分 最上川の共栄橋を通過
10時半 大淀で休憩
11時40分 隼の瀬に到着、昼食・休憩





午後1時半 隼の瀬を出発
3時15分 大石田河岸に到着

▽7月30日(日) 月山湖周遊(参加26人)
午前8時 参加受付・検艇開始
9時 月山湖の湖面広場から出発
◎三難所下りと月山湖周遊の写真&動画(撮影・塚本雅俊、小田原紫朗<膝方歳三>、中沢崇、清水孝治)
◎三難所下りの動画(撮影・真鍋賢一)
◎月山湖周遊の動画(撮影・真鍋賢一)
◎月山湖の砂防ダムの滝の動画(撮影・小田原紫朗)

正午すぎ 湖面広場に戻り、斉藤栄司さん提供の尾花沢スイカにかぶりつく

*月山湖では8月2日から、2023高校総体(インターハイ)の
カヌー競技が開かれるため、高校生の試漕が始まっていました。
≪参加者≫ 2日間で37人(1日目 32人、2日目26人)
▽7月29日(土) 参加32人
阿部明美(山形県天童市)、阿部俊裕(同)、石川毅(山形県村山市)、林和明(東京都足立区)、西沢あつし(東京都東村山市)、菊地大二郎(山形市)、七海信夫(福島県郡山市)、佐竹博文(埼玉県戸田市)、齋藤龍真(村山市)、中津希美(仙台市)、柏倉稔(山形県大江町)=29日のみ参加、清水孝治(神奈川県厚木市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、佐竹久(大江町)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、中沢崇(長野市)、結城敏宏(米沢市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、岸浩(福島市)、赤塚望(前橋市)、塚本雅俊(同)、小田原紫朗(山形県酒田市)、寒河江洋光(盛岡市)、吉田誠(千葉県松戸市)、大類晋(尾花沢市)、、矢萩剛(村山市)、山本剛生(天童市)、山本明莉(同)、阿部悠子(東京都八王子市)、崔鍾八(山形県朝日町)=2日間参加
▽7月30日(日) 参加26人(1日目参加の21人に加えて次の5人が参加)
清野礼子(仙台市)、吉田英世(同)、吉田志乃(同)、吉田蓮(同)、茂木奈津美(天童市)
*参加者のうち、最ベテランは神奈川県厚木市の清水孝治さん(82歳)、最若手は1日目が山本明莉さん(11歳)、2日目が吉田蓮さん(4歳)。山本明莉さんは2020年の第8回大会に7歳で参加しており、カヌー探訪での最上川下りの最年少記録保持者。

≪参加者の地域別内訳≫
山形県内 16人(天童市5人、村山市3人、尾花沢市2人、大江町2人、
山形市・酒田市・米沢市・朝日町各1人)
山形県外 21人(宮城県5人、東京都3人、群馬県3人、福島県2人、
埼玉県2人、神奈川県2人、岩手県・栃木県・千葉県・長野県各1人)
≪第1回―第11回の参加者≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人
第10回(2022年)45人、第11回(2023年)37人
≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省最上川ダム統合管理事務所、山形県、
朝日町、村山市、大石田町、西川町、山形県カヌー協会
(記録文・長岡昇、写真撮影・長岡典己、結城敏宏、小田原紫朗(膝方歳三)、塚本雅俊、中沢崇、動画撮影・塚本雅俊、小田原紫朗、清水孝治、真鍋賢一)
≪第11回カヌー探訪の参加記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 白田金之助▽佐竹恵子▽長岡典己▽長岡位久子▽長岡昇▽長岡佳子
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪受付設営・交通案内板設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助、長岡昇、長岡佳子
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪仕出し弁当≫ ハリス食堂(山形県村山市)
≪尾花沢スイカ提供≫斉藤栄司
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝


≪出発&到着時刻≫
▽7月29日(土) 最上川三難所下り(参加32人)
午前7時 参加受付・検艇開始
8時 出発地の碁点橋のたもとからゴールの大石田河岸(かし)に
参加者が車で移動開始
8時半 大石田河岸からマイクロバスで碁点橋に戻る
9時15分 碁点橋のたもとから順次、出発




9時40分 最上川の共栄橋を通過
10時半 大淀で休憩
11時40分 隼の瀬に到着、昼食・休憩





午後1時半 隼の瀬を出発
3時15分 大石田河岸に到着

▽7月30日(日) 月山湖周遊(参加26人)
午前8時 参加受付・検艇開始
9時 月山湖の湖面広場から出発
◎三難所下りと月山湖周遊の写真&動画(撮影・塚本雅俊、小田原紫朗<膝方歳三>、中沢崇、清水孝治)
◎三難所下りの動画(撮影・真鍋賢一)
◎月山湖周遊の動画(撮影・真鍋賢一)
◎月山湖の砂防ダムの滝の動画(撮影・小田原紫朗)

正午すぎ 湖面広場に戻り、斉藤栄司さん提供の尾花沢スイカにかぶりつく

*月山湖では8月2日から、2023高校総体(インターハイ)の
カヌー競技が開かれるため、高校生の試漕が始まっていました。
≪参加者≫ 2日間で37人(1日目 32人、2日目26人)
▽7月29日(土) 参加32人
阿部明美(山形県天童市)、阿部俊裕(同)、石川毅(山形県村山市)、林和明(東京都足立区)、西沢あつし(東京都東村山市)、菊地大二郎(山形市)、七海信夫(福島県郡山市)、佐竹博文(埼玉県戸田市)、齋藤龍真(村山市)、中津希美(仙台市)、柏倉稔(山形県大江町)=29日のみ参加、清水孝治(神奈川県厚木市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、佐竹久(大江町)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、中沢崇(長野市)、結城敏宏(米沢市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、岸浩(福島市)、赤塚望(前橋市)、塚本雅俊(同)、小田原紫朗(山形県酒田市)、寒河江洋光(盛岡市)、吉田誠(千葉県松戸市)、大類晋(尾花沢市)、、矢萩剛(村山市)、山本剛生(天童市)、山本明莉(同)、阿部悠子(東京都八王子市)、崔鍾八(山形県朝日町)=2日間参加
▽7月30日(日) 参加26人(1日目参加の21人に加えて次の5人が参加)
清野礼子(仙台市)、吉田英世(同)、吉田志乃(同)、吉田蓮(同)、茂木奈津美(天童市)
*参加者のうち、最ベテランは神奈川県厚木市の清水孝治さん(82歳)、最若手は1日目が山本明莉さん(11歳)、2日目が吉田蓮さん(4歳)。山本明莉さんは2020年の第8回大会に7歳で参加しており、カヌー探訪での最上川下りの最年少記録保持者。

≪参加者の地域別内訳≫
山形県内 16人(天童市5人、村山市3人、尾花沢市2人、大江町2人、
山形市・酒田市・米沢市・朝日町各1人)
山形県外 21人(宮城県5人、東京都3人、群馬県3人、福島県2人、
埼玉県2人、神奈川県2人、岩手県・栃木県・千葉県・長野県各1人)
≪第1回―第11回の参加者≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人
第10回(2022年)45人、第11回(2023年)37人
≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省最上川ダム統合管理事務所、山形県、
朝日町、村山市、大石田町、西川町、山形県カヌー協会
(記録文・長岡昇、写真撮影・長岡典己、結城敏宏、小田原紫朗(膝方歳三)、塚本雅俊、中沢崇、動画撮影・塚本雅俊、小田原紫朗、清水孝治、真鍋賢一)
≪第11回カヌー探訪の参加記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 白田金之助▽佐竹恵子▽長岡典己▽長岡位久子▽長岡昇▽長岡佳子
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪受付設営・交通案内板設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助、長岡昇、長岡佳子
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪仕出し弁当≫ ハリス食堂(山形県村山市)
≪尾花沢スイカ提供≫斉藤栄司
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
久しぶりに文春砲の連続弾が炸裂している。週刊文春の今回の標的は、岸田文雄首相の懐刀とされる木原誠二・官房副長官である。疑惑の内容は「木原氏の妻の元夫は殺害された可能性がある」というものだ。

週刊文春や木原氏の公式サイトなどによれば、木原氏は1970年6月生まれの53歳。東大法学部を卒業した後、大蔵省(現財務省)に入り、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに留学、2005年の郵政解散選挙で東京20区から自民党候補として立候補、当選した。
高祖父は諫早銀行頭取、曾祖父は大蔵省銀行課長という「財政金融ファミリー」の出身で、自らもその道に進んだが、英国大蔵省に出向した際、サッチャー元首相と出会い、政治を志したという。語学力も生かし、岸田政権では外交・安全保障分野で重要な役割を果たしている。
その木原氏の結婚相手は、元モデルで銀座のホステルをしていた女性だった。この女性には夫、安田種雄氏がいたが、同じくモデルだった種雄氏は2006年4月に自宅で変死体となって発見された。遺体から致死量の覚醒剤が検出されたことから、所轄の大塚警察署は「自殺」として処理した。

ところが、2018年、この対応に疑問を抱いた現場の刑事が遺族の協力を得て再捜査を始めた。遺族によれば、元夫には喉元から肺にまで達する傷があり、ナイフが足元に置かれていたという。ほかにも不審なことがいくつもあり、殺人事件の捜査にあたる警視庁の刑事たちも乗り出した。刑事たちは木原氏の妻の事情聴取や家宅捜索にこぎつけたが、捜査は「上からの指示」で突然、打ち切られたという。
7月27日の文春オンラインによれば、この再捜査にあたったベテラン刑事の佐藤誠警部補(昨年退職)は再捜査の経緯と打ち切りに至った事情を詳細に語った。佐藤氏は文春の記者に「当時から我々はホシを挙げるために全力で捜査に当たってきた。ところが、志半ばで中断させられた」と述べた。
佐藤氏が実名での告発を決断したきっかけは、一連の週刊文春の報道を受けて、警察庁の露木康浩長官が7月13日の定例会見で「証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」と語ったことだという。
この警察庁長官発言について、佐藤元警部補は「頭に来た。あの発言は真面目に仕事してきた俺たちを馬鹿にしている」と述べ、事件の捜査が上からの圧力で潰されたと、上司の名前も挙げて明言した。そして、捜査の過程で捜索令状を得て、DNAを採取するため、すでに木原誠二氏と再婚していたこの女性の採尿と採血を試みたところ、木原氏は「オマエなんて、いつでもクビ飛ばせるぞ!」と恫喝したのだという。

不可解なのは、この事件について主要な新聞やテレビがほとんど報じないことだ。元夫の遺族は警察に再捜査を求める上申書を出し、今年の7月20日には司法クラブで事件の解明を求める会見を開いたが、東京新聞など一部を除いて主要メディアは黙殺した。その一方で、木原氏の弁護士が「週刊文春の報道で(木原氏の妻の)人権侵害が起こる可能性がある」として日本弁護士連合会に人権救済の申し立てをしたことは、しっかり報じた。
一連の経緯を見て思うのは、「これはジャニー喜多川氏による性加害への対応とまるで同じ」ということだ。週刊文春が何度、性加害を報じても主要メディアは完全に黙殺した。英国のBBCが今年の3月に特報すると、やっと後追いする始末だった。
性加害事件ではジャニーズ事務所が芸能界やテレビ局に持つ巨大な影響力に怯えて、沈黙した。それに比べれば、木原官房副長官が持つ影響力ははるかに強大だ。今度も、権力に怯えて模様眺めを決め込んだ、ということだろう。
全国紙やNHK、民放各局は警視庁の記者クラブに何人もの記者を常駐させている。週刊文春には失礼ながら、文春よりはるかに人手も金もある。本気になれば、文春砲など吹き飛ばせるだけの材料を集められるはずだ。が、なにせ、本気になることがない。
それで「読者の新聞離れ」だの「視聴者のテレビ離れ」だのと愚痴を吐いても、誰も相手にするわけがない。しかるべき報酬を得て、しかるべき処遇を得ているのならば、報道の道を選んだ者としての気概と誇りを示したらどうか。
木原誠二・官房副長官の公式サイトには「誠心誠意、政策で!!」とのスローガンが掲げられている。ある賢人によれば、「人は自ら持ち合わせないものを掲げたがるものだ」という。けだし、名言と言うべきか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:ウェブコラム「情報屋台」 2023年7月27日
http://www.johoyatai.com/6140
≪写真説明≫
◎木原誠二・官房副長官
https://sakisiru.jp/44823
◎木原誠二氏の妻(ニュースサイト「One More News」)
https://one-more-life.jp/kihara-seiji-family/
◎事件の再捜査を求める元夫の父親(東京新聞のサイト)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/264383
≪参考記事&サイト≫
◎文春オンライン スクープ速報(2023年7月27日)など、一連の週刊文春の報道
https://bunshun.jp/articles/-/64612
◎木原誠二氏の公式サイト
https://kiharaseiji.com/
◎木原誠二氏の妻について(One More News)
https://one-more-life.jp/kihara-seiji-family/
◎事件の再捜査を訴える元夫の父親(東京新聞のサイト)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/264383
◎木原誠二の妻の元夫は人気モデル
https://emasora.com/kiharaseiji-wife-exhusband/

週刊文春や木原氏の公式サイトなどによれば、木原氏は1970年6月生まれの53歳。東大法学部を卒業した後、大蔵省(現財務省)に入り、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに留学、2005年の郵政解散選挙で東京20区から自民党候補として立候補、当選した。
高祖父は諫早銀行頭取、曾祖父は大蔵省銀行課長という「財政金融ファミリー」の出身で、自らもその道に進んだが、英国大蔵省に出向した際、サッチャー元首相と出会い、政治を志したという。語学力も生かし、岸田政権では外交・安全保障分野で重要な役割を果たしている。
その木原氏の結婚相手は、元モデルで銀座のホステルをしていた女性だった。この女性には夫、安田種雄氏がいたが、同じくモデルだった種雄氏は2006年4月に自宅で変死体となって発見された。遺体から致死量の覚醒剤が検出されたことから、所轄の大塚警察署は「自殺」として処理した。

ところが、2018年、この対応に疑問を抱いた現場の刑事が遺族の協力を得て再捜査を始めた。遺族によれば、元夫には喉元から肺にまで達する傷があり、ナイフが足元に置かれていたという。ほかにも不審なことがいくつもあり、殺人事件の捜査にあたる警視庁の刑事たちも乗り出した。刑事たちは木原氏の妻の事情聴取や家宅捜索にこぎつけたが、捜査は「上からの指示」で突然、打ち切られたという。
7月27日の文春オンラインによれば、この再捜査にあたったベテラン刑事の佐藤誠警部補(昨年退職)は再捜査の経緯と打ち切りに至った事情を詳細に語った。佐藤氏は文春の記者に「当時から我々はホシを挙げるために全力で捜査に当たってきた。ところが、志半ばで中断させられた」と述べた。
佐藤氏が実名での告発を決断したきっかけは、一連の週刊文春の報道を受けて、警察庁の露木康浩長官が7月13日の定例会見で「証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしている」と語ったことだという。
この警察庁長官発言について、佐藤元警部補は「頭に来た。あの発言は真面目に仕事してきた俺たちを馬鹿にしている」と述べ、事件の捜査が上からの圧力で潰されたと、上司の名前も挙げて明言した。そして、捜査の過程で捜索令状を得て、DNAを採取するため、すでに木原誠二氏と再婚していたこの女性の採尿と採血を試みたところ、木原氏は「オマエなんて、いつでもクビ飛ばせるぞ!」と恫喝したのだという。

不可解なのは、この事件について主要な新聞やテレビがほとんど報じないことだ。元夫の遺族は警察に再捜査を求める上申書を出し、今年の7月20日には司法クラブで事件の解明を求める会見を開いたが、東京新聞など一部を除いて主要メディアは黙殺した。その一方で、木原氏の弁護士が「週刊文春の報道で(木原氏の妻の)人権侵害が起こる可能性がある」として日本弁護士連合会に人権救済の申し立てをしたことは、しっかり報じた。
一連の経緯を見て思うのは、「これはジャニー喜多川氏による性加害への対応とまるで同じ」ということだ。週刊文春が何度、性加害を報じても主要メディアは完全に黙殺した。英国のBBCが今年の3月に特報すると、やっと後追いする始末だった。
性加害事件ではジャニーズ事務所が芸能界やテレビ局に持つ巨大な影響力に怯えて、沈黙した。それに比べれば、木原官房副長官が持つ影響力ははるかに強大だ。今度も、権力に怯えて模様眺めを決め込んだ、ということだろう。
全国紙やNHK、民放各局は警視庁の記者クラブに何人もの記者を常駐させている。週刊文春には失礼ながら、文春よりはるかに人手も金もある。本気になれば、文春砲など吹き飛ばせるだけの材料を集められるはずだ。が、なにせ、本気になることがない。
それで「読者の新聞離れ」だの「視聴者のテレビ離れ」だのと愚痴を吐いても、誰も相手にするわけがない。しかるべき報酬を得て、しかるべき処遇を得ているのならば、報道の道を選んだ者としての気概と誇りを示したらどうか。
木原誠二・官房副長官の公式サイトには「誠心誠意、政策で!!」とのスローガンが掲げられている。ある賢人によれば、「人は自ら持ち合わせないものを掲げたがるものだ」という。けだし、名言と言うべきか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:ウェブコラム「情報屋台」 2023年7月27日
http://www.johoyatai.com/6140
≪写真説明≫
◎木原誠二・官房副長官
https://sakisiru.jp/44823
◎木原誠二氏の妻(ニュースサイト「One More News」)
https://one-more-life.jp/kihara-seiji-family/
◎事件の再捜査を求める元夫の父親(東京新聞のサイト)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/264383
≪参考記事&サイト≫
◎文春オンライン スクープ速報(2023年7月27日)など、一連の週刊文春の報道
https://bunshun.jp/articles/-/64612
◎木原誠二氏の公式サイト
https://kiharaseiji.com/
◎木原誠二氏の妻について(One More News)
https://one-more-life.jp/kihara-seiji-family/
◎事件の再捜査を訴える元夫の父親(東京新聞のサイト)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/264383
◎木原誠二の妻の元夫は人気モデル
https://emasora.com/kiharaseiji-wife-exhusband/
第11回最上川縦断カヌー探訪(2023年7月29日、30日)は予定通り開催します。29日は午前7時から、村山市の碁点橋のたもとで検艇を始めます。30日は午前8時に月山湖のカヌー発着場にお集まりください。NPO「ブナの森」のサイトの「コース図」に詳しい地図をアップしています。ご参照ください。
今回の参加予定者は40人です。1日目は34人が最上川の三難所下りに挑み、2日目は29人が月山湖をめぐる予定です。山形県内から18人、県外から22人が参加します。県外の内訳は仙台市など宮城県から6人、東京都と群馬県から各3人、福島県・埼玉県・神奈川県から各2人など。山形県内では天童市の5人、山形市と村山市が各3人などです。
レスキュー担当がみなさんをサポートしますが、それぞれ無理のないカヌー行になるよう心がけてください。猛暑の中での開催になります。水分を十分にとるなど、熱中症対策も怠りなく。最上川の河畔、月山湖の湖畔でお待ちしています。
今回の参加予定者は40人です。1日目は34人が最上川の三難所下りに挑み、2日目は29人が月山湖をめぐる予定です。山形県内から18人、県外から22人が参加します。県外の内訳は仙台市など宮城県から6人、東京都と群馬県から各3人、福島県・埼玉県・神奈川県から各2人など。山形県内では天童市の5人、山形市と村山市が各3人などです。
レスキュー担当がみなさんをサポートしますが、それぞれ無理のないカヌー行になるよう心がけてください。猛暑の中での開催になります。水分を十分にとるなど、熱中症対策も怠りなく。最上川の河畔、月山湖の湖畔でお待ちしています。
アラブの春は2010年、チュニジアから始まった。失業と貧困、権力の腐敗に怒った民衆の大規模なデモで長期政権が倒されると、その波はエジプトに広がり、ムバラク大統領を退陣に追い込み、リビアでは独裁者カダフィ大佐を死に追いやった。
だが、春はシリアには来なかった。「中東でもっとも冷酷な独裁者」と評されるアサド大統領は激しい内戦を勝ち抜き、政権を維持している。アサド氏が生き延びることができたのは、イスラム教シーア派の国家イランに加えて、ロシアが支えたからである。

プーチン大統領は戦闘機や戦車、兵力を惜しみなく供与し、アサド大統領が敵対勢力を駆逐するのを助けた。中東でのロシアの存在感を誇示するためだ。その際、兵力の中心となったのはロシアの正規軍ではなく、今回反乱を起こしたプリゴジン氏率いる傭兵組織ワグネルである。
ワグネルに関しては、刑務所の囚人を兵士としてリクルートしていることが知られており、「囚人部隊」のように言う人もいるが、それは一面的な捉え方だろう。この傭兵組織の中核は「スペツナズ」と呼ばれるロシア軍参謀本部直属の特殊部隊の元将兵たちだ。
ワグネルの幹部ドミトリー・ウトキン氏は、チェチェン紛争で旅団長をつとめた猛者だ。スペツナズは通常の戦闘に加えて、破壊工作や要人の暗殺、ネット空間を使った電子戦も得意とする。混沌とした状況になるほど力を発揮する部隊と言っていい。
この傭兵組織が中東以上に存在感を示しているのがアフリカだ。中央アフリカ共和国やスーダン、リビア、ルワンダ、マリ、コンゴ民主共和国など十数カ国で作戦を展開している。ロシアは、外交的な配慮もあって正規軍を大規模に派遣するわけにはいかない。それをワグネルが代行している形だ。ゆえに「プーチンの影の軍団」と言われる。巨額の資金が投じられていることは言うまでもない。
フランスの植民地だった中央アフリカ共和国を例に取れば、1960年の独立以来、武力抗争とクーデターに明け暮れてきたこの国で、ワグネルは戦闘を担うだけでなく、トゥアデラ大統領の警護まで担当している。「ロシアの支えなしでは生きていけない大統領」なのだ。
もちろん、プーチン大統領もプリゴジン氏も善意で支援しているわけではない。中央アフリカ共和国にはダイヤモンドと金の有力な鉱山がある。リビアとスーダンには石油だ。プリゴジン氏の傭兵組織や関連会社はそれらの利権に深く食い込んで利益をむさぼっている、とされる。
今回、プリゴジン氏は反乱を終わらせ、部隊を撤収するにあたって、プーチン大統領側とギリギリと交渉を重ねた形跡がある。プリゴジン氏側は「部隊の撤収後もアフリカでの活動については沈黙を守る」と約束した、と見るのが自然だ。
ロシアがアフリカ諸国で行っていることを洗いざらいぶちまけられれば、国連など国際社会でのロシアの評判はガタ落ちになる。そんなことは何としても防がなければならない。一方で、プリゴジン氏側はロシアにいる妻子の安全を確保し、膨大な資産を保全しなければならない。そうしたことを秤にかけて、両者はベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介を受け入れたのだろう。
見過ごせないのは、ワグネルのアフリカでのこうした活動を調べていたジャーナリストが次々に不審な死を遂げていることだ。中央アフリカ共和国では、2018年7月に経験豊富な戦場ジャーナリストのオルハン・ジェマリ氏とドキュメンタリー映像監督のアレクサンドル・ラストルグエフ氏、カメラマンのキリル・ラドチェンコ氏が射殺体で発見された。
地元の捜査当局は「武装した強盗の仕業」として扱った。ロシア国営タス通信も「強盗目的の犯行」と報じた。だが、3人はこの国でのワグネルの活動実態を調べるため現地入りしたのだった。捜査当局やロシアの言い分を額面通りに受けとめるわけにはいかない。

ジャーナリストの不慮の死はこれだけではない。ロシアのエカテリンブルクでは同年4月、シリアでのワグネルの動きを調べていた通信社記者のマクシム・ボロディン氏がアパートの5階から転落死しているのが発見された。タス通信は例によって「犯罪の形跡はない」と報じたが、欧州安保協力機構(OSCE)のメディア担当は「深刻な懸念」を表明し、徹底的な捜査を行うよう求めた。ワグネルを追っていて命を落とした記者はもっといる。
戦場の兵士だけが命がけで戦っているのではない。ロシアでは事実を追い求め、良心に基づいて報じる――そのこと自体が命がけなのだ。報道を生涯の仕事とした者の一人として、そのことを忘れるわけにはいかない。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2023年7月3日
https://news-hunter.org/?p=18294
≪写真説明≫
◎中央アフリカで殺害されたジェマリ、ラストルグエフ、ラドチェンコの3氏(右から、BBCのサイト)
https://www.bbc.com/news/world-europe-45030087
◎不慮の死を遂げたボロディン氏(BBCのサイト)
Russian reporter Borodin dead after mystery fall - BBC News
≪参考記事&サイト≫
◎ワグネル反乱に関する読売新聞、産経新聞の記事(6月29日付、同30日付)
◎Central African Republic : Russian journalists die in ambush (BBC, 31 July 2018)
https://www.bbc.com/news/world-africa-45025601
◎ロシア人記者が自宅で転落死、シリアで展開の同国人傭兵について執筆(AFP、2018年4月16日)
https://www.afpbb.com/articles/-/3171368
◎Russian reporter Borodin dead after mistery fall (BBC, 16 April 2018)
https://www.bbc.com/news/world-europe-43781351
だが、春はシリアには来なかった。「中東でもっとも冷酷な独裁者」と評されるアサド大統領は激しい内戦を勝ち抜き、政権を維持している。アサド氏が生き延びることができたのは、イスラム教シーア派の国家イランに加えて、ロシアが支えたからである。

プーチン大統領は戦闘機や戦車、兵力を惜しみなく供与し、アサド大統領が敵対勢力を駆逐するのを助けた。中東でのロシアの存在感を誇示するためだ。その際、兵力の中心となったのはロシアの正規軍ではなく、今回反乱を起こしたプリゴジン氏率いる傭兵組織ワグネルである。
ワグネルに関しては、刑務所の囚人を兵士としてリクルートしていることが知られており、「囚人部隊」のように言う人もいるが、それは一面的な捉え方だろう。この傭兵組織の中核は「スペツナズ」と呼ばれるロシア軍参謀本部直属の特殊部隊の元将兵たちだ。
ワグネルの幹部ドミトリー・ウトキン氏は、チェチェン紛争で旅団長をつとめた猛者だ。スペツナズは通常の戦闘に加えて、破壊工作や要人の暗殺、ネット空間を使った電子戦も得意とする。混沌とした状況になるほど力を発揮する部隊と言っていい。
この傭兵組織が中東以上に存在感を示しているのがアフリカだ。中央アフリカ共和国やスーダン、リビア、ルワンダ、マリ、コンゴ民主共和国など十数カ国で作戦を展開している。ロシアは、外交的な配慮もあって正規軍を大規模に派遣するわけにはいかない。それをワグネルが代行している形だ。ゆえに「プーチンの影の軍団」と言われる。巨額の資金が投じられていることは言うまでもない。
フランスの植民地だった中央アフリカ共和国を例に取れば、1960年の独立以来、武力抗争とクーデターに明け暮れてきたこの国で、ワグネルは戦闘を担うだけでなく、トゥアデラ大統領の警護まで担当している。「ロシアの支えなしでは生きていけない大統領」なのだ。
もちろん、プーチン大統領もプリゴジン氏も善意で支援しているわけではない。中央アフリカ共和国にはダイヤモンドと金の有力な鉱山がある。リビアとスーダンには石油だ。プリゴジン氏の傭兵組織や関連会社はそれらの利権に深く食い込んで利益をむさぼっている、とされる。
今回、プリゴジン氏は反乱を終わらせ、部隊を撤収するにあたって、プーチン大統領側とギリギリと交渉を重ねた形跡がある。プリゴジン氏側は「部隊の撤収後もアフリカでの活動については沈黙を守る」と約束した、と見るのが自然だ。
ロシアがアフリカ諸国で行っていることを洗いざらいぶちまけられれば、国連など国際社会でのロシアの評判はガタ落ちになる。そんなことは何としても防がなければならない。一方で、プリゴジン氏側はロシアにいる妻子の安全を確保し、膨大な資産を保全しなければならない。そうしたことを秤にかけて、両者はベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介を受け入れたのだろう。
見過ごせないのは、ワグネルのアフリカでのこうした活動を調べていたジャーナリストが次々に不審な死を遂げていることだ。中央アフリカ共和国では、2018年7月に経験豊富な戦場ジャーナリストのオルハン・ジェマリ氏とドキュメンタリー映像監督のアレクサンドル・ラストルグエフ氏、カメラマンのキリル・ラドチェンコ氏が射殺体で発見された。
地元の捜査当局は「武装した強盗の仕業」として扱った。ロシア国営タス通信も「強盗目的の犯行」と報じた。だが、3人はこの国でのワグネルの活動実態を調べるため現地入りしたのだった。捜査当局やロシアの言い分を額面通りに受けとめるわけにはいかない。

ジャーナリストの不慮の死はこれだけではない。ロシアのエカテリンブルクでは同年4月、シリアでのワグネルの動きを調べていた通信社記者のマクシム・ボロディン氏がアパートの5階から転落死しているのが発見された。タス通信は例によって「犯罪の形跡はない」と報じたが、欧州安保協力機構(OSCE)のメディア担当は「深刻な懸念」を表明し、徹底的な捜査を行うよう求めた。ワグネルを追っていて命を落とした記者はもっといる。
戦場の兵士だけが命がけで戦っているのではない。ロシアでは事実を追い求め、良心に基づいて報じる――そのこと自体が命がけなのだ。報道を生涯の仕事とした者の一人として、そのことを忘れるわけにはいかない。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2023年7月3日
https://news-hunter.org/?p=18294
≪写真説明≫
◎中央アフリカで殺害されたジェマリ、ラストルグエフ、ラドチェンコの3氏(右から、BBCのサイト)
https://www.bbc.com/news/world-europe-45030087
◎不慮の死を遂げたボロディン氏(BBCのサイト)
Russian reporter Borodin dead after mystery fall - BBC News
≪参考記事&サイト≫
◎ワグネル反乱に関する読売新聞、産経新聞の記事(6月29日付、同30日付)
◎Central African Republic : Russian journalists die in ambush (BBC, 31 July 2018)
https://www.bbc.com/news/world-africa-45025601
◎ロシア人記者が自宅で転落死、シリアで展開の同国人傭兵について執筆(AFP、2018年4月16日)
https://www.afpbb.com/articles/-/3171368
◎Russian reporter Borodin dead after mistery fall (BBC, 16 April 2018)
https://www.bbc.com/news/world-europe-43781351
武器を持って起ち上がった場合、失敗すればその首謀者は極刑に処されるのが世の習いである。国家に対する明白な反逆であり、権力者は反逆者には死をもって報いるか終身刑に処すのが普通だ。けれども、ロシアではそうでもないようだ。不可解な国である。

エフゲニー・プリゴジン氏が率いる傭兵組織ワグネルが6月23日夜、ロシア南部のロストフ州で反乱を起こした。傭兵たちはロシア軍南部軍管区の司令部を制圧し、モスクワに向かって進軍を始めた。戦車を連ね、対空兵器を携えての反乱である。
日本でも1936年(昭和11年)に雪降る首都東京で青年将校が率いる反乱が起きたことがある。いわゆる二・二六事件だ。高橋是清蔵相や斎藤実・元海軍大臣らが殺害され、天皇と陸軍首脳を巻き込んで大騒動になったが、この時に武装蜂起した将兵は1500人足らずに過ぎない。武器も機関銃と小銃程度で、ほどなく鎮圧された。
それに比べると、「プリゴジンの反乱」はスケールがまるで異なる。傭兵組織の兵力は2万人から3万人とされる。2個師団相当である。しかも、ウクライナとの戦争の最前線で戦ってきた将兵が含まれ、戦闘力もけた違いだ。実際、ロシア軍が鎮圧のため武装ヘリコプターを差し向けたところ、ワグネルの部隊に撃墜されてしまったという。
反乱軍はものすごい勢いでモスクワへと北進した。翌24日にはモスクワまで200キロの地点に到達している。それは、ロシア軍内部にも反乱に同調もしくは黙認する動きがあったことを意味する。ネットには途中の街で反乱軍を歓呼の声で迎える市民の映像が流れた。まるで解放軍が来たかのような歓迎ぶりだった。
深刻な事態である。プーチン大統領は緊急テレビ演説で、「これは裏切りである」と断じ、武器を取った者は罰せられる、と警告した。2000年に大統領に就任し、すでに4半世紀近くその座にある絶対権力者である。断固たる措置を執る、と誰もが思った。共同通信は事態を「内戦の様相すら呈す」と報じた。
ここからがロシアが「不可解な国」であるゆえんである。蜂起から24時間もたたないうちに手打ちに至った。ロシア大統領府は「ワグネルへの(反逆罪での)捜査を打ち切る」「プリゴジン氏は隣国のベラルーシに出国(亡命)する」と発表した。プリゴジン氏もこれに応じて部隊を撤収させ、姿を消した。手打ちを仲介したベラルーシのルカシェンコ大統領の庇護を受けていると見られる。
反乱の首謀者はどのような人物なのか。プリゴジン氏はプーチン氏と同じサンクトペテルブルク(出生当時はレニングラード)出身だが、その生い立ちはポジとネガのように異なる。プーチン氏はレニングラード国立大学を出た後、KGB(国家保安委員会)の諜報員として出世の階段を駆け上っていった。ソ連共産党のエリート党員として歩み、政界に転じた。
一方のプリゴジン氏は幼くして父親を亡くし、病院で働く母親によって育てられた。英語版のウィキペディアによれば、実父も継父もユダヤ系という。全寮制の体育学校でクロスカントリースキーに打ち込んだが、目立った成績は収めていない。
18歳の時、窃盗で捕まり、執行猶予付き2年拘禁の判決を受けた。その2年後には強盗と詐欺、年少者に犯罪をそそのかした罪で12年の実刑判決。恩赦で9年の拘禁で済んだのは幸運だっただろう。プリゴジン氏は長い刑務所生活で様々なことを学び、人脈を築いていったものと見られる。
商才はあったようだ。出所後、彼は母親や継父とホットドッグの販売を始めた。商売は当たり、「ルーブル紙幣が数えきれないほど積み上がった」とニューヨークタイムズ紙に語っている。1991年のソ連崩壊後の混乱の中で、食料品チェーン店やカジノ、船上レストランとビジネスを広げていった。
とくに、古都サンクトペテルブルクでの船上レストランは大当たりした。プーチン大統領がシラク仏大統領やジョージ・W・ブッシュ米大統領を連れて食事に来た。この時の縁が「プーチンとの関係」の始まりのようだ。
プリゴジン氏が傭兵組織ワグネルを立ち上げたのは2014年頃である。ロシアがウクライナの政治的混乱に乗じてクリミア半島を併合し、東部ドンバス地方に住むロシア系住民の武装化を進めていった時期だ。ワグネルの軍事行動はシリア、中央アフリカ共和国などに広がっていった。
ロシアでは私兵組織は法的に禁じられている。が、ロシアの法律は政治の力でどのようにでも解釈、運用可能だ。それは、政治や軍事、経済のカタギの世界と裏社会との境界がはっきりせず、溶け合っていることを意味する。その闇はとてつもなく深い、と見るべきだろう。
プリゴジン氏は有力なオリガルヒ(新興財閥)の一人であり、プーチン氏の盟友である。ワグネルは「プーチンの私兵」の役割を果たし、ロシア正規軍を派遣できないような紛争に派遣されるようになっていった。中央アフリカでは、ワグネルの活動を調査していたロシアの複数のジャーナリストが殺害された。「邪魔者は消す」という露骨なやり方は、明と暗が溶け合い、法があって無いような社会でまかり通る手法だ。
たたき上げの苦労人だからか、プリゴジン氏はいわゆるエリートが大嫌いなようだ(プーチン氏を除いて)。とりわけ、セルゲイ・ショイグ国防相を口を極めてののしっている。ショイグ氏は中央アジアのテュルク系の少数民族トゥバ人で、クラスノヤルスク工業大学で建築学を学んだ。危機管理と災害復旧での実績が評価されて共産党の大幹部になり、プーチン政権で国防相に上り詰めた。軍務経験はまったくない。

傭兵を率い、前線に出ることもいとわないプリゴジン氏にとって、戦場の経験もないショイグ氏があれこれ指図するのは受け入れがたいのだろう。ネットで「ショイグ!ゲラシモフ(参謀総長)! 弾薬はどこだ」と前線での弾薬不足に激怒し、「お前らがきれいな執務室で肥え太るために彼らは死んでいったのだ」とののしった。どこの社会にも庶民には「エリートに対する反発」がある。反乱軍に対する民衆の歓呼の声はそれを裏付けるものだろう。
ショイグ氏への誹謗中傷の中で注目されるのは、ウクライナ侵攻以来、ロシア軍やワグネルに犠牲者が続出していることをプリゴジン氏が明らかにし、「お前たちはロシア兵10万人を殺した犯罪者だ」とののしったことだ。ウクライナ戦争でのロシア側の犠牲者については様々な憶測が流れているが、ロシア側から10万人という数字が出たのはこれが初めてではないか。
ロシアは侵攻当初、ウクライナに19万の兵力を投入し、その後、30万人の予備役を追加したとされる。イギリスの情報機関やアメリカの戦争研究所などがロシア側の死者数についていくつかの推計を発表しているが、プリゴジン氏が唱える10万人はその最大値に近い。
傭兵組織の存在と活用にしても、今回の反乱の顛末にしても、ロシアには「法の支配」という意識が感じられない。力こそすべて、政治がすべてを決めていく、という土壌が分厚く積もっているように感じる。私たちには想像もできないような感覚が支配している、と言うべきだろう。
と、こんな風に書いてきて、では私たちの国を外から見れば、どんな風に見えるのだろうか、と考えさせられた。もちろん、自由な国であり、法律もそれなりに機能している。だが、戦後、GHQ(連合国軍総司令部)が残した日本国憲法は、第14条で「法の下の平等」をうたいながら、天皇の特別な地位と世襲を例外として認めている。
第9条で戦争の放棄と「戦力の不保持」を明記しているのに、アジア有数の軍備を持つ自衛隊がある。現実に合わせて憲法をはじめとする法律を改変し、それを守っていくという意識が乏しい。「今の憲法を一字一句変えてはならない」と真面目な顔で唱える政治家もいる。
法と論理に厳格なドイツ人やフランス人に言わせれば、とても理解できないことであり、彼らにとっては日本もまた、ロシアとは違う意味で「不可解な国」の一つだろう。この世には不可解と不条理が山ほどある、ということか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 119」 2023年6月28日
≪写真説明≫
◎ワグネルの戦車に歓呼の声を上げる市民(BBCのサイトから)
◎戦闘服を身に着けたプリゴジン氏(CNNのサイトから)
≪参考記事&サイト≫
◎6月25日、26日の新聞各紙
◎英語版ウィキペディア「Yevgeniy Prigozhin」
https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeny_Prigozhin

エフゲニー・プリゴジン氏が率いる傭兵組織ワグネルが6月23日夜、ロシア南部のロストフ州で反乱を起こした。傭兵たちはロシア軍南部軍管区の司令部を制圧し、モスクワに向かって進軍を始めた。戦車を連ね、対空兵器を携えての反乱である。
日本でも1936年(昭和11年)に雪降る首都東京で青年将校が率いる反乱が起きたことがある。いわゆる二・二六事件だ。高橋是清蔵相や斎藤実・元海軍大臣らが殺害され、天皇と陸軍首脳を巻き込んで大騒動になったが、この時に武装蜂起した将兵は1500人足らずに過ぎない。武器も機関銃と小銃程度で、ほどなく鎮圧された。
それに比べると、「プリゴジンの反乱」はスケールがまるで異なる。傭兵組織の兵力は2万人から3万人とされる。2個師団相当である。しかも、ウクライナとの戦争の最前線で戦ってきた将兵が含まれ、戦闘力もけた違いだ。実際、ロシア軍が鎮圧のため武装ヘリコプターを差し向けたところ、ワグネルの部隊に撃墜されてしまったという。
反乱軍はものすごい勢いでモスクワへと北進した。翌24日にはモスクワまで200キロの地点に到達している。それは、ロシア軍内部にも反乱に同調もしくは黙認する動きがあったことを意味する。ネットには途中の街で反乱軍を歓呼の声で迎える市民の映像が流れた。まるで解放軍が来たかのような歓迎ぶりだった。
深刻な事態である。プーチン大統領は緊急テレビ演説で、「これは裏切りである」と断じ、武器を取った者は罰せられる、と警告した。2000年に大統領に就任し、すでに4半世紀近くその座にある絶対権力者である。断固たる措置を執る、と誰もが思った。共同通信は事態を「内戦の様相すら呈す」と報じた。
ここからがロシアが「不可解な国」であるゆえんである。蜂起から24時間もたたないうちに手打ちに至った。ロシア大統領府は「ワグネルへの(反逆罪での)捜査を打ち切る」「プリゴジン氏は隣国のベラルーシに出国(亡命)する」と発表した。プリゴジン氏もこれに応じて部隊を撤収させ、姿を消した。手打ちを仲介したベラルーシのルカシェンコ大統領の庇護を受けていると見られる。
反乱の首謀者はどのような人物なのか。プリゴジン氏はプーチン氏と同じサンクトペテルブルク(出生当時はレニングラード)出身だが、その生い立ちはポジとネガのように異なる。プーチン氏はレニングラード国立大学を出た後、KGB(国家保安委員会)の諜報員として出世の階段を駆け上っていった。ソ連共産党のエリート党員として歩み、政界に転じた。
一方のプリゴジン氏は幼くして父親を亡くし、病院で働く母親によって育てられた。英語版のウィキペディアによれば、実父も継父もユダヤ系という。全寮制の体育学校でクロスカントリースキーに打ち込んだが、目立った成績は収めていない。
18歳の時、窃盗で捕まり、執行猶予付き2年拘禁の判決を受けた。その2年後には強盗と詐欺、年少者に犯罪をそそのかした罪で12年の実刑判決。恩赦で9年の拘禁で済んだのは幸運だっただろう。プリゴジン氏は長い刑務所生活で様々なことを学び、人脈を築いていったものと見られる。
商才はあったようだ。出所後、彼は母親や継父とホットドッグの販売を始めた。商売は当たり、「ルーブル紙幣が数えきれないほど積み上がった」とニューヨークタイムズ紙に語っている。1991年のソ連崩壊後の混乱の中で、食料品チェーン店やカジノ、船上レストランとビジネスを広げていった。
とくに、古都サンクトペテルブルクでの船上レストランは大当たりした。プーチン大統領がシラク仏大統領やジョージ・W・ブッシュ米大統領を連れて食事に来た。この時の縁が「プーチンとの関係」の始まりのようだ。
プリゴジン氏が傭兵組織ワグネルを立ち上げたのは2014年頃である。ロシアがウクライナの政治的混乱に乗じてクリミア半島を併合し、東部ドンバス地方に住むロシア系住民の武装化を進めていった時期だ。ワグネルの軍事行動はシリア、中央アフリカ共和国などに広がっていった。
ロシアでは私兵組織は法的に禁じられている。が、ロシアの法律は政治の力でどのようにでも解釈、運用可能だ。それは、政治や軍事、経済のカタギの世界と裏社会との境界がはっきりせず、溶け合っていることを意味する。その闇はとてつもなく深い、と見るべきだろう。
プリゴジン氏は有力なオリガルヒ(新興財閥)の一人であり、プーチン氏の盟友である。ワグネルは「プーチンの私兵」の役割を果たし、ロシア正規軍を派遣できないような紛争に派遣されるようになっていった。中央アフリカでは、ワグネルの活動を調査していたロシアの複数のジャーナリストが殺害された。「邪魔者は消す」という露骨なやり方は、明と暗が溶け合い、法があって無いような社会でまかり通る手法だ。
たたき上げの苦労人だからか、プリゴジン氏はいわゆるエリートが大嫌いなようだ(プーチン氏を除いて)。とりわけ、セルゲイ・ショイグ国防相を口を極めてののしっている。ショイグ氏は中央アジアのテュルク系の少数民族トゥバ人で、クラスノヤルスク工業大学で建築学を学んだ。危機管理と災害復旧での実績が評価されて共産党の大幹部になり、プーチン政権で国防相に上り詰めた。軍務経験はまったくない。

傭兵を率い、前線に出ることもいとわないプリゴジン氏にとって、戦場の経験もないショイグ氏があれこれ指図するのは受け入れがたいのだろう。ネットで「ショイグ!ゲラシモフ(参謀総長)! 弾薬はどこだ」と前線での弾薬不足に激怒し、「お前らがきれいな執務室で肥え太るために彼らは死んでいったのだ」とののしった。どこの社会にも庶民には「エリートに対する反発」がある。反乱軍に対する民衆の歓呼の声はそれを裏付けるものだろう。
ショイグ氏への誹謗中傷の中で注目されるのは、ウクライナ侵攻以来、ロシア軍やワグネルに犠牲者が続出していることをプリゴジン氏が明らかにし、「お前たちはロシア兵10万人を殺した犯罪者だ」とののしったことだ。ウクライナ戦争でのロシア側の犠牲者については様々な憶測が流れているが、ロシア側から10万人という数字が出たのはこれが初めてではないか。
ロシアは侵攻当初、ウクライナに19万の兵力を投入し、その後、30万人の予備役を追加したとされる。イギリスの情報機関やアメリカの戦争研究所などがロシア側の死者数についていくつかの推計を発表しているが、プリゴジン氏が唱える10万人はその最大値に近い。
傭兵組織の存在と活用にしても、今回の反乱の顛末にしても、ロシアには「法の支配」という意識が感じられない。力こそすべて、政治がすべてを決めていく、という土壌が分厚く積もっているように感じる。私たちには想像もできないような感覚が支配している、と言うべきだろう。
と、こんな風に書いてきて、では私たちの国を外から見れば、どんな風に見えるのだろうか、と考えさせられた。もちろん、自由な国であり、法律もそれなりに機能している。だが、戦後、GHQ(連合国軍総司令部)が残した日本国憲法は、第14条で「法の下の平等」をうたいながら、天皇の特別な地位と世襲を例外として認めている。
第9条で戦争の放棄と「戦力の不保持」を明記しているのに、アジア有数の軍備を持つ自衛隊がある。現実に合わせて憲法をはじめとする法律を改変し、それを守っていくという意識が乏しい。「今の憲法を一字一句変えてはならない」と真面目な顔で唱える政治家もいる。
法と論理に厳格なドイツ人やフランス人に言わせれば、とても理解できないことであり、彼らにとっては日本もまた、ロシアとは違う意味で「不可解な国」の一つだろう。この世には不可解と不条理が山ほどある、ということか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 119」 2023年6月28日
≪写真説明≫
◎ワグネルの戦車に歓呼の声を上げる市民(BBCのサイトから)
◎戦闘服を身に着けたプリゴジン氏(CNNのサイトから)
≪参考記事&サイト≫
◎6月25日、26日の新聞各紙
◎英語版ウィキペディア「Yevgeniy Prigozhin」
https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeny_Prigozhin
イデオロギーの怖さは「決めつけること」にある。「すべての歴史は階級闘争の歴史である」とマルクスは唱えた。そして、「人間の社会は原始共産制から奴隷制、封建制、資本主義を経て社会主義、共産主義に至る」と決めつけた。
それは「歴史の発展法則であり、必然である」として、資本主義を暴力革命で打倒するよう呼びかけた。イデオロギーは「自由な発想」を許さない。それに異を唱える思想や思考を排斥した。
日本では戦前、共産党は非合法とされ、過酷な弾圧を受けた。天皇制の下で戦争に突き進み、破局を迎えると、獄中で非転向を貫いた共産党員は釈放され、マルクス主義が急激に広まった。彼らは一貫して「天皇制の廃絶」と「侵略戦争反対」を訴えていたからだ。戦後社会、とりわけ知識層に大きな影響を与えた。
被差別部落の解放をめざす運動と理論は、こうした歴史のうねりの中で展開され、構築されていった。「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、支配階級が民衆を分断統治するため新たにつくり出したもの」という近世政治起源説も戦後、マルクス主義を基盤にして成立し、広まった。
けれども、一人ひとりの人間が織り成す歴史は「階級闘争」という観点だけで説明できるものではない。「資本主義は革命によって打倒され、社会主義の世になる」というテーゼ(命題)はロシアの地で現実のものになり、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が誕生した。だが、そこで人々が経験したのは、どのような圧政も及ばないほどのすさまじい粛清であり、収奪だった。
やがて社会システムは機能不全に陥り、ソ連は崩壊した。そして、その中核だったロシアは今、ウクライナに攻め入り、「ならず者国家」と指弾されている。
歴史の審判は峻厳で冷徹だ。その審判に耐えられないイデオロギーは葬り去られる。被差別部落の起源に関する近世政治起源説も破綻し、「歴史のゴミ箱」に打ち捨てられていく。
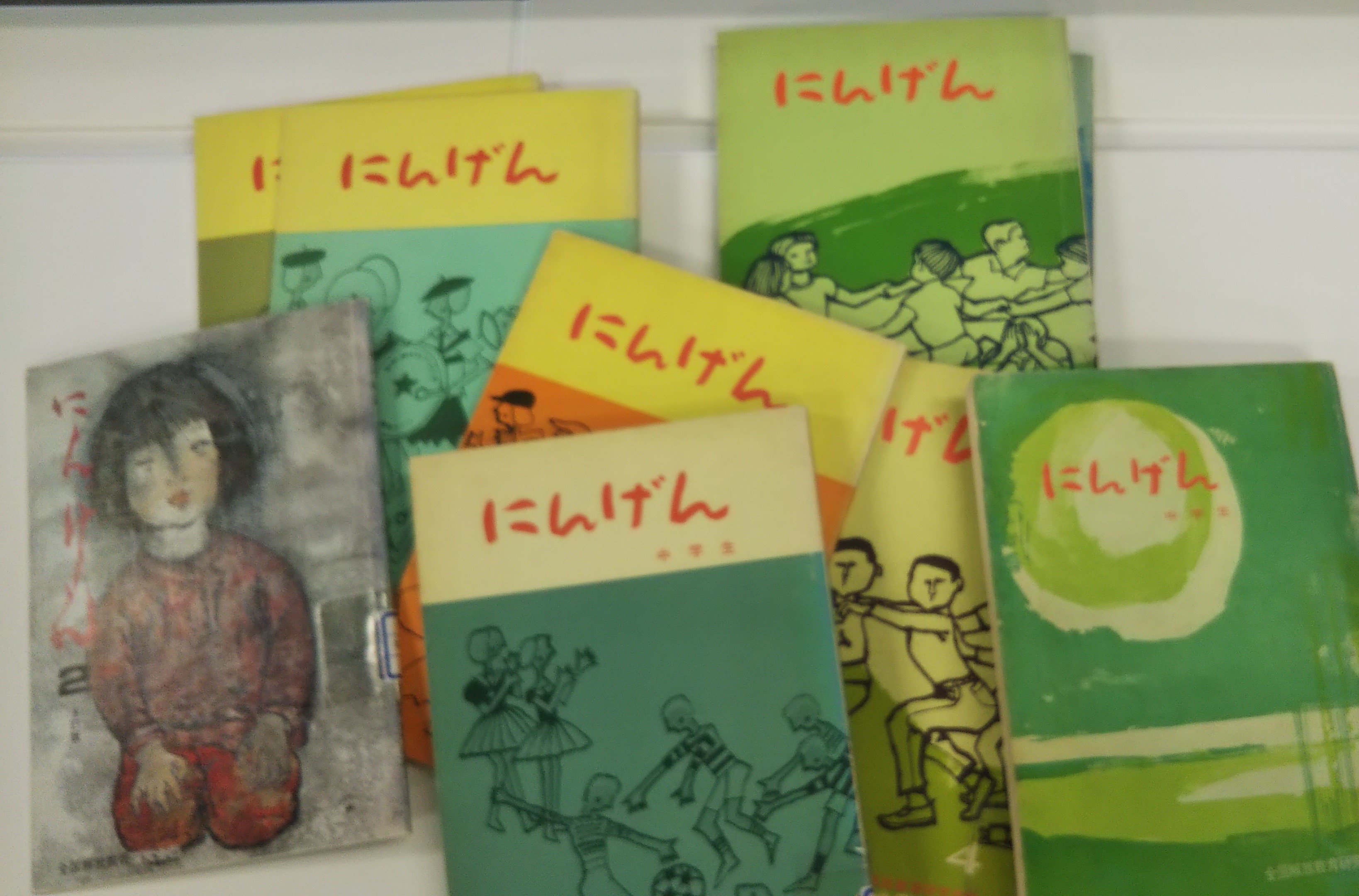
とはいえ、その破綻が明白になるまで、学校教育では「同和教育」の名の下で近世政治起源説が長い間、教え込まれた。大阪府では『にんげん』、兵庫県では『友だち』という副読本が作られ、小中学生に無償で配布された。
大阪府の副読本『にんげん』は1970年から発行が始まった。小学6年生用の『にんげん』には、被差別部落の起源について次のように記してある。
「いまの部落につながるものは、戦国時代の終わりごろから江戸時代のはじめにつくられた。豊臣秀吉は、武士に抵抗する農民をおさえつけるために検地や刀狩をし、ねんぐのとりたてをきびしくすると同時に、身分を法によって決めていく。徳川が全国を統一するようになると、鎖国をして諸大名や商人の力をおさえ、キリスト教もとりしまり、身分制度をいっそうきびしくする。今日まで尾をひく部落差別は、ここで形づくられたのである」(1973年、三訂版)
副読本を編集したのは「全国解放教育研究会」である。研究会の当時の代表は部落解放同盟の上田卓三(たくみ)大阪府連委員長と中村拡三・近畿大学教授で、現職の教師たちが編集にあたった。
この研究会が編集した『解放教育読本 にんげん 指導の手びき』という教師用の手引書には、解放教育がめざすのは「解放の学力」の涵養であり、それには「三つの柱」がある、としている。
第一は「集団主義の思想を確立すること」、第二は「科学的認識・芸術的認識を深めること」、そして第三は「子どもたちに部落解放、解放の自覚をもたせること」である。イデオロギー教育の推進を公然と唱えている。私のように東北で生まれ、同和教育を受けたことのない人間にとっては、唖然とするような指導方針だ。
おまけに、「科学的認識を深める」と言っておきながら、教えていたのは一学説にすぎない「被差別部落=近世政治起源説」であり、その後、研究が進むにつれて否定され、破綻した学説だった。
子どもたちは学び始めてまだ日が浅く、未熟である。だが、愚かではない。多くの子どもは「部落は戦国末期から江戸時代初めに新しくつくられた」という教師の説明を素直に受け入れたが、中には「どういう人たちが部落民にされたの」と尋ねる子がいた。「部落民にされた人たちは反対しなかったの」と問う子もいた。
素朴だが、鋭い質問である。それは、近世政治起源説のアキレス腱を射抜く質問だった。同和教育を担った教師たちはうろたえ、シドロモドロになったことだろう。
◇ ◇
学問の世界でもこれと同じ疑問が発せられた。イデオロギーに囚われた学者たちはそうした疑問を封じ込めようと躍起になったが、日本中世史の研究者たちはそれを打ち破っていく。
連載(9)で紹介したように、鎌倉時代にはすでに「穢多」という言葉を使った絵巻物があることが分かっており、室町時代の文献には「非人」という言葉も頻出する。それらがどのような文脈でどのように使われているか、彼らは丹念に調べ上げていった。そして、中世の賤民たちが江戸時代の穢多、非人へと連綿とつながっていることを実証していったのである。
桃山学院大学の横井清教授は著書『中世民衆の生活文化』で、鎌倉時代の絵巻物『天狗草紙』に描かれた「穢多童(えたわらわ)」とその詞書(ことばがき)を詳細に論じ、すでにこの時代に穢多は「強度の賤視の対象とされていた」と記した。
さらに、室町時代の辞典『下学(かがく)集』などを引用しながら、穢多という蔑称と皮革業という職業、河原という居住環境が密接に結びついていることを明らかにした。それは、「近世の部落の特徴は身分と職業、住所の三つが切り離せないものになった点にある」という、近世政治起源説の根幹とも言うべき「三位一体」が中世から成立していたことを示すもので、近世起源説を根本から掘り崩すものだった。
文献の研究に民俗学などの視点も加えて、「部落の形成史を学際的に考察すべきだ」と唱えたのは、中世史研究者の網野善彦・神奈川大学教授である。
網野は、従来の歴史学が「天皇をはじめとする権力者やそれを支える農民」を軸に歴史を捉えてきたことを批判し、漁民や狩猟民、手工業者や芸能民、遊女や漂白する人々にも光を当て、中世の賤民もそうした文脈から捉え直すことを提唱した。
著書『無縁・公界(くがい)・楽?-日本中世の自由と平和』で、網野は京都の蓮台野(れんだいの)が中世を通して葬送を担っていたことを詳しく論じた。蓮台野は代表的な被差別部落の一つであり、近世、明治を通して差別にさらされてきた。「部落は近世に新たにつくられた」などという学説が成り立たないことを疑問の余地なく明らかにしたのである。
また、『中世の非人と遊女』では、京都・清水坂の非人が「天皇に直属する存在」であり、平民とは「異質な存在」であったことを示した。中世においても、部落は天皇制と密接に結びついていたと主張し、「戦後の歴史学の主流は(その実証的、科学的な研究のために)どれほどのことをしてきたか」と痛烈に批判した。
1980年代になると、中世史の研究者による近世政治起源説への批判はさらに鋭く、厳しいものになった。やがて「部落史の研究者でこの説を信じる者はほとんどいない」という状況になり、今日に至っている。
振り返って、破綻した学説を唱えた人たちはどう思っているのか。大阪市立大学の原田伴彦教授は、1980年の第2回部落解放研究者会議で次のように語っている。
「部落の起源を中世、古代にさかのぼらせる見解は戦前からあり、昭和20年代においてもあった。近世の賤民身分に入れられた人々の個人的ルーツをたどってみると、中世の賤民身分の人々の血をひいているケースが多々あるわけです。当然、古代までさかのぼります。そうなりますと、結局は(中略)原始時代まで部落の起源をさかのぼらせる、ということになってくる」
「それから、もし部落の起源を古代までさかのぼらせるとすると、(中略)天皇を歴史の中核にすえる考え方になってきます。そこに重点を置きすぎると、何か割りきれない面が沢山うまれてくるのではないか」
「部落の起源を古い時代にもっていくことは、結局日本人そのものと部落問題が不可分の関係にある、日本人がなくならない限り部落問題がなくならないという考え方になるわけです。こういう考え方は、運動にとってマイナスにこそなれ、少しもプラスにならないと考えています」
運動にとってプラスかマイナスかで考える――それはイデオローグや活動家の発想であり、研究者がとるべき態度ではない。長い目で見た場合、そうした考えに立って誤った学説を唱え、次の世代に伝えることが何をもたらすか。そこに思いが至らなかった。罪深い人たちである。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2023年2月23日
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真説明≫
大阪府が作成して配布した同和教育の副読本『にんげん』(副読本の無償配布は2008年度で終了した)
≪参考文献≫
◎『共産党宣言』(カール・マルクス&フリードリヒ・エンゲルス、岩波文庫)
◎『経済学批判』(カール・マルクス、大月書店国民文庫4)
◎大阪府の小学6年用副読本『にんげん』(全国解放教育研究会編、明治図書出版、1972年三訂版)
◎『解放教育読本 にんげん 指導の手びき』(全国解放教育研究会編、明治図書出版、1973年)
◎『中世民衆の生活文化』(横井清、東京大学出版会)
◎『無縁・公界・楽?-日本中世の自由と平和』(網野善彦、平凡社選書)
◎『中世の非人と遊女』(網野善彦、講談社学術文庫)
◎『部落解放研究 第21号』(部落解放研究所編集・発行)
それは「歴史の発展法則であり、必然である」として、資本主義を暴力革命で打倒するよう呼びかけた。イデオロギーは「自由な発想」を許さない。それに異を唱える思想や思考を排斥した。
日本では戦前、共産党は非合法とされ、過酷な弾圧を受けた。天皇制の下で戦争に突き進み、破局を迎えると、獄中で非転向を貫いた共産党員は釈放され、マルクス主義が急激に広まった。彼らは一貫して「天皇制の廃絶」と「侵略戦争反対」を訴えていたからだ。戦後社会、とりわけ知識層に大きな影響を与えた。
被差別部落の解放をめざす運動と理論は、こうした歴史のうねりの中で展開され、構築されていった。「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、支配階級が民衆を分断統治するため新たにつくり出したもの」という近世政治起源説も戦後、マルクス主義を基盤にして成立し、広まった。
けれども、一人ひとりの人間が織り成す歴史は「階級闘争」という観点だけで説明できるものではない。「資本主義は革命によって打倒され、社会主義の世になる」というテーゼ(命題)はロシアの地で現実のものになり、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が誕生した。だが、そこで人々が経験したのは、どのような圧政も及ばないほどのすさまじい粛清であり、収奪だった。
やがて社会システムは機能不全に陥り、ソ連は崩壊した。そして、その中核だったロシアは今、ウクライナに攻め入り、「ならず者国家」と指弾されている。
歴史の審判は峻厳で冷徹だ。その審判に耐えられないイデオロギーは葬り去られる。被差別部落の起源に関する近世政治起源説も破綻し、「歴史のゴミ箱」に打ち捨てられていく。
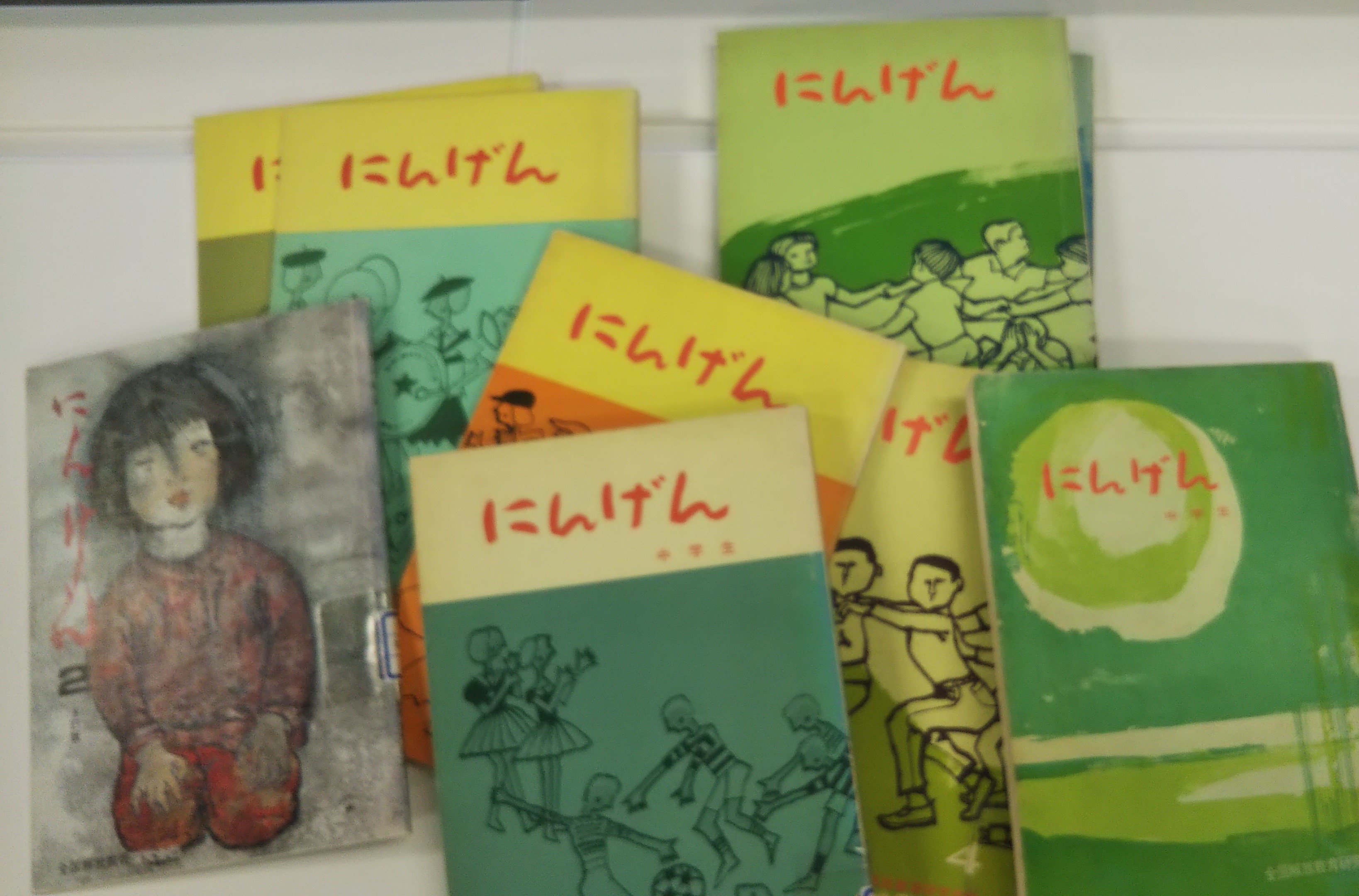
とはいえ、その破綻が明白になるまで、学校教育では「同和教育」の名の下で近世政治起源説が長い間、教え込まれた。大阪府では『にんげん』、兵庫県では『友だち』という副読本が作られ、小中学生に無償で配布された。
大阪府の副読本『にんげん』は1970年から発行が始まった。小学6年生用の『にんげん』には、被差別部落の起源について次のように記してある。
「いまの部落につながるものは、戦国時代の終わりごろから江戸時代のはじめにつくられた。豊臣秀吉は、武士に抵抗する農民をおさえつけるために検地や刀狩をし、ねんぐのとりたてをきびしくすると同時に、身分を法によって決めていく。徳川が全国を統一するようになると、鎖国をして諸大名や商人の力をおさえ、キリスト教もとりしまり、身分制度をいっそうきびしくする。今日まで尾をひく部落差別は、ここで形づくられたのである」(1973年、三訂版)
副読本を編集したのは「全国解放教育研究会」である。研究会の当時の代表は部落解放同盟の上田卓三(たくみ)大阪府連委員長と中村拡三・近畿大学教授で、現職の教師たちが編集にあたった。
この研究会が編集した『解放教育読本 にんげん 指導の手びき』という教師用の手引書には、解放教育がめざすのは「解放の学力」の涵養であり、それには「三つの柱」がある、としている。
第一は「集団主義の思想を確立すること」、第二は「科学的認識・芸術的認識を深めること」、そして第三は「子どもたちに部落解放、解放の自覚をもたせること」である。イデオロギー教育の推進を公然と唱えている。私のように東北で生まれ、同和教育を受けたことのない人間にとっては、唖然とするような指導方針だ。
おまけに、「科学的認識を深める」と言っておきながら、教えていたのは一学説にすぎない「被差別部落=近世政治起源説」であり、その後、研究が進むにつれて否定され、破綻した学説だった。
子どもたちは学び始めてまだ日が浅く、未熟である。だが、愚かではない。多くの子どもは「部落は戦国末期から江戸時代初めに新しくつくられた」という教師の説明を素直に受け入れたが、中には「どういう人たちが部落民にされたの」と尋ねる子がいた。「部落民にされた人たちは反対しなかったの」と問う子もいた。
素朴だが、鋭い質問である。それは、近世政治起源説のアキレス腱を射抜く質問だった。同和教育を担った教師たちはうろたえ、シドロモドロになったことだろう。
◇ ◇
学問の世界でもこれと同じ疑問が発せられた。イデオロギーに囚われた学者たちはそうした疑問を封じ込めようと躍起になったが、日本中世史の研究者たちはそれを打ち破っていく。
連載(9)で紹介したように、鎌倉時代にはすでに「穢多」という言葉を使った絵巻物があることが分かっており、室町時代の文献には「非人」という言葉も頻出する。それらがどのような文脈でどのように使われているか、彼らは丹念に調べ上げていった。そして、中世の賤民たちが江戸時代の穢多、非人へと連綿とつながっていることを実証していったのである。
桃山学院大学の横井清教授は著書『中世民衆の生活文化』で、鎌倉時代の絵巻物『天狗草紙』に描かれた「穢多童(えたわらわ)」とその詞書(ことばがき)を詳細に論じ、すでにこの時代に穢多は「強度の賤視の対象とされていた」と記した。
さらに、室町時代の辞典『下学(かがく)集』などを引用しながら、穢多という蔑称と皮革業という職業、河原という居住環境が密接に結びついていることを明らかにした。それは、「近世の部落の特徴は身分と職業、住所の三つが切り離せないものになった点にある」という、近世政治起源説の根幹とも言うべき「三位一体」が中世から成立していたことを示すもので、近世起源説を根本から掘り崩すものだった。
文献の研究に民俗学などの視点も加えて、「部落の形成史を学際的に考察すべきだ」と唱えたのは、中世史研究者の網野善彦・神奈川大学教授である。
網野は、従来の歴史学が「天皇をはじめとする権力者やそれを支える農民」を軸に歴史を捉えてきたことを批判し、漁民や狩猟民、手工業者や芸能民、遊女や漂白する人々にも光を当て、中世の賤民もそうした文脈から捉え直すことを提唱した。
著書『無縁・公界(くがい)・楽?-日本中世の自由と平和』で、網野は京都の蓮台野(れんだいの)が中世を通して葬送を担っていたことを詳しく論じた。蓮台野は代表的な被差別部落の一つであり、近世、明治を通して差別にさらされてきた。「部落は近世に新たにつくられた」などという学説が成り立たないことを疑問の余地なく明らかにしたのである。
また、『中世の非人と遊女』では、京都・清水坂の非人が「天皇に直属する存在」であり、平民とは「異質な存在」であったことを示した。中世においても、部落は天皇制と密接に結びついていたと主張し、「戦後の歴史学の主流は(その実証的、科学的な研究のために)どれほどのことをしてきたか」と痛烈に批判した。
1980年代になると、中世史の研究者による近世政治起源説への批判はさらに鋭く、厳しいものになった。やがて「部落史の研究者でこの説を信じる者はほとんどいない」という状況になり、今日に至っている。
振り返って、破綻した学説を唱えた人たちはどう思っているのか。大阪市立大学の原田伴彦教授は、1980年の第2回部落解放研究者会議で次のように語っている。
「部落の起源を中世、古代にさかのぼらせる見解は戦前からあり、昭和20年代においてもあった。近世の賤民身分に入れられた人々の個人的ルーツをたどってみると、中世の賤民身分の人々の血をひいているケースが多々あるわけです。当然、古代までさかのぼります。そうなりますと、結局は(中略)原始時代まで部落の起源をさかのぼらせる、ということになってくる」
「それから、もし部落の起源を古代までさかのぼらせるとすると、(中略)天皇を歴史の中核にすえる考え方になってきます。そこに重点を置きすぎると、何か割りきれない面が沢山うまれてくるのではないか」
「部落の起源を古い時代にもっていくことは、結局日本人そのものと部落問題が不可分の関係にある、日本人がなくならない限り部落問題がなくならないという考え方になるわけです。こういう考え方は、運動にとってマイナスにこそなれ、少しもプラスにならないと考えています」
運動にとってプラスかマイナスかで考える――それはイデオローグや活動家の発想であり、研究者がとるべき態度ではない。長い目で見た場合、そうした考えに立って誤った学説を唱え、次の世代に伝えることが何をもたらすか。そこに思いが至らなかった。罪深い人たちである。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2023年2月23日
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真説明≫
大阪府が作成して配布した同和教育の副読本『にんげん』(副読本の無償配布は2008年度で終了した)
≪参考文献≫
◎『共産党宣言』(カール・マルクス&フリードリヒ・エンゲルス、岩波文庫)
◎『経済学批判』(カール・マルクス、大月書店国民文庫4)
◎大阪府の小学6年用副読本『にんげん』(全国解放教育研究会編、明治図書出版、1972年三訂版)
◎『解放教育読本 にんげん 指導の手びき』(全国解放教育研究会編、明治図書出版、1973年)
◎『中世民衆の生活文化』(横井清、東京大学出版会)
◎『無縁・公界・楽?-日本中世の自由と平和』(網野善彦、平凡社選書)
◎『中世の非人と遊女』(網野善彦、講談社学術文庫)
◎『部落解放研究 第21号』(部落解放研究所編集・発行)
ロシアと戦っているウクライナに対して、ドイツとアメリカが主力戦車を提供することを決めた。独米から、高速で走行しながら射撃姿勢をデジタル制御できるレオパルト2とエイブラムスがそれぞれ供与されるという。

密林が広がるベトナムや山岳地帯が戦場となったアフガニスタンと違って、ウクライナ戦争は広大な平原で戦われている。戦車の果たす役割はきわめて大きい。ウクライナにとって朗報であることは間違いない。
この戦争では、ドローンが大きな役割を果たしていることも注目されている。偵察だけでなく敵への攻撃にも使われている。ウクライナのドローンに捕捉されたロシア兵が空を見上げ、十字を切って命乞いをする映像がネット上に流れた。「デジタル時代の戦争」を象徴するような映像だった。
武器の優劣は戦争の帰趨に決定的な影響を及ぼす。その意味で、メディアが戦車の供与やドローンの活用に注目して報道するのは当然のことだが、メディアで報じられないもので「戦争に決定的な影響」を及ぼすものがもう一つある。情報戦の行方、とりわけ暗号の解読がどうなっているかだ。
第2次大戦ではイギリスがドイツの暗号を、アメリカが日本の暗号を解読することに成功した。暗号の解読によって、ドイツと日本がどのような戦略のもとにどのような作戦を立てているか、連合国側にほぼ筒抜けになった。これでは、たとえ戦力が拮抗していたとしても勝てるはずがなかった。
日独とも、戦争の途中で「われわれの暗号は解読されているのではないか」との疑念を抱いた。だが、暗号担当の情報将校たちは「理論的にそのようなことはあり得ない」と主張し、戦争指導者たちを納得させた。当時、日独は無線通信で「5桁の乱数に符丁を組み合わせた暗号システム」を使っていた。これを解読するためには、一つの電文でも「1,000人がかりで3年かかる」とされていた。
戦争を遂行するうえでは、3年後に暗号を解読しても無意味であり、実質的には「解読不能」と言っていい。その意味では、日独の情報将校たちの釈明は間違ってはいなかった。当時普及していた電気リレー式の計算機を使う限り、解読にはそれくらいの人員と年月がかかったからだ。
だが、日独は「前提条件が変われば、解読が可能になる」ということを想定していなかった。イギリスはロンドン北西のブレッチリ―・パーク(暗号解読本部)に数学者や言語学者、クロスワードパズルの名手ら約1万人の要員を集め、総力を挙げてドイツの暗号エニグマの解読に挑んだ。
その中に数学者、アラン・チューリングと彼の仲間たちがいた。計算可能性理論の天才であるチューリングは、その理論を暗号解読に生かし、解読のための「電子計算機」を発明した(写真)。この計算機は真空管を使い、プログラムで稼働する。後のコンピューターの原型とも言える機械で、イギリスはこれを活用してドイツの暗号の解読に成功したのである。
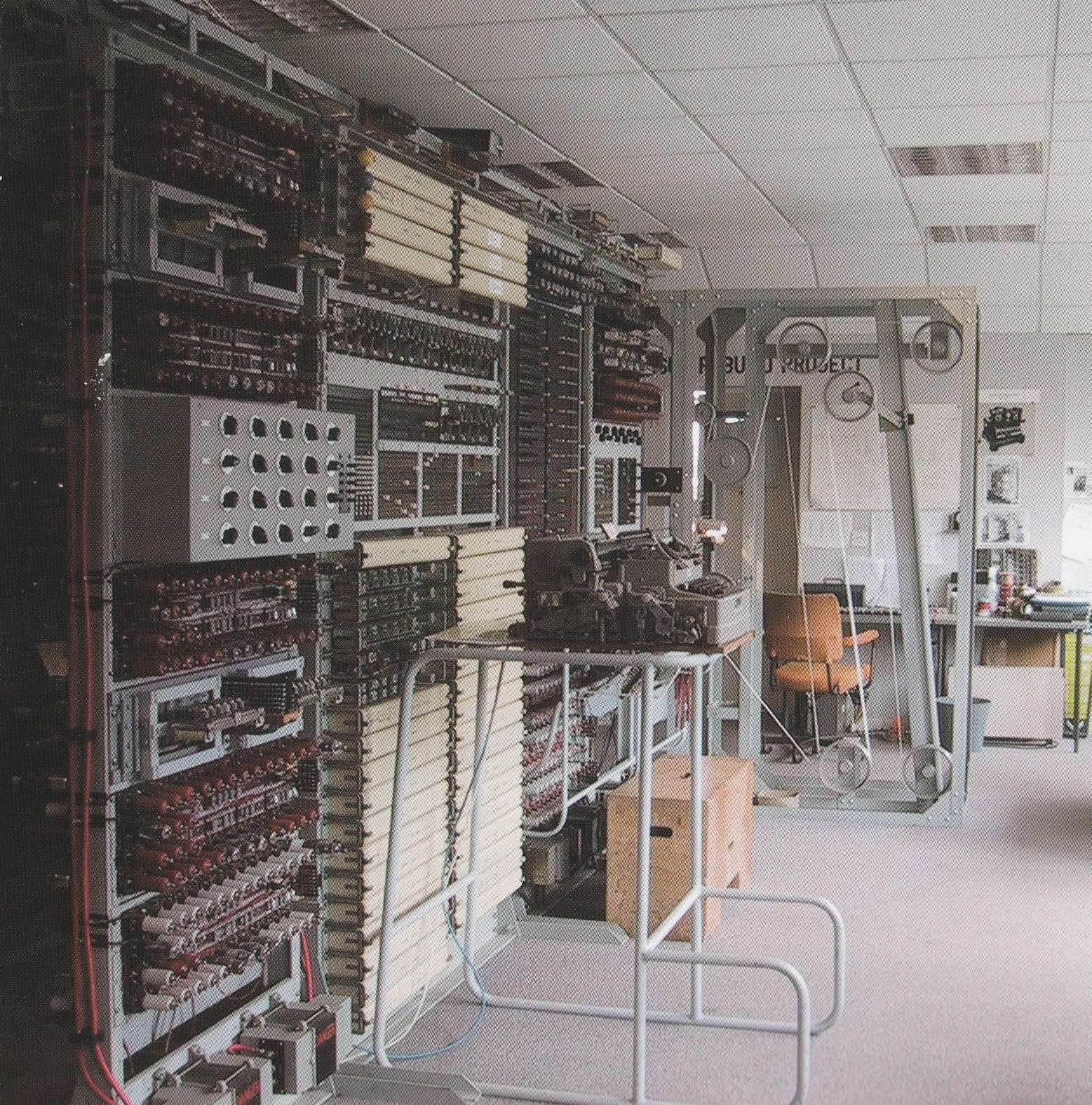
「電気リレー式の計算機」から「電子計算機」への飛躍は、暗号解読の世界をガラリと変えた。実質的に解読不能という説明の前提条件が崩れたことに、ドイツも日本も気づかなかった。「知の総合力に大きな差があった」と言うしかない。
アメリカは1941年の対日開戦前に日本の外交暗号の解読には成功していたが、重要な軍事暗号、とりわけ日本海軍のD暗号(18種類の海軍暗号の中で最も重要な暗号)は解読できていなかった。暗号解読の態勢を立て直し、開戦半年後にはD暗号の解読に成功する。イギリスとは密接な協力関係にあり、電子計算機の供与も受けている。
第2次大戦の終結後も米英による「暗号解読の成功」は極秘とされた。その解読の内実が明らかになったのは1970年代になってからである。その間、両国は冷戦で新たな敵となったソ連の暗号解読にいそしんだが、「ソ連の暗号は秘匿度が強く、解読できていない」と装い続けた。
実は、かなり早い段階で米英はソ連の暗号の解読に成功していた。それが明らかになったのは、1991年にソ連が崩壊し、関係文書が公開されてからだ。暗号の解読は常に、徹底的に秘匿される。
今回のウクライナ戦争でも、第2次大戦と似たことが起きているのではないか。米英はロシアの暗号を解読しており、それを適宜、差しさわりのない範囲でウクライナ側に提供している可能性がある。そう考えると、ウクライナ側が少ない兵力で首都キーウなどを守り抜き、侵攻したロシア軍を押し戻していることも納得がいく。
もちろん、具体的な証拠やデータは何もない。アメリカもイギリスも、こと暗号の解読に関しては厳重に秘匿し続けている。両国のメディアも報じようとしない。暗号の解読状況に触れるような記事を書こうものなら、たちまち政府と軍から「出入り禁止」にされる。「国家の安全保障に直結する機微な情報」は報じないのが米英メディアの伝統だ。
ロシア軍の暗号担当将校は「わが国の暗号はスーパーコンピューターを使っても、簡単には解読できない」とプーチン大統領に説明しているのではないか。確かに、スパコンでも解読できないようなシステムを使っているのかもしれない。
だが、米英が量子コンピューターをすでに実戦配備していたら、どうか。量子力学の原理を応用するこのコンピューターは、スパコンで1万年かかるような計算を3分ほどでこなすという。すでに試作機も登場しており、暗号解読の世界で新しい「パラダイムシフト」が起きている可能性がある。
ウクライナ戦争でロシア側の暗号はどのくらい解読されているのか。解読された情報はウクライナ側にどのくらい伝えられているのか。そうしたことが明らかになるのは20年後、あるいは30年後かもしれない。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」2023年1月31日
≪写真説明&Source≫
・ドイツ製の戦車レオパルト2(東京新聞のサイトから)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/227185
・チューリングが暗号解読のために製作した電子計算機の複製
=大駒誠一『コンピュータ開発史』(共立出版)から引用
≪参考文献≫
◎『暗号の天才』(R・W・クラーク、新潮選書)
◎『暗号解読』(サイモン・シン、新潮社)
◎『暗号 原理とその世界』(長田順行、ダイヤモンド社)
◎『ヴェノナ』(ジョン・アール・ヘインズ&ハーヴェイ・クレア、PHP研究所)

密林が広がるベトナムや山岳地帯が戦場となったアフガニスタンと違って、ウクライナ戦争は広大な平原で戦われている。戦車の果たす役割はきわめて大きい。ウクライナにとって朗報であることは間違いない。
この戦争では、ドローンが大きな役割を果たしていることも注目されている。偵察だけでなく敵への攻撃にも使われている。ウクライナのドローンに捕捉されたロシア兵が空を見上げ、十字を切って命乞いをする映像がネット上に流れた。「デジタル時代の戦争」を象徴するような映像だった。
武器の優劣は戦争の帰趨に決定的な影響を及ぼす。その意味で、メディアが戦車の供与やドローンの活用に注目して報道するのは当然のことだが、メディアで報じられないもので「戦争に決定的な影響」を及ぼすものがもう一つある。情報戦の行方、とりわけ暗号の解読がどうなっているかだ。
第2次大戦ではイギリスがドイツの暗号を、アメリカが日本の暗号を解読することに成功した。暗号の解読によって、ドイツと日本がどのような戦略のもとにどのような作戦を立てているか、連合国側にほぼ筒抜けになった。これでは、たとえ戦力が拮抗していたとしても勝てるはずがなかった。
日独とも、戦争の途中で「われわれの暗号は解読されているのではないか」との疑念を抱いた。だが、暗号担当の情報将校たちは「理論的にそのようなことはあり得ない」と主張し、戦争指導者たちを納得させた。当時、日独は無線通信で「5桁の乱数に符丁を組み合わせた暗号システム」を使っていた。これを解読するためには、一つの電文でも「1,000人がかりで3年かかる」とされていた。
戦争を遂行するうえでは、3年後に暗号を解読しても無意味であり、実質的には「解読不能」と言っていい。その意味では、日独の情報将校たちの釈明は間違ってはいなかった。当時普及していた電気リレー式の計算機を使う限り、解読にはそれくらいの人員と年月がかかったからだ。
だが、日独は「前提条件が変われば、解読が可能になる」ということを想定していなかった。イギリスはロンドン北西のブレッチリ―・パーク(暗号解読本部)に数学者や言語学者、クロスワードパズルの名手ら約1万人の要員を集め、総力を挙げてドイツの暗号エニグマの解読に挑んだ。
その中に数学者、アラン・チューリングと彼の仲間たちがいた。計算可能性理論の天才であるチューリングは、その理論を暗号解読に生かし、解読のための「電子計算機」を発明した(写真)。この計算機は真空管を使い、プログラムで稼働する。後のコンピューターの原型とも言える機械で、イギリスはこれを活用してドイツの暗号の解読に成功したのである。
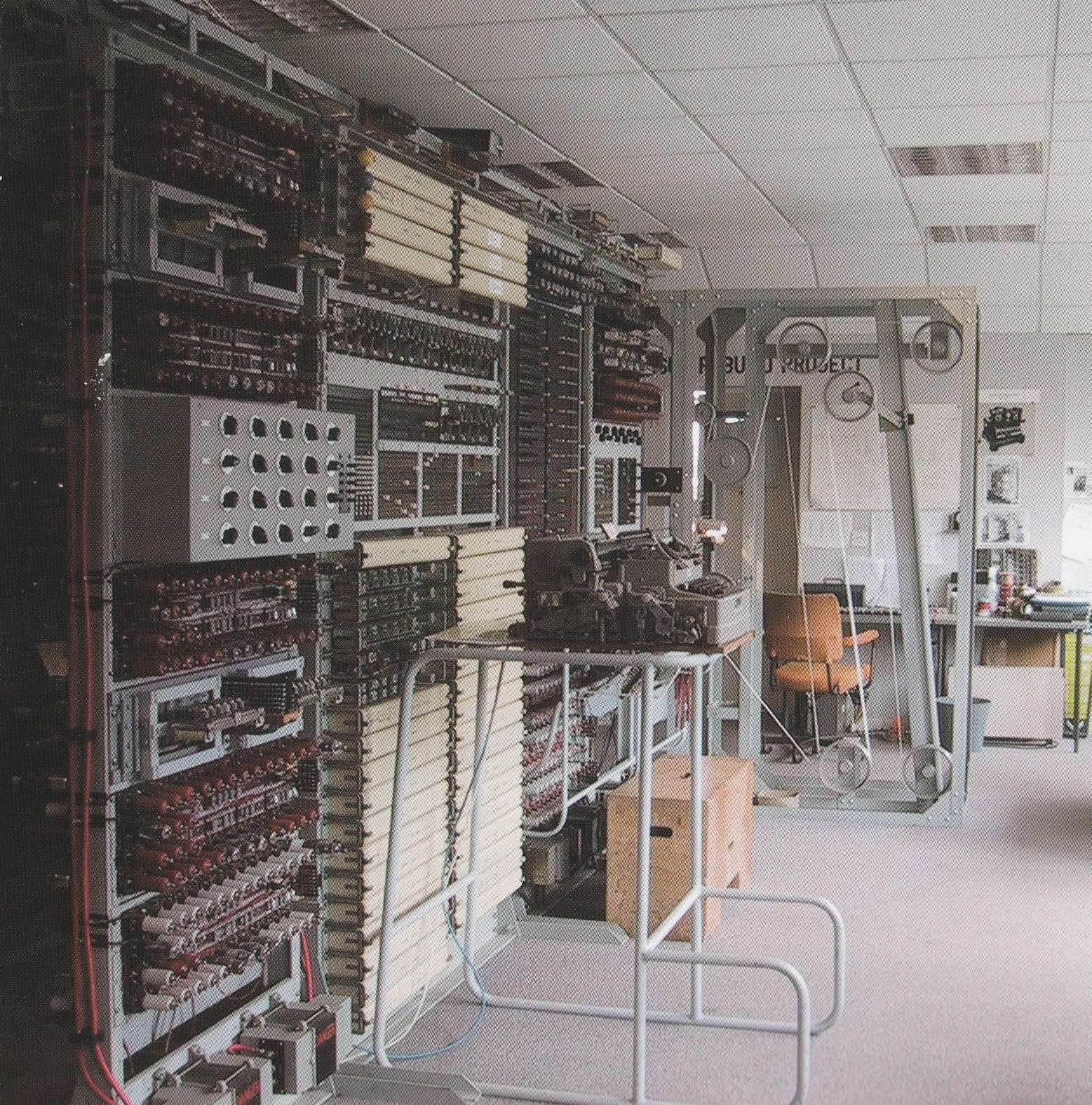
「電気リレー式の計算機」から「電子計算機」への飛躍は、暗号解読の世界をガラリと変えた。実質的に解読不能という説明の前提条件が崩れたことに、ドイツも日本も気づかなかった。「知の総合力に大きな差があった」と言うしかない。
アメリカは1941年の対日開戦前に日本の外交暗号の解読には成功していたが、重要な軍事暗号、とりわけ日本海軍のD暗号(18種類の海軍暗号の中で最も重要な暗号)は解読できていなかった。暗号解読の態勢を立て直し、開戦半年後にはD暗号の解読に成功する。イギリスとは密接な協力関係にあり、電子計算機の供与も受けている。
第2次大戦の終結後も米英による「暗号解読の成功」は極秘とされた。その解読の内実が明らかになったのは1970年代になってからである。その間、両国は冷戦で新たな敵となったソ連の暗号解読にいそしんだが、「ソ連の暗号は秘匿度が強く、解読できていない」と装い続けた。
実は、かなり早い段階で米英はソ連の暗号の解読に成功していた。それが明らかになったのは、1991年にソ連が崩壊し、関係文書が公開されてからだ。暗号の解読は常に、徹底的に秘匿される。
今回のウクライナ戦争でも、第2次大戦と似たことが起きているのではないか。米英はロシアの暗号を解読しており、それを適宜、差しさわりのない範囲でウクライナ側に提供している可能性がある。そう考えると、ウクライナ側が少ない兵力で首都キーウなどを守り抜き、侵攻したロシア軍を押し戻していることも納得がいく。
もちろん、具体的な証拠やデータは何もない。アメリカもイギリスも、こと暗号の解読に関しては厳重に秘匿し続けている。両国のメディアも報じようとしない。暗号の解読状況に触れるような記事を書こうものなら、たちまち政府と軍から「出入り禁止」にされる。「国家の安全保障に直結する機微な情報」は報じないのが米英メディアの伝統だ。
ロシア軍の暗号担当将校は「わが国の暗号はスーパーコンピューターを使っても、簡単には解読できない」とプーチン大統領に説明しているのではないか。確かに、スパコンでも解読できないようなシステムを使っているのかもしれない。
だが、米英が量子コンピューターをすでに実戦配備していたら、どうか。量子力学の原理を応用するこのコンピューターは、スパコンで1万年かかるような計算を3分ほどでこなすという。すでに試作機も登場しており、暗号解読の世界で新しい「パラダイムシフト」が起きている可能性がある。
ウクライナ戦争でロシア側の暗号はどのくらい解読されているのか。解読された情報はウクライナ側にどのくらい伝えられているのか。そうしたことが明らかになるのは20年後、あるいは30年後かもしれない。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」2023年1月31日
≪写真説明&Source≫
・ドイツ製の戦車レオパルト2(東京新聞のサイトから)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/227185
・チューリングが暗号解読のために製作した電子計算機の複製
=大駒誠一『コンピュータ開発史』(共立出版)から引用
≪参考文献≫
◎『暗号の天才』(R・W・クラーク、新潮選書)
◎『暗号解読』(サイモン・シン、新潮社)
◎『暗号 原理とその世界』(長田順行、ダイヤモンド社)
◎『ヴェノナ』(ジョン・アール・ヘインズ&ハーヴェイ・クレア、PHP研究所)
学問の世界では、ある時期に定説として扱われた学説が後に覆されることはよくあることである。新しい事実が見つかったり、新たな知見が得られたりすれば、定説は「旧説」として打ち捨てられていく。
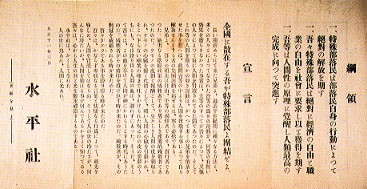
定説を唱えた者たちはそれまでの蓄積を踏まえ、精進を重ねたうえでそうしたのであって、責められるいわれはない。その当時、彼らには新しい事実を知り、知見を得るすべがなかったからである。
だが、被差別部落の歴史をめぐる研究については、いささか事情が異なる。戦後、長い間、被差別部落の起源については「戦国末期から江戸時代にかけて支配層が民衆を分断統治するため新たにつくり出したもの」という、いわゆる近世政治起源説が定説となった。
この説を唱えた者たちは「事実の持つ厳粛さ」と誠実に向き合うという学問の大原則をないがしろにし、自らが信じるイデオロギーに沿って研究を進め、その「成果」を発表し、「確固たる学説」として広めていった。
彼らが唱えた学説は、部落解放同盟が展開した運動と一体となって、「被差別部落の起源に関する自由な研究」を許さないような状況を作り出した。そして、表現と言論の自由を侵害し、部落差別の解消をめざす政府の同和対策事業をもゆがめるような結果をもたらした。
死者に鞭打つようなことはしたくはない。だが、被差別部落の歴史研究に関しては、この近世政治起源説を広めた学者たちの棺を掘り起こし、弾劾せずにはいられない。その罪は重く、それがもたらした影響はあまりにも深刻だからだ。
◇ ◇
すでに紹介したように、被差別部落=近世政治起源説の原型とも言える学説を唱えたのは、戦前の歴史学者、喜田貞吉・京都帝大教授である。喜田はこれを皇国史観に立って主張したのだが、その学説を別のイデオロギーで作り直し、定説と言えるものに仕立て上げていったのは、戦後のマルクス主義を信奉する学者たちだった。
その第一人者は、井上清・京都大学教授である。日本近代史を専門とする井上は、部落解放同盟の北原泰作書記長との共著『部落の歴史』(1956年)に、被差別部落の起源について次のように記した。
「戦国時代は『下剋上』が発展し、日本の歴史のもっとも活気あふれたときであった。古代からの天皇制は、天皇の位につく儀式の費用にもこまるほど無力になり、身分や家がらよりも、経済、軍事、知恵等々の実力がものをいった」
「近世の大名ができる過程で、すでに中世とはちがう差別された『部落』がつくられている。そして豊臣秀吉が全国をしたがえてゆくなかで、刀狩りや検地で、百姓町人の武装の自由はうばわれ、百姓の移動および職業をかえることは禁止され、百姓は孫子の末まで永久に百姓として領主の土地にしばりつけられ、士農工商の身分制の骨組がつくられる。徳川幕府時代に入って、それは細かいところまで完成される」
古代と中世の賤民制度は戦国の世を経てバラバラになり、近世に入って新たな身分制度がつくられた、という主張だ。随所にマルクス主義の歴史観がにじむ。そのうえで、井上はこう唱えた。
「百姓以下の身分として『えた』、『非人』および『宿の者』、『はちや』、『茶せん』、『おん坊』、『とうない』そのほかのいわゆる『雑種賤民』が、身分と職業と住所と三つをきりはなせないものにされ、いまに残る部落がつくられたのである」
近世の賤民の特徴は、この時代に定められた身分と職業、住所の三つが切り離せないものになった点にあるとの主張で、「三位一体説」と呼ばれ、近世政治起源説の根幹をなすものになった。
ちなみに、「被差別部落」という表現を初めて使って定着させたのも井上である。賤称を廃止するとの明治4年の太政官布告(いわゆる解放令)の後も、部落の人たちは「新平民」あるいは「特殊部落民」などと呼ばれ、差別され続けた。井上は新しい言葉を作り出して、そうした呼称を一掃したのである。
井上を中心とする学者たちが敷いた路線に沿って、近世の部落差別に関する史料や記録の発掘が進められ、研究論文の発表や書籍の出版が相次いだ。立命館大学の奈良本辰也、林家辰三郎両教授や大阪市立大学の原田伴彦教授ら錚々たるメンバーが部落問題研究所などに集い、近世政治起源説を打ち固めていった。
そして、この学説はついに政府の同和対策審議会の答申(1965年)に明記されるに至った。
同和対策審議会は、部落差別の解消に向けての基本方針と総合的な政策を打ち出すため、1961年に総理府の付属機関として設置された。4年の審議を経て出された答申は、部落差別を放置することは「断じて許されないことであり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」と記し、政府として部落の環境改善や社会福祉、教育面での支援に乗り出すよう求めるものだった。
差別に苦しみ、さいなまれてきた部落の人たちは、1922年(大正11年)に全国水平社を結成し、戦後も差別をなくすための闘争を繰り広げてきた。同対審の答申は、その長くて困難な道を歩み続けた末にたどり着いた到達点であり、部落解放運動の大きな成果であった。
問題は、その歴史的な文書に「部落の起源」に関する記述を書き加えたことである。前文の後の「第一部 同和問題の認識」に次のような文言が盛り込まれた。
「本審議会は、これら同和地区の起源を学問的に究明することを任務とするものではない。ただ、世人の偏見を打破するためにはっきり断言しておかなければならないのは、同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日本民族、日本国民である、ということである」
「同和地区は、中世末期ないしは近世初期において、封建社会の政治的、経済的、社会的諸条件に規制せられ、一定地域に定着して居住することにより形成された集落である」
内閣総理大臣、佐藤栄作あてに出された審議会の答申に、研究途上の一学説にすぎない近世政治起源説がそっくりそのまま盛り込まれのだ。異様と言うしかない。
政府側の委員として答申の作成にかかわった磯村英一は、第4回部落問題研究者全国集会でその内情を次のように語っている(1967年の同集会報告所収)。
「はっきり申し上げますと、委員のメンバーの中でのイデオロギーの相違からきた反撥の問題が、具体的内容を定めるのにかなり強くひびいたことです。(中略)同対審の会長が三回も四回もやめるといったような問題の中には、今申しましたような問題も若干あります。」
「審議の過程における意見の対立は結構ですが、どちらがイニシャティブをとるとか、またどうしてもその関係者でなければ執筆できないというような点については、もう少し広い立場に立ってよいのではないかと思います」
審議会の内部で激しい意見の対立と葛藤があったことをうかがわせる報告だが、ともあれ、マルクス主義を信奉する研究者たちの学説は「政府のお墨付き」を得た形になり、揺るぎないものとして世に広まっていった。
この答申を受けて、4年後の1969年に同和対策事業特別措置法が制定され、同和地区のインフラ整備や職業・教育支援などのために巨額の公費が投じられた。2002年に同和対策事業に終止符が打たれるまで、投じられた公費は総額15兆円とされる。
こうした同和対策事業によって被差別部落の環境が大幅に改善され、福祉や教育の面で大きな成果があったことは間違いないが、そのひずみもまた大きかった。
大阪府では同和教育のための副読本『にんげん』が作られ、すべての小中学生に無償で配布された。その副読本に書かれていたのは、もちろん「部落は戦国時代の終わりから江戸時代にかけて新しくつくられたもの」という内容だった。他の自治体でも同様である。
部落の近世政治起源説は1980年代以降、中世の史料や記録の発掘・研究が進むにつれて揺らぎ始め、やがて「破綻した学説」としてほとんどの研究者が見向きもしなくなった。
しかしこの間、数十年にわたって、教師たちは「部落は近世になって新しく作られたもの」と子どもたちに教え続けた。イデオロギーに囚われた学者たちが仕立て上げた、誤った学説を垂れ流し続けた。それは広く、深く浸透し、再生産された。
答申に「近世政治起源説」を盛り込んだのは取り返しのつかない過ちであり、その悪影響は政治や行政、学問や教育、文化、言論などあらゆる分野に及んでいった。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真説明≫
1922年に結成された全国水平社の宣言文
≪参考文献&サイト≫
◎『部落の歴史 物語・部落解放運動史』(井上清・北原泰作、理論社)
◎『賤民の後裔 わが屈辱と抵抗の半生』(北原泰作、筑摩書房)
◎『被差別部落の歴史』(原田伴彦、明石書店)
◎『同和対策審議会答申』(京都大学の公式サイト)
◎『「同対審」答申を読む』(奥田均、解放出版社)
◎『同和対策と部落問題:第4回部落問題研究者全国集会報告』(部落問題研究所)所収の磯村英一講演録=国立国会図書館のデジタルデータから抜粋
◎『部落史がかわる』(上杉聰、三一書房)
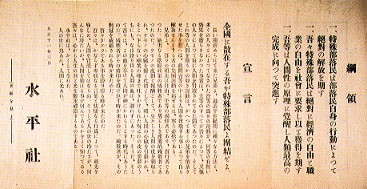
定説を唱えた者たちはそれまでの蓄積を踏まえ、精進を重ねたうえでそうしたのであって、責められるいわれはない。その当時、彼らには新しい事実を知り、知見を得るすべがなかったからである。
だが、被差別部落の歴史をめぐる研究については、いささか事情が異なる。戦後、長い間、被差別部落の起源については「戦国末期から江戸時代にかけて支配層が民衆を分断統治するため新たにつくり出したもの」という、いわゆる近世政治起源説が定説となった。
この説を唱えた者たちは「事実の持つ厳粛さ」と誠実に向き合うという学問の大原則をないがしろにし、自らが信じるイデオロギーに沿って研究を進め、その「成果」を発表し、「確固たる学説」として広めていった。
彼らが唱えた学説は、部落解放同盟が展開した運動と一体となって、「被差別部落の起源に関する自由な研究」を許さないような状況を作り出した。そして、表現と言論の自由を侵害し、部落差別の解消をめざす政府の同和対策事業をもゆがめるような結果をもたらした。
死者に鞭打つようなことはしたくはない。だが、被差別部落の歴史研究に関しては、この近世政治起源説を広めた学者たちの棺を掘り起こし、弾劾せずにはいられない。その罪は重く、それがもたらした影響はあまりにも深刻だからだ。
◇ ◇
すでに紹介したように、被差別部落=近世政治起源説の原型とも言える学説を唱えたのは、戦前の歴史学者、喜田貞吉・京都帝大教授である。喜田はこれを皇国史観に立って主張したのだが、その学説を別のイデオロギーで作り直し、定説と言えるものに仕立て上げていったのは、戦後のマルクス主義を信奉する学者たちだった。
その第一人者は、井上清・京都大学教授である。日本近代史を専門とする井上は、部落解放同盟の北原泰作書記長との共著『部落の歴史』(1956年)に、被差別部落の起源について次のように記した。
「戦国時代は『下剋上』が発展し、日本の歴史のもっとも活気あふれたときであった。古代からの天皇制は、天皇の位につく儀式の費用にもこまるほど無力になり、身分や家がらよりも、経済、軍事、知恵等々の実力がものをいった」
「近世の大名ができる過程で、すでに中世とはちがう差別された『部落』がつくられている。そして豊臣秀吉が全国をしたがえてゆくなかで、刀狩りや検地で、百姓町人の武装の自由はうばわれ、百姓の移動および職業をかえることは禁止され、百姓は孫子の末まで永久に百姓として領主の土地にしばりつけられ、士農工商の身分制の骨組がつくられる。徳川幕府時代に入って、それは細かいところまで完成される」
古代と中世の賤民制度は戦国の世を経てバラバラになり、近世に入って新たな身分制度がつくられた、という主張だ。随所にマルクス主義の歴史観がにじむ。そのうえで、井上はこう唱えた。
「百姓以下の身分として『えた』、『非人』および『宿の者』、『はちや』、『茶せん』、『おん坊』、『とうない』そのほかのいわゆる『雑種賤民』が、身分と職業と住所と三つをきりはなせないものにされ、いまに残る部落がつくられたのである」
近世の賤民の特徴は、この時代に定められた身分と職業、住所の三つが切り離せないものになった点にあるとの主張で、「三位一体説」と呼ばれ、近世政治起源説の根幹をなすものになった。
ちなみに、「被差別部落」という表現を初めて使って定着させたのも井上である。賤称を廃止するとの明治4年の太政官布告(いわゆる解放令)の後も、部落の人たちは「新平民」あるいは「特殊部落民」などと呼ばれ、差別され続けた。井上は新しい言葉を作り出して、そうした呼称を一掃したのである。
井上を中心とする学者たちが敷いた路線に沿って、近世の部落差別に関する史料や記録の発掘が進められ、研究論文の発表や書籍の出版が相次いだ。立命館大学の奈良本辰也、林家辰三郎両教授や大阪市立大学の原田伴彦教授ら錚々たるメンバーが部落問題研究所などに集い、近世政治起源説を打ち固めていった。
そして、この学説はついに政府の同和対策審議会の答申(1965年)に明記されるに至った。
同和対策審議会は、部落差別の解消に向けての基本方針と総合的な政策を打ち出すため、1961年に総理府の付属機関として設置された。4年の審議を経て出された答申は、部落差別を放置することは「断じて許されないことであり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」と記し、政府として部落の環境改善や社会福祉、教育面での支援に乗り出すよう求めるものだった。
差別に苦しみ、さいなまれてきた部落の人たちは、1922年(大正11年)に全国水平社を結成し、戦後も差別をなくすための闘争を繰り広げてきた。同対審の答申は、その長くて困難な道を歩み続けた末にたどり着いた到達点であり、部落解放運動の大きな成果であった。
問題は、その歴史的な文書に「部落の起源」に関する記述を書き加えたことである。前文の後の「第一部 同和問題の認識」に次のような文言が盛り込まれた。
「本審議会は、これら同和地区の起源を学問的に究明することを任務とするものではない。ただ、世人の偏見を打破するためにはっきり断言しておかなければならないのは、同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日本民族、日本国民である、ということである」
「同和地区は、中世末期ないしは近世初期において、封建社会の政治的、経済的、社会的諸条件に規制せられ、一定地域に定着して居住することにより形成された集落である」
内閣総理大臣、佐藤栄作あてに出された審議会の答申に、研究途上の一学説にすぎない近世政治起源説がそっくりそのまま盛り込まれのだ。異様と言うしかない。
政府側の委員として答申の作成にかかわった磯村英一は、第4回部落問題研究者全国集会でその内情を次のように語っている(1967年の同集会報告所収)。
「はっきり申し上げますと、委員のメンバーの中でのイデオロギーの相違からきた反撥の問題が、具体的内容を定めるのにかなり強くひびいたことです。(中略)同対審の会長が三回も四回もやめるといったような問題の中には、今申しましたような問題も若干あります。」
「審議の過程における意見の対立は結構ですが、どちらがイニシャティブをとるとか、またどうしてもその関係者でなければ執筆できないというような点については、もう少し広い立場に立ってよいのではないかと思います」
審議会の内部で激しい意見の対立と葛藤があったことをうかがわせる報告だが、ともあれ、マルクス主義を信奉する研究者たちの学説は「政府のお墨付き」を得た形になり、揺るぎないものとして世に広まっていった。
この答申を受けて、4年後の1969年に同和対策事業特別措置法が制定され、同和地区のインフラ整備や職業・教育支援などのために巨額の公費が投じられた。2002年に同和対策事業に終止符が打たれるまで、投じられた公費は総額15兆円とされる。
こうした同和対策事業によって被差別部落の環境が大幅に改善され、福祉や教育の面で大きな成果があったことは間違いないが、そのひずみもまた大きかった。
大阪府では同和教育のための副読本『にんげん』が作られ、すべての小中学生に無償で配布された。その副読本に書かれていたのは、もちろん「部落は戦国時代の終わりから江戸時代にかけて新しくつくられたもの」という内容だった。他の自治体でも同様である。
部落の近世政治起源説は1980年代以降、中世の史料や記録の発掘・研究が進むにつれて揺らぎ始め、やがて「破綻した学説」としてほとんどの研究者が見向きもしなくなった。
しかしこの間、数十年にわたって、教師たちは「部落は近世になって新しく作られたもの」と子どもたちに教え続けた。イデオロギーに囚われた学者たちが仕立て上げた、誤った学説を垂れ流し続けた。それは広く、深く浸透し、再生産された。
答申に「近世政治起源説」を盛り込んだのは取り返しのつかない過ちであり、その悪影響は政治や行政、学問や教育、文化、言論などあらゆる分野に及んでいった。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真説明≫
1922年に結成された全国水平社の宣言文
≪参考文献&サイト≫
◎『部落の歴史 物語・部落解放運動史』(井上清・北原泰作、理論社)
◎『賤民の後裔 わが屈辱と抵抗の半生』(北原泰作、筑摩書房)
◎『被差別部落の歴史』(原田伴彦、明石書店)
◎『同和対策審議会答申』(京都大学の公式サイト)
◎『「同対審」答申を読む』(奥田均、解放出版社)
◎『同和対策と部落問題:第4回部落問題研究者全国集会報告』(部落問題研究所)所収の磯村英一講演録=国立国会図書館のデジタルデータから抜粋
◎『部落史がかわる』(上杉聰、三一書房)
新型コロナウイルスのワクチンを開発できなかった日本の製薬会社が、ついに治療薬の開発に成功したという。塩野義製薬が北海道大学と共同で開発した「ゾコーバ」である。昨年11月下旬に厚生労働省が治療薬として緊急承認し、医療機関への供給が始まった。

本来なら、「これで一安心」と祝福したいところだが、この「コロナ治療薬」、どうもおかしい。コロナ患者の治療にあたっている医師たちがほとんど使っていないのだという。理由はハッキリしている。あまり効き目がないからだ。
厚生労働省や塩野義製薬の発表資料をよく読むと、このコロナ治療薬「ゾコーバ」は1日1回服用すると、鼻水やせき、発熱などの症状が7日間ほどでなくなり、服用しない場合に比べて症状が1日早く治まるのだという。それって、個人差あるいは誤差の範囲内ではないのか。
おまけに、この薬は「軽症や中程度の症状の患者用」で、重症化するリスクが高い患者には向かないのだとか。これでは、医師が処方したがらないのも当然だろう。12月30日付の朝日新聞によると、この薬の供給が始まってから1カ月ほどで処方されたのは7700人余り。毎日20万人前後のコロナ患者が確認されていることを考えれば、「ほとんど使われていない」と言っていい。
そんな薬を厚生労働省は塩野義製薬と事前に「100万人分購入する」と契約し、緊急承認した後、さらに100万人分、合計で200万人分も購入する契約を結んだ。常日頃、厚生労働省の仕事ぶりに首をひねっている筆者としては「また、税金の無駄遣いになるのではないか」と疑いたくもなる。
新型コロナウイルスの感染症対策が急務なのは言うまでもない。従って、昨年5月に法律を改正して治療薬の「緊急承認制度」を作ったことまでは理解できる。「ゾコーバ」はその緊急承認制度が適用された第1号の治療薬である。
だが、薬の調達は処方される量に応じて確保する、というのが常道ではないか。どの程度使われるか分からないうちから、「200万人分買います」と約束して税金を投入する必要がどこにあるのか。
ましてや、塩野義製薬の「ゾコーバ」は日本国内で治療薬として緊急承認されただけで、アメリカなどでは治療薬として承認されていない。「効き目があるかどうか分からない」ような薬を承認しないのは当たり前だろう。
コロナの感染が広がってから、政府は国産ワクチンの開発を支援するため、2020年度の補正予算に2577億円、2021年度の補正予算に2562億円を計上し、合わせて5139億円の税金を投入した。にもかかわらず、国産のワクチンは開発できず、米英の大手製薬会社のワクチンを使うはめになった。5000億円余りの補助金はムダ金になったと言うしかない。
国産のコロナ治療薬の開発にも多額の税金が投じられている。その結果が「症状を1日短縮するだけの治療薬」の開発である。しかも、それを気前よく購入する契約を結んだ。日本の医療を担う厚労省の幹部たちは、恥ずかしくないのだろうか。
塩野義製薬のコロナ治療薬の開発経過を調べていて気になるのは、早い段階から政治家がうごめいている気配があることである。自民党の甘利明・元幹事長は去年の2月4日、この治療薬の薬事承認の手続き中に「(塩野義製薬の薬は)日本人対象の治験で副作用は既存薬より極めて少なく、効能は他を圧している。外国承認をアリバイに石橋を叩いても渡らない厚労省を督促中だ」と自身のツイッターに書き込んだ。
治験の結果もまだ明らかになっていない段階で「効能は他を圧している」と書き込む神経にあきれる。塩野義製薬側から伝えられた情報をうのみにして発信したのだろう。政財官がどのように癒着しているか、問わず語りにその一端を語ってしまった、といったところか。
ああ、また私たちの貴重な税金が政治家と企業、官僚の談合で消えていく。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2023年1月16日
https://news-hunter.org/?p=15960
≪写真説明&Source≫
塩野義製薬のコロナ治療薬「ゾコーバ」
https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20221124_n01/
≪参考サイト&記事≫
◎「ゾコーバ」の緊急承認に関する塩野義製薬のプレスリリース(2022年11月22日)
https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2022/11/20221122.html
◎「塩野義製 国産コロナ薬 低調」(朝日新聞2022年12月30日付)
◎国産ワクチンの開発支援予算の概要(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21hosei/dl/21hosei_20211129_02.pdf
◎塩野義の手代木(てしろぎ)社長、甘利氏ツイート念頭に「政治など外部の影響を受けることない」(日経バイオテクONLINE、2022年2月8日)
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/22/02/07/09135/

本来なら、「これで一安心」と祝福したいところだが、この「コロナ治療薬」、どうもおかしい。コロナ患者の治療にあたっている医師たちがほとんど使っていないのだという。理由はハッキリしている。あまり効き目がないからだ。
厚生労働省や塩野義製薬の発表資料をよく読むと、このコロナ治療薬「ゾコーバ」は1日1回服用すると、鼻水やせき、発熱などの症状が7日間ほどでなくなり、服用しない場合に比べて症状が1日早く治まるのだという。それって、個人差あるいは誤差の範囲内ではないのか。
おまけに、この薬は「軽症や中程度の症状の患者用」で、重症化するリスクが高い患者には向かないのだとか。これでは、医師が処方したがらないのも当然だろう。12月30日付の朝日新聞によると、この薬の供給が始まってから1カ月ほどで処方されたのは7700人余り。毎日20万人前後のコロナ患者が確認されていることを考えれば、「ほとんど使われていない」と言っていい。
そんな薬を厚生労働省は塩野義製薬と事前に「100万人分購入する」と契約し、緊急承認した後、さらに100万人分、合計で200万人分も購入する契約を結んだ。常日頃、厚生労働省の仕事ぶりに首をひねっている筆者としては「また、税金の無駄遣いになるのではないか」と疑いたくもなる。
新型コロナウイルスの感染症対策が急務なのは言うまでもない。従って、昨年5月に法律を改正して治療薬の「緊急承認制度」を作ったことまでは理解できる。「ゾコーバ」はその緊急承認制度が適用された第1号の治療薬である。
だが、薬の調達は処方される量に応じて確保する、というのが常道ではないか。どの程度使われるか分からないうちから、「200万人分買います」と約束して税金を投入する必要がどこにあるのか。
ましてや、塩野義製薬の「ゾコーバ」は日本国内で治療薬として緊急承認されただけで、アメリカなどでは治療薬として承認されていない。「効き目があるかどうか分からない」ような薬を承認しないのは当たり前だろう。
コロナの感染が広がってから、政府は国産ワクチンの開発を支援するため、2020年度の補正予算に2577億円、2021年度の補正予算に2562億円を計上し、合わせて5139億円の税金を投入した。にもかかわらず、国産のワクチンは開発できず、米英の大手製薬会社のワクチンを使うはめになった。5000億円余りの補助金はムダ金になったと言うしかない。
国産のコロナ治療薬の開発にも多額の税金が投じられている。その結果が「症状を1日短縮するだけの治療薬」の開発である。しかも、それを気前よく購入する契約を結んだ。日本の医療を担う厚労省の幹部たちは、恥ずかしくないのだろうか。
塩野義製薬のコロナ治療薬の開発経過を調べていて気になるのは、早い段階から政治家がうごめいている気配があることである。自民党の甘利明・元幹事長は去年の2月4日、この治療薬の薬事承認の手続き中に「(塩野義製薬の薬は)日本人対象の治験で副作用は既存薬より極めて少なく、効能は他を圧している。外国承認をアリバイに石橋を叩いても渡らない厚労省を督促中だ」と自身のツイッターに書き込んだ。
治験の結果もまだ明らかになっていない段階で「効能は他を圧している」と書き込む神経にあきれる。塩野義製薬側から伝えられた情報をうのみにして発信したのだろう。政財官がどのように癒着しているか、問わず語りにその一端を語ってしまった、といったところか。
ああ、また私たちの貴重な税金が政治家と企業、官僚の談合で消えていく。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2023年1月16日
https://news-hunter.org/?p=15960
≪写真説明&Source≫
塩野義製薬のコロナ治療薬「ゾコーバ」
https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20221124_n01/
≪参考サイト&記事≫
◎「ゾコーバ」の緊急承認に関する塩野義製薬のプレスリリース(2022年11月22日)
https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2022/11/20221122.html
◎「塩野義製 国産コロナ薬 低調」(朝日新聞2022年12月30日付)
◎国産ワクチンの開発支援予算の概要(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21hosei/dl/21hosei_20211129_02.pdf
◎塩野義の手代木(てしろぎ)社長、甘利氏ツイート念頭に「政治など外部の影響を受けることない」(日経バイオテクONLINE、2022年2月8日)
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/22/02/07/09135/
長い間、文字は支配者のものだった。彼らは文字を使ってルールを定め、統治した。その統治の正統性を謳(うた)い、伝えるために記録を残した。
当然のことながら、支配する側が残した史書や記録は公平なものではあり得ない。敵は常に悪逆非道であり、「大義は我らにあり」と記す。戦いに敗れた者たちのことは「必要な範囲」で触れるだけだ。ましてや、隷属する者たちのことなど気にも留めない。かすかな断片のようなものが後世に伝えられるに過ぎない。
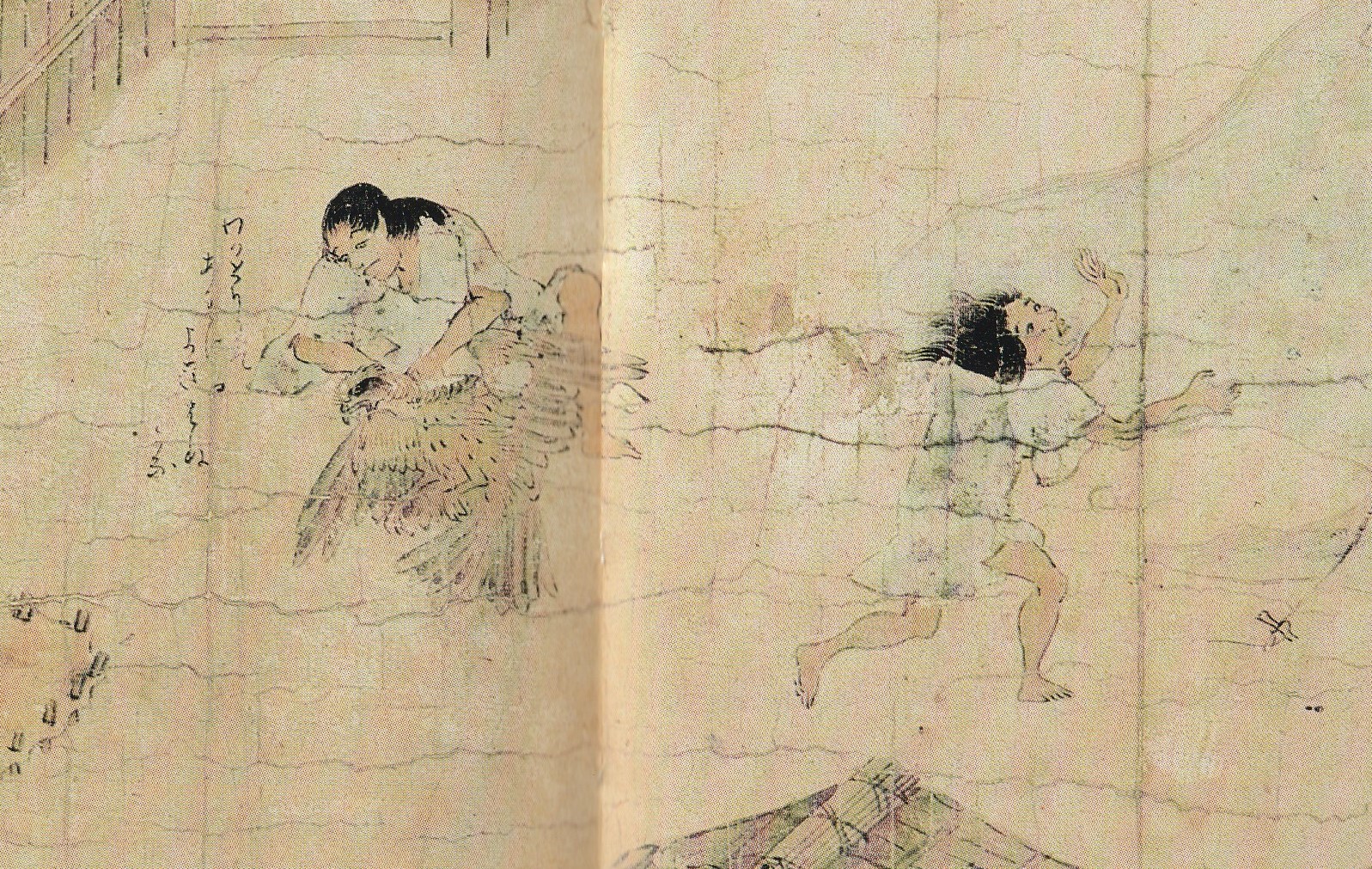
部落史の研究者によれば、「エタ」あるいは「穢多」という文字が文献に初めて出てくるのは13世紀、鎌倉時代である。随筆形式の辞典、『塵袋(ちりぶくろ)』という文献(作者不詳)に次のように記されている。
キヨメヲエタト云フハ何ナル詞(こと)ハソ
根本ハ餌取(エトリ)ト云フヘキ欤(か)
餌ト云フハシヽムラ 鷹等ノ餌ヲ云フナルヘシ 其ヲトル物ト云フ也
エトリヲハヤクイヒテ イヒユカメテエタト云ヘリ
(中略)
天竺ニ旃陀羅(せんだら)ト云フハ屠者(トシャ)也
イキ物ヲ殺テウルエタ躰(てい)ノ悪人也
(片仮名のルビは写本の通り、平仮名のルビは筆者が補足)
現代語訳すれば、「清めの仕事をする者を『エタ』と言うのはなぜか。その語源は『餌取』と言うべきか。餌とは肉のかたまり、タカなどの餌を取る者のことである。『エトリ』を早口で言い、言いゆがめて『エタ』と言った」「インドの言葉で『旃陀羅』と言うのは『屠者』のことで、生き物を殺して売る『エタ』のような悪人のことである」という内容だ。
律令国家の時代から、鷹狩は天皇や貴族のたしなみであり、軍事訓練を兼ねていた。鷹狩を取り仕切り、タカの飼育を担う役職があった。餌取とは、その役人の配下でタカの餌の調達にあたった人々のことを言う。その「エトリ」が転じて「エタ」と呼ばれるようになった、というのが『塵袋』の説明である。
作者も自信がなかったのだろう。「語源は餌取と言うべきか」と留保を付けている。また、「エタ」のところには「非人やカタイ(ハンセン病者)、エタは人と交わらない点で同じようなもの」という説明もある。彼らは蔑まれ、忌避される存在だった。
「エタ」の語源に関する『塵袋』のこれらの記述はさまざまに解釈されてきたが、重要なのはすでに鎌倉時代には「エタ」という言葉が使われていたという点だ。同じ頃に作られた『天狗草紙』という絵巻物には、「穢多童(えたわらわ)」という文字が記され、子どもが鳥を捕まえ、さばいている絵がある。
鎌倉時代にはすでに「エタ」という言葉が使われ、「穢多」という漢字が当てられていたことは疑いようがない。そして、その言葉の由来については当時、辞典を編む知識人ですら「餌取から転じたものか」といった程度のことしか記すことができなくなっていた。
冒頭に記したように、支配層にとって「社会の底辺で生きる人々」のことなど取るに足らない事柄である。「エタ」という言葉が書き留められるまでにはかなりの時が流れ、その由来すらよく分からなくなっていた、と考えるのが自然だろう。
文字には「いったん記されると独り歩きを始める」という性質がある。室町時代の辞典『壒嚢抄(あいのうしょう)』や江戸時代の百科事典『和漢三才図会』にも「エタ」についての説明があり、どちらも「エタの語源は餌取」と記す。ともに『塵袋』を参照したと見られるが、『塵袋』にあった「語源は餌取か」の「か」という留保はなくなり、両方とも断定している。被差別部落の問題を扱う本には、これらの文献を引用して「エタは餌取の転訛」と説明しているものが少なくない。「独り歩き」の好例と言える。
文字や記録を扱う者は、素直すぎてはいけない。「エタ」や「穢多」の語源に関する文献は、一字一句を注意深く、時には疑い深く読む必要があることを教えている。「エタ」の語源については諸説あるが、今となっては「よく分からない」と言うしかない。
◇ ◇
鎌倉時代や室町時代、差別にさらされた人々は穢多、非人のほか河原者、皮多(かわた)、宿(しゅく)の者、坂の者、細工、庭者、鉢たたきなどさまざまな名で呼ばれた。歌舞伎や人形浄瑠璃の役者も「河原者」として扱われ、賤視された。
戦乱や飢饉、自然災害や疫病の流行が相次いだ時代である。人々は疲弊し、社会は揺れ動いた。混乱の中で賤民からのし上がった人々も少なくなかっただろう。とりわけ、室町幕府が形骸化して戦国の世になると、下剋上という言葉に象徴されるように社会階層は激しく流動化した。
このプロセスをどのように見るかは「被差別部落の起源をどう考えるか」に直結する重要な論点となる。「大混乱の中でも多くの賤民は這い上がれなかった」と見るか。「社会階層はバラバラになり、リセットされた」と見るか。
前者の立場なら「今日の被差別部落の起源は江戸時代から中世、さらには古代にまで遡る可能性がある」となる。後者の立場からは「古代や中世の賤民とは断絶がある。豊臣政権の時代から江戸時代にかけて、支配する側は新たな身分差別制度をつくった」と説くことになる。
どちらの見解がより合理的で説得力があるかの判断はひとまず置き、話を先に進める。
16世紀末に戦国の世を治め、天下を統一したのは豊臣秀吉である。豊臣政権は田畑の検地を実施して年貢の徴収を確実なものにし、農民一揆を抑えるために刀狩をした。部落差別との関係で重要なのは、武家の奉公人が町人や百姓になること及び百姓が商人や職人になることを禁じたことだ。身分が固定され、町人や百姓の下に位置づけられた被差別民は這い上がることができなくなった。
江戸時代になると、身分の固定はさらに強化され、宗門人別改帳によって厳しく管理されるようになる。教科書では江戸期の被差別民は「穢多・非人」と表現されるが、当時の文献を見ると、「穢多」の呼称は東日本では「長吏(ちょうり)」、西日本では「かわた」や「革多」などと記されることが多い。「非人」もさまざまな名で呼ばれ、記録された。
太平の世が長く続くなるにつれて、差別はきつくなる。部落の人々は通婚の禁止に加え、「木綿と麻布以上の衣服を着てはならない」(1683年、長府藩)、「武士や百姓、町人と出会った時は道の片側に寄れ」(紀州藩)といった厳しい規制を受けた。
極め付きは、伊予(愛媛)の大洲藩の触書(1798年)である。「近頃、穢多の分限不相応な振る舞いが目立つ」として、彼らに「五寸四方の毛皮を身に着けて歩くこと。家の戸口にも毛皮を下げること」を命じた。
これらの触書は、商品経済が広まるにつれて被差別民の中にも財を蓄え、裕福な暮らしをする者が増えていったことを示している。江戸幕府の支配は揺らぎ始め、やがて幕末から明治維新へ激動の時代を迎える。
欧米先進国に追いつくため、明治新政府は富国強兵策を推し進め、明治4年(1871年)に穢多・非人などの賤称を廃止する太政官布告(いわゆる解放令)を出した。これによって非人身分の人たちの多くは平民に溶け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは取り残された。
大正11年(1922年)に全国水平社を結成し、部落差別の克服をめざして立ち上がった人々の多くは「旧穢多」の人たちであり、現在まで差別にさらされている人たちの多くもその末裔である。
◇ ◇
では、穢多のルーツは何か。江戸時代から明治にかけて、さまざまな解釈がなされてきた。
江戸後期に百科事典『守貞謾稿』を著した喜田川守貞は「高麗(朝鮮半島)から渡来し、皮なめしを業とした人たちの末裔」と記した(渡来人・帰化人説)。儒学者の帆足万里は『東潜夫論』で「穢多は昔、奥羽に住んでいた夷人の末裔である。田村麻呂が奥羽を平定し、蝦夷をことごとく日本人にした」と説いた(蝦夷起源説)。
ほかにも、仏教の教えが広まり、殺生を忌む風潮が広がる中で屠者がけがれた者として差別されるようになった(宗教起源説)、殺生を行い、血のけがれに関わる仕事に従事する者が差別されるようになった(職業起源説)、と唱える学者もいた。
実にさまざまな起源説があったが、これらを「妄説」と一蹴したのが京都帝大の歴史学の教授、喜田貞吉である。喜田は1919年(大正8年)に月刊『民族と歴史』の特殊部落研究号を出版し、次のように主張した(注1)。
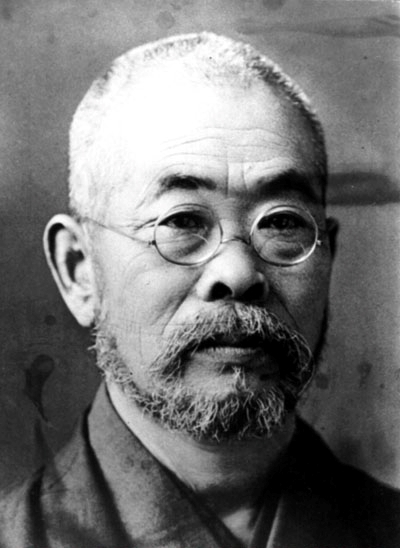
「素人はよくこういう事を申します。貴賤の別は民族から起ったので、賎民として疎外されているものは、土人や帰化人の子孫ではなかろうかと申します。一寸そうも考えやすいことではありますが、我が日本民族に於いては、決してそんな事実はありません」
「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するということは、少くとも昔はありませんでした。蝦夷人すなわちアイヌ族の出にして、立派な地位に上ったものも少くない。(中略)有名な征夷大将軍の棟梁坂上田村麿(注2)も、少くとも昔の奥州の人は蝦夷(えぞ)仲間だと思っておりました」
「世人が特に彼らをひどく賤しみ出したのは、徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」
「我が国には、民族の区別によって甚だしく貴賤の区別を立てる事は致しません。したがって、もと違った民族であっても、うまく融和同化して日本民族となったのであります。ただ境遇により、時の勢いによって、同じものでも貴となり、賎となる。今日、特殊部落と認められているものは、徳川時代のいわゆる穢多・非人でありますが、それも非人の方は多くは解放されまして、穢多のみがみな取り残されております。しかも、その穢多なるものは、もと雑戸とか浮浪人とかいう方で、法制上の昔の賎民というものではありません」
「同じく日本民族たる同胞が互いに圧迫を加えたり、反抗したりするには世界があまりに広くなっております。特殊部落の成立沿革を考え、過去に於ける賎民解放の事歴を調査しましたならば、今にしてなお彼らに圧迫を加うることの無意味なることもわかりましょう」
なにせ、京都帝大の歴史学者のご託宣である。その影響力は絶大だった。この特殊部落研究号の出版によって、「部落差別は江戸時代につくられた」という近世政治起源説の原型のようなものが打ち立てられた。
喜田はこの学説を部落差別の解消を願って唱えた。その善意は疑いようもない。学説の基盤にあったのは皇国史観である。「国民は皆、天皇の赤子である。同胞同士で差別し、圧迫を加えてどうする」と訴えたかったのだろう。
そして、それはこの研究号出版の3年後に旗揚げした全国水平社に集う人たちにとっても好ましいものだった。「同じ日本人なのに、いわれなき差別に苦しめられてきた。今こそ立ち上がる時だ」と奮い立ったのである。
水平社の運動は戦時中、翼賛体制にのみ込まれ、消えていく。敗戦後の1946年、部落解放全国委員会として再出発し、1955年に現在の部落解放同盟に改称した。
戦後、部落解放の運動を理論面で支えたのはマルクス主義を信奉する学者たちである。彼らは、喜田貞吉が打ち出した学説をより精緻に練り上げ、近世政治起源説として広め、定説にしていった。
喜田は皇国史観に立って「国民はみな天皇の赤子」と訴えた。戦後のマルクス主義の学者たちは、唯物史観の立場から「労働者も農民も部落民も、みな被搾取階級である。団結して革命を起こす主体となるべきだ」と唱えた。
拠(よ)って立つイデオロギーはまるで異なるが、どちらにとっても「部落差別をつくり出したのは豊臣政権であり、江戸幕府である」という説明は都合が良かった。「差別の根は浅い。権力者が政治的につくり出したものなら、政治的に解決しようではないか」と訴えることができるからだ。
喜田もマルクス主義の学者たちも「歴史をイデオロギーに基づいて解釈する」という点で共通している。事実の持つ厳粛さの前に謙虚になり、異なる学説への敬意を忘れず切磋琢磨していく、という姿勢が欠落していた。
だが、イデオロギーに基づく学説は事実によって掘り崩され、葬り去られていく。中世の史料の発掘が進み、後に続く研究者によって「鎌倉時代や室町時代の賤民と江戸時代の穢多・非人との強いつながり」が次々に明らかにされていった。
そして、研究はさらに「では、中世の賤民と古代の賤民とはどのような関係にあるのか」という課題の解明へと向かっている。そこでは、「天皇制と被差別の関係」に目を向けないわけにはいかない。部落史の研究は「新しい夜明け」を迎え、曇りのない目で歴史を見つめる時代を迎えている。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真説明≫
◎「天狗草紙」に描かれた穢多童(えたわらわ)=『続日本絵巻大成19』(中央公論社)から複写
◎喜田貞吉(東北大学関係写真データベースから)
≪参考文献≫
◎『塵袋1』(大西晴隆・木村紀子校注、平凡社東洋文庫)
◎『土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞 続日本絵巻物大成19』(中央公論社)
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社)
◎『部落史用語辞典』(小林茂ら編集、柏書房)
◎『入門被差別部落の歴史』(寺木伸明・黒川みどり、解放出版社)
◎『近世風俗志(守貞謾稿)(一)』(喜田川守貞、岩波文庫)
◎『近世後期の部落差別政策(上)』(井ケ田良治、同志社法学1969・1・31)
◎『帆足万里』(帆足図南次、吉川弘文館)
◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫)=『民族と歴史』特殊部落研究号の喜田論文をまとめて復刻
◎『日本歴史の中の被差別民』(奈良人権・部落解放研究所編、新人物往来社)
◎『部落・差別の歴史』(藤沢靖介、解放出版社)
*注1 喜田貞吉は『民族と歴史』特殊部落研究号を出版した1919年の時点では京都帝大専任講師。翌1920年に教授に昇格した。
*注2 喜田は「坂上田村麻呂」ではなく「坂上田村麿」と記している。
当然のことながら、支配する側が残した史書や記録は公平なものではあり得ない。敵は常に悪逆非道であり、「大義は我らにあり」と記す。戦いに敗れた者たちのことは「必要な範囲」で触れるだけだ。ましてや、隷属する者たちのことなど気にも留めない。かすかな断片のようなものが後世に伝えられるに過ぎない。
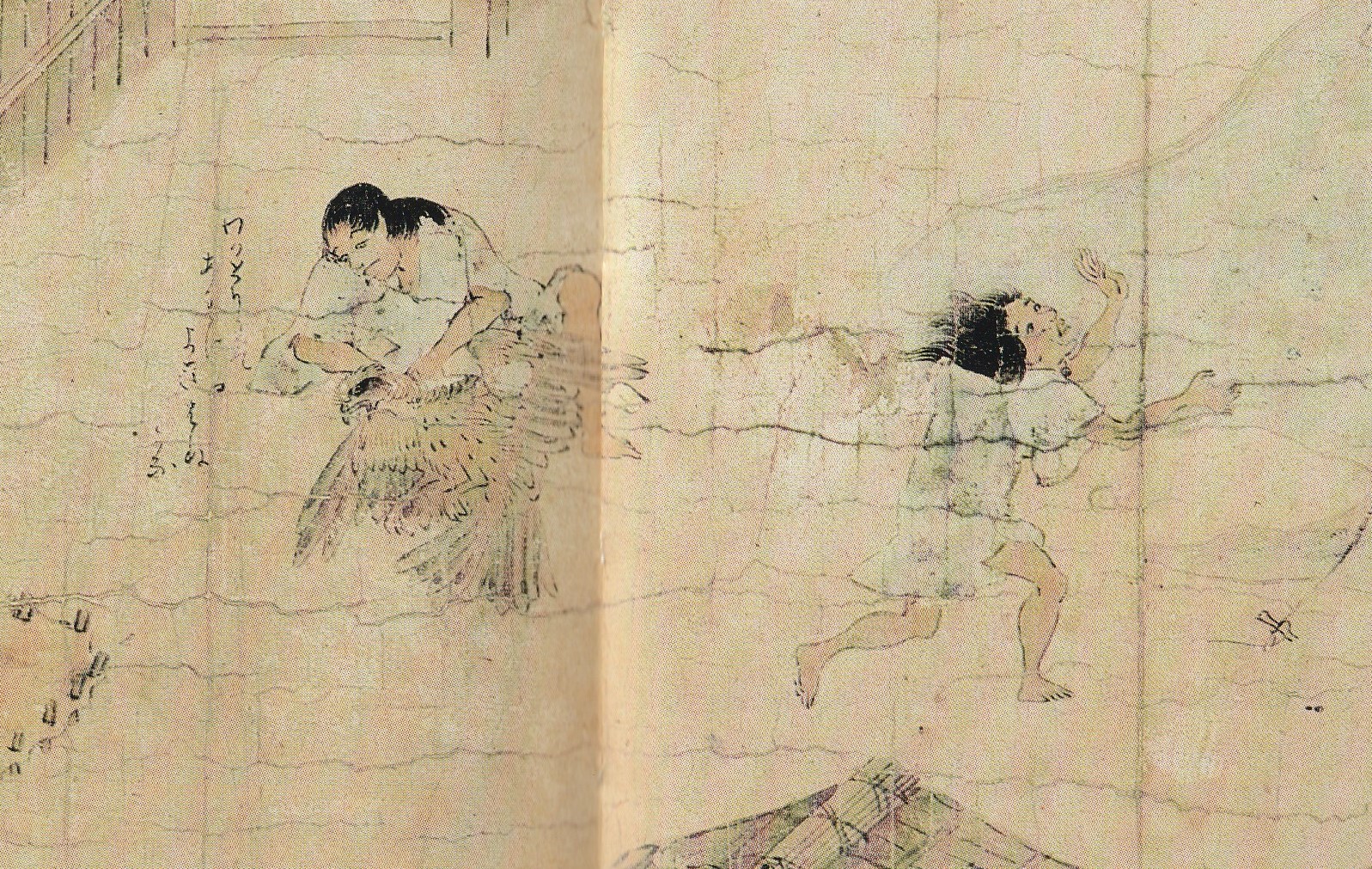
部落史の研究者によれば、「エタ」あるいは「穢多」という文字が文献に初めて出てくるのは13世紀、鎌倉時代である。随筆形式の辞典、『塵袋(ちりぶくろ)』という文献(作者不詳)に次のように記されている。
キヨメヲエタト云フハ何ナル詞(こと)ハソ
根本ハ餌取(エトリ)ト云フヘキ欤(か)
餌ト云フハシヽムラ 鷹等ノ餌ヲ云フナルヘシ 其ヲトル物ト云フ也
エトリヲハヤクイヒテ イヒユカメテエタト云ヘリ
(中略)
天竺ニ旃陀羅(せんだら)ト云フハ屠者(トシャ)也
イキ物ヲ殺テウルエタ躰(てい)ノ悪人也
(片仮名のルビは写本の通り、平仮名のルビは筆者が補足)
現代語訳すれば、「清めの仕事をする者を『エタ』と言うのはなぜか。その語源は『餌取』と言うべきか。餌とは肉のかたまり、タカなどの餌を取る者のことである。『エトリ』を早口で言い、言いゆがめて『エタ』と言った」「インドの言葉で『旃陀羅』と言うのは『屠者』のことで、生き物を殺して売る『エタ』のような悪人のことである」という内容だ。
律令国家の時代から、鷹狩は天皇や貴族のたしなみであり、軍事訓練を兼ねていた。鷹狩を取り仕切り、タカの飼育を担う役職があった。餌取とは、その役人の配下でタカの餌の調達にあたった人々のことを言う。その「エトリ」が転じて「エタ」と呼ばれるようになった、というのが『塵袋』の説明である。
作者も自信がなかったのだろう。「語源は餌取と言うべきか」と留保を付けている。また、「エタ」のところには「非人やカタイ(ハンセン病者)、エタは人と交わらない点で同じようなもの」という説明もある。彼らは蔑まれ、忌避される存在だった。
「エタ」の語源に関する『塵袋』のこれらの記述はさまざまに解釈されてきたが、重要なのはすでに鎌倉時代には「エタ」という言葉が使われていたという点だ。同じ頃に作られた『天狗草紙』という絵巻物には、「穢多童(えたわらわ)」という文字が記され、子どもが鳥を捕まえ、さばいている絵がある。
鎌倉時代にはすでに「エタ」という言葉が使われ、「穢多」という漢字が当てられていたことは疑いようがない。そして、その言葉の由来については当時、辞典を編む知識人ですら「餌取から転じたものか」といった程度のことしか記すことができなくなっていた。
冒頭に記したように、支配層にとって「社会の底辺で生きる人々」のことなど取るに足らない事柄である。「エタ」という言葉が書き留められるまでにはかなりの時が流れ、その由来すらよく分からなくなっていた、と考えるのが自然だろう。
文字には「いったん記されると独り歩きを始める」という性質がある。室町時代の辞典『壒嚢抄(あいのうしょう)』や江戸時代の百科事典『和漢三才図会』にも「エタ」についての説明があり、どちらも「エタの語源は餌取」と記す。ともに『塵袋』を参照したと見られるが、『塵袋』にあった「語源は餌取か」の「か」という留保はなくなり、両方とも断定している。被差別部落の問題を扱う本には、これらの文献を引用して「エタは餌取の転訛」と説明しているものが少なくない。「独り歩き」の好例と言える。
文字や記録を扱う者は、素直すぎてはいけない。「エタ」や「穢多」の語源に関する文献は、一字一句を注意深く、時には疑い深く読む必要があることを教えている。「エタ」の語源については諸説あるが、今となっては「よく分からない」と言うしかない。
◇ ◇
鎌倉時代や室町時代、差別にさらされた人々は穢多、非人のほか河原者、皮多(かわた)、宿(しゅく)の者、坂の者、細工、庭者、鉢たたきなどさまざまな名で呼ばれた。歌舞伎や人形浄瑠璃の役者も「河原者」として扱われ、賤視された。
戦乱や飢饉、自然災害や疫病の流行が相次いだ時代である。人々は疲弊し、社会は揺れ動いた。混乱の中で賤民からのし上がった人々も少なくなかっただろう。とりわけ、室町幕府が形骸化して戦国の世になると、下剋上という言葉に象徴されるように社会階層は激しく流動化した。
このプロセスをどのように見るかは「被差別部落の起源をどう考えるか」に直結する重要な論点となる。「大混乱の中でも多くの賤民は這い上がれなかった」と見るか。「社会階層はバラバラになり、リセットされた」と見るか。
前者の立場なら「今日の被差別部落の起源は江戸時代から中世、さらには古代にまで遡る可能性がある」となる。後者の立場からは「古代や中世の賤民とは断絶がある。豊臣政権の時代から江戸時代にかけて、支配する側は新たな身分差別制度をつくった」と説くことになる。
どちらの見解がより合理的で説得力があるかの判断はひとまず置き、話を先に進める。
16世紀末に戦国の世を治め、天下を統一したのは豊臣秀吉である。豊臣政権は田畑の検地を実施して年貢の徴収を確実なものにし、農民一揆を抑えるために刀狩をした。部落差別との関係で重要なのは、武家の奉公人が町人や百姓になること及び百姓が商人や職人になることを禁じたことだ。身分が固定され、町人や百姓の下に位置づけられた被差別民は這い上がることができなくなった。
江戸時代になると、身分の固定はさらに強化され、宗門人別改帳によって厳しく管理されるようになる。教科書では江戸期の被差別民は「穢多・非人」と表現されるが、当時の文献を見ると、「穢多」の呼称は東日本では「長吏(ちょうり)」、西日本では「かわた」や「革多」などと記されることが多い。「非人」もさまざまな名で呼ばれ、記録された。
太平の世が長く続くなるにつれて、差別はきつくなる。部落の人々は通婚の禁止に加え、「木綿と麻布以上の衣服を着てはならない」(1683年、長府藩)、「武士や百姓、町人と出会った時は道の片側に寄れ」(紀州藩)といった厳しい規制を受けた。
極め付きは、伊予(愛媛)の大洲藩の触書(1798年)である。「近頃、穢多の分限不相応な振る舞いが目立つ」として、彼らに「五寸四方の毛皮を身に着けて歩くこと。家の戸口にも毛皮を下げること」を命じた。
これらの触書は、商品経済が広まるにつれて被差別民の中にも財を蓄え、裕福な暮らしをする者が増えていったことを示している。江戸幕府の支配は揺らぎ始め、やがて幕末から明治維新へ激動の時代を迎える。
欧米先進国に追いつくため、明治新政府は富国強兵策を推し進め、明治4年(1871年)に穢多・非人などの賤称を廃止する太政官布告(いわゆる解放令)を出した。これによって非人身分の人たちの多くは平民に溶け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは取り残された。
大正11年(1922年)に全国水平社を結成し、部落差別の克服をめざして立ち上がった人々の多くは「旧穢多」の人たちであり、現在まで差別にさらされている人たちの多くもその末裔である。
◇ ◇
では、穢多のルーツは何か。江戸時代から明治にかけて、さまざまな解釈がなされてきた。
江戸後期に百科事典『守貞謾稿』を著した喜田川守貞は「高麗(朝鮮半島)から渡来し、皮なめしを業とした人たちの末裔」と記した(渡来人・帰化人説)。儒学者の帆足万里は『東潜夫論』で「穢多は昔、奥羽に住んでいた夷人の末裔である。田村麻呂が奥羽を平定し、蝦夷をことごとく日本人にした」と説いた(蝦夷起源説)。
ほかにも、仏教の教えが広まり、殺生を忌む風潮が広がる中で屠者がけがれた者として差別されるようになった(宗教起源説)、殺生を行い、血のけがれに関わる仕事に従事する者が差別されるようになった(職業起源説)、と唱える学者もいた。
実にさまざまな起源説があったが、これらを「妄説」と一蹴したのが京都帝大の歴史学の教授、喜田貞吉である。喜田は1919年(大正8年)に月刊『民族と歴史』の特殊部落研究号を出版し、次のように主張した(注1)。
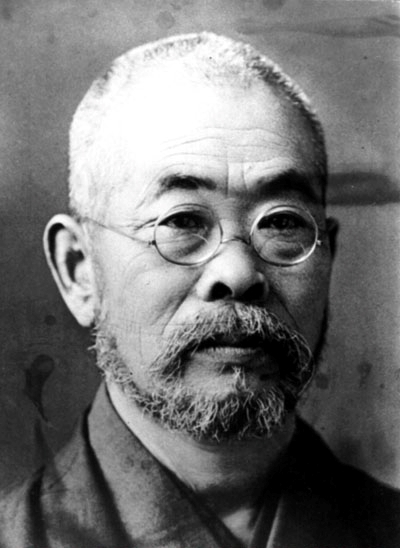
「素人はよくこういう事を申します。貴賤の別は民族から起ったので、賎民として疎外されているものは、土人や帰化人の子孫ではなかろうかと申します。一寸そうも考えやすいことではありますが、我が日本民族に於いては、決してそんな事実はありません」
「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するということは、少くとも昔はありませんでした。蝦夷人すなわちアイヌ族の出にして、立派な地位に上ったものも少くない。(中略)有名な征夷大将軍の棟梁坂上田村麿(注2)も、少くとも昔の奥州の人は蝦夷(えぞ)仲間だと思っておりました」
「世人が特に彼らをひどく賤しみ出したのは、徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」
「我が国には、民族の区別によって甚だしく貴賤の区別を立てる事は致しません。したがって、もと違った民族であっても、うまく融和同化して日本民族となったのであります。ただ境遇により、時の勢いによって、同じものでも貴となり、賎となる。今日、特殊部落と認められているものは、徳川時代のいわゆる穢多・非人でありますが、それも非人の方は多くは解放されまして、穢多のみがみな取り残されております。しかも、その穢多なるものは、もと雑戸とか浮浪人とかいう方で、法制上の昔の賎民というものではありません」
「同じく日本民族たる同胞が互いに圧迫を加えたり、反抗したりするには世界があまりに広くなっております。特殊部落の成立沿革を考え、過去に於ける賎民解放の事歴を調査しましたならば、今にしてなお彼らに圧迫を加うることの無意味なることもわかりましょう」
なにせ、京都帝大の歴史学者のご託宣である。その影響力は絶大だった。この特殊部落研究号の出版によって、「部落差別は江戸時代につくられた」という近世政治起源説の原型のようなものが打ち立てられた。
喜田はこの学説を部落差別の解消を願って唱えた。その善意は疑いようもない。学説の基盤にあったのは皇国史観である。「国民は皆、天皇の赤子である。同胞同士で差別し、圧迫を加えてどうする」と訴えたかったのだろう。
そして、それはこの研究号出版の3年後に旗揚げした全国水平社に集う人たちにとっても好ましいものだった。「同じ日本人なのに、いわれなき差別に苦しめられてきた。今こそ立ち上がる時だ」と奮い立ったのである。
水平社の運動は戦時中、翼賛体制にのみ込まれ、消えていく。敗戦後の1946年、部落解放全国委員会として再出発し、1955年に現在の部落解放同盟に改称した。
戦後、部落解放の運動を理論面で支えたのはマルクス主義を信奉する学者たちである。彼らは、喜田貞吉が打ち出した学説をより精緻に練り上げ、近世政治起源説として広め、定説にしていった。
喜田は皇国史観に立って「国民はみな天皇の赤子」と訴えた。戦後のマルクス主義の学者たちは、唯物史観の立場から「労働者も農民も部落民も、みな被搾取階級である。団結して革命を起こす主体となるべきだ」と唱えた。
拠(よ)って立つイデオロギーはまるで異なるが、どちらにとっても「部落差別をつくり出したのは豊臣政権であり、江戸幕府である」という説明は都合が良かった。「差別の根は浅い。権力者が政治的につくり出したものなら、政治的に解決しようではないか」と訴えることができるからだ。
喜田もマルクス主義の学者たちも「歴史をイデオロギーに基づいて解釈する」という点で共通している。事実の持つ厳粛さの前に謙虚になり、異なる学説への敬意を忘れず切磋琢磨していく、という姿勢が欠落していた。
だが、イデオロギーに基づく学説は事実によって掘り崩され、葬り去られていく。中世の史料の発掘が進み、後に続く研究者によって「鎌倉時代や室町時代の賤民と江戸時代の穢多・非人との強いつながり」が次々に明らかにされていった。
そして、研究はさらに「では、中世の賤民と古代の賤民とはどのような関係にあるのか」という課題の解明へと向かっている。そこでは、「天皇制と被差別の関係」に目を向けないわけにはいかない。部落史の研究は「新しい夜明け」を迎え、曇りのない目で歴史を見つめる時代を迎えている。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真説明≫
◎「天狗草紙」に描かれた穢多童(えたわらわ)=『続日本絵巻大成19』(中央公論社)から複写
◎喜田貞吉(東北大学関係写真データベースから)
≪参考文献≫
◎『塵袋1』(大西晴隆・木村紀子校注、平凡社東洋文庫)
◎『土蜘蛛草紙 天狗草紙 大江山絵詞 続日本絵巻物大成19』(中央公論社)
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社)
◎『部落史用語辞典』(小林茂ら編集、柏書房)
◎『入門被差別部落の歴史』(寺木伸明・黒川みどり、解放出版社)
◎『近世風俗志(守貞謾稿)(一)』(喜田川守貞、岩波文庫)
◎『近世後期の部落差別政策(上)』(井ケ田良治、同志社法学1969・1・31)
◎『帆足万里』(帆足図南次、吉川弘文館)
◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫)=『民族と歴史』特殊部落研究号の喜田論文をまとめて復刻
◎『日本歴史の中の被差別民』(奈良人権・部落解放研究所編、新人物往来社)
◎『部落・差別の歴史』(藤沢靖介、解放出版社)
*注1 喜田貞吉は『民族と歴史』特殊部落研究号を出版した1919年の時点では京都帝大専任講師。翌1920年に教授に昇格した。
*注2 喜田は「坂上田村麻呂」ではなく「坂上田村麿」と記している。
なんて国だろう、と思う。
森友学園問題で公文書の改竄を指示した財務省の佐川宣寿(のぶひさ)理財局長(当時)を相手に損害賠償を求めた裁判の判決があった。公文書の改竄を命じられて自死した近畿財務局の職員、赤木俊夫氏の妻が訴えていたものだが、大阪地裁は25日、佐川氏の賠償責任を認めず、請求を棄却した。

公務員が故意または過失によって他人に損害を与えた時は、国または自治体が賠償する、と国家賠償法は定めている。今回のケースでは、政府は損害賠償の責任があることをすでに認めている。従って、「佐川氏には損害を賠償する責任はない」というわけだ。
理屈は通っている。「政府または地方自治体が賠償責任を負う場合、公務員個人の責任を問うことはできない」との最高裁判所の判例(1955年4月19日)を踏襲したものだという。しかし、前代未聞の公文書改竄の「下手人」をそんな大昔の判例をそのままなぞって裁いていいのか。
2017年2月に森友学園問題が表面化し、国有地が8億円も値引きされて森友側に払い下げられ、しかも一連の公文書が改竄されていたことが発覚した際、佐川氏は国会の証人喚問で「刑事訴追の恐れがある」として証言を拒否した。
ところが、大阪地検特捜部は「虚偽有印公文書作成罪などにはあたらない」として不起訴処分にした。検察は国有地の8億円値引きについて「それが不適切であると認定するのは困難」と説明した。端(はな)から、認定する気がなかったのだろう。
佐川氏は「刑事訴追の恐れがある」という理由で国会での証言を拒否したのに国税庁長官に栄転し、結局、訴追されずに逃げ切った。すべて安倍晋三政権下での出来事であり、安倍首相を守るための所業だった。栄転はその恩賞である。
どんなに卑劣なことをしても、それが権力を握る者のためであるならば許される。許すために政府も検察も裁判所も足並みをそろえて動く――なんて国だ、と思う。
法律はもともと「2周遅れて時代に付いていく」ものだ。時代の変化に付いていけない。法改正には年月がかかり、改正した頃にはまた時代が変わっていたりする。従って、時代の要請に応えるためには、法律を柔軟に大胆に解釈するしかない。問題は、当事者たちに「時代の要請」に応えようとする意志と勇気があるかどうかだ。
森友問題をめぐる一連の動きは、この国の政治家にも官僚にも、また検察官にも裁判官にもその「意志と勇気」がないことを示している。
国家賠償法は、公務員が故意または重大な過失によって他人に損害を与え、政府が賠償した場合、政府はその公務員に求償権を有する、と規定している。つまり、政府はその公務員に「あなたの違法行為によって損害が生じ、賠償しなければならなくなった。ついてはその賠償額を返してほしい」と要求する権利があるのだ。
ならば、政府が手間暇かけて求償するより、被害者(今回のケースでは赤木氏の妻)が直接、その公務員に損害賠償を求め、政府の手間を省いてあげることも認める、と解釈する余地もあるはずだ。時代の要請に応えるべく、判例を変え、新しい判例を積み上げていく。それこそ、司法に求められていることではないか。
「そんなことを認めたら、公務員個人を相手にした損害賠償請求訴訟が続発してしまう」と心配する向きもある。が、公務員個人を訴えることができるのは「故意または重大な過失があった場合のみ」である。しかも、訴える側は「故意または重大な過失があったこと」を立証しなければならない。おいそれと起こせる訴訟ではあるまい。
森友学園問題をめぐる公文書の改竄が佐川氏の「故意」によって行われたことは明白だ。しかも、改竄を迫られた職員が自死するという事態まで招いた。このような事件について、刑事でも民事でも責任を問えないとしたら、司法は何のためにあるのか。
今の日本では、どんな嘘もごまかしも、権力者と取り巻きにとっては自由自在。責任を問われることもない――森友学園問題はそれを満天下に示すことになった。佐川氏の罪はきわめて重い。それをかばい切ることに手を貸した者たちの罪はさらに重い。未来への希望を打ち砕いたからである。
(長岡 昇:元朝日新聞記者)
*初出:ウェブコラム「情報屋台」 2022年11月26日
≪写真説明&Souce≫
◎森友学園の小学校建設現場(大阪市豊中市)
https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/486
≪参考サイト≫
◎裁判所が公務員である教員個人の損害賠償責任を認めないのはなぜか
森友学園問題で公文書の改竄を指示した財務省の佐川宣寿(のぶひさ)理財局長(当時)を相手に損害賠償を求めた裁判の判決があった。公文書の改竄を命じられて自死した近畿財務局の職員、赤木俊夫氏の妻が訴えていたものだが、大阪地裁は25日、佐川氏の賠償責任を認めず、請求を棄却した。

公務員が故意または過失によって他人に損害を与えた時は、国または自治体が賠償する、と国家賠償法は定めている。今回のケースでは、政府は損害賠償の責任があることをすでに認めている。従って、「佐川氏には損害を賠償する責任はない」というわけだ。
理屈は通っている。「政府または地方自治体が賠償責任を負う場合、公務員個人の責任を問うことはできない」との最高裁判所の判例(1955年4月19日)を踏襲したものだという。しかし、前代未聞の公文書改竄の「下手人」をそんな大昔の判例をそのままなぞって裁いていいのか。
2017年2月に森友学園問題が表面化し、国有地が8億円も値引きされて森友側に払い下げられ、しかも一連の公文書が改竄されていたことが発覚した際、佐川氏は国会の証人喚問で「刑事訴追の恐れがある」として証言を拒否した。
ところが、大阪地検特捜部は「虚偽有印公文書作成罪などにはあたらない」として不起訴処分にした。検察は国有地の8億円値引きについて「それが不適切であると認定するのは困難」と説明した。端(はな)から、認定する気がなかったのだろう。
佐川氏は「刑事訴追の恐れがある」という理由で国会での証言を拒否したのに国税庁長官に栄転し、結局、訴追されずに逃げ切った。すべて安倍晋三政権下での出来事であり、安倍首相を守るための所業だった。栄転はその恩賞である。
どんなに卑劣なことをしても、それが権力を握る者のためであるならば許される。許すために政府も検察も裁判所も足並みをそろえて動く――なんて国だ、と思う。
法律はもともと「2周遅れて時代に付いていく」ものだ。時代の変化に付いていけない。法改正には年月がかかり、改正した頃にはまた時代が変わっていたりする。従って、時代の要請に応えるためには、法律を柔軟に大胆に解釈するしかない。問題は、当事者たちに「時代の要請」に応えようとする意志と勇気があるかどうかだ。
森友問題をめぐる一連の動きは、この国の政治家にも官僚にも、また検察官にも裁判官にもその「意志と勇気」がないことを示している。
国家賠償法は、公務員が故意または重大な過失によって他人に損害を与え、政府が賠償した場合、政府はその公務員に求償権を有する、と規定している。つまり、政府はその公務員に「あなたの違法行為によって損害が生じ、賠償しなければならなくなった。ついてはその賠償額を返してほしい」と要求する権利があるのだ。
ならば、政府が手間暇かけて求償するより、被害者(今回のケースでは赤木氏の妻)が直接、その公務員に損害賠償を求め、政府の手間を省いてあげることも認める、と解釈する余地もあるはずだ。時代の要請に応えるべく、判例を変え、新しい判例を積み上げていく。それこそ、司法に求められていることではないか。
「そんなことを認めたら、公務員個人を相手にした損害賠償請求訴訟が続発してしまう」と心配する向きもある。が、公務員個人を訴えることができるのは「故意または重大な過失があった場合のみ」である。しかも、訴える側は「故意または重大な過失があったこと」を立証しなければならない。おいそれと起こせる訴訟ではあるまい。
森友学園問題をめぐる公文書の改竄が佐川氏の「故意」によって行われたことは明白だ。しかも、改竄を迫られた職員が自死するという事態まで招いた。このような事件について、刑事でも民事でも責任を問えないとしたら、司法は何のためにあるのか。
今の日本では、どんな嘘もごまかしも、権力者と取り巻きにとっては自由自在。責任を問われることもない――森友学園問題はそれを満天下に示すことになった。佐川氏の罪はきわめて重い。それをかばい切ることに手を貸した者たちの罪はさらに重い。未来への希望を打ち砕いたからである。
(長岡 昇:元朝日新聞記者)
*初出:ウェブコラム「情報屋台」 2022年11月26日
≪写真説明&Souce≫
◎森友学園の小学校建設現場(大阪市豊中市)
https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/486
≪参考サイト≫
◎裁判所が公務員である教員個人の損害賠償責任を認めないのはなぜか
新聞記事にも著作権はある。記者が取材して執筆し、編集者が見出しを付けて紙面に組むのには手間暇がかかる。それを無断で利用すれば、著作権法に触れることは言うまでもない。

一方で、新聞には「社会の公器」としての役割もある。報道したことを広く知ってもらうことは報道機関にとって好ましいことでもある。インターネットが普及し、スマホで気軽にアクセスできる時代に、新聞社や通信社がネット上に転載された記事について「著作権法上の権利」をどこまで主張し、貫くかは悩ましいところだ。
ところが、世の中にはそうした「悩ましさ」など気にかけず、著作権を振りかざして「削除と謝罪」を求める新聞社がある。山形新聞である。11月2日付の社会面トップ記事で「国会議員、県議ら70人、本紙無断転載」と報じた。
11月8日には「紙面の無断転載巡り議員6人に通告書」と追い打ちをかけ、県議2人と市議4人の実名を挙げて「著作権を侵害したとの通告書を出した」と伝えた。議員らは自らのフェイスブックやツイッター、ブログに山形新聞の記事を無断で転載していたことを認め、謝罪したという。
これに先立って、同紙は7月に共産党の県議、10月には無所属の鶴岡市議の無断転載を報じていた。これをきっかけに「県内の政治家の無断転載」を総ざらいした結果、著作権侵害のケースが多数あることが分かり、今回の報道になったようだ。
「新聞社の権益を守る」という観点に立てば、一連の報道を英断と評する人もいるかもしれない。だが、議員の実名まで挙げて報道し、転載した記事を削除させたうえ、「今後は無断で転載しません」との誓約書まで提出させるのは「報道機関の暴走」と言えないか。
この新聞が日頃、公平で誠実な報道に徹しているのなら、私も「暴走」などという表現は使わない。だが、その実態は「公平」や「誠実」とはかけ離れている。
山形新聞は部数減対策として、2016年から「教育に新聞を」「1学級に1新聞を」というキャンペーンを始めた。すると、山形県の吉村美栄子知事はこれに呼応する形で2017年度予算に2,794万円を計上し、新聞を購読する小中学校に補助金を出すことを決めた。
同紙はこれを「全国で初」と1面トップで報じた。「全国初」なのは当たり前である。このIT化の時代に学級ごとに新聞を購読させ、それに補助金や助成金を出す都道府県などほかにあるわけがない。要するに「部数減を食い止めたい。県も税金を投入して協力して」と知事に泣きついたのである。
建前として、どの新聞を取るかは市町村の教育委員会と各学校に委ねられていたが、山形県の交付要項には「郷土愛を育むことを目指す」とうたわれていた。郷土のニュースがふんだんに盛り込まれている新聞、つまりは山形新聞の購読を促す内容だった。実際、学校が購読した新聞のほとんどは山形新聞で、この事業は翌年度以降も続けられた。
吉村知事と山形新聞は「持ちつ持たれつ」の関係にある。2021年1月知事選の前年の秋、山形県は山形新聞に「コロナを克服し、大雨災害からの復旧に取り組む」との全面広告を何度か出した。
広告には吉村知事のポーズ写真とメッセージも添えられた。選挙の事前運動とも受け取られかねない内容で、「選挙前には現職知事の写真などを付した広告を掲載しない」との新聞の広告倫理に触れかねない内容だった。が、吉村知事は気にせず、気前良く税金を投じて広告を出した。
知事との関係にせよ、今回の無断転載の追及にせよ、これを仕切っているのは山形新聞の寒河江浩二(さがえ・ひろじ)社長である。編集局長を経て、2012年から社長をつとめ、主筆を兼ねる。75歳。細かい記事にまで口を出すことで知られ、今では社内で自由に意見を言える人はいないという。「山新のプーチン」と陰口をたたかれるゆえんである。
山形新聞は、民放テレビ局や観光会社、1T企業、広告会社をグループに抱える山形県のミニ財閥の中核企業だ。寒河江社長は山形県経営者協会の会長でもある。「政治は知事、経済は私」といった気分なのだろう。
なにせ、山形新聞にはかつて「山形県の政治も経済も牛耳った」という?前科?がある。服部敬雄(よしお)社長の全盛期には国会議員も知事も山形市長もひれ伏し、頭が上がらなかった。地元の人たちは「服部天皇」と呼んだ。
服部社長が1991年に亡くなり、山新グループの勢いはだいぶ衰えた。が、寒河江社長は在任が10年に及び、鼻息はいよいよ荒い。「第二の服部になりかねない」と懸念する声がある。
かつて、山新グループのトップには「天皇」という肩書が付けられた。今は「プーチン」と呼ばれる。昔も今も、面と向かって道理を説く人が周りにいない。県民の一人として切なく、情けない。
長岡 昇(元朝日新聞記者)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2022年11月15日
≪参考記事&サイト≫
◎無断転用を報じた山形新聞の記事(2022年7月8日付、10月21日付、11月2日付、11月8日付)
◎日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権」に関する見解
◎新聞著作権協議会の「新聞記事・写真の著作権と複製」に関する見解
◎小中学校での新聞購読に山形県が助成金を出すことを報じた山形新聞の記事(2017年3月16日付)
◎2021年1月の知事選の前に山形新聞に掲載された山形県の全面広告(2020年9月9日付、11月20日付)
◎「服部天皇」による山形県支配の内実を伝えるコラム(ウエブコラム情報屋台)

一方で、新聞には「社会の公器」としての役割もある。報道したことを広く知ってもらうことは報道機関にとって好ましいことでもある。インターネットが普及し、スマホで気軽にアクセスできる時代に、新聞社や通信社がネット上に転載された記事について「著作権法上の権利」をどこまで主張し、貫くかは悩ましいところだ。
ところが、世の中にはそうした「悩ましさ」など気にかけず、著作権を振りかざして「削除と謝罪」を求める新聞社がある。山形新聞である。11月2日付の社会面トップ記事で「国会議員、県議ら70人、本紙無断転載」と報じた。
11月8日には「紙面の無断転載巡り議員6人に通告書」と追い打ちをかけ、県議2人と市議4人の実名を挙げて「著作権を侵害したとの通告書を出した」と伝えた。議員らは自らのフェイスブックやツイッター、ブログに山形新聞の記事を無断で転載していたことを認め、謝罪したという。
これに先立って、同紙は7月に共産党の県議、10月には無所属の鶴岡市議の無断転載を報じていた。これをきっかけに「県内の政治家の無断転載」を総ざらいした結果、著作権侵害のケースが多数あることが分かり、今回の報道になったようだ。
「新聞社の権益を守る」という観点に立てば、一連の報道を英断と評する人もいるかもしれない。だが、議員の実名まで挙げて報道し、転載した記事を削除させたうえ、「今後は無断で転載しません」との誓約書まで提出させるのは「報道機関の暴走」と言えないか。
この新聞が日頃、公平で誠実な報道に徹しているのなら、私も「暴走」などという表現は使わない。だが、その実態は「公平」や「誠実」とはかけ離れている。
山形新聞は部数減対策として、2016年から「教育に新聞を」「1学級に1新聞を」というキャンペーンを始めた。すると、山形県の吉村美栄子知事はこれに呼応する形で2017年度予算に2,794万円を計上し、新聞を購読する小中学校に補助金を出すことを決めた。
同紙はこれを「全国で初」と1面トップで報じた。「全国初」なのは当たり前である。このIT化の時代に学級ごとに新聞を購読させ、それに補助金や助成金を出す都道府県などほかにあるわけがない。要するに「部数減を食い止めたい。県も税金を投入して協力して」と知事に泣きついたのである。
建前として、どの新聞を取るかは市町村の教育委員会と各学校に委ねられていたが、山形県の交付要項には「郷土愛を育むことを目指す」とうたわれていた。郷土のニュースがふんだんに盛り込まれている新聞、つまりは山形新聞の購読を促す内容だった。実際、学校が購読した新聞のほとんどは山形新聞で、この事業は翌年度以降も続けられた。
吉村知事と山形新聞は「持ちつ持たれつ」の関係にある。2021年1月知事選の前年の秋、山形県は山形新聞に「コロナを克服し、大雨災害からの復旧に取り組む」との全面広告を何度か出した。
広告には吉村知事のポーズ写真とメッセージも添えられた。選挙の事前運動とも受け取られかねない内容で、「選挙前には現職知事の写真などを付した広告を掲載しない」との新聞の広告倫理に触れかねない内容だった。が、吉村知事は気にせず、気前良く税金を投じて広告を出した。
知事との関係にせよ、今回の無断転載の追及にせよ、これを仕切っているのは山形新聞の寒河江浩二(さがえ・ひろじ)社長である。編集局長を経て、2012年から社長をつとめ、主筆を兼ねる。75歳。細かい記事にまで口を出すことで知られ、今では社内で自由に意見を言える人はいないという。「山新のプーチン」と陰口をたたかれるゆえんである。
山形新聞は、民放テレビ局や観光会社、1T企業、広告会社をグループに抱える山形県のミニ財閥の中核企業だ。寒河江社長は山形県経営者協会の会長でもある。「政治は知事、経済は私」といった気分なのだろう。
なにせ、山形新聞にはかつて「山形県の政治も経済も牛耳った」という?前科?がある。服部敬雄(よしお)社長の全盛期には国会議員も知事も山形市長もひれ伏し、頭が上がらなかった。地元の人たちは「服部天皇」と呼んだ。
服部社長が1991年に亡くなり、山新グループの勢いはだいぶ衰えた。が、寒河江社長は在任が10年に及び、鼻息はいよいよ荒い。「第二の服部になりかねない」と懸念する声がある。
かつて、山新グループのトップには「天皇」という肩書が付けられた。今は「プーチン」と呼ばれる。昔も今も、面と向かって道理を説く人が周りにいない。県民の一人として切なく、情けない。
長岡 昇(元朝日新聞記者)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2022年11月15日
≪参考記事&サイト≫
◎無断転用を報じた山形新聞の記事(2022年7月8日付、10月21日付、11月2日付、11月8日付)
◎日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権」に関する見解
◎新聞著作権協議会の「新聞記事・写真の著作権と複製」に関する見解
◎小中学校での新聞購読に山形県が助成金を出すことを報じた山形新聞の記事(2017年3月16日付)
◎2021年1月の知事選の前に山形新聞に掲載された山形県の全面広告(2020年9月9日付、11月20日付)
◎「服部天皇」による山形県支配の内実を伝えるコラム(ウエブコラム情報屋台)
被差別部落とは何か。部落の人たちはなぜ厳しい差別にさらされ続けるのか。それを解明するためには事実を一つひとつ積み重ね、それを基にして考えていかなければならない。
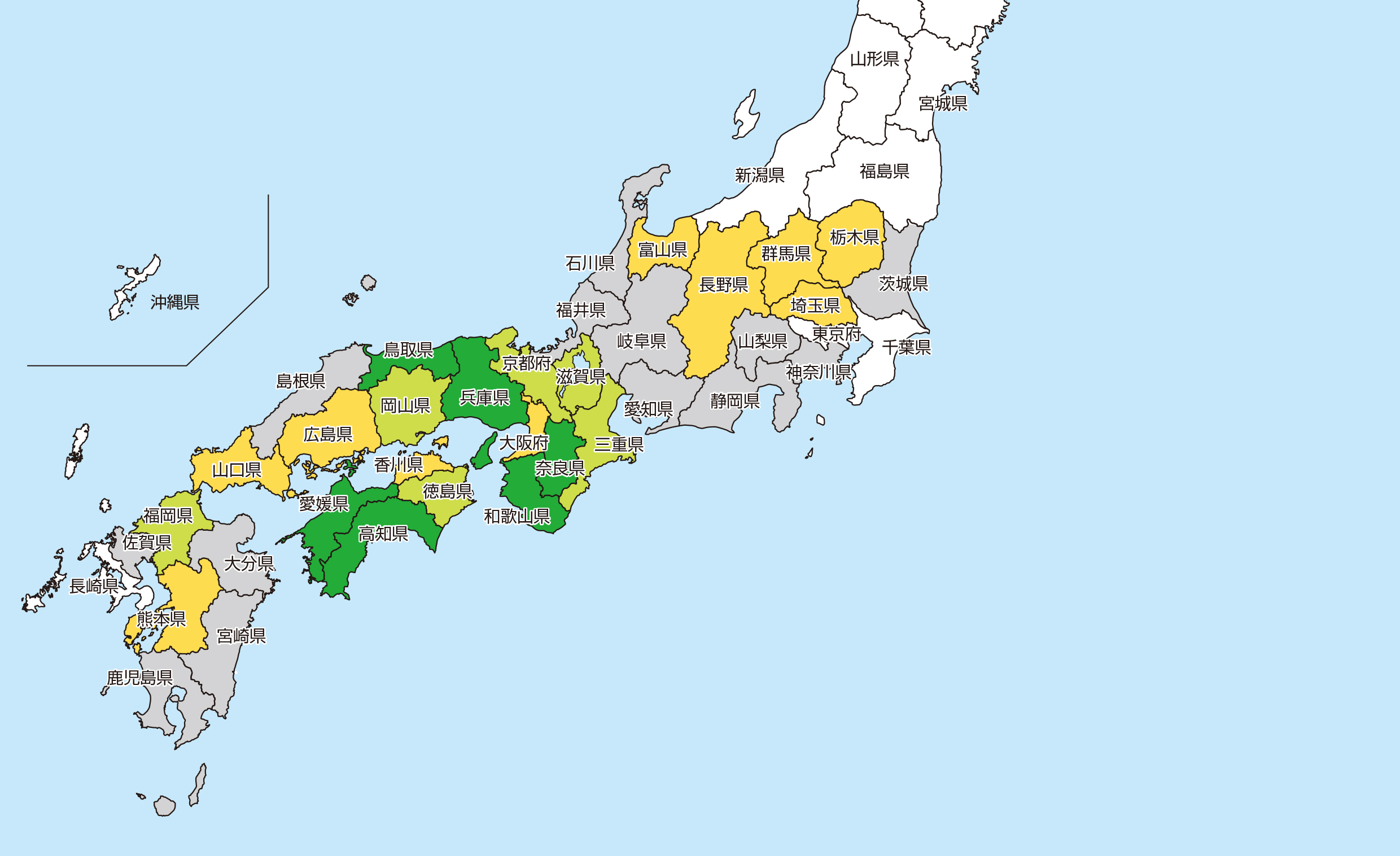
だが、部落問題に関しては、事実を積み重ねるというそのこと自体が難しい。被差別部落はどこにどのくらいあるのか。部落の人口はどのくらいか。そういう基礎的な事実すら曖昧模糊としている。
1993年の総務庁の調査によれば、全国には4,442の同和地区があり、その人口は約89万人となっている。これは、政府が被差別部落の生活向上と環境改善のために進めた同和対策事業の対象になった地区と人口の合計である。事業の対象にならなかった地区、あるいは対象となることを望まなかった地区は含まれていないので、被差別部落の人口はこれよりかなり多いと推定される。
部落解放同盟は「全国には6,000の被差別部落があり、300万の同胞がいる」という。これは、総務庁の調査結果をベースに同和対策事業の対象外の地区やその人口を推計して積み上げた概数と思われる。実態にかなり近いと考えられるが、疑問も残る。
というのは、被差別部落の解放を目指して全国水平社が設立された大正時代から、すでに「部落の数は6,000、人口は300万人」と唱えられていたからだ。こんなに長い間、部落の数も人口も変わらない、ということがあり得るだろうか。
もっと具体的で都道府県別の内訳も分かるような統計はないのか。そう思って資料を探したが、戦後のものは見当たらない。昭和10年の統計があるようだが、入手できていない。網羅的で信頼性の高い統計は、なんと大正時代まで遡らなければならなかった。
水平社運動の闘士、高橋貞樹が1924年(大正13年)に出版した『特殊部落一千年史』に、1921年(大正10年)の内務省統計が掲載されている。この統計によって、道府県別の部落の数と人口を知ることができる(高橋の著書は戦後、『被差別部落一千年史』と改題され、復刻出版された)。
図1は、この内務省統計を基に被差別部落の人口の多い道府県を五つに分類したものである(東京は当時、東京府)。1位から10位までの府県とその人口を記すと、次のようになる(11位以下は添付の資料参照)。
1.兵庫県 107,608人 2.福岡県 69,345人
3.大阪府 47,909人 4.愛媛県 46,015人
5.岡山県 42,895人 6.京都府 42,179人
7.広島県 40,133人 8.三重県 38,383人
9.和歌山県 36,072人 10.高知県 33,353人
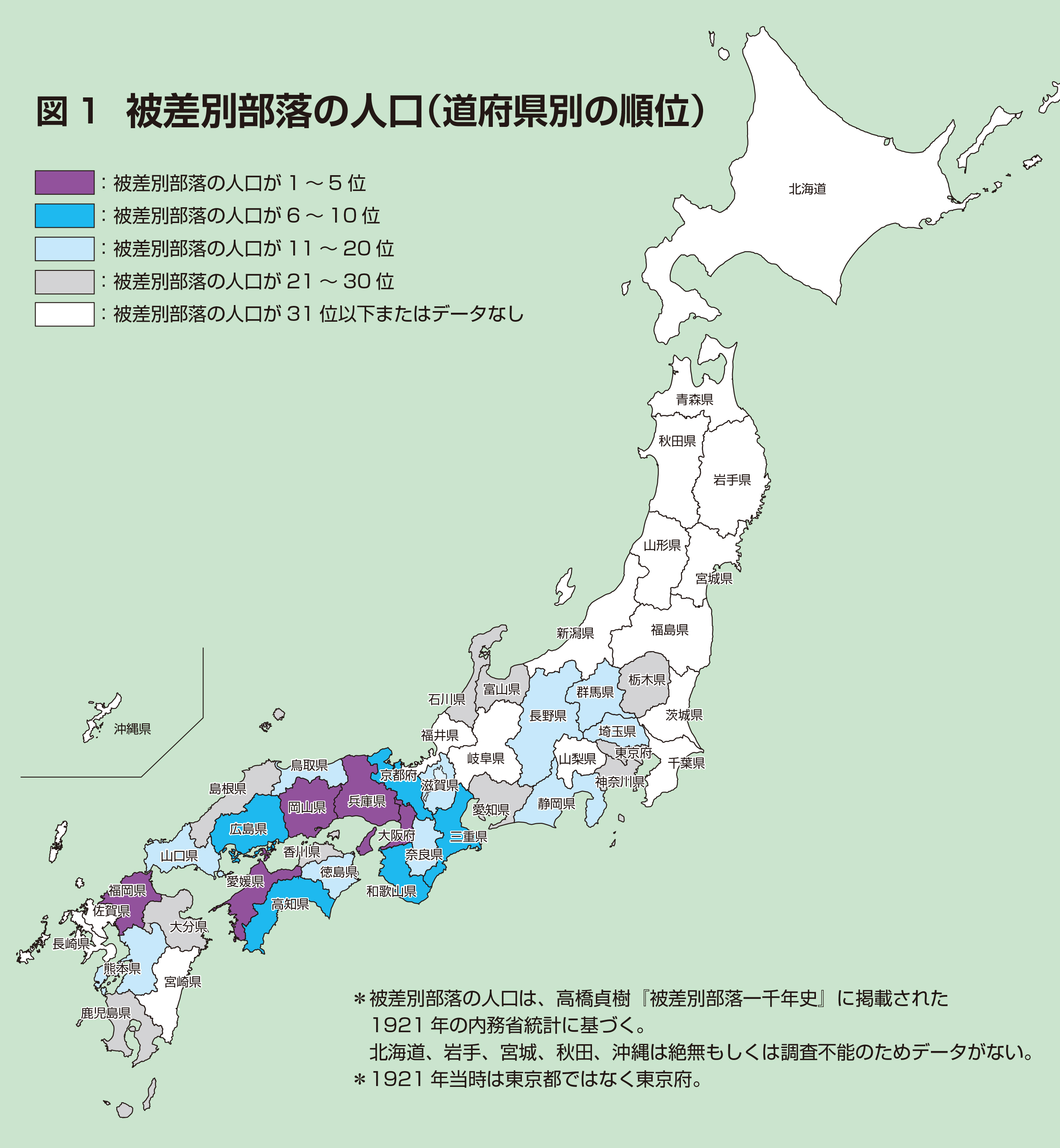
この分布図から読み取れるのは以下の3点である。(1)被差別部落は関西と中国・四国、九州北部に集中している(2)東日本では埼玉、群馬、長野、静岡、栃木にやや多いものの、全体として少ない(3)東北にはほとんどなく、北海道と沖縄にはない。
兵庫や福岡、大阪のように人口が多い府県では部落の人口も多くなる。従って、「被差別部落の人口密度」を見るためには「府県全体の人口との比率」を調べなければならない。この内務省統計の前年、大正9年には第1回の国勢調査が実施されており、この時の府県の人口を分母にすれば、部落の人口の百分率が得られる。
図2は、部落の人口比率を道府県別に5分類したものである。部落の人口比率が3%を超えるのは次の12府県だ(道府県すべての人口と比率は添付の資料を参照)。
1. 奈良県 5.79% 2.高知県 4.97%
3. 和歌山県 4.81% 4.兵庫県 4.67%
5. 愛媛県 4.40% 6.鳥取県 4.18%
7. 滋賀県 3.97% 8.三重県 3.59%
9・岡山県 3.52% 10.徳島県 3.33%
11.京都府 3.28% 12.福岡県 3.17%
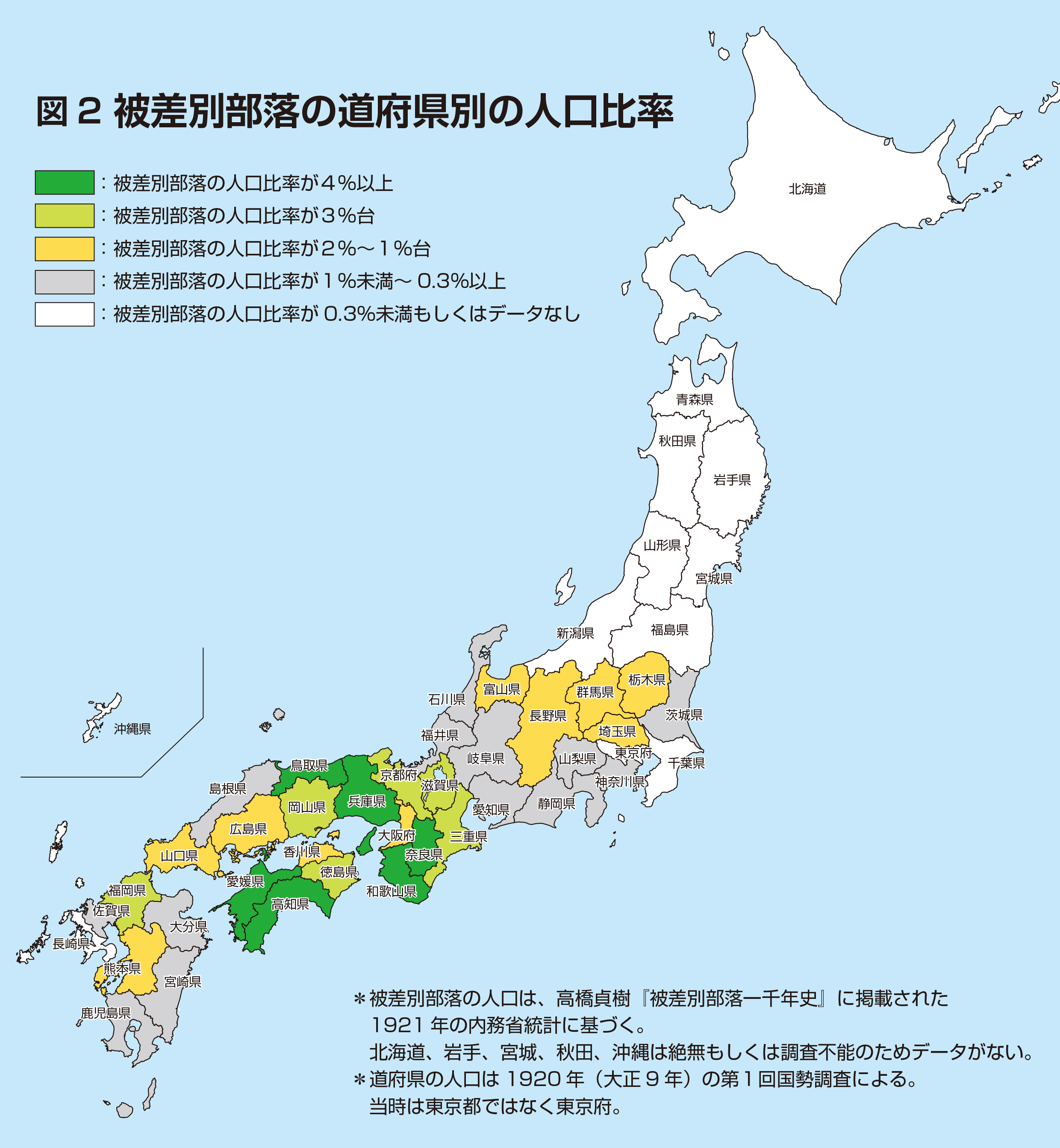
この人口比率のデータは、図1の人口分布で示された傾向をより鮮明な形で浮かび上がらせる。ここから読み取れるのは、(1)部落の人口の比率が最も高いのは奈良であり、比率の高い地域は畿内からほぼ同心円状に広がっている(2)北関東と埼玉、長野を除けば、東日本の人口比率は低い(3)とりわけ東京と千葉の比率は低く、東北はさらに低い、ということだ。奈良の被差別部落の人口比率は山形0.10%の58倍、青森0.02%の290倍になる。これらは何を意味するのだろうか。
被差別部落の起源については、戦後長い間、「部落は豊臣政権の時代から江戸時代にかけて、封建的な身分制度が固まる中で民衆を分断統治するために政治的につくられた」と唱えられてきた。いわゆる「被差別部落=近世政治起源説」である。
しかし、この二つの分布図を見れば、近世政治起源説に大きな疑問を抱かないではいられない。江戸幕府が置かれた東京とその隣の千葉に、なぜこれほど部落が少ないのか。豊臣政権や江戸幕府の支配が及んでいた東北にほとんど部落がないのはなぜか。近世政治起源説では、どちらも全く説明がつかない。
二つの分布図は、被差別部落の起源について、豊臣や徳川の武家政権より、むしろ畿内を拠点とした天皇制との関連が強いことを示唆している、と言えるのではないか。
部落の歴史についての研究が進み、中世の文献の掘り起こしが進むにつれて、近世政治起源説を唱える研究者は少なくなり、今では「部落の起源は中世あるいは古代と考えられる」という研究者が大勢を占めるようになった。部落と天皇制との関連にも、あらためて光が当てられるようになってきた。
けれども、部落問題の素人である私には「中世の文献などを調べるまでもなく、こうした人口や比率の地域的な偏りを見るだけでも、近世政治起源説がおかしいことは明白ではないか」と思える。なぜ、そのような説得力のない学説が生まれ、長い間、幅を利かせたのか。
そうした疑問を抱いて、被差別部落をめぐる研究や運動の経過をたどっていくと、イデオロギーに囚われた者たちが学問と文化をいかにゆがめ、政治や行政をどのように捻じ曲げていったのかが見えてくる。近世政治起源説の流布は「日本社会がずっと抱えてきた知的脆弱さの表れ」と言えるのではないか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」(2022年10月31日)
https://news-hunter.org/?p=14868
≪添付資料≫
◎被差別部落の道府県別の人口
◎被差別部落の道府県別の人口比率
≪参考文献≫
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社)
◎『はじめての部落問題』(角岡伸彦、文春新書)
◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)
◎『国勢調査以後 日本人口統計集成 第1巻』(内閣統計局、東洋書林)
◎『部落問題入門 部落差別解消推進法対応』(全国部落解放協議会、示現舎)
◎『天皇制と部落差別』(上杉聰、解放出版社)
◎『部落・差別の歴史』(藤沢靖介、解放出版社)
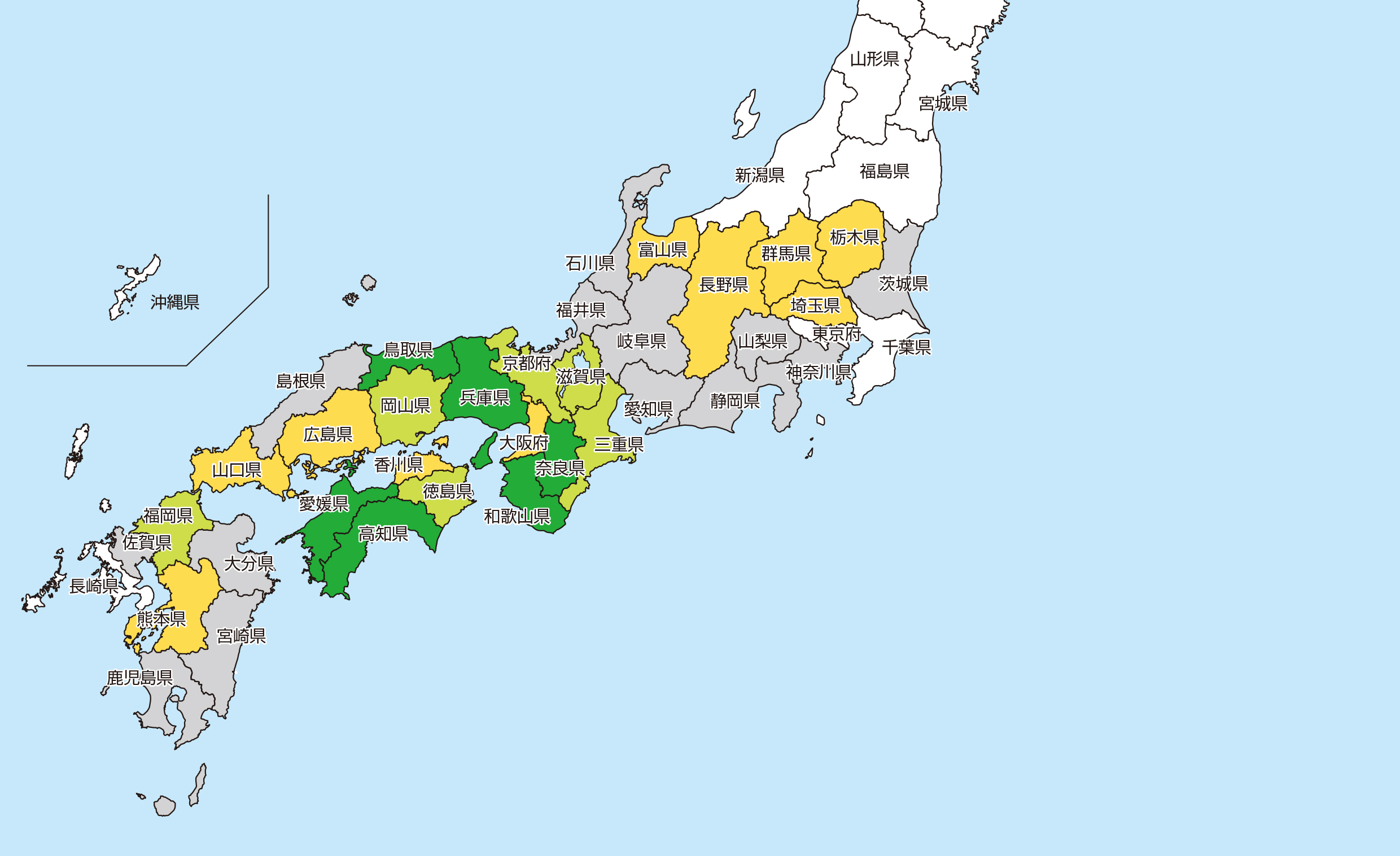
だが、部落問題に関しては、事実を積み重ねるというそのこと自体が難しい。被差別部落はどこにどのくらいあるのか。部落の人口はどのくらいか。そういう基礎的な事実すら曖昧模糊としている。
1993年の総務庁の調査によれば、全国には4,442の同和地区があり、その人口は約89万人となっている。これは、政府が被差別部落の生活向上と環境改善のために進めた同和対策事業の対象になった地区と人口の合計である。事業の対象にならなかった地区、あるいは対象となることを望まなかった地区は含まれていないので、被差別部落の人口はこれよりかなり多いと推定される。
部落解放同盟は「全国には6,000の被差別部落があり、300万の同胞がいる」という。これは、総務庁の調査結果をベースに同和対策事業の対象外の地区やその人口を推計して積み上げた概数と思われる。実態にかなり近いと考えられるが、疑問も残る。
というのは、被差別部落の解放を目指して全国水平社が設立された大正時代から、すでに「部落の数は6,000、人口は300万人」と唱えられていたからだ。こんなに長い間、部落の数も人口も変わらない、ということがあり得るだろうか。
もっと具体的で都道府県別の内訳も分かるような統計はないのか。そう思って資料を探したが、戦後のものは見当たらない。昭和10年の統計があるようだが、入手できていない。網羅的で信頼性の高い統計は、なんと大正時代まで遡らなければならなかった。
水平社運動の闘士、高橋貞樹が1924年(大正13年)に出版した『特殊部落一千年史』に、1921年(大正10年)の内務省統計が掲載されている。この統計によって、道府県別の部落の数と人口を知ることができる(高橋の著書は戦後、『被差別部落一千年史』と改題され、復刻出版された)。
図1は、この内務省統計を基に被差別部落の人口の多い道府県を五つに分類したものである(東京は当時、東京府)。1位から10位までの府県とその人口を記すと、次のようになる(11位以下は添付の資料参照)。
1.兵庫県 107,608人 2.福岡県 69,345人
3.大阪府 47,909人 4.愛媛県 46,015人
5.岡山県 42,895人 6.京都府 42,179人
7.広島県 40,133人 8.三重県 38,383人
9.和歌山県 36,072人 10.高知県 33,353人
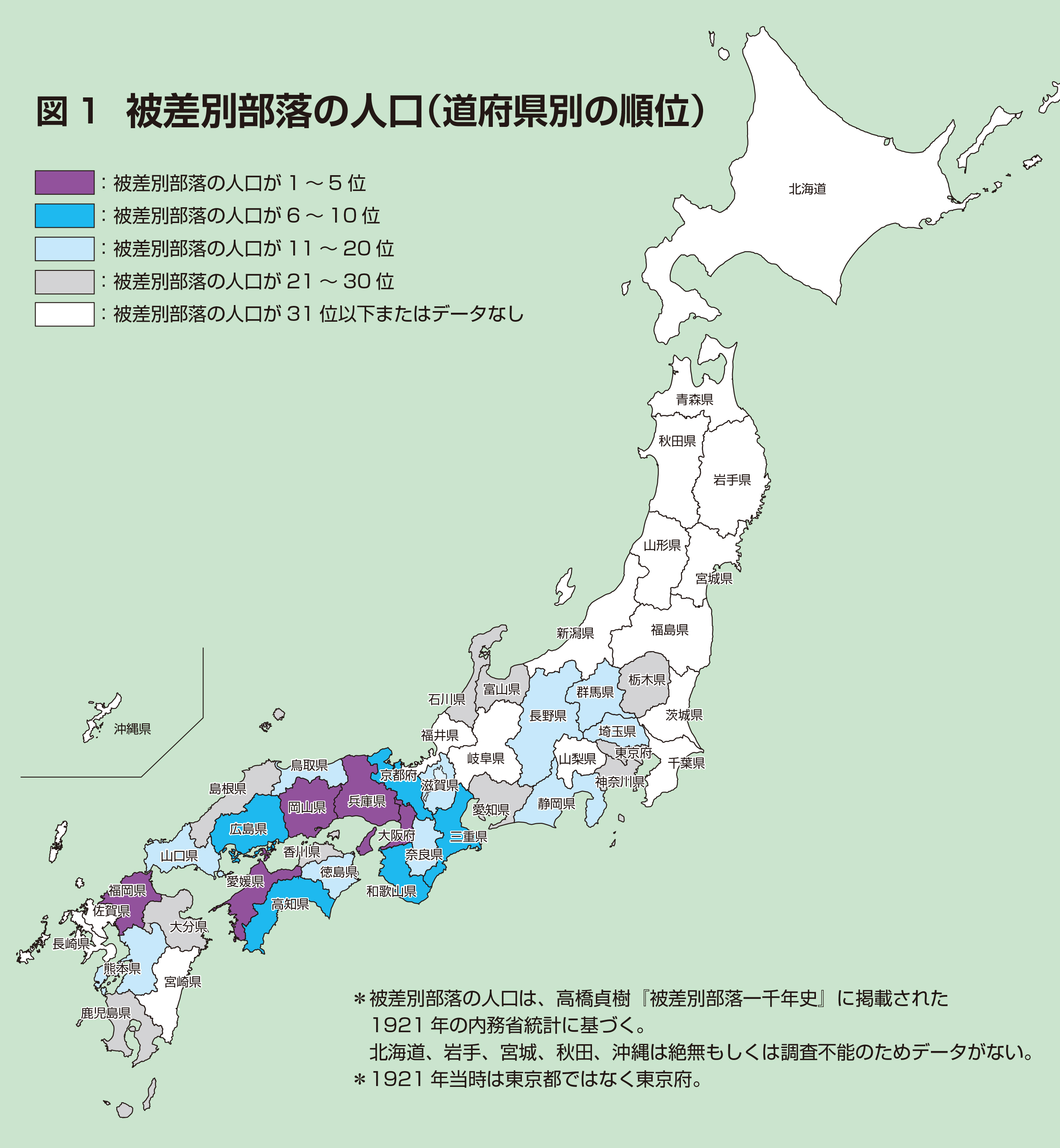
この分布図から読み取れるのは以下の3点である。(1)被差別部落は関西と中国・四国、九州北部に集中している(2)東日本では埼玉、群馬、長野、静岡、栃木にやや多いものの、全体として少ない(3)東北にはほとんどなく、北海道と沖縄にはない。
兵庫や福岡、大阪のように人口が多い府県では部落の人口も多くなる。従って、「被差別部落の人口密度」を見るためには「府県全体の人口との比率」を調べなければならない。この内務省統計の前年、大正9年には第1回の国勢調査が実施されており、この時の府県の人口を分母にすれば、部落の人口の百分率が得られる。
図2は、部落の人口比率を道府県別に5分類したものである。部落の人口比率が3%を超えるのは次の12府県だ(道府県すべての人口と比率は添付の資料を参照)。
1. 奈良県 5.79% 2.高知県 4.97%
3. 和歌山県 4.81% 4.兵庫県 4.67%
5. 愛媛県 4.40% 6.鳥取県 4.18%
7. 滋賀県 3.97% 8.三重県 3.59%
9・岡山県 3.52% 10.徳島県 3.33%
11.京都府 3.28% 12.福岡県 3.17%
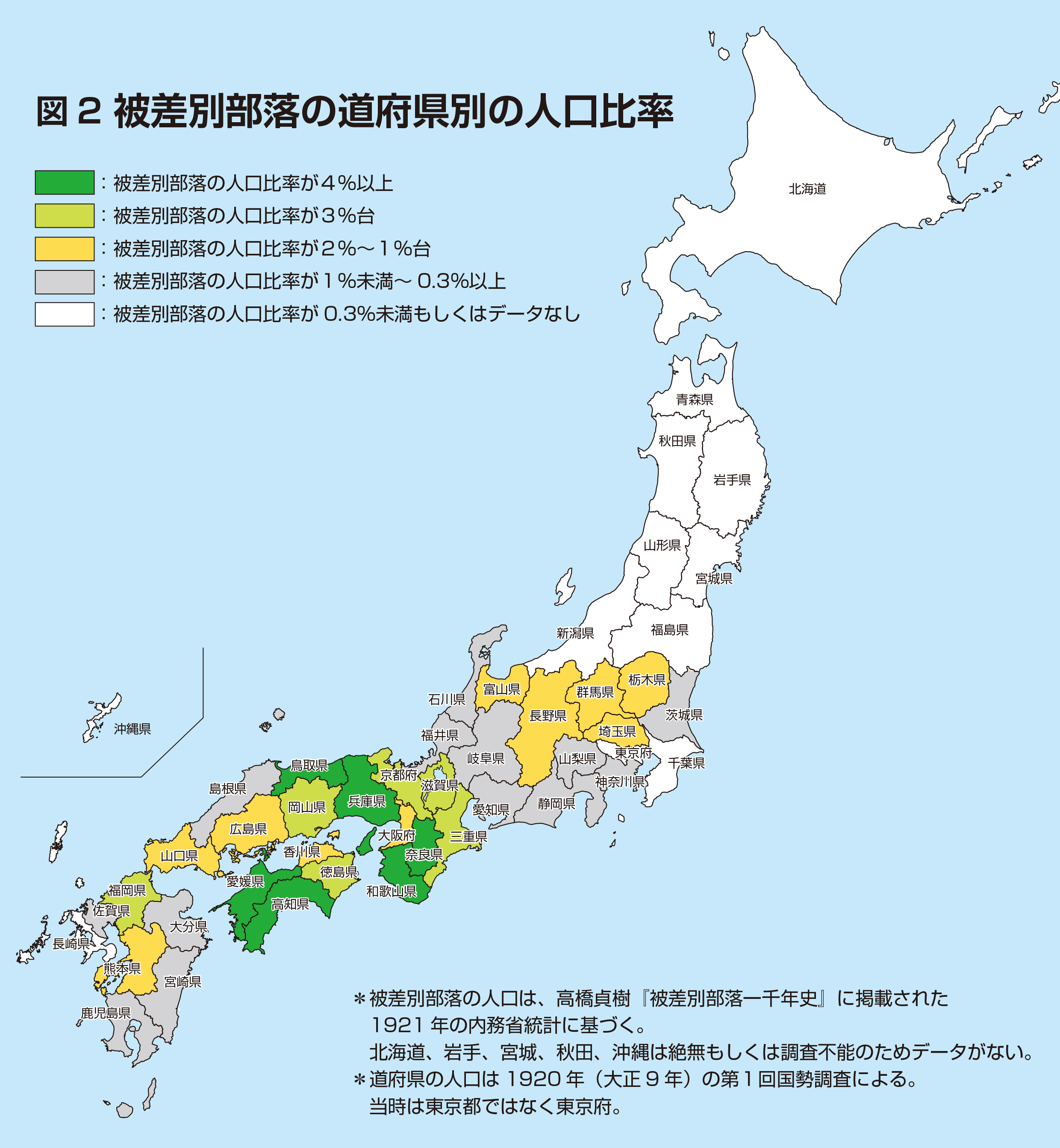
この人口比率のデータは、図1の人口分布で示された傾向をより鮮明な形で浮かび上がらせる。ここから読み取れるのは、(1)部落の人口の比率が最も高いのは奈良であり、比率の高い地域は畿内からほぼ同心円状に広がっている(2)北関東と埼玉、長野を除けば、東日本の人口比率は低い(3)とりわけ東京と千葉の比率は低く、東北はさらに低い、ということだ。奈良の被差別部落の人口比率は山形0.10%の58倍、青森0.02%の290倍になる。これらは何を意味するのだろうか。
被差別部落の起源については、戦後長い間、「部落は豊臣政権の時代から江戸時代にかけて、封建的な身分制度が固まる中で民衆を分断統治するために政治的につくられた」と唱えられてきた。いわゆる「被差別部落=近世政治起源説」である。
しかし、この二つの分布図を見れば、近世政治起源説に大きな疑問を抱かないではいられない。江戸幕府が置かれた東京とその隣の千葉に、なぜこれほど部落が少ないのか。豊臣政権や江戸幕府の支配が及んでいた東北にほとんど部落がないのはなぜか。近世政治起源説では、どちらも全く説明がつかない。
二つの分布図は、被差別部落の起源について、豊臣や徳川の武家政権より、むしろ畿内を拠点とした天皇制との関連が強いことを示唆している、と言えるのではないか。
部落の歴史についての研究が進み、中世の文献の掘り起こしが進むにつれて、近世政治起源説を唱える研究者は少なくなり、今では「部落の起源は中世あるいは古代と考えられる」という研究者が大勢を占めるようになった。部落と天皇制との関連にも、あらためて光が当てられるようになってきた。
けれども、部落問題の素人である私には「中世の文献などを調べるまでもなく、こうした人口や比率の地域的な偏りを見るだけでも、近世政治起源説がおかしいことは明白ではないか」と思える。なぜ、そのような説得力のない学説が生まれ、長い間、幅を利かせたのか。
そうした疑問を抱いて、被差別部落をめぐる研究や運動の経過をたどっていくと、イデオロギーに囚われた者たちが学問と文化をいかにゆがめ、政治や行政をどのように捻じ曲げていったのかが見えてくる。近世政治起源説の流布は「日本社会がずっと抱えてきた知的脆弱さの表れ」と言えるのではないか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」(2022年10月31日)
https://news-hunter.org/?p=14868
≪添付資料≫
◎被差別部落の道府県別の人口
◎被差別部落の道府県別の人口比率
≪参考文献≫
◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社)
◎『はじめての部落問題』(角岡伸彦、文春新書)
◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)
◎『国勢調査以後 日本人口統計集成 第1巻』(内閣統計局、東洋書林)
◎『部落問題入門 部落差別解消推進法対応』(全国部落解放協議会、示現舎)
◎『天皇制と部落差別』(上杉聰、解放出版社)
◎『部落・差別の歴史』(藤沢靖介、解放出版社)

2022年の第10回カヌー探訪は、7月30日(土)に最上川の中流域にある五百川(いもがわ)峡谷(朝日町―大江町)の急流を下り、翌31日(日)は長井ダム湖の三淵(みふち)渓谷を静かにめぐりました。参加者は45人。30日が37人、31日が21人でした。今年から、カヌーイストや朝日ナチュラリストクラブの子どもたちと一緒に最上川の河畔の清掃活動にも取り組み始めました。ご協力いただいたすべての皆様に深く感謝いたします。 (記録・長岡昇、写真撮影・長岡典己)



≪出発&到着時刻≫
◎2022年7月30日(土) 参加:37人、34艇
午前7時 山形県朝日町の雪谷(ゆきたに)カヌー公園で
カヌーイストと「ブナの森」のスタッフが清掃活動
9時20分 カヌーイストが雪谷カヌー公園から出発


10時30分 朝日ナチュラリストクラブの子どもたちや
保護者と一緒に最上川の激流「タンの瀬」
(朝日町栗木沢)で清掃活動
11時20分 カヌーイストが「タンの瀬」に到着。ナチュラリスト
クラブの子どもたちとラフティングを楽しむ



◎「タンの瀬」でラフティングを楽しむ朝日ナチュラリストクラブの子どもたち(動画撮影・結城敏宏)
午後1時30分 「タンの瀬」を出発
3時30分 大江町のゴール「おしんの筏下りロケ地」に到着


◎7月31日(日) 参加:21人、15艇
午前7時40分 長井ダム湖面広場から出発
8時20分 三淵渓谷の入り口に到着
9時 三淵渓谷の入り口に戻る
9時30分 長井ダム湖面広場に戻る


◎長井ダム湖・三淵渓谷へのツーリング(動画撮影・佐藤周平)
≪参加者≫ *エントリー順
◎7月30日、五百川峡谷 37人(34艇)
岸浩(福島市)、柳沼美由紀(福島県泉崎村)、柳沼幸男(同)、佐竹久(山形県大江町)、黒田美喜男(東根市)、寒河江洋光(盛岡市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、清水孝治(同県厚木市)、安部幸男(宮城県柴田町)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、崔鍾八(山形県朝日町)、結城敏宏(米沢市)、小田原紫朗(酒田市)、林和明(東京都足立区)、阿部俊裕(天童市)、阿部明美(同)、中沢崇(長野市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、七海孝(福島県鏡石町)、管慎太郎(岩手県北上市)、高橋洋(米沢市)、牧野格(南陽市)、矢萩剛(村山市)、柴田尚宏(山形市)、川添裕介(北上市)、川添裕加(同)、浅野智久(東根市)、阿部悠子(東京都八王子市)、内藤フィリップ邦夫(天童市)、石井拓海(山形県河北町)、馬場先詩織(東根市)、柳瀬真人(秋田県由利本荘市)、渡邉貴博(同)、菊地大二郎(山形市)、菊地恵里(同)、古家優(酒田市)
*最年少は、岩手県北上市の川添裕加(ゆうか)さん(11歳)。父親の川添裕介さんとカナディアンで参加。

◎7月31日 三淵渓谷 21人(15艇)
岸浩、柳沼美由紀、柳沼幸男、佐竹久、寒河江洋光、安部幸男、池田信一郎、吉田志乃(仙台市)、吉田英世(同)、吉田蓮(同)、真鍋賢一、佐藤周平(山形市)、崔鍾八、清野礼子(仙台市)、結城敏宏、里見優(山形市)、里見由利(同)、中沢崇、斉藤栄司(尾花沢市)、黒澤里司、管慎太郎
*最年少は、仙台市の吉田蓮君(3歳)。吉田志乃、吉田英世夫妻とカナディアンで参加。この記録はなかなか超えられないでしょう。

≪参加者の地域別内訳≫
▽山形県内 22人(山形市6人、天童市3人、東根市3人、米沢市2人、酒田市2人、村山市、尾花沢市、南陽市、大江町、朝日町、河北町各1人)
▽山形県外 23人(宮城県5人、福島県4人、岩手県4人、秋田県2人、東京都2人、神奈川県2人、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県各1人)

≪第1回ー第10回の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人
第10回(2022年)45人

≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪協力≫ 朝日ナチュラリストクラブ(最上川・タンの瀬での清掃活動)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省最上川ダム統合管理事務所、山形県、
朝日町、大江町、長井市
≪第10回カヌー探訪の参加記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 白田金之助▽長岡典己▽長岡昇▽長岡佳子
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪受付設営・交通案内設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助
≪写真撮影・動画の撮影と編集≫ 長岡典己(7月30日の五百川峡谷の写真) ▽結城敏宏(7月30日の「タンの瀬」ラフティングの動画、7月31日の三淵渓谷の写真)▽佐藤周平(7月31日の三淵渓谷ツーリングの動画)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪仕出し弁当≫ 伊藤惣菜(山形県朝日町)
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
ヴェネツィアの商人、マルコ・ポーロが父親と叔父に伴われて東方へと旅立ったのは1271年とされる。生きて帰れるかどうかも定かではない、危険な旅だった。

父親と叔父にとっては2度目、17歳のマルコにとっては初めての長旅である。一行はペルシャから中央アジアのシルクロードを通り、陸路、3年半かけてモンゴル帝国の夏の都、上都(現在の河北省張家口近郊)にたどり着いた。
時の皇帝クビライは、一行の到着をことのほか喜んだ。父親と叔父は最初の旅の際に命じられた通り、ローマ教皇の書簡とキリスト教の聖油を携えていた。書簡はローマへの使節派遣を促す好意的なものだった。息子のマルコの聡明さにも惹きつけられたようだ。3人はクビライの家臣として迎えられ、厚く遇される。
若いマルコはモンゴル語や中国語を習得し、皇帝の使者としてしばしば、帝国内に派遣された。クビライはマルコの報告を好んだという。任務の報告が的確だっただけでなく、「その土地の珍しい事柄や不思議な話を巧みに語ったから」とされる。
クビライはマルコを寵愛し、一行が帰国することをなかなか許さなかったが、モンゴルの姫をイル・ハン国(ペルシャとその周辺が版図)に嫁がせる使節団に加わることを渋々認めた。3人が船団に加わり、海路、インド洋経由で帰国したのは1295年、実に24年後のことだった。
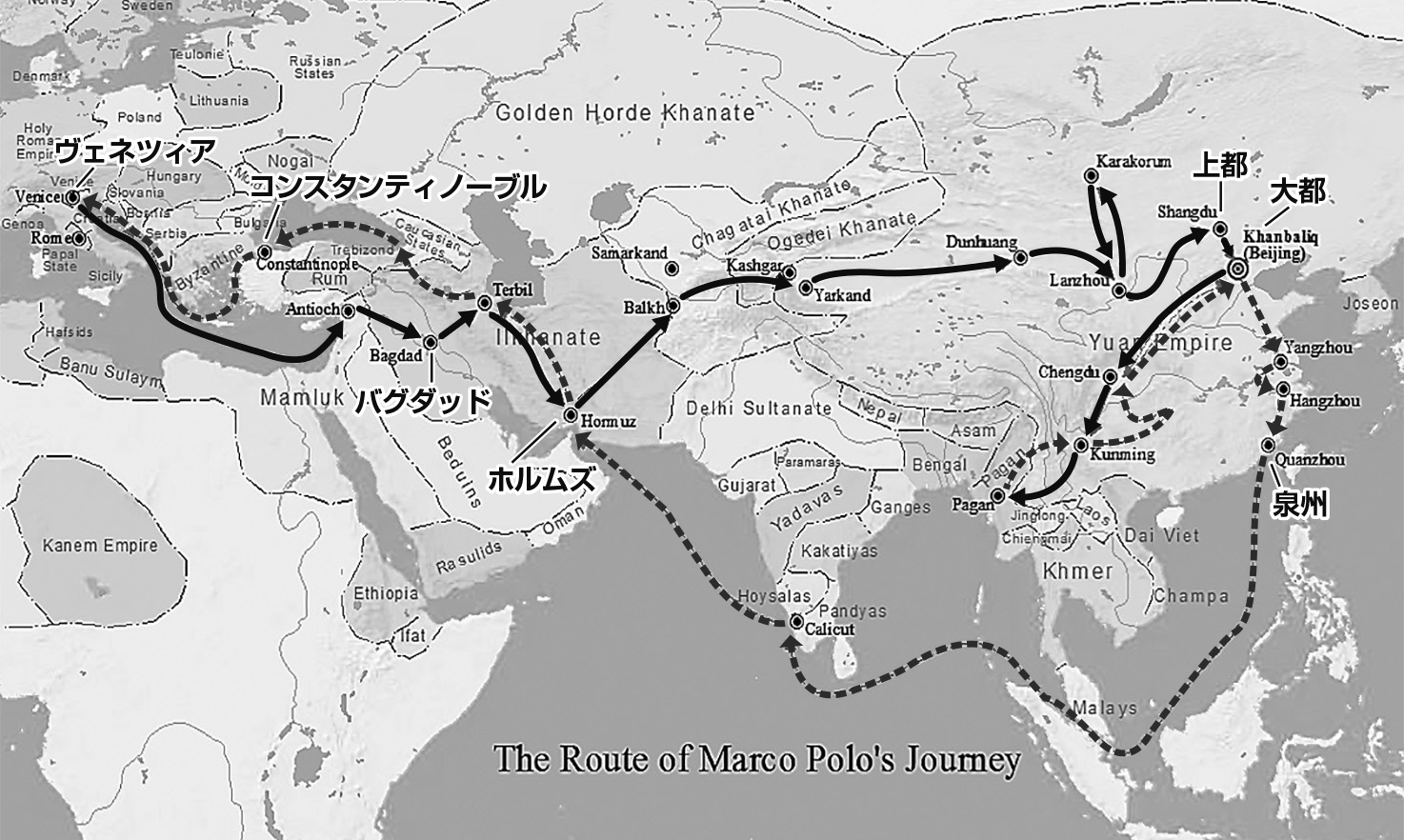
帰国してほどなく、マルコはヴェネツィアとジェノヴァの戦争に巻き込まれ、ジェノヴァの捕虜になった。獄中で、同じように捕虜になった物語作家のルスティケッロと出会う。そこで彼がマルコから聞いた長い旅の物語をまとめたものが『世界の記述』、あるいは『驚異の書』『マルコ・ポーロ旅行記』などと名付けられ、世に知られるに至った。
マルコの旅行記はフランス語やラテン語に次々に翻訳され、写本として広まった。原本は失われ、多種多様な写本が残る。日本では明治時代に『東方見聞録』の書名で紹介され、その呼び方が定着した。
マルコは日本を訪れたことはなかったが、その書には次のような伝聞が記されている。
「ジパングは東方の島で、沿岸から1500マイル離れている。とても大きな島で、人々は色白く美しく礼儀正しい。偶像を崇(あが)め、自分たちの王に統治されている」
「金がものすごく大量にあり、そこに桁外れに見つかり、王が国外に持ち出させない。(中略)ちょうど我々が家あるいは教会を鉛で葺(ふ)くように、すべて金の板で葺かれた大宮殿がある。広間や多くの部屋の天井もすべて分厚い純金の板で、窓もやはり金で飾られている」(高田英樹『世界の記』から引用、イタリア語集成本からの和訳)
ヨーロッパの人々はマルコの書で初めてシルクロードやモンゴル帝国、アジアの国々のことを知り、興奮した。とりわけ、黄金の国ジパングの物語に熱狂した。
時を経て、その熱はジェノヴァ生まれの探検家コロンブスをも巻き込む。コロンブスはスペイン王の支援を得て西回りでジパングを目指し、大西洋のかなたで「未知の大陸」に到達した。
マルコが世に広めた「黄金の国伝説」は、コロンブスを突き動かしてアメリカ大陸へと導き、歴史の歯車を大きく回す結果をもたらしたのである。
◇ ◇
では、その黄金の国伝説はどのようにして生まれたのか。話は、マルコが旅した時代からさらに500年以上さかのぼる。
天平年間(729?749年)、聖武(しょうむ)天皇は藤原一族がらみの激しい政争に加え、天然痘の大流行や旱魃と飢饉、大地震に襲われ、苦しんでいた。天皇は仏教に深く帰依し、仏教にすがって世を立て直そうと試みた。
国家鎮護のため全国に国分寺を建立する詔(みことのり)を出したのに続いて、743年(天平15年)には大仏造立(ぞうりゅう)を宣言した。奈良東大寺の大仏様である。
「私は天皇の位に就いて民を慈しんできたが、仏の恩徳はいまだ天下に行き渡っていない。三宝(仏、法、僧)の力によって天下が安らかになり、生きとし生けるものすべてが栄えることを望む」(『続日本紀』所収の詔、現代語訳は筆者)
詔には、聖武天皇の切なる思いがにじむ。「一本の草、一握りの土でも協力したいという者がいれば、それを許しなさい」との一文を付け加えている。
高さ16メートルもの大仏を造る大事業である。まず木材と土で原型を造り、さらに外型を造って間に溶銅を流し込んで鋳造する。一気にはできないので、下部から順々に鋳造していったと考えられている。
原料の銅や錫は国内にたくさんあった。だが、問題は金だった。銅による鋳造の後、大仏には鍍金(ときん)を施して金ピカにする計画だが、国内の産金はごくわずかで、中国や朝鮮半島から輸入するしかない。当然のことながら、「莫大な代価を払わなければならない」と覚悟していた。

その時である。749年(天平21年)、陸奥(むつ)の国から「大量の砂金が見つかった」との報告が寄せられ、都に黄金900両(13キロ)が届けられた。
聖武天皇の喜びようは尋常ではなかった。「願いが天に届いた」と思ったのではないか。天皇はその年のうちに元号を「天平感宝」と改め、出家して退位してしまった。
武人で歌人でもあった大伴家持は当時、越中の国守だったが、陸奥の産金を知り、産金をことほぐ長歌と次のような反歌を詠んだ。
天皇(すめろき)の 御代栄えむと 東(あづま)なる
陸奥(みちのく)山に 金(くがね)花咲く
万葉集に収められた歌の中で「最北の地を詠んだ歌」とされる。
大仏の開眼供養が営まれたのは752年(天平勝宝4年)である。大仏造立の詔から9年。その後も陸奥からは砂金が次々に届けられ、鍍金と仕上げ作業が続けられた。
日本の元号が漢字4文字で表されたのは、この時期の5代しかない。うち3代に「黄金」を意味する「宝」が使われた。朝廷の喜びがいかに大きかったかを示している。
陸奥で砂金が見つかった時の国守は、百済王(くだらのこにきし)敬福である。その名が示すように朝鮮半島の百済から渡来した王族の末裔で、陸奥に赴任する際に同行した部下にも渡来系の人たちがいたことが知られている。
砂金の発見と採取には特殊なノウハウと技術が求められる。大和朝廷の支配下にはもともとそうした人材はおらず、渡来系の人たちに頼るしかなかったのだろう。
砂金貢納の功績により、百済王敬福は従五位上から7階級特進し、その部下たちも褒賞にあずかった。朝廷にとっては「金の輸入国から輸出国に転じるきっかけを作ってくれた人たち」であった。
これ以降、陸奥では砂金や金鉱脈が相次いで発見される。大陸に渡る使者や僧侶には渡航費用に充てるため、砂金を持たせるようになっていった。
黄金を基盤にして、平泉の藤原一族は栄華を極めた。中尊寺金色堂はその象徴であり、扉も壁も天井も金箔で飾られた。マルコが記した「黄金の国ジパング伝説」はこうしたことを反映したものであり、多少の誇張はあったにせよ、伝説ではなく、事実であった。
◇ ◇
大仏造立時に大量の砂金が見つかったのは、宮城県北東部の涌谷(わくや)町である。砂金の採取地は、町の中心部の北に広がる箟岳(ののだけ)丘陵の沢筋にある。夏の渇水期には水がわずかに流れるだけの小さな沢だ。
周辺で金の鉱脈は見つかっていない。金をわずかに含む地層が隆起して浸食され、その砂金が大雨の時に押し流され、長い年月のうちに堆積したものと考えられている。
砂金が採取された場所には神社と寺が建てられた。聖武天皇は「仏が恵んでくれた金」という宣明と「天地の神々が祝福してくれた金」という宣明を同じ日に出しており、それに基づいて建立されたものだろう。「日本の神仏混淆(こんこう)はここに始まる」との見方もある。
だが、砂金が採れなくなると、神社も寺も忘れ去られた。どこの国でも、金が採れなくなった地域は「ゴーストタウン」と化す運命にある。
いつしか、「天平時代に砂金が採れたのは牡鹿半島沖の金華山」という俗説が流布し、そう信じられるようになっていった。松尾芭蕉も「奥の細道」の旅日誌に、大伴家持が「陸奥山に金花咲く」とうたったのは金華山、と記している。
こうした俗説に異を唱え、『続日本紀』などの史書を丹念に調べて是正したのは、江戸時代後期の伊勢の国学者、沖安海(おき・やすみ)である。
沖は当時の涌谷村の砂金採取地の様子を次のように記している。
「社(やしろ)があると聞いて訪ねたが、松や竹が生い茂り、道もなく荒れ果てていた。地元の人に問うたが、誰も知らない」
それでも、沖はやぶの中から大きな礎石と瓦の破片を見つけた。ここに社があったことを確信し、自ら資金を調達して黄金山神社を再建した。黄金の国伝説の起点となった場所は、一人の国学者によって息を吹き返し、歴史の表舞台に戻ってきたのである。

これ以降、地元の人たちはまた神社を大切にするようになった。昭和から平成にかけて、竹下政権は地域おこしのために市町村に1億円を交付する「ふるさと創生事業」を始めた。
涌谷町は、この事業を足がかりにして黄金山神社の周辺を整備し、神社の入り口に「天平ろまん館」というテーマ館を建てて地域おこしに取り組み始めた。展示資料が充実している。砂金採取の体験もできる施設で人気を集めた。
2019年には、涌谷町や平泉町を含む地域が「黄金の国ジパング 産金はじまりの地」として、文化庁に「日本遺産」に認定された。これで地域おこしに弾みがつくはずだった。
だが、コロナ禍の影響を大きく受け、集客に苦心しているのが実情だ。今はポスト・コロナを見据え、戦略を練り直す時だろう。
シルクロードにあこがれ、大航海時代の冒険に胸躍らせる人は世界中にたくさんいる。マルコ・ポーロとコロンブスにも登場してもらい、海外からもっと人を招き寄せる方策を探ってはどうか。「黄金をめぐる世界のネットワーク」の拠点を目指す道もある。ここは、知恵の絞りどころだろう。
◇ ◇
古代東北の蝦夷(えみし)と畿内の朝廷勢力との関係で考えると、涌谷での砂金の発見は「朝廷が蝦夷討伐に本腰を入れる要因の一つになったのではないか」との推測を生む。
8世紀の前半、東北の情勢は比較的落ち着いていた。朝廷の支配は現在の宮城県の北部まで、それ以北の岩手県や青森県の大部分は蝦夷の勢力圏、という構図で推移していた。
ところが、涌谷で砂金が発見された後、朝廷は桃生(ものう)城の建設(758年)と伊治(これはり)城の建設(767年)に踏み切った。涌谷の砂金採取地は桃生城の近くである。「陸奥にはもっと黄金があるに違いない」と見て、支配を北へ押し広げることを決意したのではないか。
実際、蝦夷と朝廷との「38年戦争」は、蝦夷側による桃生城と伊治城の襲撃から始まり、岩手県の胆沢(いさわ)を拠点とするアテルイ(阿弖流為)らの蝦夷勢力との激突、という形で展開していった。
大陸や朝鮮半島との交易において、黄金は何よりも有力な品となる。その確保は、朝廷にとって最優先課題となった可能性がある(佐渡島で金の採掘が本格化するのは江戸時代以降)。
砂金はしばしば、砂鉄と共に採取される。「朝廷は、砂金に加えて鉄などの鉱物資源の確保を目指したのではないか」という見方もある。これは、「蝦夷の刀」とされる蕨手(わらびて)刀の鍛造や伝播とも関わってくる。
古代の東北をめぐっては、解明されなければならない課題がまだ山のようにある。私たちの探求の旅は始まったばかり、と言えるのではないか。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真と図の説明&Source≫
◎マルコ・ポーロの肖像画
https://www.biography.com/explorer/marco-polo
◎マルコ・ポーロの行路
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Route_of_Marco_Polo.png
◎奈良東大寺の大仏。戦火で2度焼損し、再建された
https://seikyokudo.jp/?pid=151001936
◎宮城県涌谷町の黄金山神社(筆者撮影)
≪参考文献≫
◎『マルコ・ポーロ ルスティケッロ・ダ・ピーサ 世界の記 「東方見聞録」対校訳』(高田英樹、名古屋大学出版会)
◎『東方見聞録』(マルコ・ポーロ、愛宕<おたぎ>松男訳、平凡社・東洋文庫)
◎『奈良の大仏 世界最大の鋳造仏』(香取忠彦、イラスト・穂積和夫、草思社)
◎『東大寺大仏の研究 解説篇』(前田泰次、松山鐵夫、平川晋吾、西大由、戸津圭之介、岩波書店)
◎『日本の金』(彌永<やなが>芳子、東海大学出版会)
◎『天平産金物語』(宮城県涌谷町教育委員会)
◎『天平の産金地、宮城県箟岳(ののだけ)丘陵の砂金と地質の研究史』(鈴木舜一、地質学雑誌第116巻第6号)
◎『陸奥産金と家持』(福山宗志、『官人(つかさびと) 大伴家持』所収)
◎『日本鉱山史の研究』(小葉田<こばた>淳、岩波書店)
*注: マルコ・ポーロが訪れた当時のモンゴル帝国の皇帝について、中学や高校の教科書の多くは「フビライ」と表記していますが、研究者の間では「クビライ」と表記することが多いようです。アルファベットでは「KHUBILAI」と表記されます。「KH」は、ペルシャ語を含む中央アジア諸言語で喉の奥を使って発する音を表記する際の綴りで、「ク」と「フ」の中間のような音です。私もどちらかと言えば「ク」の方が適切と考えます。

父親と叔父にとっては2度目、17歳のマルコにとっては初めての長旅である。一行はペルシャから中央アジアのシルクロードを通り、陸路、3年半かけてモンゴル帝国の夏の都、上都(現在の河北省張家口近郊)にたどり着いた。
時の皇帝クビライは、一行の到着をことのほか喜んだ。父親と叔父は最初の旅の際に命じられた通り、ローマ教皇の書簡とキリスト教の聖油を携えていた。書簡はローマへの使節派遣を促す好意的なものだった。息子のマルコの聡明さにも惹きつけられたようだ。3人はクビライの家臣として迎えられ、厚く遇される。
若いマルコはモンゴル語や中国語を習得し、皇帝の使者としてしばしば、帝国内に派遣された。クビライはマルコの報告を好んだという。任務の報告が的確だっただけでなく、「その土地の珍しい事柄や不思議な話を巧みに語ったから」とされる。
クビライはマルコを寵愛し、一行が帰国することをなかなか許さなかったが、モンゴルの姫をイル・ハン国(ペルシャとその周辺が版図)に嫁がせる使節団に加わることを渋々認めた。3人が船団に加わり、海路、インド洋経由で帰国したのは1295年、実に24年後のことだった。
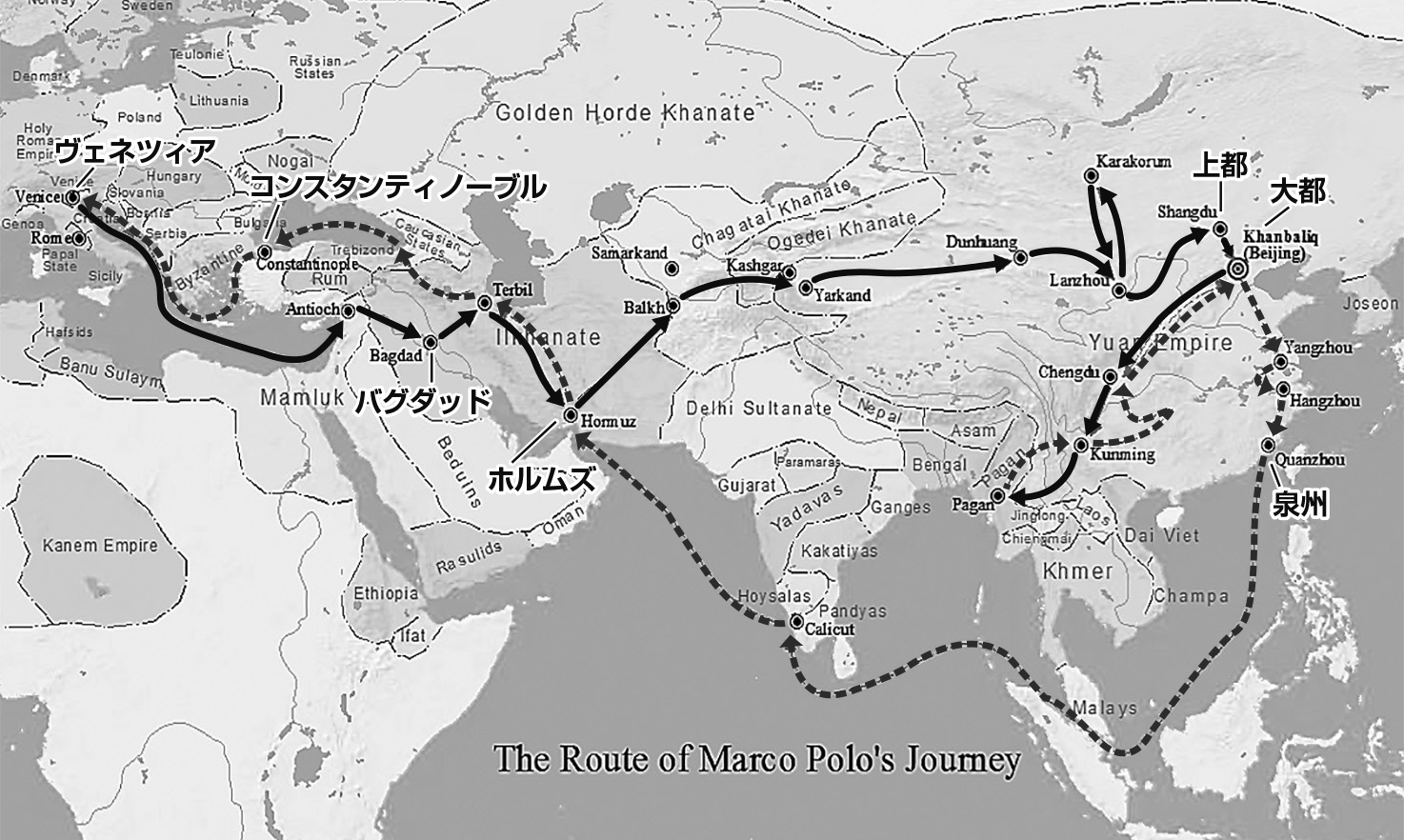
帰国してほどなく、マルコはヴェネツィアとジェノヴァの戦争に巻き込まれ、ジェノヴァの捕虜になった。獄中で、同じように捕虜になった物語作家のルスティケッロと出会う。そこで彼がマルコから聞いた長い旅の物語をまとめたものが『世界の記述』、あるいは『驚異の書』『マルコ・ポーロ旅行記』などと名付けられ、世に知られるに至った。
マルコの旅行記はフランス語やラテン語に次々に翻訳され、写本として広まった。原本は失われ、多種多様な写本が残る。日本では明治時代に『東方見聞録』の書名で紹介され、その呼び方が定着した。
マルコは日本を訪れたことはなかったが、その書には次のような伝聞が記されている。
「ジパングは東方の島で、沿岸から1500マイル離れている。とても大きな島で、人々は色白く美しく礼儀正しい。偶像を崇(あが)め、自分たちの王に統治されている」
「金がものすごく大量にあり、そこに桁外れに見つかり、王が国外に持ち出させない。(中略)ちょうど我々が家あるいは教会を鉛で葺(ふ)くように、すべて金の板で葺かれた大宮殿がある。広間や多くの部屋の天井もすべて分厚い純金の板で、窓もやはり金で飾られている」(高田英樹『世界の記』から引用、イタリア語集成本からの和訳)
ヨーロッパの人々はマルコの書で初めてシルクロードやモンゴル帝国、アジアの国々のことを知り、興奮した。とりわけ、黄金の国ジパングの物語に熱狂した。
時を経て、その熱はジェノヴァ生まれの探検家コロンブスをも巻き込む。コロンブスはスペイン王の支援を得て西回りでジパングを目指し、大西洋のかなたで「未知の大陸」に到達した。
マルコが世に広めた「黄金の国伝説」は、コロンブスを突き動かしてアメリカ大陸へと導き、歴史の歯車を大きく回す結果をもたらしたのである。
◇ ◇
では、その黄金の国伝説はどのようにして生まれたのか。話は、マルコが旅した時代からさらに500年以上さかのぼる。
天平年間(729?749年)、聖武(しょうむ)天皇は藤原一族がらみの激しい政争に加え、天然痘の大流行や旱魃と飢饉、大地震に襲われ、苦しんでいた。天皇は仏教に深く帰依し、仏教にすがって世を立て直そうと試みた。
国家鎮護のため全国に国分寺を建立する詔(みことのり)を出したのに続いて、743年(天平15年)には大仏造立(ぞうりゅう)を宣言した。奈良東大寺の大仏様である。
「私は天皇の位に就いて民を慈しんできたが、仏の恩徳はいまだ天下に行き渡っていない。三宝(仏、法、僧)の力によって天下が安らかになり、生きとし生けるものすべてが栄えることを望む」(『続日本紀』所収の詔、現代語訳は筆者)
詔には、聖武天皇の切なる思いがにじむ。「一本の草、一握りの土でも協力したいという者がいれば、それを許しなさい」との一文を付け加えている。
高さ16メートルもの大仏を造る大事業である。まず木材と土で原型を造り、さらに外型を造って間に溶銅を流し込んで鋳造する。一気にはできないので、下部から順々に鋳造していったと考えられている。
原料の銅や錫は国内にたくさんあった。だが、問題は金だった。銅による鋳造の後、大仏には鍍金(ときん)を施して金ピカにする計画だが、国内の産金はごくわずかで、中国や朝鮮半島から輸入するしかない。当然のことながら、「莫大な代価を払わなければならない」と覚悟していた。

その時である。749年(天平21年)、陸奥(むつ)の国から「大量の砂金が見つかった」との報告が寄せられ、都に黄金900両(13キロ)が届けられた。
聖武天皇の喜びようは尋常ではなかった。「願いが天に届いた」と思ったのではないか。天皇はその年のうちに元号を「天平感宝」と改め、出家して退位してしまった。
武人で歌人でもあった大伴家持は当時、越中の国守だったが、陸奥の産金を知り、産金をことほぐ長歌と次のような反歌を詠んだ。
天皇(すめろき)の 御代栄えむと 東(あづま)なる
陸奥(みちのく)山に 金(くがね)花咲く
万葉集に収められた歌の中で「最北の地を詠んだ歌」とされる。
大仏の開眼供養が営まれたのは752年(天平勝宝4年)である。大仏造立の詔から9年。その後も陸奥からは砂金が次々に届けられ、鍍金と仕上げ作業が続けられた。
日本の元号が漢字4文字で表されたのは、この時期の5代しかない。うち3代に「黄金」を意味する「宝」が使われた。朝廷の喜びがいかに大きかったかを示している。
陸奥で砂金が見つかった時の国守は、百済王(くだらのこにきし)敬福である。その名が示すように朝鮮半島の百済から渡来した王族の末裔で、陸奥に赴任する際に同行した部下にも渡来系の人たちがいたことが知られている。
砂金の発見と採取には特殊なノウハウと技術が求められる。大和朝廷の支配下にはもともとそうした人材はおらず、渡来系の人たちに頼るしかなかったのだろう。
砂金貢納の功績により、百済王敬福は従五位上から7階級特進し、その部下たちも褒賞にあずかった。朝廷にとっては「金の輸入国から輸出国に転じるきっかけを作ってくれた人たち」であった。
これ以降、陸奥では砂金や金鉱脈が相次いで発見される。大陸に渡る使者や僧侶には渡航費用に充てるため、砂金を持たせるようになっていった。
黄金を基盤にして、平泉の藤原一族は栄華を極めた。中尊寺金色堂はその象徴であり、扉も壁も天井も金箔で飾られた。マルコが記した「黄金の国ジパング伝説」はこうしたことを反映したものであり、多少の誇張はあったにせよ、伝説ではなく、事実であった。
◇ ◇
大仏造立時に大量の砂金が見つかったのは、宮城県北東部の涌谷(わくや)町である。砂金の採取地は、町の中心部の北に広がる箟岳(ののだけ)丘陵の沢筋にある。夏の渇水期には水がわずかに流れるだけの小さな沢だ。
周辺で金の鉱脈は見つかっていない。金をわずかに含む地層が隆起して浸食され、その砂金が大雨の時に押し流され、長い年月のうちに堆積したものと考えられている。
砂金が採取された場所には神社と寺が建てられた。聖武天皇は「仏が恵んでくれた金」という宣明と「天地の神々が祝福してくれた金」という宣明を同じ日に出しており、それに基づいて建立されたものだろう。「日本の神仏混淆(こんこう)はここに始まる」との見方もある。
だが、砂金が採れなくなると、神社も寺も忘れ去られた。どこの国でも、金が採れなくなった地域は「ゴーストタウン」と化す運命にある。
いつしか、「天平時代に砂金が採れたのは牡鹿半島沖の金華山」という俗説が流布し、そう信じられるようになっていった。松尾芭蕉も「奥の細道」の旅日誌に、大伴家持が「陸奥山に金花咲く」とうたったのは金華山、と記している。
こうした俗説に異を唱え、『続日本紀』などの史書を丹念に調べて是正したのは、江戸時代後期の伊勢の国学者、沖安海(おき・やすみ)である。
沖は当時の涌谷村の砂金採取地の様子を次のように記している。
「社(やしろ)があると聞いて訪ねたが、松や竹が生い茂り、道もなく荒れ果てていた。地元の人に問うたが、誰も知らない」
それでも、沖はやぶの中から大きな礎石と瓦の破片を見つけた。ここに社があったことを確信し、自ら資金を調達して黄金山神社を再建した。黄金の国伝説の起点となった場所は、一人の国学者によって息を吹き返し、歴史の表舞台に戻ってきたのである。

これ以降、地元の人たちはまた神社を大切にするようになった。昭和から平成にかけて、竹下政権は地域おこしのために市町村に1億円を交付する「ふるさと創生事業」を始めた。
涌谷町は、この事業を足がかりにして黄金山神社の周辺を整備し、神社の入り口に「天平ろまん館」というテーマ館を建てて地域おこしに取り組み始めた。展示資料が充実している。砂金採取の体験もできる施設で人気を集めた。
2019年には、涌谷町や平泉町を含む地域が「黄金の国ジパング 産金はじまりの地」として、文化庁に「日本遺産」に認定された。これで地域おこしに弾みがつくはずだった。
だが、コロナ禍の影響を大きく受け、集客に苦心しているのが実情だ。今はポスト・コロナを見据え、戦略を練り直す時だろう。
シルクロードにあこがれ、大航海時代の冒険に胸躍らせる人は世界中にたくさんいる。マルコ・ポーロとコロンブスにも登場してもらい、海外からもっと人を招き寄せる方策を探ってはどうか。「黄金をめぐる世界のネットワーク」の拠点を目指す道もある。ここは、知恵の絞りどころだろう。
◇ ◇
古代東北の蝦夷(えみし)と畿内の朝廷勢力との関係で考えると、涌谷での砂金の発見は「朝廷が蝦夷討伐に本腰を入れる要因の一つになったのではないか」との推測を生む。
8世紀の前半、東北の情勢は比較的落ち着いていた。朝廷の支配は現在の宮城県の北部まで、それ以北の岩手県や青森県の大部分は蝦夷の勢力圏、という構図で推移していた。
ところが、涌谷で砂金が発見された後、朝廷は桃生(ものう)城の建設(758年)と伊治(これはり)城の建設(767年)に踏み切った。涌谷の砂金採取地は桃生城の近くである。「陸奥にはもっと黄金があるに違いない」と見て、支配を北へ押し広げることを決意したのではないか。
実際、蝦夷と朝廷との「38年戦争」は、蝦夷側による桃生城と伊治城の襲撃から始まり、岩手県の胆沢(いさわ)を拠点とするアテルイ(阿弖流為)らの蝦夷勢力との激突、という形で展開していった。
大陸や朝鮮半島との交易において、黄金は何よりも有力な品となる。その確保は、朝廷にとって最優先課題となった可能性がある(佐渡島で金の採掘が本格化するのは江戸時代以降)。
砂金はしばしば、砂鉄と共に採取される。「朝廷は、砂金に加えて鉄などの鉱物資源の確保を目指したのではないか」という見方もある。これは、「蝦夷の刀」とされる蕨手(わらびて)刀の鍛造や伝播とも関わってくる。
古代の東北をめぐっては、解明されなければならない課題がまだ山のようにある。私たちの探求の旅は始まったばかり、と言えるのではないか。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真と図の説明&Source≫
◎マルコ・ポーロの肖像画
https://www.biography.com/explorer/marco-polo
◎マルコ・ポーロの行路
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Route_of_Marco_Polo.png
◎奈良東大寺の大仏。戦火で2度焼損し、再建された
https://seikyokudo.jp/?pid=151001936
◎宮城県涌谷町の黄金山神社(筆者撮影)
≪参考文献≫
◎『マルコ・ポーロ ルスティケッロ・ダ・ピーサ 世界の記 「東方見聞録」対校訳』(高田英樹、名古屋大学出版会)
◎『東方見聞録』(マルコ・ポーロ、愛宕<おたぎ>松男訳、平凡社・東洋文庫)
◎『奈良の大仏 世界最大の鋳造仏』(香取忠彦、イラスト・穂積和夫、草思社)
◎『東大寺大仏の研究 解説篇』(前田泰次、松山鐵夫、平川晋吾、西大由、戸津圭之介、岩波書店)
◎『日本の金』(彌永<やなが>芳子、東海大学出版会)
◎『天平産金物語』(宮城県涌谷町教育委員会)
◎『天平の産金地、宮城県箟岳(ののだけ)丘陵の砂金と地質の研究史』(鈴木舜一、地質学雑誌第116巻第6号)
◎『陸奥産金と家持』(福山宗志、『官人(つかさびと) 大伴家持』所収)
◎『日本鉱山史の研究』(小葉田<こばた>淳、岩波書店)
*注: マルコ・ポーロが訪れた当時のモンゴル帝国の皇帝について、中学や高校の教科書の多くは「フビライ」と表記していますが、研究者の間では「クビライ」と表記することが多いようです。アルファベットでは「KHUBILAI」と表記されます。「KH」は、ペルシャ語を含む中央アジア諸言語で喉の奥を使って発する音を表記する際の綴りで、「ク」と「フ」の中間のような音です。私もどちらかと言えば「ク」の方が適切と考えます。
第10回最上川縦断カヌー探訪は、7月30日(土)と31日(日)に予定通り開催します。1日目は最上川の五百川(いもがわ)峡谷(朝日町ー大江町)を15キロ下り、2日目は長井ダム湖の三淵渓谷を周遊します。
コロナの感染が再び急拡大し、厳しい状況ですが、感染対策を施しながら、なんとか開催する予定です。参加者は45人(1日目は37人、2日目は23人)です。
天気予報によれば、山形県の内陸部は30日、31日とも晴れ時々曇り。最高気温は30日が摂氏33度、31日が34度の見込みです。
コロナの感染が再び急拡大し、厳しい状況ですが、感染対策を施しながら、なんとか開催する予定です。参加者は45人(1日目は37人、2日目は23人)です。
天気予報によれば、山形県の内陸部は30日、31日とも晴れ時々曇り。最高気温は30日が摂氏33度、31日が34度の見込みです。
安倍晋三首相(当時)の昭恵夫人が知人の招きで山形県の長井市を訪れたのは、2017年の夏だった。長井市内で開かれたイベントに参加した後、昭恵さんは最上川の支流・野川の奥にある三淵(みふち)渓谷まで足を延ばした。

高さ50メートルほどの断崖が続く渓谷にはかつて三淵神社があったが、その場所は長井ダムの完成によって水没し、神社はさらに奥の山腹に移された。昭恵さんは地元の人たちが用意してくれたボートに乗って渓谷へと進み、神社の方角に向かって手を合わせたという。
「この時期はよくコシジロ(アブの一種)が出ます。お付きの人たちはキャーキャー騒いであちこち刺されていましたが、昭恵さんは泰然としていました」。一行を案内したNPO最上川リバーツーリズムネットワークの佐藤五郎・代表理事は振り返る。
ボートの手配まで依頼して昭恵さんがこの地を訪れ、手を合わせたのはなぜなのか。それは、この渓谷にまつわる不思議な物語を知ったからである。
◇ ◇
物語は1000年ほど昔にさかのぼる。舞台は古代の東北である。陸奥(むつ)と出羽で暮らしていた蝦夷(えみし)は畿内の朝廷勢力との「38年戦争」に敗れ、いったんはその支配下に組み込まれたが、11世紀の半ばには再び勢力を盛り返していた。
この時期、「奥六郡」と呼ばれた岩手県の中部から南部にかけての地域を実質的に支配していたのは安倍一族だった(図参照)。

奥六郡は砂金と馬の産地であり、アザラシの毛皮や鷲の羽、絹の供給地でもあった。それらの品々は朝廷への貢租として納められ、都の人たちに珍重されてきたが、安倍一族は貢納をやめ、その支配を衣川の南へ広げようとした。
朝廷にとっては許しがたいことである。永承6年(1051年)、「前九年の役」と呼ばれる戦争が始まる。陸奥守、藤原登任(なりとう)は出羽の軍勢も動員して、鬼切部(おにきりべ)(現在の宮城県大崎市鳴子温泉鬼首)で安倍一族との合戦に臨んだ。
結果は安倍一族の圧勝、朝廷側の惨敗だった。藤原登任は多数の死傷者を出して敗走し、更迭された。
代わって陸奥守に就任したのが、武勇のほまれ高い源頼義である。頼義は「安倍一族追討」の命を帯びて着任したが、その前後に後冷泉天皇は祖母、上東門院(藤原彰子)の病気快癒を願って恩赦を発布した。朝廷軍と戦った安倍一族の棟梁、安倍頼時(よりとき)や息子の貞任(さだとう)らの罪がすべて許されることになったのである。
安倍一族は源頼義を盛大にもてなし、恭順の意を示した。陸奥にしばしの平和が訪れた。だが、それも長くは続かなかった。
天喜4年(1056年)、源頼義の家臣と安倍貞任との間に争いが起きた。阿久利河事件と呼ばれる。頼義の家臣の妹との結婚を貞任が申し入れたのに対し、その家臣が「安倍のような賎しい一族に妹はやれぬ」と断ったことに貞任が怒り、夜討ちをかけたとされる事件で、これをきっかけに再び戦さが始まる。風雪の中、朝廷軍と安倍一族は激突し、またもや貞任率いる安倍一族が圧勝した。
前九年の役を記録した『陸奥話記』は「官軍大いに敗れ、死する者数百人なり」「将軍の従兵、散走し、残るところわずかに六騎」と伝える。源頼義は命からがら逃げ延びた。
戦争の様相が一変するのは、出羽を支配する清原一族が朝廷側に加わってからである。源頼義に懇請され、清原武則(たけのり)は1万の軍勢を率いて参戦した。朝廷・清原連合軍は城柵に立てこもる安倍一族を次々に打ち破り、壊滅に追い込む。安倍貞任は瀕死の状態で捕らえられて息絶え、息子や家臣もことごとく処刑された。
奥六郡を支配した安倍一族とは、どのような人たちだったのか。『陸奥話記』には、父祖安倍忠頼は「東夷の酋長なり」とある。「俘囚安倍貞任」と記す史書もある。
素直に読めば、古代東北の蝦夷で朝廷に服属した一族となる。だが、岩手大学の高橋崇教授は著書『蝦夷の末裔』に「地方官として陸奥に赴任し、土着化した勢力」や「移民としてやってきて豪族になった一族」である可能性も否定できない、と記した。
都で暮らす人々にとって陸奥や出羽は「地の果て」であり、住民そのものを「蝦夷」や「俘囚」と称して蔑む風潮があったからである。史書をいくら読み込んでも一族の出自を明らかにすることはできない、という。
朝廷に立ち向かうほどの力を誇った安倍一族は滅びた。ただ、ごく少数ながら生き延びた者もいた。貞任の弟の宗任(むねとう)は投降して許され、源頼義が陸奥守から四国の伊予守に転じると、伊予(愛媛県)に配流された。宗任はその後、さらに太宰府管内に流されて没した。この宗任こそ、安倍家の先祖である。
安倍晋三氏の父、晋太郎氏(元外相)は、盛岡タイムス社が発行した『安倍一族』(1989年発行)に「我が祖は『宗任』」と題して、次のような文章を寄せた。
「筑前大島(福岡県宗像郡大島村)に没した安倍宗任の後裔である松浦水軍が、壇ノ浦の合戦に平家方として参戦、敗れ散じたわが父祖が長門の国、先大津後畑(さきおおつうしろばた)の日本海に面した部落に潜み、再度転居の後、現在の地(山口県大津郡油谷<ゆや>町蔵小田)に住むことになったのは明治に入る前後のこと」
「先頃、宗任配流の地大島の住居跡に建立された安生院において、御縁の皆さんによって八百八十年の追善供養が行われましたが、八百八十年という歳月は気の遠くなるような長さにも思われますが、宇宙の大きいサイクルからみれば、ほんのしばらくの時間なのかもしれない」
「奥州文化の代表である金色堂も、毛越寺も、敗れた一族の華として今を息づいていることを思うとき、宗任より四十一代末裔の一人として自分の志した道を今一度省みながら華咲かしてゆく精進をつづけられたらと、願うことしきりです」
苦難の道を歩んだ宗任や父祖への慈愛に満ちた文章である。安倍家の系図を晋三、晋太郎、寛(かん)とたどっていくと、高祖父は英任と名付けられていることが分かる(系図参照)。宗任の「任」の名を引き継いだのは、それを誇りとしていたからだろう。
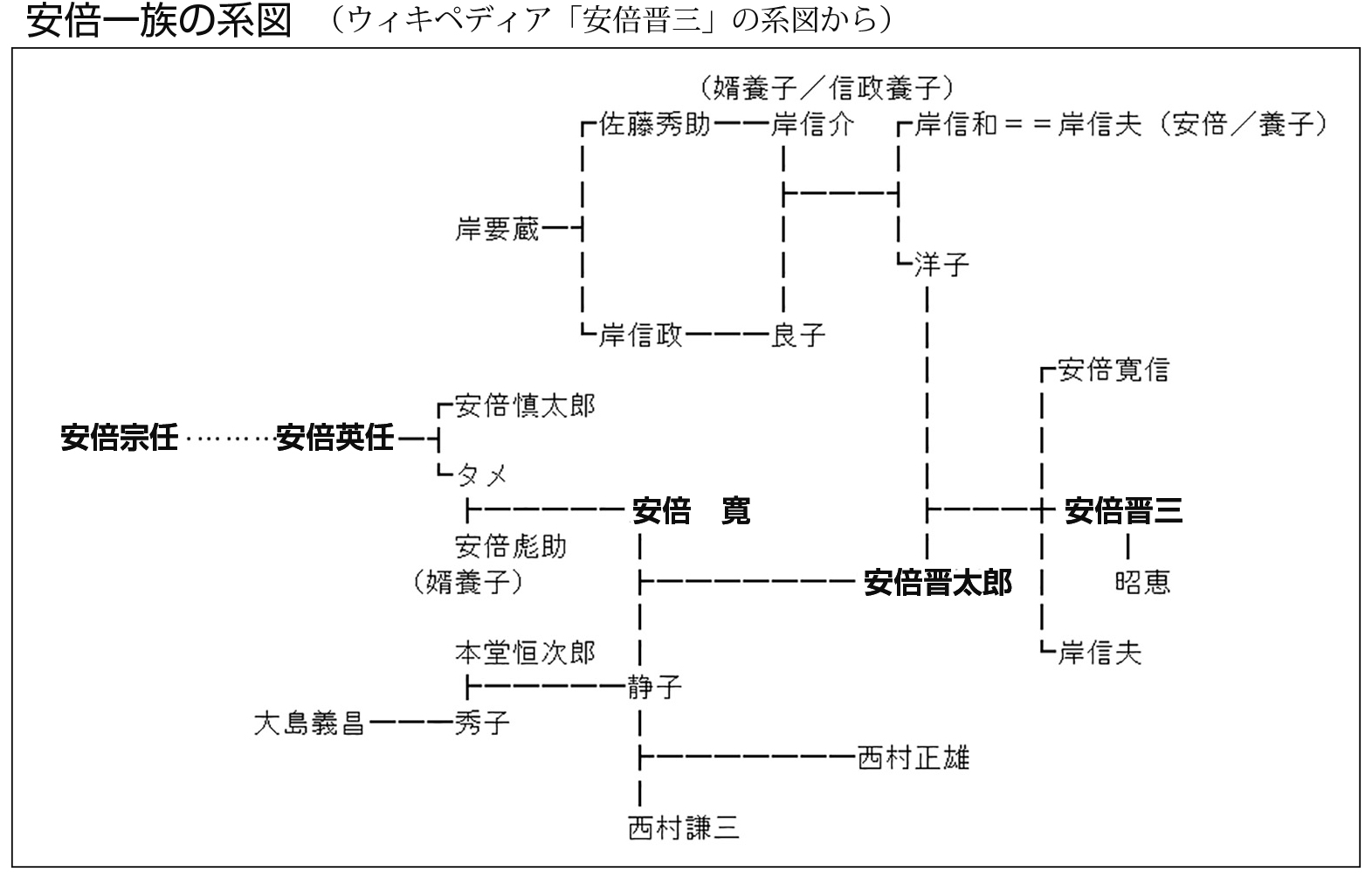
さて、昭恵夫人の三淵渓谷訪問である。長井市には、前九年の役について次のような物語が伝わっている。
安倍貞任の息女に「卯(う)の花姫」という美しい姫がいた。宗任の姪にあたる。源頼義が陸奥守として着任し、安倍一族が盛大にもてなした際、姫は頼義の長男、義家と相思相愛の仲になった。義家からは「北の方(正妻)として都にお迎えする」との文も届いたものの、戦さによってその仲は引き裂かれた。
安倍一族が敗れた後、姫と一行は出羽に逃れ、朝日連峰の山道を通って長井の庄にたどり着いた。野川の奥にある山に館を構え、僧兵の助力も得て源氏の追手と何度か戦ったものの力尽き、三淵渓谷の断崖から身を投げて自害した。付き従った女性たちも渓谷に身を投じ、兵もみな討ち死にした――。
戦記の『陸奥話記』にも『今昔物語集』にも、卯の花姫のことは出てこない。だが、三淵渓谷の奥には、この物語の通り「安部ケ館(あべがたて)山」という山があり、国土地理院の地図にも記されている(地図の山の名前は「安倍」ではなく「安部」)。
長井市を訪問するにあたって、昭恵さんはこうした物語があることを知り、三淵渓谷を訪ねることにしたのだという。手紙で問い合わせると、「私は全てはご縁と思っており、私がやるべきことは神様が与えて下さると信じて流されるままに生きております」と返事があった。
卯の花姫の物語は人々の口から口へと伝えられたものと見られ、江戸時代の医師で文人の長沼牛翁(ぎゅうおう)(1761?1834年)が見聞録『牛涎(うしのよだれ)』に書き留めている。
牛翁は長井の呉服商の長男だったが、家業を弟に譲り、全国を漫遊した人物である。江戸で医術を学ぶなど、その旅は帰郷まで足かけ29年に及んだ。見聞録『牛涎』は全60巻の大著で4巻が欠落、56巻が地元に残る。卯の花姫の物語は第15巻に収録されている。
物語はしばしば、伝説と渾然一体となる。
最期を悟った卯の花姫は「龍神となってこの地の人々を守らん」と言い残して断崖に身を投じたとされ、人々は三淵渓谷に祠(ほこら)を建てて祀(まつ)った。そして、姫は毎年、龍神となって野川を下り、化粧直しをしたうえで長井の庄の神社に入るのだという。
長井市では5月の下旬、各神社から龍神を思わせる「黒獅子」が出て市街地を練り歩く。コロナ禍で中止や規模の縮小を余儀なくされてきたが、今年は3年ぶりに黒獅子舞が披露され、街は沸き立った。
龍神の話はともかく、卯の花姫が長井の庄にたどり着き、三淵渓谷で自害したという話は、単なる伝説とは思えないところがある。姫は侍女の一人に「生き延びてわが亡き後の菩提を弔うておくれ」と申しつけ、侍女はそれを守り、その末裔が連綿と姫の霊を祀ってきた、という伝承もある。
実際、渓谷の入り口にあたる長井市平山には代々、青木半三郎を名乗り、「八朔(はっさく)の祀り」を営んできた家族がいる。八朔は旧暦の8月1日のことで、卯の花姫が自害した日とされる(今年は8月27日)。
現在の当主、青木芳弘さん(62)によれば、一家は大昔には山奥の「桂谷(かつらや)」という集落で暮らし、150年ほど前までは今より奥の川岸に2軒だけで住んでいた。八朔の日には羽織、袴姿で「木流しの職人」たちが20人ほど集まり、川岸で円陣を組んで龍神を出迎えていたという。

青木家と渋谷家が毎年交代で酒宴の席を設けてもてなし、遠来の客には泊まってもらう習わしだったが、それも先々代で途絶え、渋谷家も離れていった。その後は青木家の敷地内に建てた小さな祠に家族だけでお供えをし、手を合わせているという。
青木家には「ご神体」とされる品々が伝わる。金属製の古い鏡とベッコウの櫛、笄(こうがい)である。その由来も意味も今となっては判然としないが、いずれも伐採した木を川に流すことを生業とする職人たちとは無縁の品々だ。「卯の花姫の形見」と考える方が合点がいく。
青木家のことは昭恵さんには初耳だったようだが、安倍宗任については、手紙への返事で次のように記している。
「安倍宗任の話は安倍家に嫁に来た30年以上前から聞いてはいましたが、主人が2度目の総理になってからとても近く感じるようになり、宗像市大島にある安倍宗任のお墓に私は何度もお参りすることになります」
「一度はこの日しか行かれないということで、たまたま行った日が宗任の亡くなった日であったこともあり、1000年の時を経てご先祖様は何を主人に伝えたいのだろうかと思ったりしていました」
現職首相の妻でありながら反原発、大麻解禁を唱え、「家庭内野党」と称した人は、長い歴史の流れに身をゆだねて生きる人でもあった。
古代の東北で源氏が率いる朝廷の軍勢と戦い、一敗地にまみれた一族の末裔が生き延びて力を蓄え、安倍寛、安倍晋太郎、安倍晋三という3人の政治家を世に送り出し、ついには憲政史上最長の政権を担うに至った。
歴史のダイナミズム、人と人との巡り会いの不思議さを感じさせる物語である。
長岡 昇 ( NPO「ブナの森」代表 )
*メールマガジン「風切通信 109」 2022年5月27日
【訂正】「鬼切部(現在の宮城県鳴子町鬼首)」とあるのは「鬼切部(現在の宮城県大崎市鳴子温泉鬼首)」の誤りでした。訂正します(本文は訂正済み)。鳴子町は2006年に発足した大崎市に統合されました。
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真、図の説明&Source≫
◎三淵渓谷(山形県長井市)=最上川リバーツーリズムネットワーク提供
◎図 安倍一族が支配していた「奥六郡」
https://blog.goo.ne.jp/replankeigo/e/4eae025b68ed99721937fbfa310a36c9
◎青木芳弘さんと青木家に伝わるご神体(筆者撮影)
◎安倍一族の系図(ウィキペディア「安倍晋三」の系図から)
≪参考文献≫
◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)
◎『陸奥話記』(梶原正昭校注、現代思潮社)
◎『陸奥話記 校本とその研究』(笠栄治、桜楓社)
◎『今昔物語集 四 新 日本古典文学大系36』(小峯和明校注、岩波書店)
◎『安倍一族』(盛岡タイムス社)
◎『気骨 安倍晋三のDNA』(野上忠興、講談社)
◎『絶頂の一族』(松田賢弥、講談社)
◎『牛涎』(長沼牛翁、文教の杜ながい所蔵)
◎『長井市史 各論 第2巻』(長井市史編纂委員会、2021年)
◎『長井市史 第一巻(原始・古代・中世編)』(長井市史編纂委員会、1984年)
◎『長井市史 第二巻(近世編)』(長井市史編纂委員会、1982年)

高さ50メートルほどの断崖が続く渓谷にはかつて三淵神社があったが、その場所は長井ダムの完成によって水没し、神社はさらに奥の山腹に移された。昭恵さんは地元の人たちが用意してくれたボートに乗って渓谷へと進み、神社の方角に向かって手を合わせたという。
「この時期はよくコシジロ(アブの一種)が出ます。お付きの人たちはキャーキャー騒いであちこち刺されていましたが、昭恵さんは泰然としていました」。一行を案内したNPO最上川リバーツーリズムネットワークの佐藤五郎・代表理事は振り返る。
ボートの手配まで依頼して昭恵さんがこの地を訪れ、手を合わせたのはなぜなのか。それは、この渓谷にまつわる不思議な物語を知ったからである。
◇ ◇
物語は1000年ほど昔にさかのぼる。舞台は古代の東北である。陸奥(むつ)と出羽で暮らしていた蝦夷(えみし)は畿内の朝廷勢力との「38年戦争」に敗れ、いったんはその支配下に組み込まれたが、11世紀の半ばには再び勢力を盛り返していた。
この時期、「奥六郡」と呼ばれた岩手県の中部から南部にかけての地域を実質的に支配していたのは安倍一族だった(図参照)。

奥六郡は砂金と馬の産地であり、アザラシの毛皮や鷲の羽、絹の供給地でもあった。それらの品々は朝廷への貢租として納められ、都の人たちに珍重されてきたが、安倍一族は貢納をやめ、その支配を衣川の南へ広げようとした。
朝廷にとっては許しがたいことである。永承6年(1051年)、「前九年の役」と呼ばれる戦争が始まる。陸奥守、藤原登任(なりとう)は出羽の軍勢も動員して、鬼切部(おにきりべ)(現在の宮城県大崎市鳴子温泉鬼首)で安倍一族との合戦に臨んだ。
結果は安倍一族の圧勝、朝廷側の惨敗だった。藤原登任は多数の死傷者を出して敗走し、更迭された。
代わって陸奥守に就任したのが、武勇のほまれ高い源頼義である。頼義は「安倍一族追討」の命を帯びて着任したが、その前後に後冷泉天皇は祖母、上東門院(藤原彰子)の病気快癒を願って恩赦を発布した。朝廷軍と戦った安倍一族の棟梁、安倍頼時(よりとき)や息子の貞任(さだとう)らの罪がすべて許されることになったのである。
安倍一族は源頼義を盛大にもてなし、恭順の意を示した。陸奥にしばしの平和が訪れた。だが、それも長くは続かなかった。
天喜4年(1056年)、源頼義の家臣と安倍貞任との間に争いが起きた。阿久利河事件と呼ばれる。頼義の家臣の妹との結婚を貞任が申し入れたのに対し、その家臣が「安倍のような賎しい一族に妹はやれぬ」と断ったことに貞任が怒り、夜討ちをかけたとされる事件で、これをきっかけに再び戦さが始まる。風雪の中、朝廷軍と安倍一族は激突し、またもや貞任率いる安倍一族が圧勝した。
前九年の役を記録した『陸奥話記』は「官軍大いに敗れ、死する者数百人なり」「将軍の従兵、散走し、残るところわずかに六騎」と伝える。源頼義は命からがら逃げ延びた。
戦争の様相が一変するのは、出羽を支配する清原一族が朝廷側に加わってからである。源頼義に懇請され、清原武則(たけのり)は1万の軍勢を率いて参戦した。朝廷・清原連合軍は城柵に立てこもる安倍一族を次々に打ち破り、壊滅に追い込む。安倍貞任は瀕死の状態で捕らえられて息絶え、息子や家臣もことごとく処刑された。
奥六郡を支配した安倍一族とは、どのような人たちだったのか。『陸奥話記』には、父祖安倍忠頼は「東夷の酋長なり」とある。「俘囚安倍貞任」と記す史書もある。
素直に読めば、古代東北の蝦夷で朝廷に服属した一族となる。だが、岩手大学の高橋崇教授は著書『蝦夷の末裔』に「地方官として陸奥に赴任し、土着化した勢力」や「移民としてやってきて豪族になった一族」である可能性も否定できない、と記した。
都で暮らす人々にとって陸奥や出羽は「地の果て」であり、住民そのものを「蝦夷」や「俘囚」と称して蔑む風潮があったからである。史書をいくら読み込んでも一族の出自を明らかにすることはできない、という。
朝廷に立ち向かうほどの力を誇った安倍一族は滅びた。ただ、ごく少数ながら生き延びた者もいた。貞任の弟の宗任(むねとう)は投降して許され、源頼義が陸奥守から四国の伊予守に転じると、伊予(愛媛県)に配流された。宗任はその後、さらに太宰府管内に流されて没した。この宗任こそ、安倍家の先祖である。
安倍晋三氏の父、晋太郎氏(元外相)は、盛岡タイムス社が発行した『安倍一族』(1989年発行)に「我が祖は『宗任』」と題して、次のような文章を寄せた。
「筑前大島(福岡県宗像郡大島村)に没した安倍宗任の後裔である松浦水軍が、壇ノ浦の合戦に平家方として参戦、敗れ散じたわが父祖が長門の国、先大津後畑(さきおおつうしろばた)の日本海に面した部落に潜み、再度転居の後、現在の地(山口県大津郡油谷<ゆや>町蔵小田)に住むことになったのは明治に入る前後のこと」
「先頃、宗任配流の地大島の住居跡に建立された安生院において、御縁の皆さんによって八百八十年の追善供養が行われましたが、八百八十年という歳月は気の遠くなるような長さにも思われますが、宇宙の大きいサイクルからみれば、ほんのしばらくの時間なのかもしれない」
「奥州文化の代表である金色堂も、毛越寺も、敗れた一族の華として今を息づいていることを思うとき、宗任より四十一代末裔の一人として自分の志した道を今一度省みながら華咲かしてゆく精進をつづけられたらと、願うことしきりです」
苦難の道を歩んだ宗任や父祖への慈愛に満ちた文章である。安倍家の系図を晋三、晋太郎、寛(かん)とたどっていくと、高祖父は英任と名付けられていることが分かる(系図参照)。宗任の「任」の名を引き継いだのは、それを誇りとしていたからだろう。
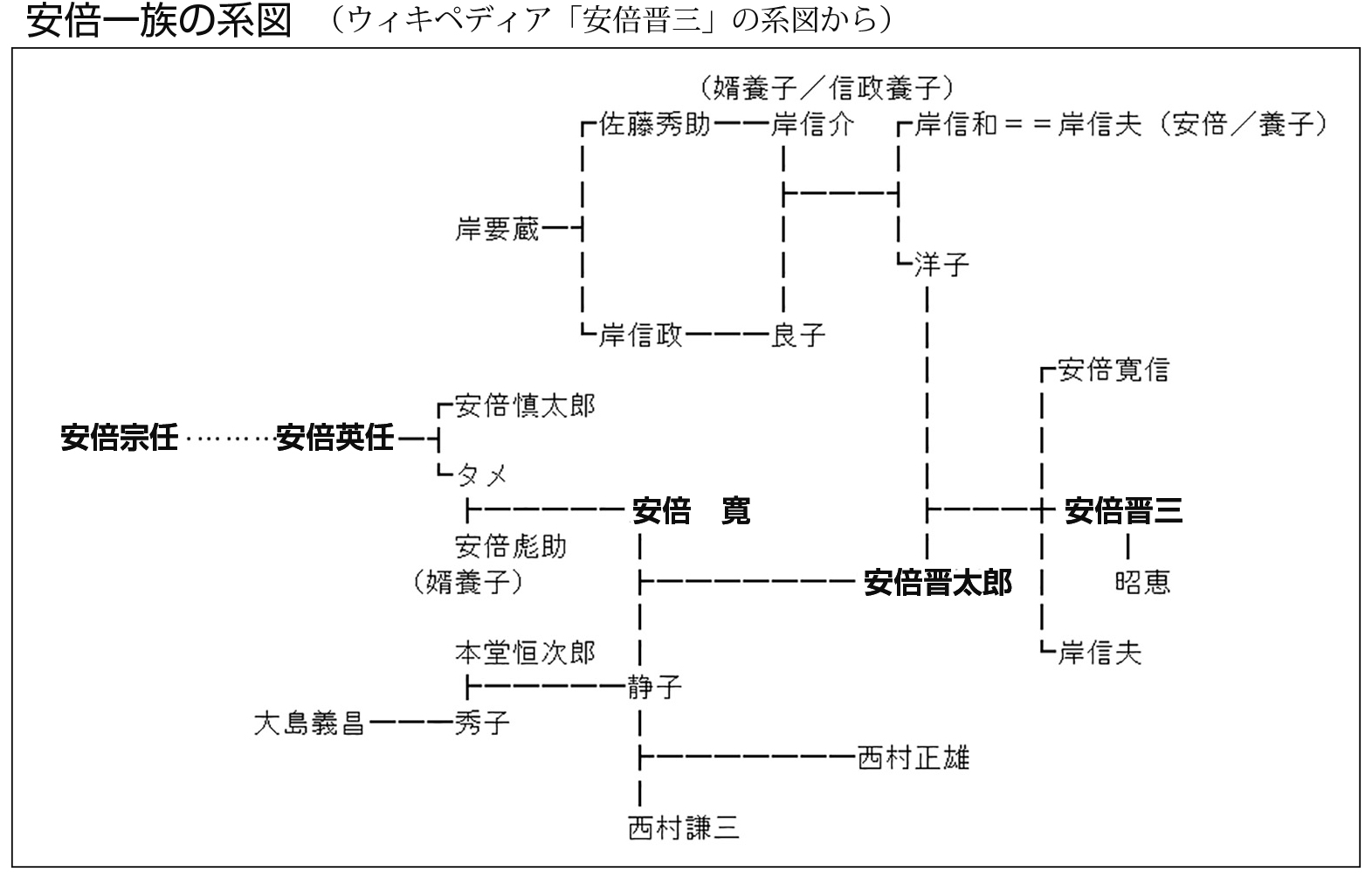
さて、昭恵夫人の三淵渓谷訪問である。長井市には、前九年の役について次のような物語が伝わっている。
安倍貞任の息女に「卯(う)の花姫」という美しい姫がいた。宗任の姪にあたる。源頼義が陸奥守として着任し、安倍一族が盛大にもてなした際、姫は頼義の長男、義家と相思相愛の仲になった。義家からは「北の方(正妻)として都にお迎えする」との文も届いたものの、戦さによってその仲は引き裂かれた。
安倍一族が敗れた後、姫と一行は出羽に逃れ、朝日連峰の山道を通って長井の庄にたどり着いた。野川の奥にある山に館を構え、僧兵の助力も得て源氏の追手と何度か戦ったものの力尽き、三淵渓谷の断崖から身を投げて自害した。付き従った女性たちも渓谷に身を投じ、兵もみな討ち死にした――。
戦記の『陸奥話記』にも『今昔物語集』にも、卯の花姫のことは出てこない。だが、三淵渓谷の奥には、この物語の通り「安部ケ館(あべがたて)山」という山があり、国土地理院の地図にも記されている(地図の山の名前は「安倍」ではなく「安部」)。
長井市を訪問するにあたって、昭恵さんはこうした物語があることを知り、三淵渓谷を訪ねることにしたのだという。手紙で問い合わせると、「私は全てはご縁と思っており、私がやるべきことは神様が与えて下さると信じて流されるままに生きております」と返事があった。
卯の花姫の物語は人々の口から口へと伝えられたものと見られ、江戸時代の医師で文人の長沼牛翁(ぎゅうおう)(1761?1834年)が見聞録『牛涎(うしのよだれ)』に書き留めている。
牛翁は長井の呉服商の長男だったが、家業を弟に譲り、全国を漫遊した人物である。江戸で医術を学ぶなど、その旅は帰郷まで足かけ29年に及んだ。見聞録『牛涎』は全60巻の大著で4巻が欠落、56巻が地元に残る。卯の花姫の物語は第15巻に収録されている。
物語はしばしば、伝説と渾然一体となる。
最期を悟った卯の花姫は「龍神となってこの地の人々を守らん」と言い残して断崖に身を投じたとされ、人々は三淵渓谷に祠(ほこら)を建てて祀(まつ)った。そして、姫は毎年、龍神となって野川を下り、化粧直しをしたうえで長井の庄の神社に入るのだという。
長井市では5月の下旬、各神社から龍神を思わせる「黒獅子」が出て市街地を練り歩く。コロナ禍で中止や規模の縮小を余儀なくされてきたが、今年は3年ぶりに黒獅子舞が披露され、街は沸き立った。
龍神の話はともかく、卯の花姫が長井の庄にたどり着き、三淵渓谷で自害したという話は、単なる伝説とは思えないところがある。姫は侍女の一人に「生き延びてわが亡き後の菩提を弔うておくれ」と申しつけ、侍女はそれを守り、その末裔が連綿と姫の霊を祀ってきた、という伝承もある。
実際、渓谷の入り口にあたる長井市平山には代々、青木半三郎を名乗り、「八朔(はっさく)の祀り」を営んできた家族がいる。八朔は旧暦の8月1日のことで、卯の花姫が自害した日とされる(今年は8月27日)。
現在の当主、青木芳弘さん(62)によれば、一家は大昔には山奥の「桂谷(かつらや)」という集落で暮らし、150年ほど前までは今より奥の川岸に2軒だけで住んでいた。八朔の日には羽織、袴姿で「木流しの職人」たちが20人ほど集まり、川岸で円陣を組んで龍神を出迎えていたという。

青木家と渋谷家が毎年交代で酒宴の席を設けてもてなし、遠来の客には泊まってもらう習わしだったが、それも先々代で途絶え、渋谷家も離れていった。その後は青木家の敷地内に建てた小さな祠に家族だけでお供えをし、手を合わせているという。
青木家には「ご神体」とされる品々が伝わる。金属製の古い鏡とベッコウの櫛、笄(こうがい)である。その由来も意味も今となっては判然としないが、いずれも伐採した木を川に流すことを生業とする職人たちとは無縁の品々だ。「卯の花姫の形見」と考える方が合点がいく。
青木家のことは昭恵さんには初耳だったようだが、安倍宗任については、手紙への返事で次のように記している。
「安倍宗任の話は安倍家に嫁に来た30年以上前から聞いてはいましたが、主人が2度目の総理になってからとても近く感じるようになり、宗像市大島にある安倍宗任のお墓に私は何度もお参りすることになります」
「一度はこの日しか行かれないということで、たまたま行った日が宗任の亡くなった日であったこともあり、1000年の時を経てご先祖様は何を主人に伝えたいのだろうかと思ったりしていました」
現職首相の妻でありながら反原発、大麻解禁を唱え、「家庭内野党」と称した人は、長い歴史の流れに身をゆだねて生きる人でもあった。
古代の東北で源氏が率いる朝廷の軍勢と戦い、一敗地にまみれた一族の末裔が生き延びて力を蓄え、安倍寛、安倍晋太郎、安倍晋三という3人の政治家を世に送り出し、ついには憲政史上最長の政権を担うに至った。
歴史のダイナミズム、人と人との巡り会いの不思議さを感じさせる物語である。
長岡 昇 ( NPO「ブナの森」代表 )
*メールマガジン「風切通信 109」 2022年5月27日
【訂正】「鬼切部(現在の宮城県鳴子町鬼首)」とあるのは「鬼切部(現在の宮城県大崎市鳴子温泉鬼首)」の誤りでした。訂正します(本文は訂正済み)。鳴子町は2006年に発足した大崎市に統合されました。
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真、図の説明&Source≫
◎三淵渓谷(山形県長井市)=最上川リバーツーリズムネットワーク提供
◎図 安倍一族が支配していた「奥六郡」
https://blog.goo.ne.jp/replankeigo/e/4eae025b68ed99721937fbfa310a36c9
◎青木芳弘さんと青木家に伝わるご神体(筆者撮影)
◎安倍一族の系図(ウィキペディア「安倍晋三」の系図から)
≪参考文献≫
◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)
◎『陸奥話記』(梶原正昭校注、現代思潮社)
◎『陸奥話記 校本とその研究』(笠栄治、桜楓社)
◎『今昔物語集 四 新 日本古典文学大系36』(小峯和明校注、岩波書店)
◎『安倍一族』(盛岡タイムス社)
◎『気骨 安倍晋三のDNA』(野上忠興、講談社)
◎『絶頂の一族』(松田賢弥、講談社)
◎『牛涎』(長沼牛翁、文教の杜ながい所蔵)
◎『長井市史 各論 第2巻』(長井市史編纂委員会、2021年)
◎『長井市史 第一巻(原始・古代・中世編)』(長井市史編纂委員会、1984年)
◎『長井市史 第二巻(近世編)』(長井市史編纂委員会、1982年)
古代の東北に住み、畿内の朝廷勢力と「38年戦争」を繰り広げた蝦夷(えみし)とはどういう人たちだったのか。

7世紀半ば、斉明天皇の時代に遣唐使が男女2人の蝦夷を連れて海を渡り、唐の皇帝に謁見したことが日中双方の文献に記されている。わざわざ蝦夷を連れていったのは「わが国にも朝廷に貢ぎ物をする異民族がいる」ということを示すためだったと考えられる。同行した蝦夷は、人の頭に載せたひょうたんを弓矢で次々に射抜いて皇帝を驚かせたという。
蝦夷は日本語とは異なる言葉を話していた。畿内勢力はそれを「夷語(いご)」と呼び、蝦夷との交渉には通訳を必要とした。史書はその通訳のことを「訳語(おさ)」と記している。彼らが「辺境の日本人」だったとしたら、通訳を必要とするはずがない(方言の使い手に官職名を付けたりしない)。
一方で、言語学者の金田一京助やアイヌ語地名研究者の山田秀三は、東北にはアイヌ語を語源とする地名がたくさん残っていることを実証的に明らかにした。東北に残るアイヌ語源と考えられる地名の分布(図1)は、8世紀時点での大和政権の東北進出状況(図2)と強い相関関係を示している。
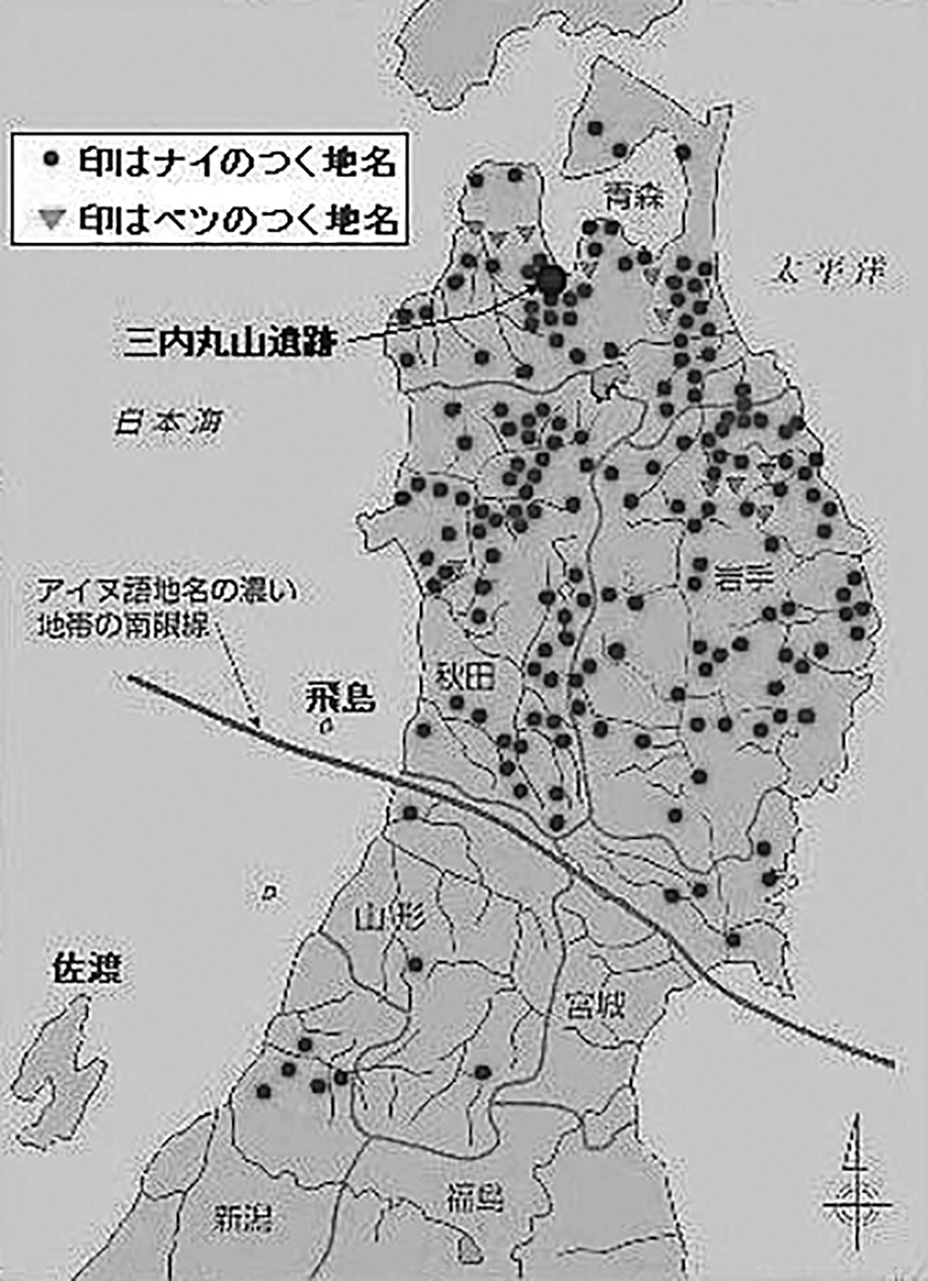
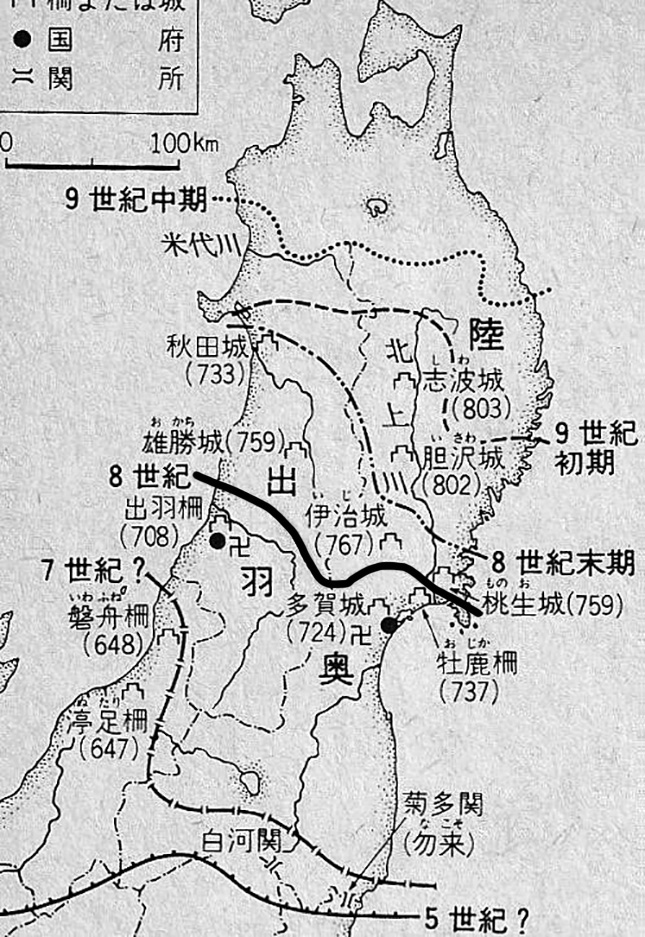
こうしたことを考えれば、古代東北の蝦夷は「アイヌ系の人たちだった」と考えるのが自然であり、私も「蝦夷=アイヌ説」を前提にして書いてきた。
ところが、「蝦夷はアイヌ系の人たちではなく、われわれの祖先と同じ日本人である」と唱える研究者が少なくない。「蝦夷とは朝廷の支配が及ばない辺境で暮らし、服属しなかった人たちである」というもので、「蝦夷=辺民説」と呼ばれる。「蝦夷=日本人説」あるいは「蝦夷=和人説」と言い換えてもいい。
彼らがその論拠とするのは「戦後、東北各地の発掘調査で得られた考古学の知見」である。たとえば、岩手県水沢市の常盤遺跡から籾(もみ)の痕が付いた弥生土器が発見された。青森県南津軽郡の垂柳(たれやなぎ)遺跡からは弥生時代の水田跡も見つかった。いずれも当時、水田稲作が行われていたことを示している。蝦夷は狩猟採集の生活をしていたはずで、アイヌ系と考えると説明がつかない、というわけだ。
古墳の存在も「蝦夷=日本人説」を後押しした。岩手県の胆沢(いさわ)町(水沢市などと共に奥州市に統合)に角塚(つのづか)古墳という前方後円墳がある。前方後円墳としては日本最北にあり、国の史跡になっている。
この古墳の存在は古くから知られており、幕末から明治にかけての探検家、松浦武四郎の図録『撥雲(はつうん)余興』第2集にも出てくるが、戦後の数次の発掘調査によってその詳細が明らかになった。
全長45メートル、後円部の直径28メートル、高さ4メートル余りの小ぶりの古墳だが、大和朝廷の支配地域で盛んに造られた前方後円墳であることは間違いない。出土した埴輪などから5世紀後半の築造であることも判明した。
岩手県の胆沢と言えば、奈良時代の後期から平安時代の初めにかけて朝廷側と戦った蝦夷の指導者、アテルイ(阿弖流為)の根拠地である。そこに300年も前に前方後円墳が造られていた。蝦夷=アイヌ説では説明しがたいことである。
こうした考古学上の発掘成果も踏まえて、岩手大学の教授、樋口知志は著書『阿弖流為』(2013年)で、古代東北の蝦夷について「現在ではほぼ学界の共有財産となる標準的な見解が成立しており、(中略)概ね彼らは私たち現代日本人の祖先のうちの一群であったことが明らかである」と記している。
歯切れのいい、思い切った表現だが、私に言わせれば「とんでもない決めつけ」であり、「牽強付会の極み」である。
東北北部から弥生時代に水田稲作が行われていたことを示す遺跡が見つかることは、蝦夷=アイヌ説に立っても説明できないことではない。「蝦夷はすべて狩猟採集の生活をしていた」という前提自体が間違っている可能性があるからである。
日本人との接触が多かった蝦夷の中には、早い段階で水田稲作の技法を学び、それを採り入れた集団があってもおかしくはない。「蝦夷にも様々な集団があり、早くから稲作をしていた集団もあれば、もっぱら狩猟採集をしていた集団もあった」と考えれば、矛盾はしない。
角塚古墳にしても、5世紀ごろには胆沢の蝦夷集団は大和政権と良好な関係にあり、大和側の了解を得て前方後円墳を造った可能性がある。この古墳からは蕨手刀(わらびてとう)が出土しており、被葬者は蝦夷の族長と考えられるからだ。
そもそも、考古学の成果を言うなら、東北の北部からは北海道で発見されたのと同型の古い土器も見つかっている。北海道のアイヌ系の人たちと文化的につながっていたことを示す証拠がたくさんある。「蝦夷=アイヌ説」は今なお、有力な説と言っていい。
だからこそ、2012年版の『日本史事典』(朝倉書店)は、「蝦夷と隼人」について次のように記しているのだ。
「蝦夷は『同じ日本人』の辺民への政治的設定とされてきたが、アイヌ民族の祖型と共通する文化をもつ独自の社会と見る説が近年再興し、日本民族形成史に問題を提起(している)」
古代東北の蝦夷については江戸時代から明治、大正、昭和とアイヌ説が強く唱えられ、戦後、日本人説を唱える研究者が増えた。だが、最近になって再びアイヌ説が盛り返している――というのが古代史学界の現状だろう。要するに、いまだに決着がつかない、ホットな問題なのである。
一連の論争を見ていて気づくのは、蝦夷=日本人説を唱える研究者たちは(1)遣唐使が蝦夷を随伴して渡航したとの記録(2)蝦夷との交渉に通訳を必要とした事実(3)東北北部に多数残るアイヌ語源と思われる地名の数々、といった蝦夷=アイヌ説の論拠についてほとんど言及しないことだ。
彼らは「考古学の発掘調査で得られた知見」を並べ立て、蝦夷=アイヌ説では説明しがたい問題を突きつけることに終始している。
そうした反省もあってか、蝦夷=日本人説を唱えてきた研究者からは「邪馬台国論争は畿内説か九州説のどちらかが正しければ、一方は誤りとなるが、古代蝦夷の問題は二者択一の論理では解決がつかない問題ではないか」といった見解も出てきた。
福島大学名誉教授の工藤雅樹は、2000年9月の講演で「東北地方北部の縄文人の子孫は北海道でアイヌ民族を形成することになる人々と途中まではほぼ同じ道をたどったものの、最終的にはアイヌ民族となる道を阻まれて日本民族の一員となった」と語った。
確かに、どちらの説に立っても、それぞれ説明が難しい問題がある。研究者の間では「蝦夷がエゾと呼ばれるようになり、アイヌ民族というものが成立したのは平安時代の末期から」というのが定説になっている。それを前提にすれば、奈良時代や平安初期の時代を生きた東北の蝦夷(えみし)を「アイヌ系」と呼ぶのはためらわれるのかもしれない。
だが、ある集団はある時点からいきなり「民族」になるわけではない。それは連続したプロセスであり、言語や風俗、習慣、規範などが変化しながら形成されていくものだろう。
そういう観点から「古代東北の蝦夷とはどういう人たちだったのか」と考えれば、やはり「アイヌ系の人たち」と見るのが自然で、蝦夷=日本人説は受け入れがたい。
古代の東北については「蝦夷はアイヌ系か日本人か」「38年戦争とは何だったのか」という論争にエネルギーを注ぎ過ぎて、その前後の探求がおろそかになっている、という指摘もある。実はこのことこそ、より重要な問題なのかもしれない。
蝦夷と呼ばれた人たちはもともと、東日本全体に広がっていた可能性がある。彼らは畿内の勢力によって関東から北へ、さらに東北北部へと追いやられたのではないか。その挙げ句に長く苦しい戦争を強いられ、敗れていったと考えられる。
だとするなら、この過程で朝廷側に投降・帰順した蝦夷は「数世紀にわたって」西日本や関東などに次々に移住させられた可能性がある。では、俘囚(ふしゅう)と呼ばれたその人たちはどうなったのか。
東北大学名誉教授の高橋富雄(2013年没)は、「それからのエゾ」についても「しっかりした見通しを立てておく必要がある」とし、「この人たちのうずもれた歴史が差別の問題にも連なっていることは明らかである。この問題は日本史の暗部に連なる」と指摘している。
移住させられた俘囚の運命、差別にさらされた彼らのその後の歩みをも視野に入れて研究し、論じていかなければならない、と後に続く人たちに呼びかけた。
残念なことに、私が知る限り、そうした長い射程で古代東北の蝦夷の問題を捉(とら)え、被差別部落の歴史まで視野に入れて探求し続けた人はほとんどいない。
在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)は長い射程でこうした問題を探求した人で、被差別部落の実態とルーツについては膨大な踏査記録を基に貴重な著作を残した。
ただ、山哉は「東北の蝦夷はアイヌではなく、別の先住民族のコロボックルである」といった突飛な説を唱えた。著書『蝦夷とアイヌ』では「その民族性が如何に殺伐性のものであるかを、深く注意する必要がある」「元来、劣等種であり獣性の脱せざる彼等」など、アイヌについて偏見に満ちた記述をしており、高橋が求めたような研究の基礎にするわけにはいかない。
「うずもれた歴史を掘り起こし、日本史の暗部を照らし出す作業」はこれからの課題、と言うしかない。
◇ ◇
岩手県胆沢町の角塚古墳のところで「蕨手刀」について触れた。この古刀の存在そのものは江戸時代から知られており、記録にも残っている。
刀の柄(つか)の頭の部分が早蕨(さわらび)のように丸まっていることから、探検家で博物学者でもあった松浦武四郎が明治初期に名付けたとされる。
この刀が注目されるのは、出土・発見された場所が図のように東北と北海道に集中しているからである。発見後に紛失したものも含めれば、これまでに300を超す蕨手刀が知られており、その8割が東北と北海道で見つかっている。このため、古くから「蝦夷の刀」と考えられてきた。
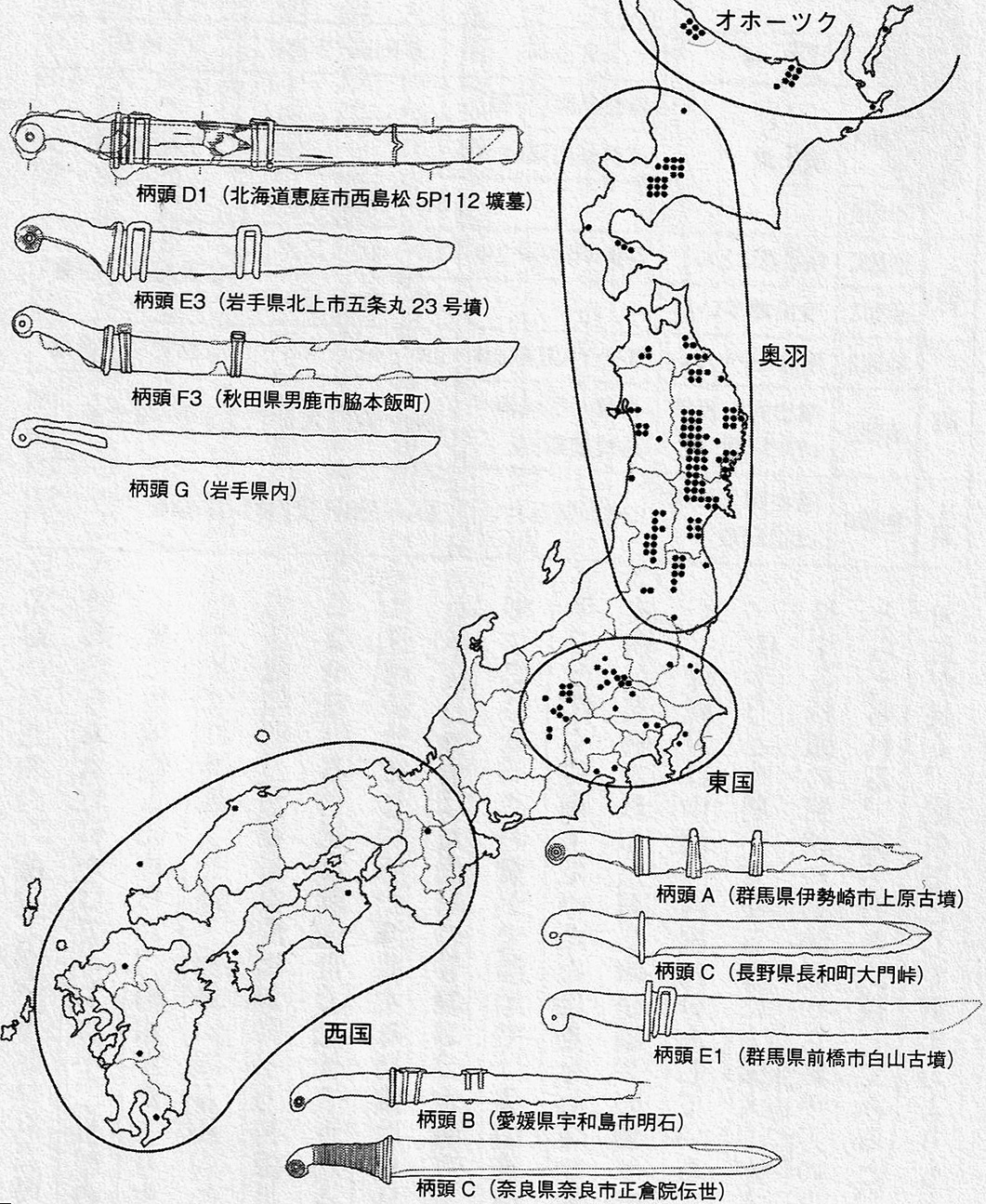
作られたのは7世紀から9世紀と推定され、その後、姿を消す。東北の蝦夷が畿内の朝廷勢力と戦った時代と重なることも「蝦夷の刀」との見方を強める。
蕨手刀は片手で持つ刀で、柄が上に反っているのも特徴の一つだ。広島大学名誉教授の下向井龍彦は、この反りが「疾駆する馬上での激しい斬り合いに耐える」ことを可能にし、「蝦夷の騎馬戦士の強さの秘密はこの蕨手刀にあった」と唱える。
蕨手刀はしばしば、古墳から副葬品として発見される。私が住む山形県の場合、南陽市だけでこの時期の小さな円墳が100以上あり、蕨手刀が副葬品としていくつも出土している。いずれも「被葬者は蝦夷の有力者」と見るのが自然だろう。
問題は、この蕨手刀が群馬県や長野県でもかなり見つかり、西日本でもわずかながら発見されていることだ。山口県萩市の沖合にある見島からも出土した。
これらをどう考えるか。歴史学者の喜田貞吉や下向井は「移住させられた俘囚が持ち込んだもの」と推測するが、異論もある。
『蕨手刀の考古学』の著者、黒済(くろずみ)和彦は、古いタイプの蕨手刀が上野(こうずけ)と信濃で見つかっていることから「上信地方が蕨手刀の発祥の地であり、そこから東北に伝わった」と見る。西日本で発見された蕨手刀についても「俘囚による持ち込み説」を否定している。
「蝦夷=アイヌ説」と「蝦夷=日本人説」の対立にも似て、蕨手刀をめぐっても「蝦夷の刀鍛冶が作り、蝦夷が使った」という説と「日本人が作り、東北に持ち込んだ」という説に分かれ、鋭く対立している。
私はもちろん、ここでも蝦夷説を採る。日本人説には「時間軸を長く取り、物事を大きな流れの中で捉える」という姿勢が感じられないからだ。
たとえば、蕨手刀の古いタイプが上野や信濃で最初に作られたのだとしても、それは刀鍛冶が日本人だったことを意味するとは限らない。この地方に残っていた蝦夷の刀鍛冶が作った可能性もあり、彼らが東北に移って作刀技術を伝えたとも考えられる。
また、西日本に送られた俘囚にしても、全員が移住後に隷属的な身分に貶(おとし)められたわけではない。史書をひも解けば、大宰府の管内で防人(さきもり)として重用された蝦夷もいたことが分かる。
山口県の見島は、朝鮮半島から来襲する海賊に備えて大和朝廷が防備を固めた島の一つである。その島に防人として赴任した俘囚たちがいて、その族長が亡くなって葬られ、棺に蕨手刀を添えた、ということも十分に考えられることなのだ。
歴史の大きなうねりの中で物事を捉える。朝廷の立場からだけでなく、蝦夷の側からも十分に光を当てる。そういう作業を地道に積み重ねていけば、古代東北の蝦夷たちがたどった道も少しずつ見えてくるのではないか。(敬称略)
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪図・写真の説明&Source≫
図1 アイヌ語源と考えられる東北の地名の分布
*安本美典『日本人と日本語の起源』から引用。アイヌ語地名の分布は金田一京助による。アイヌ語地名の濃い地帯の南限線は山田秀三による
図2 東北への大和政権の進出状況
*山川出版社『詳説 日本史』(1982年版)から引用
図3 蕨手刀の分布
*『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』所収の八木光則作成の図を引用
写真
岩手県胆沢町(現奥州市)の角塚古墳(2022年3月17日、筆者撮影)
≪参考文献&サイト≫
◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)
◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草思社)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)
◎『角塚古墳―整備基本計画策定に伴う形態確認調査報告書』(2002年3月、胆沢町教育委員会)
◎『阿弖流為(あてるい)』(樋口知志、ミネルヴァ書房)
◎『蝦夷(えみし)の古代史』(工藤雅樹、平凡社新書)
◎『エミシ・エゾ・アイヌ』(アイヌ民族文化財団での工藤雅樹の講演録、2000年9月)
◎『辺境 もう一つの日本史』(高橋富雄、教育社)
◎日本大百科全書(ニッポニカ)「蝦夷」の解説(高橋富雄)
https://kotobank.jp/word/%E8%9D%A6%E5%A4%B7-36617
◎『蕨手刀 日本刀の始源に関する一考察』(石井昌国、雄山閣)
◎『蕨手刀の考古学』(黒済和彦、同成社)
◎『武士の成長と院政 日本の歴史07』(下向井龍彦、講談社)

7世紀半ば、斉明天皇の時代に遣唐使が男女2人の蝦夷を連れて海を渡り、唐の皇帝に謁見したことが日中双方の文献に記されている。わざわざ蝦夷を連れていったのは「わが国にも朝廷に貢ぎ物をする異民族がいる」ということを示すためだったと考えられる。同行した蝦夷は、人の頭に載せたひょうたんを弓矢で次々に射抜いて皇帝を驚かせたという。
蝦夷は日本語とは異なる言葉を話していた。畿内勢力はそれを「夷語(いご)」と呼び、蝦夷との交渉には通訳を必要とした。史書はその通訳のことを「訳語(おさ)」と記している。彼らが「辺境の日本人」だったとしたら、通訳を必要とするはずがない(方言の使い手に官職名を付けたりしない)。
一方で、言語学者の金田一京助やアイヌ語地名研究者の山田秀三は、東北にはアイヌ語を語源とする地名がたくさん残っていることを実証的に明らかにした。東北に残るアイヌ語源と考えられる地名の分布(図1)は、8世紀時点での大和政権の東北進出状況(図2)と強い相関関係を示している。
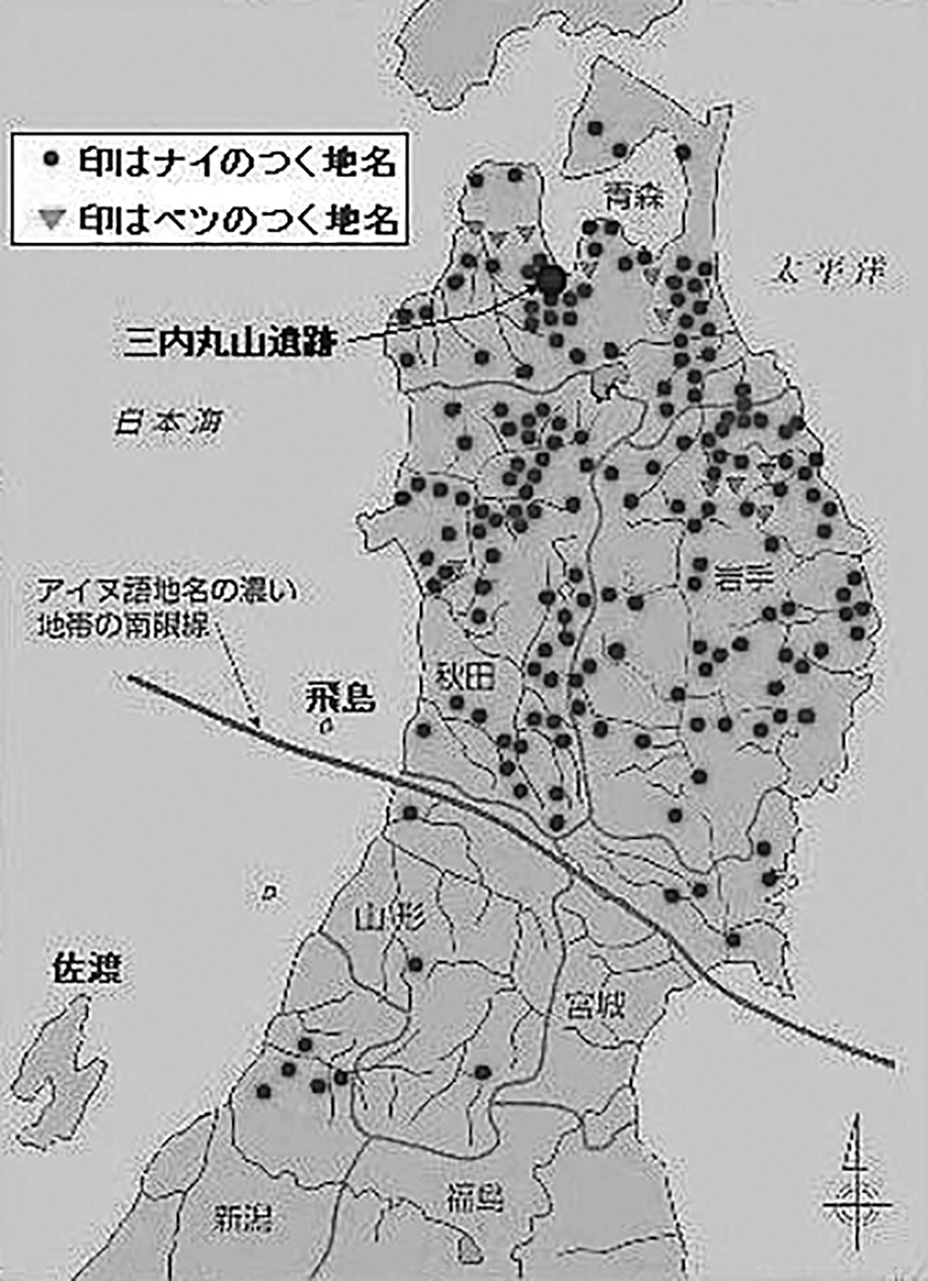
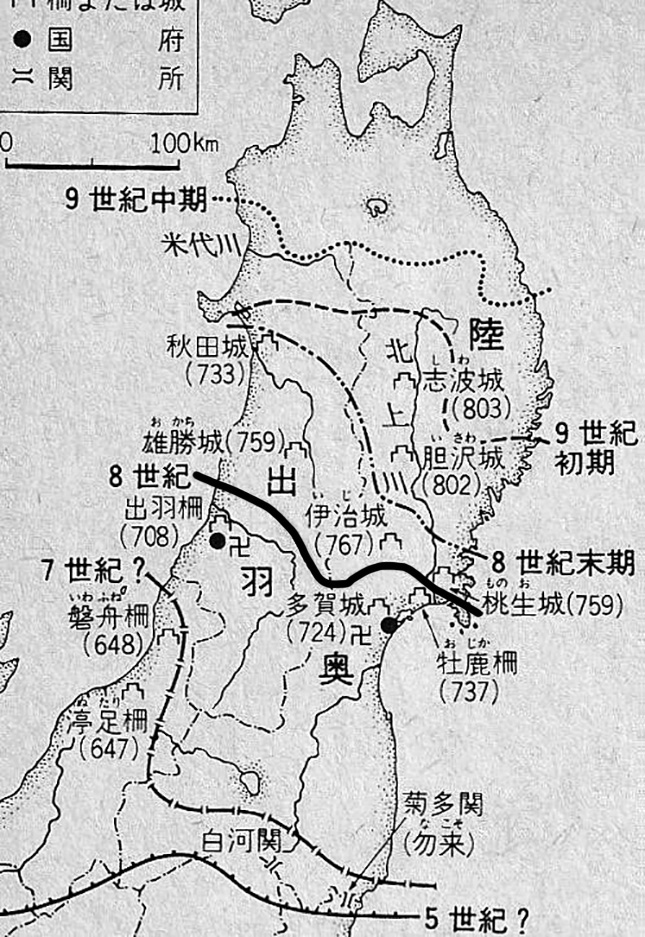
こうしたことを考えれば、古代東北の蝦夷は「アイヌ系の人たちだった」と考えるのが自然であり、私も「蝦夷=アイヌ説」を前提にして書いてきた。
ところが、「蝦夷はアイヌ系の人たちではなく、われわれの祖先と同じ日本人である」と唱える研究者が少なくない。「蝦夷とは朝廷の支配が及ばない辺境で暮らし、服属しなかった人たちである」というもので、「蝦夷=辺民説」と呼ばれる。「蝦夷=日本人説」あるいは「蝦夷=和人説」と言い換えてもいい。
彼らがその論拠とするのは「戦後、東北各地の発掘調査で得られた考古学の知見」である。たとえば、岩手県水沢市の常盤遺跡から籾(もみ)の痕が付いた弥生土器が発見された。青森県南津軽郡の垂柳(たれやなぎ)遺跡からは弥生時代の水田跡も見つかった。いずれも当時、水田稲作が行われていたことを示している。蝦夷は狩猟採集の生活をしていたはずで、アイヌ系と考えると説明がつかない、というわけだ。
古墳の存在も「蝦夷=日本人説」を後押しした。岩手県の胆沢(いさわ)町(水沢市などと共に奥州市に統合)に角塚(つのづか)古墳という前方後円墳がある。前方後円墳としては日本最北にあり、国の史跡になっている。
この古墳の存在は古くから知られており、幕末から明治にかけての探検家、松浦武四郎の図録『撥雲(はつうん)余興』第2集にも出てくるが、戦後の数次の発掘調査によってその詳細が明らかになった。
全長45メートル、後円部の直径28メートル、高さ4メートル余りの小ぶりの古墳だが、大和朝廷の支配地域で盛んに造られた前方後円墳であることは間違いない。出土した埴輪などから5世紀後半の築造であることも判明した。
岩手県の胆沢と言えば、奈良時代の後期から平安時代の初めにかけて朝廷側と戦った蝦夷の指導者、アテルイ(阿弖流為)の根拠地である。そこに300年も前に前方後円墳が造られていた。蝦夷=アイヌ説では説明しがたいことである。
こうした考古学上の発掘成果も踏まえて、岩手大学の教授、樋口知志は著書『阿弖流為』(2013年)で、古代東北の蝦夷について「現在ではほぼ学界の共有財産となる標準的な見解が成立しており、(中略)概ね彼らは私たち現代日本人の祖先のうちの一群であったことが明らかである」と記している。
歯切れのいい、思い切った表現だが、私に言わせれば「とんでもない決めつけ」であり、「牽強付会の極み」である。
東北北部から弥生時代に水田稲作が行われていたことを示す遺跡が見つかることは、蝦夷=アイヌ説に立っても説明できないことではない。「蝦夷はすべて狩猟採集の生活をしていた」という前提自体が間違っている可能性があるからである。
日本人との接触が多かった蝦夷の中には、早い段階で水田稲作の技法を学び、それを採り入れた集団があってもおかしくはない。「蝦夷にも様々な集団があり、早くから稲作をしていた集団もあれば、もっぱら狩猟採集をしていた集団もあった」と考えれば、矛盾はしない。
角塚古墳にしても、5世紀ごろには胆沢の蝦夷集団は大和政権と良好な関係にあり、大和側の了解を得て前方後円墳を造った可能性がある。この古墳からは蕨手刀(わらびてとう)が出土しており、被葬者は蝦夷の族長と考えられるからだ。
そもそも、考古学の成果を言うなら、東北の北部からは北海道で発見されたのと同型の古い土器も見つかっている。北海道のアイヌ系の人たちと文化的につながっていたことを示す証拠がたくさんある。「蝦夷=アイヌ説」は今なお、有力な説と言っていい。
だからこそ、2012年版の『日本史事典』(朝倉書店)は、「蝦夷と隼人」について次のように記しているのだ。
「蝦夷は『同じ日本人』の辺民への政治的設定とされてきたが、アイヌ民族の祖型と共通する文化をもつ独自の社会と見る説が近年再興し、日本民族形成史に問題を提起(している)」
古代東北の蝦夷については江戸時代から明治、大正、昭和とアイヌ説が強く唱えられ、戦後、日本人説を唱える研究者が増えた。だが、最近になって再びアイヌ説が盛り返している――というのが古代史学界の現状だろう。要するに、いまだに決着がつかない、ホットな問題なのである。
一連の論争を見ていて気づくのは、蝦夷=日本人説を唱える研究者たちは(1)遣唐使が蝦夷を随伴して渡航したとの記録(2)蝦夷との交渉に通訳を必要とした事実(3)東北北部に多数残るアイヌ語源と思われる地名の数々、といった蝦夷=アイヌ説の論拠についてほとんど言及しないことだ。
彼らは「考古学の発掘調査で得られた知見」を並べ立て、蝦夷=アイヌ説では説明しがたい問題を突きつけることに終始している。
そうした反省もあってか、蝦夷=日本人説を唱えてきた研究者からは「邪馬台国論争は畿内説か九州説のどちらかが正しければ、一方は誤りとなるが、古代蝦夷の問題は二者択一の論理では解決がつかない問題ではないか」といった見解も出てきた。
福島大学名誉教授の工藤雅樹は、2000年9月の講演で「東北地方北部の縄文人の子孫は北海道でアイヌ民族を形成することになる人々と途中まではほぼ同じ道をたどったものの、最終的にはアイヌ民族となる道を阻まれて日本民族の一員となった」と語った。
確かに、どちらの説に立っても、それぞれ説明が難しい問題がある。研究者の間では「蝦夷がエゾと呼ばれるようになり、アイヌ民族というものが成立したのは平安時代の末期から」というのが定説になっている。それを前提にすれば、奈良時代や平安初期の時代を生きた東北の蝦夷(えみし)を「アイヌ系」と呼ぶのはためらわれるのかもしれない。
だが、ある集団はある時点からいきなり「民族」になるわけではない。それは連続したプロセスであり、言語や風俗、習慣、規範などが変化しながら形成されていくものだろう。
そういう観点から「古代東北の蝦夷とはどういう人たちだったのか」と考えれば、やはり「アイヌ系の人たち」と見るのが自然で、蝦夷=日本人説は受け入れがたい。
古代の東北については「蝦夷はアイヌ系か日本人か」「38年戦争とは何だったのか」という論争にエネルギーを注ぎ過ぎて、その前後の探求がおろそかになっている、という指摘もある。実はこのことこそ、より重要な問題なのかもしれない。
蝦夷と呼ばれた人たちはもともと、東日本全体に広がっていた可能性がある。彼らは畿内の勢力によって関東から北へ、さらに東北北部へと追いやられたのではないか。その挙げ句に長く苦しい戦争を強いられ、敗れていったと考えられる。
だとするなら、この過程で朝廷側に投降・帰順した蝦夷は「数世紀にわたって」西日本や関東などに次々に移住させられた可能性がある。では、俘囚(ふしゅう)と呼ばれたその人たちはどうなったのか。
東北大学名誉教授の高橋富雄(2013年没)は、「それからのエゾ」についても「しっかりした見通しを立てておく必要がある」とし、「この人たちのうずもれた歴史が差別の問題にも連なっていることは明らかである。この問題は日本史の暗部に連なる」と指摘している。
移住させられた俘囚の運命、差別にさらされた彼らのその後の歩みをも視野に入れて研究し、論じていかなければならない、と後に続く人たちに呼びかけた。
残念なことに、私が知る限り、そうした長い射程で古代東北の蝦夷の問題を捉(とら)え、被差別部落の歴史まで視野に入れて探求し続けた人はほとんどいない。
在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)は長い射程でこうした問題を探求した人で、被差別部落の実態とルーツについては膨大な踏査記録を基に貴重な著作を残した。
ただ、山哉は「東北の蝦夷はアイヌではなく、別の先住民族のコロボックルである」といった突飛な説を唱えた。著書『蝦夷とアイヌ』では「その民族性が如何に殺伐性のものであるかを、深く注意する必要がある」「元来、劣等種であり獣性の脱せざる彼等」など、アイヌについて偏見に満ちた記述をしており、高橋が求めたような研究の基礎にするわけにはいかない。
「うずもれた歴史を掘り起こし、日本史の暗部を照らし出す作業」はこれからの課題、と言うしかない。
◇ ◇
岩手県胆沢町の角塚古墳のところで「蕨手刀」について触れた。この古刀の存在そのものは江戸時代から知られており、記録にも残っている。
刀の柄(つか)の頭の部分が早蕨(さわらび)のように丸まっていることから、探検家で博物学者でもあった松浦武四郎が明治初期に名付けたとされる。
この刀が注目されるのは、出土・発見された場所が図のように東北と北海道に集中しているからである。発見後に紛失したものも含めれば、これまでに300を超す蕨手刀が知られており、その8割が東北と北海道で見つかっている。このため、古くから「蝦夷の刀」と考えられてきた。
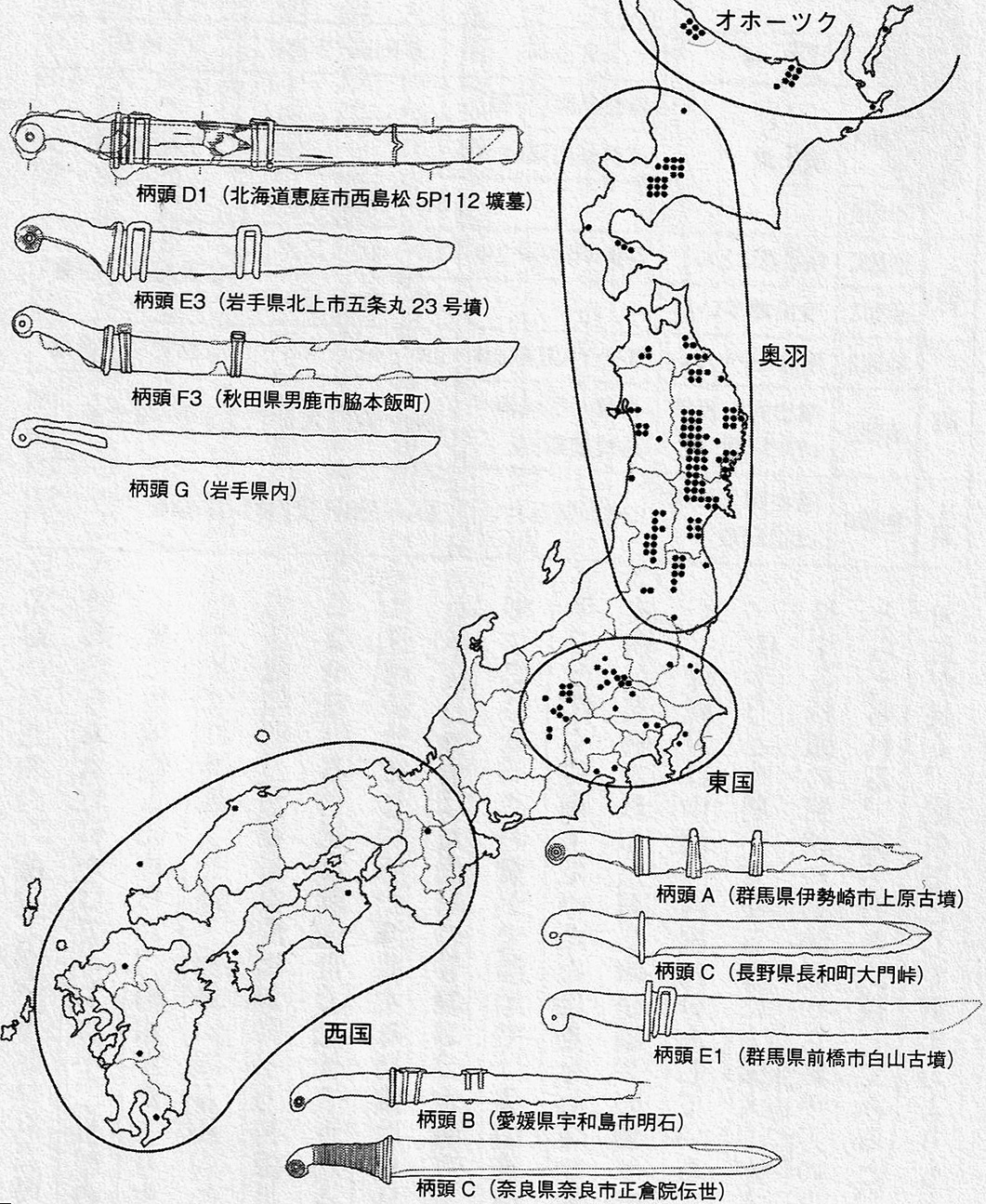
作られたのは7世紀から9世紀と推定され、その後、姿を消す。東北の蝦夷が畿内の朝廷勢力と戦った時代と重なることも「蝦夷の刀」との見方を強める。
蕨手刀は片手で持つ刀で、柄が上に反っているのも特徴の一つだ。広島大学名誉教授の下向井龍彦は、この反りが「疾駆する馬上での激しい斬り合いに耐える」ことを可能にし、「蝦夷の騎馬戦士の強さの秘密はこの蕨手刀にあった」と唱える。
蕨手刀はしばしば、古墳から副葬品として発見される。私が住む山形県の場合、南陽市だけでこの時期の小さな円墳が100以上あり、蕨手刀が副葬品としていくつも出土している。いずれも「被葬者は蝦夷の有力者」と見るのが自然だろう。
問題は、この蕨手刀が群馬県や長野県でもかなり見つかり、西日本でもわずかながら発見されていることだ。山口県萩市の沖合にある見島からも出土した。
これらをどう考えるか。歴史学者の喜田貞吉や下向井は「移住させられた俘囚が持ち込んだもの」と推測するが、異論もある。
『蕨手刀の考古学』の著者、黒済(くろずみ)和彦は、古いタイプの蕨手刀が上野(こうずけ)と信濃で見つかっていることから「上信地方が蕨手刀の発祥の地であり、そこから東北に伝わった」と見る。西日本で発見された蕨手刀についても「俘囚による持ち込み説」を否定している。
「蝦夷=アイヌ説」と「蝦夷=日本人説」の対立にも似て、蕨手刀をめぐっても「蝦夷の刀鍛冶が作り、蝦夷が使った」という説と「日本人が作り、東北に持ち込んだ」という説に分かれ、鋭く対立している。
私はもちろん、ここでも蝦夷説を採る。日本人説には「時間軸を長く取り、物事を大きな流れの中で捉える」という姿勢が感じられないからだ。
たとえば、蕨手刀の古いタイプが上野や信濃で最初に作られたのだとしても、それは刀鍛冶が日本人だったことを意味するとは限らない。この地方に残っていた蝦夷の刀鍛冶が作った可能性もあり、彼らが東北に移って作刀技術を伝えたとも考えられる。
また、西日本に送られた俘囚にしても、全員が移住後に隷属的な身分に貶(おとし)められたわけではない。史書をひも解けば、大宰府の管内で防人(さきもり)として重用された蝦夷もいたことが分かる。
山口県の見島は、朝鮮半島から来襲する海賊に備えて大和朝廷が防備を固めた島の一つである。その島に防人として赴任した俘囚たちがいて、その族長が亡くなって葬られ、棺に蕨手刀を添えた、ということも十分に考えられることなのだ。
歴史の大きなうねりの中で物事を捉える。朝廷の立場からだけでなく、蝦夷の側からも十分に光を当てる。そういう作業を地道に積み重ねていけば、古代東北の蝦夷たちがたどった道も少しずつ見えてくるのではないか。(敬称略)
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪図・写真の説明&Source≫
図1 アイヌ語源と考えられる東北の地名の分布
*安本美典『日本人と日本語の起源』から引用。アイヌ語地名の分布は金田一京助による。アイヌ語地名の濃い地帯の南限線は山田秀三による
図2 東北への大和政権の進出状況
*山川出版社『詳説 日本史』(1982年版)から引用
図3 蕨手刀の分布
*『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』所収の八木光則作成の図を引用
写真
岩手県胆沢町(現奥州市)の角塚古墳(2022年3月17日、筆者撮影)
≪参考文献&サイト≫
◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)
◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草思社)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)
◎『角塚古墳―整備基本計画策定に伴う形態確認調査報告書』(2002年3月、胆沢町教育委員会)
◎『阿弖流為(あてるい)』(樋口知志、ミネルヴァ書房)
◎『蝦夷(えみし)の古代史』(工藤雅樹、平凡社新書)
◎『エミシ・エゾ・アイヌ』(アイヌ民族文化財団での工藤雅樹の講演録、2000年9月)
◎『辺境 もう一つの日本史』(高橋富雄、教育社)
◎日本大百科全書(ニッポニカ)「蝦夷」の解説(高橋富雄)
https://kotobank.jp/word/%E8%9D%A6%E5%A4%B7-36617
◎『蕨手刀 日本刀の始源に関する一考察』(石井昌国、雄山閣)
◎『蕨手刀の考古学』(黒済和彦、同成社)
◎『武士の成長と院政 日本の歴史07』(下向井龍彦、講談社)
ロシア黒海艦隊の旗艦である巡洋艦「モスクワ」が沈没した。ロシア側は14日、「火災が起きて弾薬が爆発し、曳航中に沈没した」と発表した。一方、ウクライナ側は「対艦ミサイルで攻撃し、沈めた」と公表した。

どちらの説明に説得力があるかは明らかだ。「モスクワ」はウクライナ軍によって撃沈されたのである。
日本の新聞はそれぞれこのニュースを伝えたが、核心をつく報道はきわめて少ない。朝日新聞は16日、ロシア国営タス通信の報道とウクライナ側の発表を並べたうえで、「炎上、沈没」「攻撃・防空両面で打撃」と報じた。読売新聞も「露艦隊、防空網に打撃」と伝えた。
巡洋艦「モスクワ」が攻撃、防御の両面で大きな役割を果たしていたことは間違いなく、従ってロシア黒海艦隊にとって「沈没が大きな痛手」であることは疑いない。だが、どちらの新聞も「もっとも重要なこと」にまるで触れていない。報道する記者たちが「艦隊にとって旗艦とはどういう意味を持つか」を理解していないからである。
旗艦が持つもっとも重要な機能は「作戦の立案・実行と指揮・命令の伝達」という点だ。旗艦には司令官だけでなく、艦隊全体の作戦を立案する高級参謀や情報分析・通信解析を行う情報将校が乗り込む。「艦隊の頭脳」が集中しており、彼らが必要とする電子機器や通信設備もすべてそろっている。
日米戦争の口火を切った真珠湾攻撃の戦史をひも解けば、連合艦隊の旗艦「長門」がどういう役割を果たしたかがよく分かる。航空母艦を中心とするハワイ攻撃の機動部隊をどう動かし、何を攻撃するか。作戦はすべて旗艦「長門」で立案され、命令・実行された。旗艦とは艦隊の「頭脳」であり、「中枢」なのだ。
敵を攻撃したり、敵の攻撃から味方を防御したりする機能は、ほかの軍艦をいくつか集めれば代替可能だ。だが、「頭脳」が破壊され、機能不全に陥った場合、それに取って代わるのは容易なことではない。極めて深刻な事態に陥る。
そういう観点から見た場合、手元にある16日付の新聞でその意味合いを的確に報じたのは産経新聞だけだった。「司令塔失い 作戦打撃」と大きな見出しで報じた。旗艦が撃沈されれば、「司令塔」が失われ、「中枢機能」がマヒする。つまり、ロシアの黒海艦隊は「頭脳」を吹き飛ばされてしまったのである。
ウクライナ側は対艦ミサイルで「モスクワ」を攻撃したようだが、攻撃するためには「モスクワ」の位置を正確に把握していなくてはならない。偵察衛星などを駆使して、その動向を的確に押さえているのはアメリカ軍であり、イギリス軍だろう。米英の軍事情報がウクライナ側にリアルタイムで伝えられた、と考えるのが自然だ(米英は決して公表しないだろうが)。
日本メディアの多くは、旗艦の撃沈というニュースをなぜ的確に報道できないのか。きつい言い方をすれば、この間、戦争というものにきちんと向き合おうとせず、現場に記者を出して鍛えることを怠ってきたからではないか。
2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した際、首都キーウ(キエフ)から情報を発信した日本の報道機関は共同通信くらいだった。ほかは、安全なウクライナ西部やポーランドに記者を退避させた。キーウ周辺からロシア軍が撤退し、各国の外交官が戻ってきた時点でおずおずと記者を首都に送り込んだのが実情だ。
何かを報じようとするなら、可能な限り現場へ。そこで何が起きているのか、自分の目で見、話を聞いて伝えなければならない。それが報道機関に課せられた使命である。だが、日本の主要メディアの多くはその役割を放棄した。「原稿より健康」が大事であり、「命は何ものにも代えがたい」からである。
お題目は立派だ。だが、ギリギリまで現場に肉薄するという覚悟なしに戦争を伝えることができるのか。極限近くまで追い込まれるから、記者は「戦争とは何か」を深く考え、その意味を知ろうと必死にもがく。その積み重ねが大事な時に生きてくるのだ。
欧米の記者たちは、かつてと同じように戦争の実相に迫る努力を重ねている。日本の報道機関の多くは「これまでしてきたこと」を放棄した。その結果が今回のウクライナ侵攻をめぐる報道の惨状であり、旗艦撃沈をめぐるトンチンカンな記事の数々ではないのか。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
【訂正】日米開戦時の連合艦隊の旗艦を「大和」と記しましたが、「長門」の誤りでした。訂正します(本文は訂正済み)。「大和」は1941年12月16日に就役し、連合艦隊の旗艦になったのは1942年2月からでした(2022年4月19日追記)。
*メールマガジン「風切通信 107」 2022年4月16日
*各紙の内容と見出しは、山形県内で16日に配られた新聞による。
≪写真説明とSource≫
◎ロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」
https://trafficnews.jp/post/117672

どちらの説明に説得力があるかは明らかだ。「モスクワ」はウクライナ軍によって撃沈されたのである。
日本の新聞はそれぞれこのニュースを伝えたが、核心をつく報道はきわめて少ない。朝日新聞は16日、ロシア国営タス通信の報道とウクライナ側の発表を並べたうえで、「炎上、沈没」「攻撃・防空両面で打撃」と報じた。読売新聞も「露艦隊、防空網に打撃」と伝えた。
巡洋艦「モスクワ」が攻撃、防御の両面で大きな役割を果たしていたことは間違いなく、従ってロシア黒海艦隊にとって「沈没が大きな痛手」であることは疑いない。だが、どちらの新聞も「もっとも重要なこと」にまるで触れていない。報道する記者たちが「艦隊にとって旗艦とはどういう意味を持つか」を理解していないからである。
旗艦が持つもっとも重要な機能は「作戦の立案・実行と指揮・命令の伝達」という点だ。旗艦には司令官だけでなく、艦隊全体の作戦を立案する高級参謀や情報分析・通信解析を行う情報将校が乗り込む。「艦隊の頭脳」が集中しており、彼らが必要とする電子機器や通信設備もすべてそろっている。
日米戦争の口火を切った真珠湾攻撃の戦史をひも解けば、連合艦隊の旗艦「長門」がどういう役割を果たしたかがよく分かる。航空母艦を中心とするハワイ攻撃の機動部隊をどう動かし、何を攻撃するか。作戦はすべて旗艦「長門」で立案され、命令・実行された。旗艦とは艦隊の「頭脳」であり、「中枢」なのだ。
敵を攻撃したり、敵の攻撃から味方を防御したりする機能は、ほかの軍艦をいくつか集めれば代替可能だ。だが、「頭脳」が破壊され、機能不全に陥った場合、それに取って代わるのは容易なことではない。極めて深刻な事態に陥る。
そういう観点から見た場合、手元にある16日付の新聞でその意味合いを的確に報じたのは産経新聞だけだった。「司令塔失い 作戦打撃」と大きな見出しで報じた。旗艦が撃沈されれば、「司令塔」が失われ、「中枢機能」がマヒする。つまり、ロシアの黒海艦隊は「頭脳」を吹き飛ばされてしまったのである。
ウクライナ側は対艦ミサイルで「モスクワ」を攻撃したようだが、攻撃するためには「モスクワ」の位置を正確に把握していなくてはならない。偵察衛星などを駆使して、その動向を的確に押さえているのはアメリカ軍であり、イギリス軍だろう。米英の軍事情報がウクライナ側にリアルタイムで伝えられた、と考えるのが自然だ(米英は決して公表しないだろうが)。
日本メディアの多くは、旗艦の撃沈というニュースをなぜ的確に報道できないのか。きつい言い方をすれば、この間、戦争というものにきちんと向き合おうとせず、現場に記者を出して鍛えることを怠ってきたからではないか。
2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した際、首都キーウ(キエフ)から情報を発信した日本の報道機関は共同通信くらいだった。ほかは、安全なウクライナ西部やポーランドに記者を退避させた。キーウ周辺からロシア軍が撤退し、各国の外交官が戻ってきた時点でおずおずと記者を首都に送り込んだのが実情だ。
何かを報じようとするなら、可能な限り現場へ。そこで何が起きているのか、自分の目で見、話を聞いて伝えなければならない。それが報道機関に課せられた使命である。だが、日本の主要メディアの多くはその役割を放棄した。「原稿より健康」が大事であり、「命は何ものにも代えがたい」からである。
お題目は立派だ。だが、ギリギリまで現場に肉薄するという覚悟なしに戦争を伝えることができるのか。極限近くまで追い込まれるから、記者は「戦争とは何か」を深く考え、その意味を知ろうと必死にもがく。その積み重ねが大事な時に生きてくるのだ。
欧米の記者たちは、かつてと同じように戦争の実相に迫る努力を重ねている。日本の報道機関の多くは「これまでしてきたこと」を放棄した。その結果が今回のウクライナ侵攻をめぐる報道の惨状であり、旗艦撃沈をめぐるトンチンカンな記事の数々ではないのか。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
【訂正】日米開戦時の連合艦隊の旗艦を「大和」と記しましたが、「長門」の誤りでした。訂正します(本文は訂正済み)。「大和」は1941年12月16日に就役し、連合艦隊の旗艦になったのは1942年2月からでした(2022年4月19日追記)。
*メールマガジン「風切通信 107」 2022年4月16日
*各紙の内容と見出しは、山形県内で16日に配られた新聞による。
≪写真説明とSource≫
◎ロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」
https://trafficnews.jp/post/117672
ウクライナに侵攻したロシア軍はキーウ(キエフ)の制圧に失敗し、首都近郊から撤退した。それに伴って首都近郊の街や村はウクライナ軍が掌握し、欧米のメディアによって戦闘状況を示す多数の映像が送られてきている。

それを見て気づくのは、ロシア軍の戦闘車両の残骸の多くが兵員輸送用の装甲車や軽武装の車両であることだ。ウクライナ軍によって破壊され、焼けただれた多数の装甲車が映っている。その一方で、砲を備えた戦車の残骸は少ない。
1980年代末から90年代にかけてアフガニスタン戦争を取材した際、私は記者として首都カブールの郊外や首都から北部に通じるサラン街道の戦闘状況をつぶさに見て回った。戦車や装甲車、軍用トラックの残骸も数えきれないほど目にした。その経験から言えるのは、キーウ近郊のこの戦闘状況は「きわめて異様」ということだ。
兵員輸送用の装甲車は、文字通り兵士を輸送するための車両なので装甲は薄っぺらだ。兵装も機関銃を備えているくらいで弱々しい。当然のことながら、敵の攻撃に対しても弱い。機関銃の弾を跳ね返すくらいがせいぜいだ。従って、装甲車は戦車部隊が敵を掃討した後から進んでいく、というのが一般的だ。
ところが、首都キーウ近郊の攻防でロシア軍は戦車の大部隊を突入させるのではなく、軽武装の戦闘車両や装甲車を連ねて進み、ウクライナ軍の反撃で多数の車両を破壊された、と思われる。なぜ、そんなことになってしまったのか。
軍事専門家は「ロシアはウクライナを甘く見ていた」と分析している。2014年にクリミア半島を攻撃して占領した際、ウクライナ軍は総崩れに近い状態になり、ロシア軍は強い抵抗を受けることなく半島を制圧した。今回も「ウクライナ軍はすぐに崩れる」と見ていたのではないか。
ゼレンスキー大統領はもともと喜劇タレントで、政治経験はまるでない。ウクライナの腐敗した政治を風刺したテレビドラマで大人気になり、その勢いで大統領選挙に勝っただけ。ロシア軍が攻め込めばすぐに逃げ出す――そう判断して、侵攻すれば首都キーウにも比較的たやすく入っていける、と考えたとしか思えない。
ところが、現実はまるで違った。クリミア半島の住民は6割近くがロシア人で、ウクライナ人は24%と少数派だった。だが、首都キーウとその近郊はウクライナ人が圧倒的多数を占める。クリミアとはまるで事情が異なる。「自分たちの土地」なのだ。
ウクライナ軍もこの8年の間に立て直しを図り、ロシアの侵攻に対して身構えていた。欧米の情報機関からも「ロシア軍の作戦と動き」について十分な情報を得ていた節がある。戦意もきわめて高く、十分に備えていたのである。
ロシア軍によるキーウ制圧の失敗は、甘い状況判断と稚拙な作戦の結果であり、兵員輸送用の装甲車の多数の残骸はそれを如実に示している。ロシア兵の多くは銃を構える前に、装甲車の中で死んでいったのではないか。
犠牲者の多さに驚愕し、ロシア軍は非戦闘員である普通の住民の拘束や殺害に及んだ可能性がある。そうだとすれば、ウクライナ侵攻を立案し、遂行したプーチン大統領をはじめとするロシア指導部の責任はなおさら重い。
ロシア軍は作戦を練り直し、今後はウクライナ東部の制圧に力を注ぐと伝えられている。作戦の指揮を執る司令官も、シリア内戦で実績のあるドボルニコフ将軍に交代させたという。初期段階での失敗を認めたということだろう。
ロシア軍によるウクライナ侵攻がこれからどのような経過をたどるかは、不確定要素があまりにも多く、見通すのは難しい。核兵器や生物化学兵器が使われる恐れも排除できない。だが、少なくとも「プーチンの思惑通りに進む」ことはあるまい。
ウクライナ、ロシア双方におびただしい戦死者を出し、多数の民間人を殺害して、ロシアは何を得ようするのか。得られるのは「NATOの東方への拡大の阻止」と「ウクライナの中立化」くらいではないのか。
だとしたら、ウクライナ側が失う人命と社会インフラの破壊、ロシア側が失う人命と国際的な信用の失墜はあまりにも多く、大きい。それでも、ロシア国民は「プーチンは正しい」と言い続けるのだろうか。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信106」 2022年4月11日
≪写真説明とSource≫
◎破壊されたロシアの装甲車=4月4日、キーウ西郊ブチャ/Aris Messinis/AFP/Getty Images(CNNのサイトから)
https://www.cnn.co.jp/photo/l/1057048.html

それを見て気づくのは、ロシア軍の戦闘車両の残骸の多くが兵員輸送用の装甲車や軽武装の車両であることだ。ウクライナ軍によって破壊され、焼けただれた多数の装甲車が映っている。その一方で、砲を備えた戦車の残骸は少ない。
1980年代末から90年代にかけてアフガニスタン戦争を取材した際、私は記者として首都カブールの郊外や首都から北部に通じるサラン街道の戦闘状況をつぶさに見て回った。戦車や装甲車、軍用トラックの残骸も数えきれないほど目にした。その経験から言えるのは、キーウ近郊のこの戦闘状況は「きわめて異様」ということだ。
兵員輸送用の装甲車は、文字通り兵士を輸送するための車両なので装甲は薄っぺらだ。兵装も機関銃を備えているくらいで弱々しい。当然のことながら、敵の攻撃に対しても弱い。機関銃の弾を跳ね返すくらいがせいぜいだ。従って、装甲車は戦車部隊が敵を掃討した後から進んでいく、というのが一般的だ。
ところが、首都キーウ近郊の攻防でロシア軍は戦車の大部隊を突入させるのではなく、軽武装の戦闘車両や装甲車を連ねて進み、ウクライナ軍の反撃で多数の車両を破壊された、と思われる。なぜ、そんなことになってしまったのか。
軍事専門家は「ロシアはウクライナを甘く見ていた」と分析している。2014年にクリミア半島を攻撃して占領した際、ウクライナ軍は総崩れに近い状態になり、ロシア軍は強い抵抗を受けることなく半島を制圧した。今回も「ウクライナ軍はすぐに崩れる」と見ていたのではないか。
ゼレンスキー大統領はもともと喜劇タレントで、政治経験はまるでない。ウクライナの腐敗した政治を風刺したテレビドラマで大人気になり、その勢いで大統領選挙に勝っただけ。ロシア軍が攻め込めばすぐに逃げ出す――そう判断して、侵攻すれば首都キーウにも比較的たやすく入っていける、と考えたとしか思えない。
ところが、現実はまるで違った。クリミア半島の住民は6割近くがロシア人で、ウクライナ人は24%と少数派だった。だが、首都キーウとその近郊はウクライナ人が圧倒的多数を占める。クリミアとはまるで事情が異なる。「自分たちの土地」なのだ。
ウクライナ軍もこの8年の間に立て直しを図り、ロシアの侵攻に対して身構えていた。欧米の情報機関からも「ロシア軍の作戦と動き」について十分な情報を得ていた節がある。戦意もきわめて高く、十分に備えていたのである。
ロシア軍によるキーウ制圧の失敗は、甘い状況判断と稚拙な作戦の結果であり、兵員輸送用の装甲車の多数の残骸はそれを如実に示している。ロシア兵の多くは銃を構える前に、装甲車の中で死んでいったのではないか。
犠牲者の多さに驚愕し、ロシア軍は非戦闘員である普通の住民の拘束や殺害に及んだ可能性がある。そうだとすれば、ウクライナ侵攻を立案し、遂行したプーチン大統領をはじめとするロシア指導部の責任はなおさら重い。
ロシア軍は作戦を練り直し、今後はウクライナ東部の制圧に力を注ぐと伝えられている。作戦の指揮を執る司令官も、シリア内戦で実績のあるドボルニコフ将軍に交代させたという。初期段階での失敗を認めたということだろう。
ロシア軍によるウクライナ侵攻がこれからどのような経過をたどるかは、不確定要素があまりにも多く、見通すのは難しい。核兵器や生物化学兵器が使われる恐れも排除できない。だが、少なくとも「プーチンの思惑通りに進む」ことはあるまい。
ウクライナ、ロシア双方におびただしい戦死者を出し、多数の民間人を殺害して、ロシアは何を得ようするのか。得られるのは「NATOの東方への拡大の阻止」と「ウクライナの中立化」くらいではないのか。
だとしたら、ウクライナ側が失う人命と社会インフラの破壊、ロシア側が失う人命と国際的な信用の失墜はあまりにも多く、大きい。それでも、ロシア国民は「プーチンは正しい」と言い続けるのだろうか。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信106」 2022年4月11日
≪写真説明とSource≫
◎破壊されたロシアの装甲車=4月4日、キーウ西郊ブチャ/Aris Messinis/AFP/Getty Images(CNNのサイトから)
https://www.cnn.co.jp/photo/l/1057048.html
戦争とは、生身の人間が集団で殺し合うことである。兵士の数が多く、武器をたくさん持つ方が有利なことは言うまでもない。だが、それにも増して重要なことがある。

それは、戦いに身を投じる一人ひとりの人間が「この戦争は命をかけるに値するか」と自問し、納得できるかどうかだ。自ら納得し、覚悟を決めた集団は侮(あなど)りがたい力を発揮する。
強大な軍事力を誇ったアメリカは、なぜベトナムで敗れたのか。1979年にアフガニスタンに侵攻したソ連軍は、なぜ全面撤退に追い込まれたのか。9・11テロの後、アフガンに攻め込んだ米軍も撤退せざるを得なかったのはなぜか。
それは、攻め込んだ米兵にもソ連兵にも命をかける理由が乏しく、一方でベトナム側とアフガン側には「自らの土地を守り、同胞を守る」という揺るぎない決意があったからである。戦いが長引けば長引くほど、その差は戦況に如実に表れていった。
ロシアによるウクライナ侵攻でも、同じことが起きている。ロシア兵の多くは、なぜここで戦わなければならないのか、戸惑っているのではないか。ウクライナの兵士たちの頑強な抵抗に「なぜ、ここまで」と驚愕しているのではないか。
この戦争が最終的にどのように決着するかは見通せない。だが、戦場で命をかけるのは一人ひとりの兵士であり、その兵士たちの「覚悟の差」が戦争の帰趨に大きな影響を及ぼすことをあらためて示すことになるだろう。
◇ ◇
古代東北の地で繰り広げられた蝦夷(えみし)と大和政権との戦争もまた、覚悟を決めた集団とそうでない集団との戦いだった。
戦争は、都が平城京(奈良)にあった774年から長岡京(京都)、平安京(同)と移った後の811年まで、足かけ38年に及んだ。その中で、戦う者たちの「覚悟の差」をもっともよく示しているのは、789年(延暦8年)の桓武天皇治下での第一次征討である。
それまでの戦いで苦杯をなめた朝廷側は、この征討で5万余りの兵を動員し、蝦夷の拠点である胆沢(いさわ)(岩手県南部)の制圧を目指した。迎え撃った蝦夷側の兵力は数千人と推定されている。兵力だけを見れば、朝廷側が圧倒的に優位に立っていた。
『続日本紀(しょくにほんぎ)』によれば、紀古佐美(きのこさみ)を征東将軍とする朝廷軍は北上川の西岸を北上し、支流の衣川を越えた地点に陣を構えた。蝦夷の指導者、アテルイ(阿弖流為)の拠点・胆沢が西岸にあったからである。
ところが、この時、蝦夷側は胆沢を捨て、東岸に陣を敷いた。このため、朝廷側は征討軍の一部を前軍と中軍、後軍の三つ分け、北上川を渡河(とか)する作戦を立てた。3軍それぞれ2000人で計6000人。これで十分と見たのだろう。
蝦夷側にはモレ(母禮)という優れた軍師がいたとされる。兵力の差は歴然としている。正面から戦いを挑んだのでは勝つのは難しい。そこで、朝廷軍を北上川の両岸に分断する策略をめぐらしたと思われる。
戦端が開かれたのは5月である。北上川は雪解け水で増水していた。6000人の将兵を舟やいかだで渡河させるのは容易なことではない。前軍の2000人は蝦夷側に妨害されて河を渡ることができず、東岸の巣伏(すふし)に達したのは中軍と後軍の4000人だけだった。
この後の蝦夷側の戦術も巧みだった。最初に迎え撃った300人ほどの部隊は小競り合いの後、後退した。朝廷軍は勢いに乗って追撃し、部隊は縦に長く延びた。そこに800人ほどの蝦夷が襲いかかり、さらに潜んでいた400人ほどが背後から挟撃した。
朝廷軍は総崩れになった。北上川に飛び込んで本隊に逃げ帰ろうとする者が続出し、1000人余りが溺死した。その数は戦死者をはるかに上回った。
蝦夷にとっては「自らの土地と生活を守る戦い」である。一方の朝廷軍は坂東や東海道の各地から徴兵された寄せ集めの部隊だ。双方の戦意の差は大きく、4000人の大部隊が1500人ほどの蝦夷に蹴散らされたのである。
征東将軍の紀古佐美は戦意を喪失し、ほどなく軍を解散した。にもかかわらず、『続日本紀』によれば、古佐美は朝廷に「戦さで蝦夷の田は荒れ果て、放置しても滅びる」「わが軍は兵糧の補給が困難で、これ以上戦うのは得策ではない」などと?戦勝?の報告を送った。
桓武天皇は激怒した。「蝦夷の首級は100に満たず、官軍の死傷は3000人にも上る」として報告を虚飾と断じ、敗戦の責任を追及している。
雪辱を果たすため、桓武天皇が794年の第二次征討で10万、801年の第三次征討で4万の軍勢を陸奥に送り込み、蝦夷の制圧に執念を燃やし続けたこと、さらにこの時期の正史である『日本後紀』の写本が欠落していて第二次、第三次征討の詳しいことがほとんど分からないことは、すでにお伝えした。
次々に押し寄せる大軍との戦いに疲れ果てたのか、アテルイとモレは802年、500人の部下を伴って征夷大将軍の坂上田村麻呂に投降した。2人は都に連行され、田村麻呂が助命を嘆願したものの朝廷は受け入れず、河内の杜山(もりやま)(大阪府枚方市)で処刑された。
◇ ◇
「覚悟」を固めたとて、勝てない戦さもある。指導者と軍師は賊徒として斬首された。だが、朝廷がどのように貶(おとし)めようと、忘れ去られることはなかった。人々はアテルイとモレたちの戦いに心を揺さぶられ、語り継いできた。
京都の清水寺に「北天の雄 阿弖流為 母禮之碑」が建てられたのは1994年、平安遷都から1200年後のことである。関西在住の水沢市や胆沢町などの出身者で作る同郷会が資金を募って建立した。

清水寺は、蝦夷と戦い続けた坂上田村麻呂が創建したと伝えられる。戦いながらも蝦夷の窮状に心を寄せたとされる田村麻呂の思いをくんで、当時の貫主が快諾したという。
岩手県の地元紙、胆江(たんこう)日日新聞も供養碑設立の運動を支え、その除幕式の様子を「蘇った古代東北の歴史」「この日はあいにくの雨模様だったが、関係者の表情は晴れやかだった」と報じた。同郷会の会長、高橋敏男(故人)は同紙に「5年の際月をかけたことだけに、感慨も無量」と語っている(1994年11月7日付)。
水沢市と江刺市、胆沢町など5市町村は2006年に合併して奥州市になった。北上川の河畔には、延暦8年にアテルイらが朝廷軍を敗走させた「巣伏(すふし)の戦い」を記念する櫓(やぐら)と碑が建てられ、地域おこしのシンボルになっている。
岩手出身の作家、高橋克彦は1999年に小説『火怨 北の輝星アテルイ』を出版し、史書からこぼれ落ちた蝦夷たちの戦いに光を当てようと試みた。
「敵はほとんどが無理に徴集された兵ばかりで志など持っておらぬ。我ら蝦夷とは違う。我らは皆、親や子や美しい山や空を守るために戦っている」
「いかにも我らの暮らしは獣並みやも知れませぬ。白湯(さゆ)を啜(すす)り、わずかの芋を分け合うて凌(しの)いでおりまする。なれど獣にはあらず。人を獣と見下す者らに従って生きることなどできぬ」
こうした言葉はすべてフィクションである。だが、どの言葉にも北の大地から湧き出したような味わいがある。小説は吉川英治文学賞を受賞し、刷を重ねている。
この小説を基に、NHKは2013年の1月から2月にかけて、BS時代劇「アテルイ伝」を4回にわたって放送した。最終回で主演の大沢たかおが叫ぶ。「帝は我等(わあら)をなにゆえ憎む。なにゆえ殺す。同じ人ぞ。同じ人間ぞ」。深い問いだった。
2015年夏には歌舞伎で市川染五郎がアテルイを演じ、2年後、宝塚歌劇団のミュージカルとしても上演された。アテルイをテーマにした作品は読む者の心を揺さぶり、観る者の心をとらえてやまない。その生き方に、時を超えて語りかけてくるものがあるからだろう。
◇ ◇
歴史は勝者によって記され、勝者は自分たちに都合の悪いことには触れようとしない。だが、本当に大切なことは「触れられなかったこと」の中に埋もれているのかもしれない。古代東北の歴史を調べ、蝦夷が歩んだ道を思う時、心に浮かぶのは北アメリカの先住民たちがたどった運命である。
米国の人類学者ヘンリー・ドビンズによれば、コロンブスがアメリカ大陸に到達した15世紀当時、北米には推定で1000万人前後の先住民が暮らしていた。そこに移民としてやって来たのはヨーロッパで迫害され、貧困に打ちのめされた人たちだった。
1620年、イギリスからメイフラワー号でマサチューセッツ州のプリマスにたどり着いた101人の清教徒は、飢えと寒さで冬を越すことができず、春までに半数が亡くなった。
生き残った者たちに食糧を与え、トウモロコシやジャガイモの栽培法を教えて助けたのは、その地に暮らすワンパノアグ族の人たちである。「飢えた旅人には、自らの食を割いてでも手を差し伸べる」という古来の慣習に従ったのだった。
翌年の秋には豊かな収穫に恵まれ、白人たちは先住民と共に祝った。それがアメリカにおける感謝祭の始まりとされる。
だが、共に祝う日々はすぐに終わった。移民たちは「土地の所有」を主張し始めたからである。「大地や空は誰のものでもない」と考える先住民には理解できないことだった。
移民が持ち込んだ天然痘や赤痢、コレラといった伝染病も脅威となった。先住民には未知の病であり、治療のすべもないまま次々に倒れていった。
流入する移民と疫病が先住民を西へと追いやる。イギリスやフランス、スペインなど欧州の国々による植民地の争奪戦が始まり、先住民も巻き込まれていった。
1763年、英国王のジョージ3世が「英国の領土はアパラチア山脈まで。その西はインディアンの居住地」と宣言し、両者は住み分けることになったが、直後に独立戦争が勃発して宣言は雲散霧消した。
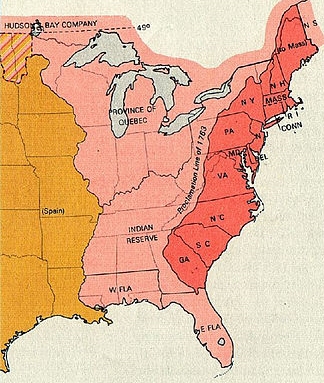
入植者は広い土地を求めてインディアンの居住地域に入り込む。金鉱が発見されれば、ならず者が殺到する。それを白人の側から描けば、「開拓を妨害するインディアン、騎兵隊と入植者がそれを追い払う」という、西部劇でおなじみの図式になる。
武力衝突が起きるたびに協定が結ばれたが、そうした約束が守られることはなかった。どのような協定が結ばれ、どのように破られていったのか。白人側が残した記録を基に、その内実を克明に記したのがディー・ブラウンの『わが魂を聖地に埋めよ』である。
非道な協定破りの数々。その典型の一つが「チェロキー族の涙の旅路」である。この部族は白人たちと戦うことをやめ、18世紀後半には指定されたジョージア州などの居住地に住んでいた。
ところが、居住地で金鉱が発見されるや、数万人が1000キロ離れたオクラホマ州に追いやられた。老人や女性、子どもを連れ、真冬に徒歩での旅。4人に1人が命を落とした。
戦うことをやめない部族には、容赦ない殺戮(さつりく)が待っていた。インディアンの戦士たちとの戦いが難渋すれば、騎兵隊は後背地にいる彼らの家族を殺害した。インディアンの人口は、19世紀末には25万人まで激減した。
軍隊と、家族を抱えた生活者との戦い・・・・。いかに決意が固かろうと、インディアンたちが抗(あらが)い続けることは困難だった。東北の蝦夷たちもまた、同じ苦しみを抱えて戦うしかなかった。
カナダ・アルバータ大学の教授、藤永茂は著書『アメリカ・インディアン悲史』に、彼らは「自分たちをあくまで大自然のほんの一部と看做(みな)す人たちだった」と記した。
「森に入れば無言の木々の誠実と愛に包まれた自分を感じ、スポーツとしての狩猟を受けいれず、奪い合うよりもわけ合うことをよろこびとし、欲望と競争心に支えられた勤勉を知らず、何よりもまず『生きる』ことを知っていた」
だから、「インディアン問題はインディアンたちの問題ではない。我々の問題である」と藤永はいう。
そうなのだ。古代東北の蝦夷たちの営為も、遠い歴史のかなたに置き去りにするわけにはいかない。彼らがたどった道は今を生きる私たちにつながり、さらに未来へと延びている。(敬称略)
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真・図の説明&Source≫
◎789年の第一次征討の合戦場となった北上川の河畔、巣伏(すふし)に建てられた櫓(奥州市水沢佐倉河字北田、筆者撮影)
◎京都の清水寺に建立されたアテルイと盟友モレの碑
yoritomo-japan.com
◎英国王の1763年宣言による英国領土とインディアン居住地の区分け図。英国の領土はアパラチア山脈まで、その西側はインディアン居住地とされた(ウィキペディアから)
≪参文献&サイト≫
◎『蝦夷と東北戦争』(鈴木拓也、吉川弘文館)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)
◎『阿弖流為 夷俘と号すること莫かるべし』(樋口知志、ミネルヴァ書房)
◎『火怨 北の輝星アテルイ』(高橋克彦、上下、講談社文庫)
◎『胆江日日新聞七十年史』(胆江日日新聞社)
◎清水寺の歴史(清水寺の公式サイトから)
https://www.kiyomizudera.or.jp/history.php
◎『アメリカ・インディアン悲史』(藤永茂、朝日新聞社)
◎『わが魂を聖地に埋めよ』(ディー・ブラウン、上下、草思社文庫)
◎『アメリカの歴史を知るための62章』(富田虎男、鵜月裕典、佐藤円編、明石書店)

それは、戦いに身を投じる一人ひとりの人間が「この戦争は命をかけるに値するか」と自問し、納得できるかどうかだ。自ら納得し、覚悟を決めた集団は侮(あなど)りがたい力を発揮する。
強大な軍事力を誇ったアメリカは、なぜベトナムで敗れたのか。1979年にアフガニスタンに侵攻したソ連軍は、なぜ全面撤退に追い込まれたのか。9・11テロの後、アフガンに攻め込んだ米軍も撤退せざるを得なかったのはなぜか。
それは、攻め込んだ米兵にもソ連兵にも命をかける理由が乏しく、一方でベトナム側とアフガン側には「自らの土地を守り、同胞を守る」という揺るぎない決意があったからである。戦いが長引けば長引くほど、その差は戦況に如実に表れていった。
ロシアによるウクライナ侵攻でも、同じことが起きている。ロシア兵の多くは、なぜここで戦わなければならないのか、戸惑っているのではないか。ウクライナの兵士たちの頑強な抵抗に「なぜ、ここまで」と驚愕しているのではないか。
この戦争が最終的にどのように決着するかは見通せない。だが、戦場で命をかけるのは一人ひとりの兵士であり、その兵士たちの「覚悟の差」が戦争の帰趨に大きな影響を及ぼすことをあらためて示すことになるだろう。
◇ ◇
古代東北の地で繰り広げられた蝦夷(えみし)と大和政権との戦争もまた、覚悟を決めた集団とそうでない集団との戦いだった。
戦争は、都が平城京(奈良)にあった774年から長岡京(京都)、平安京(同)と移った後の811年まで、足かけ38年に及んだ。その中で、戦う者たちの「覚悟の差」をもっともよく示しているのは、789年(延暦8年)の桓武天皇治下での第一次征討である。
それまでの戦いで苦杯をなめた朝廷側は、この征討で5万余りの兵を動員し、蝦夷の拠点である胆沢(いさわ)(岩手県南部)の制圧を目指した。迎え撃った蝦夷側の兵力は数千人と推定されている。兵力だけを見れば、朝廷側が圧倒的に優位に立っていた。
『続日本紀(しょくにほんぎ)』によれば、紀古佐美(きのこさみ)を征東将軍とする朝廷軍は北上川の西岸を北上し、支流の衣川を越えた地点に陣を構えた。蝦夷の指導者、アテルイ(阿弖流為)の拠点・胆沢が西岸にあったからである。
ところが、この時、蝦夷側は胆沢を捨て、東岸に陣を敷いた。このため、朝廷側は征討軍の一部を前軍と中軍、後軍の三つ分け、北上川を渡河(とか)する作戦を立てた。3軍それぞれ2000人で計6000人。これで十分と見たのだろう。
蝦夷側にはモレ(母禮)という優れた軍師がいたとされる。兵力の差は歴然としている。正面から戦いを挑んだのでは勝つのは難しい。そこで、朝廷軍を北上川の両岸に分断する策略をめぐらしたと思われる。
戦端が開かれたのは5月である。北上川は雪解け水で増水していた。6000人の将兵を舟やいかだで渡河させるのは容易なことではない。前軍の2000人は蝦夷側に妨害されて河を渡ることができず、東岸の巣伏(すふし)に達したのは中軍と後軍の4000人だけだった。
この後の蝦夷側の戦術も巧みだった。最初に迎え撃った300人ほどの部隊は小競り合いの後、後退した。朝廷軍は勢いに乗って追撃し、部隊は縦に長く延びた。そこに800人ほどの蝦夷が襲いかかり、さらに潜んでいた400人ほどが背後から挟撃した。
朝廷軍は総崩れになった。北上川に飛び込んで本隊に逃げ帰ろうとする者が続出し、1000人余りが溺死した。その数は戦死者をはるかに上回った。
蝦夷にとっては「自らの土地と生活を守る戦い」である。一方の朝廷軍は坂東や東海道の各地から徴兵された寄せ集めの部隊だ。双方の戦意の差は大きく、4000人の大部隊が1500人ほどの蝦夷に蹴散らされたのである。
征東将軍の紀古佐美は戦意を喪失し、ほどなく軍を解散した。にもかかわらず、『続日本紀』によれば、古佐美は朝廷に「戦さで蝦夷の田は荒れ果て、放置しても滅びる」「わが軍は兵糧の補給が困難で、これ以上戦うのは得策ではない」などと?戦勝?の報告を送った。
桓武天皇は激怒した。「蝦夷の首級は100に満たず、官軍の死傷は3000人にも上る」として報告を虚飾と断じ、敗戦の責任を追及している。
雪辱を果たすため、桓武天皇が794年の第二次征討で10万、801年の第三次征討で4万の軍勢を陸奥に送り込み、蝦夷の制圧に執念を燃やし続けたこと、さらにこの時期の正史である『日本後紀』の写本が欠落していて第二次、第三次征討の詳しいことがほとんど分からないことは、すでにお伝えした。
次々に押し寄せる大軍との戦いに疲れ果てたのか、アテルイとモレは802年、500人の部下を伴って征夷大将軍の坂上田村麻呂に投降した。2人は都に連行され、田村麻呂が助命を嘆願したものの朝廷は受け入れず、河内の杜山(もりやま)(大阪府枚方市)で処刑された。
◇ ◇
「覚悟」を固めたとて、勝てない戦さもある。指導者と軍師は賊徒として斬首された。だが、朝廷がどのように貶(おとし)めようと、忘れ去られることはなかった。人々はアテルイとモレたちの戦いに心を揺さぶられ、語り継いできた。
京都の清水寺に「北天の雄 阿弖流為 母禮之碑」が建てられたのは1994年、平安遷都から1200年後のことである。関西在住の水沢市や胆沢町などの出身者で作る同郷会が資金を募って建立した。

清水寺は、蝦夷と戦い続けた坂上田村麻呂が創建したと伝えられる。戦いながらも蝦夷の窮状に心を寄せたとされる田村麻呂の思いをくんで、当時の貫主が快諾したという。
岩手県の地元紙、胆江(たんこう)日日新聞も供養碑設立の運動を支え、その除幕式の様子を「蘇った古代東北の歴史」「この日はあいにくの雨模様だったが、関係者の表情は晴れやかだった」と報じた。同郷会の会長、高橋敏男(故人)は同紙に「5年の際月をかけたことだけに、感慨も無量」と語っている(1994年11月7日付)。
水沢市と江刺市、胆沢町など5市町村は2006年に合併して奥州市になった。北上川の河畔には、延暦8年にアテルイらが朝廷軍を敗走させた「巣伏(すふし)の戦い」を記念する櫓(やぐら)と碑が建てられ、地域おこしのシンボルになっている。
岩手出身の作家、高橋克彦は1999年に小説『火怨 北の輝星アテルイ』を出版し、史書からこぼれ落ちた蝦夷たちの戦いに光を当てようと試みた。
「敵はほとんどが無理に徴集された兵ばかりで志など持っておらぬ。我ら蝦夷とは違う。我らは皆、親や子や美しい山や空を守るために戦っている」
「いかにも我らの暮らしは獣並みやも知れませぬ。白湯(さゆ)を啜(すす)り、わずかの芋を分け合うて凌(しの)いでおりまする。なれど獣にはあらず。人を獣と見下す者らに従って生きることなどできぬ」
こうした言葉はすべてフィクションである。だが、どの言葉にも北の大地から湧き出したような味わいがある。小説は吉川英治文学賞を受賞し、刷を重ねている。
この小説を基に、NHKは2013年の1月から2月にかけて、BS時代劇「アテルイ伝」を4回にわたって放送した。最終回で主演の大沢たかおが叫ぶ。「帝は我等(わあら)をなにゆえ憎む。なにゆえ殺す。同じ人ぞ。同じ人間ぞ」。深い問いだった。
2015年夏には歌舞伎で市川染五郎がアテルイを演じ、2年後、宝塚歌劇団のミュージカルとしても上演された。アテルイをテーマにした作品は読む者の心を揺さぶり、観る者の心をとらえてやまない。その生き方に、時を超えて語りかけてくるものがあるからだろう。
◇ ◇
歴史は勝者によって記され、勝者は自分たちに都合の悪いことには触れようとしない。だが、本当に大切なことは「触れられなかったこと」の中に埋もれているのかもしれない。古代東北の歴史を調べ、蝦夷が歩んだ道を思う時、心に浮かぶのは北アメリカの先住民たちがたどった運命である。
米国の人類学者ヘンリー・ドビンズによれば、コロンブスがアメリカ大陸に到達した15世紀当時、北米には推定で1000万人前後の先住民が暮らしていた。そこに移民としてやって来たのはヨーロッパで迫害され、貧困に打ちのめされた人たちだった。
1620年、イギリスからメイフラワー号でマサチューセッツ州のプリマスにたどり着いた101人の清教徒は、飢えと寒さで冬を越すことができず、春までに半数が亡くなった。
生き残った者たちに食糧を与え、トウモロコシやジャガイモの栽培法を教えて助けたのは、その地に暮らすワンパノアグ族の人たちである。「飢えた旅人には、自らの食を割いてでも手を差し伸べる」という古来の慣習に従ったのだった。
翌年の秋には豊かな収穫に恵まれ、白人たちは先住民と共に祝った。それがアメリカにおける感謝祭の始まりとされる。
だが、共に祝う日々はすぐに終わった。移民たちは「土地の所有」を主張し始めたからである。「大地や空は誰のものでもない」と考える先住民には理解できないことだった。
移民が持ち込んだ天然痘や赤痢、コレラといった伝染病も脅威となった。先住民には未知の病であり、治療のすべもないまま次々に倒れていった。
流入する移民と疫病が先住民を西へと追いやる。イギリスやフランス、スペインなど欧州の国々による植民地の争奪戦が始まり、先住民も巻き込まれていった。
1763年、英国王のジョージ3世が「英国の領土はアパラチア山脈まで。その西はインディアンの居住地」と宣言し、両者は住み分けることになったが、直後に独立戦争が勃発して宣言は雲散霧消した。
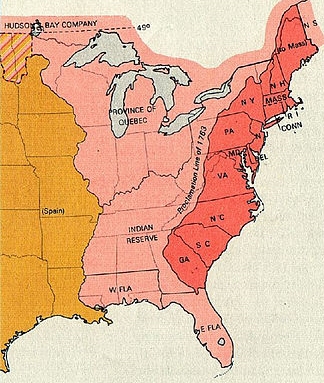
入植者は広い土地を求めてインディアンの居住地域に入り込む。金鉱が発見されれば、ならず者が殺到する。それを白人の側から描けば、「開拓を妨害するインディアン、騎兵隊と入植者がそれを追い払う」という、西部劇でおなじみの図式になる。
武力衝突が起きるたびに協定が結ばれたが、そうした約束が守られることはなかった。どのような協定が結ばれ、どのように破られていったのか。白人側が残した記録を基に、その内実を克明に記したのがディー・ブラウンの『わが魂を聖地に埋めよ』である。
非道な協定破りの数々。その典型の一つが「チェロキー族の涙の旅路」である。この部族は白人たちと戦うことをやめ、18世紀後半には指定されたジョージア州などの居住地に住んでいた。
ところが、居住地で金鉱が発見されるや、数万人が1000キロ離れたオクラホマ州に追いやられた。老人や女性、子どもを連れ、真冬に徒歩での旅。4人に1人が命を落とした。
戦うことをやめない部族には、容赦ない殺戮(さつりく)が待っていた。インディアンの戦士たちとの戦いが難渋すれば、騎兵隊は後背地にいる彼らの家族を殺害した。インディアンの人口は、19世紀末には25万人まで激減した。
軍隊と、家族を抱えた生活者との戦い・・・・。いかに決意が固かろうと、インディアンたちが抗(あらが)い続けることは困難だった。東北の蝦夷たちもまた、同じ苦しみを抱えて戦うしかなかった。
カナダ・アルバータ大学の教授、藤永茂は著書『アメリカ・インディアン悲史』に、彼らは「自分たちをあくまで大自然のほんの一部と看做(みな)す人たちだった」と記した。
「森に入れば無言の木々の誠実と愛に包まれた自分を感じ、スポーツとしての狩猟を受けいれず、奪い合うよりもわけ合うことをよろこびとし、欲望と競争心に支えられた勤勉を知らず、何よりもまず『生きる』ことを知っていた」
だから、「インディアン問題はインディアンたちの問題ではない。我々の問題である」と藤永はいう。
そうなのだ。古代東北の蝦夷たちの営為も、遠い歴史のかなたに置き去りにするわけにはいかない。彼らがたどった道は今を生きる私たちにつながり、さらに未来へと延びている。(敬称略)
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真・図の説明&Source≫
◎789年の第一次征討の合戦場となった北上川の河畔、巣伏(すふし)に建てられた櫓(奥州市水沢佐倉河字北田、筆者撮影)
◎京都の清水寺に建立されたアテルイと盟友モレの碑
yoritomo-japan.com
◎英国王の1763年宣言による英国領土とインディアン居住地の区分け図。英国の領土はアパラチア山脈まで、その西側はインディアン居住地とされた(ウィキペディアから)
≪参文献&サイト≫
◎『蝦夷と東北戦争』(鈴木拓也、吉川弘文館)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)
◎『阿弖流為 夷俘と号すること莫かるべし』(樋口知志、ミネルヴァ書房)
◎『火怨 北の輝星アテルイ』(高橋克彦、上下、講談社文庫)
◎『胆江日日新聞七十年史』(胆江日日新聞社)
◎清水寺の歴史(清水寺の公式サイトから)
https://www.kiyomizudera.or.jp/history.php
◎『アメリカ・インディアン悲史』(藤永茂、朝日新聞社)
◎『わが魂を聖地に埋めよ』(ディー・ブラウン、上下、草思社文庫)
◎『アメリカの歴史を知るための62章』(富田虎男、鵜月裕典、佐藤円編、明石書店)
大昔、東北の地で暮らす人々のことを大和政権側は「えみし」と呼んだ。なぜ、そう呼んでいたのかについては諸説あるが、定説はなく、不明である。

「蔑称だった」と唱える研究者もいる。だが、違うだろう。7世紀、飛鳥時代に権勢を誇った蘇我一族に蘇我蝦夷(えみし)がおり、当時はほかにも「えみし」の名を持つ貴族がいた。蔑称を名前にする貴族はいない、と考えるのが自然だからだ。
大和政権が編纂した正史に「えみし」という言葉が初めて登場するのは、『日本書紀』の神武天皇紀である。神武紀の中に大和の軍人たちが戦勝を祝って口にした次のような歌謡が収められている(注)。
愛瀰詩烏(えみしを)毘攮利(ひたり)
毛々那比苔(ももなひと)
比苔破易陪廼毛(ひとはいへども)
多牟伽毘毛勢儒(たむかひもせず)
「えみしは一人で百人を相手にするほど強いと人は言うけれど、俺たちには抵抗もしない」という意味である。古代から、「えみし」の戦闘能力の高さは恐れられていたようだが、「俺たちはそれよりもっと強い」と歌いあげているのだ。
日本書紀は全文、漢文で書かれている。ただ、こうした歌謡については言葉をそのまま借字で収録している。その際、「えみし」を「愛瀰詩」と記したことから見ても、蔑称という見方は的外れであることが分かる。
ただ、時を経るにつれて、「えみし」は「毛人」あるいは「蝦夷」と表記されるようになる。大和政権との軋轢が増し、戦争が続く中で「侮蔑」の意味合いが込められるようになっていったと考えられる。
◇ ◇
大和政権は7世紀に入ると東北の支配領域を急速に広げ、蝦夷勢力と激しく衝突するようになった。城冊(じょうさく)を築き、守るため各地から多くの移民を送り込む。蝦夷側では抵抗することをあきらめ、帰順して大和政権の下で生きる道を選ぶ者も増えていった。
8世紀の後半になると、大和側の支配は宮城県北部に達した。その最前線に築かれたのが桃生(ものう)城(現在の石巻市)と伊治(これはり)城(栗原市)であり、支配をさらに北へ広げるための前進基地だった(図参照)。

774年、摩擦は発火点に達し、38年戦争に突入していく。最初に蜂起したのは、宮城県北部から三陸地方に住む「海道(かいどう)蝦夷」だ。桃生城を攻撃して城郭の一部を焼き払った。帰順した蝦夷の一部も造反し、大和側は大混乱に陥る。
蝦夷を戦争へと駆り立てたものは何だったのか。自らの生活圏が侵食されていくことへの焦慮、大和政権の官人による収奪と腐敗、そして侮蔑だったのではないか。
近畿大学の鈴木拓也教授は著書『蝦夷と東北戦争』で、陸奥・出羽両国から天皇に献上されたものとして馬と鷹を挙げている。鷹狩りは当時の天皇家にとって重要な行事の一つである。軍馬の重要性は言うまでもない。
また、交易品として陸奥の砂金や毛皮、昆布を挙げる。熊やアシカ、アザラシの毛皮は都の貴族にことのほか喜ばれた。現地の官人は公式ルートで献上するほか、私的な取引にも精を出していたようだ。『続日本後紀』には、任期を終えて帰京する国司が大量の「私荷」を運んだことが記されているという。
辺境に赴任した官人による収奪や腐敗は、洋の東西を問わない。そして、彼らの住民への横暴と侮蔑もまた、繰り返されてきたことである。
大和政権に帰順し、現地の蝦夷を束ねてきた族長たちは屈折した思いを抱いていたに違いない。官人の横暴にさらされる配下の者たちからは突き上げられ、北方で抵抗し続ける蝦夷からは「裏切者」扱い・・。
そうした蝦夷の族長の一人、伊治呰麻呂(これはりのあざまろ)が780年、ついに反旗をひるがえす。伊治城で陸奥の最高責任者、紀広純らを殺害し、さらに反乱軍を率いて多賀城を略奪、焼き討ちにしたのである。
大和政権にとって、多賀城は陸奥・出羽を支配するための最大の拠点である。武器や兵糧も大量に蓄えられていた。それらをすべて奪われ、城も焼け落ちてしまった。城下の民衆も四散した。
反乱の急報が都に届いたのは6日後である。光仁天皇はただちに征東大使や副使らを任命し、坂東諸国に数万の兵の動員を命じた。それまで、陸奥と出羽の治安は現地の兵力でまかなってきたが、それでは対応できなくなり、蝦夷政策の転換を余儀なくされた。
その翌年、光仁天皇は高齢と病気のため譲位し、桓武天皇が即位した。大和政権と蝦夷勢力が全面対決の状態になるのは、この桓武天皇の治世下である。
軍の動員もけた違いになる。789年の第一次征討で5万、794年の第二次征討では10万、801年の第三次征討でも4万の兵力を投入した。徴兵は坂東にとどまらず東海道の諸国にも及び、兵糧も各地から調達した。
征討の対象は、アテルイ(阿弖流為)が率いる胆沢(いさわ=岩手県南部)の蝦夷である。38年戦争の発端も呰麻呂の反乱もその背後にいたのは胆沢の蝦夷勢力、と大和側は見ていた。
第一次征討が蝦夷勢力の巧みな作戦で惨敗に終わったことはすでに紹介した。北上川を挟んでの戦いで朝廷側は1000人余の溺死者を出し、指揮官まで逃げ出す醜態をさらした。桓武天皇が激怒したのは言うまでもない。
苦い教訓を踏まえて、第二次征討は兵力を倍増し、陣立ても一新した。征東大使に大友弟麻呂、副使には百済王俊哲や坂上田村麻呂ら4人を充て、地方の豪族を指揮官として抜擢した。
ただ、第二次と第三次征討については、これを記録したはずの『日本後紀』が欠落(全40巻のうち10巻のみ現存)しており、詳しいことは分からない。
関連史料によって、第二次征討では朝廷側が勝利したものの胆沢は陥落しなかったこと、坂上田村麻呂が征夷大将軍として率いた第三次征討についても、アテルイが500人の蝦夷を連れて投降し、胆沢が陥落したことが分かる程度だ(アテルイは都に連行され、802年に処刑)。38年戦争のもっとも重要な部分は、正史の欠落によって知り得ないのである。
◇ ◇
桓武天皇は大規模な軍事遠征で東北の蝦夷勢力を屈服させ、朝廷の支配領域を北へ大きく広げた。裏返せば、東北の蝦夷は再び立ち上がれないほどの打撃を受けた。
しかも、三次にわたる遠征によって多数の蝦夷が囚われの身になり、「俘囚(ふしゅう)」として関東や西日本の各地に移送された。移送は陸奥と出羽を除いた全国64カ国のうちの7割に及ぶ。その総数は万単位と見て、間違いない。
俘囚の一部は、九州の太宰府で防人として生きる道を与えられたりしたが、大多数は集落の外れの狭い土地に収容され、悲惨な境遇に落とされた。当然のことながら、周辺の大和側の住民との軋轢も絶えなかった。
移送先からの逃亡や騒乱も相次いだ。記録に残るだけでも、814年に出雲、848年に上総(かずさ)、875年に下総(しもうさ)と下野(しもつけ)、883年に上総で俘囚の反乱が起きている。下野の反乱では100人以上の俘囚が殺された。
彼らの多くは田を与えられなかった。従って、コメを収める租は課されなかったが、特産品や布を納める調庸の義務はあった。それも容易には納められなかった。
徴収がままならない事情について、798年の太政官符は次のように記している。
「俘囚たちは常に旧来の習俗を保ち、未だに野心(荒々しい心)を改めようとしません。狩猟と漁労を生業とし、養蚕を知りません。それだけでなく、居住地が定まらず、雲のように浮遊しています」(『蝦夷と東北戦争』)
隷属状態に追いやっておきながら、「雲のように浮遊」と責める。俘囚たちの心が静まるわけはなかった。
桓武天皇は「征夷の天皇」であると同時に、「造都の天皇」でもあった。都を平城京から長岡京に移し、さらに平安京に移した。これほどの大事業を二つも遂行したエネルギーのもとは何か。「数奇な運命」が桓武天皇を突き動かしたのかもしれない。
先帝の光仁天皇は、聖武(しょうむ)天皇の娘を皇后に迎えた。皇后には他戸(おさべ)親王という皇太子がいた。ところが、この皇后が「光仁天皇を呪詛した罪」でその地位を追われ、皇太子も廃された。2人は幽閉先で同じ日に謎の死を遂げる(藤原一族による陰謀・暗殺説がある)。
それによって、光仁天皇と百済系渡来人一族の女性との間に生まれた山部親王が急遽、皇太子になり、後に桓武天皇として即位することになるのである。天皇の生母は皇族か貴族の出という慣例がある中では異例の即位だった。
2002年の日韓共催サッカーワールドカップを前に、明仁天皇が「桓武天皇の生母が百済の武寧王(ぶねいおう)の子孫であると続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています」と発言し、話題になったが、それはこのことを指している。
二つの偉業を成し遂げることで「異例の即位」という陰口を吹き飛ばす。そんな思いがあったのかもしれない。
とはいえ、二つの大事業の負担は民衆に重くのしかかった。それは朝廷の屋台骨を揺るがしかねないほどだった。さすがの桓武天皇も第四次の征討はあきらめざるを得なかった。
811年の嵯峨天皇による征夷は、現地の陸奥・出羽の兵力だけで行われ、38年に及ぶ東北の戦火はようやく鎮まったのである。
(長岡 昇 : NPO「ブナの森」代表)
*注 日本書紀では「毘攮利」の部分の1文字目は「田へんに比」、2文字目は「手へん」ではなく「人べん」ですが、このブログでは転換できないため、それぞれこの文字で代用しました。「多牟伽毘」の4文字目も「田へんに比」です。
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真、図の説明&Source≫
(写真) 京都の清水寺にあるアテルイと盟友モレの碑。1994年、平安遷都1200年を記念して有志が建立した
https://www.yoritomo-japan.com/nara-kyoto/kiyomizudera/kiyomizudera-arutei.htm
(図) 海道蝦夷と山道蝦夷の居住範囲(『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』から複写
≪参考文献≫
◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)
◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)
◎『日本書紀?』((坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫)
◎『校本日本書紀 一 神代巻』(國學院大學日本文化研究所編、角川書店)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)
◎『蝦夷と東北戦争』(鈴木拓也、吉川弘文館)

「蔑称だった」と唱える研究者もいる。だが、違うだろう。7世紀、飛鳥時代に権勢を誇った蘇我一族に蘇我蝦夷(えみし)がおり、当時はほかにも「えみし」の名を持つ貴族がいた。蔑称を名前にする貴族はいない、と考えるのが自然だからだ。
大和政権が編纂した正史に「えみし」という言葉が初めて登場するのは、『日本書紀』の神武天皇紀である。神武紀の中に大和の軍人たちが戦勝を祝って口にした次のような歌謡が収められている(注)。
愛瀰詩烏(えみしを)毘攮利(ひたり)
毛々那比苔(ももなひと)
比苔破易陪廼毛(ひとはいへども)
多牟伽毘毛勢儒(たむかひもせず)
「えみしは一人で百人を相手にするほど強いと人は言うけれど、俺たちには抵抗もしない」という意味である。古代から、「えみし」の戦闘能力の高さは恐れられていたようだが、「俺たちはそれよりもっと強い」と歌いあげているのだ。
日本書紀は全文、漢文で書かれている。ただ、こうした歌謡については言葉をそのまま借字で収録している。その際、「えみし」を「愛瀰詩」と記したことから見ても、蔑称という見方は的外れであることが分かる。
ただ、時を経るにつれて、「えみし」は「毛人」あるいは「蝦夷」と表記されるようになる。大和政権との軋轢が増し、戦争が続く中で「侮蔑」の意味合いが込められるようになっていったと考えられる。
◇ ◇
大和政権は7世紀に入ると東北の支配領域を急速に広げ、蝦夷勢力と激しく衝突するようになった。城冊(じょうさく)を築き、守るため各地から多くの移民を送り込む。蝦夷側では抵抗することをあきらめ、帰順して大和政権の下で生きる道を選ぶ者も増えていった。
8世紀の後半になると、大和側の支配は宮城県北部に達した。その最前線に築かれたのが桃生(ものう)城(現在の石巻市)と伊治(これはり)城(栗原市)であり、支配をさらに北へ広げるための前進基地だった(図参照)。

774年、摩擦は発火点に達し、38年戦争に突入していく。最初に蜂起したのは、宮城県北部から三陸地方に住む「海道(かいどう)蝦夷」だ。桃生城を攻撃して城郭の一部を焼き払った。帰順した蝦夷の一部も造反し、大和側は大混乱に陥る。
蝦夷を戦争へと駆り立てたものは何だったのか。自らの生活圏が侵食されていくことへの焦慮、大和政権の官人による収奪と腐敗、そして侮蔑だったのではないか。
近畿大学の鈴木拓也教授は著書『蝦夷と東北戦争』で、陸奥・出羽両国から天皇に献上されたものとして馬と鷹を挙げている。鷹狩りは当時の天皇家にとって重要な行事の一つである。軍馬の重要性は言うまでもない。
また、交易品として陸奥の砂金や毛皮、昆布を挙げる。熊やアシカ、アザラシの毛皮は都の貴族にことのほか喜ばれた。現地の官人は公式ルートで献上するほか、私的な取引にも精を出していたようだ。『続日本後紀』には、任期を終えて帰京する国司が大量の「私荷」を運んだことが記されているという。
辺境に赴任した官人による収奪や腐敗は、洋の東西を問わない。そして、彼らの住民への横暴と侮蔑もまた、繰り返されてきたことである。
大和政権に帰順し、現地の蝦夷を束ねてきた族長たちは屈折した思いを抱いていたに違いない。官人の横暴にさらされる配下の者たちからは突き上げられ、北方で抵抗し続ける蝦夷からは「裏切者」扱い・・。
そうした蝦夷の族長の一人、伊治呰麻呂(これはりのあざまろ)が780年、ついに反旗をひるがえす。伊治城で陸奥の最高責任者、紀広純らを殺害し、さらに反乱軍を率いて多賀城を略奪、焼き討ちにしたのである。
大和政権にとって、多賀城は陸奥・出羽を支配するための最大の拠点である。武器や兵糧も大量に蓄えられていた。それらをすべて奪われ、城も焼け落ちてしまった。城下の民衆も四散した。
反乱の急報が都に届いたのは6日後である。光仁天皇はただちに征東大使や副使らを任命し、坂東諸国に数万の兵の動員を命じた。それまで、陸奥と出羽の治安は現地の兵力でまかなってきたが、それでは対応できなくなり、蝦夷政策の転換を余儀なくされた。
その翌年、光仁天皇は高齢と病気のため譲位し、桓武天皇が即位した。大和政権と蝦夷勢力が全面対決の状態になるのは、この桓武天皇の治世下である。
軍の動員もけた違いになる。789年の第一次征討で5万、794年の第二次征討では10万、801年の第三次征討でも4万の兵力を投入した。徴兵は坂東にとどまらず東海道の諸国にも及び、兵糧も各地から調達した。
征討の対象は、アテルイ(阿弖流為)が率いる胆沢(いさわ=岩手県南部)の蝦夷である。38年戦争の発端も呰麻呂の反乱もその背後にいたのは胆沢の蝦夷勢力、と大和側は見ていた。
第一次征討が蝦夷勢力の巧みな作戦で惨敗に終わったことはすでに紹介した。北上川を挟んでの戦いで朝廷側は1000人余の溺死者を出し、指揮官まで逃げ出す醜態をさらした。桓武天皇が激怒したのは言うまでもない。
苦い教訓を踏まえて、第二次征討は兵力を倍増し、陣立ても一新した。征東大使に大友弟麻呂、副使には百済王俊哲や坂上田村麻呂ら4人を充て、地方の豪族を指揮官として抜擢した。
ただ、第二次と第三次征討については、これを記録したはずの『日本後紀』が欠落(全40巻のうち10巻のみ現存)しており、詳しいことは分からない。
関連史料によって、第二次征討では朝廷側が勝利したものの胆沢は陥落しなかったこと、坂上田村麻呂が征夷大将軍として率いた第三次征討についても、アテルイが500人の蝦夷を連れて投降し、胆沢が陥落したことが分かる程度だ(アテルイは都に連行され、802年に処刑)。38年戦争のもっとも重要な部分は、正史の欠落によって知り得ないのである。
◇ ◇
桓武天皇は大規模な軍事遠征で東北の蝦夷勢力を屈服させ、朝廷の支配領域を北へ大きく広げた。裏返せば、東北の蝦夷は再び立ち上がれないほどの打撃を受けた。
しかも、三次にわたる遠征によって多数の蝦夷が囚われの身になり、「俘囚(ふしゅう)」として関東や西日本の各地に移送された。移送は陸奥と出羽を除いた全国64カ国のうちの7割に及ぶ。その総数は万単位と見て、間違いない。
俘囚の一部は、九州の太宰府で防人として生きる道を与えられたりしたが、大多数は集落の外れの狭い土地に収容され、悲惨な境遇に落とされた。当然のことながら、周辺の大和側の住民との軋轢も絶えなかった。
移送先からの逃亡や騒乱も相次いだ。記録に残るだけでも、814年に出雲、848年に上総(かずさ)、875年に下総(しもうさ)と下野(しもつけ)、883年に上総で俘囚の反乱が起きている。下野の反乱では100人以上の俘囚が殺された。
彼らの多くは田を与えられなかった。従って、コメを収める租は課されなかったが、特産品や布を納める調庸の義務はあった。それも容易には納められなかった。
徴収がままならない事情について、798年の太政官符は次のように記している。
「俘囚たちは常に旧来の習俗を保ち、未だに野心(荒々しい心)を改めようとしません。狩猟と漁労を生業とし、養蚕を知りません。それだけでなく、居住地が定まらず、雲のように浮遊しています」(『蝦夷と東北戦争』)
隷属状態に追いやっておきながら、「雲のように浮遊」と責める。俘囚たちの心が静まるわけはなかった。
桓武天皇は「征夷の天皇」であると同時に、「造都の天皇」でもあった。都を平城京から長岡京に移し、さらに平安京に移した。これほどの大事業を二つも遂行したエネルギーのもとは何か。「数奇な運命」が桓武天皇を突き動かしたのかもしれない。
先帝の光仁天皇は、聖武(しょうむ)天皇の娘を皇后に迎えた。皇后には他戸(おさべ)親王という皇太子がいた。ところが、この皇后が「光仁天皇を呪詛した罪」でその地位を追われ、皇太子も廃された。2人は幽閉先で同じ日に謎の死を遂げる(藤原一族による陰謀・暗殺説がある)。
それによって、光仁天皇と百済系渡来人一族の女性との間に生まれた山部親王が急遽、皇太子になり、後に桓武天皇として即位することになるのである。天皇の生母は皇族か貴族の出という慣例がある中では異例の即位だった。
2002年の日韓共催サッカーワールドカップを前に、明仁天皇が「桓武天皇の生母が百済の武寧王(ぶねいおう)の子孫であると続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています」と発言し、話題になったが、それはこのことを指している。
二つの偉業を成し遂げることで「異例の即位」という陰口を吹き飛ばす。そんな思いがあったのかもしれない。
とはいえ、二つの大事業の負担は民衆に重くのしかかった。それは朝廷の屋台骨を揺るがしかねないほどだった。さすがの桓武天皇も第四次の征討はあきらめざるを得なかった。
811年の嵯峨天皇による征夷は、現地の陸奥・出羽の兵力だけで行われ、38年に及ぶ東北の戦火はようやく鎮まったのである。
(長岡 昇 : NPO「ブナの森」代表)
*注 日本書紀では「毘攮利」の部分の1文字目は「田へんに比」、2文字目は「手へん」ではなく「人べん」ですが、このブログでは転換できないため、それぞれこの文字で代用しました。「多牟伽毘」の4文字目も「田へんに比」です。
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真、図の説明&Source≫
(写真) 京都の清水寺にあるアテルイと盟友モレの碑。1994年、平安遷都1200年を記念して有志が建立した
https://www.yoritomo-japan.com/nara-kyoto/kiyomizudera/kiyomizudera-arutei.htm
(図) 海道蝦夷と山道蝦夷の居住範囲(『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』から複写
≪参考文献≫
◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)
◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)
◎『日本書紀?』((坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫)
◎『校本日本書紀 一 神代巻』(國學院大學日本文化研究所編、角川書店)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)
◎『蝦夷と東北戦争』(鈴木拓也、吉川弘文館)
ロシア軍がウクライナとの国境を越え、新しい戦争を始めた。ロシア側はまずウクライナの戦闘指揮所やレーダー施設を破壊し、航空優勢を確保したうえで、戦車などの地上部隊を大規模に展開しようとしている。

ロシアはこれまで、ウクライナ東部のロシア系住民が多い地域の武装勢力を支援してきた。今回の侵攻によって、ロシアはこの武装勢力が支配する地域を独立させて「友好的な地域」にしたうえで、ウクライナのほかの地域を「緩衝地帯」にすることを狙っているようだ。
アメリカのバイデン大統領は「この攻撃がもたらす死と破壊はロシアだけに責任がある」と非難した。岸田文雄首相はこれに同調し、「国際社会と連携して迅速に対処していく」と述べた。武力で自分の言い分を押し通そうとするロシアの行動は非難されて当然である。だが、バイデン大統領が言うように、この戦争の責任は「ロシアだけにある」のだろうか。
今回のロシア・ウクライナ戦争を考えるうえでのキーワードは「NATOの東方拡大」である。NATO(北大西洋条約機構)は、第2次世界大戦後にアメリカとイギリスがソ連と対峙するため西欧諸国を糾合して結成した「共産圏包囲軍事同盟」である。ソ連はワルシャワ条約機構を結成して、これに対抗した。
1989年に米ソの冷戦が終結し、1991年にソ連が崩壊したのだから、本来ならNATOは「新しい軍事同盟」に改編されるべきだった。だが、アメリカはその後もその基本的な構造を維持したまま、共産圏にあった東欧諸国を一つ、また一つとNATOに組み込んでいった。
ソ連崩壊後、ロシアは政治的にも経済的にも混乱状態に陥り、NATOの東方拡大に対処する余裕がなかった。NATOの東縁はじわじわとロシアに迫り、ついにロシアと直接、国境を接するウクライナに到達しようとしている。
経済を立て直し、国力を回復したロシアのプーチン大統領が「NATOのウクライナへの拡大」に強い危機感を抱いたのは、理解できないことではない。2008年のNATO加盟国との首脳会談で、プーチン大統領は「ウクライナがNATOに加盟するなら、ロシアはウクライナと戦争をする用意がある」と発言している。
旧共産圏の東欧諸国や旧ソ連の構成国であるウクライナがNATOに加盟するということは、単に軍事同盟の組み合わせが変わる、ということだけにとどまらない。戦闘機や戦車といった武器体系がロシア製から米英製に切り替わることを意味する。そのビジネス上の損得は極めて大きい。
それ以上に深刻なのは、旧共産圏諸国が持っていた暗号解読を含む軍事機密情報が米英の手に渡ることだ。軍事情報が戦争で果たす役割は、IT革命の進展に伴ってますます大きくなってきている。かつての同盟国の寝返りは死活に直結する、と言っていい。
モンゴル帝国の来襲からナポレオンのモスクワ遠征、ナチスドイツの侵攻と、ロシア・ソ連は幾度も、陸続きの大国から攻め込まれ、そのたびに甚大な被害をこうむってきた。海に囲まれ、この1000年余で外敵に攻め込まれたのは元寇とマッカーサー率いる米軍だけ、という日本とは危機意識がまるで異なる、ということに思いを致すべきだろう。
岸田首相は「国際社会との連携」と「在留邦人の安全確保」をオウムのように繰り返している。官僚が作った文章を棒読みしているだけだ。今の国際情勢をどう捉えているのか。世界はどこへ向かおうとしているのか。自らの歴史認識や政治哲学がうかがえるような発言は皆無である。
一方のメディアはどうか。25日付朝日新聞のコラム「天声人語」は「ロシアの暴挙には一片の正当性もない」と書いた。歯切れはいいが、説得力はまるでない。追い詰められて牙をむいたロシアにも言い分はある。一方で、アメリカが振りかざす正義にはしばしば大きなごまかしがある。そうしたことを丁寧に、冷徹に報じるのがメディアの役割ではないか。
アメリカが唯一の超大国と呼ばれたポスト冷戦の第一段階は終わり、世界は第二段階に入りつつある。ロシア・ウクライナ戦争の帰趨は、それがどのような世界になるかを示すことになるだろう。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 104」 2022年2月25日
【追記 2022年2月26日】 私の自宅(山形県朝日町)に配られた25日付朝日新聞朝刊(13版S)の「天声人語」には「ロシアの暴挙には一片の正当性もない」と書いてありましたが、同日付の次の版(14版S)では「ロシアの暴挙には、正当性のかけらもない」と手直しされていました。
≪写真説明&Source≫
◎ロシア軍の侵攻が迫る中、演習をするウクライナ軍の戦車。2月18日にUkrainian Joint Forces Operation Press Serviceが提供(2022年 ロイター)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/02/post-98115.php

ロシアはこれまで、ウクライナ東部のロシア系住民が多い地域の武装勢力を支援してきた。今回の侵攻によって、ロシアはこの武装勢力が支配する地域を独立させて「友好的な地域」にしたうえで、ウクライナのほかの地域を「緩衝地帯」にすることを狙っているようだ。
アメリカのバイデン大統領は「この攻撃がもたらす死と破壊はロシアだけに責任がある」と非難した。岸田文雄首相はこれに同調し、「国際社会と連携して迅速に対処していく」と述べた。武力で自分の言い分を押し通そうとするロシアの行動は非難されて当然である。だが、バイデン大統領が言うように、この戦争の責任は「ロシアだけにある」のだろうか。
今回のロシア・ウクライナ戦争を考えるうえでのキーワードは「NATOの東方拡大」である。NATO(北大西洋条約機構)は、第2次世界大戦後にアメリカとイギリスがソ連と対峙するため西欧諸国を糾合して結成した「共産圏包囲軍事同盟」である。ソ連はワルシャワ条約機構を結成して、これに対抗した。
1989年に米ソの冷戦が終結し、1991年にソ連が崩壊したのだから、本来ならNATOは「新しい軍事同盟」に改編されるべきだった。だが、アメリカはその後もその基本的な構造を維持したまま、共産圏にあった東欧諸国を一つ、また一つとNATOに組み込んでいった。
ソ連崩壊後、ロシアは政治的にも経済的にも混乱状態に陥り、NATOの東方拡大に対処する余裕がなかった。NATOの東縁はじわじわとロシアに迫り、ついにロシアと直接、国境を接するウクライナに到達しようとしている。
経済を立て直し、国力を回復したロシアのプーチン大統領が「NATOのウクライナへの拡大」に強い危機感を抱いたのは、理解できないことではない。2008年のNATO加盟国との首脳会談で、プーチン大統領は「ウクライナがNATOに加盟するなら、ロシアはウクライナと戦争をする用意がある」と発言している。
旧共産圏の東欧諸国や旧ソ連の構成国であるウクライナがNATOに加盟するということは、単に軍事同盟の組み合わせが変わる、ということだけにとどまらない。戦闘機や戦車といった武器体系がロシア製から米英製に切り替わることを意味する。そのビジネス上の損得は極めて大きい。
それ以上に深刻なのは、旧共産圏諸国が持っていた暗号解読を含む軍事機密情報が米英の手に渡ることだ。軍事情報が戦争で果たす役割は、IT革命の進展に伴ってますます大きくなってきている。かつての同盟国の寝返りは死活に直結する、と言っていい。
モンゴル帝国の来襲からナポレオンのモスクワ遠征、ナチスドイツの侵攻と、ロシア・ソ連は幾度も、陸続きの大国から攻め込まれ、そのたびに甚大な被害をこうむってきた。海に囲まれ、この1000年余で外敵に攻め込まれたのは元寇とマッカーサー率いる米軍だけ、という日本とは危機意識がまるで異なる、ということに思いを致すべきだろう。
岸田首相は「国際社会との連携」と「在留邦人の安全確保」をオウムのように繰り返している。官僚が作った文章を棒読みしているだけだ。今の国際情勢をどう捉えているのか。世界はどこへ向かおうとしているのか。自らの歴史認識や政治哲学がうかがえるような発言は皆無である。
一方のメディアはどうか。25日付朝日新聞のコラム「天声人語」は「ロシアの暴挙には一片の正当性もない」と書いた。歯切れはいいが、説得力はまるでない。追い詰められて牙をむいたロシアにも言い分はある。一方で、アメリカが振りかざす正義にはしばしば大きなごまかしがある。そうしたことを丁寧に、冷徹に報じるのがメディアの役割ではないか。
アメリカが唯一の超大国と呼ばれたポスト冷戦の第一段階は終わり、世界は第二段階に入りつつある。ロシア・ウクライナ戦争の帰趨は、それがどのような世界になるかを示すことになるだろう。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 104」 2022年2月25日
【追記 2022年2月26日】 私の自宅(山形県朝日町)に配られた25日付朝日新聞朝刊(13版S)の「天声人語」には「ロシアの暴挙には一片の正当性もない」と書いてありましたが、同日付の次の版(14版S)では「ロシアの暴挙には、正当性のかけらもない」と手直しされていました。
≪写真説明&Source≫
◎ロシア軍の侵攻が迫る中、演習をするウクライナ軍の戦車。2月18日にUkrainian Joint Forces Operation Press Serviceが提供(2022年 ロイター)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/02/post-98115.php
気象庁が首都圏に「大雪注意報」を出したのを受けて、10日昼のNHKのトップニュースは「東京23区など大雪のおそれ」だった。リポーターが東京都調布市の街頭に立って、みぞれがちらつく様子を伝え、雪への警戒を呼び掛けていた。

これだけでは「さすがにつらい」と報道する側も思ったのか、次の映像は箱根の芦ノ湖畔の雪景色だった。記者が地面に手を差し込んで「こんなに積もっています」とのたもうた。確かに5センチほど積もっている。「すごい雪でしょ」と言いたげだった。
なんて報道だ、と思う。東京に数センチの雪が降り積もれば、かなり大変なことだとは分かる。が、それを気象庁が「大雪」と表現し、報道機関が「大雪」と報じるのは、日本語の使い方としておかしいのではないか。「積雪注意報」「東京で積雪」で十分ではないか。
雪国で暮らす人たちがこういう報道をどういう思いで見ているか、まるで考えていない。東京の報道機関が「東京ローカル」のニュースを、さも重大なニュースであるかのように報じるのに辟易(へきえき)しているのは、私だけだろうか。
私が暮らす山形県で9日夜、屋根に降り積もった雪で家がつぶれ、1人暮らしの男性(64歳)が亡くなる事故があった。県内でも豪雪地帯として知られる新庄市の住宅街での出来事である。NHKはこれを「ローカルニュース」として報じた。
雪下ろし中に屋根から転落して死亡したり、除雪機に挟まれて亡くなったりする事故は、雪国ではしばしば起きる。従って、そうしたニュースを地方ニュースとして扱うのは分かる。だが、積雪で家が潰れ、それで住民が亡くなる事故など、雪国でも滅多にあるものではない。それを「ありふれたニュース」のように扱うのはおかしい。
現場の映像を見ると、屋根に降り積もった雪は1.5メートルほどある。冬の初めに降った雪は圧縮され、一部は氷になっている。そこに次の雪が降り積もり、さらに新雪が加わる。屋根に加わる重量は相当なもので、古い住宅の場合には文字通り潰れてしまう。
倒壊を防ぐため、屋根の雪下ろしは欠かせない。私は山形と新潟の県境に近い村で暮らしている。積雪は今回の事故が起きた新庄市と同じくらいだ。ただ、山村なら空き地が十分にあるので気軽に屋根の雪下ろしができるが、市街地だとそれもままならない。屋根から下ろした雪の始末に困るからだ。
新庄市の住民に聞くと、雪下ろしの手間賃は1人当たり1日2万円前後(危険手当込み)。さらに、下ろした雪を運んだり、除雪したりする費用も必要なので、雪下ろしを数人に頼めば、1回で10万円は覚悟しなければならない。
それで雪下ろしをためらっているうちに、雪の重みで家が潰れてしまったようだ。痛ましい事故であり、雪国で暮らすことの切なさを象徴するような出来事だ。それをなぜ、全国的なニュースとして報じないのか。
調布の街頭に降るみぞれを伝える時間があるなら、せめて数秒でもいいから、1.5メートルの雪で潰れてしまった家の映像を伝えられなかったのか。「大雪」という日本語の使い方と併せて、何がニュースなのかについても、報道する人たちにはもっと神経をとがらせてほしい。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
初出:調査報道サイト「ハンター」 2022年2月11日
https://news-hunter.org/?p=10949
≪写真・映像の説明&Source≫
◎豪雪地帯の雪下ろし風景
https://sumairu-doctor.com/360/
◎山形県新庄市で起きた「積雪で家屋倒壊、住民死亡」を報じるNHK山形のニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220210/amp/k10013477011000.html

これだけでは「さすがにつらい」と報道する側も思ったのか、次の映像は箱根の芦ノ湖畔の雪景色だった。記者が地面に手を差し込んで「こんなに積もっています」とのたもうた。確かに5センチほど積もっている。「すごい雪でしょ」と言いたげだった。
なんて報道だ、と思う。東京に数センチの雪が降り積もれば、かなり大変なことだとは分かる。が、それを気象庁が「大雪」と表現し、報道機関が「大雪」と報じるのは、日本語の使い方としておかしいのではないか。「積雪注意報」「東京で積雪」で十分ではないか。
雪国で暮らす人たちがこういう報道をどういう思いで見ているか、まるで考えていない。東京の報道機関が「東京ローカル」のニュースを、さも重大なニュースであるかのように報じるのに辟易(へきえき)しているのは、私だけだろうか。
私が暮らす山形県で9日夜、屋根に降り積もった雪で家がつぶれ、1人暮らしの男性(64歳)が亡くなる事故があった。県内でも豪雪地帯として知られる新庄市の住宅街での出来事である。NHKはこれを「ローカルニュース」として報じた。
雪下ろし中に屋根から転落して死亡したり、除雪機に挟まれて亡くなったりする事故は、雪国ではしばしば起きる。従って、そうしたニュースを地方ニュースとして扱うのは分かる。だが、積雪で家が潰れ、それで住民が亡くなる事故など、雪国でも滅多にあるものではない。それを「ありふれたニュース」のように扱うのはおかしい。
現場の映像を見ると、屋根に降り積もった雪は1.5メートルほどある。冬の初めに降った雪は圧縮され、一部は氷になっている。そこに次の雪が降り積もり、さらに新雪が加わる。屋根に加わる重量は相当なもので、古い住宅の場合には文字通り潰れてしまう。
倒壊を防ぐため、屋根の雪下ろしは欠かせない。私は山形と新潟の県境に近い村で暮らしている。積雪は今回の事故が起きた新庄市と同じくらいだ。ただ、山村なら空き地が十分にあるので気軽に屋根の雪下ろしができるが、市街地だとそれもままならない。屋根から下ろした雪の始末に困るからだ。
新庄市の住民に聞くと、雪下ろしの手間賃は1人当たり1日2万円前後(危険手当込み)。さらに、下ろした雪を運んだり、除雪したりする費用も必要なので、雪下ろしを数人に頼めば、1回で10万円は覚悟しなければならない。
それで雪下ろしをためらっているうちに、雪の重みで家が潰れてしまったようだ。痛ましい事故であり、雪国で暮らすことの切なさを象徴するような出来事だ。それをなぜ、全国的なニュースとして報じないのか。
調布の街頭に降るみぞれを伝える時間があるなら、せめて数秒でもいいから、1.5メートルの雪で潰れてしまった家の映像を伝えられなかったのか。「大雪」という日本語の使い方と併せて、何がニュースなのかについても、報道する人たちにはもっと神経をとがらせてほしい。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
初出:調査報道サイト「ハンター」 2022年2月11日
https://news-hunter.org/?p=10949
≪写真・映像の説明&Source≫
◎豪雪地帯の雪下ろし風景
https://sumairu-doctor.com/360/
◎山形県新庄市で起きた「積雪で家屋倒壊、住民死亡」を報じるNHK山形のニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220210/amp/k10013477011000.html
大金を盗んだ泥棒が犯行発覚の後、「悪かった。金は返す」と言えば許されるのか。他人の金をだまし取った詐欺師がばれた後、「反省している。全額返す」と言えば許されるのか。

そんなことは法律の専門家に聞くまでもない。どちらのケースも許されるはずがない。「謝って済むなら警察は要らない」のであり、そんなことは「お天道様が許さない」からである。
だが、山形県議会の坂本貴美雄議長も吉村美栄子知事も、ものの道理など気にならないようだ。野川政文・元県議による政務活動費の不正受給について、坂本議長は「告発しない」と何度も言明し、吉村知事も記者会見で「すでに議員を辞職し、社会的制裁を受けている。全額返還する意思も示している。こういったことを総合的に判断して告訴しない」と述べた。
あきれる。2人とも、ごく普通の県民がこの事件にどのくらい怒っているか、まるで理解していない。理解しようともしていない。普通の人が毎月8万円の収入を得ようとすれば、どのくらい働かなければならないか、考えたこともないのだろう。
野川元県議は何をしたのか。あらためて確認したい。県議には月額77万8000円の議員報酬のほかに1人当たり月に28万円の政務活動費が支給される。これは報酬(給与)ではなく、県政に関する調査研究や事務所の維持、事務職員の給与などに充てるための費用である。余ったら県に返すことになっている。
政治に金がかかることは誰もが理解している。従って、政務活動費の趣旨に沿ってきちんと支出し、残余を返却している分には誰も文句は言わない。
だが、野川氏は事務職員を雇ったように装い、勤務の実態がないのに毎月8万円の領収書に署名捺印させ、政務活動費として計上していた。つまり、毎月8万円の人件費をごまかし、懐に入れていたのである。この事務職員には毎月1万円を払っていたというが、勤務実態がないのだから、これも含めてだまし取っていたことに変わりはない。
虚偽の領収書を使っての詐欺行為は、2008年度から2020年度まで13年間に及んだ。総額1248万円に達する。刑法第246条2項の詐欺罪(人をだまして不法の利益を得る)に当たることは明白だ。
許しがたいのは、こうした詐欺行為を13年にわたって続けていたことだけではない。この間、2014年には兵庫県議会で「号泣県議」こと野々村竜太郎県議の架空出張問題が明るみに出て、そのでたらめさ加減に世間があきれる事件があった。野川氏はその前後も詐欺行為を続けていた。
さらに、山形県でも2016年9月に阿部賢一県議による政務活動費の不正受給が発覚した(発覚後、阿部氏は議員を辞職)。野川氏はこの時、県議会の議長をしており、白々しくも「県議会としてけじめが必要だ」「刑事告発を検討する」と述べた(刑事告発は民進、社民系の県政クラブが反対したため見送られた)。
加えて、野川氏はこの時、全国都道府県議会議長会の会長の座にあり、議員の範たるべき立場にあった。にもかかわらず、平気で詐欺行為を続けていたのである。何と破廉恥な政治家であることか。
彼はこの詐欺行為を恥じて「自白」したわけでもない。信頼できる筋によれば、山形県警は去年の9月ごろには野川氏のこうした不正行為を把握し、政務活動費の収支報告書や人件費の領収書などを任意で提出させていたという。県警がなぜ、このような明白な詐欺事件を立件しなかったのかは不明である。何らかの力が働いて「立件見送り」の判断をしたようだ。
事件は警察の捜査ではなく、報道によって明るみに出た。NHK山形放送局が11月4日朝のニュースで特ダネとして報じ、新聞と民放各社が追いかけて広く知られるに至った。各社入り乱れての報道合戦が繰り広げられ、人件費以外の不正行為も明らかになった。野川氏は自宅の一部を事務所として使っており、自宅の光熱費の2分の1を政務活動費として計上していた。
だが、県議会が自ら定めた「政務活動費の手引」(2017年2月改訂版)によれば、事務所は県政に関する調査や研究だけでなく、選挙や後援会活動でも使うのが常であり、こうしたケースでは原則として自宅の光熱費の4分の1を政務活動費として計上するルールになっている。つまり、事務所費や事務費でも長期にわたって経費の4分の1を不正に得ていたのである。
こちらは「詐欺」と言えるかどうか微妙だが、不正であることに変わりはない。議長まで経験した議員が「知らなかった」あるいは「勘違いした」と言い訳して済む問題ではない。
悪事が露見してからの野川氏の行動は素早かった。第一報の2日後には坂本議長に議員辞職願を出し、11月15日には山形市内のレンタル会議場で記者会見を開いた。その釈明は最初から最後まで支離滅裂だった。
架空の事務職員には毎月1万円を渡し、残りの7万円は「政治資金として提供してもらった」と述べた。だが、政治資金報告書には何の記載もない。だまし取った金を「私的に流用したことはない」と言い張ったが、何に使ったかの領収書などは何もない。こんな説明では、まるで説得力がない。
「説得力がない」という点では、県議会の坂本貴美雄議長の言い分も吉村美栄子知事の主張も同じだ。
坂本議長は報道陣に対して、何度も「議会としての告発は法制度上、できない」と述べた。ウソである。議会が構成メンバーである議員を告発することは法的に可能だからだ。現に、先に述べた野々村・元兵庫県議の不正事件では、兵庫県議会が各会派代表の連名で虚偽公文書作成・同行使罪で県警に告発している。野々村氏は起訴され、2016年7月に神戸地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けた。

坂本議長はなぜ、このようなウソを繰り返したのか。県議会事務局が入れ知恵したのだろうと推測して問いただしたら、その通りだった。県議会事務局が「議会としての告発はできない」という主張の根拠にしたのは、株式会社「地方議会総合研究所」の代表取締役、廣瀬和彦氏が書いた『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい)という本にある次の一節だ。
「議会は地方公共団体の一機関であり、法人格を有しないため、一般に告発する権利を有しない」
この本は地方自治法の第100条に基づく議会による不祥事などの調査についての解説本で、いわゆる「百条調査委員会」が作られた場合のみ、議会は告発することができ、「それ以外では告発する権利がない」と解説している。
つまり、県議会事務局は株式社会の社長の見解をうのみにし、それを坂本議長に伝え、議長もそれを頼りに発言しているに過ぎない。
刑事訴訟法は第239条で「何人(なんぴと)でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と規定しており、その「何人」には法人格のない団体も含まれると考える解釈の方が有力なのだ。
だからこそ、法人格のない市民オンブズマン山形県会議でも野川氏を告発することができるのであり、必要なら私が主宰する地域おこしの小さなNPO「ブナの森」として告発することも可能なのだ。
「議会が法制度上、告発できるかどうか」は刑事訴訟法の解釈の問題であり、『100条調査ハンドブック』は「できない」という一つの解釈を示しているに過ぎない。坂本議長にも県議会事務局にも「もっとしっかり調べてから発言すべきだ」と言いたい。
百歩譲って、『ハンドブック』の解釈が正しいとしても、先に書いたように議会には「各会派の代表者の連名で告発する」という方法もある。議長が議会各派の了承を得て議長個人として告発する道もある。「法制度上、できない」という表現は誤りであり、報道陣を惑わすものだ。要するに「告発したくないんです」と言っているに過ぎない。

吉村知事の対応もお粗末きわまりない。政務活動費の問題は「一義的には議会の問題」と主張して逃げ切ろうとしている。「議会の問題」であることは間違いないが、その議会がきちんと対応しないなら、公金をだまし取られたのだから納税者の代表として知事が告訴するのは当然のことではないか。
それを「すでに社会的制裁を受けている」とか「過去に遡って全額返還する意思も示している」などと言って逃げようとするのはおかしい。1月12日の記者会見では、報道陣の追及にたまりかねたのか「さらに一歩進めて、息の根を止めるようなところまでやるのかというようなことも、ちょっと私としてはそこまでは・・」と口走った。
驚くべき発言である。法律に基づいて知事として為すべきことを「息の根を止める行為」と表現するとは。情報公開の不開示訴訟で知事を相手に争った際にも感じたことだが、この人は「法の支配の重要さ」あるいは「政治倫理の向上」といった問題についてまるで無頓着だ。知事としての適性を疑いたくなる発言である。
ともあれ、知事も県議会議長も当然為すべきことをしないのであれば、市民オンブズマン山形県会議としては「市民としての義務」を粛々と果たすしかない。みんなボランティアとして無報酬で働いており、もっと建設的なことをしたいのは山々だが、そうも言っていられない。やむなく、1月14日に山形地方検察庁に告発状を提出した。告発状は、市民オンブズマン県会議という団体として提出し、さらにメンバー4人も個人として名を連ねた。
告発するには「動かぬ証拠」が必要である。野川氏が作成して県議会議長に提出した政務活動費の収支報告関係文書のうち、保存期間が過ぎたものはすでに廃棄されていて無い。従って、関係文書が残っている2015年度以降の人件費の不正に絞って告発した。
詐欺罪の公訴時効は7年であり、それ以前の罪を問うことはできない。また、事務所費や事務費についても不正があることは明白だが、どのような罪に当たるかは難しいところだ。ゆえに、告発状ではそうしたことについては検察側に判断をゆだねた。
あとは、山形地検が県警と連携しながら適切な捜査を積み重ね、きちんと起訴するのを待つしかない。万が一、このような悪質、破廉恥な詐欺行為について、検察が「不起訴」あるいは「起訴猶予」などという不真面目な決定をしたならば、オンブズマンとして今度は検察を相手に法的な手段に訴えて闘わざるを得なくなる。
検察庁は「我々は、その重責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取り組まなければならない」との理念を掲げている。そういう人たちがよもや、自分たちの理念に反するようなことはすまい、と信じたい。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*初出:月刊『素晴らしい山形』2022年2月号
≪写真説明&Source≫
◎2017年1月の全国都道府県議会議長会の総会で挨拶する野川政文氏(同議長会のサイトから)
http://www.gichokai.gr.jp/topics/2016/170120-2/index.html
◎2021年11月、報道陣の質問に答える坂本貴美雄議長(NHKのサイトから)
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/71511.html
◎山形の名産品ラ・フランスを手に首相官邸で安倍晋三氏と写真に納まる吉村美栄子知事(2016年11月28日)。この写真は山形県政記者クラブの加盟各社に配布された

そんなことは法律の専門家に聞くまでもない。どちらのケースも許されるはずがない。「謝って済むなら警察は要らない」のであり、そんなことは「お天道様が許さない」からである。
だが、山形県議会の坂本貴美雄議長も吉村美栄子知事も、ものの道理など気にならないようだ。野川政文・元県議による政務活動費の不正受給について、坂本議長は「告発しない」と何度も言明し、吉村知事も記者会見で「すでに議員を辞職し、社会的制裁を受けている。全額返還する意思も示している。こういったことを総合的に判断して告訴しない」と述べた。
あきれる。2人とも、ごく普通の県民がこの事件にどのくらい怒っているか、まるで理解していない。理解しようともしていない。普通の人が毎月8万円の収入を得ようとすれば、どのくらい働かなければならないか、考えたこともないのだろう。
野川元県議は何をしたのか。あらためて確認したい。県議には月額77万8000円の議員報酬のほかに1人当たり月に28万円の政務活動費が支給される。これは報酬(給与)ではなく、県政に関する調査研究や事務所の維持、事務職員の給与などに充てるための費用である。余ったら県に返すことになっている。
政治に金がかかることは誰もが理解している。従って、政務活動費の趣旨に沿ってきちんと支出し、残余を返却している分には誰も文句は言わない。
だが、野川氏は事務職員を雇ったように装い、勤務の実態がないのに毎月8万円の領収書に署名捺印させ、政務活動費として計上していた。つまり、毎月8万円の人件費をごまかし、懐に入れていたのである。この事務職員には毎月1万円を払っていたというが、勤務実態がないのだから、これも含めてだまし取っていたことに変わりはない。
虚偽の領収書を使っての詐欺行為は、2008年度から2020年度まで13年間に及んだ。総額1248万円に達する。刑法第246条2項の詐欺罪(人をだまして不法の利益を得る)に当たることは明白だ。
許しがたいのは、こうした詐欺行為を13年にわたって続けていたことだけではない。この間、2014年には兵庫県議会で「号泣県議」こと野々村竜太郎県議の架空出張問題が明るみに出て、そのでたらめさ加減に世間があきれる事件があった。野川氏はその前後も詐欺行為を続けていた。
さらに、山形県でも2016年9月に阿部賢一県議による政務活動費の不正受給が発覚した(発覚後、阿部氏は議員を辞職)。野川氏はこの時、県議会の議長をしており、白々しくも「県議会としてけじめが必要だ」「刑事告発を検討する」と述べた(刑事告発は民進、社民系の県政クラブが反対したため見送られた)。
加えて、野川氏はこの時、全国都道府県議会議長会の会長の座にあり、議員の範たるべき立場にあった。にもかかわらず、平気で詐欺行為を続けていたのである。何と破廉恥な政治家であることか。
彼はこの詐欺行為を恥じて「自白」したわけでもない。信頼できる筋によれば、山形県警は去年の9月ごろには野川氏のこうした不正行為を把握し、政務活動費の収支報告書や人件費の領収書などを任意で提出させていたという。県警がなぜ、このような明白な詐欺事件を立件しなかったのかは不明である。何らかの力が働いて「立件見送り」の判断をしたようだ。
事件は警察の捜査ではなく、報道によって明るみに出た。NHK山形放送局が11月4日朝のニュースで特ダネとして報じ、新聞と民放各社が追いかけて広く知られるに至った。各社入り乱れての報道合戦が繰り広げられ、人件費以外の不正行為も明らかになった。野川氏は自宅の一部を事務所として使っており、自宅の光熱費の2分の1を政務活動費として計上していた。
だが、県議会が自ら定めた「政務活動費の手引」(2017年2月改訂版)によれば、事務所は県政に関する調査や研究だけでなく、選挙や後援会活動でも使うのが常であり、こうしたケースでは原則として自宅の光熱費の4分の1を政務活動費として計上するルールになっている。つまり、事務所費や事務費でも長期にわたって経費の4分の1を不正に得ていたのである。
こちらは「詐欺」と言えるかどうか微妙だが、不正であることに変わりはない。議長まで経験した議員が「知らなかった」あるいは「勘違いした」と言い訳して済む問題ではない。
悪事が露見してからの野川氏の行動は素早かった。第一報の2日後には坂本議長に議員辞職願を出し、11月15日には山形市内のレンタル会議場で記者会見を開いた。その釈明は最初から最後まで支離滅裂だった。
架空の事務職員には毎月1万円を渡し、残りの7万円は「政治資金として提供してもらった」と述べた。だが、政治資金報告書には何の記載もない。だまし取った金を「私的に流用したことはない」と言い張ったが、何に使ったかの領収書などは何もない。こんな説明では、まるで説得力がない。
「説得力がない」という点では、県議会の坂本貴美雄議長の言い分も吉村美栄子知事の主張も同じだ。
坂本議長は報道陣に対して、何度も「議会としての告発は法制度上、できない」と述べた。ウソである。議会が構成メンバーである議員を告発することは法的に可能だからだ。現に、先に述べた野々村・元兵庫県議の不正事件では、兵庫県議会が各会派代表の連名で虚偽公文書作成・同行使罪で県警に告発している。野々村氏は起訴され、2016年7月に神戸地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けた。

坂本議長はなぜ、このようなウソを繰り返したのか。県議会事務局が入れ知恵したのだろうと推測して問いただしたら、その通りだった。県議会事務局が「議会としての告発はできない」という主張の根拠にしたのは、株式会社「地方議会総合研究所」の代表取締役、廣瀬和彦氏が書いた『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい)という本にある次の一節だ。
「議会は地方公共団体の一機関であり、法人格を有しないため、一般に告発する権利を有しない」
この本は地方自治法の第100条に基づく議会による不祥事などの調査についての解説本で、いわゆる「百条調査委員会」が作られた場合のみ、議会は告発することができ、「それ以外では告発する権利がない」と解説している。
つまり、県議会事務局は株式社会の社長の見解をうのみにし、それを坂本議長に伝え、議長もそれを頼りに発言しているに過ぎない。
刑事訴訟法は第239条で「何人(なんぴと)でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と規定しており、その「何人」には法人格のない団体も含まれると考える解釈の方が有力なのだ。
だからこそ、法人格のない市民オンブズマン山形県会議でも野川氏を告発することができるのであり、必要なら私が主宰する地域おこしの小さなNPO「ブナの森」として告発することも可能なのだ。
「議会が法制度上、告発できるかどうか」は刑事訴訟法の解釈の問題であり、『100条調査ハンドブック』は「できない」という一つの解釈を示しているに過ぎない。坂本議長にも県議会事務局にも「もっとしっかり調べてから発言すべきだ」と言いたい。
百歩譲って、『ハンドブック』の解釈が正しいとしても、先に書いたように議会には「各会派の代表者の連名で告発する」という方法もある。議長が議会各派の了承を得て議長個人として告発する道もある。「法制度上、できない」という表現は誤りであり、報道陣を惑わすものだ。要するに「告発したくないんです」と言っているに過ぎない。

吉村知事の対応もお粗末きわまりない。政務活動費の問題は「一義的には議会の問題」と主張して逃げ切ろうとしている。「議会の問題」であることは間違いないが、その議会がきちんと対応しないなら、公金をだまし取られたのだから納税者の代表として知事が告訴するのは当然のことではないか。
それを「すでに社会的制裁を受けている」とか「過去に遡って全額返還する意思も示している」などと言って逃げようとするのはおかしい。1月12日の記者会見では、報道陣の追及にたまりかねたのか「さらに一歩進めて、息の根を止めるようなところまでやるのかというようなことも、ちょっと私としてはそこまでは・・」と口走った。
驚くべき発言である。法律に基づいて知事として為すべきことを「息の根を止める行為」と表現するとは。情報公開の不開示訴訟で知事を相手に争った際にも感じたことだが、この人は「法の支配の重要さ」あるいは「政治倫理の向上」といった問題についてまるで無頓着だ。知事としての適性を疑いたくなる発言である。
ともあれ、知事も県議会議長も当然為すべきことをしないのであれば、市民オンブズマン山形県会議としては「市民としての義務」を粛々と果たすしかない。みんなボランティアとして無報酬で働いており、もっと建設的なことをしたいのは山々だが、そうも言っていられない。やむなく、1月14日に山形地方検察庁に告発状を提出した。告発状は、市民オンブズマン県会議という団体として提出し、さらにメンバー4人も個人として名を連ねた。
告発するには「動かぬ証拠」が必要である。野川氏が作成して県議会議長に提出した政務活動費の収支報告関係文書のうち、保存期間が過ぎたものはすでに廃棄されていて無い。従って、関係文書が残っている2015年度以降の人件費の不正に絞って告発した。
詐欺罪の公訴時効は7年であり、それ以前の罪を問うことはできない。また、事務所費や事務費についても不正があることは明白だが、どのような罪に当たるかは難しいところだ。ゆえに、告発状ではそうしたことについては検察側に判断をゆだねた。
あとは、山形地検が県警と連携しながら適切な捜査を積み重ね、きちんと起訴するのを待つしかない。万が一、このような悪質、破廉恥な詐欺行為について、検察が「不起訴」あるいは「起訴猶予」などという不真面目な決定をしたならば、オンブズマンとして今度は検察を相手に法的な手段に訴えて闘わざるを得なくなる。
検察庁は「我々は、その重責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取り組まなければならない」との理念を掲げている。そういう人たちがよもや、自分たちの理念に反するようなことはすまい、と信じたい。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*初出:月刊『素晴らしい山形』2022年2月号
≪写真説明&Source≫
◎2017年1月の全国都道府県議会議長会の総会で挨拶する野川政文氏(同議長会のサイトから)
http://www.gichokai.gr.jp/topics/2016/170120-2/index.html
◎2021年11月、報道陣の質問に答える坂本貴美雄議長(NHKのサイトから)
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/71511.html
◎山形の名産品ラ・フランスを手に首相官邸で安倍晋三氏と写真に納まる吉村美栄子知事(2016年11月28日)。この写真は山形県政記者クラブの加盟各社に配布された
被差別部落とは何か。そのルーツはどこにあるのか。明治生まれの在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)は生涯かけて、それを追い続けた。
山哉がすごいのは、その探求を書斎にこもって行ったのではなく、実際に自分の足で全国の被差別部落を訪ね歩き、人々の言葉に耳を傾けて考え抜き、公表していったことだ。
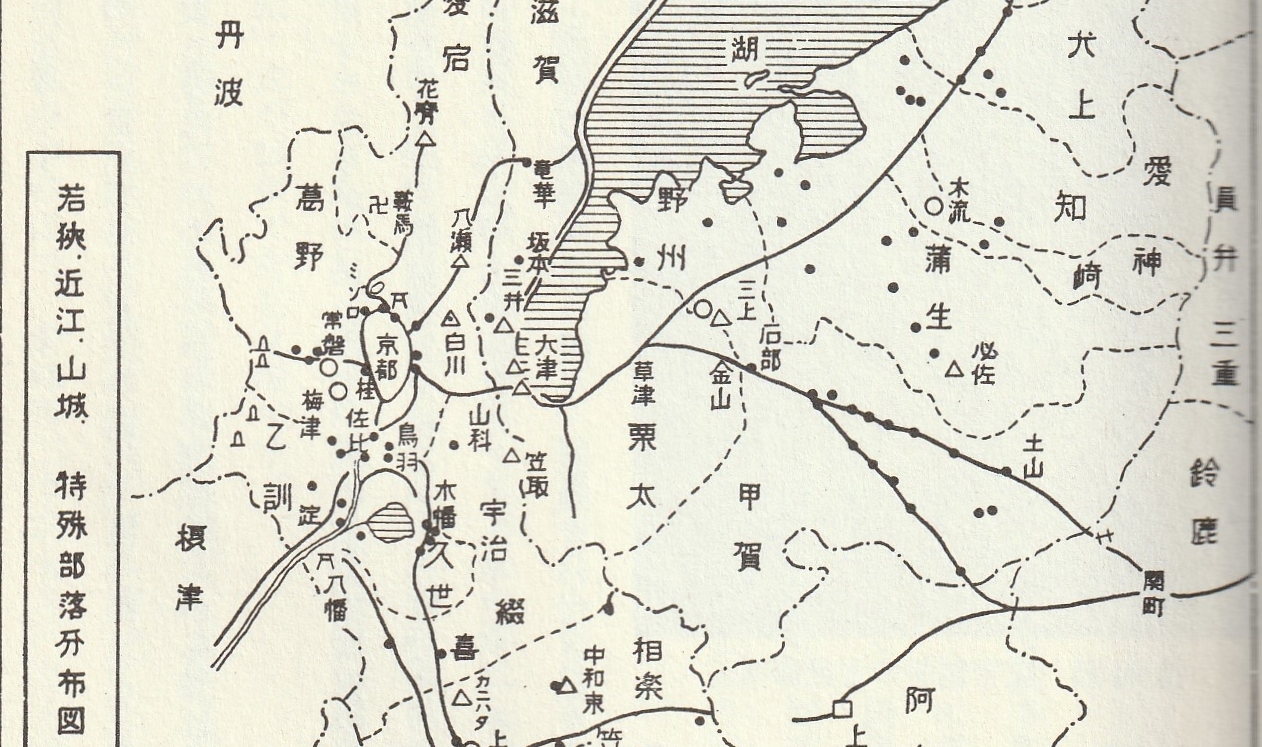
大正時代から昭和の戦前戦後を通して、彼が半世紀かけて訪ねた被差別部落の数は700を上回る。並行して古事記や日本書紀などの史書や古文書類に、可能な限り目を通している。その研究は質、量ともに群を抜いている。
もちろん、山哉よりも先に被差別部落の歴史をたどる書籍を出した人はいた。柳瀬頸介の『社会外の社会 穢多(えた)非人』(1901年)と京都帝大の歴史学者、喜田貞吉教授が主宰する研究誌『民族と歴史』特殊部落研究号(1919年)である。被差別部落の解放を目指して全国水平社が結成されて2年たった1924年には、高橋貞樹が『特殊部落一千年史』という啓蒙書を出版している。
ただ、それぞれ優れた研究ではあったものの、難点があった。3人とも、古代律令国家の頃から賎民制度があり、奴婢(ぬひ)と呼ばれる奴隷がいて、囚われの身となった東北の蝦夷(えみし)が賎民にされたことは承知しており、書籍で触れてもいる。
だが、そうした古代の賎民制度が江戸時代の穢多・非人へと連綿とつながっている、とは見なさなかった。貴族政治から武家政治へと激変した平安から鎌倉時代への移行、さらに戦国時代の下剋上によって社会の階層は流動化し、いわゆる「穢多・非人」は江戸時代に身分制度が固定される中で新たに生み出されたもの、と唱えたのだ。
それをもっとも明確に主張したのは喜田貞吉である。『民族と歴史』特殊部落研究号に喜田は次のように記した。
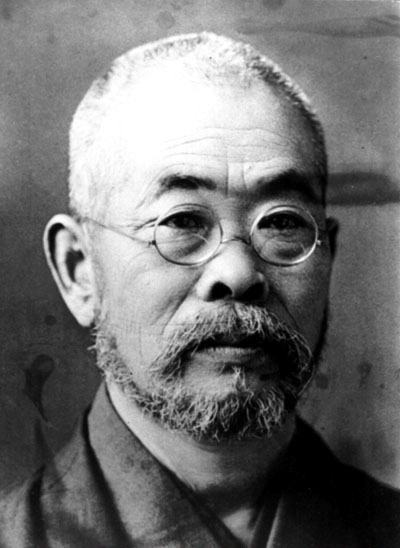
「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するということは、少くとも昔はありませんでした。蝦夷人すなわちアイヌ族の出にして、立派な地位に上ったものも少くない。(中略)有名な征夷大将軍の坂上田村麻呂も、少くとも昔の奥州の人は蝦夷(えぞ)仲間だと思っておりました」
「もともと武士には蝦夷すなわちエビス出身者が多かったから、『徒然草』などを始めとして、鎌倉南北朝頃の書物を見ますと、武士のことを『夷(えびす)』と云っております。鎌倉武士の事を『東夷(あずまえびす)』と云っております」
「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは、徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」
戦後定説となる「被差別部落=近世政治起源説」の原型とも言える学説である。喜田はこれを皇国史観に立って唱えたのだが、「同じ日本人なのになぜ差別する」と憤る水平社の人々にとっても、運動の基盤として好ましい学説だった。
菊池山哉はこうした中で、1927年(昭和2年)に『先住民族と賎民族の研究』を出版し、「エタはエッタがなまったもので我が国の先住民族である」「投降、帰順した東北の蝦夷(えみし)は西日本に移送され、賎民として扱われた」と唱えた。喜田の学説を真っ向から否定したのである。
インドのカースト差別がそうであるように、征服した民族が被征服民族を賎民に落とし込んでいくのは世界各地で見られることである。そうした観点から考えれば、山哉の立論は自然であり、説得力がある。
だが、山哉は当時、在野の無名の郷土史家で、相手は帝大の教授である。山哉の主張はまるで相手にされず、黙殺された。
◇ ◇
戦後も山哉の学説に目を向ける研究者は現れない。水平社の運動を引き継いで再出発した部落解放同盟も相手にしなかった。
それでも、山哉はめげなかった。全国の被差別部落をめぐる「巡礼」のような調査行を半世紀にわたって続け、その成果を亡くなる直前、1966年に大著『別所と特殊部落の研究』にまとめて出版した(1990年代に『特殊部落の研究』『別所と俘囚』の2冊に分けて復刻された)。
踏査を重ねた末に山哉がたどり着いた結論は?東日本と西日本では被差別部落のルーツが異なる?西日本、とくに近畿の部落は「余部(あまべ)」「河原者」「守戸(しゅこ)」「別所」の四つに大別できる?別所とは東北の蝦夷を俘囚(ふしゅう)として移送したところである、というものだった。
山哉がとりわけ力を注いだのが「別所」と呼ばれる部落の調査である。例えば、京都郊外の大原にある別所について、次のように記している(原文は読みにくいため筆者が要約)。
「ここには今は廃寺となった補陀落寺というのがある。『東鑑(あずまかがみ)』によれば、この寺に観音像があったが、奥州平泉の藤原基衡(もとひら)はこの観音像を模したものを作らせ、毛越(もうつう)寺の吉祥堂の本尊にしたという。この寺が奥州と密接な関係にあったことを裏書きするものだ」(『別所と俘囚』165ページ)
近世政治起源説の最大の弱点は、「被差別部落が豊臣政権から徳川政権への移行期に身分制度が固まるにつれて形成された」とするなら、「なぜ東北には部落がほとんどないのか」という問いに答えられない、という点にある。
山哉が説くように「大和朝廷側が古代東北の蝦夷を攻め、投降・帰順した者を移送したところが別所であり、被差別部落になった」のであれば、問いへの答えとして納得がいく。
もちろん、数は極端に少ないが、東北にも別所という地名はあり、被差別部落がある。表は、被差別部落の都道府県別の数と人口(1921年、内務省統計)を一覧表にしたものである。福島に6,山形に4,青森に1となっている。
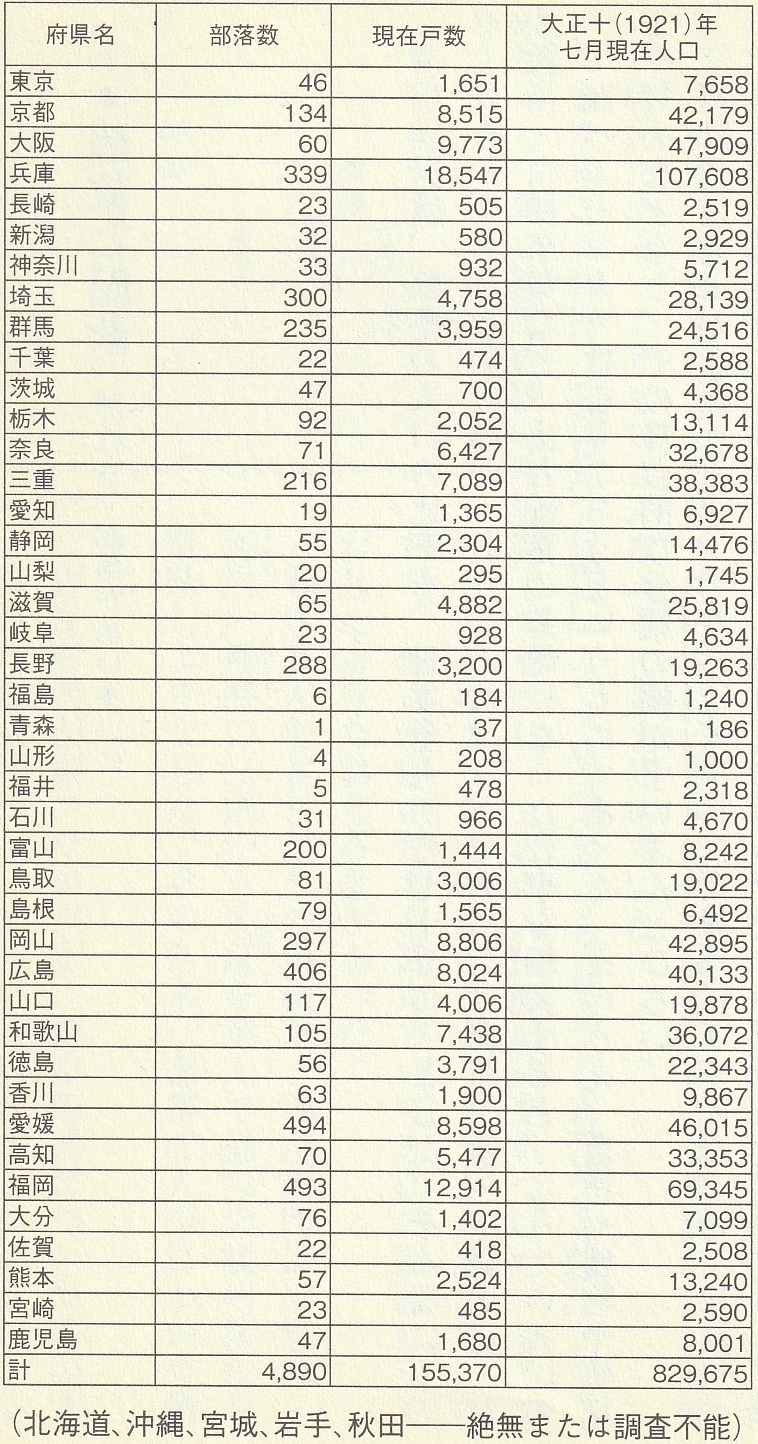
山哉はこれらの被差別部落も一つひとつ調べている。そして、東北の被差別部落のほとんどは江戸時代に国替えになった大名が前任地から引き連れてきたものであることを明らかにした。古代からその土地にあったと考えられる被差別部落は、福島県南部の部落一つだけだった。
◇ ◇
天皇の陵墓に配置され、警護と維持管理にあたる「守戸」についての記述も興味深い。これは東日本にはなく、西日本、とりわけ畿内に集中している。
奈良盆地に「神武天皇陵の守戸をつとめてきた」という被差別部落があった。この部落の人たちは少なくとも持統天皇(7世紀末)の時代から代々、尾根筋にある陵墓を守ってきたが、明治2年(1869年)に新政府がこの人たちに何の相談もなく、平地にある小さな古墳を「神武天皇の陵墓である」と認定してしまった。「そこは違う」と思っても、口に出すことはできなかったという。
古代の天皇陵については、幕末から明治維新にかけての混乱期にあたふたと認定作業を進めたこともあって、「陵墓の治定の誤りが多数ある」とされる。このため、考古学者は発掘調査を望んできたが、宮内庁は戦後も長い間「静安と尊厳を保つのが本義」と調査を拒んできた。大阪府の百舌鳥(もず)・古市古墳群が世界遺産に登録される動きが出る中で、2018年にようやくこれらの古墳の調査を認めたが、ほかの古墳群の調査が認められる見通しは立っていない。
山哉の調査は、そうした天皇陵の治定の誤りを被差別部落の側から照らし出している可能性がある。
自ら足を運び、人々の話にひたすら耳を傾ける。そうやって得た事実を愚直に記録する。それを基に仮説を組み立てていく――山哉が書き残したものは「学者たちが古文書から導き出した立論」などより、はるかに迫力があり、示唆に富む。
彼の著作は民俗学の枠にとどまらず、古代史や考古学にとっても「探求の素材の宝庫」であり、やがては被差別部落の歴史を考えるための古典になっていくのではないか。
(敬称略)
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2022年1月28日
https://news-hunter.org/?p=10695
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真&表の説明とSource≫
◎山城、近江の別所分布図(菊池山哉『別所と俘囚』から複写、トリミング)
◎喜田貞吉・京都帝大教授(東北大学関係写真データベースから)
http://webdb3.museum.tohoku.ac.jp/tua-photo/photo-img-l.php?mode=i&id=C012811
◎都道府県別の被差別部落の数と人数(1921年、内務省統計)=『部落史入門』から複写
≪参考文献≫
◎『えた非人 社会外の社会』(柳瀬頸介著、塩見鮮一郎訳、河出書房新社)
=『社会外の社会 穢多非人』を改題、復刻
◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫)
=『民族と歴史』特殊部落研究号から喜田の論文を編集、復刻
◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)
=『特殊部落一千年史』を改題
◎『部落史入門』(塩見鮮一郎、河出文庫)
◎『特殊部落の研究』(菊池山哉、批評社)
◎『別所と俘囚』(菊池山哉、批評社)
◎『余多歩き 菊池山哉の人と学問』(前田速夫、晶文社)
山哉がすごいのは、その探求を書斎にこもって行ったのではなく、実際に自分の足で全国の被差別部落を訪ね歩き、人々の言葉に耳を傾けて考え抜き、公表していったことだ。
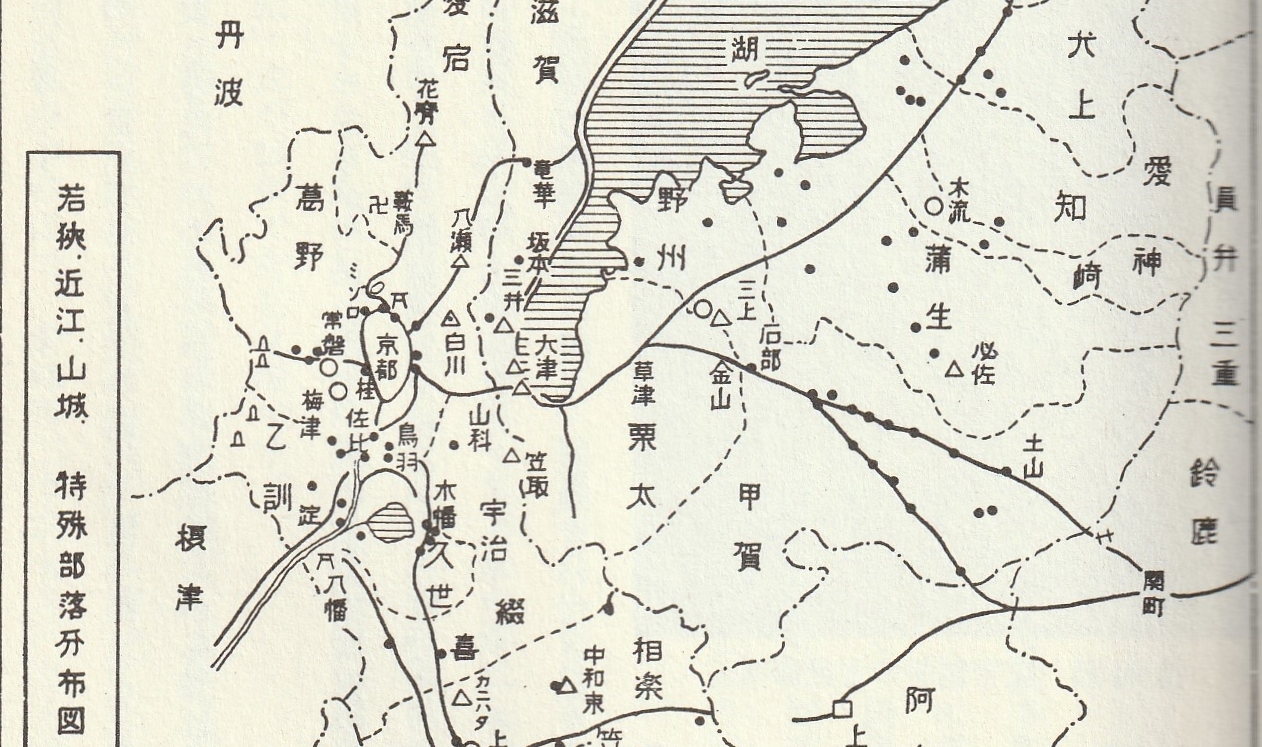
大正時代から昭和の戦前戦後を通して、彼が半世紀かけて訪ねた被差別部落の数は700を上回る。並行して古事記や日本書紀などの史書や古文書類に、可能な限り目を通している。その研究は質、量ともに群を抜いている。
もちろん、山哉よりも先に被差別部落の歴史をたどる書籍を出した人はいた。柳瀬頸介の『社会外の社会 穢多(えた)非人』(1901年)と京都帝大の歴史学者、喜田貞吉教授が主宰する研究誌『民族と歴史』特殊部落研究号(1919年)である。被差別部落の解放を目指して全国水平社が結成されて2年たった1924年には、高橋貞樹が『特殊部落一千年史』という啓蒙書を出版している。
ただ、それぞれ優れた研究ではあったものの、難点があった。3人とも、古代律令国家の頃から賎民制度があり、奴婢(ぬひ)と呼ばれる奴隷がいて、囚われの身となった東北の蝦夷(えみし)が賎民にされたことは承知しており、書籍で触れてもいる。
だが、そうした古代の賎民制度が江戸時代の穢多・非人へと連綿とつながっている、とは見なさなかった。貴族政治から武家政治へと激変した平安から鎌倉時代への移行、さらに戦国時代の下剋上によって社会の階層は流動化し、いわゆる「穢多・非人」は江戸時代に身分制度が固定される中で新たに生み出されたもの、と唱えたのだ。
それをもっとも明確に主張したのは喜田貞吉である。『民族と歴史』特殊部落研究号に喜田は次のように記した。
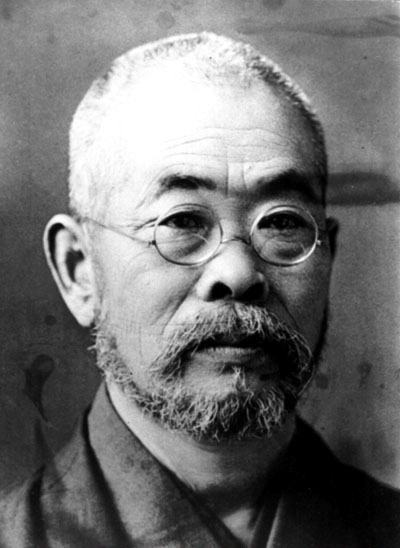
「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するということは、少くとも昔はありませんでした。蝦夷人すなわちアイヌ族の出にして、立派な地位に上ったものも少くない。(中略)有名な征夷大将軍の坂上田村麻呂も、少くとも昔の奥州の人は蝦夷(えぞ)仲間だと思っておりました」
「もともと武士には蝦夷すなわちエビス出身者が多かったから、『徒然草』などを始めとして、鎌倉南北朝頃の書物を見ますと、武士のことを『夷(えびす)』と云っております。鎌倉武士の事を『東夷(あずまえびす)』と云っております」
「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは、徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」
戦後定説となる「被差別部落=近世政治起源説」の原型とも言える学説である。喜田はこれを皇国史観に立って唱えたのだが、「同じ日本人なのになぜ差別する」と憤る水平社の人々にとっても、運動の基盤として好ましい学説だった。
菊池山哉はこうした中で、1927年(昭和2年)に『先住民族と賎民族の研究』を出版し、「エタはエッタがなまったもので我が国の先住民族である」「投降、帰順した東北の蝦夷(えみし)は西日本に移送され、賎民として扱われた」と唱えた。喜田の学説を真っ向から否定したのである。
インドのカースト差別がそうであるように、征服した民族が被征服民族を賎民に落とし込んでいくのは世界各地で見られることである。そうした観点から考えれば、山哉の立論は自然であり、説得力がある。
だが、山哉は当時、在野の無名の郷土史家で、相手は帝大の教授である。山哉の主張はまるで相手にされず、黙殺された。
◇ ◇
戦後も山哉の学説に目を向ける研究者は現れない。水平社の運動を引き継いで再出発した部落解放同盟も相手にしなかった。
それでも、山哉はめげなかった。全国の被差別部落をめぐる「巡礼」のような調査行を半世紀にわたって続け、その成果を亡くなる直前、1966年に大著『別所と特殊部落の研究』にまとめて出版した(1990年代に『特殊部落の研究』『別所と俘囚』の2冊に分けて復刻された)。
踏査を重ねた末に山哉がたどり着いた結論は?東日本と西日本では被差別部落のルーツが異なる?西日本、とくに近畿の部落は「余部(あまべ)」「河原者」「守戸(しゅこ)」「別所」の四つに大別できる?別所とは東北の蝦夷を俘囚(ふしゅう)として移送したところである、というものだった。
山哉がとりわけ力を注いだのが「別所」と呼ばれる部落の調査である。例えば、京都郊外の大原にある別所について、次のように記している(原文は読みにくいため筆者が要約)。
「ここには今は廃寺となった補陀落寺というのがある。『東鑑(あずまかがみ)』によれば、この寺に観音像があったが、奥州平泉の藤原基衡(もとひら)はこの観音像を模したものを作らせ、毛越(もうつう)寺の吉祥堂の本尊にしたという。この寺が奥州と密接な関係にあったことを裏書きするものだ」(『別所と俘囚』165ページ)
近世政治起源説の最大の弱点は、「被差別部落が豊臣政権から徳川政権への移行期に身分制度が固まるにつれて形成された」とするなら、「なぜ東北には部落がほとんどないのか」という問いに答えられない、という点にある。
山哉が説くように「大和朝廷側が古代東北の蝦夷を攻め、投降・帰順した者を移送したところが別所であり、被差別部落になった」のであれば、問いへの答えとして納得がいく。
もちろん、数は極端に少ないが、東北にも別所という地名はあり、被差別部落がある。表は、被差別部落の都道府県別の数と人口(1921年、内務省統計)を一覧表にしたものである。福島に6,山形に4,青森に1となっている。
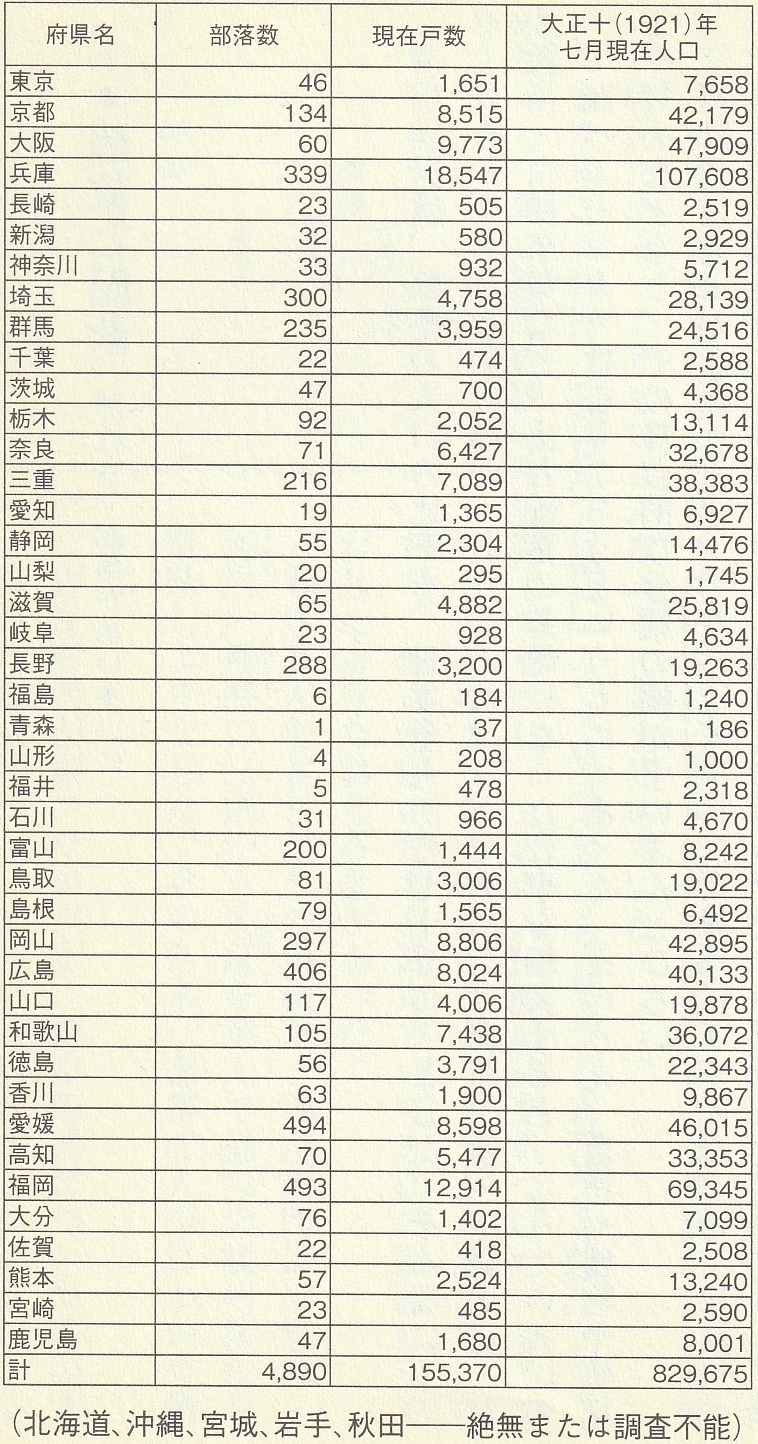
山哉はこれらの被差別部落も一つひとつ調べている。そして、東北の被差別部落のほとんどは江戸時代に国替えになった大名が前任地から引き連れてきたものであることを明らかにした。古代からその土地にあったと考えられる被差別部落は、福島県南部の部落一つだけだった。
◇ ◇
天皇の陵墓に配置され、警護と維持管理にあたる「守戸」についての記述も興味深い。これは東日本にはなく、西日本、とりわけ畿内に集中している。
奈良盆地に「神武天皇陵の守戸をつとめてきた」という被差別部落があった。この部落の人たちは少なくとも持統天皇(7世紀末)の時代から代々、尾根筋にある陵墓を守ってきたが、明治2年(1869年)に新政府がこの人たちに何の相談もなく、平地にある小さな古墳を「神武天皇の陵墓である」と認定してしまった。「そこは違う」と思っても、口に出すことはできなかったという。
古代の天皇陵については、幕末から明治維新にかけての混乱期にあたふたと認定作業を進めたこともあって、「陵墓の治定の誤りが多数ある」とされる。このため、考古学者は発掘調査を望んできたが、宮内庁は戦後も長い間「静安と尊厳を保つのが本義」と調査を拒んできた。大阪府の百舌鳥(もず)・古市古墳群が世界遺産に登録される動きが出る中で、2018年にようやくこれらの古墳の調査を認めたが、ほかの古墳群の調査が認められる見通しは立っていない。
山哉の調査は、そうした天皇陵の治定の誤りを被差別部落の側から照らし出している可能性がある。
自ら足を運び、人々の話にひたすら耳を傾ける。そうやって得た事実を愚直に記録する。それを基に仮説を組み立てていく――山哉が書き残したものは「学者たちが古文書から導き出した立論」などより、はるかに迫力があり、示唆に富む。
彼の著作は民俗学の枠にとどまらず、古代史や考古学にとっても「探求の素材の宝庫」であり、やがては被差別部落の歴史を考えるための古典になっていくのではないか。
(敬称略)
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2022年1月28日
https://news-hunter.org/?p=10695
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
≪写真&表の説明とSource≫
◎山城、近江の別所分布図(菊池山哉『別所と俘囚』から複写、トリミング)
◎喜田貞吉・京都帝大教授(東北大学関係写真データベースから)
http://webdb3.museum.tohoku.ac.jp/tua-photo/photo-img-l.php?mode=i&id=C012811
◎都道府県別の被差別部落の数と人数(1921年、内務省統計)=『部落史入門』から複写
≪参考文献≫
◎『えた非人 社会外の社会』(柳瀬頸介著、塩見鮮一郎訳、河出書房新社)
=『社会外の社会 穢多非人』を改題、復刻
◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫)
=『民族と歴史』特殊部落研究号から喜田の論文を編集、復刻
◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)
=『特殊部落一千年史』を改題
◎『部落史入門』(塩見鮮一郎、河出文庫)
◎『特殊部落の研究』(菊池山哉、批評社)
◎『別所と俘囚』(菊池山哉、批評社)
◎『余多歩き 菊池山哉の人と学問』(前田速夫、晶文社)
歴史は勝者によって綴られる。敗れ去った者たちの声が記されることは、ほとんどない。敗者の姿は歴史の闇の中に消えていく。
大昔、私たちが住む東北には蝦夷(えみし)と呼ばれる人たちが暮らしていた。その東北に、畿内で成立した大和政権の勢力が本格的に進出してくるのは古墳時代の終末期、7世紀からである。
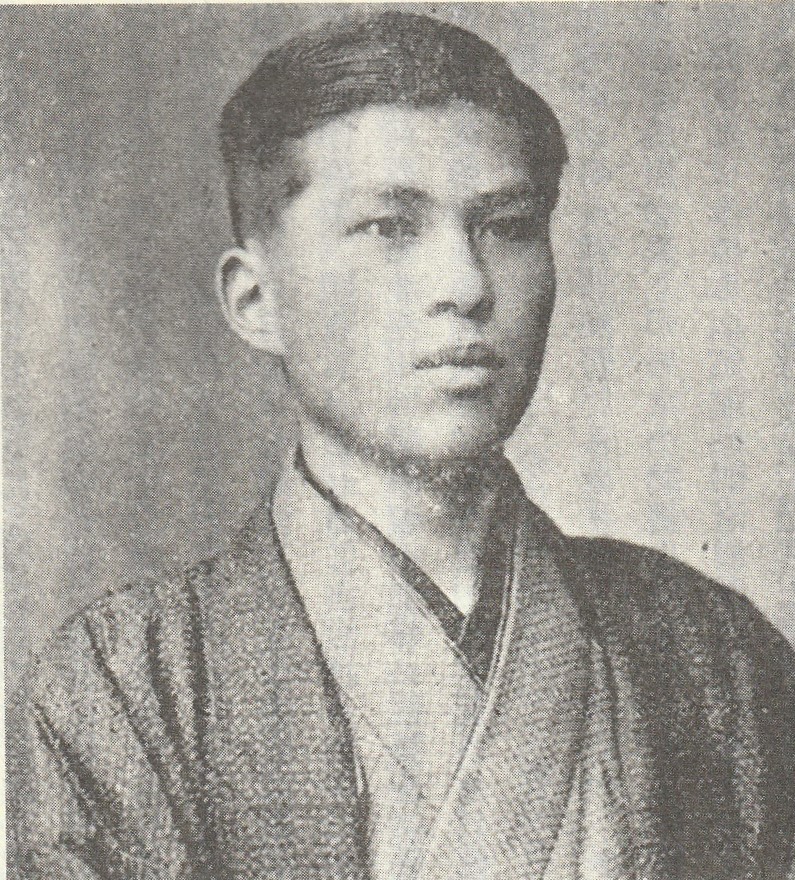
大和の勢力は北関東と越後の2方面から北上していった。8世紀、奈良時代になると、陸奥(福島、宮城、岩手)や出羽(山形、秋田)に「城柵(じょうさく)」と呼ばれる行政・軍事拠点を次々に築いて支配領域を広げ、先住民である蝦夷をのみ込んでいった(図1)。
生活圏に侵入された蝦夷との間に軋轢が生じ、争いになるのは避けられないことだった。奈良時代末期から平安時代の初期にかけて、「38年戦争」が勃発する。それは長く、激しい戦いだった。
戦争はどのようにして始まり、どのような経過をたどり、どう決着したのか。それを知るためには、大和政権側が残した古事記や日本書紀、続日本紀(しょくにほんぎ)、日本後紀(こうき)といった正史や関連史料をひも解くしかない。蝦夷は文字を持たず、記録するすべがなかったからである。
それでも、大和政権側の史書を丹念に読み込み、そこから蝦夷たちが歩んだ道をたどろうとした研究者がいた。岩手大学の古代日本史研究者、高橋崇(たかし)教授(2014年没)である。
それは労多くして実り少ない、落穂拾いのような作業ではあったが、その労苦は中公新書の3部作『蝦夷(えみし)』『蝦夷の末裔』『奥州藤原氏』として結実した。深くこうべを垂れずにはいられない労作である。高橋が残した著作を頼りに、揺れ動いた古代東北の歴史をたどってみる。
◇ ◇
蝦夷とは、どういう人たちだったのか。それを知る手がかりの一つが『日本書紀』の斉明天皇5年(659年)の条にある。この年、大和朝廷が中国の唐に派遣した使節団は東北の蝦夷男女2人を同行させ、唐の高宗に謁見した。遣唐使の渡航日誌によれば、高宗は強い関心を示し、次のような問答が交わされたという(問答の概要を筆者が現代語訳)。
高宗 蝦夷の国はどの方角にあるのか。
遣唐使 東北です。
高宗 蝦夷は幾種あるのか。
遣唐使 3種あります。遠くにいる者は都加留(つかる)、次の者は麁(あら)蝦夷、
近くにいる者を熟(にぎ)蝦夷と名付けています。今回連れて来たのは熟蝦夷
です。毎年、大和朝廷に朝貢しています。
高宗 その国に五穀はあるか。
遣唐使 ありません。肉を食って暮らしています。
唐の高宗は、蝦夷の身体や顔つきが遣唐使たちと異なるのを見て興味津々の様子だったという。この謁見については中国側の史料にも記録されており、事実と見ていい。
都加留は青森県の津軽、麁蝦夷は岩手や秋田に住み大和朝廷に服属しない蝦夷、熟蝦夷とは東北南部にいて大和朝廷に帰順した蝦夷を指すと見られる。当時の東北の政治状況をうかがわせる問答である。
東北の蝦夷と大和勢力との争いは7世紀半ば、斉明天皇の頃から激しくなった。将軍、阿部比羅夫が軍船を率いて日本海沿岸を北上して蝦夷と戦い、投降・帰順した者多数を都に連れ帰ったことが記録されている。遣唐使が中国に連れていったのも、こうした蝦夷だったと見られる。
大和勢力が北へ進むにつれ、抗争はより激しくなっていく。774年、蝦夷が桃生(ものう)城(宮城県石巻市)を襲い、38年戦争の口火を切った。780年には大和側についていた蝦夷の族長、伊治砦麻呂(これはりのあざまろ)が反旗をひるがえし、陸奥の最高責任者である紀広純らを殺害、多賀城を焼き討ちにするという大事件が発生した。
この翌年に即位した桓武天皇はこれを深刻に受けとめ、「蝦夷討伐」の号令を発した。789年、朝廷は関東などから5万余の軍を派遣し、蝦夷の拠点・胆沢(いさわ)(岩手県南部)の制圧をめざして進軍した。
ところが、北上川を挟んでの合戦で朝廷側は胆沢の族長、阿弖流為(あてるい)が率いる蝦夷のゲリラ部隊に惨敗した。多数の溺死者と戦死者を出し、将軍たちまで逃げ出す始末だった。
桓武天皇は激怒し、2回目の討伐軍を派遣する。平安京に遷都した794年、今度は10万の大軍が胆沢に押し寄せた。激しい戦闘になったと見られるが、史料は乏しく、「457人の蝦夷を斬首し、150人を捕虜にした」との戦勝報告が残る程度である。阿弖流為は降伏せず、胆沢も陥落しなかった。
坂上田村麻呂を征夷大将軍とする801年の第3次遠征によって、ようやく蝦夷の抵抗は鎮圧され、阿弖流為らも投降、処刑された。東北一帯での蝦夷との戦争が収束したのは811年、足かけ38年に及んだ。
この戦争で注目されるのは、戦闘で捕虜になったり投降したりした蝦夷が多数、西日本の各地に移送されたことである。彼らは「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれ、四国の伊予に144人、九州の筑紫に578人、畿内の摂津に115人、太宰府管内に395人、日向に66人といった記録が断片的に残っている(図2参照)。家族ごと移送された例もある。総数は不明である。

朝廷はなんのために移送したのか。史書には「蝦夷の野蛮な風俗を変え、文明化するため」といった趣旨の記述もあるが、高橋は捕虜や反抗的な者たちを彼らの根拠地から連れ去り、蝦夷勢力を分断することを狙ったのではないか、との見方を示している。捕虜を賎民として扱った可能性も否定しない。
当然のことながら、移送先となった地方にとっては大きな負担となる。田を持たない彼らから租税を取り立てるわけにはいかない。集団で住まわせることによって、周辺の住民との摩擦も起きる。騒乱もしばしば起きた。
こうしたことに配慮して、朝廷は受け入れた地方に農民から「俘囚料」を取り立て、それで移送された蝦夷の面倒を見るよう命じた。高橋はこの俘囚料についても史書を丹念に調べ、その記録から逆算して、「少なくとも4565人の俘囚を養うのに相当するものだった」との推計を明らかにしている。記録として残されなかった移送も数多くあったことを考慮に入れれば、東北から移送された蝦夷の総数は万単位であったと見ていいだろう。
そもそも、蝦夷とはどういう人たちだったのか。「大和政権の支配地からの逃亡者や落伍者」といった説もあるが、説得力はない。蝦夷の言葉は日本語とはまるで異なり、大和側が交渉する際には通訳を必要とした。風俗や生活習慣もまるで異なるものだった。
アイヌ語地名の研究者として知られる山田秀三の調査によって、北海道だけでなく東北の各地にアイヌ語源と見られる地名が多数残っていることも明らかになっている。
高橋は、こうした地名研究や北海道と東北各地で発掘された土器の共通性にも着目し、蝦夷とは「アイヌ人か、あるいは控え目にいってアイヌ語を使う人、といってよいだろう」と結論づけている。
◇ ◇
西日本の各地に「俘囚」として移住させられた蝦夷たちは、その後どうなったのか。史書は何も語らない。彼らがたどった道を知るすべはない。
だが、この問題の解明にまったく異なる立場から挑んだ人物がいた。在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)(1890―1966年)である。
山哉は明治33年、東京府府中市の富農の4男として生まれた。工学院大学の前身である工手学校の土木科を卒業した後、東京府の土木技師に採用された。後に東京市役所に移った。
技師として工事に携わっている時、作業員の中に「あいつは筋が悪い」と、うとまれる者がいることに気づき、奥多摩にあるその人の村を訪ねていった。村人の話を聞いても、差別される理由は見当がつかなかった。
同じ頃、沖積層の中に分厚い貝塚がある現場に幾度か出くわし、「先史時代にこの巨大な貝塚をつくったのはどういう人たちか」との疑問を抱く。勤務のかたわら、被差別部落と古代史の研究にのめり込んでいった。在野の民俗学者、菊池山哉の誕生である。
何事であれ、現場を訪ね、自分の目で確かめる。山哉は生涯、その流儀を貫いた。全国の被差別部落を訪ね回り、そこに住む人たちの話に耳を傾け、そこから自分の仮説と理論を構築していった。
大正12年(1923年)7月、その成果を『穢多(えた)族に関する研究』と題した本にまとめ、自費出版した。「穢多・非人」と呼ばれ、差別されてきた人たちの状況を詳細に報告し、その歴史的な経緯についての自説を次のように展開した。
「エタとはエッタのなまったもので民族名である。彼らはわが国の先住民族と考えられる」「後からやって来たヤマトが彼らを駆逐した」「ヤマトに抵抗し、俘囚として移送された蝦夷は被差別民にされた」
折しも、その前年に被差別部落の人たちは「全国水平社」を立ち上げ、部落解放運動に乗り出したばかりだった。運動は「差別は豊臣政権から徳川政権の初期にかけて形成された身分制度が起源」とする、いわゆる近世政治起源説に依拠している。山哉の説はこれを真っ向から否定するものだった。
出版予告の広告を見た水平社の幹部は、融和事業を担当する内務省に「差別図書だ」と猛烈な圧力をかけた。近世政治起源説を唱える京都帝大の喜田貞吉教授らも動き、本は「安寧秩序を乱す」として発禁処分になった。直後に関東大震災に見舞われたこともあって、すぐには改訂もかなわなかった。
興味深いのはこの後である。山哉は出版をあきらめなかった。内務省の高官や水平社の幹部に会い、この本は純粋な学術書であること、差別がいわれなきものであることを世に問うものである、と訴えた。内容にも手を加えて4年後、『先住民族と賎民族の研究』と改題して出版した。
今度は応援してくれる研究者もいた。水平社の平野小剣(しょうけん)・関東執行委員長に至っては「先に糾弾したのは自分らの誤りであった。根本思想についての研究のあった方がむしろ良い」と推薦文まで寄せてくれた。
にもかかわらず、この本が市中に出回ることはなかった。中央融和事業協会がすべて買い取ってしまったからである。「部落差別は近世の政治的所産」と主張する水平社も相手にしなかった。
刺激的すぎたという点に加えて、山哉の立論自体にも難点があった。彼はこの本で、当時有力だった「東北の蝦夷はアイヌである」という説を否定し、「日本の先住民族のうちで多数を占めたのは北方ツングース系の少数民族、オロッコ(ウイルタ)である。蝦夷と呼ばれた人たちもその多くはオロッコと見られる」と唱えたのだ(戦後、調査を重ね、この部分は撤回している)。
「日本列島にはアイヌ以前に住んでいた民族がいた」という説は目新しいものではない。大森貝塚を発見したことで知られるエドワード・S・モースが明治初期に最初に唱え、「プレ・アイヌ説」と呼ばれた。その後、日本の人類学の先駆者、坪井正五郎(しょうごろう)も「アイヌ民族の伝承に出てくるコロボックルこそ日本の旧石器人である」と唱え、大論争を巻き起こしている。
山哉の立論はこうした論争に影響を受けたものと思われるが、それを支える材料に乏しく、荒唐無稽な印象を与えたようだ。考古学会にも民俗学者にも黙殺された。
だが、山哉は少しもひるまなかった。「多麻史談会」という郷土史研究の会(のち「東京史談会」に改称)を主宰し、全国の被差別部落を訪ね歩き、その成果を会報に発表し続けた。
戦前から戦後にかけて、四国から九州まで、山哉が訪ねた被差別部落は700を超える。車ではたどり着けない山奥の村から吊り橋を渡らなければならない村まで、気の遠くなるような行脚を重ねた。
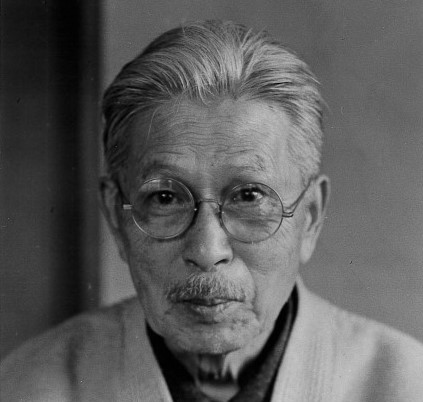
1966年、死の直前に山哉は半世紀に及ぶ研究の集大成とも言える大著『別所と特殊部落の研究』を出版した。調べ尽くしたうえでたどり着いた結論は、次のようなものだった。
(1)東日本と西日本では被差別部落のルーツが異なる(2)西日本、とくに近畿の部落は「余部(あまべ)」「河原者」「守戸」「別所」の四つに大別できる(3)別所とは東北の蝦夷を俘囚として移送したところである。
四つのルーツそれぞれについての説明は複雑きわまりないので割愛する。重要なのは、大和政権と戦い俘囚として西に移送された蝦夷は、被差別部落民のルーツの一つである、と結論づけたことである。
著書には、全国に散在する「別所」と呼ばれる部落を訪ね、そこに住む人々から聞いた話が克明に記録してある。それは、歴史の闇に消えた人々の姿を浮かび上がらせるものだった。
被差別部落について、これほど網羅的かつ詳細に調べた研究者は、菊池山哉以外にはいない。にもかかわらず、歴史学会でも民俗学会でも、山哉の業績が正面から議論されることはなかった。
水平社の運動を引き継ぎ、戦後、部落解放同盟として再出発した人たちも無視し続けた。無視しただけではない。近世政治起源説に固執し、それ以外の幅広い視点から研究に踏み出すことができないような状況をつくり出した。
なぜ、このような状況が長く続いたのか。文芸誌の編集長をつとめ、菊池山哉の再評価に力を注ぐ前田速夫は、編著『日本原住民と被差別部落』に次のように記した。
「こうした当たり前のことを誰も言えなかったのは、私が思うに、天皇制と被差別部落は近代日本の二大ダブーだったからだろう。両者が表裏の関係にあるとは、よく言われることだが、それを突き詰めて考えた人は驚くほど少ない。(中略)賢明な学者はみな用心深くそれを避けた。山哉はそこが他のどの研究者とも違っていた」
彼の著作と業績にあらためて光が当てられるようになるのは、1990年代になってからである。山哉の大著『別所と特殊部落の研究』は、批評社から『特殊部落の研究』(1993年)と『別所と俘囚』(1996年)の2冊に分けて復刻された。先の前田の編著が出版されたのは2009年である。
私は2011年に山哉のことを初めて知り、その後、2018年に出版された『被差別民の起源』を手にした。この本は、大正12年に発禁処分となった山哉の最初の本『穢多族に関する研究』を改題、復刻したものである。その目次を見ただけで圧倒され、山哉が費やしたであろうエネルギーと時間を思って身が震えた。
私は長く新聞記者として働き、現場に足を運んで人の話に耳を傾け、なにがしかのものを書く仕事をしてきた。この本にはそういう職人の心を揺さぶるものがあった。前田が記すように、山哉の著作は「空前絶後の民俗探求の宝庫」である、と感じた。
同時に、イデオロギーや利害にからめとられ、愚直に事実を追い求める心を失った時、社会で何が起きるかを見せつけられた思いがした。
これほどの宝を黙殺する社会、これほどの業績に目を向けようとしないアカデミズムとは何なのか。私たちは今も、身近なところで同じような過ちと失敗を繰り返しているのではないか。そうした思いが身の震えを大きくしたのかもしれない。
救いは、ごく少数ではあっても、山哉の偉業を忘れず、それを後世に伝えるために力を尽くした人たちがいたことだ。そして、その志を引き継ぎ、広めようとする人たちがいることに勇気づけられる。
大きな歴史の流れから見れば、菊池山哉が紡いだ糸はか細いものかもしれない。けれども、それは強靭な糸である。より多くの人が自らの糸を持ち寄り、撚(よ)り合わせれば、太い糸となって豊かな輝きを放つのではないか。そう信じて、私も一本の糸を持ち寄る列に加わりたい。 (敬称略)
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
【訂正】平城京から長岡京に遷都した784年、平安京に遷都した794年以降は「大和政権」や「大和朝廷」と表現するのは不適切なので、「朝廷」あるいは「朝廷側」と手直しした(2022年4月19日追記)。
*メールマガジン「風切通信 99」 2021年12月21日
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2021年12月21日
≪図・写真の説明とSource≫
◎写真 若き日の菊池山哉。大正2年か3年の撮影(『余多歩き 菊池山哉の人と学問』から複写)
◎図1 東北への大和政権の進出状況(『詳説 日本史』山川出版社、1982年から複写)
◎図2 蝦夷が俘囚として移送された地方(高橋崇『蝦夷』から複写)
◎写真 晩年の菊池山哉(家族提供)
≪参考文献≫
◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)
◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)
◎『奥州藤原氏』(高橋崇、中公新書)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也、吉川弘文館)
◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草風館)
◎『被差別民の起源』(菊池山哉、河出書房新社)
◎『特殊部落の研究』(菊池山哉、批評社)
◎『別所と俘囚』(菊池山哉、批評社)
◎『余多歩き菊池山哉の人と学問』(前田速夫、晶文社)
◎『日本原住民と被差別部落』(前田速夫編、河出書房新社)
◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・連載12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
・連載13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月298日)
大昔、私たちが住む東北には蝦夷(えみし)と呼ばれる人たちが暮らしていた。その東北に、畿内で成立した大和政権の勢力が本格的に進出してくるのは古墳時代の終末期、7世紀からである。
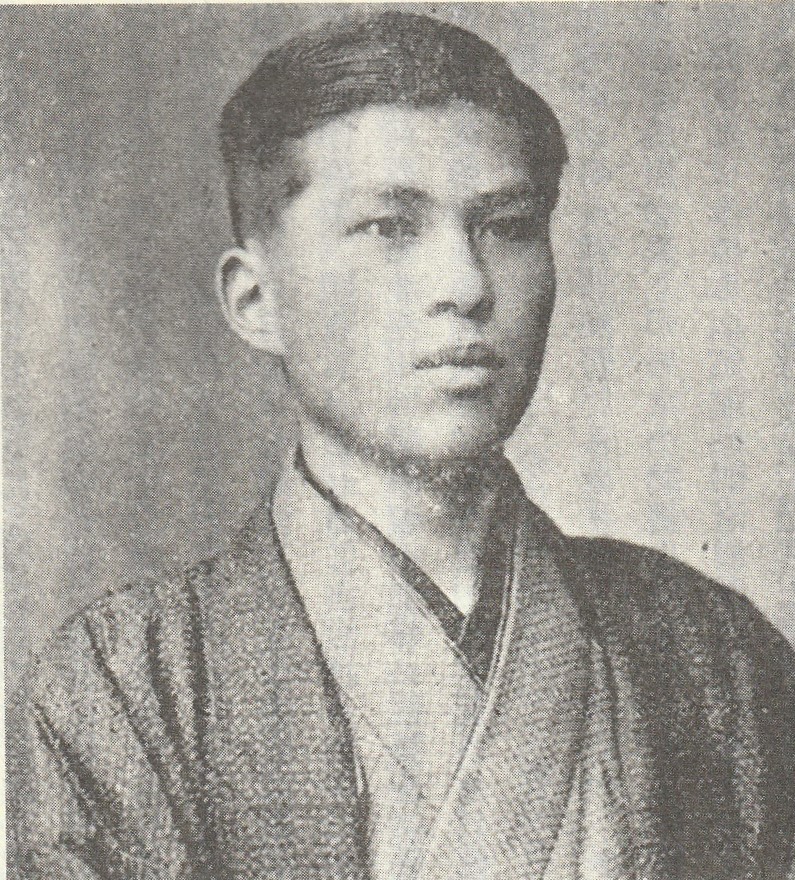
大和の勢力は北関東と越後の2方面から北上していった。8世紀、奈良時代になると、陸奥(福島、宮城、岩手)や出羽(山形、秋田)に「城柵(じょうさく)」と呼ばれる行政・軍事拠点を次々に築いて支配領域を広げ、先住民である蝦夷をのみ込んでいった(図1)。
生活圏に侵入された蝦夷との間に軋轢が生じ、争いになるのは避けられないことだった。奈良時代末期から平安時代の初期にかけて、「38年戦争」が勃発する。それは長く、激しい戦いだった。
戦争はどのようにして始まり、どのような経過をたどり、どう決着したのか。それを知るためには、大和政権側が残した古事記や日本書紀、続日本紀(しょくにほんぎ)、日本後紀(こうき)といった正史や関連史料をひも解くしかない。蝦夷は文字を持たず、記録するすべがなかったからである。
それでも、大和政権側の史書を丹念に読み込み、そこから蝦夷たちが歩んだ道をたどろうとした研究者がいた。岩手大学の古代日本史研究者、高橋崇(たかし)教授(2014年没)である。
それは労多くして実り少ない、落穂拾いのような作業ではあったが、その労苦は中公新書の3部作『蝦夷(えみし)』『蝦夷の末裔』『奥州藤原氏』として結実した。深くこうべを垂れずにはいられない労作である。高橋が残した著作を頼りに、揺れ動いた古代東北の歴史をたどってみる。
◇ ◇
蝦夷とは、どういう人たちだったのか。それを知る手がかりの一つが『日本書紀』の斉明天皇5年(659年)の条にある。この年、大和朝廷が中国の唐に派遣した使節団は東北の蝦夷男女2人を同行させ、唐の高宗に謁見した。遣唐使の渡航日誌によれば、高宗は強い関心を示し、次のような問答が交わされたという(問答の概要を筆者が現代語訳)。
高宗 蝦夷の国はどの方角にあるのか。
遣唐使 東北です。
高宗 蝦夷は幾種あるのか。
遣唐使 3種あります。遠くにいる者は都加留(つかる)、次の者は麁(あら)蝦夷、
近くにいる者を熟(にぎ)蝦夷と名付けています。今回連れて来たのは熟蝦夷
です。毎年、大和朝廷に朝貢しています。
高宗 その国に五穀はあるか。
遣唐使 ありません。肉を食って暮らしています。
唐の高宗は、蝦夷の身体や顔つきが遣唐使たちと異なるのを見て興味津々の様子だったという。この謁見については中国側の史料にも記録されており、事実と見ていい。
都加留は青森県の津軽、麁蝦夷は岩手や秋田に住み大和朝廷に服属しない蝦夷、熟蝦夷とは東北南部にいて大和朝廷に帰順した蝦夷を指すと見られる。当時の東北の政治状況をうかがわせる問答である。
東北の蝦夷と大和勢力との争いは7世紀半ば、斉明天皇の頃から激しくなった。将軍、阿部比羅夫が軍船を率いて日本海沿岸を北上して蝦夷と戦い、投降・帰順した者多数を都に連れ帰ったことが記録されている。遣唐使が中国に連れていったのも、こうした蝦夷だったと見られる。
大和勢力が北へ進むにつれ、抗争はより激しくなっていく。774年、蝦夷が桃生(ものう)城(宮城県石巻市)を襲い、38年戦争の口火を切った。780年には大和側についていた蝦夷の族長、伊治砦麻呂(これはりのあざまろ)が反旗をひるがえし、陸奥の最高責任者である紀広純らを殺害、多賀城を焼き討ちにするという大事件が発生した。
この翌年に即位した桓武天皇はこれを深刻に受けとめ、「蝦夷討伐」の号令を発した。789年、朝廷は関東などから5万余の軍を派遣し、蝦夷の拠点・胆沢(いさわ)(岩手県南部)の制圧をめざして進軍した。
ところが、北上川を挟んでの合戦で朝廷側は胆沢の族長、阿弖流為(あてるい)が率いる蝦夷のゲリラ部隊に惨敗した。多数の溺死者と戦死者を出し、将軍たちまで逃げ出す始末だった。
桓武天皇は激怒し、2回目の討伐軍を派遣する。平安京に遷都した794年、今度は10万の大軍が胆沢に押し寄せた。激しい戦闘になったと見られるが、史料は乏しく、「457人の蝦夷を斬首し、150人を捕虜にした」との戦勝報告が残る程度である。阿弖流為は降伏せず、胆沢も陥落しなかった。
坂上田村麻呂を征夷大将軍とする801年の第3次遠征によって、ようやく蝦夷の抵抗は鎮圧され、阿弖流為らも投降、処刑された。東北一帯での蝦夷との戦争が収束したのは811年、足かけ38年に及んだ。
この戦争で注目されるのは、戦闘で捕虜になったり投降したりした蝦夷が多数、西日本の各地に移送されたことである。彼らは「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれ、四国の伊予に144人、九州の筑紫に578人、畿内の摂津に115人、太宰府管内に395人、日向に66人といった記録が断片的に残っている(図2参照)。家族ごと移送された例もある。総数は不明である。

朝廷はなんのために移送したのか。史書には「蝦夷の野蛮な風俗を変え、文明化するため」といった趣旨の記述もあるが、高橋は捕虜や反抗的な者たちを彼らの根拠地から連れ去り、蝦夷勢力を分断することを狙ったのではないか、との見方を示している。捕虜を賎民として扱った可能性も否定しない。
当然のことながら、移送先となった地方にとっては大きな負担となる。田を持たない彼らから租税を取り立てるわけにはいかない。集団で住まわせることによって、周辺の住民との摩擦も起きる。騒乱もしばしば起きた。
こうしたことに配慮して、朝廷は受け入れた地方に農民から「俘囚料」を取り立て、それで移送された蝦夷の面倒を見るよう命じた。高橋はこの俘囚料についても史書を丹念に調べ、その記録から逆算して、「少なくとも4565人の俘囚を養うのに相当するものだった」との推計を明らかにしている。記録として残されなかった移送も数多くあったことを考慮に入れれば、東北から移送された蝦夷の総数は万単位であったと見ていいだろう。
そもそも、蝦夷とはどういう人たちだったのか。「大和政権の支配地からの逃亡者や落伍者」といった説もあるが、説得力はない。蝦夷の言葉は日本語とはまるで異なり、大和側が交渉する際には通訳を必要とした。風俗や生活習慣もまるで異なるものだった。
アイヌ語地名の研究者として知られる山田秀三の調査によって、北海道だけでなく東北の各地にアイヌ語源と見られる地名が多数残っていることも明らかになっている。
高橋は、こうした地名研究や北海道と東北各地で発掘された土器の共通性にも着目し、蝦夷とは「アイヌ人か、あるいは控え目にいってアイヌ語を使う人、といってよいだろう」と結論づけている。
◇ ◇
西日本の各地に「俘囚」として移住させられた蝦夷たちは、その後どうなったのか。史書は何も語らない。彼らがたどった道を知るすべはない。
だが、この問題の解明にまったく異なる立場から挑んだ人物がいた。在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)(1890―1966年)である。
山哉は明治33年、東京府府中市の富農の4男として生まれた。工学院大学の前身である工手学校の土木科を卒業した後、東京府の土木技師に採用された。後に東京市役所に移った。
技師として工事に携わっている時、作業員の中に「あいつは筋が悪い」と、うとまれる者がいることに気づき、奥多摩にあるその人の村を訪ねていった。村人の話を聞いても、差別される理由は見当がつかなかった。
同じ頃、沖積層の中に分厚い貝塚がある現場に幾度か出くわし、「先史時代にこの巨大な貝塚をつくったのはどういう人たちか」との疑問を抱く。勤務のかたわら、被差別部落と古代史の研究にのめり込んでいった。在野の民俗学者、菊池山哉の誕生である。
何事であれ、現場を訪ね、自分の目で確かめる。山哉は生涯、その流儀を貫いた。全国の被差別部落を訪ね回り、そこに住む人たちの話に耳を傾け、そこから自分の仮説と理論を構築していった。
大正12年(1923年)7月、その成果を『穢多(えた)族に関する研究』と題した本にまとめ、自費出版した。「穢多・非人」と呼ばれ、差別されてきた人たちの状況を詳細に報告し、その歴史的な経緯についての自説を次のように展開した。
「エタとはエッタのなまったもので民族名である。彼らはわが国の先住民族と考えられる」「後からやって来たヤマトが彼らを駆逐した」「ヤマトに抵抗し、俘囚として移送された蝦夷は被差別民にされた」
折しも、その前年に被差別部落の人たちは「全国水平社」を立ち上げ、部落解放運動に乗り出したばかりだった。運動は「差別は豊臣政権から徳川政権の初期にかけて形成された身分制度が起源」とする、いわゆる近世政治起源説に依拠している。山哉の説はこれを真っ向から否定するものだった。
出版予告の広告を見た水平社の幹部は、融和事業を担当する内務省に「差別図書だ」と猛烈な圧力をかけた。近世政治起源説を唱える京都帝大の喜田貞吉教授らも動き、本は「安寧秩序を乱す」として発禁処分になった。直後に関東大震災に見舞われたこともあって、すぐには改訂もかなわなかった。
興味深いのはこの後である。山哉は出版をあきらめなかった。内務省の高官や水平社の幹部に会い、この本は純粋な学術書であること、差別がいわれなきものであることを世に問うものである、と訴えた。内容にも手を加えて4年後、『先住民族と賎民族の研究』と改題して出版した。
今度は応援してくれる研究者もいた。水平社の平野小剣(しょうけん)・関東執行委員長に至っては「先に糾弾したのは自分らの誤りであった。根本思想についての研究のあった方がむしろ良い」と推薦文まで寄せてくれた。
にもかかわらず、この本が市中に出回ることはなかった。中央融和事業協会がすべて買い取ってしまったからである。「部落差別は近世の政治的所産」と主張する水平社も相手にしなかった。
刺激的すぎたという点に加えて、山哉の立論自体にも難点があった。彼はこの本で、当時有力だった「東北の蝦夷はアイヌである」という説を否定し、「日本の先住民族のうちで多数を占めたのは北方ツングース系の少数民族、オロッコ(ウイルタ)である。蝦夷と呼ばれた人たちもその多くはオロッコと見られる」と唱えたのだ(戦後、調査を重ね、この部分は撤回している)。
「日本列島にはアイヌ以前に住んでいた民族がいた」という説は目新しいものではない。大森貝塚を発見したことで知られるエドワード・S・モースが明治初期に最初に唱え、「プレ・アイヌ説」と呼ばれた。その後、日本の人類学の先駆者、坪井正五郎(しょうごろう)も「アイヌ民族の伝承に出てくるコロボックルこそ日本の旧石器人である」と唱え、大論争を巻き起こしている。
山哉の立論はこうした論争に影響を受けたものと思われるが、それを支える材料に乏しく、荒唐無稽な印象を与えたようだ。考古学会にも民俗学者にも黙殺された。
だが、山哉は少しもひるまなかった。「多麻史談会」という郷土史研究の会(のち「東京史談会」に改称)を主宰し、全国の被差別部落を訪ね歩き、その成果を会報に発表し続けた。
戦前から戦後にかけて、四国から九州まで、山哉が訪ねた被差別部落は700を超える。車ではたどり着けない山奥の村から吊り橋を渡らなければならない村まで、気の遠くなるような行脚を重ねた。
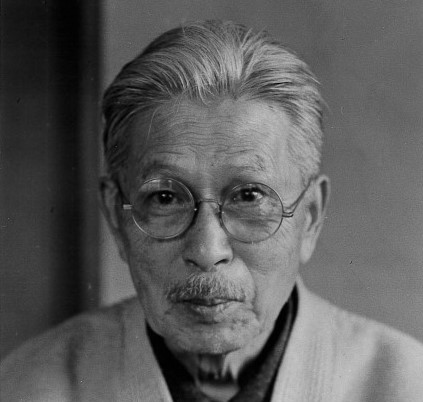
1966年、死の直前に山哉は半世紀に及ぶ研究の集大成とも言える大著『別所と特殊部落の研究』を出版した。調べ尽くしたうえでたどり着いた結論は、次のようなものだった。
(1)東日本と西日本では被差別部落のルーツが異なる(2)西日本、とくに近畿の部落は「余部(あまべ)」「河原者」「守戸」「別所」の四つに大別できる(3)別所とは東北の蝦夷を俘囚として移送したところである。
四つのルーツそれぞれについての説明は複雑きわまりないので割愛する。重要なのは、大和政権と戦い俘囚として西に移送された蝦夷は、被差別部落民のルーツの一つである、と結論づけたことである。
著書には、全国に散在する「別所」と呼ばれる部落を訪ね、そこに住む人々から聞いた話が克明に記録してある。それは、歴史の闇に消えた人々の姿を浮かび上がらせるものだった。
被差別部落について、これほど網羅的かつ詳細に調べた研究者は、菊池山哉以外にはいない。にもかかわらず、歴史学会でも民俗学会でも、山哉の業績が正面から議論されることはなかった。
水平社の運動を引き継ぎ、戦後、部落解放同盟として再出発した人たちも無視し続けた。無視しただけではない。近世政治起源説に固執し、それ以外の幅広い視点から研究に踏み出すことができないような状況をつくり出した。
なぜ、このような状況が長く続いたのか。文芸誌の編集長をつとめ、菊池山哉の再評価に力を注ぐ前田速夫は、編著『日本原住民と被差別部落』に次のように記した。
「こうした当たり前のことを誰も言えなかったのは、私が思うに、天皇制と被差別部落は近代日本の二大ダブーだったからだろう。両者が表裏の関係にあるとは、よく言われることだが、それを突き詰めて考えた人は驚くほど少ない。(中略)賢明な学者はみな用心深くそれを避けた。山哉はそこが他のどの研究者とも違っていた」
彼の著作と業績にあらためて光が当てられるようになるのは、1990年代になってからである。山哉の大著『別所と特殊部落の研究』は、批評社から『特殊部落の研究』(1993年)と『別所と俘囚』(1996年)の2冊に分けて復刻された。先の前田の編著が出版されたのは2009年である。
私は2011年に山哉のことを初めて知り、その後、2018年に出版された『被差別民の起源』を手にした。この本は、大正12年に発禁処分となった山哉の最初の本『穢多族に関する研究』を改題、復刻したものである。その目次を見ただけで圧倒され、山哉が費やしたであろうエネルギーと時間を思って身が震えた。
私は長く新聞記者として働き、現場に足を運んで人の話に耳を傾け、なにがしかのものを書く仕事をしてきた。この本にはそういう職人の心を揺さぶるものがあった。前田が記すように、山哉の著作は「空前絶後の民俗探求の宝庫」である、と感じた。
同時に、イデオロギーや利害にからめとられ、愚直に事実を追い求める心を失った時、社会で何が起きるかを見せつけられた思いがした。
これほどの宝を黙殺する社会、これほどの業績に目を向けようとしないアカデミズムとは何なのか。私たちは今も、身近なところで同じような過ちと失敗を繰り返しているのではないか。そうした思いが身の震えを大きくしたのかもしれない。
救いは、ごく少数ではあっても、山哉の偉業を忘れず、それを後世に伝えるために力を尽くした人たちがいたことだ。そして、その志を引き継ぎ、広めようとする人たちがいることに勇気づけられる。
大きな歴史の流れから見れば、菊池山哉が紡いだ糸はか細いものかもしれない。けれども、それは強靭な糸である。より多くの人が自らの糸を持ち寄り、撚(よ)り合わせれば、太い糸となって豊かな輝きを放つのではないか。そう信じて、私も一本の糸を持ち寄る列に加わりたい。 (敬称略)
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
【訂正】平城京から長岡京に遷都した784年、平安京に遷都した794年以降は「大和政権」や「大和朝廷」と表現するのは不適切なので、「朝廷」あるいは「朝廷側」と手直しした(2022年4月19日追記)。
*メールマガジン「風切通信 99」 2021年12月21日
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2021年12月21日
≪図・写真の説明とSource≫
◎写真 若き日の菊池山哉。大正2年か3年の撮影(『余多歩き 菊池山哉の人と学問』から複写)
◎図1 東北への大和政権の進出状況(『詳説 日本史』山川出版社、1982年から複写)
◎図2 蝦夷が俘囚として移送された地方(高橋崇『蝦夷』から複写)
◎写真 晩年の菊池山哉(家族提供)
≪参考文献≫
◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)
◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)
◎『奥州藤原氏』(高橋崇、中公新書)
◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也、吉川弘文館)
◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草風館)
◎『被差別民の起源』(菊池山哉、河出書房新社)
◎『特殊部落の研究』(菊池山哉、批評社)
◎『別所と俘囚』(菊池山哉、批評社)
◎『余多歩き菊池山哉の人と学問』(前田速夫、晶文社)
◎『日本原住民と被差別部落』(前田速夫編、河出書房新社)
◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)
◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧
・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)
・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)
・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)
・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)
・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)
・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)
・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)
・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)
・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)
・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)
・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)
・連載12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)
・連載13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月298日)
政務活動費の不正受給と聞けば、多くの人は兵庫県の「号泣県議」こと、野々村竜太郎県議のことを思い浮かべるのではないだろうか。

不正が発覚したのは2014年である。ものすごい数のカラ出張を繰り返す。切手を大量に購入して換金する。そうした手法で政務活動費として使ったことにして公金をだまし取っていた。その年の7月には記者会見中に泣きじゃくり、その異様な姿は海外でも報じられた。
野々村氏は兵庫県議会の各会派代表の連名で刑事告発された。翌2015年8月に913万円を詐取したとして詐欺および虚偽公文書作成・同行使容疑で在宅起訴され、2016年7月に懲役3年、執行猶予4年の神戸地裁判決が確定した。
一連の騒ぎの間、山形県議の野川政文氏は勤務実態のない女性事務員を雇用したと偽り、人件費として毎月8万円を計上し、公金をだまし取っていた。年額96万円になる(後に2008年から続けていたことが判明)。
野々村氏の判決が確定した後、2016年9月には山形県内でも阿部賢一県議の政務活動費の不正受給が明るみに出た。山形新聞がスクープしたもので、会合費や事務費をごまかしていた。阿部県議は辞職し、県議会事務局によると最終的に663万円を返納した。
野川氏はこの時、山形県議会議長で「阿部県議の刑事告発を検討する」と表明している(民進党や社民党県議らでつくる県政クラブが反対して告発はされなかった)。おまけに野川氏は全国都道府県議会議長会の会長でもあった。2016年10月中旬には、全国議長会の会長として自民党との政策懇談会に出席し、要望事項を伝えたりしている。

にもかかわらず、その後も素知らぬ顔で架空の人件費を計上し、公金をだまし取っていた。よくそんなことが続けられたものだと思う。
◇ ◇
野川氏の長年の悪事が露見したのは11月4日である。NHK山形放送局が朝のニュースで特ダネとして報じ、新聞・テレビ各社が追いかけた。
市民オンブズマン山形県会議も報道の裏付けに走り、信頼できる筋から「本人は不正を認め、辞職する意向と聞いている」との情報を得た。その日の夕方には県政記者クラブで緊急会見を開き、「刑事告発も検討する」と表明した。
山形県に限らず、市民オンブズマンは全国で議員の政務活動費の不正を追及してきた。監査請求を繰り返し、撥(は)ねつけられると、裁判に訴えて不正をただそうとしてきた。「政務活動費の収支報告書や領収書類をインターネットで公開し、その内容をガラス張りにすべきだ」と提言もしている。
だが、山形県議会はこの間、ほとんど何の努力もしてこなかった。一方、足もとの山形市議会では、議長がリーダーシップを発揮して領収書のインターネット公開など次々に改善策を打ち出した。
その結果、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年公表している「政務活動費の情報公開度ランキング」で、山形市議会は2019年の「中核市の議会でビリから3番目」から今年は「全国2位」(1位は函館市議会)へと大躍進した。改革どころか何もしない山形県議会は毎年、ズルズルと順位を下げ、今年は29位まで落ちた。その挙げ句に、県議会議長経験者の不正である。山形のオンブズマンが怒るのは当然ではないか。
不正受給が発覚すると、野川氏は2日後の6日に県議会の坂本貴美雄議長に辞職願を出し、身を引いた。15日には山形市内のレンタル会議場で記者会見を開き、人件費の架空計上が2008年度からの13年間で総額1248万円に上ることを明らかにした。
記者会見では、自宅の一部を事務所として使い、その電気代や水道代、灯油代などでも不適切な支出があるのではないかと追及され、否定しなかった。不正は人件費の架空請求にとどまらず、総額は有罪判決を受けた野々村氏のそれをかなり上回る。
不可解なのは、その後の山形県議会と山形県当局の対応である。坂本議長は「個人のモラルの問題」とし、刑事告発については「考えていない」と述べた。あきれる。「モラルの問題」であると同時に、政務活動費の制度と運用が問われているのだ。
坂本議長は「県議会には法人格がない。議会としての告発は法制度上できない」とも述べた。議会に「法人格」がないことくらい言われなくても分かっている。ならば、議会を代表して議長として、あるいは兵庫県議会のように各会派代表の連名で告発すればいいのだ。
公金詐取の被害者は納税者であり、それを代表すべきは県知事である。こちらは告発ではなく、告訴すべき立場にある。ところが、山形県の吉村美栄子知事は記者会見で対応を問われると、「一義的には議会が対応すべきこと。議会の独立性、自主性を尊重したい」と述べた。この発言だけ聞けば、もっともらしい。
だが、吉村知事は今年3月、若松正俊副知事の再任人事案が県議会で否決されるや、若松氏を議会の同意がいらない非常勤特別職に任命して続投させた。議会をこけにする暴挙である。なのに、こういう時は「議会を尊重する」と言って逃げようとする。つくづく、いい加減な政治家である。
ことは巨額の詐欺事件である。本人も詐取したことを認めている。血税をだまし取った人間がいるなら、納税者の代表として知事が告訴するのは当然のことであり、責務であると言ってもいい。
野川氏は会見で「(詐取した金を)私的には使っていない」と繰り返した。それを見出しに取った愚かな新聞もあるが、だまし取った金をどう使ったかは詐欺罪の立件には関係がない。刑の言い渡しに際して「情状酌量の材料の一つ」になるに過ぎない。
一般人が一般人から金をだまし取る詐欺でも罪は重い。ましてや、政務活動費が適切に使われるようにする責任を負う県議会の議長経験者が公金をだまし取ったのである。議会が告発し、知事が告訴するのは当然ではないか。
知事や議会のこうした対応を見ていると、この人たちは「不正を知っても、こっそりと処理して闇に葬ってしまおうとしていたのではないか」と疑ってしまう。
あらためて、報道の大切さを思う。悪いことは悪い。許されないことは許してはならない。政治や行政をしっかり監視して不正を暴くのは、報道機関の重要な役割の一つである。
警察や検察がお目こぼしをしようとしても、それが納税者のためにならないなら、見過ごしてはならない。真相の解明に果敢に挑み、人々に伝えなければならない。日々の出来事の報道ももちろん大切なことだが、やはり「スクーブ」こそ、報道の要と言うべきだろう。
長岡 昇( NPO「ブナの森」 代表)
*メールマガジン「風切通信 98」 2021年11月27日
*この文章は、月刊『素晴らしい山形』2021年12月号に寄稿したコラムを手直しし、加筆したものです。
≪写真説明&Source≫
◎記者会見で号泣する野々村竜太郎県議
https://looking.fandom.com/ja/wiki/%E9%87%8E%E3%80%85%E6%9D%91%E7%AB%9C%E5%A4%AA%E9%83%8E
◎2016年10月19日、自民党との政策懇談会で全国都道府県議会議長会の会長として発言する野川政文氏(全国都道府県議会議長会のサイトから)
http://www.gichokai.gr.jp/topics/2016/161019/index.html

不正が発覚したのは2014年である。ものすごい数のカラ出張を繰り返す。切手を大量に購入して換金する。そうした手法で政務活動費として使ったことにして公金をだまし取っていた。その年の7月には記者会見中に泣きじゃくり、その異様な姿は海外でも報じられた。
野々村氏は兵庫県議会の各会派代表の連名で刑事告発された。翌2015年8月に913万円を詐取したとして詐欺および虚偽公文書作成・同行使容疑で在宅起訴され、2016年7月に懲役3年、執行猶予4年の神戸地裁判決が確定した。
一連の騒ぎの間、山形県議の野川政文氏は勤務実態のない女性事務員を雇用したと偽り、人件費として毎月8万円を計上し、公金をだまし取っていた。年額96万円になる(後に2008年から続けていたことが判明)。
野々村氏の判決が確定した後、2016年9月には山形県内でも阿部賢一県議の政務活動費の不正受給が明るみに出た。山形新聞がスクープしたもので、会合費や事務費をごまかしていた。阿部県議は辞職し、県議会事務局によると最終的に663万円を返納した。
野川氏はこの時、山形県議会議長で「阿部県議の刑事告発を検討する」と表明している(民進党や社民党県議らでつくる県政クラブが反対して告発はされなかった)。おまけに野川氏は全国都道府県議会議長会の会長でもあった。2016年10月中旬には、全国議長会の会長として自民党との政策懇談会に出席し、要望事項を伝えたりしている。

にもかかわらず、その後も素知らぬ顔で架空の人件費を計上し、公金をだまし取っていた。よくそんなことが続けられたものだと思う。
◇ ◇
野川氏の長年の悪事が露見したのは11月4日である。NHK山形放送局が朝のニュースで特ダネとして報じ、新聞・テレビ各社が追いかけた。
市民オンブズマン山形県会議も報道の裏付けに走り、信頼できる筋から「本人は不正を認め、辞職する意向と聞いている」との情報を得た。その日の夕方には県政記者クラブで緊急会見を開き、「刑事告発も検討する」と表明した。
山形県に限らず、市民オンブズマンは全国で議員の政務活動費の不正を追及してきた。監査請求を繰り返し、撥(は)ねつけられると、裁判に訴えて不正をただそうとしてきた。「政務活動費の収支報告書や領収書類をインターネットで公開し、その内容をガラス張りにすべきだ」と提言もしている。
だが、山形県議会はこの間、ほとんど何の努力もしてこなかった。一方、足もとの山形市議会では、議長がリーダーシップを発揮して領収書のインターネット公開など次々に改善策を打ち出した。
その結果、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年公表している「政務活動費の情報公開度ランキング」で、山形市議会は2019年の「中核市の議会でビリから3番目」から今年は「全国2位」(1位は函館市議会)へと大躍進した。改革どころか何もしない山形県議会は毎年、ズルズルと順位を下げ、今年は29位まで落ちた。その挙げ句に、県議会議長経験者の不正である。山形のオンブズマンが怒るのは当然ではないか。
不正受給が発覚すると、野川氏は2日後の6日に県議会の坂本貴美雄議長に辞職願を出し、身を引いた。15日には山形市内のレンタル会議場で記者会見を開き、人件費の架空計上が2008年度からの13年間で総額1248万円に上ることを明らかにした。
記者会見では、自宅の一部を事務所として使い、その電気代や水道代、灯油代などでも不適切な支出があるのではないかと追及され、否定しなかった。不正は人件費の架空請求にとどまらず、総額は有罪判決を受けた野々村氏のそれをかなり上回る。
不可解なのは、その後の山形県議会と山形県当局の対応である。坂本議長は「個人のモラルの問題」とし、刑事告発については「考えていない」と述べた。あきれる。「モラルの問題」であると同時に、政務活動費の制度と運用が問われているのだ。
坂本議長は「県議会には法人格がない。議会としての告発は法制度上できない」とも述べた。議会に「法人格」がないことくらい言われなくても分かっている。ならば、議会を代表して議長として、あるいは兵庫県議会のように各会派代表の連名で告発すればいいのだ。
公金詐取の被害者は納税者であり、それを代表すべきは県知事である。こちらは告発ではなく、告訴すべき立場にある。ところが、山形県の吉村美栄子知事は記者会見で対応を問われると、「一義的には議会が対応すべきこと。議会の独立性、自主性を尊重したい」と述べた。この発言だけ聞けば、もっともらしい。
だが、吉村知事は今年3月、若松正俊副知事の再任人事案が県議会で否決されるや、若松氏を議会の同意がいらない非常勤特別職に任命して続投させた。議会をこけにする暴挙である。なのに、こういう時は「議会を尊重する」と言って逃げようとする。つくづく、いい加減な政治家である。
ことは巨額の詐欺事件である。本人も詐取したことを認めている。血税をだまし取った人間がいるなら、納税者の代表として知事が告訴するのは当然のことであり、責務であると言ってもいい。
野川氏は会見で「(詐取した金を)私的には使っていない」と繰り返した。それを見出しに取った愚かな新聞もあるが、だまし取った金をどう使ったかは詐欺罪の立件には関係がない。刑の言い渡しに際して「情状酌量の材料の一つ」になるに過ぎない。
一般人が一般人から金をだまし取る詐欺でも罪は重い。ましてや、政務活動費が適切に使われるようにする責任を負う県議会の議長経験者が公金をだまし取ったのである。議会が告発し、知事が告訴するのは当然ではないか。
知事や議会のこうした対応を見ていると、この人たちは「不正を知っても、こっそりと処理して闇に葬ってしまおうとしていたのではないか」と疑ってしまう。
あらためて、報道の大切さを思う。悪いことは悪い。許されないことは許してはならない。政治や行政をしっかり監視して不正を暴くのは、報道機関の重要な役割の一つである。
警察や検察がお目こぼしをしようとしても、それが納税者のためにならないなら、見過ごしてはならない。真相の解明に果敢に挑み、人々に伝えなければならない。日々の出来事の報道ももちろん大切なことだが、やはり「スクーブ」こそ、報道の要と言うべきだろう。
長岡 昇( NPO「ブナの森」 代表)
*メールマガジン「風切通信 98」 2021年11月27日
*この文章は、月刊『素晴らしい山形』2021年12月号に寄稿したコラムを手直しし、加筆したものです。
≪写真説明&Source≫
◎記者会見で号泣する野々村竜太郎県議
https://looking.fandom.com/ja/wiki/%E9%87%8E%E3%80%85%E6%9D%91%E7%AB%9C%E5%A4%AA%E9%83%8E
◎2016年10月19日、自民党との政策懇談会で全国都道府県議会議長会の会長として発言する野川政文氏(全国都道府県議会議長会のサイトから)
http://www.gichokai.gr.jp/topics/2016/161019/index.html
山形地方検察庁の友添太郎検事正が今年7月に地検の公式サイトにアップした着任挨拶文は、前任の松下裕子(ひろこ)氏の挨拶文を名前以外すべて盗用したものだ、との記事を11月11日の朝、調査報道サイト「ハンター」に掲載した。すると、ほどなく投稿欄を通して「松下氏のも前任者のコピペでした」との情報が寄せられた。

仰天した。2代続けての盗用など考えてもいなかった。投稿には次のような「証拠」も添付されていた(カッコ内の在任期間は筆者が補足)。
◎松下裕子検事正(2020年1月?2021年7月)
https://web.archive.org/web/20200828002412/http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
◎伊藤栄二検事正(2019年7月?2020年1月)
https://web.archive.org/web/20190919082509/https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
◎吉田久検事正(2018年7月?2019年7月)
https://web.archive.org/web/20180929050945/http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
クリックすると、その検事正の紹介画面が出てくる。顔写真と略歴の下に着任の挨拶がそれぞれ掲載されていた。読んでみると、松下裕子氏の着任挨拶文も前任の伊藤栄二氏(現静岡地検検事正)の文章をほぼそのままなぞったものであることが分かる。伊藤氏の挨拶文は次の通りである。
* *
この度、山形地方検察庁検事正に就任しました伊藤栄二です。山形県をはじめ東北で勤務するのは今回が初めてですが、山形県は豊かな自然と歴史・文化があり、人は温和で情に厚く、とても良い所だと聞いており、これからの生活を楽しみにしているところです。
近年の当県内における犯罪の情勢を見ますと、一人暮らしの高齢者や幼児・児童などの弱い立場にある方が被害に遭い、キャッシュカードや現金をだまし取られるなどの特殊詐欺や児童虐待に当たる事件が増え続けています。
当山形地方検察庁は、これら一つ一つの事件と真摯かつ誠実に向き合い、警察等関係機関とも連携し、罰すべき者が適切に罰されるよう対処することを通じ、山形県民の皆様の期待に応え、その安心・安全の確保に力を尽くして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
* *
松下氏は仙台地検に勤務したことがあるので「山形県をはじめ東北で勤務するのは今回が初めて」とは言えない。そこで「山形県で勤務するのは今回が初めて」と直してある。が、その後にある「山形県の犯罪情勢」と「検察官としての決意」の部分は、伊藤氏の文章をほぼそのままなぞっていた。
「被害に遭い」を「被害に遭われ」、「事件が増え続けています」を「事件が、連続的に発生しています」と手を入れている程度だ。伊藤氏の挨拶文343文字のうち、松下氏が変えたのは名前を含めて18文字のみ。文章の盗用率は95%である(ちなみに、伊藤氏の挨拶文は前任の吉田氏のものとはまるで異なる)。
この松下氏の着任挨拶文を、次の友添太郎検事正は名前の4文字を入れ替えただけで全文盗用したわけだ。伊藤氏の着任挨拶文を2代続けてパクッていたのである。

検察官同士での挨拶文の盗用なので、「論文の盗用」とは意味合いが異なる。著作権法などの法律に触れるわけではない。だが、こんな行為は「法律以前の人としての道義の問題」として許されるものではない。何よりも、地元山形の人たちに対して失礼きわまる。着任の挨拶を盗用しておきながら「一つ一つの事件と真摯かつ誠実に向き合う」などと言われても、誰が信用すると言うのか。
情報提供の詳細を知った時、筆者は「それにしても、とうの昔に検察庁の公式サイトから消えた挨拶文がなぜあるのか」と、素朴な疑問を抱いた。手がかりはURL(インターネット上の位置情報)にある、と考え、冒頭の「https://web.archive.org/」の意味をネットに強い知人に尋ねた。以下は知人の解説である。
アメリカのカリフォルニアに「インターネットアーカイブ Internet Archive 」というNPO(非営利団体)がある。ここがネット上にある世界中のサイトをほぼすべて収集して保管し、検索できるサービスを提供している。「インターネットの国際図書館」のようなものだ。1996年に設立され、運営はすべて寄付金でまかなっている。もちろん、世界にはものすごい数のサイトがあるので、すべてを毎日収集するわけにはいかない。定期的に巡回して自動的にダウンロードするプログラムを使っている。保管しているサイトのページ数は5880億ページに及ぶ。
筆者のようなアナログ人間には想像もできなかった。そんなサービスがあるとは。ウェブサイト制作会社のエンジニアたちの間では広く知られており、さまざまな目的で使われているという。利用の仕方を教わり、さっそく検索を始めた。
着任挨拶文の使い回しは山形地検だけなのか。ほかの地検にはないのか。東北を皮切りに全国の地検の公式サイトを手当たり次第に調べてみた。これまで調べた範囲では、挨拶文の盗用をしているような検事正は山形以外にはいなかった。
東日本大震災の被災地である福島、仙台、盛岡の各地検検事正は、復興状況を織り交ぜながら、被災地の人たちに寄り添う言葉を綴っていた。鳥取の検事正は自ら歩んできた道をたどりながら犯罪に立ち向かう決意を語り、佐賀の検事正は「薩長土肥の一翼を担った歴史」に触れつつ支援と協力を呼びかけていた。それぞれ、「自分の言葉」と分かる内容だった(紋切型の文章を載せている地検はある。また、そもそも検事正の着任挨拶を載せていない地検もある)。
なぜ、山形地検でこのようなことが起きたのか。検察関係者はこんな風に言う。「山形県は大きな事件もないし、落ち着いている。激務に追われた人を『しばし、リフレッシュしておいで』と送り出すところなのだ」
松下氏は千葉や横浜など主に首都圏の地検で現場を踏み、東京地検特捜部の副部長を務めた。法務省の国際課長や刑事課長も歴任している。「検察の本流」を経てきた検察官で、激務の連続だったことは間違いない。
山形県はソバと日本酒がうまい。果物も牛肉もブランドものがそろっている。温泉もいたる所にある。リフレッシュには最適の土地の一つだろう。要するに、山形県は「検察の湯治場」のようなもの、ということのようだ。
松下氏も友添氏も「地検のサイトの挨拶文をじっくり読む人などいない」とでも思ったのか。あまりと言えばあまりの見下しようである。この問題の第一報をアップした後、筆者は山形地検を訪ね、見解を問おうとした。だが、広報を担当する大林潤・次席検事は会おうともせず、事務官を通して「ノーコメント」と伝えてきた。見下しぶりは徹底している。
2代続けて盗用された着任挨拶文にあるように、山形県民の多くは「温和で情に厚い」。だが、その温和さにも限度がある、と知るべきである。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
【追記】この記事がアップされた11月22日に山形地検の公式サイトにある検事正挨拶は全面的に更新された。ようやく、自分で書く気になったようだ。
≪写真説明≫
検察官の「秋霜烈日」のバッジ
*山形地検・友添太郎検事正の着任挨拶(11月22日に更新)
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
*インターネットアーカイブの利用方法(筆者作成)
https://news-hunter.org/wp-content/uploads/2021/11/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9.pdf

仰天した。2代続けての盗用など考えてもいなかった。投稿には次のような「証拠」も添付されていた(カッコ内の在任期間は筆者が補足)。
◎松下裕子検事正(2020年1月?2021年7月)
https://web.archive.org/web/20200828002412/http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
◎伊藤栄二検事正(2019年7月?2020年1月)
https://web.archive.org/web/20190919082509/https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
◎吉田久検事正(2018年7月?2019年7月)
https://web.archive.org/web/20180929050945/http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
クリックすると、その検事正の紹介画面が出てくる。顔写真と略歴の下に着任の挨拶がそれぞれ掲載されていた。読んでみると、松下裕子氏の着任挨拶文も前任の伊藤栄二氏(現静岡地検検事正)の文章をほぼそのままなぞったものであることが分かる。伊藤氏の挨拶文は次の通りである。
* *
この度、山形地方検察庁検事正に就任しました伊藤栄二です。山形県をはじめ東北で勤務するのは今回が初めてですが、山形県は豊かな自然と歴史・文化があり、人は温和で情に厚く、とても良い所だと聞いており、これからの生活を楽しみにしているところです。
近年の当県内における犯罪の情勢を見ますと、一人暮らしの高齢者や幼児・児童などの弱い立場にある方が被害に遭い、キャッシュカードや現金をだまし取られるなどの特殊詐欺や児童虐待に当たる事件が増え続けています。
当山形地方検察庁は、これら一つ一つの事件と真摯かつ誠実に向き合い、警察等関係機関とも連携し、罰すべき者が適切に罰されるよう対処することを通じ、山形県民の皆様の期待に応え、その安心・安全の確保に力を尽くして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
* *
松下氏は仙台地検に勤務したことがあるので「山形県をはじめ東北で勤務するのは今回が初めて」とは言えない。そこで「山形県で勤務するのは今回が初めて」と直してある。が、その後にある「山形県の犯罪情勢」と「検察官としての決意」の部分は、伊藤氏の文章をほぼそのままなぞっていた。
「被害に遭い」を「被害に遭われ」、「事件が増え続けています」を「事件が、連続的に発生しています」と手を入れている程度だ。伊藤氏の挨拶文343文字のうち、松下氏が変えたのは名前を含めて18文字のみ。文章の盗用率は95%である(ちなみに、伊藤氏の挨拶文は前任の吉田氏のものとはまるで異なる)。
この松下氏の着任挨拶文を、次の友添太郎検事正は名前の4文字を入れ替えただけで全文盗用したわけだ。伊藤氏の着任挨拶文を2代続けてパクッていたのである。

検察官同士での挨拶文の盗用なので、「論文の盗用」とは意味合いが異なる。著作権法などの法律に触れるわけではない。だが、こんな行為は「法律以前の人としての道義の問題」として許されるものではない。何よりも、地元山形の人たちに対して失礼きわまる。着任の挨拶を盗用しておきながら「一つ一つの事件と真摯かつ誠実に向き合う」などと言われても、誰が信用すると言うのか。
情報提供の詳細を知った時、筆者は「それにしても、とうの昔に検察庁の公式サイトから消えた挨拶文がなぜあるのか」と、素朴な疑問を抱いた。手がかりはURL(インターネット上の位置情報)にある、と考え、冒頭の「https://web.archive.org/」の意味をネットに強い知人に尋ねた。以下は知人の解説である。
アメリカのカリフォルニアに「インターネットアーカイブ Internet Archive 」というNPO(非営利団体)がある。ここがネット上にある世界中のサイトをほぼすべて収集して保管し、検索できるサービスを提供している。「インターネットの国際図書館」のようなものだ。1996年に設立され、運営はすべて寄付金でまかなっている。もちろん、世界にはものすごい数のサイトがあるので、すべてを毎日収集するわけにはいかない。定期的に巡回して自動的にダウンロードするプログラムを使っている。保管しているサイトのページ数は5880億ページに及ぶ。
筆者のようなアナログ人間には想像もできなかった。そんなサービスがあるとは。ウェブサイト制作会社のエンジニアたちの間では広く知られており、さまざまな目的で使われているという。利用の仕方を教わり、さっそく検索を始めた。
着任挨拶文の使い回しは山形地検だけなのか。ほかの地検にはないのか。東北を皮切りに全国の地検の公式サイトを手当たり次第に調べてみた。これまで調べた範囲では、挨拶文の盗用をしているような検事正は山形以外にはいなかった。
東日本大震災の被災地である福島、仙台、盛岡の各地検検事正は、復興状況を織り交ぜながら、被災地の人たちに寄り添う言葉を綴っていた。鳥取の検事正は自ら歩んできた道をたどりながら犯罪に立ち向かう決意を語り、佐賀の検事正は「薩長土肥の一翼を担った歴史」に触れつつ支援と協力を呼びかけていた。それぞれ、「自分の言葉」と分かる内容だった(紋切型の文章を載せている地検はある。また、そもそも検事正の着任挨拶を載せていない地検もある)。
なぜ、山形地検でこのようなことが起きたのか。検察関係者はこんな風に言う。「山形県は大きな事件もないし、落ち着いている。激務に追われた人を『しばし、リフレッシュしておいで』と送り出すところなのだ」
松下氏は千葉や横浜など主に首都圏の地検で現場を踏み、東京地検特捜部の副部長を務めた。法務省の国際課長や刑事課長も歴任している。「検察の本流」を経てきた検察官で、激務の連続だったことは間違いない。
山形県はソバと日本酒がうまい。果物も牛肉もブランドものがそろっている。温泉もいたる所にある。リフレッシュには最適の土地の一つだろう。要するに、山形県は「検察の湯治場」のようなもの、ということのようだ。
松下氏も友添氏も「地検のサイトの挨拶文をじっくり読む人などいない」とでも思ったのか。あまりと言えばあまりの見下しようである。この問題の第一報をアップした後、筆者は山形地検を訪ね、見解を問おうとした。だが、広報を担当する大林潤・次席検事は会おうともせず、事務官を通して「ノーコメント」と伝えてきた。見下しぶりは徹底している。
2代続けて盗用された着任挨拶文にあるように、山形県民の多くは「温和で情に厚い」。だが、その温和さにも限度がある、と知るべきである。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
【追記】この記事がアップされた11月22日に山形地検の公式サイトにある検事正挨拶は全面的に更新された。ようやく、自分で書く気になったようだ。
≪写真説明≫
検察官の「秋霜烈日」のバッジ
*山形地検・友添太郎検事正の着任挨拶(11月22日に更新)
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yamagata/page1000025.html
*インターネットアーカイブの利用方法(筆者作成)
https://news-hunter.org/wp-content/uploads/2021/11/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9.pdf
ものを盗んだり、人を傷つけたりすれば、誰であれ咎(とが)められ、処罰される。ましてや、それが一般の人ではなく、摘発する側の警察官や検察官であれば、その罪は一段と重い。

そうした「一段と重い罪」を犯した者が、わが故郷の山形県にいる。普通の警察官や検察官ではない。山形地方検察庁のトップ、友添太郎・検事正である。
友添氏は今年7月16日付の人事で静岡地検沼津支部長から山形地検の検事正に転じた。ほどなく着任し、山形地検の公式サイトに次のような挨拶文をアップした(公式サイトはカラー文字をクリック)。
◇ ◇
このたび、山形地方検察庁検事正に就任しました友添太郎です。山形県で勤務するのは今回が初めてですが、豊かな自然と歴史・文化が大切にされ、人は温和で情に厚く、とても良い所だと聞いており、これからの生活を楽しみにしているところです。
近年の当県内における犯罪の情勢を見ますと、一人暮らしの高齢者や幼児・児童などの弱い立場にある方が被害に遭われ、現金やキャッシュカードをだまし取られるなどの特殊詐欺や児童虐待に当たる事件が、連続的に発生しています。
当山形地方検察庁は、これら一つ一つの事件と真摯かつ誠実に向き合い、警察等関係機関とも連携し、罰すべき者が適切に罰されるよう対処することを通じ、山形県民の皆様の期待に応え、その安心・安全の確保に力を尽くして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
◇ ◇
赴任地・山形についての思いを綴り、犯罪に立ち向かう決意を記した、なかなか味のある挨拶文である。が、一読して既視感を覚えた。とりわけ、「罰すべき者が適切に罰されるよう対処する」という一文が引っかかった。
友添氏の前任の松下裕子(ひろこ)山形地検検事正の着任挨拶文に同じ表現があったからである。すぐさま、松下氏の挨拶文(2020年1月にアップ)を引っ張り出し、読んでみた。
唖然とした。「このたび」から始まり、「よろしくお願いいたします」まで、一字一句、句読点に至るまでまったく同じだった。「松下裕子」の4文字を「友添太郎」と差し替えただけで、全文を盗用していた。
なんという手抜き。いや、「手抜き」などという生やさしい言葉で表現すべきではない。地元山形の人々を愚弄し、法の執行に当たる警察官や検察官をあざ笑うような所業だ。地方検察庁のトップとして、許されざる行為と言わなければならない。
実は、この着任挨拶文の盗用には7月の時点で気づいていた。それに目をつぶっていたのは「着任直後であわただしい状況にあるのだろう」と少しばかり同情したのに加えて、この時、山形県警と山形地検が「副知事の公職選挙法違反(公務員の地位利用)」という重大事件を抱えていたので、「捜査の妨げになるようなことは控えたい」という思いがあったからだ。
副知事の公選法違反事件とは、今年1月の山形県知事選をめぐって、当時副知事だった人物が県内の市長らに現職知事の対立候補を応援しないよう圧力を加えた疑いがある、というものだ。圧力を加えられたとされる市長は何人もいる。しかも、山形県当局は現職知事が4選を果たすやいなや、反旗を翻した市長らに補助金の削減をほのめかすなど露骨な動きを見せた。
山形県警は知事選の直後から内偵を進め、市長や副知事だった人物への事情聴取に乗り出した。友添氏が着任する直前、6月の半ばには「前副知事から任意で事情聴取」との報道もなされていた。
だが、その後、捜査当局は立件に向けた動きを見せない。あいまいなまま、事件の幕引きを図ろうとしている気配がある。「もはや重大事件を抱えていることへの配慮は無用」と筆者は判断し、検事正の破廉恥な行為を告発することにした。
この手の問題を報じる場合、普通なら相手(山形地検及び友添氏)の言い分を取材し、それも伝えるべきなのだろうが、今回はあえて事前に相手に接触しなかった。接触した途端、山形地検の公式サイトにある「全文盗用の着任挨拶」を削除してしまう恐れがあるからだ。
読者のみなさんには、本文中に記した山形地検の公式サイトのURLをクリックして、友添氏の挨拶文に目を通し、末尾に添付した前任者の挨拶文と照合して「盗用」を確認していただきたい。
山形地検は盗用についてどう釈明するのか。また、この記事にいつ気づき、どう動くのか。さらに、上級庁である仙台高検や最高検はどのように対応するのか。それらについては続報でお伝えしたい。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2021年11月11日
*前任の山形地検検事正、松下裕子氏の着任挨拶文
≪写真説明とSource≫
◎東京・霞が関の検察庁(Web:東京新聞 2020年5月18日)

そうした「一段と重い罪」を犯した者が、わが故郷の山形県にいる。普通の警察官や検察官ではない。山形地方検察庁のトップ、友添太郎・検事正である。
友添氏は今年7月16日付の人事で静岡地検沼津支部長から山形地検の検事正に転じた。ほどなく着任し、山形地検の公式サイトに次のような挨拶文をアップした(公式サイトはカラー文字をクリック)。
◇ ◇
このたび、山形地方検察庁検事正に就任しました友添太郎です。山形県で勤務するのは今回が初めてですが、豊かな自然と歴史・文化が大切にされ、人は温和で情に厚く、とても良い所だと聞いており、これからの生活を楽しみにしているところです。
近年の当県内における犯罪の情勢を見ますと、一人暮らしの高齢者や幼児・児童などの弱い立場にある方が被害に遭われ、現金やキャッシュカードをだまし取られるなどの特殊詐欺や児童虐待に当たる事件が、連続的に発生しています。
当山形地方検察庁は、これら一つ一つの事件と真摯かつ誠実に向き合い、警察等関係機関とも連携し、罰すべき者が適切に罰されるよう対処することを通じ、山形県民の皆様の期待に応え、その安心・安全の確保に力を尽くして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
◇ ◇
赴任地・山形についての思いを綴り、犯罪に立ち向かう決意を記した、なかなか味のある挨拶文である。が、一読して既視感を覚えた。とりわけ、「罰すべき者が適切に罰されるよう対処する」という一文が引っかかった。
友添氏の前任の松下裕子(ひろこ)山形地検検事正の着任挨拶文に同じ表現があったからである。すぐさま、松下氏の挨拶文(2020年1月にアップ)を引っ張り出し、読んでみた。
唖然とした。「このたび」から始まり、「よろしくお願いいたします」まで、一字一句、句読点に至るまでまったく同じだった。「松下裕子」の4文字を「友添太郎」と差し替えただけで、全文を盗用していた。
なんという手抜き。いや、「手抜き」などという生やさしい言葉で表現すべきではない。地元山形の人々を愚弄し、法の執行に当たる警察官や検察官をあざ笑うような所業だ。地方検察庁のトップとして、許されざる行為と言わなければならない。
実は、この着任挨拶文の盗用には7月の時点で気づいていた。それに目をつぶっていたのは「着任直後であわただしい状況にあるのだろう」と少しばかり同情したのに加えて、この時、山形県警と山形地検が「副知事の公職選挙法違反(公務員の地位利用)」という重大事件を抱えていたので、「捜査の妨げになるようなことは控えたい」という思いがあったからだ。
副知事の公選法違反事件とは、今年1月の山形県知事選をめぐって、当時副知事だった人物が県内の市長らに現職知事の対立候補を応援しないよう圧力を加えた疑いがある、というものだ。圧力を加えられたとされる市長は何人もいる。しかも、山形県当局は現職知事が4選を果たすやいなや、反旗を翻した市長らに補助金の削減をほのめかすなど露骨な動きを見せた。
山形県警は知事選の直後から内偵を進め、市長や副知事だった人物への事情聴取に乗り出した。友添氏が着任する直前、6月の半ばには「前副知事から任意で事情聴取」との報道もなされていた。
だが、その後、捜査当局は立件に向けた動きを見せない。あいまいなまま、事件の幕引きを図ろうとしている気配がある。「もはや重大事件を抱えていることへの配慮は無用」と筆者は判断し、検事正の破廉恥な行為を告発することにした。
この手の問題を報じる場合、普通なら相手(山形地検及び友添氏)の言い分を取材し、それも伝えるべきなのだろうが、今回はあえて事前に相手に接触しなかった。接触した途端、山形地検の公式サイトにある「全文盗用の着任挨拶」を削除してしまう恐れがあるからだ。
読者のみなさんには、本文中に記した山形地検の公式サイトのURLをクリックして、友添氏の挨拶文に目を通し、末尾に添付した前任者の挨拶文と照合して「盗用」を確認していただきたい。
山形地検は盗用についてどう釈明するのか。また、この記事にいつ気づき、どう動くのか。さらに、上級庁である仙台高検や最高検はどのように対応するのか。それらについては続報でお伝えしたい。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*初出:調査報道サイト「ハンター」 2021年11月11日
*前任の山形地検検事正、松下裕子氏の着任挨拶文
≪写真説明とSource≫
◎東京・霞が関の検察庁(Web:東京新聞 2020年5月18日)
イチョウが色づき始めました。ありふれた街路樹の一つですが、ある本に出合ってから、私はこの樹(き)を特別な思いで見つめるようになりました。英国の植物学者、ピーター・クレインが著した『イチョウ 奇跡の2億年史』(河出書房新社)です。

この樹には、命をめぐる壮大な物語が秘められていることを知りました。クレインの著書は、ドイツの文豪ゲーテが詠(よ)んだ次のような詩で始まります。
はるか東方のかなたから
わが庭に来たりし樹木の葉よ
その神秘の謎を教えておくれ
無知なる心を導いておくれ
おまえはもともと一枚の葉で
自身を二つに裂いたのか?
それとも二枚の葉だったのに
寄り添って一つになったのか?
こうしたことを問ううちに
やがて真理に行き当たる
そうかおまえも私の詩から思うのか
一人の私の中に二人の私がいることを
クレインによれば、シーラカンスが「生きた化石」の動物界のチャンピオンだとするなら、イチョウは植物の世界における「生きた化石」の代表格なのだそうです。恐竜が闊歩していた中生代に登場し、恐竜が絶滅した6500万年前の地球の大変動を生き抜いてきました。
ただ、氷河期にうまく適応することができず、世界のほとんどの地域から姿を消してしまいました。欧州の博物学者はその存在を「化石」でしか知らなかったのです。
けれども、死に絶えてはいませんでした。中国の奥深い山々で細々と生きていたのです。そしていつしか、信仰の対象として人々に崇められるようになり、人間の手で生息域を広げていったと考えられています。著者の探索によれば、中国の文献にイチョウが登場するのは10世紀から11世紀ごろ。やがて、朝鮮半島から日本へと伝わりました。
日本に伝わったのはいつか。著者はそれも調べています。平安時代、『枕草子』を綴った清少納言がイチョウを見ていたら、書かないはずがない。なのに、登場しない。紫式部の『源氏物語』にも出て来ない。当時の辞典にもない。
鎌倉時代の三代将軍、源実朝(さねとも)は鶴岡八幡宮にある樹の陰に隠れていた甥の公卿に暗殺されたと伝えられていますが、その樹がイチョウだというのは後世の付け足しのようです。間違いなくイチョウと判断できる記述が登場するのは15世紀、伝来はその前の14世紀か、というのがクレインの見立てです。中国から日本に伝わるまで数百年かかったことになります。
東洋から西洋への伝わり方も劇的です。鎖国時代の日本。交易を認められていたのはオランダだけでした。そのオランダ商館の医師として長崎の出島に滞在したドイツ人のエンゲルベルト・ケンペルが初めてイチョウを欧州に伝えたのです。帰国後の1712年に出版した『廻国奇観』の中で絵入りで紹介しています。それまで何人ものポルトガル人やオランダ人が日本に来ていたのに、彼らの関心をひくことはありませんでした。キリスト教の布教と交易で頭がいっぱいだったのでしょう。
博物学だけでなく言語学にも造詣の深いケンペルは、日本語の音韻を正確に記述しています。日本のオランダ語通詞を介して、「銀杏」は「イチョウ」もしくは「ギンキョウ」と発音されることを知り、著書にはginkgo と記しました。クレインは「ケンペルはなぜginkyo ではなく、ginkgo と綴ったのか」という謎の解明にも挑んでいます。

植字工がミスをしたという説もありますが、クレインは「ケンペルの出身地であるドイツ北部ではヤ・ユ・ヨの音をga、gu、goと書き表すことが多い」と記し、植字ミスではなく正確に綴ったものとみています。いずれにしても、このginkgoがイチョウを表す言葉として欧州で広まり、そのままのスペルで英語にもなっています。発音は「ギンコウ」です。
それまで「化石」でしか見たことがなく、絶滅したものと思っていた植物が生きていた――それを知った欧州でどのような興奮が巻き起こったかは、冒頭に掲げたゲーテの詩によく現れています。「東方のかなたから来たりし謎」であり、「無知なる心を導いてくれる一枚の葉」だったのです。「東洋の謎」はほどなく大西洋を渡り、アメリカの街路をも彩ることになりました。
植物オンチの私でも、イチョウに雌木(めぎ)と雄木(おぎ)があることは知っていましたが、その花粉には精子があり、しかも、受精の際には「その精子が繊毛をふるわせてかすかに泳ぐ」ということを、この本で初めて知りました。
イチョウの精子を発見したのは小石川植物園の技術者、平瀬作五郎。明治29年(1896年)のことです。維新以来、日本は欧米の文明を吸収する一方でしたが、平瀬の発見は植物学の世界を揺さぶる大発見であり、「遅れてきた文明国」からの初の知的発信になりました。イチョウは「日本を世界に知らしめるチャンス」も与えてくれたのです。
それにしても、著者のクレインは実によく歩いています。欧米諸国はもちろん、中国貴州省の小さな村にある大イチョウを訪ね、韓国忠清南道の寺にある古木に触れ、日本のギンナン産地の愛知県祖父江町(稲沢市に編入)にも足を運んでいます。
訪ねるだけではありません。中国ではギンナンを使った料理の調理法を調べ、祖父江町ではイチョウの栽培農家に接ぎ木の仕方まで教わっています。鎌倉の鶴岡八幡宮の大イチョウを見に行った際には、境内でギンナンを焼いて売っている屋台のおばさんの話まで聞いています。長い研究で培われた学識に加えて、「見るべきものはすべて見る。聞くべきことはすべて聞く」という気迫のようなものが、この本を重厚で魅力的なものにしています。
かくもイチョウを愛し、イチョウの謎を追い続けた植物学者は今、何を思うのでしょうか。クレインはゲーテの詩の前に、娘と息子への短い献辞を記しています。「エミリーとサムへ きみたちの時代に長期的な展望が開けることを願って」
壮大な命の物語を紡いできたイチョウ。それに比べれば、私たち人間など、つい最近登場したばかりの小さな、小さな存在でしかない。
*初出:メールマガジン「小白川通信 20」(2014年11月29日)。書き出しを含め一部手直し
≪写真説明とSource≫
◎青森県弘前公園の「根上がりイチョウ」
http://aomori.photo-web.cc/ginkgo/01.html
◎ピーター・クレイン(前キュー植物園長、イェール大学林業・環境科学部長)
http://news.yale.edu/2009/03/04/sir-peter-crane-appointed-dean-yale-school-forestry-and-environmental-studies
*『イチョウ 奇跡の2億年史』の原題は GINKGO : The Tree That Time Forgot 。矢野真千子氏の翻訳。ゲーテの詩は『西東(せいとう)詩集』所収。
*国土交通省は日本の街路樹について、2009年に「わが国の街路樹」という資料を発表しました。2007年に調査したもので、それによると、街路樹で本数が多いのはイチョウ、サクラ、ケヤキ、ハナミズキ、トウカエデの順でした。詳しくは次のURLを参照。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0506.htm

この樹には、命をめぐる壮大な物語が秘められていることを知りました。クレインの著書は、ドイツの文豪ゲーテが詠(よ)んだ次のような詩で始まります。
はるか東方のかなたから
わが庭に来たりし樹木の葉よ
その神秘の謎を教えておくれ
無知なる心を導いておくれ
おまえはもともと一枚の葉で
自身を二つに裂いたのか?
それとも二枚の葉だったのに
寄り添って一つになったのか?
こうしたことを問ううちに
やがて真理に行き当たる
そうかおまえも私の詩から思うのか
一人の私の中に二人の私がいることを
クレインによれば、シーラカンスが「生きた化石」の動物界のチャンピオンだとするなら、イチョウは植物の世界における「生きた化石」の代表格なのだそうです。恐竜が闊歩していた中生代に登場し、恐竜が絶滅した6500万年前の地球の大変動を生き抜いてきました。
ただ、氷河期にうまく適応することができず、世界のほとんどの地域から姿を消してしまいました。欧州の博物学者はその存在を「化石」でしか知らなかったのです。
けれども、死に絶えてはいませんでした。中国の奥深い山々で細々と生きていたのです。そしていつしか、信仰の対象として人々に崇められるようになり、人間の手で生息域を広げていったと考えられています。著者の探索によれば、中国の文献にイチョウが登場するのは10世紀から11世紀ごろ。やがて、朝鮮半島から日本へと伝わりました。
日本に伝わったのはいつか。著者はそれも調べています。平安時代、『枕草子』を綴った清少納言がイチョウを見ていたら、書かないはずがない。なのに、登場しない。紫式部の『源氏物語』にも出て来ない。当時の辞典にもない。
鎌倉時代の三代将軍、源実朝(さねとも)は鶴岡八幡宮にある樹の陰に隠れていた甥の公卿に暗殺されたと伝えられていますが、その樹がイチョウだというのは後世の付け足しのようです。間違いなくイチョウと判断できる記述が登場するのは15世紀、伝来はその前の14世紀か、というのがクレインの見立てです。中国から日本に伝わるまで数百年かかったことになります。
東洋から西洋への伝わり方も劇的です。鎖国時代の日本。交易を認められていたのはオランダだけでした。そのオランダ商館の医師として長崎の出島に滞在したドイツ人のエンゲルベルト・ケンペルが初めてイチョウを欧州に伝えたのです。帰国後の1712年に出版した『廻国奇観』の中で絵入りで紹介しています。それまで何人ものポルトガル人やオランダ人が日本に来ていたのに、彼らの関心をひくことはありませんでした。キリスト教の布教と交易で頭がいっぱいだったのでしょう。
博物学だけでなく言語学にも造詣の深いケンペルは、日本語の音韻を正確に記述しています。日本のオランダ語通詞を介して、「銀杏」は「イチョウ」もしくは「ギンキョウ」と発音されることを知り、著書にはginkgo と記しました。クレインは「ケンペルはなぜginkyo ではなく、ginkgo と綴ったのか」という謎の解明にも挑んでいます。

植字工がミスをしたという説もありますが、クレインは「ケンペルの出身地であるドイツ北部ではヤ・ユ・ヨの音をga、gu、goと書き表すことが多い」と記し、植字ミスではなく正確に綴ったものとみています。いずれにしても、このginkgoがイチョウを表す言葉として欧州で広まり、そのままのスペルで英語にもなっています。発音は「ギンコウ」です。
それまで「化石」でしか見たことがなく、絶滅したものと思っていた植物が生きていた――それを知った欧州でどのような興奮が巻き起こったかは、冒頭に掲げたゲーテの詩によく現れています。「東方のかなたから来たりし謎」であり、「無知なる心を導いてくれる一枚の葉」だったのです。「東洋の謎」はほどなく大西洋を渡り、アメリカの街路をも彩ることになりました。
植物オンチの私でも、イチョウに雌木(めぎ)と雄木(おぎ)があることは知っていましたが、その花粉には精子があり、しかも、受精の際には「その精子が繊毛をふるわせてかすかに泳ぐ」ということを、この本で初めて知りました。
イチョウの精子を発見したのは小石川植物園の技術者、平瀬作五郎。明治29年(1896年)のことです。維新以来、日本は欧米の文明を吸収する一方でしたが、平瀬の発見は植物学の世界を揺さぶる大発見であり、「遅れてきた文明国」からの初の知的発信になりました。イチョウは「日本を世界に知らしめるチャンス」も与えてくれたのです。
それにしても、著者のクレインは実によく歩いています。欧米諸国はもちろん、中国貴州省の小さな村にある大イチョウを訪ね、韓国忠清南道の寺にある古木に触れ、日本のギンナン産地の愛知県祖父江町(稲沢市に編入)にも足を運んでいます。
訪ねるだけではありません。中国ではギンナンを使った料理の調理法を調べ、祖父江町ではイチョウの栽培農家に接ぎ木の仕方まで教わっています。鎌倉の鶴岡八幡宮の大イチョウを見に行った際には、境内でギンナンを焼いて売っている屋台のおばさんの話まで聞いています。長い研究で培われた学識に加えて、「見るべきものはすべて見る。聞くべきことはすべて聞く」という気迫のようなものが、この本を重厚で魅力的なものにしています。
かくもイチョウを愛し、イチョウの謎を追い続けた植物学者は今、何を思うのでしょうか。クレインはゲーテの詩の前に、娘と息子への短い献辞を記しています。「エミリーとサムへ きみたちの時代に長期的な展望が開けることを願って」
壮大な命の物語を紡いできたイチョウ。それに比べれば、私たち人間など、つい最近登場したばかりの小さな、小さな存在でしかない。
*初出:メールマガジン「小白川通信 20」(2014年11月29日)。書き出しを含め一部手直し
≪写真説明とSource≫
◎青森県弘前公園の「根上がりイチョウ」
http://aomori.photo-web.cc/ginkgo/01.html
◎ピーター・クレイン(前キュー植物園長、イェール大学林業・環境科学部長)
http://news.yale.edu/2009/03/04/sir-peter-crane-appointed-dean-yale-school-forestry-and-environmental-studies
*『イチョウ 奇跡の2億年史』の原題は GINKGO : The Tree That Time Forgot 。矢野真千子氏の翻訳。ゲーテの詩は『西東(せいとう)詩集』所収。
*国土交通省は日本の街路樹について、2009年に「わが国の街路樹」という資料を発表しました。2007年に調査したもので、それによると、街路樹で本数が多いのはイチョウ、サクラ、ケヤキ、ハナミズキ、トウカエデの順でした。詳しくは次のURLを参照。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0506.htm
自民党の総裁選を勝ち抜き、岸田文雄氏が首相に就任した。明治の元勲、伊藤博文から数えてちょうど100代目の総理大臣という。その岸田首相の下であわただしく衆議院が解散され、総選挙に突入した。10月31日に投開票され、その日の夜には大勢が判明する。

NHKや朝日新聞は今回の総選挙について、盛んに「政権選択の選挙」と報じた。だが、この選挙で政権交代が実現する可能性があると考えている人はほとんどいないだろう。
安倍晋三、菅義偉両氏の下で9年に及んだ政権運営を有権者はどう判断するのか。ウソとごまかしの政治にどこまでお灸をすえるのか。そのお灸の度合いが示される選挙、と見る方が自然だろう。立憲民主党を中心とする野党に再び政権運営をゆだねるほど、有権者はうぶではあるまい。
選挙に向けて、岸田首相は「新しい資本主義」なるスローガンを掲げた。アメリカ型の強欲な資本主義、弱者切り捨ての資本主義とは異なるものを目指したいようだ。どのような資本主義を思い描いているのか。岸田首相は所信表明演説でこう述べた。
「成長と分配の好循環と、コロナ後の新しい社会の開拓。これがコンセプトです。成長の果実をしっかりと分配することで、初めて次の成長が実現します。大切なのは成長と分配の好循環です。『成長か分配か』という不毛な議論から脱却し、『成長も分配も』実現するためにあらゆる政策を総動員します」
具体的には何をするのか。成長するための第一の柱は「科学技術立国の実現」であり、第二の柱は「デジタル田園都市国家構想」だという。「経済安全保障に取り組み、人生100年時代の不安解消を図る」とも述べた。ズラズラと政策を並べているが、それがどのような「新しい資本主義」につながっていくのか、少しも見えてこない。一番肝心な点に触れていないからだ。
戦後日本の資本主義は、終身雇用と家族的な経営を特徴としていた。同一労働=同一賃金の原則がそれなりに守られ、少なくとも真面目に働いている限り、働く者はそれほど将来の心配をする必要がなかった。それが高度経済成長の原動力となった。
こうした日本型の資本主義が大きく変わったのは、1985年に労働者派遣法が成立してからだ。同一労働=同一賃金の大原則に風穴が空いた。当初、派遣の対象は通訳や秘書、ソフトウェア開発など特別な技能を必要とする13の業務に制限されていたが、その後、対象は少しずつ拡大されていった。
そして2004年、小泉純一郎政権の時に派遣労働は製造業にまで拡大され、事実上、歯止めがなくなった。推進する側はこれを「働き方の多様化」と呼んだが、その実態は企業側に「働かせ方の多様化」をもたらすものだった。
時を経て、それがどのような結果を招いたか。私たちはまざまざと見せつけられている。今や、働く者の4割は派遣や契約社員、パートの非正規労働者である(図1)。不安定な雇用の下、低賃金で働くことを余儀なくされている。
将来を見通せない若者たちは結婚をためらい、子育てを躊躇(ちゅうちょ)する。非婚や晩婚化、少子化は経済と雇用の大きな変化を抜きにして語ることはできない。行政が結婚の斡旋や子育て世代への支援に乗り出す、といった小手先の対応をして解決できるような問題ではなくなっている。
その結果、日本の労働者はどのような状況に追い込まれたか。先進国を中心に38の国でつくるOECD(経済協力開発機構)の統計を見れば、それが如実に分かる。図2は、主要国の平均賃金の推移を示したものである。各国の平均賃金が着実に上がっていく中で、日本人労働者の平均賃金はこの20年、横ばいのままだ。2015年には韓国にも抜かれ、イタリアと最下位を争う状態になっている。
図3を見れば、気分はさらに落ち込む。OECD加盟国の「2020年平均賃金ランキング」によれば、日本人の平均賃金は加盟国平均のかなり下だ。もはや「中進国レベル」と言うしかない。
この間、もちろん企業も苦しんできたが、その痛みは働く者よりはるかに小さい。内部留保を膨らませている企業も少なくない。
パート労働や派遣労働が広がり、働く者が低賃金にあえいでいる現状にメスを入れ、労働環境の大胆な改革に乗り出さない限り、「新しい資本主義」など夢のまた夢だ。経済界の抵抗を押し切り、覚悟をもって取り組まなければ、事態は一歩も動かない。
では、岸田首相にはその覚悟があるのだろうか。改革にかける首相の本気度を測るためには、その言葉より、彼が仕切った人事を見る方がいい。岸田首相は、官房長官とともに政権運営の要となる自民党幹事長に甘利明氏を充てた。都市再生機構(UR)がらみの補償交渉で千葉県の建設会社に肩入れし、口利き料として1200万円もの資金提供や接待を受けた政治家だ(2016年1月、週刊文春の報道で発覚)。
資金を受け取り、接待を受けたのは主に秘書のようだが、甘利氏本人も50万円の札束を2回受け取り、ポケットに入れたことを認めている。「政治資金として受け取った」と釈明したものの、斡旋利得処罰法違反の疑いが濃厚だ。東京地検特捜部が捜査に乗り出し、疑惑が深まるや、甘利氏は「睡眠障害」を理由に入院し、国会にも出て来なくなった。眠れないから入院。ふざけた政治家だ。その後、捜査は尻すぼみになり、事件は闇に葬られた。
その甘利氏が素知らぬ顔で表舞台に舞い戻り、今回の自民党総裁選では「岸田総裁誕生」のために動き、論功で自民党幹事長の要職に就いた。安倍元首相が総裁候補として担いだ高市早苗氏は政務調査会長になった。
新内閣の閣僚の顔ぶれを見ても、岸田首相が「各派閥のバランスを取ってまずは安全運転」と考えていることは明白だ。そのような政治家に「新しい資本主義」を打ち立てるための大胆な改革などできるわけがない。「小さな改革」を小出しにするのが関の山だろう。
◇ ◇
誰が首相になろうと、日本丸の舵取りはきわめて難しい。政府と地方自治体の借金は1100兆円を超える。国内総生産(GDP)の2倍以上だ。それはどのような意味を持つのか。
図4は国際通貨基金(IMF)の経済統計に基づいて、主要国の債務(借金)残高を示したものだ。借金の総額を1年間のGDPで割り、それを百分率で表している。積み重ねた借金が1年分のGDPと同額なら100%となる。日本の債務残高は250%を超え、主要国の中で突出している。2年分のGDPをすべて借金の返済に充てても足りない状態だ。主要国の労働者の平均賃金で最下位を争うイタリアより、ずっとひどい。
経済学者の中には「日本は民間の貯蓄率が際立って高い。政府が保有する資産も膨大だ。イタリアとはまるで違う。これくらいの借金でよろめくことはない」と説く者がいる。「公的な債務は将来に対する投資であり、必ずリターンがある。債務を心配する必要などそもそもない」と主張する学者すらいる。
こういう人たちには「ではなぜ、ほかの国々は債務残高を低く抑えるために必死になっているのか」と問えばいい。ドイツは政府の歳入と歳出をトントンにする、という原則を固く守っている。コロナ禍で国債を発行せざるを得なくなったものの、それを返済する段取りもきちんと国民に示している。
国の財布も個人の財布も、原理は変わらない。収入よりも多く金を使えば、借金をするしかなくなる。そして、借金を重ねていけば、いつか破産する。経済理論をいくらこねくり回しても、この原理を超越することはできないのだ。
あらためて、政府の今年度予算案を眺めてみよう(図5)。国の歳入106兆円の4割は国債を発行してまかなっている。一方で歳出のうち、借金の返済に充てる国債費は2割に過ぎない。つまり、毎年、国の借金は雪ダルマのように膨らみ続ける。
それなのに、日本はインフレにならず、株価の暴落も起きていない。歴代の自民党政権が自転車操業のような手法を編み出し、駆使してきたからだ。
その典型が安倍晋三政権である。国の借金である国債を銀行の元締めの日本銀行に引き受けさせ、どんどん買わせた。紙幣を発行する中央銀行が国債を買い付けることなど、かつては「決してやってはいけない」とされていたが、平気でそれを続けた。
安倍政権は、株価を吊り上げるための手立ても講じた。日本の厚生年金と国民年金の資金は、「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)が運用している。その運用資産は2020年度末で186兆円もあり、世界最大の機関投資家だ。図6に見るように、GPIFは発足時の2006年時点では、主にリスクの小さい国内の債券を買って運用していた。年金制度を支える積立金が目減りしたら大変なことになるからだ。
ところが、安倍政権の下でGPIFはリスクの高い内外の株式や外国債券の割合を大幅に増やしていった。2020年4月の時点では運用先は4分の1ずつ。リスクの高い株式市場に資金をジャブジャブ注ぎ込んだのである。
それは「ギャンブル」のような運用だ。図7が示しているように、2008年のリーマンショックで9兆円もの赤字を出したかと思えば、景気が上向いた2014年には15兆円の黒字になった。何とも危うい運用だ。
年金を管轄する厚生労働省やGPIFは「カナダやノルウェーの年金の株式運用の割合はもっと高い」と説明する。だが、アメリカ最大の公的年金の運用機関である社会保障信託基金(OASDI)が米国債しか買わないことには触れない。ドイツやイギリス、フランスの年金制度は「原則として徴収した資金で年金をまかなう」という堅実なもので、そもそも巨額の積立金を持っていない。それも説明しない。
要するに、年金の積み立てと運用という面でも、日本は極めてリスクの高いことをしている「突出した国家」なのだ。「アベノミクスの3本の矢、成長戦略の一環」などという声に踊らされて株式投資の割合を増やし続け、リスクは極大化した、と言わなければならない。
株価がどう動くかは誰にも予想できない。暴落すれば、年金の支給そのものに影響が出る恐れがある。政府の膨大な債務とともに、年金積立金の運用も大きなリスク要因である。
「新しい資本主義」を唱えるなら、岸田首相はこうした深刻な問題についても率直に語りかけなければならない。が、まったく触れようとしない。問題に手を付けようとするそぶりも見せない。問題の根があまりにも深くかつ重大なので、怖くて触れることすらできないのかもしれない。
◇ ◇
では、政権交代を叫ぶ立憲民主党はどうか。安倍政権は森友学園問題で公文書を改竄(かいざん)し、加計学園問題や「桜を見る会」をめぐってウソとごまかしを重ねた。立憲民主党は、それによって「政治と行政がゆがめられた」と批判し、「透明で信頼できる政府をつくる」と訴える。「原発に依存せず、自然エネルギー立国を目指す」とも唱えている。このへんまでは、すこぶるまっとうだ。
ところが、国の財政や金融の話になると、この政党は途端に突拍子もないことを言い出す。枝野幸男代表はコロナ禍で落ち込んだ消費を回復させるため、「消費税5%への減税が必要だ」と言い放った。年収1000万円程度までは一時的に「所得税をゼロにする」とも口にした。
消費税を半分の5%にすれば、それだけで10兆円の歳入が吹き飛ぶ。所得税ゼロでも兆円単位の歳入減になる。その手当てをどうすると言うのか。「財源は富裕層や大企業への優遇税制の是正で捻出する」と、もっともらしい公約を掲げているが、そうした措置でいくら捻出できるか、試算を示そうともしない。
かつて政権交代を実現した民主党は、掛け声だけは立派だったが、政策を実行する力量も覚悟もなく自滅した。立憲民主党の公約を聞いていると、その姿と二重写しになる。過去の失敗から教訓をくみ取り、今度こそ有権者の信頼を勝ち取らなければならないのに、そういう謙虚さがみじんも感じられない。立憲民主党の面々も、自民党とは異なる意味で有権者を小馬鹿にしている。
国民民主党はどうか。この政党の公約は、立憲民主党の公約が現実的に思えてしまうほど非現実的だ。コロナ禍から立ち上がるため積極財政に転じ、「今後10年間で150兆円の投資をする」のだという。まず、コロナで傷ついた生活と事業を救済するため50兆円の緊急経済対策を講じる。次に、環境やデジタルなど未来への投資に50兆円。さらに、教育と科学技術予算を倍増させ、「人づくり」に50兆円の投資をするのだという。
こんな公約は「私たちはどの党よりも速やかに国家財政を破綻させ、国を破滅に導いてみせます」と言っているに等しい。党の幹部に経済や財政、金融をまともに考えている人間が1人もいないことを示している。論外と言うしかない。
ひたすら税金のバラマキを訴えるという意味では、「0歳から高校3年生まで全員に一律10万円を支給する」と唱える連立与党の公明党も、消費税を廃止すると言う「れいわ新選組」も同列だ。どちらも「責任をもって未来を語ろうとしない」という点で共通している。
各政党の無責任な公約に堪忍袋の緒が切れたのだろう。財務事務次官の矢野康治(こうじ)氏は、月刊『文藝春秋』の11月号に「このままでは国家財政は破綻する」と題した一文を寄せた。
「これでは古代ローマ帝国のパンとサーカスです。誰が一番景気のいいことを言えるか、他の人が思いつかないような大盤振る舞いができるかを競っているかのようでもあり、かの強大な帝国もバラマキで滅亡したのです」
矢野氏は、前述したような日本の財政の危機的状況を具体的に説明しつつ、「あえて今の日本の状況を喩(たと)えれば、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものです」と記し、「破滅的な衝突を避けるためには、『不都合な真実』もきちんと直視し、先送りすることなく、最も賢明なやり方で対処していかねばなりません」と訴えている。
森友学園問題で公文書を改竄し、職員を自死にまで追い込みながら誰一人責任を取らなかった財務省のトップがなにを偉そうに、と反発する人もいるかもしれない。
けれども、「国庫の管理をまかされた立場にいる者」として、また「心あるモノ言う犬」として「どんなに叱られても、どんなに搾(しぼ)られても、言うべきことを言わなければならないと思います」と綴った文章には熱を感じる。そして、官僚をここまで追い詰めてしまった日本の政治の貧困を思わないではいられない。
長い文章になってしまった。その他の政党については、寸評するしかない。日本維新の会は主要政党の中では珍しく税金のバラマキを掲げていない。日本社会のどこをどう改革すべきか、現実的な処方箋を示している。が、いかんせん、関西の政党である。ほかの地域の有権者にとってはやはり「遠い存在」だ。
共産党は真面目な政党だが、今さら「共産主義に基づく国家建設」に与(くみ)する気にはなれない。社民党の政策に至っては「大学生の作文か」と言いたくなる。
選択に苦しむ選挙だ。こんなに重苦しい選挙は記憶にない。それでも、私たちは選ばなければならない。「下り坂にさしかかった国」ではあっても、私たちの国にはまだ底力がある。その底力を引き出して、せめてなだらかな坂道にして次の世代に引き継ぎたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
≪写真のSource≫
◎岸田文雄首相(HuffPost のサイトから)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6153bcace4b05025422bd5e5
≪参考資料&サイト≫
◎NHKウェブ特集「クローズアップ現代が見つめた17年」
https://www.nhk.or.jp/gendai/special/tokusyu01_figure_section.html
◎「日本人は韓国人より給料が38万円も安い!」(DIAMOND online)
https://diamond.jp/articles/-/278127
◎日医総研リサーチエッセイNo.90 「公的年金の運営状況についての考察(補論)」(石尾勝主任研究員)
https://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_712.html
◎「公的年金積立金運用のあり方について:予備的考察」(國枝繁樹)
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news270918_14.pdf

NHKや朝日新聞は今回の総選挙について、盛んに「政権選択の選挙」と報じた。だが、この選挙で政権交代が実現する可能性があると考えている人はほとんどいないだろう。
安倍晋三、菅義偉両氏の下で9年に及んだ政権運営を有権者はどう判断するのか。ウソとごまかしの政治にどこまでお灸をすえるのか。そのお灸の度合いが示される選挙、と見る方が自然だろう。立憲民主党を中心とする野党に再び政権運営をゆだねるほど、有権者はうぶではあるまい。
選挙に向けて、岸田首相は「新しい資本主義」なるスローガンを掲げた。アメリカ型の強欲な資本主義、弱者切り捨ての資本主義とは異なるものを目指したいようだ。どのような資本主義を思い描いているのか。岸田首相は所信表明演説でこう述べた。
「成長と分配の好循環と、コロナ後の新しい社会の開拓。これがコンセプトです。成長の果実をしっかりと分配することで、初めて次の成長が実現します。大切なのは成長と分配の好循環です。『成長か分配か』という不毛な議論から脱却し、『成長も分配も』実現するためにあらゆる政策を総動員します」
具体的には何をするのか。成長するための第一の柱は「科学技術立国の実現」であり、第二の柱は「デジタル田園都市国家構想」だという。「経済安全保障に取り組み、人生100年時代の不安解消を図る」とも述べた。ズラズラと政策を並べているが、それがどのような「新しい資本主義」につながっていくのか、少しも見えてこない。一番肝心な点に触れていないからだ。
戦後日本の資本主義は、終身雇用と家族的な経営を特徴としていた。同一労働=同一賃金の原則がそれなりに守られ、少なくとも真面目に働いている限り、働く者はそれほど将来の心配をする必要がなかった。それが高度経済成長の原動力となった。
こうした日本型の資本主義が大きく変わったのは、1985年に労働者派遣法が成立してからだ。同一労働=同一賃金の大原則に風穴が空いた。当初、派遣の対象は通訳や秘書、ソフトウェア開発など特別な技能を必要とする13の業務に制限されていたが、その後、対象は少しずつ拡大されていった。
そして2004年、小泉純一郎政権の時に派遣労働は製造業にまで拡大され、事実上、歯止めがなくなった。推進する側はこれを「働き方の多様化」と呼んだが、その実態は企業側に「働かせ方の多様化」をもたらすものだった。
時を経て、それがどのような結果を招いたか。私たちはまざまざと見せつけられている。今や、働く者の4割は派遣や契約社員、パートの非正規労働者である(図1)。不安定な雇用の下、低賃金で働くことを余儀なくされている。
将来を見通せない若者たちは結婚をためらい、子育てを躊躇(ちゅうちょ)する。非婚や晩婚化、少子化は経済と雇用の大きな変化を抜きにして語ることはできない。行政が結婚の斡旋や子育て世代への支援に乗り出す、といった小手先の対応をして解決できるような問題ではなくなっている。
その結果、日本の労働者はどのような状況に追い込まれたか。先進国を中心に38の国でつくるOECD(経済協力開発機構)の統計を見れば、それが如実に分かる。図2は、主要国の平均賃金の推移を示したものである。各国の平均賃金が着実に上がっていく中で、日本人労働者の平均賃金はこの20年、横ばいのままだ。2015年には韓国にも抜かれ、イタリアと最下位を争う状態になっている。
図3を見れば、気分はさらに落ち込む。OECD加盟国の「2020年平均賃金ランキング」によれば、日本人の平均賃金は加盟国平均のかなり下だ。もはや「中進国レベル」と言うしかない。
この間、もちろん企業も苦しんできたが、その痛みは働く者よりはるかに小さい。内部留保を膨らませている企業も少なくない。
パート労働や派遣労働が広がり、働く者が低賃金にあえいでいる現状にメスを入れ、労働環境の大胆な改革に乗り出さない限り、「新しい資本主義」など夢のまた夢だ。経済界の抵抗を押し切り、覚悟をもって取り組まなければ、事態は一歩も動かない。
では、岸田首相にはその覚悟があるのだろうか。改革にかける首相の本気度を測るためには、その言葉より、彼が仕切った人事を見る方がいい。岸田首相は、官房長官とともに政権運営の要となる自民党幹事長に甘利明氏を充てた。都市再生機構(UR)がらみの補償交渉で千葉県の建設会社に肩入れし、口利き料として1200万円もの資金提供や接待を受けた政治家だ(2016年1月、週刊文春の報道で発覚)。
資金を受け取り、接待を受けたのは主に秘書のようだが、甘利氏本人も50万円の札束を2回受け取り、ポケットに入れたことを認めている。「政治資金として受け取った」と釈明したものの、斡旋利得処罰法違反の疑いが濃厚だ。東京地検特捜部が捜査に乗り出し、疑惑が深まるや、甘利氏は「睡眠障害」を理由に入院し、国会にも出て来なくなった。眠れないから入院。ふざけた政治家だ。その後、捜査は尻すぼみになり、事件は闇に葬られた。
その甘利氏が素知らぬ顔で表舞台に舞い戻り、今回の自民党総裁選では「岸田総裁誕生」のために動き、論功で自民党幹事長の要職に就いた。安倍元首相が総裁候補として担いだ高市早苗氏は政務調査会長になった。
新内閣の閣僚の顔ぶれを見ても、岸田首相が「各派閥のバランスを取ってまずは安全運転」と考えていることは明白だ。そのような政治家に「新しい資本主義」を打ち立てるための大胆な改革などできるわけがない。「小さな改革」を小出しにするのが関の山だろう。
◇ ◇
誰が首相になろうと、日本丸の舵取りはきわめて難しい。政府と地方自治体の借金は1100兆円を超える。国内総生産(GDP)の2倍以上だ。それはどのような意味を持つのか。
図4は国際通貨基金(IMF)の経済統計に基づいて、主要国の債務(借金)残高を示したものだ。借金の総額を1年間のGDPで割り、それを百分率で表している。積み重ねた借金が1年分のGDPと同額なら100%となる。日本の債務残高は250%を超え、主要国の中で突出している。2年分のGDPをすべて借金の返済に充てても足りない状態だ。主要国の労働者の平均賃金で最下位を争うイタリアより、ずっとひどい。
経済学者の中には「日本は民間の貯蓄率が際立って高い。政府が保有する資産も膨大だ。イタリアとはまるで違う。これくらいの借金でよろめくことはない」と説く者がいる。「公的な債務は将来に対する投資であり、必ずリターンがある。債務を心配する必要などそもそもない」と主張する学者すらいる。
こういう人たちには「ではなぜ、ほかの国々は債務残高を低く抑えるために必死になっているのか」と問えばいい。ドイツは政府の歳入と歳出をトントンにする、という原則を固く守っている。コロナ禍で国債を発行せざるを得なくなったものの、それを返済する段取りもきちんと国民に示している。
国の財布も個人の財布も、原理は変わらない。収入よりも多く金を使えば、借金をするしかなくなる。そして、借金を重ねていけば、いつか破産する。経済理論をいくらこねくり回しても、この原理を超越することはできないのだ。
あらためて、政府の今年度予算案を眺めてみよう(図5)。国の歳入106兆円の4割は国債を発行してまかなっている。一方で歳出のうち、借金の返済に充てる国債費は2割に過ぎない。つまり、毎年、国の借金は雪ダルマのように膨らみ続ける。
それなのに、日本はインフレにならず、株価の暴落も起きていない。歴代の自民党政権が自転車操業のような手法を編み出し、駆使してきたからだ。
その典型が安倍晋三政権である。国の借金である国債を銀行の元締めの日本銀行に引き受けさせ、どんどん買わせた。紙幣を発行する中央銀行が国債を買い付けることなど、かつては「決してやってはいけない」とされていたが、平気でそれを続けた。
安倍政権は、株価を吊り上げるための手立ても講じた。日本の厚生年金と国民年金の資金は、「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)が運用している。その運用資産は2020年度末で186兆円もあり、世界最大の機関投資家だ。図6に見るように、GPIFは発足時の2006年時点では、主にリスクの小さい国内の債券を買って運用していた。年金制度を支える積立金が目減りしたら大変なことになるからだ。
ところが、安倍政権の下でGPIFはリスクの高い内外の株式や外国債券の割合を大幅に増やしていった。2020年4月の時点では運用先は4分の1ずつ。リスクの高い株式市場に資金をジャブジャブ注ぎ込んだのである。
それは「ギャンブル」のような運用だ。図7が示しているように、2008年のリーマンショックで9兆円もの赤字を出したかと思えば、景気が上向いた2014年には15兆円の黒字になった。何とも危うい運用だ。
年金を管轄する厚生労働省やGPIFは「カナダやノルウェーの年金の株式運用の割合はもっと高い」と説明する。だが、アメリカ最大の公的年金の運用機関である社会保障信託基金(OASDI)が米国債しか買わないことには触れない。ドイツやイギリス、フランスの年金制度は「原則として徴収した資金で年金をまかなう」という堅実なもので、そもそも巨額の積立金を持っていない。それも説明しない。
要するに、年金の積み立てと運用という面でも、日本は極めてリスクの高いことをしている「突出した国家」なのだ。「アベノミクスの3本の矢、成長戦略の一環」などという声に踊らされて株式投資の割合を増やし続け、リスクは極大化した、と言わなければならない。
株価がどう動くかは誰にも予想できない。暴落すれば、年金の支給そのものに影響が出る恐れがある。政府の膨大な債務とともに、年金積立金の運用も大きなリスク要因である。
「新しい資本主義」を唱えるなら、岸田首相はこうした深刻な問題についても率直に語りかけなければならない。が、まったく触れようとしない。問題に手を付けようとするそぶりも見せない。問題の根があまりにも深くかつ重大なので、怖くて触れることすらできないのかもしれない。
◇ ◇
では、政権交代を叫ぶ立憲民主党はどうか。安倍政権は森友学園問題で公文書を改竄(かいざん)し、加計学園問題や「桜を見る会」をめぐってウソとごまかしを重ねた。立憲民主党は、それによって「政治と行政がゆがめられた」と批判し、「透明で信頼できる政府をつくる」と訴える。「原発に依存せず、自然エネルギー立国を目指す」とも唱えている。このへんまでは、すこぶるまっとうだ。
ところが、国の財政や金融の話になると、この政党は途端に突拍子もないことを言い出す。枝野幸男代表はコロナ禍で落ち込んだ消費を回復させるため、「消費税5%への減税が必要だ」と言い放った。年収1000万円程度までは一時的に「所得税をゼロにする」とも口にした。
消費税を半分の5%にすれば、それだけで10兆円の歳入が吹き飛ぶ。所得税ゼロでも兆円単位の歳入減になる。その手当てをどうすると言うのか。「財源は富裕層や大企業への優遇税制の是正で捻出する」と、もっともらしい公約を掲げているが、そうした措置でいくら捻出できるか、試算を示そうともしない。
かつて政権交代を実現した民主党は、掛け声だけは立派だったが、政策を実行する力量も覚悟もなく自滅した。立憲民主党の公約を聞いていると、その姿と二重写しになる。過去の失敗から教訓をくみ取り、今度こそ有権者の信頼を勝ち取らなければならないのに、そういう謙虚さがみじんも感じられない。立憲民主党の面々も、自民党とは異なる意味で有権者を小馬鹿にしている。
国民民主党はどうか。この政党の公約は、立憲民主党の公約が現実的に思えてしまうほど非現実的だ。コロナ禍から立ち上がるため積極財政に転じ、「今後10年間で150兆円の投資をする」のだという。まず、コロナで傷ついた生活と事業を救済するため50兆円の緊急経済対策を講じる。次に、環境やデジタルなど未来への投資に50兆円。さらに、教育と科学技術予算を倍増させ、「人づくり」に50兆円の投資をするのだという。
こんな公約は「私たちはどの党よりも速やかに国家財政を破綻させ、国を破滅に導いてみせます」と言っているに等しい。党の幹部に経済や財政、金融をまともに考えている人間が1人もいないことを示している。論外と言うしかない。
ひたすら税金のバラマキを訴えるという意味では、「0歳から高校3年生まで全員に一律10万円を支給する」と唱える連立与党の公明党も、消費税を廃止すると言う「れいわ新選組」も同列だ。どちらも「責任をもって未来を語ろうとしない」という点で共通している。
各政党の無責任な公約に堪忍袋の緒が切れたのだろう。財務事務次官の矢野康治(こうじ)氏は、月刊『文藝春秋』の11月号に「このままでは国家財政は破綻する」と題した一文を寄せた。
「これでは古代ローマ帝国のパンとサーカスです。誰が一番景気のいいことを言えるか、他の人が思いつかないような大盤振る舞いができるかを競っているかのようでもあり、かの強大な帝国もバラマキで滅亡したのです」
矢野氏は、前述したような日本の財政の危機的状況を具体的に説明しつつ、「あえて今の日本の状況を喩(たと)えれば、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものです」と記し、「破滅的な衝突を避けるためには、『不都合な真実』もきちんと直視し、先送りすることなく、最も賢明なやり方で対処していかねばなりません」と訴えている。
森友学園問題で公文書を改竄し、職員を自死にまで追い込みながら誰一人責任を取らなかった財務省のトップがなにを偉そうに、と反発する人もいるかもしれない。
けれども、「国庫の管理をまかされた立場にいる者」として、また「心あるモノ言う犬」として「どんなに叱られても、どんなに搾(しぼ)られても、言うべきことを言わなければならないと思います」と綴った文章には熱を感じる。そして、官僚をここまで追い詰めてしまった日本の政治の貧困を思わないではいられない。
長い文章になってしまった。その他の政党については、寸評するしかない。日本維新の会は主要政党の中では珍しく税金のバラマキを掲げていない。日本社会のどこをどう改革すべきか、現実的な処方箋を示している。が、いかんせん、関西の政党である。ほかの地域の有権者にとってはやはり「遠い存在」だ。
共産党は真面目な政党だが、今さら「共産主義に基づく国家建設」に与(くみ)する気にはなれない。社民党の政策に至っては「大学生の作文か」と言いたくなる。
選択に苦しむ選挙だ。こんなに重苦しい選挙は記憶にない。それでも、私たちは選ばなければならない。「下り坂にさしかかった国」ではあっても、私たちの国にはまだ底力がある。その底力を引き出して、せめてなだらかな坂道にして次の世代に引き継ぎたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
≪写真のSource≫
◎岸田文雄首相(HuffPost のサイトから)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6153bcace4b05025422bd5e5
≪参考資料&サイト≫
◎NHKウェブ特集「クローズアップ現代が見つめた17年」
https://www.nhk.or.jp/gendai/special/tokusyu01_figure_section.html
◎「日本人は韓国人より給料が38万円も安い!」(DIAMOND online)
https://diamond.jp/articles/-/278127
◎日医総研リサーチエッセイNo.90 「公的年金の運営状況についての考察(補論)」(石尾勝主任研究員)
https://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_712.html
◎「公的年金積立金運用のあり方について:予備的考察」(國枝繁樹)
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news270918_14.pdf
昭和の政商、児玉誉士夫は戦前、海軍航空本部の嘱託として上海でコバルトやニッケルなど戦略物資の調達にあたり、莫大な富を手にした。
敗戦直前に隠匿物資とともに引き揚げ、戦後は駐留米軍に協力してその富を温存、保守勢力の黒幕として影響力を行使した。児玉の力の源泉は戦前、戦後を通して「軍」であった。

では、「令和の政商」の異名を取る大樹(たいじゅ)総研グループの代表、矢島義也(よしなり)氏の力の源泉は何か。どうやって原資を蓄えたのか。これまでの報道や関係者の話をもとに探っていくと、どうやら「女」を使って元手を蓄えたのではないか。そう思われる節がある。
矢島氏の名を初めて世に知らしめたのは、スキャンダル暴露雑誌『噂の眞相』である。1999年の8月号に「有名俳優たちの秘密乱交パーティの夜」という記事を掲載し、東京・代々木公園近くのマンションに若手のタレントと妙齢の女性たちを集め、夜ごと乱交パーティーを開いている、と報じた。記事では矢島氏は本名の「矢島義成」として登場する。
このマンションに足しげく通ってきたのはジャニーズ事務所に所属していた堂本光一や長瀬智也、俳優のいしだ壱成、加藤晴彦・・・。当時の売れっ子タレントが続々登場する。彼らの相手をしていた女性たちも突き止め、その証言も生々しく伝えた。
芸能プロの関係者によれば、「矢島はもともと神宮前にあった『ネオ・マスカレード』というバーのオーナー。バーには芸能人やプロ野球選手なんかが頻繁に来ていた。女と有名人には目がない性格で、言ってみれば一種の『芸能ゴロ』みたいなタイプ」なのだという。
このバーにしろ乱交パーティーにしろ、矢島氏とタレントたちを結び付けたのはTBSの宣伝部や編成局の幹部たちのようだ。「TBSに深く食い込み、編成部が主催するゴルフコンペはすべて矢島氏が仕切っている」との証言を伝えている。
この記事を受けて、写真週刊誌『フォーカス』も同年7月21日号で「乱交パーティー『女衒(ぜげん)芸能プロ社長』の正体」と報じた。事情通によれば、「芸能プロ社長の名刺で女の子をナンパ。タレントにしてあげるとか、芸能人に会わせてあげるなどと言って、パーティーに誘っていた」のだという。
同誌は矢島氏の故郷は長野県箕輪(みのわ)町であるとし、地元の人の話として「実家が会社を経営していた資産家の一人息子。地元の高校を中退して、その後も定職につかず、親の金で飲み歩いたり女を引っかけたり。慣れない事業に手を出して失敗、親を破産させてしまった。バカなボンボンというので?バカボン?と呼ばれていました」と伝えている。
◇ ◇
この生い立ちの記はどこまで本当なのか。長野県南部の伊那谷にある故郷を訪ねた。
彼は1961年1月、長野県箕輪町で矢島誠氏の長男として生まれた。この町には、電子部品メーカーとして世界トップクラスの技術を持つ興亜工業という会社がある(後にKOAと社名変更)。創業者は向山(むかいやま)一人氏で、衆院議員や参院議員も務めた。
父親が経営していた矢島電機は興亜の系列会社だった。日本の製造業が世界を席巻していた1980年代には父親の会社も躍進し、町内に豪邸を建てている。「資産家のボンボン」であったことは間違いない。
小中学校時代を知る人は「余裕のある性格で失敗を恐れない。人に頼られるタイプ。器が大きいと感じた。野心は持っていたように思う」と語った。
箕輪中学の卒業文集(1975年度)に寄せた文章(写真)が興味深い。タイトルは「中学卒業バンザイ 後三年で?」。中学校生活の思い出は乏しく、高校生活への期待もあまり感じられない。行数を費やしているのは高校を卒業した後に乗りたい車、とくにポルシェなど外車へのあこがれである。
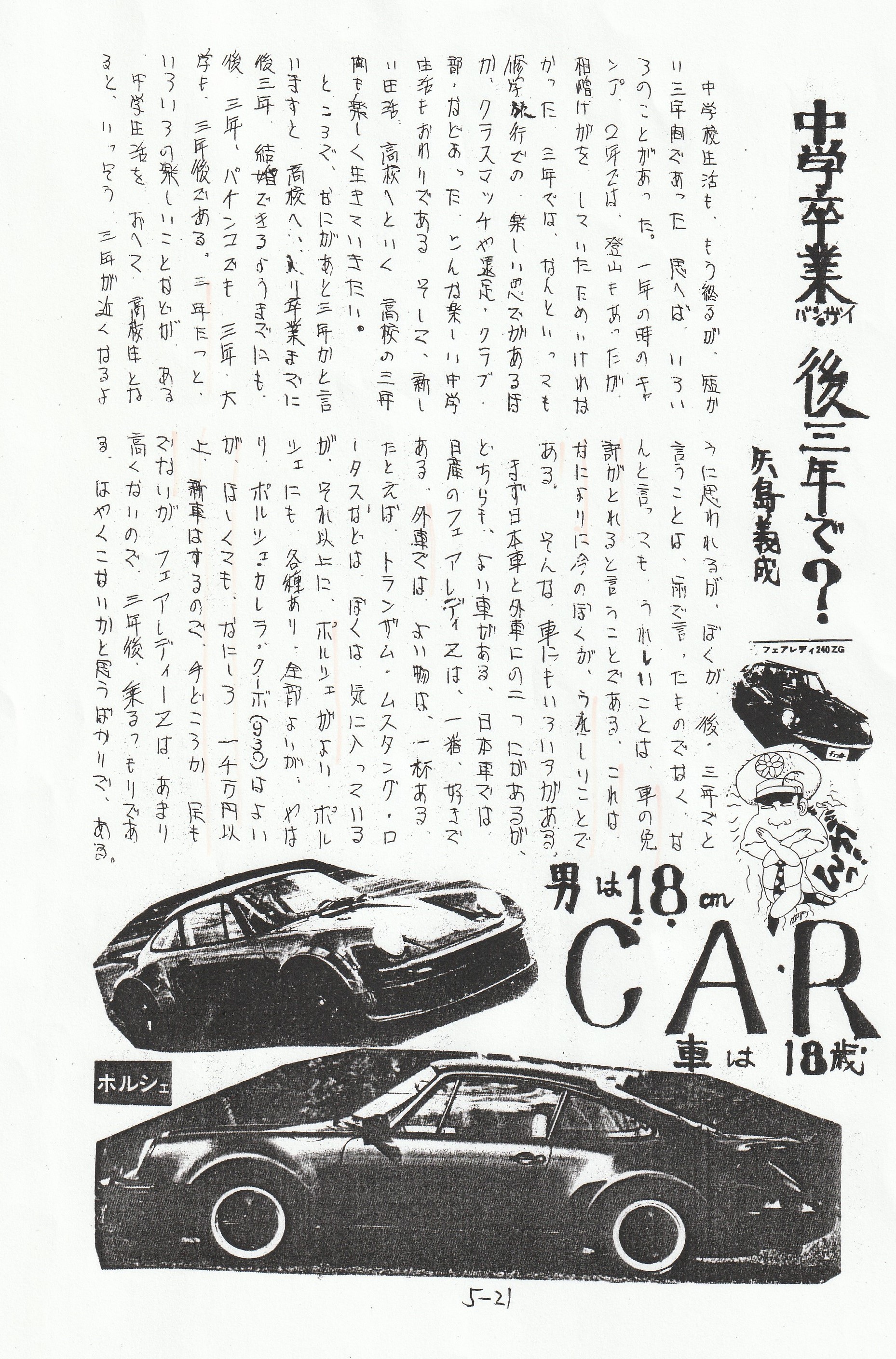
中学で長く国語の教師を務めた人にこの文章を読んでもらった。この文章から何がうかがえるのか。
「漢字の使い方はちゃんとしている。ただ、部活で活躍したとか達成感を得られた経験がなく、なんとなく過ぎていった中学生活だったのではないか。学校で知識を身につけて社会に出たいと思うタイプではない。さっさと高校を卒業して、楽しいことをしたいと考えていたのではないか」
同級生の記憶によれば、中学卒業後、バレーボールやラグビーの強豪校として知られる岡谷工業高校に入学したものの、中退したようだ。このためか、岡谷工業の同窓会名簿には見当たらない。入学者名簿は保存期間が過ぎたため廃棄されてないという。進学先は確認できなかった。
中退後、矢島氏はゴルフに打ち込んだ。愛好者を集めてコンペを主宰している。シングルプレーヤーで、プロを目指していた節もある。父親に資金を出してもらって、地元にスポーツ用品店を開いたりした。
だが、事業は失敗し、このころ父親の会社の経営も傾き始める。借金も重なり、矢島氏は逃げるように故郷を後にした。神宮前でくだんのバーを開いたのは1989年前後、20代の後半だった。父親の会社は倒産し、1998年に清算された。
会社の土地も豪邸も人手に渡ってしまったが、父親の名義ではなかったからか、生家だけは残った。現在は矢島氏と最初の妻との間にできた娘の名義になっている。父親は10年前に死去したものの、生家には今も「矢島誠」の表札が掲げられている。苦労をかけた父親への償い、なのかもしれない。
東京でバーを経営し、その時の人脈で芸能界とテレビ業界に足場を築いたことは『噂の眞相』や『フォーカス』の記事からうかがえる。だが、「乱交パーティー騒動」の後、矢島氏がどうしていたのかはよく分からない。
中曽根内閣で労働大臣を務めた山口敏夫氏によると、彼はこのころ「銀座でプータローのような生活をしていた」という。彼と知り合ったのも銀座のクラブだ。「だれか貢いでくれる女でもいたのかもしれないね。派手に遊んでいたから」。
その銀座で矢島氏に転機が訪れる。浜松出身の民主党衆院議員、鈴木康友氏と知り合ったのだ。「鈴木氏は落選中だった」というから、郵政民営化をテーマに小泉政権が仕掛けた2005年総選挙以降のことと思われる。
鈴木氏は松下政経塾の1期生で、同期に野田佳彦衆院議員がいた。矢島氏は鈴木―野田のラインをたどって、民主党内に人脈を広げていった。2007年には鈴木氏と矢島氏のイニシャルを冠した政策シンクタンク「S&Y総研」を立ち上げた(後に「大樹総研」と改称)。
鈴木氏はこの年に国政から身を引き、浜松市長に転じたが、矢島氏が政界に人脈を広げるきっかけを作ったという意味で、「政商・矢島義也」の生みの親と言っていい。
◇ ◇
銀座という「地の利」、民主党人脈という「人の和」を得た矢島氏に「天の時」が訪れたのは、2009年である。
時の麻生太郎首相の不人気、自民党の内紛、リーマンショック後の不況といった要素が重なり、この年の総選挙で民主党が圧勝したのだ。鳩山由紀夫政権が誕生し、野田氏は財務副大臣に就任した。
1955年の結党以来、自民党は初めて第2党に転落し、霞が関の官僚たちはうろたえた。大臣になったのはよく知らない政治家ばかり。ツテを求めて、官僚たちの「矢島詣で」が始まる。国会対策を担当していた財務省の福田淳一氏、法務省の黒川弘務氏らとのつながりができたのはこの時である(後に福田氏は事務次官に上り詰めたが、セクハラで失脚。黒川氏は賭け麻雀で検事総長になり損ねた)。
矢島氏は民主党政権時代、野党自民党の国会対策副委員長として苦労していた菅義偉氏に手を差し伸べている。グループの議員が軒並み落選し、派閥解消に追い込まれた二階俊博氏も支援した。このへんが矢島氏の懐の深いところだ。人間、苦しい時に助けてくれた人への恩は忘れない。
自民党が政権を奪回すると、矢島氏は菅―二階のラインで自民党にも人脈を広げ、与野党の双方に太いパイプを持つに至った。官僚や経済人が以前にも増して群がったのは言うまでもない。
矢島氏の人脈のすごさを見せつけたのが、2016年5月に帝国ホテル「富士の間」で開いた「結婚を祝う会」である。銀座で知り合った女性との再婚を祝う会なのだが、主賓は菅義偉・官房長官(当時)、乾杯の音頭は二階俊博・自民党総務会長(同)という豪華版だ。
民進党(旧民主党)からも野田佳彦氏、玄葉光一郎氏、細野豪志氏らが出席、財務省の福田氏ら有力省庁の幹部も漏れなく参じた。菅氏と親しいSBIホールディングスの北尾吉孝社長、サイバーセキュリティ分野で国内第一人者とされる安田浩・東大名誉教授、徳川宗家19代当主の徳川家広氏、インドネシアのゴベル通商大臣ら実に多彩な顔ぶれである。
こういう席にはあまり顔を出さない安倍晋三首相(同)もビデオメッセージを寄せ、それが披露されると、300人余りの出席者の間にざわめきが広がったという。
その人脈を矢島氏はどのように活用しているのか。その内実を、月刊誌『選択』が2018年8月号で詳細に暴いている。
大樹総研の傘下に再生可能エネルギー事業を手がける「JCサービス」という会社がある。この会社が鹿児島県徳之島町で太陽光発電の蓄電池増設事業を計画し、2013年に環境省から補助金を受けた。
ところが、蓄電池は一度も稼働せず、一部は現場に放置されていた。事業のずさんさを知った環境省は、補助金2億9600万円の返還と加算金1億3600万円の支払いを命じた。
問題は、このJCサービスの子会社から細野豪志氏に5000万円の資金が流れていたことだ。この補助事業が検討されていた2012年当時、細野氏は野田政権の環境大臣であり、「便宜供与への謝礼(賄賂)」ではないか、との疑惑が浮上した。
細野氏は「個人的に借りた」と釈明し、贈収賄事件として立件されることはなかったが、細野氏と会社との仲介をしたのは大樹総研グループと見られる。
『選択』は、ソーシャルレンディングをめぐる闇も追及している。ネット上で資金を募り、ネット上で融資の仲介をするベンチャービジネスの一つだが、再生可能エネルギーへの投資を名目に巨額の資金を集めながら、それとは別のことに流用するといったトラブルが頻発している。この分野でも大樹総研傘下の企業群がうごめいているという。
記事で引用している大樹コンサルティングの海老根靖典社長の言葉が興味深い。海老根氏によれば、大樹総研グループは「すべての政党と深く関わりがあり、中央官庁との色々なネットワークも持っていますので、政治的な働きかけができることが大きな強み」なのだという。
彼らはその「強み」をどのように使っているのか。政治家や官僚、企業経営者たちは大樹総研グループとどう関わっているのか。一つひとつ、それを解き明かしていく作業を続けなければなるまい。
*メールマガジン「風切通信 94」 2021年9月28日
*初出:調査報道サイト「HUNTER」
≪写真説明≫
長野県箕輪町にある矢島義也氏の生家
≪参考資料≫
◎矢島義也氏の関係年表
◎父親の会社「矢島電機」が清算されたことを示す法人登記
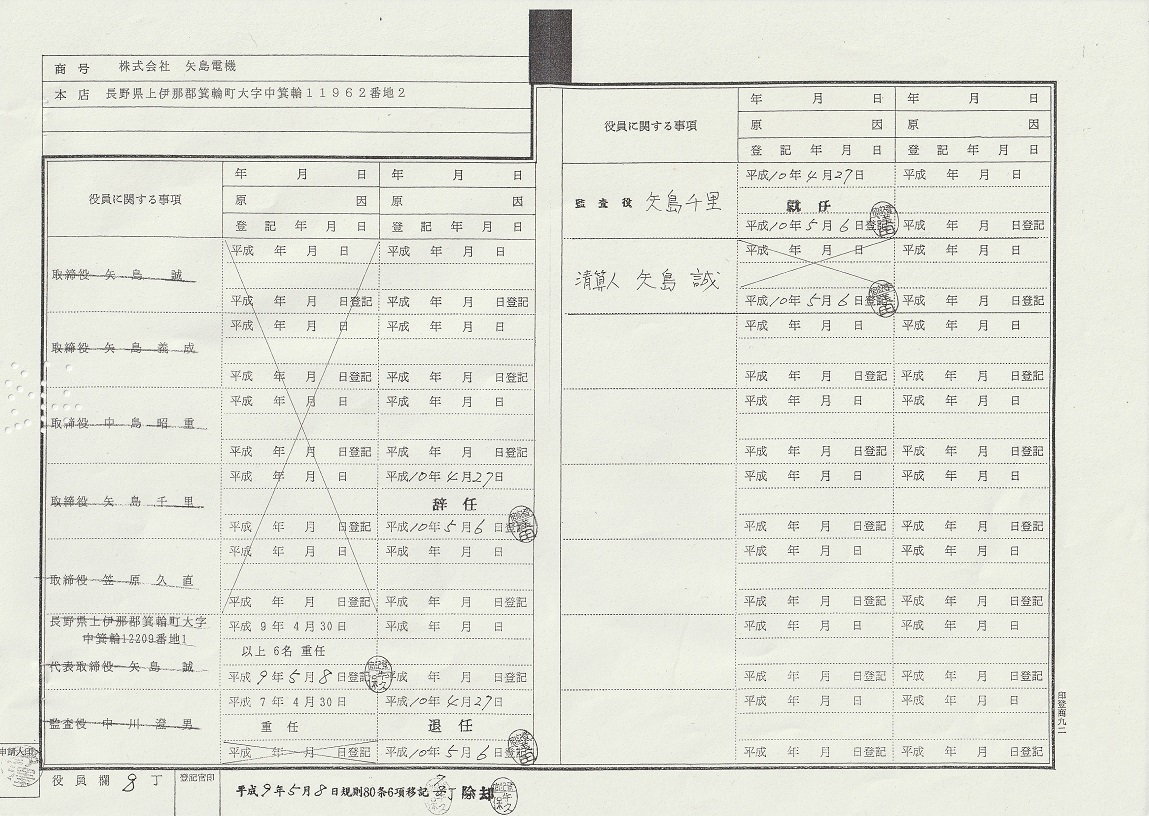
敗戦直前に隠匿物資とともに引き揚げ、戦後は駐留米軍に協力してその富を温存、保守勢力の黒幕として影響力を行使した。児玉の力の源泉は戦前、戦後を通して「軍」であった。

では、「令和の政商」の異名を取る大樹(たいじゅ)総研グループの代表、矢島義也(よしなり)氏の力の源泉は何か。どうやって原資を蓄えたのか。これまでの報道や関係者の話をもとに探っていくと、どうやら「女」を使って元手を蓄えたのではないか。そう思われる節がある。
矢島氏の名を初めて世に知らしめたのは、スキャンダル暴露雑誌『噂の眞相』である。1999年の8月号に「有名俳優たちの秘密乱交パーティの夜」という記事を掲載し、東京・代々木公園近くのマンションに若手のタレントと妙齢の女性たちを集め、夜ごと乱交パーティーを開いている、と報じた。記事では矢島氏は本名の「矢島義成」として登場する。
このマンションに足しげく通ってきたのはジャニーズ事務所に所属していた堂本光一や長瀬智也、俳優のいしだ壱成、加藤晴彦・・・。当時の売れっ子タレントが続々登場する。彼らの相手をしていた女性たちも突き止め、その証言も生々しく伝えた。
芸能プロの関係者によれば、「矢島はもともと神宮前にあった『ネオ・マスカレード』というバーのオーナー。バーには芸能人やプロ野球選手なんかが頻繁に来ていた。女と有名人には目がない性格で、言ってみれば一種の『芸能ゴロ』みたいなタイプ」なのだという。
このバーにしろ乱交パーティーにしろ、矢島氏とタレントたちを結び付けたのはTBSの宣伝部や編成局の幹部たちのようだ。「TBSに深く食い込み、編成部が主催するゴルフコンペはすべて矢島氏が仕切っている」との証言を伝えている。
この記事を受けて、写真週刊誌『フォーカス』も同年7月21日号で「乱交パーティー『女衒(ぜげん)芸能プロ社長』の正体」と報じた。事情通によれば、「芸能プロ社長の名刺で女の子をナンパ。タレントにしてあげるとか、芸能人に会わせてあげるなどと言って、パーティーに誘っていた」のだという。
同誌は矢島氏の故郷は長野県箕輪(みのわ)町であるとし、地元の人の話として「実家が会社を経営していた資産家の一人息子。地元の高校を中退して、その後も定職につかず、親の金で飲み歩いたり女を引っかけたり。慣れない事業に手を出して失敗、親を破産させてしまった。バカなボンボンというので?バカボン?と呼ばれていました」と伝えている。
◇ ◇
この生い立ちの記はどこまで本当なのか。長野県南部の伊那谷にある故郷を訪ねた。
彼は1961年1月、長野県箕輪町で矢島誠氏の長男として生まれた。この町には、電子部品メーカーとして世界トップクラスの技術を持つ興亜工業という会社がある(後にKOAと社名変更)。創業者は向山(むかいやま)一人氏で、衆院議員や参院議員も務めた。
父親が経営していた矢島電機は興亜の系列会社だった。日本の製造業が世界を席巻していた1980年代には父親の会社も躍進し、町内に豪邸を建てている。「資産家のボンボン」であったことは間違いない。
小中学校時代を知る人は「余裕のある性格で失敗を恐れない。人に頼られるタイプ。器が大きいと感じた。野心は持っていたように思う」と語った。
箕輪中学の卒業文集(1975年度)に寄せた文章(写真)が興味深い。タイトルは「中学卒業バンザイ 後三年で?」。中学校生活の思い出は乏しく、高校生活への期待もあまり感じられない。行数を費やしているのは高校を卒業した後に乗りたい車、とくにポルシェなど外車へのあこがれである。
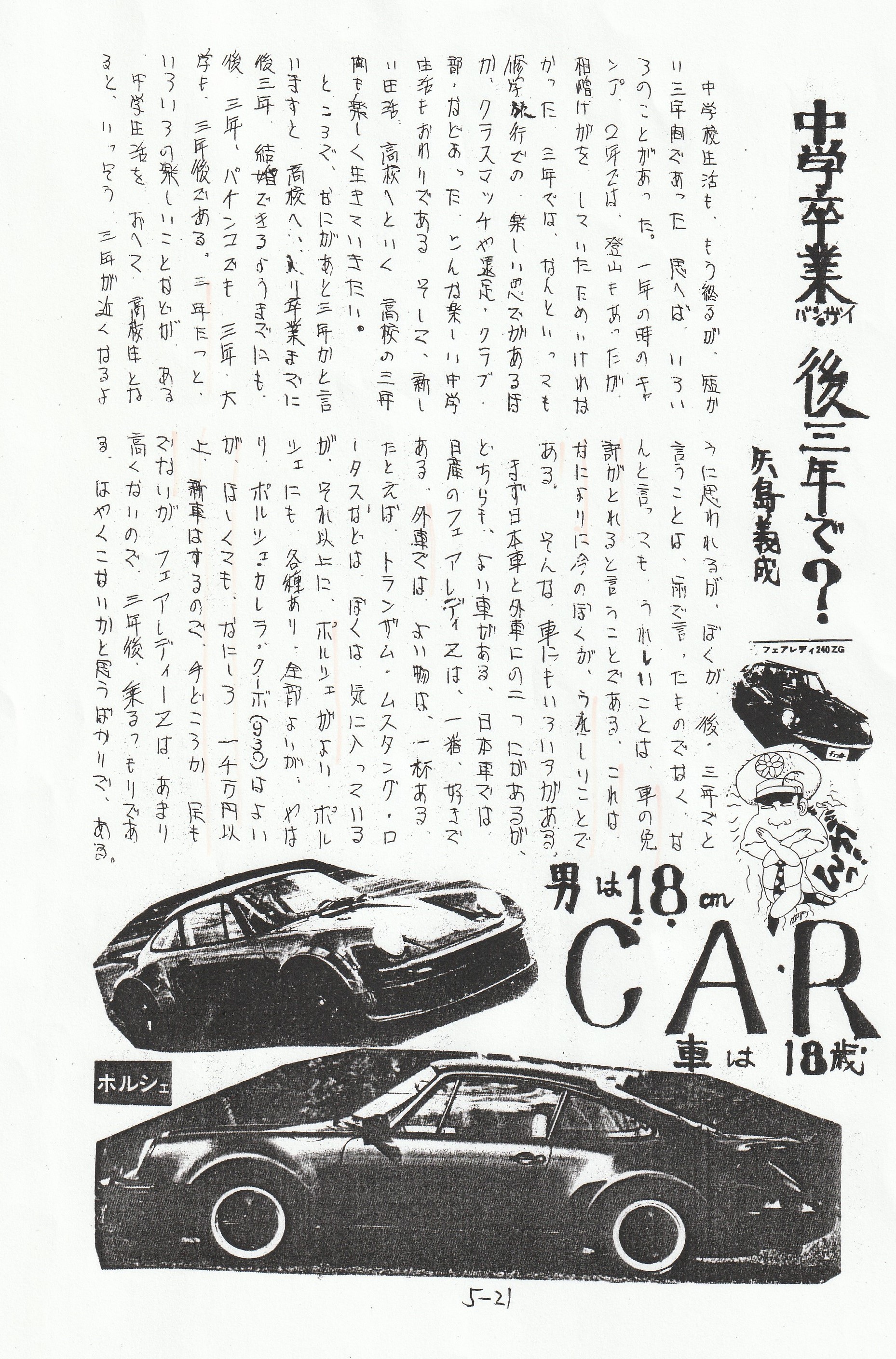
中学で長く国語の教師を務めた人にこの文章を読んでもらった。この文章から何がうかがえるのか。
「漢字の使い方はちゃんとしている。ただ、部活で活躍したとか達成感を得られた経験がなく、なんとなく過ぎていった中学生活だったのではないか。学校で知識を身につけて社会に出たいと思うタイプではない。さっさと高校を卒業して、楽しいことをしたいと考えていたのではないか」
同級生の記憶によれば、中学卒業後、バレーボールやラグビーの強豪校として知られる岡谷工業高校に入学したものの、中退したようだ。このためか、岡谷工業の同窓会名簿には見当たらない。入学者名簿は保存期間が過ぎたため廃棄されてないという。進学先は確認できなかった。
中退後、矢島氏はゴルフに打ち込んだ。愛好者を集めてコンペを主宰している。シングルプレーヤーで、プロを目指していた節もある。父親に資金を出してもらって、地元にスポーツ用品店を開いたりした。
だが、事業は失敗し、このころ父親の会社の経営も傾き始める。借金も重なり、矢島氏は逃げるように故郷を後にした。神宮前でくだんのバーを開いたのは1989年前後、20代の後半だった。父親の会社は倒産し、1998年に清算された。
会社の土地も豪邸も人手に渡ってしまったが、父親の名義ではなかったからか、生家だけは残った。現在は矢島氏と最初の妻との間にできた娘の名義になっている。父親は10年前に死去したものの、生家には今も「矢島誠」の表札が掲げられている。苦労をかけた父親への償い、なのかもしれない。
東京でバーを経営し、その時の人脈で芸能界とテレビ業界に足場を築いたことは『噂の眞相』や『フォーカス』の記事からうかがえる。だが、「乱交パーティー騒動」の後、矢島氏がどうしていたのかはよく分からない。
中曽根内閣で労働大臣を務めた山口敏夫氏によると、彼はこのころ「銀座でプータローのような生活をしていた」という。彼と知り合ったのも銀座のクラブだ。「だれか貢いでくれる女でもいたのかもしれないね。派手に遊んでいたから」。
その銀座で矢島氏に転機が訪れる。浜松出身の民主党衆院議員、鈴木康友氏と知り合ったのだ。「鈴木氏は落選中だった」というから、郵政民営化をテーマに小泉政権が仕掛けた2005年総選挙以降のことと思われる。
鈴木氏は松下政経塾の1期生で、同期に野田佳彦衆院議員がいた。矢島氏は鈴木―野田のラインをたどって、民主党内に人脈を広げていった。2007年には鈴木氏と矢島氏のイニシャルを冠した政策シンクタンク「S&Y総研」を立ち上げた(後に「大樹総研」と改称)。
鈴木氏はこの年に国政から身を引き、浜松市長に転じたが、矢島氏が政界に人脈を広げるきっかけを作ったという意味で、「政商・矢島義也」の生みの親と言っていい。
◇ ◇
銀座という「地の利」、民主党人脈という「人の和」を得た矢島氏に「天の時」が訪れたのは、2009年である。
時の麻生太郎首相の不人気、自民党の内紛、リーマンショック後の不況といった要素が重なり、この年の総選挙で民主党が圧勝したのだ。鳩山由紀夫政権が誕生し、野田氏は財務副大臣に就任した。
1955年の結党以来、自民党は初めて第2党に転落し、霞が関の官僚たちはうろたえた。大臣になったのはよく知らない政治家ばかり。ツテを求めて、官僚たちの「矢島詣で」が始まる。国会対策を担当していた財務省の福田淳一氏、法務省の黒川弘務氏らとのつながりができたのはこの時である(後に福田氏は事務次官に上り詰めたが、セクハラで失脚。黒川氏は賭け麻雀で検事総長になり損ねた)。
矢島氏は民主党政権時代、野党自民党の国会対策副委員長として苦労していた菅義偉氏に手を差し伸べている。グループの議員が軒並み落選し、派閥解消に追い込まれた二階俊博氏も支援した。このへんが矢島氏の懐の深いところだ。人間、苦しい時に助けてくれた人への恩は忘れない。
自民党が政権を奪回すると、矢島氏は菅―二階のラインで自民党にも人脈を広げ、与野党の双方に太いパイプを持つに至った。官僚や経済人が以前にも増して群がったのは言うまでもない。
矢島氏の人脈のすごさを見せつけたのが、2016年5月に帝国ホテル「富士の間」で開いた「結婚を祝う会」である。銀座で知り合った女性との再婚を祝う会なのだが、主賓は菅義偉・官房長官(当時)、乾杯の音頭は二階俊博・自民党総務会長(同)という豪華版だ。
民進党(旧民主党)からも野田佳彦氏、玄葉光一郎氏、細野豪志氏らが出席、財務省の福田氏ら有力省庁の幹部も漏れなく参じた。菅氏と親しいSBIホールディングスの北尾吉孝社長、サイバーセキュリティ分野で国内第一人者とされる安田浩・東大名誉教授、徳川宗家19代当主の徳川家広氏、インドネシアのゴベル通商大臣ら実に多彩な顔ぶれである。
こういう席にはあまり顔を出さない安倍晋三首相(同)もビデオメッセージを寄せ、それが披露されると、300人余りの出席者の間にざわめきが広がったという。
その人脈を矢島氏はどのように活用しているのか。その内実を、月刊誌『選択』が2018年8月号で詳細に暴いている。
大樹総研の傘下に再生可能エネルギー事業を手がける「JCサービス」という会社がある。この会社が鹿児島県徳之島町で太陽光発電の蓄電池増設事業を計画し、2013年に環境省から補助金を受けた。
ところが、蓄電池は一度も稼働せず、一部は現場に放置されていた。事業のずさんさを知った環境省は、補助金2億9600万円の返還と加算金1億3600万円の支払いを命じた。
問題は、このJCサービスの子会社から細野豪志氏に5000万円の資金が流れていたことだ。この補助事業が検討されていた2012年当時、細野氏は野田政権の環境大臣であり、「便宜供与への謝礼(賄賂)」ではないか、との疑惑が浮上した。
細野氏は「個人的に借りた」と釈明し、贈収賄事件として立件されることはなかったが、細野氏と会社との仲介をしたのは大樹総研グループと見られる。
『選択』は、ソーシャルレンディングをめぐる闇も追及している。ネット上で資金を募り、ネット上で融資の仲介をするベンチャービジネスの一つだが、再生可能エネルギーへの投資を名目に巨額の資金を集めながら、それとは別のことに流用するといったトラブルが頻発している。この分野でも大樹総研傘下の企業群がうごめいているという。
記事で引用している大樹コンサルティングの海老根靖典社長の言葉が興味深い。海老根氏によれば、大樹総研グループは「すべての政党と深く関わりがあり、中央官庁との色々なネットワークも持っていますので、政治的な働きかけができることが大きな強み」なのだという。
彼らはその「強み」をどのように使っているのか。政治家や官僚、企業経営者たちは大樹総研グループとどう関わっているのか。一つひとつ、それを解き明かしていく作業を続けなければなるまい。
*メールマガジン「風切通信 94」 2021年9月28日
*初出:調査報道サイト「HUNTER」
≪写真説明≫
長野県箕輪町にある矢島義也氏の生家
≪参考資料≫
◎矢島義也氏の関係年表
◎父親の会社「矢島電機」が清算されたことを示す法人登記
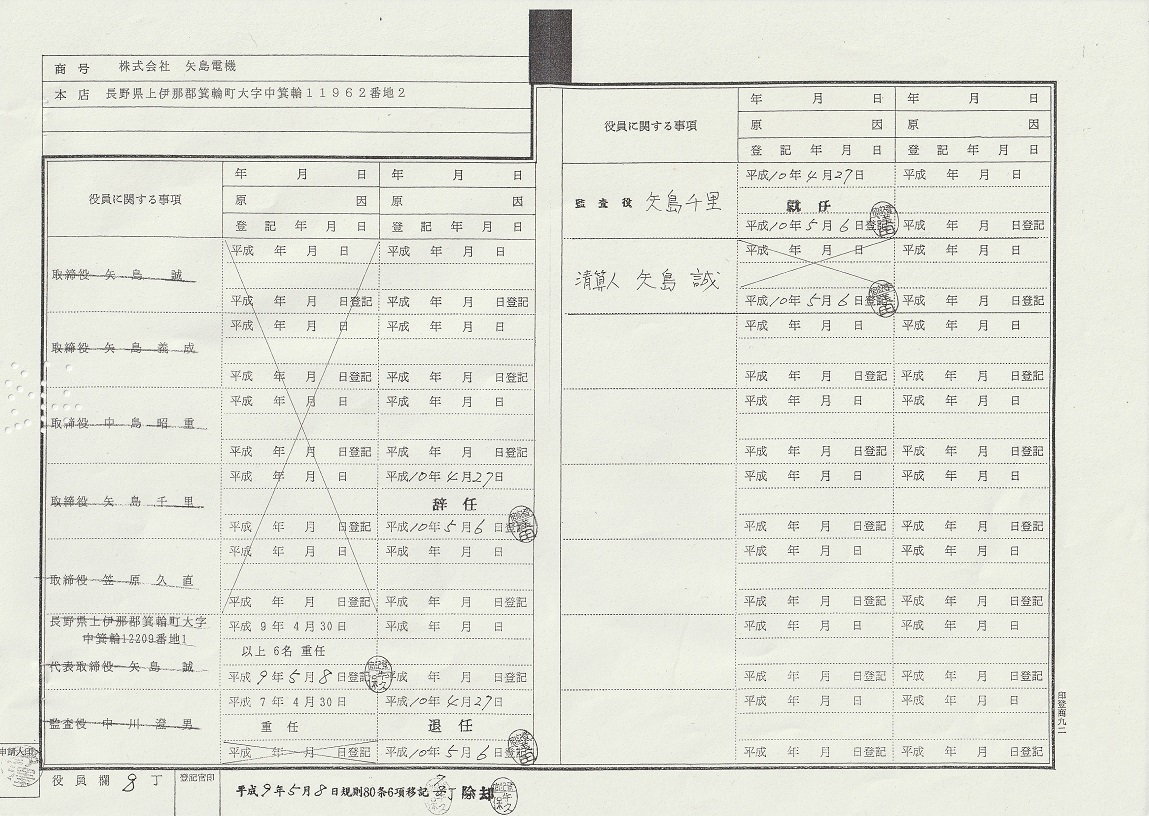
余命いくばくもなく、訪ねることができるところはあと一つだけ。そう告げられたら、あなたはどこを選ぶだろうか。
私は迷うことなく、「アフガニスタン」と答える。32年前、国際部門に配属されて最初に取材した国であり、その後も新聞記者として心血を注ぎ続けた土地だからだ。

戦争とは何か。その中で生きるとはどういうことか。アフガンの人々と接する中でそれを教えられ、考えさせられた。厳しい取材だったが、日本にいたのでは経験も想像もできないことが多かった。新聞記者として生きてゆく覚悟のようなものを植え付けられた土地だった。
この夏、そのアフガニスタンが再び国際報道の焦点になった。
2001年9月の同時多発テロの後、アメリカはこの国に攻め込んだ。当時、この国を支配していたイスラム勢力のタリバンが、テロの首謀者であるオサマ・ビンラディンらをかくまっていたからだ。
米国は圧倒的な軍事力でタリバン政権を崩壊させ、親米的な政権をつくり、この国を「自由で民主的な国」にしようと試みてきた。だが、20年にわたって戦い、支援してきたにもかかわらず、彼らが望むような国をつくることはできず、撤退に追い込まれた。
全土をほぼ支配下に収め、実権を握ったのは、米軍が一度はたたき潰したはずのタリバンである。
首都カブールの北郊にある空港は逃げ出す外国人であふれ返った。通訳や諜報員として米軍に協力したアフガン人とその家族も、報復を恐れて空港に押し寄せた。離陸する輸送機の機体にしがみつく人々を捉(とら)えた映像は、彼らの恐怖心がどれほどのものかを示している。
なにせタリバンは、アフガン各派の中で最も厳格にイスラム法を適用すると標榜している勢力である。かつて権力を掌握した際には、反対勢力を容赦なく処刑した。
女性には全身をすっぽり覆うブルカの着用を強制し、女子教育も認めなかった。「盗みを働いた者は手を切り落とす」「姦通は石打ちの刑」といった古来の刑罰を復活させ、実行した。バーミヤンの大仏を「偶像崇拝の象徴」として爆破したのもタリバンだ。
「あの恐怖の日々がまたやって来る」。普通の住民がおびえるのは無理もない。
だが、アフガニスタンの政治と社会をずっと追ってきた人間から見ると、「タリバンはかなり変わった」と映る。かつての統治の行き過ぎを認め、より現実的な方向に舵を切ろうとしているのではないか。
米軍撤退の前に米政府と交渉し、「撤退が完了するまではカブール国際空港の管理を米軍にゆだねる」と合意したのは、路線変更の証しと言っていい。かつてのタリバンなら、勢いにまかせて空港も制圧し、殺戮(さつりく)の限りを尽くしたことだろう。
権力掌握後の8月17日に開いた記者会見で、タリバンの報道官は「女性の権利を尊重する。女性は働き、学ぶことができる」「自由で独立した報道を認める」と語った。どちらも「イスラム法が認める範囲内で」という条件付きではあるが、大きな路線転換であることは間違いない。
報道官は、反対勢力の政治家や兵士に「恩赦を与える」と述べ、「外国に脅威を与えることは望まない」と表明した。「アフガンはまた『テロの温床』になってしまうのではないか」との懸念を払拭しようとしたのだろう。
こうしたタリバン側の表明を「国際社会からの批判をかわすための演技」と報じたメディアもある。確かに、額面通りに受けとめるわけにはいかない。タリバンの兵士たちがこうした約束をどれだけ守るかも定かではない。
だが、この国が歩んできた険しい道のりを思えば、「演技」と断じてしまうのは酷だろう。一線の兵士はともかく、少なくともタリバンの指導部は過去の失敗から学び、「現実的な路線を選択しなければ、安定した統治はできない」と悟ったのではないか。
◇ ◇
私が初めてアフガニスタンを訪れたのは1989年の4月である。インドのニューデリーから空路、首都のカブールに向かった。パキスタンの領土を横切り、空からこの国の風景を初めて見た時の衝撃は、今でも忘れられない。黒褐色の岩山が延々と続いていた。
国境の峰々を越えても、その色は変わらない。砂漠ではなく、岩と土漠(どばく)の世界が広がっていた。緑はほとんどない。雪融け水が流れる川に沿って草木がわずかに茂り、村々がへばり付くように点在していた。
緑に包まれた日本の風景の「ネガフィルム」を見ているような感覚。こんな厳しい土地で人々はどうやって生きてきたのか。なぜ、争いがやまないのか。褐色の大地を食い入るように見つめ続けた。
当時、この国を支配していたのは共産主義政権だった。ソ連はその政権を支えるため軍事介入したが、10年にわたって反政府イスラム武装勢力の激しい抵抗を受け、おびただしい数の犠牲者を出して2カ月前に完全撤退していた。
ソ連軍の撤退前にアメリカや日本の外交官は脱出し、国連の職員も去っていた。長い戦乱ですでにパキスタンとイランに500万人の難民が流出していたが、撤退を機に新たな難民も生まれた。この時の混乱状態は今回の米軍撤退時と重なるものがある。
政府側が支配しているのは首都カブールをはじめとする主要都市だけ。農村部は反政府勢力がおさえ、都市を包囲していた。カブールにも連日のようにロケット弾が撃ち込まれていた。
中心部のホテルは破壊され、報道陣が宿泊できるのは丘の上にあるホテルのみ。ここに世界中からやって来た多くの記者やカメラマンが陣取っていた。
国際電話はほとんど通じない。衛星電話は登場したばかりで、大型のスーツケースほどもあった。高価なうえ記者一人ではとても持ち込めない。商用のテレックス回線を使い、ローマ字で日本語の原稿を送るしかなかった。
戦況を正確に把握するためには、反政府勢力側からも取材しなければならない。何回目かの出張の際、パキスタンの国境地帯からゲリラ部隊に同行して彼らの動きも取材した。
それができたのは、当時のアフガンでは「パシュトゥンの掟」と呼ばれる慣習が強く残っていたからである。その掟は部族によって微妙に異なるが、「尚武(トゥーラ)」「客人歓待(メルマスティア)」「復讐(バダル)」の三つはどこでも固く守られていた。
自立心が強く、家族と財産を守るために命をかけて戦う。一方で、見知らぬ者でも頼ってくれば、できる限りのもてなしをする。客人として記者を受け入れた部隊は、記者を守るためにあらゆる手段を尽くしてくれた。
目にした農村の風景は強烈だった。どの家も高い土壁に囲まれ、一軒一軒が砦(とりで)のような造りになっている。どの家にも男手の数だけ自動小銃があった。男の子は物心がついたころから、銃を分解して組み立てることを仕込まれるのだという。
アメリカは「銃社会」と言われるが、それをはるかに上回る「重武装の社会」である。そして、それはこの国の地勢を考えれば、当然のことだった。
周りの国はすべて陸続きだ。いつ、どこから、武装した人間たちがなだれ込んでくるか分からない。実際、騎乗したモンゴル兵に蹂躙(じゅうりん)され、ペルシャの軍勢に攻め込まれるといった歴史をくぐり抜けてきた。自分の身は自分で守るしかない社会なのだ。
日本は海に囲まれ、外敵に突然攻め込まれる、といった心配をする必要がない。有史以来、外国の大軍に攻撃されたのは、元寇とマッカーサー率いる米軍の2回だけである。
世界でもまれなほど「安全な国」だ。軍事的な観点から見ても、日本とアフガンは「写真のネガとポジ」のような関係にある。日本人の感覚でこの国の政治や社会を考えようとしても、とても捉えきれるものではない。
◇ ◇
ソ連軍撤退の3年後、1992年に共産主義政権は崩壊し、イスラム政権が樹立された。だが、待っていたのはイスラム諸勢力による凄惨な内戦だった。
アフガニスタンの国境が現在のような形になったのは19世紀末のことである。
インドを植民地支配していた大英帝国はその版図を西に広げようとした。一方、北からはロシア帝国が南下を図って攻め込んだ。せめぎ合う二つの帝国は、直接衝突することを避けるため、アフガニスタンを「緩衝地帯」として残すことで合意した。そうして引かれたのが今の国境線である。
その結果、この地域で暮らしていた主要な民族は真っ二つに分断された。ヒンドゥークシ山脈の南麓にいたパシュトゥン人はアフガンと英領インド(現パキスタン)に二分され、山脈の北側にいたタジク人とウズベク人も、半分はロシア領に組み込まれた(図参照)。
アフガンの苦悩は、この国境画定を抜きにして語ることはできない。人口の過半数を占める民族はない。おまけに、どの民族も多くの部族に分かれ、それぞれの利害がぶつかり合う。
一口に反政府イスラム勢力と言っても、私が取材していた頃ですら、15もの組織に分かれていた。共産主義政権という「共通の敵」がいなくなった途端、そうした勢力が入り乱れて戦い始めたのだ。
90年代の半ば、国土が荒れ果て、世界が関心を失う中で台頭したのがタリバンだった。パシュトゥー語で「(神学校の)生徒」を意味する。厳格なイスラム支配を唱える宗教指導者が神学校の生徒たちを糾合して組織した、と喧伝されたが、それは表向きの顔に過ぎない。
戦車をはじめとする武器と弾薬を供給したのはパキスタンの軍部であり、資金的に支えたのは湾岸諸国のイスラム主義勢力だった。パキスタンは隣国を意のままに操ることを目指し、湾岸の同調勢力は「理想のイスラム国家」の建設を夢見た。
だが、尚武の気質を持つ民は「武器と金」をもらっても、意のままにはならなかった。支援する者たちの思惑を超えて、信じられないほど厳格なイスラム支配に乗り出し、米国を「悪の帝国」とみなすアルカイダなど過激な勢力と手を組んだ。
共産主義から厳格なイスラム支配へ。大国と周辺国の思惑に突き動かされ、アフガンは振り子の重しが外れてしまうほど激しく揺れた。そして、9・11テロへと至ったのだった。
アメリカの政治家と軍人たちは「我々には『テロの撲滅』という大義がある。今度こそ、この国を自由で開かれた国にする」と決意していたのではないか。日本や欧州諸国もそれに従って巨額の援助を注ぎ込んだ。
そうした介入と援助は水泡に帰した。なぜか。
米欧の指導者たちは、アフガン人の「気概と気風」を軽く見ていたのではないか。彼らはよそ者から押し付けられることを何よりも嫌う。自分たちの社会のことは自分たちで決めたいのだ。彼らには彼らの掟と慣習がある。それはイスラムが伝来するはるか以前から育んできたもので、イスラムの教えと溶け合って社会に深く根を下ろしている。変える必要があるとしても、根付いたものに反しないよう変え方も自分たちで決めたいのだ。
「パシュトゥンの掟」の一つに、紛争はジルガ(部族評議会)で決着を付ける、というのがある。部族の代表者が一堂に会し、納得がいくまで話し合って決めるやり方だ。それは自由選挙を基にした代議制民主主義とはまるで異なるものだが、長い歴史の中で培われ、機能してきた制度である。民主主義を採り入れるにしても、こうしたジルガの伝統との折り合いを付けた制度にしない限り、この国でうまく機能することはないだろう。
米欧の指導者たちは、アフガン人の「苦悩と誇り」にも思いが至らなかった。
アメリカのメディアは、今回の米軍の撤退を1975年の南ベトナムからの撤退になぞらえて報道した。多くの血を流しながら戦争の目的を達することができず、みじめな形で出ていった、という点では確かに似ている。
けれども、アフガンの人たちが思い浮かべたのはベトナムではないだろう。もっと長い時間軸、この100年余りの歴史を振り返っているのではないか。
19世紀から20世紀初頭にかけて、世界で最も強大だったのは大英帝国である。前述のように、大英帝国はインドの植民地を西に広げようとして、何度かアフガンに攻め込んだ。首都のカブールを占領したこともある。だが、繰り返される反乱に手を焼き、撤退した。
そして、20世紀の後半には超大国ソ連の軍隊を追い出し、今回は唯一の超大国アメリカの軍隊を追い払った。「帝国の軍隊」に3回も苦杯をなめさせたのである。
もちろん、そのたびにおびただしい犠牲を払い、語り尽くせぬほどの苦悩を味わった。だが、それも彼らの価値観に照らせば、避けられなかった犠牲であり、決して屈しなかったことを誇りとして胸に抱くことになるのだろう。
◇ ◇
現場の記者として、私がアフガニスタンを担当したのは1989年から95年までの6年間である。その後、東京でアジア担当のデスクとしてこの国の動きをフォーローし、社説を担当する論説委員になってからも足を運び続けた。
戦乱の国の取材なので、政治指導者や軍人に会うことが多かったが、可能な限り農村の様子を見て回った。戦火がどんなに激しくなっても、国土がいかに荒廃しようとも、農村には乾いた大地を耕し、乏しい水を分け合う姿があった。
食べ物を確保し、生き延びる。それだけでも大変な状況なのに、どの村でも人々は子どもたちに教育を授けるためにあらゆる努力を重ねていた。未来はそこからしか開けないことを知っていた。「この国には希望がある」。そう感じさせるものがあった。
忘れられない言葉を聞いたのも、この国の人たちからだった。
難民キャンプでみけんに深い皺を刻んだ老人に会った。戦闘に巻き込まれて孫を亡くしたばかりという。「私のような年寄りが生き残り、幼い孫が死んでいく。耐え難い」。そう嘆き、「いのちは幸運の結晶なのです」とつぶやいた。
いぶかる私の目を見ながら、老人はさとすように語った。
「君のいのちはお父さんとお母さんが出会って生まれた。どちらかが病気やけがで倒れていたら、君はこの世にいなかった。お父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんが出会って生まれた。だれかが病気やけがで倒れていたら、二人はこの世にいなかった」
「たくさんの、数えきれないほどたくさんのいのちが幸運にも生き永らえて、君にいのちをつないできた。だから、いのちは一つひとつ『幸運の結晶』なのです」
命がいともたやすく失われていく国で聞く命の意味。いや、いともたやすく失われていくからこそ紡ぎ出された言葉だったのかもしれない。その後、記者として出会い、耳にしたどんな言葉よりも深く心に沈み、忘れられない言葉となった。
アフガニスタンを「失敗国家」と呼ぶ人がいる。「破綻国家」と言う人もいる。けれども、そこに生きる人たちは「失敗人間」でも「破綻した人間」でもない。だれもが「幸運の結晶」としての生を生きている。
再び権力の座に就いたタリバンはこの国をどこへ導くのか。それを見通すうえで大切なのは、自らの価値観だけでなく、彼らの価値観、さらに第三の価値観も携えてこの国に光を当ててみることだ。
それはアフガニスタン問題に限らない。一つの尺度で物事を見る。そんな時代はとうに過ぎ去った。未来は混沌としており、複眼でも見通せない。より良く生きるために、立体的な座標軸が求められる時代なのである。
(長岡 昇)
2021年8月28日
≪写真説明&Source≫
タリバンの兵士たち(AFP、2020年3月2日撮影。BBCのサイトから)
https://www.bbc.com/japanese/51716332
≪参考文献≫
◎『アフガニスタン史』(前田耕作、山根聡)河出書房新社
◎『タリバン』(アハメド・ラシッド)講談社
◎『Afghanistan』(Louis Dupree)Princeton University Press
◎『The Great Game』(Peter Hopkirk) Butler & Tanner Ltd
私は迷うことなく、「アフガニスタン」と答える。32年前、国際部門に配属されて最初に取材した国であり、その後も新聞記者として心血を注ぎ続けた土地だからだ。

戦争とは何か。その中で生きるとはどういうことか。アフガンの人々と接する中でそれを教えられ、考えさせられた。厳しい取材だったが、日本にいたのでは経験も想像もできないことが多かった。新聞記者として生きてゆく覚悟のようなものを植え付けられた土地だった。
この夏、そのアフガニスタンが再び国際報道の焦点になった。
2001年9月の同時多発テロの後、アメリカはこの国に攻め込んだ。当時、この国を支配していたイスラム勢力のタリバンが、テロの首謀者であるオサマ・ビンラディンらをかくまっていたからだ。
米国は圧倒的な軍事力でタリバン政権を崩壊させ、親米的な政権をつくり、この国を「自由で民主的な国」にしようと試みてきた。だが、20年にわたって戦い、支援してきたにもかかわらず、彼らが望むような国をつくることはできず、撤退に追い込まれた。
全土をほぼ支配下に収め、実権を握ったのは、米軍が一度はたたき潰したはずのタリバンである。
首都カブールの北郊にある空港は逃げ出す外国人であふれ返った。通訳や諜報員として米軍に協力したアフガン人とその家族も、報復を恐れて空港に押し寄せた。離陸する輸送機の機体にしがみつく人々を捉(とら)えた映像は、彼らの恐怖心がどれほどのものかを示している。
なにせタリバンは、アフガン各派の中で最も厳格にイスラム法を適用すると標榜している勢力である。かつて権力を掌握した際には、反対勢力を容赦なく処刑した。
女性には全身をすっぽり覆うブルカの着用を強制し、女子教育も認めなかった。「盗みを働いた者は手を切り落とす」「姦通は石打ちの刑」といった古来の刑罰を復活させ、実行した。バーミヤンの大仏を「偶像崇拝の象徴」として爆破したのもタリバンだ。
「あの恐怖の日々がまたやって来る」。普通の住民がおびえるのは無理もない。
だが、アフガニスタンの政治と社会をずっと追ってきた人間から見ると、「タリバンはかなり変わった」と映る。かつての統治の行き過ぎを認め、より現実的な方向に舵を切ろうとしているのではないか。
米軍撤退の前に米政府と交渉し、「撤退が完了するまではカブール国際空港の管理を米軍にゆだねる」と合意したのは、路線変更の証しと言っていい。かつてのタリバンなら、勢いにまかせて空港も制圧し、殺戮(さつりく)の限りを尽くしたことだろう。
権力掌握後の8月17日に開いた記者会見で、タリバンの報道官は「女性の権利を尊重する。女性は働き、学ぶことができる」「自由で独立した報道を認める」と語った。どちらも「イスラム法が認める範囲内で」という条件付きではあるが、大きな路線転換であることは間違いない。
報道官は、反対勢力の政治家や兵士に「恩赦を与える」と述べ、「外国に脅威を与えることは望まない」と表明した。「アフガンはまた『テロの温床』になってしまうのではないか」との懸念を払拭しようとしたのだろう。
こうしたタリバン側の表明を「国際社会からの批判をかわすための演技」と報じたメディアもある。確かに、額面通りに受けとめるわけにはいかない。タリバンの兵士たちがこうした約束をどれだけ守るかも定かではない。
だが、この国が歩んできた険しい道のりを思えば、「演技」と断じてしまうのは酷だろう。一線の兵士はともかく、少なくともタリバンの指導部は過去の失敗から学び、「現実的な路線を選択しなければ、安定した統治はできない」と悟ったのではないか。
◇ ◇
私が初めてアフガニスタンを訪れたのは1989年の4月である。インドのニューデリーから空路、首都のカブールに向かった。パキスタンの領土を横切り、空からこの国の風景を初めて見た時の衝撃は、今でも忘れられない。黒褐色の岩山が延々と続いていた。
国境の峰々を越えても、その色は変わらない。砂漠ではなく、岩と土漠(どばく)の世界が広がっていた。緑はほとんどない。雪融け水が流れる川に沿って草木がわずかに茂り、村々がへばり付くように点在していた。
緑に包まれた日本の風景の「ネガフィルム」を見ているような感覚。こんな厳しい土地で人々はどうやって生きてきたのか。なぜ、争いがやまないのか。褐色の大地を食い入るように見つめ続けた。
当時、この国を支配していたのは共産主義政権だった。ソ連はその政権を支えるため軍事介入したが、10年にわたって反政府イスラム武装勢力の激しい抵抗を受け、おびただしい数の犠牲者を出して2カ月前に完全撤退していた。
ソ連軍の撤退前にアメリカや日本の外交官は脱出し、国連の職員も去っていた。長い戦乱ですでにパキスタンとイランに500万人の難民が流出していたが、撤退を機に新たな難民も生まれた。この時の混乱状態は今回の米軍撤退時と重なるものがある。
政府側が支配しているのは首都カブールをはじめとする主要都市だけ。農村部は反政府勢力がおさえ、都市を包囲していた。カブールにも連日のようにロケット弾が撃ち込まれていた。
中心部のホテルは破壊され、報道陣が宿泊できるのは丘の上にあるホテルのみ。ここに世界中からやって来た多くの記者やカメラマンが陣取っていた。
国際電話はほとんど通じない。衛星電話は登場したばかりで、大型のスーツケースほどもあった。高価なうえ記者一人ではとても持ち込めない。商用のテレックス回線を使い、ローマ字で日本語の原稿を送るしかなかった。
戦況を正確に把握するためには、反政府勢力側からも取材しなければならない。何回目かの出張の際、パキスタンの国境地帯からゲリラ部隊に同行して彼らの動きも取材した。
それができたのは、当時のアフガンでは「パシュトゥンの掟」と呼ばれる慣習が強く残っていたからである。その掟は部族によって微妙に異なるが、「尚武(トゥーラ)」「客人歓待(メルマスティア)」「復讐(バダル)」の三つはどこでも固く守られていた。
自立心が強く、家族と財産を守るために命をかけて戦う。一方で、見知らぬ者でも頼ってくれば、できる限りのもてなしをする。客人として記者を受け入れた部隊は、記者を守るためにあらゆる手段を尽くしてくれた。
目にした農村の風景は強烈だった。どの家も高い土壁に囲まれ、一軒一軒が砦(とりで)のような造りになっている。どの家にも男手の数だけ自動小銃があった。男の子は物心がついたころから、銃を分解して組み立てることを仕込まれるのだという。
アメリカは「銃社会」と言われるが、それをはるかに上回る「重武装の社会」である。そして、それはこの国の地勢を考えれば、当然のことだった。
周りの国はすべて陸続きだ。いつ、どこから、武装した人間たちがなだれ込んでくるか分からない。実際、騎乗したモンゴル兵に蹂躙(じゅうりん)され、ペルシャの軍勢に攻め込まれるといった歴史をくぐり抜けてきた。自分の身は自分で守るしかない社会なのだ。
日本は海に囲まれ、外敵に突然攻め込まれる、といった心配をする必要がない。有史以来、外国の大軍に攻撃されたのは、元寇とマッカーサー率いる米軍の2回だけである。
世界でもまれなほど「安全な国」だ。軍事的な観点から見ても、日本とアフガンは「写真のネガとポジ」のような関係にある。日本人の感覚でこの国の政治や社会を考えようとしても、とても捉えきれるものではない。
◇ ◇
ソ連軍撤退の3年後、1992年に共産主義政権は崩壊し、イスラム政権が樹立された。だが、待っていたのはイスラム諸勢力による凄惨な内戦だった。
アフガニスタンの国境が現在のような形になったのは19世紀末のことである。
インドを植民地支配していた大英帝国はその版図を西に広げようとした。一方、北からはロシア帝国が南下を図って攻め込んだ。せめぎ合う二つの帝国は、直接衝突することを避けるため、アフガニスタンを「緩衝地帯」として残すことで合意した。そうして引かれたのが今の国境線である。
その結果、この地域で暮らしていた主要な民族は真っ二つに分断された。ヒンドゥークシ山脈の南麓にいたパシュトゥン人はアフガンと英領インド(現パキスタン)に二分され、山脈の北側にいたタジク人とウズベク人も、半分はロシア領に組み込まれた(図参照)。
アフガンの苦悩は、この国境画定を抜きにして語ることはできない。人口の過半数を占める民族はない。おまけに、どの民族も多くの部族に分かれ、それぞれの利害がぶつかり合う。
一口に反政府イスラム勢力と言っても、私が取材していた頃ですら、15もの組織に分かれていた。共産主義政権という「共通の敵」がいなくなった途端、そうした勢力が入り乱れて戦い始めたのだ。
90年代の半ば、国土が荒れ果て、世界が関心を失う中で台頭したのがタリバンだった。パシュトゥー語で「(神学校の)生徒」を意味する。厳格なイスラム支配を唱える宗教指導者が神学校の生徒たちを糾合して組織した、と喧伝されたが、それは表向きの顔に過ぎない。
戦車をはじめとする武器と弾薬を供給したのはパキスタンの軍部であり、資金的に支えたのは湾岸諸国のイスラム主義勢力だった。パキスタンは隣国を意のままに操ることを目指し、湾岸の同調勢力は「理想のイスラム国家」の建設を夢見た。
だが、尚武の気質を持つ民は「武器と金」をもらっても、意のままにはならなかった。支援する者たちの思惑を超えて、信じられないほど厳格なイスラム支配に乗り出し、米国を「悪の帝国」とみなすアルカイダなど過激な勢力と手を組んだ。
共産主義から厳格なイスラム支配へ。大国と周辺国の思惑に突き動かされ、アフガンは振り子の重しが外れてしまうほど激しく揺れた。そして、9・11テロへと至ったのだった。
アメリカの政治家と軍人たちは「我々には『テロの撲滅』という大義がある。今度こそ、この国を自由で開かれた国にする」と決意していたのではないか。日本や欧州諸国もそれに従って巨額の援助を注ぎ込んだ。
そうした介入と援助は水泡に帰した。なぜか。
米欧の指導者たちは、アフガン人の「気概と気風」を軽く見ていたのではないか。彼らはよそ者から押し付けられることを何よりも嫌う。自分たちの社会のことは自分たちで決めたいのだ。彼らには彼らの掟と慣習がある。それはイスラムが伝来するはるか以前から育んできたもので、イスラムの教えと溶け合って社会に深く根を下ろしている。変える必要があるとしても、根付いたものに反しないよう変え方も自分たちで決めたいのだ。
「パシュトゥンの掟」の一つに、紛争はジルガ(部族評議会)で決着を付ける、というのがある。部族の代表者が一堂に会し、納得がいくまで話し合って決めるやり方だ。それは自由選挙を基にした代議制民主主義とはまるで異なるものだが、長い歴史の中で培われ、機能してきた制度である。民主主義を採り入れるにしても、こうしたジルガの伝統との折り合いを付けた制度にしない限り、この国でうまく機能することはないだろう。
米欧の指導者たちは、アフガン人の「苦悩と誇り」にも思いが至らなかった。
アメリカのメディアは、今回の米軍の撤退を1975年の南ベトナムからの撤退になぞらえて報道した。多くの血を流しながら戦争の目的を達することができず、みじめな形で出ていった、という点では確かに似ている。
けれども、アフガンの人たちが思い浮かべたのはベトナムではないだろう。もっと長い時間軸、この100年余りの歴史を振り返っているのではないか。
19世紀から20世紀初頭にかけて、世界で最も強大だったのは大英帝国である。前述のように、大英帝国はインドの植民地を西に広げようとして、何度かアフガンに攻め込んだ。首都のカブールを占領したこともある。だが、繰り返される反乱に手を焼き、撤退した。
そして、20世紀の後半には超大国ソ連の軍隊を追い出し、今回は唯一の超大国アメリカの軍隊を追い払った。「帝国の軍隊」に3回も苦杯をなめさせたのである。
もちろん、そのたびにおびただしい犠牲を払い、語り尽くせぬほどの苦悩を味わった。だが、それも彼らの価値観に照らせば、避けられなかった犠牲であり、決して屈しなかったことを誇りとして胸に抱くことになるのだろう。
◇ ◇
現場の記者として、私がアフガニスタンを担当したのは1989年から95年までの6年間である。その後、東京でアジア担当のデスクとしてこの国の動きをフォーローし、社説を担当する論説委員になってからも足を運び続けた。
戦乱の国の取材なので、政治指導者や軍人に会うことが多かったが、可能な限り農村の様子を見て回った。戦火がどんなに激しくなっても、国土がいかに荒廃しようとも、農村には乾いた大地を耕し、乏しい水を分け合う姿があった。
食べ物を確保し、生き延びる。それだけでも大変な状況なのに、どの村でも人々は子どもたちに教育を授けるためにあらゆる努力を重ねていた。未来はそこからしか開けないことを知っていた。「この国には希望がある」。そう感じさせるものがあった。
忘れられない言葉を聞いたのも、この国の人たちからだった。
難民キャンプでみけんに深い皺を刻んだ老人に会った。戦闘に巻き込まれて孫を亡くしたばかりという。「私のような年寄りが生き残り、幼い孫が死んでいく。耐え難い」。そう嘆き、「いのちは幸運の結晶なのです」とつぶやいた。
いぶかる私の目を見ながら、老人はさとすように語った。
「君のいのちはお父さんとお母さんが出会って生まれた。どちらかが病気やけがで倒れていたら、君はこの世にいなかった。お父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんが出会って生まれた。だれかが病気やけがで倒れていたら、二人はこの世にいなかった」
「たくさんの、数えきれないほどたくさんのいのちが幸運にも生き永らえて、君にいのちをつないできた。だから、いのちは一つひとつ『幸運の結晶』なのです」
命がいともたやすく失われていく国で聞く命の意味。いや、いともたやすく失われていくからこそ紡ぎ出された言葉だったのかもしれない。その後、記者として出会い、耳にしたどんな言葉よりも深く心に沈み、忘れられない言葉となった。
アフガニスタンを「失敗国家」と呼ぶ人がいる。「破綻国家」と言う人もいる。けれども、そこに生きる人たちは「失敗人間」でも「破綻した人間」でもない。だれもが「幸運の結晶」としての生を生きている。
再び権力の座に就いたタリバンはこの国をどこへ導くのか。それを見通すうえで大切なのは、自らの価値観だけでなく、彼らの価値観、さらに第三の価値観も携えてこの国に光を当ててみることだ。
それはアフガニスタン問題に限らない。一つの尺度で物事を見る。そんな時代はとうに過ぎ去った。未来は混沌としており、複眼でも見通せない。より良く生きるために、立体的な座標軸が求められる時代なのである。
(長岡 昇)
2021年8月28日
≪写真説明&Source≫
タリバンの兵士たち(AFP、2020年3月2日撮影。BBCのサイトから)
https://www.bbc.com/japanese/51716332
≪参考文献≫
◎『アフガニスタン史』(前田耕作、山根聡)河出書房新社
◎『タリバン』(アハメド・ラシッド)講談社
◎『Afghanistan』(Louis Dupree)Princeton University Press
◎『The Great Game』(Peter Hopkirk) Butler & Tanner Ltd
2012年の第1回カヌー探訪から足かけ10年。長井市から始まった最上川縦断のカヌー行は2021年夏、ついに酒田市の河口に到達しました。過去最多の49人が参加し、全員が13キロを漕破しました。最年少は高校2年の16歳、最ベテランは83歳。東京五輪が開かれ、新型コロナウイルスの感染が再び広がる中での開催になりました。イベントにご協力いただいた皆様に深く感謝いたします。


◎真鍋賢一さん撮影の動画(ドローンによる空撮を含む。44分)
≪出発&到着時刻≫
2021年7月31日(土)
午前10時 山形県庄内町の庄内橋の上流、左岸から出発
午前11時20分 酒田市新堀豊森の右岸に上陸、休憩・差し入れ
午後1時?1時40分 酒田市の出羽大橋の下流、右岸に到着


≪参加者&参加艇≫
49人、38艇
≪カヌーイスト=申込順≫
齋藤龍真(村山市)、佐藤博隆(酒田市)、和田 勤(栃木県那須塩原市)、和田基秀(同)、?橋 洋(米沢市)、牧野 格(南陽市)、阿部明美(天童市)、阿部俊裕(同)、佐藤 明(鶴岡市)、安部幸男(宮城県柴田町)、新美武司(尾花沢市)、池田丈人(酒田市)、林 和明(東京都足立区)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、柴田尚宏(山形市)、結城敏宏(米沢市)、小田原紫朗(酒田市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、石井秀明(さいたま市)、岸 浩(福島市)、七海 孝(福島県鏡石町)、門脇和人(酒田市)、柳沼幸男(福島県泉崎村)、柳沼美由紀(同)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、石川 毅(村山市)、伊藤信生(酒田市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、斉藤栄司(尾花沢市)、佐竹 久(大江町)、スマイルえりこ(新潟県新発田市)、崔 鍾八(朝日町)、清野千春(同)、清野礼子(仙台市)、清野由奈(朝日町)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、中沢 崇(長野市)、和田智枝(栃木県那須塩原市)、山田耕右(山形市)、菊地大二郎(同)、平 善昭(川西町)、菅原久之(遊佐町)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、矢萩 剛(村山市)、阿部悠子(東根市)、市川 秀(東京都中野区)、安孫子笑美里(東根市)、内藤フィリップ邦夫(天童市)

≪参加者の地域別内訳≫
▽山形県内 28人(酒田市5人、山形市3人、村山市3人、天童市3人、米沢市2人、尾花沢市2人、東根市2人、鶴岡市1人、南陽市1人、朝日町3人、大江町1人、川西町1人、遊佐町1人)
▽山形県外 21人(福島県4人、栃木県4人、群馬県3人、宮城県2人、埼玉県2人、東京都2人、神奈川県2人、新潟県1人、長野県1人)


≪第1回?第9回の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人

≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、大江カヌー愛好会、山形カヌークラブ)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省酒田河川国道事務所、山形県、
東北電力(株)山形支店、朝日町、庄内町、酒田市、山形カヌークラブ、
大江カヌー愛好会、山形県カヌー協会、美しい山形・最上川フォーラム
≪第9回カヌー探訪記念のステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一

≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇▽佐竹恵子▽長岡佳子
≪写真撮影≫ 長岡典己▽遠藤大輔
≪動画の撮影・編集≫ 真鍋賢一
≪ゴール地点でのサポート≫ 酒田市の遊快倶楽部(佐藤雅之、武田安英、長南平)
≪受付設営・交通案内設置≫ 白田金之助
≪弁当・飲料の手配・搬送≫ 安藤昭郎▽白田金之助
≪仕出し弁当≫ みずほ(山形県庄内町)
≪漬物提供≫ 安藤昭郎▽佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 庄内みどり観光バス(酒田市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝


◎真鍋賢一さん撮影の動画(ドローンによる空撮を含む。44分)
≪出発&到着時刻≫
2021年7月31日(土)
午前10時 山形県庄内町の庄内橋の上流、左岸から出発
午前11時20分 酒田市新堀豊森の右岸に上陸、休憩・差し入れ
午後1時?1時40分 酒田市の出羽大橋の下流、右岸に到着


≪参加者&参加艇≫
49人、38艇
≪カヌーイスト=申込順≫
齋藤龍真(村山市)、佐藤博隆(酒田市)、和田 勤(栃木県那須塩原市)、和田基秀(同)、?橋 洋(米沢市)、牧野 格(南陽市)、阿部明美(天童市)、阿部俊裕(同)、佐藤 明(鶴岡市)、安部幸男(宮城県柴田町)、新美武司(尾花沢市)、池田丈人(酒田市)、林 和明(東京都足立区)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、柴田尚宏(山形市)、結城敏宏(米沢市)、小田原紫朗(酒田市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、石井秀明(さいたま市)、岸 浩(福島市)、七海 孝(福島県鏡石町)、門脇和人(酒田市)、柳沼幸男(福島県泉崎村)、柳沼美由紀(同)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、石川 毅(村山市)、伊藤信生(酒田市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、斉藤栄司(尾花沢市)、佐竹 久(大江町)、スマイルえりこ(新潟県新発田市)、崔 鍾八(朝日町)、清野千春(同)、清野礼子(仙台市)、清野由奈(朝日町)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、中沢 崇(長野市)、和田智枝(栃木県那須塩原市)、山田耕右(山形市)、菊地大二郎(同)、平 善昭(川西町)、菅原久之(遊佐町)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、矢萩 剛(村山市)、阿部悠子(東根市)、市川 秀(東京都中野区)、安孫子笑美里(東根市)、内藤フィリップ邦夫(天童市)

≪参加者の地域別内訳≫
▽山形県内 28人(酒田市5人、山形市3人、村山市3人、天童市3人、米沢市2人、尾花沢市2人、東根市2人、鶴岡市1人、南陽市1人、朝日町3人、大江町1人、川西町1人、遊佐町1人)
▽山形県外 21人(福島県4人、栃木県4人、群馬県3人、宮城県2人、埼玉県2人、東京都2人、神奈川県2人、新潟県1人、長野県1人)


≪第1回?第9回の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人

≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、大江カヌー愛好会、山形カヌークラブ)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省酒田河川国道事務所、山形県、
東北電力(株)山形支店、朝日町、庄内町、酒田市、山形カヌークラブ、
大江カヌー愛好会、山形県カヌー協会、美しい山形・最上川フォーラム
≪第9回カヌー探訪記念のステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一

≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇▽佐竹恵子▽長岡佳子
≪写真撮影≫ 長岡典己▽遠藤大輔
≪動画の撮影・編集≫ 真鍋賢一
≪ゴール地点でのサポート≫ 酒田市の遊快倶楽部(佐藤雅之、武田安英、長南平)
≪受付設営・交通案内設置≫ 白田金之助
≪弁当・飲料の手配・搬送≫ 安藤昭郎▽白田金之助
≪仕出し弁当≫ みずほ(山形県庄内町)
≪漬物提供≫ 安藤昭郎▽佐竹恵子
≪マイクロバス≫ 庄内みどり観光バス(酒田市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
新聞業界に「ヨコタテ記者」という自嘲ネタがある。
役所が発表する報道資料は、ほとんどのものが横書きである。その資料に書いてあることをそのまま要約して、縦書きの新聞記事にすることを「ヨコタテ」と言う。横に書いてあるものを縦にするだけ。それで仕事をした気になっている記者を「ヨコタテ記者」と呼んで、さげすんでいるのである。

記者は日々、締め切りに追われて仕事をしている。役所が長い日数をかけてまとめた資料を短時間で読みこなし、その日の締め切りまでに記事にまとめるのは容易なことではない。その意味では、「ヨコタテ」はある程度は避けられないことである。
だが、メディアは役所の下請けではない。新聞記者なら、締め切りをにらみながら独自の視点、異なる角度から資料を読み解き、それも含めて記事に仕立て上げなければならない。それが購読料を払って新聞を読んでくれている読者に対する責任というものではないか。
こんなことを思ったのは、山形県を中心とする「6県合同プロジェクトチーム」が6月21日に「羽越・奥羽新幹線の費用対効果に関する調査報告書」を公表し、それを報じる各紙の記事を読んだからだ。
報告書は、羽越・奥羽の両新幹線をフル規格で建設する場合、それにかかる費用とそれによってもたらされる便益を試算したものだ。報告書の眼目は「フル規格新幹線を単線で整備すれば、費用対効果は1を上回る。整備は妥当」という点にある。
この発表を受けて、翌22日付で山形新聞は1面で「フル規格の妥当性確認」という見出しを付けて報じた。発表内容をダラダラと綴っただけの記事である。河北新報も大差ない。共に「ヨコタテ記者」の面目躍如と言うべきか。
朝日新聞はもっとひどい。発表から10日もたってから山形県版に記事を載せたのだが、その内容が山形新聞や河北新報とさほど変わらなかったからだ。この報告書の内容をチェックし、異なる角度から検討する時間が十分にあったのにそれをせず、要約しただけの記事を載せている。「言葉を失う」とはこういう時に使うのだろう。
6県合同の調査報告書のどこがどう、ひどいのか。
報告書は、これまでのように複線でフル規格の新幹線を整備した場合には費用対効果が0.5程度になり、とても採算が取れないことを認める。そのうえで、単線で盛り土構造にすれば建設費が安くなり、費用対効果が1を上回る、つまり採算が合うという結論を導き出している。従って、「フル規格の羽越・奥羽新幹線の整備には妥当性がある」というわけだ。
役人たちが何を狙っているか、明白である。新聞の見出しに「整備は妥当」という言葉を選ばせ、読者に「フル規格の新幹線整備を目指すのはまっとうなこと」と印象づけたいのだ。
山形新聞も河北新報も朝日新聞も、そろって「妥当」という見出しを付けてくれた。役人の思惑通り。「ヨコタテ記者」のそろい踏み、である。
元新聞記者の一人として、私は恥ずかしい。正直に言えば、駆け出し記者のころ私も似たような記事を書いたことがあるが、それでも恥ずかしい。
これらの記事を書いた記者たちが「素朴な疑問を抱き、そこから考える」という、新聞記者として当然なすべきことをしていないからだ。
素朴な疑問とは何か。それは、高速鉄道を「単線」で建設、整備することなど考えられるのか、という点だ。
国内の新幹線ではもちろん、そのような例はない。海外を見渡しても、時速200キロ以上で走る高速鉄道を単線でつくり、運行している国などどこにあるのか。
運行システムをどんなに優れたものにしても、保線作業をどれほど熱心にやっても、鉄道にはトラブルが付きものである。倒木や土砂崩れで不通になったりもする。そういう時に素早く復旧させるためにも、高速鉄道なら複線にするのが常識であり、当然のことなのだ。
つまり、単線でのフル規格新幹線の整備などというのは考えられないことであり、机上の空論に過ぎない。それをベースに「費用対効果は1を上回る。整備の妥当性が示された」などという報告書が出されたなら、記者は一言、「世界で高速鉄道を単線で運行している国はあるのか」と質問すればいいのだ。
記者会見の席でそうした質問をすることもなく、あるいは記事にするまで何日もあったのに専門家にそうしたことを尋ねることもなく、役人の思惑通り「妥当」という見出しを付けて報じるのは、新聞記者の役割を放棄しているようなものだ。
羽越・奥羽のフル規格新幹線整備を応援している大阪産業大学の波床(はとこ)正敏教授ですら、報告書を評価しつつ、「高速鉄道を単線で整備することを考えなければならないようなケチ臭い国は日本以外にはありません」と、その内容に疑問を呈している。
この6県合同の報告書をとりまとめる中心になったのは、山形県庁の「みらい企画創造部」である。その部長、小林剛也(ごうや)氏は記者会見の前の週、県内の経済人が主催するモーニングセミナーに講師として招かれ、フル規格の羽越・奥羽新幹線構想について「来週、新聞に驚くような記事が出ますよ。お楽しみに」と得意げに語ったという。
確かに、驚くほどお粗末な報告書だった。それを3紙とも、なんの疑問を呈することもなく、「整備は妥当」という見出しを付けて報じたのだから、驚きは倍加する。
小林氏は昨年夏、財務省の文書課長補佐から山形県庁に出向してきた。来年の春には、同じく出向組の大瀧洋・総務部長が総務省に戻るのに合わせて、総務部長に転じると見られている。
こんなお粗末な調査報告書をまとめる人物が県庁の企画部門のトップで、それが来年からは人事と財政をつかさどる総務部長になって号令をかける。悲しい話だ。
◇ ◇
吉村美栄子知事がフル規格の奥羽・羽越新幹線構想を唱え始めたのは東日本大震災の翌年、2012年からである。
大震災で東北の太平洋側の産業インフラがズタズタになるのを目の当たりにした。その復興を支援したくても、日本海側のインフラは脆弱(ぜいじゃく)で十分な支援ができない。そうした経験から「東北の日本海側にも太平洋側に劣らぬインフラを整備する必要がある。フル規格の新幹線が必要だ」との思いを深めたものと思われる。
北陸新幹線が金沢まで、北海道新幹線も青森から函館まで通じる見通しが立ったことで、当時、「次はどこに新幹線をつくるか」が政治課題として浮上しつつあった。それも知事の背中を押したようだ。
無投票で再選された2013年からは、県の重要施策の一つとして推進し始めた。当初は「奥羽・羽越フル規格新幹線の実現を」と呼びかけていた。福島から山形を通り、秋田に至る奥羽新幹線が先で、富山から新潟、山形、秋田を通って青森に至る羽越新幹線は2番目だった。それは、早くから「フル規格の奥羽・羽越新幹線の整備を」と主張していた山形新聞の主張とも重なる。
それが今回の報告書では「羽越・奥羽新幹線」と、順番が入れ替わった。なぜか。
吉村知事はこの構想を推進する理由について、東京で開かれたフォーラムで次のように語っている。「日本海側も太平洋側と同じく大事な国土。隅々まで新幹線ネットワークをつなぐことで、日本全体の力が発揮できる。全国の皆様にも関心を持っていただき、大きな運動のうねりをつくっていきたい」。
「リダンダンシー」という英語もよく使うようになった。太平洋側の交通インフラが災害で被害を受けた場合には日本海側でそれを補う――代替機能を担う、という意味合いだ。「災害時のリダンダンシー機能を確保し、県土の強靭化を図っていきたい」といった風に使っている。
この論理を進めていけば、山形から秋田に至る奥羽新幹線よりも日本海側の各都市を結ぶ羽越新幹線の方を優先しなければならない、ということになる。それが「奥羽・羽越」から「羽越・奥羽」になった理由だろう。
報告書が「6県合同のプロジェクトチーム」によってまとめられた、というのは、羽越新幹線のルートにある富山、新潟、山形、秋田、青森の5県、それに奥羽新幹線にかかわる福島を加えてのことだ。とはいえ、北陸新幹線が開通した富山や上越新幹線がある新潟、東北新幹線のある青森はもとより、ほとんど関心がない。「山形県が熱心だから」とお付き合いをしているに過ぎない。
田中角栄首相が日本列島改造論を唱えていた時代、あるいは高度経済成長を謳歌していた時代ならともかく、経済が右肩下がりになり、医療や社会福祉の負担がますます重くなるこれからの時代。人の往来もあまりない富山―新潟―山形―秋田―青森に1キロ当たり100億円とも試算されるフル規格の新幹線を建設する余裕がこの国にあるのか。
ごく常識的に考えただけでも「そんな余裕はない」という結論になる。
それでも、「50年後、100年後を考えれば、日本海側の産業インフラ整備も重要だ」という主張は成り立つ。が、それは「政治的な課題」というより、「長期の国家ビジョン」あるいは「政治哲学」の範疇に入れるべき議論だろう。山形県の知事がしゃかりきになって取り組み、税金を投じて県民運動を繰り広げるような課題ではあるまい。
振り返れば、このフル規格新幹線の整備を唱え始めたころから、吉村知事の迷走は始まっていたのではないか。「おかしい」と思っても、県庁内でそれを口にする者は誰もいない。
地元の山形新聞は見境もなく、一緒になって旗を振ってきた。山形1区選出の遠藤利明・衆院議員まで、何を思ってかこの空騒ぎに加わった。
吉村知事は「私が山形県を引っ張っている」といった高揚感を感じていたのかもしれない。その挙げ句に「コロナ禍での選挙で40万票を得て4選」である。
3月に県議会で若松正俊・副知事の再任人事案が否決された後、吉村知事は「民意を大切にしてほしいですね」と、鼻息荒く語った。「副知事も含めて信任を得たと思っています」とも述べた。
それは、首長と議会は対等であり地方自治の両輪である、,という大原則すら忘れ果てた、おごりたかぶる政治家の言動だった。
若松正俊・副知事が「公務員」という立場を忘れて、知事に反旗をひるがえした市長たちに「対立候補を応援しないで」「せめて中立を保って」などと働きかけたのも、そうしたおごりの延長線上で起きたことだろう。本人は、「罪を犯している」という意識すらなかったのではないか。
古来、権力の崩壊のタネは権勢のピークに芽吹くという。吉村県政もまたこの至言(しげん)通り、崩壊の道をたどり始めた、ということか。
・・・・・・・・・・・・
若松氏のメール、県は不存在と回答
1月の山形県知事選挙をめぐって、若松正俊・副知事はどのような動きをしていたのか。それを調べるため、筆者は6月17日、県に昨年7月以降の若松氏の公用車の運行記録とメール送受信記録の情報公開を求めた。
これに対し、公用車の運行記録は開示されたが、メールの送受信記録については「作成・保有していない」として「公文書不存在通知書」を受け取った(ともに7月1日付)
「不存在とはどういう意味か」と問いただしたところ、秘書課の課長補佐は「若松は副知事在任中の4年間、公務用にパソコンを貸与されていたが、まったく使っていない。従ってメールの送受信もない」と説明した。信じがたい説明である。
念のため、吉村美栄子知事の1期目の副知事、高橋節(たかし)氏と2期目の副知事、細谷知行(ともゆき)氏に尋ねたところ、2人とも「公務用のパソコンを使い、メールの送受信をしていた。知事からメールで指示を受けたこともある」と認めた。「不存在」は虚偽の疑いがある。
このため、筆者は追加で「吉村知事のメール送受信記録」「大瀧洋・総務部長のメール送受信記録」「若松氏の秘書のパソコン及びタブレット端末にある若松氏関連のメール送受信記録」(それぞれ昨年7月から今年5月まで)の情報公開を請求し、回答を待っている。
知事や公務員が業務でやり取りしたメールは「公文書」であり、その電子データも「公文書」として情報公開の対象になることは判例で確定している。条例で「不開示にできる」と定められているケースを除き、原則として公開しなければならない。
公文書が存在するのに「不存在」と回答するのは、当然のことながら県情報公開条例違反であり、違法である。さらに調べたうえで、対抗措置を検討したい。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 92」 2021年7月29日
*初出:月刊『素晴らしい山形』2021年8月号
≪写真説明&Source≫
羽越・奥羽新幹線構想を含め山形県政について語る吉村美栄子知事(ビジネス誌『事業構想』オンライン2019年6月号)
https://www.projectdesign.jp/201906/area-yamagata/006426.php
役所が発表する報道資料は、ほとんどのものが横書きである。その資料に書いてあることをそのまま要約して、縦書きの新聞記事にすることを「ヨコタテ」と言う。横に書いてあるものを縦にするだけ。それで仕事をした気になっている記者を「ヨコタテ記者」と呼んで、さげすんでいるのである。

記者は日々、締め切りに追われて仕事をしている。役所が長い日数をかけてまとめた資料を短時間で読みこなし、その日の締め切りまでに記事にまとめるのは容易なことではない。その意味では、「ヨコタテ」はある程度は避けられないことである。
だが、メディアは役所の下請けではない。新聞記者なら、締め切りをにらみながら独自の視点、異なる角度から資料を読み解き、それも含めて記事に仕立て上げなければならない。それが購読料を払って新聞を読んでくれている読者に対する責任というものではないか。
こんなことを思ったのは、山形県を中心とする「6県合同プロジェクトチーム」が6月21日に「羽越・奥羽新幹線の費用対効果に関する調査報告書」を公表し、それを報じる各紙の記事を読んだからだ。
報告書は、羽越・奥羽の両新幹線をフル規格で建設する場合、それにかかる費用とそれによってもたらされる便益を試算したものだ。報告書の眼目は「フル規格新幹線を単線で整備すれば、費用対効果は1を上回る。整備は妥当」という点にある。
この発表を受けて、翌22日付で山形新聞は1面で「フル規格の妥当性確認」という見出しを付けて報じた。発表内容をダラダラと綴っただけの記事である。河北新報も大差ない。共に「ヨコタテ記者」の面目躍如と言うべきか。
朝日新聞はもっとひどい。発表から10日もたってから山形県版に記事を載せたのだが、その内容が山形新聞や河北新報とさほど変わらなかったからだ。この報告書の内容をチェックし、異なる角度から検討する時間が十分にあったのにそれをせず、要約しただけの記事を載せている。「言葉を失う」とはこういう時に使うのだろう。
6県合同の調査報告書のどこがどう、ひどいのか。
報告書は、これまでのように複線でフル規格の新幹線を整備した場合には費用対効果が0.5程度になり、とても採算が取れないことを認める。そのうえで、単線で盛り土構造にすれば建設費が安くなり、費用対効果が1を上回る、つまり採算が合うという結論を導き出している。従って、「フル規格の羽越・奥羽新幹線の整備には妥当性がある」というわけだ。
役人たちが何を狙っているか、明白である。新聞の見出しに「整備は妥当」という言葉を選ばせ、読者に「フル規格の新幹線整備を目指すのはまっとうなこと」と印象づけたいのだ。
山形新聞も河北新報も朝日新聞も、そろって「妥当」という見出しを付けてくれた。役人の思惑通り。「ヨコタテ記者」のそろい踏み、である。
元新聞記者の一人として、私は恥ずかしい。正直に言えば、駆け出し記者のころ私も似たような記事を書いたことがあるが、それでも恥ずかしい。
これらの記事を書いた記者たちが「素朴な疑問を抱き、そこから考える」という、新聞記者として当然なすべきことをしていないからだ。
素朴な疑問とは何か。それは、高速鉄道を「単線」で建設、整備することなど考えられるのか、という点だ。
国内の新幹線ではもちろん、そのような例はない。海外を見渡しても、時速200キロ以上で走る高速鉄道を単線でつくり、運行している国などどこにあるのか。
運行システムをどんなに優れたものにしても、保線作業をどれほど熱心にやっても、鉄道にはトラブルが付きものである。倒木や土砂崩れで不通になったりもする。そういう時に素早く復旧させるためにも、高速鉄道なら複線にするのが常識であり、当然のことなのだ。
つまり、単線でのフル規格新幹線の整備などというのは考えられないことであり、机上の空論に過ぎない。それをベースに「費用対効果は1を上回る。整備の妥当性が示された」などという報告書が出されたなら、記者は一言、「世界で高速鉄道を単線で運行している国はあるのか」と質問すればいいのだ。
記者会見の席でそうした質問をすることもなく、あるいは記事にするまで何日もあったのに専門家にそうしたことを尋ねることもなく、役人の思惑通り「妥当」という見出しを付けて報じるのは、新聞記者の役割を放棄しているようなものだ。
羽越・奥羽のフル規格新幹線整備を応援している大阪産業大学の波床(はとこ)正敏教授ですら、報告書を評価しつつ、「高速鉄道を単線で整備することを考えなければならないようなケチ臭い国は日本以外にはありません」と、その内容に疑問を呈している。
この6県合同の報告書をとりまとめる中心になったのは、山形県庁の「みらい企画創造部」である。その部長、小林剛也(ごうや)氏は記者会見の前の週、県内の経済人が主催するモーニングセミナーに講師として招かれ、フル規格の羽越・奥羽新幹線構想について「来週、新聞に驚くような記事が出ますよ。お楽しみに」と得意げに語ったという。
確かに、驚くほどお粗末な報告書だった。それを3紙とも、なんの疑問を呈することもなく、「整備は妥当」という見出しを付けて報じたのだから、驚きは倍加する。
小林氏は昨年夏、財務省の文書課長補佐から山形県庁に出向してきた。来年の春には、同じく出向組の大瀧洋・総務部長が総務省に戻るのに合わせて、総務部長に転じると見られている。
こんなお粗末な調査報告書をまとめる人物が県庁の企画部門のトップで、それが来年からは人事と財政をつかさどる総務部長になって号令をかける。悲しい話だ。
◇ ◇
吉村美栄子知事がフル規格の奥羽・羽越新幹線構想を唱え始めたのは東日本大震災の翌年、2012年からである。
大震災で東北の太平洋側の産業インフラがズタズタになるのを目の当たりにした。その復興を支援したくても、日本海側のインフラは脆弱(ぜいじゃく)で十分な支援ができない。そうした経験から「東北の日本海側にも太平洋側に劣らぬインフラを整備する必要がある。フル規格の新幹線が必要だ」との思いを深めたものと思われる。
北陸新幹線が金沢まで、北海道新幹線も青森から函館まで通じる見通しが立ったことで、当時、「次はどこに新幹線をつくるか」が政治課題として浮上しつつあった。それも知事の背中を押したようだ。
無投票で再選された2013年からは、県の重要施策の一つとして推進し始めた。当初は「奥羽・羽越フル規格新幹線の実現を」と呼びかけていた。福島から山形を通り、秋田に至る奥羽新幹線が先で、富山から新潟、山形、秋田を通って青森に至る羽越新幹線は2番目だった。それは、早くから「フル規格の奥羽・羽越新幹線の整備を」と主張していた山形新聞の主張とも重なる。
それが今回の報告書では「羽越・奥羽新幹線」と、順番が入れ替わった。なぜか。
吉村知事はこの構想を推進する理由について、東京で開かれたフォーラムで次のように語っている。「日本海側も太平洋側と同じく大事な国土。隅々まで新幹線ネットワークをつなぐことで、日本全体の力が発揮できる。全国の皆様にも関心を持っていただき、大きな運動のうねりをつくっていきたい」。
「リダンダンシー」という英語もよく使うようになった。太平洋側の交通インフラが災害で被害を受けた場合には日本海側でそれを補う――代替機能を担う、という意味合いだ。「災害時のリダンダンシー機能を確保し、県土の強靭化を図っていきたい」といった風に使っている。
この論理を進めていけば、山形から秋田に至る奥羽新幹線よりも日本海側の各都市を結ぶ羽越新幹線の方を優先しなければならない、ということになる。それが「奥羽・羽越」から「羽越・奥羽」になった理由だろう。
報告書が「6県合同のプロジェクトチーム」によってまとめられた、というのは、羽越新幹線のルートにある富山、新潟、山形、秋田、青森の5県、それに奥羽新幹線にかかわる福島を加えてのことだ。とはいえ、北陸新幹線が開通した富山や上越新幹線がある新潟、東北新幹線のある青森はもとより、ほとんど関心がない。「山形県が熱心だから」とお付き合いをしているに過ぎない。
田中角栄首相が日本列島改造論を唱えていた時代、あるいは高度経済成長を謳歌していた時代ならともかく、経済が右肩下がりになり、医療や社会福祉の負担がますます重くなるこれからの時代。人の往来もあまりない富山―新潟―山形―秋田―青森に1キロ当たり100億円とも試算されるフル規格の新幹線を建設する余裕がこの国にあるのか。
ごく常識的に考えただけでも「そんな余裕はない」という結論になる。
それでも、「50年後、100年後を考えれば、日本海側の産業インフラ整備も重要だ」という主張は成り立つ。が、それは「政治的な課題」というより、「長期の国家ビジョン」あるいは「政治哲学」の範疇に入れるべき議論だろう。山形県の知事がしゃかりきになって取り組み、税金を投じて県民運動を繰り広げるような課題ではあるまい。
振り返れば、このフル規格新幹線の整備を唱え始めたころから、吉村知事の迷走は始まっていたのではないか。「おかしい」と思っても、県庁内でそれを口にする者は誰もいない。
地元の山形新聞は見境もなく、一緒になって旗を振ってきた。山形1区選出の遠藤利明・衆院議員まで、何を思ってかこの空騒ぎに加わった。
吉村知事は「私が山形県を引っ張っている」といった高揚感を感じていたのかもしれない。その挙げ句に「コロナ禍での選挙で40万票を得て4選」である。
3月に県議会で若松正俊・副知事の再任人事案が否決された後、吉村知事は「民意を大切にしてほしいですね」と、鼻息荒く語った。「副知事も含めて信任を得たと思っています」とも述べた。
それは、首長と議会は対等であり地方自治の両輪である、,という大原則すら忘れ果てた、おごりたかぶる政治家の言動だった。
若松正俊・副知事が「公務員」という立場を忘れて、知事に反旗をひるがえした市長たちに「対立候補を応援しないで」「せめて中立を保って」などと働きかけたのも、そうしたおごりの延長線上で起きたことだろう。本人は、「罪を犯している」という意識すらなかったのではないか。
古来、権力の崩壊のタネは権勢のピークに芽吹くという。吉村県政もまたこの至言(しげん)通り、崩壊の道をたどり始めた、ということか。
・・・・・・・・・・・・
若松氏のメール、県は不存在と回答
1月の山形県知事選挙をめぐって、若松正俊・副知事はどのような動きをしていたのか。それを調べるため、筆者は6月17日、県に昨年7月以降の若松氏の公用車の運行記録とメール送受信記録の情報公開を求めた。
これに対し、公用車の運行記録は開示されたが、メールの送受信記録については「作成・保有していない」として「公文書不存在通知書」を受け取った(ともに7月1日付)
「不存在とはどういう意味か」と問いただしたところ、秘書課の課長補佐は「若松は副知事在任中の4年間、公務用にパソコンを貸与されていたが、まったく使っていない。従ってメールの送受信もない」と説明した。信じがたい説明である。
念のため、吉村美栄子知事の1期目の副知事、高橋節(たかし)氏と2期目の副知事、細谷知行(ともゆき)氏に尋ねたところ、2人とも「公務用のパソコンを使い、メールの送受信をしていた。知事からメールで指示を受けたこともある」と認めた。「不存在」は虚偽の疑いがある。
このため、筆者は追加で「吉村知事のメール送受信記録」「大瀧洋・総務部長のメール送受信記録」「若松氏の秘書のパソコン及びタブレット端末にある若松氏関連のメール送受信記録」(それぞれ昨年7月から今年5月まで)の情報公開を請求し、回答を待っている。
知事や公務員が業務でやり取りしたメールは「公文書」であり、その電子データも「公文書」として情報公開の対象になることは判例で確定している。条例で「不開示にできる」と定められているケースを除き、原則として公開しなければならない。
公文書が存在するのに「不存在」と回答するのは、当然のことながら県情報公開条例違反であり、違法である。さらに調べたうえで、対抗措置を検討したい。
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 92」 2021年7月29日
*初出:月刊『素晴らしい山形』2021年8月号
≪写真説明&Source≫
羽越・奥羽新幹線構想を含め山形県政について語る吉村美栄子知事(ビジネス誌『事業構想』オンライン2019年6月号)
https://www.projectdesign.jp/201906/area-yamagata/006426.php
7月31日(土)に第9回最上川縦断カヌー探訪を予定通りに開催します。参加予定者は49人で、過去最多になる見込みです。当日の天候予報は晴れのち曇り、最高気温は32度。
大津波に襲われた福島第一原発で何が起きていたのか。それを追い続ける共同通信原発事故取材班の連載が佳境を迎えている。

「全電源喪失の記憶」の通しタイトルで2014年から続く連載は、7月6日から第5部「1号機爆発」が始まった。地震による激しい揺れ、そして襲ってきた大津波。原発の運転に欠かせない電源がすべて失われた時、原発の中央制御室にいた当直長と運転員たちは何を考え、どう動いたのか。それを当事者たちの証言で綴っている。
第5部の1回目の見出しは「DGトリップ!」」である。原発は、電力の供給が止まった場合、複数の非常用ディーゼル発電機(Diesel Generator, DG)が自動的に動き出し、原子炉を制御できるようになっている。1号機と2号機にはそれぞれ2台の非常用発電機が備えられていた。万が一、2台とも動かなくなっても隣の原子炉用の発電機から電気が供給される仕組みになっていた。
ところが、30分ほどして大津波が襲来し、ディーゼル発電機が水につかってしまった。電源盤も水浸しになったため、別の発電機の電気を回すことも不可能になった。すべての電源が失われた(トリップした)のである。その瞬間、中央制御室にいた運転員が叫んだ言葉が「DGトリップ!」だった。
事故当時、福島第一原発の1、2号機の中央制御室で当直長をしていた伊沢郁夫の証言。「心の中で弱気になったのはあの瞬間だけですね。打つ手がないという状況は人生の中で初めてでしたから」。当事者の生の証言は、政府や東京電力がまとめた事故報告書のいかなる表現よりも、現場の衝撃の大きさを端的に示している。
第5部の2回目(7月7日付)に載っている伊沢の証言も印象的だ。原発の運転員たちは様々な事故に備えてトレーニングを受けていた。その訓練の内容と現実とのギャップを、伊沢はこう語っている。「どんなに厳しい訓練でも常に最後は電源があるわけです。それがないという現実が分かったときのショック。『どうしよう、とにかく考えるんだ』って思いました」。
この証言は、日本政府や電力各社、原発メーカーが振りまいてきた「安全神話」がいかにでたらめなものだったかを示している。電力会社は原発事故に備えて保険に入っていた。その保険は、炉心溶融を含む過酷事故をも含むものだった。
ところが、事故に備えた訓練は「常に電源がある」条件で行われていた。つまり、最も厳しい局面でどう対処するか、については訓練すらしていなかったのである。欺瞞であり、国民に対する背信行為と言うしかない。
連載の3回目にも、政府と電力会社の欺瞞を示す証言が登場する。当直長の1人、遠藤英由の証言。3月11日の夜、すべての電源が失われ、運転員たちは原子炉の水位や温度を示す計器を読むことすらできない絶望的な状況に追い込まれていた。遠藤は述懐する。「スクラム(原子炉緊急停止)から時間がたっていて、まだ水を入れられていない。『これはもう炉心が駄目になっているだろうね』と話していました」
原発事故に対応する現場では、「炉心溶融は避けられない」と覚悟していた。にもかかわらず、当時の民主党政権と東京電力はそれを認めようとしなかった。新聞に「炉心溶融」の見出しが載ると、政府は「何を根拠に炉心溶融と書くのか」と猛烈な圧力をかけ、その表現を撤回させた。事実を捻じ曲げようと必死になったのである。
そうした中にも救いはあった。4回目の連載記事(9日付)では、原子炉格納容器が爆発するのを防ぐために運転員たちがベントを試みる様子が描かれている。大量被曝を避けられない、危険きわまりない現場に誰が行くか。
当直長の伊沢郁夫は「まず俺が行く」と言った。だが、応援に駆け付けた別の当直長は「君はここに残って仕切ってくれなきゃ駄目だ。俺らが行く」と言い返す。若手の運転員たちも「私も行きます」と次々に手を挙げた。命をかけて、名乗り出たのだった。
福島の原発事故をあの規模で抑え込むことができたのは、さまざまな幸運に恵まれたのに加えて、こうした運転員たちを含む現場の覚悟があったからだ。「行きます」と名乗り出た時の運転員たちの胸のうちを思うと、今でも目頭が熱くなる。
それに引き換え、東京電力の首脳たちはどうだ。2008年の段階で「最悪の場合、高さ15メートルの津波が来ることもあり得る」という報告が内部から上がってきていたのに、「信頼性に疑問がある」などと難癖をつけてその報告を退け、有効な津波対策に乗り出すことを拒んだ。
当時の東京電力の会長、勝俣恒久、社長の清水正孝、副社長の武藤栄・・・。当時の首脳は誰一人、潔く責任を認めようとしない。「万死に値する判断ミス」を犯しておきながら、いまだに責任を逃れようとあがき続けている。
ぶざまな事故対応に終始した、当時の首相、菅直人や経済産業相の海江田万里、官房長官の枝野幸男ら民主党政権の首脳たちにしても、何が足りなかったのか、どう対応すべきだったのかについて率直に語るのを聞いたことがない。
二流のトップを一流の現場が支える。それが日本社会の伝統なのか。コロナ禍でも同じことが繰り返される、と覚悟しなければなるまい。
(敬称略)
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 91」 2021年7月9日
*このコラムは、山形新聞に掲載された共同通信配信の連載をもとに書いています。共同通信の「全電源喪失の記憶」の初期の連載は、祥伝社から2015年に出版されています。今回の連載も本にまとめ、出版されるかもしれません。朝日新聞や読売新聞は共同通信と国内記事の配信を受ける契約を結んでいないため掲載できず、読者は読むことができません。
≪写真説明&Source≫
照明が点灯した福島第一原発の中央制御室=2011年3月26日、時事通信社
https://www.jiji.com/jc/d4?p=gen100-jlp10647542&d=d4_topics

「全電源喪失の記憶」の通しタイトルで2014年から続く連載は、7月6日から第5部「1号機爆発」が始まった。地震による激しい揺れ、そして襲ってきた大津波。原発の運転に欠かせない電源がすべて失われた時、原発の中央制御室にいた当直長と運転員たちは何を考え、どう動いたのか。それを当事者たちの証言で綴っている。
第5部の1回目の見出しは「DGトリップ!」」である。原発は、電力の供給が止まった場合、複数の非常用ディーゼル発電機(Diesel Generator, DG)が自動的に動き出し、原子炉を制御できるようになっている。1号機と2号機にはそれぞれ2台の非常用発電機が備えられていた。万が一、2台とも動かなくなっても隣の原子炉用の発電機から電気が供給される仕組みになっていた。
ところが、30分ほどして大津波が襲来し、ディーゼル発電機が水につかってしまった。電源盤も水浸しになったため、別の発電機の電気を回すことも不可能になった。すべての電源が失われた(トリップした)のである。その瞬間、中央制御室にいた運転員が叫んだ言葉が「DGトリップ!」だった。
事故当時、福島第一原発の1、2号機の中央制御室で当直長をしていた伊沢郁夫の証言。「心の中で弱気になったのはあの瞬間だけですね。打つ手がないという状況は人生の中で初めてでしたから」。当事者の生の証言は、政府や東京電力がまとめた事故報告書のいかなる表現よりも、現場の衝撃の大きさを端的に示している。
第5部の2回目(7月7日付)に載っている伊沢の証言も印象的だ。原発の運転員たちは様々な事故に備えてトレーニングを受けていた。その訓練の内容と現実とのギャップを、伊沢はこう語っている。「どんなに厳しい訓練でも常に最後は電源があるわけです。それがないという現実が分かったときのショック。『どうしよう、とにかく考えるんだ』って思いました」。
この証言は、日本政府や電力各社、原発メーカーが振りまいてきた「安全神話」がいかにでたらめなものだったかを示している。電力会社は原発事故に備えて保険に入っていた。その保険は、炉心溶融を含む過酷事故をも含むものだった。
ところが、事故に備えた訓練は「常に電源がある」条件で行われていた。つまり、最も厳しい局面でどう対処するか、については訓練すらしていなかったのである。欺瞞であり、国民に対する背信行為と言うしかない。
連載の3回目にも、政府と電力会社の欺瞞を示す証言が登場する。当直長の1人、遠藤英由の証言。3月11日の夜、すべての電源が失われ、運転員たちは原子炉の水位や温度を示す計器を読むことすらできない絶望的な状況に追い込まれていた。遠藤は述懐する。「スクラム(原子炉緊急停止)から時間がたっていて、まだ水を入れられていない。『これはもう炉心が駄目になっているだろうね』と話していました」
原発事故に対応する現場では、「炉心溶融は避けられない」と覚悟していた。にもかかわらず、当時の民主党政権と東京電力はそれを認めようとしなかった。新聞に「炉心溶融」の見出しが載ると、政府は「何を根拠に炉心溶融と書くのか」と猛烈な圧力をかけ、その表現を撤回させた。事実を捻じ曲げようと必死になったのである。
そうした中にも救いはあった。4回目の連載記事(9日付)では、原子炉格納容器が爆発するのを防ぐために運転員たちがベントを試みる様子が描かれている。大量被曝を避けられない、危険きわまりない現場に誰が行くか。
当直長の伊沢郁夫は「まず俺が行く」と言った。だが、応援に駆け付けた別の当直長は「君はここに残って仕切ってくれなきゃ駄目だ。俺らが行く」と言い返す。若手の運転員たちも「私も行きます」と次々に手を挙げた。命をかけて、名乗り出たのだった。
福島の原発事故をあの規模で抑え込むことができたのは、さまざまな幸運に恵まれたのに加えて、こうした運転員たちを含む現場の覚悟があったからだ。「行きます」と名乗り出た時の運転員たちの胸のうちを思うと、今でも目頭が熱くなる。
それに引き換え、東京電力の首脳たちはどうだ。2008年の段階で「最悪の場合、高さ15メートルの津波が来ることもあり得る」という報告が内部から上がってきていたのに、「信頼性に疑問がある」などと難癖をつけてその報告を退け、有効な津波対策に乗り出すことを拒んだ。
当時の東京電力の会長、勝俣恒久、社長の清水正孝、副社長の武藤栄・・・。当時の首脳は誰一人、潔く責任を認めようとしない。「万死に値する判断ミス」を犯しておきながら、いまだに責任を逃れようとあがき続けている。
ぶざまな事故対応に終始した、当時の首相、菅直人や経済産業相の海江田万里、官房長官の枝野幸男ら民主党政権の首脳たちにしても、何が足りなかったのか、どう対応すべきだったのかについて率直に語るのを聞いたことがない。
二流のトップを一流の現場が支える。それが日本社会の伝統なのか。コロナ禍でも同じことが繰り返される、と覚悟しなければなるまい。
(敬称略)
長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 91」 2021年7月9日
*このコラムは、山形新聞に掲載された共同通信配信の連載をもとに書いています。共同通信の「全電源喪失の記憶」の初期の連載は、祥伝社から2015年に出版されています。今回の連載も本にまとめ、出版されるかもしれません。朝日新聞や読売新聞は共同通信と国内記事の配信を受ける契約を結んでいないため掲載できず、読者は読むことができません。
≪写真説明&Source≫
照明が点灯した福島第一原発の中央制御室=2011年3月26日、時事通信社
https://www.jiji.com/jc/d4?p=gen100-jlp10647542&d=d4_topics
自分が仕える人のために忠勤を尽くすのは悪いことではない。普通なら褒められるべきことである。だが、その行為が法に触れるとなれば、話は別だ。
良かれと思ってしたことでも、その者は被疑者として調べられ、容疑が固まれば起訴され、裁きを受ける。山形県の若松正俊・前副知事は今、そのようなイバラの道に立たされている。容疑は公職選挙法違反、公務員の地位利用である。

話は山形県知事選挙の告示の2週間前にさかのぼる。昨年の12月24日、佐藤孝弘・山形市長や丸山至・酒田市長ら8人の市長は現職の吉村美栄子知事ではなく、自民党が推す大内理加・元県議を推薦すると発表した。「今の県政の反応の鈍さ」や「市との感覚のずれ」を理由に、知事に反旗を翻したのだ。
事前の世論調査では,、すでに「現職の吉村氏が圧倒的に有利」との結果が出ていた。だが、吉村陣営はこうした動きを「好ましくない」と見たのだろう。市長らによれば、この前後に知事の補佐役の若松副知事が「対立候補の大内氏を推さないでほしい」「せめて中立でいてくれないか」と働きかけてきたという。
これだけだったら、まだ罪は軽い。問題は若松氏の働きかけがそれにとどまらなかったことだ。市長らの証言によれば、「向こうに付いたら不利益をこうむりますよ」とほのめかしたのだという。
酒田市に対しては、県と庄内地域の自治体による東北公益文科大学(公設民営)の公立化に向けた協議が「進められなくなる」と述べたという。ローカル鉄道「フラワー長井線」の赤字に苦しむ長井市と南陽市には「県の負担金をこれまでのように出すのは難しい」と、減額する可能性があることを伝えたようだ。
市長らの証言が事実とすれば、これは公職選挙法が禁じている「公務員の地位を利用した選挙運動もしくは事前運動」にあたる。特別職とはいえ、副知事は公務員である。それが選挙で選ばれた市長に圧力をかけたわけで、「信じられないような行為」と言っていい。
公選法の規定に触れるどころではない。「きわめて悪質な地位利用」であり、「2年以下の禁固または30万円以下の罰金」を科せられて当然の犯罪行為である。
関係者の証言によれば、こうした「副知事の地位を利用した脅し」をかけられた市長は7人いる。脅しをかけられなかったのは山形市長だけだったようだ。立場が強い市長は避け、弱い市長を狙ったということだろう。
7人の市長が口裏を合わせて「吉村知事と若松副知事を追い落とそうとしている」という可能性はある。だが、それはあくまでも可能性に過ぎず、「そのような口裏合わせはなかった」と断言していい。
なぜなら、知事選の投開票日の翌日(今年1月25日)、県幹部は酒田市に対して「東北公益文科大学の公立化に向けた準備作業を停止する」と伝えたからだ。県側もそれを認めている。長井市に対しても、「赤字ローカル線への補助金を確保するのは難しい」と通告した。つまり、若松副知事がほのめかしたことを県側は選挙が終わった途端、実行したのだ。
露骨と言うか、無防備と言うか。若松氏にしても彼の意向を伝えた県幹部にしても、それが「公務員の地位を利用した犯罪行為」を実質的に裏付けることになる、ということに思い至らなかったようだ。
知事選で敗北した自民党側はこうした事実を把握していた。それゆえに、吉村知事が県議会に「若松副知事を再任する人事案」を出してきたのに対して県議団は反対し、否決した(3月9日)。若松氏の任期は10日までだったので、山形県は「副知事不在」という異常事態に陥った。
ところが、吉村知事は若松氏を11日付で非常勤特別職にし、新型コロナウイルス対策などの連絡調整にあたる「特命補佐」に任命するという奇策に出た。「副知事」という肩書から「特命補佐」という肩書に変え、事実上続投させたのである。
首長と議会は地方自治の両輪である。議会には首長の施策をチェックするという重要な役割がある。人事案の同意権限もその役割を果たすためにある。「奇策」はそうした機能をあざわらうような暴挙と言わなければならない。
若松氏を議会の同意がいらない「特命補佐」に任命した理由について、知事は「余人をもって代えがたい」と説明した。人を小馬鹿にしたような、陳腐な説明である。
その若松氏に対して、山形県警は公職選挙法違反の疑いで捜査に乗り出した。市長とその周りの人たちから話を聴く証拠固めは終わり、捜査は被疑者本人、若松氏から事情聴取する段階に至っている。
若松氏がその地位を利用して圧力をかけたのが1人だけなら、捜査は難しい。「言った」「言ってない」の水掛け論になるからだ。が、なにせ相手は7人もいる。若松氏が否定しても、起訴して有罪に持ち込むのは難しいことではない。予想されたことだが、若松氏は「そんなことは言っていない」と全面的に否定したようだ。
証拠がそろっているのに被疑者が否認した場合、捜査当局は被疑者の逮捕や事務所、自宅などの家宅捜索をし、強制捜査に踏み切るのが常道だ。だが、県警はまだ着手していない。なぜか。事件はこれからどう展開するのか。
考えられるのは次の四つのシナリオである。
?県警は強制捜査に踏み切らないまま捜査を終えて山形地検に書類送検し、地検は不起訴処分にして事件そのものを握り潰す?強制捜査はしないまま書類送検し、地検が起訴、微罪で済ませる?強制捜査に踏み切って送検し、公職選挙法違反で起訴して断罪する?強制捜査し、公選法違反にとどまらず、若松氏の余罪を追及する。
このうち、?は考えにくい。山形地検の松下裕子(ひろこ)検事正はそのような姑息な対応をする人物とは思えないからだ。東京地検をはじめ首都圏の現場で捜査を担い、法務省での勤務も長い。検察の本流を歩む人で、「将来を嘱望される検察官の一人」という。
検察OBによれば、東京地検特捜部にいた時には被疑者を呼びつけるのではなく、東京拘置所に出向いて取り調べを続けた。拘置所には当時、検事用の女性トイレがなかったが、この取り調べのために新たにつくられた、というエピソードを持つ。検察官としてなすべきことを誠実に実行する人、という。
従って、?から?の展開が予想される。どの展開になるかは、県警がきちんとした証拠をどれだけ固められるかにかかっている。捜査員たちの奮闘次第、と言っていい。この場合、吉村知事がどのように関わっていたかも問われることになる。
◇ ◇
吉村知事は若松氏の副知事再任にこだわるかのような発言を繰り返しているが、これは得意の目くらましだろう。知事はすでに3月下旬の段階で、別の副知事候補の選定作業に着手した形跡がある。
4月以降、県幹部が退職後に天下る外郭団体で異様な人事が進められた。県社会福祉協議会の会長と県産業技術振興機構の理事長はこれまで非常勤の名誉職だったが、それをどちらも常勤にして、それぞれ後任に退職したばかりの玉木康雄・前健康福祉部長と木村和浩・前産業労働部長を充てる人事である。
常勤化に伴い、両団体のトップの給与は年額120万円から500万円台に跳ね上がる。待遇以上に問題になったのは、両団体には常勤のナンバー2(専務理事)がいて実務を取り仕切っているが、新しいトップはどちらも彼らより年次が下であることだ。
前例踏襲と年功序列で生きてきた役人の世界で、こうしたことはかつてなかったことであり、あってはならないことだった。県庁の事務系OBでつくる親睦団体「平成松波会」のメンバーらは「いったい、何事だ」といぶかり、ざわついている。
OBの一人が解説する。「これは若松氏の副知事再任は困難と見て、病院事業管理者の大澤賢史氏か企業管理者の高橋広樹氏のどちらかを副知事に任命する準備ではないか。どちらかが副知事になれば、そのポストを埋めなければならない。どちらでも対応できるように外郭団体に2人の前部長をリザーブとして確保した、ということだろう。9月県議会で新しい副知事の人事案を提出するつもりではないか」
実に明快な解説だ。アップした報酬は税金で補填(ほてん)される。社会福祉や技術振興など二の次。自分たちの都合で外郭団体を自在に操ろうとする姿が透けて見えてくる。醜悪きわまりない。
◇ ◇
国有地を格安で払い下げた森友学園問題が表面化した際、当時の安倍晋三首相は「私や妻が関係していたということになれば、総理大臣も国会議員も辞める」と大見得を切った。その後、昭恵夫人が森友学園の名誉校長を引き受けていたことが分かり、安倍氏も深く関わっていたことが明らかになった。が、安倍氏は首相も国会議員も辞めなかった。
それどころか、加計学園問題でも「桜を見る会」の問題でもウソとごまかしを重ねた。安倍氏の目には、「法と規範を守ること」など単なる建前、と映っているのだろう。「政治は数と力であり、それがすべて」。そう考えているとしか思えない。
森友学園問題では公文書の改竄(かいざん)を命じられた近畿財務局の職員がことの経緯を記した文書を残して自ら命を絶った。その文書「赤木ファイル」が事件から何年もたって、ようやく開示された。こうしたことにも、何の心の痛みも感じないのだろう。

山形県の吉村美栄子氏は非自民系の知事であるにもかかわらず、その安倍氏とのツーショット写真を自慢げに披露する。彼女もまた「政治は数と力」と信じ、ごまかしを重ねて保身を図るタイプの政治家だ。私が県を相手に争った学校法人「東海山形学園」の財務書類の情報不開示訴訟に関しても、平気でウソを言い続けた。
サクランボのかぶり物をしてトップセールスに精を出す。もんぺ姿で農産物の売り込みに走り回る。そうした姿が親しみを感じさせるのか、県民の間での人気は依然として高い。しかし、彼女の言動からは、政治家として一番大切なこと、「政治を通して何を実現しようとしているのか」がまるで見えてこない。
こうした理念なき政治は何をもたらすか。政治学者の宇野重規(しげき)氏は「日本では今、民主主義の基本的な理念の部分が脅かされている」と警鐘を鳴らし、こう語る。
「自分たちが意見を言おうが言うまいが、議論をしようがしなかろうが、答えは決まっている。ならば誰か他の人が決めてくれればそれでいい――そういう諦めの感覚に支配されること。これこそが民主主義の最大の敵であり、脅威だと思います」
「私は三つのことを信じたいと思っています。自分たちにとって大切なことは、公開の場で透明性を確保して決定したい。政策決定に参加することで、誰もが当事者意識を持てる社会にしたい。そして社会の責任の一端を自発的に受け止めていきたい」(2021年6月17日付、朝日新聞オピニオン面)
若松前副知事の公職選挙法違反事件は、地方で起きた小さな事件の一つかもしれない。けれども、こうした事件をあいまいなまま終わらせれば、政治に対する諦めの感情はますます深まり、私たちの社会の土台が崩れていく。
それぞれが自分にできることを行い、小さな成果を一つひとつ積み重ねていく。そうすることでしか、社会を前に進めることはできない。
警察と検察には粛々と捜査を進め、事実を解明してほしい。そうすることが、前に進もうとする人たちを勇気づけることになる。
(長岡 昇 NPO「ブナの森」代表)
≪写真説明≫
◎山形県の副知事が不在になって3カ月。吉村知事の隣は空席のまま(6月19日付の産経新聞から)
◎ラフランスを手に首相官邸で安倍晋三氏と写真に納まる吉村美栄子知事(2016年11月28日)。この写真は山形県政記者クラブの加盟各社に送られた
良かれと思ってしたことでも、その者は被疑者として調べられ、容疑が固まれば起訴され、裁きを受ける。山形県の若松正俊・前副知事は今、そのようなイバラの道に立たされている。容疑は公職選挙法違反、公務員の地位利用である。

話は山形県知事選挙の告示の2週間前にさかのぼる。昨年の12月24日、佐藤孝弘・山形市長や丸山至・酒田市長ら8人の市長は現職の吉村美栄子知事ではなく、自民党が推す大内理加・元県議を推薦すると発表した。「今の県政の反応の鈍さ」や「市との感覚のずれ」を理由に、知事に反旗を翻したのだ。
事前の世論調査では,、すでに「現職の吉村氏が圧倒的に有利」との結果が出ていた。だが、吉村陣営はこうした動きを「好ましくない」と見たのだろう。市長らによれば、この前後に知事の補佐役の若松副知事が「対立候補の大内氏を推さないでほしい」「せめて中立でいてくれないか」と働きかけてきたという。
これだけだったら、まだ罪は軽い。問題は若松氏の働きかけがそれにとどまらなかったことだ。市長らの証言によれば、「向こうに付いたら不利益をこうむりますよ」とほのめかしたのだという。
酒田市に対しては、県と庄内地域の自治体による東北公益文科大学(公設民営)の公立化に向けた協議が「進められなくなる」と述べたという。ローカル鉄道「フラワー長井線」の赤字に苦しむ長井市と南陽市には「県の負担金をこれまでのように出すのは難しい」と、減額する可能性があることを伝えたようだ。
市長らの証言が事実とすれば、これは公職選挙法が禁じている「公務員の地位を利用した選挙運動もしくは事前運動」にあたる。特別職とはいえ、副知事は公務員である。それが選挙で選ばれた市長に圧力をかけたわけで、「信じられないような行為」と言っていい。
公選法の規定に触れるどころではない。「きわめて悪質な地位利用」であり、「2年以下の禁固または30万円以下の罰金」を科せられて当然の犯罪行為である。
関係者の証言によれば、こうした「副知事の地位を利用した脅し」をかけられた市長は7人いる。脅しをかけられなかったのは山形市長だけだったようだ。立場が強い市長は避け、弱い市長を狙ったということだろう。
7人の市長が口裏を合わせて「吉村知事と若松副知事を追い落とそうとしている」という可能性はある。だが、それはあくまでも可能性に過ぎず、「そのような口裏合わせはなかった」と断言していい。
なぜなら、知事選の投開票日の翌日(今年1月25日)、県幹部は酒田市に対して「東北公益文科大学の公立化に向けた準備作業を停止する」と伝えたからだ。県側もそれを認めている。長井市に対しても、「赤字ローカル線への補助金を確保するのは難しい」と通告した。つまり、若松副知事がほのめかしたことを県側は選挙が終わった途端、実行したのだ。
露骨と言うか、無防備と言うか。若松氏にしても彼の意向を伝えた県幹部にしても、それが「公務員の地位を利用した犯罪行為」を実質的に裏付けることになる、ということに思い至らなかったようだ。
知事選で敗北した自民党側はこうした事実を把握していた。それゆえに、吉村知事が県議会に「若松副知事を再任する人事案」を出してきたのに対して県議団は反対し、否決した(3月9日)。若松氏の任期は10日までだったので、山形県は「副知事不在」という異常事態に陥った。
ところが、吉村知事は若松氏を11日付で非常勤特別職にし、新型コロナウイルス対策などの連絡調整にあたる「特命補佐」に任命するという奇策に出た。「副知事」という肩書から「特命補佐」という肩書に変え、事実上続投させたのである。
首長と議会は地方自治の両輪である。議会には首長の施策をチェックするという重要な役割がある。人事案の同意権限もその役割を果たすためにある。「奇策」はそうした機能をあざわらうような暴挙と言わなければならない。
若松氏を議会の同意がいらない「特命補佐」に任命した理由について、知事は「余人をもって代えがたい」と説明した。人を小馬鹿にしたような、陳腐な説明である。
その若松氏に対して、山形県警は公職選挙法違反の疑いで捜査に乗り出した。市長とその周りの人たちから話を聴く証拠固めは終わり、捜査は被疑者本人、若松氏から事情聴取する段階に至っている。
若松氏がその地位を利用して圧力をかけたのが1人だけなら、捜査は難しい。「言った」「言ってない」の水掛け論になるからだ。が、なにせ相手は7人もいる。若松氏が否定しても、起訴して有罪に持ち込むのは難しいことではない。予想されたことだが、若松氏は「そんなことは言っていない」と全面的に否定したようだ。
証拠がそろっているのに被疑者が否認した場合、捜査当局は被疑者の逮捕や事務所、自宅などの家宅捜索をし、強制捜査に踏み切るのが常道だ。だが、県警はまだ着手していない。なぜか。事件はこれからどう展開するのか。
考えられるのは次の四つのシナリオである。
?県警は強制捜査に踏み切らないまま捜査を終えて山形地検に書類送検し、地検は不起訴処分にして事件そのものを握り潰す?強制捜査はしないまま書類送検し、地検が起訴、微罪で済ませる?強制捜査に踏み切って送検し、公職選挙法違反で起訴して断罪する?強制捜査し、公選法違反にとどまらず、若松氏の余罪を追及する。
このうち、?は考えにくい。山形地検の松下裕子(ひろこ)検事正はそのような姑息な対応をする人物とは思えないからだ。東京地検をはじめ首都圏の現場で捜査を担い、法務省での勤務も長い。検察の本流を歩む人で、「将来を嘱望される検察官の一人」という。
検察OBによれば、東京地検特捜部にいた時には被疑者を呼びつけるのではなく、東京拘置所に出向いて取り調べを続けた。拘置所には当時、検事用の女性トイレがなかったが、この取り調べのために新たにつくられた、というエピソードを持つ。検察官としてなすべきことを誠実に実行する人、という。
従って、?から?の展開が予想される。どの展開になるかは、県警がきちんとした証拠をどれだけ固められるかにかかっている。捜査員たちの奮闘次第、と言っていい。この場合、吉村知事がどのように関わっていたかも問われることになる。
◇ ◇
吉村知事は若松氏の副知事再任にこだわるかのような発言を繰り返しているが、これは得意の目くらましだろう。知事はすでに3月下旬の段階で、別の副知事候補の選定作業に着手した形跡がある。
4月以降、県幹部が退職後に天下る外郭団体で異様な人事が進められた。県社会福祉協議会の会長と県産業技術振興機構の理事長はこれまで非常勤の名誉職だったが、それをどちらも常勤にして、それぞれ後任に退職したばかりの玉木康雄・前健康福祉部長と木村和浩・前産業労働部長を充てる人事である。
常勤化に伴い、両団体のトップの給与は年額120万円から500万円台に跳ね上がる。待遇以上に問題になったのは、両団体には常勤のナンバー2(専務理事)がいて実務を取り仕切っているが、新しいトップはどちらも彼らより年次が下であることだ。
前例踏襲と年功序列で生きてきた役人の世界で、こうしたことはかつてなかったことであり、あってはならないことだった。県庁の事務系OBでつくる親睦団体「平成松波会」のメンバーらは「いったい、何事だ」といぶかり、ざわついている。
OBの一人が解説する。「これは若松氏の副知事再任は困難と見て、病院事業管理者の大澤賢史氏か企業管理者の高橋広樹氏のどちらかを副知事に任命する準備ではないか。どちらかが副知事になれば、そのポストを埋めなければならない。どちらでも対応できるように外郭団体に2人の前部長をリザーブとして確保した、ということだろう。9月県議会で新しい副知事の人事案を提出するつもりではないか」
実に明快な解説だ。アップした報酬は税金で補填(ほてん)される。社会福祉や技術振興など二の次。自分たちの都合で外郭団体を自在に操ろうとする姿が透けて見えてくる。醜悪きわまりない。
◇ ◇
国有地を格安で払い下げた森友学園問題が表面化した際、当時の安倍晋三首相は「私や妻が関係していたということになれば、総理大臣も国会議員も辞める」と大見得を切った。その後、昭恵夫人が森友学園の名誉校長を引き受けていたことが分かり、安倍氏も深く関わっていたことが明らかになった。が、安倍氏は首相も国会議員も辞めなかった。
それどころか、加計学園問題でも「桜を見る会」の問題でもウソとごまかしを重ねた。安倍氏の目には、「法と規範を守ること」など単なる建前、と映っているのだろう。「政治は数と力であり、それがすべて」。そう考えているとしか思えない。
森友学園問題では公文書の改竄(かいざん)を命じられた近畿財務局の職員がことの経緯を記した文書を残して自ら命を絶った。その文書「赤木ファイル」が事件から何年もたって、ようやく開示された。こうしたことにも、何の心の痛みも感じないのだろう。

山形県の吉村美栄子氏は非自民系の知事であるにもかかわらず、その安倍氏とのツーショット写真を自慢げに披露する。彼女もまた「政治は数と力」と信じ、ごまかしを重ねて保身を図るタイプの政治家だ。私が県を相手に争った学校法人「東海山形学園」の財務書類の情報不開示訴訟に関しても、平気でウソを言い続けた。
サクランボのかぶり物をしてトップセールスに精を出す。もんぺ姿で農産物の売り込みに走り回る。そうした姿が親しみを感じさせるのか、県民の間での人気は依然として高い。しかし、彼女の言動からは、政治家として一番大切なこと、「政治を通して何を実現しようとしているのか」がまるで見えてこない。
こうした理念なき政治は何をもたらすか。政治学者の宇野重規(しげき)氏は「日本では今、民主主義の基本的な理念の部分が脅かされている」と警鐘を鳴らし、こう語る。
「自分たちが意見を言おうが言うまいが、議論をしようがしなかろうが、答えは決まっている。ならば誰か他の人が決めてくれればそれでいい――そういう諦めの感覚に支配されること。これこそが民主主義の最大の敵であり、脅威だと思います」
「私は三つのことを信じたいと思っています。自分たちにとって大切なことは、公開の場で透明性を確保して決定したい。政策決定に参加することで、誰もが当事者意識を持てる社会にしたい。そして社会の責任の一端を自発的に受け止めていきたい」(2021年6月17日付、朝日新聞オピニオン面)
若松前副知事の公職選挙法違反事件は、地方で起きた小さな事件の一つかもしれない。けれども、こうした事件をあいまいなまま終わらせれば、政治に対する諦めの感情はますます深まり、私たちの社会の土台が崩れていく。
それぞれが自分にできることを行い、小さな成果を一つひとつ積み重ねていく。そうすることでしか、社会を前に進めることはできない。
警察と検察には粛々と捜査を進め、事実を解明してほしい。そうすることが、前に進もうとする人たちを勇気づけることになる。
(長岡 昇 NPO「ブナの森」代表)
≪写真説明≫
◎山形県の副知事が不在になって3カ月。吉村知事の隣は空席のまま(6月19日付の産経新聞から)
◎ラフランスを手に首相官邸で安倍晋三氏と写真に納まる吉村美栄子知事(2016年11月28日)。この写真は山形県政記者クラブの加盟各社に送られた
苦労して財を成した人が次に欲しがるものは、地位と名誉である。
「令和の政商」の異名を取る大樹(たいじゅ)総研グループの代表、矢島義也(よしなり)氏は2016年秋と2017年春の園遊会に「各界功績者」の一人として招待された。招待者名簿には本名の「矢島義成」と記されている。天皇と皇后が主催する赤坂御苑での催しに出席できたのだから、名誉欲は十分に満たされたことだろう。
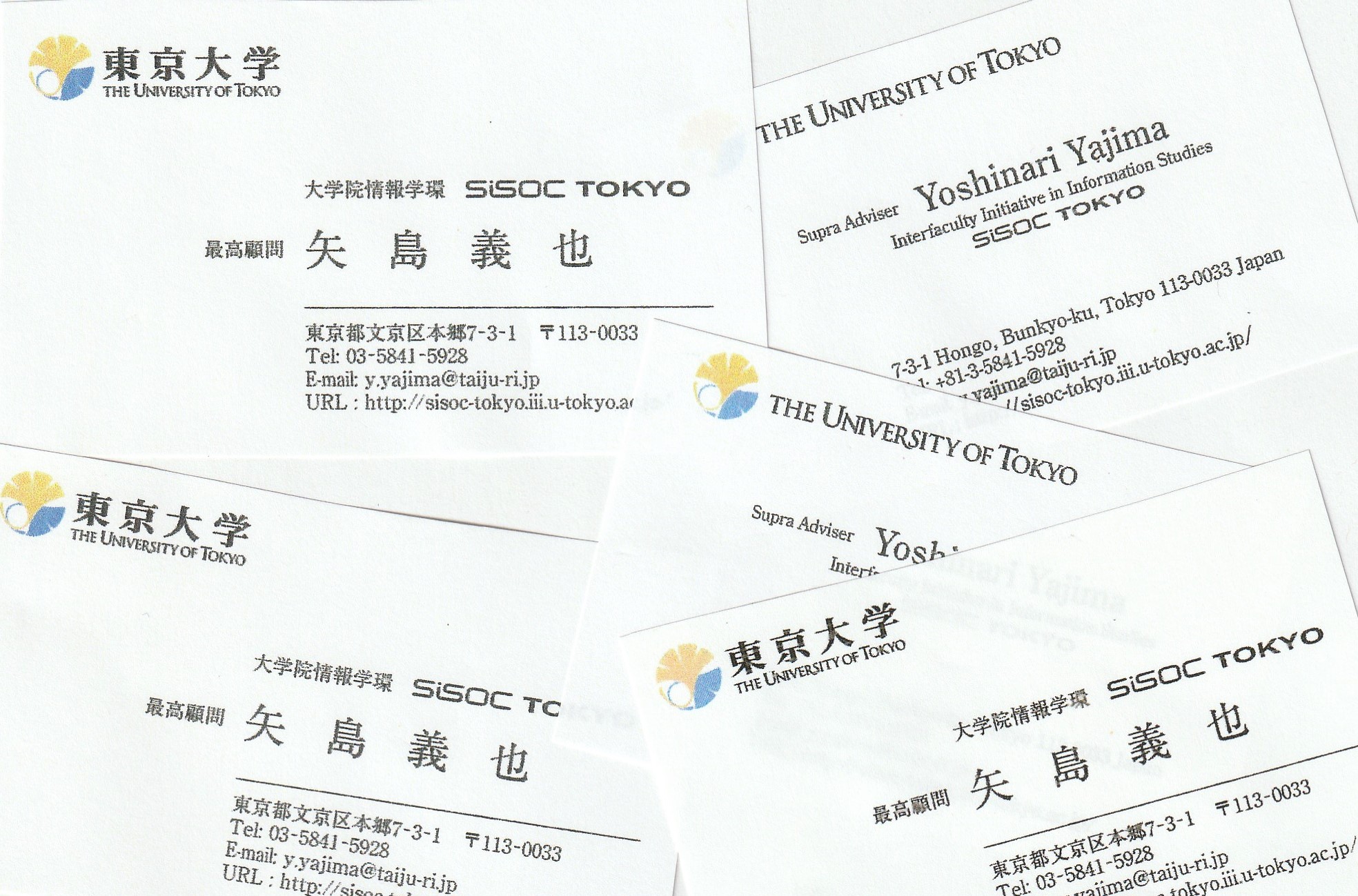
矢島氏は2016年5月に帝国ホテルで「結婚を祝う会」を開いた。彼は若いころに離婚しているので、これは再婚の披露宴である。祝う会の主賓は菅義偉・官房長官(当時)、乾杯の音頭は二階俊博・自民党総務会長(同)が取った。政財官界の要人300人余りが勢ぞろいした盛大な会だった。
園遊会には配偶者も招かれるが、内縁の妻は招かれない。矢島氏がこのタイミングで披露宴を開いたのは、夫婦そろって秋の園遊会に出席するためだったのかもしれない。配偶者にとっても、園遊会はこれ以上ない晴れ舞台だったはずだ。
これに先立って、矢島氏は「地位の確保」に向けても動き始めていた。狙いを定めたのは最高学府、東京大学である。
2014年ごろ、東大の大学院情報学環に寄付講座の申し入れがあった。名古屋市のベンチャー企業「ディー・ディー・エス(DDS)」の三吉野健滋社長が「サイバーセキュリティの共同研究のために3億円を提供したい」と申し入れてきた。
DDSは、指紋などによる生体認証のソフト開発と機器販売を目的に1995年に設立された。これが普及すれば、IDやパスワードを打ち込んで本人確認をする必要はなくなる。サイバーセキュリティの分野で注目を集めている技術の一つだ。
ただ、企業としての実績は乏しかった。DDSは東証マザーズに上場していたものの、株価は長く100円前後で低迷していた。寄付金は「三吉野社長がストックオプションで持っている株の売買益を充てる」との提案で、東大の関係者は「やや不安ではあった」と打ち明ける。
寄付講座新設の決め手になったのは、仲介者がサイバーセキュリティ分野の国内第一人者、安田浩・東大名誉教授(後に東京電機大学学長)だったからだ。「重鎮の安田先生の口添えで、しかもDDSにはほかの大学への寄付の実績もあった。学内の審査もすんなり通りました」と関係者は証言する。
この寄付を基に、東大は2015年に「情報学環セキュア情報化社会研究」という寄付講座を立ち上げ、「SISOC-TOKYO」というプロジェクトをスタートさせた。報道向けの資料によれば、その目的は「サイバーセキュリティの研究にとどまらず、国際的な視野に立った情報発信や政策提言を行う」と格調高かった。
プロジェクトを推進するため、東大は学内に加え外部からも研究者を招いた。東京電機大学や名古屋工業大学の教授を特任教授にし、元財務官僚や日本経済新聞の編集委員を客員教授として迎え入れた。
実はこの時、寄付者の三吉野社長と安田名誉教授は「大樹総研の矢島義也会長も客員教授として迎えてほしい」と打診していた。東大側は困惑し、「研究実績かそれに準ずるものがなければ、教授会で了承が得られません」と、これだけは押し返したのだという。
それでも、大樹総研はあきらめなかった。寄付講座が発足した後、今度は「東大情報学環と大樹総研で共同研究をまとめ、それを本にして出版したい」と提案してきた。東大のお墨付きで矢島氏の著書を世に出そうと考えたようだ。東大側はこれも断った。「大樹総研が示した論文のレベルが低過ぎて、とても出版に堪えられるような内容ではなかったから」という。
こうした一連の動きは、この寄付講座の真のスポンサーが誰かを明瞭に示している。寄付者として名乗り出たのはDDSだが、資金は大樹総研グループから出た、と見るのが自然だろう。
業を煮やしたのか、大樹総研の矢島氏は「東京大学 大学院情報学環 SiSOC TOKYO 最高顧問 矢島義也」という名刺を勝手に作り、配り始めた。東大のロゴと住所、寄付講座事務局の連絡先入りだ。もちろん、「最高顧問」などというポストは存在しない。「地位」も勝手に印刷してしまうところが政商らしい、と言うべきか。
これに気づいて東大側は抗議したが、受け流されたという。こうしたトラブルに加え、分割して振り込まれるはずの寄付金がしばしば滞ったこともあって、5年の計画で始まった寄付講座と共同研究は4年で打ち切られた。
この間、東証マザーズではDDSの株をめぐって不思議なことが起きていた。乱高下していたDDS株が2014年に入って急騰し、6月13日にはついに1株1,899円の高値を付けた。ほどなく株価は急落して「ナイアガラ状態」になり、元の200円台まで下がった
だが、DDS株の乱高下はその後も続き、「100万株の成り行き売り注文」「20万株の指し値買い注文がすぐさま取り消し」といったことが繰り返された。1株1,000円で100万株なら10億円の取引になる。株価の掲示板には「プロであれば、こんなことをやると業界から追放される。絶対にやらない。いったい誰だ」といった怒りの声が寄せられたりした。
こうした動きは、DDSの株価を操作して莫大な利益を得ようとした者がいたことを示している。東大大学院の寄付講座の新設も株価操作に利用された可能性が大きい。東大側はこうしたことを全く知らなかったようだ。筆者から指摘され、あわてて調べ始めている。
大樹総研グループがDDSの株価操作に関与したことを示す証拠は今のところない。だが、証券取引等監視委員会あるいは金融庁、検察、国税当局が本気になって調べれば、裏で何が起きていたのか、容易に分かるはずだ。
実際、金融庁は2011年にDDSの財務調査を行い、「システム開発や機器販売をめぐって架空取引があった」として「有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金の納付命令」を出している(10月3日付)。課徴金は3,330万円だった。
DDSの年間売上高は10億円から20億円ほどで、収支が赤字になることもしばしばだった。こうした業績から見ても、「社長のポケットマネーから東大に3億円を寄付する」といった単純な図式だったとは到底考えられない。
寄付には「善意の寄付」もある。が、同時に「寄付することでそれ以上の利益を上げることをもくろむ」という「悪意の寄付」もある。研究一筋で生きてきた人たちには、想像すらできないことだろう。
寄付講座の申し入れに関する東大のガイドラインはどうなっているのか。審査はどのように行われているのか。DDSと大樹総研の関係をどこまで把握していたのか。東大の本部に目下、問い合わせている。回答があれば、次の報告でお伝えしたい。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 89」 2021年6月14日
*追記:東京大学本部の広報課から回答がありました。「寄付金額は平成27年から平成30年までに年間6,000万円、総額2億4,000万円」「名刺については把握しており、安田浩氏(当時の特任教授)を通じて利用をやめるよう申し入れました。誠に遺憾であると考えています」とのこと。寄付の申し出は3億円でしたが、寄付講座を4年で打ち切ったため最後の1年分の寄付は受け取らなかったようです。寄付講座の新設についてのガイドラインはなく、ディー・ディー・エスが金融庁の課徴金納付命令を受けたことや同社と大樹総研グループとの関係は「把握しておりませんでした」と回答してきました(回答は2021年6月17日付)。
*初出:調査報道サイト「HUNTER」
https://news-hunter.org/?p=7252
≪写真説明≫
◎矢島義也氏が配っていた「東京大学 最高顧問」の名刺
*東大大学院寄付講座のプロジェクト名は「SISOC-TOKYO」だが、矢島義也氏の名刺では「SiSOC TOKYO」と、一部小文字になっている。
≪参考記事・資料&サイト≫
◎「令和の政商」矢島義也氏の正体(ウェブコラム「情報屋台」2020年11月7日)
http://www.johoyatai.com/3291
◎菅首相を抱き込む「令和の政商」(週刊新潮 2020年10月15日号)
◎政官界に浸透する「大樹総研」(月刊『選択』2018年8月号、9月号)
◎2017年春の園遊会招待者(2017年4月6日付、朝日新聞長野県版)
◎2016年秋の園遊会招待者(2016年10月21日付、朝日新聞長野県版)
◎矢島義也氏の「結婚を祝う会」の席次表(2016年5月29日、帝国ホテル)
◎有名俳優たちの秘密乱交パーティの夜(月刊『噂の眞相』1999年8月号)
◎東京大学大学院の寄付講座「情報学環セキュア情報化社会研究」に関する記者会見開催のお知らせ(2015年7月27日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400040786.pdf
◎株式会社ディー・ディー・エス(DDS)の公式サイト
https://www.dds.co.jp/ja/company/
◎東証マザーズにおけるDDSの株価の推移(Kabutan)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3782
◎マザーズが急落、変調を引き起こした犯人は誰だ?(会社四季報オンライン)
https://shikiho.jp/news/0/163888
◎最高顧問の矢島義也氏(YAHOO ファイナンス ディー・ディー・エス 掲示板)
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1003782/3782/107/395
◎株式会社ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(2011年10月3日、金融庁の公式サイト)
https://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111003-1.html
「令和の政商」の異名を取る大樹(たいじゅ)総研グループの代表、矢島義也(よしなり)氏は2016年秋と2017年春の園遊会に「各界功績者」の一人として招待された。招待者名簿には本名の「矢島義成」と記されている。天皇と皇后が主催する赤坂御苑での催しに出席できたのだから、名誉欲は十分に満たされたことだろう。
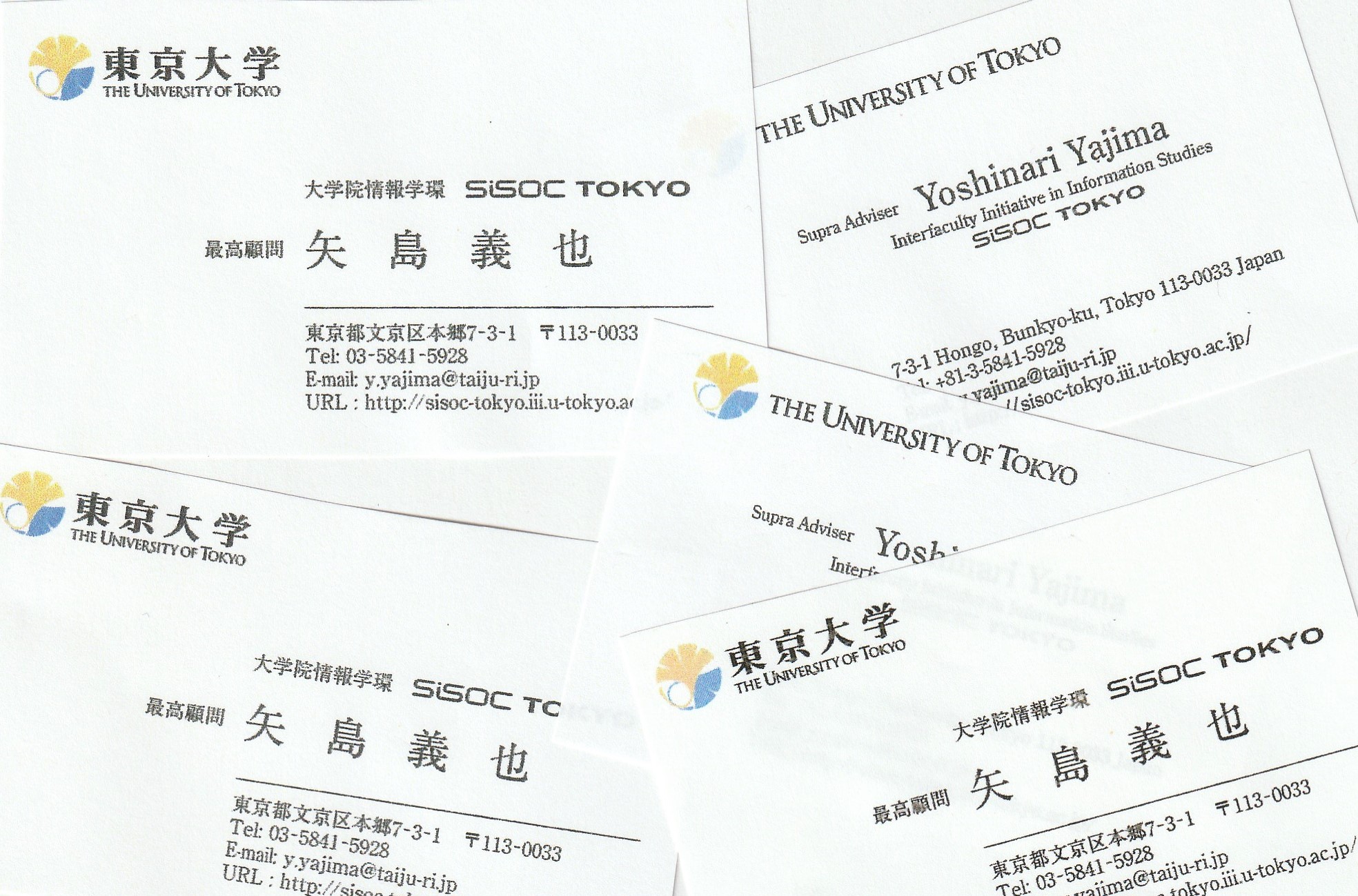
矢島氏は2016年5月に帝国ホテルで「結婚を祝う会」を開いた。彼は若いころに離婚しているので、これは再婚の披露宴である。祝う会の主賓は菅義偉・官房長官(当時)、乾杯の音頭は二階俊博・自民党総務会長(同)が取った。政財官界の要人300人余りが勢ぞろいした盛大な会だった。
園遊会には配偶者も招かれるが、内縁の妻は招かれない。矢島氏がこのタイミングで披露宴を開いたのは、夫婦そろって秋の園遊会に出席するためだったのかもしれない。配偶者にとっても、園遊会はこれ以上ない晴れ舞台だったはずだ。
これに先立って、矢島氏は「地位の確保」に向けても動き始めていた。狙いを定めたのは最高学府、東京大学である。
2014年ごろ、東大の大学院情報学環に寄付講座の申し入れがあった。名古屋市のベンチャー企業「ディー・ディー・エス(DDS)」の三吉野健滋社長が「サイバーセキュリティの共同研究のために3億円を提供したい」と申し入れてきた。
DDSは、指紋などによる生体認証のソフト開発と機器販売を目的に1995年に設立された。これが普及すれば、IDやパスワードを打ち込んで本人確認をする必要はなくなる。サイバーセキュリティの分野で注目を集めている技術の一つだ。
ただ、企業としての実績は乏しかった。DDSは東証マザーズに上場していたものの、株価は長く100円前後で低迷していた。寄付金は「三吉野社長がストックオプションで持っている株の売買益を充てる」との提案で、東大の関係者は「やや不安ではあった」と打ち明ける。
寄付講座新設の決め手になったのは、仲介者がサイバーセキュリティ分野の国内第一人者、安田浩・東大名誉教授(後に東京電機大学学長)だったからだ。「重鎮の安田先生の口添えで、しかもDDSにはほかの大学への寄付の実績もあった。学内の審査もすんなり通りました」と関係者は証言する。
この寄付を基に、東大は2015年に「情報学環セキュア情報化社会研究」という寄付講座を立ち上げ、「SISOC-TOKYO」というプロジェクトをスタートさせた。報道向けの資料によれば、その目的は「サイバーセキュリティの研究にとどまらず、国際的な視野に立った情報発信や政策提言を行う」と格調高かった。
プロジェクトを推進するため、東大は学内に加え外部からも研究者を招いた。東京電機大学や名古屋工業大学の教授を特任教授にし、元財務官僚や日本経済新聞の編集委員を客員教授として迎え入れた。
実はこの時、寄付者の三吉野社長と安田名誉教授は「大樹総研の矢島義也会長も客員教授として迎えてほしい」と打診していた。東大側は困惑し、「研究実績かそれに準ずるものがなければ、教授会で了承が得られません」と、これだけは押し返したのだという。
それでも、大樹総研はあきらめなかった。寄付講座が発足した後、今度は「東大情報学環と大樹総研で共同研究をまとめ、それを本にして出版したい」と提案してきた。東大のお墨付きで矢島氏の著書を世に出そうと考えたようだ。東大側はこれも断った。「大樹総研が示した論文のレベルが低過ぎて、とても出版に堪えられるような内容ではなかったから」という。
こうした一連の動きは、この寄付講座の真のスポンサーが誰かを明瞭に示している。寄付者として名乗り出たのはDDSだが、資金は大樹総研グループから出た、と見るのが自然だろう。
業を煮やしたのか、大樹総研の矢島氏は「東京大学 大学院情報学環 SiSOC TOKYO 最高顧問 矢島義也」という名刺を勝手に作り、配り始めた。東大のロゴと住所、寄付講座事務局の連絡先入りだ。もちろん、「最高顧問」などというポストは存在しない。「地位」も勝手に印刷してしまうところが政商らしい、と言うべきか。
これに気づいて東大側は抗議したが、受け流されたという。こうしたトラブルに加え、分割して振り込まれるはずの寄付金がしばしば滞ったこともあって、5年の計画で始まった寄付講座と共同研究は4年で打ち切られた。
この間、東証マザーズではDDSの株をめぐって不思議なことが起きていた。乱高下していたDDS株が2014年に入って急騰し、6月13日にはついに1株1,899円の高値を付けた。ほどなく株価は急落して「ナイアガラ状態」になり、元の200円台まで下がった
だが、DDS株の乱高下はその後も続き、「100万株の成り行き売り注文」「20万株の指し値買い注文がすぐさま取り消し」といったことが繰り返された。1株1,000円で100万株なら10億円の取引になる。株価の掲示板には「プロであれば、こんなことをやると業界から追放される。絶対にやらない。いったい誰だ」といった怒りの声が寄せられたりした。
こうした動きは、DDSの株価を操作して莫大な利益を得ようとした者がいたことを示している。東大大学院の寄付講座の新設も株価操作に利用された可能性が大きい。東大側はこうしたことを全く知らなかったようだ。筆者から指摘され、あわてて調べ始めている。
大樹総研グループがDDSの株価操作に関与したことを示す証拠は今のところない。だが、証券取引等監視委員会あるいは金融庁、検察、国税当局が本気になって調べれば、裏で何が起きていたのか、容易に分かるはずだ。
実際、金融庁は2011年にDDSの財務調査を行い、「システム開発や機器販売をめぐって架空取引があった」として「有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金の納付命令」を出している(10月3日付)。課徴金は3,330万円だった。
DDSの年間売上高は10億円から20億円ほどで、収支が赤字になることもしばしばだった。こうした業績から見ても、「社長のポケットマネーから東大に3億円を寄付する」といった単純な図式だったとは到底考えられない。
寄付には「善意の寄付」もある。が、同時に「寄付することでそれ以上の利益を上げることをもくろむ」という「悪意の寄付」もある。研究一筋で生きてきた人たちには、想像すらできないことだろう。
寄付講座の申し入れに関する東大のガイドラインはどうなっているのか。審査はどのように行われているのか。DDSと大樹総研の関係をどこまで把握していたのか。東大の本部に目下、問い合わせている。回答があれば、次の報告でお伝えしたい。
長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)
*メールマガジン「風切通信 89」 2021年6月14日
*追記:東京大学本部の広報課から回答がありました。「寄付金額は平成27年から平成30年までに年間6,000万円、総額2億4,000万円」「名刺については把握しており、安田浩氏(当時の特任教授)を通じて利用をやめるよう申し入れました。誠に遺憾であると考えています」とのこと。寄付の申し出は3億円でしたが、寄付講座を4年で打ち切ったため最後の1年分の寄付は受け取らなかったようです。寄付講座の新設についてのガイドラインはなく、ディー・ディー・エスが金融庁の課徴金納付命令を受けたことや同社と大樹総研グループとの関係は「把握しておりませんでした」と回答してきました(回答は2021年6月17日付)。
*初出:調査報道サイト「HUNTER」
https://news-hunter.org/?p=7252
≪写真説明≫
◎矢島義也氏が配っていた「東京大学 最高顧問」の名刺
*東大大学院寄付講座のプロジェクト名は「SISOC-TOKYO」だが、矢島義也氏の名刺では「SiSOC TOKYO」と、一部小文字になっている。
≪参考記事・資料&サイト≫
◎「令和の政商」矢島義也氏の正体(ウェブコラム「情報屋台」2020年11月7日)
http://www.johoyatai.com/3291
◎菅首相を抱き込む「令和の政商」(週刊新潮 2020年10月15日号)
◎政官界に浸透する「大樹総研」(月刊『選択』2018年8月号、9月号)
◎2017年春の園遊会招待者(2017年4月6日付、朝日新聞長野県版)
◎2016年秋の園遊会招待者(2016年10月21日付、朝日新聞長野県版)
◎矢島義也氏の「結婚を祝う会」の席次表(2016年5月29日、帝国ホテル)
◎有名俳優たちの秘密乱交パーティの夜(月刊『噂の眞相』1999年8月号)
◎東京大学大学院の寄付講座「情報学環セキュア情報化社会研究」に関する記者会見開催のお知らせ(2015年7月27日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400040786.pdf
◎株式会社ディー・ディー・エス(DDS)の公式サイト
https://www.dds.co.jp/ja/company/
◎東証マザーズにおけるDDSの株価の推移(Kabutan)
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3782
◎マザーズが急落、変調を引き起こした犯人は誰だ?(会社四季報オンライン)
https://shikiho.jp/news/0/163888
◎最高顧問の矢島義也氏(YAHOO ファイナンス ディー・ディー・エス 掲示板)
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1003782/3782/107/395
◎株式会社ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(2011年10月3日、金融庁の公式サイト)
https://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111003-1.html
2021年の第9回最上川縦断カヌー探訪の開催要項とコース図をアップしました。
参加申込の受け付けは6月21日からです。よろしくお願いいたします。
参加申込の受け付けは6月21日からです。よろしくお願いいたします。
東北の北部と北海道南部にある縄文時代の遺跡群がユネスコの世界遺産に登録される見通しになった。青森市の三内丸山遺跡や秋田県鹿角(かづの)市の大湯環状列石など17の遺跡が対象で、7月中旬に開かれる世界遺産委員会で正式に決定される。

三内丸山遺跡では、クリの巨木を使った六本柱の建造物や長さ32メートルもの大型竪穴式住居が見つかり、「狩猟採集で細々と暮らしていた」というそれまでの縄文のイメージを覆した。大湯の環状列石も最大径が50メートルを超し、その大規模さが際立つ。
さらに、青森県外ヶ浜町の大平(おおだい)山元遺跡からは、1万6000年前のものと推定される土器片が見つかっている。これはエジプトやメソポタミアで発見された土器より古く、「世界最古の土器」の一つと見られている。世界遺産にふさわしい遺跡群であり、むしろ登録が遅すぎたくらいである。
縄文時代については、まだ決着のつかない問題が多い。そもそも、縄文時代はいつ始まり、いつごろ農耕を伴う弥生時代に移行したと考えるべきか。それすら論争が続いており、定まっていない。
この時代の遺跡はなぜ北海道や東北に多く、西日本には少ないのか。これも大きな謎の一つだ。国立民族学博物館の小山修三・名誉教授は、発見された遺跡などをベースに「縄文時代の人口」を推計し、「4000年前の人口は26万人。西日本の人口は東日本の10分の1以下だった」との説を発表している(『縄文学への道』)。
その偏りの理由は何か。クリやクルミ、ドングリなど縄文人の生活を支えた堅果類が東日本の方に多かったから、といった説もあるが、腑に落ちない。
私がもっとも説得力があると考えるのは「超巨大噴火説」である。火山学や地質学の研究によって、今から7300年前に九州南部でとてつもない巨大噴火が起きたことが分かっている。
薩摩半島の南50キロにある「鬼界(きかい)カルデラ」である。噴火によってできた巨大なカルデラは海底にあって見えないが、噴煙は3万メートル上空に達し、噴き出した火砕流は屋久島や種子島をのみ込み、海を越えて鹿児島南部に達したとされる。
『歴史を変えた火山噴火』(石弘之)によれば、この時の火砕流の規模は、私たちの記憶に残る雲仙普賢岳の火砕流(1991年)の数十万倍という。火山灰は九州全土に厚く積もり、西日本全体にも降り注いだ。この噴火によって、西日本の縄文遺跡の多くは火山灰の下に埋もれ、人間が暮らすこともかなりの期間困難になった、というのが「超巨大噴火説」である。
この説によれば、縄文時代に西日本に人がいなかったわけではなく、集落は厚い火山灰の下に埋もれてしまった、ということになる。これなら、西日本で発見される縄文遺跡が少なく、それをベースにした人口推計も小さくなる理由が説明できる。
その影響は東日本にも及んだはずである。小山修三氏の推計では、縄文時代の人口は早期から増え続け、中期にピークに達し、その後、全体として激減したとされる。そうした人口の推移も九州で超巨大噴火があったと考えれば、整合性をもって説明できる。
九州南部には鬼界カルデラのほかにも、薩摩半島と大隅半島の間にある阿多(あた)カルデラ、桜島周辺の姶良(あいら)カルデラ、阿蘇カルデラなど超巨大噴火でできたものがあり、それらが帯状に連なる。
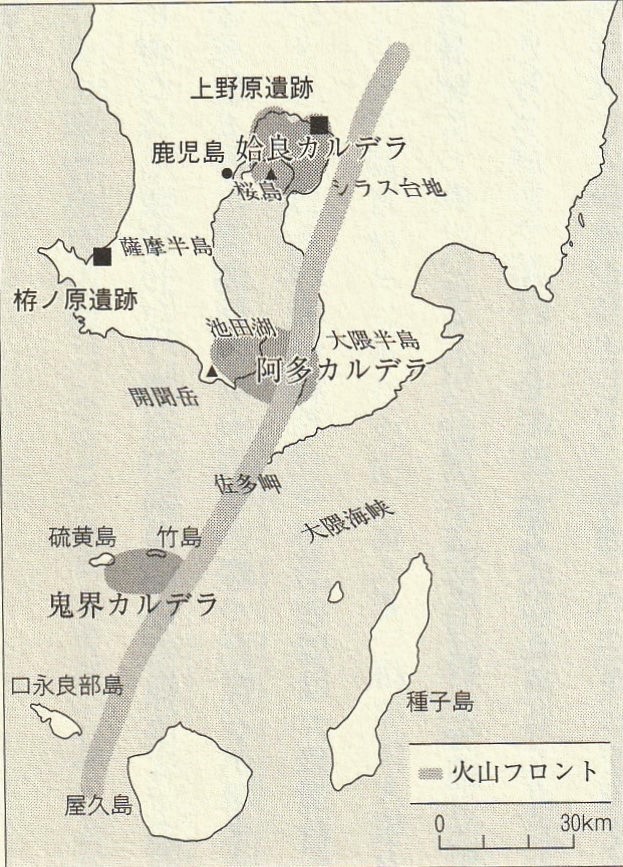
もちろん、九州だけではない。北海道の屈斜路湖や支笏湖、青森・秋田県境にある十和田湖も超巨大噴火でできたカルデラに水がたまってできたものだ。これらの噴火のエネルギーは、富士山の宝永噴火(1707年)や浅間山の天明噴火(1783年)、会津磐梯山の噴火(1888年)とは比べものにならないほど巨大なものだ。
世界に目を向ければ、アメリカ西部のイエローストーン国立公園やインドネシア・スマトラ島のトバ湖は、遠い昔に起きた超巨大噴火によってできたものだ。いずれも、地球全体の気候に影響を及ぼすほどの噴火だったとされる。
ただし、イエローストーンの最後の噴火は64万年前、トバ湖の噴火は7万4000年前で、地質調査などから分かるだけだ。歴史的な記録は何もない。その点では、鬼界カルデラの噴火と変わらない。こうした噴火の周期は数万年あるいは数十万年と推定されている。
東日本大震災と福島の原発事故の後、日本では「1000年前の貞観地震にも目を向けるべきだった」といった反省がなされたが、超巨大噴火はそれよりはるかに長いスパンで考えなければならない。科学や政治の舞台で正面から扱うのは難しい面がある。
けれども、危機管理の要諦が「最悪の事態も想定しておく」ということであれば、「頭の片隅に置いておかなければならないシナリオの一つ」であることは間違いない。46億年の地球の歴史から見れば、数万年など「誤差の範囲」とも言えるからだ。
神戸大学大学院の巽(たつみ)好幸教授と鈴木桂子准教授は2014年10月、日本で起きた超巨大噴火を詳しく調べ、「日本で今後100年間に超巨大噴火が起きる確率は1%」と発表した。その確率をどう受け止めるかは難しい問題だ。
「勇気ある提言」と見るか、「荒唐無稽な研究」と見るか。私は「無視できない確率」と見る。
*メールマガジン「風切通信 88」 2021年5月30日
≪参考文献・記事&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎「縄文遺跡群、世界遺産へ」(朝日新聞2021年5月27日付)
◎土器(ウィキペディア)
◎『縄文学への道』(小山修三、NHKブックス)
◎「縄文人口シミュレーション」(小山修三、杉藤重信)
file:///C:/Users/nagao/Downloads/KH_009_1_001%20(1).pdf
◎『歴史を変えた火山噴火』(石弘之、刀水書房)
◎『クラカトアの大噴火』(サイモン・ウィンチェスター、早川書房)
◎「巨大カルデラ噴火のメカニズムとリスク」(神戸大学の公式サイト)
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2014_10_22_01.html
≪写真説明&Source≫
◎2018年12月24日のクラカトア火山の噴火。この時の噴火は超巨大噴火ではなかった(インドネシア語の発音は「クラカタウ」)
https://www.huffingtonpost.jp/2018/12/25/what-anak-krakatau_a_23626685/
◎九州南部の巨大カルデラ(『歴史を変えた火山噴火』p47から複写)

三内丸山遺跡では、クリの巨木を使った六本柱の建造物や長さ32メートルもの大型竪穴式住居が見つかり、「狩猟採集で細々と暮らしていた」というそれまでの縄文のイメージを覆した。大湯の環状列石も最大径が50メートルを超し、その大規模さが際立つ。
さらに、青森県外ヶ浜町の大平(おおだい)山元遺跡からは、1万6000年前のものと推定される土器片が見つかっている。これはエジプトやメソポタミアで発見された土器より古く、「世界最古の土器」の一つと見られている。世界遺産にふさわしい遺跡群であり、むしろ登録が遅すぎたくらいである。
縄文時代については、まだ決着のつかない問題が多い。そもそも、縄文時代はいつ始まり、いつごろ農耕を伴う弥生時代に移行したと考えるべきか。それすら論争が続いており、定まっていない。
この時代の遺跡はなぜ北海道や東北に多く、西日本には少ないのか。これも大きな謎の一つだ。国立民族学博物館の小山修三・名誉教授は、発見された遺跡などをベースに「縄文時代の人口」を推計し、「4000年前の人口は26万人。西日本の人口は東日本の10分の1以下だった」との説を発表している(『縄文学への道』)。
その偏りの理由は何か。クリやクルミ、ドングリなど縄文人の生活を支えた堅果類が東日本の方に多かったから、といった説もあるが、腑に落ちない。
私がもっとも説得力があると考えるのは「超巨大噴火説」である。火山学や地質学の研究によって、今から7300年前に九州南部でとてつもない巨大噴火が起きたことが分かっている。
薩摩半島の南50キロにある「鬼界(きかい)カルデラ」である。噴火によってできた巨大なカルデラは海底にあって見えないが、噴煙は3万メートル上空に達し、噴き出した火砕流は屋久島や種子島をのみ込み、海を越えて鹿児島南部に達したとされる。
『歴史を変えた火山噴火』(石弘之)によれば、この時の火砕流の規模は、私たちの記憶に残る雲仙普賢岳の火砕流(1991年)の数十万倍という。火山灰は九州全土に厚く積もり、西日本全体にも降り注いだ。この噴火によって、西日本の縄文遺跡の多くは火山灰の下に埋もれ、人間が暮らすこともかなりの期間困難になった、というのが「超巨大噴火説」である。
この説によれば、縄文時代に西日本に人がいなかったわけではなく、集落は厚い火山灰の下に埋もれてしまった、ということになる。これなら、西日本で発見される縄文遺跡が少なく、それをベースにした人口推計も小さくなる理由が説明できる。
その影響は東日本にも及んだはずである。小山修三氏の推計では、縄文時代の人口は早期から増え続け、中期にピークに達し、その後、全体として激減したとされる。そうした人口の推移も九州で超巨大噴火があったと考えれば、整合性をもって説明できる。
九州南部には鬼界カルデラのほかにも、薩摩半島と大隅半島の間にある阿多(あた)カルデラ、桜島周辺の姶良(あいら)カルデラ、阿蘇カルデラなど超巨大噴火でできたものがあり、それらが帯状に連なる。
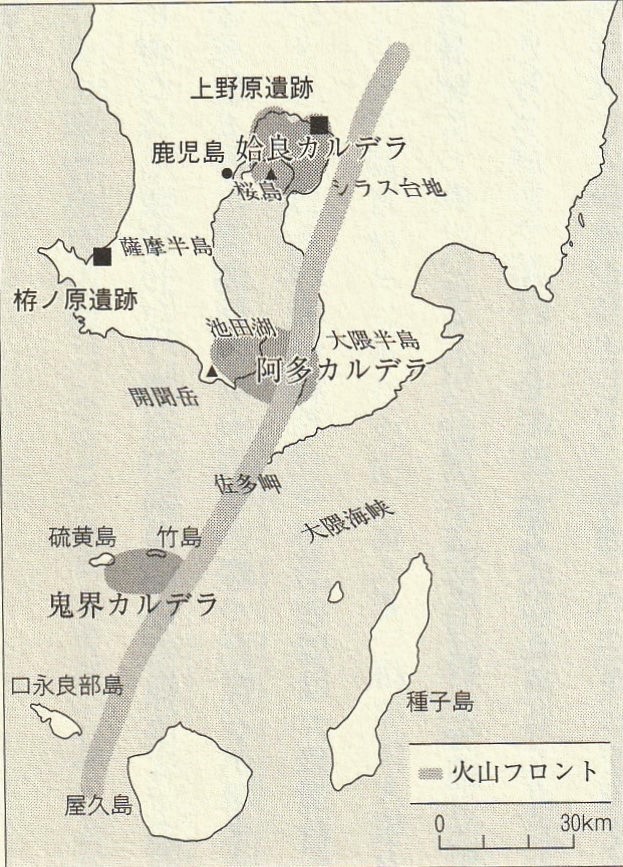
もちろん、九州だけではない。北海道の屈斜路湖や支笏湖、青森・秋田県境にある十和田湖も超巨大噴火でできたカルデラに水がたまってできたものだ。これらの噴火のエネルギーは、富士山の宝永噴火(1707年)や浅間山の天明噴火(1783年)、会津磐梯山の噴火(1888年)とは比べものにならないほど巨大なものだ。
世界に目を向ければ、アメリカ西部のイエローストーン国立公園やインドネシア・スマトラ島のトバ湖は、遠い昔に起きた超巨大噴火によってできたものだ。いずれも、地球全体の気候に影響を及ぼすほどの噴火だったとされる。
ただし、イエローストーンの最後の噴火は64万年前、トバ湖の噴火は7万4000年前で、地質調査などから分かるだけだ。歴史的な記録は何もない。その点では、鬼界カルデラの噴火と変わらない。こうした噴火の周期は数万年あるいは数十万年と推定されている。
東日本大震災と福島の原発事故の後、日本では「1000年前の貞観地震にも目を向けるべきだった」といった反省がなされたが、超巨大噴火はそれよりはるかに長いスパンで考えなければならない。科学や政治の舞台で正面から扱うのは難しい面がある。
けれども、危機管理の要諦が「最悪の事態も想定しておく」ということであれば、「頭の片隅に置いておかなければならないシナリオの一つ」であることは間違いない。46億年の地球の歴史から見れば、数万年など「誤差の範囲」とも言えるからだ。
神戸大学大学院の巽(たつみ)好幸教授と鈴木桂子准教授は2014年10月、日本で起きた超巨大噴火を詳しく調べ、「日本で今後100年間に超巨大噴火が起きる確率は1%」と発表した。その確率をどう受け止めるかは難しい問題だ。
「勇気ある提言」と見るか、「荒唐無稽な研究」と見るか。私は「無視できない確率」と見る。
*メールマガジン「風切通信 88」 2021年5月30日
≪参考文献・記事&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎「縄文遺跡群、世界遺産へ」(朝日新聞2021年5月27日付)
◎土器(ウィキペディア)
◎『縄文学への道』(小山修三、NHKブックス)
◎「縄文人口シミュレーション」(小山修三、杉藤重信)
file:///C:/Users/nagao/Downloads/KH_009_1_001%20(1).pdf
◎『歴史を変えた火山噴火』(石弘之、刀水書房)
◎『クラカトアの大噴火』(サイモン・ウィンチェスター、早川書房)
◎「巨大カルデラ噴火のメカニズムとリスク」(神戸大学の公式サイト)
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2014_10_22_01.html
≪写真説明&Source≫
◎2018年12月24日のクラカトア火山の噴火。この時の噴火は超巨大噴火ではなかった(インドネシア語の発音は「クラカタウ」)
https://www.huffingtonpost.jp/2018/12/25/what-anak-krakatau_a_23626685/
◎九州南部の巨大カルデラ(『歴史を変えた火山噴火』p47から複写)
繊維状の鉱物であるアスベスト(石綿)には、長い歴史がある。古代エジプトではミイラを包む布として使われ、ギリシャではランプの芯として利用された。中国では「火浣布(かかんぷ)」と呼ばれ、貢ぎ物として珍重された。石綿でつくった布を火に投じると、汚れだけ燃えてまたきれいになるからだ。

そのアスベストが社会で広く使われるようになったのは20世紀に入ってからである。日本では戦後、大量に輸入され、建設現場や工場で断熱材や絶縁材として使用された。産業界では「奇跡の鉱物」と呼ばれたりした。
だが、「きれいなバラにはトゲがある」の例え通り、アスベストにも「トゲ」があった。微細な繊維を吸い込むと、やがて肺がんや中皮腫を引き起こす。一部の研究者は早くからその危険性を指摘していた。長い歳月を経て発病することから「静かな時限爆弾」と呼ぶ人もいた。
にもかかわらず、政府も業界もそうした声に耳を傾けなかった。建物の防火材や断熱材にとどまらず、化学プラントの配管接続材など用途は広く、「経済発展に欠かせない」と考えたからだ。その構図は、有機水銀が水俣病の原因と指摘されても政府や企業が否定し続けた歴史と重なる。
アスベストが原因で命と健康を奪われた人たちが起こした裁判にようやく決着がついた。最高裁判所は5月17日、政府と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出した。政府が吹き付けアスベストの使用を禁止した1975年から46年、大阪・泉南アスベスト訴訟の提訴(2006年)から15年。この国では、まっとうな結論に至るまで、何事も長い年月を要する。
最高裁が被害者救済の根拠にしたのは、労働安全衛生法という法律である。この法律は1972年、労働基準法にあった労災防止関係の規定を分離・独立させ、より充実させて制定したものだ。
労働基準法が、雇用する側に労働時間の制限や差別的取り扱いの禁止など「最低限守るべきこと」を定めているのに対して、労働安全衛生法は雇用側に「快適な職場環境」をつくることを義務づけている。
つまり、雇用する側に対して、制限を超える長時間労働や国籍・性別などによる差別的取り扱いが許されないのは当然のことであり、さらに一歩進めて「働く者が安全で健康な状態で働けるような職場環境をつくりなさい」と求めているのである。
何とまっとうな法律であることか。アスベスト訴訟はこの法律にあらためて光を当て、世に広く知らしめることになった。愛する者を失った悲しみと病による苦しみを乗り越え、長い裁判を闘ってきた人たちの大きな功績と言わなければならない。
昔に比べれば大きく前進したとはいえ、働く者の立場は依然として著しく弱い。「安全で健康な職場環境」とは程遠い状態で働いている人が何と多いことか。差別やパワハラがまかり通っているのが現実だ。
私が暮らしている山形県でも最近、陰湿なパワハラ事件が発覚した。その舞台となったのは山形県総合文化芸術館(やまぎん県民ホール)である。山形県はこの新しい県民ホールを2019年秋に完成させ、その指定管理者にサントリーパブリシティサービスを中心とする共同企業体を選んだ。その会社の幹部がパワハラを繰り返していた。
この会社によるホールの運営は、当初から摩擦が絶えなかった。地元スタッフの退職が相次ぎ、幹部による特定の女性社員に対するパワハラが常態化していた。彼女は「睡眠障害と適応障害の疑い」と診断され、山形労働基準監督署に労災申請をして認定された。彼女を支援してきた労働組合が今年の4月末に記者会見して明らかにした。
本人から事前に詳しく話を聞く機会があった。上司が日々、信じられないような言動を繰り返していた。極め付きは「あなたは生きていることが恥ずかしいですか?」という発言だ。
2019年9月17日、本社から社長らが来訪して山形市内で懇親会が開かれた。その席で、県民ホールの支配人が場を盛り上げようとして「皆さん、今まで恥ずかしかったエピソードを披露していきましょう」と水を向けた。その時、副支配人が彼女にささやいたのだという。
その席には複数の地元スタッフがおり、近くにいた人にも聞こえた。サントリー側も否定することはできず、こうした発言も労災認定の決め手になったと思われる。
アスベスト被害でも、このパワハラでも、その根底にあるのは「働く者の安全と健康より利益追求を優先する姿勢」である。法律で「それは許されないことですよ」と規定しても、それに思いをいたすことなく、平気で違法なことをする人たちがいる。
企業の経営者や雇用主は、労働安全衛生法が何を求めているのか、あらためて読み返さなければなるまい。そして、働く者の憲章とも言うべき「労働基準法」の文言もかみしめてほしい。労働基準法は、その第1条(労働条件の原則)で次のように規定している。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」
労働基準法の制定は1947年、戦後間もなくだった。その頃、国民は敗戦の焼け跡の中で食うや食わずの生活をし、巷には失業者があふれていた。多くの人にとって「人たるに値する生活」など夢物語のような状況だった。
それでも、法律をつくった人たちは、日々の糧を得ることの先を見据えて、この言葉を盛り込まないではいられなかったのだろう。未来を信じ、その実現を後に続く人たちに託したのである。
人たるに値する生活。重い言葉であり、はるかなる道である。
*メールマガジン「風切通信 87」 2021年5月21日
*山形県総合文化芸術館の指定管理者については、山形県当局がきわめて不明朗な選定手続きをしており、2019年3月29日の風切通信55でその内実をお伝えしました。ご参照ください。
≪参考サイト&記事≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎石綿(ウィキペディア)
◎中皮腫について(独立行政法人環境再生保全機構のサイト)
https://www.erca.go.jp/asbestos/mesothelioma/what/what_about.html
◎「国・石綿建材業者に賠償責任 最高裁、初の統一判断」(2021年5月18日付、朝日新聞)
◎「建設石綿、国と企業の責任認める 最高裁が統一判断」(2021年5月17日、日本経済新聞電子版)
◎大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟(ウィキペディア)
◎労働安全衛生法(ウィキペディア)、労働基準法(同)
◎労働安全衛生法律とは? 経営者がやるべきことをわかりやすく解説
https://squareup.com/jp/ja/townsquare/what-is-industrial-safety-and-health-act
≪写真説明&Source≫
◎アスベスト訴訟で勝訴し、垂れ幕を掲げる原告団(日経新聞電子版2021年5月17日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE14BXJ0U1A510C2000000/

そのアスベストが社会で広く使われるようになったのは20世紀に入ってからである。日本では戦後、大量に輸入され、建設現場や工場で断熱材や絶縁材として使用された。産業界では「奇跡の鉱物」と呼ばれたりした。
だが、「きれいなバラにはトゲがある」の例え通り、アスベストにも「トゲ」があった。微細な繊維を吸い込むと、やがて肺がんや中皮腫を引き起こす。一部の研究者は早くからその危険性を指摘していた。長い歳月を経て発病することから「静かな時限爆弾」と呼ぶ人もいた。
にもかかわらず、政府も業界もそうした声に耳を傾けなかった。建物の防火材や断熱材にとどまらず、化学プラントの配管接続材など用途は広く、「経済発展に欠かせない」と考えたからだ。その構図は、有機水銀が水俣病の原因と指摘されても政府や企業が否定し続けた歴史と重なる。
アスベストが原因で命と健康を奪われた人たちが起こした裁判にようやく決着がついた。最高裁判所は5月17日、政府と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出した。政府が吹き付けアスベストの使用を禁止した1975年から46年、大阪・泉南アスベスト訴訟の提訴(2006年)から15年。この国では、まっとうな結論に至るまで、何事も長い年月を要する。
最高裁が被害者救済の根拠にしたのは、労働安全衛生法という法律である。この法律は1972年、労働基準法にあった労災防止関係の規定を分離・独立させ、より充実させて制定したものだ。
労働基準法が、雇用する側に労働時間の制限や差別的取り扱いの禁止など「最低限守るべきこと」を定めているのに対して、労働安全衛生法は雇用側に「快適な職場環境」をつくることを義務づけている。
つまり、雇用する側に対して、制限を超える長時間労働や国籍・性別などによる差別的取り扱いが許されないのは当然のことであり、さらに一歩進めて「働く者が安全で健康な状態で働けるような職場環境をつくりなさい」と求めているのである。
何とまっとうな法律であることか。アスベスト訴訟はこの法律にあらためて光を当て、世に広く知らしめることになった。愛する者を失った悲しみと病による苦しみを乗り越え、長い裁判を闘ってきた人たちの大きな功績と言わなければならない。
昔に比べれば大きく前進したとはいえ、働く者の立場は依然として著しく弱い。「安全で健康な職場環境」とは程遠い状態で働いている人が何と多いことか。差別やパワハラがまかり通っているのが現実だ。
私が暮らしている山形県でも最近、陰湿なパワハラ事件が発覚した。その舞台となったのは山形県総合文化芸術館(やまぎん県民ホール)である。山形県はこの新しい県民ホールを2019年秋に完成させ、その指定管理者にサントリーパブリシティサービスを中心とする共同企業体を選んだ。その会社の幹部がパワハラを繰り返していた。
この会社によるホールの運営は、当初から摩擦が絶えなかった。地元スタッフの退職が相次ぎ、幹部による特定の女性社員に対するパワハラが常態化していた。彼女は「睡眠障害と適応障害の疑い」と診断され、山形労働基準監督署に労災申請をして認定された。彼女を支援してきた労働組合が今年の4月末に記者会見して明らかにした。
本人から事前に詳しく話を聞く機会があった。上司が日々、信じられないような言動を繰り返していた。極め付きは「あなたは生きていることが恥ずかしいですか?」という発言だ。
2019年9月17日、本社から社長らが来訪して山形市内で懇親会が開かれた。その席で、県民ホールの支配人が場を盛り上げようとして「皆さん、今まで恥ずかしかったエピソードを披露していきましょう」と水を向けた。その時、副支配人が彼女にささやいたのだという。
その席には複数の地元スタッフがおり、近くにいた人にも聞こえた。サントリー側も否定することはできず、こうした発言も労災認定の決め手になったと思われる。
アスベスト被害でも、このパワハラでも、その根底にあるのは「働く者の安全と健康より利益追求を優先する姿勢」である。法律で「それは許されないことですよ」と規定しても、それに思いをいたすことなく、平気で違法なことをする人たちがいる。
企業の経営者や雇用主は、労働安全衛生法が何を求めているのか、あらためて読み返さなければなるまい。そして、働く者の憲章とも言うべき「労働基準法」の文言もかみしめてほしい。労働基準法は、その第1条(労働条件の原則)で次のように規定している。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」
労働基準法の制定は1947年、戦後間もなくだった。その頃、国民は敗戦の焼け跡の中で食うや食わずの生活をし、巷には失業者があふれていた。多くの人にとって「人たるに値する生活」など夢物語のような状況だった。
それでも、法律をつくった人たちは、日々の糧を得ることの先を見据えて、この言葉を盛り込まないではいられなかったのだろう。未来を信じ、その実現を後に続く人たちに託したのである。
人たるに値する生活。重い言葉であり、はるかなる道である。
*メールマガジン「風切通信 87」 2021年5月21日
*山形県総合文化芸術館の指定管理者については、山形県当局がきわめて不明朗な選定手続きをしており、2019年3月29日の風切通信55でその内実をお伝えしました。ご参照ください。
≪参考サイト&記事≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎石綿(ウィキペディア)
◎中皮腫について(独立行政法人環境再生保全機構のサイト)
https://www.erca.go.jp/asbestos/mesothelioma/what/what_about.html
◎「国・石綿建材業者に賠償責任 最高裁、初の統一判断」(2021年5月18日付、朝日新聞)
◎「建設石綿、国と企業の責任認める 最高裁が統一判断」(2021年5月17日、日本経済新聞電子版)
◎大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟(ウィキペディア)
◎労働安全衛生法(ウィキペディア)、労働基準法(同)
◎労働安全衛生法律とは? 経営者がやるべきことをわかりやすく解説
https://squareup.com/jp/ja/townsquare/what-is-industrial-safety-and-health-act
≪写真説明&Source≫
◎アスベスト訴訟で勝訴し、垂れ幕を掲げる原告団(日経新聞電子版2021年5月17日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE14BXJ0U1A510C2000000/
日本のメディアでは昔から、「朝日のトドメ」「ピリオドのNHK」と言われてきた。どんな流行もブームも「朝日新聞の紙面に載り、NHKが放送したらもうオシマイ」という意味だ。

その朝日新聞が4月22日付のオピニオン面で、Adoが歌う「うっせぇわ」の特集を組んで報じた。特集では、歌手の泉谷しげるが「怒れ 世の中に向けて叫べ」と唱え、漫画家の松本千秋が「遊んだっていいじゃない」と語った。読み応えのある特集だった。
NHKが扱ったかどうかは知らないが、その4日前にはTBSがAdoのリモートインタビューを流した。インタビューアーはタレントの林修。最近の民放はNHKに似てきたので、この大ヒット曲も賞味期限切れ、ということだろう。
それでも、私の中ではまだ終わっていない。その強烈な歌唱力と抜群のリズム、時代を切り裂くような歌詞がなかなか消えない。謎めいたところが多く、調べてみたくなる。
クソだりぃな
酒が空いたグラスあれば直ぐに注ぎなさい
皆がつまみ易いように串外しなさい
会計や注文は先陣を切る
不文律最低限のマナーです
と来て、一呼吸置いて「はぁ うっせぇ うっせぇ うっせぇわ」と勢いよく弾き飛ばす。コロナ禍でふさぎ込む社会にナイフを突き立てるようなフレーズだ。
これを18歳の女子高生Adoが歌って去年の10月にリリースし、3月にはユーチューブでの再生回数が1億回を超えた。けれども、肝心のAdoのプロフィールはまるで分からない。先のインタビューでも、林は動画配信のイラストの顔に向かって聞いていた。
本人の公式サイトによれば、小学生のころの夢は漫画家かイラストレーターになること。「地味で内気で根暗で、クラスの端っこで絵を描いているような人間だった」という。小学校の国語の授業で狂言『柿山伏』を教わり、シテ(主役)とアド(脇役)という言葉を知った。「アド」という言葉の響きに惹かれ、それを名乗ることを決めたという。
彼女にとって、音楽への扉を開いてくれたのはレコードでもCDでもなく、ニコニコ動画だった。ほどなく、ヤマハの音声合成ソフト「ボーカロイド」に出合い、中学2年から音楽活動を始める。自宅のクローゼットに防音をしてパソコンで録音、動画サイトに投稿する形でデビューしたが、名前も素顔も明らかにしていない。
彼女のように「ボーカロイド」で楽曲を作り、投稿する音楽家を「ボーカロイド・プロデューサー」、略して「ボカロP(ピー)」と呼ぶことも初めて知った。演歌やポップスのように、「ボーカロイド」というのが、今や音楽のジャンルの一つになっている。
とはいえ、高校生に「うっせぇわ」の作詞はできない。想像力がいくら豊かでも「不文律最低限のマナー」には思い至るまい。2番目の不思議、誰が作詞作曲をしたのか。それを調べていったら、またもやアルファベットの人物「syudou (しゅどう)」にたどり着いた。
彼も「ボーカロイド」で育ち、動画で楽曲を発表してきた音楽家の一人だ。同じように名前もプロフィールも明らかにしていないが、大学を卒業した後、会社勤めをしたことがあるという。
最新の流行は当然の把握
経済の動向も通勤時チェック
純情な精神で入社しワーク
社会人じゃ当然のルールです
という歌詞を紡げるだけの経験を重ねたようだ。
3番目の疑問。こうした「ボカロP」の収入源はどうなっているのか。昔のレコードやCDの売り上げとは収益構造がまるで異なる。ネットから音楽をダウンロードして楽しむ「ストリーミング」からの収入に加え、動画配信のユーチューブからの広告収入が大きいようだ。
ユーチューブのビジネスモデルを紹介しているサイトによれば、ユーチューバーの国内トップ100人の平均年収は3000万円を超えるのだとか。投稿した動画を1人クリックするたびに、動画に表示される広告の収入が0.1円程度、投稿者に支払われる。1億回再生されれば、単純計算で投稿者には1000万円が支払われる。動画をチャンネル登録した人数に応じた支払いなどもあるので、それも別途、手に入る。
映像活用提案会社「サムシングファン」によれば、動画のチャンネル登録者数が1万人なら20万円、3万人なら50万円ほどの登録料が毎月、ユーチューブから支払われるので、十分に暮らしていける。もちろん、動画をクリックすることで企業などから支払われる広告収入の取り分は、運営会社のユーチューブの方が多数の投稿者の総収入よりはるかに大きい。
ユーチューブは2005年にカリフォルニア州で設立され、翌2006年に16億5000万ドル(当時のレートで約2000億円)でGoogleに買収された。発足当初、この会社は動画の共有サービスに徹しており、売り上げはほとんどなかった。その会社にGoogleは巨費を投じた。
「投資に見合う収益を上げられるわけがない」との見方もあったが、Googleは提供する動画に広告をリンクすることで、この会社を「打ち出の小槌」に変えた。恐るべし経営戦略である。
話がそれた。「うっせぇわ」の七不思議の残り。ユーチューブにアップされたこの曲のミュージックビデオのイラストも切れ味鋭い。作者は誰かと調べたら、またWOOMAという名前が出てきた。分かったのは、ロングヘア―の女性だということだけ。皆さん、プライバシーを大切にしているようだ。
「この曲にダンスの振り付けをして踊ってみました」という動画も観た。これまた、すごい。高校ダンス界の強豪、大阪府立登美丘高校の振付師、akane(宮崎朱音)が振り付けたことまでは分かったが、踊り手がこの高校の生徒なのか、どこを舞台にしたのかはついに分からなかった。
残りの不思議は「この曲を一段と魅力的にしているドラムの演奏者は誰か」と「歌い手のAdoと作詞作曲のsyudouを支えて曲を世に送り出した音楽会社Virgin Music で全体を統括したのは誰か」の二つ。2人とも、並々ならぬ才能の持ち主だろう。
Adoは自らのサイトで「今は私の曲を聴いてくださる方々の代わりに戦える存在に、誰かの人生の脇役になれたらと思っています」と綴っている。そう、世の中はますます生きにくくなってきた。そんな時代だからこそ、刃のような音楽を聴きたい。 (敬称略)
*メールマガジン「風切通信 86」 2021年4月25日
≪写真のSource & 説明≫
◎高嶺ヒナの「うっせぇわ」コスプレ
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2102/18/news096.html
≪参考サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎「うっせぇわ」特設ページ Ado
https://www.universal-music.co.jp/ado/usseewa/
◎ウィキペディア「Ado」「syudou」「VOCALOID」「akane(振付師)」
◎ユーチューバーの収入は?徹底解説
https://richka.co/times/28437/#:~:text=YouTube%E3%81%AE%E5%8D%98%E4%BE%A1%E3%81%AF%E3%80%811,%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
◎Youtubeで稼げる金額はいくら?(株式会社サムシングファン)
https://www.somethingfun.co.jp/video_tips/youtube_income
◎ユーチューバーの収入の仕組みや平均年収は?
https://career-picks.com/average-salary/youtuber-syuunyuu/
◎「うっせぇわのMV制作のWOOMAがテレビ初出演」
https://news.mynavi.jp/article/20210412-1868725/

その朝日新聞が4月22日付のオピニオン面で、Adoが歌う「うっせぇわ」の特集を組んで報じた。特集では、歌手の泉谷しげるが「怒れ 世の中に向けて叫べ」と唱え、漫画家の松本千秋が「遊んだっていいじゃない」と語った。読み応えのある特集だった。
NHKが扱ったかどうかは知らないが、その4日前にはTBSがAdoのリモートインタビューを流した。インタビューアーはタレントの林修。最近の民放はNHKに似てきたので、この大ヒット曲も賞味期限切れ、ということだろう。
それでも、私の中ではまだ終わっていない。その強烈な歌唱力と抜群のリズム、時代を切り裂くような歌詞がなかなか消えない。謎めいたところが多く、調べてみたくなる。
クソだりぃな
酒が空いたグラスあれば直ぐに注ぎなさい
皆がつまみ易いように串外しなさい
会計や注文は先陣を切る
不文律最低限のマナーです
と来て、一呼吸置いて「はぁ うっせぇ うっせぇ うっせぇわ」と勢いよく弾き飛ばす。コロナ禍でふさぎ込む社会にナイフを突き立てるようなフレーズだ。
これを18歳の女子高生Adoが歌って去年の10月にリリースし、3月にはユーチューブでの再生回数が1億回を超えた。けれども、肝心のAdoのプロフィールはまるで分からない。先のインタビューでも、林は動画配信のイラストの顔に向かって聞いていた。
本人の公式サイトによれば、小学生のころの夢は漫画家かイラストレーターになること。「地味で内気で根暗で、クラスの端っこで絵を描いているような人間だった」という。小学校の国語の授業で狂言『柿山伏』を教わり、シテ(主役)とアド(脇役)という言葉を知った。「アド」という言葉の響きに惹かれ、それを名乗ることを決めたという。
彼女にとって、音楽への扉を開いてくれたのはレコードでもCDでもなく、ニコニコ動画だった。ほどなく、ヤマハの音声合成ソフト「ボーカロイド」に出合い、中学2年から音楽活動を始める。自宅のクローゼットに防音をしてパソコンで録音、動画サイトに投稿する形でデビューしたが、名前も素顔も明らかにしていない。
彼女のように「ボーカロイド」で楽曲を作り、投稿する音楽家を「ボーカロイド・プロデューサー」、略して「ボカロP(ピー)」と呼ぶことも初めて知った。演歌やポップスのように、「ボーカロイド」というのが、今や音楽のジャンルの一つになっている。
とはいえ、高校生に「うっせぇわ」の作詞はできない。想像力がいくら豊かでも「不文律最低限のマナー」には思い至るまい。2番目の不思議、誰が作詞作曲をしたのか。それを調べていったら、またもやアルファベットの人物「syudou (しゅどう)」にたどり着いた。
彼も「ボーカロイド」で育ち、動画で楽曲を発表してきた音楽家の一人だ。同じように名前もプロフィールも明らかにしていないが、大学を卒業した後、会社勤めをしたことがあるという。
最新の流行は当然の把握
経済の動向も通勤時チェック
純情な精神で入社しワーク
社会人じゃ当然のルールです
という歌詞を紡げるだけの経験を重ねたようだ。
3番目の疑問。こうした「ボカロP」の収入源はどうなっているのか。昔のレコードやCDの売り上げとは収益構造がまるで異なる。ネットから音楽をダウンロードして楽しむ「ストリーミング」からの収入に加え、動画配信のユーチューブからの広告収入が大きいようだ。
ユーチューブのビジネスモデルを紹介しているサイトによれば、ユーチューバーの国内トップ100人の平均年収は3000万円を超えるのだとか。投稿した動画を1人クリックするたびに、動画に表示される広告の収入が0.1円程度、投稿者に支払われる。1億回再生されれば、単純計算で投稿者には1000万円が支払われる。動画をチャンネル登録した人数に応じた支払いなどもあるので、それも別途、手に入る。
映像活用提案会社「サムシングファン」によれば、動画のチャンネル登録者数が1万人なら20万円、3万人なら50万円ほどの登録料が毎月、ユーチューブから支払われるので、十分に暮らしていける。もちろん、動画をクリックすることで企業などから支払われる広告収入の取り分は、運営会社のユーチューブの方が多数の投稿者の総収入よりはるかに大きい。
ユーチューブは2005年にカリフォルニア州で設立され、翌2006年に16億5000万ドル(当時のレートで約2000億円)でGoogleに買収された。発足当初、この会社は動画の共有サービスに徹しており、売り上げはほとんどなかった。その会社にGoogleは巨費を投じた。
「投資に見合う収益を上げられるわけがない」との見方もあったが、Googleは提供する動画に広告をリンクすることで、この会社を「打ち出の小槌」に変えた。恐るべし経営戦略である。
話がそれた。「うっせぇわ」の七不思議の残り。ユーチューブにアップされたこの曲のミュージックビデオのイラストも切れ味鋭い。作者は誰かと調べたら、またWOOMAという名前が出てきた。分かったのは、ロングヘア―の女性だということだけ。皆さん、プライバシーを大切にしているようだ。
「この曲にダンスの振り付けをして踊ってみました」という動画も観た。これまた、すごい。高校ダンス界の強豪、大阪府立登美丘高校の振付師、akane(宮崎朱音)が振り付けたことまでは分かったが、踊り手がこの高校の生徒なのか、どこを舞台にしたのかはついに分からなかった。
残りの不思議は「この曲を一段と魅力的にしているドラムの演奏者は誰か」と「歌い手のAdoと作詞作曲のsyudouを支えて曲を世に送り出した音楽会社Virgin Music で全体を統括したのは誰か」の二つ。2人とも、並々ならぬ才能の持ち主だろう。
Adoは自らのサイトで「今は私の曲を聴いてくださる方々の代わりに戦える存在に、誰かの人生の脇役になれたらと思っています」と綴っている。そう、世の中はますます生きにくくなってきた。そんな時代だからこそ、刃のような音楽を聴きたい。 (敬称略)
*メールマガジン「風切通信 86」 2021年4月25日
≪写真のSource & 説明≫
◎高嶺ヒナの「うっせぇわ」コスプレ
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2102/18/news096.html
≪参考サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎「うっせぇわ」特設ページ Ado
https://www.universal-music.co.jp/ado/usseewa/
◎ウィキペディア「Ado」「syudou」「VOCALOID」「akane(振付師)」
◎ユーチューバーの収入は?徹底解説
https://richka.co/times/28437/#:~:text=YouTube%E3%81%AE%E5%8D%98%E4%BE%A1%E3%81%AF%E3%80%811,%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
◎Youtubeで稼げる金額はいくら?(株式会社サムシングファン)
https://www.somethingfun.co.jp/video_tips/youtube_income
◎ユーチューバーの収入の仕組みや平均年収は?
https://career-picks.com/average-salary/youtuber-syuunyuu/
◎「うっせぇわのMV制作のWOOMAがテレビ初出演」
https://news.mynavi.jp/article/20210412-1868725/
日本の政府と電力会社は大切なことを隠し、国民を欺いている――原子力発電について私が疑念を抱き、不信感を深めたのは1988年のことだった。

旧ソ連のウクライナで起きたチェルノブイリ原発事故から2年。この年、北海道電力は積丹(しゃこたん)半島の泊(とまり)村に建設した原子力発電所の試運転をめざしていた。
チェルノブイリの原発事故がいかに悲惨なもので、その影響がいかに広く、深刻なものか。それが少しずつ明らかになるにつれて、日本でも「もう原発はいらない」と考える人が増え、反原発運動が急速に盛り上がり始めていた。
当時、私は札幌在勤の新聞記者で原発推進派と反対派の両方を取材していた。その過程で、北海道電力が泊原発の運転開始に備えて、国内の大手損保21社と保険契約を結ぶ交渉を進めていることを知った。
その保険契約は、原発事故で周辺の住民に損害が出た場合に備える賠償保険と、事故によって発電施設に損害が出た場合に備える財産保険の二つだった。前者は住民に対する補償、後者は電力会社がこうむる損害をカバーする保険である。
問題は、この二つの保険によって支払われる金額に大きな隔たりがあることだった。
住民向けの保険は保険料が年間3000万円、事故時に支払われる保険金は最大100億円。一方、電力会社に支払われる財産保険の保険料は年間3億円、支払い金額は900億円で住民向けの保険の9倍もあった。
なぜ、それほど差があるのか。調べていくうちに愕然とした。電力会社向けの保険は「冷却水の喪失事故」も対象にしていた。つまり、原子炉がカラ焚きになり、炉心溶融が起きることも想定していた。このため保険料も高く、補償金額も大きかった。
これに対し、住民向けの保険は「事故の影響が及ぶのはせいぜい発電所の周辺10キロまで」との前提に立っていた。「それ以上深刻な事故など起きない」というもので、明らかに矛盾していた。私は怒りを込めてその事実を書いた(記事参照)。
原発の建設を推進してきた政府と電力会社は、米国のスリーマイル島原発事故(1979年)とチェルノブイリ原発事故(1986年)の後も「日本ではこうした過酷な事故は起きない」と主張し、事故時の住民向けの保険も「この程度で十分」と説明し続けた。なのに、電力会社向けの保険では炉心溶融まで想定した契約を結んでいた。欺瞞と言うほかない。
専門家もその欺瞞を支えた。原子力安全委員会の決定(1980年6月30日)は次のように記していた。
「原子力発電所等において放射性物質の大量放出があるか、又はそのおそれがあるような異常事態が瞬時に生ずることは殆(ほどん)ど考えられないことであり、事前になんらかの先行的な事象の発生及びその検知があると考えられる」
「このような先行的事象は、原子力発電所等の防護設備及び慎重な対応等によって、周辺住民に影響を与えるような事態に至るとは考えられないが、万一そのような事態になったとしても、これに至るまでにはある程度の時間的経過があるものと考えられる」
原発の事故には前兆となるトラブルがある。それを的確に捉えて対処することによって、住民に重大な影響を及ぼすような事態は防ぐことができる、と自信たっぷりに書いていた。
原発事故の際の住民向けの保険金はその後、増額された。だが、政府も電力業界もこうした「安全神話」を振りまくことをやめなかった。
自然はそうした欺瞞と甘えを許さなかった。2011年3月11日、東京電力・福島第一原子力発電所は大津波に「瞬時に」のみ込まれ、すべての電源を失った。やがて炉心が溶融、原子炉建屋(たてや)が相次いで爆発し、大量の放射性物質を大気中に放出した。
事故の後、ある原子力研究者は「この事故で死んだ者は一人もいない」と言い張った。確かに、原発の敷地内で亡くなった人はいない。
こういう人には、原発のすぐ近くにあった双葉病院と老人介護施設で起きたことを告げるだけで十分だろう。436人の患者と入所者はいきなり電気と水のない状況に追い込まれ、すぐには避難もできなかった。混乱の中で50人が命を失った。
そして、十数万の人々が住み慣れた土地を追われた。彼らが失ったものは金銭で償えるものではない。原発を推進し、今なお推進しようとしている人たちは、そうしたことへの想像力が欠如している。
◇ ◇
南相馬市で生花店を営んでいた上野寛(ひろし)さん(56)も、原発事故で故郷を追われた被災者の一人だ。
震災当日は、いつもより仕事が立て込んでいない日だった。夕方に葬祭会館で通夜が予定されており、生花を届けることになっていたが、その準備も前日までにほぼ終わっていた。一緒に店で働く両親は、昼から海辺にあるパークゴルフ場に行くのを楽しみにしていた。
ところが、通夜のために用意していた生花の名札を従業員が「使用済みの名札」と勘違いして破棄していたことが分かり、妹を含め家族総出で作り直さなければならなくなった。このミスがなければ、両親は海辺のゴルフ場で津波にのまれていたかもしれない。世の中、何が幸いするか分からない。
家族は生花店にいて無事だったが、海寄りの葬祭会館にいた上野さんは津波に襲われた。ずぶ濡れになりながらも、波が引いた時になんとか脱出した。家族と合流できたのは日が暮れてからだった。1日目の夜は、妹の家族を含め一家8人が高台にある神社の境内で車に分乗して過ごした。
2日目の昼前、「原発が危ない」といううわさが流れ始めた。午後3時半、まず1号機が爆発した。上野さん一家をはじめ、多くの住民が北西の飯舘村に逃れた(図1)。なぜこの方向に避難したのか。上野さんによれば、ほかに選択肢はなかった。
「南には原発があるから逃げられない。海沿いに北に行こうとしても、津波で道路がやられているので行けない。飯舘村を経由して福島市をめざすしかなかったのです」
みな、着の身着のままの状態だった。まず、食べ物と水を確保しなければならない。車で移動するためのガソリンも必要だ。誰もが右往左往し、必需品を買うため長い行列に並んだ。
3日目の夜は川俣町の民家で世話になった。4日目の14日、福島県北東部の新地町にある妻の母親と連絡が取れ、母親が暮らすアパートに身を寄せた。電気も水道も通じていた。やっと風呂に入ることができた。
だが、この日、原発では3号機も爆発した。残りの原子炉も危うい。翌15日に合流した妹の夫は涙を浮かべながら「(新地町でも)もう限界。避難しないと危ない」と訴えた。彼は原発関係の下請けの仕事をしていた。
実際、15日には2号機と4号機も破損し、大量の放射性物質が風に乗って北西方面に流れた。避難してきた飯舘村経由のルートが「帯状の高濃度汚染地帯」になったのは、この時の風によると見られている(図2)。
どこに逃げるか。福島市でも危ない。仙台は空港まで津波が来たという。残る選択肢は「山に囲まれ、放射能の心配をそれほどしなくてもいい山形県」だった。同じ理由で被災者の多くが山形をめざした。
幸い、米沢市に住む妹の友人と連絡が取れ、「こっちに来て。住まいも手配しておくから」と言ってくれた。上野さん一行は合流した弟を含め11人になっていた。車4台に分乗して宮城県の七ヶ宿(しちかしゅく)町を通り、雪の峠を越えて16日に米沢にたどり着いた。
妹の友人はアパートの一室を手配してくれていた。布団もそろえ、夕食まで用意してくれていた。その温かい気配りが「米沢に腰を据える決断」につながった。
米沢市の被災者受け入れオペレーションは際立っていた。「体育館での避難生活」を解消するため、市内5カ所にある400戸の雇用促進住宅を提供することを決めた。
役所なら「入居の申し込みは書類で」となるのが普通だが、米沢市は遠方から電話で申し込むこともできるようにし、訪ねてきたその日に鍵を渡し、入居することも認めた。緊急事態に対応した柔軟な措置だった。上野さんの家族も2戸に入居できた。
6月には市役所の危機管理室の下に「避難者支援センターおいで」を新設した。ここに来れば、あらゆる相談に乗ってくれる。福島県や避難元の市町村との連絡調整もしてくれる。
米沢市は「避難者の悩みや苦しみが一番分かるのは避難者」と考え、センターの職員として避難者を積極的に登用した。上野さんもそのスタッフとして採用され、今も働き続けている。
原発事故によって避難した人は、2012年5月の時点で16万4千人に達した。内訳は福島県内での避難が6割、県外への避難が4割だった。その数は昨年7月の時点で3万7千人に減少したが、原発事故はいまだに終息していない。
放射能にさらされた大地の除染は終わっていない。原発の施設内では汚染水が増え続けている。融け落ちた核燃料の回収はめどすら立っていない。
そもそも、使用済みの核燃料やそれらを処理した後に残る高レベル放射性廃棄物をどうするのか。半世紀以上も前から検討しているのに候補地すら決まっていない。
それでも、政府や電力業界は「原子力発電を続ける」と言う。未来を見ようとしない。目をそむけたまま、次の世代にツケを回そうとしている。
不誠実で無責任な人たちが「日本」という私たちが乗る船の舵(かじ)取りを続けている。それを許してきたのは、ほかならぬ私たち自身だ。
そろそろ本気になって、信頼できる人たちに舵取りを託すためにはどうすればいいのか、考えなければならない。
◇ ◇
宮城県気仙沼市の畠山重篤(しげあつ)さん(77)は、唐桑(からくわ)半島の付け根にある西舞根(もうね)でカキとホタテの養殖をして生計を立ててきた。親の代からの漁師だ。

三陸海岸の豊かな海に異変が生じたのは、日本が経済成長に沸き立っていた1970年ごろだった。しばしば赤潮プランクトンが大発生し、白いはずのカキの身が赤くなった。「血ガキ」と呼ばれ、売り物にならない。ホタテ貝も死んでしまう。
養殖いかだが並ぶ気仙沼湾には工場排水や農薬、化学肥料、生活雑排水などあらゆるものが流れ込み、カキやホタテが育つ環境を損ねていた。
そのうえ、湾に注ぐ大川にダムの建設計画まで持ち上がった。このままでは生きていけない。山の人たちと共にダム建設の反対運動に取り組み、建設断念に追い込んだ。この時、地元の歌人、熊谷龍子さんはこう詠んだ。
森は海を海は森を恋いながら
悠久よりの愛紡ぎゆく
それは、漁師たちの思いと響き合うものだった。沖に出れば、漁師たちは山々を見て船の位置を確認する。良い漁場がどこにあるかも山を目印にして胸に刻んできた。高い山にかかる雲や雪が舞い上がる様子で天候の急変を察知し、難を逃れてきた。「山測り」と呼ばれ、その大切さは今も変わらない。
山と森、里と海はすべてつながっている。唐桑半島の漁師たちはそう信じ、1989年から上流の荒れた山々に木を植える運動を始めた。一番の目印である室根山(むろねさん)に大漁旗を掲げ、ブナやナラの苗木を植えていった。
その運動を「森は海の恋人」と名付けた。
畠山さんがただ者でないのは、この後の行動力である。では、森と海をつなぐものは何か。その探求に乗り出したのだ。
ある日、海の岩が白くなり、海藻が生えなくなる「磯焼け」の問題をNHKが特集で報じていた。その中で、北海道大学水産学部の松永勝彦教授が「森の木を伐(き)ってしまったことが原因です」と解説していた。
海藻が育つためには鉄分が欠かせない。その鉄分は森林から供給される。その森が荒れ、鉄分が海に流れて来なくなったため海藻が育たず、磯が焼けてしまった――そう説いていた。
畠山さんはすぐ、松永教授に連絡し、翌日、仲間と函館市にある研究室を訪ねた。そして、なぜ森の鉄分が海藻にとって必要不可欠なのか、そのメカニズムを詳しく解説してもらった。
森の腐葉土は「フルボ酸」というものをつくり出す。それが土中の鉄分とくっついて「フルボ酸鉄」になり、海に流れ込む。これが植物プランクトンや海藻が光合成をするのに欠かせないのだという。森と海をつなぐ大切なもの。それは鉄だった。
漁師と科学者の共同作業が始まる。1993年、松永教授は学生たちを伴って気仙沼湾を訪れ、湾内に流れ込む鉄や窒素、リンなどの分析に乗り出した。そして、川が運んでくる鉄分が植物プランクトンの生長を促し、海を豊かにしてくれていることをデータで立証した。
畠山さんの探求は、日本の海から世界の海へと広がる。
世界には「肥沃な海」とそうでない海があること。その謎を解くカギは海水に含まれる微量金属、とりわけ鉄が握っていること。困難な微量金属の分析方法を編み出したのはアメリカの海洋化学者、ジョン・マーチン博士であることを知った。
日本近くの北太平洋の海が豊かなのは、中国大陸からジェット気流に乗って飛来する黄砂のおかげであることを明らかにしたのもマーチン博士だ。あの厄介な黄砂が北洋海域に鉄分をもたらし、植物プランクトンの生育を促していたのだ。
探求の旅は、植物の光合成から人間の血液へと続く。人間は血液中の赤血球を通して酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を吐き出すが、その運び役をしているのは赤血球のヘモグロビンに含まれる鉄だ。鉄なしでは、人間もまた生きていけないのだった。
「森は海の恋人」運動から始まった探求は国境を越え、学問の垣根を越えて広がり、命の連鎖の中で鉄が果たしている役割の大きさを浮かび上がらせていった。畠山さんはその成果を次々に本にまとめ、出版した。
その運動に注目したのが京都大学だった。京大は学問が細分化され、タコ壷化していることを危ぶみ、2003年に林学と水産学、農学を統合した「森里海連環学」という新しい学問を立ち上げ、研究センターを新設した。そして、畠山さんにシンポジウムの基調講演を依頼した。新しい学問の意義を語る人間としてふさわしい、と考えたからにほかならない。
それ以降、唐桑半島の海は京都大学の森里海連環学の研究拠点の一つになり、毎年、研究者や学生が訪れるようになった。小さな漁村は「時代の先端」を走っていた。
だが、10年前のあの日、大津波は唐桑の海にも容赦なく押し寄せ、漁船と養殖いかだをすべて押し流していった。高台にある畠山さんの自宅は無事だったものの、海辺の住宅は壊滅、体の不自由な住民4人が逃げ遅れて亡くなった。家族と離れ、市街地の福祉施設に入っていた畠山さんの母親も帰らぬ人となった。
恵みの海による、あまりにも残酷な仕打ち。それでも、漁民は海に生きるしかない。唐桑の人たちはすぐさま、カキの養殖再開へと動き出した。
国内はもちろん、フランスからも養殖いかだなどの支援物資が届いた。かつて、フランスでカキの病気が蔓延し、養殖が危機に陥った際、カキの稚貝を送って救ったのは三陸の漁民たちだった。彼らはそれを忘れていなかった。
海の復元力の強さにも助けられた。住宅や港の復旧を上回るスピードで、海の生き物たちは戻ってきた。畠山さんは「直後は『海は死んだ』とうなだれた。けれども、しばらく経つと、小さなエビや魚が湧き出すような勢いで増えていった」と言う。
森と川は、海の生き物たちが必要とするものを送り続けていた。西舞根のカキの出荷は、震災の翌年には震災前を上回るまで回復した。
震災の経験から何をくみ取るべきか。畠山さんはこう語る。
「日本は森におおわれ、海に囲まれた国です。本来、生きていくのに困ることのない国です。なのに、川という川にダムを造り、護岸をコンクリートで固め、傷めつけてきた。森と川と海の関係を元の自然な状態に戻しなさい、と言われているのではないでしょうか」
豊かさと便利さを追い求める中で、私たちは断ち切ってはならないものまで断ち切ってしまったのではないか。命のつながりにかかわる大切なもの。それに思いを致す時ではないか。 (連載終了)
*メールマガジン「風切通信85」 2021年2月28日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2021年3月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎福島第一原発3号機の爆発(福島中央テレビの映像=サイエンスジャーナルのサイトから)
http://sciencejournal.livedoor.biz/archives/5685129.html
◎畠山重篤さん(佐々木惠里さんのブログから)
https://ameblo.jp/amesatin/entry-12286195283.html
≪参考記事・文献&サイト≫
◎「泊原発 保険は1千億円 核暴走事故も含む」(1988年6月24日付 朝日新聞北海道版)
◎「遅れた避難 50人の死 救えなかったか」(2021年2月17日付 朝日新聞社会面)
◎『あの日から今まで そしてこれから』(上野寛さんのお話を聞く会編)
◎「震災 原発事故9年6カ月」(2020年9月13日、福島民報電子版)
◎『森は海の恋人』(畠山重篤、文春文庫)
◎『鉄は魔法使い』(畠山重篤、小学館)

旧ソ連のウクライナで起きたチェルノブイリ原発事故から2年。この年、北海道電力は積丹(しゃこたん)半島の泊(とまり)村に建設した原子力発電所の試運転をめざしていた。
チェルノブイリの原発事故がいかに悲惨なもので、その影響がいかに広く、深刻なものか。それが少しずつ明らかになるにつれて、日本でも「もう原発はいらない」と考える人が増え、反原発運動が急速に盛り上がり始めていた。
当時、私は札幌在勤の新聞記者で原発推進派と反対派の両方を取材していた。その過程で、北海道電力が泊原発の運転開始に備えて、国内の大手損保21社と保険契約を結ぶ交渉を進めていることを知った。
その保険契約は、原発事故で周辺の住民に損害が出た場合に備える賠償保険と、事故によって発電施設に損害が出た場合に備える財産保険の二つだった。前者は住民に対する補償、後者は電力会社がこうむる損害をカバーする保険である。
問題は、この二つの保険によって支払われる金額に大きな隔たりがあることだった。
住民向けの保険は保険料が年間3000万円、事故時に支払われる保険金は最大100億円。一方、電力会社に支払われる財産保険の保険料は年間3億円、支払い金額は900億円で住民向けの保険の9倍もあった。
なぜ、それほど差があるのか。調べていくうちに愕然とした。電力会社向けの保険は「冷却水の喪失事故」も対象にしていた。つまり、原子炉がカラ焚きになり、炉心溶融が起きることも想定していた。このため保険料も高く、補償金額も大きかった。
これに対し、住民向けの保険は「事故の影響が及ぶのはせいぜい発電所の周辺10キロまで」との前提に立っていた。「それ以上深刻な事故など起きない」というもので、明らかに矛盾していた。私は怒りを込めてその事実を書いた(記事参照)。
原発の建設を推進してきた政府と電力会社は、米国のスリーマイル島原発事故(1979年)とチェルノブイリ原発事故(1986年)の後も「日本ではこうした過酷な事故は起きない」と主張し、事故時の住民向けの保険も「この程度で十分」と説明し続けた。なのに、電力会社向けの保険では炉心溶融まで想定した契約を結んでいた。欺瞞と言うほかない。
専門家もその欺瞞を支えた。原子力安全委員会の決定(1980年6月30日)は次のように記していた。
「原子力発電所等において放射性物質の大量放出があるか、又はそのおそれがあるような異常事態が瞬時に生ずることは殆(ほどん)ど考えられないことであり、事前になんらかの先行的な事象の発生及びその検知があると考えられる」
「このような先行的事象は、原子力発電所等の防護設備及び慎重な対応等によって、周辺住民に影響を与えるような事態に至るとは考えられないが、万一そのような事態になったとしても、これに至るまでにはある程度の時間的経過があるものと考えられる」
原発の事故には前兆となるトラブルがある。それを的確に捉えて対処することによって、住民に重大な影響を及ぼすような事態は防ぐことができる、と自信たっぷりに書いていた。
原発事故の際の住民向けの保険金はその後、増額された。だが、政府も電力業界もこうした「安全神話」を振りまくことをやめなかった。
自然はそうした欺瞞と甘えを許さなかった。2011年3月11日、東京電力・福島第一原子力発電所は大津波に「瞬時に」のみ込まれ、すべての電源を失った。やがて炉心が溶融、原子炉建屋(たてや)が相次いで爆発し、大量の放射性物質を大気中に放出した。
事故の後、ある原子力研究者は「この事故で死んだ者は一人もいない」と言い張った。確かに、原発の敷地内で亡くなった人はいない。
こういう人には、原発のすぐ近くにあった双葉病院と老人介護施設で起きたことを告げるだけで十分だろう。436人の患者と入所者はいきなり電気と水のない状況に追い込まれ、すぐには避難もできなかった。混乱の中で50人が命を失った。
そして、十数万の人々が住み慣れた土地を追われた。彼らが失ったものは金銭で償えるものではない。原発を推進し、今なお推進しようとしている人たちは、そうしたことへの想像力が欠如している。
◇ ◇
南相馬市で生花店を営んでいた上野寛(ひろし)さん(56)も、原発事故で故郷を追われた被災者の一人だ。
震災当日は、いつもより仕事が立て込んでいない日だった。夕方に葬祭会館で通夜が予定されており、生花を届けることになっていたが、その準備も前日までにほぼ終わっていた。一緒に店で働く両親は、昼から海辺にあるパークゴルフ場に行くのを楽しみにしていた。
ところが、通夜のために用意していた生花の名札を従業員が「使用済みの名札」と勘違いして破棄していたことが分かり、妹を含め家族総出で作り直さなければならなくなった。このミスがなければ、両親は海辺のゴルフ場で津波にのまれていたかもしれない。世の中、何が幸いするか分からない。
家族は生花店にいて無事だったが、海寄りの葬祭会館にいた上野さんは津波に襲われた。ずぶ濡れになりながらも、波が引いた時になんとか脱出した。家族と合流できたのは日が暮れてからだった。1日目の夜は、妹の家族を含め一家8人が高台にある神社の境内で車に分乗して過ごした。
2日目の昼前、「原発が危ない」といううわさが流れ始めた。午後3時半、まず1号機が爆発した。上野さん一家をはじめ、多くの住民が北西の飯舘村に逃れた(図1)。なぜこの方向に避難したのか。上野さんによれば、ほかに選択肢はなかった。
「南には原発があるから逃げられない。海沿いに北に行こうとしても、津波で道路がやられているので行けない。飯舘村を経由して福島市をめざすしかなかったのです」
みな、着の身着のままの状態だった。まず、食べ物と水を確保しなければならない。車で移動するためのガソリンも必要だ。誰もが右往左往し、必需品を買うため長い行列に並んだ。
3日目の夜は川俣町の民家で世話になった。4日目の14日、福島県北東部の新地町にある妻の母親と連絡が取れ、母親が暮らすアパートに身を寄せた。電気も水道も通じていた。やっと風呂に入ることができた。
だが、この日、原発では3号機も爆発した。残りの原子炉も危うい。翌15日に合流した妹の夫は涙を浮かべながら「(新地町でも)もう限界。避難しないと危ない」と訴えた。彼は原発関係の下請けの仕事をしていた。
実際、15日には2号機と4号機も破損し、大量の放射性物質が風に乗って北西方面に流れた。避難してきた飯舘村経由のルートが「帯状の高濃度汚染地帯」になったのは、この時の風によると見られている(図2)。
どこに逃げるか。福島市でも危ない。仙台は空港まで津波が来たという。残る選択肢は「山に囲まれ、放射能の心配をそれほどしなくてもいい山形県」だった。同じ理由で被災者の多くが山形をめざした。
幸い、米沢市に住む妹の友人と連絡が取れ、「こっちに来て。住まいも手配しておくから」と言ってくれた。上野さん一行は合流した弟を含め11人になっていた。車4台に分乗して宮城県の七ヶ宿(しちかしゅく)町を通り、雪の峠を越えて16日に米沢にたどり着いた。
妹の友人はアパートの一室を手配してくれていた。布団もそろえ、夕食まで用意してくれていた。その温かい気配りが「米沢に腰を据える決断」につながった。
米沢市の被災者受け入れオペレーションは際立っていた。「体育館での避難生活」を解消するため、市内5カ所にある400戸の雇用促進住宅を提供することを決めた。
役所なら「入居の申し込みは書類で」となるのが普通だが、米沢市は遠方から電話で申し込むこともできるようにし、訪ねてきたその日に鍵を渡し、入居することも認めた。緊急事態に対応した柔軟な措置だった。上野さんの家族も2戸に入居できた。
6月には市役所の危機管理室の下に「避難者支援センターおいで」を新設した。ここに来れば、あらゆる相談に乗ってくれる。福島県や避難元の市町村との連絡調整もしてくれる。
米沢市は「避難者の悩みや苦しみが一番分かるのは避難者」と考え、センターの職員として避難者を積極的に登用した。上野さんもそのスタッフとして採用され、今も働き続けている。
原発事故によって避難した人は、2012年5月の時点で16万4千人に達した。内訳は福島県内での避難が6割、県外への避難が4割だった。その数は昨年7月の時点で3万7千人に減少したが、原発事故はいまだに終息していない。
放射能にさらされた大地の除染は終わっていない。原発の施設内では汚染水が増え続けている。融け落ちた核燃料の回収はめどすら立っていない。
そもそも、使用済みの核燃料やそれらを処理した後に残る高レベル放射性廃棄物をどうするのか。半世紀以上も前から検討しているのに候補地すら決まっていない。
それでも、政府や電力業界は「原子力発電を続ける」と言う。未来を見ようとしない。目をそむけたまま、次の世代にツケを回そうとしている。
不誠実で無責任な人たちが「日本」という私たちが乗る船の舵(かじ)取りを続けている。それを許してきたのは、ほかならぬ私たち自身だ。
そろそろ本気になって、信頼できる人たちに舵取りを託すためにはどうすればいいのか、考えなければならない。
◇ ◇
宮城県気仙沼市の畠山重篤(しげあつ)さん(77)は、唐桑(からくわ)半島の付け根にある西舞根(もうね)でカキとホタテの養殖をして生計を立ててきた。親の代からの漁師だ。

三陸海岸の豊かな海に異変が生じたのは、日本が経済成長に沸き立っていた1970年ごろだった。しばしば赤潮プランクトンが大発生し、白いはずのカキの身が赤くなった。「血ガキ」と呼ばれ、売り物にならない。ホタテ貝も死んでしまう。
養殖いかだが並ぶ気仙沼湾には工場排水や農薬、化学肥料、生活雑排水などあらゆるものが流れ込み、カキやホタテが育つ環境を損ねていた。
そのうえ、湾に注ぐ大川にダムの建設計画まで持ち上がった。このままでは生きていけない。山の人たちと共にダム建設の反対運動に取り組み、建設断念に追い込んだ。この時、地元の歌人、熊谷龍子さんはこう詠んだ。
森は海を海は森を恋いながら
悠久よりの愛紡ぎゆく
それは、漁師たちの思いと響き合うものだった。沖に出れば、漁師たちは山々を見て船の位置を確認する。良い漁場がどこにあるかも山を目印にして胸に刻んできた。高い山にかかる雲や雪が舞い上がる様子で天候の急変を察知し、難を逃れてきた。「山測り」と呼ばれ、その大切さは今も変わらない。
山と森、里と海はすべてつながっている。唐桑半島の漁師たちはそう信じ、1989年から上流の荒れた山々に木を植える運動を始めた。一番の目印である室根山(むろねさん)に大漁旗を掲げ、ブナやナラの苗木を植えていった。
その運動を「森は海の恋人」と名付けた。
畠山さんがただ者でないのは、この後の行動力である。では、森と海をつなぐものは何か。その探求に乗り出したのだ。
ある日、海の岩が白くなり、海藻が生えなくなる「磯焼け」の問題をNHKが特集で報じていた。その中で、北海道大学水産学部の松永勝彦教授が「森の木を伐(き)ってしまったことが原因です」と解説していた。
海藻が育つためには鉄分が欠かせない。その鉄分は森林から供給される。その森が荒れ、鉄分が海に流れて来なくなったため海藻が育たず、磯が焼けてしまった――そう説いていた。
畠山さんはすぐ、松永教授に連絡し、翌日、仲間と函館市にある研究室を訪ねた。そして、なぜ森の鉄分が海藻にとって必要不可欠なのか、そのメカニズムを詳しく解説してもらった。
森の腐葉土は「フルボ酸」というものをつくり出す。それが土中の鉄分とくっついて「フルボ酸鉄」になり、海に流れ込む。これが植物プランクトンや海藻が光合成をするのに欠かせないのだという。森と海をつなぐ大切なもの。それは鉄だった。
漁師と科学者の共同作業が始まる。1993年、松永教授は学生たちを伴って気仙沼湾を訪れ、湾内に流れ込む鉄や窒素、リンなどの分析に乗り出した。そして、川が運んでくる鉄分が植物プランクトンの生長を促し、海を豊かにしてくれていることをデータで立証した。
畠山さんの探求は、日本の海から世界の海へと広がる。
世界には「肥沃な海」とそうでない海があること。その謎を解くカギは海水に含まれる微量金属、とりわけ鉄が握っていること。困難な微量金属の分析方法を編み出したのはアメリカの海洋化学者、ジョン・マーチン博士であることを知った。
日本近くの北太平洋の海が豊かなのは、中国大陸からジェット気流に乗って飛来する黄砂のおかげであることを明らかにしたのもマーチン博士だ。あの厄介な黄砂が北洋海域に鉄分をもたらし、植物プランクトンの生育を促していたのだ。
探求の旅は、植物の光合成から人間の血液へと続く。人間は血液中の赤血球を通して酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を吐き出すが、その運び役をしているのは赤血球のヘモグロビンに含まれる鉄だ。鉄なしでは、人間もまた生きていけないのだった。
「森は海の恋人」運動から始まった探求は国境を越え、学問の垣根を越えて広がり、命の連鎖の中で鉄が果たしている役割の大きさを浮かび上がらせていった。畠山さんはその成果を次々に本にまとめ、出版した。
その運動に注目したのが京都大学だった。京大は学問が細分化され、タコ壷化していることを危ぶみ、2003年に林学と水産学、農学を統合した「森里海連環学」という新しい学問を立ち上げ、研究センターを新設した。そして、畠山さんにシンポジウムの基調講演を依頼した。新しい学問の意義を語る人間としてふさわしい、と考えたからにほかならない。
それ以降、唐桑半島の海は京都大学の森里海連環学の研究拠点の一つになり、毎年、研究者や学生が訪れるようになった。小さな漁村は「時代の先端」を走っていた。
だが、10年前のあの日、大津波は唐桑の海にも容赦なく押し寄せ、漁船と養殖いかだをすべて押し流していった。高台にある畠山さんの自宅は無事だったものの、海辺の住宅は壊滅、体の不自由な住民4人が逃げ遅れて亡くなった。家族と離れ、市街地の福祉施設に入っていた畠山さんの母親も帰らぬ人となった。
恵みの海による、あまりにも残酷な仕打ち。それでも、漁民は海に生きるしかない。唐桑の人たちはすぐさま、カキの養殖再開へと動き出した。
国内はもちろん、フランスからも養殖いかだなどの支援物資が届いた。かつて、フランスでカキの病気が蔓延し、養殖が危機に陥った際、カキの稚貝を送って救ったのは三陸の漁民たちだった。彼らはそれを忘れていなかった。
海の復元力の強さにも助けられた。住宅や港の復旧を上回るスピードで、海の生き物たちは戻ってきた。畠山さんは「直後は『海は死んだ』とうなだれた。けれども、しばらく経つと、小さなエビや魚が湧き出すような勢いで増えていった」と言う。
森と川は、海の生き物たちが必要とするものを送り続けていた。西舞根のカキの出荷は、震災の翌年には震災前を上回るまで回復した。
震災の経験から何をくみ取るべきか。畠山さんはこう語る。
「日本は森におおわれ、海に囲まれた国です。本来、生きていくのに困ることのない国です。なのに、川という川にダムを造り、護岸をコンクリートで固め、傷めつけてきた。森と川と海の関係を元の自然な状態に戻しなさい、と言われているのではないでしょうか」
豊かさと便利さを追い求める中で、私たちは断ち切ってはならないものまで断ち切ってしまったのではないか。命のつながりにかかわる大切なもの。それに思いを致す時ではないか。 (連載終了)
*メールマガジン「風切通信85」 2021年2月28日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2021年3月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎福島第一原発3号機の爆発(福島中央テレビの映像=サイエンスジャーナルのサイトから)
http://sciencejournal.livedoor.biz/archives/5685129.html
◎畠山重篤さん(佐々木惠里さんのブログから)
https://ameblo.jp/amesatin/entry-12286195283.html
≪参考記事・文献&サイト≫
◎「泊原発 保険は1千億円 核暴走事故も含む」(1988年6月24日付 朝日新聞北海道版)
◎「遅れた避難 50人の死 救えなかったか」(2021年2月17日付 朝日新聞社会面)
◎『あの日から今まで そしてこれから』(上野寛さんのお話を聞く会編)
◎「震災 原発事故9年6カ月」(2020年9月13日、福島民報電子版)
◎『森は海の恋人』(畠山重篤、文春文庫)
◎『鉄は魔法使い』(畠山重篤、小学館)
コロナ禍と大雪の中で争われた山形県の知事選挙は、現職の吉村美栄子氏が圧勝し、四選を果たした。挑戦した元県議の大内理加氏は、頼みとする自民党と公明党の支持者すら十分に取り込めず、惨敗した。

吉村氏が獲得した票は40万票、大内氏は16万9千票余り。吉村氏は新庄市では大内氏のほぼ4倍、米沢市と寒河江(さがえ)市、長井市では3倍の票を獲得した。県内35市町村のうち、大内氏がダブルスコアを免れたのは、自分の選挙地盤である山形市と山辺町だけだった。前回2009年の知事選の結果と比べてみても、その圧勝ぶりは際立っている。
選挙結果が示すものは明白である。有権者は県政の刷新ではなく、継続を望んだ。現職の知事の下で新型コロナウイルスの感染拡大に対処し、その痛手から経済を再生させる道を選んだのである。
コロナで始まり、コロナで終わった選挙だった。現職は「コロナ対策に邁進する姿」を見せればいい。挑戦者には代案を示す余地もない。もとより「現職優位」の状況にあり、菅義偉(よしひで)政権のコロナ対策の不手際もあって、国政与党に支えられた挑戦者には厳しい選挙だった。
それでも、12年ぶりに知事選があった意味は大きい。この2年余り、本誌で吉村県政の澱(よど)みと一族企業・法人グループをめぐる様々な問題を報じてきたが、大内陣営はこうした問題を取り上げ、追及した。選挙を通して、吉村県政が抱える負の部分を初めて知った有権者も多かったのではないか。
山形県の現状と課題も浮かび上がった。
遊説で吉村氏は内閣府の統計を引用して「山形県の1人当たりの県民所得はずっと30位台でした。それが平成29年には26位に上がりました」とアピールした。生産農業所得についても「私が知事になった年には東北で5位でしたが、平成29年には倍増し、東北で2位になりました」と声を張り上げた。
一方の大内氏は「若い女性の県外流出率は全国一。住みたい都道府県ランキングでは46位です。県民から、そして日本中から選ばれる山形県にしましょう」と山形の現状を憂い、県政の刷新を訴えた。
どのデータもそれなりに根拠のあるものだ。それぞれ、山形県の明るい面と課題を指し示している。それらのデータのうち、現職が前向きのデータを引用し、挑戦者がマイナスのデータを使うのも自然なことだが、有権者には「心地良い数字」の方が心に響いたことだろう。
データの使い方は対照的だったが、両者に共通していることがある。それは視野が東北、あるいは日本という狭い範囲にとどまっていること、そして「大きな時代の流れ」に対する意識が希薄な点である。
目の前にあるコロナ禍への対処はもちろん大切だが、ワクチンが開発され、間もなく日本でも接種が始まる。いずれ治療方法も定まり、経済も暮らしも徐々に元に戻っていく。何年かたてば、「あの時は大変だったね」と語れるようになるだろう。
だからこそ、政治家ならコロナ対策にとどまらず、もっと長い時間軸で考え、未来を見据えた言葉を紡ぎ出してほしかった。今、私たちはどういう時代を生きているのか。世界はこれからどうなるのか。生き抜くために、私たちは何をしなければならないのか。信じるところを自らの言葉でもっと語ってほしかった。
◇ ◇
私は個人的な事情で12年前に新聞社を早期退職し、故郷の朝日町に戻って暮らし始めた。朝日連峰の南麓にある町で、実家のある村は積雪が1メートルを超える。
ここからさらに奥まったところに立木(たてき)という集落がある。当然のことながら、雪はもっと深い。60人余りが暮らす小さな村だ。
愛知県出身の牧野広大(こうだい)さん(34)がこの村に通い始めたのは2007年、東北芸術工科大学の4年生の時からである。朝日町は閉校した立木小学校を芸術家や造形作家にアトリエとして貸し出し、創作活動の場として提供していた。彼らに誘われ、その仲間に加わった。
「高校の時から雪国に行こうと思っていました」と牧野さんは言う。生まれ育った愛知県では「季節の巡り」がはっきりしない。北国なら雪が一気に景色を変える。長い冬が来て、それから嬉しい春がやって来る。「自分にはそういう季節の巡りと負荷のかかる環境が必要だと思っていました」。何でもある環境ではモノを渇望する気持ちが湧いてこない。牧野さんにとって、立木は「創作にふさわしい場所」だった。
大学院の修士課程を終えた後、空き家を探してこの村に住みついた。
学生の時から「金属工芸の道で生きていこう」と決めていた。どうせなら、誰も挑んだことのない道がいい。アルミニウムを自然の素材で染める「草木染金属工芸作家」として歩み始めた。
アルミの板を金槌でたたいて成型し、それを酸化処理すると、表面にごく小さい隙間ができる。それに草木の染料をしみ込ませる。そして、熱水で処理して色を封じ込め、食器や花器に仕上げる。そういう工芸家は、日本には牧野さんしかいない。もしかしたら、世界にもいないのではないか。
草木染の作業には広いアトリエと沢水がいる。水道水は使えないからだ。旧立木小学校の作業場が手狭になったため、昨年秋からはアトリエとして別に古民家を借りた。蛇口をひねれば、沢水がほとばしり出る。
2011年、石川県の中谷宇吉郎雪の科学館が主催した国際コンペで銀賞獲得。2015年、山形県総合美術展に「冬の引力」を出品、山形放送賞を受賞。
東京の日本橋高島屋や大丸東京店、大阪の阪急梅田本店で企画展を開き、ホテルや旅館からの注文も入るようになってきた。
結婚して、2人の子と家族4人で雪深い村に生きる。村に溶け込み、地元の消防団にも入った。「できればもっと仕事を広げて、1人でもいいから雇用を生み出したい」という。
実用品を制作して販売する一方で、将来は海外の美術展への出品を目指す。誰も挑んだことのない独創的な作品。彼らはそれをどう評価するだろうか。
実は、朝日町にはすでに世界を相手にビジネスを展開している企業がある。朝日相扶(そうふ)製作所という会社だ。
1970年、「冬の出稼ぎをなくしたい」という地元の切実な声に応えるために設立された。出稼ぎ先の一つだったオフィス家具大手の岡村製作所(現オカムラ)の支援を得て、この会社の椅子の縫製下請けとしてスタートした。相扶という社名は「相互扶助」の意味だ。
従業員23人で発足した会社はほどなく、オイルショックで経営危機に陥る。倒産の危機を救ったのは従業員たちである。「2、3カ月給料がなくても頑張る。会社をなくさないでくれ」と声を上げたのだった。
親会社に頼り切りでは次の危機を乗り越えられない。経営を多角化するため、朝日相扶は独自に家具作りにも乗り出した。県工業技術センターの指導を受け、職人の技を磨いた。
だが、独自ブランドの製造と販売を試みたものの、挫折。販売経費のかかる自社ブランドはあきらめ、家具の相手先ブランドでの製造(OEM)に切り換えて生き延びてきた。
転機は2008年に訪れた。デンマークの家具大手「ワン・コレクション社」からの受注に成功し、「あの会社の製造を手がけているなら」と国内の家具メーカーからの受注も増えていった。「全社全員ものづくり職人に徹する」という社訓を貫いた結果だった。
2012年にはワン・コレクション社が国連信託統治理事会の会議場の椅子を受注し、その製造を朝日相扶に任せた。260脚の椅子をニューヨークの会議場に届けた。
創業者の孫で4代目の阿部佳孝社長は「コロナ禍で国内向けの受注は減りましたが、ヨーロッパ向けは少し伸びました。富裕層は『旅行に行けなくなったから家具を買う』という選択をするのです」と語った。「インテリアを見れば、その人の暮らしぶりが分かる」という価値観の現れという。
経営の理念と方針という点でも、朝日相扶はユニークな会社である。年功序列の考え方をしない。完全な実力主義で「上司が年下」というのをいとわない。改善提案を奨励し、その報償も「工程を1分短縮する提案なら30・75円。作業スペースを1平方メートル空ける提案なら年間8600円」と明示する。いわば、完全ガラス張りの経営だ。
小さな下請け会社は今や従業員138人、売上高13億円の中堅企業に成長し、日々、世界の動きをにらんで挑戦し続けている。
自分の故郷の自慢をしたいわけではない。朝日町は住民6500人余りの小さな町である。そんな町にも世界を相手にビジネスを展開する会社があり、世界をにらんで作品づくりを続ける工芸作家がいる。私たちはそういう時代に生きている、ということを言いたいのだ。
目を凝らせば、山形県の各地で、さらに全国各地でそうした企業や人がそれぞれの分野で新しいことに挑戦している姿が見えてくる。東京や大阪といった大都市に依存しなくても世界とつながり、活路を見出せる時代になってきている。
悲しいことに、日本の政治と行政はそうした流れを捉えられず、置き去りにされつつある。その象徴が情報技術(IT)政策の立ち遅れだ。
山形県庁に公文書の情報公開を求めたら、ハンコを押す欄が40もある文書が出てきた。すべての欄にハンコが押されているわけではないが、ある文書には印影が14もあった。信じられない思いでその文書を眺めた。
民間企業の多くは、ずっと前から電子決裁に踏み切っている。文書を回覧し、ハンコを押す時間はロスそのもので、累積すれば大きな損失になるからだ。山形県庁では日々、税金が失われていく。そのことに声を上げる職員もいない。
吉村美栄子知事は選挙中に「県民幸せデジタル化」なる標語を掲げ、「誰ひとり取り残さない」と声を張り上げた。それを聞いて力が抜けた。「知事とその下で働く県職員こそ、すでに取り残されているのに」と。
3期12年の間、山形県庁のIT政策は迷走を続け、ほとんど進まなかった。文書の電子決裁化はロードマップすらない。県立3病院の医療情報システムの更新がぶざまな経過をたどったことは、本誌の2019年12月号でお伝えした通りである。
陣頭指揮を執るべき知事がIT革命のインパクトのすさまじさをまるで理解していない。熱を込めてそれを説くブレーンや幹部もいない。同じくIT音痴の菅首相が「デジタル庁の創設」を唱え出したので、調子を合わせて「幸せデジタル化」などという標語を唱えているに過ぎない。
ITの世界の主役は遠くない将来に、現在の電子を利用するコンピューターから量子コンピューターに交代する。量子力学を応用するコンピューターはすでに一部、実用化されており、今のスーパーコンピューターで1万年かかる計算を3分で解くという。
それは通信技術の革新と相まって、ITの世界を再び劇的に変えるだろう。普通の人がごく普通に量子コンピューターを使う時代がやがてやって来る。私たちは、次の時代を担う子どもたちにその準備をする機会を与えることができているだろうか。
◇ ◇
もちろん、ITがすべてを決めるわけではない。人工知能(AI)で何でもできるわけでもない。大地に種をまき、それを育てて収穫し、食べる、という生きる基本は変わりようがない。むしろ、より重要になっていくだろう。この分野でITやAIが果たす役割は限られている。愚直に土と向き合い、海に漕ぎ出すことを続けなければならない。
その意味では、農林水産業の担い手が減り続けていることこそ、私たちの社会が抱える最大の問題の一つかもしれない。政府も地方自治体も、第一次産業の担い手を確保するため、様々な施策を展開しているが、流れが変わる気配はない。何が問題なのか。
理容・美容店の経営からリンゴ農家に転じた浅野勇太さん(44)に話を聞いた。

2011年3月の東日本大震災まで、浅野さんは妻の実家がある福島県の浪江町を拠点に南相馬市や仙台市で五つの理美容店を経営していた。それが大震災と原発事故で一変した。
震災から3日目、浅野さん一家は浪江町の山間部に避難し、車中泊をしていた。日本テレビの人気番組「DASH村」の舞台になったところだ。東京電力の福島第一原発で何が起きているのか。カーラジオを除けば、ほかに情報を得るすべはなかった。
そこに山形県白鷹町で暮らす専門学校時代の友人から携帯に電話がかかってきた。原発が爆発したことを初めて知った。友人は「こっちに逃げてこい」と勧めてくれた。
両親を含め一家7人で車3台に分乗し、山形に向かったが、2台は福島市内でガソリンがなくなり、道端に捨てた。「同じように乗り捨てられた車がたくさんあった」という。
自ら会社を経営していただけあって、決断が早い。白鷹町の友人宅に避難して間もなく、近くの空き家を借りて住み始めた。
動きも早い。横浜で建設業をしている弟が津波の被災地でがれきの撤去作業を始め、その手伝いを頼まれると、4月から気仙沼や石巻で働き始めた。会社を経営している間に重機の特殊免許を取っていたのが役に立った。
仙台の宿から被災地に通い、がれきの撤去作業を黙々と続けた。しばしば、がれきの間から遺体が見つかった。ホーンを鳴らし、周りにいる自衛隊員に合図して収容してもらう。厳しい日々だった。
被災地から家族が暮らす白鷹町に戻る時、いつも朝日町を経由した。その度に最上川の河岸段丘に広がるリンゴ畑を目にした。心に染みる風景だった。もともと農業にも興味があった。震災の翌年、リンゴ栽培に取り組むことを決意した。
新規就農者を支援する制度は、それなりに整っている。まず2年間は研修生として受け入れ、農業のベテランが支える。研修を終えれば、5年間は政府から年150万円の給付がある。地方自治体による支援の上積みや農機具をそろえるための補助金制度もある。
浅野さんはそうした制度に支えられ、リンゴ農家としての道を歩み始めた。生活の拠点は避難してきた白鷹町のまま、隣の朝日町で借りた畑に夫婦で通って農業を営む。リンゴのほか、ラフランスやサクランボの栽培も手がけ、栽培面積も3ヘクタールまで広げた。
新規就農者として支えられているだけではない。リンゴを収穫しやすいように樹高を低くするための新しい栽培方法を考案し、その研修会の講師まで務める。師匠の阿部為吉(ためよし)さん(66)も「既存農家も大いに刺激を受けている。本当に力がある」と認める。
とはいえ、浅野さんは「ごくまれなケース」ではある。会社を経営した経験があり、事業のセンスが抜群なこと。原発事故で戻るべき故郷が失われ、就農への決意が固かったこと。事故の避難者として東京電力から受ける補償が下支えになったこと。そうしたことがリンゴ農家としての自立につながった。
実は、新規就農者の大半は農家出身で親の跡を継ぐ若者というのが現実だ。「親元(おやもと)就農」と呼ばれる彼らの定着率は高いが、「異業種からの新規就農者」の多くは夢破れて去っていく。
どんな仕事でも「5年の支援で自立する」というのは極めて難しい。農業も同じだ。栽培のノウハウを習得するのは容易なことではない。トラクターなどの農機具を確保するための初期投資にも数百万円は必要だ。政府の「新規就農者には5年間、資金を給付」という政策は中途半端なのだ。浅野さんのように特別な技能と固い決意がなければ、多くの者が挫折するのも当然と言っていい。
農林水産業の後継者の育成と確保は、今の日本では少子高齢化と並ぶ重要な課題である。だとするなら、もっと思い切った就農支援に踏み切ることを決断すべきではないか。
若い人に新しく農林業や水産業に取り組む決意を固めてもらうためには、5年の支援では短すぎる。結婚して子育てが一段落するまで、20年は公的に支える。それくらい大胆な政策に転じる必要がある。かなりの予算が必要になるが、バランスの取れた社会を取り戻そうとするなら、それだけの負担をする価値は十分にある。
決意をもって未来を語る。そのための政策を打ち出す。それこそ、政治家の仕事ではないか。
*メールマガジン「風切通信84」 2021年2月1日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2021年2月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明≫
◎牧野広大さんと妻曜さん、長男(筆者撮影)
◎浅野勇太さん(オネストのサイトから)
≪参考資料&サイト≫
◎都道府県別の1人当たり県民所得(内閣府経済社会総合研究所の平成29年度県民経済計算)
◎都道府県別の生産農業所得(農林水産省統計)
◎「若い女性流出、悩む地方」(2019年9月6日付 日経新聞夕刊)
◎住みたい都道府県ランキング2020(ブランド総合研究所)
◎「自然と暮らしに光彩を放つ、草木染金属工芸作家」(グローカルミッションタイムズ)
https://www.glocaltimes.jp/
◎『株式会社朝日相扶製作所 20周年記念誌 大樹』
◎『地域発イノベーションV 東北から世界への挑戦』(南北社)
◎農業技術のコンサルタント「オネスト」のサイト「『りんごに恋した』農家」
https://honest.yamagata.jp/archives/farmers/630
◎広報あさひまち2013年9月号の特集「わたし、就農しました」

吉村氏が獲得した票は40万票、大内氏は16万9千票余り。吉村氏は新庄市では大内氏のほぼ4倍、米沢市と寒河江(さがえ)市、長井市では3倍の票を獲得した。県内35市町村のうち、大内氏がダブルスコアを免れたのは、自分の選挙地盤である山形市と山辺町だけだった。前回2009年の知事選の結果と比べてみても、その圧勝ぶりは際立っている。
選挙結果が示すものは明白である。有権者は県政の刷新ではなく、継続を望んだ。現職の知事の下で新型コロナウイルスの感染拡大に対処し、その痛手から経済を再生させる道を選んだのである。
コロナで始まり、コロナで終わった選挙だった。現職は「コロナ対策に邁進する姿」を見せればいい。挑戦者には代案を示す余地もない。もとより「現職優位」の状況にあり、菅義偉(よしひで)政権のコロナ対策の不手際もあって、国政与党に支えられた挑戦者には厳しい選挙だった。
それでも、12年ぶりに知事選があった意味は大きい。この2年余り、本誌で吉村県政の澱(よど)みと一族企業・法人グループをめぐる様々な問題を報じてきたが、大内陣営はこうした問題を取り上げ、追及した。選挙を通して、吉村県政が抱える負の部分を初めて知った有権者も多かったのではないか。
山形県の現状と課題も浮かび上がった。
遊説で吉村氏は内閣府の統計を引用して「山形県の1人当たりの県民所得はずっと30位台でした。それが平成29年には26位に上がりました」とアピールした。生産農業所得についても「私が知事になった年には東北で5位でしたが、平成29年には倍増し、東北で2位になりました」と声を張り上げた。
一方の大内氏は「若い女性の県外流出率は全国一。住みたい都道府県ランキングでは46位です。県民から、そして日本中から選ばれる山形県にしましょう」と山形の現状を憂い、県政の刷新を訴えた。
どのデータもそれなりに根拠のあるものだ。それぞれ、山形県の明るい面と課題を指し示している。それらのデータのうち、現職が前向きのデータを引用し、挑戦者がマイナスのデータを使うのも自然なことだが、有権者には「心地良い数字」の方が心に響いたことだろう。
データの使い方は対照的だったが、両者に共通していることがある。それは視野が東北、あるいは日本という狭い範囲にとどまっていること、そして「大きな時代の流れ」に対する意識が希薄な点である。
目の前にあるコロナ禍への対処はもちろん大切だが、ワクチンが開発され、間もなく日本でも接種が始まる。いずれ治療方法も定まり、経済も暮らしも徐々に元に戻っていく。何年かたてば、「あの時は大変だったね」と語れるようになるだろう。
だからこそ、政治家ならコロナ対策にとどまらず、もっと長い時間軸で考え、未来を見据えた言葉を紡ぎ出してほしかった。今、私たちはどういう時代を生きているのか。世界はこれからどうなるのか。生き抜くために、私たちは何をしなければならないのか。信じるところを自らの言葉でもっと語ってほしかった。
◇ ◇
私は個人的な事情で12年前に新聞社を早期退職し、故郷の朝日町に戻って暮らし始めた。朝日連峰の南麓にある町で、実家のある村は積雪が1メートルを超える。
ここからさらに奥まったところに立木(たてき)という集落がある。当然のことながら、雪はもっと深い。60人余りが暮らす小さな村だ。
愛知県出身の牧野広大(こうだい)さん(34)がこの村に通い始めたのは2007年、東北芸術工科大学の4年生の時からである。朝日町は閉校した立木小学校を芸術家や造形作家にアトリエとして貸し出し、創作活動の場として提供していた。彼らに誘われ、その仲間に加わった。
「高校の時から雪国に行こうと思っていました」と牧野さんは言う。生まれ育った愛知県では「季節の巡り」がはっきりしない。北国なら雪が一気に景色を変える。長い冬が来て、それから嬉しい春がやって来る。「自分にはそういう季節の巡りと負荷のかかる環境が必要だと思っていました」。何でもある環境ではモノを渇望する気持ちが湧いてこない。牧野さんにとって、立木は「創作にふさわしい場所」だった。
大学院の修士課程を終えた後、空き家を探してこの村に住みついた。
学生の時から「金属工芸の道で生きていこう」と決めていた。どうせなら、誰も挑んだことのない道がいい。アルミニウムを自然の素材で染める「草木染金属工芸作家」として歩み始めた。
アルミの板を金槌でたたいて成型し、それを酸化処理すると、表面にごく小さい隙間ができる。それに草木の染料をしみ込ませる。そして、熱水で処理して色を封じ込め、食器や花器に仕上げる。そういう工芸家は、日本には牧野さんしかいない。もしかしたら、世界にもいないのではないか。
草木染の作業には広いアトリエと沢水がいる。水道水は使えないからだ。旧立木小学校の作業場が手狭になったため、昨年秋からはアトリエとして別に古民家を借りた。蛇口をひねれば、沢水がほとばしり出る。
2011年、石川県の中谷宇吉郎雪の科学館が主催した国際コンペで銀賞獲得。2015年、山形県総合美術展に「冬の引力」を出品、山形放送賞を受賞。
東京の日本橋高島屋や大丸東京店、大阪の阪急梅田本店で企画展を開き、ホテルや旅館からの注文も入るようになってきた。
結婚して、2人の子と家族4人で雪深い村に生きる。村に溶け込み、地元の消防団にも入った。「できればもっと仕事を広げて、1人でもいいから雇用を生み出したい」という。
実用品を制作して販売する一方で、将来は海外の美術展への出品を目指す。誰も挑んだことのない独創的な作品。彼らはそれをどう評価するだろうか。
実は、朝日町にはすでに世界を相手にビジネスを展開している企業がある。朝日相扶(そうふ)製作所という会社だ。
1970年、「冬の出稼ぎをなくしたい」という地元の切実な声に応えるために設立された。出稼ぎ先の一つだったオフィス家具大手の岡村製作所(現オカムラ)の支援を得て、この会社の椅子の縫製下請けとしてスタートした。相扶という社名は「相互扶助」の意味だ。
従業員23人で発足した会社はほどなく、オイルショックで経営危機に陥る。倒産の危機を救ったのは従業員たちである。「2、3カ月給料がなくても頑張る。会社をなくさないでくれ」と声を上げたのだった。
親会社に頼り切りでは次の危機を乗り越えられない。経営を多角化するため、朝日相扶は独自に家具作りにも乗り出した。県工業技術センターの指導を受け、職人の技を磨いた。
だが、独自ブランドの製造と販売を試みたものの、挫折。販売経費のかかる自社ブランドはあきらめ、家具の相手先ブランドでの製造(OEM)に切り換えて生き延びてきた。
転機は2008年に訪れた。デンマークの家具大手「ワン・コレクション社」からの受注に成功し、「あの会社の製造を手がけているなら」と国内の家具メーカーからの受注も増えていった。「全社全員ものづくり職人に徹する」という社訓を貫いた結果だった。
2012年にはワン・コレクション社が国連信託統治理事会の会議場の椅子を受注し、その製造を朝日相扶に任せた。260脚の椅子をニューヨークの会議場に届けた。
創業者の孫で4代目の阿部佳孝社長は「コロナ禍で国内向けの受注は減りましたが、ヨーロッパ向けは少し伸びました。富裕層は『旅行に行けなくなったから家具を買う』という選択をするのです」と語った。「インテリアを見れば、その人の暮らしぶりが分かる」という価値観の現れという。
経営の理念と方針という点でも、朝日相扶はユニークな会社である。年功序列の考え方をしない。完全な実力主義で「上司が年下」というのをいとわない。改善提案を奨励し、その報償も「工程を1分短縮する提案なら30・75円。作業スペースを1平方メートル空ける提案なら年間8600円」と明示する。いわば、完全ガラス張りの経営だ。
小さな下請け会社は今や従業員138人、売上高13億円の中堅企業に成長し、日々、世界の動きをにらんで挑戦し続けている。
自分の故郷の自慢をしたいわけではない。朝日町は住民6500人余りの小さな町である。そんな町にも世界を相手にビジネスを展開する会社があり、世界をにらんで作品づくりを続ける工芸作家がいる。私たちはそういう時代に生きている、ということを言いたいのだ。
目を凝らせば、山形県の各地で、さらに全国各地でそうした企業や人がそれぞれの分野で新しいことに挑戦している姿が見えてくる。東京や大阪といった大都市に依存しなくても世界とつながり、活路を見出せる時代になってきている。
悲しいことに、日本の政治と行政はそうした流れを捉えられず、置き去りにされつつある。その象徴が情報技術(IT)政策の立ち遅れだ。
山形県庁に公文書の情報公開を求めたら、ハンコを押す欄が40もある文書が出てきた。すべての欄にハンコが押されているわけではないが、ある文書には印影が14もあった。信じられない思いでその文書を眺めた。
民間企業の多くは、ずっと前から電子決裁に踏み切っている。文書を回覧し、ハンコを押す時間はロスそのもので、累積すれば大きな損失になるからだ。山形県庁では日々、税金が失われていく。そのことに声を上げる職員もいない。
吉村美栄子知事は選挙中に「県民幸せデジタル化」なる標語を掲げ、「誰ひとり取り残さない」と声を張り上げた。それを聞いて力が抜けた。「知事とその下で働く県職員こそ、すでに取り残されているのに」と。
3期12年の間、山形県庁のIT政策は迷走を続け、ほとんど進まなかった。文書の電子決裁化はロードマップすらない。県立3病院の医療情報システムの更新がぶざまな経過をたどったことは、本誌の2019年12月号でお伝えした通りである。
陣頭指揮を執るべき知事がIT革命のインパクトのすさまじさをまるで理解していない。熱を込めてそれを説くブレーンや幹部もいない。同じくIT音痴の菅首相が「デジタル庁の創設」を唱え出したので、調子を合わせて「幸せデジタル化」などという標語を唱えているに過ぎない。
ITの世界の主役は遠くない将来に、現在の電子を利用するコンピューターから量子コンピューターに交代する。量子力学を応用するコンピューターはすでに一部、実用化されており、今のスーパーコンピューターで1万年かかる計算を3分で解くという。
それは通信技術の革新と相まって、ITの世界を再び劇的に変えるだろう。普通の人がごく普通に量子コンピューターを使う時代がやがてやって来る。私たちは、次の時代を担う子どもたちにその準備をする機会を与えることができているだろうか。
◇ ◇
もちろん、ITがすべてを決めるわけではない。人工知能(AI)で何でもできるわけでもない。大地に種をまき、それを育てて収穫し、食べる、という生きる基本は変わりようがない。むしろ、より重要になっていくだろう。この分野でITやAIが果たす役割は限られている。愚直に土と向き合い、海に漕ぎ出すことを続けなければならない。
その意味では、農林水産業の担い手が減り続けていることこそ、私たちの社会が抱える最大の問題の一つかもしれない。政府も地方自治体も、第一次産業の担い手を確保するため、様々な施策を展開しているが、流れが変わる気配はない。何が問題なのか。
理容・美容店の経営からリンゴ農家に転じた浅野勇太さん(44)に話を聞いた。

2011年3月の東日本大震災まで、浅野さんは妻の実家がある福島県の浪江町を拠点に南相馬市や仙台市で五つの理美容店を経営していた。それが大震災と原発事故で一変した。
震災から3日目、浅野さん一家は浪江町の山間部に避難し、車中泊をしていた。日本テレビの人気番組「DASH村」の舞台になったところだ。東京電力の福島第一原発で何が起きているのか。カーラジオを除けば、ほかに情報を得るすべはなかった。
そこに山形県白鷹町で暮らす専門学校時代の友人から携帯に電話がかかってきた。原発が爆発したことを初めて知った。友人は「こっちに逃げてこい」と勧めてくれた。
両親を含め一家7人で車3台に分乗し、山形に向かったが、2台は福島市内でガソリンがなくなり、道端に捨てた。「同じように乗り捨てられた車がたくさんあった」という。
自ら会社を経営していただけあって、決断が早い。白鷹町の友人宅に避難して間もなく、近くの空き家を借りて住み始めた。
動きも早い。横浜で建設業をしている弟が津波の被災地でがれきの撤去作業を始め、その手伝いを頼まれると、4月から気仙沼や石巻で働き始めた。会社を経営している間に重機の特殊免許を取っていたのが役に立った。
仙台の宿から被災地に通い、がれきの撤去作業を黙々と続けた。しばしば、がれきの間から遺体が見つかった。ホーンを鳴らし、周りにいる自衛隊員に合図して収容してもらう。厳しい日々だった。
被災地から家族が暮らす白鷹町に戻る時、いつも朝日町を経由した。その度に最上川の河岸段丘に広がるリンゴ畑を目にした。心に染みる風景だった。もともと農業にも興味があった。震災の翌年、リンゴ栽培に取り組むことを決意した。
新規就農者を支援する制度は、それなりに整っている。まず2年間は研修生として受け入れ、農業のベテランが支える。研修を終えれば、5年間は政府から年150万円の給付がある。地方自治体による支援の上積みや農機具をそろえるための補助金制度もある。
浅野さんはそうした制度に支えられ、リンゴ農家としての道を歩み始めた。生活の拠点は避難してきた白鷹町のまま、隣の朝日町で借りた畑に夫婦で通って農業を営む。リンゴのほか、ラフランスやサクランボの栽培も手がけ、栽培面積も3ヘクタールまで広げた。
新規就農者として支えられているだけではない。リンゴを収穫しやすいように樹高を低くするための新しい栽培方法を考案し、その研修会の講師まで務める。師匠の阿部為吉(ためよし)さん(66)も「既存農家も大いに刺激を受けている。本当に力がある」と認める。
とはいえ、浅野さんは「ごくまれなケース」ではある。会社を経営した経験があり、事業のセンスが抜群なこと。原発事故で戻るべき故郷が失われ、就農への決意が固かったこと。事故の避難者として東京電力から受ける補償が下支えになったこと。そうしたことがリンゴ農家としての自立につながった。
実は、新規就農者の大半は農家出身で親の跡を継ぐ若者というのが現実だ。「親元(おやもと)就農」と呼ばれる彼らの定着率は高いが、「異業種からの新規就農者」の多くは夢破れて去っていく。
どんな仕事でも「5年の支援で自立する」というのは極めて難しい。農業も同じだ。栽培のノウハウを習得するのは容易なことではない。トラクターなどの農機具を確保するための初期投資にも数百万円は必要だ。政府の「新規就農者には5年間、資金を給付」という政策は中途半端なのだ。浅野さんのように特別な技能と固い決意がなければ、多くの者が挫折するのも当然と言っていい。
農林水産業の後継者の育成と確保は、今の日本では少子高齢化と並ぶ重要な課題である。だとするなら、もっと思い切った就農支援に踏み切ることを決断すべきではないか。
若い人に新しく農林業や水産業に取り組む決意を固めてもらうためには、5年の支援では短すぎる。結婚して子育てが一段落するまで、20年は公的に支える。それくらい大胆な政策に転じる必要がある。かなりの予算が必要になるが、バランスの取れた社会を取り戻そうとするなら、それだけの負担をする価値は十分にある。
決意をもって未来を語る。そのための政策を打ち出す。それこそ、政治家の仕事ではないか。
*メールマガジン「風切通信84」 2021年2月1日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2021年2月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明≫
◎牧野広大さんと妻曜さん、長男(筆者撮影)
◎浅野勇太さん(オネストのサイトから)
≪参考資料&サイト≫
◎都道府県別の1人当たり県民所得(内閣府経済社会総合研究所の平成29年度県民経済計算)
◎都道府県別の生産農業所得(農林水産省統計)
◎「若い女性流出、悩む地方」(2019年9月6日付 日経新聞夕刊)
◎住みたい都道府県ランキング2020(ブランド総合研究所)
◎「自然と暮らしに光彩を放つ、草木染金属工芸作家」(グローカルミッションタイムズ)
https://www.glocaltimes.jp/
◎『株式会社朝日相扶製作所 20周年記念誌 大樹』
◎『地域発イノベーションV 東北から世界への挑戦』(南北社)
◎農業技術のコンサルタント「オネスト」のサイト「『りんごに恋した』農家」
https://honest.yamagata.jp/archives/farmers/630
◎広報あさひまち2013年9月号の特集「わたし、就農しました」
人生とは何か。自分は何のために生まれてきたのかーー人は誰しも十代の半ばから、そうしたことを考え、思いわずらうようになる。性の目覚めも重なり、悩みは一層深まる。

そういう時期に「天地がひっくり返るような価値観の転換」を経験すると、人はどうなるのか。それを綴った文章に最近、出くわした。
その一文は『山形南高昭和十九年組 喜寿記念誌』という本に収録されている。昭和5年から6年にかけて生まれ、先の戦争が終わる直前に旧制の山形二中に入学、敗戦を経験した人たちの同窓会誌である。
「昭和二十年の冬頃から、二中の生徒は一斉に不良化の道を進むことになる。誰れ彼れなしに全員が打ち揃っての不良化である。ケンカ、タバコ、マージャン、中には女郎屋から登下校する先輩もいた。女郎屋で先生とバッタリ顔を合わせてしまい『オッス』と言ったら、『オッ』と答えた先生がいたそうだ。その話が学校中に聞こえて、馬鹿が先生に確認したら、革スリッパの底に鋲の出ているヤツでいきなり殴られた」
「先ごろまでは鬼畜米英、一人必殺、竹槍持っても敗けはしない、畳の上で死ぬと思うなと教えられ、その気になっていたのに、たった一年でこの有り様。自由奔放、天真爛漫、腹だけはいつも空いていたっけ」
「戦争だってオレ達の大切な青春だったけど、暗室から一気にオモテに出てみたら、世の中ゼンゼン別なのだ。先生も生徒も一緒になって、遅れて来た自由にガッツいた。何という明るさだったろうか。見慣れた景色が突然に輝いて色がついた感じ。インフレ、食糧、疎開と明るい話はなかったが、そんなことはヘノカッパ。滅茶苦茶な中からすべてが育まれていった」
多感な時期に敗戦を経験した若者たちの苦悩と希望を描いて、余すところがない。筆者は千歳倉庫グループの代表、千歳貞治郎氏(89)である。父親はガダルカナルで戦死した。遺骨どころか、遺品すら届かなかった。
戦中派の彼らの同窓会は「何年卒」と名乗ることができない。戦後の学制改革で旧制山形二中は途中で山形南高校に改編された。旧制中学の5年相当で卒業した者もいるし、新制高校に進んだ者もいる。卒業年次がバラバラなのだ。ゆえに入学年の「昭和十九年組」と称する。
厳しい時代を共に生き抜いたからだろう。彼らの結束は固い。壮年になってからは、毎年ではなく毎月、19日に同窓会を開いてきた。
その結束力は仕事でも選挙でも、遺憾なく発揮される。千歳貞治郎氏は、自民党から新進党、民主党に転じた鹿野道彦代議士の後援会「愛山会」の統括として、鹿野氏の選挙を支え続けた。余り語られることはないが、吉村美栄子氏が当選した2009年1月の知事選でも、極めて重要な役割を果たした。
現職の斎藤弘知事の評判はすこぶる悪かった。自治労や県職労は対立候補の擁立に向けて動き出す。その中で浮上してきたのが吉村美栄子氏だった。
2008年3月に山形県で知的障害者のスペシャルオリンピックス冬季日本大会が開かれた。この時に接遇役を務めた美栄子氏を細川護熙(もりひろ)元首相の佳代子夫人らが高く評価した。佳代子夫人らの勧めを受けて、連合山形の安達忠一会長(当時)や岡田新一事務局長(同)らが自宅に足を運び、何度も出馬を要請した。
だが、美栄子氏の義父で吉村家の当主である敏夫氏は頑として応じなかった。敏夫氏は県教育長や出納長をつとめた県庁OBだ。現職の知事がいかに強いか、骨身に染みて知っていた。「労組や野党が束になっても勝ち目はない」と見ていたのだろう。
それを知り、元知事の高橋和雄氏(90)や千歳貞治郎氏が動いた。「自民党を真っ二つに割れば、勝負になる」と判断し、分断工作に乗り出したのだ。2005年の知事選でも、自民党は新人の斎藤氏を担いだ加藤紘一代議士派と当時現職だった高橋氏を支持する反加藤派に割れ、そのわだかまりが残っていた。
高橋元知事が語る。
「ある日の夕方、参議院議員(自民党)の岸(宏一)さんが自宅に来た。その車に同乗して、二人で吉村家を訪ねた。敏夫さんと美栄子さんが応対したが、途中で敏夫さんは『自分で決めなさい』と席を外した。一人になった美栄子さんは『考えてみます』と答えた」
2008年秋のことだ。この日から、斎藤県政打倒に向けた動きが本格的に始まった。
ただ、大きな問題が残っていた。1億円を超えるとされる知事選の資金をどうするか。担ぎ出した連合山形には、もとよりそんな大金はない。関係者の話を総合すると、連合山形や自治労などが負担した金は全体の5分の1ほどに過ぎない。残りは県内の有力経済人と民主党が賄ったのだという。吉村一族はほとんど負担していない。
選挙資金のめどが立ち、吉村美栄子氏が正式に出馬を表明したのは11月28日のことだ。知事選の告示まで40日しかなかった。
それでも、吉村陣営は「冷(つ)ったい県政から温かい県政に」をスローガンに現職の斎藤知事を猛追し、終盤で抜き去った。
吉村知事の誕生に尽力した二人は、3期12年の県政をどう見ているのか。高橋和雄元知事は「3期やれば十分でしょう。それ以上やれば害の方が大きくなる」と言い切った。
千歳貞治郎氏は何も語らなかった。今回の知事選で吉村後援会の顧問を引き受けたのも「祭り上げられただけ」と言う。知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業と学校法人をめぐる様々な問題については、やや顔を曇らせながらも「あいつはいい奴だ」とかばう。「商売は下手だけどな」と付け加えて。
千歳氏は月刊『素晴らしい山形』の発行人、相澤嘉久治(かくじ)氏についても「あいつはいい奴だ」と言う。毎号、「政治資金で私腹を肥やした」と書かれているのに拘泥しない。千歳氏は山形二中で相澤氏の兄と同学年だった。どちらも父親は山辺町出身である。人との縁を大切にして生きてきたからだろう。
◇ ◇
庄内で吉村知事の誕生に力を尽くした人物となると、平田牧場グループの新田(にった)嘉一会長(87)を真っ先に挙げなければなるまい。
2009年の知事選で新田氏は当初、現職の斎藤知事寄りだったが、終盤になって吉村氏支持に転じた。庄内での吉村氏の得票は鶴岡市を除いて、すべての市町で斎藤氏を上回った。とりわけ、酒田市で大勝した。「新田氏の方針転換が大きく影響した」とされる。
独立不羈(ふき)の人である。何ものにもとらわれず、自分の考えを貫いて生きてきた。
米どころ庄内の南平田村(のち平田町、現酒田市)で農家の長男として生まれた。12町歩の田畑を持つ地主だったが、先の戦争で父親が召集された際、ほとんどの土地を小作人に託して出征した。
働き手を失い、小作の収入も思うように入らず、一家は困窮した。その様子を自伝『平田牧場「三元豚」の奇跡』に記している。
「父が復員するまでの間は、ただただ、ひもじかった記憶しか残っていない。水を飲んで腹を膨らませ、山から雑草を抜いてきては煮て食べていた。(中略)腹ペコの子どもたちに何か食べさせたかったのだろう。母は毎日のように実家から持ってきた着物と食糧とを交換しに出かけた」
「空腹もあるラインを超えると、暗くなっても眠れなくなるのだと初めて知った。まったく眠くならないのだ。その代わり、いろいろな妄想が頭の中に渦巻いてくる。思い描くのは食べ物のことばかりであった」
敗戦は、新田氏にも強烈な刻印を残した。
「世の中ががらりと変わってしまうことも十分にあると身をもって知った。昨日まで威張っていた大人が、途端に態度を豹変させるのも目(ま)の当たりにした。アメリカ兵が大挙して進駐してきても、大人の誰一人として反発する者はいなかった」
「私の家にも米兵が勝手に入り込んでは、家の中のものを随分と持ち出していた。それに対して怒るでもなく、『戦争に負けたのだからしょうがないよ』の一言でおしまいである」
戦後、父親が復員して暮らしは落ち着いた。ただ、父親は政治好きで選挙のたびに飛び回っていたという。
すこぶる頑固だった。「農業に学問はいらない」が持論で、息子が大学に進むことを許さなかった。新田氏は庄内農業高校を卒業して跡を継いだ。
新田氏も父親に劣らず、頑固だった。「十年一日のごとく米を作り、選挙のたびに飛び歩いて一生を終えたくはなかった」という。「遠くない将来、日本でも動物性タンパク質が食の中心になる時代が必ずやってくる」という大学教授の講演に心を動かされ、養豚に取り組むことを決意した。
「養豚業に手を出すなら勘当(かんどう)する」と激怒する父親を説き伏せ、メスの子豚2頭で新しい道に踏み出す。新田氏の悪戦苦闘の日々の始まりだった。
今でこそ、新田氏が率いる平田牧場の豚肉と肉製品は市場での評価も高く、押しも押されもせぬ企業グループへと成長したが、そこに至る道は「養豚業で行き詰まり、資金繰りに窮して自殺した同業者と私との間には、ほんの少しの違いしかなかった」という苛烈(かれつ)な道だった。
流通大手ダイエーへの納入が増え、業績も順調だったのに、ひたすら買いたたこうとするダイエー側のやり方に「震えるほどの怒り」を感じ、取引をやめた。
売り上げは急減した。救いの手を差し伸べてくれた生活クラブ生協との取引でも、無添加ウインナーが輸送時のトラブルもあって腐り、全量廃棄の憂き目にあっている。
「良い豚肉を作り続ければ、いつか必ず消費者に受け入れてもらえる」という信念を曲げずに貫いて、今日に至った。
地元へのこだわりと貢献という点でも、新田氏はユニークな経営者である。ビジネスで得た収益を惜しみなく、酒田市と庄内のために注ぎ続けている。
庄内の経済を活性化するためには「東京との距離」を縮めなければならない。そのためには「どうしても空港がいる」と、庄内空港実現のため汗を流し、身銭を切った。
酒田港を「東方水上シルクロード航路」の拠点にする構想を掲げ、自ら中国東北部に飛び、畜産の技術指導に取り組んだ。そうした労苦の甲斐(かい)あって、黒竜江省からロシアのアムール川経由で酒田港に飼料用トウモロコシを輸入する航路が開かれた。
ビジネスにとどまらず、文化にも力を注ぐ。酒田市美術館の創設に奔走し、ついには県と庄内の自治体を動かして東北公益文科大学の開学に漕ぎつけた。2009年から大学を運営する学校法人の理事長を引き受けている。
理事長としての新田氏のあいさつが興味深い。公益について、次のように語っている。
「公益とは『自立して生きること』です。自立した人間つまり社会に役立つ人間とは、『税金を納める人間』であって、『税金を使う側の人間』ではありません。公益、自立した人間とは、地域で業を起こし、地域へ税金を納める人間になることです」
権力にすり寄り、公金がらみの甘い汁を吸うことばかり考えている人間に聞かせてやりたい言葉である。
その新田氏は3期12年の吉村県政をどう評価しているのか。旧平田町にある自宅を訪ね、その思いを聞いた。
吉村知事は県議会や記者会見で「次の知事選に出るのか」と何度質問されても、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や経済の回復、7月豪雨の被害の復旧といった「県政の課題に全力でまい進する」などと、はぐらかし続けた。正式に出馬を表明したのは2020年の10月下旬だった。
ところが、同年7月9日、吉村知事は元県議を伴って酒田市にある平田牧場のゲストハウス「寄暢(きちょう)亭」(写真)で新田氏に会い、「やり残した仕事があります。よろしくお願いします」と、出馬の意向を明確に伝えたという。

新田氏は「何を残しているのか」と尋ねた。答えは曖昧模糊(あいまいもこ)としたもので、納得のいくものではなかったという。
今回の知事選で、新田氏は現職の吉村知事を支持せず、対立候補の大内理加元県議を応援する立場を明確にしている。「どういうところが納得いかないのですか」と尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「恩を受けたら、その恩を返すのが人としての道。それができていない。人間として失格だ」
具体的には何も語らなかった。推し量るしかないが、事情通は「庄内のことを真剣になって考えようとする姿勢がまるで見えないことが我慢ならないのではないか」という。
例えば、東北公益文科大学のことがある。この大学は2001年に山形県が55%、庄内の自治体が45%の出資をして設立した公設民営の私立大学である。
現在は経営も順調だが、将来を考えれば、公立大学への移行が望ましく、新田氏をはじめとする庄内の関係者はかなり前から県庁に働きかけてきた。だが、吉村知事はまったく動こうとしなかった。
知事が2期目から力を入れ始めた「フル規格の奥羽・羽越新幹線の整備促進」も、今ある山形新幹線を新庄から庄内に延ばす構想を放棄するもので、庄内切り捨ての政策と映っているのかもしれない。
◇ ◇
最初の知事選で吉村美栄子氏を推した千歳貞治郎氏と新田嘉一氏という二人の「戦中派」は12年の歳月を経て、正反対の立場に身を置くことになった。それは、「温かい県政」を期待して一票を投じた人たちの間に深い亀裂が生じていることを意味する。
メディアはその亀裂の様相に光を当て、その意味を伝えなければならない。
それは容易なことではない。それでも、「政治や選挙の報道のあり方を大きく変えなければならないのではないか」と訴えないではいられない。
二人の候補者の動きを「同じ行数で同じように伝える」といった形式的な公平さに囚われすぎているのではないか。報道全体を通してバランスを取り、公平に扱えばいいのであって、もっとメリハリの利いた報道を望みたい。
公けの席で語られたことや正式に発表されたことを報じることも大切だが、ひそかに囁(ささや)かれていることに耳を傾け、報道資料の裏側に隠れていることをえぐり出すことも、それに劣らず重要なことだ。
2021年1月7日告示、24日投開票という知事選の日程が明らかになった頃から、吉村陣営も大内陣営もそれぞれ、調査機関を使って世論調査を実施している。具体的な支持率も漏れ伝わってくる。なぜ、それを1行も書かないのか。「選挙報道とはそういうもの」と思い込み、抜けきれなくなっているのではないか。
一線の記者以上に、編集幹部にそうした報道を変えていく覚悟があるかどうかが問われている。
◇ ◇
冒頭で「天地がひっくり返るような価値観の転換」と書いた。それは先の戦争の敗戦のことであり、8月15日という明確な日付のある転変だった。
私たちは今、それに匹敵するような「価値観の大転換」の時代をくぐり抜けつつある。1989年の冷戦終結の頃から世界の政治と経済はがらりと変わり始め、人々はグローバル化という大竜巻にのみ込まれていった。
情報技術(IT)革命がその変化を加速し、新自由主義というイデオロギーが竜巻に勢いを与える。加えて、コロナ禍が暮らしと生活を強引に変えていく。
ただ、その変化には「8月15日」のような明確な転換点がない。時間軸は長く、ゆっくりしていて気づきにくい。だが、気づいた時には、まるで異なる風景が広がっていることだろう。
政治と報道に携わる者はその風を捉え、その流れに敏感でなければならない。この国にはそういう人間が少なすぎる。知事選に立候補する二人からも、そうしたことを見据えたメッセージが伝わって来ない。
前途は厳しい。あの敗戦の時のように、私たちはまた「滅茶苦茶な中」から立ち上がり、新しいものを創っていくしかないのかもしれない。
*メールマガジン「風切通信 83」 2020年12月24日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2021年1月号に寄稿した文章を若干てなおししたものです。
≪写真説明≫
◎山形南高昭和十九年組の同窓会旅行(1998年、羽黒山にて)。前列左端が千歳貞治郎氏(『山形南高昭和十九年組 喜寿記念誌』から)
≪参考文献&記事≫
◎『山形南高昭和十九年組 喜寿記念誌』(2008年発行、非売品)
◎『定本 ガダルカナル戦詩集』(吉田嘉七、創樹社)
◎AERA2017年5月1日?5月8日合併号「現代の肖像 吉村美栄子山形県知事」
◎2009年1月26日付の新聞各紙
◎『平田牧場「三元豚」の奇跡』(新田嘉一、潮出版社)
◎『商港都市酒田物語 新田嘉一の夢と情熱』(粕谷昭二、荘内日報社)
◎東北公益文科大学の公式サイト「理事長あいさつ」

そういう時期に「天地がひっくり返るような価値観の転換」を経験すると、人はどうなるのか。それを綴った文章に最近、出くわした。
その一文は『山形南高昭和十九年組 喜寿記念誌』という本に収録されている。昭和5年から6年にかけて生まれ、先の戦争が終わる直前に旧制の山形二中に入学、敗戦を経験した人たちの同窓会誌である。
「昭和二十年の冬頃から、二中の生徒は一斉に不良化の道を進むことになる。誰れ彼れなしに全員が打ち揃っての不良化である。ケンカ、タバコ、マージャン、中には女郎屋から登下校する先輩もいた。女郎屋で先生とバッタリ顔を合わせてしまい『オッス』と言ったら、『オッ』と答えた先生がいたそうだ。その話が学校中に聞こえて、馬鹿が先生に確認したら、革スリッパの底に鋲の出ているヤツでいきなり殴られた」
「先ごろまでは鬼畜米英、一人必殺、竹槍持っても敗けはしない、畳の上で死ぬと思うなと教えられ、その気になっていたのに、たった一年でこの有り様。自由奔放、天真爛漫、腹だけはいつも空いていたっけ」
「戦争だってオレ達の大切な青春だったけど、暗室から一気にオモテに出てみたら、世の中ゼンゼン別なのだ。先生も生徒も一緒になって、遅れて来た自由にガッツいた。何という明るさだったろうか。見慣れた景色が突然に輝いて色がついた感じ。インフレ、食糧、疎開と明るい話はなかったが、そんなことはヘノカッパ。滅茶苦茶な中からすべてが育まれていった」
多感な時期に敗戦を経験した若者たちの苦悩と希望を描いて、余すところがない。筆者は千歳倉庫グループの代表、千歳貞治郎氏(89)である。父親はガダルカナルで戦死した。遺骨どころか、遺品すら届かなかった。
戦中派の彼らの同窓会は「何年卒」と名乗ることができない。戦後の学制改革で旧制山形二中は途中で山形南高校に改編された。旧制中学の5年相当で卒業した者もいるし、新制高校に進んだ者もいる。卒業年次がバラバラなのだ。ゆえに入学年の「昭和十九年組」と称する。
厳しい時代を共に生き抜いたからだろう。彼らの結束は固い。壮年になってからは、毎年ではなく毎月、19日に同窓会を開いてきた。
その結束力は仕事でも選挙でも、遺憾なく発揮される。千歳貞治郎氏は、自民党から新進党、民主党に転じた鹿野道彦代議士の後援会「愛山会」の統括として、鹿野氏の選挙を支え続けた。余り語られることはないが、吉村美栄子氏が当選した2009年1月の知事選でも、極めて重要な役割を果たした。
現職の斎藤弘知事の評判はすこぶる悪かった。自治労や県職労は対立候補の擁立に向けて動き出す。その中で浮上してきたのが吉村美栄子氏だった。
2008年3月に山形県で知的障害者のスペシャルオリンピックス冬季日本大会が開かれた。この時に接遇役を務めた美栄子氏を細川護熙(もりひろ)元首相の佳代子夫人らが高く評価した。佳代子夫人らの勧めを受けて、連合山形の安達忠一会長(当時)や岡田新一事務局長(同)らが自宅に足を運び、何度も出馬を要請した。
だが、美栄子氏の義父で吉村家の当主である敏夫氏は頑として応じなかった。敏夫氏は県教育長や出納長をつとめた県庁OBだ。現職の知事がいかに強いか、骨身に染みて知っていた。「労組や野党が束になっても勝ち目はない」と見ていたのだろう。
それを知り、元知事の高橋和雄氏(90)や千歳貞治郎氏が動いた。「自民党を真っ二つに割れば、勝負になる」と判断し、分断工作に乗り出したのだ。2005年の知事選でも、自民党は新人の斎藤氏を担いだ加藤紘一代議士派と当時現職だった高橋氏を支持する反加藤派に割れ、そのわだかまりが残っていた。
高橋元知事が語る。
「ある日の夕方、参議院議員(自民党)の岸(宏一)さんが自宅に来た。その車に同乗して、二人で吉村家を訪ねた。敏夫さんと美栄子さんが応対したが、途中で敏夫さんは『自分で決めなさい』と席を外した。一人になった美栄子さんは『考えてみます』と答えた」
2008年秋のことだ。この日から、斎藤県政打倒に向けた動きが本格的に始まった。
ただ、大きな問題が残っていた。1億円を超えるとされる知事選の資金をどうするか。担ぎ出した連合山形には、もとよりそんな大金はない。関係者の話を総合すると、連合山形や自治労などが負担した金は全体の5分の1ほどに過ぎない。残りは県内の有力経済人と民主党が賄ったのだという。吉村一族はほとんど負担していない。
選挙資金のめどが立ち、吉村美栄子氏が正式に出馬を表明したのは11月28日のことだ。知事選の告示まで40日しかなかった。
それでも、吉村陣営は「冷(つ)ったい県政から温かい県政に」をスローガンに現職の斎藤知事を猛追し、終盤で抜き去った。
吉村知事の誕生に尽力した二人は、3期12年の県政をどう見ているのか。高橋和雄元知事は「3期やれば十分でしょう。それ以上やれば害の方が大きくなる」と言い切った。
千歳貞治郎氏は何も語らなかった。今回の知事選で吉村後援会の顧問を引き受けたのも「祭り上げられただけ」と言う。知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業と学校法人をめぐる様々な問題については、やや顔を曇らせながらも「あいつはいい奴だ」とかばう。「商売は下手だけどな」と付け加えて。
千歳氏は月刊『素晴らしい山形』の発行人、相澤嘉久治(かくじ)氏についても「あいつはいい奴だ」と言う。毎号、「政治資金で私腹を肥やした」と書かれているのに拘泥しない。千歳氏は山形二中で相澤氏の兄と同学年だった。どちらも父親は山辺町出身である。人との縁を大切にして生きてきたからだろう。
◇ ◇
庄内で吉村知事の誕生に力を尽くした人物となると、平田牧場グループの新田(にった)嘉一会長(87)を真っ先に挙げなければなるまい。
2009年の知事選で新田氏は当初、現職の斎藤知事寄りだったが、終盤になって吉村氏支持に転じた。庄内での吉村氏の得票は鶴岡市を除いて、すべての市町で斎藤氏を上回った。とりわけ、酒田市で大勝した。「新田氏の方針転換が大きく影響した」とされる。
独立不羈(ふき)の人である。何ものにもとらわれず、自分の考えを貫いて生きてきた。
米どころ庄内の南平田村(のち平田町、現酒田市)で農家の長男として生まれた。12町歩の田畑を持つ地主だったが、先の戦争で父親が召集された際、ほとんどの土地を小作人に託して出征した。
働き手を失い、小作の収入も思うように入らず、一家は困窮した。その様子を自伝『平田牧場「三元豚」の奇跡』に記している。
「父が復員するまでの間は、ただただ、ひもじかった記憶しか残っていない。水を飲んで腹を膨らませ、山から雑草を抜いてきては煮て食べていた。(中略)腹ペコの子どもたちに何か食べさせたかったのだろう。母は毎日のように実家から持ってきた着物と食糧とを交換しに出かけた」
「空腹もあるラインを超えると、暗くなっても眠れなくなるのだと初めて知った。まったく眠くならないのだ。その代わり、いろいろな妄想が頭の中に渦巻いてくる。思い描くのは食べ物のことばかりであった」
敗戦は、新田氏にも強烈な刻印を残した。
「世の中ががらりと変わってしまうことも十分にあると身をもって知った。昨日まで威張っていた大人が、途端に態度を豹変させるのも目(ま)の当たりにした。アメリカ兵が大挙して進駐してきても、大人の誰一人として反発する者はいなかった」
「私の家にも米兵が勝手に入り込んでは、家の中のものを随分と持ち出していた。それに対して怒るでもなく、『戦争に負けたのだからしょうがないよ』の一言でおしまいである」
戦後、父親が復員して暮らしは落ち着いた。ただ、父親は政治好きで選挙のたびに飛び回っていたという。
すこぶる頑固だった。「農業に学問はいらない」が持論で、息子が大学に進むことを許さなかった。新田氏は庄内農業高校を卒業して跡を継いだ。
新田氏も父親に劣らず、頑固だった。「十年一日のごとく米を作り、選挙のたびに飛び歩いて一生を終えたくはなかった」という。「遠くない将来、日本でも動物性タンパク質が食の中心になる時代が必ずやってくる」という大学教授の講演に心を動かされ、養豚に取り組むことを決意した。
「養豚業に手を出すなら勘当(かんどう)する」と激怒する父親を説き伏せ、メスの子豚2頭で新しい道に踏み出す。新田氏の悪戦苦闘の日々の始まりだった。
今でこそ、新田氏が率いる平田牧場の豚肉と肉製品は市場での評価も高く、押しも押されもせぬ企業グループへと成長したが、そこに至る道は「養豚業で行き詰まり、資金繰りに窮して自殺した同業者と私との間には、ほんの少しの違いしかなかった」という苛烈(かれつ)な道だった。
流通大手ダイエーへの納入が増え、業績も順調だったのに、ひたすら買いたたこうとするダイエー側のやり方に「震えるほどの怒り」を感じ、取引をやめた。
売り上げは急減した。救いの手を差し伸べてくれた生活クラブ生協との取引でも、無添加ウインナーが輸送時のトラブルもあって腐り、全量廃棄の憂き目にあっている。
「良い豚肉を作り続ければ、いつか必ず消費者に受け入れてもらえる」という信念を曲げずに貫いて、今日に至った。
地元へのこだわりと貢献という点でも、新田氏はユニークな経営者である。ビジネスで得た収益を惜しみなく、酒田市と庄内のために注ぎ続けている。
庄内の経済を活性化するためには「東京との距離」を縮めなければならない。そのためには「どうしても空港がいる」と、庄内空港実現のため汗を流し、身銭を切った。
酒田港を「東方水上シルクロード航路」の拠点にする構想を掲げ、自ら中国東北部に飛び、畜産の技術指導に取り組んだ。そうした労苦の甲斐(かい)あって、黒竜江省からロシアのアムール川経由で酒田港に飼料用トウモロコシを輸入する航路が開かれた。
ビジネスにとどまらず、文化にも力を注ぐ。酒田市美術館の創設に奔走し、ついには県と庄内の自治体を動かして東北公益文科大学の開学に漕ぎつけた。2009年から大学を運営する学校法人の理事長を引き受けている。
理事長としての新田氏のあいさつが興味深い。公益について、次のように語っている。
「公益とは『自立して生きること』です。自立した人間つまり社会に役立つ人間とは、『税金を納める人間』であって、『税金を使う側の人間』ではありません。公益、自立した人間とは、地域で業を起こし、地域へ税金を納める人間になることです」
権力にすり寄り、公金がらみの甘い汁を吸うことばかり考えている人間に聞かせてやりたい言葉である。
その新田氏は3期12年の吉村県政をどう評価しているのか。旧平田町にある自宅を訪ね、その思いを聞いた。
吉村知事は県議会や記者会見で「次の知事選に出るのか」と何度質問されても、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や経済の回復、7月豪雨の被害の復旧といった「県政の課題に全力でまい進する」などと、はぐらかし続けた。正式に出馬を表明したのは2020年の10月下旬だった。
ところが、同年7月9日、吉村知事は元県議を伴って酒田市にある平田牧場のゲストハウス「寄暢(きちょう)亭」(写真)で新田氏に会い、「やり残した仕事があります。よろしくお願いします」と、出馬の意向を明確に伝えたという。

新田氏は「何を残しているのか」と尋ねた。答えは曖昧模糊(あいまいもこ)としたもので、納得のいくものではなかったという。
今回の知事選で、新田氏は現職の吉村知事を支持せず、対立候補の大内理加元県議を応援する立場を明確にしている。「どういうところが納得いかないのですか」と尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「恩を受けたら、その恩を返すのが人としての道。それができていない。人間として失格だ」
具体的には何も語らなかった。推し量るしかないが、事情通は「庄内のことを真剣になって考えようとする姿勢がまるで見えないことが我慢ならないのではないか」という。
例えば、東北公益文科大学のことがある。この大学は2001年に山形県が55%、庄内の自治体が45%の出資をして設立した公設民営の私立大学である。
現在は経営も順調だが、将来を考えれば、公立大学への移行が望ましく、新田氏をはじめとする庄内の関係者はかなり前から県庁に働きかけてきた。だが、吉村知事はまったく動こうとしなかった。
知事が2期目から力を入れ始めた「フル規格の奥羽・羽越新幹線の整備促進」も、今ある山形新幹線を新庄から庄内に延ばす構想を放棄するもので、庄内切り捨ての政策と映っているのかもしれない。
◇ ◇
最初の知事選で吉村美栄子氏を推した千歳貞治郎氏と新田嘉一氏という二人の「戦中派」は12年の歳月を経て、正反対の立場に身を置くことになった。それは、「温かい県政」を期待して一票を投じた人たちの間に深い亀裂が生じていることを意味する。
メディアはその亀裂の様相に光を当て、その意味を伝えなければならない。
それは容易なことではない。それでも、「政治や選挙の報道のあり方を大きく変えなければならないのではないか」と訴えないではいられない。
二人の候補者の動きを「同じ行数で同じように伝える」といった形式的な公平さに囚われすぎているのではないか。報道全体を通してバランスを取り、公平に扱えばいいのであって、もっとメリハリの利いた報道を望みたい。
公けの席で語られたことや正式に発表されたことを報じることも大切だが、ひそかに囁(ささや)かれていることに耳を傾け、報道資料の裏側に隠れていることをえぐり出すことも、それに劣らず重要なことだ。
2021年1月7日告示、24日投開票という知事選の日程が明らかになった頃から、吉村陣営も大内陣営もそれぞれ、調査機関を使って世論調査を実施している。具体的な支持率も漏れ伝わってくる。なぜ、それを1行も書かないのか。「選挙報道とはそういうもの」と思い込み、抜けきれなくなっているのではないか。
一線の記者以上に、編集幹部にそうした報道を変えていく覚悟があるかどうかが問われている。
◇ ◇
冒頭で「天地がひっくり返るような価値観の転換」と書いた。それは先の戦争の敗戦のことであり、8月15日という明確な日付のある転変だった。
私たちは今、それに匹敵するような「価値観の大転換」の時代をくぐり抜けつつある。1989年の冷戦終結の頃から世界の政治と経済はがらりと変わり始め、人々はグローバル化という大竜巻にのみ込まれていった。
情報技術(IT)革命がその変化を加速し、新自由主義というイデオロギーが竜巻に勢いを与える。加えて、コロナ禍が暮らしと生活を強引に変えていく。
ただ、その変化には「8月15日」のような明確な転換点がない。時間軸は長く、ゆっくりしていて気づきにくい。だが、気づいた時には、まるで異なる風景が広がっていることだろう。
政治と報道に携わる者はその風を捉え、その流れに敏感でなければならない。この国にはそういう人間が少なすぎる。知事選に立候補する二人からも、そうしたことを見据えたメッセージが伝わって来ない。
前途は厳しい。あの敗戦の時のように、私たちはまた「滅茶苦茶な中」から立ち上がり、新しいものを創っていくしかないのかもしれない。
*メールマガジン「風切通信 83」 2020年12月24日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2021年1月号に寄稿した文章を若干てなおししたものです。
≪写真説明≫
◎山形南高昭和十九年組の同窓会旅行(1998年、羽黒山にて)。前列左端が千歳貞治郎氏(『山形南高昭和十九年組 喜寿記念誌』から)
≪参考文献&記事≫
◎『山形南高昭和十九年組 喜寿記念誌』(2008年発行、非売品)
◎『定本 ガダルカナル戦詩集』(吉田嘉七、創樹社)
◎AERA2017年5月1日?5月8日合併号「現代の肖像 吉村美栄子山形県知事」
◎2009年1月26日付の新聞各紙
◎『平田牧場「三元豚」の奇跡』(新田嘉一、潮出版社)
◎『商港都市酒田物語 新田嘉一の夢と情熱』(粕谷昭二、荘内日報社)
◎東北公益文科大学の公式サイト「理事長あいさつ」
吉村美栄子知事の義理のいとこ、吉村和文氏が社長をつとめる「ケーブルテレビ山形」は、2016年1月に「ダイバーシティメディア」と社名を変更した。

吉村県政が誕生した後、会社の売上高は急増したが、2011年3月期をピークに減少に転じた。とくに、主力のケーブルテレビ事業の収入が減り続けている(図1)。その落ち込みを補うためには経営を多角化するしかない。社名の変更は、その決意を示したものだろう。
この会社が学校法人、東海山形学園から3000万円の融資を受けたのは、社名変更から2カ月後のことだ。かなりの金額である。その融資が何のためだったのか、経営のかじ取りをする社長が記憶していないはずがない。
融資の目的について、和文氏は山形新聞の取材に対して次のように答えている。
「ダイバー社のハイビジョン化の設備投資を目的に、複数金融機関の融資承認がそろうまでの間の短期貸付だった」(2017年7月4日付の記事)
先細り気味とはいえ、ケーブルテレビ事業は売り上げの7割を占める。その部門への設備投資を怠るわけにはいかない。けれども、メインバンクの山形銀行をはじめとする金融機関はなかなか金を貸してくれない。それで自分が理事長をしている学校法人から借りた――というわけだ。
その3000万円をダイバー社は2カ月後に返済している。融資の審査が終わって銀行が貸してくれたのか、といった疑問は残るものの、それなりに筋の通った説明だった。
ところが、和文氏は最近になって「設備投資のための融資説」を撤回し、あれは「学校法人の資産運用だった」と言い始めた。今年の10月15日付で報道各社に配布した「東海山形学園の貸付についての経緯説明」という文書で次のように記している。少し長いが、冒頭部分をそのまま引用する。
「東日本大震災後の2013年当時は、国や県から校舎の耐震強化についての指導があり、本学園においても、生徒と教職員の命に関わる大事業に取り組むにあたり、いかにして自己資金を増やし経営を安定させるかが大きな課題でありました」
「このことについて理事会では何度も議論を重ね、学園の資金を増やし、耐久年数が心配される校舎の改築費用に充て、私立学校の高額な授業料を減額する目的で、文部科学省の『学校法人における資産運用について』を参考に『運用の安全性』を考慮し、元本が保証され資産が毀損(きそん)しない相手として、2013年に私個人に5000万円、2016年にダイバーシティメディアに3000万円の貸付を行いました」
このコラム(2020年9月30日)でお伝えしたように、和文氏個人にもダイバー社にもこの時期、担保として提供できる資産はほとんどなく、金融機関は融資を渋っていた。それを「元本の返済が保証される相手」と記す感覚には驚いてしまう。貸付に伴うリスクをまるで考えていない。
文書はA4判で2ページ分ある。2ページ目には、この資金運用について学校法人の理事会でどのような手続きをしたか、私学助成を担当する山形県学事文書課からどのような指摘を受けたかについて詳細につづっている。
とりわけ、和文氏が学校法人の理事長と会社の社長を兼ねていることから、金銭の貸付が利益相反行為になることについては「所轄庁である県に(特別代理人の選任を)申請しなければなりませんでしたが、その認識がなく、それを行っていませんでした。(中略)当学園の責任であり、心よりお詫び申し上げます」と陳謝している。
利益相反行為について「その認識がなかった」と書いている部分は正直とも言えるが、「会社の金も学校の金も自分のもの」と考えていたことを“自白”したようなものだ。学校法人の理事長としての資質を問われかねない重大事だが、そうした意識もないのだろう。
文書では、最初から最後まで「資産の運用だった」という主張を貫いている。「設備投資のための融資」という表現はまったく出てこない。してみると、先の山形新聞の取材に対しては「口から出まかせのウソ」を言った、ということだろう。河北新報にも当時、「資金は設備投資に充てた」と答えている(写真)。これもデタラメだったことになる。
報道機関に対してウソをつくのは許しがたいことである。ウソをつかれたと分かったなら、記者は猛烈に怒らなければならない。読者や視聴者はそれを事実と受けとめるからだ。少なくとも、報道する者にはその矛盾をきちんと追及し、フォーローする責任がある。黙って見過ごしてはいけない。
では、今回の釈明は信用できるのか。
文書によれば、最初に問題になった2016年の3000万円融資については、2カ月後に年利2・5%の利息13万円余りを付けて返済したという。そして、この秋に発覚した2013年の5000万円については「8日後」に同じ年利で2万7397円の利息を付けて返した、と記している。
資産の運用は通常、株式や債券などを購入して行う。リスクはあるが、見返りも大きい。リスクが心配なら、国債を買ったり、金融機関に定期で預けたりするのが常道だ。「8日間、金を貸して利子を得る」のを資産運用と言い張るのは和文氏くらいだろう。
金を貸して利子を取るのは「貸金業」という。もし、東海山形学園がこうしたことを繰り返せば、今度は貸金業法に触れるおそれがある。文部科学省も山形県も、学校法人が「資産運用のため」貸金業を営むのを認めることはあるまい。
いずれにせよ、利益相反行為の場合に必要な「特別代理人の選任」を怠ったので、東海山形学園は理事会でこれを追認する手続きを踏まなければならなかった。2016年の3000万円の貸付は、その年の9月の理事会で追認した。一方、2013年の5000万円については今年10月の理事会で追認したという。
なんと、7年もたってからの追認だ。異様と言うしかない。しかも、こんな重要なことを県には「口頭で報告」したのだとか。それで了承した学事文書課もどうかしている。議事録を添えて文書で報告させ、議事の内容をきちんと確認するのが当然ではないか。東海山形学園も県当局も常軌を逸している。
報道各社あてのこの文書は、10月27日に山形県私学会館で開かれた県内の学校法人の理事長・校長会でも日付だけ手直しして配布され、和文氏が釈明にあたった。出席者によれば、この会合でも「8日間の資産運用というのは短すぎるのではないか」という質問が出た。これに対し、和文氏は「試しに運用してみた」などと説明して煙に巻いたという。
質問はこれだけだった。出席者の一人は「少子化で生徒が減り、どこの高校も経営が厳しい。銀行から金を借りるのならともかく、貸すことなど考えられません」と述べ、こう言葉を継いだ。「ただ、私立学校にはそれぞれの立場があります。よその学校のことについて、あれこれ言うわけにはいきません」
誰も納得していない。和文氏はなぜ設備投資のための融資説を撤回したのか。これで資産の運用と言えるのか。和文氏に手紙をしたためて問い合わせたが、返事はない。説明を求めようと会社に電話をかけても、彼は出てこなかった。
本当は何に使ったのか。この5000万円については「プロレスに投資したのではないか」との憶測が消えない。
ジャイアント馬場、アントニオ猪木といったスター選手がリングを降りてから、プロレス業界は四分五裂の状態に陥った。5000万円の貸付があった2013年当時も、人気プロレスラーの秋山準ら5人の選手がそれまで属していた団体から離れ、全日本プロレスに移籍する騒動があった。
事情通によると、この時、秋山選手らを支えたのがケーブルテレビ山形の吉村和文氏とジャイアント馬場の元子夫人だった。元子夫人は横浜市青葉区にあるプロレスの道場と合宿所を提供し、資金はケーブルテレビ山形が負担する段取りになったようだ。興行権の確保や新会社の設立準備などのため数千万円の資金を必要としたはず、という。
翌2014年の夏、和文氏は「全日本プロレス・イノベーション」(本社・山形市)という持ち株会社と運営会社の「オールジャパン・プロレスリング」(本社・横浜市)を立ち上げ、両方の会社の取締役会長に就任した。社長は秋山選手である。
ケーブルテレビが生き残るためには、NHKや民放が放送しない、あるいは放送できない番組を提供しなければならない。プロレスはそのための有力なコンテンツの一つ、と考えて進出を決めたようだ。
和文氏はかなり前から、プロレスに関心を寄せていた。彼のブログ「約束の地へ」で「プロレス」と打ち込んで検索すると、この10年間で122件もヒットする。
ブログの主なものに目を通してみた。2013年ごろ、山形南高校応援団の後輩でプロレスのプロモーターをしていた高橋英樹氏や「平成のミスタープロレス」と呼ばれた武藤敬司氏、馬場元子夫人らが相次いで山形を訪れていた。和文氏に会うためで、彼は「プロレスのタニマチ」のように振る舞っている。新しいビジネスへの進出に意欲を燃やしていた。
ただ、この業界は昔から「売り上げの分配」をめぐる争いが絶えない。それぞれの選手にいくらギャラを払うのか。興行主の取り分をどうするのか。関連グッズの売り上げは・・・。新たにスタートした全日本プロレスも例外ではなかった。
別冊宝島のプロレス特集(2016年2月28日)によれば、立ち上げから1年で、新生全日本プロレスは5000万円の赤字になってしまった(図2)。「始める前は気分が高揚して期待を持ってしまうのだけれども、見通しが甘すぎるのと、現場の選手たちは誰も親会社に恩義など感じていないので、結果としてこうなってしまう」のだという。和文氏が会長をつとめる持ち株会社の最近3年間の決算を見ても、ずっと赤字続きだ。
秋山選手はすでに社長を退き、別のプロレス団体のコーチをしている。新会社の立ち上げ時に何があったのか。事実関係を問いただそうとしたが、ついに接触できなかった。
5000万円は何に使われたのか。いまだ闇の中である。
◇ ◇
3年前、東海山形学園からダイバーシティメディアへの3000万円融資問題が表面化した際、吉村美栄子知事は記者会見でどう思うか問われ、「(学校法人が)適切に運営されているのであれば、よろしいのではないかというふうに思っております。(中略)そのことについて問題ないようだというふうに担当のほうから聞いております」と涼しい顔で答えた。
その後、東海山形学園が私立学校法に定められた「特別代理人の選任申請」をしていなかったことが明らかになった。3000万円融資の事実は県に提出された貸借対照表に記載されており、担当者はそれが利益相反行為に該当することを知り得たのに、漫然と見過ごしていたことも判明した。
学校法人は、ちっとも「適切に運営」されていなかったし、「担当のほう」もまるで頼りにならない仕事ぶりだった。さらに、5000万円の貸付について担当者はその後、気づいたのに、市民オンブズマンが発表するまで隠していた。知事の涼しい顔は、次第に苦々しい顔に変わっていった。
とはいえ、吉村知事は4期目をめざして、来年1月の知事選に出馬することを表明した。「いつまでも、こんなことに構っていられない。知事選に全力を注ぐだけ」という心境だろう。
出馬表明の記者会見では、新型コロナウイルスへの対応と経済対策との両立を図る考えを示し、最初の知事選の時の初心に帰って「正々堂々と政策を掲げて戦いたい」と述べた。県政と吉村一族企業との問題など小さな争点にすらならない、という風情だ。
だが、一族企業と学校法人の問題はそんなに根の浅いものではない。実は、吉村和文氏は毎年のように利益相反行為を繰り返している疑いがあるのだ。
和文氏はダイバーシティメディアの社長であり、学園の理事長であると同時に、映画館運営会社「ムービーオン」の社長も兼ねている。
東海大山形高校の教職員や生徒、保護者の証言によれば、学園は毎年、生徒全員分の映画チケットを購入し、タダで配っているという。映画チケットは各映画館共通のチケットではない(そのようなものはない)。生徒に配られたのは「ムービーオン」という特定の映画館のチケットである。
筆者の取材によれば、少なくとも2014年まで遡ることができる。関係者が多数いるので、確認するのも難しいことではない。
東海大山形高校の生徒数は図3の通りである。ここ7年間の平均だと、800人ほどだ。高校生の団体割引の映画チケットは1枚800円なので、生徒数を掛けると年間64万円、7年で448万円になる。
それほど大きな金額ではないが、問題はそれらの映画チケットの購入が「東海山形学園 吉村和文理事長」の名前で行われることにある。この学校法人を代表して購入契約を結ぶ権限があるのは理事長ただ一人だけだ。
つまり、東海山形学園は毎年、理事長が社長を兼ねる映画館会社のチケットを大量に購入して売り上げ増に貢献しているが、それらのチケット購入はすべて「利益相反行為」になる、ということだ。
利益が相反する以上、そうしたことは理事長の権限で行うことはできない。私立学校法に基づいて、学園は毎年、所轄庁の山形県に「特別代理人の選任」を申請し、利害関係のない第三者に取引が公正かどうかチェックしてもらう義務があった。
さらに、今春施行の法改正によって特別代理人の選任は不要になったが、利益相反行為であることに変わりはないので、今後も理事会で厳正にチェックする必要がある。一族企業と学校法人の間で、資金の融通や物品の購入を勝手気ままに行うことは、いかなる場合でも許されないのだ。
ことは、東海山形学園とダイバーシティメディア、ムービーオンだけの関係にとどまらない。学園が一族企業と交わすすべての契約について「利益相反行為」の疑いが生じ、チェックする必要が出てくる。
多数の企業を経営する人物が学校法人の理事長を兼ねれば、常にこういう問題が起き、公平さを疑われる事態を招くことになる。
だからこそ、文部科学省は「理事長についてはできる限り常勤化や兼職の制限を行うことが期待される」との事務次官通知(2004年7月23日付)を出し、さらに「理事長は責任に見合った勤務形態を取り、対内的にも対外的にも責任を果たしていくことが重要と考える。兼職は避けることが望ましい」との見解(高等教育局私学行政課)を出しているのだ。
普通なら、都道府県の職員は中央官庁の通知に沿って、粛々と実務を進めていく。だが、問題の学校法人の理事長は知事の縁者で、知事室にわがもの顔で出入りしている人物だ。誰もその権限を適切に使い、職責をまっとうしようとしない。
それどころか、県内周遊促進事業の業務委託問題で見たように、和文氏にすり寄り、便宜を図った者がトントンと出世していく。それを周りの幹部や職員は見ている。県庁の空気はよどみ、活力が失われていく。
中堅幹部の言葉が忘れられない。彼は次のように嘆いた。
「県職員として一番やりがいを感じたのは、係長や主査のころでした。新しい事業を立ち上げるため、みんなでアイデアを出し合い、『これがいい』『こんな方法もある』と、侃々諤々(かんかんがくがく)の議論をして練っていきました。それを課長補佐や課長に上げて通し、予算化していくのが実に楽しかった」
「吉村知事は2期目の頃から、何でも自分で決めないと済まないようなスタイルになっていった。下から積み上げていっても、気に入らなければ歯牙にもかけない。一方で、上から突然、ドスンと新しい事業を下ろしてくる。フル規格の新幹線整備事業のように。これでは、若い職員はたまらない。振り回されるばかりで、意欲がなえていくのです」
吉村知事は政治や社会の小さな動きには敏感だが、歴史の大きな流れには鈍感だ。情報技術(IT)革命のインパクトのすさまじさがまるで分っていない。それゆえに、県庁ではいまだに「紙とハンコ」を使って仕事をしている。
菅政権が「デジタル庁の創設」を言い始めた途端、「県の業務のデジタル化」などと言い始めたが、この12年、いったい何をしていたのか。
「道半ば」と知事は言う。その道はどこに通じているのか。何を信じて歩んでいるのか。
*メールマガジン「風切通信 82」 2020年11月29日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』2020年12月号に寄稿した文章を若干手直しして転載したものです。写真は12月号の表紙のイラスト
*図1、2、3をクリックすると、内容が表示されます

吉村県政が誕生した後、会社の売上高は急増したが、2011年3月期をピークに減少に転じた。とくに、主力のケーブルテレビ事業の収入が減り続けている(図1)。その落ち込みを補うためには経営を多角化するしかない。社名の変更は、その決意を示したものだろう。
この会社が学校法人、東海山形学園から3000万円の融資を受けたのは、社名変更から2カ月後のことだ。かなりの金額である。その融資が何のためだったのか、経営のかじ取りをする社長が記憶していないはずがない。
融資の目的について、和文氏は山形新聞の取材に対して次のように答えている。
「ダイバー社のハイビジョン化の設備投資を目的に、複数金融機関の融資承認がそろうまでの間の短期貸付だった」(2017年7月4日付の記事)
先細り気味とはいえ、ケーブルテレビ事業は売り上げの7割を占める。その部門への設備投資を怠るわけにはいかない。けれども、メインバンクの山形銀行をはじめとする金融機関はなかなか金を貸してくれない。それで自分が理事長をしている学校法人から借りた――というわけだ。
その3000万円をダイバー社は2カ月後に返済している。融資の審査が終わって銀行が貸してくれたのか、といった疑問は残るものの、それなりに筋の通った説明だった。
ところが、和文氏は最近になって「設備投資のための融資説」を撤回し、あれは「学校法人の資産運用だった」と言い始めた。今年の10月15日付で報道各社に配布した「東海山形学園の貸付についての経緯説明」という文書で次のように記している。少し長いが、冒頭部分をそのまま引用する。
「東日本大震災後の2013年当時は、国や県から校舎の耐震強化についての指導があり、本学園においても、生徒と教職員の命に関わる大事業に取り組むにあたり、いかにして自己資金を増やし経営を安定させるかが大きな課題でありました」
「このことについて理事会では何度も議論を重ね、学園の資金を増やし、耐久年数が心配される校舎の改築費用に充て、私立学校の高額な授業料を減額する目的で、文部科学省の『学校法人における資産運用について』を参考に『運用の安全性』を考慮し、元本が保証され資産が毀損(きそん)しない相手として、2013年に私個人に5000万円、2016年にダイバーシティメディアに3000万円の貸付を行いました」
このコラム(2020年9月30日)でお伝えしたように、和文氏個人にもダイバー社にもこの時期、担保として提供できる資産はほとんどなく、金融機関は融資を渋っていた。それを「元本の返済が保証される相手」と記す感覚には驚いてしまう。貸付に伴うリスクをまるで考えていない。
文書はA4判で2ページ分ある。2ページ目には、この資金運用について学校法人の理事会でどのような手続きをしたか、私学助成を担当する山形県学事文書課からどのような指摘を受けたかについて詳細につづっている。
とりわけ、和文氏が学校法人の理事長と会社の社長を兼ねていることから、金銭の貸付が利益相反行為になることについては「所轄庁である県に(特別代理人の選任を)申請しなければなりませんでしたが、その認識がなく、それを行っていませんでした。(中略)当学園の責任であり、心よりお詫び申し上げます」と陳謝している。
利益相反行為について「その認識がなかった」と書いている部分は正直とも言えるが、「会社の金も学校の金も自分のもの」と考えていたことを“自白”したようなものだ。学校法人の理事長としての資質を問われかねない重大事だが、そうした意識もないのだろう。
文書では、最初から最後まで「資産の運用だった」という主張を貫いている。「設備投資のための融資」という表現はまったく出てこない。してみると、先の山形新聞の取材に対しては「口から出まかせのウソ」を言った、ということだろう。河北新報にも当時、「資金は設備投資に充てた」と答えている(写真)。これもデタラメだったことになる。
報道機関に対してウソをつくのは許しがたいことである。ウソをつかれたと分かったなら、記者は猛烈に怒らなければならない。読者や視聴者はそれを事実と受けとめるからだ。少なくとも、報道する者にはその矛盾をきちんと追及し、フォーローする責任がある。黙って見過ごしてはいけない。
では、今回の釈明は信用できるのか。
文書によれば、最初に問題になった2016年の3000万円融資については、2カ月後に年利2・5%の利息13万円余りを付けて返済したという。そして、この秋に発覚した2013年の5000万円については「8日後」に同じ年利で2万7397円の利息を付けて返した、と記している。
資産の運用は通常、株式や債券などを購入して行う。リスクはあるが、見返りも大きい。リスクが心配なら、国債を買ったり、金融機関に定期で預けたりするのが常道だ。「8日間、金を貸して利子を得る」のを資産運用と言い張るのは和文氏くらいだろう。
金を貸して利子を取るのは「貸金業」という。もし、東海山形学園がこうしたことを繰り返せば、今度は貸金業法に触れるおそれがある。文部科学省も山形県も、学校法人が「資産運用のため」貸金業を営むのを認めることはあるまい。
いずれにせよ、利益相反行為の場合に必要な「特別代理人の選任」を怠ったので、東海山形学園は理事会でこれを追認する手続きを踏まなければならなかった。2016年の3000万円の貸付は、その年の9月の理事会で追認した。一方、2013年の5000万円については今年10月の理事会で追認したという。
なんと、7年もたってからの追認だ。異様と言うしかない。しかも、こんな重要なことを県には「口頭で報告」したのだとか。それで了承した学事文書課もどうかしている。議事録を添えて文書で報告させ、議事の内容をきちんと確認するのが当然ではないか。東海山形学園も県当局も常軌を逸している。
報道各社あてのこの文書は、10月27日に山形県私学会館で開かれた県内の学校法人の理事長・校長会でも日付だけ手直しして配布され、和文氏が釈明にあたった。出席者によれば、この会合でも「8日間の資産運用というのは短すぎるのではないか」という質問が出た。これに対し、和文氏は「試しに運用してみた」などと説明して煙に巻いたという。
質問はこれだけだった。出席者の一人は「少子化で生徒が減り、どこの高校も経営が厳しい。銀行から金を借りるのならともかく、貸すことなど考えられません」と述べ、こう言葉を継いだ。「ただ、私立学校にはそれぞれの立場があります。よその学校のことについて、あれこれ言うわけにはいきません」
誰も納得していない。和文氏はなぜ設備投資のための融資説を撤回したのか。これで資産の運用と言えるのか。和文氏に手紙をしたためて問い合わせたが、返事はない。説明を求めようと会社に電話をかけても、彼は出てこなかった。
本当は何に使ったのか。この5000万円については「プロレスに投資したのではないか」との憶測が消えない。
ジャイアント馬場、アントニオ猪木といったスター選手がリングを降りてから、プロレス業界は四分五裂の状態に陥った。5000万円の貸付があった2013年当時も、人気プロレスラーの秋山準ら5人の選手がそれまで属していた団体から離れ、全日本プロレスに移籍する騒動があった。
事情通によると、この時、秋山選手らを支えたのがケーブルテレビ山形の吉村和文氏とジャイアント馬場の元子夫人だった。元子夫人は横浜市青葉区にあるプロレスの道場と合宿所を提供し、資金はケーブルテレビ山形が負担する段取りになったようだ。興行権の確保や新会社の設立準備などのため数千万円の資金を必要としたはず、という。
翌2014年の夏、和文氏は「全日本プロレス・イノベーション」(本社・山形市)という持ち株会社と運営会社の「オールジャパン・プロレスリング」(本社・横浜市)を立ち上げ、両方の会社の取締役会長に就任した。社長は秋山選手である。
ケーブルテレビが生き残るためには、NHKや民放が放送しない、あるいは放送できない番組を提供しなければならない。プロレスはそのための有力なコンテンツの一つ、と考えて進出を決めたようだ。
和文氏はかなり前から、プロレスに関心を寄せていた。彼のブログ「約束の地へ」で「プロレス」と打ち込んで検索すると、この10年間で122件もヒットする。
ブログの主なものに目を通してみた。2013年ごろ、山形南高校応援団の後輩でプロレスのプロモーターをしていた高橋英樹氏や「平成のミスタープロレス」と呼ばれた武藤敬司氏、馬場元子夫人らが相次いで山形を訪れていた。和文氏に会うためで、彼は「プロレスのタニマチ」のように振る舞っている。新しいビジネスへの進出に意欲を燃やしていた。
ただ、この業界は昔から「売り上げの分配」をめぐる争いが絶えない。それぞれの選手にいくらギャラを払うのか。興行主の取り分をどうするのか。関連グッズの売り上げは・・・。新たにスタートした全日本プロレスも例外ではなかった。
別冊宝島のプロレス特集(2016年2月28日)によれば、立ち上げから1年で、新生全日本プロレスは5000万円の赤字になってしまった(図2)。「始める前は気分が高揚して期待を持ってしまうのだけれども、見通しが甘すぎるのと、現場の選手たちは誰も親会社に恩義など感じていないので、結果としてこうなってしまう」のだという。和文氏が会長をつとめる持ち株会社の最近3年間の決算を見ても、ずっと赤字続きだ。
秋山選手はすでに社長を退き、別のプロレス団体のコーチをしている。新会社の立ち上げ時に何があったのか。事実関係を問いただそうとしたが、ついに接触できなかった。
5000万円は何に使われたのか。いまだ闇の中である。
◇ ◇
3年前、東海山形学園からダイバーシティメディアへの3000万円融資問題が表面化した際、吉村美栄子知事は記者会見でどう思うか問われ、「(学校法人が)適切に運営されているのであれば、よろしいのではないかというふうに思っております。(中略)そのことについて問題ないようだというふうに担当のほうから聞いております」と涼しい顔で答えた。
その後、東海山形学園が私立学校法に定められた「特別代理人の選任申請」をしていなかったことが明らかになった。3000万円融資の事実は県に提出された貸借対照表に記載されており、担当者はそれが利益相反行為に該当することを知り得たのに、漫然と見過ごしていたことも判明した。
学校法人は、ちっとも「適切に運営」されていなかったし、「担当のほう」もまるで頼りにならない仕事ぶりだった。さらに、5000万円の貸付について担当者はその後、気づいたのに、市民オンブズマンが発表するまで隠していた。知事の涼しい顔は、次第に苦々しい顔に変わっていった。
とはいえ、吉村知事は4期目をめざして、来年1月の知事選に出馬することを表明した。「いつまでも、こんなことに構っていられない。知事選に全力を注ぐだけ」という心境だろう。
出馬表明の記者会見では、新型コロナウイルスへの対応と経済対策との両立を図る考えを示し、最初の知事選の時の初心に帰って「正々堂々と政策を掲げて戦いたい」と述べた。県政と吉村一族企業との問題など小さな争点にすらならない、という風情だ。
だが、一族企業と学校法人の問題はそんなに根の浅いものではない。実は、吉村和文氏は毎年のように利益相反行為を繰り返している疑いがあるのだ。
和文氏はダイバーシティメディアの社長であり、学園の理事長であると同時に、映画館運営会社「ムービーオン」の社長も兼ねている。
東海大山形高校の教職員や生徒、保護者の証言によれば、学園は毎年、生徒全員分の映画チケットを購入し、タダで配っているという。映画チケットは各映画館共通のチケットではない(そのようなものはない)。生徒に配られたのは「ムービーオン」という特定の映画館のチケットである。
筆者の取材によれば、少なくとも2014年まで遡ることができる。関係者が多数いるので、確認するのも難しいことではない。
東海大山形高校の生徒数は図3の通りである。ここ7年間の平均だと、800人ほどだ。高校生の団体割引の映画チケットは1枚800円なので、生徒数を掛けると年間64万円、7年で448万円になる。
それほど大きな金額ではないが、問題はそれらの映画チケットの購入が「東海山形学園 吉村和文理事長」の名前で行われることにある。この学校法人を代表して購入契約を結ぶ権限があるのは理事長ただ一人だけだ。
つまり、東海山形学園は毎年、理事長が社長を兼ねる映画館会社のチケットを大量に購入して売り上げ増に貢献しているが、それらのチケット購入はすべて「利益相反行為」になる、ということだ。
利益が相反する以上、そうしたことは理事長の権限で行うことはできない。私立学校法に基づいて、学園は毎年、所轄庁の山形県に「特別代理人の選任」を申請し、利害関係のない第三者に取引が公正かどうかチェックしてもらう義務があった。
さらに、今春施行の法改正によって特別代理人の選任は不要になったが、利益相反行為であることに変わりはないので、今後も理事会で厳正にチェックする必要がある。一族企業と学校法人の間で、資金の融通や物品の購入を勝手気ままに行うことは、いかなる場合でも許されないのだ。
ことは、東海山形学園とダイバーシティメディア、ムービーオンだけの関係にとどまらない。学園が一族企業と交わすすべての契約について「利益相反行為」の疑いが生じ、チェックする必要が出てくる。
多数の企業を経営する人物が学校法人の理事長を兼ねれば、常にこういう問題が起き、公平さを疑われる事態を招くことになる。
だからこそ、文部科学省は「理事長についてはできる限り常勤化や兼職の制限を行うことが期待される」との事務次官通知(2004年7月23日付)を出し、さらに「理事長は責任に見合った勤務形態を取り、対内的にも対外的にも責任を果たしていくことが重要と考える。兼職は避けることが望ましい」との見解(高等教育局私学行政課)を出しているのだ。
普通なら、都道府県の職員は中央官庁の通知に沿って、粛々と実務を進めていく。だが、問題の学校法人の理事長は知事の縁者で、知事室にわがもの顔で出入りしている人物だ。誰もその権限を適切に使い、職責をまっとうしようとしない。
それどころか、県内周遊促進事業の業務委託問題で見たように、和文氏にすり寄り、便宜を図った者がトントンと出世していく。それを周りの幹部や職員は見ている。県庁の空気はよどみ、活力が失われていく。
中堅幹部の言葉が忘れられない。彼は次のように嘆いた。
「県職員として一番やりがいを感じたのは、係長や主査のころでした。新しい事業を立ち上げるため、みんなでアイデアを出し合い、『これがいい』『こんな方法もある』と、侃々諤々(かんかんがくがく)の議論をして練っていきました。それを課長補佐や課長に上げて通し、予算化していくのが実に楽しかった」
「吉村知事は2期目の頃から、何でも自分で決めないと済まないようなスタイルになっていった。下から積み上げていっても、気に入らなければ歯牙にもかけない。一方で、上から突然、ドスンと新しい事業を下ろしてくる。フル規格の新幹線整備事業のように。これでは、若い職員はたまらない。振り回されるばかりで、意欲がなえていくのです」
吉村知事は政治や社会の小さな動きには敏感だが、歴史の大きな流れには鈍感だ。情報技術(IT)革命のインパクトのすさまじさがまるで分っていない。それゆえに、県庁ではいまだに「紙とハンコ」を使って仕事をしている。
菅政権が「デジタル庁の創設」を言い始めた途端、「県の業務のデジタル化」などと言い始めたが、この12年、いったい何をしていたのか。
「道半ば」と知事は言う。その道はどこに通じているのか。何を信じて歩んでいるのか。
*メールマガジン「風切通信 82」 2020年11月29日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』2020年12月号に寄稿した文章を若干手直しして転載したものです。写真は12月号の表紙のイラスト
*図1、2、3をクリックすると、内容が表示されます
類は友を呼ぶ、という。似た者同士は自然と寄り集まる。それを裏返せば、友達をよく見れば、その人の性格や考え方も分かる、ということだ。
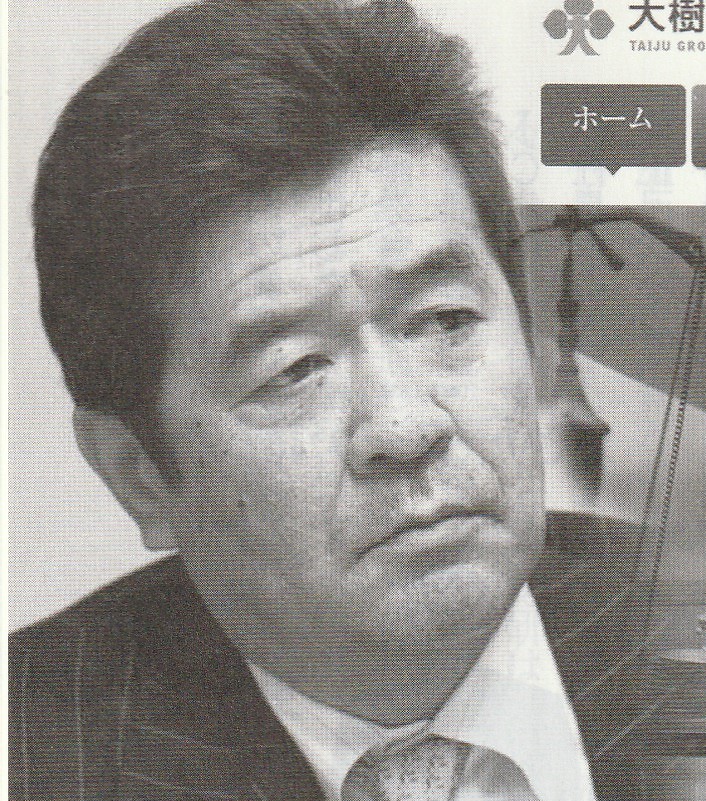
週刊新潮が10月15日号で、菅義偉首相の友達特集を載せていた。最初に、共同通信の論説副委員長から首相補佐官に転じた柿崎明二(めいじ)氏が登場する。そして、この柿崎氏と菅首相をつないだ人物として、政治系シンクタンク「大樹(たいじゅ)グループ」の矢島義也氏(59歳)を取り上げていた。「令和の政商」なのだという。
謎多き人物だ。週刊新潮は「長野県出身」と報じたが、「静岡県浜松市生まれ」とするメディアもあり、はっきりしない。高校を卒業した後、実業界に身を投じ、のし上がっていった人物のようだ。「矢島義成」と名乗っていた時期もある。
「政商」としての矢島氏の力を示したのは、2016年5月に開かれた彼の「結婚を祝う会」だった。週刊新潮によれば、主賓は当時官房長官だった菅義偉氏。二階俊博・自民党政務会長(当時)が乾杯の音頭を取り、安倍晋三首相もビデオメッセージを寄せた。
現職閣僚の林幹雄、遠藤利明、加藤勝信の各氏も出席し、さらに野党からも野田佳彦・元首相や安住淳、細野豪志、山尾志桜里の各氏が顔をそろえた。福田淳一・財務事務次官や黒川弘務・法務省官房長ら、後にセクハラや定年延長問題で世を騒がせた高官も並んだ。永田町や霞が関の事情通をうならせる顔ぶれだった。
では、これだけの人々を呼ぶことができる矢島氏とは、いかなる人物なのか。彼が率いる「大樹グループ」の公式サイトには、持ち株会社の大樹ホールディングスや大樹総研、大樹コンサルティング、大樹リスクマネジメントといったグループ企業と社長名が列記してある。所在地はすべて「中央区銀座7丁目2-22」だ。
業務内容は「戦略コンサルティング」「フェロー派遣サービス」「地方自治体向けサービス」「政策研究・提言」と記してあるが、サイトはわずか2ページしかない。説明文を読んでも、具体的なイメージがまるで湧いてこない。
その内実を探るべく、資料をあさっているうちに、月刊誌『選択』の2018年8月号と9月号にたどり着いた。
それによれば、このグループは政界と官界に人脈を張り巡らし、「口利き商売と補助金ビジネスを売り物にしている」のだという。「補助金という名の血税を巧みに吸い込み、濾過するビジネス」を得意とするグループだ、と断じている。
例えば、グループのエネルギー開発会社「JCサービス」は2013年に鹿児島県で太陽光発電の蓄電池を活用するモデル事業を計画し、環境省から補助金を得た。だが、ろくに事業も進めず、2018年に補助金2億9600万円の返還と加算金1億3600万円の支払いを命じられた。
別のグループ企業「グリーンインフラレンディング」は、再生可能エネルギー事業を進めると称して投資家から巨額の資金を集めたものの、資金の一部が不正に流用されたとして、資金の募集停止に追い込まれている。
『選択』によれば、このグループの謎を解くキーワードは「浜松」「松下政経塾」「自然エネルギー」の三つだという。矢島氏は、浜松を拠点とする熊谷弘・元官房長官(羽田内閣)や鈴木康友・浜松市長と昵懇の間柄にあり、これを足場に政界と官界の人脈を広げていった。
鈴木康友氏は松下政経塾の1期生であり、同じ1期生の野田佳彦・元首相を矢島氏につないだ。その人脈は民主党政権時代に細野豪志、安住淳の各氏や官界へと広がっていく。同時に、野党の代議士として不遇をかこっていた菅義偉氏や二階俊博氏との知遇も得た。
このグループのしたたかさは、民主党政権から自民党・安倍政権になってからも、「再生可能エネルギー関連のビジネス」をテコとして、さらに政官財とのパイプを太くしていった点だ。いわば、「自民党の不得意分野」で活路を切り開いていったのである。
見過ごしにできないのは、その手法だ。週刊新潮は、写真誌『FOCUS』の1999年7月21日号を引用して、矢島氏が<乱交パーティー「女衒芸能プロ社長」の正体>と報じられた過去があることを紹介している。東京のマンションの一室で週に1回ほど乱交パーティーを開き、有名な俳優や人気アイドルを集めていたのだという。
「金と色」で人脈を広げ、その人脈を使って影響力をさらに強めていく。「再生可能エネルギー」という衣をまとっているところが「平成流」と言うべきか。時の首相の友人として、いかがなものかと思う。
週刊新潮は11月5日号で、「菅首相のタニマチが公有地の払い下げを受け、ぼろ儲けした」と続報を放った。こちらは別の人物が主役で、地元の神奈川県を舞台にした疑惑である。安倍政権の「森友学園問題」より、はるかに露骨な利益誘導ぶりを伝えている。
地縁血縁のない横浜で政治家を志し、有力なスポンサーも見つけられない中で権力の中枢へと駆け上がっていっただけに、菅首相の周りには有象無象がうごめいている。何が起きているのか。メディアは臆することなく、その闇に分け入っていかなければならない。
*メールマガジン「風切通信 81」 2020年11月7日
≪写真説明≫
◎大樹グループの総帥、矢島義也氏
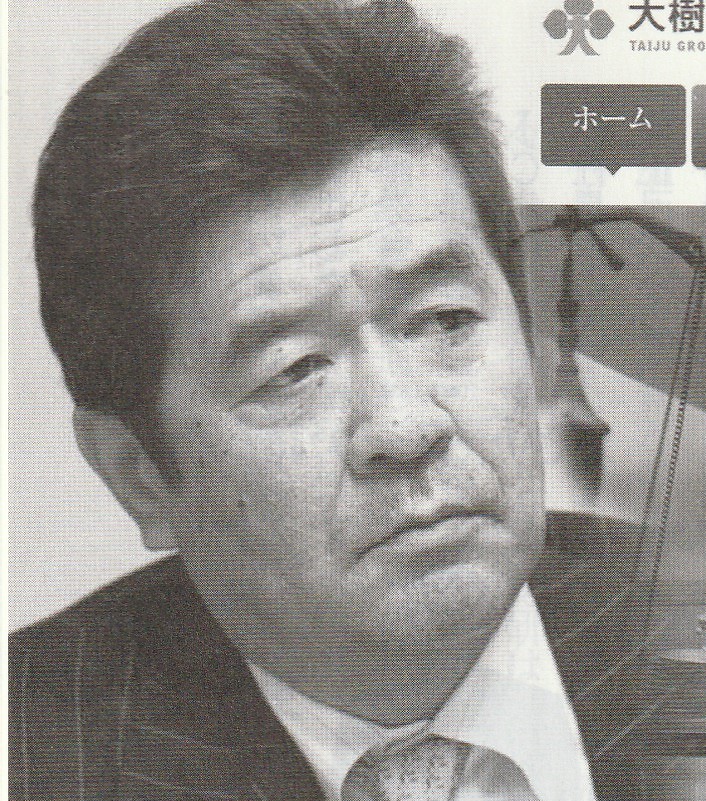
週刊新潮が10月15日号で、菅義偉首相の友達特集を載せていた。最初に、共同通信の論説副委員長から首相補佐官に転じた柿崎明二(めいじ)氏が登場する。そして、この柿崎氏と菅首相をつないだ人物として、政治系シンクタンク「大樹(たいじゅ)グループ」の矢島義也氏(59歳)を取り上げていた。「令和の政商」なのだという。
謎多き人物だ。週刊新潮は「長野県出身」と報じたが、「静岡県浜松市生まれ」とするメディアもあり、はっきりしない。高校を卒業した後、実業界に身を投じ、のし上がっていった人物のようだ。「矢島義成」と名乗っていた時期もある。
「政商」としての矢島氏の力を示したのは、2016年5月に開かれた彼の「結婚を祝う会」だった。週刊新潮によれば、主賓は当時官房長官だった菅義偉氏。二階俊博・自民党政務会長(当時)が乾杯の音頭を取り、安倍晋三首相もビデオメッセージを寄せた。
現職閣僚の林幹雄、遠藤利明、加藤勝信の各氏も出席し、さらに野党からも野田佳彦・元首相や安住淳、細野豪志、山尾志桜里の各氏が顔をそろえた。福田淳一・財務事務次官や黒川弘務・法務省官房長ら、後にセクハラや定年延長問題で世を騒がせた高官も並んだ。永田町や霞が関の事情通をうならせる顔ぶれだった。
では、これだけの人々を呼ぶことができる矢島氏とは、いかなる人物なのか。彼が率いる「大樹グループ」の公式サイトには、持ち株会社の大樹ホールディングスや大樹総研、大樹コンサルティング、大樹リスクマネジメントといったグループ企業と社長名が列記してある。所在地はすべて「中央区銀座7丁目2-22」だ。
業務内容は「戦略コンサルティング」「フェロー派遣サービス」「地方自治体向けサービス」「政策研究・提言」と記してあるが、サイトはわずか2ページしかない。説明文を読んでも、具体的なイメージがまるで湧いてこない。
その内実を探るべく、資料をあさっているうちに、月刊誌『選択』の2018年8月号と9月号にたどり着いた。
それによれば、このグループは政界と官界に人脈を張り巡らし、「口利き商売と補助金ビジネスを売り物にしている」のだという。「補助金という名の血税を巧みに吸い込み、濾過するビジネス」を得意とするグループだ、と断じている。
例えば、グループのエネルギー開発会社「JCサービス」は2013年に鹿児島県で太陽光発電の蓄電池を活用するモデル事業を計画し、環境省から補助金を得た。だが、ろくに事業も進めず、2018年に補助金2億9600万円の返還と加算金1億3600万円の支払いを命じられた。
別のグループ企業「グリーンインフラレンディング」は、再生可能エネルギー事業を進めると称して投資家から巨額の資金を集めたものの、資金の一部が不正に流用されたとして、資金の募集停止に追い込まれている。
『選択』によれば、このグループの謎を解くキーワードは「浜松」「松下政経塾」「自然エネルギー」の三つだという。矢島氏は、浜松を拠点とする熊谷弘・元官房長官(羽田内閣)や鈴木康友・浜松市長と昵懇の間柄にあり、これを足場に政界と官界の人脈を広げていった。
鈴木康友氏は松下政経塾の1期生であり、同じ1期生の野田佳彦・元首相を矢島氏につないだ。その人脈は民主党政権時代に細野豪志、安住淳の各氏や官界へと広がっていく。同時に、野党の代議士として不遇をかこっていた菅義偉氏や二階俊博氏との知遇も得た。
このグループのしたたかさは、民主党政権から自民党・安倍政権になってからも、「再生可能エネルギー関連のビジネス」をテコとして、さらに政官財とのパイプを太くしていった点だ。いわば、「自民党の不得意分野」で活路を切り開いていったのである。
見過ごしにできないのは、その手法だ。週刊新潮は、写真誌『FOCUS』の1999年7月21日号を引用して、矢島氏が<乱交パーティー「女衒芸能プロ社長」の正体>と報じられた過去があることを紹介している。東京のマンションの一室で週に1回ほど乱交パーティーを開き、有名な俳優や人気アイドルを集めていたのだという。
「金と色」で人脈を広げ、その人脈を使って影響力をさらに強めていく。「再生可能エネルギー」という衣をまとっているところが「平成流」と言うべきか。時の首相の友人として、いかがなものかと思う。
週刊新潮は11月5日号で、「菅首相のタニマチが公有地の払い下げを受け、ぼろ儲けした」と続報を放った。こちらは別の人物が主役で、地元の神奈川県を舞台にした疑惑である。安倍政権の「森友学園問題」より、はるかに露骨な利益誘導ぶりを伝えている。
地縁血縁のない横浜で政治家を志し、有力なスポンサーも見つけられない中で権力の中枢へと駆け上がっていっただけに、菅首相の周りには有象無象がうごめいている。何が起きているのか。メディアは臆することなく、その闇に分け入っていかなければならない。
*メールマガジン「風切通信 81」 2020年11月7日
≪写真説明≫
◎大樹グループの総帥、矢島義也氏
私たちが暮らす山形県という地域は、どういうところなのか。その政治風土や県民性を考える時に忘れてならないのは、「蔵王県境移動事件」である。

半世紀以上も前に起きた事件だが、山形県の政治や経済、社会の特質をこれほど雄弁に物語るものはほかにない。地元の支配的企業グループに便宜を図るため、秋田営林局と山形営林署は山形、宮城の県境を勝手に移動させた。そして、山形県当局もグルになってそれを押し通そうとした。信じがたいような出来事だ。
事件が起きたのは1963年である。
蔵王連峰を横断する道路「蔵王エコーライン」が前年に開通したのを機に、山形市の観光バス会社「北都開発」が蔵王の「お釜」(写真)に通じるリフトの建設を計画した。建設予定地は山形営林署が管轄する国有林内だった。そこで、北都開発は営林署に用地の貸付申請をし、山形県にはリフト建設の届け出をした。
すると、山形営林署長は同じように観光リフトの建設を計画していた山形交通にその内容を伝え、北都開発の貸付申請書を受理しないなど様々な妨害工作を始めた。山形県も「お釜には道路を造って行けるようにする計画だ」と、リフトの建設に反対した。
その一方で、山形交通は宮城県内の土地にお釜に通じる観光リフトの建設を決め、営林当局の支援を受けて着々と工事を進めていった。
都開発はあきらめず、妨害を跳ねのけて手続きを進めた。すると、秋田営林局と山形営林署は「山形と宮城の県境はもっと西寄りである。北都開発のリフト建設予定地は宮城県側だ。白石営林署で手続きせよ」と言い始めた。勝手に県境を変え、山形県の土地の一部を宮城県に譲り渡してしまったのである。
観光リフトの建設問題は県境紛争となり、国会議員や県知事、中央官庁も巻き込んだ大騒動に発展した。
この渦中で絶大な力を発揮したのが山形新聞の服部敬雄(よしお)社長である。グループ企業の山形交通の権益を守るため、政治家や経済人を動かし、傘下の新聞とテレビを動員して世論操作を図った。権力を監視すべきメディアが権力そのものと化していたのだ。
汚職の臭いをかぎ取り、山形地方検察庁が動き始める。警察は地元のしがらみにからめとられて、当てにできない。検察だけで捜査を進め、翌64年年に山形営林署長や山形交通の課長ら12人を逮捕し、65年に営林署長を公務員職権濫用罪で起訴した。
この刑事裁判で事実関係が明らかにされ、営林署長に有罪の判決が下っていれば、その後の展開はまるで異なるものになっていたはずだ。
ところが、一審の山形地裁でも控訴審でも営林署長は無罪になり、70年に確定した。致命的だったのは、検察側が「山形県と宮城県の本当の県境はどこか」を立証できなかったことである。
山形新聞・山形交通グループと営林当局、山形県はあらゆる手段を使って、勝手に移動させた県境こそ「本来の県境である」と主張し続けた。江戸時代の絵図を持ち出し、地図作成を担当する国土地理院の専門家まで引っ張り出して、被告に有利な証言をさせた。
裁判所は「ごまかしと嘘の洪水」にのみ込まれ、県境の画定をあきらめざるを得なかった。「県境の移動」が立証されなければ、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則にのっとり、無罪を言い渡すしかなかった。
この間、北都開発の佐藤要作(ようさく)社長は妨害を乗り越えてリフトを完成させたが、嫌がらせはその後も続いた。万が一の噴火に備えて観光客用の避難所を建設した。すると、山形県は「お釜の景観を損ねる」と別の場所への建て替えを命じ、さらにその建て替えた避難所を新たな理由を持ち出して強制的に取り壊した。
意を決して、佐藤要作社長は「営林当局による県境の移動は不法行為である。これによって生じた損害を賠償せよ」と国を相手に民事訴訟を起こした。だが、弁護士が次々に辞めるなどして訴訟は停滞した。
転機は1980年に訪れた。
この年、大阪で仕事をしていた佐藤欣哉(きんや)弁護士が山形市に移り、事務所を開いた。1946年、山形県余目(あまるめ)町(現庄内町)生まれ。鶴岡南高校、一橋大学卒。34歳の闘志あふれる弁護士がこの事件を引き受けた。弁護団に加わった三浦元(はじめ)、外塚功両弁護士も30歳前後の若さだ。彼らは刑事訴訟の分も含め、膨大な証拠と記録の洗い直しを進め、止まっていた裁判を動かしていった。
しかし、87年、一審の山形地裁ではまたしても敗れた。「営林当局が県境を勝手に移動させた」ということを立証できなかったのである。刑事訴訟を含め、三連敗。それでも、控訴して闘い続けた。みな「県境は勝手に移動された」と確信していた。
救いの神は、意外なところから現れた。地図の専門家が「山形地裁の判決は間違っている」と明言した、という情報が佐藤欣哉弁護士のもとに寄せられたのだ。会ってみると、彼はその理由を明快に語ってくれた。
山形と宮城の県境を記した蔵王周辺の地形図を最初に作成したのは明治44年(1911年)、陸軍参謀本部の陸地測量部である。それ以来、その5万分の1の地図がずっと使われてきたが、問題のお釜周辺の境界線は特殊な線で描かれていた。
彼はその線の意味を旧陸軍の内規に基づいて詳しく説明し、「この線は『登山道が県境である』という北都開発の当初からの主張が正しいことを示している」と語った。決定的な証言だった。「地図屋の良心」がごまかしを許さなかったのである。
1995年、仙台高裁は旧陸軍の内規に基づく弁護団の主張を採用し、原告逆転勝訴の判決を言い渡した。事件から、実に32年後のことだった。
「山交は県内陸部最大のバス会社であったほか、同県の政財界に多大な影響力を有していた山形新聞、山形放送とグループを形成して密接な連携を保っていた」
「山形営林署長らは姑息な理由で(北都開発の)申請の受理を拒否ないし遷延(せんえん)し、他方で山交リフトの建設に対しては陰に陽に支援・協力していた」
「(山形営林署長らの)一連の貸付権限の行使は、故意による権限の濫用つまり包括的な不法行為に該当するというべきである」
高裁判決は、山形新聞・山形交通グループの策動を暴き、営林当局者の職権濫用を厳しく断罪した。先の刑事裁判の判断を覆し、事実上の「有罪判決」を下したのである。
長い闘いの記録は、佐藤欣哉氏によって『蔵王県境が動く 官財癒着の真相』という本にまとめられ、出版された。
蔵王県境事件の弁護士たちはこの年、公金の使い方を監視する「市民オンブズマン山形県会議」を立ち上げ、山形県発注の土木建設工事をめぐる談合事件や山形市議、山形県議の政務調査費(のち政務活動費)の不適切な支出の追及に乗り出した。不正を次々に暴き、貴重な血税を取り戻すのに多大な貢献をした。
その先頭に立ってきた佐藤欣哉弁護士が10月17日、闘病の末、74歳で亡くなった。不正を許さず、闘い続けた人生だった。
◇ ◇
メディアを核に支配を広げ、「天皇」と称された山形新聞の服部敬雄氏は1991年に死去し、山新・山交(現ヤマコー)グループの結束は著しく弱まった。服部氏の番頭のような存在だった県知事も代替わりし、2009年には吉村美栄子氏が東北初の女性知事になった。
それによって、山形県の政治風土と県民性は変わったのだろうか。私たちはどれだけ前に進むことができたのだろうか。
この2年、このコラムで報じてきた通り、吉村知事が誕生して以来、知事の義理のいとこの吉村和文氏が率いる企業・法人グループは「わが世の春」を謳歌してきた。吉村県政誕生以来の10年間で、このグループに支出された公金は40億円を上回る。2019年度以降、さらに上積みされていることは言うまでもない。
吉村一族企業の所業は、山新・山交グループの振る舞いとそっくりではないか。
その実態を解明するため、筆者が学校法人東海山形学園の財務書類の情報公開を請求したところ、県は詳しい内容を白塗りにして隠し、不開示にした(2017年5月)。
「白塗り」は「黒塗り」より悪質である。「黒塗り」なら貸借対照表の備考欄に融資などの利益相反行為があることをうかがわせる痕跡が残るが、「白塗り」だと、そうしたものがあるかどうかも分からないからだ。
私学助成を担当する山形県学事文書課は「あるかどうかも分からなくする」のが得意だ。東海山形学園から和文氏の率いるダイバーシティメディアへの3000万円融資に関する「特別代理人の選任文書」について、私が情報公開を求めると、「存否(そんぴ)応答拒否」(文書があるかどうかも答えない)という決定をした(2018年10月)。その理由は「学校法人の利益を害するおそれがある」という理不尽なものだった。
私立学校法は「利益相反行為がある場合、所轄庁(山形県)は特別代理人を選んでチェックさせなさい」と規定していた。私は「その法律に基づいて選んだのですか」と問いただしたに過ぎない。「利益を害する」ことなどあり得ないのだ。知事の義理のいとこが理事長をつとめる学校法人の不始末を隠そうとした、としか考えられない対応だった。
財務書類の不開示をめぐる裁判は、仙台高裁で「山形県の対応は違法。すべて開示しなさい」との判決が出され、県の上告が退けられて確定した。この判決に基づいて全面開示された財務書類を点検したところ、2016年の3000万円とは別に、2013年にも学校法人から和文氏個人に5000万円の融資が行われていたことが明らかになった。
県学事文書課は全面開示の直前に、この5000万円融資の事実に気づいたことを認めている。だが、筆者が記者会見をして明らかにするまで口をつぐんでいた。
蔵王県境事件の際の秋田営林局や山形営林署の対応と何と似ていることか。県知事も県職員も「学校法人と一蓮托生」とでも思っているのだろうか。
3000万円の融資でも5000万円の融資でも、県は「特別代理人」を選ばず、私立学校法に定められた責務を果たしていなかった。
その点を追及されると、吉村知事は記者会見や県議会で「県としては(融資という利益相反行為を)知り得なかったのです」と答え、そこに逃げ込もうとしている。
確かに、学校法人とグループ企業の間での融資という利益相反行為を事前に知るのは難しい。だが、私学助成を受けている学校法人は次年度の6月までにはすべての財務書類を県に提出する。丁寧に目を通せば、その時点で気づくはずだ。「知り得ない」という答えは、論理的にも日本語としても間違っている。
10月13日の定例記者会見で知事が答えに窮すると、大滝洋・総務部長は助け舟を出し、こう述べた。「(貸借対照表などの)財務諸表は参考資料なんです。その注記部分はチェックすべき対象になっていない」
暴言と言うしかない。私立学校振興助成法によって、学校法人は所轄庁(山形県)に財務書類を提出することを義務づけられている。学校法人の財務状況を示す重要な書類だからだ。それを「参考資料でチェック不要」と言ってのける度胸に驚く。
大滝部長が果たしている役割は、蔵王県境事件の刑事裁判で被告側の証人になった国土地理院の専門家に似ている。訳知り顔で不正確な情報をばらまき、混乱させて真相の解明を妨げる役回りだ。
当事者である東海山形学園の吉村和文理事長はメディアに対して様々な釈明をしている。いずれも説得力がなく、信ずるに足りない。紙幅が尽きてきた。どこがどのように信用できないのか、次号で詳しく分析したい。
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年11月号に寄稿した文章を若干手直しして転載したものです。
≪写真説明≫
1995年1月23日、仙台高裁で逆転勝訴した原告と弁護団(『蔵王県境が動く 官財癒着の真相』から複写)
≪参考文献&資料≫
◎蔵王県境事件の国家損害賠償請求に対する仙台高裁の判決(1995年1月23日)
◎『蔵王県境が動く 官財癒着の真相』(佐藤欣哉著、やまがた散歩社)
◎『小説 蔵王県境事件』(須貝和輔著、東北出版企画)
◎『山形の政治 戦後40年・ある地方政界・』(朝日新聞山形支局、未来社)
◎1963年8月29日から1995年1月29日の朝日新聞山形県版の関係記事

半世紀以上も前に起きた事件だが、山形県の政治や経済、社会の特質をこれほど雄弁に物語るものはほかにない。地元の支配的企業グループに便宜を図るため、秋田営林局と山形営林署は山形、宮城の県境を勝手に移動させた。そして、山形県当局もグルになってそれを押し通そうとした。信じがたいような出来事だ。
事件が起きたのは1963年である。
蔵王連峰を横断する道路「蔵王エコーライン」が前年に開通したのを機に、山形市の観光バス会社「北都開発」が蔵王の「お釜」(写真)に通じるリフトの建設を計画した。建設予定地は山形営林署が管轄する国有林内だった。そこで、北都開発は営林署に用地の貸付申請をし、山形県にはリフト建設の届け出をした。
すると、山形営林署長は同じように観光リフトの建設を計画していた山形交通にその内容を伝え、北都開発の貸付申請書を受理しないなど様々な妨害工作を始めた。山形県も「お釜には道路を造って行けるようにする計画だ」と、リフトの建設に反対した。
その一方で、山形交通は宮城県内の土地にお釜に通じる観光リフトの建設を決め、営林当局の支援を受けて着々と工事を進めていった。
都開発はあきらめず、妨害を跳ねのけて手続きを進めた。すると、秋田営林局と山形営林署は「山形と宮城の県境はもっと西寄りである。北都開発のリフト建設予定地は宮城県側だ。白石営林署で手続きせよ」と言い始めた。勝手に県境を変え、山形県の土地の一部を宮城県に譲り渡してしまったのである。
観光リフトの建設問題は県境紛争となり、国会議員や県知事、中央官庁も巻き込んだ大騒動に発展した。
この渦中で絶大な力を発揮したのが山形新聞の服部敬雄(よしお)社長である。グループ企業の山形交通の権益を守るため、政治家や経済人を動かし、傘下の新聞とテレビを動員して世論操作を図った。権力を監視すべきメディアが権力そのものと化していたのだ。
汚職の臭いをかぎ取り、山形地方検察庁が動き始める。警察は地元のしがらみにからめとられて、当てにできない。検察だけで捜査を進め、翌64年年に山形営林署長や山形交通の課長ら12人を逮捕し、65年に営林署長を公務員職権濫用罪で起訴した。
この刑事裁判で事実関係が明らかにされ、営林署長に有罪の判決が下っていれば、その後の展開はまるで異なるものになっていたはずだ。
ところが、一審の山形地裁でも控訴審でも営林署長は無罪になり、70年に確定した。致命的だったのは、検察側が「山形県と宮城県の本当の県境はどこか」を立証できなかったことである。
山形新聞・山形交通グループと営林当局、山形県はあらゆる手段を使って、勝手に移動させた県境こそ「本来の県境である」と主張し続けた。江戸時代の絵図を持ち出し、地図作成を担当する国土地理院の専門家まで引っ張り出して、被告に有利な証言をさせた。
裁判所は「ごまかしと嘘の洪水」にのみ込まれ、県境の画定をあきらめざるを得なかった。「県境の移動」が立証されなければ、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則にのっとり、無罪を言い渡すしかなかった。
この間、北都開発の佐藤要作(ようさく)社長は妨害を乗り越えてリフトを完成させたが、嫌がらせはその後も続いた。万が一の噴火に備えて観光客用の避難所を建設した。すると、山形県は「お釜の景観を損ねる」と別の場所への建て替えを命じ、さらにその建て替えた避難所を新たな理由を持ち出して強制的に取り壊した。
意を決して、佐藤要作社長は「営林当局による県境の移動は不法行為である。これによって生じた損害を賠償せよ」と国を相手に民事訴訟を起こした。だが、弁護士が次々に辞めるなどして訴訟は停滞した。
転機は1980年に訪れた。
この年、大阪で仕事をしていた佐藤欣哉(きんや)弁護士が山形市に移り、事務所を開いた。1946年、山形県余目(あまるめ)町(現庄内町)生まれ。鶴岡南高校、一橋大学卒。34歳の闘志あふれる弁護士がこの事件を引き受けた。弁護団に加わった三浦元(はじめ)、外塚功両弁護士も30歳前後の若さだ。彼らは刑事訴訟の分も含め、膨大な証拠と記録の洗い直しを進め、止まっていた裁判を動かしていった。
しかし、87年、一審の山形地裁ではまたしても敗れた。「営林当局が県境を勝手に移動させた」ということを立証できなかったのである。刑事訴訟を含め、三連敗。それでも、控訴して闘い続けた。みな「県境は勝手に移動された」と確信していた。
救いの神は、意外なところから現れた。地図の専門家が「山形地裁の判決は間違っている」と明言した、という情報が佐藤欣哉弁護士のもとに寄せられたのだ。会ってみると、彼はその理由を明快に語ってくれた。
山形と宮城の県境を記した蔵王周辺の地形図を最初に作成したのは明治44年(1911年)、陸軍参謀本部の陸地測量部である。それ以来、その5万分の1の地図がずっと使われてきたが、問題のお釜周辺の境界線は特殊な線で描かれていた。
彼はその線の意味を旧陸軍の内規に基づいて詳しく説明し、「この線は『登山道が県境である』という北都開発の当初からの主張が正しいことを示している」と語った。決定的な証言だった。「地図屋の良心」がごまかしを許さなかったのである。
1995年、仙台高裁は旧陸軍の内規に基づく弁護団の主張を採用し、原告逆転勝訴の判決を言い渡した。事件から、実に32年後のことだった。
「山交は県内陸部最大のバス会社であったほか、同県の政財界に多大な影響力を有していた山形新聞、山形放送とグループを形成して密接な連携を保っていた」
「山形営林署長らは姑息な理由で(北都開発の)申請の受理を拒否ないし遷延(せんえん)し、他方で山交リフトの建設に対しては陰に陽に支援・協力していた」
「(山形営林署長らの)一連の貸付権限の行使は、故意による権限の濫用つまり包括的な不法行為に該当するというべきである」
高裁判決は、山形新聞・山形交通グループの策動を暴き、営林当局者の職権濫用を厳しく断罪した。先の刑事裁判の判断を覆し、事実上の「有罪判決」を下したのである。
長い闘いの記録は、佐藤欣哉氏によって『蔵王県境が動く 官財癒着の真相』という本にまとめられ、出版された。
蔵王県境事件の弁護士たちはこの年、公金の使い方を監視する「市民オンブズマン山形県会議」を立ち上げ、山形県発注の土木建設工事をめぐる談合事件や山形市議、山形県議の政務調査費(のち政務活動費)の不適切な支出の追及に乗り出した。不正を次々に暴き、貴重な血税を取り戻すのに多大な貢献をした。
その先頭に立ってきた佐藤欣哉弁護士が10月17日、闘病の末、74歳で亡くなった。不正を許さず、闘い続けた人生だった。
◇ ◇
メディアを核に支配を広げ、「天皇」と称された山形新聞の服部敬雄氏は1991年に死去し、山新・山交(現ヤマコー)グループの結束は著しく弱まった。服部氏の番頭のような存在だった県知事も代替わりし、2009年には吉村美栄子氏が東北初の女性知事になった。
それによって、山形県の政治風土と県民性は変わったのだろうか。私たちはどれだけ前に進むことができたのだろうか。
この2年、このコラムで報じてきた通り、吉村知事が誕生して以来、知事の義理のいとこの吉村和文氏が率いる企業・法人グループは「わが世の春」を謳歌してきた。吉村県政誕生以来の10年間で、このグループに支出された公金は40億円を上回る。2019年度以降、さらに上積みされていることは言うまでもない。
吉村一族企業の所業は、山新・山交グループの振る舞いとそっくりではないか。
その実態を解明するため、筆者が学校法人東海山形学園の財務書類の情報公開を請求したところ、県は詳しい内容を白塗りにして隠し、不開示にした(2017年5月)。
「白塗り」は「黒塗り」より悪質である。「黒塗り」なら貸借対照表の備考欄に融資などの利益相反行為があることをうかがわせる痕跡が残るが、「白塗り」だと、そうしたものがあるかどうかも分からないからだ。
私学助成を担当する山形県学事文書課は「あるかどうかも分からなくする」のが得意だ。東海山形学園から和文氏の率いるダイバーシティメディアへの3000万円融資に関する「特別代理人の選任文書」について、私が情報公開を求めると、「存否(そんぴ)応答拒否」(文書があるかどうかも答えない)という決定をした(2018年10月)。その理由は「学校法人の利益を害するおそれがある」という理不尽なものだった。
私立学校法は「利益相反行為がある場合、所轄庁(山形県)は特別代理人を選んでチェックさせなさい」と規定していた。私は「その法律に基づいて選んだのですか」と問いただしたに過ぎない。「利益を害する」ことなどあり得ないのだ。知事の義理のいとこが理事長をつとめる学校法人の不始末を隠そうとした、としか考えられない対応だった。
財務書類の不開示をめぐる裁判は、仙台高裁で「山形県の対応は違法。すべて開示しなさい」との判決が出され、県の上告が退けられて確定した。この判決に基づいて全面開示された財務書類を点検したところ、2016年の3000万円とは別に、2013年にも学校法人から和文氏個人に5000万円の融資が行われていたことが明らかになった。
県学事文書課は全面開示の直前に、この5000万円融資の事実に気づいたことを認めている。だが、筆者が記者会見をして明らかにするまで口をつぐんでいた。
蔵王県境事件の際の秋田営林局や山形営林署の対応と何と似ていることか。県知事も県職員も「学校法人と一蓮托生」とでも思っているのだろうか。
3000万円の融資でも5000万円の融資でも、県は「特別代理人」を選ばず、私立学校法に定められた責務を果たしていなかった。
その点を追及されると、吉村知事は記者会見や県議会で「県としては(融資という利益相反行為を)知り得なかったのです」と答え、そこに逃げ込もうとしている。
確かに、学校法人とグループ企業の間での融資という利益相反行為を事前に知るのは難しい。だが、私学助成を受けている学校法人は次年度の6月までにはすべての財務書類を県に提出する。丁寧に目を通せば、その時点で気づくはずだ。「知り得ない」という答えは、論理的にも日本語としても間違っている。
10月13日の定例記者会見で知事が答えに窮すると、大滝洋・総務部長は助け舟を出し、こう述べた。「(貸借対照表などの)財務諸表は参考資料なんです。その注記部分はチェックすべき対象になっていない」
暴言と言うしかない。私立学校振興助成法によって、学校法人は所轄庁(山形県)に財務書類を提出することを義務づけられている。学校法人の財務状況を示す重要な書類だからだ。それを「参考資料でチェック不要」と言ってのける度胸に驚く。
大滝部長が果たしている役割は、蔵王県境事件の刑事裁判で被告側の証人になった国土地理院の専門家に似ている。訳知り顔で不正確な情報をばらまき、混乱させて真相の解明を妨げる役回りだ。
当事者である東海山形学園の吉村和文理事長はメディアに対して様々な釈明をしている。いずれも説得力がなく、信ずるに足りない。紙幅が尽きてきた。どこがどのように信用できないのか、次号で詳しく分析したい。
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年11月号に寄稿した文章を若干手直しして転載したものです。
≪写真説明≫
1995年1月23日、仙台高裁で逆転勝訴した原告と弁護団(『蔵王県境が動く 官財癒着の真相』から複写)
≪参考文献&資料≫
◎蔵王県境事件の国家損害賠償請求に対する仙台高裁の判決(1995年1月23日)
◎『蔵王県境が動く 官財癒着の真相』(佐藤欣哉著、やまがた散歩社)
◎『小説 蔵王県境事件』(須貝和輔著、東北出版企画)
◎『山形の政治 戦後40年・ある地方政界・』(朝日新聞山形支局、未来社)
◎1963年8月29日から1995年1月29日の朝日新聞山形県版の関係記事
市民オンブズマンとして、山形市の学校法人がグループ企業に3000万円融資した問題を調べてきましたが、この学校法人がさらに理事長個人に5000万円の融資をしていたことが9月24日、新たに判明しました。

この学校法人の理事長と企業の社長は同一人物で、吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこの吉村和文氏です。いずれも「利益相反(そうはん)行為」に当たりますが、県も学校法人も私立学校法に定められた手続きを踏んでいませんでした。
吉村和文氏が理事長をしている学校法人は「東海山形学園」で、東海大山形高校を運営しています。3000万円の融資は2015年度に東海山形学園がダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に対して行ったものですが、この学校法人は2013年度にも吉村理事長個人に対して5000万円を貸し付けていたことが分かりました。私学助成を担当する山形県学事文書課は「事実関係を調査中」と表明しています。
3000万円の融資に関しては、私が山形県にこの学校法人の財務書類の情報公開を求めたところ、県側は文書の詳細な部分を白塗りにして隠し、不開示にしたため、情報公開を求めて裁判に訴えました。この間の経緯はすでに、風切通信でお伝えした通りです。一審の山形地裁では敗れたものの、控訴審の仙台高裁で逆転勝訴し、高裁は山形県に財務書類の全面開示を命じました。県側は最高裁に上告しましたが一蹴され、判決が確定しました。5000万円の融資はこの判決に基づいて開示された財務書類を精査して判明したものです。
山形県は裁判になった財務書類の不開示決定のほかにも、別の情報公開請求に対して「存否応答拒否」の決定をするなど不可解な対応をしてきました。「なぜ、そこまで無茶苦茶なことをするのか」といぶかしく思ってきましたが、今にして思えば、この5000万円融資のことも隠したかったのかもしれません。
5000万円の融資はグループ企業に対してではなく、グループを率いる吉村和文氏個人に対する貸付で、学校法人の理事会で検討され、追認の手続きが取られたかどうかも今のところ分かっていません。
吉村一族の企業・法人グループについては、山形県の入札や業務委託をめぐってさまざまな疑惑が表面化しており、なお追及中です。県知事の吉村美栄子氏は3000万円の融資について「学校法人が適切に運営されているのであれば、よろしいのではないか」などと釈明してきましたが、「適切な運営」という前提は崩れ去ったと言うしかありません。
吉村知事と一族企業グループの問題について、当地の月刊誌『素晴らしい山形』の10月号に20回目の寄稿をしました。5000万円の融資が判明する直前に書いたものです。問題の経緯と背景を詳しく説明していますので、長い文章ですが、ご一読ください。
◇ ◇
知事12年でも「道半ば」? あと何年居座るつもりか
権力の座に長く居続けると、人はこんな風になってしまうものなのだろうか。
山形県の吉村美栄子知事の言動を見ていると、普通の人の普通の感覚が分からなくなり、自分に都合のいい見方しかできなくなった人間の悲哀を感じる。
学校法人の東海山形学園が民間企業のダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資をした問題は、ごく普通に考えれば、「おかしなことだ」とすぐに分かる。金を貸すのは学校の仕事ではない。資金が必要なら、銀行に頼めばいい。
そのうえ、この融資では学校法人の理事長と会社の社長は同一人物、吉村知事の義理のいとこの吉村和文氏である。「グループの中で学校の金を使い回している」と見るのが当然ではないか。「そんなことが許されるのか」と疑問を抱くのが普通だろう。
火のないところに煙は立たない。腐敗のないところから腐臭は漂ってこない。
4年前、この融資のことを月刊『素晴らしい山形』の記事で知った時、私は強烈な腐臭を感じた。元新聞記者として「これをきちんと調べていけば、臭いの元にたどり着ける」と直感した。
取材は素朴な疑問を解くところから始まる。最初の疑問は「なぜ、銀行に金を貸してくれるよう頼まなかったのか」ということだ。「銀行に頼めない事情があったから」と推測した。
その推測を立証するのは、それほど難しいことではない。吉村和文氏の自宅や彼が率いる会社の土地・建物の登記簿を調べればいい。山形地方法務局に行って手数料を払えば、誰でも登記を見ることができる。
山形市小白川町にある吉村和文氏の自宅の登記簿は、土地も建物も抵当権が何重にも設定されていた(図1)。映画館を運営する「ムービーオン」が山形銀行や荘内銀行から億単位の資金を借りた際、社長として自宅の土地と建物を担保に提供したからだ。これだけ抵当権が設定されてしまえば、自宅の土地や建物にはすでに担保価値はない。
吉村一族の企業グループの中核、ダイバーシティメディアはどうか。図2のように、その登記簿も真っ黒だった。4階建ての本社ビルからケーブルテレビの放送施設やテレビカメラまで、一切合切まとめて銀行の抵当に入っていた。こちらも、これ以上抵当権を設定するのは無理だと分かる。
多額の借金を抱える「ムービーオン」の登記簿は調べるまでもない。要するに、吉村一族の企業グループにはこの時期、担保として提供できるものがなかったのである。担保のないところに、銀行は金を貸したりしない。そこで、資金が潤沢な学校法人から回したのだ。
こうしたことが分かった段階で、東海大山形高校を運営する東海山形学園の財務調査を始めた。貸した側からも「3000万円融資」の事実を確認したかったからだ。
学校法人は政府や都道府県から私学助成を受けており、資金収支計算書や貸借対照表などの財務書類をすべて監督官庁に提出している。そこで、情報公開制度を使って、山形県に財務書類を開示するよう請求した。
それに対して、山形県は詳しい項目と金額を白塗りにして隠し、開示しなかった。不開示の理由は「開示すると、その学校法人の正当な利益を害するおそれがあるから」というものだった。「財務書類を公開すると正当な利益が害される」などということは、あるわけがない。
一部上場企業の場合、そうした財務書類を公表することが法律で義務づけられている。それによって、ライバル企業に秘密やノウハウが漏れて損をしたなどということは聞いたこともない。ましてや、公的な助成を受けている学校法人でそうしたことが起きるなどとは到底、考えられない。
山形県の不開示決定は違法と考え、裁判所に訴えた。一審の山形地裁では敗れたが、仙台高裁ではこちらの主張が全面的に認められた。詳しい経緯は今年の本誌5月号でお伝えした。県側は上告したが、最高裁に一蹴され、9月10日に渋々、書類をすべて開示した(図3)。
この裁判と並行して、「利益相反行為」についても県に情報公開を求めた。同じ人物が代表をつとめる会社と学校法人の間で金の貸し借りをすれば、どちらかが得をして片方が損をする可能性がある。この3000万円の融資は、典型的な利益相反行為に当たる。
こういう場合、民間企業なら取締役会や株主総会で承認を得れば済むが、公金が注ぎ込まれている学校法人の場合はそれほど簡単ではない。私立学校法に特別の規定があり、「所轄庁(山形県)は特別代理人を選んで、学校法人の利益が害されないようにせよ」と定めていた。
山形県はその責任を果たしたのか。それを確認するため、「特別代理人の選任に関する文書」の開示を求めた。すると、県は「存否(そんぴ)応答拒否」という、とんでもない決定をした。「文書があるかどうかも明らかにできない」というのだ。理由はまたしても「学校法人の正当な利益を害するおそれがあるから」。懲りない人たちだ。
今度は裁判ではなく、県の諮問機関である情報公開・個人情報保護審査会に異議を申し立てた。審査会の専門家もあきれたのだろう。「そもそも決定にあたり、慎重かつ十分な検討が尽くされたのか」と苦言を呈したうえで、存否応答拒否を取り消す答申を出した。
この答申を受けて、県は同じ9月10日に「文書はありませんでした」と認めた。私立学校法に定められた「特別代理人の選任」という責務を果たしていなかったのである。
吉村知事は9月15日の記者会見で、この問題について問われ、こう答えた。
「特別代理人の選任については、利害関係人である学校法人(東海山形学園)から県に選任の請求がありませんでした」
そんなことは分かっている。ポイントは、学校法人から請求がない場合、「所轄庁は職権で選任しなければならない」と私立学校法で定められていることだ。つまり、どんな場合でも、県は特別代理人を選任して学校法人の利益が害されないようにしなければならないのだ。
この点については「学校法人の財務書類等からは、選任の必要性を判断することは非常に困難であります。県としては知り得なかったわけであります」と釈明した。驚くべき発言だ。知事みずから、「担当職員の目は節穴なんです」と認めたようなものである。
思い起こしていただきたい。この3000万円の融資問題は、月刊『素晴らしい山形』の発行人である相澤嘉久治(かくじ)氏がダイバーシティメディアの貸借対照表を見て気づいたことから発覚した。
相澤氏は会計の専門家でもなんでもない。素人である。そういう人が見つけられるものを、仕事でチェックしている県職員が見つけられなくてどうするのか。
知事は「当該取引(3000万円融資)について県で法人に確認をいたしましたが、理事会で追認を行い、適切に対応されていたということでありました」とも述べた。「借りた金は返したし、後日、理事会で追認されたのだから何も問題はない」と言いたいのだろう。
利益相反行為をした当人(吉村和文氏)と同じ理屈、同じ説明をしている。行政は公平、中立の立場で物事を考え、対処するところであるということを忘れているようだ。
毎年、億単位の血税を助成している学校法人で起きたことなのだ。県には監督官庁として「なぜ融資が必要だったのか。貸し倒れに備えて、担保や保証人は確保していたのか」といったことをきちんとチェックする責任がある。「追認されたから問題ない」というような簡単な問題ではない。
東海山形学園の理事会のメンバーを見てみよ。理事長の吉村和文氏に抜擢された元校長や和文氏と昵懇(じっこん)の間柄の市川昭男・前山形市長ら、和文氏のお友達がずらりと並んでいる。理事会での追認の内実も想像がつこうというものだ。
記者会見で、吉村知事は東海山形学園の融資問題についてしつこく追及された。あまりのしつこさに、知事は「なぜそこまで問題にされたのかな、ということもちょっと思います」と、愚痴までこぼしている。
「甘ったれるんじゃない」と言いたい。3000万円を借りたダイバーシティメディアには設立されて間もなく、山形県が1200万円の出資をしている。山形市や天童市、上山市なども出資した。いわゆる「第三セクター会社」で、今でもそれぞれ株を保有している(図4)。そういう会社が、人件費など経常経費の半分を税金で賄っている学校法人から3000万円も借りたのである。
しかも、知事当選後の2009年の資産公開で、吉村知事はこの会社の株主であることが明らかになっている。翌年以降の資産公開では、ケーブルテレビ山形(当時)の株は保有資産一覧には登場しない。
「さすがに好ましくないので手放したのか」と思って調べてみたら、何のことはない。長男に譲っただけだった。株主名簿を見ると、「吉村美栄子」と記してあったところに、長男の展彦(のぶひこ)氏の名前が載っている。資産公開の対象から外すためと見られ、一種の脱法行為をしているのである。情けない政治家だ。
学校法人をめぐっては、これまで様々な不正や不祥事が表面化した。学校法人を代表する理事長が関与しているケースも少なくない。
文部科学省はこうした事態を重く見て、2004年に「理事長についてはできる限り常勤化を図り、兼職の制限を行うことが期待される」との事務次官通知を出した。それを受けて、高等教育局私学行政課は「理事長については責任に見合った勤務形態を取り、対内的にも対外的にも責任を果たしていくことが重要と考える」との文書を発出した。
吉村和文氏のように「数多くの会社を経営して学校法人の理事長も兼ね、学校には滅多に顔を出さない」というようなことは好ましくない、とはっきり言っているのだ。
だが、山形県の学事文書課はこうした文書を漫然と各学校法人に流しただけで、具体的な指導は何もしていない。知事に至っては、こうした通知すら知らないのではないか。
どんな社会でも、教育はその社会の礎(いしずえ)であり、教育が揺らげば、社会そのものが揺らぐ。教育の営みは、文字通り「未来づくり」である。そういうところで、3000万円もの怪しげな融資が行われた。そして、監督する立場にある知事が「学校法人の運営が適切に行われているなら、問題ないのではないか」と平気でうそぶく。それがまかり通ろうとしている。
教育関係者はこの問題をどう見ているのか。高校を運営する学校法人の理事の一人はこう語った。
「私どもは授業料にしても私学助成にしても、教育のためにいただいています。その資金は教育活動のために使うのが当然と考えています。資金を運用するにしても、公正さと透明さが求められるのではないでしょうか」
救われる思いがした。
吉村知事は来年1月の知事選に立候補するかどうか、まだ態度を明らかにしていない。だが、鶴岡市内で開かれた農林水産関係者との会合で出馬を促され、「エールをいただいた。まだ、道半ばという思いもある」と応じた。意欲満々のようだ。
3期12年もつとめて「道半ば」とは恐れ入る。あと何年つとめるつもりなのか。いったい、何がしたいのか。
*「◇ ◇」以下は、月刊『素晴らしい山形』2020年10月号の連載(20)を転載
*メールマガジン「風切通信 79」 2020年9月30日
≪写真≫
月刊『素晴らしい山形』2020年10月号の表紙イラスト

この学校法人の理事長と企業の社長は同一人物で、吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこの吉村和文氏です。いずれも「利益相反(そうはん)行為」に当たりますが、県も学校法人も私立学校法に定められた手続きを踏んでいませんでした。
吉村和文氏が理事長をしている学校法人は「東海山形学園」で、東海大山形高校を運営しています。3000万円の融資は2015年度に東海山形学園がダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に対して行ったものですが、この学校法人は2013年度にも吉村理事長個人に対して5000万円を貸し付けていたことが分かりました。私学助成を担当する山形県学事文書課は「事実関係を調査中」と表明しています。
3000万円の融資に関しては、私が山形県にこの学校法人の財務書類の情報公開を求めたところ、県側は文書の詳細な部分を白塗りにして隠し、不開示にしたため、情報公開を求めて裁判に訴えました。この間の経緯はすでに、風切通信でお伝えした通りです。一審の山形地裁では敗れたものの、控訴審の仙台高裁で逆転勝訴し、高裁は山形県に財務書類の全面開示を命じました。県側は最高裁に上告しましたが一蹴され、判決が確定しました。5000万円の融資はこの判決に基づいて開示された財務書類を精査して判明したものです。
山形県は裁判になった財務書類の不開示決定のほかにも、別の情報公開請求に対して「存否応答拒否」の決定をするなど不可解な対応をしてきました。「なぜ、そこまで無茶苦茶なことをするのか」といぶかしく思ってきましたが、今にして思えば、この5000万円融資のことも隠したかったのかもしれません。
5000万円の融資はグループ企業に対してではなく、グループを率いる吉村和文氏個人に対する貸付で、学校法人の理事会で検討され、追認の手続きが取られたかどうかも今のところ分かっていません。
吉村一族の企業・法人グループについては、山形県の入札や業務委託をめぐってさまざまな疑惑が表面化しており、なお追及中です。県知事の吉村美栄子氏は3000万円の融資について「学校法人が適切に運営されているのであれば、よろしいのではないか」などと釈明してきましたが、「適切な運営」という前提は崩れ去ったと言うしかありません。
吉村知事と一族企業グループの問題について、当地の月刊誌『素晴らしい山形』の10月号に20回目の寄稿をしました。5000万円の融資が判明する直前に書いたものです。問題の経緯と背景を詳しく説明していますので、長い文章ですが、ご一読ください。
◇ ◇
知事12年でも「道半ば」? あと何年居座るつもりか
権力の座に長く居続けると、人はこんな風になってしまうものなのだろうか。
山形県の吉村美栄子知事の言動を見ていると、普通の人の普通の感覚が分からなくなり、自分に都合のいい見方しかできなくなった人間の悲哀を感じる。
学校法人の東海山形学園が民間企業のダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資をした問題は、ごく普通に考えれば、「おかしなことだ」とすぐに分かる。金を貸すのは学校の仕事ではない。資金が必要なら、銀行に頼めばいい。
そのうえ、この融資では学校法人の理事長と会社の社長は同一人物、吉村知事の義理のいとこの吉村和文氏である。「グループの中で学校の金を使い回している」と見るのが当然ではないか。「そんなことが許されるのか」と疑問を抱くのが普通だろう。
火のないところに煙は立たない。腐敗のないところから腐臭は漂ってこない。
4年前、この融資のことを月刊『素晴らしい山形』の記事で知った時、私は強烈な腐臭を感じた。元新聞記者として「これをきちんと調べていけば、臭いの元にたどり着ける」と直感した。
取材は素朴な疑問を解くところから始まる。最初の疑問は「なぜ、銀行に金を貸してくれるよう頼まなかったのか」ということだ。「銀行に頼めない事情があったから」と推測した。
その推測を立証するのは、それほど難しいことではない。吉村和文氏の自宅や彼が率いる会社の土地・建物の登記簿を調べればいい。山形地方法務局に行って手数料を払えば、誰でも登記を見ることができる。
山形市小白川町にある吉村和文氏の自宅の登記簿は、土地も建物も抵当権が何重にも設定されていた(図1)。映画館を運営する「ムービーオン」が山形銀行や荘内銀行から億単位の資金を借りた際、社長として自宅の土地と建物を担保に提供したからだ。これだけ抵当権が設定されてしまえば、自宅の土地や建物にはすでに担保価値はない。
吉村一族の企業グループの中核、ダイバーシティメディアはどうか。図2のように、その登記簿も真っ黒だった。4階建ての本社ビルからケーブルテレビの放送施設やテレビカメラまで、一切合切まとめて銀行の抵当に入っていた。こちらも、これ以上抵当権を設定するのは無理だと分かる。
多額の借金を抱える「ムービーオン」の登記簿は調べるまでもない。要するに、吉村一族の企業グループにはこの時期、担保として提供できるものがなかったのである。担保のないところに、銀行は金を貸したりしない。そこで、資金が潤沢な学校法人から回したのだ。
こうしたことが分かった段階で、東海大山形高校を運営する東海山形学園の財務調査を始めた。貸した側からも「3000万円融資」の事実を確認したかったからだ。
学校法人は政府や都道府県から私学助成を受けており、資金収支計算書や貸借対照表などの財務書類をすべて監督官庁に提出している。そこで、情報公開制度を使って、山形県に財務書類を開示するよう請求した。
それに対して、山形県は詳しい項目と金額を白塗りにして隠し、開示しなかった。不開示の理由は「開示すると、その学校法人の正当な利益を害するおそれがあるから」というものだった。「財務書類を公開すると正当な利益が害される」などということは、あるわけがない。
一部上場企業の場合、そうした財務書類を公表することが法律で義務づけられている。それによって、ライバル企業に秘密やノウハウが漏れて損をしたなどということは聞いたこともない。ましてや、公的な助成を受けている学校法人でそうしたことが起きるなどとは到底、考えられない。
山形県の不開示決定は違法と考え、裁判所に訴えた。一審の山形地裁では敗れたが、仙台高裁ではこちらの主張が全面的に認められた。詳しい経緯は今年の本誌5月号でお伝えした。県側は上告したが、最高裁に一蹴され、9月10日に渋々、書類をすべて開示した(図3)。
この裁判と並行して、「利益相反行為」についても県に情報公開を求めた。同じ人物が代表をつとめる会社と学校法人の間で金の貸し借りをすれば、どちらかが得をして片方が損をする可能性がある。この3000万円の融資は、典型的な利益相反行為に当たる。
こういう場合、民間企業なら取締役会や株主総会で承認を得れば済むが、公金が注ぎ込まれている学校法人の場合はそれほど簡単ではない。私立学校法に特別の規定があり、「所轄庁(山形県)は特別代理人を選んで、学校法人の利益が害されないようにせよ」と定めていた。
山形県はその責任を果たしたのか。それを確認するため、「特別代理人の選任に関する文書」の開示を求めた。すると、県は「存否(そんぴ)応答拒否」という、とんでもない決定をした。「文書があるかどうかも明らかにできない」というのだ。理由はまたしても「学校法人の正当な利益を害するおそれがあるから」。懲りない人たちだ。
今度は裁判ではなく、県の諮問機関である情報公開・個人情報保護審査会に異議を申し立てた。審査会の専門家もあきれたのだろう。「そもそも決定にあたり、慎重かつ十分な検討が尽くされたのか」と苦言を呈したうえで、存否応答拒否を取り消す答申を出した。
この答申を受けて、県は同じ9月10日に「文書はありませんでした」と認めた。私立学校法に定められた「特別代理人の選任」という責務を果たしていなかったのである。
吉村知事は9月15日の記者会見で、この問題について問われ、こう答えた。
「特別代理人の選任については、利害関係人である学校法人(東海山形学園)から県に選任の請求がありませんでした」
そんなことは分かっている。ポイントは、学校法人から請求がない場合、「所轄庁は職権で選任しなければならない」と私立学校法で定められていることだ。つまり、どんな場合でも、県は特別代理人を選任して学校法人の利益が害されないようにしなければならないのだ。
この点については「学校法人の財務書類等からは、選任の必要性を判断することは非常に困難であります。県としては知り得なかったわけであります」と釈明した。驚くべき発言だ。知事みずから、「担当職員の目は節穴なんです」と認めたようなものである。
思い起こしていただきたい。この3000万円の融資問題は、月刊『素晴らしい山形』の発行人である相澤嘉久治(かくじ)氏がダイバーシティメディアの貸借対照表を見て気づいたことから発覚した。
相澤氏は会計の専門家でもなんでもない。素人である。そういう人が見つけられるものを、仕事でチェックしている県職員が見つけられなくてどうするのか。
知事は「当該取引(3000万円融資)について県で法人に確認をいたしましたが、理事会で追認を行い、適切に対応されていたということでありました」とも述べた。「借りた金は返したし、後日、理事会で追認されたのだから何も問題はない」と言いたいのだろう。
利益相反行為をした当人(吉村和文氏)と同じ理屈、同じ説明をしている。行政は公平、中立の立場で物事を考え、対処するところであるということを忘れているようだ。
毎年、億単位の血税を助成している学校法人で起きたことなのだ。県には監督官庁として「なぜ融資が必要だったのか。貸し倒れに備えて、担保や保証人は確保していたのか」といったことをきちんとチェックする責任がある。「追認されたから問題ない」というような簡単な問題ではない。
東海山形学園の理事会のメンバーを見てみよ。理事長の吉村和文氏に抜擢された元校長や和文氏と昵懇(じっこん)の間柄の市川昭男・前山形市長ら、和文氏のお友達がずらりと並んでいる。理事会での追認の内実も想像がつこうというものだ。
記者会見で、吉村知事は東海山形学園の融資問題についてしつこく追及された。あまりのしつこさに、知事は「なぜそこまで問題にされたのかな、ということもちょっと思います」と、愚痴までこぼしている。
「甘ったれるんじゃない」と言いたい。3000万円を借りたダイバーシティメディアには設立されて間もなく、山形県が1200万円の出資をしている。山形市や天童市、上山市なども出資した。いわゆる「第三セクター会社」で、今でもそれぞれ株を保有している(図4)。そういう会社が、人件費など経常経費の半分を税金で賄っている学校法人から3000万円も借りたのである。
しかも、知事当選後の2009年の資産公開で、吉村知事はこの会社の株主であることが明らかになっている。翌年以降の資産公開では、ケーブルテレビ山形(当時)の株は保有資産一覧には登場しない。
「さすがに好ましくないので手放したのか」と思って調べてみたら、何のことはない。長男に譲っただけだった。株主名簿を見ると、「吉村美栄子」と記してあったところに、長男の展彦(のぶひこ)氏の名前が載っている。資産公開の対象から外すためと見られ、一種の脱法行為をしているのである。情けない政治家だ。
学校法人をめぐっては、これまで様々な不正や不祥事が表面化した。学校法人を代表する理事長が関与しているケースも少なくない。
文部科学省はこうした事態を重く見て、2004年に「理事長についてはできる限り常勤化を図り、兼職の制限を行うことが期待される」との事務次官通知を出した。それを受けて、高等教育局私学行政課は「理事長については責任に見合った勤務形態を取り、対内的にも対外的にも責任を果たしていくことが重要と考える」との文書を発出した。
吉村和文氏のように「数多くの会社を経営して学校法人の理事長も兼ね、学校には滅多に顔を出さない」というようなことは好ましくない、とはっきり言っているのだ。
だが、山形県の学事文書課はこうした文書を漫然と各学校法人に流しただけで、具体的な指導は何もしていない。知事に至っては、こうした通知すら知らないのではないか。
どんな社会でも、教育はその社会の礎(いしずえ)であり、教育が揺らげば、社会そのものが揺らぐ。教育の営みは、文字通り「未来づくり」である。そういうところで、3000万円もの怪しげな融資が行われた。そして、監督する立場にある知事が「学校法人の運営が適切に行われているなら、問題ないのではないか」と平気でうそぶく。それがまかり通ろうとしている。
教育関係者はこの問題をどう見ているのか。高校を運営する学校法人の理事の一人はこう語った。
「私どもは授業料にしても私学助成にしても、教育のためにいただいています。その資金は教育活動のために使うのが当然と考えています。資金を運用するにしても、公正さと透明さが求められるのではないでしょうか」
救われる思いがした。
吉村知事は来年1月の知事選に立候補するかどうか、まだ態度を明らかにしていない。だが、鶴岡市内で開かれた農林水産関係者との会合で出馬を促され、「エールをいただいた。まだ、道半ばという思いもある」と応じた。意欲満々のようだ。
3期12年もつとめて「道半ば」とは恐れ入る。あと何年つとめるつもりなのか。いったい、何がしたいのか。
*「◇ ◇」以下は、月刊『素晴らしい山形』2020年10月号の連載(20)を転載
*メールマガジン「風切通信 79」 2020年9月30日
≪写真≫
月刊『素晴らしい山形』2020年10月号の表紙イラスト
権力を握った人たちは、その権力をどんな風に使って私腹を肥やそうとするのか。山形県の吉村美栄子知事とその一族企業グループの実態を調べ、2018年末から地元の月刊誌『素晴らしい山形』に連載記事を寄稿してきた。
私は30年余り新聞記者として働き、その間、いくつか調査報道も手がけたが、記者としての技量が足りなかったこともあって、いずれも中途半端な結果に終わり、きちんとした成果を上げることはできなかった。
その意味で、生まれ育った山形の政治の実態を調べて暴く今回の取材は、「在職中に成し得なかったことに再挑戦する試み」となっている。情報公開制度をフルに使って公文書の開示を求めることで、どこまで実態に迫れるか。そのケース・スタディでもある。
すでに67歳。体力も気力も現役の時とは比べものにならないほど衰えた。けれども、この調査報道によって、地方で何が起きているのか、それが中央の政治や行政とどのように連動しているのか、いくつか見えてきたことがある。
その一つが「利権の構造は、かつてとはまるで異なるものになってしまった」ということである。私が現役の新聞記者だった頃は、政治がらみのスキャンダルと言えば、土木建設の公共事業をめぐる汚職がメインだった。
だが、今の「主戦場」は土木建設事業ではない。情報技術(IT)をめぐる利権である。
日本の政治と行政のIT化は信じられないほど悲惨な状況にある。それを私たちは安倍政権の新型コロナウイルス対応で、目の当たりにすることになった。持続化給付金をめぐる経済産業省のスキャンダルはその典型だ。
コロナ禍で打撃を受けた中小企業や事業者を支援するこの事業では、膨大な数の企業と事業者にすみやかに資金を提供しなければならない。だが、お粗末なシステムしかない経産省にはその能力がない。結局、電通やパソナなどに事業を丸投げするしかなかった。
民間企業にとって、「ITを使いこなせない政治と行政」は「甘い汁を吸う絶好の場」となる。電通やパソナ、そして多くのIT企業はその機会を大いに活用したに過ぎない。
コロナ対策の要とも言えるPCR検査でも、厚生労働省のIT無能ぶりがあぶり出された。厚労省は傘下の国立感染症研究所と都道府県の衛生研究所・保健所を使ってPCR検査を進める態勢を作った。
ところが、一連の情報を統括するシステムがない。このため、検査の対象者とその結果について、彼らは「ファクスと電話」でやり取りするしかなかった。非能率と混乱の中でPCR検査が「目詰まり」を起こしたのは、当然の帰結だった。
PCR検査の遅れを「都道府県のシステムがバラバラで統一した運用ができなかったから」と弁明する者がいる。笑止千万の言い草だ。中央省庁のITシステムこそ「バラバラ」だからだ。一つの省庁の中ですら異なるシステムを使っており、全体を統括するシステムがないのだ。
都道府県の一番大きな仕事は「中央省庁からの補助金の分配作業」である。中央省庁がバラバラなシステムを使っているから、その補助金を配る都道府県も、それに合わせてバラバラなシステムを場当たり的に構築していくしかなかったのだ。
地方は、「中央省庁の信じられないほど悲惨なIT環境」に付き従って順次、システムを構築していった。その結果、都道府県のITシステムも「信じられないほど悲惨な状況」に陥ってしまったのである。
山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏はそういう状況を熟知し、それを実に巧みに使って自らの企業グループの業績拡大に活かしてきた。ある意味、見事なほどである。
月刊『素晴らしい山形』への私の寄稿は、8月までに19回を重ねた。同誌は9月号でこれまでの主な記事を一挙に掲載したが、ここでは、その一つ、2020年2月号の抜粋を再掲したい。「『棚からボタ餅』3連発、吉村一族企業の太り方」という記事である。
山形県知事の義理のいとこが率いる企業グループは「中央省庁と地方のIT無能ぶり」にどのようにして付け込み、どのような利益を得てきたのか。それは、私たちの納める税金がいかに浪費されてきたかを示すものでもある。
◇ ◇
吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏は1992年に「ケーブルテレビ山形」を設立して、政商としての第一歩を踏み出した。
ケーブルテレビ事業は、当時の郵政省(のち総務省)が国策として推し進めたものだ。全国各地に自治体が出資する「第三セクター会社」を設立させ、ケーブル敷設費の半分を補助金として支給して広めた。普通の民間企業に対して、そのような高率の補助が与えられることはない。
ケーブルテレビ山形の場合も、県内企業に出資を募って設立した後、山形県や山形市など六つの自治体が計2900万円を出資して「第三セクター」としての体裁を整え、そこに億単位の補助金が流し込まれた。
時代の波に乗って、当初、ケーブルテレビ事業は順調に伸びていった。だが、IT革命の進展に伴ってビジネスは暗転する。一般家庭でもインターネットが気軽に利用できるようになるにつれ、「ケーブルを敷設して家庭につなげ、多様なテレビ放送を楽しむ」というビジネスモデルが優位性を失っていったからだ。
今や、若い世代は映画やテレビドラマを、主にアマゾンプライムやネットフリックス、Hulu(フールー)といったインターネットサービスを利用して見る。家でテレビにかじりつく必要はない。端末があれば、ダウンロードして都合のいい時に楽しむことができる。おまけに料金が安く、作品の質と量が勝っているのだから、当然の流れと言える。
(中略)
ケーブルテレビ各社は、敷設したケーブルを通してインターネットサービスを提供するなど生き残りを模索しているが、前途は容易ではない。ケーブルテレビ山形も2016年に「ダイバーシティメディア」と社名を変え、経営の多角化を図って難局を乗り切ろうとしている。
吉村和文氏が2番目に作ったのも「補助金頼りの会社」である。
2001年に経済産業省が「IT装備都市研究事業」という構想を打ち上げ、全国21カ所のモデル地区で実証実験を始めた。山形市もモデル地区に選ばれ、その事業の一翼を担うために設立したのが「バーチャルシティやまがた」という会社だ。ちなみに、当時の山形市長は和文氏の父親で県議から転じた吉村和夫氏である。
この事業は、国がIC(集積回路)を内蔵する多機能カードを作って市民に無料で配布し、市役所や公民館に設置された端末機器で住民票や印鑑証明書の発行を受けられるようにする、という大盤振る舞いの事業だった。登録した商店で買い物をすればポイントがたまるメリットもあるとの触れ込みで、「バーチャルシティやまがた」はこの部分を担うために作られた。
山形市は5万枚の市民カードを希望者に配布したが、利用は広がらなかった。おまけに総務省が翌2002年から住民基本台帳ネットワークを稼働させ、住基カードの発行を始めた。経産省と総務省が何の連携もなく、別々に似たような機能を持つカードを発行したのだ。「省あって国なし」を地で行く愚挙と言わなければならない。
全国で172億円を投じた経産省の実証実験はさしたる成果もなく頓挫し、総務省の住基カードも、その後、マイナンバーカードが導入されて無用の長物と化した。こちらの無駄遣いは、政府と自治体を合わせて1兆円近いとの試算がある。
国民がどんなに勤勉に働いても、こんな税金の使い方をしていたら、国の屋台骨が揺らぎかねない。だが、官僚たちはどこ吹く風。責任を取る者は誰もいない。政商は肥え太り、次の蜜を探して動き回る。
吉村和文氏は多数の企業を率いるかたわら、学校法人東海山形学園の理事長をしている。多忙で、学校法人が運営する東海大山形高校に顔を出すことは少ないが、それでも入学式や卒業式には出席して生徒に語りかける。
彼のブログ「約束の地へ」によれば、2014年4月の入学式では「自分と向かい合うこと、主体的に行動すること」を訴え、さらに「棚ボタとは、棚の下まで行かなければ、ボタ餅は受け取れない。だから、前向きの状態でいること」と述べた。
いささか珍妙な講話だが、彼が歩んできた道を思えば、意味深長ではある。
彼にとっては、郵政省のケーブルテレビ事業が第1のボタ餅、経済産業省のIT装備都市構想が第2のボタ餅なのかもしれない。そして、3番目が2007年頃から推し進められたユビキタス事業である。
ユビキタスとは、アメリカの研究者が考え出した言葉で、「あらゆる場所であらゆるものがコンピューターのネットワークにつながる社会」を意味する。衣服にコンピューターを取り付け、体温を測定して空調を自動調節する。ゴミになるものにコンピューターを取り付け、焼却施設のコンピューターと交信して処理方法を決める。そんな未来社会を思い描いていた。
日本では、坂村健・東大教授が提唱し、総務省がすぐに飛び付いた。2009年にユビキタス構想の推進を決定し、経済危機関連対策と称して195億円の補正予算を組み、全国に予算をばら撒いた。補助金の対象はまたもや「自治体と第三セクター」である。
山形県では鶴岡市や最上町とともにケーブルテレビ山形が補助の対象になり、「新山形ブランドの発信による地域・観光振興事業」に5898万円の補助金が交付された。その補助金で和文氏は「東北サプライズ商店街」なるサイトを立ち上げ、加盟した飲食店や商店の情報発信を始めた。そのサイトによってどの程度、成果が上がり、現在、どのように機能しているのかは窺い知れない。
だが、ITの技術革新は研究者や官僚たちの想定をはるかに超えて急激に進み、「ユビキタス」という言葉そのものが、すでにITの世界では「死語」と化した。スマートフォンが普及し、「あらゆる場所で誰もがネットワークにつながる社会」が到来してしまったからだ。
日本の政府や自治体がIT分野でやっていることは、IT企業の取り組みの「周回遅れ」と言われて久しい。周回遅れのランナーが訳知り顔で旗を振り、実験やら構想やらを唱えるのは滑稽である。その滑稽さを自覚していないところがいっそう悲しい。
この国はどうなってしまうのだろうか。「世の中、なんとかなる」といつも気楽に構えている私のような人間ですら、時々、本当に心配になってくる。
*メールマガジン「風切通信 78」 2020年8月30日
私は30年余り新聞記者として働き、その間、いくつか調査報道も手がけたが、記者としての技量が足りなかったこともあって、いずれも中途半端な結果に終わり、きちんとした成果を上げることはできなかった。
その意味で、生まれ育った山形の政治の実態を調べて暴く今回の取材は、「在職中に成し得なかったことに再挑戦する試み」となっている。情報公開制度をフルに使って公文書の開示を求めることで、どこまで実態に迫れるか。そのケース・スタディでもある。
すでに67歳。体力も気力も現役の時とは比べものにならないほど衰えた。けれども、この調査報道によって、地方で何が起きているのか、それが中央の政治や行政とどのように連動しているのか、いくつか見えてきたことがある。
その一つが「利権の構造は、かつてとはまるで異なるものになってしまった」ということである。私が現役の新聞記者だった頃は、政治がらみのスキャンダルと言えば、土木建設の公共事業をめぐる汚職がメインだった。
だが、今の「主戦場」は土木建設事業ではない。情報技術(IT)をめぐる利権である。
日本の政治と行政のIT化は信じられないほど悲惨な状況にある。それを私たちは安倍政権の新型コロナウイルス対応で、目の当たりにすることになった。持続化給付金をめぐる経済産業省のスキャンダルはその典型だ。
コロナ禍で打撃を受けた中小企業や事業者を支援するこの事業では、膨大な数の企業と事業者にすみやかに資金を提供しなければならない。だが、お粗末なシステムしかない経産省にはその能力がない。結局、電通やパソナなどに事業を丸投げするしかなかった。
民間企業にとって、「ITを使いこなせない政治と行政」は「甘い汁を吸う絶好の場」となる。電通やパソナ、そして多くのIT企業はその機会を大いに活用したに過ぎない。
コロナ対策の要とも言えるPCR検査でも、厚生労働省のIT無能ぶりがあぶり出された。厚労省は傘下の国立感染症研究所と都道府県の衛生研究所・保健所を使ってPCR検査を進める態勢を作った。
ところが、一連の情報を統括するシステムがない。このため、検査の対象者とその結果について、彼らは「ファクスと電話」でやり取りするしかなかった。非能率と混乱の中でPCR検査が「目詰まり」を起こしたのは、当然の帰結だった。
PCR検査の遅れを「都道府県のシステムがバラバラで統一した運用ができなかったから」と弁明する者がいる。笑止千万の言い草だ。中央省庁のITシステムこそ「バラバラ」だからだ。一つの省庁の中ですら異なるシステムを使っており、全体を統括するシステムがないのだ。
都道府県の一番大きな仕事は「中央省庁からの補助金の分配作業」である。中央省庁がバラバラなシステムを使っているから、その補助金を配る都道府県も、それに合わせてバラバラなシステムを場当たり的に構築していくしかなかったのだ。
地方は、「中央省庁の信じられないほど悲惨なIT環境」に付き従って順次、システムを構築していった。その結果、都道府県のITシステムも「信じられないほど悲惨な状況」に陥ってしまったのである。
山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏はそういう状況を熟知し、それを実に巧みに使って自らの企業グループの業績拡大に活かしてきた。ある意味、見事なほどである。
月刊『素晴らしい山形』への私の寄稿は、8月までに19回を重ねた。同誌は9月号でこれまでの主な記事を一挙に掲載したが、ここでは、その一つ、2020年2月号の抜粋を再掲したい。「『棚からボタ餅』3連発、吉村一族企業の太り方」という記事である。
山形県知事の義理のいとこが率いる企業グループは「中央省庁と地方のIT無能ぶり」にどのようにして付け込み、どのような利益を得てきたのか。それは、私たちの納める税金がいかに浪費されてきたかを示すものでもある。
◇ ◇
吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏は1992年に「ケーブルテレビ山形」を設立して、政商としての第一歩を踏み出した。
ケーブルテレビ事業は、当時の郵政省(のち総務省)が国策として推し進めたものだ。全国各地に自治体が出資する「第三セクター会社」を設立させ、ケーブル敷設費の半分を補助金として支給して広めた。普通の民間企業に対して、そのような高率の補助が与えられることはない。
ケーブルテレビ山形の場合も、県内企業に出資を募って設立した後、山形県や山形市など六つの自治体が計2900万円を出資して「第三セクター」としての体裁を整え、そこに億単位の補助金が流し込まれた。
時代の波に乗って、当初、ケーブルテレビ事業は順調に伸びていった。だが、IT革命の進展に伴ってビジネスは暗転する。一般家庭でもインターネットが気軽に利用できるようになるにつれ、「ケーブルを敷設して家庭につなげ、多様なテレビ放送を楽しむ」というビジネスモデルが優位性を失っていったからだ。
今や、若い世代は映画やテレビドラマを、主にアマゾンプライムやネットフリックス、Hulu(フールー)といったインターネットサービスを利用して見る。家でテレビにかじりつく必要はない。端末があれば、ダウンロードして都合のいい時に楽しむことができる。おまけに料金が安く、作品の質と量が勝っているのだから、当然の流れと言える。
(中略)
ケーブルテレビ各社は、敷設したケーブルを通してインターネットサービスを提供するなど生き残りを模索しているが、前途は容易ではない。ケーブルテレビ山形も2016年に「ダイバーシティメディア」と社名を変え、経営の多角化を図って難局を乗り切ろうとしている。
吉村和文氏が2番目に作ったのも「補助金頼りの会社」である。
2001年に経済産業省が「IT装備都市研究事業」という構想を打ち上げ、全国21カ所のモデル地区で実証実験を始めた。山形市もモデル地区に選ばれ、その事業の一翼を担うために設立したのが「バーチャルシティやまがた」という会社だ。ちなみに、当時の山形市長は和文氏の父親で県議から転じた吉村和夫氏である。
この事業は、国がIC(集積回路)を内蔵する多機能カードを作って市民に無料で配布し、市役所や公民館に設置された端末機器で住民票や印鑑証明書の発行を受けられるようにする、という大盤振る舞いの事業だった。登録した商店で買い物をすればポイントがたまるメリットもあるとの触れ込みで、「バーチャルシティやまがた」はこの部分を担うために作られた。
山形市は5万枚の市民カードを希望者に配布したが、利用は広がらなかった。おまけに総務省が翌2002年から住民基本台帳ネットワークを稼働させ、住基カードの発行を始めた。経産省と総務省が何の連携もなく、別々に似たような機能を持つカードを発行したのだ。「省あって国なし」を地で行く愚挙と言わなければならない。
全国で172億円を投じた経産省の実証実験はさしたる成果もなく頓挫し、総務省の住基カードも、その後、マイナンバーカードが導入されて無用の長物と化した。こちらの無駄遣いは、政府と自治体を合わせて1兆円近いとの試算がある。
国民がどんなに勤勉に働いても、こんな税金の使い方をしていたら、国の屋台骨が揺らぎかねない。だが、官僚たちはどこ吹く風。責任を取る者は誰もいない。政商は肥え太り、次の蜜を探して動き回る。
吉村和文氏は多数の企業を率いるかたわら、学校法人東海山形学園の理事長をしている。多忙で、学校法人が運営する東海大山形高校に顔を出すことは少ないが、それでも入学式や卒業式には出席して生徒に語りかける。
彼のブログ「約束の地へ」によれば、2014年4月の入学式では「自分と向かい合うこと、主体的に行動すること」を訴え、さらに「棚ボタとは、棚の下まで行かなければ、ボタ餅は受け取れない。だから、前向きの状態でいること」と述べた。
いささか珍妙な講話だが、彼が歩んできた道を思えば、意味深長ではある。
彼にとっては、郵政省のケーブルテレビ事業が第1のボタ餅、経済産業省のIT装備都市構想が第2のボタ餅なのかもしれない。そして、3番目が2007年頃から推し進められたユビキタス事業である。
ユビキタスとは、アメリカの研究者が考え出した言葉で、「あらゆる場所であらゆるものがコンピューターのネットワークにつながる社会」を意味する。衣服にコンピューターを取り付け、体温を測定して空調を自動調節する。ゴミになるものにコンピューターを取り付け、焼却施設のコンピューターと交信して処理方法を決める。そんな未来社会を思い描いていた。
日本では、坂村健・東大教授が提唱し、総務省がすぐに飛び付いた。2009年にユビキタス構想の推進を決定し、経済危機関連対策と称して195億円の補正予算を組み、全国に予算をばら撒いた。補助金の対象はまたもや「自治体と第三セクター」である。
山形県では鶴岡市や最上町とともにケーブルテレビ山形が補助の対象になり、「新山形ブランドの発信による地域・観光振興事業」に5898万円の補助金が交付された。その補助金で和文氏は「東北サプライズ商店街」なるサイトを立ち上げ、加盟した飲食店や商店の情報発信を始めた。そのサイトによってどの程度、成果が上がり、現在、どのように機能しているのかは窺い知れない。
だが、ITの技術革新は研究者や官僚たちの想定をはるかに超えて急激に進み、「ユビキタス」という言葉そのものが、すでにITの世界では「死語」と化した。スマートフォンが普及し、「あらゆる場所で誰もがネットワークにつながる社会」が到来してしまったからだ。
日本の政府や自治体がIT分野でやっていることは、IT企業の取り組みの「周回遅れ」と言われて久しい。周回遅れのランナーが訳知り顔で旗を振り、実験やら構想やらを唱えるのは滑稽である。その滑稽さを自覚していないところがいっそう悲しい。
この国はどうなってしまうのだろうか。「世の中、なんとかなる」といつも気楽に構えている私のような人間ですら、時々、本当に心配になってくる。
*メールマガジン「風切通信 78」 2020年8月30日
新型コロナウイルスの感染再拡大で開催が危ぶまれる中、第8回最上川縦断カヌー探訪は7月25日(土)、3密回避を心がけつつ、何とか開催に漕ぎ着けました。参加者は、小学2年生の山本明莉<あかり>さん(7歳)から大ベテランの清水孝治さん(79歳)まで45人。これまでで最多のカヌー行になりました。

山形県戸沢村の最上峡芭蕉ライン観光の船着き場から出発、最上川の取水堰「さみだれ大堰」の舟通し水路を通り、酒田市砂越<さごし>の庄内大橋まで20キロを漕ぎ下りました。



≪出発&到着時刻≫
▽7月25日(土) 小雨模様、出発時には雨も上がり曇天
10:00 最上峡芭蕉ライン観光の船着き場(下船場)を出発
10:30 最上川の取水堰「さみだれ大堰」に到着、2グループに分かれて舟通し水路へ
* 舟通し水路の上流側の水門を開けて艇を入れ、下流側の水門を開けて艇を通す
様子は次の写真をご参照ください。
11:05 第2グループが「さみだれ大堰」を通過
11:40 庄内町狩川の最上川河川敷(左岸)に到着、風車を眺めながら河原で昼食
12:40 河川敷を出発
14:40 酒田市砂越<さごし>の庄内大橋のたもと(右岸)にゴール
◎第8回最上川縦断カヌー探訪の動画(ユーチューブ=真鍋賢一撮影)








≪参加者&参加艇≫
45人、38艇
山形県内 25人(山形市7、天童市4、酒田市3、米沢市3、村山市2、鶴岡市1、東根市1、尾花沢市1、大江町1、朝日町1、遊佐町1)
山形県外 20人(福島県4、宮城県3、群馬県3、埼玉県3、神奈川県3、岩手県2、栃木県1、東京都1)




≪カヌーイスト=申込順≫
安部幸男(宮城県柴田町)、阿部俊裕(山形県天童市)、阿部明美(同)、佐竹久(山形県大江町)、結城敏宏(山形県米沢市)、岸浩(福島市)、柳沼幸男(福島県泉崎村)、柳沼美由紀(同)、柴田尚宏(山形市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、渡辺不二雄(山形市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、黒田美喜男(山形市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、小川治男(山形市)、古川結香子(横浜市戸塚区)、鈴木紳(山形市)、小田原紫朗(山形県酒田市)、石井秀明(さいたま市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、肥後智成(東京都八王子市)、崔鍾八(山形県朝日町)、永嶋英明(山形県鶴岡市)、前川真喜子(岩手県滝沢市)、寒河江洋光(岩手県北上市)、七海孝(福島県鏡石町)、高橋洋(山形県米沢市)、高橋啓子(同)、山田耕右(山形市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、池田丈人(山形県酒田市)、伊藤信生(同)、国塚則昭(埼玉県毛呂山町)、山本剛生(山形県天童市)、山本明莉(同)、阿部悠子(山形県東根市)、矢萩剛(山形県村山市)、菅原久之(山形県遊佐町)、菊池怜隼(宮城県利府町)、吉田英世(仙台市)、齋藤龍真(山形県村山市)、菊地大二郎(山形市)



≪これまでの参加人数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人、第7回(2019年)35人


≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体のNPO
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、国土交通省酒田河川国道事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、戸沢村、酒田市、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、山形県カヌー協会、美しい山形・最上川フォーラム
*最上川さみだれ大堰の舟通し水路の通過にあたっては、酒田河川国道事務所飽海<あくみ>
出張所の方々のご協力を得ました。深く感謝いたします。
≪協力≫ 最上峡芭蕉ライン観光(株)
≪第8回カヌー探訪記念のステッカー制作&寄付≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽長岡典己▽長岡佳子
≪受付設営・交通案内設置≫ 白田金之助
≪弁当の手配・搬送≫ 安藤昭郎▽白田金之助
≪仕出し弁当≫ みずほ(山形県庄内町)
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバスの配車≫ トランスオーシャンバス(山形県新庄市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(山形県大江町)
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝

山形県戸沢村の最上峡芭蕉ライン観光の船着き場から出発、最上川の取水堰「さみだれ大堰」の舟通し水路を通り、酒田市砂越<さごし>の庄内大橋まで20キロを漕ぎ下りました。



≪出発&到着時刻≫
▽7月25日(土) 小雨模様、出発時には雨も上がり曇天
10:00 最上峡芭蕉ライン観光の船着き場(下船場)を出発
10:30 最上川の取水堰「さみだれ大堰」に到着、2グループに分かれて舟通し水路へ
* 舟通し水路の上流側の水門を開けて艇を入れ、下流側の水門を開けて艇を通す
様子は次の写真をご参照ください。
11:05 第2グループが「さみだれ大堰」を通過
11:40 庄内町狩川の最上川河川敷(左岸)に到着、風車を眺めながら河原で昼食
12:40 河川敷を出発
14:40 酒田市砂越<さごし>の庄内大橋のたもと(右岸)にゴール
◎第8回最上川縦断カヌー探訪の動画(ユーチューブ=真鍋賢一撮影)








≪参加者&参加艇≫
45人、38艇
山形県内 25人(山形市7、天童市4、酒田市3、米沢市3、村山市2、鶴岡市1、東根市1、尾花沢市1、大江町1、朝日町1、遊佐町1)
山形県外 20人(福島県4、宮城県3、群馬県3、埼玉県3、神奈川県3、岩手県2、栃木県1、東京都1)




≪カヌーイスト=申込順≫
安部幸男(宮城県柴田町)、阿部俊裕(山形県天童市)、阿部明美(同)、佐竹久(山形県大江町)、結城敏宏(山形県米沢市)、岸浩(福島市)、柳沼幸男(福島県泉崎村)、柳沼美由紀(同)、柴田尚宏(山形市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、渡辺不二雄(山形市)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、黒田美喜男(山形市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、小川治男(山形市)、古川結香子(横浜市戸塚区)、鈴木紳(山形市)、小田原紫朗(山形県酒田市)、石井秀明(さいたま市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、肥後智成(東京都八王子市)、崔鍾八(山形県朝日町)、永嶋英明(山形県鶴岡市)、前川真喜子(岩手県滝沢市)、寒河江洋光(岩手県北上市)、七海孝(福島県鏡石町)、高橋洋(山形県米沢市)、高橋啓子(同)、山田耕右(山形市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、池田丈人(山形県酒田市)、伊藤信生(同)、国塚則昭(埼玉県毛呂山町)、山本剛生(山形県天童市)、山本明莉(同)、阿部悠子(山形県東根市)、矢萩剛(山形県村山市)、菅原久之(山形県遊佐町)、菊池怜隼(宮城県利府町)、吉田英世(仙台市)、齋藤龍真(山形県村山市)、菊地大二郎(山形市)



≪これまでの参加人数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人、第7回(2019年)35人


≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体のNPO
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、国土交通省酒田河川国道事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、戸沢村、酒田市、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、山形県カヌー協会、美しい山形・最上川フォーラム
*最上川さみだれ大堰の舟通し水路の通過にあたっては、酒田河川国道事務所飽海<あくみ>
出張所の方々のご協力を得ました。深く感謝いたします。
≪協力≫ 最上峡芭蕉ライン観光(株)
≪第8回カヌー探訪記念のステッカー制作&寄付≫ 真鍋賢一
≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽長岡典己▽長岡佳子
≪受付設営・交通案内設置≫ 白田金之助
≪弁当の手配・搬送≫ 安藤昭郎▽白田金之助
≪仕出し弁当≫ みずほ(山形県庄内町)
≪漬物提供≫ 佐竹恵子
≪マイクロバスの配車≫ トランスオーシャンバス(山形県新庄市)
≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(山形県大江町)
≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)
≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
山形県の吉村美栄子知事が下した情報不開示決定について、また新たな動きがあった。吉村知事は「開かれた県政」「県政の見える化」などと綺麗ごとを口にするが、実際の行動は真逆だ。自分や取り巻きとって都合の悪い情報は、平気で隠そうとする。

義理のいとこ、吉村和文氏が理事長を務める学校法人東海山形学園から、同じく和文氏が社長をしているダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資が行われた問題をめぐる対応は、その典型である。
学校法人が民間企業から金を借りたのなら、まだ分かる。が、その反対だ。国や県から毎年3億円もの私学助成を受け取っている学校法人が、2016年3月にグループ企業にその1割に相当する金を貸してあげた、というからあきれる。
この融資については、ダイバーシティメディアの公式サイトに決算公告がアップされており、その貸借対照表に明記してある。いわば「周知の事実」なのだが、念のため、学校法人の財務書類でも確認したいと考え、私は山形県が保有する財務書類を情報公開するよう求めた。すんなり出てくる、と思っていた。
ところが、県は財務書類の詳細な部分を白く塗りつぶして開示してきた(一部不開示)。理由は「法人の内部管理に関する情報であって、開示することにより法人の正当な利益を害するおそれがあるため」(県情報公開条例第6条)というものだった。
県の言い分をもう少し丁寧に紹介する。学校法人の財務書類が全面的に明らかにされれば、学校経営の秘密やノウハウが他の高校の関係者の知るところとなり、その学校の競争力を損ね、利益を大きく害することも十分に考えられる、というものだ。
貸借対照表などの財務書類がどういうものか、まるで理解していない空理空論である。一部上場企業は、そうした財務書類を公開することが法的に義務付けられている。それによって「ライバル企業から秘密やノウハウを盗まれ、損をした」などという話は聞いたこともない。財務書類とはそもそも、そうしたことが生じるようなものではないからだ。
「こんな理屈は通るはずがない」と思ったが、それが甘かった。裁判に訴え、「情報不開示処分の取り消し」を求めたところ、山形地方裁判所の裁判官は県の言い分を認めてしまった。「世の中には浮世離れした人もいる」ということを忘れていた。
脇を固めて論理を練り直し、仙台高等裁判所に控訴した。その顚末(てんまつ)はこのサイトの2020年5月1日付のコラムで詳しく紹介したので省くが、仙台高裁の裁判官は今年の3月、県側の主張を一蹴し、財務書類を全面的に開示するよう命じた。
財務書類とはどういうものか。公共性の高い学校法人はどのような説明責任を果たすべきか。情報公開制度はどのような意義を持っているのか。こちらの主張を全面的に認める逆転判決だった。
けれども、吉村知事はそれでへこたれるような政治家ではない。仙台高裁のまっとうな判決に背を向け、すぐさま最高裁判所に上告した。未来に向けて、情報公開制度をどうやって充実したものにしていくのか、といったことにはまるで関心がないようだ。
もう一つの情報不開示は、もっとひどい。
同じ人物が代表を務める会社と法人の間で金の貸し借りをするのは「利益相反行為」になる。一方が得をすれば、もう一方は損をする関係にあるからだ。私立学校法はこうした場合、不正が起きないよう、所轄庁(山形県)は利害関係のない第三者を特別代理人に選んでチェックさせなさい、と規定していた。
そこで、山形県は法律で義務付けられていることを実際に行ったのか、それを知るために特別代理人の選任に関する公文書の開示を請求した。すると、「そういう文書があるかどうかも言えない」と回答してきた(2018年10月23日付)。
「存否(そんぴ)応答拒否」という対応だ。文書を白塗りにして隠すより、もっとこずるい情報隠しだ。理由は、前回と同じく「法人の正当な利益を害するおそれがあるから」である。
確かに、山形県情報公開条例には存否応答拒否もできる、と書いてある。けれども、それは「個人の措置入院に関する文書」や「生活保護の申請書類」「特定企業の開発・投資計画」などが情報公開請求の対象になった場合だ。
こうしたケースでは、それに関する公文書があることを明らかにしただけで、個人や企業の権利を侵害するおそれがある。誰もが納得できる事例だ。その例外的な規定を「法律で義務付けられている行政行為をしたかどうか」を記した公文書の開示請求に対して適用したのである。
「苦し紛れの支離滅裂な不開示処分」と言わざるを得ない。そうせざるを得ない、何か特別な事情があるのだろう。
裁判を二つも起こすのは大変だ。そこで、知事の諮問機関である県情報公開・個人情報保護審査会に「存否応答拒否は不当なので取り消しを求める」と審査を申し立てた。1年8カ月経って、その答申が7月17日にようやく出された。
審査会は法律の専門家で構成されている。審査したメンバーも県の処分にあきれたのだろう。「県の存否応答拒否の決定を取り消す」と記したうえで、次のように苦言を呈した。
「本事案について示された、存否を明らかにしないで開示をしない旨を決定した理由は、甚だ不十分であると言わざるを得ず、(中略)そもそも不開示決定にあたり、慎重かつ十分な検討が尽くされたのか疑問が残る」
審査会のメンバーは県が選ぶ。内規には「答申を尊重して対応する」とある。吉村知事は答申に沿って、そもそもそういう文書があるかどうかまず明らかにしたうえで、どのように対処するか決めるべきである。
とはいえ、吉村知事はそんな潔い政治家ではない。記者会見で対応を問われると、「(これから)裁決に向けた手続きを進めていくので、この段階で所感を申し上げることは差し控えたい」と逃げた。「答申を尊重する」という言葉はついに出なかった。
山形県の公式サイトの「知事室」というコーナーに、記者会見の様子を撮影した動画がアップされている。役人が用意した文章を棒読みし、想定外の質問が出るとオロオロする様子が映っている。
山形県の知事は、情報公開という重要な問題について自分の頭で考え、自分の言葉で語ることができない。悲しい政治家だ。
*メールマガジン「風切通信 77」 2020年8月20日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年8月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪山形県情報公開・個人情報保護審査会の答申全文 2020年7月17日≫
≪写真説明≫
地域月刊誌『素晴らしい山形』2020年8月号の表紙のイラスト
人物は山形県の吉村美栄子知事と義理のいとこ吉村和文氏

義理のいとこ、吉村和文氏が理事長を務める学校法人東海山形学園から、同じく和文氏が社長をしているダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資が行われた問題をめぐる対応は、その典型である。
学校法人が民間企業から金を借りたのなら、まだ分かる。が、その反対だ。国や県から毎年3億円もの私学助成を受け取っている学校法人が、2016年3月にグループ企業にその1割に相当する金を貸してあげた、というからあきれる。
この融資については、ダイバーシティメディアの公式サイトに決算公告がアップされており、その貸借対照表に明記してある。いわば「周知の事実」なのだが、念のため、学校法人の財務書類でも確認したいと考え、私は山形県が保有する財務書類を情報公開するよう求めた。すんなり出てくる、と思っていた。
ところが、県は財務書類の詳細な部分を白く塗りつぶして開示してきた(一部不開示)。理由は「法人の内部管理に関する情報であって、開示することにより法人の正当な利益を害するおそれがあるため」(県情報公開条例第6条)というものだった。
県の言い分をもう少し丁寧に紹介する。学校法人の財務書類が全面的に明らかにされれば、学校経営の秘密やノウハウが他の高校の関係者の知るところとなり、その学校の競争力を損ね、利益を大きく害することも十分に考えられる、というものだ。
貸借対照表などの財務書類がどういうものか、まるで理解していない空理空論である。一部上場企業は、そうした財務書類を公開することが法的に義務付けられている。それによって「ライバル企業から秘密やノウハウを盗まれ、損をした」などという話は聞いたこともない。財務書類とはそもそも、そうしたことが生じるようなものではないからだ。
「こんな理屈は通るはずがない」と思ったが、それが甘かった。裁判に訴え、「情報不開示処分の取り消し」を求めたところ、山形地方裁判所の裁判官は県の言い分を認めてしまった。「世の中には浮世離れした人もいる」ということを忘れていた。
脇を固めて論理を練り直し、仙台高等裁判所に控訴した。その顚末(てんまつ)はこのサイトの2020年5月1日付のコラムで詳しく紹介したので省くが、仙台高裁の裁判官は今年の3月、県側の主張を一蹴し、財務書類を全面的に開示するよう命じた。
財務書類とはどういうものか。公共性の高い学校法人はどのような説明責任を果たすべきか。情報公開制度はどのような意義を持っているのか。こちらの主張を全面的に認める逆転判決だった。
けれども、吉村知事はそれでへこたれるような政治家ではない。仙台高裁のまっとうな判決に背を向け、すぐさま最高裁判所に上告した。未来に向けて、情報公開制度をどうやって充実したものにしていくのか、といったことにはまるで関心がないようだ。
もう一つの情報不開示は、もっとひどい。
同じ人物が代表を務める会社と法人の間で金の貸し借りをするのは「利益相反行為」になる。一方が得をすれば、もう一方は損をする関係にあるからだ。私立学校法はこうした場合、不正が起きないよう、所轄庁(山形県)は利害関係のない第三者を特別代理人に選んでチェックさせなさい、と規定していた。
そこで、山形県は法律で義務付けられていることを実際に行ったのか、それを知るために特別代理人の選任に関する公文書の開示を請求した。すると、「そういう文書があるかどうかも言えない」と回答してきた(2018年10月23日付)。
「存否(そんぴ)応答拒否」という対応だ。文書を白塗りにして隠すより、もっとこずるい情報隠しだ。理由は、前回と同じく「法人の正当な利益を害するおそれがあるから」である。
確かに、山形県情報公開条例には存否応答拒否もできる、と書いてある。けれども、それは「個人の措置入院に関する文書」や「生活保護の申請書類」「特定企業の開発・投資計画」などが情報公開請求の対象になった場合だ。
こうしたケースでは、それに関する公文書があることを明らかにしただけで、個人や企業の権利を侵害するおそれがある。誰もが納得できる事例だ。その例外的な規定を「法律で義務付けられている行政行為をしたかどうか」を記した公文書の開示請求に対して適用したのである。
「苦し紛れの支離滅裂な不開示処分」と言わざるを得ない。そうせざるを得ない、何か特別な事情があるのだろう。
裁判を二つも起こすのは大変だ。そこで、知事の諮問機関である県情報公開・個人情報保護審査会に「存否応答拒否は不当なので取り消しを求める」と審査を申し立てた。1年8カ月経って、その答申が7月17日にようやく出された。
審査会は法律の専門家で構成されている。審査したメンバーも県の処分にあきれたのだろう。「県の存否応答拒否の決定を取り消す」と記したうえで、次のように苦言を呈した。
「本事案について示された、存否を明らかにしないで開示をしない旨を決定した理由は、甚だ不十分であると言わざるを得ず、(中略)そもそも不開示決定にあたり、慎重かつ十分な検討が尽くされたのか疑問が残る」
審査会のメンバーは県が選ぶ。内規には「答申を尊重して対応する」とある。吉村知事は答申に沿って、そもそもそういう文書があるかどうかまず明らかにしたうえで、どのように対処するか決めるべきである。
とはいえ、吉村知事はそんな潔い政治家ではない。記者会見で対応を問われると、「(これから)裁決に向けた手続きを進めていくので、この段階で所感を申し上げることは差し控えたい」と逃げた。「答申を尊重する」という言葉はついに出なかった。
山形県の公式サイトの「知事室」というコーナーに、記者会見の様子を撮影した動画がアップされている。役人が用意した文章を棒読みし、想定外の質問が出るとオロオロする様子が映っている。
山形県の知事は、情報公開という重要な問題について自分の頭で考え、自分の言葉で語ることができない。悲しい政治家だ。
*メールマガジン「風切通信 77」 2020年8月20日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年8月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪山形県情報公開・個人情報保護審査会の答申全文 2020年7月17日≫
≪写真説明≫
地域月刊誌『素晴らしい山形』2020年8月号の表紙のイラスト
人物は山形県の吉村美栄子知事と義理のいとこ吉村和文氏
私は1978年に朝日新聞社に入り、最初の10年余りを静岡と横浜、東京、札幌の4カ所で記者として過ごした。この時期、日本の経済は活力に満ちていた。

鉄鋼業と造船業は世界のトップクラスになり、トヨタや本田は自動車の本場、アメリカで米国製を上回る人気を得つつあった。当時、「産業のコメ」と呼ばれた半導体の生産でも、日本は先頭を走っていた。
ニューヨークのマンハッタン中心部にあるロックフェラー・センタービルを三菱地所が1200億円で買収、松下電器はハリウッドのユニバーサル・スタジオを7800億円で手に入れた。日本経済の絶頂期だった。
なぜ、アメリカは凋落したのか。日本が成功したのはなぜか。
ハーバード大学のエズラ・ヴォ―ゲル教授(社会学)は、日本の政治と経済、社会の構造をつぶさに分析し、『ジャパン アズ ナンバーワン』という本を世に送り出した。副題は「アメリカへの教訓」。1979年のことである。
ヴォ―ゲル氏はこの著書で、日本人の組織運営の巧みさや知識欲の旺盛さ、教育水準の高さなどに加えて、日本独特の高級官僚制度を詳しく紹介し、エリート官僚集団が果たした役割を極めて高く評価している。
「日本で政治的決断を下すグループは二つある。一つは総理大臣をはじめ各大臣を含む政治家グループ。もう一つは高級官僚のグループである。各省庁の重要な実務は政治家ではなく、官僚自身の手によってなされる」
「彼らの給料は年功序列に基づいて上がっていくが、民間企業の同輩に比べると額は少ない。オフィスも質素だし、特別手当の額も少ないが、彼らは自分たちが重要な問題を扱っていることを十分に意識しているし、それをうまく処理することに大きな誇りを感じている」
「彼らは献身的であり、集団としての使命感が彼らを結び付けている」とも記している。経済政策や貿易交渉で高級官僚が果たした役割は確かに大きかった。日本の企業を取りまとめ、牽引し、世界の市場を切り拓いていった。
ヴォ―ゲル氏は、日本企業の組織運営や官僚制度、教育や福祉のあり方から教訓を引き出し、「アメリカの再生に活かさなければならない」と説いた。
そうした日本の優れた制度が壁に突き当たり、むしろ裏目に出始めたのはいつからか。私は「1989年が分岐点だった」と考えている。日本中がバブル景気に沸き立っていた頃だ。
この年の秋、東欧の国々で人々が自由を求めて動き始め、社会主義体制が次々に倒れていった。11月には東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が崩壊、12月にはソ連のゴルバチョフ書記長とブッシュ米大統領がマルタ島で会談し、冷戦の終結を宣言した。2年後にはソ連そのものが瓦解した。
この1989年の初めに、私は国際報道部門に異動になり、激流に投げ込まれるような経験を重ねた。日本がバブルに浮かれている間に、世界の構造はがらりと変わってしまった。
情報技術(IT)の世界でも、この前後に大変革が起きた。ITの巨人IBMが主役の座から滑り落ち、マイクロソフトが取って代わったのだ。
パソコンの性能が向上し、これに合わせてマイクロソフトはウィンドウズという使い勝手の良いソフトを開発して大々的に売り出した。大型コンピューターを中心にして端末をピラミッド状に配置する大規模集中処理システムから、パソコンを連結して対応する個別分散処理システムへ。ITの世界でも、パラダイム(基本的な枠組み)シフトが起きた。
1990年代、日本はバブルが弾け、銀行や証券会社の倒産が相次いで金融危機の始末に追われた。国内のゴタゴタに振り回されて世界の激変に対応するのが遅れ、時は虚しく流れた。識者は「失われた10年」と言う。
それが巡り巡って、どんな悲惨な結果をもたらすか。私たちは、今回の新型コロナウイルス禍でまざまざと見ることになった。
厚生労働省は豪華クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号での感染を封じ込めることに失敗した。加えて、自らの傘下にある国立感染症研究所と地方の衛生研究所を使ってPCR検査を実施することにこだわり、いつまで経っても検査体制を拡充することができなかった。海外の最新検査機器を導入して国民のために活用するより、自分たちの権益を守ることに固執したからだ。
安倍晋三首相は窮屈そうなマスクを着け、それを国民に配ることにこだわり続けた。感染の勢いが収まり、マスクが店頭に並ぶ頃にやっと届く始末。
外出や営業の自粛で苦しむ人々への支援策を盛り込んだ補正予算の執行は、もっとひどかった。第一次補正予算が25兆6914億円、第二次補正予算が31兆9114億円。首相は「空前絶後、世界最大規模」と胸を張ったが、財源はすべて借金だ。
官僚たちにはそれをきちんと配る力がない。中央省庁のIT環境は民間に比べ、ひどく遅れている。膨大なデータを処理するシステムもノウハウもない。結果、民間に丸投げした。
丸投げしても、その手続きが適正で税金がちゃんと国民の手元に届くのならまだ我慢できる。だが、持続化給付金をめぐる経済産業省の仕事のでたらめぶりはすさまじいものだった。
コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主に最大200万円を給付するこの事業を受注したのは「サービスデザイン推進協議会」という一般社団法人だ。
この法人の実態を最初に暴いたのは週刊文春である。記者が東京・築地にあるこの法人の事務所を訪ね、「入り口にカギがかかっている。連絡先の電話番号もない。法律で義務付けられている決算公告を一度も出していない。幽霊法人だ」と報じた(6月4日号)。
2016年にこの法人を作ったのは広告最大手の電通と人材派遣のパソナ、IT業務の外注を請け負うトランスコスモスである。政府の事業を直接受注し、公金を電通の口座から振り込むのは案配が悪い。そこで、トンネル法人を経由させる手法を編み出したようだ。
法人の初代代表理事、赤池学氏(評論家)も、次の代表理事の笠原英一氏(立教大学客員教授)もメディアの取材に「私はお飾り。実務のことは分かりません」と答えている。正直ではあるが、無責任な人たちだ。
この法人が持続化給付金の事業を769億円で受注、そこから20億円を中抜きして電通に749億円で再委託、さらに電通の子会社やパソナなどに再々委託していた(図1参照)。法人の事務所がある築地は、電通の本社がある汐留から歩いて数分だ。
要するに、仕事のできない経済産業省に代わって民間企業が請け負い、たっぷりと甘い汁を吸っているのである。どんな汁を吸ってきたのか。朝日新聞が6月2日付で一覧表を載せている。図2に見るように、最初は「おもてなし規格認証事業」なるものから始め、IT絡みの事業を次々に受注してきた。
コロナ禍は「格好のビジネスチャンス」となった。電通グループは持続化給付金に続いて、経済産業省が主導する「Go To キャンペーン」も取るつもりだったようだ。「コロナが収まったら観光や外食に行きましょう。政府がその費用を補助します」という事業だ。
こちらは事業規模1兆6794億円、委託費は3095億円と、持続化給付金よりはるかにおいしい。
経済産業省はこの事業の説明会を6月1日に行い、8日に公募を締め切る段取りだった。本誌の昨年2月号で山形県が観光キャンペーンを企画し、吉村美栄子知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いるケーブルテレビ山形(現ダイバーシティメディア)に業務委託した経緯をお伝えしたが、それと同じ手口だ。
公平さを装って募集はするものの、委託する業者はあらかじめ決めている。募集期間を短くして競争相手が対応できないようにしてしまうのだ(山形県の場合はさらに業務の仕様にも細工を施した)。なりふり構わず突き進む役人のやり口は、国も県も変わらない。
その実態がメディアで暴露されるに至り、さすがに「Go To キャンペーン」の公募は仕切り直しになった。
持続化給付金にしろ、このキャンペーンにしろ、経済産業省の官僚たちの仕事ぶりは、ヴォ―ゲル教授が描いた官僚の姿からはかけ離れている。「国家の将来を見据えて考え、行動する」といった誇りはかけらも感じられない。見えてくるのは「税金の使い方は俺たちが好きなように決める」という思い上がりだけだ。
そうした官僚の典型が経済産業省の中小企業庁長官、前田泰宏氏である。アメリカのテキサスで開かれる大規模な見本市のたびに、シェアハウスを借りて「前田ハウス」と称し、民間企業の幹部たちと親しく交わっていた。
その中に、「サービスデザイン推進協議会」の設立で中心的な役割を果たした元電通幹部の平川健司氏もいた。「前田ハウス」問題は、経済産業省と電通の癒着の象徴と言える。日本では目立つことはできないが、「遠いテキサスなら平気だろう」と考えたようだ。その実態を写真付きで詳細に暴いたのも週刊文春の記者たちである(6月18日号)。
奥歯に物が挟まったような書き方ではなく、核心にズバリと切り込み、実名で赤裸々に書いていく。ここ数年の週刊文春の報道は秀逸だ。新聞各紙も「週刊文春によると」と書いて引用するようになった。かつては「一部報道によると」といった表現しか使おうとしなかったが、彼我の取材力の差を認めざるを得なくなったのだろう。
週刊新潮にも、たまに興味深い記事が載る。6月25日号に「Go To キャンペーンも食い物にする『パソナ』の政治家饗宴リスト」という記事があった。
コロナ対策の補正予算事業を電通と一緒になって貪(むさぼ)る人材派遣のパソナは、東京・元麻布の高級住宅街に「仁風林(にんぷうりん)」なるゲストハウスを構えている。ここに政治家や経済産業省の幹部、有名人らを招いて夜な夜なパーティーを繰り広げ、もてなしているのだとか。
接待するのはパソナの南部靖之代表の「美人秘書軍団」。歌手のASKAが覚醒剤取締法違反で逮捕された際、一緒に逮捕された愛人もこの秘書軍団の一人で、ここでのパーティーで知り合ったという。
招待された政治家のリストも興味深かったが、そのパソナの現在の会長は小泉政権で経済財政担当相を務めた竹中平蔵氏である、という記述に私は目をむいた。担当大臣として派遣労働を製造業にまで拡大した、その張本人が人材派遣会社の会長に収まっていたとは・・・・。
これまで本誌で、吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏の政商ぶりを報じてきたが、そうした構図を何百倍、何千倍にしたスケールで政府の公金を貪る政商が東京にはゴロゴロいる。電通やパソナは「政商たちの巣窟(そうくつ)」であり、安倍政権はとてつもなく気前のいいスポンサーと言うべきか。
世界の流れに乗り遅れ、日本の政治と行政のシステム、産業構造は根元から揺らぎ始めている。救いは、私たちの国には自分の仕事に誇りを持ち、自らの務めを誠実に果たそうとする人がまだたくさんいることだ。
新型コロナウイルスの感染が広がり、政府が右往左往しても、亡くなった人を現在のレベルで抑えられているのは、そういう人たちが医療や介護などそれぞれの現場で踏ん張ってくれているからだろう。
「失われた10年」を取り戻すことはできない。けれども、そういう人たちがいる限り、苦難を乗り越え、新しい道を切り拓くことはできる。私たちの社会にはまだその力がある、と信じたい。
*メールマガジン「風切通信 76」 2020年6月29日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年7月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎電通との関係について国会で答弁する前田泰宏・中小企業庁長官
https://gogotamu2019.blog.fc2.com/blog-entry-11668.html

鉄鋼業と造船業は世界のトップクラスになり、トヨタや本田は自動車の本場、アメリカで米国製を上回る人気を得つつあった。当時、「産業のコメ」と呼ばれた半導体の生産でも、日本は先頭を走っていた。
ニューヨークのマンハッタン中心部にあるロックフェラー・センタービルを三菱地所が1200億円で買収、松下電器はハリウッドのユニバーサル・スタジオを7800億円で手に入れた。日本経済の絶頂期だった。
なぜ、アメリカは凋落したのか。日本が成功したのはなぜか。
ハーバード大学のエズラ・ヴォ―ゲル教授(社会学)は、日本の政治と経済、社会の構造をつぶさに分析し、『ジャパン アズ ナンバーワン』という本を世に送り出した。副題は「アメリカへの教訓」。1979年のことである。
ヴォ―ゲル氏はこの著書で、日本人の組織運営の巧みさや知識欲の旺盛さ、教育水準の高さなどに加えて、日本独特の高級官僚制度を詳しく紹介し、エリート官僚集団が果たした役割を極めて高く評価している。
「日本で政治的決断を下すグループは二つある。一つは総理大臣をはじめ各大臣を含む政治家グループ。もう一つは高級官僚のグループである。各省庁の重要な実務は政治家ではなく、官僚自身の手によってなされる」
「彼らの給料は年功序列に基づいて上がっていくが、民間企業の同輩に比べると額は少ない。オフィスも質素だし、特別手当の額も少ないが、彼らは自分たちが重要な問題を扱っていることを十分に意識しているし、それをうまく処理することに大きな誇りを感じている」
「彼らは献身的であり、集団としての使命感が彼らを結び付けている」とも記している。経済政策や貿易交渉で高級官僚が果たした役割は確かに大きかった。日本の企業を取りまとめ、牽引し、世界の市場を切り拓いていった。
ヴォ―ゲル氏は、日本企業の組織運営や官僚制度、教育や福祉のあり方から教訓を引き出し、「アメリカの再生に活かさなければならない」と説いた。
そうした日本の優れた制度が壁に突き当たり、むしろ裏目に出始めたのはいつからか。私は「1989年が分岐点だった」と考えている。日本中がバブル景気に沸き立っていた頃だ。
この年の秋、東欧の国々で人々が自由を求めて動き始め、社会主義体制が次々に倒れていった。11月には東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が崩壊、12月にはソ連のゴルバチョフ書記長とブッシュ米大統領がマルタ島で会談し、冷戦の終結を宣言した。2年後にはソ連そのものが瓦解した。
この1989年の初めに、私は国際報道部門に異動になり、激流に投げ込まれるような経験を重ねた。日本がバブルに浮かれている間に、世界の構造はがらりと変わってしまった。
情報技術(IT)の世界でも、この前後に大変革が起きた。ITの巨人IBMが主役の座から滑り落ち、マイクロソフトが取って代わったのだ。
パソコンの性能が向上し、これに合わせてマイクロソフトはウィンドウズという使い勝手の良いソフトを開発して大々的に売り出した。大型コンピューターを中心にして端末をピラミッド状に配置する大規模集中処理システムから、パソコンを連結して対応する個別分散処理システムへ。ITの世界でも、パラダイム(基本的な枠組み)シフトが起きた。
1990年代、日本はバブルが弾け、銀行や証券会社の倒産が相次いで金融危機の始末に追われた。国内のゴタゴタに振り回されて世界の激変に対応するのが遅れ、時は虚しく流れた。識者は「失われた10年」と言う。
それが巡り巡って、どんな悲惨な結果をもたらすか。私たちは、今回の新型コロナウイルス禍でまざまざと見ることになった。
厚生労働省は豪華クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号での感染を封じ込めることに失敗した。加えて、自らの傘下にある国立感染症研究所と地方の衛生研究所を使ってPCR検査を実施することにこだわり、いつまで経っても検査体制を拡充することができなかった。海外の最新検査機器を導入して国民のために活用するより、自分たちの権益を守ることに固執したからだ。
安倍晋三首相は窮屈そうなマスクを着け、それを国民に配ることにこだわり続けた。感染の勢いが収まり、マスクが店頭に並ぶ頃にやっと届く始末。
外出や営業の自粛で苦しむ人々への支援策を盛り込んだ補正予算の執行は、もっとひどかった。第一次補正予算が25兆6914億円、第二次補正予算が31兆9114億円。首相は「空前絶後、世界最大規模」と胸を張ったが、財源はすべて借金だ。
官僚たちにはそれをきちんと配る力がない。中央省庁のIT環境は民間に比べ、ひどく遅れている。膨大なデータを処理するシステムもノウハウもない。結果、民間に丸投げした。
丸投げしても、その手続きが適正で税金がちゃんと国民の手元に届くのならまだ我慢できる。だが、持続化給付金をめぐる経済産業省の仕事のでたらめぶりはすさまじいものだった。
コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主に最大200万円を給付するこの事業を受注したのは「サービスデザイン推進協議会」という一般社団法人だ。
この法人の実態を最初に暴いたのは週刊文春である。記者が東京・築地にあるこの法人の事務所を訪ね、「入り口にカギがかかっている。連絡先の電話番号もない。法律で義務付けられている決算公告を一度も出していない。幽霊法人だ」と報じた(6月4日号)。
2016年にこの法人を作ったのは広告最大手の電通と人材派遣のパソナ、IT業務の外注を請け負うトランスコスモスである。政府の事業を直接受注し、公金を電通の口座から振り込むのは案配が悪い。そこで、トンネル法人を経由させる手法を編み出したようだ。
法人の初代代表理事、赤池学氏(評論家)も、次の代表理事の笠原英一氏(立教大学客員教授)もメディアの取材に「私はお飾り。実務のことは分かりません」と答えている。正直ではあるが、無責任な人たちだ。
この法人が持続化給付金の事業を769億円で受注、そこから20億円を中抜きして電通に749億円で再委託、さらに電通の子会社やパソナなどに再々委託していた(図1参照)。法人の事務所がある築地は、電通の本社がある汐留から歩いて数分だ。
要するに、仕事のできない経済産業省に代わって民間企業が請け負い、たっぷりと甘い汁を吸っているのである。どんな汁を吸ってきたのか。朝日新聞が6月2日付で一覧表を載せている。図2に見るように、最初は「おもてなし規格認証事業」なるものから始め、IT絡みの事業を次々に受注してきた。
コロナ禍は「格好のビジネスチャンス」となった。電通グループは持続化給付金に続いて、経済産業省が主導する「Go To キャンペーン」も取るつもりだったようだ。「コロナが収まったら観光や外食に行きましょう。政府がその費用を補助します」という事業だ。
こちらは事業規模1兆6794億円、委託費は3095億円と、持続化給付金よりはるかにおいしい。
経済産業省はこの事業の説明会を6月1日に行い、8日に公募を締め切る段取りだった。本誌の昨年2月号で山形県が観光キャンペーンを企画し、吉村美栄子知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いるケーブルテレビ山形(現ダイバーシティメディア)に業務委託した経緯をお伝えしたが、それと同じ手口だ。
公平さを装って募集はするものの、委託する業者はあらかじめ決めている。募集期間を短くして競争相手が対応できないようにしてしまうのだ(山形県の場合はさらに業務の仕様にも細工を施した)。なりふり構わず突き進む役人のやり口は、国も県も変わらない。
その実態がメディアで暴露されるに至り、さすがに「Go To キャンペーン」の公募は仕切り直しになった。
持続化給付金にしろ、このキャンペーンにしろ、経済産業省の官僚たちの仕事ぶりは、ヴォ―ゲル教授が描いた官僚の姿からはかけ離れている。「国家の将来を見据えて考え、行動する」といった誇りはかけらも感じられない。見えてくるのは「税金の使い方は俺たちが好きなように決める」という思い上がりだけだ。
そうした官僚の典型が経済産業省の中小企業庁長官、前田泰宏氏である。アメリカのテキサスで開かれる大規模な見本市のたびに、シェアハウスを借りて「前田ハウス」と称し、民間企業の幹部たちと親しく交わっていた。
その中に、「サービスデザイン推進協議会」の設立で中心的な役割を果たした元電通幹部の平川健司氏もいた。「前田ハウス」問題は、経済産業省と電通の癒着の象徴と言える。日本では目立つことはできないが、「遠いテキサスなら平気だろう」と考えたようだ。その実態を写真付きで詳細に暴いたのも週刊文春の記者たちである(6月18日号)。
奥歯に物が挟まったような書き方ではなく、核心にズバリと切り込み、実名で赤裸々に書いていく。ここ数年の週刊文春の報道は秀逸だ。新聞各紙も「週刊文春によると」と書いて引用するようになった。かつては「一部報道によると」といった表現しか使おうとしなかったが、彼我の取材力の差を認めざるを得なくなったのだろう。
週刊新潮にも、たまに興味深い記事が載る。6月25日号に「Go To キャンペーンも食い物にする『パソナ』の政治家饗宴リスト」という記事があった。
コロナ対策の補正予算事業を電通と一緒になって貪(むさぼ)る人材派遣のパソナは、東京・元麻布の高級住宅街に「仁風林(にんぷうりん)」なるゲストハウスを構えている。ここに政治家や経済産業省の幹部、有名人らを招いて夜な夜なパーティーを繰り広げ、もてなしているのだとか。
接待するのはパソナの南部靖之代表の「美人秘書軍団」。歌手のASKAが覚醒剤取締法違反で逮捕された際、一緒に逮捕された愛人もこの秘書軍団の一人で、ここでのパーティーで知り合ったという。
招待された政治家のリストも興味深かったが、そのパソナの現在の会長は小泉政権で経済財政担当相を務めた竹中平蔵氏である、という記述に私は目をむいた。担当大臣として派遣労働を製造業にまで拡大した、その張本人が人材派遣会社の会長に収まっていたとは・・・・。
これまで本誌で、吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏の政商ぶりを報じてきたが、そうした構図を何百倍、何千倍にしたスケールで政府の公金を貪る政商が東京にはゴロゴロいる。電通やパソナは「政商たちの巣窟(そうくつ)」であり、安倍政権はとてつもなく気前のいいスポンサーと言うべきか。
世界の流れに乗り遅れ、日本の政治と行政のシステム、産業構造は根元から揺らぎ始めている。救いは、私たちの国には自分の仕事に誇りを持ち、自らの務めを誠実に果たそうとする人がまだたくさんいることだ。
新型コロナウイルスの感染が広がり、政府が右往左往しても、亡くなった人を現在のレベルで抑えられているのは、そういう人たちが医療や介護などそれぞれの現場で踏ん張ってくれているからだろう。
「失われた10年」を取り戻すことはできない。けれども、そういう人たちがいる限り、苦難を乗り越え、新しい道を切り拓くことはできる。私たちの社会にはまだその力がある、と信じたい。
*メールマガジン「風切通信 76」 2020年6月29日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年7月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎電通との関係について国会で答弁する前田泰宏・中小企業庁長官
https://gogotamu2019.blog.fc2.com/blog-entry-11668.html
第8回最上川縦断カヌー探訪を7月25日(土)に予定通り開催します。
東京や大阪で新型コロナウイルスの感染がまた広がり始め、心配される状況ですが、「3密」の状況を作らないように十分に気を付け、川下りを楽しむ予定です。出発前に参加予定者の検温を実施し、マイクロバスでの移動の際にはマスクの着用をお願いします。
参加予定者は46人です。山形県内が26人、県外が20人。最年少は7歳、最ベテランは79歳です。
東京や大阪で新型コロナウイルスの感染がまた広がり始め、心配される状況ですが、「3密」の状況を作らないように十分に気を付け、川下りを楽しむ予定です。出発前に参加予定者の検温を実施し、マイクロバスでの移動の際にはマスクの着用をお願いします。
参加予定者は46人です。山形県内が26人、県外が20人。最年少は7歳、最ベテランは79歳です。
大きなニュースがあれば、小さなニュースは吹き飛ばされてしまう。切ないけれども、それは避けられないことだ。
新聞の紙面には限りがある。テレビニュースにも時間の枠がある。新型コロナウイルスのような大きなニュースがあれば、ほかのことが入り込む余地は極端に少なくなる。取材する記者も「コロナ関連の話題」を追って走り回る。
そのあおりで影が薄くなってしまった県内ニュースの一つに、自民党の「次期知事選挙の候補者選び」がある。
山形県の吉村美栄子知事は2009年に自民党が支援する現職を破って初当選した。その後は無投票で再選、さらに三選された。政権党にとって、とりわけ保守基盤が厚い山形の自民党にとってつらいことである。このままズルズルと四選を許すのか。県民の関心は高い。
昨年9月、自民党県連の会長に就任した加藤鮎子衆院議員は「(3度目の)不戦敗はあり得ない」と述べ、2021年1月の知事選では独自候補を擁立する方針を明らかにした。「候補者は公募で決める」と宣言し、今年の2月末締め切りで候補者を募った。
山形市選出の大内理加(りか)県議がまず、名乗りを上げた。続いて、山形市出身で国土交通省から復興庁に転じた官僚の伊藤洋(よう)氏も意欲を示した。この頃までは、メディアも2人の経歴などを丁寧に報じていた。
ところが、3月末に山形県内でも新型コロナの感染者が確認されるや、報道は「コロナ一色」に染まっていった。公募に応じた2人による討論会を開くこともできない。暮らしや経済への影響が大きく、外出自粛が続く中ではやむを得ないことだった。
この間、実は深刻なことが進行していた。事情通によれば、知事選の公募に応じた2人について自民党本部が「身体検査」を実施したところ、片方は「候補者として不適格」という判定が下されていたのだ。
自民党の「身体検査」の主な判定基準は二つ、金と色、である。政治資金や資産についてはどちらも問題はなかったが、伊藤氏は2番目のハードルをクリアできなかったという。さまざまな噂が飛び交っているものの、確たることは分からない。
いずれにしても、3月下旬には「伊藤氏は降りる」という方向が固まっていた。山形新聞が「伊藤氏、公募申請を取り下げ」と短く報じたのは4月11日。本人が自民党県連の加藤鮎子会長あてに「一身上の都合で辞退する」と届け出た、という内容だった。
取材した記者は舞台裏で飛び交った話をたくさん聞いているはずなのに、1行も書いていない。「裏付ける証拠がないから」と言い訳するのだろうが、こんな書き方しかしないから「新聞離れ」が進むのではないか。
少なくとも、自民党本部の調査によって伊藤氏に「一身上の都合」が生じたこと、その結果、公募申請の取り下げに追い込まれたことが分かるように書くべきだろう。
伊藤氏が辞退したため、自民党は身内の大内理加氏を知事候補にかついで戦うしかなくなった。「選挙にめっぽう強い女性県議」ではあるが、それは選挙区の山形市内でのこと。米沢や鶴岡、酒田には何の足場もない。
「吉村知事の人気は高く、支持基盤も厚い。四選出馬を決めれば、大内氏に勝ち目はない」という観測がもっぱらだ。先読みが得意な人は「彼女の狙いは次の参院選ではないか。たとえ知事選で敗れても、有力候補として名乗り出ることができる」と見る。確かに、自民党県連は「次の参院選の候補者」のめどが立たず、窮している。
肝心の吉村知事はまだ、去就を明らかにしていない。山形新聞が「四選出馬についてどう考えているか」と水を向けても、「期待する声が大きくなってきている。大変ありがたいことだと思う。しかし、今はしっかりと県政にまい進することが私の最大の役割で使命」と受け流している(2月3日付の記事)。余裕しゃくしゃく、である。
山形県の自民党にとって、知事選はずっと「紛糾の種」になってきた。
2005年の知事選では、自民党県議の多くが現職で四選を目指す高橋和雄知事を推したのに、高橋氏とそりが合わない加藤紘一衆院議員は日銀出身の斎藤弘氏を担ぎ出して争った。
分裂選挙の結果は、4千票余りの僅差で斎藤氏の勝利。現職の高橋氏が74歳と高齢だったこと、それに「笹かまぼこ事件」が響いたとされる。高橋氏が不在の折にゼネコン大手の幹部が2000万円の現金入りの笹かまぼこを知事室に置いていった事件である。高橋氏はすぐに返したが、「金権体質の現れ」と攻撃され、打撃を受けた。
この時の遺恨(いこん)が2009年の知事選に影を落とした。民主党や社民党が担いだ吉村美栄子氏を高橋陣営や岸宏一参院議員、一部の自民党県議が応援したのだ。自民党は再び分裂状態に陥り、吉村美栄子氏は1万票余りの差で現職の斎藤氏を破り、知事の座を射止めた。
加藤紘一氏は2005年の知事選では「産婆役」として、2009年には「墓掘り人」としての役割を果たした。そしてさらに、吉村知事の無投票再選に終わった2013年の知事選でもキーマンになった。
その前年、2012年に加藤氏は健康を害し、歩くのも困難な状態のまま12月の総選挙に臨み、同じ自民党系の阿部寿一氏(元酒田市長)に敗れた。自らの選挙区で保守分裂の選挙を繰り広げたうえ、高齢のため比例東北ブロックでの重複立候補も認められず、比例復活で議席を確保することもできなかった。
かつて、自民党の名門派閥「宏池会」のプリンスと呼ばれ、一時は有力な首相候補でもあった加藤氏の惨めな敗戦に、自民党県連は混乱状態に陥る。年明けにあった知事選には候補者を立てることもできず、吉村美栄子氏に再選を許す結果になった。
意地の悪い見方をすれば、加藤紘一氏こそ「吉村知事誕生の伏線を張った功労者」であり、「2013年の無投票再選の立役者」と言える。
自民党県連の元会長、遠藤利明衆院議員も「吉村県政への貢献度」では、加藤氏に引けを取らない。
2016年夏の参院選で、遠藤氏はJA全農山形出身の月野薫氏を自民党の候補者として担ぎ出した。当時の最大の争点はTPP(環太平洋パートナーシップ協定)に反対か否か。対立候補の元参院議員、舟山康江氏は強硬な反対論者で農民の支持を集めていた。
遠藤氏は「全農出身の候補者を立てれば農協票は割れ、それに頼る舟山陣営を切り崩すことができる」と踏んで、月野氏を擁立したようだが、肝心の候補者本人に魅力が乏しかった。結果は12万票の大差での敗北。遠藤氏はその敗戦処理に追われ、翌2017年の知事選対策どころではなくなった。
結局、吉村知事に挑戦する者は現れず、無投票での三選を許した。遠藤氏の選挙下手のおかげ、と言うべきだろう。ちなみに、今回、知事候補の公募に応じた伊藤洋氏を引っ張ってきたのも遠藤氏という。つくづく「人を見る目」がない。
遠藤氏は「フル規格の奥羽、羽越新幹線の建設」を唱えている。地元の山形新聞がキャンペーンを張り、吉村知事が力を入れている政策だ。これに後追いで乗っかった。フル規格の両新幹線建設構想が時代錯誤の政策で、実現の可能性がおよそないことは、すでに何度も書いた。「時代の流れを読む力もない」と言うべきだろう。
そもそも、山形県の自民党は本気で吉村県政を倒す気があるのだろうか。
吉村知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業・法人グループにはこの10年で40億円もの公金が流れ込んでいる(表再掲)。その詳細はこれまで、月刊『素晴らしい山形』で報じてきた通りだ。
もっとも多額の公金が支出されているのは、和文氏が理事長を務める学校法人、東海山形学園である。毎年3億円前後、多い年には10億円を超える私学助成が支給されている。なのに、その学校法人からグループの中核企業、ダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資が行われたりしている。学校法人の監督権限を持つ山形県はその内容を調べようともしない。
当方が独自に調べるため、学校法人の財務書類の情報公開を求めても、「当該法人の利益を害するおそれがある」との理由で肝心な部分を開示しない。「非開示は不当」と裁判に訴え、仙台高裁で開示を命じる判決が出ても、最高裁に上告して開示を引き延ばす。
吉村知事が観光キャンペーンを始めれば、県幹部が露骨な方法でグループ企業に業務委託をして潤わせる。その幹部が抜擢され、出世していく。知事が奥羽、羽越新幹線の建設を唱え始めれば、その関連業務もまたグループ企業に委託するーー。
中国の故事「瓜田(かでん)に履(くつ)を納(い)れず、李下に冠を正さず」に反するどころではない。吉村一族企業は、瓜(うり)畑にずかずかと入り込み、スモモの木の下にブルーシートを張って幹を揺さぶり、収穫して恥じるところがない。
次の知事選に本気で取り組もうとするなら、自民党はこうした問題を一つひとつ追及し、吉村知事の下で何が起きているのか、明らかにする必要がある。
長期県政による澱(よど)みを許さないように、知事の多選を制限する条例を制定することも考えられる。
2003年に東京都の杉並区が多選自粛条例を制定して以来、神奈川県が2007年に「知事は連続3期12年まで」との条例を作るなど、すでに先行例が多数ある。いったん制定した条例を廃止した自治体もあり、難しい面もあるが、山形県のように同じ人物が権力を握り続け、専横と腐敗を招いた歴史がある土地では試みる価値が十分にある。
県議会で過半数を握る自民党がその気になれば、すぐにでも制定できる条例だ。その条例を突き付けて、吉村知事の四選出馬を牽制することも考えられる。
要は、自分たちが住む土地をより良いものにするために、次の世代により良いものを残すために、何かを為す気概があるかどうかだ。その気概があるからこそ、政治を志したのではないのか。
吉村県政の1期目は新鮮だった。前任の斎藤知事の冷たい政策に凍えていた県民の心を包み込むような温かさも感じた。けれども、2期目以降、高い人気を背にして「おごり」が見え始めた。知事に当選した際のキャッチフレーズ「温かい県政」は、いつしか「身内と取り巻きに温かい県政」に転じていった。
救いがたいのは「時代の流れ」にあまりにも鈍感なことだ。情報技術(IT)革命が進み、変化のスピードが増しているのに、まったく対応できていない。山形県庁はいまだに「紙とハンコ」で仕事をしている。行政事務の電子決裁化はロードマップすらない。
トップに「このままでは時代に取り残されてしまう」という思いがないからだろう。フル規格の新幹線建設などという「20世紀の夢」を追い続ける人物に、次の4年を託すのは耐えがたい。私たちに続く世代は、21世紀の後半を生きなければならないのだから。
*メールマガジン「風切通信 75」 2020年5月31日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年6月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
*加藤紘一氏は2016年、岸宏一氏は2017年に死去。
新聞の紙面には限りがある。テレビニュースにも時間の枠がある。新型コロナウイルスのような大きなニュースがあれば、ほかのことが入り込む余地は極端に少なくなる。取材する記者も「コロナ関連の話題」を追って走り回る。
そのあおりで影が薄くなってしまった県内ニュースの一つに、自民党の「次期知事選挙の候補者選び」がある。
山形県の吉村美栄子知事は2009年に自民党が支援する現職を破って初当選した。その後は無投票で再選、さらに三選された。政権党にとって、とりわけ保守基盤が厚い山形の自民党にとってつらいことである。このままズルズルと四選を許すのか。県民の関心は高い。
昨年9月、自民党県連の会長に就任した加藤鮎子衆院議員は「(3度目の)不戦敗はあり得ない」と述べ、2021年1月の知事選では独自候補を擁立する方針を明らかにした。「候補者は公募で決める」と宣言し、今年の2月末締め切りで候補者を募った。
山形市選出の大内理加(りか)県議がまず、名乗りを上げた。続いて、山形市出身で国土交通省から復興庁に転じた官僚の伊藤洋(よう)氏も意欲を示した。この頃までは、メディアも2人の経歴などを丁寧に報じていた。
ところが、3月末に山形県内でも新型コロナの感染者が確認されるや、報道は「コロナ一色」に染まっていった。公募に応じた2人による討論会を開くこともできない。暮らしや経済への影響が大きく、外出自粛が続く中ではやむを得ないことだった。
この間、実は深刻なことが進行していた。事情通によれば、知事選の公募に応じた2人について自民党本部が「身体検査」を実施したところ、片方は「候補者として不適格」という判定が下されていたのだ。
自民党の「身体検査」の主な判定基準は二つ、金と色、である。政治資金や資産についてはどちらも問題はなかったが、伊藤氏は2番目のハードルをクリアできなかったという。さまざまな噂が飛び交っているものの、確たることは分からない。
いずれにしても、3月下旬には「伊藤氏は降りる」という方向が固まっていた。山形新聞が「伊藤氏、公募申請を取り下げ」と短く報じたのは4月11日。本人が自民党県連の加藤鮎子会長あてに「一身上の都合で辞退する」と届け出た、という内容だった。
取材した記者は舞台裏で飛び交った話をたくさん聞いているはずなのに、1行も書いていない。「裏付ける証拠がないから」と言い訳するのだろうが、こんな書き方しかしないから「新聞離れ」が進むのではないか。
少なくとも、自民党本部の調査によって伊藤氏に「一身上の都合」が生じたこと、その結果、公募申請の取り下げに追い込まれたことが分かるように書くべきだろう。
伊藤氏が辞退したため、自民党は身内の大内理加氏を知事候補にかついで戦うしかなくなった。「選挙にめっぽう強い女性県議」ではあるが、それは選挙区の山形市内でのこと。米沢や鶴岡、酒田には何の足場もない。
「吉村知事の人気は高く、支持基盤も厚い。四選出馬を決めれば、大内氏に勝ち目はない」という観測がもっぱらだ。先読みが得意な人は「彼女の狙いは次の参院選ではないか。たとえ知事選で敗れても、有力候補として名乗り出ることができる」と見る。確かに、自民党県連は「次の参院選の候補者」のめどが立たず、窮している。
肝心の吉村知事はまだ、去就を明らかにしていない。山形新聞が「四選出馬についてどう考えているか」と水を向けても、「期待する声が大きくなってきている。大変ありがたいことだと思う。しかし、今はしっかりと県政にまい進することが私の最大の役割で使命」と受け流している(2月3日付の記事)。余裕しゃくしゃく、である。
山形県の自民党にとって、知事選はずっと「紛糾の種」になってきた。
2005年の知事選では、自民党県議の多くが現職で四選を目指す高橋和雄知事を推したのに、高橋氏とそりが合わない加藤紘一衆院議員は日銀出身の斎藤弘氏を担ぎ出して争った。
分裂選挙の結果は、4千票余りの僅差で斎藤氏の勝利。現職の高橋氏が74歳と高齢だったこと、それに「笹かまぼこ事件」が響いたとされる。高橋氏が不在の折にゼネコン大手の幹部が2000万円の現金入りの笹かまぼこを知事室に置いていった事件である。高橋氏はすぐに返したが、「金権体質の現れ」と攻撃され、打撃を受けた。
この時の遺恨(いこん)が2009年の知事選に影を落とした。民主党や社民党が担いだ吉村美栄子氏を高橋陣営や岸宏一参院議員、一部の自民党県議が応援したのだ。自民党は再び分裂状態に陥り、吉村美栄子氏は1万票余りの差で現職の斎藤氏を破り、知事の座を射止めた。
加藤紘一氏は2005年の知事選では「産婆役」として、2009年には「墓掘り人」としての役割を果たした。そしてさらに、吉村知事の無投票再選に終わった2013年の知事選でもキーマンになった。
その前年、2012年に加藤氏は健康を害し、歩くのも困難な状態のまま12月の総選挙に臨み、同じ自民党系の阿部寿一氏(元酒田市長)に敗れた。自らの選挙区で保守分裂の選挙を繰り広げたうえ、高齢のため比例東北ブロックでの重複立候補も認められず、比例復活で議席を確保することもできなかった。
かつて、自民党の名門派閥「宏池会」のプリンスと呼ばれ、一時は有力な首相候補でもあった加藤氏の惨めな敗戦に、自民党県連は混乱状態に陥る。年明けにあった知事選には候補者を立てることもできず、吉村美栄子氏に再選を許す結果になった。
意地の悪い見方をすれば、加藤紘一氏こそ「吉村知事誕生の伏線を張った功労者」であり、「2013年の無投票再選の立役者」と言える。
自民党県連の元会長、遠藤利明衆院議員も「吉村県政への貢献度」では、加藤氏に引けを取らない。
2016年夏の参院選で、遠藤氏はJA全農山形出身の月野薫氏を自民党の候補者として担ぎ出した。当時の最大の争点はTPP(環太平洋パートナーシップ協定)に反対か否か。対立候補の元参院議員、舟山康江氏は強硬な反対論者で農民の支持を集めていた。
遠藤氏は「全農出身の候補者を立てれば農協票は割れ、それに頼る舟山陣営を切り崩すことができる」と踏んで、月野氏を擁立したようだが、肝心の候補者本人に魅力が乏しかった。結果は12万票の大差での敗北。遠藤氏はその敗戦処理に追われ、翌2017年の知事選対策どころではなくなった。
結局、吉村知事に挑戦する者は現れず、無投票での三選を許した。遠藤氏の選挙下手のおかげ、と言うべきだろう。ちなみに、今回、知事候補の公募に応じた伊藤洋氏を引っ張ってきたのも遠藤氏という。つくづく「人を見る目」がない。
遠藤氏は「フル規格の奥羽、羽越新幹線の建設」を唱えている。地元の山形新聞がキャンペーンを張り、吉村知事が力を入れている政策だ。これに後追いで乗っかった。フル規格の両新幹線建設構想が時代錯誤の政策で、実現の可能性がおよそないことは、すでに何度も書いた。「時代の流れを読む力もない」と言うべきだろう。
そもそも、山形県の自民党は本気で吉村県政を倒す気があるのだろうか。
吉村知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業・法人グループにはこの10年で40億円もの公金が流れ込んでいる(表再掲)。その詳細はこれまで、月刊『素晴らしい山形』で報じてきた通りだ。
もっとも多額の公金が支出されているのは、和文氏が理事長を務める学校法人、東海山形学園である。毎年3億円前後、多い年には10億円を超える私学助成が支給されている。なのに、その学校法人からグループの中核企業、ダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資が行われたりしている。学校法人の監督権限を持つ山形県はその内容を調べようともしない。
当方が独自に調べるため、学校法人の財務書類の情報公開を求めても、「当該法人の利益を害するおそれがある」との理由で肝心な部分を開示しない。「非開示は不当」と裁判に訴え、仙台高裁で開示を命じる判決が出ても、最高裁に上告して開示を引き延ばす。
吉村知事が観光キャンペーンを始めれば、県幹部が露骨な方法でグループ企業に業務委託をして潤わせる。その幹部が抜擢され、出世していく。知事が奥羽、羽越新幹線の建設を唱え始めれば、その関連業務もまたグループ企業に委託するーー。
中国の故事「瓜田(かでん)に履(くつ)を納(い)れず、李下に冠を正さず」に反するどころではない。吉村一族企業は、瓜(うり)畑にずかずかと入り込み、スモモの木の下にブルーシートを張って幹を揺さぶり、収穫して恥じるところがない。
次の知事選に本気で取り組もうとするなら、自民党はこうした問題を一つひとつ追及し、吉村知事の下で何が起きているのか、明らかにする必要がある。
長期県政による澱(よど)みを許さないように、知事の多選を制限する条例を制定することも考えられる。
2003年に東京都の杉並区が多選自粛条例を制定して以来、神奈川県が2007年に「知事は連続3期12年まで」との条例を作るなど、すでに先行例が多数ある。いったん制定した条例を廃止した自治体もあり、難しい面もあるが、山形県のように同じ人物が権力を握り続け、専横と腐敗を招いた歴史がある土地では試みる価値が十分にある。
県議会で過半数を握る自民党がその気になれば、すぐにでも制定できる条例だ。その条例を突き付けて、吉村知事の四選出馬を牽制することも考えられる。
要は、自分たちが住む土地をより良いものにするために、次の世代により良いものを残すために、何かを為す気概があるかどうかだ。その気概があるからこそ、政治を志したのではないのか。
吉村県政の1期目は新鮮だった。前任の斎藤知事の冷たい政策に凍えていた県民の心を包み込むような温かさも感じた。けれども、2期目以降、高い人気を背にして「おごり」が見え始めた。知事に当選した際のキャッチフレーズ「温かい県政」は、いつしか「身内と取り巻きに温かい県政」に転じていった。
救いがたいのは「時代の流れ」にあまりにも鈍感なことだ。情報技術(IT)革命が進み、変化のスピードが増しているのに、まったく対応できていない。山形県庁はいまだに「紙とハンコ」で仕事をしている。行政事務の電子決裁化はロードマップすらない。
トップに「このままでは時代に取り残されてしまう」という思いがないからだろう。フル規格の新幹線建設などという「20世紀の夢」を追い続ける人物に、次の4年を託すのは耐えがたい。私たちに続く世代は、21世紀の後半を生きなければならないのだから。
*メールマガジン「風切通信 75」 2020年5月31日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年6月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
*加藤紘一氏は2016年、岸宏一氏は2017年に死去。
日本の新型コロナウイルス対策の失敗は、マスクとPCR検査に見て取れる。安倍晋三首相は「全国民にマスクを配る」と大見得を切って巨費を投じたが、アベノマスクは髪の毛が入っていたり、汚れていたりでトラブル続きだ。いつ届くのか見当もつかない。

そもそも、国家の一大事に首相が「マスクの配布」に躍起になること自体がおかしい。マスクの確保も確かに大切だが、全体を見渡して、もっと優先しなければならないことがいくつもある。感染しているかどうかを確認するためのPCR検査の拡充もその一つである。
新型コロナウイルスの感染がどのくらい広がっているのか。それを可能な限り正確に把握することは、すべての対策の基本だからだ。人口10万人当たりの検査実施数を見れば、最初から現在まで、日本のPCR検査は主要先進国の中で最低レベルにある。
なぜ、日本のPCR検査の実施数はこんなに少ないのか。メディアはさまざまな分析を試みているが、ズバリと核心をつく報道が少なすぎる。この問題の核心にあるのは、感染症対策の中心になるべき厚生労働省が自らの権益と縄張りにこだわり、政治家も思い切った決断ができなかったことにあるのではないか。
日経新聞の関連グループサイト「日経バイオテク」が2月20日に報じた「新型コロナウイルス、検査体制の拡充が後手に回った裏事情」は、問題の核心に迫った優れた報道の一つだ。PCR検査とはそもそもどのような検査なのか。それを詳しく解説したうえで、厚生労働省が「自前の検査」にこだわった経過を丁寧に報じている。
厚生労働省は国立感染症研究所(感染研)を中心にして、都道府県や政令市の衛生研究所が検査を担う、というこれまでの感染症対策を踏襲した。中国が1月中旬に公表した新型コロナウイルスの遺伝子配列を基にして、感染研は自前の検査方法を開発し、各地の衛生研究所に検査のやり方を伝授した。そのうえで、検査受け付けの窓口を都道府県の保健所に一本化した。
これが「PCR検査の目詰まり」を引き起こし、検査の拡充を阻害する結果を招いた。
世界規模の感染症対策において、PCR検査技術の先頭を走っているのはメガファーマと呼ばれる巨大製薬会社だ。アメリカのファイザー、スイスのノバルティスとロシュがトップスリー。日本の製薬会社はトップテンに1社もなく、武田薬品工業がかろうじて16位に入っているのが現実だ(2015年時点)。
新しい感染症が見つかれば、これらの巨大製薬会社はただちにPCR検査方法の確立と検査キットの開発に走り出す。中でもスイスのロシュが強い。世界保健機関(WHO)がスイスにあり、ロシュはWHOと緊密に連携しながら感染症対策にあたっている。情報の入手も早く、開発に巨費を投じることもできる。
今回も、ロシュはいち早く検査の試薬を開発し、1月末には効率のいい検査装置を製造して売り出した。その後、24時間で4000人分の検体を全自動で解析できる最新式の装置も市場に投入した。欧州各国は速やかにこれらの装置を購入して検査に使い、感染症対策に活かしている。
ところが、前述したように厚生労働省は自前の開発にこだわり、国立感染症研究所に検査手法を開発させ、これを全国に広めようとした。「何でもかんでも外国に依存するわけにはいかない。自前で開発する技術とノウハウを維持し、磨く必要がある」という言い分も理解できないではない。
けれども、それは平時の論理だ。未曾有の事態には「前例にとらわれない決断」をしなければならない。マンパワーの面でも資金面でも、感染研が世界の大手製薬会社に太刀打ちできないのは自明のことだ。自力での検査手法とキットの開発にこだわった結果が「先進国で最低レベルのPCR検査状況」となって現れた、と見るべきだろう。
検査の窓口を都道府県や政令市の保健所一本に絞ったことも、PCR検査の拡充を阻むことになった。これも「前例踏襲」の結果だ。非常時には「前例のない対応」を決断しなければならない。前例や縄張りにこだわらず、大学の医学部、民間の検査会社などあらゆる力を総動員しなければならない。なのに、厚労省はその決断ができず、前例を踏襲した。安倍政権もその壁を突き破ることができなかった。
感染研のスタッフも都道府県の衛生研究所も保健所も、持てる力を最大限に発揮しようとしていることは疑いない。その人たちを責めることはできない。問題は「一生懸命に働いたかどうか」ではない。「世界を見渡して、最善の策は何か」という発想で対処できない、日本の政治家と官僚たちの度量の狭さにある。
感染症対策のように、検査技術や情報技術(IT)の最先端の知見を縦横に活用する必要がある分野で、日本はすでに「二流のレベル」にあるのではないか。そうした自省と自覚がないから、出だしでつまずき、混乱が続いているのだ。
山梨大学の島田真路学長は日本の感染症対策を批判し、「未曾有の事態の今だからこそ、権威にひるまず、権力に盲従しない、真実一路の姿勢がすべての医療者に求められている」と語った(朝日新聞5月6日付)。あまりの惨状に、医学の専門家として黙っていられなくなったのだろう。
こうした批判に対して、頑迷な厚労省官僚や彼らに追随する専門家は「新型コロナウイルスによる死者数を見れば、人口当たりで日本はもっとも少ない国の一つだ。対策は全体としてうまくいっている」と反論するのかもしれない。
確かに、公式に発表された死者だけを基にすれば、日本の感染症対策はうまく行っているようにも見える。が、それは日本の医療の水準の高さと医療関係者の献身的な努力に支えられている面が多いのではないか。
さらに言えば、「新型コロナウイルスによる死者」として公表されているデータそのものについても、今後、精密な解析をしなければならない。PCR検査が進まないせいで、日本では新型コロナウイルスの感染者を正確に把握できていない。「新型コロナが原因なのに無関係」とされた死者がどのくらいいるのか。それを検証しなければ、「死者は少ない」ということも簡単には言えないだろう。
非常事態の日々から日常の暮らしへと徐々に戻っていくためにも、PCR検査の拡充は欠かせない。感染状況と「ぶり返し」の兆候を見極めながら、経済活動の規制を緩め、普通の暮らしへと段階的に戻っていかなければならないからだ。
救いは、大阪府の吉村洋文知事のように政府の指針を待つことなく、独自に自粛の解除に向けた基準を打ち出す動きが出てきたことだ。政府や厚労省が権益や縄張りの壁を乗り越えられないでいるなら、自分たちでその壁を乗り越えるしかない。
それは政府と地方の役割を根本から見直し、新しい形を創り出していくことにつながるだろう。
*メールマガジン「風切通信 74」 2020年5月7日
≪写真説明とSource≫
PCR検査のための検体採取
https://www.recordchina.co.jp/b784821-s0-c10-d0135.html
≪参考サイト&記事≫
◎新型コロナウイルス、検査体制の拡充が後手に回った裏事情(日経バイオテク2020年2月20日)
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/20/02/28/06625/
◎製薬業界の世界ランキング(ビジネスIT 2015年4月21日)
https://www.sbbit.jp/article/cont1/29564
◎新型肺炎「日本の対応」は不備だらけの大問題(上昌広・医療ガバナンス研究所理事長、東洋経済オンライン2020年2月6日)
https://toyokeizai.net/articles/-/329046
◎PCR検査体制、地方から異議(朝日新聞2020年5月6日付)

そもそも、国家の一大事に首相が「マスクの配布」に躍起になること自体がおかしい。マスクの確保も確かに大切だが、全体を見渡して、もっと優先しなければならないことがいくつもある。感染しているかどうかを確認するためのPCR検査の拡充もその一つである。
新型コロナウイルスの感染がどのくらい広がっているのか。それを可能な限り正確に把握することは、すべての対策の基本だからだ。人口10万人当たりの検査実施数を見れば、最初から現在まで、日本のPCR検査は主要先進国の中で最低レベルにある。
なぜ、日本のPCR検査の実施数はこんなに少ないのか。メディアはさまざまな分析を試みているが、ズバリと核心をつく報道が少なすぎる。この問題の核心にあるのは、感染症対策の中心になるべき厚生労働省が自らの権益と縄張りにこだわり、政治家も思い切った決断ができなかったことにあるのではないか。
日経新聞の関連グループサイト「日経バイオテク」が2月20日に報じた「新型コロナウイルス、検査体制の拡充が後手に回った裏事情」は、問題の核心に迫った優れた報道の一つだ。PCR検査とはそもそもどのような検査なのか。それを詳しく解説したうえで、厚生労働省が「自前の検査」にこだわった経過を丁寧に報じている。
厚生労働省は国立感染症研究所(感染研)を中心にして、都道府県や政令市の衛生研究所が検査を担う、というこれまでの感染症対策を踏襲した。中国が1月中旬に公表した新型コロナウイルスの遺伝子配列を基にして、感染研は自前の検査方法を開発し、各地の衛生研究所に検査のやり方を伝授した。そのうえで、検査受け付けの窓口を都道府県の保健所に一本化した。
これが「PCR検査の目詰まり」を引き起こし、検査の拡充を阻害する結果を招いた。
世界規模の感染症対策において、PCR検査技術の先頭を走っているのはメガファーマと呼ばれる巨大製薬会社だ。アメリカのファイザー、スイスのノバルティスとロシュがトップスリー。日本の製薬会社はトップテンに1社もなく、武田薬品工業がかろうじて16位に入っているのが現実だ(2015年時点)。
新しい感染症が見つかれば、これらの巨大製薬会社はただちにPCR検査方法の確立と検査キットの開発に走り出す。中でもスイスのロシュが強い。世界保健機関(WHO)がスイスにあり、ロシュはWHOと緊密に連携しながら感染症対策にあたっている。情報の入手も早く、開発に巨費を投じることもできる。
今回も、ロシュはいち早く検査の試薬を開発し、1月末には効率のいい検査装置を製造して売り出した。その後、24時間で4000人分の検体を全自動で解析できる最新式の装置も市場に投入した。欧州各国は速やかにこれらの装置を購入して検査に使い、感染症対策に活かしている。
ところが、前述したように厚生労働省は自前の開発にこだわり、国立感染症研究所に検査手法を開発させ、これを全国に広めようとした。「何でもかんでも外国に依存するわけにはいかない。自前で開発する技術とノウハウを維持し、磨く必要がある」という言い分も理解できないではない。
けれども、それは平時の論理だ。未曾有の事態には「前例にとらわれない決断」をしなければならない。マンパワーの面でも資金面でも、感染研が世界の大手製薬会社に太刀打ちできないのは自明のことだ。自力での検査手法とキットの開発にこだわった結果が「先進国で最低レベルのPCR検査状況」となって現れた、と見るべきだろう。
検査の窓口を都道府県や政令市の保健所一本に絞ったことも、PCR検査の拡充を阻むことになった。これも「前例踏襲」の結果だ。非常時には「前例のない対応」を決断しなければならない。前例や縄張りにこだわらず、大学の医学部、民間の検査会社などあらゆる力を総動員しなければならない。なのに、厚労省はその決断ができず、前例を踏襲した。安倍政権もその壁を突き破ることができなかった。
感染研のスタッフも都道府県の衛生研究所も保健所も、持てる力を最大限に発揮しようとしていることは疑いない。その人たちを責めることはできない。問題は「一生懸命に働いたかどうか」ではない。「世界を見渡して、最善の策は何か」という発想で対処できない、日本の政治家と官僚たちの度量の狭さにある。
感染症対策のように、検査技術や情報技術(IT)の最先端の知見を縦横に活用する必要がある分野で、日本はすでに「二流のレベル」にあるのではないか。そうした自省と自覚がないから、出だしでつまずき、混乱が続いているのだ。
山梨大学の島田真路学長は日本の感染症対策を批判し、「未曾有の事態の今だからこそ、権威にひるまず、権力に盲従しない、真実一路の姿勢がすべての医療者に求められている」と語った(朝日新聞5月6日付)。あまりの惨状に、医学の専門家として黙っていられなくなったのだろう。
こうした批判に対して、頑迷な厚労省官僚や彼らに追随する専門家は「新型コロナウイルスによる死者数を見れば、人口当たりで日本はもっとも少ない国の一つだ。対策は全体としてうまくいっている」と反論するのかもしれない。
確かに、公式に発表された死者だけを基にすれば、日本の感染症対策はうまく行っているようにも見える。が、それは日本の医療の水準の高さと医療関係者の献身的な努力に支えられている面が多いのではないか。
さらに言えば、「新型コロナウイルスによる死者」として公表されているデータそのものについても、今後、精密な解析をしなければならない。PCR検査が進まないせいで、日本では新型コロナウイルスの感染者を正確に把握できていない。「新型コロナが原因なのに無関係」とされた死者がどのくらいいるのか。それを検証しなければ、「死者は少ない」ということも簡単には言えないだろう。
非常事態の日々から日常の暮らしへと徐々に戻っていくためにも、PCR検査の拡充は欠かせない。感染状況と「ぶり返し」の兆候を見極めながら、経済活動の規制を緩め、普通の暮らしへと段階的に戻っていかなければならないからだ。
救いは、大阪府の吉村洋文知事のように政府の指針を待つことなく、独自に自粛の解除に向けた基準を打ち出す動きが出てきたことだ。政府や厚労省が権益や縄張りの壁を乗り越えられないでいるなら、自分たちでその壁を乗り越えるしかない。
それは政府と地方の役割を根本から見直し、新しい形を創り出していくことにつながるだろう。
*メールマガジン「風切通信 74」 2020年5月7日
≪写真説明とSource≫
PCR検査のための検体採取
https://www.recordchina.co.jp/b784821-s0-c10-d0135.html
≪参考サイト&記事≫
◎新型コロナウイルス、検査体制の拡充が後手に回った裏事情(日経バイオテク2020年2月20日)
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/20/02/28/06625/
◎製薬業界の世界ランキング(ビジネスIT 2015年4月21日)
https://www.sbbit.jp/article/cont1/29564
◎新型肺炎「日本の対応」は不備だらけの大問題(上昌広・医療ガバナンス研究所理事長、東洋経済オンライン2020年2月6日)
https://toyokeizai.net/articles/-/329046
◎PCR検査体制、地方から異議(朝日新聞2020年5月6日付)
新型コロナウイルスの感染が広がってから、「ウイルスに打ち勝つ」という言葉をしばしば耳にするようになった。この言葉を口にする人たちは、それがどんなにおこがましいことか分かっているのだろうか。

ウイルスが誕生したのは数十億年前とされる。地球ではその後、何度も生物の大絶滅が起きた。大規模な地殻変動や隕石の衝突によって、命あるものの多くが滅びた。恐竜もその一つだ。ウイルスはそうした大絶滅を何度もくぐり抜けてきた。
私たち人間はどうか。先祖が登場したのは数百万年前、地球の長い歴史から見れば、つい最近のことだ。戦争や疫病で多くの人が命を失ったことはあるが、大絶滅の危機を経験したことはまだ一度もない。
ウイルスにしてみれば、「ぽっと出の若造が何をほざく」と笑い飛ばしたいところだろう。「打ち勝つ」ことができるような相手ではない。私たちにできるのは、手を尽くして被害を最小限に食い止めること、そして、治療薬やワクチンを開発して共に生きる道を切り拓くことくらいだ。
感染防止策も生活と経済の維持も、そういう前提に立って進めることが大切だろう。どこかの大統領のように「これは戦争だ」などと意気がってみても、何の意味もない。
わが山形県の吉村美栄子知事も、あまり意味のないことに力を注いでいる。県境で検査をして「ウイルスの侵入を食い止める」と提唱したものの、「道路を走っている車を停めることはできない」と言われ、パーキングエリアでドライバーのおでこに検温計を向けることくらいしかできなかった。
そんなことに人員と資金を注ぐより、医療や介護の現場で奮闘している人たちを支えるために全力を尽くすべきだ。仕事を失い、暮らしが立ち行かなくなっている人たちに一刻も早く手を差し伸べるために何をすべきか。それも急がなければならない。
物事に優先順位をつけ、それに応じて力の注ぎ具合を考える。吉村知事はそれが苦手のようだ。農産物の売り込みや観光客の誘致といった「分かりやすいこと」には一生懸命になるが、情報技術(IT)を行政や医療にどう活かしていくか、といった重要かつ複雑な問題になると、途端に「専門家や部下にお任せ」となる。人の話に耳を傾け、自分で深く考え、そのうえで判断する。それができないのだろう。
未来に向かって開かれた社会をつくっていくうえで、情報公開制度をどうやってより充実したものにしていくか。それも、間違いなく優先しなければならないことの一つだが、吉村知事には「後回しにしてもいいこと」と映っているようだ。
そうでなければ、私が学校法人東海山形学園の財務書類の情報公開を請求したのに対して、詳細な部分を白塗りにして開示する(表1再掲)というようなことも起きなかったはずだ。
この白塗り文書が出てくるまでの経緯は表2の通りである。
4年前の秋、月刊『素晴らしい山形』が吉村知事の義理のいとこ、吉村和文氏の率いるダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)と学校法人、東海山形学園の間で不可解な取引があった、と報じた。
会社の貸借対照表によると、学校法人から会社に3000万円の融資が行われていたのだ。学校法人が会社から金を借りたのではない。その逆だ。しかも、和文氏は会社の社長と学校法人の理事長を兼ねている。お互いの利益がぶつかる「利益相反行為」に該当する。
この学校法人は東海大山形高校を運営しており、政府と山形県から毎年、3億円前後の私学助成を受けている。その助成額の1割に相当する金がグループ企業に貸し付けられていたことになる。そんなことが許されるのか。法に触れないのか。
会社の貸借対照表に3000万円の融資が記載されているなら、学校法人の貸借対照表にも記載されているはずだ。私は、それを確認するため山形県に情報公開請求を行った。私学助成を受ける学校法人は監督官庁の山形県に財務書類を提出している。県にはすべての書類がそろっているからだ。
政府や自治体が持っている情報は国民のものであり、原則として公開しなければならない。私は、すんなり出てくるものと思っていた。ところが、詳しい部分が白く塗られて出てきたのだ。
県学事文書課の担当者から「非開示の理由」を聞かされて驚いた。「会計文書の詳しい内容を明らかにすると、学校法人の正当な利益を害するおそれがあるから」(県情報公開条例第6条に該当)というものだった。
納得できず、2017年7月に非開示処分の取り消しを求めて山形地方裁判所に提訴した。一審の経過と結末は本誌2019年6月号で詳しく書いた。山形地裁は「財務関係書類の詳細な部分が明らかになれば、学校法人の経営上の秘密やノウハウが判明して他の高校の知るところとなり、学校法人の競争力を損ね、利益を大きく害することになることも考えられる」という県側の主張をほぼそのまま認め、私の請求を棄却した。
当方が唖然(あぜん)するような、およそ現実離れした空理空論に基づく判決だった。すぐさま、仙台高等裁判所に控訴した。
ただ、敗訴したのは「こちらの主張に甘いところがあったからかもしれない」と反省した。そもそも、財務書類とは歴史的にどのようにして成立したのか。経済的、社会的にどのような役割を果たしてきたのか。日本では今、学校法人の財務書類の公開がどこまで進んでいるのか。そうしたことを丁寧に記した控訴理由書を出して、高裁の判断を仰いだ。
幸いなことに、仙台高裁の裁判官は私立学校の現状にきちんと目を向け、情報公開制度の意義も深く理解している人たちだった。3月26日に一審判決を取り消し、山形県に東海山形学園の財務書類をすべて開示するよう命じる判決を下した(表3の骨子参照)。
私立学校は手厚い私学助成を受けており、文部科学省も積極的に財務情報を公開するよう促してきた。これを受けて、大学を運営する学校法人だけでなく、高校を設置する学校法人についても自発的に財務書類を一般に公表している事例は少なくない。
高裁の判決はそうした現実を踏まえ、「財務書類の詳細な内容を開示すれば、学校法人の正当な利益を害するおそれがある」という山形県側の主張を一蹴した。
判決には、文部科学相の諮問機関である「大学設置・学校法人審議会」の小委員会の検討結果を引用する形で、「情報公開は社会全体の流れであり、学校法人が説明責任を果たすという観点からも、財務情報を公開することが求められている。それによって、社会から評価を受け、質の向上が図られていく」という表現も盛り込まれた。
情報公開制度がこれからどういう役割を果たしていくのか。どれほど重要な制度であるか。そうしたことを見据えて、開かれた社会を築こうとする人たちの背中を押す判決だった。
学校法人の財務書類に関しては昨年5月、地裁判決の直後に私立学校法が改正され、文部科学省が所管する学校法人(大学や短大を運営)については財務書類の公開が法的に義務づけられるに至った。
高校などを運営する都道府県所管の学校法人については「公開の義務づけ」が見送られたものの、文科省は「それぞれの実情に応じて積極的に公表するよう期待する」との通知を出した。この法改正も高裁の判断に大きな影響を及ぼしたとみられる。
吉村美栄子知事はこの判決を不服として、最高裁判所に上告した。仙台高裁の論理は明快で説得力があり、覆ることはないと信じているが、知事は上告することによって社会に二つのメッセージを発することになった。
一つは、情報公開の重要性について鈍感な政治家である、ということ。もう一つは、山形地裁と仙台高裁の判決の質的な違いについて理解できず、周りにもその違いについて解説してくれる人が誰もいない、ということだ。
質的な違いとは「時代が求めていること、社会を前に進めるために為すべきこと」を強烈に意識しているかどうか、という点である。判決文からそれが読み取れないとしたら、政治家として悲しすぎる。
東海山形学園からダイバーシティメディアへの3000万円融資問題については、財務書類の非開示問題に加えて、もう一つ、大きな問題がある。本文の途中でも触れた「利益相反行為」という問題だ。
同じ人物が会社の社長と学校法人の理事長を兼ねている状態で双方が取引をするのは、典型的な「利益相反行為」になる。一方の利益になることは他方の不利益になるからだ。
このような場合、株式会社なら株主総会もしくは取締役会の承認を得れば済むが、学校法人の場合はそうはいかない。私立学校法に特別の規定があり、監督官庁(山形県)は特別代理人を選んでその取引に問題がないかチェックさせなければならないことになっている。
そこで、私は県に対して「この取引にかかわる特別代理人の選任に関する文書」の情報公開を求めた。すると、県は「存否(そんぴ)応答拒否」という暴挙に出た。そういう文書があるかどうかも明らかにしないまま、情報公開を拒否したのである(2018年10月23日付)。
理由はまたしても、県情報公開条例の第6条「(法人の内部管理に関する情報であって)その存否を明らかにすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため」だった。都合が悪い情報は、この条項を使えば出さなくても済む、と考えているようだ。
冗談ではない。法律に定められた手続きを踏んだのかどうか、それを記した文書が「法人の正当な利益を害する」などということはあるわけがない。もし、文書の中に「法人の内部管理に関する情報」が含まれているなら、その部分を伏せて開示すれば済む話だ。文書があるかどうかすら答えたくない、何か特別な事情があるのだろう。
今度は裁判ではなく、県情報公開・個人情報保護審査会に異議を申し立てた。外部の有識者5人で構成される県の諮問機関だ(表4)。すでに実質的な審査は終わっており、結果を待っている段階だ。こちらも「県の存否応答拒否は不当」との裁決が出るものと期待している。
この3000万円融資問題は、知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業・法人グループの「アキレス腱」である。
これに目を凝らせば、吉村知事の権勢を背に巨額の公金を手にしてきた企業グループの中で何が起きているのか、何のために学校法人の3000万円を必要としたのか、少し見えてくるかもしれない。
*メールマガジン「風切通信 73」 2020年5月1日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年5月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。見出しも異なります。
◎仙台高裁の判決全文
≪写真説明&Source≫
山形県境でドライバーに検温計を向ける県職員
https://ameblo.jp/event-x/entry-12590606440.html

ウイルスが誕生したのは数十億年前とされる。地球ではその後、何度も生物の大絶滅が起きた。大規模な地殻変動や隕石の衝突によって、命あるものの多くが滅びた。恐竜もその一つだ。ウイルスはそうした大絶滅を何度もくぐり抜けてきた。
私たち人間はどうか。先祖が登場したのは数百万年前、地球の長い歴史から見れば、つい最近のことだ。戦争や疫病で多くの人が命を失ったことはあるが、大絶滅の危機を経験したことはまだ一度もない。
ウイルスにしてみれば、「ぽっと出の若造が何をほざく」と笑い飛ばしたいところだろう。「打ち勝つ」ことができるような相手ではない。私たちにできるのは、手を尽くして被害を最小限に食い止めること、そして、治療薬やワクチンを開発して共に生きる道を切り拓くことくらいだ。
感染防止策も生活と経済の維持も、そういう前提に立って進めることが大切だろう。どこかの大統領のように「これは戦争だ」などと意気がってみても、何の意味もない。
わが山形県の吉村美栄子知事も、あまり意味のないことに力を注いでいる。県境で検査をして「ウイルスの侵入を食い止める」と提唱したものの、「道路を走っている車を停めることはできない」と言われ、パーキングエリアでドライバーのおでこに検温計を向けることくらいしかできなかった。
そんなことに人員と資金を注ぐより、医療や介護の現場で奮闘している人たちを支えるために全力を尽くすべきだ。仕事を失い、暮らしが立ち行かなくなっている人たちに一刻も早く手を差し伸べるために何をすべきか。それも急がなければならない。
物事に優先順位をつけ、それに応じて力の注ぎ具合を考える。吉村知事はそれが苦手のようだ。農産物の売り込みや観光客の誘致といった「分かりやすいこと」には一生懸命になるが、情報技術(IT)を行政や医療にどう活かしていくか、といった重要かつ複雑な問題になると、途端に「専門家や部下にお任せ」となる。人の話に耳を傾け、自分で深く考え、そのうえで判断する。それができないのだろう。
未来に向かって開かれた社会をつくっていくうえで、情報公開制度をどうやってより充実したものにしていくか。それも、間違いなく優先しなければならないことの一つだが、吉村知事には「後回しにしてもいいこと」と映っているようだ。
そうでなければ、私が学校法人東海山形学園の財務書類の情報公開を請求したのに対して、詳細な部分を白塗りにして開示する(表1再掲)というようなことも起きなかったはずだ。
この白塗り文書が出てくるまでの経緯は表2の通りである。
4年前の秋、月刊『素晴らしい山形』が吉村知事の義理のいとこ、吉村和文氏の率いるダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)と学校法人、東海山形学園の間で不可解な取引があった、と報じた。
会社の貸借対照表によると、学校法人から会社に3000万円の融資が行われていたのだ。学校法人が会社から金を借りたのではない。その逆だ。しかも、和文氏は会社の社長と学校法人の理事長を兼ねている。お互いの利益がぶつかる「利益相反行為」に該当する。
この学校法人は東海大山形高校を運営しており、政府と山形県から毎年、3億円前後の私学助成を受けている。その助成額の1割に相当する金がグループ企業に貸し付けられていたことになる。そんなことが許されるのか。法に触れないのか。
会社の貸借対照表に3000万円の融資が記載されているなら、学校法人の貸借対照表にも記載されているはずだ。私は、それを確認するため山形県に情報公開請求を行った。私学助成を受ける学校法人は監督官庁の山形県に財務書類を提出している。県にはすべての書類がそろっているからだ。
政府や自治体が持っている情報は国民のものであり、原則として公開しなければならない。私は、すんなり出てくるものと思っていた。ところが、詳しい部分が白く塗られて出てきたのだ。
県学事文書課の担当者から「非開示の理由」を聞かされて驚いた。「会計文書の詳しい内容を明らかにすると、学校法人の正当な利益を害するおそれがあるから」(県情報公開条例第6条に該当)というものだった。
納得できず、2017年7月に非開示処分の取り消しを求めて山形地方裁判所に提訴した。一審の経過と結末は本誌2019年6月号で詳しく書いた。山形地裁は「財務関係書類の詳細な部分が明らかになれば、学校法人の経営上の秘密やノウハウが判明して他の高校の知るところとなり、学校法人の競争力を損ね、利益を大きく害することになることも考えられる」という県側の主張をほぼそのまま認め、私の請求を棄却した。
当方が唖然(あぜん)するような、およそ現実離れした空理空論に基づく判決だった。すぐさま、仙台高等裁判所に控訴した。
ただ、敗訴したのは「こちらの主張に甘いところがあったからかもしれない」と反省した。そもそも、財務書類とは歴史的にどのようにして成立したのか。経済的、社会的にどのような役割を果たしてきたのか。日本では今、学校法人の財務書類の公開がどこまで進んでいるのか。そうしたことを丁寧に記した控訴理由書を出して、高裁の判断を仰いだ。
幸いなことに、仙台高裁の裁判官は私立学校の現状にきちんと目を向け、情報公開制度の意義も深く理解している人たちだった。3月26日に一審判決を取り消し、山形県に東海山形学園の財務書類をすべて開示するよう命じる判決を下した(表3の骨子参照)。
私立学校は手厚い私学助成を受けており、文部科学省も積極的に財務情報を公開するよう促してきた。これを受けて、大学を運営する学校法人だけでなく、高校を設置する学校法人についても自発的に財務書類を一般に公表している事例は少なくない。
高裁の判決はそうした現実を踏まえ、「財務書類の詳細な内容を開示すれば、学校法人の正当な利益を害するおそれがある」という山形県側の主張を一蹴した。
判決には、文部科学相の諮問機関である「大学設置・学校法人審議会」の小委員会の検討結果を引用する形で、「情報公開は社会全体の流れであり、学校法人が説明責任を果たすという観点からも、財務情報を公開することが求められている。それによって、社会から評価を受け、質の向上が図られていく」という表現も盛り込まれた。
情報公開制度がこれからどういう役割を果たしていくのか。どれほど重要な制度であるか。そうしたことを見据えて、開かれた社会を築こうとする人たちの背中を押す判決だった。
学校法人の財務書類に関しては昨年5月、地裁判決の直後に私立学校法が改正され、文部科学省が所管する学校法人(大学や短大を運営)については財務書類の公開が法的に義務づけられるに至った。
高校などを運営する都道府県所管の学校法人については「公開の義務づけ」が見送られたものの、文科省は「それぞれの実情に応じて積極的に公表するよう期待する」との通知を出した。この法改正も高裁の判断に大きな影響を及ぼしたとみられる。
吉村美栄子知事はこの判決を不服として、最高裁判所に上告した。仙台高裁の論理は明快で説得力があり、覆ることはないと信じているが、知事は上告することによって社会に二つのメッセージを発することになった。
一つは、情報公開の重要性について鈍感な政治家である、ということ。もう一つは、山形地裁と仙台高裁の判決の質的な違いについて理解できず、周りにもその違いについて解説してくれる人が誰もいない、ということだ。
質的な違いとは「時代が求めていること、社会を前に進めるために為すべきこと」を強烈に意識しているかどうか、という点である。判決文からそれが読み取れないとしたら、政治家として悲しすぎる。
東海山形学園からダイバーシティメディアへの3000万円融資問題については、財務書類の非開示問題に加えて、もう一つ、大きな問題がある。本文の途中でも触れた「利益相反行為」という問題だ。
同じ人物が会社の社長と学校法人の理事長を兼ねている状態で双方が取引をするのは、典型的な「利益相反行為」になる。一方の利益になることは他方の不利益になるからだ。
このような場合、株式会社なら株主総会もしくは取締役会の承認を得れば済むが、学校法人の場合はそうはいかない。私立学校法に特別の規定があり、監督官庁(山形県)は特別代理人を選んでその取引に問題がないかチェックさせなければならないことになっている。
そこで、私は県に対して「この取引にかかわる特別代理人の選任に関する文書」の情報公開を求めた。すると、県は「存否(そんぴ)応答拒否」という暴挙に出た。そういう文書があるかどうかも明らかにしないまま、情報公開を拒否したのである(2018年10月23日付)。
理由はまたしても、県情報公開条例の第6条「(法人の内部管理に関する情報であって)その存否を明らかにすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため」だった。都合が悪い情報は、この条項を使えば出さなくても済む、と考えているようだ。
冗談ではない。法律に定められた手続きを踏んだのかどうか、それを記した文書が「法人の正当な利益を害する」などということはあるわけがない。もし、文書の中に「法人の内部管理に関する情報」が含まれているなら、その部分を伏せて開示すれば済む話だ。文書があるかどうかすら答えたくない、何か特別な事情があるのだろう。
今度は裁判ではなく、県情報公開・個人情報保護審査会に異議を申し立てた。外部の有識者5人で構成される県の諮問機関だ(表4)。すでに実質的な審査は終わっており、結果を待っている段階だ。こちらも「県の存否応答拒否は不当」との裁決が出るものと期待している。
この3000万円融資問題は、知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業・法人グループの「アキレス腱」である。
これに目を凝らせば、吉村知事の権勢を背に巨額の公金を手にしてきた企業グループの中で何が起きているのか、何のために学校法人の3000万円を必要としたのか、少し見えてくるかもしれない。
*メールマガジン「風切通信 73」 2020年5月1日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年5月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。見出しも異なります。
◎仙台高裁の判決全文
≪写真説明&Source≫
山形県境でドライバーに検温計を向ける県職員
https://ameblo.jp/event-x/entry-12590606440.html
そもそも、生物とは何か。現代の科学では「細胞とそれを包む細胞膜を持つもの」と定義されている。
あらゆる生物は、細胞の形態や構造によって「細菌」と「古細菌」、「真核生物」の三つに分類される。動物も植物も真核生物の一種である。ウイルスはそのどれにも含まれない。細胞も細胞膜もないからだ。遺伝情報を含む核酸とそれを取り囲むタンパク質で構成される「微小な粒子」なのだという。
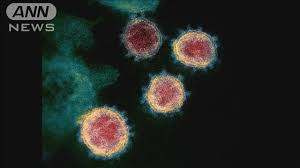
「ちょっと待て」と言いたくなる。新型コロナウイルスの猛威にさらされ、右往左往している人間から見れば、ウイルスはどう見ても「生きている」。生きて我々に取り付き、ものすごい勢いで増殖しているではないか、と。
それでも、生物学者の多くは「ウイルスは生物である」とは認めない。ネット上の百科事典「ウィキペディア」のウイルスの項には「生物と非生物、両方の特性を持つ」と書いてある。理解不能である。
ウイルスは「生命とは何か」というテーマにも関わる、深い謎を秘めた存在のようだ。世界はいまだ多くの謎に満ちている、と言うしかない。
その謎の一つが中国の武漢で突然変異を起こし、中国から日本を含む周辺国、そして世界に広がった。人々をおののかせ、政治家を悩ませ、世界経済の屋台骨を揺さぶるに至った。
新型コロナウイルスの感染拡大に、それぞれの国はどう対処したのか。それを追っていくと、その国の光と影が炙(あぶ)り出され、見えてくる。
このウイルスの存在に最初に気付いたのは武漢の李文亮(リーウェンリアン)医師たちだった。昨年末、「新しいタイプのコロナウイルスの感染が確認された」として、同僚の医師らにSNS(交流サイト)で患者の症状や肺のCT検査データを伝え、注意を喚起した。
ところが、それがネットで広がると、武漢市の公安局(警察)は「デマを流した」として李医師らを訓戒処分にし、国内メディアも「悪質なデマ」と報じた。処分を受けた後も、彼は患者の治療にあたっていたが、自らもウイルスに感染し、身重の妻を残して33歳で死去した。
亡くなる前、李医師はインタビューに応え、「健全な社会には一つだけでなく、様々な声があるべきだ」と語った。穏やかな表現の中に「自由がない国」への痛烈な批判を読み取ることができる。こうした初期の硬直した対応が中国での感染爆発を引き起こした。
もっとも、初期の失態に気付いた後の中国共産党の対応は「断固たるもの」だった。武漢市全体を封鎖し、全国から医師や看護師を動員して送り込んだ。さらに、軍隊を使って仮設の隔離病棟をたちまち完成させた。
中国には「土地の所有権」というものはない。土地はすべて国家のものであり、個人や企業には利用権が与えられているだけだ。このため、必要になれば、すぐに土地を収用できる。仮設の隔離病棟を短期間で建設できたのも、簡単な手続きで必要な土地を確保できるからだ。
この土地収用の簡便さは「腐敗の温床」の一つになっている。改革開放路線が始まってから、企業が次々に設立され、中国は「世界の工場」と呼ばれるようになったが、その過程で「金もうけに目がくらんだ共産党幹部と起業家」が農民や住民を追い出し、土地を強奪する事件が頻発している。中国にはその不正を告発し、正す自由がない。
腐敗はとめどなく広がり、暴動や流血事件となって噴き出している。その実態を赤裸々に描いたのが『中国の闇 マフィア化する政治』(何清漣、扶桑社)という本だ。著者は米国に逃れ、「共産党幹部が黒社会を束ね、あるいは黒社会の幹部が要職に就いて暴虐の限りを尽くしている」と、実名を挙げて告発している。
その中国での感染拡大はピークを越え、パンデミック(世界的大流行)の震源は欧米に移った。その中でも深刻なのがイタリアである。
新型コロナによるイタリアの死者は3月中旬には中国を上回った。最初の死者が確認されてから3週間余りで3000人を超えており、初期の段階で事態を甘く見て警戒を怠ったことがうかがえる。
医師や看護師が身に付けるマスクや防護服が足りない。肺炎を発症した患者を救うために必要な人工呼吸器も集中治療の設備も不足しているという。初期対応の失敗に加えて、こうした医療体制の脆弱さが事態を悪化させている。
欧州連合(EU)の創設メンバーでありながら、イタリアはずっと「財政の劣等生」として扱われてきた。豊かな北部と貧しい南部、競争力のある一握りの大企業と膨大な数の零細企業、恵まれた公務員と不安定な雇用に甘んじなければならない民衆・・・。イタリアはそうした様々な「二重構造」を抱えながら、政府が借金を重ねてしのいできた。
昨年の6月、欧州委員会は「イタリアの財政状況はEUの基準から逸脱している」として、「制裁手続きに入ることが正当化される」との報告書を公表した。「政府は支出を抑え、増税に踏み切れ」と圧力をかけたのである。それに応えるため、イタリアでは医療や福祉の予算が削られ、医師の国外への流出も起きていた。
新型コロナは、そんな悶え苦しむイタリアを襲った。防護服が足りない病院では透明なゴミ袋を加工して使い、長時間勤務で疲れ切った看護師は机につっぷしたまま寝込んでしまう。そうした映像がネットで流れ、「医療崩壊寸前」と報じられている。
外出を控えて自宅にとどまるよう求められた住民たちは、フェイスブックなどのSNSで「治療に取り組む人たちを励まそう」と呼びかけ始めた。ベランダに一人、また一人と姿を現し、声を合わせて歌い出す様子がテレビで流れた。さすが「芸術と文化の国」である。
人様のことはこれくらいにして、わが国の光と影を考えてみたい。
新型コロナの侵入を水際で食い止めることを目指した初期対応は無残なものだった。横浜港の桟橋に係留された豪華クルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号は「巨大なウイルス培養器」と化してしまった。
厚生労働省が対策の中心になったからである。感染を防止するため、客船には厚労省の職員や災害派遣医療チーム、自衛隊の隊員らが送り込まれたが、指揮系統がバラバラで、厚労省にはそれを統率する力がなく、対応も不適切だった。
薬害エイズの経緯を振り返ってみれば明らかなように、この役所は医療や製薬の権益がからむことには必死で取り組む。けれども、「国民の命と健康を守るために何を為すべきか」を真剣に考える人が少なすぎる。ゆえに、危機に対応する能力がない。
クルーズ船の惨状を見て、安倍晋三首相も腹をくくったのだろう。その後は、厚労省の幹部ではなく、感染症の専門家の意見に耳を傾けるようになった。その専門家の一人、川崎市健康安全研究所長の岡部信彦氏は朝日新聞(3月18日付)のインタビューに応えて、こう語っている。
「私は医療がある程度保たれていれば、致死率はそんなに高くならないのではと思っています。重症になる人ができるだけきちんとした医療を受けられるようにしておくことが大事で、それができれば日本での致死率は1%前後で収まるのではないでしょうか」
「データに基づいて、最終的には一つの方向性を出していかなければならないと考えています。無症状の人からうつったという論文も出てきているので、パーフェクトな『封じ込め』は不可能です。それでも社会活動を止めて『封じ込め』を追求するのか、ある程度の流行を前提に重症者・死亡者数の減少、最小の社会的被害に抑える方向にかじを切るのか」
説得力のある考え方である。新型コロナと普通のインフルエンザの大きな違いは、前者には特効薬がなく、予防のためのワクチンもないことだ。そのため、不安が広がっているが、手立てを講じて感染の爆発を防ぎ、医療体制を維持し続ければ、なんとか乗り切ることができるはずだ。
幸いなことに、私たちの国には献身的な医師や看護師、医療従事者がたくさんいる。介護や福祉の現場も踏ん張っている。彼らを支えつつ、社会的なダメージや経済的な損失をできるだけ小さくするために何を為すべきか。指導者も私たち一人ひとりも、これからそれを問われることになる。
新型コロナで炙り出された「日本の闇」は何か。私は「マスク不足」にそれを感じる。安倍政権は「マスクの増産をお願いしている」「増産する企業には財政的な支援をする」と何度も表明したが、マスクはいまだに不足している。
しかも、政治家は「マスクの増産」は口にするが、「マスクの供給がどうなっているか」については語らない。語れないのだろう。日本の政府にはマスクの供給状況についての信頼できるデータがないのではないか、と疑っている。
日本政府の情報技術(IT)対応は、信じられないほど遅れている。各省庁がバラバラに情報機器とソフトを導入した。それどころか、一つの省庁の中でも部局によってシステムが異なる。情報を共有したくてもできない状況にある。貴重なデータを連携して活用するすべもない。
政府からの補助金に頼って仕事をしてきた都道府県も右ならえ、である。私は「山形県の知事部局のシステム」について情報公開を求めた。その結果、出てきた文書を見て仰天した。78ものシステムがただ羅列してあったからだ。どのシステムを基幹にして、どのような態勢を築くのか。基本構想がまるで分からない。そもそも、構想がないのだろう。
日本と対照的なのが台湾だ。4年前に発足した蔡英文(ツァイインウェン)政権は、「台湾IT十傑」の一人とされる唐鳳(タンフォン)氏をデジタル担当相に抜擢した。当時、35歳。歴代最年少での入閣だった。
この人物が今回の新型コロナ対策で縦横無尽の活躍を見せた。1月末からマスクの管理に乗り出し、どのように流通しているかネットで公開した。民間のアプリを使えば、自分の地域のどの薬局にマスクがあるか、スマホで誰でも見られるようになった。
マスクを配給制にし、住民はICチップ入りの健康保険カードを示せば、確実にマスクを手にすることができる。3月末からは、スマホで予約すればコンビニで受け取れるシステムも動き出す。世界最先端の取り組みと言っていい。
唐鳳氏は「中国と台湾は距離的に近くても価値観は正反対だ」と言う。中国は民衆を監視し、管理するためにITを利用する。これに対し、台湾は政府を監視し、開かれた社会をつくるために活用するのだ、と。「徹底的な透明性」を唱え、理念でも最先端を行く。
わが日本のIT担当相は誰か。大阪選出の竹本直一(なおかず)代議士である。「入閣待望組」の一人で、昨年9月の内閣改造の際、78歳で初めて閣僚になった。最高齢での初入閣だった。
おまけにこの時、竹本氏の公式サイトは「ロックされて閲覧不能」になっていた。記者会見でその理由を問われ、竹本氏は「なぜロックされているのかよく分からない」と答え、失笑を買った。
日本と台湾のIT担当相の、この絶望的なまでの格差。それはそのまま、日本の政治と行政のIT化がいかに絶望的な状況にあるかを示している。次の世代のことを考えると、私にはこちらの方が新型コロナウイルスより、はるかに恐ろしい。
*メールマガジン「風切通信 72」 2020年3月30日
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の2020年4月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎新型コロナウイルス(テレビ朝日のサイト)
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000178040.html
≪参考文献・記事&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎ウィキペディアの「細菌」「古細菌」「真核生物」「ウイルス」
◎コロナウイルスの基礎知識(国立感染症研究所)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/9303-coronavirus.html
◎ウィキペディアの「李文亮」
◎李文亮の名言「今週の防災格言634」
https://shisokuyubi.com/bousai-kakugen/index-795
◎『中国の闇 マフィア化する政治』(何清漣、扶桑社)
◎「イタリア制裁手続き入り『正当化』」(日本経済新聞2019年6月5日)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45727360V00C19A6FF2000/
◎「イタリア財政危機の構造と制度改革」(経済企画庁経済研究所)
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun094/bun94a.pdf
◎「新型コロナ 緊急事態宣言は必要か」(朝日新聞2020年3月18日付)
◎ウィキペディアの「唐鳳」「竹本直一」
◎Wikipedia 「Audrey Tang」
https://en.wikipedia.org/wiki/Audrey_Tang
◎「台湾のコロナ政策 奏功」(朝日新聞2020年3月7日付)
◎「パンデミック 世界はいま」(朝日新聞2020年3月21日付)
◎月刊『選択』2020年3月号の新型コロナ関連記事
あらゆる生物は、細胞の形態や構造によって「細菌」と「古細菌」、「真核生物」の三つに分類される。動物も植物も真核生物の一種である。ウイルスはそのどれにも含まれない。細胞も細胞膜もないからだ。遺伝情報を含む核酸とそれを取り囲むタンパク質で構成される「微小な粒子」なのだという。
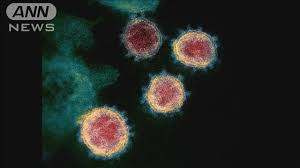
「ちょっと待て」と言いたくなる。新型コロナウイルスの猛威にさらされ、右往左往している人間から見れば、ウイルスはどう見ても「生きている」。生きて我々に取り付き、ものすごい勢いで増殖しているではないか、と。
それでも、生物学者の多くは「ウイルスは生物である」とは認めない。ネット上の百科事典「ウィキペディア」のウイルスの項には「生物と非生物、両方の特性を持つ」と書いてある。理解不能である。
ウイルスは「生命とは何か」というテーマにも関わる、深い謎を秘めた存在のようだ。世界はいまだ多くの謎に満ちている、と言うしかない。
その謎の一つが中国の武漢で突然変異を起こし、中国から日本を含む周辺国、そして世界に広がった。人々をおののかせ、政治家を悩ませ、世界経済の屋台骨を揺さぶるに至った。
新型コロナウイルスの感染拡大に、それぞれの国はどう対処したのか。それを追っていくと、その国の光と影が炙(あぶ)り出され、見えてくる。
このウイルスの存在に最初に気付いたのは武漢の李文亮(リーウェンリアン)医師たちだった。昨年末、「新しいタイプのコロナウイルスの感染が確認された」として、同僚の医師らにSNS(交流サイト)で患者の症状や肺のCT検査データを伝え、注意を喚起した。
ところが、それがネットで広がると、武漢市の公安局(警察)は「デマを流した」として李医師らを訓戒処分にし、国内メディアも「悪質なデマ」と報じた。処分を受けた後も、彼は患者の治療にあたっていたが、自らもウイルスに感染し、身重の妻を残して33歳で死去した。
亡くなる前、李医師はインタビューに応え、「健全な社会には一つだけでなく、様々な声があるべきだ」と語った。穏やかな表現の中に「自由がない国」への痛烈な批判を読み取ることができる。こうした初期の硬直した対応が中国での感染爆発を引き起こした。
もっとも、初期の失態に気付いた後の中国共産党の対応は「断固たるもの」だった。武漢市全体を封鎖し、全国から医師や看護師を動員して送り込んだ。さらに、軍隊を使って仮設の隔離病棟をたちまち完成させた。
中国には「土地の所有権」というものはない。土地はすべて国家のものであり、個人や企業には利用権が与えられているだけだ。このため、必要になれば、すぐに土地を収用できる。仮設の隔離病棟を短期間で建設できたのも、簡単な手続きで必要な土地を確保できるからだ。
この土地収用の簡便さは「腐敗の温床」の一つになっている。改革開放路線が始まってから、企業が次々に設立され、中国は「世界の工場」と呼ばれるようになったが、その過程で「金もうけに目がくらんだ共産党幹部と起業家」が農民や住民を追い出し、土地を強奪する事件が頻発している。中国にはその不正を告発し、正す自由がない。
腐敗はとめどなく広がり、暴動や流血事件となって噴き出している。その実態を赤裸々に描いたのが『中国の闇 マフィア化する政治』(何清漣、扶桑社)という本だ。著者は米国に逃れ、「共産党幹部が黒社会を束ね、あるいは黒社会の幹部が要職に就いて暴虐の限りを尽くしている」と、実名を挙げて告発している。
その中国での感染拡大はピークを越え、パンデミック(世界的大流行)の震源は欧米に移った。その中でも深刻なのがイタリアである。
新型コロナによるイタリアの死者は3月中旬には中国を上回った。最初の死者が確認されてから3週間余りで3000人を超えており、初期の段階で事態を甘く見て警戒を怠ったことがうかがえる。
医師や看護師が身に付けるマスクや防護服が足りない。肺炎を発症した患者を救うために必要な人工呼吸器も集中治療の設備も不足しているという。初期対応の失敗に加えて、こうした医療体制の脆弱さが事態を悪化させている。
欧州連合(EU)の創設メンバーでありながら、イタリアはずっと「財政の劣等生」として扱われてきた。豊かな北部と貧しい南部、競争力のある一握りの大企業と膨大な数の零細企業、恵まれた公務員と不安定な雇用に甘んじなければならない民衆・・・。イタリアはそうした様々な「二重構造」を抱えながら、政府が借金を重ねてしのいできた。
昨年の6月、欧州委員会は「イタリアの財政状況はEUの基準から逸脱している」として、「制裁手続きに入ることが正当化される」との報告書を公表した。「政府は支出を抑え、増税に踏み切れ」と圧力をかけたのである。それに応えるため、イタリアでは医療や福祉の予算が削られ、医師の国外への流出も起きていた。
新型コロナは、そんな悶え苦しむイタリアを襲った。防護服が足りない病院では透明なゴミ袋を加工して使い、長時間勤務で疲れ切った看護師は机につっぷしたまま寝込んでしまう。そうした映像がネットで流れ、「医療崩壊寸前」と報じられている。
外出を控えて自宅にとどまるよう求められた住民たちは、フェイスブックなどのSNSで「治療に取り組む人たちを励まそう」と呼びかけ始めた。ベランダに一人、また一人と姿を現し、声を合わせて歌い出す様子がテレビで流れた。さすが「芸術と文化の国」である。
人様のことはこれくらいにして、わが国の光と影を考えてみたい。
新型コロナの侵入を水際で食い止めることを目指した初期対応は無残なものだった。横浜港の桟橋に係留された豪華クルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号は「巨大なウイルス培養器」と化してしまった。
厚生労働省が対策の中心になったからである。感染を防止するため、客船には厚労省の職員や災害派遣医療チーム、自衛隊の隊員らが送り込まれたが、指揮系統がバラバラで、厚労省にはそれを統率する力がなく、対応も不適切だった。
薬害エイズの経緯を振り返ってみれば明らかなように、この役所は医療や製薬の権益がからむことには必死で取り組む。けれども、「国民の命と健康を守るために何を為すべきか」を真剣に考える人が少なすぎる。ゆえに、危機に対応する能力がない。
クルーズ船の惨状を見て、安倍晋三首相も腹をくくったのだろう。その後は、厚労省の幹部ではなく、感染症の専門家の意見に耳を傾けるようになった。その専門家の一人、川崎市健康安全研究所長の岡部信彦氏は朝日新聞(3月18日付)のインタビューに応えて、こう語っている。
「私は医療がある程度保たれていれば、致死率はそんなに高くならないのではと思っています。重症になる人ができるだけきちんとした医療を受けられるようにしておくことが大事で、それができれば日本での致死率は1%前後で収まるのではないでしょうか」
「データに基づいて、最終的には一つの方向性を出していかなければならないと考えています。無症状の人からうつったという論文も出てきているので、パーフェクトな『封じ込め』は不可能です。それでも社会活動を止めて『封じ込め』を追求するのか、ある程度の流行を前提に重症者・死亡者数の減少、最小の社会的被害に抑える方向にかじを切るのか」
説得力のある考え方である。新型コロナと普通のインフルエンザの大きな違いは、前者には特効薬がなく、予防のためのワクチンもないことだ。そのため、不安が広がっているが、手立てを講じて感染の爆発を防ぎ、医療体制を維持し続ければ、なんとか乗り切ることができるはずだ。
幸いなことに、私たちの国には献身的な医師や看護師、医療従事者がたくさんいる。介護や福祉の現場も踏ん張っている。彼らを支えつつ、社会的なダメージや経済的な損失をできるだけ小さくするために何を為すべきか。指導者も私たち一人ひとりも、これからそれを問われることになる。
新型コロナで炙り出された「日本の闇」は何か。私は「マスク不足」にそれを感じる。安倍政権は「マスクの増産をお願いしている」「増産する企業には財政的な支援をする」と何度も表明したが、マスクはいまだに不足している。
しかも、政治家は「マスクの増産」は口にするが、「マスクの供給がどうなっているか」については語らない。語れないのだろう。日本の政府にはマスクの供給状況についての信頼できるデータがないのではないか、と疑っている。
日本政府の情報技術(IT)対応は、信じられないほど遅れている。各省庁がバラバラに情報機器とソフトを導入した。それどころか、一つの省庁の中でも部局によってシステムが異なる。情報を共有したくてもできない状況にある。貴重なデータを連携して活用するすべもない。
政府からの補助金に頼って仕事をしてきた都道府県も右ならえ、である。私は「山形県の知事部局のシステム」について情報公開を求めた。その結果、出てきた文書を見て仰天した。78ものシステムがただ羅列してあったからだ。どのシステムを基幹にして、どのような態勢を築くのか。基本構想がまるで分からない。そもそも、構想がないのだろう。
日本と対照的なのが台湾だ。4年前に発足した蔡英文(ツァイインウェン)政権は、「台湾IT十傑」の一人とされる唐鳳(タンフォン)氏をデジタル担当相に抜擢した。当時、35歳。歴代最年少での入閣だった。
この人物が今回の新型コロナ対策で縦横無尽の活躍を見せた。1月末からマスクの管理に乗り出し、どのように流通しているかネットで公開した。民間のアプリを使えば、自分の地域のどの薬局にマスクがあるか、スマホで誰でも見られるようになった。
マスクを配給制にし、住民はICチップ入りの健康保険カードを示せば、確実にマスクを手にすることができる。3月末からは、スマホで予約すればコンビニで受け取れるシステムも動き出す。世界最先端の取り組みと言っていい。
唐鳳氏は「中国と台湾は距離的に近くても価値観は正反対だ」と言う。中国は民衆を監視し、管理するためにITを利用する。これに対し、台湾は政府を監視し、開かれた社会をつくるために活用するのだ、と。「徹底的な透明性」を唱え、理念でも最先端を行く。
わが日本のIT担当相は誰か。大阪選出の竹本直一(なおかず)代議士である。「入閣待望組」の一人で、昨年9月の内閣改造の際、78歳で初めて閣僚になった。最高齢での初入閣だった。
おまけにこの時、竹本氏の公式サイトは「ロックされて閲覧不能」になっていた。記者会見でその理由を問われ、竹本氏は「なぜロックされているのかよく分からない」と答え、失笑を買った。
日本と台湾のIT担当相の、この絶望的なまでの格差。それはそのまま、日本の政治と行政のIT化がいかに絶望的な状況にあるかを示している。次の世代のことを考えると、私にはこちらの方が新型コロナウイルスより、はるかに恐ろしい。
*メールマガジン「風切通信 72」 2020年3月30日
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の2020年4月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎新型コロナウイルス(テレビ朝日のサイト)
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000178040.html
≪参考文献・記事&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎ウィキペディアの「細菌」「古細菌」「真核生物」「ウイルス」
◎コロナウイルスの基礎知識(国立感染症研究所)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/9303-coronavirus.html
◎ウィキペディアの「李文亮」
◎李文亮の名言「今週の防災格言634」
https://shisokuyubi.com/bousai-kakugen/index-795
◎『中国の闇 マフィア化する政治』(何清漣、扶桑社)
◎「イタリア制裁手続き入り『正当化』」(日本経済新聞2019年6月5日)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45727360V00C19A6FF2000/
◎「イタリア財政危機の構造と制度改革」(経済企画庁経済研究所)
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun094/bun94a.pdf
◎「新型コロナ 緊急事態宣言は必要か」(朝日新聞2020年3月18日付)
◎ウィキペディアの「唐鳳」「竹本直一」
◎Wikipedia 「Audrey Tang」
https://en.wikipedia.org/wiki/Audrey_Tang
◎「台湾のコロナ政策 奏功」(朝日新聞2020年3月7日付)
◎「パンデミック 世界はいま」(朝日新聞2020年3月21日付)
◎月刊『選択』2020年3月号の新型コロナ関連記事
あの日から、間もなく9年になる。
海が黒い壁となって押し寄せ、あまたの命をのみ込んでいった。目に見えない放射能にさらされ、多くの人が住み慣れた土地を追われた。

先の戦争が終わった8月15日を節目に「戦前」「戦後」と言うように、東日本大震災があった3月11日を境にして「災前」「災後」と呼ぶようになるのではないか。誰かがそんなことを書いていた。あの大震災は、そうなってもおかしくないほど強烈なインパクトを私たちの社会に与えた。
けれども、そうはならなかった。福島の原発事故では原子炉がメルトダウンして放射性物質をまき散らし、首都圏を含む東日本全体が人の住めない土地になる恐れもあった。それを免れることができたのは、いくつかの幸運が重なったからに過ぎない。なのに、政府も電力業界も素知らぬ顔で原発の再稼働を推し進めようとしている。
大震災の前と変わらない日々。災いから教訓を汲(く)み取り、それを活かして新しい道を切り拓く。それがなぜ、できないのか。
津波に目を向ければ、石巻市の大川小学校の悲劇がある。
学校に残っていた78人の子どものうち74人、教職員11人のうち10人が亡くなった。被災地にあったすべての小中学校で教員の統率下にあった子どものうち、命を落としたのは大川小学校以外では南三陸町の1人しかいない。高台に逃げる途中で波にのまれたケースだ。こうした事実は、この小学校で「考えられないような過ち」がいくつも重なったことを示している。
にもかかわらず、石巻市も宮城県も過ちを認めようとせず、言い逃れと責任回避に終始した。子どもを亡くした親たちが裁判に訴え、最高裁判所が昨年10月に石巻市と宮城県に損害賠償を命じるまで「津波の襲来は予見できなかった。過失はなかった」と言い続けた。
責任逃れをしただけではない。当事者がウソをつき、事実を隠蔽した。それが、子どもを失って打ちひしがれた親たちの心をどれほど苛(さいな)んだことか。
数々のウソの中で最もひどいのは、教職員で唯一生き残った遠藤純二・教務主任のウソである。大川小の子どもたちは北上川沿いの高台に向かう途中で津波にのまれたが、列の最後尾にいた遠藤教諭は学校の裏山に登って助かった。
イギリス人ジャーナリスト、リチャード・ロイド・パリー氏の著書『津波の霊たち 3・11 死と生の物語』(早川書房)によれば、被災から4週間後に開かれた保護者向けの説明会で、遠藤教諭は次のように語った。
「山の斜面についたときに杉の木が2本倒れてきて、私は右側の腕のところと左の肩のところにちょうど杉の木が倒れて、はさまる形になりました。その瞬間に波をかぶって、もう駄目だと思ったんですが、波が来たせいかちょっと体が、木が軽くなって、そのときに斜面の上を見たら、数メートル先のところに3年生の男の子が助けを求めて叫んでいました。(中略)絶対にこの子を助けなきゃいけないと思って、とにかく『死んだ気で上に行け』と叫びながら、その子を押し上げるようにして、斜面の上に必死で登っていきました」
この証言の中に、いくつものウソがあった。学校の裏山の杉の木は1本も倒れていなかった。遠藤教諭は「波をかぶった」と言ったが、彼が男の子を連れて助けを求めた民家の千葉正彦さんと妻はそろって「服は濡れていなかった」と明言した。
唯一生き残った教員がなぜ、ウソをつかなければならなかったのか。記憶が混濁していただけなのか。彼はその後の裁判でも、「精神を病んでいる」として証言に立つことはなかった。虚偽の事実を並べ立てた理由は、いまだに分からない。
大川小の子どもの中には、学校に迎えに来た親と帰ったため難を逃れた子もいる。そうした子どもの1人は、6年生の男の子が「先生、山さ上がっぺ。ここにいたら地割れして地面の底に落ちていく。おれたち、ここにいたら死ぬべや!」と訴えていたのを覚えていた。
石巻市の教育委員会は被災後、生き残った子どもたちからも事情を聴き、記録した。ところが、公表した記録にはこうした証言が収録されていなかった。それどころか、保護者たちが事情聴取のメモの開示を求めたところ、「メモはすべて廃棄した」と答えた。
学校や教育委員会の過失とみなされるような証拠を隠蔽したのである。メモを廃棄した指導主事は翌年、小学校の校長に昇進した。「組織を守るために力を尽くした」ということなのだろう。
大川小学校の悲劇については、ジャーナリストの池上正樹、加藤順子両氏による『あのとき、大川小学校で何が起きたのか』(青志社)など優れた本がいくつか出版されているが、取材の広さと深さという点で、リチャード・ロイド・パリー氏の著書は群を抜いている。
パリー氏が初めて日本を訪れたのは高校生の時である。クイズ番組で優勝し、そのご褒美が日本旅行だった。オックスフォード大学で学んだ後、イギリスの新聞の東京特派員になった。震災の時点で在日16年。日本の内情についても、地震についても熟知していた。
この本を書くために、彼は6年の歳月を費やした。インタビューするたびに遺族は涙を流した。「どうしてこの人たちを泣かせなければならないのか」と苦しんだという。それでも、意を決して彼らの声に耳を傾け続けた。
子どもをすべて奪われた親がいた。子どもだけでなく、家族全員が亡くなった人もいる。遺体がすぐに見つかった親もいれば、いつまでたっても見つからない親もいた。遺体を見つけるために重機の免許を取って探し続けた母親もいる。命の数だけ深い悲しみと苦悩があった。
遺族の中には石巻市と教育委員会の対応に納得できず、「一生かげで、死んだがきどもの敵(かだぎ)とってやっからな」と怒りをぶつける者もいた。裁判で責任を追及しようとする親もいれば、それに反発する親たちもいた。
苦悩に打ちのめされた親の中には、死んだ者の霊を自分の身体に乗り移らせて、その言葉を語る「口寄せ」の女性に頼る人も出てきた。日本のジャーナリストはまず、こういう話を取材しようとしない。だが、パリー氏はそこにも分け入っていく。それが大川小学校の周りで起きたことの一つだからだ。
被災地では「幽霊を見た」という話がささやかれるようになった。そうした中で、津波が到達せず、まったく被害を受けなかった家族が10日後、車で山を越えて被災地を見に行った。その晩から、男性の様子がおかしくなった。
彼は飛び上がって四つん這いになり、畳と布団をなめ、獣のように身をよじらせて叫んだ。「死ね、死ね、みんな死んで消えてしまえ」。奇行は何日も続き、妻は知り合いの住職に除霊を依頼した。
般若心経を唱えて霊を取り除いた住職は次のように語った。
「彼は被災地の浜辺を、アイスクリームを食べながら歩いたと言っていました。多くの人が亡くなったような場所に行くなら、畏敬の念をもって行かなければいけません」「自分の行動に対して、ある種の罰を受けたんです。何かがあなたに取り憑(つ)いた。おそらくは、死を受け容れることができない死者の霊でしょう」
こうしたことも、被災地で起きたことの一つとして書き留めた。
避難所での経験にも触れている。取材するパリー氏に対して、避難した人たちはしばしば食べ物を分け与えようとした。「次の数日、あるいは次の数時間のための食べ物しか持たないはずの避難者たちが、私に食べ物を渡そうとした。つい最近、家を失ったばかりの人々が、おもてなしが不充分であることを心からすまなそうに謝った」
「これこそが日本の最高の姿ではないかと感じた。このような広大無辺な慈悲の心こそ、私がこの国についてもっとも愛し、賞賛することの一つだった。日本の共同体の強さは、現実的で、自然発生的で、揺るぎないものだった」
そして同時に、東北の哀しみについても書く。
「東北地方の住人たちは、とりわけ我慢強いことで有名だった。だからこそ、彼らは何世紀にもわたって寒さ、貧困、不安定な収穫に耐えることができた。歴史的に中央政府が損な役回りを彼らに押しつけてきたのも、その我慢強さゆえのことかもしれない。東北地方では、娘たちを身売りし、息子たちを帝国軍の捨て駒として送り出すのが珍しいことではなかった」
「人々は文句も言わずに黙々と働いた。そうやって黙り込むことがなにより大切だった。(中略)住人たちは変化することを拒み、変化するための努力を拒んだ。理想的な村社会とは、対立が不道徳とみなされる世界だった」
震災の後、被災地でも私たちが暮らす山形でも「がんばろう東北」という標語をよく目にした。その言葉に共感しながらも、私はどこか引っかかるものを覚えていた。それが何なのか、自分でも理解できなかったが、パリー氏の著書を読んで、腑に落ちた。
そうなのだ。我慢することは大切だ。黙り込むことも時には必要だ。けれども、それをやめなければならない時、というのがあるのではないか。
黙り込むことによって、この山形では、地元の新聞とその企業グループがすべてを支配し、逆らう者を許さないという状態が何十年も続いた。逆らえば暮らしていけない、という状況を生み出し、それを多くの県民が黙認した。
そして、それがようやく終わったと思ったら、今度は吉村美栄子知事の権勢を背に、吉村一族の企業グループがのさばり始めた。政治家も経済人もメディアも、それに異を唱えようとしない。
何をしなければならないのか。その答えも、パリー氏の著書に見出すことができる。彼は「日本人の受容の精神にはもううんざりだ」としたため、次のように語りかけている。
「日本にいま必要なのは、(石巻市の責任を追及した)紫桃(しとう)さん夫妻、只野(ただの)さん親子、鈴木さん夫妻のような人たちだ。怒りに満ち、批判的で、決然とした人々。死の真相を追い求める闘いが負け戦になろうとも、自らの地位や立場に関係なく立ち上がって闘う人々なのだ」
*メールマガジン「風切通信 71」 2020年2月28日
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の2020年3月号に寄稿した文章を転載したものです。
≪写真説明&Source≫
◎震災から5年後の大川小学校
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/photos/160326/lif16032609230004-p1.html
海が黒い壁となって押し寄せ、あまたの命をのみ込んでいった。目に見えない放射能にさらされ、多くの人が住み慣れた土地を追われた。

先の戦争が終わった8月15日を節目に「戦前」「戦後」と言うように、東日本大震災があった3月11日を境にして「災前」「災後」と呼ぶようになるのではないか。誰かがそんなことを書いていた。あの大震災は、そうなってもおかしくないほど強烈なインパクトを私たちの社会に与えた。
けれども、そうはならなかった。福島の原発事故では原子炉がメルトダウンして放射性物質をまき散らし、首都圏を含む東日本全体が人の住めない土地になる恐れもあった。それを免れることができたのは、いくつかの幸運が重なったからに過ぎない。なのに、政府も電力業界も素知らぬ顔で原発の再稼働を推し進めようとしている。
大震災の前と変わらない日々。災いから教訓を汲(く)み取り、それを活かして新しい道を切り拓く。それがなぜ、できないのか。
津波に目を向ければ、石巻市の大川小学校の悲劇がある。
学校に残っていた78人の子どものうち74人、教職員11人のうち10人が亡くなった。被災地にあったすべての小中学校で教員の統率下にあった子どものうち、命を落としたのは大川小学校以外では南三陸町の1人しかいない。高台に逃げる途中で波にのまれたケースだ。こうした事実は、この小学校で「考えられないような過ち」がいくつも重なったことを示している。
にもかかわらず、石巻市も宮城県も過ちを認めようとせず、言い逃れと責任回避に終始した。子どもを亡くした親たちが裁判に訴え、最高裁判所が昨年10月に石巻市と宮城県に損害賠償を命じるまで「津波の襲来は予見できなかった。過失はなかった」と言い続けた。
責任逃れをしただけではない。当事者がウソをつき、事実を隠蔽した。それが、子どもを失って打ちひしがれた親たちの心をどれほど苛(さいな)んだことか。
数々のウソの中で最もひどいのは、教職員で唯一生き残った遠藤純二・教務主任のウソである。大川小の子どもたちは北上川沿いの高台に向かう途中で津波にのまれたが、列の最後尾にいた遠藤教諭は学校の裏山に登って助かった。
イギリス人ジャーナリスト、リチャード・ロイド・パリー氏の著書『津波の霊たち 3・11 死と生の物語』(早川書房)によれば、被災から4週間後に開かれた保護者向けの説明会で、遠藤教諭は次のように語った。
「山の斜面についたときに杉の木が2本倒れてきて、私は右側の腕のところと左の肩のところにちょうど杉の木が倒れて、はさまる形になりました。その瞬間に波をかぶって、もう駄目だと思ったんですが、波が来たせいかちょっと体が、木が軽くなって、そのときに斜面の上を見たら、数メートル先のところに3年生の男の子が助けを求めて叫んでいました。(中略)絶対にこの子を助けなきゃいけないと思って、とにかく『死んだ気で上に行け』と叫びながら、その子を押し上げるようにして、斜面の上に必死で登っていきました」
この証言の中に、いくつものウソがあった。学校の裏山の杉の木は1本も倒れていなかった。遠藤教諭は「波をかぶった」と言ったが、彼が男の子を連れて助けを求めた民家の千葉正彦さんと妻はそろって「服は濡れていなかった」と明言した。
唯一生き残った教員がなぜ、ウソをつかなければならなかったのか。記憶が混濁していただけなのか。彼はその後の裁判でも、「精神を病んでいる」として証言に立つことはなかった。虚偽の事実を並べ立てた理由は、いまだに分からない。
大川小の子どもの中には、学校に迎えに来た親と帰ったため難を逃れた子もいる。そうした子どもの1人は、6年生の男の子が「先生、山さ上がっぺ。ここにいたら地割れして地面の底に落ちていく。おれたち、ここにいたら死ぬべや!」と訴えていたのを覚えていた。
石巻市の教育委員会は被災後、生き残った子どもたちからも事情を聴き、記録した。ところが、公表した記録にはこうした証言が収録されていなかった。それどころか、保護者たちが事情聴取のメモの開示を求めたところ、「メモはすべて廃棄した」と答えた。
学校や教育委員会の過失とみなされるような証拠を隠蔽したのである。メモを廃棄した指導主事は翌年、小学校の校長に昇進した。「組織を守るために力を尽くした」ということなのだろう。
大川小学校の悲劇については、ジャーナリストの池上正樹、加藤順子両氏による『あのとき、大川小学校で何が起きたのか』(青志社)など優れた本がいくつか出版されているが、取材の広さと深さという点で、リチャード・ロイド・パリー氏の著書は群を抜いている。
パリー氏が初めて日本を訪れたのは高校生の時である。クイズ番組で優勝し、そのご褒美が日本旅行だった。オックスフォード大学で学んだ後、イギリスの新聞の東京特派員になった。震災の時点で在日16年。日本の内情についても、地震についても熟知していた。
この本を書くために、彼は6年の歳月を費やした。インタビューするたびに遺族は涙を流した。「どうしてこの人たちを泣かせなければならないのか」と苦しんだという。それでも、意を決して彼らの声に耳を傾け続けた。
子どもをすべて奪われた親がいた。子どもだけでなく、家族全員が亡くなった人もいる。遺体がすぐに見つかった親もいれば、いつまでたっても見つからない親もいた。遺体を見つけるために重機の免許を取って探し続けた母親もいる。命の数だけ深い悲しみと苦悩があった。
遺族の中には石巻市と教育委員会の対応に納得できず、「一生かげで、死んだがきどもの敵(かだぎ)とってやっからな」と怒りをぶつける者もいた。裁判で責任を追及しようとする親もいれば、それに反発する親たちもいた。
苦悩に打ちのめされた親の中には、死んだ者の霊を自分の身体に乗り移らせて、その言葉を語る「口寄せ」の女性に頼る人も出てきた。日本のジャーナリストはまず、こういう話を取材しようとしない。だが、パリー氏はそこにも分け入っていく。それが大川小学校の周りで起きたことの一つだからだ。
被災地では「幽霊を見た」という話がささやかれるようになった。そうした中で、津波が到達せず、まったく被害を受けなかった家族が10日後、車で山を越えて被災地を見に行った。その晩から、男性の様子がおかしくなった。
彼は飛び上がって四つん這いになり、畳と布団をなめ、獣のように身をよじらせて叫んだ。「死ね、死ね、みんな死んで消えてしまえ」。奇行は何日も続き、妻は知り合いの住職に除霊を依頼した。
般若心経を唱えて霊を取り除いた住職は次のように語った。
「彼は被災地の浜辺を、アイスクリームを食べながら歩いたと言っていました。多くの人が亡くなったような場所に行くなら、畏敬の念をもって行かなければいけません」「自分の行動に対して、ある種の罰を受けたんです。何かがあなたに取り憑(つ)いた。おそらくは、死を受け容れることができない死者の霊でしょう」
こうしたことも、被災地で起きたことの一つとして書き留めた。
避難所での経験にも触れている。取材するパリー氏に対して、避難した人たちはしばしば食べ物を分け与えようとした。「次の数日、あるいは次の数時間のための食べ物しか持たないはずの避難者たちが、私に食べ物を渡そうとした。つい最近、家を失ったばかりの人々が、おもてなしが不充分であることを心からすまなそうに謝った」
「これこそが日本の最高の姿ではないかと感じた。このような広大無辺な慈悲の心こそ、私がこの国についてもっとも愛し、賞賛することの一つだった。日本の共同体の強さは、現実的で、自然発生的で、揺るぎないものだった」
そして同時に、東北の哀しみについても書く。
「東北地方の住人たちは、とりわけ我慢強いことで有名だった。だからこそ、彼らは何世紀にもわたって寒さ、貧困、不安定な収穫に耐えることができた。歴史的に中央政府が損な役回りを彼らに押しつけてきたのも、その我慢強さゆえのことかもしれない。東北地方では、娘たちを身売りし、息子たちを帝国軍の捨て駒として送り出すのが珍しいことではなかった」
「人々は文句も言わずに黙々と働いた。そうやって黙り込むことがなにより大切だった。(中略)住人たちは変化することを拒み、変化するための努力を拒んだ。理想的な村社会とは、対立が不道徳とみなされる世界だった」
震災の後、被災地でも私たちが暮らす山形でも「がんばろう東北」という標語をよく目にした。その言葉に共感しながらも、私はどこか引っかかるものを覚えていた。それが何なのか、自分でも理解できなかったが、パリー氏の著書を読んで、腑に落ちた。
そうなのだ。我慢することは大切だ。黙り込むことも時には必要だ。けれども、それをやめなければならない時、というのがあるのではないか。
黙り込むことによって、この山形では、地元の新聞とその企業グループがすべてを支配し、逆らう者を許さないという状態が何十年も続いた。逆らえば暮らしていけない、という状況を生み出し、それを多くの県民が黙認した。
そして、それがようやく終わったと思ったら、今度は吉村美栄子知事の権勢を背に、吉村一族の企業グループがのさばり始めた。政治家も経済人もメディアも、それに異を唱えようとしない。
何をしなければならないのか。その答えも、パリー氏の著書に見出すことができる。彼は「日本人の受容の精神にはもううんざりだ」としたため、次のように語りかけている。
「日本にいま必要なのは、(石巻市の責任を追及した)紫桃(しとう)さん夫妻、只野(ただの)さん親子、鈴木さん夫妻のような人たちだ。怒りに満ち、批判的で、決然とした人々。死の真相を追い求める闘いが負け戦になろうとも、自らの地位や立場に関係なく立ち上がって闘う人々なのだ」
*メールマガジン「風切通信 71」 2020年2月28日
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の2020年3月号に寄稿した文章を転載したものです。
≪写真説明&Source≫
◎震災から5年後の大川小学校
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/photos/160326/lif16032609230004-p1.html
「憧れの対象」だった豪華クルーズ船は昨今、「浮かぶ隔離病棟」のような目で見られるようになってしまった。横浜港に停泊中のダイヤモンド・プリンセス号の乗客から、また新型コロナウイルスの感染者が見つかり、患者が61人になったという。日本国内で確認された感染者は計86人なので、なんと7割がこの豪華客船に乗っていた人ということになる。

客船という外界から隔絶された空間は、「ウイルスが効率よく拡散する空間」でもあることを図らずも立証する形になった。乗り合わせた人たちは不運とあきらめ、潜伏期間が過ぎ去るのを待つしかない。
私も隔離病棟に収容されたことがある。1989年の春、ソ連軍撤退後のアフガニスタンを取材するため、首都カブールで過ごし、その後、パキスタンのペシャワル周辺で難民の取材をした。この時に赤痢にかかったようで、帰国の航空機内で発症した。
成田空港で症状を申告し、検体を提出したところ、数日後に保健所からお迎えが来た。お漏らしをしても大丈夫なようにだろう。車の座席にはビニールシートが張られ、そのまま東京都内の隔離病棟に入院となった。残された家族は、私の衣類の焼却やら食器の消毒やら大変だったという。
帰国してすぐに抗生物質を飲んでいたので、私は症状も軽くなり、いたって元気だった。それでも体内にはまだ赤痢菌が残っており、完全になくなるまで10日間ほど強制隔離された。当時はまだ伝染病予防法という法律があり、赤痢も法定伝染病の一つだった。治療にあたった医師は「赤痢なんて、今じゃ怖い病気じゃないんだけどね」と気の毒がってくれた。
隔離病棟は木造の古い建物で、入院しているのは私一人。貸切だった。入院時にはいていたパンツなどの下着は没収されて焼却。代わりに「お上のパンツ」を支給された。お風呂も変わった作りだった。煙突のようなものが天井から吊り下げられ、浴槽に差し込んである。上から高温の水蒸気を送り込み、水の中でブクブクと泡立てて沸かすようになっていた。使ったお湯も滅菌する、と聞いた。
入院したのは5月末から6月初めで、世界は天安門事件で大騒ぎになっていた。入院患者はひまである。出張の整理をしながら、看護師に頼んで売店から新聞を買ってきてもらい、各紙を熟読した。朝日新聞の報道が一番、冴えなかった。退院後、出社して報道に加わり、その理由が分かった。
当時の朝日新聞北京支局の特派員は2人とも書斎派で、銃弾飛び交う天安門広場に行こうとしない。最新の衛星電話を装備していた社もあったが、朝日新聞にはそれもなかった。「現場に行って、見たことをそのまま書く」という基本ができていないのだから、いい紙面を作れるはずもなかった。
では、どうしたのか。東京編集局の外報部にいる記者を総動員して、足りないところを補ったのである。当時は、東京から国際電話をかけて北京市民の話を聞く、といったことはできなかった。やむなく、ロイターやAFP、AP通信が北京から報じる内容や香港情報を拾い集めてしのいだのである。冴えない紙面になるはずだ。
この経験が「国際報道であっても、新聞記者の基本は国内と何も変わらない。現場に足を運んで自分の目で見たこと、感じたことをきちんと書くしかない」と肝に銘じるきっかけになった。
1992年にニューデリー駐在になり、インド亜大陸を一人でカバーした(今は複数の記者がいる)。3年目にインドでペストが蔓延する事件があった。中世にペスト禍を経験している欧州各国は即座に定期便の運航をやめた。外国人の多くが国外に逃げ出した。
記事を送りながら、すぐに「ペストはどのくらい怖いのか」を調べ始めた。その結果、肺ペストの場合、感染力はインフルエンザと同じ程度でマスクをしても完全には防げないこと、ただし、今ではテトラサイクリン系の特効薬があるため、服用すれば死亡するリスクはほとんどないことが分かった。家族とスタッフ用に特効薬を確保した。
事件の現場に肉薄するのが取材の基本だ。インドでペストが最初に発生したのは北西部のスーラットという街である。ダイヤモンド加工が盛んで、出稼ぎ労働者がたくさんいた。彼らが逃げ出して帰郷したため、あっという間にインド全土にペストが広まってしまったのだった。
感染の拡大を抑えるため、世界保健機関(WHO)の専門家がインドに乗り込んできた。小型機でスーラットに向かうというので同乗させてもらい、現地に行った。ペスト患者の隔離病棟を視察して驚いた。患者は個室ではなく、大部屋のベッドで寝ていた。
それを見て回ったのだから、マスクはしていても、WHOの幹部も私を含む報道陣も感染した可能性が高い。特効薬を持参しているとはいえ、あまり気持ちのいいものではない。急いで東京に原稿を吹き込み、薬をゴクンと飲み込んだ。幸い、何の症状も出なかった。
今回の新型コロナウイルスが怖いのは、特効薬もワクチンもまだないからだ。患者総数に対する死者の割合、いわゆる致死率も2%前後と小さくはない。みんながマスクと消毒用アルコールの買いだめに走るのも無理はない。
疫病の歴史を振り返れば、さまざまな手段を講じても疫病を完全に封じ込めることはできない、ということが分かる。人間にできるのは、広がるスピードを抑えることだけだ。
中世のペスト禍では、人々は田園に逃げた。都市の雑踏が怖かったからだ。新型コロナウイルスでも、最良の方法はとりあえず田舎に避難することかもしれない。少なくとも、豪華客船よりは、ずっと安全だ。
*メールマガジン「風切通信 70」 2020年2月8日
≪写真説明&Source≫
多くの感染者が出たダイヤモンド・プリンセス号
http://www.at-s.com/event/article/kids/570843.html

客船という外界から隔絶された空間は、「ウイルスが効率よく拡散する空間」でもあることを図らずも立証する形になった。乗り合わせた人たちは不運とあきらめ、潜伏期間が過ぎ去るのを待つしかない。
私も隔離病棟に収容されたことがある。1989年の春、ソ連軍撤退後のアフガニスタンを取材するため、首都カブールで過ごし、その後、パキスタンのペシャワル周辺で難民の取材をした。この時に赤痢にかかったようで、帰国の航空機内で発症した。
成田空港で症状を申告し、検体を提出したところ、数日後に保健所からお迎えが来た。お漏らしをしても大丈夫なようにだろう。車の座席にはビニールシートが張られ、そのまま東京都内の隔離病棟に入院となった。残された家族は、私の衣類の焼却やら食器の消毒やら大変だったという。
帰国してすぐに抗生物質を飲んでいたので、私は症状も軽くなり、いたって元気だった。それでも体内にはまだ赤痢菌が残っており、完全になくなるまで10日間ほど強制隔離された。当時はまだ伝染病予防法という法律があり、赤痢も法定伝染病の一つだった。治療にあたった医師は「赤痢なんて、今じゃ怖い病気じゃないんだけどね」と気の毒がってくれた。
隔離病棟は木造の古い建物で、入院しているのは私一人。貸切だった。入院時にはいていたパンツなどの下着は没収されて焼却。代わりに「お上のパンツ」を支給された。お風呂も変わった作りだった。煙突のようなものが天井から吊り下げられ、浴槽に差し込んである。上から高温の水蒸気を送り込み、水の中でブクブクと泡立てて沸かすようになっていた。使ったお湯も滅菌する、と聞いた。
入院したのは5月末から6月初めで、世界は天安門事件で大騒ぎになっていた。入院患者はひまである。出張の整理をしながら、看護師に頼んで売店から新聞を買ってきてもらい、各紙を熟読した。朝日新聞の報道が一番、冴えなかった。退院後、出社して報道に加わり、その理由が分かった。
当時の朝日新聞北京支局の特派員は2人とも書斎派で、銃弾飛び交う天安門広場に行こうとしない。最新の衛星電話を装備していた社もあったが、朝日新聞にはそれもなかった。「現場に行って、見たことをそのまま書く」という基本ができていないのだから、いい紙面を作れるはずもなかった。
では、どうしたのか。東京編集局の外報部にいる記者を総動員して、足りないところを補ったのである。当時は、東京から国際電話をかけて北京市民の話を聞く、といったことはできなかった。やむなく、ロイターやAFP、AP通信が北京から報じる内容や香港情報を拾い集めてしのいだのである。冴えない紙面になるはずだ。
この経験が「国際報道であっても、新聞記者の基本は国内と何も変わらない。現場に足を運んで自分の目で見たこと、感じたことをきちんと書くしかない」と肝に銘じるきっかけになった。
1992年にニューデリー駐在になり、インド亜大陸を一人でカバーした(今は複数の記者がいる)。3年目にインドでペストが蔓延する事件があった。中世にペスト禍を経験している欧州各国は即座に定期便の運航をやめた。外国人の多くが国外に逃げ出した。
記事を送りながら、すぐに「ペストはどのくらい怖いのか」を調べ始めた。その結果、肺ペストの場合、感染力はインフルエンザと同じ程度でマスクをしても完全には防げないこと、ただし、今ではテトラサイクリン系の特効薬があるため、服用すれば死亡するリスクはほとんどないことが分かった。家族とスタッフ用に特効薬を確保した。
事件の現場に肉薄するのが取材の基本だ。インドでペストが最初に発生したのは北西部のスーラットという街である。ダイヤモンド加工が盛んで、出稼ぎ労働者がたくさんいた。彼らが逃げ出して帰郷したため、あっという間にインド全土にペストが広まってしまったのだった。
感染の拡大を抑えるため、世界保健機関(WHO)の専門家がインドに乗り込んできた。小型機でスーラットに向かうというので同乗させてもらい、現地に行った。ペスト患者の隔離病棟を視察して驚いた。患者は個室ではなく、大部屋のベッドで寝ていた。
それを見て回ったのだから、マスクはしていても、WHOの幹部も私を含む報道陣も感染した可能性が高い。特効薬を持参しているとはいえ、あまり気持ちのいいものではない。急いで東京に原稿を吹き込み、薬をゴクンと飲み込んだ。幸い、何の症状も出なかった。
今回の新型コロナウイルスが怖いのは、特効薬もワクチンもまだないからだ。患者総数に対する死者の割合、いわゆる致死率も2%前後と小さくはない。みんながマスクと消毒用アルコールの買いだめに走るのも無理はない。
疫病の歴史を振り返れば、さまざまな手段を講じても疫病を完全に封じ込めることはできない、ということが分かる。人間にできるのは、広がるスピードを抑えることだけだ。
中世のペスト禍では、人々は田園に逃げた。都市の雑踏が怖かったからだ。新型コロナウイルスでも、最良の方法はとりあえず田舎に避難することかもしれない。少なくとも、豪華客船よりは、ずっと安全だ。
*メールマガジン「風切通信 70」 2020年2月8日
≪写真説明&Source≫
多くの感染者が出たダイヤモンド・プリンセス号
http://www.at-s.com/event/article/kids/570843.html
2月に入ったのに、里山にも田畑にも雪がない。私が暮らしている村は山形・新潟県境の豪雪地帯にあり、例年ならこの時期、1メートルを超える雪に埋もれる。「そろそろ、屋根の雪下ろしをしないといけないね」と心配する時期だ。なのに、積雪ゼロ。

村の古老に聞けば、口をそろえて「こだな冬は初めでだ」と言う。朝晩、寒さを覚えることはあるが、「凍りつくような寒さ」はまだ一度もない。雪かきをしなくても済むので、それは嬉しいのだが、なんだか落ち着かない。
スキー場は雪不足に苦しみ、雪祭りの関係者はあせっている。ついには「雪乞い」の神事を執り行うところまで出てきた。1月末から2月初めに「やまがた雪フェスティバル」を開催した寒河江(さがえ)市の実行委員会である。
雪像をつくるための雪は、月山の麓から運んでなんとか確保したが、肝心の会場にまったく雪がない。これでは、予定していた雪掘り競争もソリ遊びもできない。困り果てて、祭りの2週間前に地元の寒河江八幡宮に「雪乞い」を依頼した。
頼まれた八幡宮も困った。「雨乞い」ならともかく、「雪乞い」など聞いたこともない。宮司代務者の鬼海(きかい)智美さんは、そもそも「雪乞い」をすることに躊躇を覚えた。「雪が少なくて、助かっている人も多い。産土(うぶすな)の神に『あまねく雪を降らせたまえ』とはお願いできないのです」と言う。
そこで「雪祭りの成功を願い、雪像をつくる人たちの安全を祈願する」ということで引き受けた。雪については「必要なところに降らせたまえ」と控えめにお願いするにとどめた。地元の人たちの暮らしに目配りした、心優しい祈願だった。
にもかかわらず、その後も雪はほとんど降らない。住民の多くは「雪がなくて助かるねぇ」と喜んでいるが、あまり声高には言わない。リンゴやサクランボを栽培している農家がこの異変に気をもんでいる。それを知っているからだ。
「寒さをグッとこらえ、それをバネにして果樹は甘い実を付ける。こんな冬だと、甘味が足りなくなるのではないか」「春先、早く芽を出して、霜にやられたりしないだろうか」。果樹農家の不安は尽きない。
雪祭りにとどまらず、冬の観光全体にも影響が出ている。樹氷で知られる蔵王温泉は、やはり例年より客が少ないという。スキーを楽しむことはできるのだが、シンボルの樹氷がやせ細って元気がない。そこに、中国発の新型コロナウイルスによる肺炎が重なった。老舗旅館の女将は「蔵王は台湾からのお客様が多いんです。旅行を控える動きが広がっているようで、キャンセルが出始めました。ダブルパンチです」と嘆く。
やはり、冬は冬らしく、銀世界が広がってほしい。雪かきはしんどいけれども、降り積もる雪は少しずつ解けて、春から夏まで大地を潤す。北国にとっては恵みでもある。「雪乞い」をしなければならないような冬はつらい。
*メールマガジン「風切通信 69」 2020年2月3日
≪写真説明&Source≫
◎やまがた雪フェスティバルの会場で行われた「雪乞い」
https://www.fnn.jp/posts/7392SAY

村の古老に聞けば、口をそろえて「こだな冬は初めでだ」と言う。朝晩、寒さを覚えることはあるが、「凍りつくような寒さ」はまだ一度もない。雪かきをしなくても済むので、それは嬉しいのだが、なんだか落ち着かない。
スキー場は雪不足に苦しみ、雪祭りの関係者はあせっている。ついには「雪乞い」の神事を執り行うところまで出てきた。1月末から2月初めに「やまがた雪フェスティバル」を開催した寒河江(さがえ)市の実行委員会である。
雪像をつくるための雪は、月山の麓から運んでなんとか確保したが、肝心の会場にまったく雪がない。これでは、予定していた雪掘り競争もソリ遊びもできない。困り果てて、祭りの2週間前に地元の寒河江八幡宮に「雪乞い」を依頼した。
頼まれた八幡宮も困った。「雨乞い」ならともかく、「雪乞い」など聞いたこともない。宮司代務者の鬼海(きかい)智美さんは、そもそも「雪乞い」をすることに躊躇を覚えた。「雪が少なくて、助かっている人も多い。産土(うぶすな)の神に『あまねく雪を降らせたまえ』とはお願いできないのです」と言う。
そこで「雪祭りの成功を願い、雪像をつくる人たちの安全を祈願する」ということで引き受けた。雪については「必要なところに降らせたまえ」と控えめにお願いするにとどめた。地元の人たちの暮らしに目配りした、心優しい祈願だった。
にもかかわらず、その後も雪はほとんど降らない。住民の多くは「雪がなくて助かるねぇ」と喜んでいるが、あまり声高には言わない。リンゴやサクランボを栽培している農家がこの異変に気をもんでいる。それを知っているからだ。
「寒さをグッとこらえ、それをバネにして果樹は甘い実を付ける。こんな冬だと、甘味が足りなくなるのではないか」「春先、早く芽を出して、霜にやられたりしないだろうか」。果樹農家の不安は尽きない。
雪祭りにとどまらず、冬の観光全体にも影響が出ている。樹氷で知られる蔵王温泉は、やはり例年より客が少ないという。スキーを楽しむことはできるのだが、シンボルの樹氷がやせ細って元気がない。そこに、中国発の新型コロナウイルスによる肺炎が重なった。老舗旅館の女将は「蔵王は台湾からのお客様が多いんです。旅行を控える動きが広がっているようで、キャンセルが出始めました。ダブルパンチです」と嘆く。
やはり、冬は冬らしく、銀世界が広がってほしい。雪かきはしんどいけれども、降り積もる雪は少しずつ解けて、春から夏まで大地を潤す。北国にとっては恵みでもある。「雪乞い」をしなければならないような冬はつらい。
*メールマガジン「風切通信 69」 2020年2月3日
≪写真説明&Source≫
◎やまがた雪フェスティバルの会場で行われた「雪乞い」
https://www.fnn.jp/posts/7392SAY
政治家や官僚と癒着して利益をむさぼる商人のことを世間では「政商」と呼ぶ。この言葉を聞いて私が思い浮かべるのは、児玉誉士夫(よしお)と小佐野賢治の2人である。ともに、田中角栄元首相がロッキード社の航空機の売り込みにからんで、首相在任中に5億円の賄賂を受け取ったとして逮捕、起訴された「ロッキード疑獄」で名を馳せた。

児玉は福島県、小佐野は山梨県の生まれである。2人とも極貧の家に生まれた。子どものころ、児玉は父親と掘っ立て小屋で暮らし、小佐野に至っては家すらなく、村の寺の軒先で夜露をしのいだと伝わる。その生い立ちを抜きにして、2人の壮絶な人生は語れない。
児玉は戦前、右翼の活動家になり、笹川良一の紹介で海軍航空本部の嘱託(佐官待遇)になる。上海を拠点に航空機の生産に欠かせないタングステンやニッケルなど戦略物資の調達にあたった。アヘンの密売に手を染め、その収益と軍費で物資を買い集めたという。
敗戦の直前、児玉はそうした戦略物資や貴金属を大量に抱えて引き揚げた。戦後はその資産を元手に影響力を行使し、岸信介首相らを陰で支えた。
ロッキード社の幹部の証言によれば、同社は航空機を日本に売り込むため、児玉に700万ドル(当時のレートで21億円)のコンサルタント料を支払った。首相への5億円の賄賂はその一部と見られるが、彼は病気を理由に国会でも法廷でも証言に立たず、世を去った。
小佐野は戦前、自ら設立した自動車部品販売会社を足場に軍需省の仕事をし、戦後は駐留米軍を相手にした中古車販売や観光事業で財を成した。ホテル経営にも乗り出し、帝国ホテルも傘下に収めた。ロッキード事件では、国会で証人喚問に応じたものの「記憶にございません」という言葉を連発し、その年の流行語になった。
2人に共通しているのは「常に時の権力にすり寄る」という点である。それは戦前には軍部であり、戦後はアメリカだった。権力の周りには「甘い蜜」がふんだんにあることを知っていたからにほかならない。
安土桃山時代の大盗賊で釜茹での刑にされた石川五右衛門の歌舞伎のせりふを借りるなら、「浜の真砂(まさご)は尽きるとも世に政商の種は尽きまじ」と言うべきか。時と所は変わっても、政商は常に存在する。
わが故郷の山形県では、地元紙山形新聞の服部敬雄(よしお)社長が長く政商として君臨し、県政と山形市政を壟断(ろうだん)した。当時の板垣清一郎知事と金澤忠雄市長をあごで使い、巷では「服部天皇、板垣総務部長、金澤庶務課長」と揶揄された。
その服部氏が1991年に亡くなるや登場したのが吉村和文氏で、吉村美栄子知事の義理のいとこにあたる。彼は1992年にケーブルテレビ山形を設立して、政商としての第一歩を踏み出した。服部氏の後を継ぐかのように。
この会社の設立について、和文氏は朝日新聞の東北各県版に掲載されたインタビュー記事「私の転機」(2013年10月24日)で、次のように語っている。
「政治家になりたい、と思っていました。小学生の頃、朝起きると、いつも色んな人が茶の間に集まっていました。議員秘書だった父に、陳情に来ていたんです。(中略)その後、県議になった父をずっと見ていて、次第に政治家は困っている人を助ける仕事なんだと、志すようになりました」
「転機は1990年の山形市長選です。父は2度目の挑戦でしたが、7期目を目指す現職に僅差で敗れました。2回もサラリーマンを辞めて父の秘書をした私にとって、失意のどん底でした。(中略)ただ、山形を変えたいとの思いは強く、政治からメディアにツールを変えたんです」
「30代の仲間と準備を進め、92年に起業しました。500社を訪問して、50社から200万円ずつ出資を得て、資本金1億円を集めました」
事実関係に誤りはない。ただ、重要な要素が抜けている。この記事だけを読めば、「情報技術(IT)の世界に活路を見出そうとした実業家」のようなイメージを受けるが、この会社の設立は「起業」と呼べるようなものではなかった、という点である。
以前、このコラムで詳述したように、ケーブルテレビ事業は当時の郵政省(のち総務省)が国策として推し進めたものだ。全国各地に自治体が出資する「第三セクター会社」を設立させ、ケーブル敷設費の半分を補助金として支給して広めた。普通の民間企業に対して、そのような高率の補助が与えられることはない。
ケーブルテレビ山形の場合も、設立後に山形県や山形市など六つの自治体が計2900万円を出資して「第三セクター」としての体裁を整え、そこに億単位の補助金が流し込まれた。最初に出資した企業も、そうした仕組みが分かっているから安心して協力したのだ。
時代の波に乗って、当初、ケーブルテレビ事業は順調に伸びていった。だが、IT革命の進展に伴ってビジネスは暗転する。一般家庭でもインターネットが気軽に利用できるようになるにつれ、「ケーブルを敷設して家庭につなげ、多様なテレビ放送を楽しむ」というビジネスモデルが優位性を失っていったからだ。
今や、若い世代は映画やテレビドラマを、主にアマゾンプライムやネットフリックス、Hulu(フールー)といったIT企業のインターネットサービスを利用して見る。家でテレビにかじりつく必要はない。端末があれば、ダウンロードして都合のいい時に楽しむことができる。おまけに料金が安く、作品の質と量が勝っているのだから、当然の流れと言える。
日本のケーブルテレビ各社は、そうした新しいビジネスと生き残りをかけた競争を強いられている。小さい会社は次々に吸収合併されて消えていった。図1は、日本政策投資銀行がまとめた『ケーブルテレビ事業の現状』(2016年度決算版)に掲載された業界の略図である。
最大手のジュピターテレコムは、KDDIと住友商事が出資して作ったケーブルテレビ事業の統括会社だ。傘下に東京や大阪、九州のケーブルテレビ会社を擁し、サービス契約は2127万世帯。次が関西電力系のケイ・オプティコム(昨年、オプテージと社名変更)である。
各社とも、ケーブルを通してインターネットサービスを提供するなど生き残りを模索しているが、前途は容易ではない。ケーブルテレビ山形も4年前に「ダイバーシティメディア」と社名を変え、経営の多角化を図って難局を乗り切ろうとしている。
吉村和文氏が2番目に作ったのも「補助金頼りの会社」である。
2001年に経済産業省が「IT装備都市研究事業」という構想を打ち上げ、全国21カ所のモデル地区で実証実験を始めた。山形市もモデル地区に選ばれ、その事業の一翼を担うために設立したのが「バーチャルシティやまがた」という会社だ。ちなみに、当時の山形市長は和文氏の父親で県議から転じた吉村和夫氏である。
この事業は、国がIC(集積回路)を内蔵する多機能カードを作って市民に無料で配布し、市役所や公民館に設置された端末機器で住民票や印鑑証明書の発行を受けられるようにする、という大盤振る舞いの事業だった。登録した商店で買い物をすればポイントがたまるメリットもあるとの触れ込みで、「バーチャルシティやまがた」はこの部分を担うために作られた。
山形市は5万枚の市民カードを希望者に配布したが、利用は広がらなかった。おまけに総務省が翌2002年から住民基本台帳ネットワークを稼働させ、住基カードの発行を始めた。経産省と総務省が何の連携もなく、別々に似たような機能を持つカードを発行したのだ。「省あって国なし」を地で行く愚挙と言わなければならない。
全国で172億円を投じた経産省の実証実験はさしたる成果もなく頓挫し、総務省の住基カードも、その後、マイナンバーカードが導入されて無用の長物と化した。こちらの無駄遣いは、政府と自治体を合わせて1兆円近いとの試算がある(注参照)。
国民がどんなに勤勉に働いても、こんな税金の使い方をしていたら、国の屋台骨が揺らぎかねない。だが、官僚たちはどこ吹く風。責任を取る者は誰もいない。政商は肥え太り、次の蜜を探して動き回る。
吉村和文氏は多数の企業を率いるかたわら、学校法人東海山形学園の理事長をしている。多忙で、学校法人が運営する東海大山形高校に顔を出すことは少ないが、それでも入学式や卒業式には出席して生徒に語りかける。
彼のブログ「約束の地へ」によれば、2014年4月の入学式では「自分と向かい合うこと、主体的に行動すること」を訴え、さらに「棚ボタとは、棚の下まで行かなければ、ボタ餅は受け取れない。だから、前向きの状態でいること」と述べた。
いささか珍妙な講話だが、彼が歩んできた道を思えば、意味深長ではある。彼にとっては、郵政省のケーブルテレビ事業が第1のボタ餅、経済産業省のIT装備都市構想が第2のボタ餅なのかもしれない。そして、3番目が2007年頃から推し進められたユビキタス事業である。
ユビキタスとは、アメリカの研究者が考え出した言葉で、「あらゆる場所であらゆるものがコンピューターのネットワークにつながる社会」を意味する。衣服にコンピューターを取り付け、体温を測定して空調を自動調節する。ゴミになるものにコンピューターを取り付け、焼却施設のコンピューターと交信して処理方法を決める。そんな未来社会を思い描いていた。
日本では、坂村健・東大教授が提唱し、総務省がすぐに飛び付いた。2009年にユビキタス構想の推進を決定し、経済危機関連対策と称して195億円の補正予算を組み、全国に予算をばら撒いた。補助金の対象はまたもや「自治体と第三セクター」である。
山形県では鶴岡市や最上町とともにケーブルテレビ山形が補助の対象になり、「新山形ブランドの発信による地域・観光振興事業」に5898万円の補助金が交付された。その補助金で和文氏は「東北サプライズ商店街」なるサイトを立ち上げ、加盟した飲食店や商店の情報発信を始めた。そのサイトによってどの程度、成果が上がり、現在、どのように機能しているのかは窺い知れない。
だが、ITの技術革新は研究者や官僚たちの想定をはるかに超えて急激に進み、「ユビキタス」という言葉そのものが、すでにITの世界では「死語」と化した。スマートフォンが普及し、「あらゆる場所で誰もがネットワークにつながる社会」が到来してしまったからだ。
日本の政府や自治体がIT分野でやっていることは、IT企業の取り組みの「周回遅れ」と言われて久しい。周回遅れのランナーが訳知り顔で旗を振り、実験やら構想やらを唱えるのは滑稽である。その滑稽さを自覚していないところがいっそう悲しい。
この国はどうなってしまうのだろうか。「世の中、なんとかなる」といつも気楽に構えている私のような人間ですら、時々、本当に心配になってくる。
*注 週刊現代2016年1月31日号は、総務官僚の証言として次のように報じている。「住基ネットに費やされた税金は、システム構築の初期費用と運営維持費で2100億円ほど(13年間の合算)とされているが、全国の自治体でもシステム構築費と維持費がかかっており、それらを合計すれば全体で1兆円近い」
*メールマガジン「風切通信 68」 2020年1月29日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』2020年2月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎ロッキード事件で国会の証人喚問に応じた小佐野賢治
https://picpanzee.com/tag/%E5%B0%8F%E4%BD%90%E9%87%8E%E8%B3%A2%E6%B2%BB
≪参考文献&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎最後の「フィクサー」児玉誉士夫とは何者だったのか(週刊現代2016年12月10月号)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/50389
◎稀代の政商「小佐野賢治」国際興業社長(週刊新潮3000号記念別冊「黄金の昭和」)
https://www.dailyshincho.jp/article/2016/08211100/
◎『政商 小佐野賢治』(佐木隆三、徳間文庫)
◎石川五右衛門(ウィキペディア)
◎『ケーブルテレビ事業の現状』(2016年度決算版)日本政策投資銀行
◎ジュピター・テレコム(ウィキペディア)
◎オプテージ(同)
◎『NETFLIX コンテンツ帝国の野望』(ジーナ・キーティング、新潮社)
◎ICカードの普及等によるIT装備都市研究事業(電子自治体情報)
http://www.jjseisakuken.jp/elocalgov/contents/c108.html
◎血税1兆円をドブに捨てた「住基ネット」(週刊現代2016年1月31日号)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/47571
◎ユビキタスタウン構想実現を支援(総務省報道資料、2009年12月22日)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h2110-12/1222b1001.html

児玉は福島県、小佐野は山梨県の生まれである。2人とも極貧の家に生まれた。子どものころ、児玉は父親と掘っ立て小屋で暮らし、小佐野に至っては家すらなく、村の寺の軒先で夜露をしのいだと伝わる。その生い立ちを抜きにして、2人の壮絶な人生は語れない。
児玉は戦前、右翼の活動家になり、笹川良一の紹介で海軍航空本部の嘱託(佐官待遇)になる。上海を拠点に航空機の生産に欠かせないタングステンやニッケルなど戦略物資の調達にあたった。アヘンの密売に手を染め、その収益と軍費で物資を買い集めたという。
敗戦の直前、児玉はそうした戦略物資や貴金属を大量に抱えて引き揚げた。戦後はその資産を元手に影響力を行使し、岸信介首相らを陰で支えた。
ロッキード社の幹部の証言によれば、同社は航空機を日本に売り込むため、児玉に700万ドル(当時のレートで21億円)のコンサルタント料を支払った。首相への5億円の賄賂はその一部と見られるが、彼は病気を理由に国会でも法廷でも証言に立たず、世を去った。
小佐野は戦前、自ら設立した自動車部品販売会社を足場に軍需省の仕事をし、戦後は駐留米軍を相手にした中古車販売や観光事業で財を成した。ホテル経営にも乗り出し、帝国ホテルも傘下に収めた。ロッキード事件では、国会で証人喚問に応じたものの「記憶にございません」という言葉を連発し、その年の流行語になった。
2人に共通しているのは「常に時の権力にすり寄る」という点である。それは戦前には軍部であり、戦後はアメリカだった。権力の周りには「甘い蜜」がふんだんにあることを知っていたからにほかならない。
安土桃山時代の大盗賊で釜茹での刑にされた石川五右衛門の歌舞伎のせりふを借りるなら、「浜の真砂(まさご)は尽きるとも世に政商の種は尽きまじ」と言うべきか。時と所は変わっても、政商は常に存在する。
わが故郷の山形県では、地元紙山形新聞の服部敬雄(よしお)社長が長く政商として君臨し、県政と山形市政を壟断(ろうだん)した。当時の板垣清一郎知事と金澤忠雄市長をあごで使い、巷では「服部天皇、板垣総務部長、金澤庶務課長」と揶揄された。
その服部氏が1991年に亡くなるや登場したのが吉村和文氏で、吉村美栄子知事の義理のいとこにあたる。彼は1992年にケーブルテレビ山形を設立して、政商としての第一歩を踏み出した。服部氏の後を継ぐかのように。
この会社の設立について、和文氏は朝日新聞の東北各県版に掲載されたインタビュー記事「私の転機」(2013年10月24日)で、次のように語っている。
「政治家になりたい、と思っていました。小学生の頃、朝起きると、いつも色んな人が茶の間に集まっていました。議員秘書だった父に、陳情に来ていたんです。(中略)その後、県議になった父をずっと見ていて、次第に政治家は困っている人を助ける仕事なんだと、志すようになりました」
「転機は1990年の山形市長選です。父は2度目の挑戦でしたが、7期目を目指す現職に僅差で敗れました。2回もサラリーマンを辞めて父の秘書をした私にとって、失意のどん底でした。(中略)ただ、山形を変えたいとの思いは強く、政治からメディアにツールを変えたんです」
「30代の仲間と準備を進め、92年に起業しました。500社を訪問して、50社から200万円ずつ出資を得て、資本金1億円を集めました」
事実関係に誤りはない。ただ、重要な要素が抜けている。この記事だけを読めば、「情報技術(IT)の世界に活路を見出そうとした実業家」のようなイメージを受けるが、この会社の設立は「起業」と呼べるようなものではなかった、という点である。
以前、このコラムで詳述したように、ケーブルテレビ事業は当時の郵政省(のち総務省)が国策として推し進めたものだ。全国各地に自治体が出資する「第三セクター会社」を設立させ、ケーブル敷設費の半分を補助金として支給して広めた。普通の民間企業に対して、そのような高率の補助が与えられることはない。
ケーブルテレビ山形の場合も、設立後に山形県や山形市など六つの自治体が計2900万円を出資して「第三セクター」としての体裁を整え、そこに億単位の補助金が流し込まれた。最初に出資した企業も、そうした仕組みが分かっているから安心して協力したのだ。
時代の波に乗って、当初、ケーブルテレビ事業は順調に伸びていった。だが、IT革命の進展に伴ってビジネスは暗転する。一般家庭でもインターネットが気軽に利用できるようになるにつれ、「ケーブルを敷設して家庭につなげ、多様なテレビ放送を楽しむ」というビジネスモデルが優位性を失っていったからだ。
今や、若い世代は映画やテレビドラマを、主にアマゾンプライムやネットフリックス、Hulu(フールー)といったIT企業のインターネットサービスを利用して見る。家でテレビにかじりつく必要はない。端末があれば、ダウンロードして都合のいい時に楽しむことができる。おまけに料金が安く、作品の質と量が勝っているのだから、当然の流れと言える。
日本のケーブルテレビ各社は、そうした新しいビジネスと生き残りをかけた競争を強いられている。小さい会社は次々に吸収合併されて消えていった。図1は、日本政策投資銀行がまとめた『ケーブルテレビ事業の現状』(2016年度決算版)に掲載された業界の略図である。
最大手のジュピターテレコムは、KDDIと住友商事が出資して作ったケーブルテレビ事業の統括会社だ。傘下に東京や大阪、九州のケーブルテレビ会社を擁し、サービス契約は2127万世帯。次が関西電力系のケイ・オプティコム(昨年、オプテージと社名変更)である。
各社とも、ケーブルを通してインターネットサービスを提供するなど生き残りを模索しているが、前途は容易ではない。ケーブルテレビ山形も4年前に「ダイバーシティメディア」と社名を変え、経営の多角化を図って難局を乗り切ろうとしている。
吉村和文氏が2番目に作ったのも「補助金頼りの会社」である。
2001年に経済産業省が「IT装備都市研究事業」という構想を打ち上げ、全国21カ所のモデル地区で実証実験を始めた。山形市もモデル地区に選ばれ、その事業の一翼を担うために設立したのが「バーチャルシティやまがた」という会社だ。ちなみに、当時の山形市長は和文氏の父親で県議から転じた吉村和夫氏である。
この事業は、国がIC(集積回路)を内蔵する多機能カードを作って市民に無料で配布し、市役所や公民館に設置された端末機器で住民票や印鑑証明書の発行を受けられるようにする、という大盤振る舞いの事業だった。登録した商店で買い物をすればポイントがたまるメリットもあるとの触れ込みで、「バーチャルシティやまがた」はこの部分を担うために作られた。
山形市は5万枚の市民カードを希望者に配布したが、利用は広がらなかった。おまけに総務省が翌2002年から住民基本台帳ネットワークを稼働させ、住基カードの発行を始めた。経産省と総務省が何の連携もなく、別々に似たような機能を持つカードを発行したのだ。「省あって国なし」を地で行く愚挙と言わなければならない。
全国で172億円を投じた経産省の実証実験はさしたる成果もなく頓挫し、総務省の住基カードも、その後、マイナンバーカードが導入されて無用の長物と化した。こちらの無駄遣いは、政府と自治体を合わせて1兆円近いとの試算がある(注参照)。
国民がどんなに勤勉に働いても、こんな税金の使い方をしていたら、国の屋台骨が揺らぎかねない。だが、官僚たちはどこ吹く風。責任を取る者は誰もいない。政商は肥え太り、次の蜜を探して動き回る。
吉村和文氏は多数の企業を率いるかたわら、学校法人東海山形学園の理事長をしている。多忙で、学校法人が運営する東海大山形高校に顔を出すことは少ないが、それでも入学式や卒業式には出席して生徒に語りかける。
彼のブログ「約束の地へ」によれば、2014年4月の入学式では「自分と向かい合うこと、主体的に行動すること」を訴え、さらに「棚ボタとは、棚の下まで行かなければ、ボタ餅は受け取れない。だから、前向きの状態でいること」と述べた。
いささか珍妙な講話だが、彼が歩んできた道を思えば、意味深長ではある。彼にとっては、郵政省のケーブルテレビ事業が第1のボタ餅、経済産業省のIT装備都市構想が第2のボタ餅なのかもしれない。そして、3番目が2007年頃から推し進められたユビキタス事業である。
ユビキタスとは、アメリカの研究者が考え出した言葉で、「あらゆる場所であらゆるものがコンピューターのネットワークにつながる社会」を意味する。衣服にコンピューターを取り付け、体温を測定して空調を自動調節する。ゴミになるものにコンピューターを取り付け、焼却施設のコンピューターと交信して処理方法を決める。そんな未来社会を思い描いていた。
日本では、坂村健・東大教授が提唱し、総務省がすぐに飛び付いた。2009年にユビキタス構想の推進を決定し、経済危機関連対策と称して195億円の補正予算を組み、全国に予算をばら撒いた。補助金の対象はまたもや「自治体と第三セクター」である。
山形県では鶴岡市や最上町とともにケーブルテレビ山形が補助の対象になり、「新山形ブランドの発信による地域・観光振興事業」に5898万円の補助金が交付された。その補助金で和文氏は「東北サプライズ商店街」なるサイトを立ち上げ、加盟した飲食店や商店の情報発信を始めた。そのサイトによってどの程度、成果が上がり、現在、どのように機能しているのかは窺い知れない。
だが、ITの技術革新は研究者や官僚たちの想定をはるかに超えて急激に進み、「ユビキタス」という言葉そのものが、すでにITの世界では「死語」と化した。スマートフォンが普及し、「あらゆる場所で誰もがネットワークにつながる社会」が到来してしまったからだ。
日本の政府や自治体がIT分野でやっていることは、IT企業の取り組みの「周回遅れ」と言われて久しい。周回遅れのランナーが訳知り顔で旗を振り、実験やら構想やらを唱えるのは滑稽である。その滑稽さを自覚していないところがいっそう悲しい。
この国はどうなってしまうのだろうか。「世の中、なんとかなる」といつも気楽に構えている私のような人間ですら、時々、本当に心配になってくる。
*注 週刊現代2016年1月31日号は、総務官僚の証言として次のように報じている。「住基ネットに費やされた税金は、システム構築の初期費用と運営維持費で2100億円ほど(13年間の合算)とされているが、全国の自治体でもシステム構築費と維持費がかかっており、それらを合計すれば全体で1兆円近い」
*メールマガジン「風切通信 68」 2020年1月29日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』2020年2月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明&Source≫
◎ロッキード事件で国会の証人喚問に応じた小佐野賢治
https://picpanzee.com/tag/%E5%B0%8F%E4%BD%90%E9%87%8E%E8%B3%A2%E6%B2%BB
≪参考文献&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎最後の「フィクサー」児玉誉士夫とは何者だったのか(週刊現代2016年12月10月号)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/50389
◎稀代の政商「小佐野賢治」国際興業社長(週刊新潮3000号記念別冊「黄金の昭和」)
https://www.dailyshincho.jp/article/2016/08211100/
◎『政商 小佐野賢治』(佐木隆三、徳間文庫)
◎石川五右衛門(ウィキペディア)
◎『ケーブルテレビ事業の現状』(2016年度決算版)日本政策投資銀行
◎ジュピター・テレコム(ウィキペディア)
◎オプテージ(同)
◎『NETFLIX コンテンツ帝国の野望』(ジーナ・キーティング、新潮社)
◎ICカードの普及等によるIT装備都市研究事業(電子自治体情報)
http://www.jjseisakuken.jp/elocalgov/contents/c108.html
◎血税1兆円をドブに捨てた「住基ネット」(週刊現代2016年1月31日号)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/47571
◎ユビキタスタウン構想実現を支援(総務省報道資料、2009年12月22日)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h2110-12/1222b1001.html
2003年1月20日付 朝日新聞 社説
ただひたすら土を集める。造形作家の栗田宏一さん(40)が修行僧のような仕事を始めてから、もう10年以上がたつ。
車で全国を回る。持ち帰る土は、いつも一握りだけ。「もっと欲しいと思いだしたら、際限がなくなるから」という。山梨県石和(いさわ)町の自宅で、その土を乾かし、ふるいにかけてサラサラにする。淡い桃色の土、青みを帯びた土、灰白色の土。同じものはひとつとしてない。
少しずつ色合いの異なる土を細いガラス管に詰めて並べると、長い虹ができる。そうして生まれた作品が「虹色の土」だ。京都の法然院では、庫裏に小さな土盛りを多数配して曼陀羅をつくった。ふだん気にもとめない土が放つ色彩の豊かさに、訪れた人は息をのんだ。
古い土器のかけらを手にしたり、石ころを集めたりするのが好きな子どもだった。宝石加工の専門学校を出た後、アジアやアフリカを旅した。宿代を含め1日千円で暮らす日々。触れ合う人々は貧しかったが、大地を踏みしめて生きていた。その国々の土をテープではがきにはり付けて、日本の自分の住所に送った。

帰国して見た日本。比較にならないほど便利でぜいたくな暮らしをしているのに、あまり幸せそうには見えない。遺跡発掘の作業員をしながら、焼き物や窯跡を訪ね歩く生活を続け、土の魅力にますます取り込まれていった。
「土は美しい。それを伝えたい」と栗田さんはいう。
地球の表面を覆う土の厚さは、平均するとわずか18センチしかない。地上のすべての生き物は、この土の恵みにすがって生きている。だが、私たちはいつしか、そのことを忘れ、被膜のように薄い土や、土の再生に欠かせない生き物を傷めつけてきた。
栃木県の足尾銅山がその典型だ。明治以来の発展を支えた銅山の鉱毒は、緑に覆われた山々をはげ山に変えてしまった。閉山から30年たつというのに、鉱山跡からは、いまだに鉱毒が流れ出している。
死んだ山々を生き返らせるために、地元や県内の人々が立ち上がったのは7年前のことだ。足尾に緑を育てる会をつくり、大規模な緑化に乗り出した。足尾の土には亜硫酸ガスが染み込んでいる。苗木を植えても枯れてしまう。緑を取り戻すために、まずよそから生きた土を運び込んでいる。
育てる会の神山英昭さん(65)は「日光に修学旅行に来た子どもたちが植樹をしていってくれる。足尾は緑化の聖地のようになってきました」と語る。
土は命の源であり、文明の糧である。土の美しさ、大切さを見つめ直したい。
繁栄の果てに行き先を見失い、漂い続ける日本。豊かさと引き換えに失ったものの大きさをいま思う。
「一つずつ小さなことを積み重ねていく。何かを成し遂げるためには、そうするしかない」
志半ばで凶弾に斃(たお)れた医師、中村哲さんはそう語っていた。パキスタンの辺境で貧しい人たちの治療にあたっていたものの、「飢えや渇きは医療では治せない」と思い定め、アフガニスタンで井戸を掘り、農業用水路を造ることに力を注いだ。「生きておれ。病気は後で治す」と。

指図する人ではなかった。自らスコップを握って大地を掘り、もっこを担いで土を運んだ。農民と一緒に汗を流し、生きる道を切り拓いていった。
30年前、アフガニスタン内戦を取材した際に、ペシャワルの診療所で中村哲さんと言葉を交わしたことがある。口数は少なく、野武士のような人だった。「こんな所にいないで、現場に行って、何が起きているか自分の目で見てきなさい」と背中を押されたような気がした。
それから、私はアジア担当の新聞記者として各地を転々とし、混沌とした国々を見てきた。退職して、今は生まれ育った村に戻って暮らしている。すこぶる平和だ。けれども、私たちの国は戦争をしている国とは異なる厳しさに直面している、と感じる。社会の仕組みを大きく変えなければならないのに、それができずにもがいている。
仕組みを変えられない理由はハッキリしている。年寄りが多すぎて、しかも権限と権益を手放さないからだ。情報技術(IT)革命の大波にもまれているのに、その意味もインパクトのすさまじさも分からない人間が決定権を握って放さない。昔の成功体験にこだわっていてはいけないのに、その延長線上でしか物事を考えることができない。ならば、身を引いて、若い人たちに舵取りを任せるべきなのだ。
山形県の吉村美栄子知事(68歳)は「知事は私の天職」と口にしたと聞いた。「転職」の聞き間違いではない。困ったものだ。今の時代、ITの衝撃度が分からない指導者は「羅針盤が読めない船長」と同じだ。乗り合わせた客は、悲惨な航海を覚悟しなければならない。
山形県庁という船の船長室には、義理のいとこの吉村和文氏がしょっちゅう出入りしている。彼が率いる企業や法人が県庁からどのような物品を受注し、どのような業務を受託しているのか。これまで調べた結果を月刊『素晴らしい山形』に寄稿してきた。表1は、それをまとめたものである。総額で36億円近い。
2009年に吉村美栄子氏が知事になった途端、和文氏が経営するケーブルテレビ山形が突如として、山形県からパソコン(NEC製)を続けて受注するようになった。総額2億3927万円。ケーブルテレビ会社が入札でパソコン販売を得意とする会社を次々に打ち負かすことができたのはなぜか。いまだ謎である。
NECはこの時期、山形県の米沢市に工場を持ち、パソコンを製造していたが、その後、中国のパソコンメーカー、レノボにこれを譲渡した。2012年度以降、受注が途切れたのはそのことが影響していると考えられる。
先月号で伝えたように、NECは2018年に山形県立病院の医療情報システムを37億円で受注した。「パソコンの落札はこれと連動している」との見方もあるが、NEC側は「パソコンに関しても医療情報システムに関しても、和文氏の会社とは販売契約を結んでいない」と、関係を否定している。
ケーブルテレビ山形は1992年に、郵政省(のち総務省)の電気通信格差是正事業の補助金受け皿会社として吉村和文氏がつくった会社だ。表2のように、山形県や山形市、天童市など六つの自治体が合わせて2900万円出資した。いわゆる第三セクター会社で、ケーブルテレビ網の敷設費の半分が補助金でまかなわれた。
当初、順調だったケーブルテレビ事業がその後、IT革命の進展で苦境に陥った経緯はすでに報告した通りである。図1に見るように、本業の売上高は年々、減っており、県庁からの受注や受託でしのいでいる状況だ。社名も2016年1月に「ダイバーシティメディア」に変更した。
和文氏は事業の多角化を進め、2014年度以降は山形県が外注した県内周遊促進のキャンペーン事業を連続して受託している。その最初の業務委託が「出来レース」のような形で行われたことは、2019年2月号で詳しく報告した。
和文氏の会社と県内の民放4社、合わせて5社を指名してコンペ方式で競わせたのだが、事業の仕様書には民放テレビには対応できない項目が含まれていた。ゆがんだ発注というよりは、県幹部による「限りなく不正行為に近い発注」と言っていい。この事業での受託総額は1億2035万円になる(共同企業体としての受託分を含む)。
吉村美栄子知事が新しい事業を始めるたびに、和文氏の会社が登場する。知事は2016年から「いきいき雪国やまがた」なる標語を掲げて、安全な雪国暮らしや冬の観光の推進事業を始め、ウェブサイトの制作を発注した。これを139万円で受注したのもこの会社である。しかも、そのサイトの制作を担当したのは和文氏の長男だ。
「ミニ新幹線ではなく、フル規格の奥羽新幹線と羽越新幹線を実現しよう」と知事が呼びかけ、新しい事業が始まれば、またダイバーシティメディアが顔を出す。2018年に「奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」のシンポジウムの開催や広告業務を1817万円で受託した。県発注のさまざまな事業で、知事と義理のいとこの名前が並ぶ契約書が交わされる。
それでも、これら3分野の落札・受託の総額は3億7920万円にとどまる。公金支出の大部分を占めるのは私学助成である。表1の通り、情報公開された2012年度以降の助成金は32億円を上回る。36億円近い総額はここまでの集計だ。
2009年度から2011年度の私学助成に関する文書は保存期間が過ぎており、文書がないため具体的な金額は不明だが、東海大山形高校を運営する学校法人東海山形学園にはこの間も億単位の助成金が支給されているのは間違いない。私学助成はおおむね、生徒数や教職員数に応じて配分されるからだ。図2の生徒数の推移から判断すれば、助成額は年間2億円前後とみられる。
これらの助成金を含めれば、吉村美栄子氏が知事に就任した2009年以降の10年間で、吉村和文氏が率いるダイバーシティメディアと学校法人東海山形学園に支出された公金(国費と県費の合計)は40億円を上回る。
和文氏はこの会社と学校法人のほかにも、映画館会社やプロバスケットボールチームの運営会社など多数の企業を率いている。これらの会社にもさまざまな形で公金が支出されていることは言うまでもない。
とはいえ、受け取る公金の巨額さという点で、やはり学校法人東海山形学園は群を抜いている。グループ企業・法人の大黒柱と言っていい。
この学校法人の前身は、1956年につくられた山形経理実務学校である。山形大学人文学部で会計学の教授をしていた安田三代人(みよと)氏が実務者の養成をめざして創立した夜間学校だ。その後、安田氏の母校、一橋大学にちなんで一橋高等経理学校、一橋商業高校と名を変え、東海大学との提携を機に現在の東海大山形高校という校名になった(表3参照)。
1995年に安田三代人氏が亡くなった後、高校を運営する学校法人の理事長は、息子の直人氏(歯科医)が継いだ。もともと吉村一族との縁が深く、吉村和文氏も理事に名を連ねていた。その学校法人で異変が起きたのは2011年の3月6日、東日本大震災の5日前のことだった。
臨時の理事会が開かれ、安田直人理事長の解任と吉村和文氏の理事長就任、新校長人事の撤回が次々に決議された。背景にあったのは安田理事長と教職員組合との対立だ。生徒数の減少から経営難に陥って教職員にボーナスが払えなくなり、理事長は激しい突き上げを受けていたという。
「そこに和文氏が『仲裁してやる』と入ってきて、いつの間にか乗っ取られてしまった」と安田直人氏は言う。事務長として経理を担当していた妻も追い出された。ただ、教職員側の事情を証言してくれる人が見つからず、この間の詳しい経緯は判然としない。東日本大震災の報道にかき消されたのか、騒動のその後を伝える新聞記事も見当たらない。
理事長に就任した後、吉村和文氏は新しい校長の任命など矢継ぎ早に手を打ったようだ。理事会の態勢固めにも抜かりはない。彼のブログ「約束の地へ」(2012年8月23日)によれば、震災の年の夏から、理事と評議員、監事の合同暑気払いを山形市内の料亭で行うようになった。「山形の花柳界の歴史と文化に触れるため」という。
「なかなか粋な計らい」と言いたいところだが、花柳界を知ることが高校の教育にどうつながるのか、理解不能である。それよりも、「毎年、億単位の私学助成を受けている学校法人の理事長が月に数回しか学校に顔を出さない」ということの方が気になる。
本来なら、学校法人を指導監督する山形県学事文書課は「理事長については原則、常勤とする」という文部科学省の事務次官通知(2004年)に沿って、是正を求めるのが筋だ。だが、学事文書課長は「通知を各学校に伝えました」と言うだけだ。
吉村和文氏が2016年3月に東海山形学園の資金3000万円を自分が社長を務めるダイバーシティメディアに融資した問題についても、課長は「監査報告書を見る限り、契約は適正と考える」と答え、吉村知事も「(学校法人が)適切に運営されているのであれば、よろしいのではないか」と応じた。
誰も、この問題に真剣に向き合おうとしない。東海山形学園の場合、学校法人を代表する権限を持っているのは理事長だけである。その理事長が社長をしている会社と金の貸し借りをすれば、明らかに「利益相反行為」になり、この融資については法人の代表権を失う。
つまり、この金銭貸借契約はこのままでは無効なのだ。だからこそ、私立学校法は「所轄庁(この場合は山形県)は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない」と定め、第三者に融資内容をチェックさせるよう求めているのだが、吉村知事は、法律も文部科学省の通知も気にならないようだ。
再選、三選と無投票当選を重ね、知事は「ミニ女帝」と化している。周りには諫(いさ)める人もいない。山形の自民党には対立候補を立てる気概もなさそうだ。地元の新聞はもとより、頼りにならない。当てもなく、船は荒海を進む。
*メールマガジン「風切通信 67」 2019年12月24日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年1月号に寄稿した文章を転載したものです。
≪写真説明&サイト≫
◎2018年7月の後援会総会で挨拶する吉村美栄子山形県知事(吉村みえこ Official Website から)
http://yoshimuramieko.com/2018/07/28/%E5%90%89%E6%9D%91%E7%BE%8E%E6%A0%84%E5%AD%90%E5%BE%8C%E6%8F%B4%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BC%9A%E5%90%88%E5%90%8C%E7%B7%8F%E4%BC%9A-2/
≪参考資料&サイト≫
◎山形県のパソコン調達に関する文書(2009ー2018年度の入札調書、契約書など)
◎山形県の県内周遊促進事業(観光キャンペーン)の業務委託に関する文書(2014年度以降)
◎山形県の「いきいき雪国やまがた」の2016年度業務委託に関する文書
◎山形県の2018年度「奥羽・羽越新幹線の整備推進に向けた広報・啓発等事業」に関する文書(業務委託契約書など)
◎山形県の学校法人東海山形学園に対する私学助成に関する文書(2012ー2018年度)
◎ケーブルテレビ山形に対する山形県、山形市、天童市、上山市、山辺町、中山町の出資に関する文書
◎ダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)の決算書(2009年3月期ー2019年3月期)
◎同社の株主総会配布資料
◎山形県教育委員会の学校名鑑(2009ー2018年度、県教委のサイトから)
◎『学校法人一橋学園 東海大学山形高等学校 50周年記念誌』(東海大学山形高等学校発行、2007年3月31日)
◎東海山形学園の安田理事長解任に関する山形新聞の記事(2011年3月8日、3月9日)
◎吉村和文氏のブログ「約束の地へ」(2012年8月23日、2016年8月27日)
https://ameblo.jp/stokimori/day-20120823.html
https://ameblo.jp/stokimori/day-20160827.html
志半ばで凶弾に斃(たお)れた医師、中村哲さんはそう語っていた。パキスタンの辺境で貧しい人たちの治療にあたっていたものの、「飢えや渇きは医療では治せない」と思い定め、アフガニスタンで井戸を掘り、農業用水路を造ることに力を注いだ。「生きておれ。病気は後で治す」と。

指図する人ではなかった。自らスコップを握って大地を掘り、もっこを担いで土を運んだ。農民と一緒に汗を流し、生きる道を切り拓いていった。
30年前、アフガニスタン内戦を取材した際に、ペシャワルの診療所で中村哲さんと言葉を交わしたことがある。口数は少なく、野武士のような人だった。「こんな所にいないで、現場に行って、何が起きているか自分の目で見てきなさい」と背中を押されたような気がした。
それから、私はアジア担当の新聞記者として各地を転々とし、混沌とした国々を見てきた。退職して、今は生まれ育った村に戻って暮らしている。すこぶる平和だ。けれども、私たちの国は戦争をしている国とは異なる厳しさに直面している、と感じる。社会の仕組みを大きく変えなければならないのに、それができずにもがいている。
仕組みを変えられない理由はハッキリしている。年寄りが多すぎて、しかも権限と権益を手放さないからだ。情報技術(IT)革命の大波にもまれているのに、その意味もインパクトのすさまじさも分からない人間が決定権を握って放さない。昔の成功体験にこだわっていてはいけないのに、その延長線上でしか物事を考えることができない。ならば、身を引いて、若い人たちに舵取りを任せるべきなのだ。
山形県の吉村美栄子知事(68歳)は「知事は私の天職」と口にしたと聞いた。「転職」の聞き間違いではない。困ったものだ。今の時代、ITの衝撃度が分からない指導者は「羅針盤が読めない船長」と同じだ。乗り合わせた客は、悲惨な航海を覚悟しなければならない。
山形県庁という船の船長室には、義理のいとこの吉村和文氏がしょっちゅう出入りしている。彼が率いる企業や法人が県庁からどのような物品を受注し、どのような業務を受託しているのか。これまで調べた結果を月刊『素晴らしい山形』に寄稿してきた。表1は、それをまとめたものである。総額で36億円近い。
2009年に吉村美栄子氏が知事になった途端、和文氏が経営するケーブルテレビ山形が突如として、山形県からパソコン(NEC製)を続けて受注するようになった。総額2億3927万円。ケーブルテレビ会社が入札でパソコン販売を得意とする会社を次々に打ち負かすことができたのはなぜか。いまだ謎である。
NECはこの時期、山形県の米沢市に工場を持ち、パソコンを製造していたが、その後、中国のパソコンメーカー、レノボにこれを譲渡した。2012年度以降、受注が途切れたのはそのことが影響していると考えられる。
先月号で伝えたように、NECは2018年に山形県立病院の医療情報システムを37億円で受注した。「パソコンの落札はこれと連動している」との見方もあるが、NEC側は「パソコンに関しても医療情報システムに関しても、和文氏の会社とは販売契約を結んでいない」と、関係を否定している。
ケーブルテレビ山形は1992年に、郵政省(のち総務省)の電気通信格差是正事業の補助金受け皿会社として吉村和文氏がつくった会社だ。表2のように、山形県や山形市、天童市など六つの自治体が合わせて2900万円出資した。いわゆる第三セクター会社で、ケーブルテレビ網の敷設費の半分が補助金でまかなわれた。
当初、順調だったケーブルテレビ事業がその後、IT革命の進展で苦境に陥った経緯はすでに報告した通りである。図1に見るように、本業の売上高は年々、減っており、県庁からの受注や受託でしのいでいる状況だ。社名も2016年1月に「ダイバーシティメディア」に変更した。
和文氏は事業の多角化を進め、2014年度以降は山形県が外注した県内周遊促進のキャンペーン事業を連続して受託している。その最初の業務委託が「出来レース」のような形で行われたことは、2019年2月号で詳しく報告した。
和文氏の会社と県内の民放4社、合わせて5社を指名してコンペ方式で競わせたのだが、事業の仕様書には民放テレビには対応できない項目が含まれていた。ゆがんだ発注というよりは、県幹部による「限りなく不正行為に近い発注」と言っていい。この事業での受託総額は1億2035万円になる(共同企業体としての受託分を含む)。
吉村美栄子知事が新しい事業を始めるたびに、和文氏の会社が登場する。知事は2016年から「いきいき雪国やまがた」なる標語を掲げて、安全な雪国暮らしや冬の観光の推進事業を始め、ウェブサイトの制作を発注した。これを139万円で受注したのもこの会社である。しかも、そのサイトの制作を担当したのは和文氏の長男だ。
「ミニ新幹線ではなく、フル規格の奥羽新幹線と羽越新幹線を実現しよう」と知事が呼びかけ、新しい事業が始まれば、またダイバーシティメディアが顔を出す。2018年に「奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」のシンポジウムの開催や広告業務を1817万円で受託した。県発注のさまざまな事業で、知事と義理のいとこの名前が並ぶ契約書が交わされる。
それでも、これら3分野の落札・受託の総額は3億7920万円にとどまる。公金支出の大部分を占めるのは私学助成である。表1の通り、情報公開された2012年度以降の助成金は32億円を上回る。36億円近い総額はここまでの集計だ。
2009年度から2011年度の私学助成に関する文書は保存期間が過ぎており、文書がないため具体的な金額は不明だが、東海大山形高校を運営する学校法人東海山形学園にはこの間も億単位の助成金が支給されているのは間違いない。私学助成はおおむね、生徒数や教職員数に応じて配分されるからだ。図2の生徒数の推移から判断すれば、助成額は年間2億円前後とみられる。
これらの助成金を含めれば、吉村美栄子氏が知事に就任した2009年以降の10年間で、吉村和文氏が率いるダイバーシティメディアと学校法人東海山形学園に支出された公金(国費と県費の合計)は40億円を上回る。
和文氏はこの会社と学校法人のほかにも、映画館会社やプロバスケットボールチームの運営会社など多数の企業を率いている。これらの会社にもさまざまな形で公金が支出されていることは言うまでもない。
とはいえ、受け取る公金の巨額さという点で、やはり学校法人東海山形学園は群を抜いている。グループ企業・法人の大黒柱と言っていい。
この学校法人の前身は、1956年につくられた山形経理実務学校である。山形大学人文学部で会計学の教授をしていた安田三代人(みよと)氏が実務者の養成をめざして創立した夜間学校だ。その後、安田氏の母校、一橋大学にちなんで一橋高等経理学校、一橋商業高校と名を変え、東海大学との提携を機に現在の東海大山形高校という校名になった(表3参照)。
1995年に安田三代人氏が亡くなった後、高校を運営する学校法人の理事長は、息子の直人氏(歯科医)が継いだ。もともと吉村一族との縁が深く、吉村和文氏も理事に名を連ねていた。その学校法人で異変が起きたのは2011年の3月6日、東日本大震災の5日前のことだった。
臨時の理事会が開かれ、安田直人理事長の解任と吉村和文氏の理事長就任、新校長人事の撤回が次々に決議された。背景にあったのは安田理事長と教職員組合との対立だ。生徒数の減少から経営難に陥って教職員にボーナスが払えなくなり、理事長は激しい突き上げを受けていたという。
「そこに和文氏が『仲裁してやる』と入ってきて、いつの間にか乗っ取られてしまった」と安田直人氏は言う。事務長として経理を担当していた妻も追い出された。ただ、教職員側の事情を証言してくれる人が見つからず、この間の詳しい経緯は判然としない。東日本大震災の報道にかき消されたのか、騒動のその後を伝える新聞記事も見当たらない。
理事長に就任した後、吉村和文氏は新しい校長の任命など矢継ぎ早に手を打ったようだ。理事会の態勢固めにも抜かりはない。彼のブログ「約束の地へ」(2012年8月23日)によれば、震災の年の夏から、理事と評議員、監事の合同暑気払いを山形市内の料亭で行うようになった。「山形の花柳界の歴史と文化に触れるため」という。
「なかなか粋な計らい」と言いたいところだが、花柳界を知ることが高校の教育にどうつながるのか、理解不能である。それよりも、「毎年、億単位の私学助成を受けている学校法人の理事長が月に数回しか学校に顔を出さない」ということの方が気になる。
本来なら、学校法人を指導監督する山形県学事文書課は「理事長については原則、常勤とする」という文部科学省の事務次官通知(2004年)に沿って、是正を求めるのが筋だ。だが、学事文書課長は「通知を各学校に伝えました」と言うだけだ。
吉村和文氏が2016年3月に東海山形学園の資金3000万円を自分が社長を務めるダイバーシティメディアに融資した問題についても、課長は「監査報告書を見る限り、契約は適正と考える」と答え、吉村知事も「(学校法人が)適切に運営されているのであれば、よろしいのではないか」と応じた。
誰も、この問題に真剣に向き合おうとしない。東海山形学園の場合、学校法人を代表する権限を持っているのは理事長だけである。その理事長が社長をしている会社と金の貸し借りをすれば、明らかに「利益相反行為」になり、この融資については法人の代表権を失う。
つまり、この金銭貸借契約はこのままでは無効なのだ。だからこそ、私立学校法は「所轄庁(この場合は山形県)は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない」と定め、第三者に融資内容をチェックさせるよう求めているのだが、吉村知事は、法律も文部科学省の通知も気にならないようだ。
再選、三選と無投票当選を重ね、知事は「ミニ女帝」と化している。周りには諫(いさ)める人もいない。山形の自民党には対立候補を立てる気概もなさそうだ。地元の新聞はもとより、頼りにならない。当てもなく、船は荒海を進む。
*メールマガジン「風切通信 67」 2019年12月24日
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の2020年1月号に寄稿した文章を転載したものです。
≪写真説明&サイト≫
◎2018年7月の後援会総会で挨拶する吉村美栄子山形県知事(吉村みえこ Official Website から)
http://yoshimuramieko.com/2018/07/28/%E5%90%89%E6%9D%91%E7%BE%8E%E6%A0%84%E5%AD%90%E5%BE%8C%E6%8F%B4%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BC%9A%E5%90%88%E5%90%8C%E7%B7%8F%E4%BC%9A-2/
≪参考資料&サイト≫
◎山形県のパソコン調達に関する文書(2009ー2018年度の入札調書、契約書など)
◎山形県の県内周遊促進事業(観光キャンペーン)の業務委託に関する文書(2014年度以降)
◎山形県の「いきいき雪国やまがた」の2016年度業務委託に関する文書
◎山形県の2018年度「奥羽・羽越新幹線の整備推進に向けた広報・啓発等事業」に関する文書(業務委託契約書など)
◎山形県の学校法人東海山形学園に対する私学助成に関する文書(2012ー2018年度)
◎ケーブルテレビ山形に対する山形県、山形市、天童市、上山市、山辺町、中山町の出資に関する文書
◎ダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)の決算書(2009年3月期ー2019年3月期)
◎同社の株主総会配布資料
◎山形県教育委員会の学校名鑑(2009ー2018年度、県教委のサイトから)
◎『学校法人一橋学園 東海大学山形高等学校 50周年記念誌』(東海大学山形高等学校発行、2007年3月31日)
◎東海山形学園の安田理事長解任に関する山形新聞の記事(2011年3月8日、3月9日)
◎吉村和文氏のブログ「約束の地へ」(2012年8月23日、2016年8月27日)
https://ameblo.jp/stokimori/day-20120823.html
https://ameblo.jp/stokimori/day-20160827.html
地方紙を購読している人は、今日(12月22日)の朝刊に公文書の管理に関する大きな記事が載っているのに気づいたのではないか。私が暮らしている山形の地元紙は「公文書専門職 1000人養成」「政府方針 2021年から認証開始」と、1面トップで報じた。ブロック紙の中日新聞も同じ記事を掲載しているから、地方紙などに記事を配信している共同通信の特ダネだろう。

記事に目を通して、あきれた。公文書の管理をよりしっかりしたものにするため、政府は公文書管理の専門職(アーキビスト)の公的な資格認証制度をつくる方針を固め、2021年から認証を始めるのだという。お題目はその通りでも、本当の狙いはまるで違うだろう。
安倍政権の下では、森友学園問題で公文書を改竄し、加計学園問題では愛媛県が作成した文書を「怪文書」扱いするなど、公文書をめぐる不祥事が相次いだ。それでも懲りず、首相主催の「桜を見る会」騒動では、招待客のリストを手際よくシュレッダーにかけて廃棄した。
「それらを深く反省し、公文書の管理をしっかりしたものにするため専門職を養成する」と言えば、聞こえはいいが、安倍首相や政権の幹部、官僚たちがそんな殊勝なことを考えているとは思えない。不祥事を利用して新しい事業を始め、官僚の天下り先をまた一つ増やそう――それを狙っているのではないか。政権への批判をかわすのにも役立つ、と。実にあくどい。
共同通信の記事には「現在は民間資格に基づく少数のアーキビストしかおらず、欧米の先進国に比べて態勢の不備が指摘されている」とある。「公文書の管理でも欧米先進国に追いつくための良い政策」と印象づけたいのだろう。官僚が用意した文言を引き写したに違いない。情けない。
共同通信は9月に関西電力・高浜原発がらみの巨額裏金疑惑をスクープした。金沢国税局の税務調査を基にした、実に見事な特ダネだった。が、今回の「特ダネ」はこれとは真逆である。安倍政権の高官か官僚が意図的にリークしたものを膨らませて書いた、いわば「おこぼれスクープ」だ。
本文で「民間にも公文書専門職(アーキビスト)の資格認証制度がある」と書いているのに、その具体的な内容を、本文でも解説記事でもまったく報じていないのだ。詳しく伝えると“スクープ”の迫力が損なわれてしまうので意図的に軽く触れるに留めた、としか思えない。
ネットで調べたら、すぐに分かった。この「民間の資格認証制度」とは、日本アーカイブズ学会が2012年から始めた制度のことだ。確かに「公的な制度」ではないが、制度を運用しているのは日本カーカイブズ学会というきちんとした団体である。すでに100人近い専門家がアーキビストとして認定されている。
この学会は、2004年設立と歴史は浅いが、日本学術会議の協力学術団体であり、しっかりした組織だ。初代の会長は学習院大学文学部の高埜(たかの)利彦教授、二代目の現会長は人間文化研究機構の高橋実教授。公文書の管理はどうあるべきか。そのためにアーキビストをどのようにして養成、認証していくか。それを真剣に考え、実践してきた人たちがつくった学会である。
こういう人たちがつくった認証制度なら、安倍政権の下で公文書の改竄と廃棄に励んできた官僚たちがこれから作ろうとしている「公的な資格認証制度」などより、はるかに信頼できる。公的な制度をつくるとなれば、また新しい外郭団体ができ、官僚の天下り先になるに決まっている。不祥事をテコにして権益の拡大を図る、得意の手口ではないか。
それが透けて見えるなら、少なくとも解説記事では「歴代の自民党政権は『民間の力を活用する』と言ってきた。きちんとした民間の認証制度がすでにあるのだから、税金を使って屋上屋を架す制度をつくる意味があるのか」くらいのことが書けないのか。
この特ダネを書いた記者は日頃、永田町の首相官邸や霞が関の官庁に張り付いて取材しているのだろう。権力周辺の悪臭にどっぶりと漬かり、いつの間にか記者として欠かせないバランス感覚まで失ってしまったとしか思えない。
日々、次々に起こることを追いかける記者の仕事はきつい。他社を出し抜くスクープを放つのはより難しい。さらに、権力が仕掛ける罠にかからないようにするのはもっと難しい。報道という仕事の困難さとほろ苦さを感じさせてくれる記事ではあった。
*メールマガジン「風切通信 66」 2019年12月22日
≪写真説明&Source≫
◎「公文書専門職の養成」を報じる山形新聞の1面
≪参考記事&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎12月22日付の山形新聞、中日新聞(電子版)
◎日本アーカイブズ学会(ウィキペディア)
◎日本アーカイブズ学会の公式サイト
http://www.jsas.info/

記事に目を通して、あきれた。公文書の管理をよりしっかりしたものにするため、政府は公文書管理の専門職(アーキビスト)の公的な資格認証制度をつくる方針を固め、2021年から認証を始めるのだという。お題目はその通りでも、本当の狙いはまるで違うだろう。
安倍政権の下では、森友学園問題で公文書を改竄し、加計学園問題では愛媛県が作成した文書を「怪文書」扱いするなど、公文書をめぐる不祥事が相次いだ。それでも懲りず、首相主催の「桜を見る会」騒動では、招待客のリストを手際よくシュレッダーにかけて廃棄した。
「それらを深く反省し、公文書の管理をしっかりしたものにするため専門職を養成する」と言えば、聞こえはいいが、安倍首相や政権の幹部、官僚たちがそんな殊勝なことを考えているとは思えない。不祥事を利用して新しい事業を始め、官僚の天下り先をまた一つ増やそう――それを狙っているのではないか。政権への批判をかわすのにも役立つ、と。実にあくどい。
共同通信の記事には「現在は民間資格に基づく少数のアーキビストしかおらず、欧米の先進国に比べて態勢の不備が指摘されている」とある。「公文書の管理でも欧米先進国に追いつくための良い政策」と印象づけたいのだろう。官僚が用意した文言を引き写したに違いない。情けない。
共同通信は9月に関西電力・高浜原発がらみの巨額裏金疑惑をスクープした。金沢国税局の税務調査を基にした、実に見事な特ダネだった。が、今回の「特ダネ」はこれとは真逆である。安倍政権の高官か官僚が意図的にリークしたものを膨らませて書いた、いわば「おこぼれスクープ」だ。
本文で「民間にも公文書専門職(アーキビスト)の資格認証制度がある」と書いているのに、その具体的な内容を、本文でも解説記事でもまったく報じていないのだ。詳しく伝えると“スクープ”の迫力が損なわれてしまうので意図的に軽く触れるに留めた、としか思えない。
ネットで調べたら、すぐに分かった。この「民間の資格認証制度」とは、日本アーカイブズ学会が2012年から始めた制度のことだ。確かに「公的な制度」ではないが、制度を運用しているのは日本カーカイブズ学会というきちんとした団体である。すでに100人近い専門家がアーキビストとして認定されている。
この学会は、2004年設立と歴史は浅いが、日本学術会議の協力学術団体であり、しっかりした組織だ。初代の会長は学習院大学文学部の高埜(たかの)利彦教授、二代目の現会長は人間文化研究機構の高橋実教授。公文書の管理はどうあるべきか。そのためにアーキビストをどのようにして養成、認証していくか。それを真剣に考え、実践してきた人たちがつくった学会である。
こういう人たちがつくった認証制度なら、安倍政権の下で公文書の改竄と廃棄に励んできた官僚たちがこれから作ろうとしている「公的な資格認証制度」などより、はるかに信頼できる。公的な制度をつくるとなれば、また新しい外郭団体ができ、官僚の天下り先になるに決まっている。不祥事をテコにして権益の拡大を図る、得意の手口ではないか。
それが透けて見えるなら、少なくとも解説記事では「歴代の自民党政権は『民間の力を活用する』と言ってきた。きちんとした民間の認証制度がすでにあるのだから、税金を使って屋上屋を架す制度をつくる意味があるのか」くらいのことが書けないのか。
この特ダネを書いた記者は日頃、永田町の首相官邸や霞が関の官庁に張り付いて取材しているのだろう。権力周辺の悪臭にどっぶりと漬かり、いつの間にか記者として欠かせないバランス感覚まで失ってしまったとしか思えない。
日々、次々に起こることを追いかける記者の仕事はきつい。他社を出し抜くスクープを放つのはより難しい。さらに、権力が仕掛ける罠にかからないようにするのはもっと難しい。報道という仕事の困難さとほろ苦さを感じさせてくれる記事ではあった。
*メールマガジン「風切通信 66」 2019年12月22日
≪写真説明&Source≫
◎「公文書専門職の養成」を報じる山形新聞の1面
≪参考記事&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎12月22日付の山形新聞、中日新聞(電子版)
◎日本アーカイブズ学会(ウィキペディア)
◎日本アーカイブズ学会の公式サイト
http://www.jsas.info/
パキスタン北西辺境州の古都、ペシャワルで医師の中村哲さんに初めてお会いしたのは1989年の春、今から30年も前のことです。ペシャワル郊外に診療所を開き、周辺の貧しい人々やアフガニスタンから逃れてきた難民の治療にあたっていました。
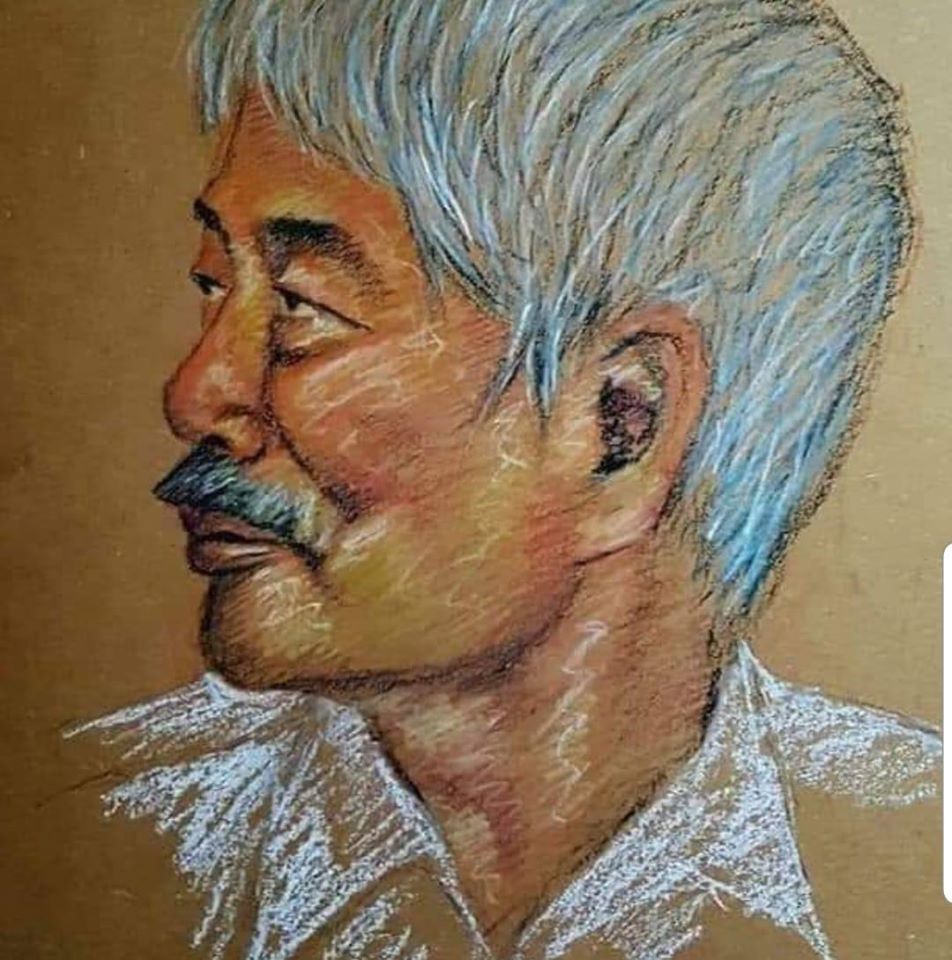
「らい病や眼病、感染症の患者が多い」。口数は少なく、問われたことに簡潔に答える。「野武士のような人だなぁ」と感じたことを覚えています。
当時のアフガニスタンは、2月に駐留ソ連軍が完全に撤退し、内戦が「ソ連軍とそれに支えられた社会主義政権 vs 米欧が支援するイスラム反政府ゲリラ」という米ソ代理戦争の構図から、「アフガン人同士の血で血を洗う内戦」という、より熾烈な段階に移行しつつある時期でした。
長い内戦で、隣国のパキスタンとイランにはすでに500万人の難民があふれていましたが、戦闘が激しくなり、両国には新たな難民が次々に流れ込んでいました。乾燥した大地に無数のテントが張られ、難民たちは照り付ける太陽に傷めつけられていました。
「難民キャンプにたどり着いた人たちはまだいい。報道陣が行かない国境地帯の状況はさらに悲惨だ」。中村さんは、そう言いました。「何が起きているのか、自分の目でしっかり見なさい」。そう諭されているように感じました。
その後、私のアフガン出張は十数回に及びました。首都カブールや主要都市だけでなく、できるだけ多く、農村にも足を運びました。村人の目にこの戦争はどんな風に映っているのか。それも伝えたい、と思いました。中村さんの言葉が心の片隅に残って消えなかったのかもしれません。
アフガニスタンの主要民族、パシュトゥンには「パシュトゥン・ワリ」という掟があります。まず、名誉を重んじること。次に、客人を歓待すること。それが良く守られていて、当時は外国人に危害を及ぼすことはほとんどなく、比較的自由に動き回ることができました。
それが大きく変わったのは、タリバーン政権の誕生と2001年の米同時多発テロのころからです。報復のため米軍がアフガンに攻め込み、タリバーン政権を倒し、オサマ・ビンラディン率いるアルカイダ勢力を一掃しましたが、国内はより混沌とした状況に追い込まれました。客人歓待の掟など忘れ去られ、外国人が襲われるようになってしまったのです。
そうした中でも、中村さんはアフガニスタンに通い続け、活動の軸足を医療から農村振興へと移していきました。「飢えや渇きは医療では治せない」という信念からです。安全な飲み水がないため赤痢で次々に命を落とす村人たちを救うために、井戸を掘る。戦争で破壊された農業用水路を復活させ、村人たちが生きていけるようにする。その活動ぶりは、著書『医者 井戸を掘る』(石風社)で詳しく知ることができます。
中村さんの活動が欧米の援助団体と異なるのは、村人たちの身の丈にあった支援に徹したことです。井戸掘りには、中田正一さん(故人)が主宰する「風の学校」の協力を得ました。中田さんは、日本に昔から伝わる「上総(かずさ)掘り」の技法を活かした井戸掘りを世界に広めた人です。竹と綱を使って井戸を掘る技法です。
用水路の取水堰をつくるにしても、日本の伝統的な技法を活用しました。江戸時代に築かれ、今でも使われている福岡県朝倉市の山田堰などを参考にした、と伝えられています。アフガンの農民たちが手にすることができるもので作り、維持することにこだわったのです。
それが農民たちをどれだけ勇気づけ、励ましたことか。民族や部族の利害が複雑にからまり、危険きわまりないアフガニスタンで中村さんが活動を続けることができたのは、その人柄に加え、こうした仕事ぶりに地元の人たちが絶大な信頼を寄せていたからでした。
その中村さんが銃で撃たれ、亡くなりました。アフガニスタンの人々、そしてアフガンを思う人たちに与えた衝撃の大きさは計り知れません。
「私は旅をしてきた。人の何倍か余計に生きた気がする。この旅はいつまで続くのだろう。今後も現地活動は際限がない。だが、そこに結晶した心ある人々の思いが、一隅の灯りとして、静かに続くことを祈る」
中村さんは『医は国境を越えて』(石風社)の結びにそう記しました。そう、中村さんが倒れても、灯りは消えず、人々の営みは静かに続く。信じて赴く者がいる限り。
*メールマガジン「風切通信 65」 2019年12月5日
≪写真説明&Source≫
◎中村哲・医師 (Zaheer Asefi さんのfacebook から)
≪参考サイト≫
◎上総掘りの技法(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=xzZp9flWZZw
◎山田堰の構造(動画)
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO92614040Y5A001C1000000/
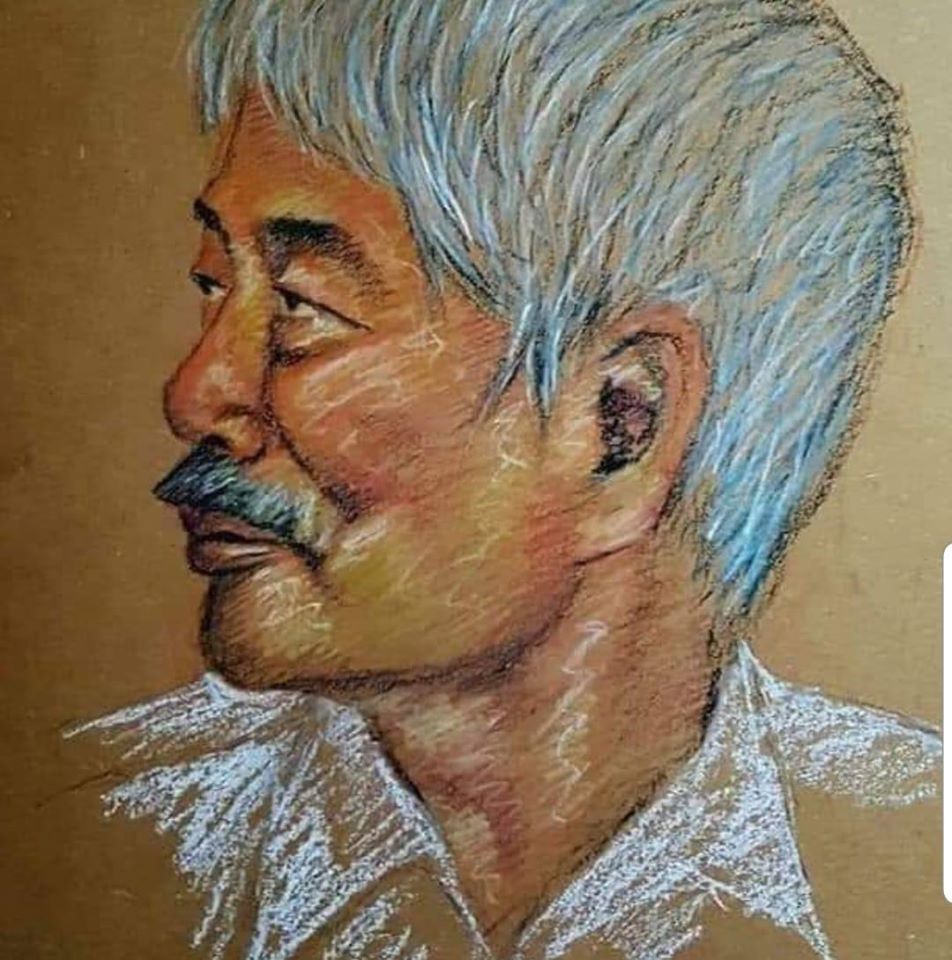
「らい病や眼病、感染症の患者が多い」。口数は少なく、問われたことに簡潔に答える。「野武士のような人だなぁ」と感じたことを覚えています。
当時のアフガニスタンは、2月に駐留ソ連軍が完全に撤退し、内戦が「ソ連軍とそれに支えられた社会主義政権 vs 米欧が支援するイスラム反政府ゲリラ」という米ソ代理戦争の構図から、「アフガン人同士の血で血を洗う内戦」という、より熾烈な段階に移行しつつある時期でした。
長い内戦で、隣国のパキスタンとイランにはすでに500万人の難民があふれていましたが、戦闘が激しくなり、両国には新たな難民が次々に流れ込んでいました。乾燥した大地に無数のテントが張られ、難民たちは照り付ける太陽に傷めつけられていました。
「難民キャンプにたどり着いた人たちはまだいい。報道陣が行かない国境地帯の状況はさらに悲惨だ」。中村さんは、そう言いました。「何が起きているのか、自分の目でしっかり見なさい」。そう諭されているように感じました。
その後、私のアフガン出張は十数回に及びました。首都カブールや主要都市だけでなく、できるだけ多く、農村にも足を運びました。村人の目にこの戦争はどんな風に映っているのか。それも伝えたい、と思いました。中村さんの言葉が心の片隅に残って消えなかったのかもしれません。
アフガニスタンの主要民族、パシュトゥンには「パシュトゥン・ワリ」という掟があります。まず、名誉を重んじること。次に、客人を歓待すること。それが良く守られていて、当時は外国人に危害を及ぼすことはほとんどなく、比較的自由に動き回ることができました。
それが大きく変わったのは、タリバーン政権の誕生と2001年の米同時多発テロのころからです。報復のため米軍がアフガンに攻め込み、タリバーン政権を倒し、オサマ・ビンラディン率いるアルカイダ勢力を一掃しましたが、国内はより混沌とした状況に追い込まれました。客人歓待の掟など忘れ去られ、外国人が襲われるようになってしまったのです。
そうした中でも、中村さんはアフガニスタンに通い続け、活動の軸足を医療から農村振興へと移していきました。「飢えや渇きは医療では治せない」という信念からです。安全な飲み水がないため赤痢で次々に命を落とす村人たちを救うために、井戸を掘る。戦争で破壊された農業用水路を復活させ、村人たちが生きていけるようにする。その活動ぶりは、著書『医者 井戸を掘る』(石風社)で詳しく知ることができます。
中村さんの活動が欧米の援助団体と異なるのは、村人たちの身の丈にあった支援に徹したことです。井戸掘りには、中田正一さん(故人)が主宰する「風の学校」の協力を得ました。中田さんは、日本に昔から伝わる「上総(かずさ)掘り」の技法を活かした井戸掘りを世界に広めた人です。竹と綱を使って井戸を掘る技法です。
用水路の取水堰をつくるにしても、日本の伝統的な技法を活用しました。江戸時代に築かれ、今でも使われている福岡県朝倉市の山田堰などを参考にした、と伝えられています。アフガンの農民たちが手にすることができるもので作り、維持することにこだわったのです。
それが農民たちをどれだけ勇気づけ、励ましたことか。民族や部族の利害が複雑にからまり、危険きわまりないアフガニスタンで中村さんが活動を続けることができたのは、その人柄に加え、こうした仕事ぶりに地元の人たちが絶大な信頼を寄せていたからでした。
その中村さんが銃で撃たれ、亡くなりました。アフガニスタンの人々、そしてアフガンを思う人たちに与えた衝撃の大きさは計り知れません。
「私は旅をしてきた。人の何倍か余計に生きた気がする。この旅はいつまで続くのだろう。今後も現地活動は際限がない。だが、そこに結晶した心ある人々の思いが、一隅の灯りとして、静かに続くことを祈る」
中村さんは『医は国境を越えて』(石風社)の結びにそう記しました。そう、中村さんが倒れても、灯りは消えず、人々の営みは静かに続く。信じて赴く者がいる限り。
*メールマガジン「風切通信 65」 2019年12月5日
≪写真説明&Source≫
◎中村哲・医師 (Zaheer Asefi さんのfacebook から)
≪参考サイト≫
◎上総掘りの技法(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=xzZp9flWZZw
◎山田堰の構造(動画)
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO92614040Y5A001C1000000/
フランス革命の前夜、ルイ16世の王妃マリー・アントワネットは、民衆が飢えに苦しんでいると聞いて「パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない」とうそぶいた、と伝えられている。

それは史実ではなく、王政を憎悪する革命派が作り上げたエピソードのようだが、マリー・アントワネットが絶対君主制に固執し、自由と平等を「唾棄すべきもの」と考えていたことは間違いない。18世紀末、時代がどう動いているか、ついに理解できなかった。
今の日本を「革命前夜のフランス」にたとえるつもりはないが、「時代の風に鈍感」という点で、山形県の吉村美栄子知事にはフランスの王妃と重なるものがある。吉村知事は「奥羽新幹線と羽越新幹線の二つを新たに造ろう」と提唱している。それは、富士山からゆっくりと下山している人たちに「次はエベレストを目指そう」と呼びかけるようなものだ。
鈍感さは、山形県庁の情報技術(IT)政策の面でも見てとれる。
IT革命の波は、私たちの命と健康にかかわる医療分野にも急速に及び、山形県は斎藤弘知事の時代に県立病院に大々的にITを導入することを決めた。2007年から08年にかけて、赤字続きの県立病院を立て直すために経営改善計画を立て、最新の医療情報システムを導入する手立てを講じた。
医療分野はすでに世界中で、IT企業の主戦場の一つになっていた。入札に参加した複数の企業の中から、山形県が選んだのがアクセンチュアの医療情報システムだった。吉村美栄子氏が斎藤弘氏の後を継いで知事に就任した年のことである。
アクセンチュアは、ニューヨークやシカゴを拠点とする世界最大のコンサルタント会社だ。従業員は48万人。経営戦略の助言にとどまらず、ITサービスの提供も得意とする。この会社の日本法人が2009年、約18億円で山形県の医療情報システムの落札に成功した。
同社の医療情報システムを考案したのは秋山昌範(まさのり)・東大教授である。徳島大学医学部を卒業した後、国内で医師として働き、マサチューセッツ工科大学の客員教授を務めた。秋山氏は医療とITの両方が分かる研究者として東大に迎えられ、医師の中には彼のシステムを「画期的」ともてはやす人も少なくなかった。
ただ、心配する声はあった。秋山氏の唱えるシステムを実際に導入して動かしている病院は、まだ一つもなかったからだ。不安は現実になる。県立中央、河北、新庄の3病院に共通の新システムを導入するはずだったのに、その構築作業は遅々として進まなかった。
病院の医療情報システムは複雑極まりない。図1のように、医師が患者を診断して書き込む電子カルテ、各種の検査や薬の処方を処理するオーダリングシステム、看護師の支援システム、診療報酬を扱う医事会計といった基幹システムに入退院の手続きや手術管理、輸血管理、地域の医療機関との連携など多数のサブシステムが連結される。
しかも、これらすべてのシステムを24時間、365日、動かさなければならない。地震や水害で電気が来なくなったからダウンした、などということは許されない。おまけに、扱うのは患者の繊細な個人情報がほとんど。「システムの極致」とも言える代物だ。
ただでさえ、システムの構築は至難の技なのに、日本には「ガラパゴスの壁」もあった。日本の携帯電話は「インターネットにつながる」「ワンセグでテレビを観ることもできる」など独自の進化を遂げたが、スマートフォンが登場するや、それまでの携帯は「ガラパゴス携帯」、略して「ガラケー」と呼ばれ、隅に追いやられた。
それと同じことが医療情報システムの世界でも起きている。日本の医師たちの細かい注文に応じてユニークなシステムを作っているうちに、世界の標準からかけ離れたシステムになってしまったのだ。日本の「ガラパゴス医療情報システム」を秋山氏が構想するシステムに円滑に切り替えるのはそもそも不可能だった、と言うしかない。
受注から1年後、アクセンチュアは契約の1割、約1億8000万円の違約金を払って山形県から撤退した。システムの考案者、秋山教授はその後、架空の研究費をだまし取ったとして詐欺罪で有罪判決を受け、表舞台から姿を消した。
一度目の失敗には幾分、同情の余地がある。東大教授が考案した画期的なシステムを引っ提げて、世界最大のコンサルタント会社が乗り込んできたのだ。幻惑されたとしても無理からぬ面がある。問題はその後にある。
3病院共通の医療情報システムの構築に失敗した山形県は取りあえず、表1のように県立中央、河北、新庄の3病院にNEC、CSI、富士通という別々のシステムを導入して急場をしのいだ。システム統一という目標を先送りしたのだ。
ITの技術革新はものすごいスピードで進む。新しいシステムも5年ほどで陳腐化する。それを考えれば、県は速やかに態勢を立て直し、気を引き締めてシステムの更新と統一の準備に取りかからなければならなかった。
ところが、吉村美栄子知事は「態勢の立て直し」を指示していない。県立病院を管轄する病院事業局の職員はそれまで通り、2、3年で知事部局の職員と入れ替わる人事を続けた。これでは、職員が難解な医療情報システムの仕組みに習熟できるわけがない。専門のシステムエンジニアを採用して育てることもしていない。
岩手県の場合、県立病院が多いこともあり、医療局に配属されると、職員の7割ほどは医療局に留まり、県立病院と行き来しながらノウハウを蓄積して次のシステム更新に備える。宮城県の県立病院の数は山形県と大差ないが、病院事業を県庁から切り離して地方独立行政法人「宮城県立病院機構」を作り、専門家を育ててきた。両県ともエンジニアを抱えている。そうしなければ、複雑な医療情報システムの設計と発注ができないからだ。
知事を筆頭に、山形県の幹部たちは「この間、何を考え、何をしていたのか」と問いたくなる。ことの重大さと困難さがまるで分っていないのではないか。当然のことながら、山形県立病院の医療情報システムの更新は、無様な経過をたどった(表2参照)。
県立3病院に電子カルテを納入したメーカーやベンダー(販売会社)に対して、県病院事業局が「医療情報システムの整備に関する提案をしてほしい」と要請したのは2015年のことだ。要請に応じたのは、かつて入札でアクセンチュアに敗れたNECと富士通だった。
その後、何が起きたのか。ここから先は関係者の証言があまりにも食い違い、判然としない。富士通の販売代理業務をしている山形新聞グループのYCC情報システムは「医療情報システムの更新計画から弊社を排除する動きがあった」として、2017年10月に朝井正夫社長名で新澤(しんざわ)陽英・県病院事業管理者あてに公開質問状を出した。
公開質問状には「県病院事業局は富士通社員を恫喝し、事実上、(入札)辞退を迫った」「富士通を撤退に追い込んで、同一系列の特定メーカー同士の入札をもくろんでいるとしか思えません」と記してある。「最初からNECとその提携先のCSIのシステムで統一するつもりで動いていた」と言いたかったようだ。
当時の県病院事業局の幹部の証言はまるで異なる。「私たちはNECと富士通の両方から提案してもらい、きちんとした入札をするつもりでいた。ところが、富士通が途中で入札手続きから降りてしまった。富士通社内の事情からと聞いている」と言う。
この騒動について、山形新聞は2017年12月に1面トップで「県立3病院のシステム統合 メーカー統一を先行」とセンセーショナルに報じた。翌年1月には3回の連載記事を掲載して「迷走、医療行政の怠慢」と指弾した。
県幹部の怠慢は記事で指摘している通りだ。その部分は納得がいく。だが、それ以外の記述は山新グループのYCC情報システムの言い分をなぞっただけである。今回のシステム統合で県の仕事がなくなるYCCの恨み辛みを綴っているに過ぎない。ひどい報道だ。
医療情報システムは今、どうなっているのか。日本国内の各社のシェア(図2参照)はどうか。そうしたことを踏まえて、医療とITの世界で起きていること、山形県当局が為すべきことを丁寧に、誠実に読者に伝えるのが新聞記者の務めではないか。
医療情報システムをめぐる県当局の仕事ぶりは、悲惨な結果をもたらした。新しいシステムへの更新時期が迫る中で、入札に参加した企業はNEC1社だけとなった。
情報公開された入札調書(表3)によれば、県病院事業局が設定した予定価格は34億2743万円。これに対して、NECは3回の入札でいずれも39億円台の価格で応じた。競争相手がいないのだから、入札不調に終わってもNECはちっとも困らない。
困ったのは県側である。やむなく、NECに随意契約を持ちかけ、昨年3月、最終的に37億円で契約を交わした。入札時の予定価格に8%の消費税を加えた金額で落着した。
山形新聞が非難の矛先を県病院事業局に絞り、吉村知事の責任にまったく言及していないのも理解しがたい。確かに、病院を管轄する病院事業局とダムや水道を運営する企業局は会計上、知事部局から半ば独立しているが、山形県が行うすべての決定の最終的な責任が知事にあるのは自明のことだ。知事のみが選挙の洗礼を受け、幹部の人事権を握っているからだ。
吉村知事はサクランボやコメの販売促進、観光振興など「絵になること」には先頭に立って走り回る。だが、医療情報システムといった込み入った問題には、口をつぐむ。情報公開でどこまで公文書を出すかといったデリケートな問題についても、「法律の専門家の意見をお聞きして」などと逃げるのが常だ。
組織のトップは、すべての決定とその結果について責任を負わなければならない。重要な問題については、専門家の意見を聞いたうえで自ら考え、判断しなければならない。吉村知事には、その覚悟が感じられない。
(2019年11月29日 長岡 昇)
≪訂正≫最後から4段落目に「最終的に37億円で契約を交わした。予定価格を3億円も上回る」とあるのは誤りでした。「最終的に37億円で契約を交わした。入札時の予定価格に8%の消費税を加えた金額で落着した」と訂正します(本文は手直し済み)。入札時の予定価格は税抜きの価格でした。その後にあった「県の不手際によって、巨額の血税が失われた」という文章は削除します。
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の12月に寄稿した文章を転載したものです。見出しは異なります。
*図や表はクリックすると表示されます。
≪写真説明とSource≫
◎マリー・アントワネット(ヨコ)(名言倶楽部のサイト)
https://meigen.club/marie-antoinette/
≪参考サイト&文献≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎マリー・アントワネット(ウィキペディア)
◎Accenture
https://www.accenture.com/us-en
◎アクセンチュア株式会社(Accenture Japan Ltd)
https://www.accenture.com/jp-ja/company-japan-over-facts
◎秋山昌範(ウィキペディア)
◎国内外における医療情報の標準化の現状と展望(山本隆一、『情報管理』2017年12月号)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/60/9/60_619/_pdf/-char/ja
◎山形県立病院の医療情報システムのイメージ(山形県のサイト)
https://www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/publicfolder201802268403743825/8cc765991_30a430e130fc56f3.pdf
◎山形県の医療情報システムをめぐる経過(同)
https://www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/publicfolder201802268403743825/8cc765992_3053308c307e306e7d4c904e7b49306b306430443066.pdf
◎医療情報システムの入札に関する山形県の公文書

それは史実ではなく、王政を憎悪する革命派が作り上げたエピソードのようだが、マリー・アントワネットが絶対君主制に固執し、自由と平等を「唾棄すべきもの」と考えていたことは間違いない。18世紀末、時代がどう動いているか、ついに理解できなかった。
今の日本を「革命前夜のフランス」にたとえるつもりはないが、「時代の風に鈍感」という点で、山形県の吉村美栄子知事にはフランスの王妃と重なるものがある。吉村知事は「奥羽新幹線と羽越新幹線の二つを新たに造ろう」と提唱している。それは、富士山からゆっくりと下山している人たちに「次はエベレストを目指そう」と呼びかけるようなものだ。
鈍感さは、山形県庁の情報技術(IT)政策の面でも見てとれる。
IT革命の波は、私たちの命と健康にかかわる医療分野にも急速に及び、山形県は斎藤弘知事の時代に県立病院に大々的にITを導入することを決めた。2007年から08年にかけて、赤字続きの県立病院を立て直すために経営改善計画を立て、最新の医療情報システムを導入する手立てを講じた。
医療分野はすでに世界中で、IT企業の主戦場の一つになっていた。入札に参加した複数の企業の中から、山形県が選んだのがアクセンチュアの医療情報システムだった。吉村美栄子氏が斎藤弘氏の後を継いで知事に就任した年のことである。
アクセンチュアは、ニューヨークやシカゴを拠点とする世界最大のコンサルタント会社だ。従業員は48万人。経営戦略の助言にとどまらず、ITサービスの提供も得意とする。この会社の日本法人が2009年、約18億円で山形県の医療情報システムの落札に成功した。
同社の医療情報システムを考案したのは秋山昌範(まさのり)・東大教授である。徳島大学医学部を卒業した後、国内で医師として働き、マサチューセッツ工科大学の客員教授を務めた。秋山氏は医療とITの両方が分かる研究者として東大に迎えられ、医師の中には彼のシステムを「画期的」ともてはやす人も少なくなかった。
ただ、心配する声はあった。秋山氏の唱えるシステムを実際に導入して動かしている病院は、まだ一つもなかったからだ。不安は現実になる。県立中央、河北、新庄の3病院に共通の新システムを導入するはずだったのに、その構築作業は遅々として進まなかった。
病院の医療情報システムは複雑極まりない。図1のように、医師が患者を診断して書き込む電子カルテ、各種の検査や薬の処方を処理するオーダリングシステム、看護師の支援システム、診療報酬を扱う医事会計といった基幹システムに入退院の手続きや手術管理、輸血管理、地域の医療機関との連携など多数のサブシステムが連結される。
しかも、これらすべてのシステムを24時間、365日、動かさなければならない。地震や水害で電気が来なくなったからダウンした、などということは許されない。おまけに、扱うのは患者の繊細な個人情報がほとんど。「システムの極致」とも言える代物だ。
ただでさえ、システムの構築は至難の技なのに、日本には「ガラパゴスの壁」もあった。日本の携帯電話は「インターネットにつながる」「ワンセグでテレビを観ることもできる」など独自の進化を遂げたが、スマートフォンが登場するや、それまでの携帯は「ガラパゴス携帯」、略して「ガラケー」と呼ばれ、隅に追いやられた。
それと同じことが医療情報システムの世界でも起きている。日本の医師たちの細かい注文に応じてユニークなシステムを作っているうちに、世界の標準からかけ離れたシステムになってしまったのだ。日本の「ガラパゴス医療情報システム」を秋山氏が構想するシステムに円滑に切り替えるのはそもそも不可能だった、と言うしかない。
受注から1年後、アクセンチュアは契約の1割、約1億8000万円の違約金を払って山形県から撤退した。システムの考案者、秋山教授はその後、架空の研究費をだまし取ったとして詐欺罪で有罪判決を受け、表舞台から姿を消した。
一度目の失敗には幾分、同情の余地がある。東大教授が考案した画期的なシステムを引っ提げて、世界最大のコンサルタント会社が乗り込んできたのだ。幻惑されたとしても無理からぬ面がある。問題はその後にある。
3病院共通の医療情報システムの構築に失敗した山形県は取りあえず、表1のように県立中央、河北、新庄の3病院にNEC、CSI、富士通という別々のシステムを導入して急場をしのいだ。システム統一という目標を先送りしたのだ。
ITの技術革新はものすごいスピードで進む。新しいシステムも5年ほどで陳腐化する。それを考えれば、県は速やかに態勢を立て直し、気を引き締めてシステムの更新と統一の準備に取りかからなければならなかった。
ところが、吉村美栄子知事は「態勢の立て直し」を指示していない。県立病院を管轄する病院事業局の職員はそれまで通り、2、3年で知事部局の職員と入れ替わる人事を続けた。これでは、職員が難解な医療情報システムの仕組みに習熟できるわけがない。専門のシステムエンジニアを採用して育てることもしていない。
岩手県の場合、県立病院が多いこともあり、医療局に配属されると、職員の7割ほどは医療局に留まり、県立病院と行き来しながらノウハウを蓄積して次のシステム更新に備える。宮城県の県立病院の数は山形県と大差ないが、病院事業を県庁から切り離して地方独立行政法人「宮城県立病院機構」を作り、専門家を育ててきた。両県ともエンジニアを抱えている。そうしなければ、複雑な医療情報システムの設計と発注ができないからだ。
知事を筆頭に、山形県の幹部たちは「この間、何を考え、何をしていたのか」と問いたくなる。ことの重大さと困難さがまるで分っていないのではないか。当然のことながら、山形県立病院の医療情報システムの更新は、無様な経過をたどった(表2参照)。
県立3病院に電子カルテを納入したメーカーやベンダー(販売会社)に対して、県病院事業局が「医療情報システムの整備に関する提案をしてほしい」と要請したのは2015年のことだ。要請に応じたのは、かつて入札でアクセンチュアに敗れたNECと富士通だった。
その後、何が起きたのか。ここから先は関係者の証言があまりにも食い違い、判然としない。富士通の販売代理業務をしている山形新聞グループのYCC情報システムは「医療情報システムの更新計画から弊社を排除する動きがあった」として、2017年10月に朝井正夫社長名で新澤(しんざわ)陽英・県病院事業管理者あてに公開質問状を出した。
公開質問状には「県病院事業局は富士通社員を恫喝し、事実上、(入札)辞退を迫った」「富士通を撤退に追い込んで、同一系列の特定メーカー同士の入札をもくろんでいるとしか思えません」と記してある。「最初からNECとその提携先のCSIのシステムで統一するつもりで動いていた」と言いたかったようだ。
当時の県病院事業局の幹部の証言はまるで異なる。「私たちはNECと富士通の両方から提案してもらい、きちんとした入札をするつもりでいた。ところが、富士通が途中で入札手続きから降りてしまった。富士通社内の事情からと聞いている」と言う。
この騒動について、山形新聞は2017年12月に1面トップで「県立3病院のシステム統合 メーカー統一を先行」とセンセーショナルに報じた。翌年1月には3回の連載記事を掲載して「迷走、医療行政の怠慢」と指弾した。
県幹部の怠慢は記事で指摘している通りだ。その部分は納得がいく。だが、それ以外の記述は山新グループのYCC情報システムの言い分をなぞっただけである。今回のシステム統合で県の仕事がなくなるYCCの恨み辛みを綴っているに過ぎない。ひどい報道だ。
医療情報システムは今、どうなっているのか。日本国内の各社のシェア(図2参照)はどうか。そうしたことを踏まえて、医療とITの世界で起きていること、山形県当局が為すべきことを丁寧に、誠実に読者に伝えるのが新聞記者の務めではないか。
医療情報システムをめぐる県当局の仕事ぶりは、悲惨な結果をもたらした。新しいシステムへの更新時期が迫る中で、入札に参加した企業はNEC1社だけとなった。
情報公開された入札調書(表3)によれば、県病院事業局が設定した予定価格は34億2743万円。これに対して、NECは3回の入札でいずれも39億円台の価格で応じた。競争相手がいないのだから、入札不調に終わってもNECはちっとも困らない。
困ったのは県側である。やむなく、NECに随意契約を持ちかけ、昨年3月、最終的に37億円で契約を交わした。入札時の予定価格に8%の消費税を加えた金額で落着した。
山形新聞が非難の矛先を県病院事業局に絞り、吉村知事の責任にまったく言及していないのも理解しがたい。確かに、病院を管轄する病院事業局とダムや水道を運営する企業局は会計上、知事部局から半ば独立しているが、山形県が行うすべての決定の最終的な責任が知事にあるのは自明のことだ。知事のみが選挙の洗礼を受け、幹部の人事権を握っているからだ。
吉村知事はサクランボやコメの販売促進、観光振興など「絵になること」には先頭に立って走り回る。だが、医療情報システムといった込み入った問題には、口をつぐむ。情報公開でどこまで公文書を出すかといったデリケートな問題についても、「法律の専門家の意見をお聞きして」などと逃げるのが常だ。
組織のトップは、すべての決定とその結果について責任を負わなければならない。重要な問題については、専門家の意見を聞いたうえで自ら考え、判断しなければならない。吉村知事には、その覚悟が感じられない。
(2019年11月29日 長岡 昇)
≪訂正≫最後から4段落目に「最終的に37億円で契約を交わした。予定価格を3億円も上回る」とあるのは誤りでした。「最終的に37億円で契約を交わした。入札時の予定価格に8%の消費税を加えた金額で落着した」と訂正します(本文は手直し済み)。入札時の予定価格は税抜きの価格でした。その後にあった「県の不手際によって、巨額の血税が失われた」という文章は削除します。
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』の12月に寄稿した文章を転載したものです。見出しは異なります。
*図や表はクリックすると表示されます。
≪写真説明とSource≫
◎マリー・アントワネット(ヨコ)(名言倶楽部のサイト)
https://meigen.club/marie-antoinette/
≪参考サイト&文献≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎マリー・アントワネット(ウィキペディア)
◎Accenture
https://www.accenture.com/us-en
◎アクセンチュア株式会社(Accenture Japan Ltd)
https://www.accenture.com/jp-ja/company-japan-over-facts
◎秋山昌範(ウィキペディア)
◎国内外における医療情報の標準化の現状と展望(山本隆一、『情報管理』2017年12月号)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/60/9/60_619/_pdf/-char/ja
◎山形県立病院の医療情報システムのイメージ(山形県のサイト)
https://www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/publicfolder201802268403743825/8cc765991_30a430e130fc56f3.pdf
◎山形県の医療情報システムをめぐる経過(同)
https://www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/publicfolder201802268403743825/8cc765992_3053308c307e306e7d4c904e7b49306b306430443066.pdf
◎医療情報システムの入札に関する山形県の公文書
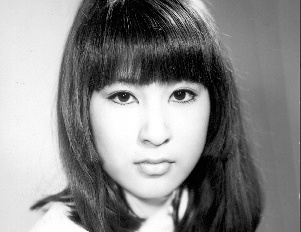
歌手の藤圭子は1951年、岩手県一関市で生まれた。本名、宇多田純子。若い人には「宇多田ヒカルの母」と言った方がピンと来るかもしれない。
父親は浪曲師、母親は三味線弾きで、東北や北海道を旅して回った。貧しい暮らしだった。泊まる宿がなく、町外れのお堂で夜露をしのいだこともあったという。高校への進学をあきらめ、彼女は一家の暮らしを支えるため歌手になった。
十五 十六 十七と
私の人生 暗かった
過去はどんなに暗くとも
夢は夜ひらく
絞り出すような声で歌う『圭子の夢は夜ひらく』が大ヒットしたのは1970年、18歳の時である。暗い生い立ちと相まって、彼女の歌は人々の心に沁み込んでいった。
藤圭子に登場してもらったのは、コンピューターとインターネットの生い立ちも、実はとても暗いからだ。
今日のコンピューターの原型の一つは、第2次大戦の最中、イギリスによって作られた。戦争に勝つため、イギリスはドイツの暗号「エニグマ」の解読に人材と資金を惜しみなく注ぎ込んだ。ピーク時には、天才数学者アラン・チューリングら1万人の人員が動員され、ドイツの暗号を次々に解読していった。
暗号の解読で決定的な役割を果たしたのが「コロッサス」という電子計算機である(写真参照)。暗号を解読するためには膨大な数の順列組み合わせを解かなければならない。それは、多くの数学者や言語学者がかかりきりになっても、とてつもなく時間がかかる困難な作業だった。「人力では解読不能」とドイツ側は見ていた。その隘路(あいろ)をイギリスは電子計算機を開発して突破したのである。
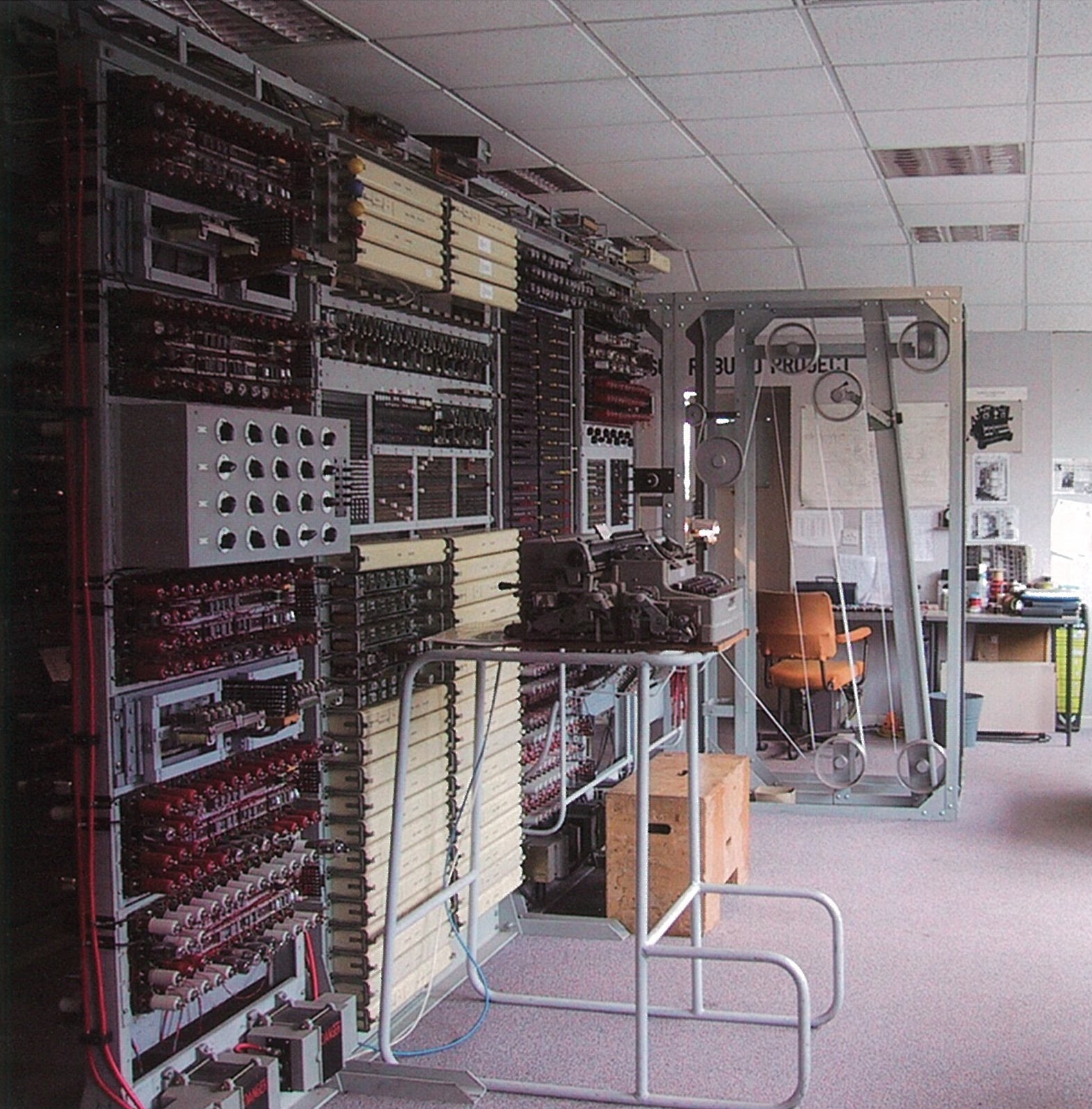
コロッサスは戦争に勝つうえで極めて重要な役割を果たしたが、その存在は戦後も長い間、秘密にされた。ドイツや日本との戦争の後、イギリスとアメリカはすぐさま、ソ連との冷戦に突入したからだ。冷戦は「全面核戦争」も辞さない、非情な戦いだった。
核兵器を次々に撃ち込まれれば、軍の指揮命令系統はズタズタになる。報復もできなくなる。どうするか。米国防総省は1958年に高等研究計画局(ARPA Advanced Research Projects Agency)を設立し、その対策に着手した。国防総省と重要な基地を分散型のネットワークで結び、核攻撃に備えることにした。
当初、ネットワークの構築に取り組んだのはカリフォルニア大学やスタンフォード研究所、ユタ大学の研究者たちであり、プロジェクトは研究機関の大型コンピューターを結ぶ形で進行した。このため、「インターネットの誕生と核戦略は無関係」と唱える人たちがいる。
だが、国防総省や軍は「学術振興」のために多額の研究費を出したりしない。彼らは戦争に備えるために働いているのであり、その目的は戦争に勝つことである。最初に構築されたネットワークがARPANET(アーパネット)と名付けられたのは、その生い立ちを何よりも雄弁に物語っている。インターネットが米ソ冷戦の中で生まれたことを認めない人たちは、歴史の闇に目を向けようとしない人たちである。

コンピューターもインターネットも、その生い立ちはとても暗い。けれども、軍事的な制約から解き放たれるや、どちらも民需をバネにして飛躍的な発展を遂げた。
イギリスが開発した電子計算機は会議室の壁を埋めるような大きさだったが、いま私たちはそれとは比べようもないほど高性能で小型のスマホ(電子計算機の進化形)を手にしている。初期のインターネットは大型コンピューター同士で短い文章をやり取りするレベルだったが、その後、急激に改良され、経済と社会の仕組みを一変した。コンビニも宅配便も、インターネットが普及して可能になったビジネスだ。
情報技術(IT)の進展は、農業革命や産業革命に次ぐ「第三の革命」と呼ぶにふさわしい変化をもたらし、さらに新しい地平を切り拓きつつある。
いつの世も、革命に抵抗するのは権力を握る者と既得権益層と、相場が決まっている。民間企業は市場経済の波にもまれ、生き抜くためにIT革命に懸命に対応しようとしているが、行政や議会、裁判所はどこの国でもグズグズしている。「対応しなければ立ち行かない」という切迫感がないからだ。
それは「情報公開を渋る」という形で顕著に現れる。自分たちが何をしているのか。それを主権者である国民に説明する責任があるのは自明のことだ。税金の使い方をガラス張りにするのも当たり前のこと。ITを存分に活用すべきだ。なのに、何かと理由を付けて逃れようとする。
この秋、全国市民オンブズマン連絡会議は「2019年 政務活動費 情報公開度ランキング」というのを発表した。都道府県、政令市、中核市ごとに議会の情報公開状況を採点してランク付けしたもので、情報公開の「渋り具合」一覧にもなっている。
採点は?政務活動に使った経費の領収書をインターネットで公開しているか?議員が作る会計帳簿をネットで公開しているか?活動報告書の提出義務付けと公開状況?視察報告書の提出義務付けと公開状況?政務活動費の手引書の公開状況、の5項目について百点満点で行っている(表1)。
表2と表3、表4は一覧表から抜粋して作成した。都道府県別では兵庫県がトップである。でたらめな出張を繰り返し、それが露見するや「号泣会見」をして有名になった野々村竜太郎県議(詐欺罪で有罪、執行猶予中)がいたところだ。2位の奈良県でも、かつて県議の領収書偽造が発覚した。不正があったところが悔い改めた結果、と言える。政令市では静岡市、中核市では函館市が1位だ。
わが故郷、山形県はどうか。県議会は47都道府県中、26位。ここ3年、ずっと20位台だ。「このくらいは公開しておくか」といった風情で、まったくやる気が感じられない。一方、この春めでたく中核市に昇格した山形市は初めてランキングに登場したと思ったら、全国に58ある中核市のうち、なんとワースト3だった。
市民オンブズマン山形県会議は、2005年度分から2007年度分まで山形市議の政務調査費を連続して調べ、住民監査請求をしたうえで返還訴訟を起こした。裁判は、返還請求の対象になった山形市議が請求額の20%を自主的に返納し、議長が「使途基準を明確にして透明性の確保に努める」と約束したため訴えを取り下げる、という経過をたどった。
オンブズマン側はその後、山形県議会議員の政務調査費(2012年、政務活動費に改称)のチェックに力を注いだため、山形市議の分は調べていない。この間、山形市議会は透明度を上げる努力をほとんどしていなかった。
山形市を除く鶴岡、酒田、米沢など県内のすべての市議会は、すでに領収書をインターネットで公開するなど、有権者に対する責任を果たしている。山形市議会だけがオンブズマンとの約束を破り、怠けていたのである。「中核市」の看板が泣く。
オンブズマン山形は比較的穏健なことで知られる。が、ここまでコケにされては黙っているわけにはいかない。というわけで、十数年ぶりに山形市議全員の政務活動費を調べることを決め、10月中旬、領収書など全文書の公開を請求した。市議33人分の文書が6千ページほど開示される見込みだ。きっちり調べ、不適切な支出があれば追及したい。
山形市議会政務活動費条例には「議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、その使途の透明性の確保に努める」(第7条)と明記してある。議長はどう考えているのか。
山形市議会は今年4月の選挙で顔ぶれと会派の構成が変わり、30年ぶりに自民党の議長が選出された。その斎藤武弘議長は「「ビリから3番目と聞いて、私もびっくりした。正直言って恥ずかしい」と述べた。そのうえで、「公金を使っているのだから、きちんと説明するのは当然のこと。各会派の意向もうかがいながら、領収書のインターネット公開など、できることから取り組みたい」と語った。
IT革命はこれからさらに進む。30年後、社会はどうなっているのか。予測できる人はほとんどいない。私たちの世代の多くは、もうこの世にいない。それを目撃するのは子の世代、孫の世代である。
いま、私たちにできることは何か。静かに、しかし深いところで進む革命をしっかり受けとめ、為すべきことをきちんと為すことではないか。情報公開制度をより充実したものにして、何が起きているのか、みんなが分かる社会を造っていくことではないのか。未来への扉を広く開けて、次の世代に引き継ぎたい。
*メールマガジン「風切通信 63」 2019年10月30日
*この文章は、月刊『素晴らしい山形』11月に寄稿したものです。
≪写真説明と出典≫
◎歌手、藤圭子(1970年当時、ウェブ論座から)
https://webronza.asahi.com/culture/themes/2913090200003.html
◎イギリスが暗号解読のために開発したコロッサスの復元機(大駒誠一『コンピュータ開発史』から複写)。暗号解読の本部があったブレッチリーパークに保存されている
◎米国防総省(ペンタゴン)。現在は人工知能(AI)の軍事利用に巨額の研究費を投じている(CNNのサイトから)
https://www.cnn.co.jp/tech/35125493.html
≪参考文献&サイト≫ *ウィキペディアのURLは省略
◎藤圭子(ウィキペディア)
◎藤圭子さんの壮絶な生い立ち(女性セブン2013年9月12日号、ライブドアニュースに転載)
https://news.livedoor.com/article/detail/8018068/
◎『悲しき歌姫』(木下英治、イースト・プレス)
◎『コンピュータ開発史』(大駒誠一、共立出版)
◎『暗号の天才』(R・W・クラーク、新潮選書)
◎『暗号解読』(サイモン・シン、新潮社)
◎『ヴェノナ』(ジョン・アール・ヘインズ&ハーヴェイ・クレア、中西輝政監訳、PHP研究所)
◎アラン・チューリング(ウィキペディア)
◎インターネットの歴史(木暮仁のサイト)
http://www.kogures.com/hitoshi/history/internet/index.html
◎インターネットの歴史(ウィキペディア)
◎Who invented the internet?
https://www.history.com/news/who-invented-the-internet
◎A simple history of the Internet
https://intetics.com/blog/a-simple-history-of-the-internet
◎ARPANET(ウィキペディア)
◎政務活動費の情報公開度ランキング(2019年9月、全国市民オンブズマン連絡会議)
権力者は孤独である。総理大臣にせよ、県知事にせよ、あらゆる問題について最終的には一人で決断しなければならない。そして、その決断がどのような結果になろうとも、すべての責任を負わなければならない。

その重圧は、時には耐えがたいほどだろう。だからこそ、優れた政治家は「ブレーン(知恵袋)」を持つ。経済や外交の専門家、情報のプロや文化人を抱え、折に触れてその知恵に頼る。そうしなければ、孤独に耐えられないからだ。
3期10年余りの吉村美栄子・山形県知事の県政運営を見ていて思うのは、「この知事にはブレーンがいない」ということである。ブレーンなき政治は何をもたらすか。6月29日付のコラムで取り上げた「フル規格の新幹線整備構想」はその答えの一つと言っていい。
政府も地方自治体も膨大な借金を抱えている。医療と福祉の負担は膨らむばかり。子どもが減り、高齢者があふれる社会でどのような道を切り拓いていくのか。私たちの社会は未知の海に漕ぎ出し、荒波を乗り越えて行かなければならない。
そういう時代に「東北に二つの新しい新幹線を造ろう」と呼びかけることがどれほど「お門(かど)違いの政策」か。フル規格の新幹線の建設費は1キロ100億円前後、100キロで1兆円もかかる。冷静に考えれば、中学生でも「とても無理な話」と分かる。
なのに、吉村知事には冷静にそう説くブレーンがいない。「フル規格の奥羽・羽越新幹線の実現」に向かってひた走る。地元の山形新聞も経済界も「オール山形で夢を叶えよう」と、熱にうかされたように叫んでいる。
新聞や経済人が叫ぶだけなら、何も問題はない。だが、県知事が唱えるとなると、話は違ってくる。新しい事業が始まり、県職員が走り回り、私たちの血税が費やされていくからだ。
吉村知事が2期目に入った2013年(平成25年)から、フル規格の新幹線整備運動のためにどのくらいの県費が投入されたのか。図1はその一覧グラフである。最初の年は「新幹線推進県民運動事業費」と名付けられ、202万円と小さな予算だった。それが翌年は484万円、翌々年は819万円と、倍々ゲームのように膨らみ続けた。
3期目初年の2017年(平成29年)には3162万円に達し、以後、ほぼ同額の予算が計上されている。総額1億2112万円。知事が唱え、地元の山形新聞があおり、市町村長や経済人も加わる「県民運動」に多額の県費が投じられた。
いったい、どのように使われているのか。その実情を調べていくと、嘆きは一段と深まる。表1は支出の主な内容である。2014年3月に山形市で、京都大学の藤井聡教授を講師に招いて初めてのシンポジウムが開かれた。教授は「フル規格新幹線の整備によってビジネスが生まれ、人が定着する。山形の人口減少に歯止めをかけるだけでなく、増加に転じさせることができる」と語った(同年3月21日付の山形新聞記事)。
その藤井教授は4年後の講演では「財務省は『山形にはミニ新幹線がある。まだ何もない四国や山陰に比べ、優先順位は低い』と言って簡単には(奥羽・羽越新幹線を)認めない」と語った。そこまではいいが、続いて「仙山線ルートに新幹線を通してはどうか」と、突拍子もない提案をした(河北新報の2018年9月3日付社説)。なんとも無責任な学者である。
それでも、講演会くらいなら費用は少なくて済む。予算が膨らみ始めたのは、2015年から外部の専門家を招いて「ワーキングチーム」を発足させ、フル規格の新幹線整備に向けて本格的な検討を始めたあたりからだ。旅費や謝礼で費用がかさむ。表2はそのチームのメンバー表である。運輸政策研究機構は旧運輸省系の外郭団体、エム・アール・アイリサーチアソシエイツは三菱総研系のシンクタンク、フィディア総合研究所は荘内銀行が作ったシンクタンクだ。
チームには、人口の減少を示す県内の地域ごとのデータや鉄道や空路、車を使った県民の移動データなどが示され、議論が交わされるのだが、情報公開された文書を読むと、データの膨大さに比べて議論があまりにも空疎なことに脱力感を覚える。誰も「実現の展望」を見出せないからだろう。
専門家らしい指摘もある。「山形県目線だけでなく、全国的なネットワークの視点、県外の方々の視点、外国人の視点などについて踏まえる必要がある」(第1回会合)、「フル規格新幹線を整備することは目標ではなく、新しい山形を作るための手段である。山形の目指す方向性を定め、その次にフル規格新幹線の事業性を検討すべきだ」(第7回会合)。
それぞれ、まっとうな意見だが、こうした考えが報告書に反映されることはない。なにせ、ワーキングチームの設置を指示した吉村知事本人が「目標と手段」を取り違え、奥羽・羽越新幹線の実現に血眼になっているからだ。
県庁の内部では何が起きているのか。部長会議のメンバーに話を聞いた。一人は「フル規格新幹線の整備のことが部長会議で議論されたことは、記憶する限り、2期目の4年間で一度もない」と述べた。もう一人の述懐はより率直だった。彼は次のように語った。
「新幹線関係の予算が話題になったことはない。部長会議では報告事項が多く、政策論議が交わされることはまずない。予算編成にしても、下から積み上げていっても知事が『いらない』と言えば、それまで。そもそも、知事は県職員を信用していないのではないか。県経済同友会の朝食会などで吹き込まれたアイデアで動くことが多かった」
ブレーン不在の県知事の下、部長会議での議論もないまま、フル規格の新幹線整備促進の予算はますます膨らんでいった。2016年5月、県主導で市町村や経済団体で構成する「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」を立ち上げた。吉村知事の「オール山形翼賛組織」である(写真参照)。
この年から、実現同盟の運営やそのホームページの制作、シンポジウム開催の外注が始まる。表3にあるように、公募式の最初のコンペでこの仕事を受注したのは山形新聞グループの広告会社、山形アドビューロだ。業務には新聞広告の掲載やラジオでのPRも含まれる。知事が唱え、山形新聞がキャンペーン記事を載せ、グループ企業が広告の仕事を請け負う。同社の業務委託料は3年分で4000万円近くになる。
去年は吉村知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いるダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)が1817万円で受託した。山形アドビューロとダイバーシティメディアの2社に支払われた委託料の合計は5700万円を上回り、これだけで約1億2千万円の新幹線整備事業予算の半分近くになる。
ダイバーシティメディアについては、今年の1月30日付のコラムで同社が県内周遊促進の観光キャンペーン事業を受注した経緯を詳しく報告した。県の仕事を取ってくるのが実にうまい。ちなみに、観光キャンペーン事業を担当したのは吉村和文氏の長男で同社取締役の和康氏である。2017年3月期の株主総会資料に書いてある。知事が発注し、義理のいとこが受注した仕事をその長男がこなす。「身内と取り巻きに温かい県政」の極みではないか。
フル規格の新幹線整備促進事業について、県の幹部が公然と異を唱えたことは皆無のようだが、職員全員が唯々諾々と知事の意向通りに動いているわけではない。情報公開で開示された2775ページの公文書の中に、かすかに抵抗の痕跡があった。
2015年度予算査定の「財政課長調整結果報告書」の参考欄に、次のような記述がある。「(フル規格新幹線の整備を求める)県の要望が認められたとしても、工事の着工は現在の整備計画が完了する平成47年(2035年)以降となり、さらに工事完成まで10年?30年を要すると想定される」(カッコ内は筆者が補足)。
わずか3行のメモ。だが、その行間からは「実現する可能性があるか疑わしい。仮に実現するとしても、30年から50年も先のことではないか」との思いがにじみ出る。財政をつかさどるプロとして、書き残さないではいられなかったのだろう。
県幹部の証言によれば、政策にしても予算にしても、2期目に入った頃から、吉村知事は自分の考えを強烈に貫くようになったという。自由に議論を交わし、より良い県政を進めていく雰囲気が失われて久しい。では、本人はどのような心境にあるのか。
ここは、吉村和文氏のブログ「約束の地へ」から引用したい。2016年5月8日のブログによれば、吉村美栄子知事は自らの後援会の総会で次のように挨拶した。「自分はこの7年間、ただ愚直に県民の皆さんの笑顔が見たい、県民の皆さんから幸せになってほしいという一心で走り続けてきた。県民の方としっかりと向かい合い、温かい県政を願い、作ってきた。これからも、みんなで心の通った山形県を作っていきましょう」
吉村知事が一生懸命、働いていることは疑いない。知事交際費の明細を見れば、よくある「宴会政治」とは無縁であることも分かる。災害の現場などにもよく足を運ぶ。温かさを感じる時もある。けれども、足元の県庁内ですら「心が通わなくなっている現実」を知事は自覚しているのか。
冒頭に記したように、吉村知事はブレーンを作り、助言を求めることをしてこなかった。自らと異なる意見を持つ人の声に耳を傾ける度量も乏しい。性格に加えて、大きい組織を率いた経験がないからかもしれない。在任が長くなるにつれて、それが「身内・取り巻き県政」の様相を呈し、度し難いほどひどくなってきた。
そのように批判されれば、本人は「人のあら探しばかりしていないで、自分ならどうするか前向きのことが言えないの」と反論するかもしれない。一人の元新聞記者としては、こう答えるのが精いっぱいである。
「時代の風に敏感でありたい。世界は、田中角栄氏が日本列島改造論を唱えた時代とは、まるで違うものになってしまった。地味ではあっても、人を育て、人を惹きつけるために力を尽くす時ではないか」
*この文章は、月刊『素晴らしい山形』の10月号に寄稿したものを若干手直ししたものです。
≪写真説明とSource≫
◎山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟の2016年総会。吉村知事と県内選出の与野党国会議員が山形市内のホテルで気勢を上げた(実現同盟の公式サイトから)
≪参考資料&サイト≫
◎奥羽・羽越新幹線整備構想に関して山形県が情報公開した文書
◎山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟の公式サイト
https://www.ou-uetsu-shinkansen.jp/
◎奥羽・羽越新幹線整備構想に関する山形新聞、河北新報の記事

その重圧は、時には耐えがたいほどだろう。だからこそ、優れた政治家は「ブレーン(知恵袋)」を持つ。経済や外交の専門家、情報のプロや文化人を抱え、折に触れてその知恵に頼る。そうしなければ、孤独に耐えられないからだ。
3期10年余りの吉村美栄子・山形県知事の県政運営を見ていて思うのは、「この知事にはブレーンがいない」ということである。ブレーンなき政治は何をもたらすか。6月29日付のコラムで取り上げた「フル規格の新幹線整備構想」はその答えの一つと言っていい。
政府も地方自治体も膨大な借金を抱えている。医療と福祉の負担は膨らむばかり。子どもが減り、高齢者があふれる社会でどのような道を切り拓いていくのか。私たちの社会は未知の海に漕ぎ出し、荒波を乗り越えて行かなければならない。
そういう時代に「東北に二つの新しい新幹線を造ろう」と呼びかけることがどれほど「お門(かど)違いの政策」か。フル規格の新幹線の建設費は1キロ100億円前後、100キロで1兆円もかかる。冷静に考えれば、中学生でも「とても無理な話」と分かる。
なのに、吉村知事には冷静にそう説くブレーンがいない。「フル規格の奥羽・羽越新幹線の実現」に向かってひた走る。地元の山形新聞も経済界も「オール山形で夢を叶えよう」と、熱にうかされたように叫んでいる。
新聞や経済人が叫ぶだけなら、何も問題はない。だが、県知事が唱えるとなると、話は違ってくる。新しい事業が始まり、県職員が走り回り、私たちの血税が費やされていくからだ。
吉村知事が2期目に入った2013年(平成25年)から、フル規格の新幹線整備運動のためにどのくらいの県費が投入されたのか。図1はその一覧グラフである。最初の年は「新幹線推進県民運動事業費」と名付けられ、202万円と小さな予算だった。それが翌年は484万円、翌々年は819万円と、倍々ゲームのように膨らみ続けた。
3期目初年の2017年(平成29年)には3162万円に達し、以後、ほぼ同額の予算が計上されている。総額1億2112万円。知事が唱え、地元の山形新聞があおり、市町村長や経済人も加わる「県民運動」に多額の県費が投じられた。
いったい、どのように使われているのか。その実情を調べていくと、嘆きは一段と深まる。表1は支出の主な内容である。2014年3月に山形市で、京都大学の藤井聡教授を講師に招いて初めてのシンポジウムが開かれた。教授は「フル規格新幹線の整備によってビジネスが生まれ、人が定着する。山形の人口減少に歯止めをかけるだけでなく、増加に転じさせることができる」と語った(同年3月21日付の山形新聞記事)。
その藤井教授は4年後の講演では「財務省は『山形にはミニ新幹線がある。まだ何もない四国や山陰に比べ、優先順位は低い』と言って簡単には(奥羽・羽越新幹線を)認めない」と語った。そこまではいいが、続いて「仙山線ルートに新幹線を通してはどうか」と、突拍子もない提案をした(河北新報の2018年9月3日付社説)。なんとも無責任な学者である。
それでも、講演会くらいなら費用は少なくて済む。予算が膨らみ始めたのは、2015年から外部の専門家を招いて「ワーキングチーム」を発足させ、フル規格の新幹線整備に向けて本格的な検討を始めたあたりからだ。旅費や謝礼で費用がかさむ。表2はそのチームのメンバー表である。運輸政策研究機構は旧運輸省系の外郭団体、エム・アール・アイリサーチアソシエイツは三菱総研系のシンクタンク、フィディア総合研究所は荘内銀行が作ったシンクタンクだ。
チームには、人口の減少を示す県内の地域ごとのデータや鉄道や空路、車を使った県民の移動データなどが示され、議論が交わされるのだが、情報公開された文書を読むと、データの膨大さに比べて議論があまりにも空疎なことに脱力感を覚える。誰も「実現の展望」を見出せないからだろう。
専門家らしい指摘もある。「山形県目線だけでなく、全国的なネットワークの視点、県外の方々の視点、外国人の視点などについて踏まえる必要がある」(第1回会合)、「フル規格新幹線を整備することは目標ではなく、新しい山形を作るための手段である。山形の目指す方向性を定め、その次にフル規格新幹線の事業性を検討すべきだ」(第7回会合)。
それぞれ、まっとうな意見だが、こうした考えが報告書に反映されることはない。なにせ、ワーキングチームの設置を指示した吉村知事本人が「目標と手段」を取り違え、奥羽・羽越新幹線の実現に血眼になっているからだ。
県庁の内部では何が起きているのか。部長会議のメンバーに話を聞いた。一人は「フル規格新幹線の整備のことが部長会議で議論されたことは、記憶する限り、2期目の4年間で一度もない」と述べた。もう一人の述懐はより率直だった。彼は次のように語った。
「新幹線関係の予算が話題になったことはない。部長会議では報告事項が多く、政策論議が交わされることはまずない。予算編成にしても、下から積み上げていっても知事が『いらない』と言えば、それまで。そもそも、知事は県職員を信用していないのではないか。県経済同友会の朝食会などで吹き込まれたアイデアで動くことが多かった」
ブレーン不在の県知事の下、部長会議での議論もないまま、フル規格の新幹線整備促進の予算はますます膨らんでいった。2016年5月、県主導で市町村や経済団体で構成する「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」を立ち上げた。吉村知事の「オール山形翼賛組織」である(写真参照)。
この年から、実現同盟の運営やそのホームページの制作、シンポジウム開催の外注が始まる。表3にあるように、公募式の最初のコンペでこの仕事を受注したのは山形新聞グループの広告会社、山形アドビューロだ。業務には新聞広告の掲載やラジオでのPRも含まれる。知事が唱え、山形新聞がキャンペーン記事を載せ、グループ企業が広告の仕事を請け負う。同社の業務委託料は3年分で4000万円近くになる。
去年は吉村知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いるダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)が1817万円で受託した。山形アドビューロとダイバーシティメディアの2社に支払われた委託料の合計は5700万円を上回り、これだけで約1億2千万円の新幹線整備事業予算の半分近くになる。
ダイバーシティメディアについては、今年の1月30日付のコラムで同社が県内周遊促進の観光キャンペーン事業を受注した経緯を詳しく報告した。県の仕事を取ってくるのが実にうまい。ちなみに、観光キャンペーン事業を担当したのは吉村和文氏の長男で同社取締役の和康氏である。2017年3月期の株主総会資料に書いてある。知事が発注し、義理のいとこが受注した仕事をその長男がこなす。「身内と取り巻きに温かい県政」の極みではないか。
フル規格の新幹線整備促進事業について、県の幹部が公然と異を唱えたことは皆無のようだが、職員全員が唯々諾々と知事の意向通りに動いているわけではない。情報公開で開示された2775ページの公文書の中に、かすかに抵抗の痕跡があった。
2015年度予算査定の「財政課長調整結果報告書」の参考欄に、次のような記述がある。「(フル規格新幹線の整備を求める)県の要望が認められたとしても、工事の着工は現在の整備計画が完了する平成47年(2035年)以降となり、さらに工事完成まで10年?30年を要すると想定される」(カッコ内は筆者が補足)。
わずか3行のメモ。だが、その行間からは「実現する可能性があるか疑わしい。仮に実現するとしても、30年から50年も先のことではないか」との思いがにじみ出る。財政をつかさどるプロとして、書き残さないではいられなかったのだろう。
県幹部の証言によれば、政策にしても予算にしても、2期目に入った頃から、吉村知事は自分の考えを強烈に貫くようになったという。自由に議論を交わし、より良い県政を進めていく雰囲気が失われて久しい。では、本人はどのような心境にあるのか。
ここは、吉村和文氏のブログ「約束の地へ」から引用したい。2016年5月8日のブログによれば、吉村美栄子知事は自らの後援会の総会で次のように挨拶した。「自分はこの7年間、ただ愚直に県民の皆さんの笑顔が見たい、県民の皆さんから幸せになってほしいという一心で走り続けてきた。県民の方としっかりと向かい合い、温かい県政を願い、作ってきた。これからも、みんなで心の通った山形県を作っていきましょう」
吉村知事が一生懸命、働いていることは疑いない。知事交際費の明細を見れば、よくある「宴会政治」とは無縁であることも分かる。災害の現場などにもよく足を運ぶ。温かさを感じる時もある。けれども、足元の県庁内ですら「心が通わなくなっている現実」を知事は自覚しているのか。
冒頭に記したように、吉村知事はブレーンを作り、助言を求めることをしてこなかった。自らと異なる意見を持つ人の声に耳を傾ける度量も乏しい。性格に加えて、大きい組織を率いた経験がないからかもしれない。在任が長くなるにつれて、それが「身内・取り巻き県政」の様相を呈し、度し難いほどひどくなってきた。
そのように批判されれば、本人は「人のあら探しばかりしていないで、自分ならどうするか前向きのことが言えないの」と反論するかもしれない。一人の元新聞記者としては、こう答えるのが精いっぱいである。
「時代の風に敏感でありたい。世界は、田中角栄氏が日本列島改造論を唱えた時代とは、まるで違うものになってしまった。地味ではあっても、人を育て、人を惹きつけるために力を尽くす時ではないか」
*この文章は、月刊『素晴らしい山形』の10月号に寄稿したものを若干手直ししたものです。
≪写真説明とSource≫
◎山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟の2016年総会。吉村知事と県内選出の与野党国会議員が山形市内のホテルで気勢を上げた(実現同盟の公式サイトから)
≪参考資料&サイト≫
◎奥羽・羽越新幹線整備構想に関して山形県が情報公開した文書
◎山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟の公式サイト
https://www.ou-uetsu-shinkansen.jp/
◎奥羽・羽越新幹線整備構想に関する山形新聞、河北新報の記事
肌の色が違う。言葉や宗教、風俗が異なる――人間は長い間、そんな理由でいがみ合ってきた。けれども、そのルーツをたどれば、すべての民族、すべての人間のふるさとはアフリカである。それは疑いようのない事実だ。

そのアフリカは近代以降、もっとも醜い争いの舞台になり、収奪と殺戮が繰り返されてきた。それもまた、疑いようのない事実だ。そのアフリカで今、何が起きているのか。朝日新聞で連載中の記事「アフリカはいま」はその断片を拾い上げ、この大陸のことを考える素材を提供しようとしている。実に優れた連載だ。
「リープフロッグ(カエル跳び)」をキーワードにした8月14日付の連載は、とりわけ読み応えがあった。アフリカ中部、ルワンダの病院で輸血の管理がどのようになされているかを紹介している。病院のパソコンで輸血用の血液の注文をすると、配送の拠点からドローンで血液が運ばれてくる。所要時間は30分。それまでは、でこぼこ道を車で2時間かけて運んでいたという。最新の技術と機器を使って、難題を一挙に跳び越えてしまった。
「カエル跳び」は教育分野でも起きている。経済的に苦しい家庭は、子どもに教育を受けさせたいと思っても、教科書代を負担することができない。そこで、携帯のショートメッセージサービス(SMS)を使って学習サービスを提供する企業が現れた。1日3円ほどの負担。これなら、なんとか払える。そうやって学びの機会を広げている。
先進国はまず鉄道を敷設し、道路網を整え、次に電線と電話線を張り巡らせて富国強兵の道を歩んできた。が、アフリカの国々が同じプロセスを辿ったのでは、いつ追いつけるか分からない。それとは異なる道、それがカエル跳びの道だ。飛躍的な技術革新がその可能性を切り拓いてくれるかもしれない。
どんなに技術革新が進もうとも、まずは食べることが先だ。食糧を確保しなければ、何事も始まらない。そこで注目されているのがネリカ米だ。New Rice for Africa(アフリカのための新しいコメ)から名付けられたネリカ米は、1990年代にアフリカと日本の農業技術者が力を合わせて品種改良を重ね、実用にこぎつけた。
生産量はこの10年間で2800万トンと倍増し、次の10年でさらに倍にすることを目指している。その普及にもっとも貢献した人物の一人が坪井達史(たつし)さん(69)である。大分県出身、日大農獣医学部卒の技術者だ。2004年からアフリカのウガンダを拠点にネリカ米の普及のために汗を流してきた。
坪井さんの普及方法はとても日本的だ。農民に栽培方法を教えて、種もみを1キロ与える。条件は「倍返し」。ただし、農民たちは収穫したら、種もみ2キロを坪井さんではなく、近隣の農民に与えなければならない。そうやって、少しずつ栽培面積を広げてきた。最初は陸稲から始め、その後、水稲の品種も広めてきた(8月16日付)。
欧米の種苗会社は先端技術を駆使して高収量の種子を開発し、それを独占して巨利を得ようとする。坪井さんや日本の国際協力機構(JICA)は、それとは対極の方法でアフリカの食糧事情の改善を図ろうとしている。そして、それは確実にアフリカの農民たちの心をつかみ始めている。
坪井さんには、12年前にアフリカ農業の取材をした際にお世話になった。普及の方法や農民との接し方を淡々と語る人だった。「こういう人たちが流す汗がアフリカを、そして世界を少しずつ良くしていくんだなぁ」としみじみ思った。坪井さんは故郷の大分県に戻ったとのことだが、今でも請われればアフリカに出張して、普及に努めているという。
8月11日付の連載記事によれば、女性1人当たりの出生率は日本の1.4人に対して、アフリカ諸国は4.4人。それは、現在の世界の人口77億人をさらに押し上げる。アフリカの国々がどのような道を歩むのかは、この大陸だけの問題ではなく、私たちが暮らす地球そのものの問題でもある。
私たちはアフリカとどう向き合うのか。連載には、それを考える素材があふれている。
≪写真説明とSouce≫
◎アフリカでネリカ米の普及に努める坪井達史さん
http://www.adca.or.jp/page/seminar/files/H25seminar.pdf
≪参考記事≫
◎朝日新聞の連載「アフリカはいま TICAD 7」(2019年8月11日?8月16日)
◎朝日新聞の連載「新戦略を求めて 第6章 7」(2007年3月27日)

そのアフリカは近代以降、もっとも醜い争いの舞台になり、収奪と殺戮が繰り返されてきた。それもまた、疑いようのない事実だ。そのアフリカで今、何が起きているのか。朝日新聞で連載中の記事「アフリカはいま」はその断片を拾い上げ、この大陸のことを考える素材を提供しようとしている。実に優れた連載だ。
「リープフロッグ(カエル跳び)」をキーワードにした8月14日付の連載は、とりわけ読み応えがあった。アフリカ中部、ルワンダの病院で輸血の管理がどのようになされているかを紹介している。病院のパソコンで輸血用の血液の注文をすると、配送の拠点からドローンで血液が運ばれてくる。所要時間は30分。それまでは、でこぼこ道を車で2時間かけて運んでいたという。最新の技術と機器を使って、難題を一挙に跳び越えてしまった。
「カエル跳び」は教育分野でも起きている。経済的に苦しい家庭は、子どもに教育を受けさせたいと思っても、教科書代を負担することができない。そこで、携帯のショートメッセージサービス(SMS)を使って学習サービスを提供する企業が現れた。1日3円ほどの負担。これなら、なんとか払える。そうやって学びの機会を広げている。
先進国はまず鉄道を敷設し、道路網を整え、次に電線と電話線を張り巡らせて富国強兵の道を歩んできた。が、アフリカの国々が同じプロセスを辿ったのでは、いつ追いつけるか分からない。それとは異なる道、それがカエル跳びの道だ。飛躍的な技術革新がその可能性を切り拓いてくれるかもしれない。
どんなに技術革新が進もうとも、まずは食べることが先だ。食糧を確保しなければ、何事も始まらない。そこで注目されているのがネリカ米だ。New Rice for Africa(アフリカのための新しいコメ)から名付けられたネリカ米は、1990年代にアフリカと日本の農業技術者が力を合わせて品種改良を重ね、実用にこぎつけた。
生産量はこの10年間で2800万トンと倍増し、次の10年でさらに倍にすることを目指している。その普及にもっとも貢献した人物の一人が坪井達史(たつし)さん(69)である。大分県出身、日大農獣医学部卒の技術者だ。2004年からアフリカのウガンダを拠点にネリカ米の普及のために汗を流してきた。
坪井さんの普及方法はとても日本的だ。農民に栽培方法を教えて、種もみを1キロ与える。条件は「倍返し」。ただし、農民たちは収穫したら、種もみ2キロを坪井さんではなく、近隣の農民に与えなければならない。そうやって、少しずつ栽培面積を広げてきた。最初は陸稲から始め、その後、水稲の品種も広めてきた(8月16日付)。
欧米の種苗会社は先端技術を駆使して高収量の種子を開発し、それを独占して巨利を得ようとする。坪井さんや日本の国際協力機構(JICA)は、それとは対極の方法でアフリカの食糧事情の改善を図ろうとしている。そして、それは確実にアフリカの農民たちの心をつかみ始めている。
坪井さんには、12年前にアフリカ農業の取材をした際にお世話になった。普及の方法や農民との接し方を淡々と語る人だった。「こういう人たちが流す汗がアフリカを、そして世界を少しずつ良くしていくんだなぁ」としみじみ思った。坪井さんは故郷の大分県に戻ったとのことだが、今でも請われればアフリカに出張して、普及に努めているという。
8月11日付の連載記事によれば、女性1人当たりの出生率は日本の1.4人に対して、アフリカ諸国は4.4人。それは、現在の世界の人口77億人をさらに押し上げる。アフリカの国々がどのような道を歩むのかは、この大陸だけの問題ではなく、私たちが暮らす地球そのものの問題でもある。
私たちはアフリカとどう向き合うのか。連載には、それを考える素材があふれている。
≪写真説明とSouce≫
◎アフリカでネリカ米の普及に努める坪井達史さん
http://www.adca.or.jp/page/seminar/files/H25seminar.pdf
≪参考記事≫
◎朝日新聞の連載「アフリカはいま TICAD 7」(2019年8月11日?8月16日)
◎朝日新聞の連載「新戦略を求めて 第6章 7」(2007年3月27日)
松尾芭蕉が門弟の曾良と最上川を舟で下ったのは元禄2年(1689年)のことでした。それから330年後の夏。第7回カヌー探訪は7月27日(土)、芭蕉乗船の碑が立つ山形県新庄市の本合海(もとあいかい)からスタートし、戸沢村古口まで18キロを下りました。参加者は35人で、第2回カヌー探訪(2014年)と並んで過去最多でした。


この区間には、最上峡芭蕉ライン観光の舟下りコースがあり、同社の全面的なご協力を得てのカヌー行となりました。また、源義経一行が立ち寄ったとの伝説が残る仙人堂もあり、義経ロマン観光にもご配慮いただきました。
◎第7回カヌー探訪の動画(ユーチューブ=真鍋賢一撮影)
≪出発&到着時刻≫
▽7月27日 薄曇り、後晴れ9:55 新庄市本合海(もとあいかい)の本合海大橋を出発
11:40 戸沢村古口の芭蕉ライン観光の乗船場に到着、昼食
13:00 昼食休憩を終えて出発
川のコンビニに立ち寄り、かき氷を堪能
源義経一行が立ち寄ったとの伝説が残る仙人堂でコーヒータイム
15:40 戸沢村古口の芭蕉ライン観光の下船場に到着

≪参加者&参加艇≫
35人、28艇:山形県内14人(山形5、天童2、東根2、鶴岡、酒田、尾花沢、大江、朝日各1人)▽県外21人(群馬9、福島3、岩手、栃木、埼玉、東京各2、千葉1)


≪カヌーイスト=申込順≫
柳沼美由紀(福島県泉崎村)、柳沼幸男(同)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、真鍋史子(同)、佐藤守孝(千葉県松戸市)、林和明(東京都足立区)、岸浩(福島市)、国塚則昭(埼玉県毛呂山町)、小林和弘(群馬県みどり市)、中島健策(群馬県伊勢崎市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、飯塚正英(群馬県伊勢崎市)、佐々木健雄(山形市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、藍澤亨(群馬県前橋市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、阿部俊裕(山形県天童市)、阿部明美(同)、崔鍾八(山形県朝日町)、黒田美喜男(山形県東根市)、渡辺不二雄(山形市)、石田太郎(盛岡市)、石田優太(同)、市川秀(東京都中野区)、佐竹久(山形県大江町)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、永嶋英明(山形県鶴岡市)、古家優(山形県酒田市)、塚本雅俊(群馬県前橋市)、塚本弘美(同)、菊地大二郎(山形市)、菊地恵里(同)、柴田尚宏(同)、阿部悠子(山形県東根市)

≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽長岡典己
≪動画撮影≫ 真鍋賢一
≪漬物提供≫ 安藤昭郎▽佐竹恵子
≪過去の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
*2013年は山形豪雨のため開催中止

≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力?山形支店、朝日町、新庄市、戸沢村、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 新庄市本合海地区、八向尚(やむき・ひさし)▽最上峡芭蕉ライン観光
≪ウェブサイト更新≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪ポスターとTシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
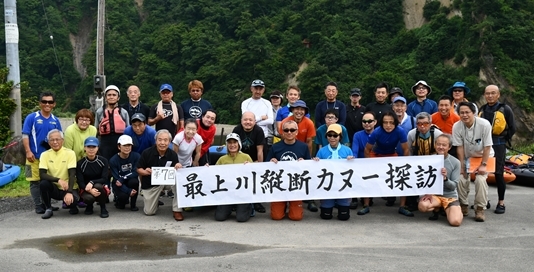


この区間には、最上峡芭蕉ライン観光の舟下りコースがあり、同社の全面的なご協力を得てのカヌー行となりました。また、源義経一行が立ち寄ったとの伝説が残る仙人堂もあり、義経ロマン観光にもご配慮いただきました。
◎第7回カヌー探訪の動画(ユーチューブ=真鍋賢一撮影)
≪出発&到着時刻≫
▽7月27日 薄曇り、後晴れ9:55 新庄市本合海(もとあいかい)の本合海大橋を出発
11:40 戸沢村古口の芭蕉ライン観光の乗船場に到着、昼食
13:00 昼食休憩を終えて出発
川のコンビニに立ち寄り、かき氷を堪能
源義経一行が立ち寄ったとの伝説が残る仙人堂でコーヒータイム
15:40 戸沢村古口の芭蕉ライン観光の下船場に到着

≪参加者&参加艇≫
35人、28艇:山形県内14人(山形5、天童2、東根2、鶴岡、酒田、尾花沢、大江、朝日各1人)▽県外21人(群馬9、福島3、岩手、栃木、埼玉、東京各2、千葉1)


芭蕉ライン観光の遊覧船。すれ違う際には速度を緩めてくれました
≪カヌーイスト=申込順≫
柳沼美由紀(福島県泉崎村)、柳沼幸男(同)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、真鍋史子(同)、佐藤守孝(千葉県松戸市)、林和明(東京都足立区)、岸浩(福島市)、国塚則昭(埼玉県毛呂山町)、小林和弘(群馬県みどり市)、中島健策(群馬県伊勢崎市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、飯塚正英(群馬県伊勢崎市)、佐々木健雄(山形市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、藍澤亨(群馬県前橋市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、阿部俊裕(山形県天童市)、阿部明美(同)、崔鍾八(山形県朝日町)、黒田美喜男(山形県東根市)、渡辺不二雄(山形市)、石田太郎(盛岡市)、石田優太(同)、市川秀(東京都中野区)、佐竹久(山形県大江町)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、永嶋英明(山形県鶴岡市)、古家優(山形県酒田市)、塚本雅俊(群馬県前橋市)、塚本弘美(同)、菊地大二郎(山形市)、菊地恵里(同)、柴田尚宏(同)、阿部悠子(山形県東根市)

≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽長岡典己
≪動画撮影≫ 真鍋賢一
≪漬物提供≫ 安藤昭郎▽佐竹恵子
≪過去の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人
*2013年は山形豪雨のため開催中止

最年少の石田優太君(15)と最ベテランの市川秀さん(81)
≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力?山形支店、朝日町、新庄市、戸沢村、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 新庄市本合海地区、八向尚(やむき・ひさし)▽最上峡芭蕉ライン観光
≪ウェブサイト更新≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)
≪ポスターとTシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
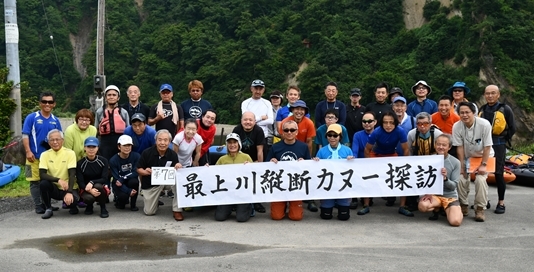
「落下傘候補」とは、その選挙区に地縁や血縁がないのに出馬する候補者のことを言う。2013年の参議院選挙で山形選挙区から自民党公認で立候補して初当選し、今回の選挙で再選をめざす大沼瑞穂(みずほ)議員は、その意味では「落下傘候補」とは言えない。

父親の大沼保昭氏は山形市の生まれだ。造り酒屋の次男として生まれ、東京大学法学部を卒業、東大教授として国際法を講じた。戦争責任を厳しく問う一方で、憲法9条の改正を容認する現実的なリベラリストだった。惜しまれつつ、昨年10月に死去した。
祖父の大沼勘四郎氏は造り酒屋の9代目で、山形県酒造組合連合会の会長を務めた。曾祖父の大沼保吉氏はその先代の酒造経営者で、戦前に山形県議や山形市長を務めた。大沼瑞穂氏は東京で生まれ育ったが、そのルーツは山形にある。あえて言えば、「半落下傘候補」ということになろうか。
「落下傘候補」であれ、「半落下傘候補」であれ、その人物が政治家としてきちんとした仕事をしているのであれば、問題はない。私は「政治とは一定の距離を置く」「特定の政党の応援はしない」のを信条としてきた。これまで特定の政治家のことを選挙がらみで書いたことはない。
だが、今回だけは書くことにした。大沼瑞穂氏が自らの公式サイトに「ウソ」を記しているからである。公式サイトのプロフィールの1行目に「昭和54年生まれ。山形市七日町在住」とある。後段は真っ赤なウソである。
本人は「住民票は山形市に移した。マンションもある」と反論するのかもしれない。が、私が問いたいのは「住民票がどこにあるか」ではない。2013年に参議院議員に当選して以来、夫と子どもはずっと東京にいる、本人もほとんどの時間を東京で過ごしている、という事実である。
山形市の中心部に購入、もしくは借りているマンションで過ごすのは、山形に来た時だけだ。ホテル代わり、というのが実態であり、「山形市在住」とは言えない。こういうウソを平然と公式サイトのプロフィールに記す感覚が許しがたい。
当選を重ねて国政で重要なポストに就き、地元に帰ってくる余裕がないという政治家は珍しくない。が、1期目から「自民党の重鎮」のような暮らしをして、恥じるところはないのか。地元の有権者をなんだと思っているのか。
選挙区の支持者の集まりで、彼女は「山形に引っ越してきて、こちらで暮らしては」と水を向けられた際、やんわりと断り、次のように言ったという。「山形で子育てをするのはちょっと・・・」。もっとはっきり「山形は子育てをする環境にはない」と述べた、との証言もある。信頼できる自民党の政治家や党員から聞いた話なので、間違いない。
大沼瑞穂氏は慶応大学の大学院(修士課程)を修了した後、NHKの記者になり、外務省の専門調査員(香港駐在)、東京財団の研究員、内閣府の上席政策調査員を経て、政界に転じた。経歴も経験もなかなかのものだ。
しかし、政治家としての資質を判断する場合には、その政策や活動の実績にも増して、常日頃の言動や振る舞いを見なければならない。人間としての資質がよく現れるからだ。公式サイトに平然とウソを書き、選挙区の支持者を前に、その地に生きる人たちの心を踏みにじるような言葉を口にする。そのような人物は政治家としてふさわしくない。
今回、参議院選挙の山形選挙区には野党統一候補の芳賀(はが)道也氏が無所属で立候補している。私は芳賀氏のことを知らないので、論評する立場にはない。その政策にも共感は覚えない。が、少なくとも大沼瑞穂氏のような破廉恥さは感じない。
平気でウソをつく人間は、政治家としてふさわしくない。落選させて、有権者はよく見ていること、政治の世界はそんなに甘いものではないことを思い知らせるべきである。
≪写真説明とSouce≫
大沼瑞穂参議院議員(参議院自民党の公式サイトから)
https://sangiin-jimin.jp/523/%E7%9C%8C%E6%94%BF%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%88%E5%A4%A7%E6%B2%BC%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%EF%BC%89/

父親の大沼保昭氏は山形市の生まれだ。造り酒屋の次男として生まれ、東京大学法学部を卒業、東大教授として国際法を講じた。戦争責任を厳しく問う一方で、憲法9条の改正を容認する現実的なリベラリストだった。惜しまれつつ、昨年10月に死去した。
祖父の大沼勘四郎氏は造り酒屋の9代目で、山形県酒造組合連合会の会長を務めた。曾祖父の大沼保吉氏はその先代の酒造経営者で、戦前に山形県議や山形市長を務めた。大沼瑞穂氏は東京で生まれ育ったが、そのルーツは山形にある。あえて言えば、「半落下傘候補」ということになろうか。
「落下傘候補」であれ、「半落下傘候補」であれ、その人物が政治家としてきちんとした仕事をしているのであれば、問題はない。私は「政治とは一定の距離を置く」「特定の政党の応援はしない」のを信条としてきた。これまで特定の政治家のことを選挙がらみで書いたことはない。
だが、今回だけは書くことにした。大沼瑞穂氏が自らの公式サイトに「ウソ」を記しているからである。公式サイトのプロフィールの1行目に「昭和54年生まれ。山形市七日町在住」とある。後段は真っ赤なウソである。
本人は「住民票は山形市に移した。マンションもある」と反論するのかもしれない。が、私が問いたいのは「住民票がどこにあるか」ではない。2013年に参議院議員に当選して以来、夫と子どもはずっと東京にいる、本人もほとんどの時間を東京で過ごしている、という事実である。
山形市の中心部に購入、もしくは借りているマンションで過ごすのは、山形に来た時だけだ。ホテル代わり、というのが実態であり、「山形市在住」とは言えない。こういうウソを平然と公式サイトのプロフィールに記す感覚が許しがたい。
当選を重ねて国政で重要なポストに就き、地元に帰ってくる余裕がないという政治家は珍しくない。が、1期目から「自民党の重鎮」のような暮らしをして、恥じるところはないのか。地元の有権者をなんだと思っているのか。
選挙区の支持者の集まりで、彼女は「山形に引っ越してきて、こちらで暮らしては」と水を向けられた際、やんわりと断り、次のように言ったという。「山形で子育てをするのはちょっと・・・」。もっとはっきり「山形は子育てをする環境にはない」と述べた、との証言もある。信頼できる自民党の政治家や党員から聞いた話なので、間違いない。
大沼瑞穂氏は慶応大学の大学院(修士課程)を修了した後、NHKの記者になり、外務省の専門調査員(香港駐在)、東京財団の研究員、内閣府の上席政策調査員を経て、政界に転じた。経歴も経験もなかなかのものだ。
しかし、政治家としての資質を判断する場合には、その政策や活動の実績にも増して、常日頃の言動や振る舞いを見なければならない。人間としての資質がよく現れるからだ。公式サイトに平然とウソを書き、選挙区の支持者を前に、その地に生きる人たちの心を踏みにじるような言葉を口にする。そのような人物は政治家としてふさわしくない。
今回、参議院選挙の山形選挙区には野党統一候補の芳賀(はが)道也氏が無所属で立候補している。私は芳賀氏のことを知らないので、論評する立場にはない。その政策にも共感は覚えない。が、少なくとも大沼瑞穂氏のような破廉恥さは感じない。
平気でウソをつく人間は、政治家としてふさわしくない。落選させて、有権者はよく見ていること、政治の世界はそんなに甘いものではないことを思い知らせるべきである。
*メールマガジン「風切通信 60」 2019年7月7日
≪写真説明とSouce≫
大沼瑞穂参議院議員(参議院自民党の公式サイトから)
https://sangiin-jimin.jp/523/%E7%9C%8C%E6%94%BF%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%88%E5%A4%A7%E6%B2%BC%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%EF%BC%89/
日本人は「自然なもの」を好む傾向が強い。それは庭園の様式を見れば、よく分かる。ヨーロッパの庭園は直線や円で仕切ることが多いが、日本の庭園は自然をそのまま凝縮した形で造られる。まっすぐな線を美しいとは感じない。あいまいさを愛(め)でる。

そうした特質は言葉にも現れる。欧米の人たち、とりわけドイツ人は言葉の定義にこだわる。あいまいさを嫌い、何でも定義しようとする。ドイツの鉄血宰相ビスマルクが「政治とは妥協の産物であり、可能性の芸術である」と言い切ったのはその典型だろう。
「可能性の芸術」という表現は美しすぎるが、政治の要諦が妥協にあるのは間違いない。何を譲り、何を得るのか。政治はつくづく難しい。
山形県の吉村美栄子知事は2期目から、山形新幹線の機能強化や延伸ではなく、フル規格の奥羽、羽越新幹線の建設を求める政策を唱えだした。知事は何を譲り、何を得ようとしているのか。
1992年に山形新幹線が開通してから、県内では交通インフラについてさまざまな議論が交わされてきた。表1に見るように、7年後に山形新幹線が新庄市まで延びた後、当時の高橋和雄知事は「陸羽西線を使って庄内まで延ばす構想」に前向きだった。専門家を集めて「山形新幹線機能強化検討委員会」を立ち上げ、庄内までの延伸と福島・山形県境にある板谷峠のトンネル化を検討するよう要請した。
ところが、高橋知事は2005年の知事選で、加藤紘一代議士らが担いだ斎藤弘氏に敗れた。財政再建と採算重視を掲げる斎藤知事は、庄内延伸にも板谷峠のトンネル化にも関心を示さなかった。機能強化検討委は翌年の3月、新しい知事の意向に沿った報告書を出し、庄内延伸の構想は頓挫した。
新幹線論議が山形で再燃するのは2012年からだ。再選をめざす吉村知事は「簡単でないのは承知しているが、奥羽、羽越新幹線の整備を求めたい」と言い始めた。福島から山形を通って秋田に至る奥羽新幹線。富山から新潟、庄内、秋田、青森へと延びる羽越新幹線。その二つをフル規格の新幹線として建設する構想だ(図1)。知事は2期目の公約にし、山形県の長期計画にも盛り込んだ。
前の年に起きた東日本大震災で日本海側の交通インフラの脆弱さを痛感したこと、整備新幹線5路線の工事計画が固まり、「次の新幹線建設の優先順位をどうするか」が政治の重要課題になってきたことが念頭にあったと思われる。
山形新幹線は、法的には「新幹線」ではない。福島で東北新幹線につながる「新幹線直行特急」であり、福島から山形、新庄までは在来線の奥羽本線を走る。直行を実現するため、奥羽本線は新幹線用の標準軌道に改修されたが、踏切が残り、一部だが単線区間もある。福島・山形県境の板谷峠は急峻で、豪雪地帯だ。雪に阻まれ、運休することも少なくない。
開業当初こそ、「3時間足らずで東京に行ける」と喜ばれたが、「しょせんはミニ新幹線」といった不満が募っていった。決定的だったのは東北新幹線の青森延伸(2010年)である。東京から新青森までは713キロと、山形までの倍近くある。なのに、所要時間はそれほど変わらない。「フル規格の新幹線が欲しい」という声が出てくるのも無理はない。
「日本海側も太平洋側と同じく大事な国土。隅々まで新幹線ネットワークをつなぐことで、日本全体の力が発揮できる。全国の皆様にも関心を持っていただき、大きな運動のうねりをつくっていきたい」。吉村知事は昨年2月に開かれた日経フォーラムで、フル規格の奥羽、羽越新幹線構想に理解を求めた。
正論である。正面切って、反対はしにくい。だが、果たして実現の可能性はあるのか。整備新幹線の5路線に次いで、奥羽、羽越新幹線構想が政府の基本計画に載ったのは1973年、高度経済成長期である。それから半世紀。日本は少子高齢化と人口減の時代を迎え、緩やかな下り坂に差しかかっている。図2に見るように、北海道の新幹線整備はこれからだ。四国にも山陰にも新幹線網は届いていない。
東北の日本海側を貫く新幹線はないが、山形も秋田もミニ新幹線で東京とつながっている。北陸新幹線の建設には1キロ100億円もかかった。政府も自治体も膨大な借金を抱えている。そうしたことを考えれば、奥羽新幹線も羽越新幹線も夢物語と言うしかない。夢を追うのは夢想家の仕事であって、政治家の為すべきことではない。
現在の新幹線整備計画が一段落した後に考えるべきことは、むしろミニ新幹線の知恵と経験を全国でどのように活かしていくか、ということではないか。
ミニ新幹線第1号となった山形新幹線は、1987年末の予算折衝で政府の建設費補助が内定してから5年足らずで開業にこぎつけた。在来線を使ったこともあり、用地買収の必要はなく、総事業費は620億円で収まった(開業時の概算)。フル規格の新幹線建設とはけた違いの安さだ。ある意味、時代を先取りした「エコな事業だった」と再評価されていい。
実際、四国では「スーパー特急方式」と名付けて、ミニ新幹線と同様、在来線を活用する案も検討されている(図3参照)。山陰にしても、大阪から鳥取、島根とつながるフル規格の新幹線を待つより、岡山から松江へと中国山地を縦断するミニ新幹線を建設する方が現実的だろう。
話を地元に戻せば、山形県が一体となって発展していくという観点からも、山形新幹線の庄内延伸をもう一度、真剣に検討すべきではないか。夢物語の奥羽、羽越新幹線構想を追う限り、山形新幹線の庄内延伸は店(たな)ざらし状態のまま、一歩も進まない。
もちろん、庄内延伸も簡単ではない。何よりも、庄内の2都市、酒田と鶴岡の利益が一致しない、という問題がある。JRの鉄路は余目(あまるめ)駅で酒田方面と鶴岡方面に分かれる(図4)。まず、どちらに延ばすかでもめる。酒田市は新幹線の延伸に熱心だが、より新潟に近い鶴岡市の人たちは「羽越本線を高速化して新潟で上越新幹線に乗り換えた方が早い」と考えているようで、延伸に背を向ける人もいる。
しかし、そういう時こそ、政治家の出番ではないか。余目駅から酒田、鶴岡の両方に新幹線を延ばして両方を終着駅にする、という方法もある(始発は半分ずつ)。あるいは、酒田に延伸する代わりに鶴岡には別の面で力を注いで妥協を図る道もある。要は、山形新幹線をなんとしてでも庄内まで延ばし、名実ともに「山形新幹線」という名にふさわしいものにする、という決意があるかどうかだ。
フル規格の奥羽、羽越新幹線構想に関しては、実は吉村知事より先に提唱した人たちがいる。山形新聞である。表1にも記したが、2000年1月に「幻の新幹線・奥羽、羽越の実現決意」という社説を掲げた。両新幹線を整備計画線に格上げする運動を「怠りなく、より強めていかなければならない」と訴え、「本県が“ミニ”のままでよいのか」と結んでいる。
その心意気は理解できるが、この社説を書いた時、筆者は庄内の人たちの気持ちをどのくらい思いやったのだろうか。「奥羽、羽越」と併記してみても、奥羽が優先されることは目に見えている。フル規格の新幹線構想を唱えることは、そのまま「庄内のことは自分たちで何とかしたら」と言うに等しい。
もともと、庄内の人たちには「内陸のやつらは信用できない」という思いがある。内陸の人たちは「庄内の連中は気位が高く、いがみ合ってばかりいる」と反論するのかもしれない。戊辰戦争以来の怨恨(えんこん)がいまだにうずいている、と指摘する人もいる。
そういうわだかまりを解きほぐしていくためにも、フル規格の奥羽、羽越新幹線の建設より山形新幹線の庄内延伸の方がはるかに優れた選択肢ではないか。
フル規格の新幹線構想にこだわる吉村知事は最近、板谷峠にトンネルを掘る計画にご執心だ。長さ23キロの長大なトンネル。JR東日本によれば、事業費は在来線用のトンネルで1500億円、フル規格の新幹線用となれば、さらに120億円上積みされる。上積み分は地元負担になるという。このトンネルによって短縮される時間は10分ほどだ。
田中角栄氏が日本列島改造論を唱えた時代ならともかく、膨らむ医療費や福祉と介護の負担をまかなうため消費税を引き上げる算段をしている時期に、このような話が通るわけがない。私たちの社会がこれから辿る道を考えれば、何を優先すべきか、自ずから見えてくるだろう。
吉村知事には、ビスマルクのもう一つの言葉を伝えたい。彼は、政治家としての長くて厳しい歩みを踏まえ、こう言っている。「政治とは、歴史に刻まれる神の足音に注意深く耳を傾け、その道をひととき共に歩むことである」
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の7月号に寄稿した文章を転載したものです。
≪写真説明≫
山形新幹線
≪参考文献&サイト≫
◎『山形新幹線 鉄路の復権』(鹿野道彦、翠嵐社)1992年
142ページに山形新幹線の総事業費620億円の内訳がある(工事費320億円、車両費200億円、標準軌用車両費など100億円)
◎『山形新幹線 鉄道21世紀への飛躍』(東日本旅客鉄道株式会社、今野平版印刷)1992年
◎「次の新幹線はどこに?」熱を帯びる誘致合戦(東洋経済ONLINE 2018年2月5日 )
図1の「奥羽、羽越新幹線構想」、図3の「四国新幹線構想」はこの記事から引用
https://toyokeizai.net/articles/-/207148?page=3
◎盛岡?新青森、320キロ解禁へ JR東が防音工事(朝日新聞DIGITAL 2019年1月14日)
図2の「新幹線の整備状況」はこの記事から引用
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190114000403.html
◎日経フォーラム「実装に入った地方創生」での吉村美栄子・山形県知事の講演概要
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3550948019092018000000/
◎ウィキペディアの「山形新幹線」「整備新幹線」「奥羽新幹線」「四国新幹線」の各項(URL省略)
◎板谷峠トンネル化、「フル」か「ミニ」か、仕様巡り県と地元摩擦(河北新報ONLINE NEWS 2019年1月22日)
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190122_53004.html
◎新板谷トンネルの概要(鉄道計画データベース)
https://railproject.tabiris.com/yamagatatunnel.html
◎山形新聞の2000年1月10日付社説「幻の新幹線・奥羽、羽越の実現決意」、「山形にフル規格新幹線を」と題した一連のキャンペーン記事
◎ビスマルクの言葉「政治とは、歴史に刻まれる神の足音に注意深く耳を傾け、その道をひととき共に歩むことである」(筆者訳)の英語表現は次の通り(ニューヨークタイムズの書評とURL)。
Statesmanship consists of listening carefully to the footsteps of God through history and walking with him a few steps of the way.
https://www.nytimes.com/2011/04/03/books/review/book-review-bismarck-by-jonathan-steinberg.html
◎ドイツ語版ウィキペディア「ビスマルク Bismark」
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck

そうした特質は言葉にも現れる。欧米の人たち、とりわけドイツ人は言葉の定義にこだわる。あいまいさを嫌い、何でも定義しようとする。ドイツの鉄血宰相ビスマルクが「政治とは妥協の産物であり、可能性の芸術である」と言い切ったのはその典型だろう。
「可能性の芸術」という表現は美しすぎるが、政治の要諦が妥協にあるのは間違いない。何を譲り、何を得るのか。政治はつくづく難しい。
山形県の吉村美栄子知事は2期目から、山形新幹線の機能強化や延伸ではなく、フル規格の奥羽、羽越新幹線の建設を求める政策を唱えだした。知事は何を譲り、何を得ようとしているのか。
1992年に山形新幹線が開通してから、県内では交通インフラについてさまざまな議論が交わされてきた。表1に見るように、7年後に山形新幹線が新庄市まで延びた後、当時の高橋和雄知事は「陸羽西線を使って庄内まで延ばす構想」に前向きだった。専門家を集めて「山形新幹線機能強化検討委員会」を立ち上げ、庄内までの延伸と福島・山形県境にある板谷峠のトンネル化を検討するよう要請した。
ところが、高橋知事は2005年の知事選で、加藤紘一代議士らが担いだ斎藤弘氏に敗れた。財政再建と採算重視を掲げる斎藤知事は、庄内延伸にも板谷峠のトンネル化にも関心を示さなかった。機能強化検討委は翌年の3月、新しい知事の意向に沿った報告書を出し、庄内延伸の構想は頓挫した。
新幹線論議が山形で再燃するのは2012年からだ。再選をめざす吉村知事は「簡単でないのは承知しているが、奥羽、羽越新幹線の整備を求めたい」と言い始めた。福島から山形を通って秋田に至る奥羽新幹線。富山から新潟、庄内、秋田、青森へと延びる羽越新幹線。その二つをフル規格の新幹線として建設する構想だ(図1)。知事は2期目の公約にし、山形県の長期計画にも盛り込んだ。
前の年に起きた東日本大震災で日本海側の交通インフラの脆弱さを痛感したこと、整備新幹線5路線の工事計画が固まり、「次の新幹線建設の優先順位をどうするか」が政治の重要課題になってきたことが念頭にあったと思われる。
山形新幹線は、法的には「新幹線」ではない。福島で東北新幹線につながる「新幹線直行特急」であり、福島から山形、新庄までは在来線の奥羽本線を走る。直行を実現するため、奥羽本線は新幹線用の標準軌道に改修されたが、踏切が残り、一部だが単線区間もある。福島・山形県境の板谷峠は急峻で、豪雪地帯だ。雪に阻まれ、運休することも少なくない。
開業当初こそ、「3時間足らずで東京に行ける」と喜ばれたが、「しょせんはミニ新幹線」といった不満が募っていった。決定的だったのは東北新幹線の青森延伸(2010年)である。東京から新青森までは713キロと、山形までの倍近くある。なのに、所要時間はそれほど変わらない。「フル規格の新幹線が欲しい」という声が出てくるのも無理はない。
「日本海側も太平洋側と同じく大事な国土。隅々まで新幹線ネットワークをつなぐことで、日本全体の力が発揮できる。全国の皆様にも関心を持っていただき、大きな運動のうねりをつくっていきたい」。吉村知事は昨年2月に開かれた日経フォーラムで、フル規格の奥羽、羽越新幹線構想に理解を求めた。
正論である。正面切って、反対はしにくい。だが、果たして実現の可能性はあるのか。整備新幹線の5路線に次いで、奥羽、羽越新幹線構想が政府の基本計画に載ったのは1973年、高度経済成長期である。それから半世紀。日本は少子高齢化と人口減の時代を迎え、緩やかな下り坂に差しかかっている。図2に見るように、北海道の新幹線整備はこれからだ。四国にも山陰にも新幹線網は届いていない。
東北の日本海側を貫く新幹線はないが、山形も秋田もミニ新幹線で東京とつながっている。北陸新幹線の建設には1キロ100億円もかかった。政府も自治体も膨大な借金を抱えている。そうしたことを考えれば、奥羽新幹線も羽越新幹線も夢物語と言うしかない。夢を追うのは夢想家の仕事であって、政治家の為すべきことではない。
現在の新幹線整備計画が一段落した後に考えるべきことは、むしろミニ新幹線の知恵と経験を全国でどのように活かしていくか、ということではないか。
ミニ新幹線第1号となった山形新幹線は、1987年末の予算折衝で政府の建設費補助が内定してから5年足らずで開業にこぎつけた。在来線を使ったこともあり、用地買収の必要はなく、総事業費は620億円で収まった(開業時の概算)。フル規格の新幹線建設とはけた違いの安さだ。ある意味、時代を先取りした「エコな事業だった」と再評価されていい。
実際、四国では「スーパー特急方式」と名付けて、ミニ新幹線と同様、在来線を活用する案も検討されている(図3参照)。山陰にしても、大阪から鳥取、島根とつながるフル規格の新幹線を待つより、岡山から松江へと中国山地を縦断するミニ新幹線を建設する方が現実的だろう。
話を地元に戻せば、山形県が一体となって発展していくという観点からも、山形新幹線の庄内延伸をもう一度、真剣に検討すべきではないか。夢物語の奥羽、羽越新幹線構想を追う限り、山形新幹線の庄内延伸は店(たな)ざらし状態のまま、一歩も進まない。
もちろん、庄内延伸も簡単ではない。何よりも、庄内の2都市、酒田と鶴岡の利益が一致しない、という問題がある。JRの鉄路は余目(あまるめ)駅で酒田方面と鶴岡方面に分かれる(図4)。まず、どちらに延ばすかでもめる。酒田市は新幹線の延伸に熱心だが、より新潟に近い鶴岡市の人たちは「羽越本線を高速化して新潟で上越新幹線に乗り換えた方が早い」と考えているようで、延伸に背を向ける人もいる。
しかし、そういう時こそ、政治家の出番ではないか。余目駅から酒田、鶴岡の両方に新幹線を延ばして両方を終着駅にする、という方法もある(始発は半分ずつ)。あるいは、酒田に延伸する代わりに鶴岡には別の面で力を注いで妥協を図る道もある。要は、山形新幹線をなんとしてでも庄内まで延ばし、名実ともに「山形新幹線」という名にふさわしいものにする、という決意があるかどうかだ。
フル規格の奥羽、羽越新幹線構想に関しては、実は吉村知事より先に提唱した人たちがいる。山形新聞である。表1にも記したが、2000年1月に「幻の新幹線・奥羽、羽越の実現決意」という社説を掲げた。両新幹線を整備計画線に格上げする運動を「怠りなく、より強めていかなければならない」と訴え、「本県が“ミニ”のままでよいのか」と結んでいる。
その心意気は理解できるが、この社説を書いた時、筆者は庄内の人たちの気持ちをどのくらい思いやったのだろうか。「奥羽、羽越」と併記してみても、奥羽が優先されることは目に見えている。フル規格の新幹線構想を唱えることは、そのまま「庄内のことは自分たちで何とかしたら」と言うに等しい。
もともと、庄内の人たちには「内陸のやつらは信用できない」という思いがある。内陸の人たちは「庄内の連中は気位が高く、いがみ合ってばかりいる」と反論するのかもしれない。戊辰戦争以来の怨恨(えんこん)がいまだにうずいている、と指摘する人もいる。
そういうわだかまりを解きほぐしていくためにも、フル規格の奥羽、羽越新幹線の建設より山形新幹線の庄内延伸の方がはるかに優れた選択肢ではないか。
フル規格の新幹線構想にこだわる吉村知事は最近、板谷峠にトンネルを掘る計画にご執心だ。長さ23キロの長大なトンネル。JR東日本によれば、事業費は在来線用のトンネルで1500億円、フル規格の新幹線用となれば、さらに120億円上積みされる。上積み分は地元負担になるという。このトンネルによって短縮される時間は10分ほどだ。
田中角栄氏が日本列島改造論を唱えた時代ならともかく、膨らむ医療費や福祉と介護の負担をまかなうため消費税を引き上げる算段をしている時期に、このような話が通るわけがない。私たちの社会がこれから辿る道を考えれば、何を優先すべきか、自ずから見えてくるだろう。
吉村知事には、ビスマルクのもう一つの言葉を伝えたい。彼は、政治家としての長くて厳しい歩みを踏まえ、こう言っている。「政治とは、歴史に刻まれる神の足音に注意深く耳を傾け、その道をひととき共に歩むことである」
*メールマガジン「風切通信 59」 2019年6月29日
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の7月号に寄稿した文章を転載したものです。
≪写真説明≫
山形新幹線
≪参考文献&サイト≫
◎『山形新幹線 鉄路の復権』(鹿野道彦、翠嵐社)1992年
142ページに山形新幹線の総事業費620億円の内訳がある(工事費320億円、車両費200億円、標準軌用車両費など100億円)
◎『山形新幹線 鉄道21世紀への飛躍』(東日本旅客鉄道株式会社、今野平版印刷)1992年
◎「次の新幹線はどこに?」熱を帯びる誘致合戦(東洋経済ONLINE 2018年2月5日 )
図1の「奥羽、羽越新幹線構想」、図3の「四国新幹線構想」はこの記事から引用
https://toyokeizai.net/articles/-/207148?page=3
◎盛岡?新青森、320キロ解禁へ JR東が防音工事(朝日新聞DIGITAL 2019年1月14日)
図2の「新幹線の整備状況」はこの記事から引用
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20190114000403.html
◎日経フォーラム「実装に入った地方創生」での吉村美栄子・山形県知事の講演概要
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3550948019092018000000/
◎ウィキペディアの「山形新幹線」「整備新幹線」「奥羽新幹線」「四国新幹線」の各項(URL省略)
◎板谷峠トンネル化、「フル」か「ミニ」か、仕様巡り県と地元摩擦(河北新報ONLINE NEWS 2019年1月22日)
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190122_53004.html
◎新板谷トンネルの概要(鉄道計画データベース)
https://railproject.tabiris.com/yamagatatunnel.html
◎山形新聞の2000年1月10日付社説「幻の新幹線・奥羽、羽越の実現決意」、「山形にフル規格新幹線を」と題した一連のキャンペーン記事
◎ビスマルクの言葉「政治とは、歴史に刻まれる神の足音に注意深く耳を傾け、その道をひととき共に歩むことである」(筆者訳)の英語表現は次の通り(ニューヨークタイムズの書評とURL)。
Statesmanship consists of listening carefully to the footsteps of God through history and walking with him a few steps of the way.
https://www.nytimes.com/2011/04/03/books/review/book-review-bismarck-by-jonathan-steinberg.html
◎ドイツ語版ウィキペディア「ビスマルク Bismark」
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
松尾芭蕉の舟下り330年を記念する「第7回最上川縦断カヌー探訪」は予定通り、7月27日(土)午前10時スタートで開催いたします。山形県新庄市の当日の天気は「曇のち晴」の予報です。最近の雨で最上川はやや増水していますが、カヌー川下りには差し支えない状態です。芭蕉ゆかりの地でお待ちしています。
出だしの音だけで曲名を当てる「音楽のイントロクイズ」は難しい。知っている歌でも、出だしだけでは思い出せないことがよくある。それに比べれば、「裁判のイントロクイズ」はすごく簡単、と教わった。

民事訴訟の判決の場合、裁判官が発する最初の音だけで、裁判の勝ち負けが分かるという。裁判官が「ゲ」と言えば、原告の負け。「原告の請求を棄却する」と、短い主文が読み上げられておしまいだ。判決の言い渡しが「ヒ」で始まれば、原告の勝ち。「被告は何々をせよ」と、原告の請求を認める言葉が続くからだ。
新聞記者として裁判の取材をしたことは何度もあるが、自分が裁判の当事者になったのは2年前の7月、64歳にして初めてのことだった。東海大山形高校を運営する学校法人、東海山形学園の財務会計書類を情報公開請求したのに対して、山形県が詳細な部分を伏せて開示したのは不当、として訴えたのだ。その私の裁判の判決は「ゲ」で始まり、負けた。山形地方裁判所の裁判官は「原告の請求を棄却する」との判決を下したのである。
この2年、「ああだ、こうだ」と理屈をこね回す県側の弁護士の主張をさんざん聞かされた挙げ句、この判決。「被告(山形県)は会計書類の不開示処分を取り消し、全面開示せよ」との判決を勝ち取ることはできなかった。怒りは湧いてこなかった。落胆もしなかった。正直に言えば、拍子抜けして、心の中で「はあ?」とひとりごちた。4月23日のことである。
こんな風に書いても訳が分からない方も多いはずなので、裁判の端緒と経緯をあらためて詳しく紹介したい。
学校法人の東海山形学園がダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資を行ったことを私が知ったのは、2016年11月のことだ。よく行く山形市内の蕎麦屋さんに地元の月刊誌『素晴らしい山形』が置いてあり、それに書いてあった(表1)。
『素晴らしい山形』はその少し前から、ダイバーシティメディアの社長であり、東海山形学園の理事長でもある吉村和文氏と、吉村美栄子・山形県知事をめぐる様々な問題を取り上げていた。吉村知事と和文氏は「義理のいとこ」である(知事の亡夫が和文氏のいとこ)。和文氏はこの会社と学校法人のほかにも、映画館会社やIT企業など10を超える会社を経営している。月刊誌は、それらの企業グループと山形県や山形市が癒着している、と告発していた。
事実であれば、ゆゆしき問題である。しばらく、様子を見ていた。だが、メディアはまったく報じる気配がない。議会でも何の質問も出ない。元新聞記者として、また、税金の使途を監視する市民オンブズマン山形県会議の会員として、そして何よりも、一人の人間として義憤に駆られた。
月刊誌の編集者兼発行人の相澤嘉久治(かくじ)氏は、かつて山形の政財界を牛耳り、「山形の天皇」と呼ばれた服部敬雄(よしお)・山形新聞社長に立ち向かい、「メディアの独占と横暴は許されない」と訴え続けた人だ。会ったことはなかったものの、東京で新聞記者をしていた頃からその追及ぶりは知っており、「わが故郷にも気骨のある人がいるなぁ」と感じていた。
その人が老骨に鞭打って新しい闘いを始めたのに、誰も加勢しないのはひど過ぎる。というわけで、2017年の春から、私は市民オンブズマン山形県会議の仲間の協力を得ながら、この問題を本格的に調べ始めた。山形地方法務局に行って和文氏が率いる会社の法人登記や土地登記の写しを取り、山形県庁に出向いて関係文書の情報公開を請求し始めた。調査の基礎資料として欠かせないからだ。
現役の新聞記者なら、県内の人脈を駆使し、コネも使って情報を集めることができるが、早期退職して故郷に戻った私にはそういうものはない。登記と開示情報が頼りである。山形県の情報公開制度はしっかりしている。県庁1階の行政情報センターに行けば、学事文書課の担当者が同席して、どういう公文書をどういう風に絞って請求すれば目的のものを入手できるか、手伝ってくれる。大いに助かった。
ところが、この3000万円融資問題に関しては、学校法人東海山形学園から山形県に提出された財務会計書類(資金収支計算書や消費収支計算書、貸借対照表)の公開を請求したところ、書類の細かい項目の部分が白くマスキングされて開示された(表2)。細部を伏せた理由は、情報公開条例の第6条に規定されている「開示することにより、法人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報」に該当するから、というものだった。
納得できなかった。私立学校を運営する学校法人には多額の私学助成費が政府と県から支出されている。その代わり、学校法人には毎年、財務会計書類を監督官庁(この場合は山形県)に提出することが義務付けられている。いわば、学校法人の運営状況を判断するための基礎資料とも言えるものだ。
こうした財務会計書類は、上場企業なら誰でも見ることができる。老人ホームを運営する社会福祉法人の場合も、一般に公開することが義務付けられている。公開されたことによって企業や社会福祉法人の利益が害された、などという話は聞いたこともない。なぜ、学校法人だと「利益が害される」となるのか。
最初は「この学校法人の理事長は知事の縁者だ。その法人が年間の私学助成費の1割にも当たる資金をグループ企業に融資するという、おかしなことをした。だから、県の職員はかばおうとしているのではないか」と疑った。
だが、裁判の準備をするため調べていくうちに「それほど単純な話ではない」と分かってきた。学校法人の財務会計書類をどのように扱うべきか。実は、文部科学省そのものが矛盾した対応をしているのだ。
不正入試などの不祥事が相次いだため、私立学校法は2004年に大幅に改正され、学校法人の理事機能を強化し、財務情報の公開を進めることになった。これを受けて、文部科学省は2009年に「広く一般の人や関係者の理解を得るため、財務情報の公開は極めて重要である。学校法人に財務書類の公開を法的に義務付けることが必要である」と、かなり踏み込んだ考え方を打ち出した。
ところが、それから10年も経つのに、学校法人の財務情報の公開はいまだ法的に義務付けられていない。それどころか、私立学校関係者の働きかけもあってか、大学に比べると規模の小さい高校を運営する学校法人について、文科省は「財務情報の公開義務付け」から除外しようとする動きを見せている。
今年の1月、大学設置・学校法人審議会の学校法人制度改善検討小委員会は「高校以下の学校を設置する学校法人については、中小規模の法人が多く、地域的に限られた運営を行っている。私学助成などを通じて各都道府県が独自に監督を行っており、財務状況等について広く全国を対象に公表することを義務付けることには慎重であるべきである」との提言をまとめた。文科省の意向を受けた提言と見ていいだろう。
表向きは「学校法人の財務情報の公開推進」を唱えながら、裏に回れば、私立高校を運営する法人について「財務情報の公開」を渋る文科省。山形県は右ならえ、の対応をしているのだ。
山形地裁の裁判官は「財務会計書類の詳細が明らかになれば、学校経営上の秘密やノウハウが他の高校の知るところとなり、当該学校法人の利益を害する可能性がある」という県側の荒唐無稽な言い分を鵜(う)呑みにして、全面開示の請求を棄却した。裁判所は、高校を運営する学校法人の情報公開に背を向ける文科省や山形県の対応を追認したのである(表3参照)。
現実はどうか。このような文科省や山形県、裁判所の考えより、はるか先まで進んでしまっている。文科省がまとめた「学校法人の財務情報等の公開状況に関する調査」(2018年10月時点)によれば、全国の大学・短大はすべて財務会計書類をすでに一般公開している。そのうち、貸借対照表の細かい内容まで(小科目まで含めて)公開している大学は56%に達している。
それでも、学校法人の情報公開に後ろ向きの人は「高校は違う。経営上のノウハウを他校にまねされやすいのだ」と言い募るのかもしれない。そういう人には「愛知県の私学助成を見よ」と言いたい。
愛知県の場合は19年前から、高校などを運営する学校法人に財務情報を一般に公開するよう指導している。それにとどまらず、実際に公開している法人には100万円の補助金を追加して支給している。
これに応じて公開している学校法人は、同県江南市の滝学園(中高一貫校を運営)など全体の3割近くある(表4は滝学園の資金収支計算書の一部)。愛知県以外でも、埼玉県の立教新座高校や静岡県の菊川南陵高校も公開している。こうした高校の関係者に山形県の言い分や山形地裁の判決内容を伝えると、ただ苦笑するだけだった。
情報公開は、ただ単に物事をガラス張りにして分かりやすくする、というだけではない。事実を公開することによって、組織の運営に緊張感がもたらされる。不祥事を未然に防ぐことにもつながる。物事をより良い方向に変えていく力になるのだ。
それは時代の流れであり、誰にも押しとどめることはできない。山形地裁の裁判官は法律や条例の細かい解釈にこだわり、大切なことを見落としている。情けない判決だ。これでは、控訴してさらに争うしかない。
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の6月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明とSource≫
山形地裁の判決後、記者会見する原告(筆者)と弁護団(産経デジタルから)
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/photos/190424/evt19042414220009-p1.html

民事訴訟の判決の場合、裁判官が発する最初の音だけで、裁判の勝ち負けが分かるという。裁判官が「ゲ」と言えば、原告の負け。「原告の請求を棄却する」と、短い主文が読み上げられておしまいだ。判決の言い渡しが「ヒ」で始まれば、原告の勝ち。「被告は何々をせよ」と、原告の請求を認める言葉が続くからだ。
新聞記者として裁判の取材をしたことは何度もあるが、自分が裁判の当事者になったのは2年前の7月、64歳にして初めてのことだった。東海大山形高校を運営する学校法人、東海山形学園の財務会計書類を情報公開請求したのに対して、山形県が詳細な部分を伏せて開示したのは不当、として訴えたのだ。その私の裁判の判決は「ゲ」で始まり、負けた。山形地方裁判所の裁判官は「原告の請求を棄却する」との判決を下したのである。
この2年、「ああだ、こうだ」と理屈をこね回す県側の弁護士の主張をさんざん聞かされた挙げ句、この判決。「被告(山形県)は会計書類の不開示処分を取り消し、全面開示せよ」との判決を勝ち取ることはできなかった。怒りは湧いてこなかった。落胆もしなかった。正直に言えば、拍子抜けして、心の中で「はあ?」とひとりごちた。4月23日のことである。
こんな風に書いても訳が分からない方も多いはずなので、裁判の端緒と経緯をあらためて詳しく紹介したい。
学校法人の東海山形学園がダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)に3000万円の融資を行ったことを私が知ったのは、2016年11月のことだ。よく行く山形市内の蕎麦屋さんに地元の月刊誌『素晴らしい山形』が置いてあり、それに書いてあった(表1)。
『素晴らしい山形』はその少し前から、ダイバーシティメディアの社長であり、東海山形学園の理事長でもある吉村和文氏と、吉村美栄子・山形県知事をめぐる様々な問題を取り上げていた。吉村知事と和文氏は「義理のいとこ」である(知事の亡夫が和文氏のいとこ)。和文氏はこの会社と学校法人のほかにも、映画館会社やIT企業など10を超える会社を経営している。月刊誌は、それらの企業グループと山形県や山形市が癒着している、と告発していた。
事実であれば、ゆゆしき問題である。しばらく、様子を見ていた。だが、メディアはまったく報じる気配がない。議会でも何の質問も出ない。元新聞記者として、また、税金の使途を監視する市民オンブズマン山形県会議の会員として、そして何よりも、一人の人間として義憤に駆られた。
月刊誌の編集者兼発行人の相澤嘉久治(かくじ)氏は、かつて山形の政財界を牛耳り、「山形の天皇」と呼ばれた服部敬雄(よしお)・山形新聞社長に立ち向かい、「メディアの独占と横暴は許されない」と訴え続けた人だ。会ったことはなかったものの、東京で新聞記者をしていた頃からその追及ぶりは知っており、「わが故郷にも気骨のある人がいるなぁ」と感じていた。
その人が老骨に鞭打って新しい闘いを始めたのに、誰も加勢しないのはひど過ぎる。というわけで、2017年の春から、私は市民オンブズマン山形県会議の仲間の協力を得ながら、この問題を本格的に調べ始めた。山形地方法務局に行って和文氏が率いる会社の法人登記や土地登記の写しを取り、山形県庁に出向いて関係文書の情報公開を請求し始めた。調査の基礎資料として欠かせないからだ。
現役の新聞記者なら、県内の人脈を駆使し、コネも使って情報を集めることができるが、早期退職して故郷に戻った私にはそういうものはない。登記と開示情報が頼りである。山形県の情報公開制度はしっかりしている。県庁1階の行政情報センターに行けば、学事文書課の担当者が同席して、どういう公文書をどういう風に絞って請求すれば目的のものを入手できるか、手伝ってくれる。大いに助かった。
ところが、この3000万円融資問題に関しては、学校法人東海山形学園から山形県に提出された財務会計書類(資金収支計算書や消費収支計算書、貸借対照表)の公開を請求したところ、書類の細かい項目の部分が白くマスキングされて開示された(表2)。細部を伏せた理由は、情報公開条例の第6条に規定されている「開示することにより、法人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報」に該当するから、というものだった。
納得できなかった。私立学校を運営する学校法人には多額の私学助成費が政府と県から支出されている。その代わり、学校法人には毎年、財務会計書類を監督官庁(この場合は山形県)に提出することが義務付けられている。いわば、学校法人の運営状況を判断するための基礎資料とも言えるものだ。
こうした財務会計書類は、上場企業なら誰でも見ることができる。老人ホームを運営する社会福祉法人の場合も、一般に公開することが義務付けられている。公開されたことによって企業や社会福祉法人の利益が害された、などという話は聞いたこともない。なぜ、学校法人だと「利益が害される」となるのか。
最初は「この学校法人の理事長は知事の縁者だ。その法人が年間の私学助成費の1割にも当たる資金をグループ企業に融資するという、おかしなことをした。だから、県の職員はかばおうとしているのではないか」と疑った。
だが、裁判の準備をするため調べていくうちに「それほど単純な話ではない」と分かってきた。学校法人の財務会計書類をどのように扱うべきか。実は、文部科学省そのものが矛盾した対応をしているのだ。
不正入試などの不祥事が相次いだため、私立学校法は2004年に大幅に改正され、学校法人の理事機能を強化し、財務情報の公開を進めることになった。これを受けて、文部科学省は2009年に「広く一般の人や関係者の理解を得るため、財務情報の公開は極めて重要である。学校法人に財務書類の公開を法的に義務付けることが必要である」と、かなり踏み込んだ考え方を打ち出した。
ところが、それから10年も経つのに、学校法人の財務情報の公開はいまだ法的に義務付けられていない。それどころか、私立学校関係者の働きかけもあってか、大学に比べると規模の小さい高校を運営する学校法人について、文科省は「財務情報の公開義務付け」から除外しようとする動きを見せている。
今年の1月、大学設置・学校法人審議会の学校法人制度改善検討小委員会は「高校以下の学校を設置する学校法人については、中小規模の法人が多く、地域的に限られた運営を行っている。私学助成などを通じて各都道府県が独自に監督を行っており、財務状況等について広く全国を対象に公表することを義務付けることには慎重であるべきである」との提言をまとめた。文科省の意向を受けた提言と見ていいだろう。
表向きは「学校法人の財務情報の公開推進」を唱えながら、裏に回れば、私立高校を運営する法人について「財務情報の公開」を渋る文科省。山形県は右ならえ、の対応をしているのだ。
山形地裁の裁判官は「財務会計書類の詳細が明らかになれば、学校経営上の秘密やノウハウが他の高校の知るところとなり、当該学校法人の利益を害する可能性がある」という県側の荒唐無稽な言い分を鵜(う)呑みにして、全面開示の請求を棄却した。裁判所は、高校を運営する学校法人の情報公開に背を向ける文科省や山形県の対応を追認したのである(表3参照)。
現実はどうか。このような文科省や山形県、裁判所の考えより、はるか先まで進んでしまっている。文科省がまとめた「学校法人の財務情報等の公開状況に関する調査」(2018年10月時点)によれば、全国の大学・短大はすべて財務会計書類をすでに一般公開している。そのうち、貸借対照表の細かい内容まで(小科目まで含めて)公開している大学は56%に達している。
それでも、学校法人の情報公開に後ろ向きの人は「高校は違う。経営上のノウハウを他校にまねされやすいのだ」と言い募るのかもしれない。そういう人には「愛知県の私学助成を見よ」と言いたい。
愛知県の場合は19年前から、高校などを運営する学校法人に財務情報を一般に公開するよう指導している。それにとどまらず、実際に公開している法人には100万円の補助金を追加して支給している。
これに応じて公開している学校法人は、同県江南市の滝学園(中高一貫校を運営)など全体の3割近くある(表4は滝学園の資金収支計算書の一部)。愛知県以外でも、埼玉県の立教新座高校や静岡県の菊川南陵高校も公開している。こうした高校の関係者に山形県の言い分や山形地裁の判決内容を伝えると、ただ苦笑するだけだった。
情報公開は、ただ単に物事をガラス張りにして分かりやすくする、というだけではない。事実を公開することによって、組織の運営に緊張感がもたらされる。不祥事を未然に防ぐことにもつながる。物事をより良い方向に変えていく力になるのだ。
それは時代の流れであり、誰にも押しとどめることはできない。山形地裁の裁判官は法律や条例の細かい解釈にこだわり、大切なことを見落としている。情けない判決だ。これでは、控訴してさらに争うしかない。
*メールマガジン「風切通信 58」 2019年5月31日
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の6月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。
≪写真説明とSource≫
山形地裁の判決後、記者会見する原告(筆者)と弁護団(産経デジタルから)
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/photos/190424/evt19042414220009-p1.html
旧優生保護法に基づいて行われた強制不妊について、仙台地裁は「法律そのものが違憲だった」とする一方で、「除斥期間が過ぎているので損害賠償は請求できない」という判決を下した。その内容を報じる新聞記事を読みながら、私の心はワナワナと震えた。

戦後、国家が「あなたのような障害や遺伝性疾患のある人が子どもを産んでも不幸になるだけ」と、女性に不妊手術を強制した。「それはおかしい」と声を上げたのに、政府も国会も怠けて1996年まで法律を変えなかった。
その間、不妊手術を強いられた人たちはただ耐えるしかなかった。手術の記録は「保存期間が過ぎたから」と廃棄されていった。かろうじて残っていた記録を頼りに、「人間としての尊厳を踏みにじった責任を取って欲しい」と裁判に訴えたのに、この判決。このような判決文を書いた裁判官たちの責任は重大である。
旧優生保護法が「すべて国民は個人として尊重される」とうたった憲法13条に違反している、と判断したところまではいい。だが、それに続けて「除斥期間の20年が過ぎているので、国に損害賠償を請求することはできない」とは何事か。とんでもない判決だ。
除斥期間は時効に似た法理だ。ただ、時効が「他人の不動産も20年間、平穏に占有していれば所有権を得る」「工事の代金は3年間たてば請求できなくなる」などと、権利ごとに民法に規定されていて、期間も異なるのに対して、除斥期間は民法には詳しい規定がなく、期間も一律だ。「20年たてばどんな権利も行使できない。それは自明の理」というもので、時効より強烈といえる。
仙台地裁の裁判官はその除斥期間を適用して、損害賠償を求める被害者たちの請求を退けた。一応、理屈は通っている。だが、正義にはかなっていない。国民の多くもこの判決には納得しないだろう。強制不妊を迫られた人たちは何十年も「法律に基づく手術だから」と放っておかれたのだ。
そういう人たちの訴えを「法律によれば、そうなる」と切って捨てるのは、血の通った人間のすべきことではない。法律は、正義を実現し、苦しむ人たちに救いの手を差し伸べるための手段として使うべきものだ。為政者に都合のいいように解釈、運用されたのではたまらない。
日本の民法は、明治時代にフランスの民法をベースにドイツの法理論などを加味して、あわてて作られたものだ。19世紀に作られた法律を21世紀の今、杓子定規に適用してどうするのか。強制不妊をめぐるこれまでの経緯を踏まえ、訴えを起こせなかった事情に配慮して法律を解釈し、適用すればいいのだ。
被害者たちはずっと、権利を行使しようとしても行使できない状態に置かれていた。訴えても政府も国会も動かなかった。そのような「特段の事情」があったのだから、そういう場合には「20年以上たったから請求できない」と言うことはできない、という新しい解釈を編み出し、それを判例にすればいいではないか。
裁判官たちにそうした決断ができないのは、法曹という狭い世界に生きてきたからだろう。若い頃から、法律の細かい条文、くどくどした解釈ばかり目にしてきたから、広い世界で何が起きているのか、時代に求められているものは何なのか、そういうことに思いが至らない。彼らは利発だけれど、賢明ではない。
この判決に関する新聞各紙の報道はもの足りなかった。29日の朝日新聞の社説は、賠償を命じなかったのは「承服できない」と批判したが、除斥期間を適用したことに触れていない。毎日新聞の社説は「除斥期間を過ぎても『特段の理由』で訴えが認められた判決も過去にはある」と指摘したが、踏み込みが足りない。「人生踏みにじる罪深さ」という東京新聞の社説が一番、心に響いた。
こういう判決が出た時には、もっとズバッと書けばいいではないか。「ひどい判決だ」と。憲法によって裁判官に特別な身分保障が与えられているのは何のためか。きちんとした処遇と報酬が約束されているのは何のためなのか。こんな判決を書くためではないだろう。
*メールマガジン「風切通信 57」 2019年5月29日
≪参考記事&文献≫
◎5月29日の朝日新聞、毎日新聞、読売新聞
◎東京新聞(電子版)の社説「人生踏みにじる罪深さ」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019052902000162.html
◎『民法概論?』(星野英一、良書普及会)
◎『新訂 民法總則』(我妻栄、岩波書店)
≪写真説明&Source≫
◎仙台地裁の判決に抗議する原告弁護団
https://mainichi.jp/articles/20190528/k00/00m/040/130000c

戦後、国家が「あなたのような障害や遺伝性疾患のある人が子どもを産んでも不幸になるだけ」と、女性に不妊手術を強制した。「それはおかしい」と声を上げたのに、政府も国会も怠けて1996年まで法律を変えなかった。
その間、不妊手術を強いられた人たちはただ耐えるしかなかった。手術の記録は「保存期間が過ぎたから」と廃棄されていった。かろうじて残っていた記録を頼りに、「人間としての尊厳を踏みにじった責任を取って欲しい」と裁判に訴えたのに、この判決。このような判決文を書いた裁判官たちの責任は重大である。
旧優生保護法が「すべて国民は個人として尊重される」とうたった憲法13条に違反している、と判断したところまではいい。だが、それに続けて「除斥期間の20年が過ぎているので、国に損害賠償を請求することはできない」とは何事か。とんでもない判決だ。
除斥期間は時効に似た法理だ。ただ、時効が「他人の不動産も20年間、平穏に占有していれば所有権を得る」「工事の代金は3年間たてば請求できなくなる」などと、権利ごとに民法に規定されていて、期間も異なるのに対して、除斥期間は民法には詳しい規定がなく、期間も一律だ。「20年たてばどんな権利も行使できない。それは自明の理」というもので、時効より強烈といえる。
仙台地裁の裁判官はその除斥期間を適用して、損害賠償を求める被害者たちの請求を退けた。一応、理屈は通っている。だが、正義にはかなっていない。国民の多くもこの判決には納得しないだろう。強制不妊を迫られた人たちは何十年も「法律に基づく手術だから」と放っておかれたのだ。
そういう人たちの訴えを「法律によれば、そうなる」と切って捨てるのは、血の通った人間のすべきことではない。法律は、正義を実現し、苦しむ人たちに救いの手を差し伸べるための手段として使うべきものだ。為政者に都合のいいように解釈、運用されたのではたまらない。
日本の民法は、明治時代にフランスの民法をベースにドイツの法理論などを加味して、あわてて作られたものだ。19世紀に作られた法律を21世紀の今、杓子定規に適用してどうするのか。強制不妊をめぐるこれまでの経緯を踏まえ、訴えを起こせなかった事情に配慮して法律を解釈し、適用すればいいのだ。
被害者たちはずっと、権利を行使しようとしても行使できない状態に置かれていた。訴えても政府も国会も動かなかった。そのような「特段の事情」があったのだから、そういう場合には「20年以上たったから請求できない」と言うことはできない、という新しい解釈を編み出し、それを判例にすればいいではないか。
裁判官たちにそうした決断ができないのは、法曹という狭い世界に生きてきたからだろう。若い頃から、法律の細かい条文、くどくどした解釈ばかり目にしてきたから、広い世界で何が起きているのか、時代に求められているものは何なのか、そういうことに思いが至らない。彼らは利発だけれど、賢明ではない。
この判決に関する新聞各紙の報道はもの足りなかった。29日の朝日新聞の社説は、賠償を命じなかったのは「承服できない」と批判したが、除斥期間を適用したことに触れていない。毎日新聞の社説は「除斥期間を過ぎても『特段の理由』で訴えが認められた判決も過去にはある」と指摘したが、踏み込みが足りない。「人生踏みにじる罪深さ」という東京新聞の社説が一番、心に響いた。
こういう判決が出た時には、もっとズバッと書けばいいではないか。「ひどい判決だ」と。憲法によって裁判官に特別な身分保障が与えられているのは何のためか。きちんとした処遇と報酬が約束されているのは何のためなのか。こんな判決を書くためではないだろう。
*メールマガジン「風切通信 57」 2019年5月29日
≪参考記事&文献≫
◎5月29日の朝日新聞、毎日新聞、読売新聞
◎東京新聞(電子版)の社説「人生踏みにじる罪深さ」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019052902000162.html
◎『民法概論?』(星野英一、良書普及会)
◎『新訂 民法總則』(我妻栄、岩波書店)
≪写真説明&Source≫
◎仙台地裁の判決に抗議する原告弁護団
https://mainichi.jp/articles/20190528/k00/00m/040/130000c

あることを表すのに、どのような言葉を選ぶか。それは、その人あるいはその組織の品格にかかわる重大事である。そういう観点から山形県庁の組織図を眺めると、吉村美栄子知事の県政運営は及第点には程遠い。
土木部を県土整備部と改めたのは愚の骨頂である。「汚職や談合疑惑にまみれてイメージが悪いから」といった理由で変えたようだが、土木という言葉に罪はない。むしろ、近代以降、橋やダム造りに汗を流した人たちは誇りにすら思っていたはずだ。実際、見識を持って、そのまま使い続けている自治体も少なくない。
新設した観光文化スポーツ部という名称には、元新聞記者として情けなくなる。観光産業とスポーツの間に「文化」を挟み込む、その粗雑な感覚。文化とは、もっとふくよかで奥深いもの。こんな使い方をして、いいはずがない。
その部の幹部が新しい県民会館の指定管理者選びでどのような振る舞いをしたか。月刊『素晴らしい山形』の4月号で詳しく報告したら、選考にかかわった部次長と課長が3人とも春の人事異動でいなくなってしまった。在席1年で異動になった人もいる。
「指定管理者の問題で責任を取らされた」と見る向きもあるが、「そうではない」との観測もある。事情通は「サッカーの新しいスタジアム建設構想をめぐって不手際があった。そっちの方ではないか」と言う。
われらのチーム、モンテディオ山形は天童市の陸上競技場をホームにしている。1992年の「べにばな国体」のメイン会場として建設された施設で、球技場を兼ねている。かなり傷んでおり、何よりも「観客席の3分の1以上を屋根で覆うこと」というJリーグの基準を満たしていない。サポーターからは「サッカー専用のところでプレーを観たい」と、新しいスタジアムを望む声が寄せられていた。
新スタジアム構想が具体的に語られ始めたのは、表1に見るようにモンテディオ山形のチーム運営が県の外郭団体、山形県スポーツ振興21世紀協会から株式会社モンテディオ山形に移された2013年前後からである。山形市の市川昭男市長が吉村知事に新スタジアムの建設を要望し、(株)モンテディオ山形の高橋節(たかし)社長(元副知事)が構想に意欲を示す、といった動きが出始めた。
ただ、新スタジアムの建設には100億円前後の資金が必要になる。建設地をめぐって、新スタジアムを街起こしの起爆剤にしたい山形市とホームを抱える天童市との間で激しい鍔迫(つばぜ)り合いになることが予想される。誰もが「実現するのは容易なことではない」と分かっていた。
2015年に新スタジアム構想検討委員会を立ち上げた高橋氏も「資金や建設候補地の議論には踏み込まなかった。どのようなスタジアムが建設可能かというビジョンを検討することに留めた」と語る。
鍔迫り合いは、山形市と天童市の間よりも先に、まず同年9月の山形市長選で演じられた。市川市長が後継候補の梅津庸成(ようせい)氏の出陣式で「吉村知事が新スタジアムを山形市内に建設することを了解した」と受けとめられる発言をした、と報じられたのだ。
対立候補の佐藤孝弘氏を担いだ自民党はいきり立った。県議会自民党は梅津氏支持の知事に釈明を求めようと、知事室に押しかけた。知事は面談を拒み、記者会見で「事実無根のことが書いてある」と説明する騒ぎになった。
市長選で佐藤氏が勝ったことで市川・梅津陣営の目論見はついえたが、火種はくすぶり続けた。一昨年9月の新スタジアム推進事業株式会社の発足は、第2ラウンドの始まりを告げるものだった。
新スタジアム会社の代表取締役には、県経営者協会の寒河江(さがえ)浩二会長(山形新聞社長)と県商工会議所連合会の清野伸昭会長(山形パナソニック会長)、県経済同友会の鈴木隆一代表幹事(でん六社長)が就いた。表2のように、役員には県内の主な企業と団体のトップが名を連ねた。強力な布陣である。
ただし、内情を知る関係者によると、3人の代表取締役も他の役員も頼まれて神輿に乗っただけ。プロジェクトを実際に仕切っているのは吉村知事の義理のいとこ、ダイバーシティメディアの吉村和文社長とアビームコンサルティングの松田智幸執行役員の2人だという。両者とも発足と同時に新スタジアム会社の取締役になっている。
和文氏が知事との縁を活かして、地元の経済界と県庁内の根回しに動く。県の窓口は、かねて昵懇の観光文化スポーツ部の面々だ。アビームはNECグループのコンサルタント会社で、松田氏はスタジアムの建設構想と事業化計画を担う。寝技と頭脳のタッグだ。
実は、この2人の付き合いは長い。和文氏のブログ「約束の地へ」(2016年11月20日)によれば、この10年ほどの間に総務省関連の情報通信技術(ICT)事業や地域活性化プロジェクトを一緒に手がけた仲という。
吉村知事が2016年春に山形にゆかりのある著名人を「山形ブランド特命大使」に委嘱して「山形の応援団」を組織した際には、ともに「特命大使」に選ばれたりもしている。和文氏とNECとの関係の深さは、『素晴らしい山形』の連載の1回目で報じた「山形県庁のパソコン入札問題」を通して、うかがい知ることができる。
この2人が手を組み、県内の経済界のトップをそろえたのだから、普通なら「新スタジアム構想は官民合同のプロジェクトとして粛々と進む」はずだ。ところが、現実にはなかなか進まなかった。県庁内の根回し、つまり観光文化スポーツ部の幹部による財政課を始めとする関係部局との調整がうまく行かず、吉村知事の了承も得られなかったようなのだ。同部の幹部3人の人事はその不手際の始末、という見方が出る背景にはこうした経緯がある。
吉村知事は、経済3団体の代表が新スタジアム構想で面会を求めても、なかなか会おうとしなかったという。新スタジアム会社の日程表には「2018年9月に山形県に官民連携事業化を要請」とあったが、それが半年もずれ込み、今年の3月27日にようやく面会が実現した。
知事に提示された新スタジアムの整備基本計画は(1)観客席のみ覆う固定式屋根型かフィールドまで覆う可動式屋根型のどちらか=図1参照(2)観客席は1万5000人から2万人分(3)建設費は72億5000万円から113億円(4)建設地は公募して2020年9月に決定(5)2025年に運用開始、というものだった。建設費は県費で、運営は民間でという「大甘の計画」だ。
当然のことながら、吉村知事は「協力します」という言質を与えなかった。「将来的には必要なものと認識している」と、そっけなく応じた。面会後、経済3団体の代表は憮然としていたという。「神輿に乗ったのに、はしごを外された」という思いがあるのかもしれない。
歯車はうまく回っていない。吉村知事は巨額の負担を抱えそうで躊躇している。山形市は静かに見守っている風情。天童市に至っては冷淡ですらある。口に出しては言わないものの、誰もが「どこか既視感がある」と感じているからではないか。
新スタジアム会社の立ち上げは、吉村和文氏が27年前、1992年に起業したケーブルテレビ山形の構図とそっくりである。経済界の重鎮を担ぎ上げ、経営の実権は自分がしっかりと握る。事業費は国や県、市からの公金を当てにする、という点で。
潤沢な補助金を受け、最初の頃、ケーブルテレビ山形の経営は順調だった。だが、情報技術革命の急激な進展で環境はがらりと変わった。図2のように、ケーブルテレビ関係の売上高がじりじりと減っており、経営は極めて厳しい。表3にある山形県からのパソコン落札や業務委託で経営を支えている状態だ。
同社のある株主はこう語った。「彼はこの会社を作ってから、一度も株主に配当を出したことがない。経営者なら、きちんと利益を上げて株主に配当するのが基本。その基本ができていない」
吉村和文氏の仕事ぶりを見ていると、「政商」という言葉が浮かんでくる。三省堂の『大辞林』には、政商とは「政府や政治家と結びつき、特権的な利益を得ている商人」とある。なんと簡潔で的確な定義であることか。
そういえば、かつて山形にはもう少しスケールの大きな政商がいた。彼が亡くなって真空状態が生じた途端、取って代わろうとする者が現れ、動き回っている。
メールマガジン「風切通信 56」2019年4月27日
◇ ◇
≪訂正≫本誌4月号の山形県総合文化芸術館の指定管理者選考に関する記事(4ページ)に「細谷理事長に『県側から要請されて、渋々引き受けたと聞きました』と問うと、肯定も否定もしなかった」と書きましたが、「問うと、否定した」に訂正します。細谷氏から申し入れがありました。山形県生涯学習文化財団が指定管理者の共同企業体の代表を引き受けた経緯についてはなお調査中です。
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の5月号に寄稿した文章を若干手直しし、加筆したものです。見出しも異なります。表や図をクリックすると、内容が表示されます。
≪写真説明とSource≫
モンテディオ山形の選手。胸には山形のブランド米「つや姫」の文字(モンテディオ山形広報のサイトから)
https://twitter.com/monte_prstaff/status/1072399042469081088
*メールマガジン「風切通信 55」 2019年3月29日
人は誰しも過ちを犯す。間違えることなく生きていける人などいない。ただ、前に進もうとする人はその過ちから何かを学ぶ。少なくとも、学ぼうとする。

だが、山形県庁には過ちを過ちとして自覚せず、教訓を引き出そうとしない人たちがいる。月刊『素晴らしい山形』の2月号で観光キャンペーンをめぐる山形県幹部職員による露骨な業務委託の実態を報告したばかりなのに、今度は山形駅西口に建設中の新しい県民会館をめぐって、同じようなことが繰り返された。しかも、県庁の同じ部局の手で。
新しい県民会館の正式名称は、山形県総合文化芸術館という。完成後にその運営にあたる指定管理者を選ぶ審査委員会が1月9日に県庁で開かれた。名乗りを上げたのは、山形県生涯学習文化財団を代表とする共同企業体とステージアンサンブル東北という会社である。
生涯学習文化財団は山形県が50億円の資金を投じて作った外郭団体で、細谷知行・前副知事が理事長を務めている。県立図書館に事務所を構え、文翔館(旧県庁)の運営も担っている。この財団と山形交響楽協会、サントリーのグループ企業(サントリーパブリシティサービス)の3者が共同企業体を組んだ。
一方のステージアンサンブル東北には、現在の県民会館を10年間、指定管理者として運営してきた実績がある。とはいえ、従業員22人、資本金1000万円の小さな会社である。規模という点では、共同企業体にとても太刀打ちできない。山形県の担当者の胸の内を推し量れば、「勝負は最初から見えている」というところだったのではないか。
ところが、双方の提案を審査した結果は意外なものだった。表1のように、僅差ながらステージアンサンブル東北の評価が共同企業体を上回ったのである。とくに、中高生や文化団体など幅広い層が利用できる条件を整えているか、専門的な能力のある人材はいるか、といった面での評価が高かった。
上野雅郷(まさと)社長は「新しい会館になれば、利用料金が高くなって中学や高校の吹奏楽部や合唱部は利用しにくくなります。なので、こうした利用には料金を減免するといった提案も盛り込みました。今まで、限られた人数で県民会館をしっかり運営してきたことも評価していただいたと思っています」と語る。
審査委員7人の構成は表2の通りである。外部の有識者が4人、カラー文字で表示した3人が県幹部だ。外部の審査委員は4人のうち3人がステージアンサンブル東北に軍配を上げた。とりわけ、全国の音楽ホールの運営状況を熟知する間瀬(ませ)勝一氏と草加叔也(としや)氏が高く評価した。3人の県幹部はそろって共同企業体に高い点数を付けたが、及ばなかった。
県の指定管理者募集要項は、選定基準や審査項目、配点を詳細に記している。それに基づいた審査であり、本来なら「この評価で決定」のはずだった。ところが、審査委員長の齋藤真幸(まさき)・観光文化スポーツ部次長ら県幹部は、「僅差なので協議したい」と言い出した。協議は延々と続き、最終的には齋藤氏が「(委員長を除くと)3対3の同数なので私に一任していただきたい」と述べ、共同企業体を指定管理者候補にすることを決めたという。
強引な裁定である。全国公立文化施設協会のアドバイザーも務める草加氏は「審査の評価点で決めるのが本来あるべき姿」と言う。同じく協会アドバイザーでもある間瀬氏は「共同企業体の内部でどのように責任を分担するのか、あいまいな点が気になった」と指摘する。
あいまいなはずである。事情通によれば、共同企業体の代表を引き受けた生涯学習文化財団は、もともと指定管理者に応募するつもりなどなかったのだという。財団は50億円の基金の利子で運営する前提でスタートしたが、低金利が長く続いて資産を取り崩すしかなくなり、基金は32億円まで目減りした。財団の運営そのものが厳しい状況にあり、リスクを背負う余裕などないのだ。
細谷理事長に「県側から要請されて、渋々引き受けたと聞きました」と問うと、否定した。財団の財政状況に触れ、「総合文化芸術館の運営で赤字が出れば、大変なことになる」と聞くと、「(損失が出ても)負担は最小限にと伝えてあります」と答えた。実際に運営を担うサントリーパブリシティサービスの文化事業担当部長、篠原慎一氏は「責任分担は9対1で合意ずみです。私どもが9、財団と協会が合わせて1」と認めた。
なんのことはない。事業の幅を広げたい山形交響楽協会がサントリー側に声をかけたが、指定管理者の募集要項には「県内に主たる事務所(本店)があること」という資格要件があり、サントリー側は代表にはなれない。かといって、山形交響楽協会では代表として力不足。そこで県の幹部が生涯学習文化財団に頼み込んだ、という構図のようだ。県の外郭団体をダミーとして使ったのである。
2月下旬の県議会常任委員会で、選定のプロセスが問題になった。村形弘也・県総合文化芸術館整備推進室長は「財務状況が健全で安定的な運営が可能となる経営基盤があるか」などを総合的に評価した、と答弁した。おかしな答えである。表1にあるように、審査項目には「財務状況と経営基盤」も含まれている。7人の審査委員はそれも含めて採点しているからだ。
審査委員長を務めた齋藤真幸次長に説明を求めた。事実関係については「議事概要をご覧ください」と答えるのみ(現在、開示請求中)。決定のプロセスについても「(村形室長の)答弁の通りです」とかわした。「木で鼻をくくる」という表現がぴったりの対応だった。
指定管理者制度は2003年、小泉政権の時に導入された。公営施設の運営に民間の活力とノウハウを導入してサービスの向上と効率化を図るために作られた制度だ。県の外郭団体をダミーとして担ぎ出し、県の幹部職員が審査結果をひっくり返して管理者を決めた今回のケースは、制度の根幹を揺るがすもので、審査委員を引き受けた専門家たちもあきれたことだろう。
この制度に詳しい香川大学の三野(みの)靖・法学部長は「指定管理者をどのようにして決めるかについて、自治体には裁量権がある。ただ、裁量権を逸脱していないかという問題はある。制度の趣旨から考えれば、これは問題になり得るケースだろう」と言う。
実際、自治体による指定管理者の決定が違法とされた事例がある。2014年に北茨城市が観光施設の指定管理者を公募し、審査会が民間企業を選んだのに、市長がこれを覆して市の外郭団体を管理者にした。これを不当として企業側が訴え、水戸地裁でも東京高裁でも企業側が勝訴した(昨年、判決が確定)。今回は、知事が決定する前に県幹部が審査委員会の評価を覆しており、より巧妙と言える。
吉村美栄子知事は「冷ったい県政から温かい県政に」と唱えて当選したが、いつの間にかそれは「身内と取り巻きに温かい県政」に転じてしまったようだ。ステージアンサンブル東北のように、小粒ながら一生懸命働いてきた人たちの努力に砂をかけるようなことをしておいて、「山形を元気に」と呼びかけても虚しく響くだけだ。
知事は観光の振興に熱心だ。サクランボのかぶり物をして、トップセールスに精を出している。県商工労働観光部の末席にあった観光振興課は、吉村県政になってから人員も予算も急増した。ついには観光文化スポーツ部として独立し、観光立県推進課と名を変えて主幹課になった。その部局が勢いに乗り、歪んだ行政を推し進めている。
山形駅西口の県総合文化芸術館は、表3に見るように計画の検討開始から27年の曲折を経て、ようやくこの秋に完成する。用地取得に67億円、建設に148億円が投じられる。さらに、来年春に本格的にオープンすれば、指定管理者に年間約3億円、5年余で15億円の管理料が支払われる。
長い年月と多額の血税を費やして、山形に新しい文化の拠点が誕生する。その施設を舞台にして、県の幹部が意のままに振る舞い、物事を決めていく。こんなことをいつまで繰り返すのか。いつまで許すのか。目を覚まし、声を上げる時だ。
*このコラムは月刊『素晴らしい山形』の4月号に寄稿した文章を若干手直ししたものです。表1から表3をクリックすると、内容が表示されます。
≪訂正≫月刊『素晴らしい山形』4月号の山形県総合文化芸術館の指定管理者選考に関する記事(4ページ)に「細谷理事長に『県側から要請されて、渋々引き受けたと聞きました』と問うと、肯定も否定もしなかった」と書きましたが、「問うと、否定した」に訂正します(ウェブ版は訂正ずみ)。細谷氏から申し入れがありました。山形県生涯学習文化財団が指定管理者の共同企業体の代表を引き受けた経緯についてはなお調査中です。
≪写真説明とSource≫
山形駅西口に建設中の山形県総合文化芸術館の完成予想図(「ふるさとチョイス」のサイトから)
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/06000/4411576
*メールマガジン「風切通信 54」 2019年3月10日
あの日、東北は雪だった。大きく、異様に長い揺れ。海が巨大な壁となって押し寄せ、家と工場をなぎ倒していった。後に残された瓦礫の山と黒い泥。降りしきる雪の中で、被災者は凍えていた。その光景を思い出すと、今でも目がうるむ。

東北全域が停電になり、その夜は光がなかった。被災者は天を仰ぎ、今まで見たこともない満天の星を目にした。海を押し上げた地殻のとてつもないエネルギー。そして、何事もなかったかのようにまたたく星。心に沁みる星空だったという。
自然の力におののきながらも、被災者は健気だった。声を荒げることもなく、静かに列をつくって支援物資を受け取り、生きるために歩き始めた。災害列島に生まれ、しばしば天災に見舞われ、耐え抜くしか術(すべ)がないから、ということもあるのかもしれない。けれども、それだけだったのか。
私は「被災した人たちは信じていたのだ」と思う。私たちの社会は、苦しむ人たちを見捨てたりしない。支援の手が必ず差し伸べられる。だから、いたわり合いながら、それを待とう――そう確信していたから、静かに並ぶことができたのではないか。その姿を通して、見つめる人たちまで元気づけることができたのではないか。
大きな災害や紛争があり、食べ物と飲み水が欠乏すれば、誰もが家族を守るために血眼になる。貧しい国に限った話ではない。ハリケーンに襲われたアメリカでも、支援物資を受け取るために集まった群衆を力で押しとどめなければならなかった。それは自然なことであり、誰も非難したりできない。
だからこそ、世界は驚いたのだ。あれほどの大災害が起き、あれだけの犠牲者を出したのに、生き残った人たちが静かに列をなしていることに。そうした社会を作り上げてきたことを、少なくとも私たちは誇りにしてもいいのではないか。
東日本大震災の後、国連関係者や災害支援の国際組織の人たちの間で、「日本から学ぶ10のこと」という詩が作られ、広まった。
1. 静けさ
胸をたたいたり、取り乱したりする映像はまったくなかった。悲しみそのものが気高いものになった。
2. 厳粛さ
水や食料を求める整然とした行列。声を荒げることも粗野な振る舞いもなく。
3. 才覚
例えば、信じがたいような建築家たち。建物は揺れたが、倒れなかった。
4. 品格
人々は取りあえず必要な物だけを買った。だから、みんな何がしかのものを手にすることができた。
5. 秩序
商店の略奪なし。道路には警笛を鳴らす者も追い越しをする者もいない。思慮分別があった。
6. 犠牲
50人の作業員が原子炉に海水を注入するためにとどまった。彼らに報いることなどできようか。
7. 優しさ
レストランは料金を下げた。ATMは警備もしていないのにそこにある。強き者が弱き者の世話をした。
8. 訓練
老人も子どもも、みんな何をすべきかよく分かっていた。そして、それを実行した。
9. 報道
速報に際して、彼らはとてつもない節度を示した。愚かな記者はいない。落ち着いた報道だった。
10. 良心
店が停電になると、人々は品物を棚に戻し、静かに立ち去った。
大震災から8年。被災地はまだ、復興のただ中にある。福島では、いつ終わるとも知れない原発事故への対処が続いている。私たちも、後に続く世代もそれを背負って生きていくしかない。険しい道だ。けれども、私たちの社会には世界を驚かせる力もある。その力を信じて、ともに歩んでいきたい。
《詩のSource》
「日本から学ぶ10のこと」 “ 10 things to learn from JAPAN “ には、いくつかのバージョンがあります。上記の詩は次のURLから引用したものです(日本語訳は長岡昇)。
http://www.facebook.com/notes/xkin/10-things-to-learn-from-japan-/202059083151692
≪写真説明とSource≫
冬の星座(ブログ「星空の珊瑚礁」から)
https://hosiya.at.webry.info/201902/article_1.html
メールマガジン「風切通信 53」 2019年2月27日
時間的にも能力の面でも、人間には限界がある。普通の人の場合、二つか三つのことに力を注ぐだけで精一杯だろう。かの聖徳太子のように「同時に10人の話を聞いて、すべて聞き分ける」といった芸当ができる人は滅多にいるものではない。

吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏は自身のブログに「現在は、15の会社経営を担っている」と書いている。これを目にして驚く人もいるかもしれないが、苦労した人なら「なんだかなぁ」と斜に構えて読む。私も、長い新聞記者生活で苦い思いをたくさんしてきたので、額面通りに受けとめたりはしない。むしろ、「どっか怪しい」と感じる。
そもそも、「15の会社」がどれなのか、いくら調べても分からない。1992年にケーブルテレビ山形(現ダイバーシティメディア)を設立してから、吉村和文氏は次々に新しい会社を立ち上げてきた。傘下に吸収した会社もある。けれども、そうした会社を含めても、まだ足りない。思いあぐねて、本人に手紙で問い合わせたりもしたが、返事はない。ただ、一つだけ、その答えのようなものが見つかった。
彼は4年前に山形県の村山法人会に依頼されて東根市で講演をしたことがある。図1は、その講演会のチラシに掲載されたプロフィール部分である。ちょうど、15の会社と法人、団体の名前が並んでいる。講演会の主催者が勝手に略歴を作ることはないから、このプロフィールは本人が伝えたものだろう。これが「15の会社」なのかもしれない。
「文は人なり」という。文章にはその人の考え方から感じ方、生き方まですべてが滲み出る。本人が記す略歴にも似たところがある。生い立ちや職歴には触れず、会社や団体の名前と自分の肩書をずらりと並べ、胸を反らす――それが彼のスタイルなのだろう。
プロレス興行の会社とその持ち株会社や岩手ケーブルテレビジョンなどは把握していたが、「株式会社モンテディオ山形」や「山形交響楽団」まで並んでいるのには驚いた。地元のサッカーチームや交響楽団の経営も自分が担っている、と言うつもりか。かなりの心臓の持ち主である。
これらの会社や法人、団体の中で経営がもっとも安定しているのは、彼が理事長をしている学校法人東海山形学園だろう。東海大山形高校を運営しているこの学校法人の資金収支計算書によると、2017年度の収入は29億円余り。支出に占める人件費の割合は14%と低く、翌年度への繰越金は5億円もある。
学校法人の好決算を支えているのは国と県からの私学助成だ。表1の通り、東海山形学園には毎年、3億円を超える公金が注ぎ込まれている。その内訳は、教職員の人件費などに充てる一般補助金や生徒の授業料を軽減するための就学支援金(国費)と補助金(県費)などだ。2017年度には校舎の耐震改築工事のため施設整備費が膨らんだこともあって、助成費は10億円を上回った。2012年度からの6年間で助成の総額は27億円を超える。
もちろん、私学助成そのものに異議を差しはさむつもりはない。山形県の場合、斎藤弘・前知事は財政再建を掲げて私学助成費を削り込んだが、吉村美栄子知事は私学の支援に力を注いだ。経常経費の40%台まで落ち込んだ一般補助金の補助割合を段階的に50%まで引き上げ、授業料を軽減するための支援策も充実させた。それによって、生徒の保護者の負担は軽くなり、私学の経営を底支えしている。納得のいく施策だ。
問題は、吉村和文氏が学校法人の理事長としてこうした手厚い助成を受けながら、学校の資金3000万円を自分の会社、ダイバーシティメディアに融資したことにある。2016年3月のことだ。その後、返済されたとはいえ、年間助成費の1割もの資金を自分が社長をしている会社に貸し出す――そんなことが許されるのか。
詳しく調べるため、私は2年前に県学事文書課が保有する東海山形学園の財務諸表の情報公開を求めた。すると、文書は開示されたものの、細部を隠したものが出てきた(表2)。貸借対照表に「3000万円の融資」が記されているはずなのに、その部分も白くマスキングされていた。一部不開示にした理由は、細部まで明らかにすると「法人の正当な利益を害するおそれがあるため」というものだった。
あきれた。財務諸表は学校法人のいわば基本データのようなものだ。3000万円の融資については、借りた側のダイバーシティメディアの貸借対照表に明記されており、それは株主総会で配布されている。学校法人の会計文書でそれが明らかになったからと言って、「利益が害されるおそれ」などどこにあるのか。あまりにも理不尽なので、私は山形地方裁判所に「情報公開の不開示処分の取り消し」を求める訴えを起こした。長い審理を経て、4月下旬にその判決が出る。
3000万円の融資問題が表面化した後、私立学校の指導監督にあたる県学事文書課の遠藤隆弘課長(当時)は県議会の常任委員会で「監査報告書を見る限り、(融資の)契約は適正と考えている」と答弁した。吉村美栄子知事も記者会見で「(学校法人が)適切に運営されているのであれば、よろしいのではないか」と述べた。「とくに問題はない」と擁護したのである。
では、東海山形学園と同じように私学助成を受けている私立高校の関係者はどう見ているのか。山形県内には、表3のように高校を運営し、私学助成を受けている学校法人が14ある。各校に見解を問うと、匿名を条件に「少子化で生徒が減る中で、なんとか経営を維持している。よそに資金を貸す余裕などないし、考えたこともない」「公的な支援を受けている学校法人の場合、外部に寄付することにも制限がある。ましてや融資などあり得ないこと」といった答えが返ってきた。
公金を支出する側と受け取る側との間に見られる、この大きな落差。それは吉村県政が今、どのような状態にあるかを示すとともに、県政と吉村一族の企業・法人グループとのいびつな関係を照らし出している。
東海山形学園については、融資問題のほかにも問題がある。十数の企業・法人を率いる吉村和文氏がこの学園の理事長を兼務していることだ。会社経営で多忙な和文氏が高校に顔を出すのは月に数回というのが常態化している。表3にある他の学校法人の場合、理事長は常勤というのがほとんどだ。一つだけ医師が理事長を兼務している法人があるが、和文氏のように数多く兼職しているケースはない。
東海山形学園では、東海大山形高校の阿部吉宏校長が理事を兼ねており、実務的には支障ない、と言うのかもしれない。山内励・元校長や市川昭男・前山形市長も理事に名を連ねている。だが、学校法人を代表する権限を持つのは理事長ただ一人である。その人物が学校にほとんどいない、というのは尋常ではない。
こうした状態をどう考えるか。文部科学省の見解ははっきりしている。公式サイトに「理事機能の強化について」という文書をアップし、「理事長については責任に見合った勤務形態を取り、対内的にも対外的にも責任を果たしていくことが重要と考える。このため、理事長については原則、常勤とするとともに、その職務に専念するためほかの学校法人の理事長等との兼職は避けることが望ましい」という考えを打ち出している。
学校法人をめぐっては、過去に私立大学の不正入試など不祥事が相次いだ。山形県では、出稼ぎ目的の中国人留学生を多数受け入れていた酒田短大が解散を命じられた。2004年に私立学校法が大幅に改正されたのは、こうした不正を防ぐためであり、この文科省の見解も法改正を受けて出されたものだ。
山形県内の学校法人を所管する県学事文書課は、東海山形学園の現状をどのように考えているのか。理事長の常勤化と兼職の制限について指導したことはあるのか。質問書を出したが、いまだに回答がない。
手厚い私学助成に異論はない。ただし、多額の公金を支出するのだから、受け取る学校法人はそれにふさわしいものであって欲しい。非常勤の理事長など論外だ。
*このコラムは、月刊『素晴らしい山形』2019年3月号に寄稿した文を若干手直ししたものです。見出しも異なります。
*追記(3月15日)
2月8日に出した質問書に対して、山形県学事文書課の菅原和彦課長から3月14日付で回答があった。その内容は、学校法人の理事長の常勤化や兼職の制限を期待するとの文部科学事務次官の通知(平成16年7月23日付)を「県内の各学校に対して通知しております」というものだった。わずか8行。15年前に通知を流しただけ、ということのようだ。
≪写真説明とSource≫
東海大山形高校は野球もサッカーも強い(高校野球の2011年秋季東北地区大会、朝日新聞の高校野球サイトから)
https://vk.sportsbull.jp/koshien/localnews/TKY201110110078.html?ref=reca
月刊『論座』2005年4月号掲載「社説の現場から」
「人の生き死に。それを書くのが俺たちの仕事だ」
新聞記者になりたての頃、初任地の静岡で支局長からよくそう諭された。小さな火事や交通事故でも、できるだけ現場に行く。常に自分の目で見て書く。「それが大事だ」と教え込まれた。
おっかない人だった。甘い記事を見逃さなかった。酔眼で「どういうつもりだ」と説教が始まる。酔いが深まるにつれて言葉は激しくなり、「甘ったれんじゃねぇ。死ね! 死んでしまえ!」で終わるのが常だった。こういう上司の下で働くのは、正直言ってしんどい。神経がすり減っていく。けれども、指摘は鋭く、いつも的確だった。新聞記者の仕事をこれほど端的に表現し、追い求めた人に、その後ついぞ巡り合わなかった。

外報部に配属になり、アジア担当になった。ニューデリーとジャカルタに住み、戦争や暴動、騒乱、災害の取材に追われた。「生き死に」へのこだわりを忘れてはいけないと思いつつ、日々流される血があまりにも多く、徐々に鈍感になっていくのを抑えることができなかった。
取材の一線を離れ、社説を書く論説委員になると、現場から遠くなる。ニュースに対する感度が鈍る。それでいて、アジア担当としてのカバー範囲は東南アジアの国々からインドとその周辺、アフガニスタンまでと広大だ。いまひとつ確信が持てないようなことでも、訳知り顔で書かなければならないときもある。論説委員になって4年。「これでいいのか」。自問することが多くなっていた。
スマトラ沖地震は、そんな自問を吹き飛ばすようにやってきた。2004年12月26日、日曜日だった。
論説委員は通常、土日は休む。担当デスク(論説副主幹)のほかには、仕事を抱えた人が数人出てくるだけだ。その日は私も、正月用のひまだね原稿を書くために出社していた。昼過ぎに地震の発生を知ったが、夕方までその原稿を仕上げるのに専念した。緊張感を欠いていた。
ニュースに向き合う編集局はさすがに違った。呼び出しを受けて記者が続々と集まり、殺到する情報をさばいていた。夜、刷り上がった朝刊のゲラを見た。早版は「死者3000人、マグニチュード8.9」。それが最終版では「死者6600人」に膨らんでいた。大災害である。その場ですぐ社説を書くべきだった。が、すでにタイミングを失していた。
一夜明けた月曜日。論説委員室の会議で「即座に対応しなかったことを反省しています」と述べてから、どういう社説を書くかのプレゼンテーションをした。「明日はわが身」とか「教訓をくみ取れ」といった、紋切り型の社説は書きたくなかった。会議で議論をしている間にも、伝えられる死者は万単位で増えていった。阪神大震災も、少し前に起きた新潟県中越地震も大変な災害だが、それらとはスケールの違う、何かとてつもないことが起きたことが分かってきた。
会議では、次の4点を中心に説明した。
(1)地震の規模を示すマグニチュードは9.0に上方修正された。これは、この100年で4番目の大きさだ。阪神大震災の360倍(計算方式によっては1600倍)の規模になる。犠牲者も災害史上に残る数になる可能性がある。(2)解き放たれたエネルギーはものすごい。1000キロ以上離れたインドやスリランカの沿岸まで津波が押し寄せた。「自然が持つ力におののく」という表現を使いたい。(3)これまでの情報から判断すると、もっとも多くの犠牲者が出るのは震源に近いインドネシアのアチェ地方とスリランカ東部だろう。どちらも紛争地で、被災地はもともと疲弊している。救援活動は難航するだろう。(4)インド洋沿岸の国々は貧しい。地震対策はなきに等しい。津波の警報システムなどあるわけもなく、誰もが何も知らされないまま波にのみ込まれた。緊急支援が一段落したら、「地震とは何か」といった基本的なことを知ってもらうための援助ができないものかーー。
これに対し、国際担当のデスク、村松泰雄は「いま起きていることは非常事態だ。将来の対策も大事だが、まずは行方不明者の捜索と被災者の救援に全力を注がなければならない。それをしっかりと書くべきだ」と主張した。専用回線で会議に参加している大阪の論説委員、大峯伸之からは「ぐらりと来たら、何を置いても高台に逃げる。津波対策はそれに尽きる。なのに、日本ですらきちんと教訓化されていない。それを書き込んでほしい」との声が寄せられた。
それぞれ、足りないところを補う意見だった。こうした声を踏まえて、12月28日付で「スマトラ地震 巨大な津波におののく」という社説を書いた。意見を踏まえたつもりだったが、「国際社会としてどう取り組むべきか」という視点が弱かった。そこで、科学担当の論説委員、辻篤子が第2弾の社説「スマトラ地震 史上最大の救援作戦だ」(12月30日付)を執筆した。第二次大戦で連合国軍がノルマンディーに上陸した「史上最大の作戦」を例に引きつつ、今回の災害支援の規模の大きさを指摘し、それが持つ政治的な意味を説いた。
電気も電話もない被災地で、一線の記者はどうやって取材し、原稿を送ったのか。
ジャカルタ支局長の藤谷健は、発生翌日の27日夕にはスマトラ島北部アチェ地方の中心都市、バンダアチェに入った。被災から1週間ほど経ってから、街の真ん中を海が濁流となって流れ、人と車を押し流していく映像が世界に伝えられ、衝撃を与えた、あの街である。バンダアチェの空港は内陸部にあるため、被害を受けなかった。空港に着いたのはいいが、タクシーがいない。ようやく車を見つけて取材し、泥まみれの遺体が折り重なる惨状を原稿にして衛星電話でふき込んだ。
ジャカルタ支局に衛星電話を常備していたこと。電源が長持ちする高性能のパソコンを持っていたこと。市内で唯一、自家発電機が動いていた州知事の公舎にたどり着き、充電できたこと。日頃の準備と機転で、厳しい状況を乗り切った。
泊まるホテルはなかった。地震でつぶれたもの、津波で泥につかったもの。全滅だった。幸い、津波の前の地震の揺れは震度5程度で、津波が押し寄せなかった地域には無傷の建物がたくさん残っていた。民家に転がり込み、ろうそくの明かりで食事を取ったという。

朝日新聞として、取材態勢の面で改善すべき点があったとするなら、初期の段階で被害と取材人員の釣り合いが取れていなかったことだろう。震源に近いアチェ地方は、沿岸部が幅数キロにわたって壊滅的な打撃を受けた。電話局もテレビ局も被災して機能しなくなった。被害を外部に向かって報告、発信する手段がすべて失われた。紛争地のため、もともと外国人は立ち入りが規制されている。津波の前にはメディアもなかなか入れなかった。「衝撃的な映像」が外部に伝わるまで1週間もかかったのには、こうした事情があった。
一方、タイ南部のプーケット島の被害は、海辺の幅数百メートルほどに限られていた。その奥は無事だったので、大波が打ち寄せる映像がすぐ世界に伝えられた。しかも、欧米や日本からの旅行者で犠牲になった人が多かった。スリランカやインドの被害も、インドネシアよりはずっと早く伝わった。このため、応援の取材陣はまず、タイやスリランカ、インドなどに向かった。朝日新聞の場合も、当初は「アチェには記者が1人しかいないのに、タイ南部には記者とカメラマンが6人もいる」という態勢が続いた。
「インド洋全域で死者と行方不明者は約30万人(*)。その8割はアチェ」という被災の全体状況が分かったのはだいぶ経ってからであり、初動段階での取材態勢のアンバランスを問うのは酷かもしれない。ただ、日本のテレビ各局は、日本人犠牲者の報道にエネルギーの大部分を使い、この大津波による被害の全体像を伝えようとする気概を欠いていた。東京で取材の指揮を執る人たちに少なからぬ影響を与え、新聞の報道もこれに引きずられた面があったように思う。英国のBBCは、早い段階からアチェ地方とインドのアンダマン・ニコバル諸島に複数の取材チームを送り込み、果敢な報道をしていた。大災害の全体像に迫ろうとする気迫を感じた。
地震でも津波でも、震源に近い所が一番大きな被害を受ける。初期の段階で被害が伝わらないとしたら、そこには別の理由があるはずだ。想像力を働かせなくてはならないーーそれが今回の地震と大津波の報道での教訓の一つだろう。
話を「社説の現場」に戻す。
年が明けてから、朝日新聞は「アジアの力が試される スマトラ沖大地震」(1月5日付)、「津波サミット 競い合い、支え合え」(1月7日付)という社説を掲げた。前者は、通常2本の社説が掲載される欄を全部使った、いわゆる「一本社説」である。憲法問題やイラク戦争の重大な局面、ブッシュ大統領の再選といった節目に、十分なスペースを使って朝日新聞としての基本的なスタンスを打ち出すために載せる社説だ。
一つの災害のために、これだけ多くの国々が軍隊や医療チームを派遣して救援にあたったことはない。小泉首相やパウエル米国務長官(当時)、中国の温家宝首相、国連のアナン事務総長らがジャカルタに集まり、被災者の支援策を話し合う。これも異例のことだ。論説委員室の会議で「一本社説で論ずるべきだ」との声が出され、そう決した。
米国は、今回の津波でアチェに1万4000人の兵力と空母部隊を投入した。多数のヘリコプターを使っての支援活動は水際立っていた。オーストラリアも輸送艦でブルドーザーやショベルカーといった重機を大量に持ち込み、がれきの除去などで貢献した。
だが、インドネシア側は「米国はイラク戦争で高まったイスラム圏の反米感情を和らげようとしている」と斜に構えている。過去に東ティモール独立をめぐって対立したオーストラリアに対しては「次はアチェへの影響力を確保しようとしているのではないか」と疑っている。
迅速さや機動力という点では、日本やアジア諸国の支援は米豪両国に到底、及ばない。だが、インドネシアとの間で摩擦が生じる恐れは少ない。息の長い支援を旗印にして、日本が復旧と復興のイニシアチブを取ることは可能だし、取るべきだーーそれが一本社説の眼目だった。
被災地からの報道を受ける形で、論説としてもそれなりに書いたつもりだが、不満があった。現場を自分の目で見ていないことだ。新潟県中越地震では論説委員も次々に現地入りし、余震に揺られながら社説を書いた。それを思えば、これだけの大災害で現場取材をしないわけにはいかないだろう。議論の末、アジア担当と地震担当の論説委員が順次、被災地を訪ねることになった。
大津波については、すでに膨大な量の報道がなされていたが、私は「まだまだ空白域がある」と感じていた。新聞の小さな地図で見ると、アチェ地方は小さく見えるが、実は九州の1・3倍もある。西海岸は約500キロ。東京?京都間に等しい。この長い海岸線がどうなっているのか、あまり報じられていない。気になっていた。バンダアチェより震源に近く、大津波を正面から受ける位置にあるからだ。
1月下旬にアチェを訪ね、米軍の支援ヘリに同乗して空から海岸線を200キロほど見た。呆然とした。海沿いの地域がごっそり削り取られたようになり、町や村が消えていた。がれきすら、あまり残っていない。これでは映像で伝えにくい。あっさりしすぎて、悲惨さが伝わらないのだ。
ちょうど同じ時期に、東大地震研究所の都司嘉宣(つじ・よしのぶ)助教授が現地調査に来ていた。「バンダアチェより西海岸の方が被害は深刻なのではないか」と聞いてみた。「たぶん、そうでしょう。高さ30メートルくらいの津波があちこちに押し寄せたのではないか」と言う。その光景を想像すると、絶句するしかなかった。
映像ではうまく伝えられないーーそういうところにこそ、新聞記者が入り込み、じっくりと取材して報道すべきだ。映像が力を持つようなフィールドでテレビと競争しても、活字メディアが勝てるわけはないのだから。
アチェでの取材であきれたのは、復旧の見通しすら立っていないのに、インドネシア政府が「外国軍の早期撤退」を言い続けていたことだ。米豪両国軍がいることにわだかまりがあることは理解できる。しかし、今はそんなことを言っているときではあるまい。怒りを感じた。アチェから衛星電話で「アチェ報告 国の威信より人の命だ」と題した社説を送った(1月31日付で掲載)。
インドネシアでの取材を終えて、タイ南部に回った。プーケット島より、その北のパンガー県の方が被害はひどいという。訪ねると、内陸深くまで津波が達している地区があった。カオラックという。専門家によれば、浜が遠浅なうえに北側に岬が突き出しているため、津波のエネルギーを丸ごと受けてしまったとのことだった。
ここにも「取材の空白域」があった。この辺りには、ミャンマー(ビルマ)からの出稼ぎ労働者が多数いた。犠牲者もかなりいたはずなのだが、彼らは住所を登録しているわけではない。確認のしようがないのだ。
白い砂浜には波が穏やかに打ち寄せていた。その海のかなたには、インドのアンダマン・ニコバル諸島があり、ミャンマーの島々が横たわっている。これらの島々の被災状況も実はよく分かっていない。インドは同諸島が軍事的に重要な意味を持つため、外国人の立ち入りを快く思っていない。ミャンマーの軍事政権は、そもそも外国人ジャーナリストを国内に入れようとしない。
社説で「息の長い支援を」と何度も書いた。当然、メディアとしても「息の長い報道」をしなければならない。一線の取材も、論説の取材も、まだまだ終わらない。
(長岡 昇 ・朝日新聞論説委員)
*この記事は、朝日新聞社発行の月刊『論座』2005年4月号に次のタイトルで掲載された。
「社説の現場から」 まだまだ「報道の空白域」がある スマトラ沖地震と大津波
*その後の調査によれば、死者と行方不明者は約22万人と推定される。この地震は「スマトラ沖地震」あるいは「スマトラ島地震」などと表現されたが、メディアでは「インド洋大津波」の呼称が定着した。
≪写真説明≫
1 陸に打ち上げられた貨物船。この辺りには高さ30メートルを超える津波が押し寄せた
=スマトラ島北部のロックガで(1月29日、筆者撮影)
2 スマトラ島アチェの西海岸。道路は寸断され、この先は車で行くことはできない(同)
ながおか・のぼる 1953年生まれ。東京大学法学部卒。1977年、東芝入社。78年、朝日新聞入社。静岡支局、横浜支局、東京本社整理部、北海道報道部を経て外報部に。ニューデリー支局長、外報部次長、ジャカルタ支局長を務め、2001年から現職。
メールマガジン「風切通信 52」 2019年1月30日
時に逆行することはあっても、歴史はより自由で、より公平で、より開かれた社会に向かって動いている。自由は「法の支配」を確立することによって広がり、公平さは普通選挙の実現や農地の解放によってもたらされた。そして、次の「開かれた社会」を実現するために生み出されたのが情報公開制度である。

北欧生まれのこの制度を日本で初めて導入したのは山形県の金山町である。1982年に金山町情報公開条例を制定し、翌83年に神奈川県と埼玉県がこれに続いた。国が情報公開法を施行したのは2001年、19年後のことだ。「開かれた社会」への挑戦は、日本では地方から始まったのである。
吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業・法人グループは山形県や山形市からどのような形で公金を受け取っているのか。その実態を解明するうえで、情報公開制度は抜群の威力を発揮する。その好例が今回お伝えする「山形県による観光キャンペーンの業務委託問題」である。
吉村知事の2期目、2014年にJRグループは「山形デスティネーションキャンペーン(DC)」という大規模な誘客事業を展開した。メインテーマは「山形日和。」。豊かな自然と食、温かい人情を多様なメディアを駆使してアピールし、より多くの観光客を惹(ひ)きつけようとした。
山形県は、これに連動する形で「山形DC関連県内周遊促進事業」という新しいプロジェクトを立案した。県民向けに県内の観光地を訪れるよう促すキャンペーンを繰り広げることにしたのである。もちろん、県職員が直接こうした誘客事業を行うわけではなく、業務は3500万円の予算内で民間企業に委託することにした。
事業を担当したのは商工労働観光部の観光交流課である。業務委託は公募ではなく、指名型プロポーザル方式という独特な方法で行われた。県側が業務を引き受けてくれそうな企業5社を選定・指名し、各社に企画案を出してもらい、審査して決める方法だ。建築物の設計などでよく使われる手法で、業界では「コンペ方式」と呼ばれる。
選ばれたのはケーブルテレビ山形と県内の民放4社(YBC、YTS、TUY、さくらんぼテレビ)である。県民向けにどのようなキャンペーンを展開することを期待していたのか。情報開示された県内周遊促進事業の基本仕様書によると、委託する業務の主な内容は次のようなものだった。
(1)県民に県内周遊を促すテレビCMを4種類以上制作し、県内のテレビ2局以上で延べ240回以上流す(2)県内周遊を促す3分程度のテレビ情報番組を制作し、県内のテレビ2局以上で延べ24回以上放送する(3)二つ以上の新聞、二つ以上の雑誌などに周遊を促す広告を掲載する(4)テレビで放送した内容と関連する内容をウェブサイトにも掲載する(5)リーフレットなどのPR資料を作成する(6)これらの映像媒体、印刷媒体を組み合わせて展開する(7)効果的なPRイベントを1回以上開催する。
観光交流課は2014年2月24日、この仕様書を含む文書を5社に郵送し、企画書を出すよう促した。提出の締め切りは3月10日。当時、この文書を受け取った民放テレビの担当者は一読して、「何だ、これは」と驚いたという。企画のメニューが多岐にわたり難しい内容なのに、締め切りまでわずか2週間しかなかったからだ。
それ以上に問題だったのが仕様書の第2項目だ。「情報番組を作って県内の2局以上で放送する」という内容に目をむいた。民放テレビが自ら番組を制作した場合、それを系列が異なる県内の他のテレビ局で放送することはあり得ない。つまり、仕様書には「民放テレビにはできないこと」が盛り込まれていたのである。
当然のことながら、民放4社は企画書を出すことができず、ケーブルテレビ山形だけが締め切りまでに提出した。県の内規によれば、1社だけを対象にして審査会を開いて決めることも許される。開示された審査結果に関する文書には「5社のうち1社応募、4社辞退」と記され、審査の結果、「ケーブルテレビ山形が最上位に決定された」と書いてある。
民放各社には達成できない条件を設定したうえで企画書の提案を促し、「4社辞退」と表現する。さらに、審査の対象は1社だけだったのに、臆面もなく、審査の結果、「ケーブルテレビ山形が最上位に決定された」と記す、この破廉恥さ。民放の担当者の中には県庁まで出向いて抗議した者もいたが、「手続きは適正」という言葉が返ってきただけだったという。
そもそも、県民に県内を旅行するよう促すために3500万円も費やす必要があったのか。素朴な疑問を抱いて、この事業の予算査定に関する公文書の開示を求めた。すると、さらに興味深い事実が浮かび上がってきた。
予算配分の権限を持つ財政課は当初、この事業の必要性を認めず、観光交流課の予算要求を撥(は)ねつけていたのだ。表1にあるように、課長レベルの折衝ではゼロ査定。部長折衝でもゼロ回答をしたうえで、「事業のロードマップだけが示され、具体的なイメージができるものがなければ、議論さえできない」と突き放した。
ところが、財政課が「議論さえできない」と酷評した事業の予算は、最後の知事による折衝で満額復活した。2014年度の予算編成で「知事復活」の対象になった事業は7件あったという。山形DC関連県内周遊促進事業はその一つになった。どのような理由で復活したのか。文書はなく、不明である。
翌2015年度から、この県内周遊促進事業は公募方式になり、県のホームページに企画募集のお知らせがアップされるようになったが、その後もケーブルテレビ山形(2016年にダイバーシティメディアに社名変更)が受託し続けている(表2)。途中から「コンソーシアム(共同企業体)」に加わった山形アドビューロと山形コミュニティデータセンターは、山形新聞グループの会社である。
県内の広告業界では「あの事業はヒモ付き。応募しても無駄」との見方が広がった。応募する会社がなくなることを恐れたのか、観光交流課(2016年に観光立県推進課に改称)から「企画を出しませんか」と誘いを受けた広告会社もあると聞いた。
とはいえ、どの業界にも一匹狼のような会社はある。今年度はダイバーシティメディアを中心とする共同企業体とシー・キャドに加え、エーディーバンクという会社が事情を知らずに応募した。表3は今年度の「重点テーマPR誘客促進事業(近県向け)」の審査結果である。
審査員は外部の有識者2人と主管する観光立県推進課長の3人。関連する文書と照らし合わせると、審査員AとBが外部有識者、Cが課長と考えていい。AとBの点数を合計すると、ダイバーシティメディアを中心とする共同企業体の企画案(提案2)は、エーディーバンクの企画案(提案3)にかなり差をつけられていた。
ところが、C(課長)が前者に最高点、後者に低い点数を付けたため、3人の合計では形勢が逆転し、業務の委託先は共同企業体に決まった。吉村県政の下で幹部がどのように振る舞っているのか。それを象徴する結末である。
一連の業務委託で、ダイバーシティメディアと同社を核とする共同企業体に支出された公金は1億2000万円を超える。その出発点となったのは2014年度の業務委託である。観光交流課長としてこの仕事を仕切った武田啓子氏はその後、村山総合支庁の保健福祉環境部長、本庁の健康福祉部長とトントン拍子で出世し、昨春、観光文化スポーツ部長に上り詰めた。
民放4社を指名しておきながら民放テレビには達成できない条件を付け、ケーブルテレビ山形しか応募できないような事業を推し進めたことをどう考えているのか。面会を求めたが、武田氏は応じない。課員に質問書を託したが、回答はなかった(*2)。
「資産隠しではないか」との質問に答えない吉村知事と同じく、武田氏も黙してやり過ごす気のようだ。山形県庁には、公務員として堅く守るべき公平さをかなぐり捨て、それを恬(てん)として恥じない人たちがいる。
*1 この文章は、月刊『素晴らしい山形』2019年2月号に寄稿したものを若干手直しして転載したものです(表1、表2、表3をクリックすると、内容が表示されます)。
*2 『素晴らしい山形』2月号の締め切り後、武田啓子氏から「平成26年度山形DC関連県内周遊促進事業に係る業務委託につきましては、地方自治法等に基づき適正に行っております」との回答が届いた。寄稿文で指摘した問題についての釈明はなかった。
≪写真説明とSource≫
山形への旅にいざなうJRグループのポスター。レトロな雰囲気が人気の銀山温泉(日本観光振興協会のサイトから)
https://www.kankou-poster.com/66vote_result/63vote_result/63nyuusho/15-%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3.html
メールマガジン「風切通信 51」 2018年12月26日
1期目の知事や市長は強い、というのが選挙の常識である。現職が再選を目指して敗れることは滅多にない。だが、2009年1月の山形県知事選挙ではその稀有(けう)なことが起きた。1万票の僅差ながら、新顔の吉村美栄子氏が現職の斎藤弘氏を破ったのである。東北初の女性知事誕生。鮮烈なデビューだった。

当時の麻生太郎首相の不人気、山形県の保守勢力の分裂、野党共闘の巧みさといったことに加えて、吉村陣営のキャッチフレーズ「冷(つ)ったい県政から温かい県政に」が効いた。元銀行マンの斎藤氏は財政再建を旗印に公共事業や福祉の予算をバサバサ削った。その容赦のなさに、多くの県民は凍えていたのである。
斎藤氏の日ごろの言動も、人々の心を萎(な)えさせた。知事室に陣取り、あまり人に会おうとしない。また、会った人に聞いても「こっちの話に耳を傾けようとしなかった」という。この人は、知事になったその日から、毎日、票を減らすような振る舞いをしてきたのだろう。行政運営の冷たさにも増して、人柄への嫌気が敗北の大きな原因だったのではないか。
吉村美栄子氏が知事に就任したのは2月14日である。新しい知事はよく人の話を聞いた。土砂崩れがあれば、すぐに現場に駆け付けた。前任者との落差は大きく、人気は日増しに高まった。だが、順風満帆の帆には、すでに小さなほころびが生じていた。
就任から5カ月後、吉村知事は条例に基づいて自らの資産を公開した。表1の通り、土地や建物、預貯金や国債など総額1億598万円。「普通の主婦から県知事に、と報道されたりしたけど、ちょっと違うね」と感じた県民は少なくない。この条例は、国会議員の資産公開法に基づいて制定されたもので、もともと抜け穴が多い。不動産は固定資産税の課税標準額で報告すればよく、実勢価格とはかけ離れている。預貯金も普通口座の分は含まれない。株式に至っては銘柄と株数を公表すればいいことになっている。
株取引に詳しい知人によれば、東京海上ホールディングスの2009年1月5日の始値(はじめね)は1株2650円なので、これで計算すれば計437万円になる。ケーブルテレビ山形の株は非公開だが、1株の額面は5万円なので単純計算すれば200万円になる。鉄鋼関係の貿易会社、首長国際(香港)の株価は安く、2万株でも6万円ほどである(2018年11月末の株価で計算)。安徽海螺水泥股分は2000株で 100万円ほど。羅欣薬業は非公開なので資産 価値は不明だ。
これらの株式と不動産の実勢価格との差額を加えれば、吉村知事の資産は公表されたものよりはるかに多いが、私が「小さなほころび」と呼ぶのはそのことではない。ケーブルテレビ山形の株を保有していたこと、そして、それだけでなく、その後、この株を「手放した」ように装っていること。それが問題なのだ。
山形県庁が実施する入札に参加する企業は数多くある。その中で、発注者である知事がたった1社、ケーブルテレビ山形の株式を持っているのは「入札の公平性の確保」という観点から好ましくない。資産公開は知事に就任した2月14日時点の資産を明らかにすることになっている。厳しい選挙の直後で、そうしたことまで配慮が行き届かなかったのかもしれない。だから、その時点で保有していたことを批判しようとは思わない。
問題はその後だ。先月号で私は「(知事はこの株を)ほどなく手放している」と書いたが、ケーブルテレビ山形の「株主名簿」にあらためて目を通してみると、なんと知事と同居している長男の名前があるではないか。長男を直撃すると、彼は「会社から書類が送られてきている」と述べ、株を保有していることを認めた。
すべての年度の株主名簿が入手できているわけではないので断言はできないが、問題の40株は資産公開の前後に吉村知事から長男に譲渡された疑いが濃厚である。息子に株を譲って「私は持っていません」と言っても、有権者の多くは納得しないだろう。いつ、株を譲ったのか。知事あての質問書を秘書課長に託したが、回答は得られていない。
「法律にも条例にも違反していない。回答する必要はない」と言いたいのかもしれない。確かに、違反してはいない。だが、知事に資産公開を義務付けている条例の正式な名称は「政治倫理の確立のための山形県知事の資産等の公開に関する条例」である。政治倫理、さらには人としての道義という観点から見れば、大いに問題がある。
政治家の資産公開問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之(かみわき・ひろし)教授は「資産を隠すために配偶者や子どもに譲った形にしてごまかすケースが後を絶たない。同居の親族や扶養する親族の資産も公開の対象にすべきだ」と提唱している。
こうした批判にさらされて、政府は2001年1月に「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」を閣議決定し、閣僚や副大臣、政務官については「配偶者及びその扶養する子の資産も公開する」と決めた。許認可権限の大きさを考えれば、都道府県知事についても資産公開の対象を広げるのは当然であり、同居の親族の資産も公開の対象にすべきだろう。
吉村知事は昨秋、県政運営の透明性を高めるため、有識者を集めて「情報公開・提供の検証見直し第三者委員会」(通称・見える化委員会)を立ち上げた。委員会は審議を重ね、この秋に「公文書は原則として公開する。非公開は必要最小限にとどめるべきだ」といった提言・報告書をまとめた。時代は、より一層の情報公開を求めている。なのに、知事は自分や身内のことになると「見えない化」にいそしむ。
そうした姿勢は、山形県の情報通信技術(ICT)政策にどのような形で現れてくるか。表2は、吉村美栄子氏が知事になった2009年以降の「山形県情報化推進懇話会」の年度ごとのメンバー一覧である。情報技術を県政にどのように活かしていくのか。外部の有識者を集めて助言を求め、県の計画に反映させることを目的にしている。2018年から「山形県ICT政策推進懇談会」と名前を変えた。
懇話会や懇談会には毎回、県の情報技術政策を担当する部長や課長、課長補佐が出席する。委員には「山形県ICT推進方針(仮称)中間報告(案)」や「今年度のICT関連事業一覧」といった資料が配布される。県の担当者との人脈を築き、県の大まかな方針と事業の概略を知ることができる。私がこの分野の営業担当者なら「お金を払ってでも入れてほしい」と思う集まりである。
会のメンバーは毎回、少しずつ入れ替わっている。社長や支店長の交代があるからだが、この10年間、ずっと委員を務めている人物がいる。ケーブルテレビ山形(現ダイバーシティメディア)の吉村和文氏である。知事が直接、指名したのか。それとも、担当部局が忖度(そんたく)して入れたのか。判然としないが、知事の義理のいとこだけがたった一人、座り続けているのは異様と言うほかない。
先月号で、吉村和文氏が代表取締役社長あるいは理事長として率いる企業や法人は確認できただけで六つある、と書いたが、和文氏のブログ「約束の地へ」のプロフィールによれば、彼は「現在、15の会社経営を担っている」という。残りの九つがどれなのか、いずれはっきりさせたい。
グループ企業の法人登記を見ると、所在地はダイバーシティメディアの本社がある「山形市あこや町一丁目2ー4」となっている会社が多い。取締役にしても、同じ人物が何度も顔を出す。従業員もいくつかの会社の仕事を掛け持ちしているのだろう。新しい仕事を始めるたびに新しい会社を立ち上げている、という印象だ。こうした手法にどういうメリットがあるのか。それも解明したい。
これまで調べた限りでは、吉村一族の企業・法人グループには、主に次の分野で公金が支出されている。(1)ケーブルテレビの施設整備(2)情報通信技術分野(ハード&ソフト)(3)映画など映像メディア分野(4)観光キャンペーン・広告分野(5)教育や福祉などの公益事業、の五つである。いくつか重なるケースもある。
これらを一つひとつ丁寧に腑分けしていけば、山形県庁や山形市役所の周りで何が起きているのか、おぼろげながら見えてくるだろう。
*この記事は、地域月刊誌『素晴らしい山形』2019年1月号に寄稿したものを若干手直しして転載したものです(表1、表2をクリックすると、内容が表示されます)。
≪写真説明とSource≫
山形県知事選挙から一夜明け、自宅で新聞を手にしながら取材に応じる吉村美栄子氏(2009年1月26日、山形市内で)=時事通信社
http://junskyblog.blog.fc2.com/blog-entry-1206.html
*メールマガジン「風切通信 50」 2018年12月2日
権力は水に似ている。澄んだ水も同じところにとどまれば、やがて濁っていくように、権力もまた、同じ人間が握り続ければ、いつしか澱(よど)んでいく。それは、洋の東西を問わず、時代を経ても変わらない。

月刊誌『素晴らしい山形』は2年前の秋から、吉村美栄子・山形県知事の義理のいとこ、吉村和文氏が率いる企業グループがらみの様々な問題を報じてきた。それらの問題の多くには、何らかの形で吉村知事の存在が影を落としている。吉村県政の誕生から間もなく10年。私たちが暮らす山形でも、権力の周りに「澱み」が生じ始めている、と見るべきだろう。
いったい、何が起きているのか。地域おこしの小さなNPOを主宰する者として、また一人の納税者として、このまま見過ごすわけにはいかない。山形県の情報公開制度を利用して公文書を入手し、関係者に教えを請いながら独自に調査を進めてきた。その結果を中間報告の形でお伝えしたい。
まず、吉村和文氏が代表取締役社長を務めるケーブルテレビ山形(2016年にダイバーシティメディアに社名変更)のパソコン入札問題から取り上げる。山形県庁で職員が使うパソコンは数万台に上り、県は古いものから順次、廃棄処分にして、入札にかけて新製品を調達する。一覧表(表1)は、吉村美栄子氏が知事に就任した2009年以降の入札結果である。
県の入札公告や入札調書によると、この9年間に12回の入札があり、そのうちの6回はケーブルテレビ山形が落札に成功した。入札価格ベースで見ると、総額5億154万円(千円以下切り捨て)のうち、2億2748万円(同)と半分近くを受注している。物品購入契約の際には、これに消費税を加えた金額が県から支払われる。ケーブルテレビ山形が落札、納入したパソコンはすべてNEC製である。残りは東芝製品を扱う管理システム(本社・酒田市)と富士通製品を扱うリコージャパン(本社・東京都港区)、NEC製品を扱うメコム(本社・山形市)が落札した。
パソコン機器の販売・流通事情を知る人間ならば、この落札結果を見て「ケーブルテレビ会社がなぜ、次々に落札に成功するのか」と疑問を抱く。『素晴らしい山形』でも報じられたように、この会社の主な業務はケーブルテレビ網の整備と顧客へのテレビ放送の提供である。会社の法人登記を見ても、事業目的の欄に「パソコン機器の販売」に関わる記述はまったくない。吉村県政が誕生する前、2008年度のパソコン調達に関する文書にも、ケーブルテレビ山形は登場しない。
「この会社はそもそも、入札参加資格を満たしていたのか」との疑問を抱き、県に対してそれ以前の入札調書の公開を求めた。県の財務規則によれば、入札に参加するためには「1年以上前からパソコンの販売をしている」という実績が必要になるからだが、「2007年度以前の入札調書は文書の保存期限が過ぎており、存在しない」との理由で、入手できなかった。
やむなく、ダイバーシティメディアに文書で問い合わせたところ、「平成14年(2002年)以降、山形県に対して販売実績はあります」との返答があった。入札参加資格に関しては別途、公文書でも問題がないことを確認した。しかし、それにしてもなぜ、吉村美栄子氏が知事になった途端、パソコン販売を得意とする企業を打ち破ってこの会社が次々に落札することができたのか。疑問は消えない。
その疑問は、ケーブルテレビ山形の生い立ちを知れば、いっそう募る。この会社は、ケーブルテレビ網を全国に広げることを目指して総務省が推進した「電気通信格差是正事業」の補助金受け皿会社として1992年に設立された。吉村和文氏はメディアのインタビューに「50社から200万円ずつ出資を得て資本金1億円を集め、起業した」と語り、普通の民間企業のように述べているが、これは誤った印象を与える発言である。
この事業の「補助金交付要綱」には、「都道府県、市町村又は第三セクター等」に対して補助金を出す、と明記されており、最初から地方自治体の出資も前提にした「第三セクター」を事業の対象にしていたからである。実際、起業後にケーブルテレビ山形が増資した際、山形県は1997年に360万円、2001年に840万円、計1200万円の出資をした。県は、各社の当初の出資額200万円の6倍の資金を投入しているのである。
山形県が出資して第三セクターとしての体裁が整うと、ケーブルテレビ山形に巨額の補助金が流れ込み始める。事業費の半分は会社が用意し、残りの半分を国と県、市町(山形市と天童市など)が補助金として交付する仕組みだ。国から4分の1、県と市町からそれぞれ8分の1が交付される。1998年度から2003年度までに交付された補助金の内訳は表2の通りで、この期間だけで総額2億2239万円に上る。
巨費が投入され、山形市や天童市などにケーブルテレビ網が敷設されてサービスは徐々に広がっていった。当初はケーブルテレビの業績も順調だった。だが、衛星テレビの内容が充実し、家庭用のパソコンやスマートフォンが普及するにつれて、ケーブルテレビの普及は先細りになっていく。経営の先行きを危ぶんで、ケーブルテレビ山形は事業の多角化に乗り出し、その一環としてパソコン機器の販売を始めたと見られる。慣れない分野で苦労したはずである。なのに、2009年以降のこの躍進ぶり。なぜなのか。システム構築などソフトウェア分野の入札にも視線を向けて、その背景をさらに探りたい。
吉村美栄子氏は知事に就任した2009年に条例に基づいて、個人資産を公開した。その中に「保有株式」に関する項目があった。その内訳は表3の通りである。なんと、ケーブルテレビ山形の株主だった。知事は記者会見で 「ほとんど亡き夫が残してくれたもの」と語ったが、さすがに「好ましくない」と考えたのか、この株はほどなく手放している。
吉村美栄子氏が46歳の時、夫は病で没した。弁護士だった夫の和彦氏と吉村和文氏は父親同士が兄弟という間柄だ。和彦氏の父は元県出納長、和文氏の父は元山形市長で、山形では著名な一族である。夫が亡くなった後も親戚付き合いは続く。和文氏のブログ「約束の地へ」には、知事と和文氏が居間で談笑する写真がアップされている(2016年1月10日付、撮影は2015年夏)。
義理のいとこ同士なのだから、仲良く付き合うのは自然なことである。問題は、片方が県知事という立場にあり、もう一方の和文氏が「補助金の受け皿会社」を足場にして次々に新しい会社を立ち上げ、県や山形市から多額の補助金や助成金を受け取り続けていることにある。そこに情実が入り込む余地はないのか。厳しく問われなければならない。
吉村和文氏が代表取締役社長や理事長として率いる企業や法人は、表4のように確認できただけで六つもある。これらの企業と法人に共通しているのは、いずれも公金が注ぎ込まれている点だ。吉村ファミリーの企業や法人(この表にない社会福祉法人や公益社団法人を含む)で「国や自治体との接点があまりない」と言えるものは、今のところ見当たらない。
では、ほかの企業や法人はどのような問題を抱えているのか。次回以降、ケーブルテレビ山形にまつわる問題に加えて、そうした疑問にも触れていきたい。
≪写真説明とSource≫
吉村美栄子・山形県知事
http://tohoku-genki.com/1339
*このコラムは、山形の月刊誌『素晴らしい山形』の2018年12月号に寄稿した文を若干手直しして転載したものです。
第6回カヌー探訪は7月28日(土)と29日(日)の両日、開催しました。連日の猛暑で最上川の水位はかつてないほど下がり、渇水状態でのカヌー行になりました。このため、28日は予定していた朝日町雪谷から大江町「おしんの筏下りロケ地」までの15キロを短縮し、朝日町雪谷から朝日町栗木沢のカヌーランド(タンの瀬)までの8キロで行いました。天候は晴れ、参加者は22人(18艇)でした。28日の夜は昨年同様、尾花沢市の名木沢公民館で参加者と「ブナの森」のメンバー計11人で懇親会を開き、カヌー談義に興じました。


◎真鍋賢一さん撮影の動画と写真(1日目)
◎真鍋賢一さん撮影の動画と写真(2日目)
2日目の29日(日)は予定通り、尾花沢市の猿羽根(さばね)大橋から新庄市の本合海(もとあいかい)大橋まで20キロを下りました。晴れ時々薄曇り、強い追い風の中でのカヌー行に20人(17艇)が参加し、穏やかな最上川の川下りを楽しみました。

≪参加者数≫
26人:山形県内13人、県外13人(群馬5人、秋田2人、栃木2人、東京・千葉・埼玉・福島が各1人)。1日目の参加者は22人(18艇)、2日目は20人(17艇)

≪日程別の参加者≫
【28日の朝日町雪谷ー朝日町栗木沢 8キロ】22人(18艇=3人乗りが1艇、2人乗りが2艇)。28日のみ参加が6人、28日と29日参加が16人
渡辺不二雄(山形市)、三浦優美子(山形県鶴岡市)、池田剛(山形県尾花沢市)、柏倉稔(山形県大江町)、原竜司(山形県尾花沢市)、大類晋(同)崔鍾八(山形県朝日町)、清野由奈(同)、岸浩(福島市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、真鍋史子(同)、佐藤守孝(千葉県松戸市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、林和明(東京都足立区)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、佐竹久(山形県大江町)、齋藤純一(群馬県伊勢崎市)、宮坂岳宏(秋田県由利本荘市)、塚本雅俊(群馬県前橋市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)



【29日の尾花沢市・猿羽根大橋ー新庄市・本合海大橋 20キロ】20人(17艇=2人乗りが3艇)。28日と29日参加が16人、29日のみ参加が4人
崔鍾八(山形県朝日町)、清野由奈(同)、岸浩(福島市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、真鍋史子(同)、佐藤守孝(千葉県松戸市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、林和明(東京都足立区)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、佐竹久(山形県大江町)、齋藤純一(群馬県伊勢崎市)、宮坂岳宏(秋田県由利本荘市)、塚本雅俊(群馬県前橋市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、永嶋英明(山形県鶴岡市)、佐藤真一郎(秋田県潟上市)、伊藤信生(山形県酒田市)、池田丈人(同)



≪過去の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人
*2013年は山形を襲った7月豪雨のため中止、
2017年は直前の大雨のため1日目のみの川下りに変更


≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇▽長岡佳子
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽佐久間淳
≪昼食のデザート、漬物提供≫ 斉藤栄司▽安藤昭郎▽佐竹恵子

≪出発、到着時刻≫
▽1日目(7月28日)
9:50 朝日町の雪谷カヌー公園を出発
12:50 朝日町栗木沢のカヌーランド(タンの瀬)に到着、昼食
*渇水でコースを短縮して時間的な余裕があったため、途中で川遊びを堪能
*夕方、参加者11人は尾花沢市の名木沢公民館で懇談
▽2日目(7月30日)
9:30 尾花沢市の猿羽根大橋を出発
12:45 大蔵村の烏川(からすがわ)公民館で昼食、休憩
15:00 新庄市の本合海大橋に到着
≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、大江町、尾花沢市、舟形町、大蔵村、新庄市、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 朝日町雪谷区長、鈴木進▽尾花沢市名木沢区長、阿部良一▽大蔵村赤松区長、八鍬茂▽新庄市本合海地区、八向尚
≪ウェブサイト更新≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、長嶋広海)
≪ポスター、Tシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell 保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝


◎真鍋賢一さん撮影の動画と写真(1日目)
◎真鍋賢一さん撮影の動画と写真(2日目)
2日目の29日(日)は予定通り、尾花沢市の猿羽根(さばね)大橋から新庄市の本合海(もとあいかい)大橋まで20キロを下りました。晴れ時々薄曇り、強い追い風の中でのカヌー行に20人(17艇)が参加し、穏やかな最上川の川下りを楽しみました。

≪参加者数≫
26人:山形県内13人、県外13人(群馬5人、秋田2人、栃木2人、東京・千葉・埼玉・福島が各1人)。1日目の参加者は22人(18艇)、2日目は20人(17艇)

≪日程別の参加者≫
【28日の朝日町雪谷ー朝日町栗木沢 8キロ】22人(18艇=3人乗りが1艇、2人乗りが2艇)。28日のみ参加が6人、28日と29日参加が16人
渡辺不二雄(山形市)、三浦優美子(山形県鶴岡市)、池田剛(山形県尾花沢市)、柏倉稔(山形県大江町)、原竜司(山形県尾花沢市)、大類晋(同)崔鍾八(山形県朝日町)、清野由奈(同)、岸浩(福島市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、真鍋史子(同)、佐藤守孝(千葉県松戸市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、林和明(東京都足立区)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、佐竹久(山形県大江町)、齋藤純一(群馬県伊勢崎市)、宮坂岳宏(秋田県由利本荘市)、塚本雅俊(群馬県前橋市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)



【29日の尾花沢市・猿羽根大橋ー新庄市・本合海大橋 20キロ】20人(17艇=2人乗りが3艇)。28日と29日参加が16人、29日のみ参加が4人
崔鍾八(山形県朝日町)、清野由奈(同)、岸浩(福島市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、真鍋史子(同)、佐藤守孝(千葉県松戸市)、池田信一郎(埼玉県狭山市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、林和明(東京都足立区)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、佐竹久(山形県大江町)、齋藤純一(群馬県伊勢崎市)、宮坂岳宏(秋田県由利本荘市)、塚本雅俊(群馬県前橋市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、永嶋英明(山形県鶴岡市)、佐藤真一郎(秋田県潟上市)、伊藤信生(山形県酒田市)、池田丈人(同)



≪過去の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、
第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人
*2013年は山形を襲った7月豪雨のため中止、
2017年は直前の大雨のため1日目のみの川下りに変更


≪陸上サポート≫ 安藤昭郎▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡典己▽長岡昇▽長岡佳子
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽佐久間淳
≪昼食のデザート、漬物提供≫ 斉藤栄司▽安藤昭郎▽佐竹恵子

≪出発、到着時刻≫
▽1日目(7月28日)
9:50 朝日町の雪谷カヌー公園を出発
12:50 朝日町栗木沢のカヌーランド(タンの瀬)に到着、昼食
*渇水でコースを短縮して時間的な余裕があったため、途中で川遊びを堪能
*夕方、参加者11人は尾花沢市の名木沢公民館で懇談
▽2日目(7月30日)
9:30 尾花沢市の猿羽根大橋を出発
12:45 大蔵村の烏川(からすがわ)公民館で昼食、休憩
15:00 新庄市の本合海大橋に到着
≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、大江町、尾花沢市、舟形町、大蔵村、新庄市、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 朝日町雪谷区長、鈴木進▽尾花沢市名木沢区長、阿部良一▽大蔵村赤松区長、八鍬茂▽新庄市本合海地区、八向尚
≪ウェブサイト更新≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、長嶋広海)
≪ポスター、Tシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell 保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
第6回最上川縦断カヌー探訪は予定通り、7月28日(土)、29日(日)に開催します。連日の猛暑のため最上川の水量はかなり少なく、渇水状態とも言える流量ですが、なんとか川下りができる状態です。2日目のゴール地点、新庄市の本合海(もとあいかい)は『奥の細道』を著した江戸時代の俳人、松尾芭蕉が最上川の舟下りを始めた所です(芭蕉の舟下りは本合海から清川<現在の庄内町清川>まで)。
*メールマガジン「風切通信 49」 2018年4月12日
森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改竄に続いて、朝日新聞が加計学園の獣医学部新設について「首相案件」と記した文書がある、とスクープしました。10日の朝刊によると、その文書には、愛媛県や今治市、加計学園の幹部が2015年4月に首相官邸で柳瀬唯夫(ただお)首相秘書官に面会した際、柳瀬氏が「本件は首相案件となっている」と語った、と明記されているというのです。

文書には、この席で「加計学園(の関係者)から、安倍総理と同学園理事長が会食した際に、下村文科大臣が加計学園は課題への回答もなくけしからんといっている、との発言があった」という記述もありました。これは当時、文部科学省が加計学園の計画に難色を示していた経緯とも符合し、安倍首相が2015年の時点ですでに獣医学部の新設計画を知っていたことを示すものです。
柳瀬首相秘書官に面会したのは愛媛県の地域政策課長ら4人と今治市の企画課長、加計学園の事務局長らで、柳瀬氏に会う前に内閣府の藤原豊・地方創生室次長にも会い、藤原氏が「内容は総理官邸から聞いている」「これまでの構造改革特区とは異なり、国家戦略特区の手法を使って突破口を開きたい」と発言した、といったことも記しています。
報道を受けて、愛媛県の中村時広知事は記者会見し、首相官邸を訪れた県職員の1人が作った文書であることを認めました。「職員が文書をいじる必然性はまったくない。全面的に信頼している」と語り、面談の事実をそのまま記録した文書、との認識を示しました。企画課長が同席した今治市にも首相官邸に出張した記録が残っています。決裁文書をいじくり回した財務省とは異なり、こちらは事実を正確に記した文書と考えて間違いありません。
ところが、当の柳瀬氏(現在は経済産業審議官)は文書でコメントを出し、「自分の記憶の限りでは、愛媛県や今治市の方にお会いしたことはありません」と否定しました。柳瀬氏は昨年7月の衆院予算委員会で今治市職員らとの面談の有無を問われ、「お会いした記憶はございません」と答えています。今さら「実は会っていました」とは言えない、ということでしょう。一度、嘘をついたら、嘘をつき続けるしかありません。
首相のお友達、産経新聞は12日の社説で「一体、何が本当なのか。国民は戸惑うばかりである」などと、乙女チックなことを書いていますが、「どっちが本当のことを言っているのか」などと問う必要もないほど白黒はハッキリしています。愛媛県の文書の信憑性を疑う理由は何一つないからです。文書の性格についても、中村知事は「(知事への)口頭報告のために作ったメモ」と説明しましたが、この文書が文部科学省や農林水産省への説明にも使われたことを考えれば、立派な公文書でしょう。
このスクープは、決裁文書の改竄に劣らぬ破壊力を持っています。「安倍晋三首相は嘘つきだ」ということを示す文書だからです。首相は国会で、国家戦略特区を活用した加計学園の獣医学部新設計画を知ったのは2017年1月だ、と繰り返し答弁してきました。首相が議長をつとめる国家戦略特区諮問会議が加計学園を事業者として正式に決定した時です。「それまでは知らなかった」と説明してきたのですが、愛媛県の文書は、安倍首相のそうした答弁は嘘で、ずっと前から首相が獣医学部新設計画に関与していたこと、首相の秘書官らもこの計画を「首相案件」として取り扱ってきたことを示しています。
安倍首相と加計学園の加計孝太郎理事長はアメリカに留学していた時からの友だちです。一緒にゴルフをし、しばしば会食する仲です。獣医学部の新設について語り合ったとしても不思議ではないのに、首相は「立場を利用して何かを成し遂げようとしたことは一度もない。獣医学部をつくりたいとか、今治にという話は一切なかった」と釈明してきました。
こういう発言は、ひっくり返すと真実により近くなる。「立場を利用していろいろなことを成し遂げたし、獣医学部のことも何度も話になった」と言っているようなものです。この1年間の推移を振り返れば、森友学園問題でも加計学園問題でも首相は嘘をつき続けている、と判断するしかありません。言葉を大切にする、自分の言葉に責任を持つ、という意識がまるで感じられません。
首相の嘘を取り繕うために、財務省の佐川宣寿・理財局長(当時)は国会で嘘の答弁を繰り返し、決裁文書の改竄にまで手を染めました。今回も、首相秘書官だった柳瀬氏は嘘をつき続けるしかないのでしょう。理財局長から国税庁長官に上り詰めた官僚が今や訴追される恐れがあるとおびえ、日本の通商交渉を担当する経済産業省の幹部が記者の質問に答えることなく、紙に書いたコメントを出して逃げ回る。そして、首相自身も「柳瀬元秘書官の発言を元上司として信頼している」と、その嘘にしがみつく――。
ここまで来ると、哀れさを覚えるほどです。嘘に嘘を重ね、政治家どころか人間としての信頼すら失って、落ちてゆくしかないでしょう。私たちの国は、こういう人物を宰相とするしかなかった。それが何よりも悲しい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
≪参考記事&サイト≫
◎2018年4月10日?12日の朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞(山形県内で販売されている版)
◎愛媛県職員が作成した柳瀬唯夫・首相秘書官との面談記録全文(東京新聞電子版)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201804/CK2018041102000126.html
◎下村博文・文部科学相(当時)の「加計学園はけしからん」発言について(中日新聞電子版)
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018041102000081.html
◎加計孝太郎・加計学園理事長の略歴(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%A8%88%E5%AD%9D%E5%A4%AA%E9%83%8E
◎月刊『文藝春秋』2018年5月号の「佐川氏に渡された総理のメモ」(安倍首相が経済産業省の官僚を重用する理由と背景を描いて秀逸)
≪写真説明&Source≫
◎柳瀬唯夫・元首相秘書官(東京新聞電子版)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201804/CK2018041002000246.html
*メールマガジン「風切通信 48」 2018年3月26日
このコラムには時折、読者からコメントが寄せられます。「その通りだ」と共感してくださる方もいれば、「でたらめな事を書くんじゃない」とお叱りを受けることもあります。つくづく、世の中にはいろんな人がいるものだ、と感じさせられます。
コメントは、コラムの発信から数日以内に寄せられることが多いのですが、昨日は珍しいことに、1年前の3月14日に書いた「森友学園問題で公明党が沈黙する理由」への投稿がありました。「トラ・イシカワ(表記はTra ishikawa))」さんからのコメントで、次のような内容でした。

「実質200万の出費で手に入れた9億の土地を担保に、21億の融資をしてもらう話。それをまとめるために、安倍は国会開催中の忙しい中、大阪に飛んだのである。総理大臣が金にもならない話のために半日、時間を割くわけがない。21億の融資が入れば、最大の功労者に10%から20%が召し上げられる。ブローカーの公明代議士の子息には3%から5%か。モリトモの最終的な狙いは数億円単位のヤミ献金だったはず。しかし、あまりにあからさまで、認可だ、土地貸借だ、売買だと、かかわった人間が多すぎたために、知る人ぞ知る『安倍案件』として噂になってしまい、そのうえ、獲物の分け前で、籠池側と安倍側で仲間割れになってしまい、その筋書きが狂ってしまったために、夫婦は知らなかった、関わりなかったことにしておけと改竄疑獄事件になってしまった」
一読して、「数学の図形の補助線のような投稿だなぁ」と感心しました。難しそうな図形問題も、一本の補助線を引けば、すっきりと解けることがあります。この投稿に沿って、森友学園問題に「数億円単位のヤミ献金」という補助線を引けば、もやもやしていた謎が解けるのではないか、と。
投稿の冒頭部分は事実と思われます。森友学園は時価9億円の国有地を1億3400万円で入手しましたが、その後、埋設物除去や土壌汚染対策の名目で1億3200万円の公金が注ぎ込まれていますので、森友側が負担したのはわずか200万円と報じられています。その土地を担保に、小学校の建設費として都市銀行から21億円の融資を受けたのも周知のことです。
1年前の上記のコラムでも指摘しましたが、森友学園問題でもっとも重要なのは2015年9月3日から5日までの3日間です。どんな3日間だったのか。あらためて、産経新聞に掲載された「安倍日誌」をベースに注釈を加えて、首相と昭恵夫人の動静を記します。
▽9月3日 午後2時17分から財務省の岡本薫明官房長、迫田(さこた)英典・理財局長に会う(注:迫田氏は首相と同じ山口県出身で旧知の仲。その後、国税庁長官に栄進。理財局長、国税庁長官とも後任は佐川宣寿氏)
▽9月4日 午前、羽田空港から全日空機で伊丹空港へ。午後1時半から読売テレビで番組の収録。午後4時7分、大阪市北区の海鮮料理店「かき鉄」で故冬柴鉄三・元国土交通相の次男、大(ひろし)さん、秘書官らと食事(注:同席した首相秘書官は今井尚哉<たかや>氏。経済産業省の官僚)
▽9月5日 前夜、大阪から帰京した首相は私邸で過ごす。昭恵夫人は森友学園経営の幼稚園で講演し、開校予定の小学校の名誉校長に就任
この時期、国会は安倍政権が重要課題としていた安全保障関連法案の審議が大詰めを迎えていました。衆議院は通過したものの、参議院での審議が難航、法案が成立するかどうか、ギリギリの攻防が続いていました。その最中に、安倍首相は大阪を訪問したのです。参議院で野党と対峙していた自民党の鴻池祥肇(よしただ)参院平和安全法制特別委員長が「一国の首相としてどういったものか」と苦言を呈したのも当然でしょう。
こうした状況を踏まえれば、導かれる解は「首相にとって重要法案の審議より優先度の高い案件が大阪にあった」というものです。訪問の前日に財務省の高官を呼んで十分に経緯を把握し、大阪では森友学園と国の仲介役と懇談して内容を固め、その翌日に昭恵夫人が現地で講演をして名誉校長を引き受けた、その見返りが億単位のヤミ献金、というのが投稿の趣旨です。
与党公明党の大物代議士だった冬柴元国交相の次男、大氏は、りそな銀行の前身である大和銀行に1986年に入行し、最初に豊中支店に配属されました。森友学園の小学校の建設予定地、豊中市で銀行員として働いていたのですから、土地勘も十分でしょう。首相とは父親を介しての縁もあります。りそな銀行を退職した後は、「冬柴パートナーズ」というコンサルタント会社を経営していますので、ブローカー役として彼以上の適任者は見つからないほどです。
安倍首相と冬柴大氏との会食に今井尚哉秘書官が同席していたことも、この懇談がきわめて重要なものだったことを示しています。今井氏は、叔父の今井善衛氏が岸信介・元首相と商工省の官僚同士、同じ叔父の今井敬氏が元経団連会長で、「経産省のサラブレッド」と称されました。安倍政権の発足以降、首相の懐刀として辣腕を振るっている人物です。昭恵夫人の秘書を務めた谷査恵子氏も今井氏の部下です。
この補助線の通りであるならば、安倍首相は「森友問題には一切関係していない。妻が応援していただけ」どころか、夫唱婦随、息の合った連携プレーだったことになります。首相夫妻を支えた2人の秘書も上司とその部下です。財務省の佐川理財局長らが決裁文書を書き換えてまで昭恵夫人の関与を隠し通そうとしたのも納得がいきます。
そうであるならば、事の真相を知悉(ちしつ)しているのは、隠蔽役の佐川・元理財局長らではなく、首相本人と夫人、首相秘書官、ブローカー役を果たしたと見られる冬柴大氏である、ということになります。佐川氏の国会喚問は、森友疑惑解明の第一幕に過ぎません。第二幕、第三幕と進まなければ、真相は一向に見えてこないでしょう。
小泉進次郎議員が言う通り、森友学園問題は「ポスト平成の政治の形とは何なのか。そういった問題にまでつながっていくような、平成の政治史に残る大きな事件」であり、うやむやのまま幕を引けるような疑惑ではありません。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
≪参考サイト≫
◎コラム「森友学園問題で公明党が沈黙する理由」(情報屋台、2017年3月14日)
http://www.johoyatai.com/1055
◎森友学園の小学校建設費「21億8000万円」の調達先(日刊ゲンダイ)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200917
◎安倍首相の動静(産経新聞の「安倍日誌」2015年9月3日)
http://www.sankei.com//politics/print/150904/plt1509040010-c.html
◎今井尚哉首相秘書官の経歴(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%B0%9A%E5%93%89
◎コンサルタント会社「冬柴パートナーズ」の概要と冬柴大氏の略歴(同社のサイト)
http://fuyushiba.com/aisatsu.htm
◎小泉進次郎・自民党筆頭副幹事長の記者団への発言(朝日新聞デジタル)
https://www.asahi.com/articles/ASL3T55DNL3TUTFK00P.html
≪写真説明&Source≫
◎大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/584.html
*メールマガジン「風切通信 47」 2018年3月16日
森友学園への国有地売却に関する決裁文書を書き換えて国会に提出した財務省の幹部を訴追すべきか否か。検察の内部は「これを見過ごせば、世間から『検察もしょせんは権力の手先か』と見られる。立件すべきだ」という積極派と、「刑法の条文に照らせば、起訴するのは難しい」という消極派に割れている、と報じられています。

佐川宣寿(のぶひさ)・元理財局長らの行為は何罪にあたるのか。確かに悩ましい問題です。まず、公文書偽造・変造罪は無理です。この罪は、民間人であれ公務員であれ、作成権限のない者が公文書を作った場合に適用される条文だからです。権限のある公務員が嘘の公文書を作った場合は虚偽公文書作成罪にあたりますが、書き換えた文書にはでたらめな事が書いてあるわけではありません。今回のケースは、ほとんどが「元の決裁文書にあった肝心の部分を削除した」というもので、「虚偽公文書」と言えるかどうか。「淡々と事実を記しただけ」と言い逃れをする可能性があります。
もちろん、問題は削除した内容です。安倍晋三首相の昭恵夫人が森友学園の開設を熱心に応援していたこと。何人もの政治家が秘書を動かして国有地の売却が森友学園側に有利になるように働きかけたこと。売り手の財務省が譲渡に際して特別な計らいをしたこと。何があったのかを理解するのに欠かせない重要な事柄がことごとく削除されていました。
なぜ、こんな事をしたのか。森友問題が発覚した直後、安倍首相は国会審議で「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」と大見えを切りました。国会対策にあたる財務省の幹部としては「国のトップを辞めさせるわけにはいかない」としゃかりきになった、と多くの人は推測していました。そして、明らかになった元の決裁文書は、真相がその推測通りだったことをはっきりと示しています。
なのに、上記のような理由で、公文書偽造罪も虚偽公文書作成罪も適用するのが難しい。公用文書等毀棄罪という条文も取り沙汰されています。公文書を捨てたり、焼却したり、隠したりした場合の罪です。「毀棄(きき)」というのは物理的に棄損した場合だけでなく、その文書の効用や意味合いを損なうことも含みますから、この条文なら適用可能かもしれません。他人の犯罪に関する証拠を隠滅したり、偽造もしくは変造したりした場合に適用される証拠隠滅罪にあたる可能性もあります。
と、刑法演習のようなことをこまごまと書き連ねてきました。人を訴追して裁く以上、やはり法律にのっとって行うことが法治国家の大原則だからです。しかし、今回の決裁文書書き換え問題のポイントは、「法治国家が想定していないような手法で法治国家の屋台骨を揺るがす悪事をした人間がいる。これをどうやって裁くか」という点にあります。官僚によるこのような行為は、文字通り前代未聞のことです。
日本の現行刑法は明治40年(1907年)にドイツ刑法をお手本にして作られました。戦後、天皇に対する不敬罪が削除されたり、1980年代にコンピューターの普及に伴って電子計算機損壊等業務妨害罪が新設されたり、幾度か改正されていますが、ほとんどは100年前に制定された当時のままです。つまり、公文書偽造にしろ虚偽公文書作成にしろ、当時の人たちが「官僚が犯す罪はこういうもの」と想定して作った、ということです。法律は常に保守的で、いつも時代を追いかける宿命にあるのです。
では、前代未聞のことが起きた場合、法律家は何を頼りにすべきなのか。「時代の制約を受ける法律」を杓子定規に適用するのではなく、「歴史の中で育まれてきた叡智と規範」に深く思いを致し、今ある法律を許される範囲内で柔軟に使いこなす、ということではないでしょうか。そういう思考に立てば、国会でうそとごまかしを連発した佐川元理財局長らを起訴し、その背後で彼らにそのような犯罪行為を強いた人間たちをあぶり出すことはできるはずです。検察が為すべきことを為すよう期待します。
安倍首相よ。あなたには、財務省幹部の刑事責任追及を待つまでもなく、やるべきことがあるのではありませんか。よもや、衆人環視の場で「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」と明言したことを忘れたわけではないでしょう。「関係していたこと」がはっきりしたのですから、さっさと身を引いて、頭でも丸めて、「日々これ懺悔」の暮らしに入ってはいかがでしょうか。
【追補】(第5段落の後に以下の文章を追加します)
佐川氏らには背任罪の適用も考えられます。その場合には、今回の決裁文書の書き換えではなく、国有地を大幅に値引きして森友学園に売却した行為そのものを「国に、ひいては納税者に損害を与えた犯罪」と捉えて立件することになります。地中深くにありもしないゴミがあったとして8億円も値引きして売却したのですから、証拠固めさえしっかりすれば、十分に立件可能でしょう。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
≪参考記事、文献&サイト≫
◎3月13日の河北新報4面「森友文書改ざん 専門家2氏に聞く」の郷原信郎(のぶお)弁護士のコメント
◎3月13日の読売新聞社会面の記事「大阪地検特捜部 財務省中枢の関与注目」
◎『岩波基本六法』(岩波書店)の刑法
◎『刑法綱要 各論』(団藤重光、創文社)
◎「日本の刑法および刑法理論の流れ」(川端博・明治大学教授)
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/1411/1/horitsuronso_69_1_117.pdf
≪写真説明&Source≫
◎財務省の決裁文書書き換え問題について、参議院予算委員会で陳謝する安倍晋三首相(HUFFPOSTのサイトから)
https://www.huffingtonpost.jp/2018/03/13/abe-moritomo_a_23385038/
*メールマガジン「風切通信 46」 2018年3月12日
去年の夏、あるセミナーで参加者の一人が「朝日新聞はいつまでネチネチと森友問題を書き続けるんだ。国有地の値引きと言ったって、たかが8億円の問題じゃないか。小さな問題だ。北朝鮮の核開発問題とか、世界経済の動向とか、ほかにいくらでも大きい問題があるだろう」と発言しました。

自由討論の時間でした。その場にいた私は、あまりにも露骨な政府寄りの発言に驚き、即座に反論しました。「小さな問題ではない。この国の在り方と制度の根幹にかかわる問題をはらんでいる。権力を笠に着て、国民の財産を官僚たちが好きなように処分している。しかも、それが発覚するや、嘘とごまかしで逃げ切ろうとしている。こんなことがまかり通ったら、世の中がおかしくなる」
あれから半年。森友学園に対する国有地の払い下げ疑惑を包んでいた霧がようやく晴れてきました。3月2日に朝日新聞が「森友学園との国有地取引の際に財務省が作成した決裁文書がその後、書き換えられ、国会には別の文書が提出された疑いがある」とスクープしました。もとの決裁文書は押収されて、大阪地検特捜部にあります。その文書を入手した、と報じたのです。
オリジナルの決裁文書にあって、国会に提出された文書から削除された文言で重要なのは「森友学園との取引は特例的なものであり、特殊性がある」という記述と「学園の提案に応じて鑑定評価を行い、価格提示を行う」という二つの文言です。これらの記述は、財務省の高級官僚たちが「森友学園の小学校開設は安倍晋三首相の息のかかったプロジェクトである」と認識し、「前例にとらわれず特別な計らいをする」と決めて実行したことをはっきりと示しています。
国会の質疑は正式な文書をベースにして行われます。このオリジナル文書を提出すれば、言い逃れはできません。そこで、国会での答弁に差しさわりのある表現は削除もしくは書き換えて別の決裁文書を作り、それを提出した疑いがある、というのです。報道の通りなら、国会をないがしろにし、国民をあざ笑うような所業です。戦後、営々として築いてきた政治や行政の在り方を覆すような暴挙と言うしかありません。それが「小さな問題」であるわけがありません。
国会での森友問題審議で中心的な役割を果たしたのは、当時の財務省理財局長、佐川宣寿(のぶひさ)氏です(その後、国税庁長官に就任)。彼は当然、この決裁文書の書き換えにも深く関与していたと考えられます。国有財産を管理する要職にあり、その後、国税庁長官に就いた官僚が政治と行政の根本を揺るがすようなことを行った疑いが濃厚です。スクープから、すでに10日たちました。問題のオリジナル文書を入手したのは朝日新聞だけのようですが、毎日新聞はその後、財務省の別の決裁文書を情報公開で入手し、その文書にも「本件の特殊性」や「特例処理」という文言があった、と報じました。さらに、NHKも検察の当局者が「オリジナルの決裁文書が大阪地検特捜部にあることを認めた」と伝えました。朝日新聞の報道が事実であることを間接的に補強するものでした。
嘘とごまかしで森友疑惑の追及をかわそうとしてきた安倍政権と財務省は追いつめられています。財務省近畿財務局の担当職員は自殺、佐川国税庁長官は辞任しました。財務省は決裁文書を書き換えたことを認める方針を固めたようです。しかし、佐川氏が辞任し、決裁文書の書き換えを認めたことで決着するような事ではありません。
佐川氏ら財務省幹部は複数の市民団体から、国有財産を不当な価格で売却した背任容疑や関連の公用文書を毀棄(きき)した容疑、さらに証拠隠滅の容疑で告発され、検察はこの告発を受理しました。高級官僚たちがどのような罪を犯したのか。なぜ、そのような行為をするに至ったのか。検察はきちんと調べて訴追し、それをつまびらかにしなければなりません。官僚たちにこのような行為をさせたのは安倍晋三首相とその周辺の人々であり、その責任も問われなければなりません。
森友・加計学園問題について、朝日新聞は特別な取材チームをつくって追及し続けています。昨年2月に最初の報道をしてから1年余り。よくぞ、問題の核心を記した決裁文書に辿り着いたものです。その粘り強い取材に、わが古巣ながら畏敬の念すら覚えます。新聞記者には強制的な捜査権限はありません。日本の新聞記者はお金を払って情報を取ることもしません。「こんなことが許されていいのか」という思いで取材相手に肉薄するしかないのです。その誠意と熱意が通じた、ということでしょう。
その思いに誰かが打たれて、オリジナルの決裁文書を見せたのです。可能性としては財務省の職員か検察官かのいずれかですが、後者と見るのが自然でしょう。その人物の行ったことは形式的には「国家公務員に課された守秘義務違反」ということになります。けれども、この世の中には「守秘義務」よりも重いものがあります。人として何を為すべきか、という物差しです。その人は胸に手を当てて深く考え、託するに足る人間に決裁文書を託した、と考えられます。
「天網恢恢(てんもうかいかい)、疎(そ)にして漏らさず」という中国の故事を思い起こさせる展開です。天の網は広くて大きい。粗いように見えても悪事を見逃すことはない、という言い伝えです。お天道様に顔向けできないようなことはしない。それが社会の隅々にまで行き渡る世の中にしていく。そのために為すべきことは何か。森友・加計学園疑惑で問われているのは、そういうことだと思うのです。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
10 情報公開制度をあざ笑う財務官僚の所業(2025年5月13日)
≪参考記事&サイト≫
◎2018年3月2日以降の朝日新聞、毎日新聞、NHKの報道
◎佐川宣寿・財務省理財局長、武内良樹・財務省国際局長ら7人の告発状(公用文書等毀棄罪)
http://shiminnokai.net/doc/kokuhatsu170510.pdf
◎「天網恢恢、疎にして漏らさず」について(「故事ことわざ辞典」サイト)
http://kotowaza-allguide.com/te/tenmoukaikai.html
≪写真説明≫
◎辞任した佐川宣寿・国税庁長官(中日新聞の公式サイトから)
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018031002000101.html
*メールマガジン「風切通信 45」 2018年2月19日
韓国で開かれているピョンチャン・オリンピックが佳境を迎えています。フィギュアスケートの羽生結弦選手はけがを克服して堂々の二連覇、スピードスケートの小平奈緒選手はオランダでの修行を経て大輪の花を咲かせました。スノーボードの平野歩夢選手の妙技には「トップアスリートはこんなことまでできるのか」と目を見張りました。

日本選手の活躍に一喜一憂しつつ、大好きなアルペンスキーのテレビ中継も楽しんでいます。根が単純な性格なものですから、一番好きなのは猛スピードで斜面を駆け抜ける滑降なのですが、今回は男子大回転の生中継をまじまじと見てしまいました。優勝したオーストリアのヒルシャー選手らの滑りが見事だったこともあるのですが、それ以上にアフリカから複数の選手が参加していることに驚いたからです。
エリトリアのシャノン・アベダ選手とモロッコのアダム・ラムハメディ選手です。「炎熱の大陸アフリカになぜスキーの選手がいるんだ」と一瞬、戸惑ったのですが、テレビのアナウンサーがすぐに「2人ともカナダ生まれで二重国籍」と解説してくれたので納得しました。どのような生い立ちなのか、ネットで調べてみました。カナダの地方紙フォートマクマレー・トゥデイによると、アベダ選手の両親はエリトリアからの難民でした。
エチオピアとイエメンの間にあるエリトリアは、かつてはアフリカと中東を結ぶ交易地として栄えたこともあったようですが、私の記憶にあるのは「凄惨な飢餓の戦争をくぐり抜けてきた国」というイメージです。イギリスとイタリアの支配を受けた後、エリトリアはエチオピアに編入され、1960年代から30年にわたって分離独立を求めて戦い続けました。エチオピア政府軍との戦いに加えてエリトリア人同士の内戦も勃発、数多くの餓死者と難民が出た紛争でした。
私がエリトリアの独立戦争と内戦の記事を読んだのは、駆け出し記者だった1980年代のこと。自分がその後、似たような紛争を取材することになるとは考えてもいない時期でした。アベダ選手の母親が16歳で戦禍を逃れて海を渡ったのはその頃です。父親も若くして難民になり、2人は避難先で知り合って結婚、カナダ西部のアルバータ州フォートマクマレーで3人の子どもを育てました。アベダ選手は末っ子。ロッキー山脈にあるスキー場で兄や姉と3歳から滑り始めたのだそうです。上記のカナダ紙のインタビューにアベダ選手の母アリアムさんは語っています。
「アベダは小さい頃、オリンピックの表彰台に立つ絵を描いたりしていました。その後、カルガリーに引っ越しましたが、フォートマクマレーでの暮らしは私の人生で最高のものでした。信じられないような友情を育むことができました。今でもお付き合いが続いています。子どもたちはスポーツでもほかのことでも、生き生きとしていました」
エリトリア初の冬季五輪選手となったアベダ選手は同紙の取材に「自分の力量は分かっています」とメダルには手が届かないことを認めつつ、こう語りました。「エリトリアの人たちはきっと『誰かが自分たちの代表として出ている。私たちの存在を知らせてくれている』と思うはずです。だから、全力を尽くします」。結果は2回目の試技に進んだ85人中、67位。メダルには遠く及びませんでしたが、その姿は光り輝いていました。
モロッコ代表のラムハメディ選手もカナダ生まれ。父親がモロッコ人の大学教授、母親がカナダ人です。アベダ選手と同じく二つの国籍を持ち、オーストリア・インスブルックの国際ユーススキー大会で優勝したこともある実力者です。4年前のソチ・オリンピックに続いて2回目の五輪参加で、今回の大回転では61位でした。アルペンスキーのこの2人を含め、平昌五輪にはアフリカから過去最多の8カ国13人が参加と報じられています。
欧米のスポーツだったウィンタースポーツにアジアや中南米の選手が挑み、今やアフリカ諸国の選手も少しずつ増えていることを知りました。ゆっくりとではあっても、世界は着実に一つに結ばれる方向に進んでいます。平昌五輪のスローガンは「ひとつになった情熱 Passion. Connected.」。難民の子がエリトリアの代表としてスロープを疾走する姿は、そのスローガンを体現しているように思えました。
≪参考サイト&文献≫
◎エリトリアのスキー選手、シャノン・アベダ Shannon Abeda(英語版ウィキペディア)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shannon-Ogbani_Abeda
◎モロッコのスキー選手、アダム・ラムハメディAdam Lamhamedi(同)
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Lamhamedi
◎アベダ選手のことを報じるカナダのフォートマクマレー・トゥデイ紙(電子版)
http://www.fortmcmurraytoday.com/2018/01/03/mcmurray-born-skiier-first-to-represent-eritrea-at-winter-olympics
◎アフリカの五輪選手の活躍を伝えるフランスのテレビ局「France 24」の記事(同)
http://www.france24.com/en/20180206-sport-olympics-africa-five-rings-one-dream-athletes-road-pyeongchang-winter-games-2018
◎アフリカからの冬季五輪参加が8カ国になったことを伝える記事(ウェブメディアQuartzから)
https://qz.com/1197726/pyeongchang-2018-will-be-the-african-winter-olympics/
◎エリトリアの歴史(日本語版ウィキペディアから)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%88%A6%E4%BA%89
◎エリトリア独立戦争(同)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%88%A6%E4%BA%89
◎共同通信社『世界年鑑2007』
≪写真説明≫
◎エリトリアから冬季五輪に初めて参加したシャノン・アベダ選手(カナダのフォートマクマレー・トゥデイ紙の電子版から)
http://www.fortmcmurraytoday.com/2018/01/03/mcmurray-born-skiier-first-to-represent-eritrea-at-winter-olympics
*メールマガジン「風切通信 44」 2018年2月8日
北陸の福井県が37年ぶりの大雪に見舞われ、生活に甚大な影響が出ています。福井市の2月7日現在の積雪は143センチ。しかも、その多くが数日のうちに降ったそうですから、車が立ち往生して物流が滞り、市民生活がマヒしたのも当然でしょう。1日で大人の腰の高さまで積もったところもあるとか。これでは、雪に慣れた地域でも簡単には対処できません。

福井の人たちの困惑と困窮はどのようなものか。わがふるさと、山形県に引き付けて考えれば、以下のようなことかと推察します。同じ雪国でも、山の位置や風の通り道によって、雪の降り方はまるで異なります。県庁所在地の山形市の平年の積雪は28センチほど。これに対し、私が暮らす朝日町の平年の積雪は140センチ前後と、この冬の福井市並みです。この差は、冬の暮らしに各段の違いをもたらします。
まず、日々の雪かきのレベルが異なります。山形市の降雪は一晩で通常5センチほど、多くても15センチくらいです。これなら、一般の住宅の場合、スコップかラッセルスノーという幅広のスコップでかき出すことができます。これが朝日町になると、一晩に20センチから30センチ、多い時には50センチほど積もります。こうなると、スコップでは大変なので、ガソリンエンジン駆動のロータリー式除雪機が「標準装備」として必要になります。庭が広く、母屋に加えて納屋やお蔵の周りも除雪しなければならないからです。
わが家は玄関先が車1台分ほどと狭く、除雪スペースが小さいので除雪機はありません。手作業で雪かきをしています。それでも、スコップやラッセルでは対処できないので、スノーダンプと呼ばれる、両手で押す大きなスコップのような雪かき道具が必要になります。これで新雪をゴソッとすくい取り、側溝に流し込みます。田んぼに水を供給するための村の水路が、冬は融雪溝として活躍してくれるのです。
降った雪はその重みで沈み、日中の日差しで少しずつ解けますから、積雪量は上記のように山形市で28センチ、朝日町で140センチほどになります。積雪が1メートルを超すと、雪の重みで家が破損する恐れが出てきます。そこで、必ず屋根の雪下ろしをしなければなりません。つまり、山形市程度の積雪なら屋根の雪下ろしをする必要はないが、朝日町では雪下ろしをしなれければ家がつぶれる危険性がある、ということです。
今回の福井の大雪は、例年なら山形市程度の積雪なのに、急に、しかも数日で朝日町並みの雪が降ってしまった、ということになります。それなりに雪に備えていたとしても、これでは市民生活がマヒ状態に陥ったのも無理はありません。日ごろ雪かきに追われ、大汗をかいている身としては「今年の冬将軍はなんて気まぐれなんだ」と思ってしまいます。
9年前に東京から山形に戻り、最初の冬に「雪かきは容易じゃない」とぼやきました。すると、近くの西川町大井沢出身の人から「こだな、雪(ゆぎ)んね!」と、いさめられました。「この程度の雪で大変だなんて、冗談じゃない」という意味です。月山のふもとにある大井沢の平年の積雪は3メートルほど。同じ西川町の志津(しづ)温泉はさらに多く、時には6メートルを超します(志津温泉は気象庁のアメダスの観測地点になっていないため積雪記録がニュースになることはありません)。「何事も上には上がある」と、あらためて思い知らされました。
積雪がある程度以上になると、雪かきよりも「雪の始末」の方が大変なことも知りました。取り除いた雪をどう始末するか。除雪機があれば、広い庭や畑に雪を飛ばしてしまえばいいのですが、私のように手作業でやる場合には、それもできません。側溝に流し込みたくても、肝心の側溝がしばしば埋もれてしまいます。そこで、雪かきの後に必ず「側溝を掘り出す作業」をしなければなりません。古い雪は往々にして氷と化しています。なので、剣先スコップで氷を削り、側溝を掘り出さなければならないのです。
降ったら除雪し、氷を削って側溝を掘り出し、流し込む。多い時には朝、昼、晩と1日に3回。いつも大汗をかきます。これを繰り返していると、時折、「まるでシシュフォスの石みたいだなぁ」と思ってしまいます。ギリシャ神話に出てくるコリントスの王シシュフォスは、神々を何度も欺いた罰として、巨大な石を山頂に押し上げる苦役を課されました。大石はいつも山頂まであと一歩というところで、またふもとまで転げ落ちる。かくして、シシュフォスは終わることのない苦行を続けなければならなくなった、という神話です。
私は神々を欺いたことはありませんが、何度か会社を欺いたことはあります。取材を装って職場を抜け出し、映画を観に行ったり、上野の鈴本演芸場に落語を聞きに行ったり。そうやって適当にさぼっているから、ストレスの多い仕事を続けることができるのだ、と開き直っていました。雪かきは、その罰なのか。
いや、シシュフォスの石と違って、雪は春になれば解けます。そして、雪解け水は夏まで田畑を潤し、農民に「干魃の恐れのない大地」をもたらしてくれます。しんどい雪かきの一方で恵みも与えるという点で、シシュフォスの石とはまるで違います。冬将軍様、不適切な例えでした。お詫びして訂正しますので、北陸にはもうあまり雪を降らせないでください。お願いいたします。青森や新潟、山形は例年より少し多い程度ですので、お願い事はとくにありません。はい。
≪参考サイト&文献≫
◎全国各地の積雪データ(気象庁の公式サイトから)
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/snc_rct/alltable/snc00.html#a35
◎雪かき道具のあれこれ(楽天市場「雪かき道具の通販」から)
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E9%9B%AA%E3%81%8B%E3%81%8D+%E9%81%93%E5%85%B7/
◎山形県西川町の積雪データ(同町の公式サイトから)
https://www.facebook.com/295465570563835/photos/a.644330602343995.1073741831.295465570563835/1399251570185224/?type=3&theater
◎志津温泉の積雪については、2013年6月1日のメールマガジン「小白川通信 3」参照
http://www.bunanomori.org/NucleusCMS_3.41Release/index.php?catid=10&blogid=1
◎シシュフォスの石(「コトバンク」から)
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B9-73318
◎『北越雪譜』(鈴木牧之編撰、岩波文庫)
≪写真説明≫
◎山形県朝日町のわが家の積雪状況(2月7日、筆者撮影)。積雪に加えて、屋根から下した雪が積み重なっています。車の右前にある黄色の雪かき道具がスノーダンプ
*メールマガジン「風切通信 43」 2017年12月7日
池澤夏樹という作家はただ者ではない。私が初めてそう感じたのは、河出書房新社から出版した『池澤夏樹=個人編集 世界文学全集』の中に、ベトナムの作家バオ・ニンの小説『戦争の悲しみ』を選んで入れた、と知った時でした。
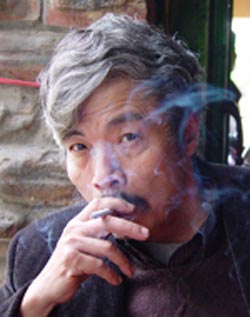
トルストイの『戦争と平和』をはじめ、戦争をテーマにした小説は数限りなくありますが、私はバオ・ニンの『戦争の悲しみ』は戦争文学の傑作の一つと受けとめています。彼は、ベトナム戦争に北ベトナム軍の兵士として加わった人間です。部隊は全滅状態になり、その中の数少ない生き残りの一人でした。戦場の実相とはどのようなものなのか。バオ・ニンはそれを淡々とした筆致で描いています。一緒にいた仲間が次々に死んでいく。それを繰り返すうちに、兵士の人としての心は乾き、少しずつ死んでいくのだ、と書いています。
ベトナムは社会主義国家です。社会主義圏の作家は「祖国と革命の大義のために命をささげた英雄たちの姿」を描くよう求められるのが常です。が、バオ・ニンはそれを拒み、自らの体験をそのまま記しました。作品には北ベトナム軍の兵士が女性を暴行する場面も出てきます。このため、ベトナムの軍機関紙からは「人民軍の名誉ある歴史に泥を塗る作品」と指弾されました。十数年前にハノイを訪れ、彼の話を聞いたことがあります。寡黙な人でした。彼にとって、戦争においては「勝者もまた悲しみを運命づけられた存在」であり、作家にできることは「すべての死者と生者のために忠実に記録すること」だったのです。
「池澤夏樹はただ者ではない」と再び思ったのは、この秋、英国の作家カズオ・イシグロの作品『遠い山なみの光』の解説で、作家と作中の登場人物について池澤が次のように書いているのを読んだ時です。
「作家には、作中で自分を消すことができる者とそれができない者がある。三島由紀夫は登場人物を人形のように扱う。全員が彼の手中にあることをしつこく強調する。会話の途中にわりこんでコメントを加えたいという欲求を抑えることができない。司馬遼太郎はコメントどころか、登場人物たちの会話を遮って延々と大演説を振るう。長大なエッセーの中で小説はほとんど窒息している。(中略)カズオ・イシグロは見事に自分を消している。映画でいえば、静かなカメラワークを指示する監督の姿勢に近い。この小説を読みながら小津安二郎の映画を想起するのはさほどむずかしいことではない」
作家は作品の中で会話をどのように組み立てるのか。それについてこのような解説をしたためる力量にうなりました。司馬遼太郎の小説に違和感を覚える理由はそこにあったのか、と得心もいきました。司馬作品は文学というより歴史物語なのだ、と。池澤夏樹は同じ解説で次のようなことも書いています。
「われわれの日常的な会話の大半はそれほど生成的ではない。双方の思いの違いが明らかになるばかりで、いかなるC(という考え)にも到達できないのが普通の会話というものだ。それがまた哲学と文学の違いでもある。両者がボールを投げるばかりで相手の球を受け取らないのでは、会話はキャッチボールにならない。人間は互いに了解可能だという前提から出発するのが哲学であり、人間はやはりわかりあえないという結論に向かうのが文学である」
文学とは何か。哲学とは何か。それについて、これほど簡潔に表現した文章を初めて目にしました。これが誰かの文章からの引用なのか、池澤夏樹の独創なのか不勉強で知りませんが、胸にストンと落ちるものがありました。すでに読んだことのある小説のほかに、彼はどんな作品を発表しているのか。もっと読んでみたくなりました。ある作家から次の作家へ。こういう形で進む読書もあるのだ、と知った秋でした。
≪参考文献&サイト≫
◎『戦争の悲しみ』(バオ・ニン、井川一久訳、めるくまーる)
*河出書房新社『池澤夏樹=個人編集 世界文学全集』第1期第6巻には全面改訳を収録
◎ウィキペディア「バオ・ニン」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%B3
◎『遠い山なみの光』(カズオ・イシグロ、小野寺健訳、早川epi文庫)
◎『浮世の作家』(カズオ・イシグロ、飛田茂雄訳、早川epi文庫)
◎『光の指で触れよ』『すばらしい新世界』『スティル・ライフ』(いずれも池澤夏樹、中公文庫)
≪写真説明&Source≫
◎ベトナムの作家、バオ・ニン
http://hanoi36.sblo.jp/article/174876700.html
*メールマガジン「風切通信 42」 2017年11月8日
英国の作家カズオ・イシグロの父、石黒鎮雄(しずお)はその生涯を波の研究にささげました。彼の最初の仕事とも言うべき博士論文「エレクトロニクスによる海の波の記録ならびに解析方法」を読んでみたい。海洋学者の友人に相談すると、「論文のデータベースに標題が載っているが、電子化されていないようで内容は分からない。国会図書館なら国内のすべての博士論文を所蔵している」とのこと。
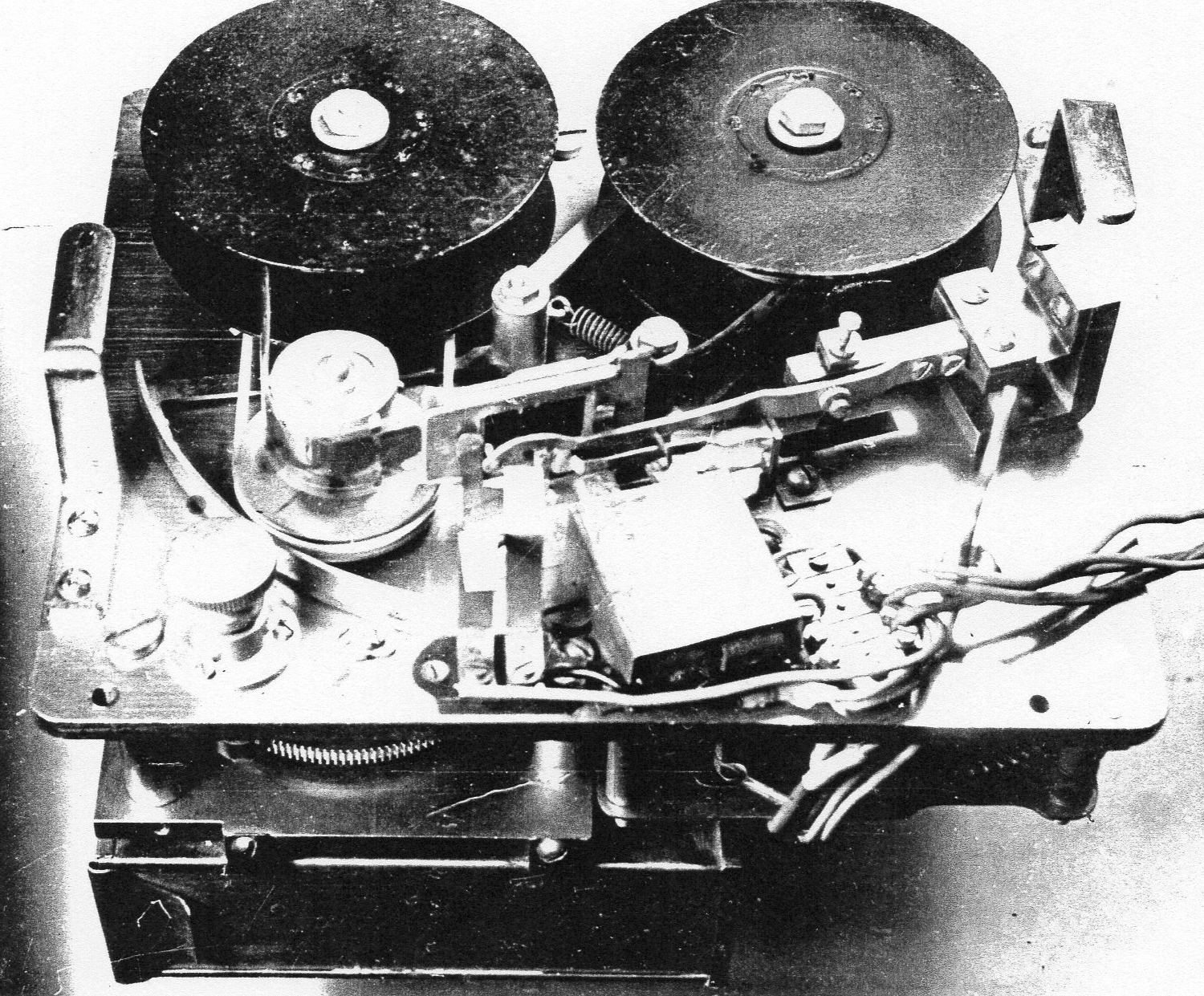
上京して永田町にある国会図書館を訪ねました。国立国会図書館法によって設立された日本唯一の国立図書館で、法定納本図書館とされています。国内で出版した書籍や論文、雑誌はすべてここに納本しなければなりません。同法の前文は「真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される」と格調高い。歴史哲学者、羽仁(はに)五郎の文とされています。
図書館職員の助けを借りて、石黒鎮雄の論文を検索すると、すぐに見つかりました。ただし、収納スペースの制約もあって、博士論文をはじめとする学術資料は京都府精華町にある関西館が所蔵しているとのこと。肩を落とすと、職員は「すべて電子化されていますので、国会図書館の会員になれば、インターネットで請求できますよ」と勧めてくれました。
会員登録を済ませ、山形の自宅に戻ってパソコンで論文の郵送を依頼すると、1週間ほどで念願の博士論文が届きました。原本は英文で200ページ余り。著作権法の定めにより、その半分、前半の100ページほどをコピーして送ってきてくれました(コピー代は後日振り込み)。論文の標題は「An Electronic Method for Recording and Analysing Ocean Waves」。カズオ・イシグロの父がタイプライターで一文字一文字、丁寧に打ち込んだ文章と手書きの数式が並んでいました。
微分積分も分からない文系の私には、論文の内容を正確に理解するのはもとより不可能です。ルート(平方根)の中にルートがあるような数式が頻繁に出てくるのですから。それでも、イギリスの国立海洋研究所がこの論文に注目し、石黒鎮雄を招聘することに決めた理由は理解できるような気がしました。
彼は手先が器用だったと言われています。市販されている電気製品を利用して、自分で波の高さや圧力を測定する装置を作り、それを使って計測したデータを論文にまとめたことが分かりました。装置の設計図や完成品の写真も載せ、実際に海に設置する方法も図解してありました。北海油田を開発するため、石油プラットフォーム(掘削櫓)を建設しなければならず、苦闘していたイギリスの関係者はこの論文に光を見たはずです。
荒れ狂う北海の波の高さはどれくらいなのか。波の圧力はどのくらいなのか。掘削櫓は、そうしたデータを得たうえで設計し、建設しなければなりません。「これで計画の土台を固めることができる」。関係者はそう確信し、三顧の礼をもって石黒鎮雄を招いたのではないか。そして、鎮雄も生涯をかけてその期待に応えることを決意した――妻や子どもたちが日本に一時帰国したがっていることは分かっていても、その余裕はついぞ生まれなかったのかもしれません。
この博士論文が、長崎で穏やかに暮らしていた5歳のカズオ・イシグロをイギリスに連れ去り、日本の思い出を繰り返し反芻する少年にし、作家への道を歩ませることになったのかと思うと、読みながら何か熱いものが込み上げてきました。
「ひとはみな、執事のような存在だと思うのです。自分が信じたもののために仕え、最善を尽くし、生きる」「人生は、とても短い。振り返って間違いがあったと気づいても、それを正すチャンスはない。ひとは、多くの間違いを犯したことを受け入れ、生きていくしかないのです」。代表作『日の名残り』について、カズオ・イシグロはそう語ったことがあります。その言葉は、家族を省みる余裕もないほど波の研究に没頭した父を許し、生きるためにそうせざるを得ない多くの人々の哀しみに寄り添うために発したのではないか、と思えてきました。
将来、何者になるかに惑い、さまよう中で、若きカズオ・イシグロはこの父の博士論文を読んだのではないか。そして、タイプライターで打たれた文章の行間から、波の研究にかける父の思いを汲み取り、さまざまなことに自分なりに折り合いをつけて歩み始めたのではないか。そう思わせる論文でした。
≪参考文献&サイト≫
◎石黒鎮雄の博士論文「An Electronic Method for Recording and Alalysing Ocean Waves」(1958年、学位授与)
◎国立国会図書館法
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/laws/pdf/a1102.pdf
◎ウィキペディア「国立国会図書館」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
◎国立国会図書館の公式サイト
http://www.ndl.go.jp/
◎週刊誌『AERA』2001年12月24日号のカズオ・イシグロの日本講演に関する記事(伊藤隆太郎)
≪写真説明&Source≫
◎石黒鎮雄が開発した波高測定装置の一つ(博士論文から複写)
*メールマガジン「風切通信 41」 2017年11月4日
セクハラという言葉もジェンダーという言葉も、まだ世間では使われていない頃の話です。朝日新聞に入社して配属された静岡支局には独身の男性記者が5人、事務の女性スタッフが2人いました。妻子持ちの記者がこの7人を馬に見立てて、「結婚予想レース」なるものを貼り出しました。クラシック音楽好きのもっさりした記者は「クマノハチゴロー」、少し優柔不断なところのある記者は「ヤイタノグズル」といった具合です。

女性の馬名がすごい。結婚願望が強い女性には「ウンノテキレイ(適齢)」、入社したての女性には、なんと「ホウマン(豊満)チブサ」と付けたのです。今なら、とても許されない命名です。私の馬名は「レイケツ(冷血)ノボル」。これも今ならパワハラと言われるかもしれませんが、私は意外と気に入っていました。どんな時でも冷静さを失わず、しつこく取材する。褒め言葉と受けとめたのです(昔から能天気でした)。
レースのその後の展開はともかく、私の冷血ぶりは今も変わりません。街頭で署名や募金を呼びかけられても、一瞥もくれず通り過ぎるのが常です。誰が何のために署名や寄付金を使うのか、知れたものではないからです。ただ、そんな冷血人間がつい募金箱にお金を入れてしまうことがあります。遺児の教育支援を呼びかける「あしなが学生募金」です。高校生が懸命に「お願いします!」と声を嗄らしているのを見ると、足が止まってしまうのです。
「あしなが育英会」は1960年代に、交通事故で親を亡くした遺児の進学を応援するために作られました。その後、交通事故だけでなく、病気や災害の遺児にも奨学金を支給するようになり、5200人の高校生や大学生に24億円の奨学金(2015年度実績)を貸し出しています。政府から補助金を受けたりせず、すべて寄付でまかなっているところがすごい。奨学生のために学生寮を建て、彼らが交流するための施設をつくるなど、運営もスマートです。
この秋に寄付した際、小さなチラシをいただきました。書かれていることを読んで、仰天しました。「あしなが学生募金」の半分は、今ではアフリカの苦学生のために使われている、と書いてあったからです。日本には進学したくてもできない若者がたくさんいる。けれども、アフリカにはもっと厳しい状況にある若者が無数にいる。そこで「アフリカ遺児高等教育支援100年構想」というプロジェクトを始めたのです。
「100年構想」の特設サイトがあり、内容が紹介してありました。アフリカのサハラ砂漠以南にある49カ国から毎年1人ずつ世界の大学に留学させることを目指すプロジェクトです。支援の対象に選ばれた学生たちはまず、ウガンダにある「あしながウガンダ心塾」で留学の準備をして、世界各地の大学に巣立っていくのです。2014年の第一期生10人の中に、隣国ルワンダの女子学生がいました。
アンジェリーク・ウワベラ(19歳、ルワンダ)
「両親は私が2歳の時に反乱軍の犠牲になり、私は完全に孤児になってしまいました。あしながは私にとって第二の家です。先生や仲間の励ましのおかげで、素晴らしい将来を想像できるようになりました。これまでずっと貧困に苦しんできたので、将来は国際ビジネスを勉強して自立し、自分の会社を作りたいです」
アフリカでは今でも紛争が絶えず、幼い子どもが酷使され、次々に死んでいっています。原因はいくつもあるでしょう。が、私には奴隷貿易の歴史がいまだに尾を引いている面がある、と思えてなりません。16世紀から300年余り、アフリカからは推定で1250万人を超える黒人が北米や中南米などに奴隷として売られていきました。白人たちは健康で働けそうな者だけを連行して船に乗せました。航海の途中で病死すれば、海に投げ捨てられるのが常でした(『環大西洋奴隷貿易 歴史地図』参照。奴隷貿易の総数については諸説ある)。
頑健な働き手をごっそり失ったアフリカの社会はその後、どのような道をたどったのか。想像するだけで胸が痛みます。コロンブスのアメリカ到達に象徴される大航海時代の始まりは、アフリカにとっては「大惨事の時代」の始まりだったのです。日本の中学や高校の歴史の教科書がそのことをあまりきちんと書かないのは、欧米を通して世界を見る習性が染みついているからでしょう。
東京大学名誉教授が著した『図説 大航海時代』という本は、スペインやポルトガルがいかにして世界の海に繰り出し、戦い、征服していったかを延々と綴っていますが、それによって奴隷の搬出地アフリカや移動先の南北アメリカで何が起きたのかについて触れることはない。アメリカの西部劇が騎兵隊や開拓者の側から描かれるのと同じです。敗者のことが念頭にない。いや、視野に入れようと思い付くことすらない。
歴史を広い視野から問い直し、学び直す。21世紀はそういう世紀になるような気がします。「あしなが育英会」にはそれが分かっていて、実践しているのだと思う。だから、このプロジェクトは胸を打つ。
募金に感謝するチラシには、スワジランド生まれでこの奨学金を得て日本の国際基督教大学に留学したボンゲ・キレさん(女性)の言葉が記されていました。
「私たちの国で留学しているのは、多くが英国や米国といったかつての宗主国です。でも、私はそうしたアフリカにとって身近な国ではなく、世界でも特別でユニークな文化を持つ日本で学びたいと考えました。私はそうしたユニークな考え方をアフリカに持ち込みたいと考えているからです」
私たちの国、私たちの社会の希望とは何なんだろうか。それを考える糸口を「あしなが育英会」とアフリカから世界の大学に飛び立った若者たちに教えてもらったような気がします。
【追補】
「あしなが育英会」は発足して半世紀になります。創設者の玉井義臣(よしおみ)氏(82)が会長をつとめ、役員には下村博文・元文科相や有馬朗人・元東大総長、明石康・元国連事務次長らが名を連ねています。法人格はなく、任意団体のままです。事業報告や収支報告を公開していますが、詳しい会計内容とりわけ支出の詳細は開示していません。事業規模が58億円(2015年度)に達し、多くの人の善意に支えられていることを考えれば、収支を一層透明にすることが望まれます。
≪参考文献&サイト≫
◎「あしなが育英会」の公式サイト
http://www.ashinaga.org/
◎「あしなが育英会」の活動・収支報告(公式サイトから)
http://www.ashinaga.org/about/report.html
◎『第95回あしなが学生募金』のチラシ
◎「アフリカ遺児高等教育支援100年構想」とは
http://ashinaga100-yearvision.org/year100/
◎「アフリカ遺児高等教育支援100年構想」で世界の大学に留学した第一期生の顔ぶれ
http://ashinaga100-yearvision.org/year100/class2014/
◎『環大西洋奴隷貿易 歴史地図』(デイヴィッド・エルティス、デイヴィッド・リチャードソン共著、東洋書林)
◎『図説 大航海時代』(増田義郎、河出書房新社)
≪写真説明&Source≫
◎あしなが育英会の奨学生のつどい(同会の公式サイトから)
http://www.ashinaga.org/activity/index.html
*メールマガジン「風切通信 40」 2017年10月31日
今朝の朝日新聞(10月31日)に掲載された「耕論 リベラルを問い直す」というオピニオン面を読んで、私は心底、ガックリ来ました。法政大学教授の山口二郎、教育社会学者の竹内洋、LGBT(性的少数者)コンサルタントの増原裕子の3人の意見を掲載して「リベラルとは何か」を論じていました。もちろん、3人とも識見豊かで、その主張にもそれなりに説得力がありました。が、問題はその人選です。
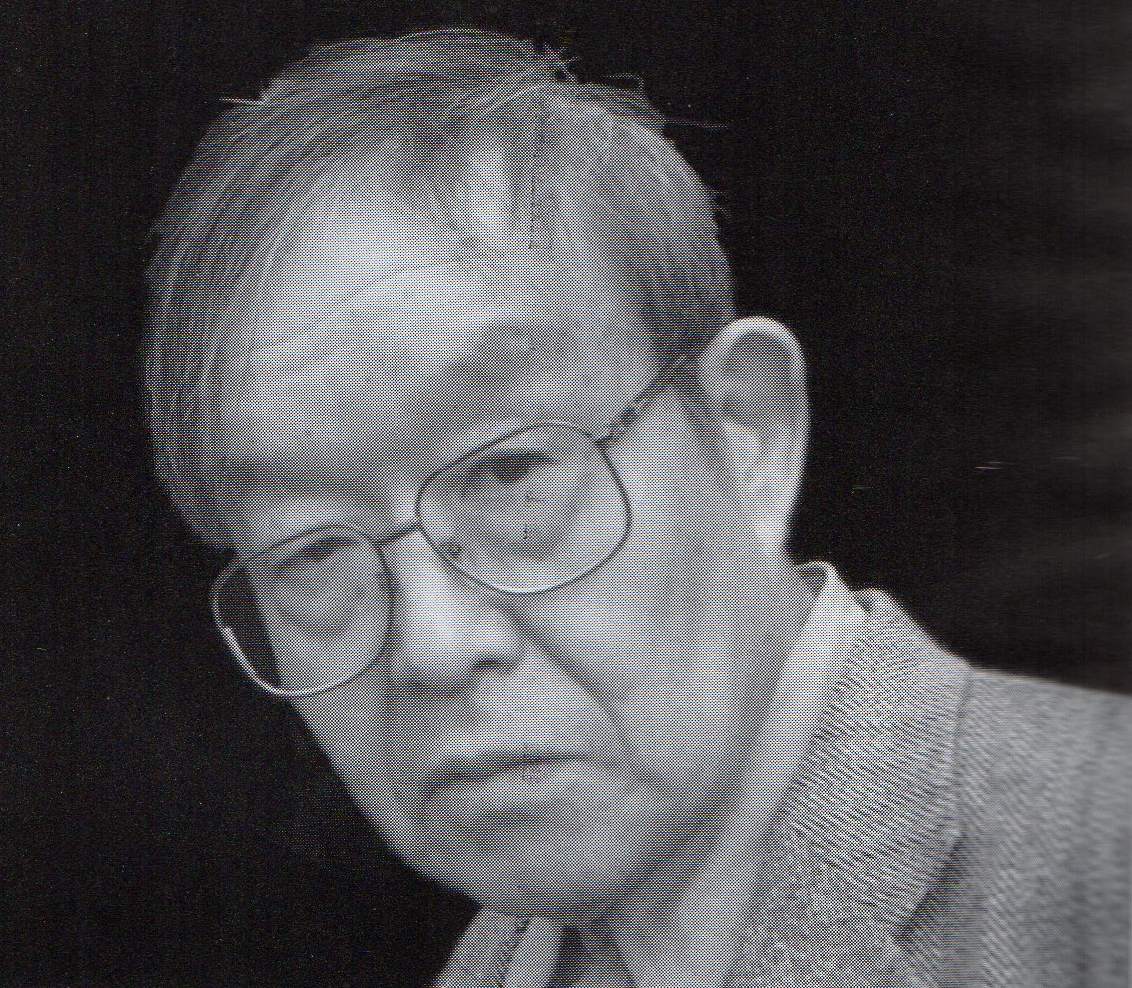
3人とも護憲派で、枝野幸男が率いる立憲民主党の支持者のようです。つまり、朝日新聞の社論の賛同者を3人並べているのです。これでは、議論を闘わせる「耕論」ではなく、「賛論」です。自分たちで作ったタイトルすら実践できず、同じ歌を別々の歌手に歌わせるような紙面をつくる編集者。慰安婦報道で問われた朝日新聞の体質とは何だったのか。たとえ自分たちと意見が異なっても、謙虚にその声に耳を傾ける。その努力を積み重ねる、と誓ったはずではなかったのか。
「リベラルを問い直す」というなら、立憲民主党の支持者、その批判者、さらに世界の潮流を見据えて日本の未来を語ることができる人物、たとえば、京都大学教授の山室信一や東京大学准教授の池内恵(さとし)、評論家の田中直毅のような論客を登場させて欲しい。それならば、今の日本の政治と社会を複眼で見つめ、世界の中での立ち位置を考えることもできるはずなのに。イデオロギーに縛られ、社の幹部にへつらうような翼賛紙面をつくっているようでは、この新聞の未来は危うい。そう思わざるを得ないオピニオン面でした。
思い出すのは、朝日新聞論説委員室に在籍していた2001年の「白黒論争」です。毎年、5月3日の憲法記念日に掲載する社説は論説主幹が執筆することになっていました。社説の内容はすべて、掲載の前に「昼会」と呼ばれるミーティングに提示して議論を闘わせるのが決まりです。論説主幹の原稿とて例外ではありません。当時の論説主幹は佐柄木(さえき)俊郎。筋金入りの護憲派で『改憲幻想論』という本を著しています。主張の眼目はサブタイトルにある「壊れていない車は修理するな」です。社説の原稿もそれに沿った内容でした。
論説委員室の改憲派、元ウィーン支局長の大阿久尤児(ゆうじ)はこの社説原稿を厳しく批判しました。「できて半世紀以上もたつ憲法を一字一句直すな、というのは無理がある。時の流れを踏まえて、より良いものにするのは自然なことだ。実際、同じ敗戦国のドイツは何回も修正している」。諄々と諭すような口調でした。佐柄木は朝日新聞の伝統を踏まえて反論する。大阿久がそれを論破する。その春に論説委員になったばかりの私は「論説主幹の論理は破綻している」と感じ、心の中で大阿久に軍配を上げました。
議論は延々と続き、佐柄木も大阿久も次第に感情的になっていきました。「白黒論争」に発展したのはその時です。佐柄木が「君たち国際派が何と言おうと、私の目の黒いうちは護憲の主張は変えない」と言い放ったのです。それに対して、大阿久は憤然として「目が黒いとか白いとか、そんな問題じゃない。こんな社説を載せたら、われわれの後輩が恥をかくのだ。それでいいのか」と叫んだのです。「白黒論争」とは私が勝手につけた呼称です。
論理的に破綻していても、社論をつかさどるのは論説主幹です。憲法制定の記念日にその社説はそのまま掲載されました。佐柄木の後を継いだ若宮啓文(よしぶみ)は護憲というより論憲の立場でした。「一字一句変えないと主張し続けるのは無理」と考え、佐柄木とよく議論していました。それでも、「安倍政権の下での改憲などもってのほか。今、改憲を唱えれば敵を利するだけ」と考え、護憲の論陣を張っていました。
憲法の施行から60年になる2007年の5月3日、若宮は論説主幹として21本の社説を一挙に掲載するという偉業を成し遂げました。21世紀を生き抜くための戦略。それを意識して21本にしたのです。どのような主張をするか。それを詰めるため、事前に社内の俊英を集めて「安保研究会」をつくり、熟議を尽くしたうえでの掲載でした。憲法9条については「変えることのマイナスが大き過ぎる」との主張。同じ護憲でも、ぐっと腰を下ろして構えた主張でした。
この安保研究会での議論も忘れられません。朝日新聞の俊英とは言えない私もメンバーになっていました。「翼賛会議」になるのを避けるための彩りとして加えられた、と理解しています。憲法改正が議題になった大会議室での議論はさして活発でもなく、「それでは、今言ったような線で護憲の主張をします」とまとまりかけました。私の脳裏に敬愛する大阿久の顔が浮かび、「これで議論を終わらせてはいけない」と思って改憲論を唱え、次のような言葉で締めくくりました。「このまま護憲を主張し続けるのは自殺行為ではないか」。会議室はシーンとなり、司会者の取り繕うようなコメントで終わりました。「自殺」ではなく、「心中」の方が適切だったかもしれません。
大阿久も私も改憲論者ですが、もちろん、自民党の保守派や読売新聞、産経新聞の改憲論には大反対です。とりわけ、「押し付け憲法だから改正すべし」という主張は唾棄すべき言説、と考えています。敗戦後、マッカーサー司令部に憲法の改正を求められた当時の幣原(しではら)喜重郎首相は松本蒸治国務大臣に新憲法の起草を命じました。松本がとりまとめた憲法案は天皇について「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」と記していました。明治憲法にあった「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」の「神聖」を「至尊」に変えただけ。310万人あまりの同胞の命が失われたあの戦争の後も、為政者たちは天皇制をできるだけそのまま維持しようとしていたのです。
マッカーサーがあきれ果て、自分のスタッフに日本国憲法の草案をつくるように命じたのは当然のことです。「たった1週間で書かれた憲法」という批判もあります。が、これも正確ではない。米軍は占領後の日本統治を考え、半年も前から若手の憲法学者に研究させていました。日本軍が竹やりで「本土決戦」を呼号していた頃、米軍は法学者を動員して新憲法の準備に着手していたのです。これも、彼我の国力の差を無残なまでに物語るエピソードの一つでしょう。
マッカーサーに提示された憲法案に当時の為政者はどう応じたのか。彼らは「天皇を戦犯訴追から守り、その地位を保障してもらうこと」で頭がいっぱいだったのではないか。それが叶うと知り、彼らはわずかな修正をほどこしただけで国会に上程し、国会議員も諸手を挙げて賛成しました。それが歴史的な事実です。「押し付け憲法論」を主張するなら、そうした歴史も一緒に語らなければ、公正とは言えない。
哀しいことですが、戦争に敗れた日本の為政者には、新しい憲法を書く力はありませんでした。与えられるしかなかった憲法。国民の多くはそれを支持し、銃剣で蹂躙された近隣の国々にも安心感を与えました。時代に合わせて、憲法は修正されてしかるべきです。けれども、それは焼け跡の中で産声をあげた憲法を抱きしめ、戦後の成長の中で果たした大きな役割に心から敬意を表したうえでのことでなければならない、と思うのです。
先のコラムで私は「北海油田の開発に苦しむイギリスは世界の英知を集めることにした」と書きました。荒れる海に石油プラットフォーム(掘削櫓)を建設するために、彼らは世界の英知を集めたのです。私たちに、この国の礎となる新しい憲法をつくるために世界の英知を集める覚悟はあるのか。憲法試案を発表した読売新聞にそれだけの覚悟はあったのか。
大阿久尤児はガンを患い、退社して間もなく63歳でこの世を去りました。息を引き取る間際まで穏やかに振る舞い、好きな将棋を指していました。潔い死でした。送別の会では、「白黒論争」を交わした佐柄木俊郎が弔辞を読みました。「君は実によく闘いました。大国の横暴や偏狭なナショナリズムをあおるメディアと闘い、体を何度もメスで切り刻まれながら、繰り返し襲い来る病魔と闘った。いまは、ただ安らかにお休みください。そのことだけを心から念じています」
大阿久が言葉を発することができるなら、皮肉っぽい笑みを浮かべながら、こう言うのではないか。「後輩たちは苦労してるんじゃないの。だから言っただろ、あの時」
(敬称略)
【追補】このコラムについて、複数の朝日新聞関係者から「竹内洋氏は保守の論客で改憲論者です。立憲民主党の支持者ではありません」との指摘を受けました。オピニオン面の論評で、竹内氏は立憲民主党について「反対だけの党になったり、数合わせに走ったりせず、自民党に柔軟な態度で臨み、だからこそ自民党が無視はできないような、存在感のある『外部』になってほしいと思います」と語っていました。私は「立憲民主党への辛口の応援」と受けとめたのですが、「自民党が勝ち過ぎるのは良くない」と考えての論評だったようです。
≪参考文献&サイト≫
◎2017年10月31日付の朝日新聞朝刊オピニオン面
◎『思想課題としてのアジア』(山室信一、岩波書店)
◎『現代アラブの社会思想』(池内恵、講談社)
◎『改憲幻想論』(佐柄木俊郎、朝日新聞社)
◎『詩人が新聞記者になった 追悼・大阿久尤児』(尚学社)
◎『地球貢献国家と憲法 提言・日本の新戦略』(朝日新聞論説委員室編、朝日新聞社)
◎『闘う社説』(若宮啓文、講談社)
◎ウェブ上の「『日本国憲法の制定過程』に関する資料」(衆議院憲法審査会事務局)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi090.pdf/$File/shukenshi090.pdf
◎読売新聞の憲法改正試案(同社の公式サイトから)
https://info.yomiuri.co.jp/media/yomiuri/feature/kaiseishian.html
≪写真説明&Source≫
◎ありし日の大阿久尤児(『詩人が新聞記者になった』から複写)
*メールマガジン「風切通信 39」 2017年10月25日
総選挙での自民党の圧勝をどう受けとめればいいのか。新聞を読みながら、つらつら考えました。古巣の朝日新聞には「なるほど」とうなずく解説も、「そういう見方もあるのか」と目を見開く記事も見当たりませんでした。世界と日本を見渡す「鳥の目」の記事もなければ、時代の流れを映し出す「魚の目」の論評もない。どのページをめくっても、「虫の目」の記事ばかり。「選挙の朝日」と呼ばれた日は遠い。

安倍首相が大嫌いであることだけはよく分かりました。23日付朝刊の1面で編成局長が「おごりやひずみが指摘され続けた『1強政治』を捨て、政治姿勢を見直す機会とすべきだ」と首相に苦言を呈し、「この先の民意の行方を首相が読み誤れば、もっと苦い思いをすることになるだろう」と警告していましたから。「自分たちは民意の行方がきちんと読めているのかい」と茶々を入れたくなりましたが。
もとより、安倍首相の「お友達新聞」の読売は読むところが少ない。それでも、「ここは友として『勝って兜の緒を締めよ』と言っておかねばなるまい」と思ったか。23日付朝刊の社説の袖見出しは「『驕り』排して丁寧な政権運営を」でした。「驕り」にかぎかっこを付けたのは友達としての配慮でしょう。「私はそんな風には思ってないけど、世間でそう言われてますよ」という、優しいかぎかっこ。
朝日と読売が「新聞」ならぬ、聞きふるした「旧聞」を書き連ねているのに対して、25日付の毎日新聞朝刊には「新しい息吹」を感じました。1面の連載「安倍続投を読む」の1回目は中西寛・京大教授(国際政治)からの聞き書き。中西教授は、自民党圧勝の背景には「若年層が新しい自民党支持層になっている事情もある」と語り、「昭和を知らない世代が『安倍政権になって社会・経済が安定した』と認識しても不思議ではない」と論評しています。
今の10代、20代の若者たちは、高度経済成長もバブル景気も経験していません。もの心がついた頃には、日本経済はすでに右肩下がりになっていました。中学、高校と進むにつれ、少子高齢化はますます深刻になり、東日本大震災では「危機に対応できない国」であることを肌で知りました。共同通信の出口調査によれば、10代の有権者の自民党支持率は4割で、全有権者平均の3割台半ばよりも高いのだとか。
これを「若者は世間を知らないから」「判断力が足りないから」と見下すのは簡単です。けれども、希望が見出しにくいような社会を作ったのは誰なのか。「希望」の名を掲げながら、すぐさまそれを粉々に打ち砕くような政治をしているのは誰なのか。そうやって見下す大人たちではないか。
いつの時代であれ、若者を未熟者と見下すのは根本的に間違っている。彼らは未来について年長者よりはるかに真剣なはずです。当然です。「人生の一番いい時期」を過ぎた世代と違って、彼らにはこれから「長い未来」があるのですから。50年後、100年後を真摯に考えているのは古い世代ではなく若者たちなのだ、と認めることから始めなければなりません。
毎日新聞はそれを正面から受けとめ、紙面に刻もうとしています。1面の連載を支えるように、社会面では10代の有権者の投票行動とその理由を聞き取り、詳しく紹介しています。「理念や政策の違う政党に合流できる政治家が何を考えているのかわからない」「日本は戦後で一番、実質的な危険にさらされている」といった声を掲載し、憲法改正についても「時代に合ったものに」と答える声が目立った、と報じました。
数字データによる選挙結果の分析や解説より、こういう一人ひとりの言葉の方が読む者の心に沁みていく。新聞記者であれ雑誌記者であれ、もの書きならば、誰もが感じていることです。要は、それを愚直に試み、紙面にしていくかどうか。「虫の目」の記事が「鳥の目」や「魚の目」の記事より光るのは、こういう時です。
毎日新聞は乱脈経営がたたって、1970年代に一度、経営が破綻しています。それ以降も苦しい状況が続いているようです。それゆえか、時折、恐れることなく、新しいことに挑戦しようとする気概を感じます。朝日新聞や読売新聞の行間からは感じない何かがある。それがある限り、経営陣さえしっかりしていれば、毎日新聞が昔日の輝きを取り戻す可能性はある。そう思わせる紙面でした。
≪参考記事≫
◎10月23日から25日の朝日、読売、毎日新聞(山形県で配達されているもの)
≪写真説明&Source≫
◎安倍晋三首相
http://news.livedoor.com/article/detail/13790732/
*メールマガジン「風切通信 38」 2017年10月19日
英国人の作家、カズオ・イシグロについてのコラムを書いた際、父親の石黒鎮雄(しずお)のことがとても気になりました。どんな研究者なのか。なぜ妻と幼い子どもたちを連れて40歳で英国に渡ったのか。海洋学を専門とする大学時代の友人に調べてもらったところ、父親が英国に渡った詳しい事情が分かりました。

石黒鎮雄は1920年に商社員をしていた石黒昌明の子として上海で生まれました。戦前、陸軍航空士官学校で学び、その後、九州工業大学を卒業して東京大学で博士号を取っています。博士論文のタイトルは「エレクトロニクスによる海の波の記録ならびに解析方法」です。「エレクトロニクス」という表現が時代を感じさせます。戦後の日本では、普通の研究者がコンピューターを入手することは困難でした。そこで、さまざまな電子機器を駆使して研究に活かしたのでしょう。手先の器用な人だったようです。
彼は「潮位と波高の変化」を研究テーマにしていました。たとえば、ある海域で海難事故が多発するのはなぜなのか。それを調べるため、その海域の海底を模したモデルを作り、実際に起こる波を再現してみる。そして、その成果を踏まえて、現場の海底に消波ブロックを設置して流れを変え、海難事故を減らす、といった業績を上げています。長崎海洋気象台にいた時には、地元の人たちが苦しめられていた長崎湾の海面の大きな変動の解明にあたったりもしています。
その研究成果に注目したのがイギリス国立海洋研究所の所長、ジョージ・ディーコンでした。1960年当時、イギリスは北海油田の開発に躍起になっていました。第二次大戦で国力を使い果たし、戦時国債の支払いに追われる国にとって、石油を自力で確保することは最優先課題の一つだったからです。問題は、油田が見つかった北海が荒れ狂う海だったこと。海底油田を採掘するためには、巨大なヘリポートのような石油プラットホーム(掘削櫓)を建設しなければなりません。その建設自体が至難の技でした。しかも、完成後は、どんなに海が荒れ狂っても、壊れることは許されません。大規模な海洋汚染を引き起こすからです。
苦難に立ち向かうイギリスは、世界中の英知を結集することにしました。そのリサーチの目が石黒鎮雄の論文に辿り着き、彼を国立海洋研究所に招くことになったわけです。鎮雄はその招聘に「研究者としての冥利」を感じたはずです。渡英した1960年当時、若者の留学はともかく、研究者が家族連れで海外に出て行くことは珍しいことでした。妻静子と子ども3人(カズオ・イシグロと2人の姉妹)を抱えての海外生活。期するところがあったに違いありません。家族が日本に一時帰国したがっていることは分かっていても、それに応じる余裕はなかったのでしょう。波の研究者として生き、2007年に没しました。
イギリスを石油輸出国にした北海油田。その開発の苦しみが石黒鎮雄をイギリスに引き寄せた。幼いカズオ・イシグロは父の転勤に翻弄され、異様なほどに長崎を懐かしみ、日本に焦がれる少年になりました。父と北海油田の出会いが時を経て、イシグロワールドを醸し出したのです。この世の巡り合わせの不思議さを感じさせる物語でした。(敬称略)
≪参考文献&サイト≫
◎エッセイ「イギリスに渡った研究者 シズオ・イシグロをさがして」(海洋学者、小栗一将)
http://www.jamstec.go.jp/res/ress/ogurik/essay2.html
◎「海洋学者 Shizuo Ishiguro、日本出身地球物理学者の波」(masudako)
http://d.hatena.ne.jp/masudako/20121014/1350215515
◎石黒鎮雄の博士論文「エレクトロニクスによる海の波の記録ならびに解析方法」(論文検索サイトの検索結果のみ。論文そのものは国会図書館にある模様)
http://ci.nii.ac.jp/naid/500000493143
◎ウィキペディア「陸軍航空士官学校」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%A3%AB%E5%AE%98%E5%AD%A6%E6%A0%A1
◎カズオ・イシグロの父を招聘した英国立海洋研究所長、ジョージ・ディーコン(wikipedia、英語)
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Deacon
≪写真説明&Source≫
◎海底油田を採掘するために建設された北海油田の石油プラットフォーム
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E6%B2%B9%E7%94%B0
*メールマガジン「風切通信 37」 2017年10月17日
日本生まれの英国人作家、カズオ・イシグロの代表作『日の名残り』を読んだ時、私は不思議な感覚を味わいました。舞台は第二次大戦前後のイギリス、貴族のダーリントン卿に仕える執事スティーブンスの物語です。第一次大戦の惨状を知るダーリントン卿は新たな戦争を避けるため、ドイツとイギリスが共存する道を探ろうとします。国王や首相をヒトラーに会わせるべく、卿はドイツとのパイプ役となって動くという筋立てです。

英独の仲介を試みるダーリントン卿について、貴族の友人は「卿は紳士だ。ドイツとの戦争を戦った。敗れた敵に寛大に振る舞い、友情を示すのは、紳士としての卿の本能のようなものだ」と語りかけ、ドイツはその高貴な本能を汚い目的のために利用しているのだ、それを黙って見ているのか、と執事のスティーブンスに迫ります。それに対して、長く卿に仕えてきたスティーブンスはこう答えます。「申し訳ございません、カーディナル様。私はご主人様のよき判断に全幅の信頼を寄せております」
物語は、貴族の館ダーリントン・ホールを舞台に淡々と進む。卿は対独宥和派とさげすまれ、失意のうちに世を去る。派手な立ち回りは何もない。ロマンスもごく淡いものが少し描かれるだけ。文章も平易です。普通なら途中で投げ出してしまうところですが、なぜかやめることができず、そのまま読み通してしまいました。最初に手にした本で、私も「イシグロワールド」に引き入れられてしまったのかもしれません。
次に読んだ『わたしたちが孤児だったころ』はもう少しドラマチックでした。戦火にさらされ、混乱きわまる1930年代の上海。この街で失踪した両親の行方を追うイギリス人探偵の物語です。戦場の状況が描かれ、父と母がなぜ失踪したのか、少しずつ解き明かされていきます。イシグロ作品の中では、一番ドキドキワクワクする小説かもしれません。が、それも普通のミステリー小説に比べれば、きわめて地味でイシグロらしい。
生まれ育った長崎と並んで、上海はイシグロにとって特別な街です。祖父の石黒昌明は滋賀県大津市の出身で、上海の名門私大・東亜同文書院を卒業した後、伊藤忠商事に入社し、上海で働いていました。父の石黒鎮雄はこの上海で生まれ、東大で学んだ海洋学者です。カズオ・イシグロは父親が長崎海洋気象台に勤務していた時に誕生し、5歳まで長崎で暮らしました。その父がイギリス国立海洋研究所に招かれ、家族で渡英しました。
長崎での穏やかな暮らしは突然、断ち切られてしまいました。彼がかなりの映画好きで小津安二郎の作品を繰り返し観たのは、長崎の記憶と重なるところがあるからなのでしょう。英国で勤め始めた父は何度も「来年は日本に帰るから」と約束したそうですが、それが果たされることはありませんでした。懐かしい長崎の思い出を何度も何度も切なく思い出していたのです。それが彼の作家としての礎になったと思われます。
カズオ・イシグロはイギリスで教育を受け、ケント大学とイースト・アングリア大学大学院で文学を学んで作家になりました。最初の作品『遠い山なみの光』を出版した1980年代初めに英国籍を取得しています。彼をよく「日系英国人作家」と表現します。その通りなのですが、彼の場合は5歳で故郷から不意に引き離され、長崎の記憶を忘れまいともがき続けたという点が特異です。むしろ、ディアスポラ(故郷喪失者)と呼びたくなります。
『日の名残り』のあとがきで翻訳家の土屋政雄は、カズオ・イシグロが最初の2冊の作品(『遠い山なみの光』と『浮世の画家』)について、次のように語ったと紹介しています。「私の日本を2冊の本に封じ込め、初めて日本を訪れる気持ちになった」。土屋によれば、最初の2作は「彼が自分の日本人性を再確認し、それに形を与えるための作業だったといえるのではなかろうか」という。心の中の日本と折り合いをつけ、もはやその喪失を心配しなくてもよくなって、第3作『日の名残り』に進んだのだと。
彼はまず、自らの日本への追憶を小説という作品にして、それから世界に飛び出していったのです。彼が作品に込めた思いは『日の名残り』の執事が語る言葉に象徴的に示されています。執事のスティーブンスはこう語るのです。
「私は選ばずに、信じたのです。私は卿の賢明な判断を信じました」「私どものような人間は、何か真に価値あるもののために微力を尽くそうと願い、それを試みるだけで十分であるような気がいたします。そのような試みに人生の多くを犠牲にする覚悟があり、その覚悟を実践したとすれば、結果はどうであれ、そのこと自体がみずからに誇りと満足を覚えてよい十分な理由となりましょう」
読みながら、胸が熱くなったくだりです。2001年に来日して講演した際、カズオ・イシグロは別の言葉で自らの思いを語りました。「ひとはみな、執事のような存在だと思うのです」「人生はとても短い。振り返って間違いがあったと気づいても、それを正すチャンスはない。ひとは、多くの間違いを犯したことを受け入れ、生きていくしかないのです」(『AERA』2001年12月24日号)
ノーベル文学賞については、かつてこんな風に語っていました。「それほど重要な賞でしょうか。科学分野では権威はありますが、文学の世界では奇妙な賞だと思います。たしかに偉大な作家が受賞していますが、受賞後はあまり素晴らしい作品が書けていません。ノーベル賞の影響なのか、それともキャリアの終わりを迎えた人に賞が贈られているのか、私にはよく分かりません」
連続テレビドラマ『わたしを離さないで』の主演女優、綾瀬はるかと原作者カズオ・イシグロとの対談も味わい深い。主役のキャシーの生き方について質問した綾瀬に、彼はこう答えています。「キャシーは臓器提供のために作られたクローンで、閉ざされた、非常に特殊な環境で育ったわけですよね。外の世界の価値観を知らない。だから、過酷な運命も自然に受け入れる。現実の世界を見てみてください。今も様々な国で、本当に過酷な環境で生きている人が大勢います。彼らは天使なのではなく、必然としてその環境に適応し、精一杯生きている。自分が生きている意味を何とか築こうと奮闘している」
カズオ・イシグロを「記憶と追憶の作家」のように言う人がいますが、私は違うと思う。彼は「人が生きることの哀しみ」を描きたいのではないか。そして、その哀しみに寄り添い、そっと励ます。それが自分の役割、と考えているのではないか。ノーベル文学賞はその営みへの小さなご褒美、と受けとめているように思います。(敬称略)
≪参考文献・記事&サイト≫
◎『日の名残り』(カズオ・イシグロ、土屋政雄訳、中央公論社)
◎『わたしたちが孤児だったころ』(カズオ・イシグロ、入江真佐子訳、早川書房)
◎『忘れられた巨人』(カズオ・イシグロ、土屋政雄訳、早川書房)
◎『夜想曲集』(カズオ・イシグロ、土屋政雄訳、早川書房)
◎文芸ブログ「Living Well Is the Best Revenge」(ペンネーム、クリティック)
http://tomkins.exblog.jp/20864422/
◎ウィキペディア「カズオ・イシグロ」(日本語)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%BA%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%AD
◎Wikipedia 「Kazuo Ishiguro」(英語)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazuo_Ishiguro
◎ウィキペディア「東亜同文書院大学」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E5%90%8C%E6%96%87%E6%9B%B8%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6_(%E6%97%A7%E5%88%B6)
◎週刊誌『AERA』2001年12月24日号のカズオ・イシグロ日本講演に関する記事(伊藤隆太郎)
◎2009年7月20日の朝日新聞朝刊文化欄の記事「たそがれの愛・夢描く 初の短編集『夜想曲集』を出版」でノーベル賞について言及(土佐茂生)
◎2017年10月15日の朝日新聞朝刊読書欄の書評「忘れてはならない記憶の物語」(福岡伸一)
◎カズオ・イシグロと綾瀬はるかの対談記録(文春オンラインから)
http://bunshun.jp/articles/-/4425
◎2002年7月18日の朝日新聞夕刊のコラム・窓「望郷の念」(長岡昇)
≪写真説明&Source≫
◎作家カズオ・イシグロ
http://muagomagazine.com/1825.html
*メールマガジン「風切通信 36」 2017年10月12日
小池百合子という政治家のことを私が初めて強く意識したのは2004年のことでした。取材でエジプトを訪れた際、中東専門の記者から彼女の父親がカイロで日本料理店を経営していたことを教わりました。それだけなら、「ヘエーッ」で終わり、記憶に残ることもなかったのでしょうが、同僚はカイロ名物のハト肉の料理をほおばりながら、意外なことを口にしました。「彼女は国立カイロ大学の卒業生なんです」

エジプトに留学してアラビア語を学ぶ場合、多くはカイロ・アメリカン大学に行くとのこと。英語をベースにしてアラビア語を学ぶのです。どの国の言葉を学ぶにせよ、外国語はそれぞれに難しいものですが、同僚によれば、アラビア語は飛び抜けて難しい。アラビア語で行われる授業についていくのは普通の外国人にはとうてい無理なのだそうです。その理由は、アラビア語では文語と口語の乖離がはなはだしく、文語で書かれた文献を読みこなすことができないからです。
イスラム圏を旅すると、朝な夕なに街中のモスクから礼拝の呼びかけ(アザーン)が聞こえてきます。その呼びかけのアラビア語は、預言者ムハンマドが生きていた7世紀のアラビア語のままです。聖典のコーランももちろん、当時のアラビア語がそのまま使われています。しかも、敬虔なイスラム教徒は日々、それを唱えているのです。
そうした宗教的、文化的な背景があるためか、アラビア語圏の新聞や雑誌で使われている言語は、日常生活で使われているアラビア語とはかけ離れており、アラビア語を習得する場合には、口語のアラビア語と文語のアラビア語の二つを学ばなければなりません。日本に置き換えてみれば、文章では聖徳太子が生きていた頃の色合いが濃い日本語を学び、同時に現代の日本語も学ぶ、ということになります。そうしなければ、新聞ひとつ読むことができないからです。「それは大変なことだ」と納得しました。
アラビア語を学ぶことを決めた若き小池百合子は、在籍していた関西学院大学を中退してカイロ・アメリカン大学に進み、ここでアラビア語を習得した後、国立カイロ大学の文学部で4年間みっちり勉強して卒業しています。つまり、彼女のアラビア語は「話せる」というレベルではなく、「仕事で使える」レベルだということです。
なぜ、アラビア語だったのか。小池百合子編著『希望の政治』(中公新書ラクレ)で、彼女自身がその理由を明らかにしています。
「振り返ってみると、私は高校生の頃から自己マーケティングをやっていました。日本における女性の居場所、女性が今後伸びる方向、その中で自分はどういう位置にいて、10代で何をし、20代でどういうスキルを身に付けるか、と。自分を一種の『商品』に見立て、いわば商品開発を考えるのです。我ながら怖い女子高生でした」(p37)
怖いかどうかはともかく、高校生の頃から「ひとかどの人物(a man of something)」になりたいという志を抱いていたのは立派と言うべきでしょう。彼女の場合は、a woman of something と記すべきかもしれません。英語でも中国語でも、ドイツ語でもフランス語でもなく、これから伸びる言語はアラビア語である、と判断したところに、私は「勝負師としての小池百合子」の面目躍如たるものを感じます。
彼女が働く女性としてステップアップしていった過程を見ても、アラビア語は決定的な役割を果たしています。まずアラビア語の通訳として働き始め、日本テレビがリビアのカダフィ大佐やPLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長と会見する際のコーディネーターをしています。その縁で、政治評論家・竹村健一のアシスタントとしてテレビの世界に入り、次いでテレビ東京のビジネス番組のキャスターに抜擢されました。東京とニューヨーク、ロンドンの三大市場を結ぶ経済番組のキャスターとしての仕事は、彼女に世界経済の動向を知り、日本だけでなく、世界のビジネスリーダーと知り合う機会を与えてくれました。
政界入りは1992年、40歳の時です。日本新党を立ち上げた細川護熙(もりひろ)熊本県知事に請われて参議院議員になってからの「政界渡り鳥」ぶりは有名です。細川の日本新党から小沢一郎が率いる新進党へ、さらに自由党、保守党を経て自民党に入り、昨夏、東京選出の衆議院議員の地位を投げ打って都知事選に立候補して、当選したことはご承知の通りです。
言葉に対する感覚にも鋭いものがあります。前掲書で、小池は尊敬する人物として台湾総督府の民政長官や満鉄初代総裁、第7代東京市長をつとめた後藤新平を挙げ、彼が残した「人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そしてむくいを求めぬよう」という言葉を胸に秘めている、と述べています(p110)。これは「渡り鳥」批判に対する彼女なりの反論でもあるようです。私の志は何一つ変わっていない、政党の方が時代に揺さぶられてコロコロと変わっただけ、と言いたいのでしょう。
読売新聞記者から小池の秘書に転じた宮地美陽子(みよこ)が出版した『小池百合子 人を動かす100の言葉』(プレジデント社)では、この後藤新平の言葉とともに、小池が好きな「三つの目」が紹介されています(p106)。
「鳥の目で物事を俯瞰し、虫の目で細やかな部分を見て、魚の目でトレンドをつかむ」
「三つの目」の二番目は「蟻の目」というのもあるようですが、あらためて政治家・小池百合子の好きな言葉として読むと、味わい深い。群れなす魚が潮の流れを敏感に感じ取るように、私は時代の潮流を感じ取り、大きな流れに乗りたい、といったところでしょうか。
「三つの目」は歴史を学び、歴史を考える場合にも欠かせません。その時代を俯瞰し、人々の動きをつかむだけでなく、微細なことも知る必要があります。そこにその時代の本質的なものが現れることがあるからです。視点で言えば、勝者と敗者、賢者の三つの目から歴史を見ることも大切です。
そういう観点から判断すると、小池の歴史認識はあやうい。あやういというより、著しくバランスが悪い。今年、関東大震災時に虐殺された朝鮮人犠牲者の追悼式に都知事名の追悼文を送るのをやめたのはなぜなのか。去年は送っていたのに。石原慎太郎や舛添要一も追悼文を寄せたのに。会見で記者に問われて、小池は「昨年は事務的に(追悼文を送るとの決裁書を)戻していた。今回は私自身が判断をした」「さまざまな歴史的な認識があろうかと思う。亡くなられた方々に対して慰霊する気持ちは変わらない」と述べました。
歴史認識は政治家の資質を判断するうえで、とても重要な要素です。政治家の根っこにかかわることだからです。日本語とアラビア語、英語という三つの言葉を自在に操り、「三つの目」を大切にしている政治家が朝鮮人虐殺に疑問を呈するような言動をするのはなぜか。国際経済をよく学び、政界の権謀術策にもまれてきた政治家がなぜ、歴史をないがしろにするような発言をするのか。私には理解できません。
歴史認識に疑問を感じるようでは、彼女が選んだという衆議院選挙の候補者たちまで、「大丈夫なのか」と心配になってきます。小池百合子が「稀代の勝負師」であることは間違いなさそうですが、歴史に残る政治家であるかどうかは分かりません。後世、「世渡り上手な権力亡者だった」と評されるおそれ、なしとしない。 (敬称略)
≪参考文献&サイト≫
◎『希望の政治 都民ファーストの会講義録』(小池百合子編著、中公新書ラクレ)
◎『小池百合子 人を動かす100の言葉』(宮地美陽子、プレジデント社)
◎『女子の本懐 市ヶ谷の55日』(小池百合子、文春新書)
◎関東大震災の朝鮮人犠牲者追悼式に追悼文を送らないことに決めた小池知事の記者会見を報じるハフィントンポスト
http://www.huffingtonpost.jp/2017/08/26/yuriko-koike-great-kanto-earthquake-of-1923_a_23186257/
◎冒頭に記した私のエジプト出張は、朝日新聞・別刷りbe「ことばの旅人 開け、ゴマ!」の取材、執筆のため。2004年7月17日付の別刷りに掲載された企画記事は次のサイトでご覧ください。
http://www.bunanomori.org/NucleusCMS_3.41Release/?itemid=37
≪写真説明&Source≫
◎関東大震災時の朝鮮人虐殺問題について定例記者会見で答える小池知事(8月25日)
http://blogos.com/article/242368/
2004年7月17日付 朝日新聞 別刷りbe「ことばの旅人」
キリスト教と同じく、イスラム教でも、人間の始祖はアダムとイブである。聖典のコーランに、2人が禁断の木の実を食べて楽園を追われる話が出てくる。旧約聖書とほぼ同じ内容だ。
ただ、コーランでは、追放される2人に神がこう宣告する。
「落ちて行け。お互い同士、敵となれ。お前たちには地上に仮の宿と儚い一時の楽しみがあろう」(井筒俊彦訳)

船上でのベリーダンス。この日の踊り子はアルゼンチン人 (撮影:カレド・エル・フィキ〈エジプトの写真家〉)
厳しい言葉である。男と女、そして性についての、イスラムの厳格な教えを凝縮したような言葉だ。
イスラム学の総本山、カイロのアズハル大学のモハマド・オスマン教授は言う。
「性は結婚した男女間のものでなければなりません。婚姻外の交渉は許されない。性的な感情をかき立てるようなこともいけない。女性に顔と手以外は肌を見せないように求めているのも、そのためです」
昼間、エジプトの人たちは比較的よく戒律を守っている。だが、日が沈み、涼しい川風が吹く夜になると、イスラムの教えは闇の中にのみ込まれていく。
ナイル川に浮かぶ船上レストランで、ピラミッドに近いナイトクラブで、肌もあらわなベリーダンサーが踊りまくる。
「私たちは第4のピラミッドなのよ」
売れっ子のダンサーが豪語した。「外国人観光客がエジプトに来るのは、ギザの3大ピラミッドに加えて、私たちの踊りがあるから」と自負する。
観光だけではない。結婚式や誕生祝いでも、ベリーダンスは人気だ。暮らしの中に深く根付いている。
謹厳なオスマン教授に「伝統文化の一つと言えるのではないか」と尋ねてみた。教授は言下に否定した。「ただ楽しみを追い求めるものは文化とは言えない」。「でも人気があります」。なお食い下がる。教授は少し不機嫌な顔になった。
「この世には犯罪が絶えない。だが、絶えないからといって合法になるわけではない。それと同じことです」
犯罪と同じ扱いにされてしまった。
実は、アラビア文学の傑作とされる千夜一夜物語も、エジプトではベリーダンサーのような扱いを受けている。
一般には、「開け、ゴマ!」の呪文で知られる「アリババと40人の盗賊」や「アラジンと魔法のランプ」といった子供向けの話が有名だが、大人向けの艶話もふんだんに盛り込まれているからだ。
論説委員・長岡 昇
ゴマは「美の象徴」
出だしからして、おどろおどろしい。
千夜一夜物語は、ペルシャ王妃の密通で幕を開ける。不貞を知った王は打ちひしがれ、同じように妻に裏切られた弟と共に旅に出る。と、今度は旅先で魔王の愛人から淫らな誘いを受ける。
事を終えて、愛人はささやく。
「女がこうと思い込んだら、誰にも引きとめることはできないのよ」
魔王すら裏切られる。王の女性不信はここに極まる。旅から戻ると王妃を殺し、ひと晩ごとに乙女を召して殺すようになる。そこに才女シャハラザードが登場して、千夜一夜にわたって奇想天外な物語を語り続ける、という筋立てだ。
もともとが枕辺での夜話である。口語体なので、表現もどぎつい。
カイロ大学の文学部で千夜一夜物語を教材に使ったところ、女子学生の親たちから「とんでもない」と抗議される事件があった。1984年のことだ。
授業を担当したアフマド・シャムスディン教授は「大学当局から教材に使わないように圧力をかけられた」と振り返る。学生たちが擁護に回ったこともあって、大学側は要求を取り下げたが、それ以降、授業ではあまり使われなくなった。
攻撃される自由奔放な物語
翌85年には、千夜一夜物語を出版した業者がわいせつ罪で起訴され、有罪判決を受けた。控訴審で無罪になったものの、イスラム強硬派は勢いづき、しばらく出版が途絶えた。
詩人のマサウード・ショマーン氏は「彼らは、艶っぽい話だけを取り上げて攻撃する。ろくに読んでもいない。先達が残してくれた貴重な財産なのに」と嘆く。
千夜一夜物語は、民衆の日々の営みの中から生まれ、長い歴史にもまれながら今のような形になっていった。愛と憎悪、希望と欲望、人の気高さといやらしさ。それらすべてを、想像力の翼を思い切り広げて、これほど自由奔放に描ききった物語がほかにあるだろうか。
なんとも不思議な物語の数々。
「アリババと40人の盗賊」も、謎に満ちている。盗賊たちは、金銀財宝を隠した洞穴の岩を開ける時の呪文を、なぜ、「開け、ゴマ!」にしたのか。小麦やエンドウ豆では、どうして開かないのか。
ものの本には「ゴマの栽培は、古代エジプト時代までさかのぼることができる。搾油のほか、薬草としても使われた貴重な作物」とある。が、古くて貴重な作物ならほかにもある。
どこで生まれた物語なのかも分かっていない。エジプト芸術学院のサラーフ・アルラーウィ助教授によると、スーダン国境のハライブ地方の語り部たちは「ここが物語の発祥地だ」と言い張っているという。もともと洞穴の多い土地で、「アリババの洞穴」と呼ばれるものもあるとか。
そういえば、ゴマの原産地はアフリカのサバンナというのが定説だ。スーダンも含まれる。洞穴があり、しかもゴマのふるさとに近い。身を乗り出したが、どうも話ができすぎている。
日本とエジプトの研究者に呪文のいわれを聞いて回っても、謎は深まるばかり。困り果てて、カイロの旧市街にあるスパイスと薬草の老舗「ハラーズ」を訪ねた。
強権政治が文化を守る役割
主人のアフメド・ハラーズ氏は、笑みを浮かべながら「誰にも分からないでしょう。謎は謎のままにしておけばいいではありませんか」と慰めてくれた。そして、ゴマを使った面白い表現を教えてくれた。
アラビア語では、美しい女性のことを「ゴマのようね」と言って、ほめる。目がパッチリして、ふくよかなことがエジプト美人の条件だが、鼻と耳は小さい方が好まれる。
ゴマは、小さくて美しいものの象徴なのだった。
90年代に入って、エジプト政府はイスラム組織への締め付けを強めた。日本人も多数犠牲になったクルソールでの外国人観光客襲撃事件の後、弾圧はさらに苛烈になった。今なお続く非常事態宣言の下で、多くの活動家が逮捕令状もないまま身柄を拘束されている。
宗教勢力からの圧力が弱まり、千夜一夜物語の出版は細々とながら再開された。宗教勢力と世俗勢力が歩み寄って文化を育むのではなく、強権政治が文化を守る。悲しいことだが、それがエジプトの現実だ。
「開け、ゴマ!」。盗賊たちが残した呪文は、心の扉を開くことができずにもがく社会に、皮肉な隠喩となって響き渡る。
****************************************
出典
千夜一夜物語の起源についてはインド、ペルシャ、アラブの3説があり、決着がついていない。特定の作者や編者のいない説話文学で、エジプトで発見された9世紀の写本が最古。各地の説話を取り込みながらバグダッドやカイロで内容が発展し、15世紀ごろ今に伝わる形になった。
18世紀の初め、フランスの東洋学者アントワーヌ・ガランがアラビア語の写本から仏語に翻訳して紹介、中東以外の世界に広まった。19世紀になると、アラビア語の印刷本も登場した。英語版では「アラビアン・ナイト」の書名が付けられた。
日本では、明治8(1875)年に「暴夜物語」の書名で英語版から初めて部分訳された。仏語版と英語版からの完訳出版の後、慶応大学の前嶋信次教授(故人)と四天王寺国際仏教大学の池田修教授が、1966年から26年かけてアラビア語原典から完訳し、平凡社東洋文庫から出版した(さし絵は同文庫「アラビアン・ナイト別巻」から)。
ガランの翻訳以来、アラビア語の写本探しが続けられ、ほとんどの説話の原典が見つかった。「アラジンと魔法のランプ」と「アリババと40人の盗賊」の原典も、それぞれ19世紀末と20世紀初めに発見と伝えられたが、その後の研究で偽物と判明した。原典はともに未発見。
****************************************
訪ねる
ベリーダンス=写真=はカイロ市内のホテルやピラミッド近くのナイトクラブで毎日、演じられている。だが、ショーは午前1時ごろから未明まで。そんな時間にやるのは、地元の人や湾岸産油国からの観光客が日中は暑いので体を休め、涼しい夜にくつろぐため。これでは、欧米や日本からの観光客はなかなか行けない。そこで、夕食をとりながらダンスを鑑賞できる船上レストランがある。ナイル川を2時間ほど上がり下りする間に、ベリーダンスとスーフィーダンス(旋舞)が演じられる。最高級の船上レストランで、酒代を含めて1人3千円から4千円ほど。
*メールマガジン「風切通信 35」 2017年9月29日
衆議院の解散、総選挙を伝える今朝の新聞各紙の見出しを目にして、思わず溜め息を漏らしてしまった方も多いのではないでしょうか。1面の見出しは、毎日新聞が「自民vs希望 政権選択」、朝日新聞は「安倍政治5年問う 自公vs.希望vs.共産など」、読売新聞は「自公と希望 激突」、日本経済新聞は「安倍vs.小池 号砲」でした。

「なんだ、これは」という印象です。毎日は「政権選択の選挙」と言い、日経は「安倍vs.小池」と言うけれど、希望の党を率いる小池百合子氏は東京都知事であって、衆議院議員ではない。従って、現時点では首相候補になり得ない。自民党以外の政権を望むにしても、誰を首相にかつぐのかはっきりしない政党に投票して、それで「政権選択」と言えるのでしょうか。
なんでもいいから、とにかく安倍首相を政権の座から引きずり降ろしたい朝日新聞の気持ちは分かる。にしても、「自公vs.希望vs.共産など」はないだろう。なぜ、素直に「自公vs希望」とうたえないのか。「vs」の後のピリオドもいらないし、「共産など」も余計でしょう。それを省くことができないのは、いつまでたっても律儀なうえに、共産党と共産主義への郷愁を捨てきれない人たちがまだたくさんいる、ということか。
読売新聞は1面肩に前木理一郎・政治部長の「政党政治の否定だ」という論評を掲げました。「民主党時代に政権を担った野党第1党が一夜にして結党間もない新党に身売りするという、前代未聞の事態だ。理念や政策を度外視した野合で、政党政治の否定にほかならない」と歯切れがいい。けれども、民主党だって、安全保障政策や原発問題で意見がバラバラな議員が寄り集まった、理念も政策もあやふやな政党でした。いまさら、「政党政治の否定だ」と力まれても、鼻白んでしまいます。
日本経済新聞は「号砲」という勇ましい見出しを掲げましたが、内容はいつものように穏やかです。2面の社説で「実感が伴う景気回復まで消費増税は立ち止まる。議員の定数や報酬は縮減。原発ゼロを目指す」という小池氏の基本的な考えを紹介しつつ、「(もっと)具体性のある総合的な政策を早くまとめてもらいたい」と注文を付けています。ドタバタでこうなってしまったのは今さら変えようがない。せめて選挙戦では、この国をどうしたいのか、きちんとした未来像を分かりやすい言葉で語ってほしい、と願うしかありません。
無残きわまりないのは民進党です。新聞の主見出しにも取ってもらえず、そのわきに「事実上の解党へ」とか「希望と合流」などという言葉と共に「消えゆく政党」として烙印を押されてしまいました。ついこの間の代表選挙は、喪主選びの選挙だったのか。前原誠司という政治家の本性が現れたと言うべきか、それがこの政党の定めだったと言うべきか。
かつて民主党が旗挙げした時、「これでリベラルの結集軸ができた」と持ち上げたメディアがありました。確かに、そう期待する声もありました。が、その内実は、自民党の本流・田中派に属していた小沢一郎氏が金と人事を握り、極右のような政治家から社会党に見切りを付けた議員までが身を寄せた、文字通り「野合」の政党でした。基本政策が定まらず、ずっとフラフラし続けたのも、その出自を考えれば、当然のことでした。
リベラルが凋落し、仮初めの受け皿すら消えてしまったのも、また自然の成り行きと言わなければなりません。理路整然ときれいな事を言うが、世間の汚濁を正面から見つめようとしない。世界の現実から目をそむけ続ける。何よりも、人が生き、暮らしていくということがどういうことなのか、それを肌で感じ、泥だらけになって対処しようとしない。わが身を顧みれば、それがしみじみと、今になって理解できるのです。
もっとも、私がリベラルの一員だったのかについては、朝日新聞社内でも異論がありました。半世紀以上も前につくられた憲法を一字一句変えないで維持していくのは無理がある。で、論説委員室の議論では「改憲するのは自然なこと」と主張していました。国際報道を担った論説委員には、私のような改憲派がかなりいました。安全保障についても、「核兵器の廃絶は世界政治では現実味がない。いかに管理するかを論じるしかない」と主張し、「お前は産経新聞の論説委員か」と罵倒されたこともありました。
それでも、古い伝統より新しい息吹に魅力を感じ、より自由でより開かれた社会を目指す者をリベラルと呼ぶなら、「私はリベラルだ」と思って生きてきました。今の日本では、その思いを託す政治勢力がなくなり、漂泊の民になったとしても、自分が大切にしてきたものを変えるつもりはありません。「犀(さい)の角のようにただ独り歩め」。ブッダはそういう者のためにこの言葉を残してくれたのだ、と信じて。
≪参考記事&文献≫
◎2017年9月29日の新聞各紙(山形県で配達されているもの)
◎『ブッダのことば』(中村元訳、岩波書店)
≪写真説明≫
◎希望の党の代表に就任することを発表した小池百合子・東京都知事(東京新聞のサイトから)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201709/CK2017092602000111.html
*メールマガジン「風切通信 34」 2017年9月19日
わが家に時折、三毛猫がやって来るようになったのは3年前の秋のことでした。最初は「立ち寄り先の一つ」のような風情でした。来るたびに食べ物を与えていたのですが、そのうち頻繁に顔を見せるようになり、ついには2匹の子猫を連れて居ついてしまいました。不思議に思って調べてみると、もともとはわが家の100メートルほど先にある老夫婦の家で飼われていたのですが、2人とも老人ホームに入居してしまったため、やむなく引っ越してきたことが分かりました。

老夫婦にかわいがられていたからでしょう。親猫はとても人なつこくて、賢い猫でした。ミケと名付けました(安直な命名でご免)。対照的に、子猫は警戒心が強く、エサをもらう時も「シャー!」と威嚇する始末。気心が知れて、2匹を撫でられるようになるまで、だいぶ時間がかかりました。白と黒のまだら模様の雄猫はフグ、チャコールグレーと白い毛がきれいな雌猫はリプ子と名付けました。フグはまだら模様が魚のフグのようなので、リプ子は、顔つきが当時活躍していたロシアのフィギアスケートの選手、リプニツカヤに似ているからと、家人が付けた名前です。
親子3匹との暮らしは、山村での生活にうるおいを与えてくれました。が、そのうるおいも雪が解けるまででした。春になって発情期を迎えると、親猫は再び妊娠して出産、雌猫のリプ子も出産。秋にも出産・・・。2年後には孫も出産するようになり、わが家はたちまち「猫屋敷」と化してしまいました。次々に里親を募集して里子に出しましたが、里親探しも行き詰まり、この春、やむなく雌猫にはすべて不妊手術を施す羽目になりました。
「猫口爆発」はこれでやっと終息。現在、わが家をすみかにしている猫は7、8匹。ミケとリプ子は別のところにねぐらを構えて、お腹がすくとやって来る、という状態です。家人に言わせると、私の性格は「猫より気まぐれ」。食べ物を与えるのもいい加減で、外泊した場合などは一日中ほったらかしにすることもあります。
なので、わが家の猫は自活能力がすこぶる発達しています。「足りない分は自分で確保する」という習性が身に着いています。近所を駆けずり回ってネズミを捕るのはもちろん、スズメやトカゲ、ヘビも捕まえて食べる。夏はエサが豊富です。ミンミンゼミ、アブラゼミ、ヒグラシ、アゲハチョウにクロアゲハと、食材は実に多彩です。
猫は獲物を捕らえると、ねぐらに持ち込んで食べる習性があります。セミや蝶の羽は食べないので、わが家の猫部屋を見ると、彼らの食生活がよく分かるのです。意外なのは、オニヤンマをよく食べていることでした。よく知られているように、トンボの幼虫はヤゴと呼ばれ、水の中で数年暮らしてから、早朝にヤゴから羽化して飛び立ちます。羽化しても羽が乾くまでは飛ぶことができず、じっとしているので、簡単に捕まえることができます。猫は早起きですから、その時に捕まえているのだろう、と推測していました。
ところが、ある日の昼下がり、わが家の猫(サンちゃん)がオニヤンマをくわえて戻ってくるのを目撃しました。仰天しました。なんと、飛行中のオニヤンマを捕まえていたのです。オニヤンマは小さな虫がいる水路などを何度も往復してエサ捕りをします。待ち伏せ攻撃が得意な猫は、オニヤンマのそういう習性が分かっているのか、飛行ルートでじっと待って跳び付いてキャッチしていたのです。
そうか。オニヤンマが飛び立てない時間帯を狙って捕まえるなどという姑息なことはせず、堂々と勝負してゲットしていたのか。お見逸れしました、サンちゃん。ほかの猫もそうやってオニヤンマを捕まえていたのかもしれません。そういえば、コウモリを捕まえて持ち帰り、食べていた猫もいました。コウモリのねぐらの出入り口で、得意の待ち伏せ攻撃をしたのでしょう。
猫の狩猟能力は高く、自活能力も高い。私のような気まぐれな人間が付き合うのにぴったりの動物だ、とあらためて思った昼下がりでした。
≪参考文献≫
◎『美しき孤高のハンター 世界の野生猫』(エンディング出版編集部、ファミマ・ドット・コム)
◎『ネコ学入門』(クレア・ベサント、築地書館)
◎『猫は魔術師』(『ねこ新聞』編集部、竹書房)
◎『The CAT』(Penguin Random House, UK)
≪写真説明≫
◎柿の木に登って遊ぶクリちゃん(耳のあたりが栗色)=撮影・長岡昇
*メールマガジン「風切通信 33」 2017年9月11日
税金の無駄遣いを監視し、不正を追及する市民オンブズマンの全国大会が9月2日と3日に和歌山市で開かれ、山形県の会員の一人として参加してきました。各地で活動するオンブズマンが200人ほど集い、数多くの事例発表がありました。公務員が職務遂行のために日々発信しているメールも公文書であること。これをどうやって開示させ、追及の素材にしていくのかといった報告もあり、とても有益でした。

全国大会で先達に学んだことを山形県の税金の無駄遣いの追及にどう活かしていくのか。それは後日、報告するとして、今回は市民オンブズマンの全国大会に先立って行われた記者会見で特筆すべき資料が公表されましたので、ご紹介します。
全国市民オンブズマン連絡会議は大会前日の1日に記者会見を開き、2016年度の政務活動費の執行率調査というのを発表しました。都道府県や政令市、中核市の議会の議員が昨年度に支給された政務活動費をどの程度使ったのか(執行したのか)を一覧表にまとめたものです。これが都道府県の政治状況やオンブズマンの追及ぶりを如実に反映していて、実に興味深いのです。
政務活動費の執行率が一番落ち込んだのは富山市でした。2016年度に使われた富山市議の政務活動費は支給額の62.4%で、前年度から37.6ポイントも減りました。つまり、富山市議会は2015年度に支給された政務活動費を全議員が100%使い切り、「文句なしの全国トップ」だったのに、2016年度は3分の2しか使わず、残りの3分の1を「余りました」と富山市に返却したのです。この結果、富山市議会は全国48の中核市のうち、執行率が三番目に低い市議会になってしまいました(一番低いのは函館市議会の59.5%、二番目が長崎市議会の60.7%)。
富山では、白紙領収書を使った架空請求やカラ出張などが次々に発覚し、元議長を含め14人の市議が辞職に追い込まれました。悪質なケースについては有印私文書偽造・同行使の疑いで刑事告発されています。それに懲りて、市議たちが正直ベースで請求したら、2016年度は政務活動費が3分の1も余ってしまった、というわけです。裏返して言えば、それまではその分の税金をかすめ取っていた疑いがある、ということになります。
ちなみに、48の中核市のうち、政務活動費の執行率が高いところは?青森県八戸市議会の97.6%?愛知県豊橋市議会の97.0%?愛知県豊田市議会の95.4%の順です。20の政令市では?横浜市議会の99.6%?川崎市議会の95.7%?大阪市議会の93.4%が飛び抜けて高い。議員のみなさんが熱心に活動した結果、政務活動費をほぼ使い切ってしまった、という可能性もあるのですが、それはあくまでも「論理的にはあり得る」という話です。オンブズマンとして自治体の議会を監視してきた経験から言えば、それぞれ「無駄遣いの多い議会の順位」と考えていいでしょう。富山市議会の激変ぶりが何よりの証拠です。
都道府県別の政務活動費の執行率一覧も興味深い。執行率の低い県議会は次の通りです。
?徳島県議会の62.2%?兵庫県議会の65.2%?鳥取県議会の67.5%。兵庫県議会は、カラ出張を繰り返した野々村竜太郎県議(当時)が号泣会見をして有名になりました(詐欺罪などで有罪確定)。その後、ほかの議員も悔い改めて質素になった、ということでしょう。徳島県議会も不正が発覚したところ。鳥取県議会は政務活動費をガラス張りにする努力を重ねてきた議会です。きちんとすれば、政令市や中核市と同じく、都道府県議会でも政務活動費の執行率は3分の2程度に収まる、ということを示しています。
そうなると、政務活動費の執行率が高い都道府県議会はどこかが気になります。順位は次の通りです。?神奈川県議会 99.1%?鹿児島県議会 97.0%?熊本県議会96.3%?東京都議会 95.2%?京都府議会94.9%?長野県議会 94.7%?福島県議会 94.3%?香川県議会 93.6%?埼玉県議会 93.1%?福岡県議会 92.9%。この数字は東京、京都、神奈川、埼玉といった大都市の議会で無駄遣いがいまだに続いている可能性を示しています。大震災と原発事故からの復興に取り組むべき福島県の議会でも、このような政務活動費の使い方がまかり通っていることが悲しい。
政務活動費の無駄遣いを減らすために何をすべきか。市民オンブズマンたちの長い監視活動の経験から、為すべきことは明白です。収支報告書や領収書だけでなく、その明細である会計帳簿の公開をいっそう進めること。そして、政務活動費を一括して支給して後で精算する仕方をやめ、まず議員が自分の金で支払い、後で実費を精算する方法(世間では当たり前のこと)に変えることです。
政務活動費の一括前払いという手法は、経済が成長し続けて気前よく税金をばら撒いていた時代の名残りです。そんな時代はとうに過ぎ去ったのに、いまだに改めようとしない議員たち。彼らの意識を変えていくことが大切です。限られた資産をどう有効に使っていくのか。そういう時代になっていることを肝に銘じてもらわなければなりません。
≪参考サイト&記事≫
◎全国市民オンブズマン連絡会議が発表した「2017年度 政務活動費 情報公開度ランキング」。都道府県、政令市、中核市ごとの一覧は118?119ページ。兵庫県議会の政務活動費の執行率は46.7%と発表されましたが、65.2%の誤り。後日、訂正されました。
https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2017.pdf
◎2017年9月2日の毎日新聞の記事
≪写真説明とSource≫
◎政務活動費の無駄遣いを追及され、号泣して有名になった野々村竜太郎氏
http://www.huffingtonpost.jp/2014/07/09/nonomura-kokuhatsu_n_5569542.html
*メールマガジン「風切通信 32」 2017年8月24日
「対馬でカワウソ発見」を伝える新聞記事に「フンを回収してDNA解析をしたところ、カワウソと確認された」という表現がありました。山林に設置した自動撮影カメラの映像だけでは心配なので、念のためDNA鑑定もして慎重を期した、ということでしょう。

「カワウソおたく」としては、「では、フンの何をDNA鑑定したのか」が気になります。食べたものをいくら解析しても、カワウソかどうかは分かりません。毛繕いをする際に飲み込み、フンと一緒に出てくる体毛を鑑定したのか。旧知の動物生態学者、齊藤隆さん(北海道大学教授)に問い合わせたところ、丁寧な解説が寄せられました。専門家のすごさを感じさせる文章です。以下、全文を引用させていただきます。
* *
フンには未消化物以外にも様々なものが含まれていますが、フンをした当該個体の組織としては体毛と腸の細胞が含まれている可能性があります。体毛は毛繕いした時に口に入るものですが、体毛が含まれていないフンもあります。一方、腸の細胞はすべてのフンに含まれていると期待されます。
フンから持ち主(当該個体)のDNAを分析したい場合は、フンの表面を丁寧にぬぐい、腸の細胞を採取します。フンの表面についた細胞の劣化は早く、また、もともとの量も多くないために、分析の成功率はあまり高くありません(よくて50%くらい)。今回の場合は、複数のフンからDNAが採取できたと思われます。
分析対象のDNAは、ミトコンドリアDNAとマイクロサテライトDNAであったと思われます。ミトコンドリアDNAからは母系分析が可能です。家系図のような系統解析から、類縁関係が推定できます。カワウソのDNA分析にはすでに蓄積がありますから、種ごとに特徴的なミトコンドリアDNAのタイプがすでに明らかになっています。ですから、採取されたミトコンドリアDNAのタイプがユーラシアカワウソのタイプであるならば、フンをした個体はほぼ間違いなくユーラシアカワウソであると考えて良いことになります(この個体が別の種でユーラシアカワウソを食っていた可能性は、論理的には排除できませんが、仮にそうだったとしても、対馬に食われたユーラシアカワウソがいたことになりますから、今回の発見は揺らぎません)。
ミトコンドリアDNAを使って、種よりも小さな単位の分析も可能ですが、まだその分析は進んでいないようです。近い将来、亜種レベルでの特徴も分析できるようになると思います。
マイクロサテライトDNAを分析すれば、個体識別や親子判定が可能です。今回は韓国で分析された個体のマイクロサテライトDNAの特徴と似たものを検出できたようです。このような分析を丁寧に進めていけば、対馬にいる個体の由来をかなりの確度で推定できるでしょう。どのような分析を行ったのかわかりませんが、性別もDNAでわかったようです。
* *
この解説に先立って、私が「発見されたカワウソがニホンカワウソとユーラシアカワウソのどちらか、などということは瑣末なこと」と表現したことについては、お叱りを受けました。一つひとつの事実を丁寧に洗い出し、解明していく、専門家の仕事への敬意を欠いた表現でした。お詫びします。今回発見された個体はユーラシアカワウソなのか、ニホンカワウソなのか。それによって、何が明らかになるのか。以下、再び、齊藤隆さんの文章を引用させていただきます。
* *
それは、いつ(カワウソが日本に)渡ってきたのかが問題となるからです。ユーラシア大陸からの渡来が頻繁で最近(昭和の前半くらまで)も続いていたのならば、「どちらでも良い」と考えても差し支えないと思います。しかし、ユーラシア大陸からの渡来が古く(20ー30万年前)、その後の遺伝的な交流が限られ、日本で独自に進化を遂げていたのなら、どちらでも良いことになりません。
日本列島の哺乳類相の成り立ちはまだ十分に解明されていません。陸続きでなければ渡来できない種、列島成立後も大陸と交流を持ち続けた種などの類別は不十分です。今回の発見が対馬を経由した朝鮮→九州の可能性を強く示唆するのならば、日本列島の哺乳類相の成り立ちを考える上で重要な知見になります。
≪写真説明とSource≫
◎イギリスのカワウソ(英紙Express から)
http://www.express.co.uk/news/weird/380943/Otters-eat-2m-fishery
*メールマガジン「風切通信 31」 2017年8月22日
何を隠そう、と気張って言うほどのことでもないのですが、実は私は「カワウソおたく」の一人です。「カワウソ」という言葉を聞いただけで、心がピクッと動いてしまいます。当然のことながら、長崎県の対馬でカワウソが発見された、というニュースには血がザワザワと騒ぎました。

琉球大学の伊沢雅子教授らのグループが「ツシマヤマネコ」の生態を調査するため、対馬の山林に自動撮影カメラを設置したところ、それにカワウソが写っていたというのです。8月17日に発表されました。フンのDNAを鑑定し、カワウソに間違いないと確認したようです。日本でカワウソの姿が最後に確認されたのは高知県須崎市の新荘川で、昭和54年(1979年)のこと。実に38年ぶりの生存確認です。
ニホンカワウソはユーラシアカワウソの亜種もしくは独立種とされています。対馬で発見されたのがどちらのカワウソか、まだ判然としないようですが、そんなことは瑣末なことです。日本列島にいるカワウソは、もともとユーラシア大陸から渡ってきたと考えられるからです。目撃例が途絶え、2012年に環境省によって「絶滅種」とされたカワウソが日本で生きていた。それだけで十分、心躍るニュースです。
私が「カワウソおたく」の仲間入りをしたのは1980年代初めのことです。当時、私は駆け出しの新聞記者として朝日新聞の横浜支局で働いていました。同僚の一人が神奈川県の清川村で建設計画が進んでいた宮ケ瀬ダムの取材をしていて、彼から「なんか宮ケ瀬にはまだカワウソがいるらしいよ」と聞いたのがきっかけです。
同僚はダム建設をめぐる補償交渉の取材に追われ、カワウソの話はしなくなったのですが、変人の私は「スイッチが入った状態」になってしまい、日頃の取材などそっちのけで、カワウソに関する情報収集にのめり込んでいきました。かつては日本のあちこちの川にカワウソがいたといいます。山形の山村に住んでいた父親に聞くと、「昔はおらほの川にもいたようだ」と言うではありませんか。
清流が姿を消すにつれ、また川岸がコンクリートで固められていくにつれてすみかを奪われ、消えていったニホンカワウソ。それが神奈川県の山奥でまだ生きているとなれば、間違いなく1面トップのニュースです。高知県の新荘川でその姿が確認されたと報じられてから、まだ数年しかたっていない頃のことでした。
もちろん、「宮ケ瀬のカワウソ」は確認できなかったのですが、簡単にあきらめたりしないのが「おたく」の「おたく」たるゆえんです。その後、北海道に転勤になってからも「カワウソの残影」を追い続けました。日本海親善ヨットレースの取材で、札幌からソ連のシベリアに出張した際には、ヨットレースの取材もそこそこに、「カワウソはいるか?」と聞き回る始末(ロシア人から「アムール川にいっぱいいるよ」と言われ、拍子抜けしました)。
国際報道部門に異動になり、インドに駐在していた時にもこっそり隠れて、カワウソの資料を集めていました。イギリスをはじめヨーロッパ各地にも生存しており、海岸伝いに別の川に移動したり、人間になついて猟の手伝いをしたりすることも知りました。
人間が生息域を広げるのに伴って住む場所を奪われ、消えていった生き物はカワウソに限りません。ニホンオオカミもそうです。けれども、山や森の奥深くではなく、身近な川にいたカワウソには、何か惹かれるものを感じます。対馬だけではないのではないか。まだ、日本のどこかで、カワウソはしたたかに生き延びているのではないか。人間たちのさかしらな「絶滅宣言」など、あざ笑うかのように。
≪参考サイト≫
◎対馬で撮影されたカワウソの動画(琉球大学のサイト)
http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/announcement/press2017081701/
◎ニホンカワウソ(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%A6%E3%82%BD
◎1979年にニホンカワウソが確認された高知県の新荘川についてのサイト
http://mantentosa.com/sightseeing/susaki/try/shinjo_river/index.html
◎神奈川県の宮ケ瀬ダムについて(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E3%83%B6%E7%80%AC%E3%83%80%E3%83%A0
◎イギリス各地にカワウソ Otter が生息していることを伝える報告(英文)。推定生息数は12,900匹で、最近は微増傾向にあるという。
https://www.britishwildlifecentre.co.uk/planyourvisit/animals/otter.html
≪写真説明とSource≫
◎1979年ごろ、高知県須崎市の新荘川で撮影された二ホンカワウソ(須崎市の鍋島誠郎さん提供)
http://www.sankeibiz.jp/compliance/photos/170817/cpd1708171337002-p2.htm

7月27日(木)に「予定通り開催します」とホームページでお知らせしましたが、28日夜から29日朝にかけて大雨になり、最上川が急に増水しました。このため、1日目の29日(土)は「山形県朝日町の雪谷カヌー公園から大江町のふれあい会館まで17キロ」の予定を変更し、流れが比較的穏やかな「大江町のふれあい会館から中山町の長崎大橋まで10キロ」を漕ぎ下りました。参加者は13人(10艇=2人乗りが3艇)でした。天候は薄曇り。



夕方から、尾花沢市の名木沢コミュニティーセンターで「ブナの森」の会員と参加者の懇親会を開きました。今回の反省と来年以降の「カヌー探訪」の内容について、率直に意見を交換し、貴重なアドバイスをいただきました。今後の企画に活かしていきます。



2日目の30日(日)は、尾花沢市の猿羽根(さばね)大橋から新庄市の本合海(もとあいかい)大橋まで20キロを下る予定でしたが、カヌー行そのものを中止しました。1日目の予定変更で気勢をそがれたこと、雨量の予測が難しく、リスクが高いと判断したためです。2日目に参加を予定していたカヌーイストの皆様と昼食会場を提供してくださる予定だった大蔵村赤松地区の皆様、ゴール地点の新庄市本合海(もとあいかい)の皆様にはご迷惑をおかけしました。事情をご理解のうえ、なにとぞご容赦ください。


≪参加申込者≫
25人:山形県内15人、県外10人(東京4、神奈川3、宮城、福島、岩手各1人)
≪参加者≫
【29日に大江町ー中山町まで10キロを漕ぐ】13人(10艇=2人乗りが3艇)
永嶋英明(山形県鶴岡市)、大類晋(山形県尾花沢市)、渡辺政幸(山形県大江町)、林和明(東京都足立区)、市川秀(東京都中野区)、岸浩(福島市)、吉田英世(盛岡市)、佐竹久(山形県大江町)、菊地大二郎(山形市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、崔鍾八(山形県朝日町)、柏倉稔(山形県大江町)、森太介(山形県朝日町)

*きよかわアウトドアスポーツクラブの齋藤健司(神奈川県海老名市)、池辺民雄(神奈川県座間市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、岸一博(東京都町田市)、岸君子(同)は自主判断で参加見送り。懇親会で貴重なアドバイスをしてくださいました。

≪過去の参加者数≫
第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人、第4回(2016年)31人
≪陸上サポート≫ 安藤昭雄▽遠藤大輔▽白田金之助▽長岡昇▽長岡典己▽長岡佳子
≪写真撮影≫ 遠藤大輔▽長岡昇
≪昼食の漬物提供≫ 安藤昭雄▽佐竹恵子
≪出発、通過、到着時刻≫
▽1日目(7月29日)
9:30 大江町ふれあい会館を出発
10:10 寒河江市ゆーチェリーに到着
10:30 寒河江市ゆーチェリーを出発
11:30 中山町・長崎大橋に到着、昼食
▽2日目(7月30日) 中止
≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、大江町、西川町、大石田町、尾花沢市、舟形町、大蔵村、新庄市、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 尾花沢市名木沢区長、阿部良一▽大蔵村赤松区長、斉藤英幸▽新庄市本合海地区、八向尚
≪ウェブサイト更新≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、阿部可奈)
≪ポスター、Tシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス(株)
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell 保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
*メールマガジン「風切通信 30」 2017年7月27日
7月初めに集中豪雨に襲われ、甚大な被害を受けた福岡県の朝倉市は今、どうなっているのか。今朝のニュースで、NHKが被災地のその後を伝えていました。道路が土砂で埋まり、まだ孤立状態の集落がある。災害ボランティアの人たちも、この村には来ることができないのだそうです。初老の男性は、自宅の床上1メートルの高さにまで達した濁流の跡を指さしながら、「家族で少しずつ片付けとります」と語っていました。

田んぼも畑も濁流に呑み込まれました。水が引いたサトウキビ畑は石ころだらけ。74歳の農民は小石を取り除く作業をしながら、淡々と「それでも(サトウキビ作りは)やめんよ。今まで、ずっとやってきたことじゃけん」と話していました。茎を傷めつけられながらも、サトウキビは生き抜こうとしている。彼はその力を信じているのです。
私たちが暮らすこの国を誇らしく思うのは、こういう生き方に接した時です。豊かな水に恵まれ、緑に包まれた国、日本。その見返りのように、あらゆる天災が降りかかるこの国で、私たちは災害から免れることはできません。けれども、それに打ちのめされることなく、再び歩み始めることはできる。そういう気高い心を持つ人たちがそこかしこにいることを誇らしく思うのです。
6年前、雪が舞う東日本大震災の被災地で、支援物資を受け取るため、静かに列に並ぶ人たちがいました。その時にも、同じ気持ちになりました。こんな時にこそ、声を荒らげることなく、いつものように振る舞う。「いずれ、支援の手がきちんと届くはず」。社会にそういう信頼感があるからこそ、被災した人たちのあの姿があるのだ、と。
その映像は世界に衝撃を与えました。大規模な災害が起こり、ライフラインが破壊されれば、人々は飢え、生き残るために必死になります。支援物資が届けば、我さきに奪い取ろうとして、暴力沙汰になる。それが普通のことだからです。2005年夏にアメリカ南部がハリケーン・カトリーナに襲われた時も同様で、先進国も例外ではありません。被災者が静かに並んで支援物資を受け取る姿が世界に流れたのは、あれが初めてだったのです。
生きかはり死にかはりして打つ田かな
そういう姿を見るたびに、私は、市井の人々の暮らしを謳い続けた俳人、村上鬼城(きじょう)のこの句を思い出します。春先、固く締まった田んぼに三本鍬を打ち込み、一つひとつ掘り起こしてゆく。子どもの頃、冷たい雨に打たれながら鍬を振るっている姿を見て、粛然とした気持ちになったことを今でも覚えています。
今では、トラクターが軽やかに土を掘り返していきますが、かつて田起こしは農作業の中でも、とりわけきつい労働でした。けれども、すべてはそこから始まります。次いで代(しろ)掻きをし、田植えをし、夏の草取りをして、ようやく秋の収穫を迎えることができるのです。命をつなぐための最初の仕事。だからこそ、代々、あのつらい仕事に耐えることができたのです。私には、三本鍬を振るう姿と被災者の姿が重なって見えてくるのです。
被災地のその後を丁寧に伝えようとするNHKの取材陣にも頭が下がります。カメラをかついで徒歩で被災地を回り、また徒歩で戻ってその姿を伝える。「災害報道を担うのは自分たちだ」という気概が伝わってくる映像でした。息長く、丁寧な報道。成熟した社会でメディアに求められているのは、そういう仕事です。
昨今、永田町や霞が関から流れてくるニュースは、ごまかしと嘘のオンパレード。何と醜悪なことか。被災地から伝えられる気高い心とのその著しいコントラストもまた、私たちの社会が抱える哀しい現実の一つです。気高さ、とは言わない。せめて、まともさを政治の世界にも広げられないものか。
≪参考サイト≫
◎ウィキペディア「平成29年7月九州北部豪雨」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B47%E6%9C%88%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%8C%97%E9%83%A8%E8%B1%AA%E9%9B%A8
◎ウィキペディア「村上鬼城」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%AC%BC%E5%9F%8E
◎「生きかはり死にかはりして打つ田かな」の解説
https://note.mu/masajyo/n/n200114148230
≪写真説明とSource≫
◎福岡県朝倉市の豪雨被災地(2017年7月7日撮影)
http://www.afpbb.com/articles/-/3134927
第5回最上川縦断カヌー探訪は予定通り、7月29日(土)、30日(日)に開催します。先般の大雨で最上川は一時、氾濫状態になりましたが、その後、天候も回復し、流量は落ち着いています。今日はミンミンゼミの声が里山に響き渡っています。予報では、今週末の山形県内の天気は「曇時々雨」。大雨の心配はなさそうです。皆様のお越しをお待ちしております。
*メールマガジン「風切通信 29」 2017年7月5日
次の世代に何を語りかけ、どう育むのか。教育は「人づくり」であり、「未来づくり」です。教育がおかしくなれば、社会そのものがおかしくなってしまいます。だからこそ、教育という仕事には使命感と誠実さが求められるのです。

その根本をないがしろにして、金儲けに走れば、どういうことになるか。私たちは、加計学園による獣医学部新設問題を通して、その寒々とした光景を日々、見せつけられています。獣医師をどのようにして育てていくのか、という長期的な視点などおかまいなしに、四国の今治市に無理やり獣医学部の新設を試みる。文部科学省や獣医師会が学部の新設に難色を示せば、首相の権勢を笠に着て押し切ろうとする。
人口減に悩む地方都市にとって、若者が集まる大学や学部の新設は無理をしてでも実現したい。だからこそ、今治市は36億円相当の土地16ヘクタールを無償で提供し、愛媛県と今治市は総事業費の半分、96億円の負担に応じたのです。締めて132億円。これがタダで学校法人のものになるのですから、純粋にビジネスとして考えれば、今時、こんなにボロイ商売はありません。教育を「金儲けの手段の一つ」と考える人たちの所業です。
教育を利用する錬金術の全国版の主役が安倍晋三首相と加計幸太郎理事長とするなら、山形県の教育錬金術の主役は、吉村美栄子知事の義理の従兄弟である吉村和文(かずふみ)氏です。彼は、東海大学山形高校を運営する学校法人「東海山形学園」の理事長をつとめる傍ら、株式会社「ケーブルテレビ山形」(本社・山形市)の社長の座にあり、IT企業や興行会社などのファミリー企業を率いています。
ケーブルテレビ山形は、全国にケーブルテレビ網を広げることを目指した総務省の施設整備促進事業の補助金受け皿会社として、1992年に設立されました。ケーブル網の敷設費の半分を国と県、市町村が補助し、ケーブルテレビを広げようとする事業です。総務省が「アメリカで流行っているから日本でも広がるはず」と目論んで始めた事業ですが、四半世紀たっても、日本ではそれほど広がりませんでした。
ケーブルテレビ山形も契約件数が伸びず、本業は先細り気味です。事業の多角化を図り、山形県からのパソコン受注や宣伝PR委託事業の受託に力を注いでいます。社名も、昨年1月に「ダイバーシティメディア」に変更しました。
ファミリー企業の経営は、いずれもバラ色とは言い難い。ファミリー内で資金を融通したり、債務保証をしたりしています。それでも、資金繰りに窮したのでしょう。吉村和文氏は昨年の3月、理事長を務める学校法人「東海山形学園」の資金3000万円を自らが社長である「ダイバーシティメディア」に貸し付けました。この事実が昨年秋に山形の地域月刊誌『素晴らしい山形』11月号で報じられました。
私は、地域おこしの小さなNPOを主宰する傍ら、公金の使途を監視する市民オンブズマン山形県会議にも加わっています。学校法人が民間企業に金を貸すなどということが許されるのか。なんらかの法令に触れるのではないか。私立高校である東海大学山形高校には毎年、山形県から運営費の半分、3億円余りが私学助成費として支給されています。その1割近い資金が「短期貸し付け」とはいえ、民間企業への融資に回されたのですから。
私学助成を所管する山形県学事文書課の見解を問うため、今年の4月、県情報公開条例に基づいて東海学園山形関係の公文書の開示を求めました。私学助成の実績などの公文書は比較的すんなり開示されましたが、東海山形学園の会計文書に関しては白くマスキングされたり、黒塗りされたりして、かなりの部分が不開示になりました。その理由は「学校法人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある」というものでした。
あきれました。学校法人の収支計算書や貸借対照表は、民間企業の損益計算書や貸借対照表に相当する基本的な会計文書です。民間企業は株主総会でそうした会計文書を株主に配布しています。そうしたからといって、自社の利益を損なうおそれなどないからです。学校法人にとっても、利益を害するおそれなど、あるはずがありません。
あまりにも理不尽なので、私は「法的措置を取ります」と宣言し、一昨日(7月3日)、不開示の決定をした吉村美栄子・山形県知事を相手取り、山形地裁に不開示処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。新聞やテレビがこの処分取消訴訟について報じましたが、山形県学事文書課のコメントが興味深い。河北新報の取材に「毎年、学校法人の監査報告書を確認している。現時点で学園側に問題は見当たらない」と答えているのです。
毎年度、3億円余りの私学助成を受け取っている学校法人が、年度末に3000万円もの資金を民間企業に貸し出している。なぜ、そんなに余裕があるのか調べたのか。一方で、借りた側のダイバーシティメディアの吉村和文氏は山形新聞に「複数金融機関の融資承認がそろうまでの間の短期貸付」として、設備投資を目的に借りた、と語っています。
融資が本業の金融機関の承認が間に合わないような経営状態の会社に、学校法人が3000万円も貸すとは、驚きです。吉村氏は「学校法人の評議員会や理事会の承認も得ている」と主張していますが、学校法人側はきちんと担保を取ったのでしょうか。3000万円の貸付金は2カ月後に金利を含めて返済されたとのことですが、返せば済む話ではありません。「学校法人を率いるのも自分。会社の社長も自分」という意識が為せるわざでしょう。
情報公開請求に対応する山形県の職員からは「グループを率いるのは知事の従兄弟。余計な詮索から守ってあげなければ」という意識が透けて見えます。でなければ、学校法人の基本的な会計文書を開示することが「法人の利益を害するおそれがある」などという理由を思い付くはずがありません。彼らの脳裏には「私学助成の原資は国民の税金。その使途について、納税者には知る権利がある」という考えは、まったく浮かんで来なかったのでしょう。
この国の主権者は国民であり、政府や自治体が持つ公文書も本来、国民のもの。原則として公開されるべきものであり、非公開になるのは明確な理由がある場合に限られる。それが情報公開制度の大原則です。そうした大原則すら忘れ果て、権力者につながる者の顔色をうかがって動く。加計学園問題と同じ構図がここにもあるのです。黙って見ているわけにはいきません。
≪参考記事&サイト≫
◎ダイバーシティメディア(旧ケーブルテレビ山形)の公式サイト
http://www.catvy.jp/company/
◎ウィキペディア「吉村和文」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E6%9D%91%E5%92%8C%E6%96%87
◎地域ケーブルテレビネットワーク整備事業(総務省の公式サイト)
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/cable_kyoujin.html
◎地域月刊誌『素晴らしい山形』2016年11月号?2017年7月号
◎2017年7月4日の河北新報、山形新聞の非開示処分取消訴訟に関する記事
≪写真説明とSource≫
◎吉村美栄子・山形県知事(PRESIDENT Online のサイトから)
http://president.jp/articles/-/18589
第5回最上川縦断カヌー探訪の参加申し込みは、6月12日正午から受付を始めました。7月15日(土)までに申し込んでください。今年は7月29日(土)と30日(日)に開催します。1日目は山形県朝日町雪谷から大江町ふれあい会館までの17キロ、2日目は尾花沢市・猿羽根(さばね)大橋から新庄市・本合海(もとあいかい)大橋までの20キロ、計37キロのコースを漕ぎ下ります。開催要項とコース図、参加申し込みフォームはウェブサイトの各ページをご覧ください。
直前に大雨が降るなどして最上川が荒れた場合には、前々日の7月27日までにウェブサイトに中止のお知らせを掲載します。予備日は設けていません。ご了承ください。
直前に大雨が降るなどして最上川が荒れた場合には、前々日の7月27日までにウェブサイトに中止のお知らせを掲載します。予備日は設けていません。ご了承ください。
*メールマガジン「風切通信 28」 2017年5月25日
かつて、この国には「ブルドーザー宰相」と呼ばれた政治家がいました。新潟が生んだ鬼才、田中角栄氏です。苦労を重ねて首相まで上り詰めた人だけあって、人々の心の襞(ひだ)をよく知り、一方で利権漁りも得意でした。公共事業がらみの情報をいち早く入手して土地を転がし、土建業界から得た資金で政界を牛耳り、日本列島改造論をぶち上げました。「ブルドーザー宰相」と呼ばれた所以です。

その内実が立花隆氏の論考『田中角栄研究ーその金脈と人脈』(1974年)で暴かれ、2年後にはロッキード事件が発覚して、角栄氏は政治の表舞台から消えていきました。これ以降、土木建設工事をめぐって談合事件の摘発や報道が相次いだこともあって、公共事業や土地転がしで巨利を得るのは段々と難しくなっていきました。
代わって、政治家の金づるになったのが株取引です。その象徴的な事例が、値上がり確実な未公開株を政治家や官僚にばらまいて便宜を図ってもらったリクルート事件(1988年発覚)でした。この事件には多くの政治家や官僚が関与し、当時の竹下登首相は辞任、藤波孝生(たかお)官房長官は受託収賄罪で有罪判決を受けました。
公共事業で利権を漁るのはダメ。株取引で甘い汁を吸うのもいけない。ならば、政治家はどうやって資金を得ればいいのか――。1990年代に政治改革論議が高まり、政党交付金の制度ができたのは、そうした政治家の悲鳴に応えた面もありました。「税金で面倒を見るから、汚い金には手を出さないでね」というわけです。その延長線上で、地方議員にも政務活動費(旧政務調査費)という公金が支給されるようになりました。
とはいえ、どんなに手厚い制度を作っても、権力に群がり、公金をむさぼろうとする連中がいなくなるわけがありません。それは、森友学園問題や最近、報道が増えた愛媛県今治市の獣医学部新設問題を見れば、明らかです。安倍晋三首相のお友達が経営する学校法人「加計(かけ)学園」が新設を計画している岡山理科大学の獣医学部には、今治市が16ヘクタールの土地(36億円相当)を無償で譲渡し、愛媛県と今治市が総事業費の半分96億円を負担することになっています。注がれる公金は締めて132億円。これがタダで手に入るわけですから、関係者は笑いが止まらないでしょう。
小泉政権が「構造改革特区」構想を打ち出してから、加計学園は獣医学部を新設したいと15回も提案したのに、これまでは「獣医師は足りている」という日本獣医師会の意向や文部科学省の反対にあって、ことごとく却下されていました。それが安倍政権になり、「構造改革特区」が「国家戦略特区」に衣替えされた途端、トントン拍子に事が進んだというのですから、便宜供与がなかったと考える方がおかしい。
森友学園問題では、矢面に立った財務省が「関係書類は保存期間が過ぎたので全て破棄した」とか「土地売却費の8億円値引きは適正な手続きに基づく決定」とか、強弁と詭弁を繰り返しています。加計学園問題では、獣医学部の新設容認が「総理のご意向だと聞いている」と記した文部科学省の内部文書について、菅義偉(すが・よしひで)官房長官が「怪文書みたいな文書じゃないか」と迷言を吐く有り様です。
私たちの社会にとって深刻なのは、こうした政治家や官僚の醜い対応が「教育」を舞台にして為されている、ということです。次の時代、未来を担う人間をどうやって育てていくのか。それを考え、実践していくべき場で、公金をむさぼる行為がまかり通り、不正をごまかす言葉がまき散らされているのです。憂うべきことです。
自民党や文部科学省は「人間としての生き方についての考えを深める学習が必要だ」として、道徳をこれまでの「教科外の活動」から「教科」に格上げすることを決めました。来年以降、小中学校で正式に教科としての道徳の授業が始まります。いっそのこと、森友問題や加計問題での政治家や官僚の嘘とごまかしをそのまま教材にしてはどうか。子どもたちにとって、何より分かりやすい「道徳の反面教師」になるのではないか。
子は親の背中を見て育つ、と言います。政府が嘘とごまかしで押し切ろうとする姿を見ていれば、子である都道府県や孫である市町村も右ならえをすることになります。実際、私が暮らしている山形県でも似たようなことが起きています。全国津々浦々で続く公金のむさぼり合い。こんなことを許していたら、それこそ、国が滅びてしまいます。
≪参考文献・記事&サイト≫
◎『田中角栄研究?その金脈と人脈』(立花隆、月刊誌『文藝春秋』1974年11月号)
◎リクルート事件(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6
◎加計学園の獣医学部新設問題に関する報道
・2017年5月18日付の朝日新聞、毎日新聞(山形県で販売されている版)
・2017年5月25日付の朝日新聞(同)
◎今治市と愛媛県の獣医学部新設に伴う負担に関する報道(毎日新聞のサイト)
https://mainichi.jp/articles/20170304/ddl/k38/010/544000c
◎道徳教育について(文部科学省の資料)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/078/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/08/05/1375323_4_1.pdf
≪写真説明とSource≫
◎愛媛県今治市に新設される岡山理科大学獣医学部の完成予想図
http://mera.red/%E5%8A%A0%E8%A8%88%E5%AD%A6%E5%9C%92%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81
*メールマガジン「風切通信 27」 2017年5月17日
優れた本は、すらすらと読み進むことができません。時折、本を置いて考え込んでしまいます。忘れかけていた記憶を呼び覚ましたりもします。国谷裕子(くにや・ひろこ)さんの著書『キャスターという仕事』(岩波新書)も、しばしば立ち止まってしまう本でした。
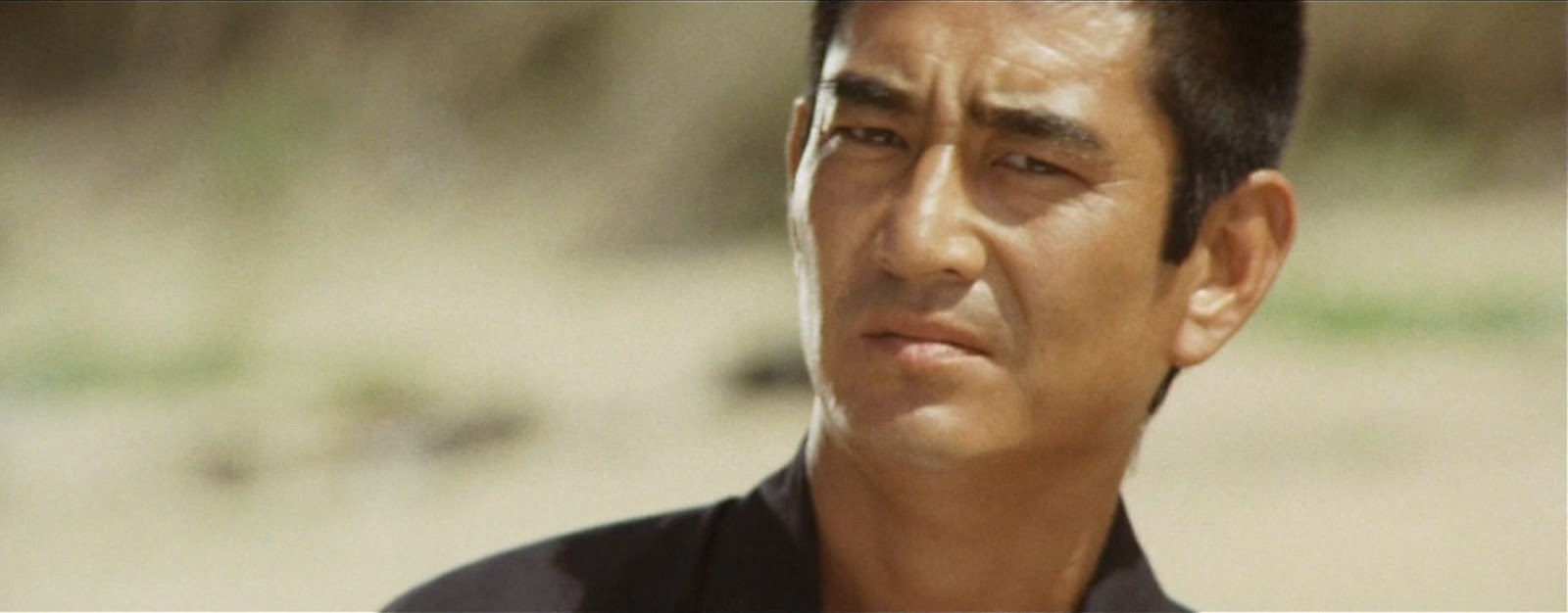
NHKの「クローズアップ現代」はよく観ていましたので、番組のキャスター、国谷さんの顔は何度も拝見していましたが、どういう道を歩んできた人かはこの本で初めて知りました。彼女は、父親の勤務の関係で海外生活が長く、小学校の数年間を除けば日本での教育を受けていません。そのため、英語は堪能なのに日本語に自信が持てず、日本の事情にも疎いためコンプレックスを抱いていたといいます。
彼女のキャスターとしてのキャリアは、1981年にNHKが夜7時のニュースを英語でも放送し始めた際、その英語放送用のアナウンサーとして採用されて始まりました。といっても、大事なところはベテランのアナウンサーが読むので、国谷さんは日本語の原稿を受け取って英語放送用の作業部屋に走って届ける、といった雑用もこなしたといいます。
駆け出しのアナウンサーからNHKの看板番組のキャスターになるまでの艱難辛苦は読み応えがあります。毎週4回、23年にわたって続けたキャスターとしての仕事を振り返り、反芻している各章は、それぞれがドラマのようです。一人の人間が修練を積み重ね、骨太のジャーナリストになっていく物語になっています。
その意味で、この本はジャーナリストを志す若者にとって教科書とも言えるような良書なのですが、私にとって最も印象深かったのは、2001年5月17日に放送された「クローズアップ現代 高倉健 素顔のメッセージ」について詳述しているところでした。
俳優の高倉健は寡黙なことで知られています。番組でインタビューを始めたものの、返ってくるのは短い答えのみ。対話はまったく弾まなかったといいます。国谷さんは、「テレビのインタビューにほとんど応じることのない高倉さんがくださった貴重な機会。覚悟を決めて待とう」と思った、と記しています(p133)。実際、インタビューの中で沈黙が17秒も続いたのだとか。
当時、高倉健は映画『ホタル』の撮影を終えたばかり。「これからはどういう作品に出たいと思いますか?」という彼女の問いかけに、高倉健はこう答えました。
「まだ頭のなか、何にも考えていないですね。もう嫌でも封切りの日がきますから、その日が一番辛くなる日なんですけど。でも、どっかでいい風に吹かれたいというふうに思いますね」「いい風に吹かれるためには、自分が意識して、いい風が吹きそうな所へ自分の身体とか心を持っていかないと。じっと待ってても吹いてきませんから。吹いてこないっていうのが、この頃わかってきましたね」
「いい風に吹かれたい」。この言葉に出くわして、私は忘れかけていた、南インドで吹かれた風のことを思い出しました。1992年から3年間のインドでの仕事と暮らしは、充実していたものの、とてもしんどいものでした。摂氏50度の熱波にさらされる取材。出張先は戦火が収まらないアフガニスタンや政争激しいパキスタン・・・。その厳しさからしばし逃れるために、私は南インドの古都マイソールに旅に出ました。
マイソールは南インド研究の泰斗、辛島昇・東大名誉教授(故人)が若い頃に貴子夫人と暮らした街です。インドとはどういう国、どういう社会なのか。戸惑い、立ちすくむたびに、私は辛島夫妻に教えを請い、2人の著書をひもときました。私にとって、辛島氏監修の『インド 読んで旅する世界の歴史と文化』と貴子夫人の著書『私たちのインド』は、どちらもインド取材の礎のような本でした。
2人が暮らした街はどんな街なのか。それが知りたくて、私は南インドのバンガロールに飛び、さらに車を駆ってマイソールを訪ねました。記事になるような話は何もなく、今となってはどんな街だったのかすら思い出せないのですが、その帰り道のことはかすかに覚えています。マイソールを去り、ダム湖のほとりに辿り着いた時です。空っぽの心を抱えて、漫然と湖を眺めていると、柔らかな風が吹き、頬をかすめていったのです。「いい風だな」。生まれて初めて、心からそう思いました。そして、「これでまた明日から力を出すことができる」と感じたのです。
楽しいことや嬉しいこともあるけれど、つらいことや悲しいことの方が多いのが人生です。つらくて、つまずきそうになった時、支えてくれるのは、ささやかな喜びや小さな恵みの記憶です。この頃、しみじみそう思います。いい風に吹かれたい。そして、また少し、生きる力を補いたい。
≪参考文献≫
◎『キャスターという仕事』(国谷裕子、岩波新書)
◎『私たちのインド』(辛島貴子、中公文庫)
◎『インド 読んで旅する世界の歴史と文化』(辛島昇監修、新潮社)
◎『今夜、自由を』(上下、ドミニク・ラピエール、ラリー・コリンズ共著、早川書房)
≪写真説明とSource≫
◎高倉健
http://pinky-media.jp/I0004294
*メールマガジン「風切通信 26」 2017年4月12日
シリアでの化学兵器使用疑惑、トランプ政権によるシリア空軍基地へのミサイル攻撃と大きなニュースが続き、森友学園問題は小さなニュースになりつつあります。大阪地検特捜部は、森友学園の籠池泰典氏が国の補助金を不正に受け取った疑いがあるとの告発を受理し、補助金適正化法違反で取り調べる構えを見せています。新聞各紙はこの告発受理を比較的大きく取り上げ、「ここが落としどころ」のような報道をしています。
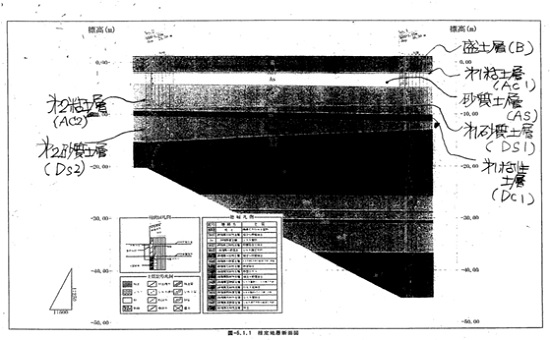
冗談ではありません。こんな報道をしているから、新聞はますます「信用できない」と相手にされなくなるのです。森友学園問題の核心は、「9億円の国有地がなぜ8億円も値引きされて森友側に売却されたのか」にあります。新聞各紙には、その核心に迫る記事が見当たりません。掘り下げようとする気迫も感じられません。そんな中で、またしてもウェブのニュースサイトに核心をつく記事が登場しました。環境ジャーナリスト、青木泰(やすし)氏の「森友問題 地中深部ごみは『存在しない』との報告書」という記事です(全文は末尾のURL参照)。
すでに報道されている通り、森友学園が「瑞穂の國記念小學院」の建設を予定していた土地は、隣の豊中市の公園建設予定地とともに国有地でした。もともと住宅地だったところを国土交通省大阪航空局が伊丹空港の騒音防止区域として買い上げ、取得した土地です。阪神大震災の後、豊中市はこの土地を防災避難公園として国から購入しようとしたのですが、財政的に全部買うのは無理だったため半分だけ購入し、あとの半分は国有地のまま残っていたものです。それを森友学園が小学校建設用地として購入した、という経緯があります。
豊中市は9492平方メートルの土地を14億2300万円で購入、一方の森友学園は隣の8770平方メートルを1億3400万円と格安の値段で購入しました。しかも、財務省近畿財務局は森友学園への売却額を非公開にしました。それを、豊中市の木村真(まこと)市議(無所属)が情報公開請求をして暴露し、8億円も値引きしていたことが明るみに出たのです。これが明らかになるや、財務省は「地下に大量のごみがある。その撤去費用として8億円値引きした」と釈明しました。とくに、「地中深くにごみがたくさんある」というのが大幅値引きの理由でした。
従って、メディアが追及すべきは「本当に地中深くに大量のごみがあったのか」という点です。青木泰氏は、技術者の立場からこの問題を掘り下げ、「地中深くにごみなどない。専門業者がボーリング調査した報告書があり、財務省が保管している」ということを突きとめ、Business Journal というニュースサイトで特報しました。
青木氏によれば、問題の報告書が作成されたのは平成26年(2014年)12月で、「(仮称)M学園小学校新築工事 地盤調査報告書」というタイトルが付いています。この報告書には土地の地層図も添えられており、?盛り土(3メートル)?沖積層(7.3メートル)?洪積層(4?7メートル)という3層になっていることが分かります。?の盛り土は、沼地や田畑だったところを宅地化するさいに盛られたもので、ここには植物の根や塩化ビニール片、木片などが混入している可能性があります。しかし、その下部、沖積層や洪積層には、大量のごみなど存在し得ないのです(あったら、考古学上の大発見になります)。
財務省はそうした報告書を保管し、土地の状況を知っていながら、国土交通省大阪航空局に「地下深くに大量のごみがあり、撤去に多額の費用がかかる」との鑑定を出させ、8億円の値引きをしていたわけです。これは国有財産の価値を不当に下げて政府に損害を与える背任行為であり、立派な犯罪です。「籠池氏は小学校建設工事の契約額をごまかして補助金を不正に受け取った」という容疑より、はるかに深刻で姑息な行為です。
そうした罪を犯した者たちが素知らぬ顔で国の財政をつかさどり、国民から税金を取り立てる。そんなことがまかり通っていいはずがありません。森友学園への8億円値引き売却を暴いた木村真・豊中市議らは3月22日、大阪地検特捜部に「財務省近畿財務局の職員(氏名不詳)が国有地を不当に安く売却して国に損害を与えた」として、背任容疑で告発しました。大阪地検特捜部は4月5日、この告発を受理し、新聞各紙はそのニュースをベタ記事で伝えました。「どうせ受理しただけ。検察には立件する気はない」と言いたいのでしょう。
検察にも心ある人はまだいる、と信じたい。告発を正面から受けとめ、「裁かれるべき者には裁きを与えなければならない」との判断が下る日が来ることを信じたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
10 情報公開制度をあざ笑う財務官僚の所業(2025年5月13日)
≪参考サイト≫
◎森友問題、地中深部ごみは「存在しない」との報告書(青木泰氏、Business Journalのサイト)
http://biz-journal.jp/2017/04/post_18667.html
◎環境ジャーナリスト、青木泰(やすし)氏による解説「実はなかった8億円のごみ」の動画(ユーチューブ)
https://www.youtube.com/watch?v=Cxm6YoXgXL4
◎青木泰氏のプロフィール
http://www.hmv.co.jp/artist_%E9%9D%92%E6%9C%A8%E6%B3%B0_200000000454851/biography/media_all/
≪写真説明とSource≫
◎財務省保有の「(仮称)M学園小学校新築工事 地盤調査報告書」(平成26年12月)に添えられている地層図(記事の中ほどにあります)
http://biz-journal.jp/2017/04/post_18667_3.html
*メールマガジン「風切通信 25」 2017年3月22日
疑獄事件と言えば、政治家がその権限を使って民間人に便宜を図り、見返りに大金を受け取る、というのが通り相場でした。昭電疑獄(1948年)、造船疑獄(1954年)、九頭竜(くずりゅう)ダム疑獄(1965年)、ロッキード事件(1976年)、リクルート事件(1988年)ではいずれも政治家が巨額の金品を受け取ったとされ、収賄容疑で追及されました。

ところが、今回の森友学園への国有地売却問題はいささか様相が異なります。9億円の国有地が8億円も値引きされて払い下げられたのですから、特段の便宜が図られたことは間違いないのですが、森友側から「大金」が流れた形跡がありません。かつての疑獄とどこがどう異なるのか。それを分析した優れたリポートがあります。『サンデー毎日』の3月26日号と4月2日号に掲載された伊藤智永(ともなが)毎日新聞編集委員の記事です。
記事のタイトル「森友疑惑は思想事件である」が問題の所在を的確に表現しています。伊藤編集委員の分析はこうです。
「この事件は、安倍政治に特有の『何だか嫌な感じ』がてんこ盛りになっている。つまり、政治事件としての本筋は、『教育・首相夫人・勅語(=天皇制・国体論)・排外主義』の問題にこそある。ひっくるめて『安倍流保守』の問題と名付けよう。これは政治思想事件なのである」
森友学園問題をめぐってモヤモヤしていたものが、この記事を読んですっきりと晴れていくような気がしました。「戦後レジームからの脱却」を目指す安倍晋三首相にとって、取り戻すべき日本の美点のエッセンスは、戦前の教育勅語でうたわれていることと重なります。森友学園が推し進めようとする「日本で初めての神道に基づく小学校教育」とも共鳴するところがあります。だからこそ、昭恵夫人は講演を引き受け、「こちらの教育方針は主人もすばらしいと思っていて」と語ったと考えられるのです。
安倍首相夫妻と思想やイデオロギーを共有し、シンクロナイズする。交友もある。それゆえに、籠池泰典理事長は財務省や国土交通省との折衝で強気を押し通すことができたのではないか。官僚たちも、それを知っているから目端を利かせて譲歩に譲歩を重ねたのではないか。森友学園側から巨額の金品を贈らなくても小学校の開校準備がスムーズに進んだ背景にそうした構図があったと考えると、これまでの経緯が分かりやすくなります。
伊藤編集委員の続報「安倍政治を担いだ『保守ビジネス』」も、戦後日本の政治思想の変遷を考えるうえで、示唆に富んでいます。記事の中で、保守ビジネスの起業家の「1990年代末から保守が売り物として成立するようになった」という言葉が紹介されています。このころから、日本の神話や皇室、国史をテーマにしたセミナーを開催すると、3000円の会費で参加者が面白いように集まる。ネット塾にも有料会員が次々に登録してくる。「保守ビジネス」が成り立つようになり、太い流れになっていった、というのです。
1989年に東欧の社会主義体制が次々に倒れていきました。1991年には社会主義の本家、ソ連そのものが消滅し、共産主義・社会主義というイデオロギーは総崩れになりました。政治思想やイデオロギーという面から考えると、「社会の左翼」が真空状態になり、その空白を埋めるべき「強靭なリベラル」が育たないまま、21世紀を迎えました。空いた領域に中道と保守がじわじわと広がっていったのです。
日本では、2009年に民主党が政権の奪取に成功しましたが、ぶざまな政権運営によって有権者に愛想を尽かされ、「やっぱり自民党に任せるしかないね」という選択が定着してしまいました。そうした中でグローバリゼーションは勢いを増す。冷戦を勝ち抜いた自由主義・資本主義体制の中で、大手を振ってまかり通るのはアメリカ型の貪欲な資本主義。社会は不安定さを増し、その不安を巧みに掬い取ったのは保守のタカ派であり、極右勢力だったのです。森友学園問題はそうした中で噴き出しました。今の日本社会の病理を象徴するスキャンダルと言えるのではないか。
悲しいのは、今の日本には、これをただす勢力があまり見当たらないことです。国会での民進党議員の追及を見ていると、脱力感に襲われます。なんでこんな質問しかできないのか。自分たちで腐敗の根っこを掘り起こす力がない。一番気を吐いているのが、なんと共産党です。けれども、彼らにはノスタルジア(郷愁)はあっても、未来の展望はないでしょう。かつて腐敗した政治家に恐れられた検察官もどこへ消えてしまったことやら。
繰り言を重ねても、未来を切り開くことはできません。どんな社会も、一人ひとりの人間が集まってできています。一人ひとりが、今いる場所でできることを積み重ねて、この社会を変えていくしかありません。森友学園問題は「今、あなたにできることは何か」と問いかけているとも言えます。
山形の山村で暮らす私にできることは限られていますが、幸いなことに、こんな山奥にも光ファイバー回線が張り巡らされ、情報はあふれ返っています。ネットの海に漕ぎ出し、森友疑惑の核心に可能な限り迫るつもりです。元新聞記者として、何が至らなかったのか、深く自省しつつ。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
10 情報公開制度をあざ笑う財務官僚の所業(2025年5月13日)
≪参考サイト、記事≫
◎戦後の疑獄政治史
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/seitoron/seijikasotuishi/sengoshi.htm
◎『サンデー毎日』(2017年3月26日号)の記事「森友疑惑は思想事件である 教育勅語と安倍政権の危険度」
◎上記の記事(毎日新聞のニュースサイトから)
http://mainichi.jp/sunday/articles/20170313/org/00m/040/003000d
◎『サンデー毎日』(2017年4月2日号)の記事「安倍首相を担いだ『保守ビジネス』 稲田防衛相、森友学園、田母神俊雄の交点」
◎上記の記事(毎日新聞のニュースサイトから)
http://mainichi.jp/sunday/articles/20170319/org/00m/070/004000d
◎毎日新聞のコラム「1強栄えて吏道廃れる」(伊藤智永編集委員、3月4日)
http://mainichi.jp/articles/20170304/ddm/005/070/003000c
≪写真説明とSource≫
◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/f5b90bd8e3ab960b5bf0d8e648239e0f
*メールマガジン「風切通信 24」 2017年3月14日
森友学園への国有地売却問題には不可解なことがたくさんあります。その一つが「国会でも大阪府議会でも、小学校の建設予定地がある豊中市の議会でも、公明党の議員がまったく質問しないこと」です。公明党の支持母体である創価学会の会員の中には不満が渦巻いているとのことです。

公明党の議員はなぜ、この問題に触れないのか。その理由を探っていくと、一人の人物に辿り着きます。かつて国土交通相をつとめた冬柴鉄三代議士(故人)の次男、冬柴大(ひろし)氏です。1988年から大和銀行(現りそな銀行)に16年勤め、2004年にソニー生命保険に転職、冬柴元国交相が病没した2011年にソニー生保を退職して「冬柴パートナーズ株式会社」(大阪市)を設立しました。その代表取締役です。経営コンサルタントを業務とし、人脈紹介や助成金の申請援助を得意としている会社です。
官僚側のキーパーソンが財務省の前理財局長、迫田(さこた)英典氏(国税庁長官)とするなら、民間側のキーパーソンは、この冬柴大氏と言っていいでしょう。前回のコラムで、「この問題には疑惑の3日間がある。2015年の9月3日から5日までの3日間だ」との志葉玲(しば・れい)氏の記事を引用し、安倍晋三首相が9月4日、安保法制法案の国会審議のさなかに大阪を訪問していたことを紹介しました。安倍首相はこの日、大阪・東梅田駅前の海鮮料理店「かき鉄」で冬柴大氏と会食しています。店のオーナーは冬柴氏です。牡蠣(かき)料理の店で、父親の名前「鉄三」の一文字を冠したのでしょう。
日刊ゲンダイの電子版(3月8日)は、経営が思わしくない森友学園は小学校の建設資金に窮していたが、ある都市銀行が20億円を超す融資に応じた、と報じました。そして、その融資を仲介したのは「大臣経験者の子息A氏ではないか、という憶測が流れている」と伝えています。日刊ゲンダイの取材に対して、A氏は「その日に安倍首相と会食したのは事実です」と認めたものの、融資の仲介については「まったくありませんでした」と否定しました。この「A氏」が冬柴大氏で、融資に応じたのは彼がかつて勤めていた「りそな銀行」と見られています。
多忙を極める首相が国会審議の合間を縫って大阪を訪れてテレビに出演し、その後、経営コンサルタントと彼の店で会食する。「重要な案件があったから」と見るのが自然です。その前日、安倍首相は財務省の迫田理財局長と会い、翌日(9月5日)には昭恵夫人が森友学園経営の幼稚園で講演し、小学校の名誉校長就任を引き受けています。「疑惑の3日間」と言われる所以です。
キーパーソンが冬柴元国交相の息子では、公明党の議員は国会でも大阪府議会でも質問する気にはなれないでしょう。これで「不可解なこと」の一つへの疑問は氷解します。問題の土地の評価を民間の不動産会社ではなく、国土交通省の出先機関、大阪航空局が行ったことも「冬柴人脈」を考慮に入れれば、納得がいきます。
もう一つの疑問、土地の評価をした国土交通省大阪航空局はなぜ「ゴミの撤去」を理由に8億円も値引きしたのか。大阪航空局の鑑定によれば、縄文時代に相当する深い地層にも「たくさんゴミがあるので、撤去に多額の費用がかかる」ということになります。これに関しては、この土地の元地権者たちが怒って、メディアに発言し始めています。元地権者の1人、乗光恭生さん(元豊中市議)は「災害時の一次避難地としての役割も担う公園を建設するというから、みんなで立ち退いて土地を国に売ったのに、いつの間にか森友学園に売られていた。あそこはもともと田んぼや畑。立ち退き時に家を解体してきれいにしたのでゴミなどない」と語っています。なんということでしょうか。
森友学園の籠池泰典理事長が小学校の設置認可の申請を取り下げ、理事長も退任する意向を表明したことで、関係者はこの問題の「幕引き」を図る構えを見せていますが、冗談ではありません。「公園にする」と称して大勢の住民を立ち退かせて土地を国有化した挙げ句、元地権者たちが「ゴミなどない」と言う土地を8億円も値引きして森友学園に譲り渡し、そのうえ「ゴミの撤去」と「土壌汚染対策」の名目で1億3200万円もの公金を支給していたのです。森友学園が払ったのは、実質わずか200万円。ただ同然です。
国の財産も税金も、自分たちの裁量でどうにでもなる、と考えているのです。こんな人たちにこの国の未来を託せるのか。こんな人たちが責任を問われることもなく、のうのうと生きていていいのか。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
10 情報公開制度をあざ笑う財務官僚の所業(2025年5月13日)
≪参考サイト、記事≫
◎森友学園の資金調達問題を報じた記事(日刊ゲンダイの電子版から)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200917
◎冬柴パートナーズ株式会社の公式サイト
http://fuyushiba.com/index.html
◎産経ニュース「安倍日誌」2015年9月4日
http://www.sankei.com/politics/news/150905/plt1509050012-n1.html
◎東梅田の海鮮料理店「かき鉄」(「食べログ」から)
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27084357/
◎「公園にするというから立ち退いた」と憤る元地権者の1人、乗光恭生さんの記事(YAHOOニュースから)
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20170313-00068645/
◎メディアに経過を説明する乗光恭生さん(ユーチューブの動画)
https://www.youtube.com/watch?v=YArhC_jOI1Y
≪写真説明とSource≫
◎メディアに語る元地権者の1人、乗光恭生さん(中央)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200917
*メールマガジン「風切通信 23」 2017年3月10日
大阪の森友学園への国有地払い下げ問題は、ますます奇怪な様相を呈してきました。学園の籠池(かごいけ)泰典理事長の言動は支離滅裂ですが、国有地の売却を決めた財務省の対応も奇怪です。この問題を所管する理財局の佐川宣寿(のぶひさ)局長は3日の参議院予算委員会で次のように答弁しています。「2012年の閣僚懇談会の申し合わせで、(政治家の不当な働きかけがあれば)記録を保存することになっていますが、不当な働きかけが一切なかったので、記録は保存されていません」

この人は官僚としては優秀なのかもしれませんが、役者としては「折り紙付きの大根」です。何かを、そして誰かをかばおうとしていることが見え見えです。佐川局長はこれに先立つ、2月24日の衆議院予算委員会では次のように答弁しています。
福島伸享(のぶゆき)議員「このような異例中の異例のやり方で(国有地の処分を)やっている時の理財局長はどなたでしょうか?」
佐川理財局長「えーと、今、手もとに資料がございません。大至急、調べてきます。(質疑を中断)前々任者ということであれば、えーと、中原でございます」
福島議員「なんでそんなにとぼけるんですか。(平成)27年から28年、前任者の理財局長!」
佐川理財局長「27年の夏から28年の夏という意味で言えば、迫田でございます」
自分の前任者の名前を出したくないので、「手もとに資料がない」と言う。中座して戻ってきたら、前々任者の名前を出す。森友学園への国有地処分を決めた時の理財局長の名前を何とかして隠そうとする。が、隠しきれなくなって、ついに苗字だけ出してしまった、ということです。本当に大根です。彼が必死になってかばおうとした迫田英典(さこた・ひでのり)氏とは、どのような人物なのか。
1959年、山口県生まれ。県立山口高校から東大法学部に進み、1982年に卒業して大蔵省に入省。竹下首相の秘書官補、金融庁信用機構室長、徳島県企画総括部長、東京国税局徴収部長、関東信越国税局長、主計局次長、財務省大臣官房総括審議官を経て、2015年7月に国有財産を管理する理財局長に就任。2016年6月、1年足らずで国税庁長官に就任しています。後輩が一所懸命、守ろうとするのもうなずける経歴です。
2月28日のYAHOOニュースに掲載されたフリージャーナリスト、志葉玲(しば・れい)氏の記事「国有地8億円値引した迫田英典氏を国会に!」によれば、この迫田氏こそ、森友学園に国有地を8億円も値引きして売却した疑惑のキーマンです。志葉氏によれば、森友学園問題を解く鍵は2015年9月3日から5日までの3日間にある、といいます。
産経新聞の「安倍日誌」9月3日によると、安倍首相は午後2時17分から10分間、財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長に会いました。その翌4日、首相は国会で安保法制の法案審議が続いていたにもかかわらず、空路、大阪入りしました。大阪の読売テレビに出演し、海鮮料理店で食事をしています。翌々日の5日、安倍首相夫人の昭恵さんは森友学園が経営する塚本幼稚園で講演し、「瑞穂の國記念小學院」の名誉校長を引き受けました。なるほど、いろいろなことを想像させる3日間です。
「昭恵夫人は籠池理事長に頼まれ、断りきれなくて『名誉校長』を引き受けた」といった報道もなされていますが、むしろ、その教育方針に賛同して積極的に引き受けたのではないか。夫の安倍首相も事情を承知したうえで同時期に大阪を訪れたのではないか。もしそうならば、この疑惑をめぐる様々なことが実にすっきりと見えてきます。
権勢のピークにある首相とその夫人が賛同する小学校の設立計画。ここで思い切った仕事をすれば、強く印象づけることができる――目端の利く官僚なら「勝負のとき」と考えるでしょう。あらゆる手段を駆使して便宜を図り、売却価格も隠す。仲介する政治家も「ここで貸しを作っておいて、損はない」と蠢く。与党自民党はそんな実情が明るみに出たのでは政権の屋台骨が揺らぎかねないので、国会への参考人招致を認めない・・・。実に分かりやすい構図です。ついでに、「次の首相をめざす政治家は悠々と高みの見物」という姿も見えてきます。
今、日本の国家財政は莫大な借金を抱えて火の車です。きるだけ支出を減らして、財政を立て直さなければなりません。国有財産も大切にして、次の世代に引き継がなければなりません。それが今を生きる私たちの責任です。ですが、森友学園問題に登場する面々には、そうした責任感はかけらもないようです。それどころか、疑惑のキーマンが国民から税金を取り立てる国税庁の長官としてふんぞり返っているとは・・・
この問題は、特異な学校法人の風変りな理事長が引き起こした小さなスキャンダルではありません。安倍長期政権の下で政治家や官僚たちが何をしているのか。その陰で私たちの未来がどんな風に蝕まれているのか。それを端的に示す、極めて大きな問題です。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
【森友問題に関する筆者のコラム一覧】
1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)
2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)
3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)
4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)
5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)
6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)
7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)
8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)
9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)
10 情報公開制度をあざ笑う財務官僚の所業(2025年5月13日)
≪参考サイト、記事≫
◎「国有地8億円値引きした迫田英典氏を国会に!」の記事(YAHOOニュースのサイト)
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20170228-00068180/
◎フリージャーナリスト志葉玲氏のブログ
http://reishiva.exblog.jp/
◎迫田英典氏の略歴(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%AB%E7%94%B0%E8%8B%B1%E5%85%B8
◎産経ニュース「安倍日誌」2015年9月3日
http://www.sankei.com/politics/news/150904/plt1509040010-n1.html
◎同2015年9月4日
http://www.sankei.com/politics/news/150905/plt1509050012-n1.html
◎朝日新聞(2017年3月8日)の2面記事「理事長ら招致、自民難渋」
◎サンデー毎日(2017年3月19日号)の「森友学園と政・官 疑惑の闇」
≪写真説明とSource≫
◎記者団に囲まれる籠池泰典理事長(3月9日)(ハフィントン・ポストのサイトから)
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/09/kagoike-moritomo_n_15257798.html
*メールマガジン「風切通信 22」 2017年3月5日
こんな人物が13年間も日本の首都のトップとして君臨していたのか。3日の石原慎太郎・元東京都知事の会見を聞いて、ため息を漏らした方も多かったのではないでしょうか。築地市場の豊洲移転について、石原氏は「行政上の責任は当然、裁可した最高責任者にある」と認めたものの、あとは嘘とごまかしと言い逃れのオンパレード。その姿から思い浮かんだのは「老醜をさらす」という言葉でした。

石原氏は会見の冒頭で声明を読み上げ、「1999年4月、知事に就任して早々に豊洲という土地への移転は既定の路線であるような話を担当の福永副知事から聞いた」と述べました。まず、これが事実とは思えない。彼が都知事になる前、東京都は築地市場の移転を断念し、市場の再整備を目指していました。立体駐車場や冷蔵庫棟を新たにつくり、築地を生まれ変わらせる計画だったのです。そして、その工事は財政難のため中断していました。
当時、東京都は臨海副都心の開発に失敗し、8000億円もの借金を抱えていました。単年度会計も実質赤字が続き、財政再建団体に転落しかねない状況にあったのです。そうした中で、副知事が莫大な予算を必要とする築地市場の豊洲移転を「既定路線です」と知事に進言するなど考えられないことです。だからこそ、石原氏は「既定の路線であるような話を聞いた」という、あいまいな表現を使ってごまかそうとしたのでしょう。知事就任前に築地市場を豊洲に移す計画があったにせよ、豊洲に移転させることを決め、本格的に動き出したのは石原都政になってからです。
次に、東京ガスからの豊洲工場跡地の買収について。石原氏は「具体的な交渉は2000年10月以降、浜渦副知事に担当してもらいました。浜渦氏から、交渉の細かな経緯について逐一報告は受けていませんでした。大まかな報告は受けていたかもしれません」と述べました。巧妙な表現です。豊洲工場跡地の土地代や関連費用として1281億円。その後の土壌汚染の対策工事費を加えれば、2000億円を超す大規模なプロジェクトです。しかも、移転後に築地市場の土地を売れば、莫大な収入が見込まれ、財政再建の夢も叶う。そのプロジェクトの重要事項が知事に報告されないわけがありません。
当の浜渦武生氏は、『サンデー毎日』(3月5日号)のインタビューに答えて、土地買収交渉の経緯を語っています。東京ガスは工場跡地の売却を拒んでいました。都市ガスの製造工場だった跡地は土壌汚染がひどい。そこで、土壌汚染対策工事をしたうえでマンションやショッピングセンター、大学を誘致する開発計画を立て、すでに経営会議で正式に決定していたのです。
浜渦氏はインタビューの中で、「東京ガスが難色を示したのは当たり前です」「決定事項を蒸し返されるのは、株主への説明も大変だし困るということでした」と述べています。そこで「水面下での交渉」に入り、東京ガスが計画していた1000億円の防潮護岸工事を東京都が引き受け、代わりに土壌汚染対策工事はすべて東京ガスが行う、という方向で土地の売買交渉を進めた、と証言しています。
では、なぜ、護岸工事だけでなく、土壌汚染の対策工事まで東京都が行うことになったのか。浜渦氏は都議会での「やらせ質問」が問題になって2005年に辞任しており、その後の交渉には関わっていません。2011年に東京都と東京ガスが交わした土地売買契約に「土壌汚染対策費も東京都が負担する」との内容が盛り込まれたことについて、浜渦氏は「まったくもって分からない。私がいたら、こんなことにはならなかった」と語っています。
その後の交渉で何があったのか。売買の対象物(土地)に瑕疵(かし)があった場合、売り手(東京ガス)が責任を持って対処するのが普通の取引ですが、石原氏は会見で「瑕疵担保責任留保の報告も相談も受けていない。それはもう、(部下に)任せきり。そんな小さなことにかまけてられません」と開き直りました。860億円もの費用がかかった土壌汚染対策を「小さなこと」と言ってのける神経に、唖然とします。
土壌汚染対策のことを聞かれると、「私は専門家ではありませんから」と逃げる。「私は素人ですし、担当の司々(つかさつかさ)の職員の判断を仰ぐしかない」と部下に責任をかぶせる。挙げ句の果てに「議会も含めて都庁全体の責任じゃないですか」と言う。この人には「トップとしてすべての責任を取る」という覚悟や潔さは全くありません。
民間企業なら経営者が背任の罪に問われてもおかしくないケースです。石原氏に対しては、都民が東京都に対して「豊洲の土地を578億円で取得したのは違法だ。都は石原氏に購入の全額を請求すべきだ」との訴訟を起こしています。元都議による住民監査請求もなされています。石原氏のような破廉恥な人間は、都議会の百条委員会に証人として呼ばれても、責任逃れを繰り返すだけでしょう。法廷に引きずり出して、ぎりぎりと締め上げるしかありません。それでも、「体調がすぐれない」などと言って逃げ回るのだろうけれど。
≪参考サイト、文献≫
◎石原慎太郎氏の記者会見(3月3日)の詳細(ハフィントン・ポストのサイト)
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/02/ishihara-shintaro-conference_n_15124104.html
◎石原氏の声明全文(同サイト)
http://big.assets.huffingtonpost.com/20170303ishihara.PDF
◎週刊誌『サンデー毎日』(2017年3月5日号)
「浜渦武生・元副知事、全真相を独白。本当の戦犯は誰なのか」
◎『黒い都知事 石原慎太郎』(一ノ宮美成&グループ・K21、宝島社)
≪写真説明とSource≫
◎日本記者クラブで会見した石原慎太郎氏(ハフィントン・ポストのサイトから)
http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/02/ishihara-shintaro-conference_n_15124104.html
*メールマガジン「風切通信 21」 2017年2月22日
宮城県の伊豆沼は冬鳥の飛来地として知られ、隣接する内沼とともに、湿原の保存をうたったラムサール条約のリストに登録されています。その伊豆沼・内沼にやって来るオオハクチョウがこの冬、例年の4倍近い6000羽以上になったという話を、記者仲間の島田博さんから聞きました。

その原因が面白い。伊豆沼・内沼は蓮(はす)の花の名所としても知られています。毎年夏には淡いピンクの花が沼一面に咲き乱れ、地元主催の「はすまつり」が盛大に開かれています。ところが、岸辺のヨシが増えすぎて祭りの趣向がそがれてしまうのが悩み。そこで、ヨシを刈り取ってその繁茂を抑えるために、沼の水位を15センチほど下げたのだそうです。
宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団の研究者、嶋田哲郎さんによれば、この水位の低下が白鳥たちを呼び寄せたと考えられる、というのです。白鳥は水草の新芽や田んぼに残る落ち穂を好んで食べます。蓮の新芽やレンコン(蓮根)も好物で、白鳥は頭を水中に突っ込んで沼の底にあるレンコンを食べます。沼の水位が下がったことで、レンコンを食べられる範囲が広がり、これが飛来数の急増につながったというわけです。
「風が吹けば桶屋が儲かる」の白鳥版のような話ですが、これはいい加減な話ではなく、説得力があります。「優雅な鳥」の典型のような白鳥にとっても、食べ物が少ない冬を乗り切るのは大変なことです。春になってシベリアに帰るまでに、しっかりと栄養を蓄えておかなければなりません。一所懸命に生きていることが伝わってきます。
この話を聞いて、「白鳥たちは伊豆沼のレンコンが食べやすくなったことをどうやって知るのだろうか」という疑問が湧いてきました。毎年、伊豆沼に飛来する白鳥が何らかの方法で仲間に伝えているのか。嶋田哲郎さんの推論はこうです。鳥たちには餌場が何カ所かある。そこで仲間の様子をよく見ている。「あいつ、たくさん食べているな」と察知したら、その仲間に付いていく、というわけです。白鳥には白鳥の情報察知能力があり、ねぐらや餌場が情報交換の場になっている、と考えられるのだそうです。
「伊豆沼の白鳥飛来数、急増」の記事は、1月29日の朝日新聞宮城県版に特ダネとして掲載され、2月7日には加筆して東京発行の夕刊に転載されました。その筆者が記者仲間の島田博さんです。特ダネになった経緯がまた、興味深い。宮城県の自然保護課は毎冬、各地の白鳥などの飛来数を取りまとめて記者クラブに配布しています。この冬も投げ込み資料として配られました。目にした記者はたくさんいたはずですが、数字が羅列してあるだけの資料です。ほとんどの記者はスルーしてしまいました。
ところが、朝日新聞大崎支局長の島田さんは管内にある伊豆沼の異変に素朴な疑問を抱き、沼の環境保全に取り組む専門家に会いに行きました。そして、その背景事情を知り、特ダネとして報じるに至ったのです。彼は朝日新聞外報部時代の先輩で、元モスクワ特派員です。定年後、故郷の宮城県でシニア記者として働き続けています。「気にかかったことは愚直に追う」という新聞記者の基本動作を忘れことなく実践し、書いたのです。
特ダネにも、いろいろなものがあります。政治家や官僚がひた隠しにしている悪事を暴く衝撃的な特ダネ。権力者にすり寄って「おこぼれ」のような話をもらって書く情けない特ダネ。半ば周知の事実をきちんと取材して伝える特ダネ・・・。伊豆沼の白鳥の記事は最後のタイプです。私はこういう特ダネが大好きです。白鳥の生態や蓮とレンコン、湖沼の保全など様々なことを考えさせ、想像力を膨らませてくれます。何よりも、行間から新聞記者の一所懸命な姿が伝わってくるところがいい。
≪参考サイト≫
◎「伊豆沼の白鳥、飛来数4倍に」の記事(朝日新聞デジタルのサイト)
http://www.asahi.com/articles/DA3S12786154.html
◎宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団の公式サイト
http://izunuma.org/
◎水草を食べる白鳥(「NHK for School」のサイト)
http://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300650_00000&p=box
◎レンコンの栽培方法(「山里の素人農業」のサイト)
http://daii.jp/a_cul/renkon.php
≪写真説明とSource≫
◎宮城県伊豆沼の白鳥(「好きです。栗原」のサイト)
http://yumenet-kawashima.seesaa.net/article/332147463.html
*メールマガジン「風切通信 20」 2017年1月15日
大統領の就任式を間近に控えた今の時期、その地位に就く政治家の胸は高揚感に満ちている、というのが普通でしょう。が、今、トランプ氏の胸に渦巻いているのは怒りと困惑、いら立ちと不安ではないか。彼と彼の側近たちはロシアのプーチン政権とどのような関係にあるのか。その内実を詳細に記したとされる極秘文書がメディアで報じられたからです。

1月10日、ウェブメディアの「バズフィード」が「アメリカ大統領選挙:共和党候補ドナルド・トランプ氏のロシアにおける活動とクレムリンとの不名誉な関係」と題された極秘文書の内容を特報しました。次いで、ニュース専門テレビのCNNが「クラッパ―国家情報長官(米国の情報機関の元締め)とコミーFBI長官、ブレナンCIA長官、ロジャーズNSA(国家安全保障局)長官の4人がオバマ大統領とトランプ次期大統領に極秘文書とその要約版を提出した」と報じました。
CNNはA4判2ページ分の要約版の内容を伝え、極秘文書の詳細については「内容を確認できていない」として報じませんでしたが、バズフィードはこのCNNの報道の直後、「アメリカ国民が自ら判断できるように」と、ウェブで極秘文書の全文35ページの公開に踏み切りました(末尾のサイト参照)。
極秘文書は「ロシア政府は5年前からトランプ氏との関係を深め、支持し、支援してきた。その目的は西側の同盟を分裂させ、分断するためであり、プーチン大統領の了解を得ていた」と記し、大統領選挙ではクリントン候補の足を引っ張り、トランプ氏に有利になるように、あらゆる手段を駆使して秘密工作を繰り広げたことを明らかにしています。
その内容は詳細を極め、プーチン政権とトランプ陣営の間で定期的に情報交換がなされていたこと、ロシア側がクリントン陣営と民主党本部に大規模なサイバー攻撃を仕掛けたこと、トランプ氏の側近がプラハでロシア側と外交と安全保障にかかわる極秘の事前交渉を重ねていたといったことを具体的に明らかにしています。
その一方で、プーチン政権はトランプ氏の弱みを握ることにも力を注いでいた、としています。トランプ氏がモスクワを訪れてリッツ・カールトンホテルに宿泊した際、オバマ大統領夫妻が利用したのと同じスイートルームを予約し、この部屋に複数の売春婦を招き入れて目の前で「ゴールデン・シャワー」と称するオシッコ・プレーをさせた、といったことまで把握し、記録していたというのです。ホテルも売春婦もロシア連邦保安庁(FSB)の支配下にあり、「必要な時には脅しの材料として使える」というわけです。
この文書の内容が報じられた翌11日の記者会見で、トランプ氏はCNNを「インチキニュース fake news」と罵り、バズフィードを「ぶざまなゴミの山 failing pile of garbage」と切り捨て、文書の内容を事実上、全否定しました。会見場にいたCNNの記者は何度も「私たちを攻撃するなら質問の機会を与えてほしい」と要請しましたが、トランプ氏が彼を指さすことはありませんでした。そして、文書の内容を報じなかったメディアを褒めたたえたのです。
これに応えるかのように、バズフィードとCNNの報道について、ニューヨーク・タイムズの編集主幹は「われわれは自信を持って出せない内容を公表したりはしない」とコメントし、ワシントン・ポストの幹部は「メディア全体の信用が低下している中、悪影響を及ぼす」と懸念を表明しました(14日の朝日新聞記事)。「良識ある態度」のように見えますが、私はどちらの説明にも納得できません。
この極秘文書の存在は、昨年の夏には一部の政治家や報道関係者の間で知られていたといいます。情報の内容からいって、報道機関が裏付けを取るのは極めて難しい代物です。が、CIAやFBIといった情報機関なら、その真偽の見極めは困難ではないでしょう。彼らは、必死になってその検証を試みたはずです。そして、調べた結果、現職と次の大統領に報告するに値すると判断したからこそ、情報機関の長官4人が顔をそろえて要約版を付けて報告したのです。
ならば、大統領と次期大統領に報告したという事実を報道することのどこがおかしいのか。彼らが手にした重要な文書を主権者である国民が共有できるようにすることのどこがおかしいのか。権力者たちが「秘密にしておきたい」と考える代物を、報道機関が「裏付けできないので自分たちも内密に」と同調するのは、ジャーナリストとしての判断と責任の放棄ではないか。
今回の事態は、米英がテロ対策の名の下にインターネットや有線・無線通信といったあらゆる分野で情報を収集している問題をスノーデンが暴露した時と同じ構図です。既存のメディアはその内容を知りながら権力者におもねり、沈黙し続けました。だからこそ、スノーデンは既存のメディアではなく、ウェブで発信しているジャーナリストに全情報を提供するに至ったのです。スノーデン事件は「メディアの主役が新聞やテレビからウェブに移行しつつあること」を鮮やかに示しました。今回のトランプ極秘文書報道は、それに次ぐ象徴的な出来事になるでしょう。
この極秘文書は怪文書の類とは質的に異なります。調査の資金を提供したのは共和党主流派とクリントン陣営とされています。請け負ったのは民間の調査会社で、担当者も判明しています。ロイター通信によれば、英国の情報機関MI6や英外務省で働いた経験のあるクリストファー・スティールという人物です。ロシア通の諜報のプロです。文書を読めば、「だからこそ、これだけ迫力のある報告書をまとめることができたのだ」と納得がいきます。文書では、プーチン大統領がこのような工作に手を染めるのは「理念より国益に軸足を置いた19世紀型のグレートパワー政治を信奉しているから」と分析しています。時代錯誤の危険な政治家、との見立てです。
不勉強で私は「バズフィード BuzzFeed」というメディアを知りませんでした。2006年にジョナ・ペレッティ氏によって設立されたベンチャーメディアで、2015年には「バズフィード・ジャパン」という日本法人を作り、2016年1月から日本語版の配信も始めています。日本語版の編集長は元朝日新聞記者の古田大輔氏と知りました。
トランプ氏に「ゴミの山」と罵倒されたバズフィードのベン・スミス編集長は、極秘文書の全文公開に踏み切った後、次のようなコメントを発表しました。「この決断はジャーナリズムにおける透明性を担保し、持っている情報は読者に提供するという前提に基づいています。私たちの選択に賛成されない方もいると思います。しかし、この調査文書の公開は、2017年における記者の仕事とは何か、ということに関するバズフィードの考えを反映したものです」
まともな考え方だ、と私は思います。取材の手法と報道のあり方は時代と共に変わる。変わらなければ、時代に置き去りにされ、やがて消えていくしかない。
≪参考サイト≫
◎ウェブメディア「バズフィード」の日本語版サイトに掲載された極秘文書の記事
https://www.buzzfeed.com/bfjapannews/these-reports-allege-trump-has-deep-ties-to-russia-2?utm_term=.dfLdKde2Gd#.asV6O6LAW6
◎極秘文書の全文(英語)
https://www.documentcloud.org/documents/3259984-Trump-Intelligence-Allegations.html
◎「バズフィード」の米国版サイト(英語)
https://www.buzzfeed.com/?country=en-us
◎米国版サイトの極秘文書に関する記事(英語)
https://www.buzzfeed.com/kenbensinger/these-reports-allege-trump-has-deep-ties-to-russia?utm_term=.qb3Q2QoyjQ#.bnwy6yB4ey
◎「バズフィード」の会社概要(日本語版ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89
◎「バズフィード」の会社概要(英語版ウィキペディア)
https://en.wikipedia.org/wiki/BuzzFeed
≪写真説明とSource≫
◎11日の記者会見時のトランプ次期大統領
https://www.buzzfeed.com/bfjapannews/these-reports-allege-trump-has-deep-ties-to-russia-2?utm_term=.nsr0d09rW0#.bwGp3p06Mp
*メールマガジン「風切通信 19」 2016年11月10日
後世の歴史家は、ヒラリー・クリントン氏が敗れ、ドナルド・トランプ氏が勝った今回のアメリカ大統領選挙をどのように位置づけるのでしょうか。幾人かは「長かったアメリカの世紀が終わったことを世界に向けて告げた選挙」と記すのではないか。

メディアの多くは「大方の予想を覆してトランプ氏が勝利した」と伝えました。けれども、この表現には違和感を覚えます。確かに、米国内ではニューヨーク・タイムズをはじめとする多くの新聞が「クリントン支持」を打ち出し、各種の世論調査でも「クリントン優位」という結果が出ていました。が、世論調査での両候補の支持率の差はごくわずかでした。その差1ポイント台というのもありました。
新聞記者時代に実際に何度か世論調査を担当した経験で言えば、1、2ポイントの差は「誤差の範囲内」です。それは「情勢は混沌としていて判断不能」と言うしかない調査結果です。もともと、投票箱を開けてみなければ何とも言えない情勢だったのであり、今回の場合、「予想を覆して」という決まり文句を使うのは適切ではない。そういう表現を使う記者の胸には「私たちメディアの期待に反して」という思いが潜んでいるのではないか。
トランプ氏の主要な支持者は「アメリカ社会のエスタブリッシュメント(既得権層)に強い不満を抱く低所得の白人層」とされています。彼らにとって、ニューヨーク・タイムズなど主要なメディアは「既得権層」そのものであり、「世論調査などクソくらえ」と思って胸の内を明かさない有権者も多かったのではないか。トランプ氏が勝ったのは、そうした心理が強く働いたことを示唆しています。
トランプ氏が大統領になったら、どんな政治をするのか。私も心配です。日本や韓国がアメリカの「核の傘」で守られていることを批判し、日韓の核保有まで容認するかのような発言を聞くと、「とんでもない人物がトップになってしまった」と思います。が、同時に「アメリカ国内にはトランプ氏のように考えている人がたくさんいるのだ」という現実をあらためて突きつけられた気もします。
未来に希望があれば、人は理想や夢を追い求めます。希望が見えず、不満の種をためこめば、どうなるか。「昔は良かった」と思い出に浸り、古き良き時代を壊したものを攻撃することで溜飲を下げようとします。彼らは「アメリカの世紀が終わった」ことを認めたくないのです。トランプ氏は「再び偉大なアメリカに」というスローガンを掲げて、彼らの不満をすくい取ることに成功しました。しかし、歴史は冷厳です。「偉大なアメリカ」が同じような形で戻ってくることは決してないのです。
20世紀は「戦争と革命の世紀」であり、「アメリカの世紀」でした。それまで「世界の覇者」として君臨していた大英帝国は、第一次世界大戦で疲労困憊し、第二次世界大戦で破産寸前に追い込まれました。戦後、英国は戦争中に発行した公債の返済に追われ、広大な植民地も次々に独立し、失いました。大英帝国の栄華が戻ってくることはありませんでした。
アメリカはどちらの大戦でも、真珠湾や植民地フィリピンが戦火にさらされたことを除けば、国土が戦場になることはありませんでした。戦後、サウジアラビアをはじめとする湾岸諸国で石油利権を手にしたのもアメリカでした。政治経済や軍事、科学技術で頂点に立ち、莫大な富が流れ込みました。冷戦時代、まさに「西側の雄」でした。1991年にソ連が崩壊し、冷戦が終わった後は「唯一の超大国」と称されました。このころが栄華のピークと言っていいでしょう。
栄えれば滅びの芽が育ち始めるのは世の常です。敗戦国の日本とドイツが灰の中から立ち上がり、「もの作り」でアメリカの優位を脅かす。産油国は石油輸出国機構(OPEC)を結成して利権の独占を阻む。中国やインドの台頭も「唯一の超大国」の地位を揺るがし始めました。「慣性の法則」が働きますので、アメリカの優位はもうしばらく続くでしょうが、元の立場に戻ることは考えられません。
時に小さな逆流や揺り戻しが起きることはあっても、大きな歴史の流れを押しとどめることは誰にもできません。トランプ氏の勝利は、そうした「小さな逆流」の一つでしょう。ただ、アメリカという国家は巨大なので、歴史的に見れば「小さな逆流」ではあっても、日本を含め多くの国には「大きな衝撃波」となって跳ね返ってくるかもしれません。
21世紀はどんな世紀になるのか。予測は困難ですが、少なくとも「アメリカの世紀」と呼ばれることはないでしょう。多極化、分極化が進むのは避けられません。今はただ、それが流血と戦争に至ることがないように、調整と和解の新しいシステムがつくりだされることを願うしかありません。単に願うだけではなく、そのためにできることを自分の持ち場でコツコツと積み重ねるしかありません。歴史は、より自由で、より公平で、より透明な世界に向かって進んでいる、と信じて。
≪参考文献≫
◎『覇者の驕(おご)り』(上、下)(デイビッド・ハルバースタム、日本放送出版協会)
◎『石油の世紀』(上、下)(ダニエル・ヤーギン、日本放送出版協会)
◎『東西逆転』(クライド・プレストウィッツ、NHK出版)
◎『アメリカ 多数派なき未来』(浅海保、NTT出版)
≪写真説明とSource≫
◎大統領選で当選を決め、ガッツポーズをするトランプ氏=ロイター・共同
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201611/CK2016111002000130.html
*メールマガジン「風切通信 18」 2016年11月7日
絵画も陶磁器も、素人の私には正直言ってその価値や良さはよく分かりません。ただ、眺めるのは好きで、時折、強く惹きつけられ、心を揺さぶられることがあります。3年前、鹿児島県の薩摩焼の窯元(かまもと)、十五代沈壽官(ちん・じゅかん)さんの作品に初めて接した時もそうでした。象牙細工のような繊細な陶磁器を見て、「なんて美しく優雅なのだろう」と感じ入りました。

この時に沈壽官さんから、薩摩焼の歴史についてもお聞きしました。16世紀末、豊臣秀吉が朝鮮半島に2度にわたって出兵した際、諸藩の武将は撤収時に朝鮮半島の陶工や木綿職人、測量技師といった人たちを一種の戦利品として多数、日本に連れ帰りました。その数は5万人とも言われ、彼の先祖もその一人だったのです。彼らは先進技術を持つ者として厚く遇され、陶工たちは各地で窯を立ち上げました。薩摩焼だけでなく、有田焼や加賀焼、萩焼もこの時代に始まったとのことでした。
その沈壽官さんがこの秋、盛岡市の百貨店「川徳」で個展を開くというので、盛岡を訪ねました。10月25日まで開かれた個展は大変なにぎわいで、ギャラリートークの際には椅子が足りなくなり、主催者側があわてて追加していました。彼のトークがまた味わい深かった。韓国にルーツを持ち、日本に根を下ろして生きてきた者として、沈壽官さんは両国の文化について、こんな話をしました。
「韓国の古い陶磁器としては、高麗時代の青磁があります。ところが、14世紀末に李氏朝鮮が成立すると、それまでの青磁は打ち捨てられ、以後は白磁一色になりました。それまでのものを否定して、新しいものを創っていく。否定と創造の文化です。日本はまるで異なります。自然災害から逃れられない社会だからでしょうか。日本人の心には無常観が染み込んでいます。そして、連綿として受け継いできたものを大切にして、それをより良いものにしていく。諦観と継承の文化と言っていいのではないでしょうか」
興味深い文化論でした。そして、これと重なるような話を私の故郷、山形県朝日町のリンゴ農園経営者、崔鍾八(ちぇ・じょんぱる)さんから聞いたことを思い出しました。崔さんは、2018年に冬季五輪が開かれる韓国・平昌(ピョンチャン)生まれの46歳。23歳の時に日本に留学し、仙台の農業短期大学で学んでいる時に朝日町の「清野りんご園」の跡取り娘と知り合って結婚、リンゴ栽培専業の共同経営者として暮らしています。
崔さんはカヌーが趣味で、私が主宰する地域おこしのNPO「ブナの森」のメンバーです。毎年夏に最上川の急流をカヌーで下るイベントを開催しており、その準備のために一緒に河川敷の草刈りをしたりしています。そうした作業をしながら、いろいろな話をするのですが、ある時、崔さんから韓国の言語事情について、こんな話を聞きました。
「韓国では漢字をほとんど教えていない。義務教育を終えた段階だと、自分の名前を漢字でやっと書ける程度です。それではいけない、と思ったのは日本に来てからです。例えば、学期末の試験のことを韓国語で『キマル・ゴサ』と言います。私は、ハングルで書かれたものを『音』として覚えて使っていましたが、日本に来て、それが『期末考査』のことだと初めて知りました。こうした日本語由来の言葉が韓国にはたくさんある。なのに、漢字を教えないので、そもそもの意味が分からないまま使っている。だから、言葉に深みがないのです」
日本も韓国も、大昔に中国の漢字を導入して長い間使ってきました。日本はその漢字を崩して平仮名と片仮名を生み出しましたが、漢字もそのまま使い続けました。一方の韓国は、15世紀に漢字とは関係なく「ハングル文字」を生み出し、その後、歴史的な経緯もあって漢字を締め出して今日に至っています。現在の両国の言語状況もまた「否定と創造」、「諦観と継承」の一例のように思えてきます。
歴代政権のトップが追いつめられ、断罪される韓国。一時は野に下ったものの自民党が息を吹き返し、権力を握り続ける日本。これも「否定と創造」、「諦観と継承」の一例かもしれません。
≪参考サイト≫
◎薩摩焼・十五代沈壽官の公式サイト
http://www.chin-jukan.co.jp/
◎清野りんご園(山形県朝日町)の公式サイト
http://www.47club.jp/07M-000037sre
≪写真説明とSource≫
◎十五代沈壽官の薩摩籠目総透筒型香爐
http://www.chin-jukan.co.jp/museumPreview.php?num=32&TB_iframe=true&width=520&height=500
*メールマガジン「風切通信 17」 2016年10月24日
アメリカは厄介な問題をたくさん抱えている国です。傲慢さに腹が立つこともあります。けれども、米国発のこういう記事を読むと、「活力にあふれた、実に面白い国だ。この世界を良くするために闘う気概にあふれている」とあらためて感じます。
「ヤクザ・オリンピック」と銘打った記事が米国のウェブ情報サイト「デイリー・ビースト」に掲載されたのは2014年2月8日(米東部時間)のことでした。ロシアのソチで冬季五輪が開催されているさなか、森喜朗・元首相がその直前に東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長に選出されたタイミングをとらえて、気鋭のジャーナリストが放ったスクープです。それは次のような書き出しで始まります。
「米財務省は2012年9月、日本で2番目に大きい暴力団住吉会とその会長、福田晴瞭(はれあき)氏ら幹部に制裁措置を課した。これによって、米国内の彼らの資産は凍結され、米国の企業や団体は彼らと取引できなくなる。福田氏とその仲間は米国政府のブラックリストに載せられたが、日本オリンピック委員会(JOC)は彼らを『歓迎されざる団体』とは見ていないようだ。写真や文書、住吉会関係者の証言、警察筋によると、JOCの田中英壽(ひでとし)副会長は住吉会の福田会長とかつて昵懇の間柄(good friends)にあった。田中氏は日本最大の暴力団山口組や他の暴力団のメンバーとも交友がある」
「田中氏に加えて、森喜朗・元首相もヤクザと付き合いがあったとメディアで報じられている。彼は1月24日に東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長に就任した。警察筋は、この2人がヤクザと過去にどのくらい関わりがあったのか、現在どの程度のつながりがあるのかを調べている、と語った。安倍晋三首相は誘致の際、2020年東京五輪はクリーンで犯罪と無縁の大会になると約束したが、書籍や雑誌、ゲームソフトでのヤクザの人気ぶりを考えると、そのようなイメージは持てない。東京五輪は『ヤクザ・オリンピック』として、多くの観光客を惹きつけることになるのではないか」
JOC副会長の田中英壽氏は日本大学の理事長です。日大相撲部の選手として学生横綱になり、相撲部の監督、日大常務理事を経て理事長に上り詰めました。1998年、福田晴瞭氏が住吉会の二代目会長を襲名し、ホテルニューオータニで襲名披露のパーティーを開いた際、田中氏はその祝いに駆けつけ、一緒に写真に収まっています。スポーツ界からの暴力追放をうたうJOCは、暴力団の会長襲名披露宴に出席するような人物を副会長に据えているのです。もう一人の森喜朗氏も暴力団との付き合いが長い。暴力団稲川会の会長らが主賓の結婚式に出席して来賓としてあいさつしていたことや大阪で暴力団の幹部と酒を酌み交わしていたことが週刊誌で報じられています。
米国発の記事は、こうした日本国内での報道を警察関係者への取材で裏付けし、田中英壽氏と森喜朗氏の暴力団との付き合いが長くて深いものであることを明らかにしています。そして、東京五輪では開催に向けて巨額の公共事業が行われること、暴力団にとって土木建設工事は大きなビジネスチャンスであること、入札をめぐる情報をいち早く入手するために暴力団がJOCや五輪組織委とのコネを必要としていることを指摘しています。今日の東京五輪の競技会場建設をめぐる騒動や築地市場の豊洲移転をめぐる疑惑を見通していたかのような、鋭い記事です。
この記事を書いたジェイク・エーデルスタイン記者は米国ミズーリ州の出身です。19歳で来日し、上智大学で日本文学を専攻した後、読売新聞に外国人初の記者として採用されました。社会部に所属し、日本の暴力団を徹底的に取材した記者です。山口組系の後藤忠政組長が米国で肝臓移植手術をするためFBIと取引していることをスッパ抜こうとして後藤組に察知され、家族ともども脅されたため読売新聞を退社して帰国した、と別の記事で明らかにしています。米国に拠点を移して、日本の裏社会を追い続けているのです。
記事を掲載した「デイリー・ビースト」というウェブ情報サイトも面白い。直訳すれば「野獣日報」。編集長のモットーは「われわれはスクープとスキャンダル、秘められた物語を追う。ごろつきや頑固者、偽善者に立ち向かうことを愛する」。米国内で「ベストニュースサイト賞」を2度受賞しているだけのことはあります。
当時、日本のメディアはこの記事を黙殺しました。転電したのは日刊ゲンダイだけだった、ということを前々回のコラムで紹介した『2020年東京五輪の黒いカネ』(宝島社)で知りました。こういう記事が出ると、「そんな裏の事情など知っていた。だけど、書けない事情があるんだ」とうそぶく記者がいます。立花隆氏が『文藝春秋』で田中角栄首相の金脈と人脈を暴露した時にそうであったように。しかし、書かない記者、書かれない記事には何の価値もありません。半ば周知の事実ではあっても、それをきちんと調べ、的確に書くことは大変なエネルギーと勇気を要することです。
この記事が優れているのは、政治家とゼネコン、暴力団というトライアングルが持つもう一つの意味を暗示しているところにあります。政治家が一番恐れるのは、談合にかかわったり、入札情報を流したりしたことが発覚し、捜査の対象になって政治生命が危うくなることです。どんなに揉まれていても、ゼネコンの幹部や社員は堅気のサラリーマンです。検察官の前に引きずり出されて尋問されれば、動揺してしゃべってしまう恐れがあります。が、互いに暴力団を経由して情報をやり取りすればどうか。
暴力団はもともと「法の支配」など気にしていません。検察官など怖くはありません。刑務所に行くことも厭いません。むしろ、箔が付くくらいです。情報を暴力団経由で流すことで発覚のリスクは格段に小さくなります。暴力団と付き合う政治家はそのメリットを十分に承知しているのです。暴力団が手に入れた資金を「マネーロンダリング」できれいにしようとするように、政治家は入手した事業計画や入札価格を暴力団経由でゼネコンに流して「情報ロンダリング」をしてきたのでしょう。
森喜朗・元首相や石原慎太郎・元都知事といった面々はその効用をよく知っているからこそ、ゼネコンと暴力団の両方と付き合い、社会の表と裏を巧みに泳いできたと考えられます。このまま逃げ切れるか、それとも棺の蓋が閉まる前に悪事の数々が白日の下にさらされるのか。今回の騒動は伏魔殿・東京の改革などという枠を越えて、日本の政治や司法の成熟度、社会そのものの成熟度が試される機会となるのではないか。
≪参考サイト&文献≫
◎デイリー・ビーストの記事「ヤクザ・オリンピック」(英文)
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/07/the-yakuza-olympics.html
◎ウィキペディア「福田晴瞭・住吉会会長」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E6%99%B4%E7%9E%AD
◎日本大学の公式サイトにある田中英壽理事長のプロフィール
http://www.nihon-u.ac.jp/history/successive/chairman_12.php
◎英語版ウィキペディア「The Daily Beast」
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Beast
◎The Daily Beast の公式サイト(英文)
http://www.thedailybeast.com/
◎日本語版ウィキペディア「ジェイク・エーデルスタイン」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3
◎『2020年東京五輪の黒いカネ』(一ノ宮美成+グループ・K21、宝島社)
≪写真説明とSource≫
◎暴力団住吉会の福田晴瞭会長(右)の襲名披露パーティーに出席した田中英壽氏(左、現在はJOC副会長、日大理事長)
http://urashakai.blogspot.jp/2015/07/blog-post_22.html
*この写真について、アークレスト法律事務所の野口明男弁護士から「依頼者は本件投稿に掲載されている肖像画像の掲載を許可した事実はないため、依頼者に対する肖像権侵害に該当します」との削除要請がインターネットサービス会社経由で寄せられました。画像に写っている田中英壽氏から許可を得たわけではありませんので、要請を受けて2021年9月17日に削除しました。
*メールマガジン「風切通信 16」 2016年10月18日
新潟県の知事選挙で野党3党の推薦を受けた米山隆一氏(医師、弁護士)が、自民党と公明党が推薦した森民夫氏(前長岡市長)を破って当選しました。米山氏の立候補表明は告示の6日前。一方の森氏は自民、公明の推薦に加えて連合新潟の支持も得て、早くから事実上の選挙戦を展開していました。各政党のいわゆる「基礎票」だけをみれば、誰がみても「森氏の楽勝」のはずでした。
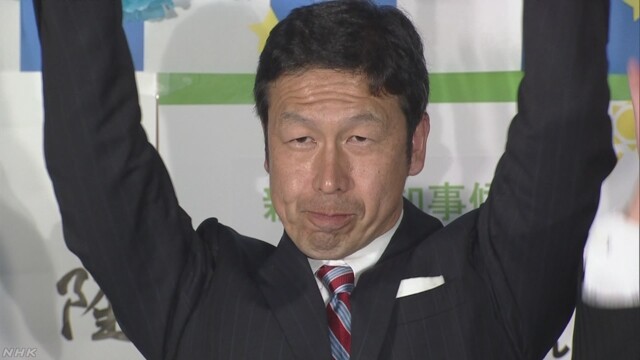
選挙結果は、そうした事前の予想を覆しました。何が起きたのか。新聞各社が投票直後に実施した出口調査をみれば、それは明らかです。新潟県の柏崎刈羽(かりわ)原発の再稼働には有権者の6割が反対しています。普段、自民と公明を支持している有権者のかなりの部分が再稼働に反対する米山氏に投票したのです。「政党の基礎票をもとに考える」という従来の政治手法、選挙分析そのものが「大きなテーマ」が争点になった場合には役に立たないということを示しています。
当選後に米山氏が発したメッセージは実に明快でした。彼は「原発再稼働に関しては、皆さんの命と暮らしを守れない現状で認めることはできない」と明言したのです。新潟県知事選は、原発の再稼働の是非という問題を越えて、実は「私たちの命と暮らしをどう守り、これからどのような道を切り開いていくのか」というより大きなテーマが問われた選挙だったのではないか。
新聞各紙は「柏崎刈羽原発の再稼働が遠のけば、東京電力の経営再建が危うくなり、日本のエネルギー政策そのものが揺らぐ」といった解説記事を載せました。もちろん、そうしたことも重要なことですが、世の中には経済の効率や発電のコストよりもっと重要なことがあります。それは「私たちはどのような社会、どのような未来を望むのか」ということです。
原子力発電について、政府与党も経済産業省も電力各社もずっと「日本では炉心溶融のような過酷事故はあり得ない」と言ってきました。「だから、広域の避難計画は必要ない」と主張してきました。そうした説明はすべて虚偽でした。しかも、そのように説明してきたことを心から謝罪し、進むべき道を根本から考え直そうとする政治家、官僚、経済人はほとんどいません。
福島の原発事故の検証もまともにせず、放射性廃棄物をどう処理するかの目途も立たないのに、原発の再稼働と輸出にしゃかりきになる政治家、官僚、財界人。誰も責任を取ろうとしない。誰も改めようとしない。そんな政治でいいのか。そんな社会でいいのか。新潟県の有権者は「いいわけがない」という強烈なメッセージを発した、と言うべきでしょう。
メディアは、日本のエネルギー政策や電力供給、経済全体への影響という面からの分析に力を入れがちです。もちろんそれも必要ですが、一人ひとりの心の在り様、未来への眼差しは実はもっと「大きなテーマ」なのではないか。それを的確に伝える記事が少なかったことに寂しさを感じたのは私だけでしょうか。
心に浮かぶのは福島県の飯舘(いいたて)村の光景です。私が初めてこの村を訪れたのは2007年の晩秋のことでした。日本の町や村に残る伝統や文化に触れ、その魅力をあらためて見出すことを目指す「日本再発見塾」がこの村で開かれると知り、参加しました。飯舘は阿武隈山系の高原に広がる人口6000人ほどの小さな村ですが、高原の地形と気候を活かして畜産や野菜・花卉(かき)の栽培に取り組む元気な村でした。
1989年に「一番きつい立場にある嫁を海外旅行に送り出す」という試みを始めた村としても知られています。「若妻の翼」と名付けられたこの事業は、稲刈りの準備が始まる初秋に行われました。「若い女性たちがどれだけ大きな役割を果たしているか。一番忙しい時期に送り出すことで分かってほしかった」と、当時の村長は語っています。19人がヨーロッパに旅立ち、その体験を綴った『天翔けた19妻の田舎もん』は、地域おこしに取り組む人々を大いに勇気づけました。
5年前の福島原発事故で放射能に汚染され、この村が全村避難に追い込まれたことはご承知の通りです。苦しい中で、村民が力を合わせて取り組んできた様々な試みはすべて吹き飛ばされてしまいました。日本再発見塾に参加した時、私が宿泊させていただいた藤井富男さんの家族も住み慣れた土地を追われ、福島市のアパートで避難生活を始めました。事故の翌年、人影が消えた飯舘村を歩き、その帰りに藤井さんの避難先を訪ねました。「畑に出られなくなって、父ちゃんは元気ないです」と嘆いていました。
原発事故は数万、数十万の人たちに藤井さんの家族と同じ苦しみを与え、今も与え続けています。それは避難に伴う補償金をいくら積もうと、償えるものではありません。福島から多くの避難者を受け入れ、支えてきた近隣の宮城や山形、新潟の人たちはその悲しみを肌で知り、一人ひとりが「原発って何なんだろう」とずっと考えてきたのです。その思いは、安全な東京で机に座って「エネルギー政策はどうあるべきか」とか「発電コストはどのくらいか」などと頭をひねっている政治家や官僚より、もっと切実なのです。
せつないのは、この国にはそうした思いを受けとめる政党が見当たらないことです。自民党や公明党は現世利益にしがみつき、そっぽを向いています。民進党は今回の新潟県知事選で自主投票という名の「逃亡」をしました。終盤にドタバタと、蓮舫代表が米山氏の応援に駆けつけても「逃亡」の烙印は消せません。「大きなテーマ」に出くわすたびに、この政党はバラバラになって逃げ出してしまうのです。
米山氏を推薦した3党はどうか。共産主義の実現を目指す政党に私たちの未来を託すことができるでしょうか。自由党? 代表の小沢一郎氏は東日本大震災と福島の原発事故で人々が苦しんでいる時に、被災地を訪ねるどころか東京から逃げ出す算段をしていた政治家です。社民党は「過去の政党」。私たちの思いを掬い取ってくれる政党はどこにも見当たりません。多くの人が深い悲しみをもって、投票所に足を運んだのではないか。
≪参考文献&サイト≫
◎ウィキペディア「米山隆一」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E9%9A%86%E4%B8%80_(%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6)
◎米山隆一氏の公式サイト
http://www.yoneyamaryuichi.com/profile.html
◎『飯舘村は負けない』(千葉悦子、松野光伸、岩波新書)
◎「日本再発見塾」の公式サイト
http://www.e-janaika.com/index.html
≪写真説明とSource≫
◎新潟県知事選で当選した米山隆一氏
http://togetter.com/li/1037751
*メールマガジン「風切通信 15」 2016年10月15日
石原慎太郎・元東京都知事の三男、石原宏高(ひろたか)代議士とは一度だけ、一緒に食卓を囲んだことがあります。昔の取材ノートを繰ってみると、2006年5月29日のパワーブレックファストの席でした。「忙しい人が昼もしくは夜に時間を取るのは難しい。朝なら集まりやすい」というので流行った朝の食事会でのことです。

主賓は、来日したフィリピンのデヴェネシア下院議長。当時、私はアジア担当の論説委員をしており、フィリピンの政情に詳しいジャーナリスト、若宮清氏に誘われて参加したのでした。会場はデヴェネシア氏が滞在していたホテルニューオータニの一室。6人ほどでテーブルを囲んだ記憶があります。この朝食会に宏高代議士も同席していました。
話題の中心はフィリピンの内政で、英語での懇談でした。宏高氏は政治家になる前、日本興業銀行のニューヨーク支店やバンコク支店で勤務していますので、英語での会話にも不自由しなかったはずですが、終始寡黙でほとんど発言しませんでした。食事の前後に記した取材メモにも「昭和39年6月19日生まれ、41歳。東京3区選出の衆議院議員。石原慎太郎の3男坊」などの略歴以外、何も記述がありません。
それでもこの会食のことを覚えていたのは、宏高代議士がずっとオドオドしていたからです。かすかながら、目には怯(おび)えのようなものがありました。気楽な朝食の席なのに、なんでそんな目をしているのか。当時は「父親の石原慎太郎氏が立ち上げた新銀行東京がらみで、苦労しているのかな」くらいに考えていました。けれども、最近明らかになった東京都をめぐる様々な疑惑を調べていくうちに、その怯えの一端が分かったような気がしました。彼が足を踏み入れた東京の闇はとてつもなく深く、暗いものだったのではないか。
石原宏高代議士をめぐるスキャンダルで一番有名なのは「森伊蔵疑惑」です。彼は2005年9月11日投開票の総選挙で初当選しました。その直後、9月14日の夜に銀座の老舗料亭、吉兆でその当選祝いの会が開かれました。呼びかけ人は、三重県の中堅ゼネコン水谷建設のオーナーで「平成の政商」として知られる水谷功氏です。祝いの会には宏高代議士に加えて父親の石原慎太郎氏も招かれ、富豪の糸山英太郎氏も同席しています。この時に鹿児島の芋焼酎「森伊蔵」の箱に詰めて2000万円の祝い金が手渡された、とされる疑惑です。これは資金を提供した関係者の間でゴタゴタがあって表面化したものの、証言が食い違ったこともあってうやむやのまま蓋をされてしまいました。
宏高氏の選挙区は東京3区です。品川区と大田区の一部、小笠原諸島などが地盤で、昔ながらの町工場が多いところです。石原慎太郎都知事の主導で2005年4月に新銀行東京が設立されるや、宏高氏の選挙区にある中小企業からは融資の申し込みが殺到し、どさくさの中で詐欺師や暴力団関係者も新銀行東京の金に群がりました。森伊蔵の箱が手渡された頃、新銀行東京はすでに「金のむしり取り合戦の場」になっており、宏高氏は困惑と混乱の中にあったと思われます。
宏高氏は「選挙が弱い」ことで知られています。そういう政治家には「折り目正しいスポンサー」は付かないものです。有象無象が集まってきます。宏高氏の選挙を支えたグループ、大手パチスロメーカー「ユニバーサルエンターテインメント(UE)」もそうしたスポンサーの一つです。2009年の総選挙で宏高氏が落選すると、UEは彼の妻が代表を務める会社に毎月100万円のコンサルタント料を払って、落選中の活動と生活を支えました。
UEの創業者、岡田和生氏は高額納税者日本一になったこともある大富豪です。日本国内でのビジネスに加えて、フィリピンで巨大なカジノリゾートの建設を進めており、石原慎太郎・宏高親子が2010年6月にマニラを訪問した際には、石原親子に先立ってマニラに入り、訪問の地ならしをしています。石原親子は日本でのカジノ解禁を熱心に唱えており、持ちつ持たれつの関係にあったことを示しています。
一ノ宮美成氏ら関西在住ジャーナリストの共著『2020年東京五輪の黒いカネ』によると、このフィリピンでのカジノリゾート計画をめぐって、UEの岡田氏はカジノライセンスの取得がらみで4000万ドルをフィリピンに送金し、そのうちの1000万ドル(約10億円)を日本に還流させたことが明らかになっています。そして、その金は日本での政界工作に使われ、一部は石原慎太郎氏に流れた疑いがある、というのです(p204)。与野党の政治家が「日本でのカジノ解禁」に熱を上げる裏ではそうした工作が行われており、石原親子もその渦にドップリと漬かっていたということです。
築地市場の豊洲移転や東京五輪がらみの大規模な公共事業をめぐって、日本の政治家や企業が黒幕や暴力団まで巻き込んで、どのような利権争奪戦を繰り広げているのか。前掲書には、日本オリンピック委員会の竹田恒和会長(旧皇族竹田家の出身)や皇族と旧皇族でつくる親睦団体「菊栄親睦会」の存在、この親睦会を支えるゼネコンの鹿島、日本生命、裏千家、和歌山県の世耕一族(世耕弘成参議院議員の一族)の思惑、彼らを取り巻く右翼団体の人脈も紹介されていて、その叙述は迫力満点です(p47)。
東京都知事の交代によって、蓋をされていた「東京の闇」に少しずつ光が当てられ、患部の摘出が始まろうとしています。親の七光りを浴びて若くして代議士になった宏高氏は、当選した直後から、こうした東京の深い闇の中に叩き込まれ、身悶えしていたのではないか。怯えたようなあの目はその苦しみを映し出していた、と今にして思うのです。
≪参考文献&サイト≫
◎『2020年東京五輪の黒いカネ』(一ノ宮美成+グループ・K21、宝島社)
◎石原宏高代議士の公式サイト
http://www.ishihara-hirotaka.com/
◎ウィキペディア「水谷建設」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%B0%B7%E5%BB%BA%E8%A8%AD
◎ユニバーサルエンターテインメントの公式サイト
http://www.universal-777.com/corporate/
◎英紙フィナンシャル・タイムスの電子版記事「日本のパチンコ王がフィリピンでのカジノ建設に挑戦」(2016年6月11日)
https://courrier.jp/news/archives/53985/
◎日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長のプロフィール(ウィキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E6%81%86%E5%92%8C
◎ウィキペディア「菊栄親睦会」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%A0%84%E8%A6%AA%E7%9D%A6%E4%BC%9A
≪写真説明とSource≫
◎石原宏高代議士
http://www.t-hamano.com/cgi/topics2/topics.cgi
*メールマガジン「風切通信 14」 2016年10月7日
いつ、誰が豊洲新市場の建物の下に盛り土をしないと決めたのか。小池百合子・東京都知事は先週、都職員による自己検証報告書を発表し、責任者を「ピンポイントで指し示すのは難しい」と述べました。なぜ難しいのか。実は、それを決めたのは当時の石原慎太郎都知事とその取り巻きであり、都庁の幹部や職員は決定の理由と背景を知らされていなかったからではないのか。今週発売の週刊誌『サンデー毎日』がその内実を詳しく報じています。

『サンデー毎日』のトップ記事「豊洲疑惑の核心! 石原都政の大罪」は、都庁幹部やOBに取材し、「盛り土の設計変更を言い出したのは、石原慎太郎都知事を支えていたメンバーです」との重要な証言を引き出しています。なぜ、設計の変更が必要になったのか。その背景にあったのは、石原氏が立ち上げた新銀行東京の経営破綻だったというのです。
新銀行東京は、石原氏が「金融機関の貸し渋りに苦しむ中小企業を救済する」と唱えて立ち上げた「官製銀行」です。東京都が1000億円を出資して2005年4月に発足しました。当初から、「バブルの崩壊後、景気が低迷して既存の銀行ですら苦しんでいるのに、役人がつくる銀行がうまくやっていけるわけがない」との批判が噴出しました。が、石原氏は「東京から金融改革を果たす」と反対論を押し切りました。
石原氏の政策と発言はいつも威勢がいい。けれども、誠実さと慎重さを欠くので、しばしば破綻する。新銀行東京も発足から3年で不良債権の山を抱えることになりました。経営不振の企業や詐欺師まがいの輩が国会議員や都議の口利きで次々に融資を申し込み、踏み倒したからです。これで軌道修正するなら救いがありますが、石原氏はさらに400億円もの追加出資をして傷口を広げ、厳しい批判にさらされました。
土壌汚染を解決するため、豊洲新市場の予定地全体に盛り土をしなければならないとの専門家会議の提言が出されたのはこの頃です。費用はまたもや1000億円余り。盛り土工事をそのまま実行したら、都政への逆風は強まり、ダメージは計り知れない。そこで、都知事とその取り巻きで「設計の変更による経費の削減」へと突き進んでいった、と記事は伝えています。
たとえ都知事からそうした指示が出されたとしても、「食の安全を損なうような設計の変更はすべきでない」と進言するのが都庁幹部の役割でしょう。ですが、石原都政の下でそのような進言をすることは即、更迭を意味していました。トップも側近も強面ぞろい。「金満自治体」の東京都にそうした気骨のある幹部を求める方が無理でした。都議会与党の自民党と公明党は一蓮托生の関係、野党民主党の一部もすり寄り、議会はチェック機能を果たせませんでした。
せめて、「設計を変更して主な建物の下には盛り土はしない」と正直に発表していれば、救いようもありました。ところが、当時の政治情勢がそれを許さなかった。2007年の参院選で民主党が大勝し、2009年の都議選と総選挙でも自民党は大敗しました。「盛り土をしない」などと発表しようものなら、築地市場の移転に反対していた陣営が勢いづき、市場の移転計画そのものが頓挫してしまう。知事と周辺はそれを恐れて「盛り土せず」を覆い隠してしまった――というのが『サンデー毎日』の報道です。
見出しの謳い文句に偽りはなく、文字通り「疑惑の核心をつく」優れた記事ですが、実はこの週刊誌が発売される数日前に、私は山形県立図書館で偶然、築地市場の移転や新銀行東京の問題をえぐった本に出くわしました。『黒い都知事 石原慎太郎』(宝島社)という本です。東日本大震災の直前、2011年1月の出版。執筆したのは、関西を拠点とする一ノ宮美成(よしなり)氏とグループ・K21というジャーナリスト集団です。
この本は、羽田空港の沖合拡張工事をめぐる黒い利権疑惑から説き起こし、石原慎太郎氏と大手ゼネコン鹿島(かじま)のつながり、鹿島と指定暴力団・住吉会との関係を詳述した後、石原氏がなぜ「築地市場の豊洲への移転」に固執したのかを大きな文脈の中で活写しています。鈴木俊一都知事時代に始まった臨海副都心開発の失敗で、東京都は8000億円もの借金を抱え、臨海開発の事業会計は大赤字に陥っていた。築地市場を豊洲に移転し、都心の一等地であるその跡地を民間に売却すれば赤字を一挙に解消できる。それで移転に固執した、というのです。
東京五輪の誘致も同じような動機とされています。オリンピックを起爆剤にして各種スポーツ施設や環状2号線の建設を進め、臨海副都心の開発を軌道に乗せて東京再生へとつなげる、という発想です。かつて田中角栄首相が唱えた「日本列島改造」の東京版ともいうべき構想。それを経済が右肩下がりになった時代に無理やり推し進め、政治家やゼネコンが利権漁りに躍起になったことが、今日の豊洲市場や東京五輪をめぐるスキャンダルにつながっている、というわけです。
大言壮語の裏で利権漁りに走り回り、疑惑が表面化するや逃げ回る。そのような政治家が国会議員として肩で風を切り、東京都知事として13年間も君臨していたのかと思うと、怒りより情けなさが募ります。石原慎太郎氏の公式サイト「宣戦布告」に、彼が政界を引退した際の挨拶文が載っています。
「見回して見ると世界の中で今の日本ほど危うい立ち位置におかれている国はないような気がしてなりません。(中略)他力本願で贅沢を当たり前のこととするような心の甘えを払拭していかないとこの国は立っていけないのではないでしょうか」(2014年12月)
盗人猛々(たけだけ)しい、とはこういう時に使う言葉でしょう。
≪参考記事、文献、URL≫
◎週刊誌『サンデー毎日』10月16日号の記事「豊洲疑惑の核心! 石原都政の大罪」
◎『黒い都知事 石原慎太郎』(一ノ宮美成+グループ・K21、宝島社)
◎石原慎太郎公式サイト「宣戦布告」
http://www.sensenfukoku.net/
≪写真説明とSource≫
◎石原慎太郎氏(2007年2月6日)
http://www.huffingtonpost.jp/2013/09/23/sakaicity-ishihara-yaji_n_3979408.html
*メールマガジン「風切通信 13」 2016年9月30日
大阪府と大阪市による二重行政の無駄と非効率を批判して「大阪都構想」を推し進めた橋下徹氏は、その言動から判断して「保守の政治家」に分類していいでしょう。東京の改革を訴えて都知事選に勝ち、築地市場の移転と東京五輪開催費用の検証に乗り出した小池百合子氏はもともと自民党の代議士ですから、間違いなく保守の政治家です。

東京と大阪。日本の核ともいうべき二つの大都市の改革がいずれも保守政治家の手で推し進められつつあるのは、今の日本の政治状況を端的に表しています。この国の変革を牽引するのは、かつて「革新」と呼ばれた政治勢力ではなく、保守の指導者だということです。皮肉なめぐり合わせのように思えますが、過去半世紀の歩みを振り返ってみれば、当然の帰結だったような気もします。
かつての「革新陣営」の主体は、社会党と共産党でした。平和と護憲の旗印を掲げ、自民党の政権運営を「大企業中心」と批判し、働く者のための政治を訴えてきました。国際情勢や国家の安全保障は二の次、三の次。市場経済の厳しさと激しさも意に介さず、自民党と大企業の批判を繰り返していれば済んだのです。社会党の土井たか子委員長(1986ー1991年)が北朝鮮の日本人拉致について、「社会主義の国がそんなことをするはずがない。拉致は創作された事件」と断言したのは象徴的な出来事でした。
1970年代に学生生活を送った私は、キャンパスで共産主義に触れ、マルクスや毛沢東の著作を熟読した人間の一人です。新聞記者になってからも「革新陣営の応援団」のような気分で取材していました。それが徐々に変わっていったのは、社会の現実に触れ、選挙取材で生身の政治家に触れるようになってからです。自民党には、清廉な政治家はほとんどいない。言うことにも理路整然としたところはない。けれども、懐の深い人が多く、何よりも「人々の心の襞(ひだ)」をよく理解していると感じました。人間として魅力を覚える人もいました。
一方、革新陣営の政治家はどうだったか。その主張は自分の考えに重なるものでした。訴えていることも、もっともらしい。ですが、どこか虚ろで、深さが感じられない。人間味も足りない。何よりも、この国の政治を担い、社会を変えていくという気概が感じられませんでした。労働組合や左翼的な人たちが主な支持層で、それを越えて共感を広げていくことができませんでした。「恵まれない人々のための政治」を唱えながら、本当に苦しんでいる人たちに寄り添うことが十分にできなかった、と言ったら言い過ぎでしょうか。
インドやアフガニスタンで取材を重ねたことも、「政治とは何か」を考えるうえで貴重な体験でした。カースト差別に打ちのめされ、宗教の違いを理由に暴虐の限りを尽くされる人々に出会って思ったのは「日本はなんて牧歌的な、恵まれた社会なんだろう」ということでした。民族と部族、宗教と宗派で分断され、いつまでも戦い続けるアフガンの人々からは「生き抜くことの厳しさ」を教えられたような気がします。抜け目なく考え、振る舞わなければ生きていけない社会でした。
1995年にインドから帰国してみると、日本では政党の再編が花盛り。自民党と社会党の五五年体制は崩れ、合従連衡が始まっていました。名前を覚えきれないほどの政党の乱立と消滅。2009年の民主党政権の誕生はその一つの帰結とも言えるものでした。この時に民主党が掲げた「コンクリートから人へ」というスローガンは、日本の社会が向かうべき方向をある意味、的確に示していたのではないか。
惜しむらくは、その政権を担う政治家たちに「1億2000万人の国家」を率いる責任の重さへの自覚がまるでなく、変革を推し進める覚悟も欠落していたことでした。大規模な公共事業の見直しは腰砕け。事業仕分けをつかさどった蓮舫氏は「2番じゃダメなんですか」と子どもじみた妄言を吐く始末。東日本大震災という未曽有の災害に襲われ、危機管理能力のなさを完膚なきまでに露呈してしまったのは不運でもあった、と言うべきかもしれません。
実際に政権を担うことで、変革を唱えてきた政治家たちの力量と本性が露わになり、その政治勢力は瓦解してしまいました。民進党と名前を変えてみても、体質は変わりようがないでしょう。息も絶え絶えだった自民党は勢いを取り戻し、今や「一強多弱」の様相。あれだけの原発事故を経験しながら教訓とすることもなく、なお原発の再稼働と輸出をもくろむ政治家と政治は「羅針盤が壊れてしまった船とその操舵手」と言うしかありません。それに乗り合わせた恐ろしさ。日本は進むべき道から大きく外れ、厄災への道を静かに歩んでいる、と感じます。
もはや「保守と革新」という区分けは意味がない。海図なき航海をしなければならない今という時代に、イデオロギーなど何の役にも立ちません。私たちは、進むべき道からどれほど外れてしまったのか。未来にどんな厄災が待っているのか。まず、それをしっかりと見つめなければなりません。そして、覚悟をもって患部に切り込まなければなりません。
小池都知事は、東京五輪の準備作業や築地市場の移転問題になぜ、あのように果敢に挑むことができるのか。それは、東京選出の自民党代議士として、東京を舞台にして蠢く政治家や経済人の動きをつぶさに見て、その実態と闇の深さを知っているからでしょう。森喜朗・元首相や内田茂都議らがその闇の奥で何をしていたのか。石原慎太郎・元都知事が息子の伸晃代議士や宏高代議士かわいさから、どのように泥にまみれていったのか。詳細はともかく、その輪郭を知っているからこそ、「勝機がある」とみたのではないか。
一人の政治家がその政治生命をかけて、東京の闇の切開手術に踏み切ったのです。心あるジャーナリストなら、その患部を照らし出す仕事をしてみてはどうか。まだ志を捨てていない検察官がいるなら、闇に蠢く人間たちを裁きの場に引きずり出す算段をしてみてはどうか。
≪写真説明とSource≫
◎東京五輪組織委員会の森喜朗会長
http://cyclestyle.net/article/2015/12/18/31004.html
*メールマガジン「風切通信 12」 2016年9月16日
中国の有名な故事に「人間万事、塞翁(さいおう)が馬」というのがあります。何が幸運をもたらし、何が災いを招くのか、人知の及ぶところではないという教えです。舛添要一・前都知事の政治資金のせこい使い方に端を発した東京都のスキャンダルは、舛添氏の辞任から都知事選、選挙での自民党の分裂と小池百合子氏の圧勝という結果をもたらしました。

その過程で、東京都を牛耳る「都議会のドン」内田茂都議の醜聞や内田氏と昵懇の間柄にある森喜朗・元首相の役割を炙り出し、2020年東京五輪をめぐる利権疑惑や豊洲新市場への移転をめぐる不可解な経緯が次々に暴露されるに至りました。すべては、政治資金を使って千葉・木更津の温泉リゾートに家族旅行に行くような「舛添氏のせこさ」が引き金になって表沙汰になったものです。納税者にとっては、まさに「万事、塞翁が馬」であり、ここは舛添氏に「ありがとう」と言ってもいい場面ではないでしょうか。
疑惑追及の焦点は、招致活動時の予算7300億円が2兆円を超えるまでに膨れ上がった東京五輪の開催準備費用と、首都圏の台所「築地市場」の豊洲移転問題の二つに絞られてきました。そして、築地市場の豊洲移転は環状2号線の建設工事と密接不可分の関係にあります。この道路は築地市場を貫いて造られ、東京五輪の選手村と主な競技場を結ぶ幹線道路になる予定で、なんとしても市場を豊洲に移転させなければならないのです。つまり、二つの疑惑は「東京五輪の開催準備」という問題に収斂していくのです。
週刊文春9月1日号によれば、環状2号線の「虎の門ー豊洲間 5キロ」の総事業費は4000億円と推定され、1キロ800億円もの血税が投じられる超贅沢道路です。その工事を受注した中堅ゼネコンのナカノフドー建設(千代田区)や鹿島道路(文京区)はいずれも、内田茂都議が代表をつとめる政治資金団体に名誉会長が献金したり、幹部が内田氏の長女の結婚披露宴に出席したりする間柄、と報じられています。
利幅の大きい公共工事を受注し、そのおこぼれのような金を政治家に届ける。政治家はそうした金をかき集めて権勢を振るう。昔ながらの利権構造が日本の首都、東京に温存されていることに驚きます。移転先の豊洲新市場の土壌汚染対策をめぐる「盛り土騒動」の背後にも、似たような構図が見え隠れしています。
もとは東京ガスの製造工場跡地。そんな所に食品を扱う新市場を造るという構想そのものに無理があるのですが、ベンゼンなどの有害物質で汚染された土壌を削り取って盛り土をし、4.5メートルの厚さの土で封じ込める、というのが専門家会議の提言でした。が、専門家の見識など吹き飛ばされ、実際に工事をするゼネコン側の都合で設計図が引かれ、入札・落札されていった経過が徐々に明らかになりつつあります。
醜悪きわまりないのが石原慎太郎・元東京都知事の言動です。なされるべき盛り土がなされず、建物の下に「謎の地下空間」があることが判明すると、石原氏はテレビのインタビューに「私はだまされた。(盛り土を)したことにして予算措置をしていた。都の役人は腐敗している」とまくしたてました。
ところが、なんのことはない、石原氏本人が2008年5月10日の定例記者会見で「(盛り土より)もっと費用のかからない、効果の高い技術を模索したい」と口火を切り、「地下空間」づくりの地ならしをしていたことが分かりました。それどころか、石原氏は当時の東京都中央卸売市場の比留間(ひるま)英人・市場長に対して「こんな案(地下にコンクリートの箱を埋める案)がある。検討してみてくれ」と直接、指示していたことまで判明したのです(9月16日、東京新聞電子版)。
こうしたことが明るみに出るや、石原氏はさらに「私は素人だからね。全部、下(都の職員)や専門家に任せていた。建築のいろはも知らないのに、そんなことを思い付くわけがない」と釈明し、「東京は伏魔殿だ」と言い放ちました。何という品性の持ち主であることか。東京都知事として13年間も、自らが伏魔殿の主であったことをすっかり忘れてしまったようです。この破廉恥さに比べれば、舛添氏の振る舞いなど、かわいらしく見えてきます。
人間万事、塞翁が馬。この際、日本の首相や東京都の知事として権力を振るった政治家たちがどのような品性の持ち主なのか、可能な限り明らかにしてほしい。そして、私たちの悲しい首都、東京にたまった膿を切開手術で取り除き、もっとまともな街にして、2020年の祭典を迎えたい。
≪参考記事&サイト≫
◎週刊文春9月1日号の記事「都議会のドン内田茂と4000億円五輪道路」
◎日刊ゲンダイ電子版「豊洲新市場『盛り土案潰し』真犯人は石原元都知事だった」(9月15日)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/189920/2
◎東京新聞電子版「コンクリ箱案 石原氏が検討指示」(9月16日)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016091690070606.html
≪写真説明とSource≫
◎豊洲新市場の「盛り土」問題で釈明する石原慎太郎氏(東京新聞電子版)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016091690070606.html
*メールマガジン「風切通信 11」 2016年8月25日
マーケティングとは、顧客が本当に求めている商品やサービスを的確につかみ、それを効果的に提供すること。それに沿って考えれば、昨今、日本ではやりの「おもてなしの心」だけでは外国人観光客を呼び込むのは難しい。では、何が必要なのか。人は旅に出て、何に心を揺さぶられるのか。それをすくい取る知恵が求められている――。
そんなことを思ったのは、日本を拠点に中国情報を発信しているジャーナリストの莫邦富(モー・バンフ)さんの話を聞いたからです。伊豆半島でのセミナーに一緒に参加した後、帰りのバスの中で、莫さんからこんな話を聞きました。

「山梨県の観光アドバイザーとして甲府を訪ねたら、どこへ行っても武田信玄と風林火山の話ばかり。日本人にとっては馴染み深い人物と旗印なのでしょうが、中国人の観光客には興味が湧かない。それよりは、山梨側から見る『湖に映える富士山』の方がずっといい。静岡側からの見慣れた富士の姿とも違って、魅力的です。東京から近いことも利点。そこから『週末は山梨にいます』という新しいキャッチフレーズが生まれ、訪れる外国人観光客が大幅に増えたのです」
「高知県に招かれたら、今度はどこへ行っても坂本龍馬。桂浜に行けば、龍馬の銅像。はりまや橋でも龍馬・・・。でも、中国人はそもそも知らないんです、坂本龍馬という人物を。知らない人を何度も紹介されてもつらい。それより、桂浜から眺める雄大な太平洋こそ、中国の人に見せたい。中国大陸には、美しい砂浜の先に大海原が広がるこうした風景はほとんどないんです」
「高知県には『日本最後の清流』と言われる四万十(しまんと)川があります。この川も中国人観光客には興味が湧かない。黄土色した中国の大河に比べれば、日本の川はどこへ行ってもきれいで、あちこちに清流があります。わざわざ高知に行くまでもありません。それよりも、四万十川で獲れる『ツガニ』の方がずっと嬉しい。これは上海ガニの仲間。しかも天然です。日本の秘境で天然の上海ガニを食べる―――これなら、中国から観光客を呼ぶことができます」

「足摺岬もいい観光スポットです。ただし、高知市からバスで3時間もかかって退屈する。『途中に立ち寄るところはないの』と聞いたら、四万十町に廃校を活用したフィギュアの博物館があるという。行ってみたら、山奥にすごい博物館があって、日本人観光客もわんさと押し寄せている。なんだ、あるじゃないの、とびっくりしました」
この博物館は、模型や食品玩具の専門メーカー「海洋堂」(本社・大阪府門真市)が2011年にオープンさせた「海洋堂ホビー館四万十」です。フィギュアファンのみならず、模型好きにとっては「聖地」のような存在なのだとか。海洋堂の創業者が高知県出身という縁もあって建設されたようです。莫邦富さんは「中国でも農村の過疎は深刻な問題の一つです。そういうことに関心のある人にとっても、この博物館は興味深く、人気を集めるはず」と言います。
中国からは毎年、かなりの数の観光客が来日しており、リピーターは「あまり知られていない日本」を知りたがっているようです。キーワードの一つは「秘境」。ただし、四万十川の例に見るように、日本人とは異なる視点が必要です。清流は魅力にならない。「ツガニ(上海ガニ)」や「ホビー館」のようなものが欲しい。いくつか組み合わせて、麻雀で言えば、役を二つも三つも付け加えるような工夫が必要です、と莫さんは言います。
「秘境」ということなら、わが故郷の山形は断然、有利です。莫さんもすでに何度か来たことがあるそうで、「掘り起こせば、中国人観光客を惹きつけられそうな観光スポットがいくつも見つかりそうですね」と乗り気でした。ところが、私が「蔵王の樹氷なんかどうでしょう?」と水を向けると、莫さんは言下に「あれは駄目です」とのご託宣。「つらい体験を思い出すから」と言うのです。
莫さんは、私と同じ1953年の生まれ。上海生まれの都会っ子です。この世代は文化大革命の真っただ中で青春を迎え、その嵐に翻弄された人たちです。文革中、都市部の若者を農村に送り込む、いわゆる「下放(かほう)運動」が大々的に展開されました。労農の団結という革命思想を叩き込むため、とされました。莫さんは中国東北部の黒竜江省の農村で若き日々を送ったのです。
「あの厳しい寒さは忘れられない。氷点下の蔵王に樹氷を見に行く気には、とてもなれません」と、莫さんは言うのです。なるほど、外国から観光客を誘致するためには、そういう歴史にも目配りしなければならないのか。マーケティングと一口に言うけれど、やはりどの世界も奥が深く、難しい。
≪参考サイト≫
◎土佐のツガニについて(「旬どき・うまいもの自慢会・土佐」のサイト)
http://tosa-no-umaimono.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_57c9.html
◎四万十町のフィギュア博物館「海洋堂ホビー館四万十」
http://buzzap.jp/news/20150301-kaiyodo-hobby-kan-shimanto/
◎莫邦富さんの公式サイト
http://www.mo-office.jp/
≪写真説明とSource≫
◎四万十川でのシラスウナギ漁(「ファインド トラベル」のサイト)
http://find-travel.jp/article/38544
◎土佐のツガニ(札幌を刺激するウェブマガジン「sappoko」から)
http://sappoko.com/archives/18899
*メールマガジン「風切通信 10」 2016年8月14日
最上川をカヌーで下る地域おこしを始めた時から、「いつか最上川の源流を訪ねてみたい」と思っていました。なかなか機会がなかったのですが、最上川の源流部に「秘湯中の秘湯」があると知り、思い切って車で行ってきました。福島県境に近い米沢市の大平(おおだいら)温泉というところです。
この大平温泉には、宿は1軒しかありません。米沢の市街地を抜け、車で山道をたどって40分ほど。尾根に駐車場があり、そこに車を停めて、あとは徒歩で渓流に下りていきます。急な坂道を20分ほど歩くと吊り橋があり、その先に目指す「滝見屋」がありました。玄関先に掲げられた由緒書には「貞観2年(西暦860年)、清和天皇の御宇(ぎょう)に修行僧によって発見された」と記してありました。江戸時代には湯治客用の宿があったといいますから、とても古い温泉宿です。

雪深いところです。11月上旬から4月下旬までは雪に埋もれるので、営業できません。宿のスタッフの今井正良さんによると、4月の初めから再開の準備を始めるのですが、その時期でも積雪が2メートルほどあるそうです。雪の重みで吊り橋が壊れてしまう恐れがあるので、晩秋に吊り橋の床板を外しておくのだとか。厳冬期の積雪は5メートルを超えるでしょう。
その吊り橋を覆うようにモミジの枝が伸びていました。なんと、8月の上旬というのに、その一部が早くも朱に染まっていました。8月の紅葉を見たのは生まれて初めてです。「日本で一番紅葉が早い」とされる北海道大雪山の温泉宿でも、色づき始めるのは9月上旬ですから、最初はわが目を疑いました。宿の標高は1000メートルほど。渓流を流れる冷たい水が木々の冬支度を早めているのかもしれません。
宿には電線も電話線も来ていません。自家発電で明かりをとり、衛星電話で外部とつながっています。谷底なのでテレビの電波も届きません。宿の案内書には「快適さを求めるお客様にはほかの宿をお勧めしています」とあり、奥ゆかしい。滝と渓流を眺めながら湯量豊かな露天風呂につかり、ボーッとするには最適の宿です。だだし、渓流が大きな音を立てて流れていますので、寝つきの悪い人には不向きでしょう。
「よくぞ、この宿を維持してきたものだ」というのが率直な感想です。女将の安部綾子さんにお聞きすると、やはり並大抵の苦労ではありません。秘湯と呼ばれる宿でも、たいていは玄関先まで車を付けることができるので、業者に注文すれば、食材も酒類も車で届けてくれるのですが、この宿は自力で買い出しをして運ぶしかありません。予約も米沢市内の本宅の電話で受け、宿には衛星電話か無線で伝えています。東日本大震災と原発事故の後は、「福島を通って行かなければならないので」と敬遠され、予約は半減したそうです。
それでも続けてこられたのは、代々営んできた宿を大切にしたいという思いと、「支えてくださる方がたくさんいらっしゃるから」と、綾子女将は言います。地元の人たちがスタッフとして支え、常連客は「客が少なくて困ったら電話して。いつでも行くから」と言ってくれる。言うだけでなく、本当にやって来る。大平温泉は本当の秘湯です。本物には、やはり人を惹きつけてやまないものがあるのでしょう。

山道に薄紫色の花が咲いていました。宿の料理を作っている佐藤きよ子さんに尋ねると、「フジバカマ(藤袴)ですよ」と教えてくれました。源氏物語に登場する藤袴がこういう花だと、初めて知りました。山菜料理の腕を磨きながら、きよ子さんは山野草のことも学び続けているのです。訪ねた人の心が安らぎ、和らぐ、すがすがしい宿でした。
≪参考サイトと文献≫
◎大平温泉・滝見屋のサイト
http://takimiya.blogdehp.ne.jp/
◎「日本秘湯(ひとう)を守る会」のサイト
http://www.hitou.or.jp/
◎ガイドブック『日本の秘湯』(日本秘湯を守る会編)
≪写真説明とSource≫
◎吊り橋を覆うモミジの紅葉(8月9日、長岡昇撮影)
◎大平温泉の山道に咲いていたフジバカマ(同)
*メールマガジン「風切通信 9」 2016年8月11日
リオ五輪のカヌースラローム競技で、羽根田卓也選手が銅メダルを獲得しました。日本人がカヌー競技でメダルを獲得するのは初めてです。カヌー選手だった父の指導で小学3年生からカヌーを始め、高校時代には早朝から自転車で川に通って練習、放課後にまた川に戻って夜遅くまで漕いだのだそうです。国内にいては世界で戦えないと、10年前にカヌー強豪国のスロバキアに渡って練習を続けたと報じられています。長い精進が実っての快挙です。

昨日(10日)、羽根田選手のメダル獲得のニュースに接して、「立派な成績だけれど、これで『だから日本にもカヌーの人工コースが必要なのだ』という記事が出るな」と思いました。今朝、朝日新聞を開くと、案の定、社会面に「主要な国際大会のほとんどが人工コースで行われるが、日本には本格的な人工コースがない」「東京五輪では、東京都江戸川区の臨海部に日本初の本格的な人工コースとなるスラローム会場が新設される」という関連記事が載っていました。記事は「メダルも大きな追い風になる」とのカヌー協会関係者の言葉で締めくくってありました。
はあー、とため息が出ました。東京五輪組織委員会の面々はニンマリしていることでしょう。これで、金にあかせて東京に人工の急流コースを造る計画に弾みがつく、と。朝日新聞は読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞と4社で計60億円を払って、東京五輪のオフィシャルパートナーになりました。1社15億円ものお金を出してくれて、おまけに「公共事業の大盤振る舞い」のような競技場建設計画の後押しまでしてくれるのですから、笑いが止まらないでしょう。
オリンピックを資金面で支援するオフィシャルパートナーは「1業種1スポンサー」が原則です。なのに、そうした原則などどこ吹く風。日頃の談合批判もどこへやら。オリンピックについては、4社仲良く手を組んで「御用新聞」になることに決めたのです。このことについて、日刊ゲンダイ(電子版)は1月29日に「大手新聞が公式スポンサーの異常」という記事を掲載し、「知らなければいけない不都合な情報や問題が隠され、報道されないという事態」になりかねない、と批判しました。
朝日、読売、毎日、日経の4紙がスポーツ新聞に「きちんと監視役を果たせ」と説教される日が来ようとは・・・。東京に人工のカヌースラローム競技場を造ることの問題点を指摘するどころか、それを造らなければ世界の強豪と渡り合えない、と煽り立てる記事。こういうのを典型的な「提灯(ちょうちん)記事」と言うのでしょう。記事を書いた記者が善意で、純粋にスポーツの観点から書いているだけに、なおさら影響は大きく、罪も深いのです。
日本の経済が上向きで資金が潤沢な時期なら、話は別です。が、いまや経済はずっと右肩下がり。医療や介護に回さなければならない予算は膨らむばかり。政府も自治体も借金まみれです。そういう時代に「金にあかせた五輪」など許されるはずがありません。できる限りコンパクトに、ただし、温かい心でもてなす五輪をめざす、という道もあるはずです。東京一極集中の是正も、今の日本の大きな課題の一つです。東京への人工カヌー競技場建設はその流れにも反します。
こういう主張をすると、「それはカヌー競技を知らない者の戯言だ」と反論されるでしょう。世界大会やオリンピックのほとんどで、カヌースラローム競技は人工のコースで行われるのだ、人工コースがなければ選手の強化もできない、と。純粋にスポーツのことだけを考えるなら、それも一理あるのかもしれません。ですが、オリンピックはスポーツ大会であると同時に、「これからの世界はどうあるべきか」ということに思いを巡らせ、メッセージを発する祭典でもあるのです。
急流がないなら人間が造ればいい。水が必要なら巨大な揚水ポンプで揚げればいい。それが欧米的な考え方で、スポーツの世界でも支配的なのかもしれません。けれども、日本がそれに同調する必要はどこにもありません。自然の中で、自然が許す範囲で生きていく。それこそ、日本やアジアの国々が育んできた考え方であり、生き方ではないのか。川がつくり出す自然の流れの中でカヌーの技を競えばいいではないか。ごく最近まで、ずっとそうしてきたのですから。
百歩譲って、8月は渇水期で日本のどこにも適当な水量の渓流がないとするなら、人工のカヌースラローム競技場は東京以外に造るべきです。「すべて東京に」という考えにこだわった結果が今の東京一極集中と地方の疲弊をもたらしたのですから。2020年東京五輪の公式種目に追加されたサーフィンも東京以外で開催される予定です。狭い東京ですべてをまかなう必要など、どこにもないのです。
朝日新聞が社会面で無邪気な提灯記事を書いているのに対して、読売新聞や毎日新聞が羽根田選手の歩みを中心に人間ドラマとしての報道に徹していたのも印象的でした。目を通した範囲では、「カヌースラロームの人工コース」に触れた記事を書いているのは共同通信くらいでした(日経新聞と山形新聞が掲載)。東京五輪をどういうオリンピックにしたいのか。どういう理念で4年に一度の祭典を照らしたいのか。リオ五輪の熱狂から覚めたら、そうした視点で東京五輪の計画と準備状況の問題点をえぐり出し、より良き祭典につながるような報道に接したい。
≪参考サイト≫
◎「4紙で60億円負担 大手新聞が東京五輪公式スポンサーの異常」(日刊ゲンダイ電子版)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/174215
◎カヌースラローム競技場とスプリントカヌー競技場の整備計画(カヌーカヤックネットマガジンのサイトから)。この記事によれば、スプリントカヌー競技場の整備費は491億円、カヌースラローム競技場の整備費は73億円。
http://www.fochmag.com/kayak/index.php?itemid=1272
≪参考記事≫
◎8月11日付の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、山形新聞、河北新報(いずれも山形県で配達された版)
≪写真説明とSource≫
◎リオ五輪のカヌースラローム(男子カナディアンシングル)で銅メダルを獲得した羽根田卓也選手
http://www2.myjcom.jp/special/rio/news/story/0022021276.shtml
*メールマガジン「風切通信 8」 2016年8月6日
郷里の山形に戻って間もなく、2010年に地元の人たちと地域おこしのNPOを立ち上げ、毎年7月の下旬に最上川をカヌーで下るイベントを開いています。日本三大急流の一つとされる最上川は変化に富み、カヌーを愛する人たちの間でとても人気があります。この夏も県内外から31人が集い、急流下りを楽しみました。

最上川の急流を下るカヌーイストたち(山形県朝日町)
このイベントに参加した首都圏在住の人たちから、都市伝説ならぬ都市怪談のような話を聞きました。2020年に開かれる東京オリンピックのために、東京の江戸川区にカヌーのスラロームコースを造る計画があるというのです。カヌーのスラローム競技は、300メートルほどの激流に旗門を設けてカヌーで下り、タイムを競うものです。スキーの回転のカヌー版のような競技です。仰天して調べてみたら、本当の話でした。
東京都オリンピック・パラリンピック準備局のホームページに計画の概要が掲載されています。それによると、東京都立葛西臨海公園の隣にある都有地に水路を造り、国内で初めての人工的なカヌーのスラロームコースを整備する、となっています。上流に巨大な貯水池を建造し、大量の水を流して急流を造り、そこをカヌーで下る。流れ落ちた水は揚水ポンプでまた貯水池に戻す、という計画です。要するに、税金で東京に渓流を造ってカヌー競技を開催する、というわけです。

福島県二本松市で開かれたカヌースラローム競技会(2013年5月)
あきれました。東京オリンピックの開催を推進する人たちがどういう思考の持ち主かを象徴的に示しています。カヌーに限らず、ヨットやサーフィンは自然の中で行う競技です。実際、カヌーのスラローム競技は富山県の井田川や岐阜県の揖斐(いび)川、福島県の阿武隈川などで開かれています。ただし、水量が豊富でなければなりませんから、大会は雪解け水が流れる春先か秋雨の集まる時期に開かれるのが普通です。
しかし、東京の中心部にはそうした川はありません。東京近郊の川を活用することも考えられますが、2020年東京五輪は7月下旬から8月上旬にかけての開催ですから、渇水期でカヌー競技はとても無理です。そこで「人工的に造ってしまえ」となったのでしょう。いったい、いくらかかるのか。組織委員会も東京都も試算を示していませんが、建設費は数十億円あるいは数百億円の規模になると見込まれます。
建設だけでなく、維持管理も大変です。建設系シンクタンクを経営する橋爪慶介氏の試算によれば、カヌースラロームの競技をするとなると、少なくとも毎秒13トンの水量が必要で、その水を貯水池に揚水するための電気代だけで、年に60日動かすとして1億1300万円もかかります。これに施設維持のための人件費や管理費が加わります。橋爪氏が「恒久的な施設を造るべきではない。自然の中で開催すべきだ」と見直しを提言したのは当然でしょう。
ですが、この提言に従えば、上記のような川の水量の問題があり、夏に自然の川でカヌースラローム競技を開催するのは困難になります。議論は、そもそも東京で夏にオリンピックを開催することには無理がある、という振り出しに戻ってしまうのです。熱中症が多発するような時期になぜ開くのか、と。では、開催時期を変更することは可能か。東京五輪の夏季開催を決めたのは、巨額の放映権料を支払う世界の(具体的には主にアメリカの)テレビ局の意向を踏まえたもの、とされています。とすれば、開催時期の変更は困難です。時期を変えれば、テレビ各社に莫大な違約金を払わなければならないからです。
思えば、1964年の東京五輪の開催を担った人たちは、とてもまともな人たちでした。東京でスポーツ大会を開くなら、気候が良くて晴れも多い10月と素直に考え、粛々と準備を進めました。それが人々の記憶に残る見事な五輪大会となって結実したのです。それに引き換え、2020年東京五輪を担う人たちには、なんと胡散臭い人が多いことか。
新国立競技場の建設計画をめぐるドタバタ劇。五輪エンブレムのデザイン盗用疑惑。いずれも誰かがきちんと責任を取らなければならないのに、みんなで逃げ回り、東京五輪組織委員会の会長、森喜朗・元首相(79)はどこ吹く風といった顔。「せこい」という日本語を世界に広めた舛添要一氏は都知事の座を追われましたが、森元首相の取り巻きとお友達はいまだに、組織委員会でとぐろを巻いています。
その腐敗と腐臭のすさまじさをえぐり出して見せたのが週刊文春の特集記事です。8月4日号と8月11日・18日号には、森元首相と昵懇の間柄で都政と都議会を牛耳る内田茂・自民党東京都連幹事長(77)の行状が具体的なデータに基づいて暴露されています。東京都議会から組織委員会の理事として送り込まれた高島直樹・前都議会議長と川井重勇(しげお)議長は、2人とも内田都議の側近。都庁出身の組織委役員も内田氏の息がかかった人物。要するに、東京五輪の重要な話はすべて、「都議会のドン」と呼ばれる内田氏のところに集まる仕組みになっている、というのです。
あまり表には立たず、金と人脈で物事を動かす人物を黒幕とかフィクサーと言います。普通、フィクサーは舞台の裏手に居るものですが、東京都庁と都議会の場合はなんと表舞台に立っていた、というわけです。これも驚くべきことです。東京もまた「一つの村」だったということか。メディアも検察もこうした事情は承知していたのでしょうが、怖くて手が出せなかったのでしょう。都知事選で内田氏ら自民党都連が担いだ増田寛也氏が大敗し、東京都の利権構造はガラガラと音を立てて壊れ始めています。
週刊文春が報じた内田茂都議の政治資金をめぐる疑惑(事務所の家賃を家族が役員を務める会社に政治資金から支出していた疑い)や、内田氏が役員を務める「東光電気工事」という会社をめぐる疑惑(五輪関連の事業を不思議な経緯で落札した疑い)に徐々に光が当てられようとしています。検察もメディアも、権勢のピークにある人物は怖いが、水に落ちた権力者は怖くない。みんなで叩き始めるでしょう。司直の手がどこまで伸びるのか、注目されるところです。
それにしても、東京五輪をめぐる招致と準備のプロセスを見ていると、第二次大戦末期にビルマからインドに攻め込んで多くの犠牲者を出した日本陸軍のインパール作戦を思い出します。「おかしい」と思っていても、トップが怖くて口にできない。ズルズルと引きずられているうちに、数万の将兵が屍をさらす結果になりました。その悪名高い作戦を指揮した牟田口廉也(むたぐち・れんや)第15軍司令官は戦後も生き延び、「あれは私のせいではなく、部下の無能のせいだ」と言い続けました。
このままでは、東京五輪は「現代日本のインパール作戦」になってしまうのではないか。森喜朗・元首相はさしずめ、「平成の牟田口」か。準備が本格化する前に大掃除が必要です。小池百合子・新知事に期待するところ大ですが、週刊文春によれば、小池氏の周りに集まる人たちにも「はてなマーク」の人が多いのだとか。政治の世界は本当に難しい。
≪参考サイト≫
◎東京都オリンピック・パラリンピック準備局の公式サイト
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/2020/index.html
◎同サイトのカヌースラローム会場関係
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_15/index.html
◎東京2020大会開催基本計画
https://tokyo2020.jp/jp/games/plan/data/GFP-JP.pdf
◎カヌースラローム競技場計画の見直しを求める提言(橋爪慶介氏)
http://www.dexte-k.com/image/lobbying/lobbying(proposal_of_the_temporary_stadium).pdf
◎最上川カヌー川下りのイベントと記録
http://www.bunanomori.org/NucleusCMS_3.41Release/index.php?catid=9
≪写真説明とSource≫
◎最上川の急流を下るカヌーイストたち(7月30日、撮影・佐久間淳)
◎2013年5月に福島県二本松市で開かれた「あぶくま大会」のワンシーン
http://www.canoe.or.jp/album/ww2_sla3_japancup.html
1日目の7月30日(土)は山形県朝日町の雪谷カヌー公園から寒河江市の「ゆーチェリー」まで23キロ、2日目の31日(日)は大石田町の大石田河岸(かし)から尾花沢市の猿羽根(さばね)大橋まで19キロをカヌーで下りました。合計42キロのコースでした。参加者は1日目が26人20艇(2人乗りが6艇)、2日目が16人13艇(同3艇)。計31人が最上川の流れを満喫しました(11人が2日間参加)。


1日目は曇時々小雨、一時雷雨の天候。最上川の水量はかなり少なく、朝日町から大江町にかけての五百川(いもがわ)峡谷の急流はともかく、後半はトロ場で参加者はかなり苦労しました。ただ、この日午後に山形市などで局所的な集中豪雨があり、2日目はこの降雨が最上川に流れ込み、豊かな流れになりました。空は晴れ、追い風にも助けられて、大石田からは快調な漕ぎでした。2人乗りの艇が多く、カナディアンカヌーの方も多かったのが第4回の特徴です。



≪参加者≫
31人:山形県内21人、県外10人(宮城3、埼玉2、東京2、青森、福島、長野各1人)
【2日間で42キロを完漕】11人
菊地大二郎(山形市)、菊地恵里(同)、林和明(東京都足立区)、岸浩(福島市)、崔鍾八(山形県朝日町)、清野由奈(同)、渡辺佳久(埼玉県東松山市)、多田英之輔(山形県山辺町)、伊藤信生(山形県酒田市)、佐竹久(山形県大江町)、小野俊博(同)
【1日目、23キロを完漕】15人
瀧口宗紀(山形市)、森谷久範(同)、東海林憲夫(山形県寒河江市)、山川治雄(山形市)、調所孝芳(同)、鈴木基之(同)、丹野睦(同)、高田徹(青森県八戸市)、三塚志乃(仙台市太白区)、中沢崇(長野市)、渡辺政幸(山形県大江町)、大類晋(山形県尾花沢市)、徳宮龍男(同)、斉藤栄司(同)、市川秀(東京都中野区)
【2日目、19キロを完漕】5人
福田泉(さいたま市北区)、池田丈人(山形県酒田市)、鈴木未知哉(宮城県柴田町)、鈴木達哉(同)、佐藤博隆(山形県酒田市)
*過去の参加者数(2012年 第1回 24人、2014年 第2回 35人、2015年 第3回 30人)
≪陸上サポート≫ 安藤昭雄▽白田金之助▽清野千春▽長岡昇▽長岡典己▽長岡佳子
≪写真、動画撮影≫ 佐久間淳▽村山彩▽長岡昇▽長岡典己▽鈴木達哉
≪昼食のデザート、漬物提供≫斉藤栄司(尾花沢スイカ)▽佐竹恵子(キュウリ漬、ナス漬)


≪出発、通過、到着時刻≫
▽1日目(7月30日)
10:00 朝日町・雪谷カヌー公園を出発
12:10 朝日町・タンの瀬に到着、昼食
*タンの瀬下りをユーチューブにアップしました(カラー文字をクリック)
13:10 タンの瀬を出発
16:40 寒河江市・ゆーチェリーに到着
▽2日目(7月31日)
9:30 大石田町・大石田河岸を出発
*出発の様子をユーチューブにアップしました(カラー文字をクリック)
11:40 尾花沢市・舟戸大橋に到着、昼食
12:40 舟戸大橋を出発
13:40 猿羽根大橋に到着



≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、大江町、西川町、寒河江市、中山町、大石田町、尾花沢市、舟形町、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江町カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 大石田町東町区長、矢作(やはぎ)善一▽東町公民館長 細矢裕▽東町公民館の皆様
*7月30日夕、東町公民館でのビアガーデンに参加させていただきました




≪ウェブサイト制作≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、佐藤大介)
≪ポスター、Tシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス(株)
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell 保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
≪参照ウェブサイト≫
山形県朝日町の公式サイトの「まちの写真館」 (カラー文字をクリック)




1日目は曇時々小雨、一時雷雨の天候。最上川の水量はかなり少なく、朝日町から大江町にかけての五百川(いもがわ)峡谷の急流はともかく、後半はトロ場で参加者はかなり苦労しました。ただ、この日午後に山形市などで局所的な集中豪雨があり、2日目はこの降雨が最上川に流れ込み、豊かな流れになりました。空は晴れ、追い風にも助けられて、大石田からは快調な漕ぎでした。2人乗りの艇が多く、カナディアンカヌーの方も多かったのが第4回の特徴です。



≪参加者≫
31人:山形県内21人、県外10人(宮城3、埼玉2、東京2、青森、福島、長野各1人)
【2日間で42キロを完漕】11人
菊地大二郎(山形市)、菊地恵里(同)、林和明(東京都足立区)、岸浩(福島市)、崔鍾八(山形県朝日町)、清野由奈(同)、渡辺佳久(埼玉県東松山市)、多田英之輔(山形県山辺町)、伊藤信生(山形県酒田市)、佐竹久(山形県大江町)、小野俊博(同)
【1日目、23キロを完漕】15人
瀧口宗紀(山形市)、森谷久範(同)、東海林憲夫(山形県寒河江市)、山川治雄(山形市)、調所孝芳(同)、鈴木基之(同)、丹野睦(同)、高田徹(青森県八戸市)、三塚志乃(仙台市太白区)、中沢崇(長野市)、渡辺政幸(山形県大江町)、大類晋(山形県尾花沢市)、徳宮龍男(同)、斉藤栄司(同)、市川秀(東京都中野区)
【2日目、19キロを完漕】5人
福田泉(さいたま市北区)、池田丈人(山形県酒田市)、鈴木未知哉(宮城県柴田町)、鈴木達哉(同)、佐藤博隆(山形県酒田市)
*過去の参加者数(2012年 第1回 24人、2014年 第2回 35人、2015年 第3回 30人)
≪陸上サポート≫ 安藤昭雄▽白田金之助▽清野千春▽長岡昇▽長岡典己▽長岡佳子
≪写真、動画撮影≫ 佐久間淳▽村山彩▽長岡昇▽長岡典己▽鈴木達哉
≪昼食のデザート、漬物提供≫斉藤栄司(尾花沢スイカ)▽佐竹恵子(キュウリ漬、ナス漬)


≪出発、通過、到着時刻≫
▽1日目(7月30日)
10:00 朝日町・雪谷カヌー公園を出発
12:10 朝日町・タンの瀬に到着、昼食
*タンの瀬下りをユーチューブにアップしました(カラー文字をクリック)
13:10 タンの瀬を出発
16:40 寒河江市・ゆーチェリーに到着
▽2日目(7月31日)
9:30 大石田町・大石田河岸を出発
*出発の様子をユーチューブにアップしました(カラー文字をクリック)
11:40 尾花沢市・舟戸大橋に到着、昼食
12:40 舟戸大橋を出発
13:40 猿羽根大橋に到着



≪主催≫ NPO「ブナの森」 *NPO法人ではなく任意団体のNPOです
≪主管≫ カヌー探訪実行委員会(ブナの森、山形カヌークラブ、大江カヌー愛好会で構成)
≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、国土交通省新庄河川事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、朝日町、大江町、西川町、寒河江市、中山町、大石田町、尾花沢市、舟形町、山形県カヌー協会、山形カヌークラブ、大江町カヌー愛好会、美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫ 大石田町東町区長、矢作(やはぎ)善一▽東町公民館長 細矢裕▽東町公民館の皆様
*7月30日夕、東町公民館でのビアガーデンに参加させていただきました



30日夕、大石田町の東町公民館でのビアガーデンに参加させていただきました

30日昼に続いて、31日のゴール後にも斉藤栄司さんがスイカをふるまってくださいました
≪ウェブサイト制作≫
コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、佐藤大介)
≪ポスター、Tシャツのデザイン・制作≫ 遠藤大輔(ネコノテ・デザインワークス)
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス(株)
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell 保険オフィス
≪横断幕揮毫≫ 成原千枝
≪参照ウェブサイト≫
山形県朝日町の公式サイトの「まちの写真館」 (カラー文字をクリック)

1日目の参加メンバー(朝日町雪谷カヌー公園)

2日目の参加メンバー(大石田河岸)
今年で4回目になる最上川縦断カヌー探訪(NPO「ブナの森」主催)は、予定通り7月30日(土)と31日(日)に開催します。気象庁による山形県内の天気予報では、30日は曇時々晴、最高気温33度、31日は晴時々曇、最高気温32度とのことです。暑さ厳しい中でのカヌー行になりそうです。
今年のコースは30日が朝日町の雪谷カヌー公園から寒河江(さがえ)市のゆ?チェリーまでの23キロ、31日は大石田町から尾花沢市・猿羽根(さばね)大橋までの19キロ、合わせて42キロです。参加者は30日が26人20艇、31日が17人14艇の予定です。2日間参加する方もいますので、全体の参加予定者は31人になります。
30日は午前10時から朝日町の雪谷カヌー公園で開会式を行い、10時半にスタートする予定ですが、準備が整い次第、出発しますので、早まるかもしれません。31日は大石田町の大石田河岸(かし)から午前10時にスタートします。これも早く出発する可能性があります。出発地点やゴール地点の詳しい地図は、NPO「ブナの森」のホームページにある「コース図」をご参照ください。
ご参考までに、2012年の第1回カヌー探訪の参加者は24人、2013年は山形豪雨のために中止、2014年の第2回探訪は35人、2015年の第3回探訪は30人でした。詳しいことは「ブナの森」ホームページの「記録」欄をご覧ください。
今年のコースは30日が朝日町の雪谷カヌー公園から寒河江(さがえ)市のゆ?チェリーまでの23キロ、31日は大石田町から尾花沢市・猿羽根(さばね)大橋までの19キロ、合わせて42キロです。参加者は30日が26人20艇、31日が17人14艇の予定です。2日間参加する方もいますので、全体の参加予定者は31人になります。
30日は午前10時から朝日町の雪谷カヌー公園で開会式を行い、10時半にスタートする予定ですが、準備が整い次第、出発しますので、早まるかもしれません。31日は大石田町の大石田河岸(かし)から午前10時にスタートします。これも早く出発する可能性があります。出発地点やゴール地点の詳しい地図は、NPO「ブナの森」のホームページにある「コース図」をご参照ください。
ご参考までに、2012年の第1回カヌー探訪の参加者は24人、2013年は山形豪雨のために中止、2014年の第2回探訪は35人、2015年の第3回探訪は30人でした。詳しいことは「ブナの森」ホームページの「記録」欄をご覧ください。
*メールマガジン「風切通信 7」 2016年6月25日
社会がさまざまな人によって構成されているように、新聞社もさまざまな記者や社員によって構成されています。読売新聞の記者が全員、渡邉恒雄主筆(90)に心酔しているわけではないように、朝日新聞の記者も全員が「朝日の社論」で統一されているわけではありません。英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱が決まったことを報じた25日の朝日新聞を読むと、そのことがよく分かります。

EU離脱派の集会で演説するジョンソン前ロンドン市長
「これが朝日新聞の社論なのだろう」とすぐに分かるのは、1面のコラム「天声人語」でした。自分の家が独立国家だと妄想している男の姿を描いたSF作家、星新一の短編『マイ国家』から説き起こし、最後はチャーチル元首相の次の言葉で締めくくっています。「築き上げることは、多年にわたる長く骨の折れる仕事である。破壊することは、たった1日の思慮のない行為で足りる」
その言わんとするところは明白です。英国がEUから離脱するとの選択は「思慮のない行為」であり、愚かな選択、ということです。欧州統合は「戦争のない欧州」を築き上げるという崇高な理念に基づく営みであり、その道から外れるような選択は危うい、と言いたいのでしょう。社会面はもっと率直で、情緒的です。「英国よ まさか」の見出し。前文には「日本国内では今後の暮らしへの影響に不安が広がった」とあります。「これはポピュリズムの勝利であり、偏狭なナショナリズムの台頭を示すものだ」と言いたいのでしょう。社説はそうした見方をこぎれいにまとめ、「内向き志向の連鎖を防げ」という見出しを掲げました。
「相変わらずのワンパターン。昔の歌を歌い続けているなぁ」というのが率直な読後感です。EU離脱=偏狭なナショナリズム=右翼の選択、というワンパターン。欧州を中心に起きている複雑極まりない世界の動きを理解するのには、何の役にも立たない思考です。これだけなら、新聞を即ゴミ箱に投げ込むところですが、救いがありました。「偏狭な社論」に与(くみ)しない、骨のある記者もいるからです。
1面の左肩に掲載されたヨーロッパ総局長、梅原季哉(としや)の解説は骨太でとてもいい。欧州統合の理想が崇高なものであることは認めつつ、「だが、EU本部は選挙による審判を経ない形で各国の閣僚を経験したエリートらが牛耳っている。人々の手の届かない、そんな『遠い場所』で決められる政治は、強い反発を招いている」ときちんと書いているからです。ブリュッセル支局長として、EU官僚の実態をつぶさに見てきただけに、思いも深い。離脱派=民族主義=右翼と割り切れるような、そんな単純な事態ではないことをはっきりと書いています。
梅原の解説を肉付けするように、ブリュッセルの吉田美智子は国際面の記事で、EU官僚3万人の実態をえぐり出しています。平均月給は75万円、局長クラスなら190万円。さらに、子供1人につき毎月4万3000円の手当が上乗せされ、所得税も免除される。役人の厚遇きわまれり、と言っていいでしょう。英国では多くの人が、東欧や中東から流れ込んだ移民に仕事を奪われ、苦しい生活を強いられています。治安にも不安が募ります。こうした人たちが「おかしい」と異議を申し立てるのを「愚かだ」の一言で済ませられるわけがないのです。左翼か右翼かといった物差しで測れる問題でもありません。
戦争が起こらないような政治・経済体制をどうやって築いていくのか。同時に、東欧や中東、アフリカの人たちの苦境に手を差し伸べるためにはどうすればいいのか。その狭間で、英国だけでなく欧州の多くの人たちが煩悶しているのです。悩み抜いた末に1票を投じた人たちの選択の結果をワンパターンの思考で報じる記者を私は信用しません。共に悩み、苦しむ心があるならば、それが行間に滲み出るはずだからです。社論は社論として、新聞記者である前にまず一人の人間として、自分の信ずるところに忠実でありたい。
日本の憲法改正についても、朝日新聞の記者たちの意見は昔から統一などされていません。ずっと、揺れ動いていました。私が論説委員室に在籍していた2001年から2007年ころは、護憲派、改憲派、中間派(日和見)がそれぞれ3分の1の状態だったと理解しています。私を含め、国際報道を担った記者には改憲派が多く、「戦後の長い歩みを踏まえて憲法を現実に沿った形に改めるのは自然なこと」と考えていました。編集担当の幹部や論説主幹は護憲派から出てくるので、社説は護憲一本やりでしたが、論説委員室では憲法に関する社説案を議論するたびに激論になっていました。
安倍晋三首相や自民党が唱える憲法改正は、少し前の選挙スローガン「日本を、取り戻す。」に象徴されるように「古い日本は良かった」がベースにあり、私にはとても受け入れられません。けれども、護憲を唱える朝日新聞の社論も受け入れがたい。素直に読めば、自衛隊が違憲となるような条文をそのままにしておいていいはずがない、と考えるからです。後に続く人たちのためにも「未来に耐えうる憲法」に変革していく必要がある、と考えるのです。
英国の有権者は苦しみながら、幅広い議論を積み重ねて、この結論に達しました。私たちの社会はそれに匹敵するような広く、深い議論をしているのか。世界経済と政治の地殻がギシギシと音を立てて軋み、変わろうとしている時代にふさわしい挑戦を試みているのか。苦しむ覚悟がなければ、私たちは時代に置き去りにされ、やがて忘れ去られてしまうでしょう。
*山形県のわが家に配達される朝日新聞は「13版▲」という統合版です。夕刊はありません。
≪写真説明とSource≫
◎EU離脱派の集会で演説するジョンソン前ロンドン市長(ロイター=共同、東京新聞のニュースサイトから)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016062301000915.html
*メールマガジン「風切通信 6」 2016年6月23日
政治はその国、その社会のありようを映し出す鏡であり、縮図だと言います。だとするなら、私たちの国は自信を失い、目標を定めることもできずに漂い続ける巨大な船なのか。参議院選挙の公示前日、21日に東京・日比谷の日本プレスセンターで開かれた党首討論会をテレビで見ながら、私はそんな惨めな気持ちになりました。

壇上に並んだのは、なんと九つもの政党の党首。政党と党首の名前を覚えるだけでも一苦労です。そのうち、政党の党首と呼ぶにふさわしい器量をそなえた政治家が果たして何人いるのか。こんなに多くては、そもそも討論会として成り立たない。案の定、質問は自民党の総裁である安倍晋三首相に集中し、党首討論会は安倍首相の「実績宣伝の場」と化してしまいました。
2012年末に安倍首相が再登板して以来、低迷していた日本の株価は一時的に持ち直し、雇用情勢も改善されました。「経済を成長軌道に戻した」との主張は、それなりに説得力があるように見えます。けれども、日本の経済は成長軌道に戻ったと言えるのか。そもそも、経済を成長させることが最優先されるべき時代なのか。そういった根本的なことがあまり論じられていないのではないか。重要な指標とされる株価ですら、再び動きが怪しげになりつつあります。
経済に疎い私ですら、安倍政権が打ち出した政策には「こんなことをして大丈夫なのか」と心配になります。日本政府の財政はだいぶ前から借金頼みで、大量の国債を発行していますが、安倍政権下で日本銀行はその国債の買い入れに踏み切りました。中央銀行である日銀が国債を買うことは長年、「タブー」とされてきたはずです。そのタブーを破ったのです。紙幣の発行権限を持つ日銀が国債を引き受け、支払いは紙幣を増刷してまかなう。それによって、意図的にインフレに持っていってデフレから脱却するのだ、と説明されました。
けれども、タブーにはそれなりの理由があったはずです。日銀がそんなことをしたら、財政規律が保てなくなるから禁じ手とされていたはずです。「デフレ脱却のための異次元金融緩和」などという謳い文句で「財政規律」を放り出していいのか。「収入の範囲で金を使って暮らしていく」という規律を踏み外せば、待っているのは破産、というのは子どもでも分かる道理です。「自分たちの目の黒いうちは大丈夫。地獄の訪れはずっと先」と、政治家も官僚も高をくくっているのではないか。
厚生年金と国民年金を運用している「年金積立金管理運用独立行政法人」が安倍政権になってから、株式での運用比率を倍増させたのも気になります。年金の積立金はもともと、安全性の高い国内債券を中心に運用してきました。東洋経済オンラインの解説記事によれば、2014年10月の資産構成は国内債券60%、国内株式12%、外国債券11%、外国株式12%でした。それを国内債券38%、国内株式23%、外国債券14%、外国株式23%と劇的に変えたのです。株価が上がれば、資産は増えますが、下がれば減ります。きわめて危うい運用です。
年金積立金の運用変更は、国内の株価を吊り上げるため、と批判されています。これも、「取りあえず、景気が持ち直したと装うことができればいい」という態度の現れではないのか。「下々の者たちの積立金など、どうなろうと構いはしない」とうそぶく声が聞こえてきそうです。この運用変更は厚生年金と国民年金の積立金を対象にしたものです。議員年金や公務員の共済年金の積立金の運用は別途行っているとか。そちらの運用比率と資産構成もぜひ知りたいところです。
憲法改正や安全保障の問題についても、安倍政権が推し進めようとすることには危惧の念を覚えます。けれども、「ならば民進党に期待できるのか」と切り返されると、「できないよね」と答えるしかありません。2009年からの民主党政権下で何があったのか。マニフェストにはきれいごとをたくさん並べたのにほとんど実行できず、2011年の東日本大震災では惨め極まりない姿をさらけ出しました。名前を民主党から民進党に変えてみたところで、その「甘ちゃん体質」と「寄り合い所帯ぶり」は変わりようがないでしょう。
だったら共産党か。まさか。共産主義に基づく国づくりがどのようなものか。私たちはそれを嫌というほど見聞きしてきました。先進国で共産党と名乗る政党があるのは日本だけです。戦前、戦後のいきさつもあって生き延びてきた政党に未来を託すことなど、できるはずもありません。創価学会に無縁の身には公明党も遠い存在。「生活の党云々」を率いる小沢一郎氏は、福島原発事故が起きた時に被災地に行くどころか、東京から逃げ出す算段をしていたというから論外。社民党は「まだ居たの?」という感じ。あとの3党は失礼ながら割愛させていただきます。
一つの選挙区から複数の議員を選ぶ中選挙区制から「1選挙区1議員」の小選挙区制に変えたのは、二大政党制を実現するためだったはずです。なのに、政党の数は昔より増え、党首討論会すら実質的に成り立たないような国になってしまった日本。民族も宗教も多様なアメリカやイギリスで二大政党制が機能し、政権交代が実現しているのに、民族も宗教も比較的均質な日本で、なぜこんなに政党が乱立するのか。外から見れば、「なんとも奇妙な国」と見えることでしょう。
海を隔てたすぐそこに歴史的にも稀な「独裁国家」があり、核兵器と弾道ミサイルの開発に血道をあげているのに、まともな安全保障論議もなされない。安保関連法の問題を憲法との関連のみで論じるのは不毛です。憲法との整合性が図れないなら、憲法の改正も視野に入れて、現実を踏まえた安全保障の論議をすべきでしょう。選挙戦で経済政策や財政運営、安全保障問題がまともに語られない奇妙な国。なのに、選択肢だけはやたらにたくさんある、奇妙な選挙。ぼやいてみても、投票日は確実にやって来ます。取りあえずは「ひどさが一番少なそうな候補」に一票を投じるしかないのかもしれません。
≪参考サイト≫
◎ 東洋経済オンライン(「年金運用で巨額評価損」という不都合な真実)
http://toyokeizai.net/articles/-/113102
◎年金積立金管理運営独立行政法人の公式サイト
http://www.gpif.go.jp/gpif/mechanism.html
≪写真説明とSource≫
◎9党の党首討論会(毎日新聞の公式サイトから)
http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160622/ddm/010/010/029000c
*メールマガジン「風切通信 5」 2016年6月7日
キリスト教は異国の宗教である。唯一絶対の神を信じており、やおよろずの神々をあがめるわが国の精神風土に合わない。過激な信徒もいる――こんな理屈で警察が日本にいるキリスト教徒全員を監視の対象にしたら、大変な騒ぎになるでしょう。メディアも黙っていないはずです。ところが、これと似たことが起きているのに、日本ではほとんど騒がれることがありません。監視の対象がキリスト教徒ではなく、イスラム教徒だからです。
2010年10月に警視庁公安部の国際テロ捜査に関する情報が大量に流出する事件が起きました。流出した文書にはテロ関連の捜査対象者の情報に加えて、テロとは何の関係もない在日イスラム教徒の情報(名前や生年月日、住所、旅券番号、出入りしているモスクの名前など)が含まれていました。それが流出したのです。流出した情報を『流出「公安テロ情報」全データ』と題して本にする出版社(第三書館)まで現れました。その結果、銀行口座が凍結されたり、インターネットのプロバイダー契約を解除されたりした人もいたといいます。
とんでもない事件です。翌2011年5月に日本人と外国人のイスラム教徒17人が政府と東京都に計1億5400万円の損賠賠償を求める裁判を起こしたのは当然でしょう。裁判は東京地裁、東京高裁とも東京都に賠償責任があることを認め、最高裁判所も5月31日付で高裁の判断を支持する決定を下しました。東京都は被害者に9020万円支払うことになりました。が、問題なのは「すべてのイスラム教徒を対象とする警視庁の捜査は違法ではない」という地裁と高裁の判断がそのまま最高裁でも認められたことです。

自由人権協会70周年プレシンポジウムの会場
あきれました。「こうした情報収集は国際テロ防止のためやむを得ない」と裁判所が認めてしまったのです。なんという人権感覚、なんという時代認識であることか。イスラム過激派によるテロは日本にとっても深刻な脅威であり、捜査に全力を尽くすのは当然のことです。ですが、どんな捜査であっても、憲法と法律に基づいて行うのが法治国家というものです。ある特定の宗教の信者すべてを監視の対象とするような捜査が許されるはずはありません。それなのに、最高裁判所は「やむを得ない」とする下級審の判断を支持して判決を確定させてしまったのです。
これは大ニュースです。メディアが「とんでもない判決が確定してしまった」と大騒ぎすべき事件です。なのに、日本の通信社も新聞も「ベタ記事」扱いで報じました。私は見逃してしまい、つい先日(6月4日)、東京で開かれた自由人権協会の70周年プレシンポジウムに参加して、井桁(いげた)大介弁護士からこの最高裁の決定を聞きました。決定の内容に仰天し、それにも増して、メディアがそれをベタ記事扱いしたことに驚いてしまいました。
日本の憲法は第14条で「法の下の平等」をうたい、「人種や信条、性別などで差別されない」と規定しています。第20条では「信教の自由」を保障しています。宗教を理由に差別することは許されないのです。これらの規定が日本国民だけでなく、日本で暮らす外国人にも適用されることは言うまでもありません。「情報が流出して損害を受けたから賠償しなさい」と言って済む話ではないのです。
自由人権協会によれば、アメリカでも同じように捜査機関がすべてのイスラム教徒を監視の対象にしていることが発覚して大問題になりました。9・11テロを経験し、さらなるテロにおびえる国です。捜査当局としては「あらゆる手段を駆使して次のテロを防ぐ」といきり立ったのでしょう。ところが、裁判でこれが「違法」として争われ、今年の1月17日に連邦控訴審で和解が成立しました。
その内容は「ニューヨーク市警は今後、宗教や人種に着目したプロファイリング捜査はしない」「警察の内部に民間の監督官を入れ、人権侵害的な捜査についてチェックさせる」というものです。つまり、すべてのイスラム教徒を監視の対象にして一覧資料を作るようなことはしない、と約束したのです。テロの脅威と向き合わざるを得なくても、法治国家として人権保障の大原則をゆがめるわけにはいかない。捜査する側もそれを認めたということです。まっとうな判断、と言うべきでしょう。
なのに、なぜ日本の裁判所では「当たり前の判断」が下せないのか。憲法判断に踏み込むのを避ける体質。警察を含む行政府のすることを追認する癖が染みついており、波風を立てるような判決を嫌がる――いくつか理由は考えられるのですが、要は日本という社会に「法とはいかにあるべきか」という根本的なことが根付いていない、ということなのではないでしょうか。
明治の憲法はドイツの憲法の焼き直し。今の憲法は戦争で負けてアメリカに書いてもらったもの。私たちの国は一度も「悶え苦しみながら、みんなで憲法を練り上げる」という営みをしたことがありません。それがこういう時に滲み出てくる、ということなのかもしれません。メディアも右へ倣え。「畏れ多くも、最高裁判所が下した判断なのだから妥当なのだろう」と思い込む。それがいかに重大な憲法問題を孕んでいるかを考えないから、「ベタ記事扱い」になってしまうのです。
イスラム過激派によるテロの脅威を過小評価するつもりはありません。日本国内でも起きる恐れは十分にあります。捜査当局は全力を尽くすべきだし、一市民としてそれに協力する心構えもあります。けれども、犯罪の捜査はしかるべき根拠に基づいて、テロを犯す疑いのある人物を対象にして行うのが鉄則です。モスク(イスラム礼拝所)に出入りする人たちを監視する必要も出てくるでしょう。が、その場合でも、出入りするすべての信徒の個人情報を調べ上げ、それを一覧リストにするようなことは許されないはずです。
そうした捜査そのものが「イスラム教徒はすべて危険だ」という差別感を助長し、一人ひとりの人権を守るという法治国家の大原則を掘り崩すことになるからです。日本に住むイスラム教徒はごく少数です。けれども、彼らの人権を守ることを怠れば、それは自分たち自身の厄災となって跳ね返ってきます。ある特定の宗教を信じる人たちすべてを捜査の対象にする。そんなことは法治国家で許されることではありません。
最高裁判所がどんな理屈をこねくり回そうと、おかしいものはおかしい。それを「おかしい」と指弾しないメディアは職務怠慢ではないか。このままでは、職を失う危険を冒してまで警視庁のファイルを暴露した、勇気ある内部告発者が浮かばれない。
≪参考サイト≫
◎警視庁のテロ情報流出事件に関する最高裁判所の判断(共同通信のニュースサイトから)
http://this.kiji.is/110662350981809661?c=39546741839462401
◎警視庁国際テロ捜査情報流出事件(ウィキペディアから)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%86%E3%83%AD%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%B5%81%E5%87%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
◎アメリカのイスラム捜査事件の概要と和解内容(ムスリム違法捜査弁護団のサイトから)
http://k-bengodan.jugem.jp/?eid=56
◎日本国憲法第14条、第20条(政府の公式サイト「電子政府」から)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
≪写真説明とSource≫
◎ 自由人権協会70周年プレシンポジウム。シンポジウムでは、米英政府による広範な個人情報収集活動を告発したエドワード・スノーデン氏がネット回線を通して講演した(6月4日、東大本郷キャンパス福武ホール。長岡遼子撮影)
*メールマガジン「風切通信 4」 2016年5月29日
「71年前の、雲一つない晴れ渡った朝、死が空から舞い降り、世界を変えてしまいました」。バラク・オバマ大統領は広島での演説をそう切り出しました。「なぜ、私たちはここ広島に来るのか。私たちは、そう遠くない過去に解き放たれた恐ろしい力に思いを馳せるためここに来るのです」と言葉を継ぎ、広島への原爆投下で亡くなった10万人以上の日本人に加えて、広島にいて命を落とした数千人の朝鮮人と十数人の米国人捕虜を悼みました。

心のこもった優れた演説でした。歴史への深い洞察と未来への希望を感じさせる演説でした。アメリカでは大統領だけでなく著名な政治家も、作家やジャーナリストをスピーチライターとして抱えて演説の草稿を書いてもらうのが一般的なようですが、最後にその草稿に自分の思いも十分に織り込んだのではないか、と思わせる内容でした。
「私たちは悪事をなす人間の力を根絶することはできないかもしれません。だから、国家や同盟は自衛する手段を持たなければなりません。しかし、わが国をはじめ核兵器を持つ国々は、恐怖の論理から抜け出して核なき世界をめざす勇気を持たなければなりません。私の生きている間には、この目標は実現できないかもしれません。しかし、たゆまぬ努力によって破局が起きる可能性を押し戻すことはできるし、蓄積された核兵器の廃絶に至る道筋を描くことはできるはずです」
オバマ大統領の広島演説を聞いて、かつてイスラエルのシモン・ペレス首相(当時)が口にした言葉を思い出しました。1995年12月6日に広島で開かれた国際会議「希望の未来」。ペレス首相はエルサレムの首相官邸からインターネット回線を通してこの会議に参加し、こう言ったのです。「問題は武器ではなく、政治システムだ。最も危険なのは、邪悪な運動と核兵器が結び付くこと。独裁や腐敗した政府に信を置くことはできない。全体が民主的な体制にならない限り、核兵器のない世界にたどり着けると考えるのは妄想だ。未来の世界にとっての真の保障は民主的なシステムだ」
この国際会議は朝日新聞社と米国のウィーゼル財団が共催したもので、私は担当記者の一人としてこの演説を聞き、記事を書きました。最初、私は「核廃絶は幻想だ」と書いたのですが、英語が堪能な同僚から「いや、 disillusion(幻想、幻滅)ではなく、delusion(妄想)と言っている。そのまま書くべきだ」と指摘され、発言を確認したうえで手直ししたのを覚えています。淡々とした口調ながら断固とした表現で、強烈な記憶として残りました。ペレス首相の言葉は国際政治の冷徹な現実を映し出したものでした。
現実を率直に語るのは、政治家のなすべきことの一つです。米英仏やロシア、中国に加えてイスラエルやインド、パキスタン、北朝鮮が核兵器を保有していることを考えれば、核廃絶を唱えるのは、彼の言う通り、限りなく「妄想」に近いのかもしれません。しかし、それでも、現実だけでなく、理想と夢を語るのも政治家の大切な仕事の一つです。オバマ大統領の言葉もまた重いし、胸に刻みたいと思うのです。
たとえ妄想に近いものであっても、核廃絶をめざす勇気を持ちたい。私だけでなく、多くの人が勇気と妄想のはざまで揺れ動きつつ、世界の行く末を思っているのではないでしょうか。こういう時、心の支えにする言葉があります。南アフリカで白人政権のアパルトヘイト(人種隔離)政策と闘い、長い投獄を経て政権を奪取し、黒人と白人が共存する道を切り拓いたネルソン・マンデラ氏の言葉です。彼は、自伝『自由への長い道』(東江一紀訳)の最後にこう記しました。
「あらゆる人間の心の奥底には、慈悲と寛容がある。肌の色や育ちや信仰のちがう他人を、憎むように生まれついた人間などいない。人は憎むことを学ぶのだ。そして、憎むことが学べるのなら、愛することだって学べるだろう」
(*オバマ演説は長岡昇訳、マンデラ自伝は東江一紀訳)
≪参考サイト、文献≫
◎バラク・オバマ大統領の広島演説全文(日本語、朝日新聞のウェブサイトから)
http://www.asahi.com/articles/ASJ5W4TKRJ5WUHBI01N.html
◎バラク・オバマ大統領の広島演説全文(英語、朝日新聞のウェブサイトから)
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201605270097.html
◎ネルソン・マンデラ著『自由への長い道』(上下、東江一紀訳、NHK出版)
≪写真説明とSource≫
◎広島で演説するバラク・オバマ大統領
http://nikkidoku.exblog.jp/25273980
*メールマガジン「風切通信 3」 2016年5月23日
山村の実家で年金生活を始めた私の目下の課題は「生活力の向上」です。新聞記者として30年余り生き、その後、小学校と大学で働きましたが、炊事、洗濯、掃除のノウハウをほとんど知りません。かみさんに基礎から教えてもらっていますが、「こんなこともできないの」と冷ややかに言われる毎日。かみさんは山形市の実家で母親(92歳)の世話をするかたわら、毎週、私の生活を支援するため山奥の家まで来てくれます。「これじゃあ家事手伝いとも言えないので、家事見習いね」とのご託宣。悔しくても、言い返せません。

農村で生まれ育ったのに、草花や木々のこともほとんど分かりません。それではうるおいに欠けるので、前回のコラムでも書きましたが、庭先に咲いている花の名前を調べることから始めました。古い人間なので植物図鑑や山野草のハンドブックに頼る。が、本をめくってもなかなか分かりません。インターネットのサイト「みんなの花図鑑」や「四季の山野草」の方がずっと頼りになることを知りました。
「みんなの花図鑑」はNTTグループが運営しているサイトです。2010年秋に3億円を出資してリニューアルし、3000種以上の花のデータを収めています。登録利用者は現在、1万8000人余り。このサイトに花の写真を投稿して「名前を教えてください」とお願いすると、早い時には数分で次々に回答が寄せられます。
庭の片隅に、白い可憐な花が咲いていました。草丈10数センチ、花径3センチほど。根元から細長い葉をいくつも出しています。図鑑で調べて「ホソバノアマナ(細葉の甘菜)」ではないかと見当をつけたのですが、「みんなの花図鑑」に投稿した写真に寄せられた回答は「オオアマナ(大甘菜)」と「タイリンオオアマナ(大輪大甘菜)」の二つでした。この二つの花をさらにネットで検索しても、なかなか分からなかったのですが、コメント付きで答えてくれた方がいて、ようやくヨーロッパ原産の「オオアマナ」と判明しました(ホソバノアマナは日本原産)。
そのコメントがすごかった。花の名前だけでなく、オオアマナの学名Ornithogalum umbellatum L. と英語名 Star of Bethlehem(ベツレヘムの星)を記し、「 学名で検索するとオオアマナとタイリンオオアマナの違いがよくわかります」というアドバイスまで付けてくれていたのです。さっそく、両方の学名で検索すると、英語のサイトに辿り着き、その説明で両者の違いがよく分かりました。タイリンオオアマナの花がバナナの房のようにくっついて咲くのに対して、オオアマナは茎から散開して咲くのです。「総状花序(かじょ)」に対して「繖形(さんけい)花序」と言うのだそうです。
インターネットのすごさを感じるのはこういう時です。日本語のサイトで分からなければ、英語のサイトに当たり、別の言語ができれば、その言語のサイトで調べることもできます。「知識と情報の世界で革命が起きた」というのは誇張ではなく、現実であり、その流れはさらに勢いを増しています。租税回避地をめぐるパナマ文書の暴露と報道も、ネット時代でなければ考えられない出来事です。次の時代を生き抜くためには「ネットと語学」がどうしても必要になるのです。
それなのに、日本の教育現場では何が起きているのか。小学校の校長をしている時、インターネット教育の状況に愕然としました。講師役で登場したのは地元の警察署の少年補導係の警察官だったのです。これは、私が勤めていた小学校に特有のことではなく、山形県内の小中学校の一般的な傾向でした。「ネットにはエログロがあふれている。援助交際の窓口もある。裏サイトでのいじめも深刻だ。いかに危険なものかを教えなければならない」という感覚なのです。「最初にそれを教えるのはおかしい」と私が言うと、「教育現場の厳しさを知らないよそ者の戯言」と言い返される有り様でした。山形県に限った話ではないでしょう。
インターネットの世界は現実の世界と背中合わせになっており、ネット上には小学生や若者に有害なものもあふれています。それに対処するのは重要なことです。けれども、最初の段階でそれを強調するのは、包丁の使い方を説明するのに「包丁は危ないものだ」と教えるのと同じです。料理を作るのに包丁は不可欠です。なのに、「包丁は人を傷つけるのに使われるから危ない」と最初に教えてどうするのか。
こういう教育が行われているのは「大人の都合による教育」がまかり通っているからでしょう。子どもを「管理する対象」として捉えており、「大人たちとは異なる時代、異なる世界を生きていく人間」として遇しようとしていない、と言ったら言い過ぎでしょうか。学校現場のIT環境の劣悪さと併せて、「世界の流れと教育の現状との乖離」を強く感じました。
最近、文部科学省は小学校の教育に「プログラミング」を導入しようとしていると報じられています。小学生にプログラミングの基礎を教えようというわけです。「相変わらず、トンチンカンな役所だなぁ」と感じます。公立小中学校の教員のほぼ全員にパソコンが貸与されるようになって、まだ5、6年しかたっていないというのに。教員のIT教育をなおざりにし、学校のネット環境もきちんと整備しないまま、メディアが飛びつくような新規事業に血道をあげる文科省。それを垂れ流す記者クラブの面々。そのツケを払わされるのは私たちの子どもたちであり、孫たちです。
「包丁はこうやって使って料理しましょう。でも、使い方を間違えると危ないよ」。インターネットについても、同じようにその効用とリスクをきちんと教えるべきです。教育の場にこそ、最新の設備とノウハウを提供する必要があります。そのためには、今の教育行政と教育現場を大胆に変革しなければなりません。が、このままでは、変革どころか改善すらできそうもありません。それがとても切ないです。
≪参考サイト≫
◎「みんなの花図鑑」
https://minhana.net/
◎「四季の山野草」
http://www.ootk.net/shiki/
◎ 「みんなの花図鑑」とは(NTTのホームページから)
http://www.ntt.co.jp/news2011/1104/110413a.html
≪写真説明≫
◎ 庭の片隅に咲いている「オオアマナ」(2016年5月14日、山形県朝日町で撮影)
*メールマガジン「風切通信 2」 2016年5月9日
山形県の山村にある実家で暮らし始めて、二度目の春を迎えました。去年は亡くなった母の遺品や不要物の後片付けに追われ、庭は荒れ放題でしたが、やっと余裕が出てきたので、少しだけ庭の手入れも始めました。その庭にいくつか変わった花が咲いています。
雪解けの後、福寿草に続いて咲いたのは「キバナノアマナ(黄花の甘菜)」という可憐な花でした。図鑑によるとユリ科の植物で、一枚だけアヤメの葉のような細長い葉を出しているのが特徴です。しばらくすると、赤紫の楚々とした花も咲きました。山と渓谷社の『春の野草』(永田芳男著)で調べても分からず、園芸愛好家のウェブサイトに写真を投稿して「どなたか花の名前を教えてください」とお願いしました。

自宅の庭に咲いているルナリア
ところが、投稿される「名前不詳の花」の写真はかなりの数で、どなたからも回答が寄せられませんでした。やむなく、図鑑やネット上の画像を手掛かりに探索したところ、ようやく「ルナリア」というヨーロッパ原産の花であることが分かりました。花の近くにある平べったい鞘(さや)に種子が6個ほど入っており、これが決め手になりました。この鞘は、熟すと割れて種子が飛び出し、銀貨のようにキラキラ輝くのだそうです。このため、ドライフラワーの愛好家に人気で、「銀扇草」や「大判草」の異名もあるとか。
説明文を読んで驚きました。「みんなの趣味の園芸」というウェブサイトに、「和名の『ゴウダソウ』は、フランスからタネを持ち帰り、日本に導入した大学教授の合田(ごうだ)清氏の名前に由来します」とあったからです。合田氏は幕末の文久2年(1862年)、江戸・赤坂の生まれ。明治13年、18歳で兄と共にフランスに渡って西洋木版画を学んでその先駆者になり、東京美術学校(東京芸大美術学部の前身)で長く教壇に立った人物です。その合田氏がルナリアの種子を持ち帰り、広めたのでした。
志を抱いてフランスに渡った若者が持ち帰った花が、いったいどのようにして広まり、どのようなルートで新潟県境に近いこの山村まで辿り着いたのか。不思議な思いにとらわれました。合田氏は、私が働いていた朝日新聞と深い縁のある人でした。手もとにある『朝日新聞社史 明治編』によると、大阪の新聞だった朝日新聞が明治21年に東京進出を決めた際、社主の村山龍平はフランスから帰った合田氏に入社するよう懇請したといいます。写真製版の技術がなかった当時、西洋木版は最先端の技術で、それを活用して紙面を飾りたいと考えたのでしょう。
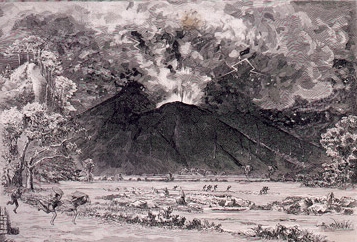
東京朝日新聞の付録に掲載された「磐梯山噴火真図」
合田氏は「自由な立場で活動したい」と入社は断りましたが、版画家の山本芳翠氏と共に設立した生巧館を拠点にして朝日新聞に協力しました。明治21年7月15日、東京朝日新聞の創刊5日後に起きた会津磐梯山の大噴火に際しては、山本氏が被災地に急行して下絵を描き、合田氏が版木に彫って「磐梯山噴火真図」という作品に仕上げて、新聞の付録として発行しました。噴火真図は大変な評判になり、朝日新聞の東京進出を勢いづかせたといいます。この版画は有名で、私も何度か見た記憶があります。「あの版画を制作した人が持ち帰った花だったのか」と、感慨深いものがありました。
私は18歳で山形を離れて大学に進み、新聞記者として30年余り各地を転々としましたが、インドとインドネシアに駐在した5年間を除けば、ほぼ毎年、帰省していました。その際、実家の庭にある草花も目にしていました。このルナリアも咲いていたに違いないのですが、それに心を寄せることはありませんでした。疲れ果てて、ただだらしなく眠りこけるだけ。なんと余裕のない人生だったことか。
新聞社を早期退職して山形に戻り、民間人校長として4年、大学教員として3年働いている間も、何かに追い立てられるような日々で、相変わらず草花を愛でる余裕はありませんでした。「ひっそりと庭に咲いているこの花は何という名前なのだろう」。そんな気持ちになれるまで、63年もかかってしまいました。
それでも、遅すぎるということはないはずです。身近にある草花や木々をゆっくりと眺め、その名前を探し、来歴に思いを巡らして楽しむことにします。月を意味する「ルナ」を冠した名前を持ち、西洋木版画の先駆者にちなむ別名を持つ「ルナリア」に続いて、「オダマキ(苧環)」という花も見つけました。淡い青紫の花で先端に白い縁取りがある素敵な花です。

オダマキの花
この花の漢字名の最初の文字「苧」は、日本で綿花の栽培が広まる江戸時代まで衣服や漁網の素材として広く使われていた「青苧(あおそ)=カラムシ」を意味する文字で、麻の一種です。山形県の内陸部はその青苧の大産地の一つでした。オダマキもまた、不思議な物語を秘めているに違いありません。ゆっくりと、その物語をひもとくことにします。
≪参考サイト、文献≫
◎ ルナリアの説明(ウェブサイト「みんなの趣味の園芸」から)
https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-821
◎合田清氏の経歴(東京文化財研究所のホームページから)
http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8444.html
◎『山渓フィールドブックス9 春の野草』(永田芳男著、山と渓谷社、2006年)
◎『朝日新聞社史 明治編』(朝日新聞百年史編修委員会編)194-197ページ
≪写真説明とSource≫
◎自宅の庭に咲いているルナリアとオダマキ(2016年5月7日、山形県朝日町で撮影)
◎山本芳翠・画、合田清・刻の「磐梯山噴火真図」(明治21年8月1日の朝日新聞付録に掲載)=郡山市立美術館のホームページから
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/collestion/05/16.html
*メールマガジン「風切通信 1」 2016年4月22日
ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家主席、シリアのアサド大統領、パキスタンのシャリフ首相、そして英国のキャメロン首相。租税回避地の内部文書が大量に暴露された、いわゆる「パナマ文書」事件は、日ごろ光を浴びることのない世界の裏側でどの国のどういう政治家がうごめいているのかを実に生々しく照らし出してくれました。

権力の専横を追及するジャーナリストが次々に奇怪な死を遂げる国、ロシア。指導部が「汚職撲滅」を唱えても全く説得力がない国、中国。アラブの春で独裁者が相次いで失脚したのに「冷酷無比」とされる独裁者が生き残った国、シリア。政治家の腐敗ぶりでは第一級と折り紙つきの国、パキスタン。こうした国々と一緒に自分の国の名前が、しかも首相がらみで出てきたことに英国の有権者が怒り、キャメロン首相に「辞任しろ」と迫るのは当然のことでしょう。
そもそも、租税回避地(タックス・ヘイブン)という名称が美しすぎる。本来は、法人税や所得税を極端に安くして金融や物流の拠点として栄えることを目的にした制度だったようですが、その後、「こちらの方がより安全で便利」という競争原理が働いて暴走し、今ではその多くが「資産隠匿地」と呼ぶべき代物になってしまいました。腐敗した権力者が資産を隠し、大企業が税逃れに活用し、ギャングが資金洗浄に利用する場と化しています。なにせ、登記した会社の内容を詳しく公開する必要がなく、会計報告も不透明なままでいいのですから。不正が疑われる資産は数億円、数十億円というスケールのものが多数あると伝えられています。
主要国で構成するOECD(経済協力開発機構)が透明性を高めるための行動計画を取りまとめ、対策に乗り出していますが、その主要国の中にも租税回避地を利用している政治家や企業人がいるのは半ば周知の事実です。実効性が上がるわけがありません。膨大な電子ファイルを入手した人が南ドイツ新聞に情報を提供し、同紙が「国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)」に協力を求めたのは賢明で適切だった、と言うべきでしょう。
新聞社にいた頃、先輩記者に「日本の政治家の錬金術は主に三つある」と教わったことがあります。土地転がしと株の売買、海外取引の三つです。土地転がしは、田中角栄首相の金脈報道をきっかけに露骨な手法は通用しなくなりました。株の売買もまた、竹下登首相もからんだリクルートの未公開株汚職が発覚してからルールが厳格になり、簡単にはあぶく銭を手にすることができなくなりました。けれども、海外取引や対外援助がらみの闇資金は追及するのが極めて難しく、腐敗した政治家の錬金手法として温存されてきました。
どの国でも、権力者の腐敗と闘ってきたジャーナリストはみな、「海外取引の壁」の厚さに何度も煮え湯を飲まされ、切歯扼腕してきたのです。国際調査報道ジャーナリスト連合は、そうしたジャーナリストたちがこの壁を乗り越えるために創った組織であり、パナマ文書事件は長く苦しい闘いの末に辿り着いた成果なのです。これまでに報道されたのは1150万点とされる文書のごく一部であり、これから続々とスクープが放たれることでしょう。
一連の文書は、租税回避地での会社設立を引き受けているパナマの法律事務所から流出したため、「パナマ文書」事件と呼ばれていますが、会社そのものの所在地はカリブ海のバージン諸島やケイマン諸島が多いとされています。どちらも英国の領土です。その気になれば、英国の政府と議会が情報公開や会計の透明さを求める政策を打ち出して改善できるはずです。が、金融サービス部門で世界を引っ張る英国は「大事な顧客を失いたくない」と考えるかもしれません。当局に期待するのは無理でしょう。
この手の金融サービスで英国と競っているのはアメリカです。多くの米国の政治家や企業人が「租税回避地」を利用しているはずですが、今回は全く名前が出てきていません。「大事な文書を漏らしてしまうような法律事務所」ではなく、もっとしっかりした(より悪質な)法律事務所を使っているため無傷で残っているのかもしれません。あるいは、競争相手の英国をたたくために米国寄りの勢力が意図的にリークした、という可能性も否定できません。金融取引の闇は深く、現時点では情報提供の背景は不明です。
それにしても、カリブ海に浮かぶバージン諸島やケイマン諸島が今、「資産隠匿の島」として世界の注目を集めていることに、私は歴史の暗喩のようなものを感じます。これらの島々は大航海時代が始まってから、アフリカで拉致され売買された黒人奴隷たちが最初に連れてこられ、サトウキビ栽培の奴隷労働に従事させられたところです。厳しい歴史を背負わされた人々の島が、腐敗した政治家や企業人が資産を隠す場所として利用され指弾される――そういう歴史を強い、おとしめた人間たちの末裔が過去を振り返ることもなく、のうのうと生きているのに。
*3月末で山形大学を退職し、4月から実家がある山形県朝日町の太郎という村で年金生活に入りました。村は、風切(かざきり)という山のふもとにあります。今月からは「風切(かざきり)通信」と改題してメールマガジンをお送りします。
≪参考サイト≫
◎国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)とは何か(東洋経済Online)
http://toyokeizai.net/articles/-/112693
◎国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)の公式サイト(英語)
https://www.icij.org/index.html
◎パナマ文書に登場する主な政治家(ICIJのサイト内。英語)
https://panamapapers.icij.org/the_power_players/
◎パナマ文書に登場する3万7000人の名前が検索できるサイト(英国の日曜紙サンデー・タイムズが開設。英語)
http://features.thesundaytimes.co.uk/web/public/2016/04/10/index.html
≪写真説明とSource≫
◎パナマ文書に登場する政治家の似顔絵(上記の3番目のサイト)
*メールマガジン「小白川通信 42」 2016年3月15日
「チェスの世界チャンピオンがコンピューター(人工知能)に負けた」と聞いても、それほど驚きはしませんでした。チェスは駒の数が少なく、相手の駒を取っても使うことはできません。手数は膨大ですが、高速計算が得意なコンピューターにとっては苦になるような手数ではないからです。1997年のことでした。
その16年後の2013年に将棋のプロ棋士が人工知能に負けた時には驚きました。将棋はチェスより駒が多く、はるかに複雑です。何よりも、取った相手の駒を使うことができますから、変化は飛躍的に増えます。「アマチュアはともかく、プロには当分勝てないだろう」と思っていたのですが、その壁はあっさり乗り越えられてしまいました。

囲碁棋士のイ・セドル(左)と人工知能の開発者デミス・ハサビス
それでも、囲碁については「人工知能がプロに勝つには数十年かかるだろう」と言われてきました。囲碁は変化が将棋より格段に多いのに加えて、数値で表すのが難しい価値判断をして打たなければならない場面が序盤から終盤まで連続して現れるからです。
その一つに「劫(こう)」という局面があります。これは、お互いに相手の石を取ることができる状態のことです。ただし、交互に石を取っていたら勝負はエンドレスになってしまいますので、「劫」になった場合、対局者は「一度別のところに打ち、相手がそれに応じたら石を取ってもいい」というルールになっています。別のところに打たれた相手は「それに応じないことで生じる損失と、劫に勝って得られる利のどちらが大きいか」を判断しなければなりません。こうした複雑極まる局面がほかにいくつもあり、コンピューターでプロに勝つプログラムを組むのはすぐには無理だろうと考えられていたのです。
しかし、その囲碁も人工知能に屈しました。世界最強の囲碁棋士の一人、韓国のイ・セドルが人工知能との5番勝負に敗れたのです。今日(3月15日)、5回目の対局が終わり、人工知能が4勝1敗と圧勝しました。囲碁の敗北は単なる「ゲームの世界の勝敗」にとどまるものではありません。人工知能のプログラム開発が新たな段階に到達したことを示し、新しい可能性が切り開かれたことを意味しているからです。
チェスの場合も将棋の場合も、コンピューター技術者は「可能なものはすべて記憶させ、すべて計算して選択する」というプログラムを組んで、プロの選手に対抗しました。人間では太刀打ちできない計算速度と記憶容量を持つコンピューターの特性を活かして勝負したのです。ただし、同じ発想でプログラムを組んで囲碁のプロ棋士に挑戦しようとすれば、チェスや将棋とは比べものにならない記憶容量と計算速度を持つ「とてつもないコンピューター」が必要になり、「勝つまでには数十年かかる」はずだったのです。
今回、囲碁棋士に勝った人工知能「アルファ碁」というプログラムは、「すべてを計算する」という発想を捨てました。その代わりに、どの手がより良い結果を生むのかを判断して絞り込む、独創的なプログラムを開発したようです。専門家でない私には具体的な内容は分かりませんが、それによって「とてつもないコンピューター」ではなく、「今ある普通のコンピューター」で勝負できるようになったのです。このプログラムは、自分で新しいデータを次々に吸収して価値判断の能力を向上させる特性を持つ、とも伝えられています。ITの世界に新しい地平を切り開いた、と言っていいでしょう。
これを開発したのは、英国の若き天才たちです。開発の中心になったデミス・ハサビス(39)は4歳でチェスを覚え、2週間で大人を負かしたと伝えられる天才です。15歳でケンブリッジ大学コンピューター学部に合格、コンピューターゲームの開発に乗り出しました。2010年に仲間と「ディープマインド」という人工知能開発会社を立ち上げ、4年後に検索エンジンで知られるグーグルがこの会社を4億ポンド(推定)で買収し、傘下に収めています。
コンピューター開発の主戦場は、とっくの昔にハード(機械)からソフト(プログラム開発)に移っていますが、そのソフト開発の中でもっとも激烈な競争が行われているのは人工知能の開発とされています。去年夏のセミナーで日本IBMの近況を知る機会がありましたが、IT業界の巨人IBMが力を注いでいるのはコンピューターの製造販売ではなく、今や人工知能の開発です。とりわけ、大口の顧客が見込める「危機管理と危機対応」などの分野で人工知能の開発を進め、活路を見出そうとしています。
例えば、森林火災にどう対処するか。火災の発生場所、風向きなどの天候、動員できる人員と機材を即座に割り出し、人工知能が最適の対処方法を決めてくれるのです。人間がデータを集めて入力するのではなく、ある人が「天候はどうなっている」「人員と機材は」「道路状況は」と次々に聞けば、人工知能が自分でデータベースから必要な情報を引っ張り出してきて、損害を最小に抑える対策を示してくれるのです。もちろん、原発事故の対応などにも応用できるでしょう。
そして、こうしたソフト開発のはるか先に見えてくるのは、究極の危機管理とも言える「戦争の仕方」を提示してくれる人工知能です。政治や軍事の専門家の中にも目をみはった人がいるに違いありません。SF的な世界に向かって、人工知能の開発は大きな一歩を踏み出したのです。どこまで進化するのか。どのくらいのスピードで成長するのか。ワクワクする一方で、空恐ろしくもあります。
とはいえ、まだ「ゲームという限られた世界」での大きな一歩に過ぎません。SF的世界が現れるまでには、まだいくつものブレイクスルーが必要でしょう。「人工知能には学習能力がある」とは言っても、学習の仕方のプログラムを組むのはあくまでも人間であり、人間の能力が無限だとも思いません。最後の最後に、人間の力では突破できない壁が立ちはだかるかもしれません。
宇宙は広大です。そして、一人ひとりの人間、さらには生きものが内包するものも深遠です。人工知能も人間が生み出したものであり、人間が考えるものである以上、そうした広さや深さに到達することはあり得ないのではないか、とも思うのです。
《参考サイト》
人工知能の開発会社Google DeepMind の公式サイト(英語)
https://deepmind.com/
Google DeepMind の代表デミス・ハサビス(英語版ウィキペディア)
https://en.wikipedia.org/wiki/Demis_Hassabis
≪写真のSource≫
http://wired.jp/2016/03/12/deepmind/
*メールマガジン「小白川通信 41」 2016年3月6日
あらゆる鳥の中で
カラスよ お前は一番の嫌われもの
春 木々が柔らかい光を浴びて芽吹き
里山がモスグリーンに染まるころ
お前は黒い一筋の線となって横切る
なんと目障りなことか

夏 木々が葉裏を白く返してそよぎ
照り付ける日差しの中で育つころ
お前は黒い染みのように鎮座している
なんと暑苦しいことか
秋 吹き渡る風に稲穂が波打ち
山々がうっすらと色づき始めるころ
お前は人間の残り物を黙々とついばむ
なんと見苦しいことか
けれども 冬
荒れ狂う吹雪をものともせず
お前は雪原高く舞い上がり
白い大地を睥睨(へいげい)しつつ飛んでゆく
カラスよ お前は美しい
*写真 姉崎一馬氏が撮影、提供
*メールマガジン「小白川通信 40」 2016年2月13日
雪が降る、側溝に捨てる。雪が降る、側溝に捨てる――北国の冬の暮らしはその繰り返しです。側溝がないところは、除雪機かスコップで雪を投げ上げるしかありません。のしのしと雪が降る日には50センチほど積もることもあり、一日に何度も雪かきをしなければなりません。楽な暮らしではありませんが、誰もぼやいたりしません。
春になれば、降り積もった雪が少しずつ解けて田畑を潤してくれます。深山の雪は初夏まで残って沼を満たし、日照りの心配をする必要はありません。土に生きる人々にとって、冬の雪は恵みでもあることを知っているからです。

蔵王・地蔵岳の黎明
スキーという楽しみもあります。あらゆるスポーツの中で、私はスキーが一番好きです。身を切るような寒さの中を滑り下りる爽快さは、何とも言えません。雪かきのしんどさも吹き飛ばしてくれます。しかも、山形には蔵王(ざおう)という広々としたスキー場があります。朝、久しぶりに空が晴れ渡ったら、「今日は蔵王で滑ろう」と気軽に出かけることもできます。新聞記者時代のスキー仲間からは「贅沢だなぁ」と羨ましがられています。
先週の週末、その友人たちと蔵王で恒例のスキー合宿をしました。昼はスキー、夜は温泉三昧。年に一度の楽しい会ですが、今年は仲間の一人が蔵王の山と雪をテーマにした写真集を見つけてきました。温泉街で働いている鏡學(かがみ・まなぶ)さんが自費出版した本です。出版社は地元山形市の小さな会社、部数も700と少ないのですが、驚くべき写真集でした。
表紙は、厳冬期の蔵王・地蔵岳の黎明をとらえた作品。夜明けのかすかな光を浴びて、稜線が黄金色に輝く。陽光が雪原に淡く流れる。この一瞬をとらえるために、鏡さんは何回、雪に埋もれて夜明けを待ったことか。珠玉の一枚です。蔵王名物の樹氷の間を若いカップルがスノーボードを抱えてゆっくりと歩いていく写真もいい。周りは氷点下のはずなのに、ほんのりとした温かみが伝わってくるのです。
どの作品からも蔵王に対する撮影者の愛情があふれ出てくるのですが、「この写真集から一枚だけ選ぶとしたらどれか」と問われれば、私は新雪に包まれた紅葉の写真を選びます。蔵王の初雪は早く、ブナやカエデの紅葉が終わらないうちに山は白銀に染まります。そこに薄日が差す。すると、真っ白な木々の間から、また紅葉が姿を現すのです。この世のものとは思えないような色彩。森の妖精がひそんでいるような世界。これまた、何度もトライして、ようやくとらえた一瞬でしょう。

新雪に包まれた紅葉
撮影した鏡さんは福井県敦賀市の生まれ、66歳。東京でデッサンを学び、各地で商業用の写真や自然の写真を撮り続け、8年前に奥さんの実家がある山形県上山(かみのやま)市に移ってきました。蔵王のふもとの街です。これを機に、蔵王の撮影に本格的に取り組み始めました。「それまでは仕事で撮ってきました。やっと、自分の好きなものを納得がいくまで撮れるようになりました」と鏡さん。それから6年。蔵王に通い続けて撮った写真から選び抜いて、2014年に出版したのがこの写真集です。
温泉街で写真集を見つけてきた友人は「いいものは埋もれていくんだよ」と言います。その通りなのかもしれません。ですが、この世の中には「いいものを埋もれたままにしておいてなるものか」と思う人もいる、と信じたい。
*写真集のタイトルは「Zao can be seen from my room」、3600円
問い合わせは鏡學さんの下記のメールアドレスか電話へ。
メール:kagami-24@ab.auone-net.jp
電 話:023-672-6856
≪写真≫ 鏡學さん提供
*メールマガジン「小白川通信 39」 2016年1月29日
週刊文春が甘利明・経済再生担当相の金銭授受疑惑を報じて1週間。あいまいだった甘利氏の記憶は、弁護士らの助けを借りて急にクリアになったようです。大臣室と選挙区の事務所でそれぞれ50万円受け取ったことを認め、28日に閣僚を辞任しました。「金銭授受疑惑」は「疑惑」の2文字が取れ、金銭授受問題になりました。第1ラウンドは週刊文春の圧勝、と言うべきでしょう。

28日に記者会見し、閣僚を辞任する意向を表明した甘利明・経済再生担当相
甘利氏は記者会見で、自身が受け取った100万円も秘書がもらった500万円もともに政治献金だった、と主張しました。政治資金収支報告書の記載にミスがあったり、500万円のうち300万円を秘書が使い込んだりしたものの、どちらも「政治資金の報告に不手際があった」というわけです。それなら、閣僚は辞任しなければなりませんが、衆議院議員まで辞める必要はない、という理屈になります。これが甘利氏側の防衛ラインのようです。
それで世間は納得するか。週刊文春の報道によれば、くだんの建設会社が甘利氏側に供与した金とサービスは少なくとも1200万円とされています。民間企業はボランティア団体ではありません。利益が見込めないところに資金をつぎ込んだり、グラブやパブで接待したりしません。では、その金と接待にはどんな思惑が込められていたのか。第2ラウンド「金の意味」をめぐる攻防が始まりました。
この建設会社は、千葉県内の道路工事をめぐって都市再生機構(UR)とトラブルになり、URに補償を要求していたといいます。交渉は難航し、建設会社の総務担当者が甘利氏の秘書に助力を頼んだ、というところまでは双方に争いがありません。問題は、そこから先です。秘書が国土交通省の局長に問い合わせ、国交省の支配下にあるURの担当者に話をつないでもらった、というところで収まれば、「甘利氏側の防衛ライン」の内側に収まります。
しかし、もし秘書が安倍政権の重要閣僚である甘利氏の看板をチラつかせ、「国交省とURに圧力をかけた」ということになれば防衛ラインをはみ出し、「あっせん利得処罰法」に抵触します。この法律は2000年に成立、翌2001年に施行された新しい法律で、訴追されて有罪となれば、3年以下の懲役という厳罰が待っています。甘利氏がその経緯を承知していれば、もちろん甘利氏も訴追される可能性があります。犯罪だからです。
29日の毎日新聞社会面に注目すべき記事が掲載されていました。その記事によれば、上記のトラブルは2013年に入って甘利氏の秘書が関わるようになってから急に交渉が進み、まず1600万円の補償がなされ、さらに追加で2億2000万円の補償をすることになった、というのです。地元の建設関係者は「300坪の土地が50万円でも買い手が付かない場所で、2億円以上の補償金を払うなんてどうかしている」と話した、とも報じています。各紙に目を通した範囲では、もっとも核心をついた記事でした。この後に、甘利氏と秘書に金が供与されているからです。
国土交通省と都市再生機構(UR)、建設会社の間でどのような交渉が行われ、甘利氏と秘書がそれにどう関わったのか。また、右翼団体の構成員から建設会社の総務担当に転じ、週刊文春に一部始終を暴露した人物は、どのような理由で告発するに至ったのか。その事実関係と背後関係を一つひとつ解きほぐしていけば、事件の構図はおのずから明らかになっていくでしょう。その過程で「甘利氏側が圧力をかけた」ことが判明すれば、「政治資金収支報告書の記載ミスでした」などという言い訳は通用しなくなります。
法律の専門家の中には「あっせん利得処罰法違反になるのは『その権限に基づいて影響力を行使した場合』に限られる。国交省やURは甘利明・経済再生担当相の職務権限外だから、『権限に基づく影響力』を行使できるわけがない。問題にはならない」と主張する人もいるようです。法律家らしい、もっともらしい論理ですが、政治と利権の実態を無視した形式論でしょう。安倍政権で経済政策の中枢を担ってきた重要閣僚の影響力が国交省やURに及ばない、と考える方がどうかしています。
それにしても、甘利氏が閣僚辞任を表明した28日の記者会見は見応えがありました。矛盾を鋭く追及する記者あり、甘利氏に露骨にすり寄るような質問をする記者あり。気高い志を持った記者と心根の卑しい記者を、高性能のリトマス試験紙をかざしたように炙り出してくれました。もちろん、日本は自由な国です。権力べったりの新聞やテレビがあっても構いません。それも「言論の自由」のうちです。ですが、報道機関で働く者として、それで虚しくはないのか。自分で自分が惨めにならないのか。
記事を読み、映像を見つめ、ネットで情報を追っている人の多くは「メディアで働く人たちのプロとしての気概を見たい」と思っているのではないか。固唾をのんで「第2ラウンド」「第3ラウンド」の展開を見守っているのではないか。
(長岡 昇)
≪写真のSource≫ 東京新聞の公式サイトから
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201601/CK2016012902000139.html
*メールマガジン「小白川通信 38」 2016年1月22日
同じニュース媒体でも、新聞とネットには大きな違いがあります。その一つがニュースの価値判断です。ネットのニュースサイトは一般に見出しを同じ大きさの文字で並べるだけです。価値判断は掲載の順番で示す程度、と言っていいでしょう。
これに対して、新聞ははるかに明確にそれぞれのニュースの価値を判断して読者に提示します。その日、もっとも重要だと判断したニュースは1面で大きな見出しとともに扱い、重要度が低いと考えるニュースは順次、奥の面に掲載していく、というのが大原則です。

ニュースの価値判断に関して、新聞編集者の間にはもう一つ、重要な原則があります。それは「第一報を小さな扱いにしたのに続報で大きな扱いをするのは編集者の敗北だ」というものです。これが残酷なまでに示されたのは、1986年に旧ソ連でチェルノブイリ原発事故が起きた時でした。歴史的とも言える大事故でしたが、ソ連は当初、完全に沈黙し、第一報はスウェーデン政府による「異常な放射能を検知した。重大な事故があったと思われる」という、きわめて曖昧な情報でした。新聞各紙の第一報の扱いは、1面トップから社会面の4段見出しまでバラバラでした。どの扱いが適切だったかは言うまでもありません。
今回、週刊文春(1月28日号)が報じた「甘利明・経済再生担当相の口利き現金授受疑惑」についても、各新聞社の価値判断能力が問われました。21日付の朝日新聞は3面トップ、毎日新聞は社会面4段と、それぞれ腰の引けた扱いでした。週刊誌の報道を基にして1面トップの紙面を作るわけにはいかない、という古臭い沽券(こけん)にしがみついた結果でしょう。読売新聞は第2社会面で2段、政治面の補足記事が3段の扱い。この新聞は「権力を監視する」というメディアの重要な役割にあまり関心がないようですから、順当な扱いなのかもしれません(いずれも山形県で配布された各紙の扱い)。
「一番まともだ」と感じたのは、地元の山形新聞でした。共同通信の配信と思われる記事「『甘利氏に1200万円提供』週刊文春報道」を1面トップで扱い、4面で週刊文春の報道内容も詳しく伝えました。翌22日も1面トップで「甘利氏『記憶あいまい』」と、ポイントを的確に押さえた続報を載せました。朝日は「甘利氏 与党から進退論」というピンボケの続報が1面トップ、毎日も1面3段。どちらも「新聞編集者としての敗北」を紙面に刻む結果になりました。
20日の記者会見での甘利氏の発言「まだ週刊誌の現物を読んでいない」には、思わず笑ってしまいました。木曜日発売の週刊誌の場合、水曜日(20日)にはゲラ刷りが永田町周辺や新聞各社に出回ります。甘利氏もゲラ刷りのコピーを一字一句、食い入るように読んだはずです。が、そんなことは言いたくない。で、「(ゲラではなく)週刊誌の現物は読んでいない」と、嘘とは言えない表現で急場をしのいだものと思われます。
記者会見の前に、すでに弁護士との打ち合わせも十分にしているはずです。今回の現金授受はストレートに贈収賄事件になる可能性があるからです。贈収賄事件で弁護団がまず考える防壁は(1)現金の授受そのものを否定する(2)金を受け取ったとしても、受け取った側(甘利氏側)に職務権限がないと主張する、の二つでしょう。金を渡した側は週刊文春に実名で登場しており、手許に動かぬ証拠がたくさんあるようです。「(1)では勝ち目はない」と踏んで、逃げ込んだのが「記憶があいまい」という言葉なのでしょう。田中角栄元首相が逮捕されたロッキード疑獄で政商の小佐野賢治氏が多用した「記憶にございません」を思い出します。
記憶にあるかどうか。これを本人以外の人間が立証するのは不可能です。第一の防壁「金銭の授受」についてはこの言葉で時間をかせぎ、第二の防壁「職務権限」のところで勝負する――それが弁護団の方針と思われます。金をもらった建設会社のために、補償をめぐってもめている都市再生機構(UR)に口を利いてあげたのは確かだが、それは経済再生担当大臣の職務権限には含まれない。権限外だが、親切心で手を差し伸べてあげたのだ、と立証すればいいわけです。
その点はどうなのか。それを検察や警察に取材し、実務に詳しい専門家にも当たってギリギリと詰め、読者にきちんと提供するのがメディアの仕事ですが、この数日の報道を見ていると、第二の防壁の取材でも新聞各社は週刊文春の後塵を拝することになりそうです。
最近の週刊文春の政治腐敗追及には、目をみはるものがあります。去年の12月上旬に表面化した「就学支援金の詐取事件」は、三重県の高校が舞台なのに東京地検特捜部が家宅捜索に乗り出した、というものでした。事件に関心がある人なら「政治家が絡んでいる」とピンと来るはずです。大物政治家が絡むようだと、地元の三重県警や三重地検では手に負えません。だから東京地検が乗り出した、と考えるのが自然だからです。「どういう続報が出てくるか」と注目していましたが、当方の関心に応える記事を掲載した新聞を見つけることはできませんでした。
これに対し、週刊文春は2015年12月24日号に「特捜部が狙う"詐欺"学校と下村前文科大臣との『点と線』」と題する記事を載せ、事件の背景を伝えました。就学支援金をだまし取ったのは株式会社が運営する「ウィッツ青山学園高校」という学校ですが、この高校の創設者は森本一(はじめ)という人物で、彼は下村博文・前文部科学相の全国後援会の会長だ、と報じたのです。何のことはない。塾経営者の森本氏が同じく塾経営の経歴を持つ下村氏を応援し、三重県に教育特区を作る手助けをしてもらって株式会社運営の高校を創立し、それが税金の詐取という事態を招いた、という構図が浮かんでくるのです。
これまた、限りなく「贈収賄」に近い構図で、強烈な腐臭が漂ってくる事件です。にもかかわらず、主要な新聞はこの事件の背後にどういう風景が広がっているのか書こうとしない。あまり先走ったことを書くと、東京地検から「捜査妨害だ」と怒られるからでしょう。検察という盾の後ろからチビチビと矢を放つような続報しか書かない。だから、事件の構図もその重大さも新聞報道からは伝わってこないのです。
私は元新聞記者です。正直に言えば、古巣の新聞と仲の良くない週刊文春の報道を褒めるようなことはしたくありません。ですが、最近の報道については「実に果敢な、勇気ある報道だ」と認めざるを得ません。
イギリスの政治家で歴史家のジョン・アクトンは「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する」という言葉を残しました。それは時代をも空間をも越える金言と言っていいでしょう。だからこそ、権力を監視し、追及する報道の役割は重要なのです。その仕事は、たとえ報い少ないものであっても一生を賭けるに値する、と思うのです。もっと鋭く、そしてもっと深く、権力を笠に着て税金を食い物にするような輩の所業を暴き出してほしい。
≪写真説明とSource≫
週刊文春の報道を受けて記者会見する甘利明・経済再生担当相(東京新聞の公式サイト)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016012102000136.html
*メールマガジン「小白川通信 37」 2016年1月17日
東京から山形に戻って農村で暮らすようになってから、私のライフスタイルは大きく変わりました。大きな変化の一つが移動手段です。私の住んでいる朝日町には鉄道がありませんので、もっぱら車で移動しています。そのため、自然と運転しながらラジオを聞く機会が増えました。聞いてみると、ラジオはかなり面白い。
NHKラジオ第1で昨日(1月16日)の朝、ラジオアドベンチャーという番組の再放送を流していました。進行役は壇蜜、ゲストは写真家の佐藤健寿(けんじ)さん。テーマは「きかいいさん」というので、「機械遺産」のことかと思ったら、さにあらず。「奇界遺産」のことでした。初めて耳にしました。紹介された「シュバルの理想宮」の内容を聞いて、また驚きました。世の中には、こんな不思議な人生、こんな奇妙な創造物もあるのだと。

フランス南部オートリーブにある「シュバルの理想宮」
シュバルは1836年、フランス南部の小さな村で、貧しい農民の子として生まれました。日本で言えば、江戸時代後期の天保年間です。仕事は村の郵便配達夫。車はもちろん、自転車もありませんでしたので、テクテク歩いて配っていたのだそうです。そんなある日、奇しくも43歳の誕生日に、小さな石につまずきます。ソロバンの玉を重ねたような奇妙な石。それがすべての始まりでした。
何かが彼の心の琴線に触れたのでしょう。その日から、シュバルは路傍の石を拾い、石材を調達して自分の宮殿を造り始めたのです。石工として働いた経験も、建築や美術の心得もなかったそうです。デザインは、配達するハガキに印刷された建造物などを参考にしたと伝えられています。村人の目には「見たこともない、薄気味の悪いもの」と映ったのでしょう。変人扱いされて、あまり人が近寄って来なくなったとか。
けれども、彼は気にすることなく、「理想宮」と名付けて、自分の宮殿を造り続けました。カンボジアのアンコール・ワットのようでもあり、ヨーロッパのゴシック様式の教会のようでもあり。西洋と東洋の文化が溶け合った、実にユニークな建造物です。完成したのは着手してから33年後、76歳の時でした。変人扱いされたまま、1924年に88歳で亡くなりました。
シュバルの理想宮は振り向かれることもなく、時が流れていきました。そして、ずいぶん経ってから、シュールレアリスムを提唱した詩人アンドレ・ブルトンの目にとまり、彼がこの建造物を称賛する詩を発表したことから評価がガラリと変わりました。いろいろな人が足を運ぶようになり、1969年にはついにフランス政府から重要な歴史的建造物に指定されるに至りました。今では世界中から観光客がやって来るようになり、ここでコンサートや個展も開かれています。村にとっては「最大の資産」です。
シュバルが残した言葉がまたいい。
「私は、人間の意志が何を成しうるかを示したかった」
彼が残した、もっとも大切なことは「信じて生きる」ということなのかもしれません。
≪参考サイト≫
◎「シュバルの理想郷」の公式サイト(英語)
◎日本語版ウィキペディア「シュヴァルの理想宮」
≪写真のSource≫
http://lai-lai.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_1d0e.html
≪参考文献・写真集≫
◎『奇界遺産』(佐藤健寿、エクスナレッジ)
◎『郵便配達夫シュヴァルの理想宮』(岡谷公二、河出文庫)
*メールマガジン「小白川通信 36」 2016年1月11日
世の中の「常識」の中には、当てにならない常識もあります。文部省唱歌の『雪』で「犬は喜び庭かけ回り 猫は炬燵(こたつ)で丸くなる」と歌われていることもあってか、「猫は寒がり、犬は雪が大好き」のように思われています。かく言う私も、漫然と「そんなもんだろう」と思っていました。ところが、現実はまるで異なるようです。

子猫のマロ(生後5カ月)
山形の山村にある実家では、母親がずっと一人暮らしをしていました。私は7年前に山形に戻り、団地から通って母親の世話をしてきたのですが、去年、90歳で他界したため、空き家になった実家に引っ越して暮らし始めました。実家には以前から、お腹をすかした野良猫が食べ物を求めて出入りしていたのですが、引っ越しを機に、日当たりのいい小部屋を「猫部屋」に改装して「出入り自由」にしてみました。食べ物も与えています。
たっぷりと栄養を摂れるようになったからか、メス猫とその娘が去年、それぞれ2匹と3匹の子を出産しました。5匹の子猫にとっては、この冬が初めての冬。雪の朝、どうするか観察していたら、興味津々、雪の降り積もった庭をかけ回っています。同じ時期に生まれた子猫でも、庭に出ることなく、室内でうずくまっている猫もいます。臆病で神経質な性格の猫です。要は、好奇心が強く行動的な猫は、初めて目にするものが大好きで、転げ回らないではいられない、ということのようです。
疑い深く、「信じられない」とお思いの方のために、庭をかけ回る子猫の動画をユーチューブにアップしました。シベリアの雪原を行く虎のような(大げさですが)身のこなしも見せています。カラー文字のところをクリックしてご確認ください。
雪の朝。猫も喜び庭かけ回る
庭を走り回っている三毛猫とシャムネコ風の猫は、どちらも去年8月の生まれ、生後5カ月。画面をチラリと横切る黒白まだらの猫は5月生まれで生後8カ月。いずれも生粋の野良猫です。世間には「夏猫は飼うな」という言い伝えがあるとか。寒さに弱いからのようですが、わが家に出入りしている子猫たちは、そんな言い伝えも吹き飛ばす元気さです。時折、どこかに出張って行っては子ネズミを捕まえて持ち帰り、ムシャムシャと食べています。この3匹を含め5匹の子猫のうち4匹がメス猫なので、「これ以上増えたらどうしよう。避妊手術を施すしかないか」というのが目下の悩みです。
同じ野良猫でも、親猫は雪の庭をかけ回ったりはしません。厳しい冬を乗り切るために為すべきことを黙々と為す、という風情です。人間も猫も、無邪気に転げ回っていられるのは子どもの時だけ、ということでしょうか。
ネットで調べてみると、「寒がりでなかなか外に出ようとしない犬」も珍しくないようです。「うちの犬は雪が降っても外に出ようとしません。大丈夫でしょうか」と悩み事相談のような投稿もありました。「人生いろいろ」と言いますが、猫もいろいろ、犬もいろいろ。どんな生き物にもそれぞれに個性があり、一概には言えないということでしょう。作詞、作曲とも不詳の童謡『雪』はとても味わい深い歌ですが、猫と犬にとっては「異議ありの歌」と言えそうです。
(長岡 昇)
≪注≫
三毛猫は「八重(やえ)」、シャムネコ風の猫は「マロ」、黒白まだらの猫は「オペラ」という名前で呼んでいます。命名の理由は省略。
≪参考サイト≫
「snow cat play」で検索したら、雪と戯れる猫の動画がたくさんありました。カラー文字のところをクリックしてみてください。
Elaine burrows in snow (イレインの雪掘り)
Cute Cats playing in the snow (雪と戯れるかわいい猫ちゃん)
Funny Cats Playing in the Snow First Time Compilation 2015 (雪と戯れる愉快な猫たち<2015年初編纂>)
≪写真≫
撮影・長岡遼子、2016年1月4日
*メールマガジン「小白川通信 35」 2015年12月26日
天皇陛下は今年の82歳の誕生日に先立って皇居で記者会見し、口永良部島の噴火や鬼怒川の洪水、大村智・梶田隆章両氏のノーベル賞受賞に触れた後、戦時中に徴用された船員の犠牲者について次のように述べました。
「将来は外国航路の船員になることも夢見た人々が、民間の船を徴用して軍人や軍用物資などをのせる輸送船の船員として働き、敵の攻撃によって命を失いました」「制空権がなく、輸送船を守るべき軍艦などもない状況下でも、輸送業務に携わらなければならなかった船員の気持ちを本当に痛ましく思います」
日本殉職船員顕彰会によれば、徴用された船員の死亡率は43%で、陸軍の20%や海軍の16%を上回ります。民間人である船員の方が軍人よりも死亡率がはるかに高い。何という戦争であったことか。船員の犠牲者への言及がこうした事情を踏まえたものであることは言うまでもありません。
会見の結びは、今年4月のパラオ共和国訪問についてでした。パラオには日本軍守備隊と米海兵隊が死闘を繰り広げたペリリュー島があります。ペリリューの戦いは硫黄島での戦闘の前哨戦とされ、双方の死傷者の多さに加えて、戦闘のあまりの凄惨さに数千人の米軍兵士が精神に異常をきたしたことで知られています。結びの言葉はこうでした。
「パラオ共和国は珊瑚礁に囲まれた美しい島々からなっています。しかし、この海には無数の不発弾が沈んでおり、今日、技術を持った元海上自衛隊員がその処理に従事しています。危険を伴う作業であり、この海が安全になるまでには、まだ大変な時間のかかることと知りました。先の戦争が、島々に住む人々に大きな負担をかけるようになってしまったことを忘れてはならないと思います」「この1年を振り返ると、様々な面で先の戦争のことを考えて過ごした1年だったように思います」

ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官
70年たっても、「国民統合の象徴」として深く思いを巡らさないではいられない戦争。しかも、公的には「先の戦争」などという曖昧模糊とした言葉でしか語れない戦争。私たちの国は、300万人を超える同胞が命を落とした戦争について、その呼称すらいまだに定められない国なのです。
新聞や教科書では「太平洋戦争」という呼称が定着していますが、この呼び方が戦争の実相にそぐわないものであり、研究者たちの間で論争が続いていることは今年6月12日に配信した「小白川通信27」で指摘しました。この呼称は、戦後、日本を占領したGHQ(連合国軍総司令部)が「大東亜戦争」と呼ぶことを禁じた際に代案として、いわば一時しのぎの呼称として出してきたものです。太平洋を主戦場として戦った「米軍」にとってはピタッとくる表現だったのでしょうが、中国大陸やインド洋でも戦った日本にとっても、英国やオランダにとってもふさわしくない呼称です(米国政府すら、当時は「太平洋戦争」と表現しておらず、公式には第2次世界大戦の一部として「対日戦争」と称していたとみられます。調査中です)。
占領後、GHQは日本の新聞社や出版社を直接統制下に置き、真珠湾攻撃の4周年にあたる1945年(昭和20年)12月8日を期して、全国の新聞に「太平洋戦争史」という長大な連載記事を載せるよう命じました。物資不足で印刷用紙も配給制の時代。この連載を掲載させるために、GHQは新聞各社に印刷用紙を特配しています。全国紙も地方紙も、通常なら2ページ立ての紙面をこの日は4ページ立てにし、紙面の半分を使って連載の前半を一挙に掲載しました。毎日新聞と朝日新聞、山形新聞に目を通した限りでは、残りは12月9日から17日までGHQ提供の章立てに沿って掲載しています。連載記事の冒頭部分は次の通りです(漢字は旧字体を新字体に、仮名遣いも現代風に改めました)。
「日本の軍国主義者が国民に対して犯した罪は枚挙に暇がないほどであるが、そのうち幾分かは既に公表されているものの、その多くは未だ白日の下に曝されておらず、時のたつに従って次々に動かすことの出来ぬような明瞭な資料によって発表されて行くことになろう。これによって初めて日本の戦争犯罪史は検閲の鋏を受けることもなく、また戦争犯罪者達に気兼ねすることもなく詳細に且つ完全に暴露されるであろう。これらの戦争犯罪の主なものは軍国主義者の権力濫用、国民の自由剥奪、捕虜及び非戦闘員に対する国際慣習を無視した政府並びに軍部の非道なる取り扱い等であるが、これらのうち何といっても彼らの非道なる行為で最も重大な結果をもたらしたものは『真実の隠蔽』であろう」
この文章からうかがえるように、連載では日本軍による捕虜虐待など戦争犯罪を暴露することに力を注いでいますが、それに留まらず、1931年の満州事変から1945年の米戦艦ミズーリ上での降伏文書調印まで、データをちりばめながら戦争の経緯を詳細に叙述しています。大本営発表しか知らなかった国民にとっては衝撃的な記事であり、ある程度内情を知っていた報道関係者にとっても驚くべき内容でした。
執筆したのはマッカーサー司令部の下にあった戦史室のスタッフ、陣容は歴史学者や米軍幹部ら約100人とされています。英文の記事を共同通信が翻訳して新聞各社に配信しました。戦史室の責任者は「小白川通信15(2014年7月18日)」でも紹介したメリーランド大学のゴードン・プランゲ教授です(当時はGHQの文官)。歴史学者が統率しただけあって、その内容は後の研究者の検証にも堪え得るものでした。
例えば、1937年の日本軍による南京虐殺事件について。この事件の記録をユネスコの記憶遺産に登録申請した中国政府は、犠牲者を30万人以上と主張して研究者たちをあきれさせていますが、GHQのこの連載では「証人達の述ぶるところによれば、このとき実に2万人からの男女、子供達が殺戮されたことが確証されている」と記されています。南京事件については、長い研究の末に「犠牲者は数万人規模」という見方に収斂しつつあり、70年前に書かれたこの記事の質の高さを示しています。
日本軍の戦死者212万人(1964年の厚生省調査)のうち、地域別では最も多い49万人もの犠牲者を出したフィリピンでの戦闘についても、実にバランス良く、正確に書いています。この戦いで日本軍は情勢を十分に把握できないまま敗北を重ね、将兵の多くを餓死や病死に追いやる結果になりました。GHQの記事は「9ヶ月間の戦闘において日本軍の損害は42万6070、捕虜1758及び莫大なる鹵獲(ろかく)品を得た」と実態に極めて近い叙述をしているのです。
内容が正確で衝撃的だったうえに新聞各紙が一斉にこの連載記事を載せたこともあって、戦後、「太平洋戦争」という呼称は日本国内に広まり、定着していきました。出版社も一部を除いて「太平洋戦争」を使い続けています。一方、政府は「大東亜戦争」という呼称を禁じられてからは、法律や公文書で「先の戦争」あるいは「今次の大戦」などと表現するようになり、今日に至っています。
「太平洋戦争」という呼称の生い立ちを知り、政府の対応に批判的な論客の中には「戦争中に使った大東亜戦争がもっともふさわしい呼び方だ」と主張する人もいます。しかし、大東亜共栄圏という侵略のバックボーンになった言葉を冠した呼称は、アジア諸国だけでなく国際社会でも到底受け入れられないでしょう。地理的概念としても、太平洋では狭すぎるのと同じく、大東亜でも戦争全体をカバーしきれません。現状では、妥協案として編み出された「アジア太平洋戦争」という呼称を使うしかない、というのが私の立場です。
歴史研究者の間では、この呼称がかなり使われるようになってきましたが、「太平洋戦争」という呼び方を広める役割を果たした新聞は当然のように同じ呼称を使い続けています。当時は占領下で拒絶する余地などなかったという事情があるにせよ、70年間もそのまま使い続けていていいのか。中学や高校の歴史教科書の出版社の多くが「太平洋戦争」という表現を変えないのも、新聞各社の動向と無縁ではないでしょう。日本のメディアと出版社は、いまだにGHQの呪縛から抜け出せないでいる、と言うしかありません。
あの戦争からどのような教訓を汲み出し、それを未来にどう活かしていくのか。真摯に考えるなら、漫然と「太平洋戦争」などと書き続けることはできないのではないか。新聞記者として自らも漫然と書いてきた者の一人として、自戒しつつそう思うのです。
(長岡 昇)
*「太平洋戦争」という呼称についてはさらに調べて、続編を書く予定です。
≪参考文献・資料≫
・『太平洋戦争史』(高山書院、1946年刊=GHQ提供の新聞連載記事をまとめたもの)
・1945年12月の毎日新聞、朝日新聞、山形新聞
≪参考サイト≫
・天皇誕生日の記者会見全文(宮内庁公式ホームページ)
・日本殉職船員顕彰会のウェブサイト
≪写真のSource≫
ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官
http://wadainotansu.com/wp/1707.html
*メールマガジン「小白川通信 34」 2015年12月11日
長く一緒に暮らしているうちに夫婦は似てくる、と言います。本当にその通りだと思います。毒舌をふるう私と30年余りも暮らしたせいで、かみさんはしばしば、どぎつい表現を口にするようになってしまいました。「こんな女じゃなかったのに」と、不憫に思うこの頃です。
私は6年前に朝日新聞を早期退職して、夫婦で故郷の山形に戻りました(かみさんも山形出身)。同じ頃、新聞社や通信社を定年前に退職して郷里で暮らし始めた記者仲間が何人かいました。転勤生活の末に、ようやく東京で落ち着いた暮らしができるようになったと喜んでいたかみさんは憤懣やるかたなく、「男どもはみんな、ホッチャレか」と毒づきました。ホッチャレは北海道の方言で、生まれ育った川に戻って産卵や放精を終え、ヨレヨレになった鮭のことを言います。「なるほど、うまい例えだなぁ」と思う半面、「ホッチャレはほどなく死んでしまう。俺たちも似たようなものと言うのか」と、いささかムッとした覚えがあります。

馬毛島で草をはむニホンジカの固有亜種「マゲシカ」。遠景は種子島
私の「ホッチャレ仲間」に、鹿児島県・種子島出身の八板俊輔(やいた・しゅんすけ)さんがいます。駆け出し記者時代、初任地の静岡で一緒に警察回りをした仲です。彼も朝日新聞を早期退職して、生まれ故郷の種子島に戻りました。種子島は鉄砲伝来の地として有名ですが、伝来した鉄砲の複製を試みた刀鍛冶、八板金兵衛とも遠くつながる家系とか。その縁もあって、鉄砲伝来から450年になる1993年にはポルトガルに出張して特集記事を書いています。
故郷・種子島への思いは深く、その西に浮かぶ小さな島、馬毛島(まげしま)にも忘れがたいものがあったのでしょう。このたび、この小島のことをうたった短歌や写真、島の歴史を織り込んだ著書『馬毛島漂流』(石風社)を出版しました。江戸時代、種子島が飢饉に襲われるたびに、人々の命を救ったのは馬毛島に自生するソテツの実だったといいます。島で暮らすのは、トビウオ漁などをする一握りの漁民だけ。戦後は復員対策も兼ねて開拓農民が入植した時期もあったようですが、経済成長期に入ると、大規模レジャー施設計画や石油備蓄基地構想が持ち上がって土地が買収され、住民はいなくなってしまいました。
しかし、レジャー施設計画や石油備蓄構想はいずれも頓挫。その後も、自衛隊のレーダー基地や使用済み核燃料の貯蔵施設計画、米空母艦載機の離着陸訓練の候補地といった話が次々に浮上したものの、いずれも実を結ぶことはありませんでした。中央の政治と経済に振り回され、漂い続けて今日に至っています。帰郷した後、八板さんはこの島に何度も足を運び、打ち捨てられた島への思いを綴り、その風景を詠んできました。
漂流したのは島だけではありません。最後には八板さん自身も海を漂います。種子島から小船に乗り、沖合からカヤックを漕いで馬毛島に上陸したものの、携帯電話をなくして迎えの船を頼むことができなくなりました。食料も水もほぼ尽き、カヤックを漕いで自力で戻るしかない状況。強い潮に流されながら、パドルを漕ぐこと8時間余り。体力が尽きる寸前にようやく種子島の海岸に辿り着きました。最後の章でその顚末をルポ風に書いていますが、大学ボード部での経験がなければ遭難していただろう、と思わせる内容です。

馬毛島に自生するソテツ。飢饉の時、種子島の人たちの命を救った
短歌も島の写真も、遭難寸前の漂流記もそれぞれ印象的ですが、私がもっとも惹かれたのは「7300年前の大噴火の話」でした。この本では、九州薩摩半島の南で起きた大噴火は「東西22キロ、南北19キロの巨大なカルデラを残しました」(p121)とサラリと触れているだけですが、私はこの噴火のことを調べずにはいられなくなりました。大学の講義で「縄文時代の遺跡と人口」を取り上げ、「縄文時代の遺跡が北海道と東北に多く、人口も東日本が圧倒的に多いと推定されているのはなぜか」という問題に触れたことがあったからです。
その理由については、縄文時代には北海道と東北の方が食糧を手に入れやすく、冬を越すのに適した環境だったから、という見方が有力のようです。北方には栗やクルミ、栃の木など貯蔵に適した木の実を付ける落葉広葉樹が多く、秋には鮭、春にはサクラマスが大量に遡上して来るので飢えをしのぐことができた、というわけです。ただ、異論もあり、その一つが「西日本で巨大噴火があったために生活できなくなり、遺跡の多くも埋もれてしまった」という説です。講義では「異論の一つ」として紹介しただけでしたが、もっと詳しく調べざるを得なくなりました。
巨大噴火と言えば、インドネシアのジャワ島とスマトラ島の間にあるクラカトア火山の大噴火がよく知られています(地元の発音はクラカタウ)。1883年(明治16年)に山体が吹き飛ぶ大爆発を起こし、海に崩れ落ちた山が大津波を引き起こして3万人以上が亡くなった、とされる噴火です。被害は東南アジアに留まりませんでした。天高く舞い上がった火山灰や微粒子は太陽光を遮り、北半球全体の気温を引き下げたとされています。この大噴火を叙事詩のように描いたのが英国の作家サイモン・ウィンチェスターの名著『クラカトアの大噴火』(早川書房)です。読むと恐ろしくなる本です。
ところが、火山学や地質学の知見を基にした噴火についての本を読むと、過去にはクラカトアの大噴火をはるかにしのぐ超巨大噴火が何度も起きており、日本は「そのリスクが極めて高い国の一つ」であることが分かります。九州だけでも、種子島と馬毛島の西にある「鬼界(きかい)カルデラ」(これが7300年前に噴火した)、薩摩半島と大隅半島にまたがる「阿多(あた)カルデラ」、桜島から霧島にかけての「姶良(あいら)カルデラ」、その北に「加久藤(かくとう)カルデラ」、「阿蘇カルデラ」と連なっています。それぞれ、大昔に超巨大噴火を起こしており、その噴火エネルギーは東日本大震災を引き起こした地震のエネルギーをはるかに上回る、とされています。
問題は「それがいつ起きるか」です。数万年あるいは数十万年に一度であれば、それほど心配する必要はないのかもしれません。が、46億年という地球の歴史から見れば、数万年も数十万年も「刹那のようなもの」であり、私たちなど「刹那の刹那を生きているだけ」なのかもしれません。明日も1万年後も「刹那のうち」だとすれば、「いつ起きてもおかしくない」と言うこともできます。
そういう前提に立って書かれた小説が『死都日本』(石黒耀、講談社)です。九州南部で超巨大噴火(破局噴火)が起きて、日本という国家そのものが破滅してしまう物語で、2002年に発売されてベストセラーになりました。この小説では、火山学者が前兆現象を捉え、政府は的確な危機管理をし、九州電力は噴火の前に川内原発から核燃料を取り出す措置を取ります。ですが、その9年後に起きた大震災で、私たちは地震学者が何の警告も発することができず、政府の危機管理もお粗末極まりなく、東京電力も炉心溶融を防ぐことができなかったことを知りました。
あの大震災のエネルギーをはるかにしのぐような大噴火が起きた時、この国は、そしてこの星はどうなるのか。私たちにできるのは、ただ祈ることだけなのかもしれません。
(長岡 昇)
≪参考文献≫
・『馬毛島漂流』(八板俊輔、石風社)
・『クラカトアの大噴火』(サイモン・ウィンチェスター、早川書房)
・『歴史を変えた火山噴火』(石弘之、刀水書房)
・『死都日本』(石黒耀、講談社)
*写真はいずれも八板俊輔さん撮影
*メールマガジン「小白川通信 33」 2015年11月8日
それは新聞記者になって4年目のことでした。1981年の晩秋から冬にかけて、横浜市内の警察を担当していた私は、いつものように横浜水上警察署の発表資料に目を通していました。「川に男性の水死体」との資料。「またか」と思いました。そのころは、毎月のように港や水路に男の水死体が浮かび、発見されていたのです。
当時の取材ノート(1981年11月10日?)に、次のようなメモ書きがありました。
発見日時:11月25日午前6時48分
場 所:横浜市中区吉浜町の中村川水門付近
発見者:横浜市中区の船員(42)
事 案:身元不明の男の水死体。年齢、推定で50歳前後。頭髪はスポーツ刈り。
茶色のチャック付きジャンパー、茶色のズボン、ゴムの半長靴。
所持金なし。外傷なし。ズボンの前チャックがはずれている。
発見状況:船の甲板で作業をしていた船員が岸壁と船の間に浮いている死体を発見
死 因:溺死とみられる。酔っていた模様
死亡推定:25日午前5時ごろ

横浜のドヤ街・寿町。30年前に比べると、ずいぶんこぎれいになった
殺人や強盗が相次ぐ横浜では、ベタ記事にもならない事件でした。実際、記事にすることもなく、取材ノートにはすぐに別の事件のメモが走り書きしてありました。記憶の底にうずもれていく小さな事件の一つでした。ただ、かすかに引っかかるものがありました。寒くなって水死体で発見されるのはいつも中年か初老の男性であること、決まってズボンの前チャックが開いており、酒に酔った状態だったことです。けれども、その引っかかりを深く掘り下げる余裕もなく、事件取材に追われて時は過ぎ去っていきました。
「横浜の水死体」のことが記憶の底からよみがえってきたのは、それから10数年後のことでした。外報部で国際ニュースをカバーしていた時期、気晴らしに新宿・歌舞伎町を舞台にしたヤクザと中国人マフィアの抗争を描いた小説を読んでいたら、こんな記述が出てきたのです。
「犯罪を重ねていくと、刑罰はどんどん重くなる。3回目、4回目ともなると、長期刑は避けられない。これをなんとかしようとして、裏社会では『新しい戸籍を手に入れて、犯歴を消す方法』が編み出された。横浜には、東京の山谷や大阪の釜ヶ崎と並ぶドヤ街・寿町(ことぶきちょう)がある。ここで暮らす日雇い労働者の中から、係累が少なく、姿を消しても誰も気にしないような男を探し出す。寒くなったら、夜、酒をしこたま飲ませて、ズボンのチャックを開けて川に突き落とす。酔っ払って小便をしようとして落ちたことにするのだ。むろん、事前に戸籍を調べて犯罪歴がないことを確認しておく。この男になりすませば、重罪を犯しても初犯として扱われる。短い刑期で娑婆に出て来られるのだ」
頭をガツンと殴られたような衝撃を覚えました。小説の一場面として描かれていましたが、「これは事実だ」と直感しました。寒い季節になるたびに、毎月のように発見される酔っ払いの水死体。決まって開いているズボンのチャック。警察が「身元不明の溺死体」として処理し、新聞記事にもならないような事件の裏に、そんなことが隠されていたとは・・。新聞記者として裏社会の一端をのぞいたような気になっていましたが、その闇がどれほど深いのか、初めて目の前に突きつけられた思いでした。
事件取材で同業他社にスクープされて地団駄を踏んだことは数知れませんが、これほど腹の底に響くような「抜かれ」は初めてでした。悔しさは感じませんでした。むしろ、そんなところまで掘り下げて暴き出す作家の力量に畏敬の念すら覚えました。「日々のニュースを追いかけるのに精いっぱいの新聞記者にできることは限られている。その、さらに奥を追いかけている人たちがいるのだ」と感じ入り、これからは「心の引っかかり」を覚えたことにはきっと何かがある、と考えて取材しなければならない、と肝に銘じたのでした。
こんな古い話を思い出したのは、最近読んだ『中国 狂乱の「歓楽街」』(富坂聰、KADOKAWA)に「北京で発見される身元不明の変死体」のことが書かれていたからです。中国では戸籍が都市戸籍と農村戸籍に分かれており、地方に住む者が都市戸籍を得るのは極めて難しい。都会に出稼ぎに行き、売春婦として働く女性のほとんどは身分証を偽造して偽名で働いている。このため、トラブルに巻き込まれて殺される売春婦の多くは「身元不明の変死体」として処理されてしまうのだそうです。こういう事件は「無頭案(ウートウアン)」と呼ばれ、多い時には北京だけで月に20件に達したこともあるというのです。中国社会の深いところで何が起きているのか。それを鋭くえぐり出している本でした。
どの社会も、それぞれ深い闇を抱えています。新聞記者として駐在したインドでは、被差別カーストの人たちが置かれた、すさまじい状況を垣間見ました。戦禍のアフガニスタンで感じた底知れぬ憎悪の連鎖。次に赴任したインドネシアでは、微笑みを浮かべた独裁者、スハルト前大統領の下で、どす黒い犯罪がいかにまかり通っていたかを見聞きしました。新聞記者として伝えられることには限界があると知りつつ、「闇はさらに深い」ということをにじませる記事を書くように努めました。どこまでできたか、自信はありませんが。
それぞれの社会が抱える闇は深く、一人ひとりの人間が抱える闇もまた深い。しみじみ、そう感じます。その闇の深いところに少しずつ光を当てていく。闇の領域をできるだけ小さくしていく――開かれた社会とは、そうした試みをあきらめることなく、コツコツと積み重ねていく社会のことであり、そうした積み重ねの先にこそより開かれた社会がある、と信じたい。
(長岡 昇)
* * *
横浜の水死体の話は、馳星周氏か大沢在昌氏の小説で読んだと記憶しているのですが、いくつかの作品を再読しても見つけることができませんでした。別の人の小説だったのかもしれません。
《参考文献》
▽『不夜城』『鎮魂歌 不夜城?』『長恨歌 不夜城完結編』(馳星周、角川書店)
▽『絆回廊 新宿鮫X』(大沢在昌、光文社)
*写真 2015年12月13日、長岡昇撮影
null
NPO「ブナの森」が主催する第3回最上川縦断カヌー探訪は、2015年7月25日(土)に朝日町雪谷から中山町・長崎大橋までの28キロ、26日(日)は村山市・碁点橋から大石田町まで20キロのコースで開かれました。最上川は、木曜日の激しい雷雨と金曜日の雨で少し増水し、川下りにちょうどいいコンディションでした。1日目は薄曇り、2日目は快晴。2日間の参加者は30人で、2人乗りの艇が6組ありましたので、24艇でのカヌー行でした(2012年の第1回カヌー探訪は24人、2014年の第2回は35人が参加)。
圧縮.jpg)


≪参加者≫ 30人+2匹(チワワ、プードル)
山形県内13人、県外17人(宮城3人、福島3人、埼玉3人、栃木2人、群馬2人、東京2人、青森1人、長野1人)
【2日間で48キロを完漕】 18人(エントリー順)
林 和明(東京都足立区)▽菊地 大二郎(山形市)▽菊地 恵里(同)▽崔 鍾八(山形県朝日町)▽清野 由奈(同)▽塚本 雅俊(群馬県前橋市)▽塚本 弘美(同)▽根本 学(福島県郡山市)▽鶴巻 泰(福島県いわき市)▽斉藤 栄司(山形県尾花沢市)▽中沢 崇(長野市)▽和田 勤(栃木県那須塩原市)▽和田 智枝(同)▽市川 秀(東京都中野区)▽岸 浩(福島市)▽佐竹 久(山形県大江町)▽伊藤 敏史(埼玉県本庄市)▽小野 俊博(山形県大江町)=崔・清野艇にコナン<プードル>同乗
圧縮.jpg)
.jpg)

【2日間で40キロを完漕】 1人(2日目の昼、村山市・隼の瀬まで)
高田 徹(青森県八戸市)
【1日目、28キロを完漕】 3人
東海林 憲夫(山形県寒河江市)▽小林 悟志(埼玉県川口市)▽小林 忍(同)=小林艇にショコラ<チワワ>同乗
【2日目、20キロを完漕】 8人
細谷 敏行(山形県大江町)▽伊藤 信生(山形県酒田市)▽鈴木 達哉(宮城県柴田町)▽鈴木 未知哉(同)▽池田 丈人(山形県酒田市)▽佐藤 博隆(同)▽三塚 志乃(仙台市太白区)▽渡辺 政幸(山形県大江町)


≪陸上サポートスタッフ≫
安藤 昭雄▽佐久間 淳▽白田 金之助▽鈴木 賢一▽鈴木 智▽長岡 昇▽長岡 典己▽長岡 佳子▽山口 義博
≪出発、通過、到着時刻≫
1日目(7月25日)
10:00 朝日町の雪谷カヌー公園を出発(予定を30分繰り上げ)
10:20 八天の瀬を通過、2艇が沈
10:50 八天橋を通過
11:20 朝日町の川通に到着、根本・鶴巻艇の水漏れを修理
11:30 川通を出発
11:50 最大の難所、タンの瀬を通過
12:20 大江町用(よう)の用橋を通過
13:25?14:30 大江町「おしんの筏下りロケ地」で昼食、休憩
16:10 中山町の長崎大橋に到着
村山市・碁点橋のたもとにカヌーを置き、大石田町に移動
18:30 大石田町・東町公民館での歓迎ビアガーデンに参加(18人)

圧縮.jpg)

2日目(7月26日)
8:30 大石田河岸から車で出発、2日目の出発地点、碁点橋へ
9:15 村山市・碁点橋から出発
9:30 竜神の吊橋を通過
10:20 大淀を通過、陸上サポート要員は真下慶治記念美術館から声援
10:50 三ケ瀬橋を通過
11:10 長島橋を通過
11:30?12:45 村山市の隼の瀬眺望公園で昼食、休憩
13:05 隼橋を通過
14:15 大石田河岸に到着
14:40 閉会式
圧縮.jpg)
圧縮.jpg)
.jpg)
≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県西村山郡朝日町宮宿1115 朝日町公所会館)
email:bunanomori.npo@gmail.com
≪主管≫ 最上川縦断カヌー探訪実行委員会(NPO「ブナの森」、大江カヌー愛好会、山形カヌークラブの3者で構成)


≪後援≫
国土交通省山形河川国道事務所▽山形県▽東北電力(株)山形支店▽朝日町▽大江町▽西川町▽寒河江市▽河北町▽中山町▽村山市▽大石田町▽山形カヌークラブ▽大江カヌー愛好会▽山形県カヌー協会▽美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫
大石田町・東町区長 矢作(やはぎ)善一▽東町公民館長 細矢裕▽東町公民館の皆様
*7月25日夕、東町公民館でのビアガーデンに参加させていただきました
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell保険オフィス
≪写真撮影≫
佐久間淳、長岡昇、長岡典己
≪ウェブサイト、ポスター、Tシャツ制作、横断幕≫
ウェブサイト制作 コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、原田美穂)
ポスター制作 若月印刷(デザイン・高子あゆみ)
Tシャツデザイン 遠藤大輔
横断幕揮毫 成原千枝
【ウェブアルバム、ユーチューブの動画】 カラー文字のところをクリックしてご覧ください
▽塚本雅俊さん撮影のウェブアルバム
▽中沢崇さん撮影のウェブアルバム(三ヶ瀬、隼の瀬の動画もあります)
▽隼の瀬の動画(Youtube 撮影・長岡昇)
圧縮.jpg)
第3回探訪の難所、村山市の隼(はやぶさ)の瀬を行く鶴巻・根本艇

1日目、五百川(いもがわ)峡谷のタンの瀬に入る小林艇(愛犬ショコラ同乗)

カナディアンでタンの瀬を乗り切る中沢艇
≪参加者≫ 30人+2匹(チワワ、プードル)
山形県内13人、県外17人(宮城3人、福島3人、埼玉3人、栃木2人、群馬2人、東京2人、青森1人、長野1人)
【2日間で48キロを完漕】 18人(エントリー順)
林 和明(東京都足立区)▽菊地 大二郎(山形市)▽菊地 恵里(同)▽崔 鍾八(山形県朝日町)▽清野 由奈(同)▽塚本 雅俊(群馬県前橋市)▽塚本 弘美(同)▽根本 学(福島県郡山市)▽鶴巻 泰(福島県いわき市)▽斉藤 栄司(山形県尾花沢市)▽中沢 崇(長野市)▽和田 勤(栃木県那須塩原市)▽和田 智枝(同)▽市川 秀(東京都中野区)▽岸 浩(福島市)▽佐竹 久(山形県大江町)▽伊藤 敏史(埼玉県本庄市)▽小野 俊博(山形県大江町)=崔・清野艇にコナン<プードル>同乗
圧縮.jpg)
.jpg)
開会式を終え、さあ出発(山形県朝日町雪谷で)

崔・清野艇の船頭をつとめた愛犬コナン
【2日間で40キロを完漕】 1人(2日目の昼、村山市・隼の瀬まで)
高田 徹(青森県八戸市)
【1日目、28キロを完漕】 3人
東海林 憲夫(山形県寒河江市)▽小林 悟志(埼玉県川口市)▽小林 忍(同)=小林艇にショコラ<チワワ>同乗
【2日目、20キロを完漕】 8人
細谷 敏行(山形県大江町)▽伊藤 信生(山形県酒田市)▽鈴木 達哉(宮城県柴田町)▽鈴木 未知哉(同)▽池田 丈人(山形県酒田市)▽佐藤 博隆(同)▽三塚 志乃(仙台市太白区)▽渡辺 政幸(山形県大江町)

2日目は碁点橋のたもとからスタート

今年も軽やかなパドルさばきを見せた菊地艇
≪陸上サポートスタッフ≫
安藤 昭雄▽佐久間 淳▽白田 金之助▽鈴木 賢一▽鈴木 智▽長岡 昇▽長岡 典己▽長岡 佳子▽山口 義博
≪出発、通過、到着時刻≫
1日目(7月25日)
10:00 朝日町の雪谷カヌー公園を出発(予定を30分繰り上げ)
10:20 八天の瀬を通過、2艇が沈
10:50 八天橋を通過
11:20 朝日町の川通に到着、根本・鶴巻艇の水漏れを修理
11:30 川通を出発
11:50 最大の難所、タンの瀬を通過
12:20 大江町用(よう)の用橋を通過
13:25?14:30 大江町「おしんの筏下りロケ地」で昼食、休憩
16:10 中山町の長崎大橋に到着
村山市・碁点橋のたもとにカヌーを置き、大石田町に移動
18:30 大石田町・東町公民館での歓迎ビアガーデンに参加(18人)

難所、三ケ瀬(みかのせ)の手前にある大淀で横に広がる
圧縮.jpg)
同じく大淀で

塚本艇に続く三塚・斉藤艇
2日目(7月26日)
8:30 大石田河岸から車で出発、2日目の出発地点、碁点橋へ
9:15 村山市・碁点橋から出発
9:30 竜神の吊橋を通過
10:20 大淀を通過、陸上サポート要員は真下慶治記念美術館から声援
10:50 三ケ瀬橋を通過
11:10 長島橋を通過
11:30?12:45 村山市の隼の瀬眺望公園で昼食、休憩
13:05 隼橋を通過
14:15 大石田河岸に到着
14:40 閉会式
圧縮.jpg)
最大の難所、隼(はやぶさ)の瀬を乗り切る三塚・斉藤艇
圧縮.jpg)
隼の瀬を行く林艇。舳先に取り付けてあるのは大江町をPRする旗
.jpg)
アンカーの佐竹艇も隼の瀬を通過
≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県西村山郡朝日町宮宿1115 朝日町公所会館)
email:bunanomori.npo@gmail.com
≪主管≫ 最上川縦断カヌー探訪実行委員会(NPO「ブナの森」、大江カヌー愛好会、山形カヌークラブの3者で構成)

親子で参加した鈴木艇

大石田河岸に最初にゴールした市川艇
≪後援≫
国土交通省山形河川国道事務所▽山形県▽東北電力(株)山形支店▽朝日町▽大江町▽西川町▽寒河江市▽河北町▽中山町▽村山市▽大石田町▽山形カヌークラブ▽大江カヌー愛好会▽山形県カヌー協会▽美しい山形・最上川フォーラム
≪協力≫
大石田町・東町区長 矢作(やはぎ)善一▽東町公民館長 細矢裕▽東町公民館の皆様
*7月25日夕、東町公民館でのビアガーデンに参加させていただきました
≪輸送と保険≫
マイクロバス・チャーター 朝日観光バス
旅行保険 あいおいニッセイ同和損保、Bell保険オフィス
≪写真撮影≫
佐久間淳、長岡昇、長岡典己
≪ウェブサイト、ポスター、Tシャツ制作、横断幕≫
ウェブサイト制作 コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、原田美穂)
ポスター制作 若月印刷(デザイン・高子あゆみ)
Tシャツデザイン 遠藤大輔
横断幕揮毫 成原千枝
【ウェブアルバム、ユーチューブの動画】 カラー文字のところをクリックしてご覧ください
▽塚本雅俊さん撮影のウェブアルバム
▽中沢崇さん撮影のウェブアルバム(三ヶ瀬、隼の瀬の動画もあります)
▽隼の瀬の動画(Youtube 撮影・長岡昇)
*メールマガジン「小白川通信 32」 2015年8月27日
この夏、マレーシアのマラヤ大学で開かれたサマーキャンプに参加しました。キャンプの趣旨は「欧州とアジアの交流をさらに拡大する」という高邁なもの。ただ、その割には参加者は私を含めて9人と、いささか寂しかったのですが、講師のラインナップは素晴らしく、参加者との会話も刺激的で、とても実り多いキャンプでした。

マレーシアのナジブ・ラザク首相
折しも、マレーシアではナジブ・ラザク首相の蓄財疑惑が発覚し、巷はその話題でもちきりでした。疑惑は、マレーシア政府が100%出資する投資会社「ワン・マレーシア・ディベロップメント(1MDB)」の関連会社や金融機関から、ナジブ首相の個人口座に7億ドル(約840億円)が不正に振り込まれた疑いがある、というもの。この投資会社はナジブ首相の肝いりで設立されたもので、首相兼財務相のナジブ氏はこれを監督する立場にあります。
「個人的に流用したことはない」とナジブ首相は弁明しています。送金は何回かに分けて行われ、2013年5月の総選挙直前に振り込まれた金もあります。このため、「与党の選挙資金ではないか」との憶測や「マレーシア政界の権力闘争がらみ」といった見方が飛び交っています。この問題を最初に報じたのはウォール・ストリート・ジャーナルで、メディアの追及は厳しく、その後、首相の夫人の蓄財疑惑まで報じられました。
サマーキャンプで一緒だったフィリピンの大学院生は「まるで、マルコス大統領とイメルダ夫人みたいだね。イメルダは豪華な靴を宮殿に残して有名になったけど、ナジブ夫人はお金を何につぎ込んだのかな」と興味津々の様子。中国通の学生が「中国の腐敗に比べたら、マレーシアの腐敗なんてかわいいもんだ」と話に割って入りました。
.jpg)
周永康・前政治局常務委員
今年の6月に終身刑が言い渡された中国共産党の前政治局常務委員、周永康は「本人と一族が蓄え、当局に押収された資産は900億元」と報じられました。円に換算すれば1兆円以上です。中国の石油ガス業界のドンで、党中央の序列9位まで上り詰めた人物だけに、蓄財もけた違いです。この学生によれば、数百億円程度の不正蓄財なら「中国にはゴロゴロある」のだそうです。
別の学生は「蓄財より、こっちの方が驚きだ」と切り返しました。スマートフォンで中国メディアの記事を検索しながら、「140人以上もの愛人を囲っていた党幹部がいる。江蘇省建設庁のトップ、徐其耀という男だ。愛人の数では、今のところ彼が一番」と言う。自ら手を付ける。賄賂として女性を差し出させる。徐は権力と金にものをいわせて女漁りにふけりました。2000年10月に逮捕され、翌年、執行猶予2年の死刑判決(事実上の終身刑)を受けています。愛人数ナンバーツーは湖北省天門市の共産党市委員会書記、張二江で、囲った愛人107人。歴史小説『水滸伝』で梁山泊に立てこもった豪傑108人になぞらえ、本妻を含めて108人の女豪傑を相手にした男として「時の人」になったとか。こちらは懲役18年。

江蘇省の幹部、徐其耀
知名度という点で、この2人を上回るのが重慶市の党幹部、雷政富だそうな。雷は賄賂として建設会社から送り込まれた18歳の少女とトラブルになり、彼女がこっそり撮影したビデオをネット上で公開されてしまいました。そのセックスビデオの中で、雷は13秒で果ててしまったため「雷十三」と名付けられ、ビデオの公開から63時間後に失脚したため「雷六三」とも呼ばれて、一躍有名になったのだそうです。判決も懲役13年。
日本で暮らす私たちから見れば、800億円の蓄財も140人の愛人汚職も「けた違いの腐敗」です。そして、共通しているのは、どちらの国でも権力が一つに集中していることです。中国もマレーシアも建前としては権力の分立をうたっていますが、その実態はそれぞれ、中国共産党とマレーシア国民戦線という政党の一党独裁です。権力を握る者の暴走を食い止める仕組みがないか、なきに等しい。だから、腐敗もとめどなく広がり、深まるのです。
中国経済の先行きを懸念して、このところ世界各地で株価が乱高下しています。つい最近まで「中国は世界の工場」とか「世界経済の成長を牽引する中国」とかもてはやしていたのが嘘のようです。腐敗や暴走をチェックし、行き過ぎをコントロールする仕組みがない社会がどうなるのか。私たちはこれから、その危うさを目撃することになるでしょう。
同時に、この混乱すら「大もうけのチャンス」とみなして、欧米や日本のハゲタカファンドは牙を研いでいるはずです。先進国や産油国の「ダブついた金」もまた、歯止めなきゲームの重要なプレーヤーであり、私たちにとっても決して他人事ではありません。世界は漂い、乱れ始めています。
(長岡 昇)
《参考サイト》
▽マレーシア・ナジブ首相の蓄財疑惑(フランスの通信社AFP)
▽徐其耀と張二江のスキャンダル(日経ビジネスONLINE)
▽雷政富のスキャンダル(ニューズウィーク日本語版)
《写真のSource》
▽ナジブ・ラザク首相(2015年7月、AFP)
http://www.afpbb.com/articles/-/3053735?ref=jbpress
▽周永康(2007年10月、ロイター)
http://jp.reuters.com/article/2015/06/11/china-corruption-idJPKBN0OR1B520150611?feedType=RSS&feedName=worldNews
▽徐其耀
http://news.sina.com.cn/c/239519.html
*メールマガジン「小白川通信 31」 2015年8月17日
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の類いでしょうか。戦後70年の節目の夏に安倍晋三首相が発表した談話について、首相の政治信条に批判的な朝日新聞は「いったい何のための、誰のための談話なのか」「この談話は出す必要がなかった。いや、出すべきではなかった」と、いささか感情的とも言える社説を掲げました(8月15日付)。
確かに、安倍首相の談話は「わが国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明してきました」と、歴代政権が反省し、わびてきたことを確認しただけで、自らの言葉で謝罪することはありませんでした。「侵略」という言葉も一回だけ、「事変、侵略、戦争」と並べて使っただけです。まるで「侵略という言葉も入れたよ」と、アリバイを主張するような言及の仕方でした。

21世紀構想懇談会の初会合(2015年2月25日)
あの戦争をどう受けとめるのか。命を落とした、すべての人々に何を語りかけたかったのか。政治家としての真摯さを感じさせるものではありませんでした。ですが、戦後50年の村山談話や戦後60年の小泉談話に比べると、「優れている」と評価できる内容も含まれていました。それは、日中戦争やアジア太平洋戦争を、長い歴史の文脈の中で捉え、語っている点です。
今回の首相談話は、戦争への道を「100年以上前の世界」から説き起こしています。20世紀の初め、アジアや中東、アフリカで「われわれは独立国だ」と胸を張って言える国はほんの一握りしかありませんでした。日本、タイ、ネパール、アフガニスタン、トルコ、エチオピア、リベリアくらいではないでしょうか。ほかの地域は大部分、欧米の植民地あるいは保護領として過酷な収奪にさらされ、列強の縄張り争いの場となっていました。
小国、日本はその中で独立をまっとうしようとして必死に生きたのであり、ロシアとの戦争にかろうじて勝利を収めたのです。1905年の日露戦争の勝利がアジアや中東、アフリカで植民地支配にあえぐ人々に「勇気と希望」を与えたのは、まぎれもない歴史的事実です。その後、日本は時代の流れを見誤り、増長して戦争への道に踏み込んでいきましたが、その戦争は「侵略」という一つの言葉で語り尽くせるような、生易しいものではありません。どういう時代状況の中で日本が戦争に突き進んでいったのか。それは極めて重要なことであり、村山談話でも小泉談話でもきちんと語らなければならないことでした。
97歳の中曽根康弘元首相は毎日新聞への寄稿(8月10日付)で、日本軍が中国や東南アジアで行ったことは「まぎれもない侵略行為である」と認めつつ、「第二次大戦、太平洋戦争、大東亜戦争と呼ばれるものは、複合的で、対米英、対中国、対アジアそれぞれが違った、一面的解釈を許さぬ、複雑な要素を持つ」と記しました。「あの戦争は侵略戦争だったのか、それとも自存自衛の戦争だったのか」といった、一面的な設問と論争はもう終わりにしなければなりません。「侵略や植民地支配、反省とおわび」のキーワードを使ったのかどうか、といった表層的な見方にも終止符を打ちたいのです。そのためには、1930年代と40年代の戦争だけを切り取って語るような狭量さから抜け出さなければならない、と思うのです。
「そうは言っても、歴史的な叙述のところは安倍首相の本音ではないはずだ。首相の私的懇談会(21世紀構想懇談会)の受け売りではないか」とあげつらう向きもあるでしょう。その通りかもしれません。けれども、戦後70年の首相談話のような重要な演説は、だれが下書きを書いたのかとか、だれの助言が反映されたのかといったことを乗り越えて記録され、人々の記憶になっていくのです。時がたてば、読み上げた首相の名前すら忘れ去られ、独り歩きしていく歴史的な文書なのです。
2015年、戦後70年という節目に、日本という社会は先の戦争をどう総括し、未来をどのように切り拓こうとしていたのか。それを物語る記録なのです。その意味で、戦争の意味合いを曖昧にし、謝罪も不十分だったことは残念ですが、あの戦争が一面的な解釈を許さない、苛烈な戦争であったことを長い歴史の文脈の中で語ったことは、後に続く世代のためにも有益なことでした。
そして、追悼の対象を「300万余の日本人戦没者」にとどめるのではなく、戦争で斃れたすべての人々に思いを致さねばならないこと、戦後の日本に温かい手を差し伸べてくれた中国やアジア諸国、戦勝国の人々に感謝する心を忘れてはならないと述べたこと、戦後の平和国家としての歩みを「静かな誇りを抱きながら」貫くと宣言したことも、意義深いことでした。そうした点も評価しなければ、公平とは言えないでしょう。
私には、安倍首相の政治信条は理解できません。首相にふさわしい器とも思いません。けれども、私たちの社会が今、首相として担いでいるのは安倍晋三という政治家であり、それ以外に持ち得なかったのも事実です。戦後70年談話という重要な政治声明も、彼の口を通して語られるしかなかったのです。切ないことですが、それも認めざるを得ません。なのに、その談話を「出すべきではなかった」などとバッサリ切り捨て、そこには何の意味もないかのように論じるのでは、あまりにもさもしい。
非は非として厳しく追及し、認めるべきことは率直に認める。そのうえで、未来を生きるために何をしなければならないのかを論じる。メディアには、政治家の器量を超えて物事を捉え、未来を照らすような、懐の広さと深い洞察力が求められていると思うのです。
首相が談話を読み上げた後の会見のあり方も変えてほしい。記者クラブの幹事が質問し、その後の質問は政権側の司会進行役が指名するような方法をいつまで続けるつもりなのか。朝日、読売、毎日の3大紙とNHKの記者がだれも質問しないような首相会見を視聴者がどう受けとめるかも考えてほしい。誰が質問するかはメディアの側がくじ引きで決める。そのうえで、自由にガンガンと質問する。そういう方法に変えるべく力を尽くすべきではないか。
安倍政権の提灯持ちのようなメディアと、遠吠えのような批判を繰り返すメディア。これも、私たちの社会が戦後70年で辿り着いた現実の一つですが、変えようとする強い意志があれば、変えられる現実ではないか。
(長岡 昇)
≪参考資料≫
▽戦後70年の安倍首相談話(首相官邸公式サイト)
▽20世紀を振り返り21世紀の世界秩序と日本の役割を構想するための有識者懇談会(21世紀構想懇談会)の報告書
≪写真のSource≫
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201502/25_21c_koso.html
*メールマガジン「小白川通信 30」 2015年8月8日
しなければならないことをせず、ほかの人に大きな迷惑をかけたならば、その人は責任を取らなければなりません。これは小学生でも分かる論理です。ところが、この当たり前のことが検察官の間では通用しないようです。原発事故の被災者が東京電力の幹部や政府関係者を告訴・告発したのに、東京地方検察庁は2度にわたって「裁判で刑事責任を問うことはできない」として不起訴処分にしました。
検察の言い分は「あのような大きな津波が発生することを確実に予測することはできなかった。従って、東京電力の備えが不十分だったとは言えない」というものです。確かに、東京電力はそう主張しています。規制官庁の原子力安全・保安院も右へならえです。しかし、本当にそうだったのでしょうか。大津波を予測し、警告した人はいなかったのか。東電と保安院はなすべきことをきちんとしてきたのか。

事故から1年後の福島第一原子力発電所(2012年2月)
福島の原発事故を考える際に、つい見落としてしまいがちなことがあります。それは、2011年3月11日に東北の沖合で巨大地震が発生し、大津波に襲われたのは福島第一原発だけではない、ということです。大津波は宮城県にある女川原発にも福島第二原発にも押し寄せました。なのになぜ、福島第一原発だけがこの悲惨な事故を引き起こしたのか。しかも、福島第一に6基ある原子炉のうち、なぜ1?4号機だけが全電源の喪失、原子炉の制御不能、炉心溶融と放射性物質の大量放出という大惨事を招いてしまったのか。それには、しかるべき理由と原因があるはずです。
その点をとことん突き詰めた本があります。昨年の11月に出版された添田孝史氏の『原発と大津波 警告を葬った人々』(岩波新書)です。添田氏は朝日新聞の科学記者でしたが、2011年5月に退社してこの問題の追及に専念し、本にまとめました。実に優れた報告です。とりわけ、女川原発と福島第一原発の設置時の津波想定を比較している序章が秀逸です。
原発の設置申請は福島第一の1号機が1966年、女川原発の1号機が1971年でした。まだ地震の研究が十分に進んでいない時期で、津波の研究はさらに立ち遅れていました。そうした中で、東京電力が福島第一原発の設置申請をする際に想定した津波は、1960年のチリ地震の津波でした。この時、福島第一原発に近い小名浜港で記録された津波の高さは3.122メートル。これに安全性の余裕を見て5メートルほどの津波を想定し、海面から30メートルあった敷地を10メートルまで削っで原発を建設したのです。当時はこれで十分、と判断したのでしょう。
これに対して、女川原発では明治29年と昭和8年の三陸大津波に加えて、869年の貞観(じょうがん)地震による大津波をも念頭に置いて津波対策を施し、原発の敷地を14.8メートルに設定しました。東電が調べたのはわずか10数年分の津波データ。それに対し、平安時代まで遡って津波を考えた東北電力。その結果が海面からの敷地の高さが10メートルの福島第一と14.8メートルの女川という差となって現れたのです。この4.8メートルの差が決定的でした。
添田氏は、女川原発の建設にあたって、東北電力がなぜそのように慎重に津波の想定をしたのかを詳しく調べています。そのうえで、同社の副社長だった平井弥之助氏の存在が大きかった、と結論づけています。宮城県岩沼市出身の平井氏は、三陸大津波の記録に加えて、地元に伝わる貞観大津波のことを知っていたのです。そして、部下たちに「自然に対する畏れを忘れず、技術者としての結果責任を果たさなければならない」と力説していました。(前掲書p12)。平井氏の思いは部下に伝わり、女川原発を津波から守った、と言うべきでしょう。
東京電力の大甘の津波想定がその後もそのまま通用するはずがありません。地震と津波の研究が進むにつれて、東京電力は「津波対策を強化すべきだ」という圧力にされされ続けます。1993年の北海道南西沖地震では、奥尻島に8メートルを超える津波が押し寄せ、最大遡上高は30メートルに達しました。これを受けて、国土庁や建設省、消防庁など7省庁が「津波防災対策の手引き」をまとめ、「これまでの津波想定にとらわれることなく、想定しうる最大規模の地震津波も検討すべきである」と打ち出しました。
1995年の阪神大震災の後には、政府の地震調査研究本部が「宮城沖や福島沖、茨城沖でも大津波が起きる危険性がある」と警告を発しました。2004年のインド洋大津波の後にも、津波対策を急がなければならないと問題提起した専門家は何人もいたのです。

インド洋大津波でスマトラ島アチェの海岸に打ち上げられたタグボート
それらに、東京電力はどう対処したのか。2008年には社内からも「15メートルを超える津波が押し寄せる可能性がある」という報告が上がってきていたのに、上層部が握りつぶし、ほとんど何の対策も取らなかったのです。それどころか、意のままになる地震学者を動員して、警告を発する専門家や研究者の動きを封じて回った疑いが濃厚です。東電はこの間、度重なる原発の事故隠しスキャンダルで逆風にさらされ、中越地震で損壊した柏崎刈羽原発の補修工事にも追われて赤字に陥り、経営的にも厳しい状況にありました。巨額の費用がかかる津波対策を先送りにせざるを得ない状況に追い込まれていたのですが、そうした事情を割り引いても、許しがたい対応と言わなければなりません。
添田氏は地震の研究者や原子力規制の担当官、電力会社の幹部らに取材して、その経過と実態を白日の下にさらそうとしています。経済産業省や保安院が東電をかばって資料を見せようとしないのに対しては、情報公開制度を駆使して文書を開示させています。彼の本はそのタイトル通り、津波に対する警告を葬った人々に対する弾劾の書です。
日本の検察は「有罪にできる自信がない限り、起訴しない」というのを鉄則にしています。いったん起訴されれば、被告の負担は大きく、たとえ無罪になったとしても取り返しのつかない打撃を受けるおそれがあるからです。それはそれで立派な原則ですが、それを権力を握り(地域独占企業である東京電力は限りなく「権力機関」に近い)、中央省庁を巻き込んで都合の悪いことを隠そうとする組織の幹部にまで同じように適用しようとするから、おかしなことになるのです。
11人の市民からなる東京第五検察審査会が東京地検の不起訴処分を覆して、東電の勝俣恒久・元会長と武黒一郎・元副社長、武藤栄・元副社長の3人を業務上過失致死傷の罪で強制起訴する、と決めたのは極めて健全な判断と言うべきです。検察は「大津波を確実に予測することはできなかった」と主張しているようですが、そもそも数千年、数万年、数十万年というスパンで動く地球の動きを地震学者が「確実に予測する」ことなど、昔からできなかったし、今でもできはしないのです。できることは「自然に対する畏れを忘れず、謙虚に研究を積み重ね、できる限りの対策を施す」ということに尽きます。東北電力はそれを愚直に守り、東京電力は「小さな世界」に閉じこもって姑息な手段を弄し、大自然の鉄槌を浴びる結果を招いたのです。
「小さな世界に閉じこもる」という点では、検察も同じです。日本で現在のような法体系ができたのは明治維新以降で、まだ1世紀半しか経っていません。そういう小さな枠組みで、東日本大震災という未曽有の事態に対処しようとするから、おかしなことになるのです。突き詰めれば、法の淵源は一人ひとりの良心と良識、その総和にほかなりません。そういう大きな枠組みに立ち、未来を見据えて、東電の幹部は司法の場で裁かれるべきかどうか判断すべきでした。有罪か無罪かはその先の問題であり、最終的な判断は裁判所に託すべきだったのです。
検察審査会が東電の旧経営陣3人の強制起訴を決めたことに関する新聞各紙の報道(8月1日付)も興味深いものでした。原発政策の推進を説く読売新聞が冷ややかに報じたのは理解できますが、朝日新聞まで1面に「検察と市民 割れた判断」と題した解説記事を掲載したのには首をかしげざるを得ませんでした。中立的と言えば聞こえはいいのですが、それは検察の言い分をたっぷり盛り込んだ、他人事のような記事でした。
中央省庁や電力会社の人間に取り囲まれ、その言い分に染まり、既得権益の海に沈んだ検察。その検察の取り巻きのようになって、一緒に沈んでいく司法クラブの記者たち。朝日、毎日、読売の3紙を読み比べた範囲では、「予見・回避できた」という検察審査会の主張を1面の大見出しでうたった毎日新聞が一番まともだ、と感じました。「法と正義はどうあるべきか」を決めるのは検察ではありません。三権のひとつ、司法の担い手である裁判所であり、最終的には主権者である私たち、国民です。その意味で、検察審査会のメンバーは立派にその職責を果たした、と言うべきです。
(長岡 昇)
《写真のSource》
▽福島第一原子力発電所(2012年2月)
http://www.imart.co.jp/houshasen-level-jyouhou-old24.3.19.html
▽スマトラ島アチェのタグボート(2005年1月29日、長岡昇撮影)
*メールマガジン「小白川通信 29」 2015年7月31日
また「戦争を語る季節」が巡ってきました。戦後70年の節目とあって、この夏は早くから新聞各紙で「戦争企画」の連載が始まりました。それぞれ、歴史の闇に埋もれてしまいかねないものを掘り起こそうとする意欲を感じ、学ぶところも多いのですが、大学で現代史の講義を担当している立場からは、やはり不満が残ります。あの戦争について、いまだに大きなテーマの一つが取り上げられないままになっている、と感じるからです。
それは、アジア太平洋戦争に動員され、命を落とした日本軍将兵の半数近くが戦闘による死ではなく、食べるものがないために餓死、あるいは栄養失調に陥って病死した、という事実です。私もこの問題については無知でした。ガダルカナル島やインパール作戦、さらにはフィリピンでの戦闘で多くの餓死者が出たことは知っていましたが、それが局所的なことではなく、中国大陸を含め、多くの戦場で起きていたとは知りませんでした。自分で調べ、その実態を詳しく知るにつれて、あまりのひどさに愕然としています。

この問題を正面から扱っているのは、藤原彰(あきら)一橋大学名誉教授の著書『餓死(うえじに)した英霊たち』(青木書店)です。藤原氏は陸軍士官学校を卒業し、中国大陸を転戦した将校です。戦後、大学に入って歴史学者になり、自らの戦場体験を踏まえてこの本を著しました。冒頭、彼はこう記しています。
「戦死よりも戦病死の方が多い。それが一局面の特殊な状況でなく、戦場の全体にわたって発生したことがこの戦争の特徴であり、そこに何よりも日本軍の特質をみることができる。悲惨な死を強いられた若者たちの無念さを思い、大量餓死をもたらした日本軍の責任と特質を明らかにして、そのことを歴史に残したい。死者に代わって告発したい」
ガダルカナルやニューギニアのポートモレスビー、インド北東部のインパールで起きた補給途絶による餓死を詳述した後、藤原氏はフィリピンでの大量餓死を扱っています。フィリピンは、先の戦争で日本軍の将兵が最も多く犠牲になった戦域です(次に多いのは中国本土)。1964年の厚生省援護局の資料によれば、陸海軍の軍人・軍属の死者は約212万1000人(1937年の日中戦争以降の死者。戦後のシベリア抑留による死者も含む)。このうち、49万8600人もの人命がフィリピンで失われているのです(フィリピン政府の発表によれば、戦闘に巻き込まれて亡くなったフィリピン人も100万人を上回ります)。
フィリピン、その中でも酸鼻を極めたレイテ島での戦いで、兵士たちはどのような状況に追い込まれたのか。それを小説にして世に問うたのが大岡昇平でした。『野火』(新潮文庫)の主人公、田村一等兵は作者自身の姿であり、米軍の捕虜になった著者がレイテ島の捕虜収容所で出会った兵士たちの分身でもあったでしょう。作品の中で、飢えにさいなまれる田村一等兵に死相を呈した将校が上腕部をたたきながら語りかけるシーンがあります。
「何だ、お前まだいたのか。可哀そうに。俺が死んだら、ここを食べてもいいよ」
将校は顔にぼろのように山蛭(やまびる)をぶら下げながら「帰りたい」とつぶやき、息絶えます。田村一等兵はまず、その山蛭の血をすすり、誰も見ていないことを確かめてから右手に剣を握り、腕の肉をそぎ落とそうとします。その時、不思議なことに、左の手が右の手首を握り、剣を振るうのを許さなかった――。死の瀬戸際で、人は何を思い、どう振る舞うのか。田村一等兵はかろうじて自分を制しますが、踏みとどまれなかった者もたくさんいたのです。
戦場で将兵の治療にあたった軍医たちの記録『大東亜戦争 陸軍衛生史 1』(陸上自衛隊衛生学校編)には、食糧が尽き、医薬品もないまま、マラリアや下痢で死んでいった兵士たちの状況が延々と綴られています。そしてついには、日本陸軍の医療記録に「戦争栄養失調症」なる病名が登場するに至ったのです。衛生史の筆者は「軍内のいわゆる政治的配慮により、かかる特殊な病名がでっちあげられたと説く学者もあり、現に栄養物の補給にこと欠かなかった米軍には、本症の如き記載はない」と記しています(p151)。
軍医たちは、戦死者と戦病死者の割合をどうみていたのか。『陸軍衛生史』は「敗戦によって統計資料は焼却または破棄されており、推定するよしもない」と記すのみです。藤原氏は著書でこのことを「もっとも重大な問題を欠落させている」と批判していますが、「そう書くしかなかった」と言うべきでしょう。緒戦の勝利の後、日本軍は多くの戦線で敗走し、指揮官が自分の部隊の状況すら把握できないといった事態がいたるところで現出したからです。従って、「戦病死の方が多い」と断定するのは難しいのですが、少なくとも「半数近くは戦闘による死亡ではない」とは言えるのではないか。だからこそ、戦後、復員した兵士の中に「戦友の家族を訪ねてその最期を伝えたいと思っても、できない」と懊悩する人が幾人もいたのです。嘆き悲しむ遺族に「やせ衰え、排泄物にまみれて死んでいった」などと、どうして伝えられようか、と。
長い歴史の中で、戦争はいろいろな国で幾度も繰り返されてきました。ですが、その軍隊の兵士の半分近くが「食べ物がなくて斃(たお)れた」というような戦争がほかにあったでしょうか。そのような戦争を命じた指導者たちがいたでしょうか。日清、日露の戦争に勝ち、日中戦争で蒋介石軍を蹴散らしているうちに、「皇軍は無敵」と酔いしれ、大きな世界が見えなくなる。冷静に分析し、合理的に行動することもできなくなる――その挙げ句、70年前の破局を迎えたのです。
「それは日本軍の特質」と言って済ますことはできないでしょう。形を変えて、戦後の日本社会に引き継がれ、今なお脈々と生き続けているのではないか。膨大な借金を抱えながら、その支払いを次の世代に押し付けて恥じない。広島、長崎に続き、福島の原発事故であれだけの惨禍をこうむりながら、なお平然と原発の再稼動をめざす――その破廉恥な姿は、前線の苦しみをよそに東京の大本営で無責任な戦争指導を続けた軍人たちの姿と重なって見えてくるのです。
ガダルカナルの戦場で飢え、フィリピン、ビルマと転戦しながら詩を書き続けた吉田嘉七(かしち)は『ガダルカナル戦詩集』(創樹社)の最後に、次のような詩を掲げました。
遠い遠い雲の涯に
たばにして捨てられた青春よ
今尚大洋を彷徨する魂よ
俺達の永遠に癒えない傷あと
私たちの国は、今また「人としての心」をたばにして捨てるような道へ踏み込もうとしているのではないか。
(長岡 昇)
《参考文献》
◎『餓死(うえじに)した英霊たち』(藤原彰、青木書店)
◎『野火』(大岡昇平、新潮文庫) *大岡昇平の小説を原作にした映画『野火』(塚本晋也監督)が公開されています。詳しくは色塗りの部分をクリックしてください。
◎『大東亜戦争 陸軍衛生史 1』(1971年、陸上自衛隊衛生学校編)
◎『定本 ガダルカナル戦詩集』(吉田嘉七、創樹社)
≪写真説明とSource≫
◎写真は映画『野火』のワンシーン
Source : http://eiga.com/movie/80686/gallery/5/
*メールマガジン「小白川通信 28」 2015年7月10日
村の朝は早い。村人が総出で農道の改修や田んぼの水路の泥かきをすることを「普請(ふしん)」といい、たいていは日曜日の朝5時すぎから作業が始まります。5時半集合、ということになっているのですが、なにせみんな早起きで、集合時間の前に作業が始まってしまうのです。
山形県朝日町の山あいの村にある実家では母親が一人で暮らしていたため、去年まで普請の仕事は免除されていました。私は隣の地区にある団地に住んで通いで介護をしていたのですが、今年の1月に母親が90歳で亡くなったため、週末は私が空き家になった実家で暮らすようになりました。遺品や荷物を片付けてリフォームを済ませ、秋には実家に引っ越すつもりです。
というわけで、引っ越しの前なのですが、村の人から「普請があるよ」とお誘いがかかり、このあいだの日曜日に私も参加しました。「主な作業は田んぼの畦(あぜ)の草刈りと農道の側溝の泥かき」と教えてもらったので、草刈り鎌のほかに、先のとがったスコップ(剣スコ)と四角いスコップ(角スコ)を持ってでかけました。側溝の泥かきには剣(けん)スコより角(かく)スコの方がいいからです。
現場に着いてすぐ、ずっと村で暮らしている人との差を見せつけられました。草刈り鎌などを持ってきているのは私ともう一人くらい。あとは各自、エンジン駆動の草刈り機を肩からぶら下げています。側溝からすくい上げた泥を運ぶために、軽トラックで来た人も何人かいました。こちらは徒歩で、手に草刈り鎌。「新米の村人」には機動力も機械力もありません。草刈りはお任せして、私は側溝の泥かきに専念しました。
1時間ほど泥かきをして作業が終わりかけた頃、泥の中から奇妙な石を見つけました。こびりついた泥を落としてみると、細長い打製石器でした。長さ8センチ、幅3センチほど。木にくくりつけて槍として使った石器のように見えます。それほど驚きもしませんでした。と言うのも、生まれ故郷の朝日町には旧石器時代や縄文時代の遺跡がいくつもあり、打製石器や古い土器がたくさん見つかっているからです。
.jpg)
田んぼのわきで見つかった打製石器
一部の考古学者の間では、朝日町は旧石器が日本で初めて発見され、記録されたところとして知られています。こんなことを書くと、「何を言ってるんだ。旧石器が日本で初めて発見されたのは群馬県の岩宿(いわじゅく)だ。行商をしながら考古学の研究をしていた相沢忠洋という人が見つけて、明治大学の研究者が1949年(昭和24年)の秋に記者会見して発表している。どの教科書にも書いてある」とお叱りを受けそうです。
.jpg)
岩宿遺跡で発見された槍先形尖頭石器
確かに、どの教科書にもそう書いてあります。しかし、相沢忠洋氏が旧石器を発見し、明治大学の研究者がその成果を発表する前に、実は山形県朝日町の大隅(おおすみ)というところで旧石器が多数見つかっており、地元で小学校の教員をしていた菅井進氏が1949年発行の考古学の同人誌『縄紋』第三輯に「粗石器に関して」という論文を寄稿していたのです。岩宿遺跡についての発表の半年前のことでした。
けれども、東北の寒村での発見。小学校の教員が書いた論文は、考古学者の目に触れることはありませんでした。たとえ、目にとまったとしても、当時の考古学会では「日本には旧石器時代はない」というのが常識でしたから、黙殺されたことでしょう。岩宿遺跡の旧石器が「日本初」として記憶されるに至ったのは、相沢忠洋氏の尽力に加えて、その成果が明治大学の著名な考古学者によって発表され、その後も継続して発掘調査が行なわれたからです。大隅の旧石器は世に認められることなく、歴史の谷間に埋もれてしまったのです。
考古学の研究史に残ることはありませんでしたが、群馬県の岩宿よりも先に山形県の大隅で旧石器が発見され、記録されていたという事実は消えません。そして、大昔、新潟県境に近い山形のこんな山奥で多くの人間が暮らしていたのは確かなのです。朝日町には大隅遺跡以外にも旧石器時代の遺跡があり、縄文時代のものとみられる遺跡もたくさんあるのです。
さらに興味深いのは、この町には発掘調査が行なわれなかった遺跡もかなりある、と考えられることです。私の実家がある太郎地区の遺跡もその一つです。小学生の頃(今から半世紀前)、村のおじさんから「こだなものが出できた」と、打製石器をいくつかもらいました。この場所は県や町に届けられることなく、農地としてそのまま開墾されたと聞きました。戦後の食糧難の時代、農民は何よりも食糧の増産を求められていたました。役所に「遺跡が見つかりました」と届け出て発掘調査などされたのでは、仕事にならなかったからです。
黙って開墾し続け、石器や土器を片隅に追いやった村人の気持ちも分かります。朝日町のほかの地区でもこうした例があったと聞いています。私の故郷だけの話ではないでしょう。全国各地でこうしたことがあったと考えるのが自然です。近年はともかく、戦前、戦後の時期に考古学者が発掘することができたのは、見つかった遺跡のごく一部と考えるべきでしょう。
そして、思うのです。今、わが故郷の朝日町は過疎に苦しんでいますが、旧石器時代や縄文時代にはとても暮らしやすいところだったのだろう、と。遺跡はいずれも、日当たりのいい河岸段丘にあります。秋、山ではクリやドングリがたくさん採れ、最上川や支流の朝日川にはサケが群れをなして遡上してきたはずです。厳しい冬を生き抜くための糧が得やすい場所だったのです。もちろん、旧石器時代を懐かしんでも何の足しにもなりません。けれども、そこには、厳しい過疎の時代を生き抜き、新しい時代を切り拓いていくためのヒントが何か潜んでいるような気がするのです。
(長岡 昇)
《参考サイト》
戸沢充則・明治大学学長の講演「岩宿遺跡より早かった大隅遺跡」抄録(朝日町エコミュージアム協会)
大隅遺跡発見の経緯(同)
明治大学HPの考古学関係(岩宿遺跡)
相沢忠洋記念館
群馬県みどり市岩宿博物館
《参考文献》
◎『朝日町史 上巻』(朝日町史編纂委員会、朝日町史編集委員会編、2007年発行)
◎『人間の記録 80 相沢忠洋 「岩宿」の発見 幻の旧石器を求めて』(相沢忠洋、日本図書センター)
◎『日本の旧石器文化』1?4巻(雄山閣出版)
◎『日本考古学を見直す』(日本考古学協会編、学生社)
第3回最上川縦断カヌー探訪は、2015年7月25日(土)と26日(日)に予定通り開催されます。
1日目は山形県朝日町から中山町まで28キロ、2日目は村山市から大石田町までの20キロを下る予定です。山形県の内陸部は22日夕、激しい雷雨に襲われ、23日も小雨模様です。予報では当日、大雨になる心配はありませんが、「清流を下る」というわけにはいかないかもしれません。
参加を申し込まれた方は30人です。山形県内から13人、県外から17人。日程別では1日目のみの参加が3人、2日間のフル参加が19人、2日目のみ参加が8人。従って、1日目に川下りをするのは22人(17艇)、2日目に下るのは27人(22艇)になる予定です。両日とも、2人乗りの艇が5艇あります。
25日は午前10時から、山形県朝日町の雪谷カヌー公園で簡素な開会式を行い、10時半にスタート、26日は村山市・碁点橋のたもと(右岸)から午前10時スタートの予定です。ご参考までに、2012年の第1回カヌー探訪の参加者は24人(山形県内21人、県外3人)、2013年は山形豪雨のために中止、2014年の第2回カヌー探訪の参加者は35人(県内19人、県外16人)でした。
1日目は山形県朝日町から中山町まで28キロ、2日目は村山市から大石田町までの20キロを下る予定です。山形県の内陸部は22日夕、激しい雷雨に襲われ、23日も小雨模様です。予報では当日、大雨になる心配はありませんが、「清流を下る」というわけにはいかないかもしれません。
参加を申し込まれた方は30人です。山形県内から13人、県外から17人。日程別では1日目のみの参加が3人、2日間のフル参加が19人、2日目のみ参加が8人。従って、1日目に川下りをするのは22人(17艇)、2日目に下るのは27人(22艇)になる予定です。両日とも、2人乗りの艇が5艇あります。
25日は午前10時から、山形県朝日町の雪谷カヌー公園で簡素な開会式を行い、10時半にスタート、26日は村山市・碁点橋のたもと(右岸)から午前10時スタートの予定です。ご参考までに、2012年の第1回カヌー探訪の参加者は24人(山形県内21人、県外3人)、2013年は山形豪雨のために中止、2014年の第2回カヌー探訪の参加者は35人(県内19人、県外16人)でした。
*メールマガジン「小白川通信 27」 2015年6月12日
父親の世代が兵士として戦った70年前の戦争の呼称について、私たちの世代は中学や高校で「太平洋戦争」と教わりました。新聞記者になってからもこの呼び方に疑問を抱くことはなく、長い間、記事の中でもそう書いてきました。この呼称に違和感を覚えるようになったのは、1990年代にニューデリー特派員としてインドに駐在したころからのような気がします。
インドからスリランカに出張し、コロンボでお年寄りに昔の思い出話を聞いた時のことです。彼は戦争中のことを語り始め、こう言ったのです。「あの時はびっくりしたよ。日本軍の航空機が銀翼をきらめかせて急降下して、港に停泊していたイギリスの船を爆撃したんだ。日の丸のマークが見えたよ。いつも落ち着いているイギリス人があわてふためく様子が実に印象的だった」。真珠湾を攻撃した後、日本の連合艦隊がインド洋にも出撃したことは記憶していましたが、当時この地域を植民地として支配していた英国にこれほど大規模な攻撃を仕掛けていたとは、不勉強でこの時まで知りませんでした。

インド洋での日英の戦いはどのようなものだったのか。ニューデリー特派員としての取材の合間に戦史をひもとき、調べました。ビルマ南方の海に浮かぶアンダマン・ニコバル諸島をめぐっても、激しい争奪戦が繰り広げられたことを知りました。そして、1944年(昭和19年)のインパール作戦。日本軍の無謀、悲惨な戦闘の典型とされるこの作戦の主戦場は、太平洋どころかインド洋からも遠く離れています。作戦から50年後の1994年に、遺族の慰霊団に同行して現地を訪ねる機会がありましたが、戦場になったインパールもコヒマもインド北東部の山岳地帯にあるのです。
あの戦争を「太平洋戦争」と呼んだのでは、これらの戦いはすべてその枠組みから抜け落ちてしまいます。中国本土での日本軍と蒋介石軍や中国共産党軍(八路軍)との戦いを「太平洋戦争の一部」とするのもしっくりしません。この呼称に対する違和感が膨らんでいきました。かと言って、当時、日本政府が使っていた「大東亜戦争」を引っ張り出してきて使う気にはなれません。この戦争の内実は、「大東亜共栄圏を築くための戦争だった」などという綺麗ごとで済ませられるような、生易しいものではありません。アジアの隣人たちも快く思わないでしょう。
では、どう呼べばいいのか。2年前に山形大学で現代史の講義を担当するようになってから、コツコツと調べてきました。そして、この30年ほどの間に戦争の呼称について多くの本や論文が書かれ、激しい論争が繰り広げられてきたことを知りました。それらの文献の中で、もっとも参考になったのは文芸評論家、江藤淳氏の『閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本』(文春文庫)と、軍事・外交史の専門家、庄司潤一郎氏の論考『日本における戦争呼称に関する問題の一考察』(2011年3月、防衛研究所紀要第13巻第3号)の二つでした。「太平洋戦争という呼称はそもそも、だれが、どういう経緯で使い始めたのか」という点について、多くのことを教わりました。
1945年夏に日本を占領した連合国軍総司令部(GHQ)は、すぐさま戦争犯罪人の追及と軍国主義体制の解体に着手しますが、並行して検閲と報道規制に乗り出しました。同年9月19日に報道各社向けに「プレス・コード」を出し、「大東亜戦争」「大東亜共栄圏」「八紘一宇」「英霊」といった戦時用語の使用を避けるように指示しました。GHQの意向を受けて、新聞に「太平洋戦争」という表現が登場し始めます。この年の12月8日からは新聞各紙にGHQ提供の連載記事「太平洋戦争史」が一斉に掲載されました。1931年の満州事変から敗戦に至るまで、大本営の発表がいかに事実とかけ離れたものだったかを暴露し、日本軍による南京虐殺やフィリピンでの捕虜虐待などを告発する衝撃的な内容でした。この連載記事によって「太平洋戦争」という表現が日本社会に浸透していった、ということを江藤、庄司両氏の叙述で知りました。

一方で、GHQはこの連載開始の直後(12月15日)、日本政府に対していわゆる「神道指令」を出し、「大東亜戦争」「八紘一宇」など「国家神道、軍国主義、過激ナル国家主義ト切リ離シ得ザルモノハ之ヲ使用スルコトヲ禁止スル」と命じました。これ以降、日本政府は法令や公文書で「大東亜戦争」という言葉を使うのをやめ、「今次の戦争」や「先の大戦」「第二次世界大戦」といった表現を用いるようになりました。それは今に至るまで続いています。今年4月に慰霊のためパラオを訪れた天皇のあいさつでも、用いられた言葉は「先の戦争」でした。日本という国は公的な場で、いまだに「あの戦争についてのきちんとした呼称」を持たない国なのです。
では、アメリカではこの戦争をどう呼んでいたのか。英語版のウィキペディアで検索すると「Pacific War」という項目があり、意外なことが書いてありました。「Names for the war (戦争の呼称)」という段落の冒頭に次のように書いてあるのです(長岡訳)。
「戦争中、連合国では“ The Pacific War (太平洋戦争)”は通常、第二次世界大戦と区別されることはなく、むしろ単にthe War against Japan(対日戦争)として知られていた。米国ではPacific Theatre (太平洋戦域)という用語が広く使われていた」
つまり、米国では戦争中、対日戦争と対独戦争をひっくるめて第二次世界大戦と呼んでおり、Pacific (太平洋)という用語が使われたのは軍の作戦区域や管轄を示す場合であった、というのです。出典が示されていないため、それ以上は調べられませんでしたが、この記述は「太平洋戦争 The Pacific War 」という表現そのものが戦後、GHQによって採用されて日本で定着し、それが後に英語圏にも広がっていったことを示唆しています。「大東亜戦争」に取って代わる呼称としてGHQが普及させた、と言ってよさそうです。英国は主にインド洋で戦い、蒋介石軍・中国共産党軍との戦いは中国本土が舞台でしたが、米国にとっては「太平洋こそ主戦場」でしたから、ぴったりの呼称だったわけです。
米国の占領統治の影響は絶大です。日本の新聞や書籍では、いまだに「太平洋戦争」と表記されるのが普通です。「アジア太平洋戦争」や「アジア・太平洋戦争」あるいは「大東亜戦争」という呼称はパラパラと見える程度です。高校で現在使われている日本史と世界史の教科書はどうか。入手できる範囲で調べてみました。私たちが学んだ頃から半世紀たつのに、ほとんどの教科書は「太平洋戦争」のままでした。いくつかは「最近ではアジア太平洋戦争ともよばれている」といった注釈を付けてお茶を濁しています。教科書会社も執筆者も「模様眺め」を決め込んでいるようです。
そんな中で、異彩を放っているのが実教出版の『新版 世界史A』です。「アジア太平洋戦争(太平洋戦争)」という見出しを立て、なぜこう呼ぶのか、丁寧な説明を付けているのです。地図にはインド洋での戦闘も明示しています。歴史を学ぶ生徒に少しでも多く、考える素材を提供したい――そんな執筆者の熱意が伝わってくる記述でした。一つひとつ、こうした努力を積み重ねていくことが歴史を考えるということであり、そうやって次の世代にバトンをつないでいかなければならないのだ、としみじみ思いました。
歴史の刻印は強烈です。戦後70年たっても消えることなく、人々の心を縛り続けています。私もまた、縛りつけられた一人でした。最近になってようやくその呪縛から抜け出し、授業では「アジア太平洋戦争」という呼称を使うようになりました。もちろん、もっとピシッとした表現があるなら、それを使いたいと考えています。あれだけの戦争です。その歴史が定まるまでには、まだまだ時間がかかるわけですから。
(長岡 昇)
*庄司潤一郎氏の論考『日本における戦争呼称に関する問題の一考察』はカラー文字のところをクリックすれば、読むことができます。
URLは次の通りです。
*1945年12月8日から日本の新聞各紙に連載された『太平洋戦争史』は、翌1946年に高山書院から単行本『太平洋戦争史』として出版されました。大きな図書館なら所蔵していると思います。
*1994年に長岡がインパールへの遺族慰霊団に同行した際のルポ記事はカラー文字をクリックしてご参照ください。
≪写真説明とSource≫
セイロン沖海戦で日本軍の攻撃を受けて沈む英空母ハーミーズ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%B2%96%E6%B5%B7%E6%88%A6
GHQの神道指令を報じる毎日新聞
http://mahorakususi.doorblog.jp/archives/38143475.html
*メールマガジン「小白川通信 26」 2015年4月7日
沖縄県の翁長雄志(おなが・たけし)知事は5日、米軍普天間飛行場の移設をめぐって菅義偉(すが・よしひで)官房長官と会談し、次のように発言したと伝えられています。
「今日まで沖縄県が自ら基地を提供したことはない、ということを強調しておきたい。普天間飛行場もそれ以外の取り沙汰される飛行場も基地も全部、戦争が終わって県民が収容所に入れられている間に、県民がいるところは銃剣とブルドーザーで、普天間飛行場も含めて基地に変わった。私たちの思いとは全く別に、すべて強制接収された。そして、今や世界一危険になったから、普天間は危険だから大変だというような話になって、その危険性の除去のために『沖縄が負担しろ』と。『お前たち、代替案を持ってるのか』と。『日本の安全保障はどう考えているんだ』と。『沖縄県のことも考えているのか』と。こういった話がされること自体が日本の国の政治の堕落ではないかと思う」(琉球新報の電子版から)

翁長氏は自民党沖縄県連の幹事長を務めたこともある保守の政治家です。その彼が安倍政権の官房長官に向かって「日本の政治の堕落」という言葉を突きつけたのです。この言葉には、戦争中の沖縄戦の惨状や戦後の米国統治下での苦難、祖国復帰後も続く基地負担、そうした沖縄が背負わされたすべてのことに対する思いがこもっている、と感じました。政治の堕落――沖縄の基地問題に対する本土の政治家たちの対応は、自民党にしろ民主党にしろ、まったくその通りだと思うのです。
300万人を超える日本人が命を落としたアジア太平洋戦争で、南方や北方の戦場を除けば、沖縄は唯一、住民を巻き込んだ地上戦が行われたところです。日本軍にとって、沖縄戦の位置づけは明白でした。「本土決戦までの時間稼ぎ」です。圧倒的な兵力と物量で押し寄せる米軍を1日でも長く釘付けにして、本土決戦の準備を整えるために時間稼ぎをしようとしたのです。
その目的のために、沖縄の住民を文字通り根こそぎ動員しました。男たちを兵士として徴兵しただけでは足りず、町村ごとに義勇隊を組織し、男子生徒は鉄血勤皇隊、女子生徒はひめゆり学徒隊などと名付けて動員し、戦闘に投入しました。沖縄県平和祈念資料館によれば、沖縄戦の日本側死者は約18万8000人、その半数は一般の住民でした(米軍の死者は1万2520人)。

その献身ぶりとあまりの犠牲の多さに、当時の沖縄方面根拠地隊司令官、大田実・海軍少将は海軍次官あてに次のような電報を送っています(昭和20年6月6日付)。
「沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ県ニハ既ニ通信力ナク 三十二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルルニ付 本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ 之ニ代ツテ緊急御通知申上グ
沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ暇ナカリキ シカレドモ本職ノ知レル範囲ニ於テハ県民ハ青壮年全部ヲ防衛召集ニ捧ゲ 残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋ト家財ノ全部ヲ焼却セラレ僅ニ身ヲ以テ軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小防空壕ニ避難尚砲爆撃ノ・・・ニ中風雨ニ曝サレツツ乏シキ生活ニ甘ジアリタリ 而モ若キ婦人ハ率先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦烹炊婦ハ元ヨリ砲弾運ビ挺身斬込隊スラ申出ルモノアリ(中略)本戦闘ノ末期ト沖縄島ハ実情形・・・一木一草焦土ト化セン 糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ 沖縄県民斯ク戦ヘリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」(・・・は判読不能の部分)
海軍守備隊の司令官ですら「後世、特別のご高配をたまわりたい」と打電しないではいられなかったほどの犠牲を払った沖縄に、戦後の日本はどう報いたのか。報いるどころか、見捨てたのです。戦争が終わるやいなや、米国がソ連との対決色を強め、対ソ包囲網の一環として沖縄の軍事基地化を要求したからですが、共産主義の台頭を恐れる日本の指導層も自ら進んで沖縄を差し出したという側面があります。
公開された米国の公文書によれば、昭和天皇は1947年9月、宮内庁御用掛の寺崎英成を通してGHQ(連合国軍総司令部)に次のような申し出をしています。
「アメリカが沖縄を始め琉球の他の諸島を軍事占領し続けることを希望している。その占領はアメリカの利益になるし、日本を守ることにもなる。(中略)アメリカによる沖縄の軍事占領は、日本に主権を残存させた形で、長期の(25年から50年ないしそれ以上の)貸与をするという擬制の上になされるべきである」
(月刊誌『世界』1979年4月号所収、進藤榮一「分割された領土」から引用)
見捨てられた沖縄の人たちは当時、このような申し出があったことを知るよしもなく、戦後27年間も米国の統治下に置かれました。そして、本土復帰を果たした後も基地は戻らず、国土の0.6%を占めるにすぎない沖縄にいまだに在日米軍基地の74%があるのです。「普天間基地を返してほしい」「辺野古(へのこ)にその代替基地を造るのは認められない」と叫ぶのを、誰が非難できるというのか。
菅官房長官にしてみれば、「普天間基地の移設問題は長い間、歴代政権が米国と協議を重ねてきたことであり、辺野古への移設以外に選択肢はないのだ」と言いたいのでしょう。「沖縄振興のために3千億円台の予算を確保する」とも発言しています。新たな方策を見出すのが至難のわざであるのはその通りでしょう。しかし、これまでの沖縄の苦しみを思うなら、また昨年11月の沖縄県知事選で示された移設に反対する民意を尊重するなら、為すべきことはまだあるのではないか。少なくとも、木で鼻をくくったような「(辺野古への移設を)粛々と進める」といった言葉ではなく、もっと沖縄の人々の心に響く言葉があるはずです。
沖縄の米軍基地問題は、あの戦争が終わって70年たつというのにまだ戦後が終わっていないこと、沖縄はいまだに見捨てられた存在であること、本土の政治家で本気になって沖縄の現状を変えようとする者がいないことを私たちに突きつけてきます。それは「政治の堕落」としか言いようのない現実であり、私たち一人ひとりにも「あなたは沖縄の痛みに思いを寄せたことがありますか」という問いとなって返ってくるのです。
(長岡 昇)
《Sourceとリンク》
翁長雄志・沖縄県知事の冒頭発言全文(琉球新報電子版)
菅義偉・官房長官の冒頭発言全文(同)
大田実・沖縄方面根拠地隊司令官の電文
《写真説明とSource》
翁長雄志・沖縄県知事
http://tamutamu2011.kuronowish.com/onagatijisyuuninn.htm
ふじ学徒隊の女子生徒たち
http://www.qab.co.jp/news/2012052935780.html
◇2014年度の会計報告
2014年度の会計報告
2014年度の会計報告
*メールマガジン「小白川通信 25」 2015年3月28日
私にとって、今年は神々の国、出雲と縁が深い年になりそうです。
年明けに、高校時代の同級生で作家の飯嶋和一(かずいち)氏から最新作『狗賓(ぐひん)童子の島』(小学館)を贈っていただきました。島根県の隠岐(おき)諸島を舞台にした幕末期の物語です。今週は岡山市で講演を依頼されたのを機に島根県まで足を延ばし、松江市と出雲市を訪ねてきました。味わい深い作品であり、実り多い旅でした。
江戸時代や幕末に素材を求める作家はたくさんいますが、多くは武将や武士、勤皇の志士を主人公にして「武士道」や「憂国の志」を描いています。そんな中で、飯嶋氏は異彩を放つ存在です。武士の多くは、農民や漁民が汗水たらして働いて得たものを掠め取り、特権商人と結託して甘い汁を吸う「腐敗した奸吏(かんり)である」と断じ、歴史を動かすエネルギーは幕藩体制の下であえぎつつ生きた市井の人々の中にこそあった、と語りかけてくるのです。

隠岐諸島で一番大きな島、島後(どうご)
『狗賓(ぐひん)童子の島』は、天保8年(1837年)に大阪で起きた大塩平八郎の乱の描写から始まります。天保の大飢饉のころ、江戸でも大阪でも行き倒れの死体がそこかしこに転がっているような状況なのに、大阪東町奉行の跡部良弼(あとべ・よしすけ)は実弟の老中、水野忠邦から江戸に米を回すよう命じられるやこれに応じ、民の困窮に拍車をかけました。私財を投げ打って貧民の救済に走り回っていた元与力で陽明学者の大塩平八郎は、ことここに至って門弟らと世直しのために立ち上がることを決意し、米を買い占めて私腹をこやしていた豪商らを襲撃したのです。
内通者がいたこともあって、乱はわずか1日で鎮圧されてしまいましたが、江戸の幕臣や旗本たちのすさまじい腐敗と無能ぶりをあぶり出し、揺らぎ始めていた幕藩体制への痛烈な一撃になりました。高校の日本史の教科書では「幕末の社会」の中で10行ほど触れているだけの反乱の内実がどのようなものだったのか。それを「飢えた側」から活写しています。
当然のことながら、乱に加わった者は極刑に処せられました。処罰は、大塩平八郎の高弟で豪農の西村履三郎(りさぶろう)の長男、6歳の常太郎にまで及びました。乱から9年後、15歳になると、常太郎は出雲の隠岐諸島に流人として送られたのです。物語は、この常太郎が隠岐で「大塩平八郎の高弟の息子」として温かく迎えられ、やがて漢方医になって島の人々と共に生き、故郷の大阪・河内に還るまでを描いています。狗賓とは島の千年杉に巣くう魔物で、島の守り神です。
この本を読むと、異国船が出没する幕末、隠岐諸島は対馬列島などと並んで「国防の最前線」であったことがよく分かります。異国船は「未知の伝染病」をもたらすものでもありました。安政年間には外国人によって持ち込まれたコレラによって、2カ月足らずの間に江戸だけで26万人が死亡した、と紹介されています。「最前線」の隠岐諸島にも伝わり、漢方医の常太郎らは治療に追われます。隠岐を支配する松江藩の役人たちは無力で、コレラに立ち向かったのは流刑の島で生きる住民たち自身でした。庄屋は薬種の調達を助け、島民は漢方医の常太郎の手足となって奮闘したのです。
大佛(おさらぎ)次郎賞を受賞した飯嶋氏の前作『出星前夜』も、キリシタンへの苛烈な弾圧に抗して蜂起した天草の乱を民衆の側から描いた作品でした。いつの時代でも、支配した側は膨大な史料を残しますが、つぶされていった者たちの言葉を伝えるものはわずかしかありません。それを丹念に拾い集め、想像力の翼を広げて書く――それがこの作家の流儀です。5、6年に一作しか世に問うことができないのも無理はありません。むしろ、よくぞ折れることなく書き続けてきたものだ、と驚嘆します。どの作品も長大で難解ですが、時の試練に耐えうるのではないかと感じています。個人的には、江戸時代に手製の凧で空を舞うことに挑んだ職人の物語『始祖鳥記』が特に好きです。
岡山では、民間人校長としての体験を踏まえて「里山教育の勧め」というテーマで講演し、JR伯備(はくび)線で松江に向かいました。松江城の堂々たる構えに感心しながらも、『狗賓童子の島』を思い起こし、複雑な思いに駆られました。お堀端に「小泉八雲記念館」がありましたので見学し、館内で彼の作品『神々の国の首都』(講談社学術文庫)を買い求め、宿で読みました。彼の書いたものは断片的にしか触れたことがなく、しっかり読んだのは初めてです。

小泉八雲と妻の節子
八雲は、明治初期の横浜や松江の人々と風俗を温かい目で描きつつ、自らの思いをたっぷりと書いています。そこには、アイルランド人の父とギリシャ人の母との間に生まれ、両親の離婚、父親の死去、引き取ってくれた大伯母の破産といった試練をくぐり抜け、新天地アメリカでジャーナリストとして身を立てた、彼の人生そのものが濃縮されていると感じました。例えば芸術について、彼はこう記します。
「あらゆる芸術家は、過去の亡霊の中で仕事をするのだ。飛ぶ鳥や山の霞や朝な夕なの風物の色合や木々の枝ぶりや春やおそしと咲き出した花々を描く時、その指を導くのは、今は亡き名匠たちだ。代々の練達の工匠たちが、一人の芸術家にその妙技を授け、彼の傑作の中によみがえるのだ」(p18)
キリスト教社会の厳しい戒律と偽善を嫌う八雲は、明治日本の大らかな人々と神々に心を寄せ、こう吐露してもいます。
「いかなる国、いかなる土地において宗教的慣習が神学と一致したためしがあっただろうか? 神学者や祭司たちは教義を創り、教条を公布する。しかし善男善女は自分たちの心根に従って自分たちの神様を作り出すことに固執する。そしてそうして出来た神様こそ神様の中ではずっと上等の部に属する神様なのである」(p231)
八雲がこよなく愛した出雲の国は今、北陸新幹線の開通に湧く金沢や富山を横目に、人口減と高齢化に苦しみ、あまり元気とは言えません。観光案内をしてくれたタクシーの運転手さんは「島根の人口は70万を切りました。隣の鳥取に次いでビリから2番目ですわ」と嘆いていました。
けれども、車窓から眺めると、そこには広々とした家屋でゆったりと暮らす人々の姿がありました。家々を守る立派な黒松の防風林は、数百年にわたって丹精を重ねてきた賜物です。すべては流転し、変転します。長い歴史の中に身を置いてみれば、今の大都市の繁栄もまた、つかの間の幻影のようなものかもしれません。いつの日にか、出雲をはじめとする日本海側の地域が再び「時代の最前線」に立つ日が来る、と私は信じています。
(長岡 昇)
*写真のSource:
隠岐諸島の島後(どうご)
http://shimane.take-uma.net/%E9%9A%A0%E5%B2%90%E3%81%AE%E5%B3%B6%E7%94%BA_15/%E3%80%90%E6%B5%B7%E8%BF%91%E3%81%8F%E3%80%91%E9%9A%A0%E5%B2%90%E3%81%AE%E5%B3%B6%E7%94%BA%E3%81%AB%E3%82%82%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E7%89%A9%E4%BB%B6%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%82%88%E3%80%90%E5%8F%A4%E6%B0%91%E5%AE%B6%E3%80%91
小泉八雲と妻の節子
http://isegohan.hatenablog.com/entry/2014/03/23/162941
*メールマガジン「小白川通信 24」 2015年3月6日
大学関係者が「地方の国立大学から文系の学部がなくなるらしい」と騒いでいます。「そんなバカな」と思うのですが、それを本気で唱えている人がいます。文部科学省は昨年10月に「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」という諮問会議を立ち上げました。18人から成るこの有識者会議のメンバー、冨山(とやま)和彦氏(経営コンサルタント)がその人です。

どういう時代認識と論理で冨山氏は「地方の国立大学の文系学部廃止」を訴えているのでしょうか。彼が上記の有識者会議で配布した資料や、3月4日付の朝日新聞オピニオン面に掲載されたインタビュー記事から要約すると、次のような認識と論理に基づく主張です。
「日本経済は大きく二つの世界に分かれてしまいました。世界のトップと競う大企業中心のグローバル経済圏(G)と、地域に根差したサービス産業・中小企業のローカル経済圏(L)です。Gは競争力も生産性も十分だが、Lは欧米諸国に比べて生産性が低い。だから、地方の大学には学術的な教養ではなく、職業人として必要な実践的なスキルを学生に教えてほしい。従来の文系学部のほとんどは不要です。何の役にも立ちません。シェイクスピアよりも観光業で必要な英語を、サミュエルソンの経済学ではなく簿記会計を、憲法学ではなく宅建法こそ学ばせるべきです」
実に歯切れのいい主張です。現在の大学が激変する時代の要請に十分に応えているかと問われれば、否と答える人の方が多いでしょう。時代が変わる中で、大学もまた変わらなければならないことは確かです。けれども、冨山氏の主張は乱暴すぎるのではないか。彼が描く大学の将来像は次のようなものです。
「日本の大学はアカデミズム一本やりの『一つの山』構造になっています。これを、高度な資質を育てるアカデミズムの学校と、実践的な職業教育に重点を置いた実学の学校という『二つの山』にすべきです。地方大学の文系の教授には辞めてもらうか、職業訓練教員として再教育を受けてもらいます。(不足する教員は)民間企業の実務経験者から選抜すればいいのです」
これでは、大学関係者が騒ぐのも当然です。彼の主張には一部納得できるところもありますが、学問や教育に対する深い洞察が感じられません。そもそも、その時代認識と日本の現状についての考え方に同意できないものがあります。
アメリカの大学院で経営学を学んだ人らしく、冨山氏も二元論が得意なようです。善か悪か、敵か味方か。アメリカで二元論が好まれるのは、騎兵隊がインディアンを追い立てて西部開拓に邁進した歴史の投影かもしれません。キリスト教的な価値観が影響している面もあるのでしょう。けれども、今はアメリカ的な価値観・世界観そのものが問われているのではないか。1%の富豪が国富の多くを占めるような貪欲な資本主義の下でグローバル化がこのまま進んでもいいのか。新しい第2、第3の道があるのではないか。その模索が続く中で、単純な二元論で時代を認識し、対策を打ち出せば、道を過るおそれがあります。
何よりも、冨山氏が唱える「二つの山」論は、日本の経済成長を支えた「東京一極集中」の焼き直しです。東京がすべてを握り、地方に号令をかけて邁進する――江戸時代から綿々と続き、明治維新後も敗戦後も維持された上意下達型の社会構造を強化せよ、と言っているに等しい。そんなことで、多極化するこれからの世界を生きていけるのか。それこそが問われているのに、古い歌の替え歌を歌ってどうするのか。
6年前に東京から故郷の山形に戻り、その実情に触れてきました。相変わらず東京の顔色をうかがい、中央政府から補助金を引き出すことに知恵を絞っている面があることは事実です。けれども、その一方で農村を拠点に世界と競う中堅企業が育っているという現実もあります。私が勤める山形大学にも世界に通用する研究者が幾人もいます。冨山氏の主張は、地方を拠点に世界と競い、汗を流している人たちに冷水を浴びせるものです。育ちつつある芽をつぶしてしまいかねません。

私は「東京一極集中」の焼き直しの「二つの山」など見たくはありません。それで未来が開けるとも思えません。大小さまざまな山が連なる社会へと変わって行く姿を見たい。そして、そのために必要な財源は「実は東京にある」と考えています。
4年前の東日本大震災で、私たちは東京で号令をかける政治家や中央省庁の官僚たちが、いざという時にいかに頼りにならないかを骨身に染みて思い知らされました。政治システムも官僚制度もすでに時代にそぐわなくなっているのです。補助金分配機関と化した中央省庁は今の半分以下の人員と予算でいいのではないか。政官を取り巻く利権構造にも大ナタを入れなければなりません。いまだに甘い汁を吸い続けている組織と人間がいかに多いことか。
地方の政治・経済や大学も改革を迫られていることは間違いありません。それを逃れるための「反対のための反対」は終わりにしなければなりません。けれども、より根本的なところに手を付けないまま、痛みを地方にだけ押し付けるような「大学改革論」にくみするわけにはいきません。いくつもの山々が連なるような社会へと変わる。そういう改革にこそ力を注ぎたい。
(長岡 昇)
《写真説明》
冨山和彦氏
Source:http://blogos.com/article/100873/
新緑の飯豊(いいで)連峰
Source:http://blogs.yahoo.co.jp/utsugi788/61642479.html
*メールマガジン「小白川通信 23」 2015年2月1日
つらい事や切ない事があると、思い出す言葉があります。チェコのプラハ生まれの詩人、リルケの言葉です。
一行の詩のためには
あまたの都市、あまたの人々、あまたの書物を
見なければならぬ
あまたの禽獣(きんじゅう)を知らねばならぬ
空飛ぶ鳥の翼を感じなければならぬし
朝開く小さな草花のうなだれた羞(はじ)らいを究めねばならぬ
追憶が僕らの血となり、目となり
表情となり、名まえのわからぬものとなり
もはや僕ら自身と区別することができなくなって
初めてふとした偶然に
一編の詩の最初の言葉は
それら思い出のまん中に
思い出の陰から
ぽっかり生れて来るのだ
〈リルケ『マルテの手記』(大山定一訳、新潮文庫)から〉

この文章に接したのは今から30年前、新聞社の編集部門に配属されている時でした。新聞記者として入社したのに失敗を重ねて編集部門に回され、記事を書くことができない立場にありました。他人の書いた原稿を読み、それに見出しを付けて紙面を編集する日々・・・。鬱々としている時でした。「何を甘えているんだ。お前はあまたの都市を見たのか。あまたの書物を読んだのか」。そんな言葉を突き付けられたようで胸に染み、忘れられない言葉になりました。
その後、取材する立場に戻り、外報部に配属されました。アフガニスタンの内戦取材に追われ、インドの宗教対立のすさまじさにおののき、インドネシアの腐敗と闇の深さに度肝を抜かれて、心がすさんでいくのが自分でも分かりました。走りながら、なぐり書きを繰り返すような毎日。そんな時に、またこの文章に戻って反芻していました。「いつの日にか、心にぽっかりと浮かんだものを書ければ、それでいいではないか」と思えて、心が安らぐのでした。
取材の一線を離れて論説委員になってからは、それまでよりは書物を読む時間を多く持てるようになりました。先輩や同僚の論説委員の書くものに接する機会も増えました。その中で、忘れられない文章があります。2001年5月1日の朝日新聞に掲載された「歴史を学ぶ」という社説です。筆者は、退社して間もなく2004年に死去した大阿久尤児(おおあく・ゆうじ)さん。長い社説ですが、全文をご紹介します。
~ ~ ~
「歴史」という日本語にも歴史がある。それも比較的にまだ新しい。
小学館の『国語大辞典』によると、この言葉が初めて出てくる文献は『艶道通鑑』という江戸時代中期の本だそうだ。明治以後、英語のヒストリーにあたる言葉として広く使われるようになる。日本語には多くの漢語が取り入れられてきたが、「歴史」は日本生まれの言葉だ。中国にもいわば逆輸入されて、リーシという発音で、同じ意味に使われている。
歴史教育もまた歴史的な産物だ。英国の学者ノーマン・デイウィス氏がその著『ヨーロッパ』で書いている。「そもそも19世紀に歴史教育というものが始まった時点で、それは愛国心に奉仕するように動員された」(別宮貞徳訳、共同通信社)
19世紀とはどんな時代だったのか。それまでの欧州には、君主がいわば財産としてもつ領土と、そこに暮らす民とがあったが、現在の意味での国家や国民という概念はまだ存在していなかった。フランス革命と、その後のナポレオンの戦争で、今のフランスにつながる国家が初めて成立し、その領域に住む人々に同じフランス人という意識が芽生えた。現在にいたる「国民国家」(ネーション・ステート)体制の始まりだ。
この国民国家という仕組みはまず、欧州を中心に急速に広まった。ドイツやイタリアができた。そのころ鎖国を脱した日本がめざしたのも、この仕組みだった。昔の人は「武蔵の国の住人」などと名乗っていたのである。国家、国民という日本語も、西洋をモデルとして、明治になってから使われるようになった言葉だ。
「国民国家という形態が普及したおもな原因は、軍事だ」と、東京外大名誉教授の岡田英弘さんが書いている(『歴史とはなにか』文春新書)。「国民国家のほうが戦争に強いという理由」で、この政治形態が世界中に広まった、と岡田さんは説明する。
戦争という国家単位の生存競争に勝ち残るには、国民の総力を動員しなければならない。その手段として歴史教育も始まり、それぞれに祖国の栄光が強調された。歴史教育のこういう生い立ちは、何をもたらしたのか。
さきに紹介したデイウィス氏は同じ著書で先輩たちを批判する。ヨーロッパの歴史家たちは、自分たちの文明こそ最良と思い込み、他の地域をかえりみず、自己満足にふけってきた、と。同氏は、「悪質な」教科書などの特徴を次のように数え上げる。「理想化された、したがって本質的にうその姿を、過去の真実の姿として描く。好ましいと思うものはすべてとりあげ、不快と思えばはじき出す」
最近問題になった日本のある教科書の編集者の態度とどこか似ている。ヨーロッパ中心主義はおかしいが、日本の過去は何でも立派といいたげな教科書や歴史の本も、これまたおかしい。人はみな自分のルーツを知りたい。ご先祖はけなげで、立派だったと思いたいのは人情である。だが、そういう記述だけを、誇張もまじえて寄せ集めたのでは、歴史はただのうぬぼれ鏡になってしまう。
8年にわたって国連の難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんに、ドイツのラウ大統領から最高位の功労勲章が授与された。東京のドイツ大使館で行われた授与式には、たまたま来日したティールゼ連邦議会議長が立ち会った。「緒方さんは人間として、アフリカやバルカンの難民の救援に全力をあげた」と授与の理由を述べた。
日本人の緒方さんが「人間として」努力したことに対して、ドイツの元首がその国最高の栄誉でたたえる。国家をめぐる風景が、そんなふうに変化してきている。国民国家という「戦争向き」の体制は果たして、2度の世界大戦という悲惨な破局をもたらした。国家中心主義を真っ先に始めた欧州も、さすがに反省を迫られる。
もはや国家はすべてではない。国家の枠を超えて互いに協力できることはいくらでもある。歴史から学ぶとは、例えばこういうことだろう。いまの欧州連合(EU)までの統合の歩みはその実践例である。
日本もまた、歴史から学ぶことが多い。少し遅れて国民国家となったこの国も、内外に数々の不幸をもたらしてきた。日本人として、同時に人間として、いまの私たちは生きている。「お国のため」が当たり前とされた半世紀前までに比べて、「人間として」の部分が広がっている。これからももっと広がるだろう。
父母や祖父母の世代に起きたことが、さまざまに関連しあって、今日ただいまの社会が出来ている。何を維持し、何を変えてゆくのか。過去をきちんと知らないでは、明日のことは決められない。かつては弱肉強食が当然だった。今では人道が前面にでる。価値観は時とともに変わる。その時点までの人類の経験の総体から、新しい価値観が生まれる。その経験を整理する術(すべ)が歴史だ、ともいえよう。
人間として過去を知り、あすの指針にする。いびつな自己満足を排し、大人の判断力を培う。それが本当の歴史教育だ。
~ ~ ~
*注 リルケの『マルテの手記』は、彼が30歳代半ばの時の作品です。パリで暮らす貧乏詩人を主人公にした長編小説で、パリで妻子と離れて暮らしていたリルケ自身の生活を投影した作品と言われています。極度の貧困と壮絶な孤独。随筆を連ねるようなタッチでパリ時代を描いています。全編が詩、と言ってもいいような作品です。冒頭の文章は『マルテの手記』の一部を抜粋したもので、句点を省いて詩の形式にしてあります。
(長岡 昇)
《写真説明》 詩人ライナー・マリア・リルケ(1875-1926年)
Source:http://www.oshonews.com/2011/10/rainer-maria-rilke/
【2009年】
10月17日 第1回最上川縦断カヌーレース検討会(朝日町)
10月29日 山形県河川砂防課の齋藤隆課長に企画説明
11月 9日 国土交通省山形河川国道事務所の山谷博志・副所長に企画説明
11月14日 第2回最上川縦断カヌーレース検討会
12月14日 西川町カヌー協会の荒川政司会長に企画説明
12月15日 第3回最上川縦断カヌーレース検討会
【2010年】
1月23日 山形県カヌー協会の小林久雄事務局長に説明
1月26日 第4回最上川縦断カヌーレース検討会
3月 1日 第5回最上川縦断カヌーレース検討会兼NPO「ブナの森」の設立総会
(朝日町)
3月 8日 朝日町公所会館に「ブナの森」の事務所オープン
3月16日 宮宿郵便局に寄付受付用の振替口座と総合口座を開設
3月29日 「ブナの森」の第1回定例事務局会議(第2回総会を兼ねる)
イベントの名称を「最上川縦断カヌーレース」から
「最上川縦断カヌー探訪」に変更する
タイムレースではなく、 川下りをゆったり楽しむ企画にすることを決める
4月 5日 「カヌー探訪」実現のため寄付要請の手紙50通を投函。募金活動を始める
4月11日 地元・上郷の宇津野区長、海野信雄氏に協力要請
5月 1日 第2回定例事務局会議。トライアルイベントについて協議
準備不足のため臨時会議を開くことに
5月10日 臨時事務局会議でトライアルイベントの準備
5月15日、16日 最上川縦断カヌー探訪のトライアルイベント
1日目は9人(8艇)、2日目は4人(4艇)で下る
6月14日 第3回定例事務局会議。トライアルイベントの反省をし、
ホームページ作成に着手することを決定
6月24日 朝日町志藤六郎村おこし基金に補助金の交付申請を提出
「ブナの森」の看板が取り付けられる
7月 5日 ホームページ制作会社コミュニティアイと1回目の打ち合わせ
7月16日 第4回定例事務局会議
志藤六郎基金への補助申請とホームページ作成について事務局が報告
事務局の専従スタッフが細谷智美さん(初代)から長岡由衣さんに(ゆい)
さんに交代
7月29日 朝日町志藤六郎基金からの補助金交付が決まる
8月 5日 コミュニティアイと2回目の作業打ち合わせ
国交省山形河川国道事務所に地図データの提供を要請
9月23日 第5回定例事務局会議
9月26日 最上川クリーンアップ作戦(第5回)に参加
10月 2日 山形カヌークラブの中川和夫理事長に最上川縦断カヌー探訪開催に向けて
協力を要請
10月 5日 最上川縦断カヌー探訪のホームページを公開
10月26日 第6回定例事務局会議
11月25日 第7回定例事務局会議
12月 7日 朝日町上郷地区の安藤稔・連合区長、海野信雄・宇津野区長、奈良崎
美雄・大滝区長、伊藤正男・松原区長に協力を要請
12月 9日 カヌー探訪のポスター制作をディーエムサインの渡邉幸雄氏に依頼
12月14日 山形県と国土交通省山形河川国道事務所、東北電力山形支店に後援を要請
以後、流域の自治体にも後援を正式に要請
12月23日 山形大学漕艇部の鈴木隆部長(地域教育文化部教授)に協力を要請
12月27日 第8回定例事務局会議(兼第3回総会)
事務局長が初代梅原宙(ひろし)さんから佐竹久さん(大江カヌー愛好会
会長)に交代
【2011年】
1月27日 第9回定例事務局会議
2月 3日 朝日町が最上川縦断カヌー探訪の後援を決定。以後、関係団体から順次後援を
いただく
2月24日 第10回定例事務局会議
2月25日 朝日町の町議のみなさんにカヌー探訪の企画を説明
3月 1日 朝日町の創遊館でカヌー探訪実行委員会の結成大会を開き、第1回大会の
開催日程(4月30日、5月1日)を決める
3月10日 春先のカヌー川下りの危険性を考慮し、夏に延期する方向に転換
朝日町議会の議員のみなさんに説明
3月11日 東日本大震災が発生。以後、「ブナの森」は活動休止状態に
6月 6日 「ブナの森」の活動を本格再開。第11回定例事務局会議を開き、
第1回最上川縦断カヌー探訪を2012年に1年延期することを決定
6月14日 「ブナの森」のホームページで第1回大会を2012年に延期すると告知
7月 4日 第12回定例事務局会議で2回目のトライアル実施を決める
7月30日、31日
昨年の5月中旬に続いて2回目のトライアル川下り
1日目は6艇9人、2日目は4艇5人が参加
新潟・福島豪雨の直後で最上川は濁流状態だった
9月18日 最上川クリーンアップ作戦に「ブナの森」として参加
9月29日 第13回定例事務局会議
トライアルの報告と総括。長岡昇が10月下旬に共著『未来を生きる
ための教育』を出版し、その売上金を「ブナの森」の運営資金にする
ことを報告
10月27日 第14回定例事務局会議
11月28日 第15回定例事務局会議。第1回大会に向けて準備作業の洗い出し
【2012年】
1月17日 第16回定例事務局会議。最上川縦断カヌー探訪の第1回大会を7月
28日(土)、29日(日) に開催することを内定。開催に向けて作業
日程表を作る
2月27日 第17回定例事務局会議。荘内銀行ふるさと創造基金への助成申請を検討
3月 7日 荘内銀行ふるさと創造基金に助成金の申請書類を郵送
(5月の連休前に「今回は助成対象にならず」との連絡あり)
3月27日 第18回定例事務局会議。5月17日にカヌー探訪実行委員会の再結成大会を
開くことを決定
4月24日 第19回定例事務局会議。年次総会を兼ねて開き、NPO「ブナの森」の規約
第27条(事業年度)「9月から翌年8月まで」を「4月から翌年3月まで」と
改正
4月27日 国土交通省山形河川国道事務所や山形県、東北電力山形支店など、後援を
依頼する。組織や団体にこの日以降、順次、依頼文書を手交もしくは送付
5月13日 上郷ダム公園から大滝公民館への小路を大滝地区の役員の方々と整備
5月17日 カヌー探訪実行委員会の再結成大会を朝日町の創遊館で開催。開催要項と結成
宣言を採択し、実行委の委員長に長岡昇、事務局長に佐竹久を選出した。
鈴木浩幸・朝日町長、高橋正志・国土交通省長井出張所長、美しい山形・
最上川フォーラムの柴田洋雄会長ら18人が出席
5月29日 第20回定例事務局会議。第1回カヌー探訪の準備作業の詰め。
6月27日 第21回定例事務局会議。6月上旬から「ブナの森」ホームページで、カヌー
探訪の参加者を募り始める。佐竹久事務局長が2日目のコースを試走して報告
7月 6日 第1回カヌー探訪のポスター500枚がようやく届く
7月14日 第1回カヌー探訪の参加申し込みを締め切る(実際には締め切り後も若干名を
受け入れる)
7月17日 第22回定例事務局会議。カヌー探訪の参加者とレスキュー担当は合計で25人
(24艇)の見込み。上郷の花畑組合と食事提供について打ち合わせた結果を
報告
7月26日 ブナの森スタッフの分担・配置表を作ってメール送り
7月27日 前日の準備。上郷ダム公園に仮設の船着き場を設置し、テントを張る。
長井橋河川公園にもテントを仮設
7月28日 第1回最上川縦断カヌー探訪を開催
1日目は長井橋から朝日町まで24キロメートルを漕ぐ。
21人(19艇)が参加(レスキュー要員を含む)。参加者の多くが朝日町の
りんご温泉で汗を流し、上郷ダム公園近くの大滝公民館に宿泊。花畑組合が
夕食を提供した
7月29日 第1回カヌー探訪2日目
上郷ダム下流にある赤釜(あかがま)からスタート。2日目は22人
(20艇)が参加。八天橋の瀬で2艇が転覆。大江町の「おしんの筏くだり
ロケ地」で昼食。午後4時半すぎに中山町の長崎大橋河川公園に到着。
2日目は29キロ、合計で53キロを漕いだ
8月 4日 「ブナの森」ホームページの「おおや通信」欄で第1回最上川縦断カヌー探訪の
概要を報告
8月11日 第1回カヌー探訪の参加者と支援者に報告とお礼を兼ねた手紙を発送
8月29日 「ブナの森」ホームページに「記録」欄を新設、第1回カヌー探訪の参加者や
支援者の名前、各ポイントの通過時刻などをアップ
9月21日 第23回定例事務局会議(兼総会)を開き、第1回カヌー探訪の総括と反省を
行った。NPOを法人化するためにも財政基盤を強化する必要があることを
確認、年会費(一口5千円)を収める賛助会員を募ることを決める。
来年の第2回カヌー探訪も7月最後の週末に開催する方向
10月2日 以降 第1回最上川縦断カヌー探訪の事業報告書を後援団体に発送
【2013年】
1月29日 第24回定例会議事務局会議を4ヵ月ぶりに開催。ポスターの試作など第2回大会
の準備作業を始める。事務局の専従スタッフが長岡由衣(ゆい)さん(2代目)
から和南城千陽(わなじょう・ちはる)さんに交代。和南城さんが常駐するのは
3月から
2月27日 第25回定例事務局会議。第2回最上川縦断カヌー探訪を7月27日(土)、
28日(日)の両日に開催することを正式に決定。開催費用に充てるため、
企業や団体からから協賛を募り、寄付を仰ぐことも決めた
3月13日 荘内銀行ふるさと創造基金に助成申請書類を郵送
3月26日 第26回定例事務局会議。7月27日、28日の第2回大会に向けて、準備作業の
日程を固める
4月25日 第27回定例事務局会議。第2回大会の開催要項と予算案を決めた。荘内銀行
ふるさと基金の助成は受けられないとの連絡あり
5月21日 第2回最上川縦断カヌー探訪の実行委員会結成大会朝日町の創遊館で開く。
朝日町の川口幸男・副町長、国土交通省山形河川国道事務所の伊藤基博・長井
事務所長らが出席、開催要項と事業予算を正式に決定
5月27日 第2回大会の参加申込みの受け付け開始日(ただし、ホームページの更新が遅れ、
実際に受け付けを始めたのは6月上旬。7月14日締め切り)
6月24日 第28回定例事務局会議。レスキュー体制など準備作業を詰めた。県外から
朝日町に移住した水沼佑太さん、橋本蕗さんが手伝ってくれることになった
7月19日 第29回定例事務局会議。参加者は23人(レスキュー要員9人を含む)の予定。
進行シナリオやサポート要員の配置図などを作成
7月25日 山形県を襲った集中豪雨のために最上川が氾濫。第2回大会の中止を決める。
参加費を返却することに
7月27日、28日 第2回最上川縦断カヌー探訪の開催を豪雨のために中止
9月6日 第30回定例事務局会議(兼大会中止残念会)。8人が出席。第2回大会準備に
要した費用は9万8676円。会議後に朝日町の居酒屋「番外地」で懇親会
【2014年】
3月27日 定例事務局会議を半年ぶりに再開(第31回)。2014年の大会を
「出直し第2回最上川縦断カヌー探訪」と銘打って、7月26日、27日に開催
することを内定。豪雨の場合は1週間順延し、8月2日、3日に開催する予定
4月上旬 白鷹町地先の国道287号線で大規模な土砂崩れの起きるおそれがあることが判明。
「1日目、長井市?白鷹町?朝日町」の川下りを断念し、朝日町から出発する
ことに変更
4月25日 第32回定例事務局会議。川下りのコースを「1日目 朝日町?中山町」
「2日目 中山町?大石田町」に。その後、2日目のコースが長すぎるので
「中山町?村山市」に変更
5月27日 朝日町の創遊館で「出直し第2回最上川順段カヌー探訪」の実行委員会結成大会を
開き、開催要項案と予算案を採択。安藤昭郎・朝日町教育長ら8人が出席。
コースは「1日目朝日町雪谷?中山町・長崎大橋 28?」「2日目 中山町・
長崎大橋?村山市・碁点橋20?」の計48?に決定。
結成大会に続いて、第33回定例事務局会議を開催
6月 9日 「ブナの森」ホームページで参加申し込みの受け付けを開始
6月13日 ホームページに「出直し第2回カヌー探訪」のコース図をアップ
6月14日 出直し第2回のポスターを発注。予算不足のため100枚に
6月19日 専門誌『カヌーワールド』の西沢あつしさんから取材申し入れ
6月27日 第34回定例会議。開催に向けて準備作業の詰め
6月30日 流域の消防と警察に開催要項を郵送
7月12日 参加受け付けを締め切る。38人が申し込む(後に3人が辞退、参加35人に)
7月15日 NHKプレミアム「ニッポンぶらり鉄道旅」のディレクター笠原正己さんから
取材申し入れ
7月19日 佐竹久、雀鍾八、長岡 昇の3人がコースを下見し、草刈り
7月24日 ホームページで「予定通りに開催」と告知。佐竹久、雀鍾八、白田金之助、長岡昇
の4人で中山町・長崎大橋の船着き場の泥かき
7月25日 雪谷公民館を利用する6人が到着
7月26日 出直し第2回最上川カヌー探訪の1日目。朝日町雪谷から中山町・長崎大橋までの
28?に25人、20艇が参加。大江町「おしんの筏下りロケ地」昼食。
10人が朝日町の北部公民館を利用
7月27日 カヌー探訪2日目。31人が参加。中山町・長崎大橋から村山市・碁点橋まで
20?。谷地橋で昼食。2日間の参加者は35人(山形県内19人、
県外16人)、28艇
7月28日 「ブナの森」ホームページに記録をアップ
8月11日 第35回定例会議事務局会議。出直し第2回カヌー探訪を総括
8月14日 NHKBSプレミアムの「ニッポンぶらり鉄道旅」でカヌー探訪が紹介される
8月31日 事務局員の和南城千陽さんが退職。事務局の仕事は
「まよひが企画(新林美幸さん)」に業務委託
11月22日 第36回定例事務局会議を開き、第3回カヌー探訪の準備を始める
2015年7月25日、26日に開催することを内定
【2015年】
2月27日 第37回定例事務局会議。第3回大会のコースを検討し、1日目は朝日町?中山
町、2日目は村山市碁点橋?大石田町とすることを内定
3月30日 第38回定例事務局会議。カヌー探訪実行委員会を5月15日に結成することを
決定
4月25日 第39回定例事務局会議。準備作業を本格化
5月15日 第3回カヌー探訪の実行委員会の結成大会を開催
開催要項と予算(35万円)を正式に決定
6月 8日 第3回カヌー探訪の参加申し込みの受付開始
6月26日 第40回定例事務局会議。マイクロバスや弁当の手配など作業の分担を確認
7月11日 参加受け付けを締め切る。申し込みは30人(山形県内13人、県外17人)
7月17日 第41回定例事務局会議。参加賞のTシャツや完漕賞など最後の詰め
7月25日 第3回最上川カヌー探訪の1日目。朝日町雪谷から中山町・長崎大橋までの
28?に22人、17艇が参加。大江町「おしんの筏下りロケ地」で昼食
大石田町の東町公民館で開かれた歓迎ビアガーデンに18人が参加、公民館に宿泊
7月26日 カヌー探訪2日目。27人、22艇が参加。村山市・碁点橋から大石田河岸まで
20?を漕ぐ。隼の瀬眺望公園で昼食、休憩。
2日間の参加者は30人(山形県内13人、県外17人)、24艇
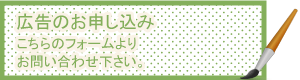
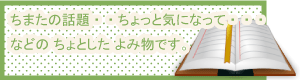
10月17日 第1回最上川縦断カヌーレース検討会(朝日町)
10月29日 山形県河川砂防課の齋藤隆課長に企画説明
11月 9日 国土交通省山形河川国道事務所の山谷博志・副所長に企画説明
11月14日 第2回最上川縦断カヌーレース検討会
12月14日 西川町カヌー協会の荒川政司会長に企画説明
12月15日 第3回最上川縦断カヌーレース検討会
【2010年】
1月23日 山形県カヌー協会の小林久雄事務局長に説明
1月26日 第4回最上川縦断カヌーレース検討会
3月 1日 第5回最上川縦断カヌーレース検討会兼NPO「ブナの森」の設立総会
(朝日町)
3月 8日 朝日町公所会館に「ブナの森」の事務所オープン
3月16日 宮宿郵便局に寄付受付用の振替口座と総合口座を開設
3月29日 「ブナの森」の第1回定例事務局会議(第2回総会を兼ねる)
イベントの名称を「最上川縦断カヌーレース」から
「最上川縦断カヌー探訪」に変更する
タイムレースではなく、 川下りをゆったり楽しむ企画にすることを決める
4月 5日 「カヌー探訪」実現のため寄付要請の手紙50通を投函。募金活動を始める
4月11日 地元・上郷の宇津野区長、海野信雄氏に協力要請
5月 1日 第2回定例事務局会議。トライアルイベントについて協議
準備不足のため臨時会議を開くことに
5月10日 臨時事務局会議でトライアルイベントの準備
5月15日、16日 最上川縦断カヌー探訪のトライアルイベント
1日目は9人(8艇)、2日目は4人(4艇)で下る
6月14日 第3回定例事務局会議。トライアルイベントの反省をし、
ホームページ作成に着手することを決定
6月24日 朝日町志藤六郎村おこし基金に補助金の交付申請を提出
「ブナの森」の看板が取り付けられる
7月 5日 ホームページ制作会社コミュニティアイと1回目の打ち合わせ
7月16日 第4回定例事務局会議
志藤六郎基金への補助申請とホームページ作成について事務局が報告
事務局の専従スタッフが細谷智美さん(初代)から長岡由衣さんに(ゆい)
さんに交代
7月29日 朝日町志藤六郎基金からの補助金交付が決まる
8月 5日 コミュニティアイと2回目の作業打ち合わせ
国交省山形河川国道事務所に地図データの提供を要請
9月23日 第5回定例事務局会議
9月26日 最上川クリーンアップ作戦(第5回)に参加
10月 2日 山形カヌークラブの中川和夫理事長に最上川縦断カヌー探訪開催に向けて
協力を要請
10月 5日 最上川縦断カヌー探訪のホームページを公開
10月26日 第6回定例事務局会議
11月25日 第7回定例事務局会議
12月 7日 朝日町上郷地区の安藤稔・連合区長、海野信雄・宇津野区長、奈良崎
美雄・大滝区長、伊藤正男・松原区長に協力を要請
12月 9日 カヌー探訪のポスター制作をディーエムサインの渡邉幸雄氏に依頼
12月14日 山形県と国土交通省山形河川国道事務所、東北電力山形支店に後援を要請
以後、流域の自治体にも後援を正式に要請
12月23日 山形大学漕艇部の鈴木隆部長(地域教育文化部教授)に協力を要請
12月27日 第8回定例事務局会議(兼第3回総会)
事務局長が初代梅原宙(ひろし)さんから佐竹久さん(大江カヌー愛好会
会長)に交代
【2011年】
1月27日 第9回定例事務局会議
2月 3日 朝日町が最上川縦断カヌー探訪の後援を決定。以後、関係団体から順次後援を
いただく
2月24日 第10回定例事務局会議
2月25日 朝日町の町議のみなさんにカヌー探訪の企画を説明
3月 1日 朝日町の創遊館でカヌー探訪実行委員会の結成大会を開き、第1回大会の
開催日程(4月30日、5月1日)を決める
3月10日 春先のカヌー川下りの危険性を考慮し、夏に延期する方向に転換
朝日町議会の議員のみなさんに説明
3月11日 東日本大震災が発生。以後、「ブナの森」は活動休止状態に
6月 6日 「ブナの森」の活動を本格再開。第11回定例事務局会議を開き、
第1回最上川縦断カヌー探訪を2012年に1年延期することを決定
6月14日 「ブナの森」のホームページで第1回大会を2012年に延期すると告知
7月 4日 第12回定例事務局会議で2回目のトライアル実施を決める
7月30日、31日
昨年の5月中旬に続いて2回目のトライアル川下り
1日目は6艇9人、2日目は4艇5人が参加
新潟・福島豪雨の直後で最上川は濁流状態だった
9月18日 最上川クリーンアップ作戦に「ブナの森」として参加
9月29日 第13回定例事務局会議
トライアルの報告と総括。長岡昇が10月下旬に共著『未来を生きる
ための教育』を出版し、その売上金を「ブナの森」の運営資金にする
ことを報告
10月27日 第14回定例事務局会議
11月28日 第15回定例事務局会議。第1回大会に向けて準備作業の洗い出し
【2012年】
1月17日 第16回定例事務局会議。最上川縦断カヌー探訪の第1回大会を7月
28日(土)、29日(日) に開催することを内定。開催に向けて作業
日程表を作る
2月27日 第17回定例事務局会議。荘内銀行ふるさと創造基金への助成申請を検討
3月 7日 荘内銀行ふるさと創造基金に助成金の申請書類を郵送
(5月の連休前に「今回は助成対象にならず」との連絡あり)
3月27日 第18回定例事務局会議。5月17日にカヌー探訪実行委員会の再結成大会を
開くことを決定
4月24日 第19回定例事務局会議。年次総会を兼ねて開き、NPO「ブナの森」の規約
第27条(事業年度)「9月から翌年8月まで」を「4月から翌年3月まで」と
改正
4月27日 国土交通省山形河川国道事務所や山形県、東北電力山形支店など、後援を
依頼する。組織や団体にこの日以降、順次、依頼文書を手交もしくは送付
5月13日 上郷ダム公園から大滝公民館への小路を大滝地区の役員の方々と整備
5月17日 カヌー探訪実行委員会の再結成大会を朝日町の創遊館で開催。開催要項と結成
宣言を採択し、実行委の委員長に長岡昇、事務局長に佐竹久を選出した。
鈴木浩幸・朝日町長、高橋正志・国土交通省長井出張所長、美しい山形・
最上川フォーラムの柴田洋雄会長ら18人が出席
5月29日 第20回定例事務局会議。第1回カヌー探訪の準備作業の詰め。
6月27日 第21回定例事務局会議。6月上旬から「ブナの森」ホームページで、カヌー
探訪の参加者を募り始める。佐竹久事務局長が2日目のコースを試走して報告
7月 6日 第1回カヌー探訪のポスター500枚がようやく届く
7月14日 第1回カヌー探訪の参加申し込みを締め切る(実際には締め切り後も若干名を
受け入れる)
7月17日 第22回定例事務局会議。カヌー探訪の参加者とレスキュー担当は合計で25人
(24艇)の見込み。上郷の花畑組合と食事提供について打ち合わせた結果を
報告
7月26日 ブナの森スタッフの分担・配置表を作ってメール送り
7月27日 前日の準備。上郷ダム公園に仮設の船着き場を設置し、テントを張る。
長井橋河川公園にもテントを仮設
7月28日 第1回最上川縦断カヌー探訪を開催
1日目は長井橋から朝日町まで24キロメートルを漕ぐ。
21人(19艇)が参加(レスキュー要員を含む)。参加者の多くが朝日町の
りんご温泉で汗を流し、上郷ダム公園近くの大滝公民館に宿泊。花畑組合が
夕食を提供した
7月29日 第1回カヌー探訪2日目
上郷ダム下流にある赤釜(あかがま)からスタート。2日目は22人
(20艇)が参加。八天橋の瀬で2艇が転覆。大江町の「おしんの筏くだり
ロケ地」で昼食。午後4時半すぎに中山町の長崎大橋河川公園に到着。
2日目は29キロ、合計で53キロを漕いだ
8月 4日 「ブナの森」ホームページの「おおや通信」欄で第1回最上川縦断カヌー探訪の
概要を報告
8月11日 第1回カヌー探訪の参加者と支援者に報告とお礼を兼ねた手紙を発送
8月29日 「ブナの森」ホームページに「記録」欄を新設、第1回カヌー探訪の参加者や
支援者の名前、各ポイントの通過時刻などをアップ
9月21日 第23回定例事務局会議(兼総会)を開き、第1回カヌー探訪の総括と反省を
行った。NPOを法人化するためにも財政基盤を強化する必要があることを
確認、年会費(一口5千円)を収める賛助会員を募ることを決める。
来年の第2回カヌー探訪も7月最後の週末に開催する方向
10月2日 以降 第1回最上川縦断カヌー探訪の事業報告書を後援団体に発送
【2013年】
1月29日 第24回定例会議事務局会議を4ヵ月ぶりに開催。ポスターの試作など第2回大会
の準備作業を始める。事務局の専従スタッフが長岡由衣(ゆい)さん(2代目)
から和南城千陽(わなじょう・ちはる)さんに交代。和南城さんが常駐するのは
3月から
2月27日 第25回定例事務局会議。第2回最上川縦断カヌー探訪を7月27日(土)、
28日(日)の両日に開催することを正式に決定。開催費用に充てるため、
企業や団体からから協賛を募り、寄付を仰ぐことも決めた
3月13日 荘内銀行ふるさと創造基金に助成申請書類を郵送
3月26日 第26回定例事務局会議。7月27日、28日の第2回大会に向けて、準備作業の
日程を固める
4月25日 第27回定例事務局会議。第2回大会の開催要項と予算案を決めた。荘内銀行
ふるさと基金の助成は受けられないとの連絡あり
5月21日 第2回最上川縦断カヌー探訪の実行委員会結成大会朝日町の創遊館で開く。
朝日町の川口幸男・副町長、国土交通省山形河川国道事務所の伊藤基博・長井
事務所長らが出席、開催要項と事業予算を正式に決定
5月27日 第2回大会の参加申込みの受け付け開始日(ただし、ホームページの更新が遅れ、
実際に受け付けを始めたのは6月上旬。7月14日締め切り)
6月24日 第28回定例事務局会議。レスキュー体制など準備作業を詰めた。県外から
朝日町に移住した水沼佑太さん、橋本蕗さんが手伝ってくれることになった
7月19日 第29回定例事務局会議。参加者は23人(レスキュー要員9人を含む)の予定。
進行シナリオやサポート要員の配置図などを作成
7月25日 山形県を襲った集中豪雨のために最上川が氾濫。第2回大会の中止を決める。
参加費を返却することに
7月27日、28日 第2回最上川縦断カヌー探訪の開催を豪雨のために中止
9月6日 第30回定例事務局会議(兼大会中止残念会)。8人が出席。第2回大会準備に
要した費用は9万8676円。会議後に朝日町の居酒屋「番外地」で懇親会
【2014年】
3月27日 定例事務局会議を半年ぶりに再開(第31回)。2014年の大会を
「出直し第2回最上川縦断カヌー探訪」と銘打って、7月26日、27日に開催
することを内定。豪雨の場合は1週間順延し、8月2日、3日に開催する予定
4月上旬 白鷹町地先の国道287号線で大規模な土砂崩れの起きるおそれがあることが判明。
「1日目、長井市?白鷹町?朝日町」の川下りを断念し、朝日町から出発する
ことに変更
4月25日 第32回定例事務局会議。川下りのコースを「1日目 朝日町?中山町」
「2日目 中山町?大石田町」に。その後、2日目のコースが長すぎるので
「中山町?村山市」に変更
5月27日 朝日町の創遊館で「出直し第2回最上川順段カヌー探訪」の実行委員会結成大会を
開き、開催要項案と予算案を採択。安藤昭郎・朝日町教育長ら8人が出席。
コースは「1日目朝日町雪谷?中山町・長崎大橋 28?」「2日目 中山町・
長崎大橋?村山市・碁点橋20?」の計48?に決定。
結成大会に続いて、第33回定例事務局会議を開催
6月 9日 「ブナの森」ホームページで参加申し込みの受け付けを開始
6月13日 ホームページに「出直し第2回カヌー探訪」のコース図をアップ
6月14日 出直し第2回のポスターを発注。予算不足のため100枚に
6月19日 専門誌『カヌーワールド』の西沢あつしさんから取材申し入れ
6月27日 第34回定例会議。開催に向けて準備作業の詰め
6月30日 流域の消防と警察に開催要項を郵送
7月12日 参加受け付けを締め切る。38人が申し込む(後に3人が辞退、参加35人に)
7月15日 NHKプレミアム「ニッポンぶらり鉄道旅」のディレクター笠原正己さんから
取材申し入れ
7月19日 佐竹久、雀鍾八、長岡 昇の3人がコースを下見し、草刈り
7月24日 ホームページで「予定通りに開催」と告知。佐竹久、雀鍾八、白田金之助、長岡昇
の4人で中山町・長崎大橋の船着き場の泥かき
7月25日 雪谷公民館を利用する6人が到着
7月26日 出直し第2回最上川カヌー探訪の1日目。朝日町雪谷から中山町・長崎大橋までの
28?に25人、20艇が参加。大江町「おしんの筏下りロケ地」昼食。
10人が朝日町の北部公民館を利用
7月27日 カヌー探訪2日目。31人が参加。中山町・長崎大橋から村山市・碁点橋まで
20?。谷地橋で昼食。2日間の参加者は35人(山形県内19人、
県外16人)、28艇
7月28日 「ブナの森」ホームページに記録をアップ
8月11日 第35回定例会議事務局会議。出直し第2回カヌー探訪を総括
8月14日 NHKBSプレミアムの「ニッポンぶらり鉄道旅」でカヌー探訪が紹介される
8月31日 事務局員の和南城千陽さんが退職。事務局の仕事は
「まよひが企画(新林美幸さん)」に業務委託
11月22日 第36回定例事務局会議を開き、第3回カヌー探訪の準備を始める
2015年7月25日、26日に開催することを内定
【2015年】
2月27日 第37回定例事務局会議。第3回大会のコースを検討し、1日目は朝日町?中山
町、2日目は村山市碁点橋?大石田町とすることを内定
3月30日 第38回定例事務局会議。カヌー探訪実行委員会を5月15日に結成することを
決定
4月25日 第39回定例事務局会議。準備作業を本格化
5月15日 第3回カヌー探訪の実行委員会の結成大会を開催
開催要項と予算(35万円)を正式に決定
6月 8日 第3回カヌー探訪の参加申し込みの受付開始
6月26日 第40回定例事務局会議。マイクロバスや弁当の手配など作業の分担を確認
7月11日 参加受け付けを締め切る。申し込みは30人(山形県内13人、県外17人)
7月17日 第41回定例事務局会議。参加賞のTシャツや完漕賞など最後の詰め
7月25日 第3回最上川カヌー探訪の1日目。朝日町雪谷から中山町・長崎大橋までの
28?に22人、17艇が参加。大江町「おしんの筏下りロケ地」で昼食
大石田町の東町公民館で開かれた歓迎ビアガーデンに18人が参加、公民館に宿泊
7月26日 カヌー探訪2日目。27人、22艇が参加。村山市・碁点橋から大石田河岸まで
20?を漕ぐ。隼の瀬眺望公園で昼食、休憩。
2日間の参加者は30人(山形県内13人、県外17人)、24艇
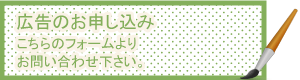
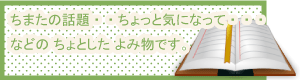
*メールマガジン「小白川通信 22」 2014年12月23日
今年8月上旬の特集に続いて、古巣の朝日新聞が23日の朝刊に、慰安婦報道を検証する第三者委員会の報告書を掲載しました。1面と3面、真ん中の特集7ページ、さらに社会面の記事を含めれば11ページに及ぶ長文の報告、報道でした。
精神的にも肉体的にも、最も充実した時期をこの新聞に捧げた者の一人として、実に切ない思いで目を通しました。何よりも切なかったのは、事実を掘り起こし、それを伝えることを生業(なりわい)とする新聞記者の集団が自らの手では検証することができず、その解明を「第三者委員会」なるものの手に委ねざるを得なかったことです。その報告を通してしか、慰安婦報道の経過を知るすべがないことです。
報告書には、かつての上司や同僚、後輩の記者たちの名前がずらずらと出てきます。「これだけの人間が関わっていて、なんで自分たちの力で検証紙面を作れないんだ」と叫びたくなる思いでした。危機管理能力を失い、自浄能力も失くしてしまった、ということなのかもしれません。前途は容易ではない、と改めて感じさせられました。
朝日新聞の慰安婦報道に関して、私は、1982年9月2日の朝日新聞大阪社会面に掲載された吉田清治(故人)の記事にこだわってきました。大阪市内での講演で「私は朝鮮半島で慰安婦を強制連行した」と“告白した”という記事です。これが朝日新聞にとっての慰安婦報道の原点であり、出発点だからです。その後の吉田に関する続報を含めて、彼の証言の裏取りをきちんとし、疑義が呈された段階でしっかりした検証に乗り出していれば、その後の展開はまるで違ったものになったはずなのです。
実は、吉田清治が朝日新聞の記者に接したのはこの時が初めてではありません。1980年ごろ、彼は朝日新聞川崎支局の前川惠司記者に電話して「朝鮮人の徴用について自分はいろいろと知っているので話を聞いて欲しい」と売り込んできたといいます。前川氏は川崎・横浜版で在日韓国・朝鮮人についての連載を書いていました。自分の話を連載で取り上げて欲しい様子だったといいます。著書『「慰安婦虚報」の真実』(小学館)で、前川氏はその時の様子を詳しく書いています。
吉田は「朝鮮の慶尚北道に2度行き、畑仕事をしている人たちなどを無理やりトラックに載せて連れ去る『徴用工狩り』をした」といった話をしたといいます。それまで徴用工として来日した人の話をたくさん聞いていた前川氏は、「吉田の話には辻褄の合わないところがある」と感じたといい、会った時の印象を「何かヌルッとした、つかみどころのない感じ」と表現しています。この時に前川氏が書いた記事も、今回の検証で取り消しの対象として追加されましたが、不思議なのは、この時、吉田は前川氏に対して、慰安婦の強制連行の話をまったくしていないことです。
そして、彼は1982年9月1日に大阪市内で講演し、慰安婦狩りの証言をしました。「徴用工狩り」から「慰安婦狩り」への軌道修正。前川氏の取材内容が大阪社会部に伝わっていれば何らかの役に立った可能性もあるのですが、新聞社に限らず、大きな組織というのは横の連絡が悪いのが常です。大阪の記者は吉田の軌道修正に気づくことなく、講演の内容をそのまま記事にしました。今年8月の慰安婦特集で、この記事を執筆したのは「大阪社会部の記者(66)」とされ、それが清田治史(はるひと)記者とみられることを、9月6日付のメールマガジン(小白川通信)で明らかにしました。清田氏もその後、週刊誌の取材に対して事実上それを認める発言をしています。
ところが、朝日新聞は9月29日の朝刊で「大阪社会部の記者(66)は当時、日本国内にいなかったことが判明しました」と報じ、問題の吉田講演を書いたのは別の大阪社会部の記者で「自分が書いた記事かも知れない、と名乗り出ています」と伝えました。清田氏は日本にいなかったのに「自分が書いた」と言い、8月の特集記事が出た後で別の記者が名乗り出る。驚天動地の展開でした。しかも、今回の第三者委員会の報告書ではそれも撤回し、「執筆者は判明せず」と記しています。
慰安婦報道の原点ともいえる記事についてのこの迷走。どういうことなのか、理解不能です。細かい記事はともかく、新聞記者なら、第2社会面のトップになるような記事を書いて記憶していないなどということは考えられません。しかも、ただの「第2社会面トップ記事」ではなく、その後、なにかと話題になった記事なのです。折に触れて仲間内で話題になったに違いないのです。原稿を書き、記事になるまでにはデスクの筆も入ります。編集者や校閲記者の目にも触れます。後で調べて、「誰が書いたのか分からない」などということは考えられないのです。
とするなら、結論は一つしかありません。誰かが、あるいは複数の人間が「何らかの理由と事情があっていまだに嘘をついている」ということです。自らが属した新聞社にこれだけの深手を負わせて、なお嘘をついて事実の解明を妨げようとする。この人たちは、良心の呵責(かしゃく)を感じないのだろうか。
(長岡 昇)
*メールマガジン「小白川通信 21」 2014年12月16日
北国に住む住民の感覚で言えば、今回の総選挙は「みぞれ雪のような選挙」でした。晩秋の氷雨に感じる哀愁もなく、初冬の新雪がもたらす凛とした厳しさもない。やたら水分が多く、ぐずらぐずらと降って始末に困るみぞれ・・・。ふたを開けてみれば、自民党と公明党は合わせて1増の325議席、衆議院で3分の2を維持しました。弱々しい野党各党の議席数がいくらか増減しただけ。投票率が戦後最低を更新したのも、選挙戦を見ていれば「そうだろうな」と思えるものでした。なんとも虚しい結末です。
.jpg)
けれども、その意味するところは重大です。これから4年間、安倍晋三首相は心おきなく、自ら信じる政策を推し進めることが可能になりました。彼の政治信条と政策を支持する人たちは「してやったり」と快哉を叫んでいることでしょうが、私は「とんでもないことになってしまった」と受けとめています。
民主党政権時代の政治があまりにもひどかったため、安倍政権の手綱さばきが国民に安心感を与えていることは理解できます。株価もそれなりに持ち直しましたから、財界の受けがいいのも当然でしょう。おまけに「日本の法人税は先進諸国に比べて高すぎる。法人税の減税を検討する」と言い出していますから、なおさら受けはいいはずです。ですが、安倍政権が推し進める「アベノミクス」がこの国を苦境から救い出してくれるとは到底、思えないのです。
エコノミストの浜矩子(のりこ)同志社大学大学院教授は「株価が上がれば経済がよくなるという考え方は本末転倒です」「最大の眼目が成長戦略だというのも時代錯誤です」と、アベノミクスを批判しています。私も同感です。今、日本が直面しているのは「冷戦後の混沌とした時代、多極化する難しい過渡期をどう生きていくのか」という難題であり、「人類が経験したことのない急激な少子高齢化の中で、富の分配をどう変革していくのか」という難題です。そういう新しい時代に、アベノミクスは「過去の延長線上の政策」で対処しようとしている、と考えるからです。「ビジョン」が欠落しています。前回の総選挙の際のスローガン「日本を、取り戻す。」は、そのことを何よりも雄弁に物語っています。

私は「自民党の政治など元々どうしようもないのだ」などと言うつもりはありません。新聞記者として働く中で、私は何度も「自民党の強さ」を思い知らされる経験をしました。懐が深い人が多い、と感じたのも自民党でした。なるほど、彼らの政策や主張はいわゆる革新政党のように筋道立ってはいません。正義や公平にも鈍感です。が、自民党は肌で知っているのです。多くの人にとって、何よりも大切なのは今日の暮らしであり、明日の糧を得ることです。そこにピタリと寄り添い、彼らは全力を尽くしてきたのです。敗戦の焼け跡から立ち上がり、経済成長の道をひた走るためにはそれが何よりも重要な政策であり、路線であると彼らは信じ、行動してきたのです。グダグダ言わずに一生懸命働き、ひたすらパイを大きくする――1980年代までは、それで良かったのかもしれません。
しかし、世界の風景は激変しました。寄り添う大樹(米国とソ連)はもうありません。比較的落ち着いていた海は荒れ、海図も当てにならない時代。見たこともない航路も通らなければならなくなったのです。「日本を、取り戻す。」などと過去を振り返っている場合ではありません。この難しい過渡期をどうやって生き抜き、道を切り拓いていくのか。今日と明日に加えて、もっと先の未来をも語らなければならない時代なのです。なのに、選挙戦で「今という時代」と「未来のビジョン」を語る政党と政治家がいかに少なかったことか。有権者もまた、それを求めることなく、選択を避けようとしているように見えました。
未来が不透明であればあるほど、私たちは多様な価値観を理解する懐の深さを持ち、かじ取りを確かなものにするための手立てを考えなければなりません。また、若い人たちが難しい航海に乗り出すために準備するのを手助けしなければなりません。なのに、この国はますます「若者に冷たい国」になりつつあります。落ち着いて働き、将来の計画を立てることができるような仕事は減るばかり。財務省が発表している「世代ごとの生涯を通じた受益と負担」というデータを見ただけでも、それは明らかです。若者は重い負担と少ない受益に甘んじ、年寄りは負担した以上のものを受け取る仕組みになっており、その傾向は強まっています。それでいて、「今時の若者は内向きだ。覇気がない」などと平気で批判する世の中。若者に冷たい国、ニッポン。
総選挙の公示日(12月2日)の翌日、私が勤める山形大学で「グローバル化への対応」をテーマにしたシンポジウムがありました。その席で、フランス人の講師が「アジア各国の英語習熟度」というデータを紹介してくれました。留学を希望する大学生や社会人が受けるTOEFL(トウフル)というテストの成績比較表(2013年)です。それによれば、1位はシンガポール、2位はインド、3位はパキスタン、4位はフィリピンとマレーシア、6位が韓国。以下、香港、ベトナム、中国、タイと続き、なんと日本は遠く離されてビリから3番目。日本より英語の成績が悪いのはカンボジアとラオスだけでした。
それは、日本の英語教育のお粗末さを無残なまでに示すデータでした。アジアで長く取材してきた私の実感とも合致するデータでした。英語が世界の共通語となりつつある世界で、日本の若者は先進諸国どころか、アジア各国の若者にも遅れを取っているのです。「英語支配に追随する必要はない」という意見もあります。まっとうな意見です。が、それなら、スペイン語でもドイツ語でも、中国語でも韓国語でも構いません。「日本語以外の言語で意思の疎通を図る資質」を養う必要があります。日本の教育はその努力もしていません。これからの時代を、この島国に立てこもって生きていけと言うのか。
若者への富の分配をどんどん薄くし、新しい時代に備える機会も十分に与えない。それでいて、膨大な借金の返済を彼らに押しつけ、原発の運転で生じた廃棄物の処理も押しつける――それが今、私たちが暮らしている社会の現実です。こんな社会でいいはずがありません。選挙こそそれを変える機会であり、政治こそそれを変革する原動力であるべきなのに、師走は虚しく過ぎ去りました。とんでもないことになってしまった、と思うのです。
(長岡 昇)
*浜矩子氏の言葉は2014年12月2日の朝日新聞朝刊オピニオン面からの引用です。
*財務省のデータは「世代ごとの生涯を通じた受益と負担」をご覧ください。
*アジア各国の英語習熟度データはNikkei Asian Reviewのサイトを参照してください。
《投開票日の自民党本部の写真》 Source:NHKのニュースサイト
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2014_1215.html
《浜矩子氏の本の写真》 Source : PRTIMESのサイト
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000007006.html
*メールマガジン「小白川通信 20」 2014年11月29日
大学構内のイチョウの木々に残る葉も少なくなり、山形は冬将軍の到来を静かに待っています。黄金色の絨毯は間もなく、白銀に覆われることでしょう。いろいろな土地で何度となく眺めてきたイチョウの黄葉ですが、この秋は格別な思いで見つめました。英国の植物学者、ピーター・クレインの著書『イチョウ 奇跡の2億年史』(河出書房新社)を読み、この木をめぐる壮大な物語を知ったからです。著者は冒頭に、ドイツの文豪ゲーテが詠(よ)んだイチョウの詩を掲げています。

はるか東方のかなたから
わが庭に来たりし樹木の葉よ
その神秘の謎を教えておくれ
無知なる心を導いておくれ
おまえはもともと一枚の葉で
自身を二つに裂いたのか?
それとも二枚の葉だったのに
寄り添って一つになったのか?
こうしたことを問ううちに
やがて真理に行き当たる
そうかおまえも私の詩から思うのか
一人の私の中に二人の私がいることを
初めて知りました。シーラカンスが「生きた化石」の動物版チャンピオンだとするなら、イチョウは植物の世界における「生きた化石」の代表なのだそうです。恐竜が闊歩していた中生代に登場し、恐竜が絶滅した6500万年前の地球の激動を生き抜いたにもかかわらず、氷河期に適応することができずに世界のほとんどの地域から姿を消してしまいました。欧州の植物学者はその存在を「化石」でしか知らなかったのです。
けれども、死に絶えてはいませんでした。中国の奥深い山々で細々と生きていたのです。そしていつしか、信仰の対象として人々に崇められるようになり、人間の手で生息域を広げていったとみられています。著者の探索によれば、中国の文献にイチョウが登場するのは10世紀から11世紀ごろ。やがて、朝鮮半島から日本へと伝わりました。
日本に伝わったのはいつか。著者はそれも探索しています。平安時代、『枕草子』を綴った清少納言がイチョウを見ていたら、書かないはずがない。なのに、登場しない。紫式部の『源氏物語』にも出て来ない。当時の辞典にもない。鎌倉時代の三代将軍、源実朝(さねとも)は鶴岡八幡宮にある木の陰に隠れていた甥の公卿に暗殺されたと伝えられていますが、その木がイチョウだというのは後世の付け足しらしい。間違いなくイチョウと判断できる記述が登場するのは15世紀、伝来はその前の14世紀か、というのが著者の見立てです。中国から日本に伝わるまで数百年かかったことになります。
東洋から西洋への伝わり方も劇的です。鎖国時代の日本。交易を認められていたのはオランダだけでした。そのオランダ商館の医師として長崎の出島に滞在したドイツ人のエンゲルベルト・ケンペルが初めてイチョウを欧州に伝えたのです。帰国後の1712年に出版した『廻国奇観』に絵入りで紹介されています。それまで何人ものポルトガル人やオランダ人が日本に来ていたのに、彼らの関心をひくことはありませんでした。キリスト教の布教と交易で頭がいっぱいだったのでしょう。
博物学だけでなく言語学にも造詣の深いケンペルは、日本語の音韻を正確に記述しています。日本のオランダ語通詞を介して、「銀杏」は「イチョウ」もしくは「ギンキョウ」と発音すると聞き、ginkgo と表記しました。著者のクレインは「なぜginkyo ではなく、ginkgo と綴ったのか」という謎の解明にも挑んでいます。植字工がミスをしたという説もありますが、クレインは「ケンペルの出身地であるドイツ北部ではヤ・ユ・ヨの音をga、gu、goと書き表すことが多い」と記し、植字ミスではなく正確に綴ったものとみています。いずれにしても、このginkgoがイチョウを表す言葉として広まり、そのままのスペルで英語にもなっています。発音は「ギンコー」です。
「化石」でしか知らなかった植物が生きていたことを知った欧州でどのような興奮が巻き起こったかは、冒頭に掲げたゲーテの詩によく現れています。「東方のかなたから来たりし謎」であり、「無知なる心を導く一枚の葉」だったのです。「東洋の謎」はほどなく大西洋を渡り、アメリカの街路をも彩ることになりました。
植物オンチの私でも、イチョウに雌木(めぎ)と雄木があることは知っていましたが、その花粉には精子があり、しかも、受精の際にはその精子が繊毛をふるわせてかすかに泳ぐということを、この本で初めて知りました。イチョウの精子を発見したのは小石川植物園の技術者、平瀬作五郎。明治29年(1896年)のことです。維新以来、日本は欧米の文明を吸収する一方でしたが、平瀬の発見は植物学の世界を震撼させる発見であり、「遅れてきた文明国」からの初の知的発信になりました。イチョウは「日本を世界に知らしめるチャンス」も与えてくれたのです。
.jpg)
それにしても、著者のクレインは実によく歩いています。欧米諸国はもちろん、中国貴州省の小さな村にある大イチョウを訪ね、韓国忠清南道の寺にある古木に触れ、日本のギンナン産地の愛知県祖父江町(稲沢市に編入)にも足を運んでいます。訪ねるだけではありません。中国ではギンナンを使った料理の調理法を調べ、祖父江町ではイチョウ栽培農家に接ぎ木の仕方まで教わっています。鎌倉の鶴岡八幡宮の大イチョウを見に行った時には、境内でギンナンを焼いて売っていた屋台のおばさんの話まで聞いています。長い研究で培われた学識に加えて、「見るべきものはすべて見る。聞くべきことはすべて聞く」という気迫のようなものが、この本を重厚で魅力的なものにしています。
かくもイチョウを愛し、イチョウを追い求めてきた植物学者は今、何を思うのでしょうか。クレインはゲーテの詩の前に、娘と息子への短い献辞を記しています。
「エミリーとサムへ きみたちの時代に長期的な展望が開けることを願って」
壮大な命の物語を紡いできたイチョウ。それに比べて、私たち人間はなんと小さく、せちがらい存在であることか。
(長岡 昇)
*『イチョウ 奇跡の2億年史』は矢野真千子氏の翻訳。ゲーテの詩は『西東(せいとう)詩集』所収。
*ゲーテの詩のオリジナル(ドイツ語)と英語訳はここをクリックしてください。ゲーテの手書き原稿を見ると、ドイツ語でもイチョウのスペルは Ginkgo です。このサイトのドイツ語のスペルは誤りと思われます。
*国土交通省は日本の街路樹について、2009年に「わが国の街路樹」という資料を発表しました。2007年に調査したもので、それによると、街路樹で本数が多いのはイチョウ、サクラ、ケヤキ、ハナミズキ、トウカエデの順でした。
《写真説明》
◎青森県の弘前公園にある「根上がりイチョウ」
Source:http://aomori.photo-web.cc/ginkgo/01.html
◎ピーター・クレイン(前キュー植物園長、イェール大学林業・環境科学部長)
Source:http://news.yale.edu/2009/03/04/sir-peter-crane-appointed-dean-yale-school-forestry-and-environmental-studies
*メールマガジン「小白川通信 19」 2014年9月6日
古巣の朝日新聞の慰安婦報道については「もう書くまい」と思っていました。虚報と誤報の数のすさまじさ、お粗末さにげんなりしてしまうからです。書くことで、今も取材の一線で頑張っている後輩の記者たちの力になれるのなら書く意味もありますが、それもないだろうと考えていました。
ただ、それにしても、過ちを認めるのになぜ32年もかかってしまったのかという疑問は残りました。なぜお詫びをしないのかも不思議でした。そして、それを調べていくうちに、一連の報道で一番責任を負うべき人間が責任逃れに終始し、今も逃げようとしていることを知りました。それが自分の身近にいた人間だと知った時の激しい脱力感――外報部時代の直属の上司で、その後、朝日新聞の取締役(西部本社代表)になった清田治史氏だったのです。
一連の慰安婦報道で、もっともひどいのは「私が朝鮮半島から慰安婦を強制連行した」という吉田清治(せいじ)の証言を扱った記事です。1982年9月2日の大阪本社発行の朝日新聞朝刊社会面に最初の記事が掲載されました。大阪市内で講演する彼の写真とともに「済州島で200人の朝鮮人女性を狩り出した」「当時、朝鮮民族に対する罪の意識を持っていなかった」といった講演内容が紹介されています。この記事の筆者は、今回8月5日の朝日新聞の検証記事では「大阪社会部の記者(66)」とされています。

その後も、大阪発行の朝日新聞には慰安婦の強制連行を語る吉田清治についての記事がたびたび掲載され、翌年(1983年)11月10日には、ついに全国の朝日新聞3面「ひと」欄に「でもね、美談なんかではないんです」という言葉とともに吉田が登場したのです。「ひと」欄は署名記事で、その筆者が清田治史記者でした。朝日の関係者に聞くと、なんのことはない、上記の第一報を書いた「大阪社会部の記者(66)」もまた清田記者だったと言うのです。だとしたら、彼こそ、いわゆる従軍慰安婦報道の口火を切り、その後の報道のレールを敷いた一番の責任者と言うべきでしょう。
この頃の記事そのものに、すでに多くの疑問を抱かせる内容が含まれています。勤労動員だった女子挺身隊と慰安婦との混同、軍人でもないのに軍法会議にかけられたという不合理、経歴のあやしさなどなど。講演を聞いてすぐに書いた第一報の段階ではともかく、1年後に「ひと」欄を書くまでには、裏付け取材をする時間は十分にあったはずです。が、朝日新聞の虚報がお墨付きを与えた形になり、吉田清治はその後、講演行脚と著書の販売に精を出しました。そして、清田記者の愛弟子とも言うべき植村隆記者による「元慰安婦の強制連行証言」報道(1991年8月11日)へとつながっていったのです。
この頃には歴史的な掘り起こしもまだ十分に進んでおらず、自力で裏付け取材をするのが難しい面もあったのかもしれません。けれども、韓国紙には「吉田証言を裏付ける人は見つからない」という記事が出ていました。現代史の研究者、秦郁彦・日大教授も済州島に検証に赴き、吉田証言に疑問を呈していました。証言を疑い、その裏付けを試みるきっかけは与えられていたのです。きちんと取材すれば、「吉田清治はでたらめな話を並べたてるペテン師だ」と見抜くのは、それほど難しい仕事ではなかったはずです。
なのに、なぜそれが行われなかったのか。清田記者は「大阪社会部のエース」として遇され、その後、東京本社の外報部記者、マニラ支局長、外報部次長、ソウル支局長、外報部長、東京本社編集局次長と順調に出世の階段を上っていきました。1997年、慰安婦報道への批判の高まりを受けて、朝日新聞が1回目の検証に乗り出したその時、彼は外報部長として「過ちを率直に認めて謝罪する道」を自ら閉ざした、と今にして思うのです。
悲しいことに、社内事情に疎い私は、外報部次長として彼の下で働きながらこうしたことに全く気付きませんでした。当時、社内には「従軍慰安婦問題は大阪社会部と外報部の朝鮮半島担当の問題」と、距離を置くような雰囲気がありました。そうしたことも、この時に十分な検証ができなかった理由の一つかもしれません。彼を高く評価し、引き立ててきた幹部たちが彼を守るために動いたこともあったでしょう。
東京本社編集局次長の後、彼は総合研究本部長、事業本部長と地歩を固め、ついには西部本社代表(取締役)にまで上り詰めました。慰安婦をめぐる虚報・誤報の一番の責任者が取締役会に名を連ねるグロテスクさ。歴代の朝日新聞社長、重役たちの責任もまた重いと言わなければなりません。こうした経緯を知りつつ、今回、慰安婦報道の検証に踏み切った木村伊量社長の決断は、その意味では評価されてしかるべきです。
清田氏は2010年に朝日新聞を去り、九州朝日放送の監査役を経て、現在は大阪の帝塚山(てづかやま)学院大学で人間科学部の教授をしています。専門は「ジャーナリズム論」と「文章表現」です。振り返って、一連の慰安婦報道をどう総括しているのか。朝日新聞の苦境をどう受けとめているのか。肉声を聞こうと電話しましたが、不在でした。
「戦争責任を明確にしない民族は、再び同じ過ちを繰り返すのではないでしょうか」。彼は、吉田清治の言葉をそのまま引用して「ひと」欄の記事の結びとしました。ペテン師の言葉とはいえ、重い言葉です。そして、それは「報道の責任を明確にしない新聞は、再び同じ過ちを繰り返す」という言葉となって返ってくるのです。今からでも遅くはない。過ちは過ちとして率直に認め、自らの責任を果たすべきではないか。
(長岡 昇)
《追記》1982年9月2日の吉田清治の講演に関する大阪社会面の記事の筆者について、朝日新聞は2014年9月29日の朝刊で「別の記者が『初報は私が書いた記事かもしれない』と名乗り出ました」と報じました。さらに、同年12月23日朝刊の第三者委報告書では「当初この記事の執筆者と目された清田治史は韓国に語学留学中であって執筆は不可能であることが判明」「調査を尽くしたが、執筆者は判明せず」と伝えました。2014年末の時点では、1982年の初報の筆者は不明です。
*メールマガジン「小白川通信 18」 2014年8月31日
いわゆる従軍慰安婦問題について、朝日新聞が8月上旬に特集を組んで一連の報道に間違いがあったことを認め、主要な記事を取り消しました。慰安婦報道の口火を切った1982年9月2日付の吉田清治(せいじ)証言(韓国の済州島で自ら慰安婦を強制連行したとの証言)を虚偽だと認め、この記事を始めとする吉田清治関係の記事16本のすべてを取り消したのです。なんともすさまじい数の取り消しです。これ以降、朝日新聞は新聞や週刊誌、ネット上で袋叩きの状態にあります。
1978年から30年余り、私は朝日新聞で記者として働きました。体力的にも精神的にも一番エネルギッシュな時期を新聞記者として働き、そのことを喜びとしていた者にとって、慰安婦問題をめぐる不祥事は耐えがたいものがあります。仕事でしくじることは誰にでもあります。私も、データを読み間違えて誤った記事を書いたりして訂正を出したことが何度かあります。日々、締め切りに追われ、限られた時間の中で取材して書くわけですから、頻度はともかく、間違いは避けられないことです。ですが、慰安婦報道をめぐる過ちは、勘違いや単純ミスによる記事の訂正と同列に論じるわけにはいきません。
朝日新聞は吉田清治の証言記事を手始めに大々的な従軍慰安婦報道を繰り広げ、他紙が追随したこともあって、大きな流れを作り出しました。それは宮沢喜一首相による韓国大統領に対する公式謝罪(1992年)や河野洋平官房長官による「お詫びと反省の談話」発表(1993年)につながり、国連の人権問題を扱う委員会で取り上げられるに至ったのです。その第一歩が「ウソの証言だった」というのですから、記事を取り消して済む話ではありません。8月上旬の特集記事では、彼女たちが「本人の意に反して慰安婦にされる強制性があった」ことが問題の本質であり、それは今も変わっていない、として一連の虚報と誤報について謝罪しませんでした。それが非難する側をますます勢いづかせています。
「問題の本質は何か」などという論理で逃げるのはおかしい。新聞記者の何よりも重要な仕事は、事実を可能な限り公平にきちんと書き、伝えることです。吉田清治証言を検証した現代史家の秦郁彦氏は「彼は職業的な詐話師である」と断じました。そのような人物のでたらめな証言を一度ならず、16回も記事にしてしまったのです。しかも、そうした証言も踏まえて、社説やコラムで何度も「日本は償いをすべきだ」と主張しました。それら一連の報道や論説の土台がウソだったのですから、取り消すだけではなくきちんとお詫びをして、関係者を処分するのが報道機関として為すべきことではないのか。
慰安婦報道に関して思い出すのは、この問題に深くかかわっていた松井やより元編集委員のことです。彼女は退社した後、私がジャカルタ支局長をしていた時にインドネシアを訪れ、かつての日本軍政時代のことを取材していきました。来訪した彼女に対して、私は後輩の記者として知り得る限りの情報と資料を提供しようとしたのですが、彼女は私の話にまったく耳を傾けようとしませんでした。ただ、自分の意見と主張を繰り返すだけ。それは新聞記者としての振る舞いではなく、活動家のそれでした。亡くなった人を鞭打つようで心苦しいのですが、「こういう人が朝日新聞の看板記者の一人だったのか」と、私は深いため息をつきました。イデオロギーに囚われて、新聞記者としての職業倫理を踏み外した人たち。そういう人たちが慰安婦問題の虚報と混乱をもたらしたのだ、と私は考えています。
慰安婦報道を非難する人の中には「朝日新聞を廃刊に追い込む」と意気込んでいる人もいます。冗談ではありません。過ちを犯し、さまざまな問題を抱えているかもしれませんが、朝日新聞で働いている同僚や後輩の多くは誠実な人たちです。朝日新聞は権力者の腐敗を粘り強く、圧力に屈することなく書き続けてきた新聞であり、福島の原発事故の実相と意味をどこよりも息長く深く追い続けている新聞です。この国を少しでも良くするために奮闘してきた新聞です。だからこそ、慰安婦報道の検証を中途半端な形で終わらせるのではなく、不祥事を正面から見つめ、問い直してほしいと思うのです。
権力者の顔色をうかがい、そのお先棒をかつぐのを常とするような新聞記者や雑誌編集者が肩で風切るような世の中になったら、それこそ、この国に未来はありません。権力におもねることなく、財力にも惑わされず、市井の人と共に歩む。そういうメディアを私たちは必要としています。
(長岡 昇)
*メールマガジン「小白川通信 17」 2014年8月17日
戦争をしている国が敵国の使っている暗号を解読するということは、どういうことを意味するのでしょうか。ポーカーや麻雀を例にとれば、分かりやすくなります。対戦相手の後ろに立っている人がその相手の手の内をすべて教えてくれるのと同じです。暗号の場合は、暗号解読を担当する人たちが「後ろに立っている人」に当たります。
ゲームでは、後ろに立っている人が仲間に対戦相手の手の内を教えるのは「八百長」と呼ばれますが、戦争で暗号を解読するのは「極めて重要な戦闘」の一つです。同じような戦力、国力であっても、暗号を解読されてしまえば、まず勝ち目はありません。戦略や戦術、作戦をすべて見透かされてしまうわけですから、戦えば悲惨な結果になることは目に見えています。日本外務省の暗号は1941年の真珠湾攻撃のずっと前から、日本海軍の作戦暗号も1942年の春ごろから解読されていました。手の内を知られていたわけですから、海軍の暗号が解読されてからは、どんなに死にもの狂いになろうとも勝てるはずがなかったのです。

日本海軍の暗号書の一部(長田順行『暗号 原理とその世界』から)
当然のことながら、第2次大戦の前から、日本もドイツも暗号の重要性はよく分かっていました。ですから、「絶対に解読されない暗号システム」をそれぞれ開発し、運用しているつもりだったのです。日本海軍の場合には、よく知られているように重要な作戦暗号(いわゆるD暗号)は「数字5ケタの暗号」でした。5ケタの数字の組み合わせは10の5乗、つまり10万通りあります。(実際には通信兵が検算しやすいように、そのうちの3の倍数のみを使用)。その5ケタの数字を組み合わせて、「49728」は「連合艦隊」、「20058」は「連合艦隊司令長官」を表す、といった具合に打電していました。地名についてはそのまま表現することはせず、例えばミッドウェー島を「AF」という略号で表し、たとえ解読されてもそれがどこを意味するか分からないように工夫していました。また、すべての単語を5ケタの数字にすると暗号書が分厚くなりすぎて戦場で使いにくいため、仮名や数字にも5ケタの数字を割り振って運用していました。
もちろん、こうした5ケタの数字だけで無線通信を交わせば、比較的簡単に暗号解読者に解読されてしまいます。お互いに専門家を集めて、解読にしのぎを削っていたのですから。そこで、5ケタの数字にさらに5ケタの「乱数」を加えて、その数字をモールス信号で発信していました。多くの乱数を用意し、それと組み合わせることで、5ケタの数字の組み合わせは天文学的な多様さを生み出します。それでも、理論的には解読は可能ですが、手作業で解読しようとすれば、「1000人がかりで10年かかる」といった状態になります。10年後であれば、たとえ解読されたとしても実害はなく、そのシステムは事実上「解読不可能なシステム」のはずだったのです。
ではなぜ、日本とドイツの暗号は解読されてしまったのでしょうか。いくつかの原因が折り重なっており、戦闘の中で重要な暗号書が米英軍の手に落ちてしまったといったこともあったようですが、私は「手作業で解読する」という前提条件が崩れてしまったことが最大の要因だった、とみています。英国と米国は数学者や統計学者、言語学者、文化人類学者らを総動員して解読に当たると同時に、解読のための解析に「電気リレー式の計算機」を利用しました。そしてほどなく、より計算速度の速い、真空管を使った「電子計算機」を開発して、暗号解読に活用するに至ったのです。「1000人がかりで10年かかる」はずのものが「数時間で計算し、解析できる」――それは日本もドイツも想定していなかった事態でした。「総合的な知力の戦い」と「科学技術の軍事への応用」の両面で、日本とドイツは英米に敗れたのです。
その実態は、前回の通信で紹介した暗号関係の本を読めば、うかがい知ることができます。そして、第2次大戦中の熾烈な暗号解読の戦いの中で、電気計算機や電子計算機は飛躍的な発展を遂げ、それが現在のコンピューターやIT技術の基礎になったのです。このあたりの事情を知るためには、大駒誠一・慶応大学名誉教授の労作『コンピュータ開発史』(共立出版)を参照することをお薦めします。
英国と米国はそれぞれ、英国はドイツ、米国は日本の暗号解読を主に担当し、その手法と成果を共有しましたが、第2次大戦後もその緊密な協力関係は続きました。そしてさらに、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドを加えた英語圏5カ国が「情報収集と暗号解読の連合」を組み、冷戦の主要な敵であるソ連や中国の暗号の解読にあたりました。長い間、「ソ連の暗号は強力で米国はついに解読することができなかった」と信じられていましたが、現実にはソ連の暗号の解読にもかなり成功していたことが明らかになっています。それを詳しく紹介しているのが1999年に出版された『Venona : Decoding Soviet Espionage in America 』(邦訳『ヴェノナ 解読されたソ連の暗号とスパイ活動』PHP研究所)です。
「ソ連の暗号が解読されていた」というのは、乱数を巧みに織り込んだソ連の複雑な暗号システムを知る者にとっては実に驚くべきことですが、それ以上に衝撃的なのは、米英を中心とする5カ国が2001年の9・11テロ後に乗り出した「情報収集活動」です。彼らは「テロとの戦い」という旗印の下で、暗号の解読にとどまらず、あらゆる有線・無線通信、インターネット空間を飛び交う情報の収集と解析を始めたのです。
9・11テロの後、その活動は「エシュロン」プロジェクトという名称でおぼろげに浮かび上がり、国際社会で一時問題になりかけましたが、「ならば国際テロ組織とどうやって戦うのか」という恫喝めいた圧力の中で、追及は尻すぼみに終わってしまいました。そのプロジェクトの中心になり、牽引役を果たしているのが米国の国家安全保障局(NSA)と英国の政府通信本部(GCHQ)です。両者の活動はその後、ますますエスカレートしていきました。権力の監視役を果たしてきた米国のジャーナリズムもその中に取り込まれていき、ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストといった新聞ですら、十分に追及できないような状況が生まれてしまいました。「何よりも優先しなければならないのはテロとの戦いだ」という風潮が法の支配や表現の自由を覆い尽くしてしまったのです。
彼らは何をしているのか。2013年、その内情を完膚なきまでに暴露したのがエドワード・スノーデンでした。NSAやCIA(米中央情報局)でコンピューターのセキュリティ担当者として働いていたスノーデンは、ある時から「これは言論、出版の自由をうたった合衆国憲法に違反する」と思い始め、周到な準備を重ねて内部告発に踏み切ったのです。内部告発する相手として、ニューヨーク・タイムズなどの大手メディアを避けたのも、上記のような米国の言論状況を考えれば、当然の選択だったのです。

Edward Joseph Snowden
スノーデンが内部告発の相手として選んだのは、米国の権力機関からの圧力を避けるためブラジルを拠点に活動していたフリージャーナリストのグレン・グリーンウォルドでした。そして、グリーンウォルドと手を組んで果敢な報道を展開したのは英国の新聞ガーディアンの米国オフィス(ウェブメディア)です。伝統的な活字メディアではなく、インターネット上で情報を発信するジャーナリストが権力の濫用を追及する主役に躍り出た、という意味でも、スノーデンの内部告発は画期的な意味を持っています。
彼が内部告発に至るまでの経過は、まるでアクション映画のようです。グリーンウォルドの著書『暴露 スノーデンが私に託したファイル』(新潮社)と、ガーディアンの記者ルーク・ハーディングが著した『スノーデンファイル』(日経BP社)はどちらも、実にスリリングで刺激的な本です。と同時に、NSA(米国家安全保障局)やGCHQ(英政府通信本部)はそんなことまで行っているのかと驚愕し、ついにはおぞましさを覚えてしまうほどです。
NSAは外国諜報活動監視裁判所(諜報活動を規制するため1978年に設立された米国の秘密裁判所)の令状を得て、プロバイダー会社にデータをすべて提供させる。グーグルやヤフー、フェイスブック、アップルにもすべてのデータを提供させる。海底ケーブルを使う有線通信もバイパスを作ってすべて覗き見る――要するに、すべて。「穴があればテロリストに悪用される」という理由で、彼らはすべてのデータへのアクセスを通信会社やIT企業に要求し、裁判所もそれを追認しているというのです。
英国の作家ジョージ・オーウェルは代表作『1984年』ですべての行動が当局によって監視される社会を描き、全体主義への警鐘を鳴らしましたが、皮肉なことに、スノーデンの内部告発は「自由の国」アメリカが自分たちの憲法すら踏みにじって監視社会への先導役となり、その完成に向かって邁進していることをあぶり出したのです。
「発言や行動のすべて、会って話をする人すべて、そして愛情や友情の表現のすべてが記録される世界になど住みたくない」。スノーデンは告発の動機をそう語っています。その彼が、南米への亡命を望んでいたにもかかわらず、米国の強烈な圧力のせいで受け入れてもらえず、トランジットのつもりで立ち寄ったロシアで亡命生活を送らざるを得なくなってしまいました。自由を求めて立ちあがった者が、旧ソ連の強権体質を受け継ぎ、いまだに言論弾圧を繰り返している国に庇護を求めるしかなかった――なんという不条理、なんという巡り合わせであることか。
(長岡 昇)
*エドワード・スノーデンの写真:Source
http://www.csmonitor.com/USA/2013/0609/Edward-Snowden-NSA-leaker-reveals-himself-expects-retribution
NPO「ブナの森」が主催する「出直し第2回最上川縦断カヌー探訪」は、2014年7月26日(土)と27日(日)に山形県朝日町を出発し、村山市の碁点橋にゴールする1泊2日のコースで開催されました。26日は朝日町雪谷から中山町の長崎大橋までの28キロ、27日は中山町から村山市の碁点橋まで20キロ、計48キロのコースで行われ、2日間の参加者は35人、28艇でした(1日だけの参加者を含む)。2012年の第1回カヌー探訪の参加者は24人、22艇。
.JPG)
「出直し第2回」と名付けたのは、2013年に開催する予定だった「第2回最上川縦断カヌー探訪」が7月の山形豪雨のため、中止せざるを得なくなったためです。2014年7月にも山形県内は豪雨に見舞われ、大きな被害が出ましたが、下旬までに天候が回復し、何とか開催することができました。1日目は強烈な夏空、2日目はにわか雨のち薄曇りの空の下での開催になりました。参加したカヌーイストの皆様、開催にご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。
《参加者》 35人、28艇(エントリー順)
山形県内 19人 県外16人(東京6、神奈川4、福島3、宮城1、群馬1、青森1)


【2日間で48キロを完漕】 20人
林 和明(東京都足立区)▽根本 学(福島県郡山市)▽岸 一博(東京都町田市)▽岸 君子(町田市)▽清水孝治(神奈川県厚木市)▽塚本雅俊(群馬県前橋市)▽齋藤健司(神奈川県海老名市)▽齊藤栄司(山形県尾花沢市)▽佐竹 久(山形県大江町)▽鶴巻 泰(福島県いわき市)▽長澤敬行(山形市)▽茨田康裕(横浜市)▽崔 鍾八(山形県朝日町)▽清野由奈(朝日町)▽市川 秀(東京都中野区)▽高田 徹(青森県八戸市)▽上原晋一(東京都中野区)▽菊地大二郎(山形市)▽菊地恵理(山形市)▽岸 浩(福島市)
【26日に28キロを完漕】 5人
西沢あつし(東京都東村山市)▽調所孝芳(山形市)▽鈴木宏幸(山形県山辺町)▽小野俊博(大江町)▽池辺民雄(神奈川県座間市)
【27日に20キロを完漕】 10人
佐藤雅之(山形県酒田市)▽長南 平(酒田市)▽武田安英(酒田市)▽佐藤 明(山形県鶴岡市)▽小田原紫朗(酒田市)▽池田丈人(酒田市)▽齋藤正弘(鶴岡市)▽佐藤博隆(酒田市)▽小松正則(仙台市)▽蘆野眞一郎(山形市)

《陸上サポートスタッフ》 17人(アイウエオ順)
安藤昭郎▽佐久間淳▽佐竹恵子▽白田金之助▽鈴木賢一▽長岡里子▽長岡 昇▽長岡典己▽長岡遼子▽長岡佳子▽中川和夫▽橋本 蕗▽服部雄二郎▽藤山純一▽桃色ウサヒ▽山口義博▽和南城千陽

.JPG)
《出発、通過、到着時刻》
1日目(7月26日)
9:50 朝日町の雪谷カヌー公園を出発
11:30 朝日町の「タンの瀬」を通過
13:30 大江町の「おしんの筏下りロケ地」に到着、昼食


14:30 「おしんの筏下りロケ地」から再スタート
16:30 中山町・長崎大橋の船着き場にゴール


2日目(7月27日)
8:50 中山町・長崎大橋付近でNHKBSプレミアム「ニッポンぶらり鉄道旅」の取材
9:50 長崎大橋の船着き場から2日目のスタート
12:10 河北町・谷地橋に到着、昼食
13:20 谷地橋から再スタート
15:00 村山市・碁点橋に到着



.JPG)
《後援団体》
国土交通省山形河川国道事務所▽山形県▽東北電力?山形支店▽朝日町▽大江町▽西川町▽寒河江市▽中山町▽河北町▽天童市▽東根市▽村山市▽山形カヌークラブ▽大江カヌー愛好会▽山形県カヌー協会▽美しい山形・最上川フォーラム
《ウェブサイト、ポスター、横断幕》
ウェブサイト制作 コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、栗原一弘)
ポスター制作 若月印刷(高子あゆみ)▽横断幕揮毫(きごう) 成原千枝
《協力》
最上川三難所舟下り・船長 関 勇喜
《取材》
カヌー専門誌『カヌーワールド』 西沢あつし
NHKBSプレミアム『ニッポンぶらり鉄道旅』 クリエイティブネクサス・ディレクター 笠原正己
*放送予定:8月14日(木)午後7時半、8月16日(土)午前7時45分
《リンク》次のウェブサイトやウェブアルバムでも紹介されています(青い文字をクリックしてください)
朝日町公式ホームページの「まちの写真館」
桃色ウサヒのコーナー
塚本雅俊さんのウェブアルバム
《この記録ページの写真撮影》
1日目=佐久間 淳(最上堰の写真は塚本雅俊)
2日目=橋本 蕗 (三郷堰の写真は塚本雅俊)
.JPG)
五百川(いもがわ)峡谷の難所、タンの瀬を下る岸夫妻の艇
「出直し第2回」と名付けたのは、2013年に開催する予定だった「第2回最上川縦断カヌー探訪」が7月の山形豪雨のため、中止せざるを得なくなったためです。2014年7月にも山形県内は豪雨に見舞われ、大きな被害が出ましたが、下旬までに天候が回復し、何とか開催することができました。1日目は強烈な夏空、2日目はにわか雨のち薄曇りの空の下での開催になりました。参加したカヌーイストの皆様、開催にご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝いたします。
《参加者》 35人、28艇(エントリー順)
山形県内 19人 県外16人(東京6、神奈川4、福島3、宮城1、群馬1、青森1)

朝日町の雪谷カヌー公園で開会式。マスコットキャラクターの桃色ウサヒはいつもの虚ろな目

朝日町雪谷の川岸からスタート
【2日間で48キロを完漕】 20人
林 和明(東京都足立区)▽根本 学(福島県郡山市)▽岸 一博(東京都町田市)▽岸 君子(町田市)▽清水孝治(神奈川県厚木市)▽塚本雅俊(群馬県前橋市)▽齋藤健司(神奈川県海老名市)▽齊藤栄司(山形県尾花沢市)▽佐竹 久(山形県大江町)▽鶴巻 泰(福島県いわき市)▽長澤敬行(山形市)▽茨田康裕(横浜市)▽崔 鍾八(山形県朝日町)▽清野由奈(朝日町)▽市川 秀(東京都中野区)▽高田 徹(青森県八戸市)▽上原晋一(東京都中野区)▽菊地大二郎(山形市)▽菊地恵理(山形市)▽岸 浩(福島市)
【26日に28キロを完漕】 5人
西沢あつし(東京都東村山市)▽調所孝芳(山形市)▽鈴木宏幸(山形県山辺町)▽小野俊博(大江町)▽池辺民雄(神奈川県座間市)
【27日に20キロを完漕】 10人
佐藤雅之(山形県酒田市)▽長南 平(酒田市)▽武田安英(酒田市)▽佐藤 明(山形県鶴岡市)▽小田原紫朗(酒田市)▽池田丈人(酒田市)▽齋藤正弘(鶴岡市)▽佐藤博隆(酒田市)▽小松正則(仙台市)▽蘆野眞一郎(山形市)

朝日町清水(すず)の断崖を背に最上川を下る
《陸上サポートスタッフ》 17人(アイウエオ順)
安藤昭郎▽佐久間淳▽佐竹恵子▽白田金之助▽鈴木賢一▽長岡里子▽長岡 昇▽長岡典己▽長岡遼子▽長岡佳子▽中川和夫▽橋本 蕗▽服部雄二郎▽藤山純一▽桃色ウサヒ▽山口義博▽和南城千陽

朝日町栗木沢の激流、タンの瀬に挑む
.JPG)
最上堰の魚道を1艇ずつ慎重に通過
《出発、通過、到着時刻》
1日目(7月26日)
9:50 朝日町の雪谷カヌー公園を出発
11:30 朝日町の「タンの瀬」を通過
13:30 大江町の「おしんの筏下りロケ地」に到着、昼食

おしんの筏下りロケ地の船着き場に着きました

尾花沢の齊藤栄司さんが名産のスイカを差し入れてくれました
14:30 「おしんの筏下りロケ地」から再スタート
16:30 中山町・長崎大橋の船着き場にゴール

参加者のうちで最年少は9歳の由奈ちゃん。お父さんの崔鍾八(チェ・ジョンパル)さんの艇に同乗しました

最年長は76歳の市川秀さん。前回に続いて堂々のパドルさばきでした
2日目(7月27日)
8:50 中山町・長崎大橋付近でNHKBSプレミアム「ニッポンぶらり鉄道旅」の取材
9:50 長崎大橋の船着き場から2日目のスタート
12:10 河北町・谷地橋に到着、昼食
13:20 谷地橋から再スタート
15:00 村山市・碁点橋に到着

2日目の出発前にNHKBSプレミアムの番組「ニッポンぶらり鉄道旅」の取材に応えるカヌーイスト(8月14日午後7時半から放送予定)

記念写真を撮影した後、一斉にスタート

朝日町のマスコットキャラクター、桃色ウサヒもカヌーに挑戦 (防水タイプじゃないので、ちょっと心配?)
.JPG)
中山町の三郷堰では、水量が少なくて魚道を通れないため、いったん下船しました
《後援団体》
国土交通省山形河川国道事務所▽山形県▽東北電力?山形支店▽朝日町▽大江町▽西川町▽寒河江市▽中山町▽河北町▽天童市▽東根市▽村山市▽山形カヌークラブ▽大江カヌー愛好会▽山形県カヌー協会▽美しい山形・最上川フォーラム
《ウェブサイト、ポスター、横断幕》
ウェブサイト制作 コミュニティアイ(成田賢司、成田香里、栗原一弘)
ポスター制作 若月印刷(高子あゆみ)▽横断幕揮毫(きごう) 成原千枝
《協力》
最上川三難所舟下り・船長 関 勇喜
《取材》
カヌー専門誌『カヌーワールド』 西沢あつし
NHKBSプレミアム『ニッポンぶらり鉄道旅』 クリエイティブネクサス・ディレクター 笠原正己
*放送予定:8月14日(木)午後7時半、8月16日(土)午前7時45分
《リンク》次のウェブサイトやウェブアルバムでも紹介されています(青い文字をクリックしてください)
朝日町公式ホームページの「まちの写真館」
桃色ウサヒのコーナー
塚本雅俊さんのウェブアルバム
《この記録ページの写真撮影》
1日目=佐久間 淳(最上堰の写真は塚本雅俊)
2日目=橋本 蕗 (三郷堰の写真は塚本雅俊)
*メールマガジン「小白川通信 16」 2014年8月6日
前回の「小白川通信」で真珠湾攻撃をテーマにし、当時のルーズベルト米大統領は事前に攻撃計画を知っていたにもかかわらず、現地の司令官たちに知らせず、日本軍の奇襲を許したという、いわゆる「ルーズベルト陰謀説」を扱いました。そして、こうした陰謀説について「断片的な事実を都合のいいように継ぎはぎした、まやかしの言説で、もはや論じる価値もない」と書いたところ、旧知の研究者から「違います。陰謀説は否定のしようがないほど明らかです」とのメールが届きました。
びっくり仰天しました。門外漢ならいざ知らず、彼はアメリカ外交や国際政治の専門家です。そういう研究者の中にも「陰謀説」を信じている人がいるとは・・・。これでは、高校の歴史の授業で「陰謀説」を事実として教える教師が出てきても不思議ではありません。メールには「スティネットの『真珠湾の真実』と藤原書店から出た『ルーズベルトの戦争』を読むことをお薦めします」とありました。不勉強でどちらも読んでいませんでしたので、取りあえず、『真珠湾の真実』(文藝春秋)を読んでみました。

著者プロフィールによれば、ロバート・B・スティネットは1924年、カリフォルニア州生まれ。アジア太平洋戦争では海軍の兵士として従軍、戦後は同州のオークランド・トリビューン紙の写真部員兼記者として働き、本書執筆のために退社、とあります。さらにBBC、NHK、テレビ朝日の太平洋戦争関係顧問とも書いてありました。米国の情報公開制度を利用して機密文書の公開を次々に請求し、入手した膨大な文書をもとにして書かれた本であることが分かります。労作ではあります。
しかし、じっくり読めば、専門家とは言えない私ですら、いたるところに論理の飛躍と「都合のいい事実の継ぎはぎ」があることが分かります。例えば、米国が日本海軍の作戦暗号(いわゆるD暗号)をどの時点で解読できるようになったのかについて。スティネットは「日本海軍の暗号が解読できるようになったのは開戦後の1942年春から」という定説を否定して、「1940年の秋には解読に成功していた」と主張しています(『真珠湾の真実』p46)。真珠湾攻撃は1941年12月ですから、その1年も前から解読できていたと主張しています。そして、その有力な根拠の一つとして、フィリピン駐留米軍の無線傍受・暗号解読担当のリートワイラー大尉が海軍省あてに出した手紙(1941年11月16日付)を収録しています(同書p498)。
その手紙には「われわれは2名の翻訳係を常に多忙ならしめるのに十分なほど、現在の無線通信を解読している」という記述があります。なるほど、これだけを取り出せば、「米海軍は真珠湾攻撃の前にすでに日本海軍の作戦暗号を解読していた」という証拠のように見えます。けれども、暗号解読の歴史を少しでも学んだことのある人なら、日本海軍は当時、主な暗号だけでも10数種類使っていたこと、そのうちで秘匿度の弱い暗号(航空機や船舶の発着を伝える暗号など)が解読されていた可能性はある、といったことを知っています。ですから、この手紙の内容だけではどの暗号を解読するのに『多忙』なのかは不明で、重要な作戦暗号が解読されていたことを裏付ける証拠にはなりません。
細かい注釈をやたらと多く付けているのも、この本の特徴の一つです。第2章の最後の注釈には「米陸軍参謀総長ジョージ・C・マーシャル大将は1941年11月15日にワシントンで秘密の記者会見を開き、アメリカは日本の海軍暗号を破ったと発表した」とあります。これも作戦暗号の解読に成功していたことを印象づける記述ですが、「秘密の記者会見」の開催を裏付ける証拠や会見内容を詳述する資料はまったく示されていません。都合のいい断片的な事実、あるいは事実と言えるかどうかも怪しいようなことを散りばめて、「日本海軍の作戦暗号は真珠湾攻撃の前に解読されていた」と印象づけようとしています。

米国による日本海軍の暗号解読については、すでに専門家の手で信頼できる著書がいくつも出版され、日本語にも翻訳されています。解読の全般的な歴史については『暗号の天才』(新潮選書)や『暗号戦争』(ハヤカワ文庫)、解読にあたった当事者の本としてはW・J・ホルムズの『太平洋暗号戦史』(ダイヤモンド社)、解読された側からの本としては長田順行の『暗号 原理とその世界』(同)があります。いずれの本も「米国は開戦前に日本外務省の暗号を解読していたが、日本海軍の作戦暗号を解読することはできていなかった」ということを物語っています。
この『真珠湾の真実』には暗号解読に限らず、外交官や諜報機関がもたらした情報も含めて、これまでの研究を覆すような事実は何もありませんでした。だからこそ、この本が1999年に出版された時、米国の主要な新聞や雑誌は書評で取り上げなかったのでしょう。上記の『暗号戦争』の著者デイヴィッド・カーンは「始めから終わりまで間違いだらけ」と酷評したと伝えられています。ただ、陰謀説が好きな人は多いようで、アメリカでも日本でもよく売れました。とりわけ日本では、京都大学の中西輝政教授が巻末に解説を寄せ、「ようやく本当の歴史が語られ始めた」と激賞したこともあって、よく売れたようです。著名なジャーナリストの櫻井よしこ氏も「真実はいつの日かその姿を現す」と褒めそやし、来日した著者のスティネットと対談したりして、販売促進に貢献しています。
前回の通信で「陰謀説がなぜ消えないのか、不思議でなりません」と書きましたが、ようやく理解できました。この本をはじめ、この10数年の間に出版された陰謀説を唱える本がよく売れ、広く読まれた結果と考えるべきなのでしょう。暗然たる思いです。「真実」という言葉をうたい文句にして、ウソを広める本。それを支える人たち・・・。この本の原題は『Day of Deceit』(欺瞞の日)ですが、邦訳を『欺瞞の書』とすれば、ぴったりだったでしょう。この本については、現代史家の秦郁彦氏や須藤眞志氏らが『検証・真珠湾の謎と真実』(中公文庫)という本を出し、徹底的な批判を加えています。これはしっかりした本です。むしろ、こちらを読むことをお薦めします。
そして、あらためて思い知りました。前回の通信で紹介したゴードン・W・プランゲの著書『真珠湾は眠っていたか』(1?3巻、講談社、原題:At Dawn We Slept)はなんと奥深く、誠実な本であることか。彼の死の翌年(1981年)に出版されたこの本の第1巻「まえがき」に、弟子たちは次のように記しているのです。
「ゴードン・プランゲ教授は、自身の言葉が最終的な決着をつけたという印象を与えることを欲しなかった。(将来)自分こそ『真珠湾の残された最後の秘密』を知っており、読者にそれを提供するのだと主張するような人があれば、それはペテン師か自己欺瞞に陥っている人なのである」
(長岡 昇)
日本海軍の空母艦載機の写真:Source
http://images.china.cn/attachement/jpg/site1004/20110810/001372acd73d0fac71124e.jpg
*メールマガジン「小白川通信 15」 2014年7月18日
山形大学で現代史の講義をして学生たちと問答をしていると、時々、「アレッ」と思うことがあります。アジア太平洋戦争中の「暗号解読」をテーマに講義した際にも「アレッ」がありました。聴講している学生の半分近くが「真珠湾攻撃=ルーズベルト陰謀説」を歴史的な事実として受けとめていることが分かった時です。「高校の歴史の授業で先生にそう教わりました」という学生までいました。これは由々しきことです。なぜ、こうした陰謀説が若い人の間でこれほど広がっているのでしょうか。
ルーズベルト陰謀説の概要は次のようなものです。
「米国のフランクリン・ルーズベルト大統領は1940年の選挙で『欧州での戦争には加わらない』と公約した。一方で、前年からドイツと戦争になっていた英国や日本と戦っていた中国からは参戦を迫られ、ジレンマに陥っていた。このため、日本が真珠湾を攻撃することを事前に知っていたにもかかわらず、これを現地ハワイの司令官たちに知らせず、あえて日本軍に奇襲させた。それによって、米国の世論を厭戦(えんせん)から参戦へと劇的に変えた」

炎上する戦艦ウェストバージニア
この説明の前段は間違いなく歴史的な事実です。ですが、後段の「ルーズベルト大統領は日本軍の真珠湾攻撃を事前に知っていた」という部分は事実ではありません。少なくとも、知っていたことを裏付ける資料や信頼できる証言はありません。むしろ、「知らなかった」ことを示す資料が時を経るにつれて増えている、というのが現実です。
もちろん、ルーズベルト大統領は諸般の事情から「日本との戦争は避けられない」と考えていたと思われます。大統領だけでなく、日米双方の指導者の多くが当時そう考えていたはずです。が、そのことと「日本軍が真珠湾を攻撃することを事前に知っていた」ということとは、その意味がまったく異なります。
大統領が事前に「真珠湾への攻撃計画」を知るとすれば、それは「外交官や諜報機関が人的な情報源から得た情報」か「日本の暗号を解読して得た情報」のどちらかを通してしかありません。前者については次のような事実があります。
「1941年1月、アメリカのグル―駐日大使は旧知のペルー駐日公使から『日本は真珠湾に対する大規模な奇襲攻撃を計画している』との情報を得て、これを暗号電報でワシントンに送った。米国務省はこれを海軍省に送り、ハロルド・スターク海軍省作戦部長はこれを海軍情報部に送った。情報はさらにハワイの米太平洋艦隊司令官、キンメル大将に伝えられた」(学習研究社『歴史群像 太平洋戦史シリーズ? 奇襲ハワイ作戦』p52から)
後者の「暗号解読による情報」については、次のような事実があります。
「1944年の大統領選挙でルーズベルトの四選を阻むために立候補した共和党のトマス・E・デューイは『アメリカを戦争に引きずり込むことを狙い、日本の暗号を解読して日本の企図を知っていたにもかかわらず、彼は犯罪的怠慢によって何も対策を講じなかった』とルーズベルトを非難した」(デイヴィッド・カーン『暗号戦争』p190)
これらはいずれも確かな事実です。これだけを取り上げれば、「ルーズベルト陰謀説」を裏付ける材料のようにも思えます。が、両書の著者はこうした事実に加えて、次のような事情を添えて、ルーズベルト大統領が真珠湾攻撃を事前に知っていた可能性を否定しています。つまり、グル―駐日大使がこの電報を送った1941年1月の時点では、日本海軍の内部ですら真珠湾を攻撃することはまだ決まっておらず(実際の攻撃は同年12月)、それは巷の「風説の一つ」に過ぎませんでした。数ある噂の一つとして伝えられたのであり、米海軍内部でもそのように扱われ、大統領の執務室に届いて検討された形跡はまったくありません。こうした情報はもし本当であれば、次々に補強する情報が集積されるものですが、補強するものはありませんでした。共和党大統領候補のデューイの非難にしても、暗号解読の実態を知らず、政敵攻撃の材料として「激しい表現」を使ったに過ぎません。その証拠に、デューイは米陸軍参謀総長の懇切丁寧な説明を受けた後は、こうした非難をしなくなりました。
にもかかわらず、米国では戦後も「ルーズベルト陰謀説」を唱える人が少なくありませんでした。その代表格が歴史学者のハリー・エルマー・バーンズです。彼は同じような説を唱える研究者とともに、米国の歴史学会を二分する論争を繰り広げました。そして、その論争は1981年にメリーランド大学の歴史学教授、ゴードン・W・プランゲの著書『At Dawn We Slept』(邦訳『真珠湾は眠っていたか』、講談社)が出版されるまで続いたのです。この本によって、ルーズベルト陰謀説は学問的に葬り去られた、と言っていいように思います。

ゴードン・W・プランゲ教授
ゴードン・W・プランゲの生涯は「研究者の執念とはかくもすさまじいものか」と思わせるものがあります。1937年、27歳の若さでメリーランド大学の歴史学教授に就任。戦争勃発に伴って海軍の士官になり、戦後は日本を占領したマッカーサー元帥の戦史担当者として日本に駐在し、真珠湾攻撃やミッドウェー海戦の研究にあたりました。マッカーサーは戦史スタッフとして100人の要員を抱えていたとされ、プランゲはその責任者でした。日本に滞在している間に、彼は真珠湾攻撃時の連合艦隊首席参謀、黒島亀人や航空参謀、源田実ら200人を超える関係者にインタビューし、焼却を免れた機密資料など膨大な文書を集めました。そして、米国に持ち帰り、メリーランド大学の教授として復職してからも研究を続けました。戦勝国の人間だからできたこととはいえ、戦後日本の戦史研究とは質、量ともに桁違いの研究です。プランゲは1980年に没し、前述の著書はその死の翌年、彼の弟子たちによってまとめられたものです。米歴史学会で長く続いた論争に終止符を打つのに十分な内容の本でした。「ルーズベルト陰謀説」は、断片的な事実を都合のいいように継ぎはぎした、まやかしの言説であることが明らかにされたのです。
もっとも、そのプランゲですら、米国による日本の暗号解読がどのようなものだったのか、その実態について詳しく叙述することはできませんでした(そのへんが「ルーズベルト陰謀説」がブスブスとくすぶり続けた理由の一つなのかもしれません)。英国と米国は戦後も、暗号解読の実態をひた隠しにしました。何も明らかにしないことが一番良かったからです。その一端が明るみに出たのは、1974年に英国の空軍大佐、F・W・ウィンターボザムが『ウルトラの秘密』を刊行してドイツの暗号を解読していたことを暴露し、1977年に米国の暗号解読専門家ウィリアム・フリードマンの伝記(邦訳『暗号の天才』、新潮選書)が出版されて、日本の暗号解読の内実が紹介されてからでした。そのころには、晩年のプランゲに自分でそうした事実の検証をする余力は残っていませんでした。
けれども、この両書の出版を機に公開された機密文書の研究が進むにつれて、プランゲの著書の声価はますます高まりました。米国は戦争のかなり前から日本外務省の暗号をほぼ完全に解読していたこと。しかし、外交暗号をいくら解読しても日本軍の攻撃企図を推し量ることはできず、日本の力をあなどって真珠湾の奇襲を許してしまったこと。屈辱感に駆られた米国は軍人はもちろん、数学・統計学・言語学・日本文化研究の俊英を総動員して日本軍の暗号解読に取り組み、開戦から半年ほどで日本海軍の作戦暗号を解読することに成功したのです。それが、ミッドウェー海戦で米軍に勝利をもたらし、連合艦隊の山本五十六司令長官を待ち伏せ攻撃で死に至らしめる結果をもらたしたことは今ではよく知られています。
私は「陰謀説などすべてバカバカしい」などと言う気はありません。中には、隠された真実を鋭くえぐり出すものもあります。ですが、その多くは時の審判に耐えられず、消えていきます。「ルーズベルト陰謀説」などもそうした言説の一つで、私は「もはや論じる価値もない」と考えています。なのに、なぜ消えないのか。高校の歴史の授業にまで登場してしまうのか。不思議でなりません。
悪貨が良貨を駆逐するごとく、読みこなすのに時間がかかる良書は時に悪書に駆逐されてしまうのでしょうか。手軽で百花繚乱のインターネット空間では、悪書の方が強い影響力を及ぼすのでしょうか。若い人の間では、活字離れが急速に進んでいます。私の授業を聴いている学生の中で、新聞を日常的に読んでいる者はゼロです。彼らは情報の多くをネットを通して得ています。ならば、ネットの世界で「良書を広げ、悪書を駆逐する戦い」に乗り出すしかありません。
(長岡 昇)
*真珠湾攻撃の写真のSource:http://konotabi.com/japamerican/ja3pharbor/japame3pearlhar.htm
*メールマガジン「小白川通信 14」 2014年7月5日
英国の豪華客船、タイタニック号が初航海で氷山にぶつかって沈没したのは、今から102年前のことです。この船は当時の技術の粋を集めて造られ、不沈船とうたわれていました。氷山との衝突から3時間足らず、救援の船も間に合わないうちに沈んでしまうなどとは誰も考えていなかったのです。このため、救命ボートは乗客乗員の半数の分しかありませんでした。女性と子どもを優先せざるを得ず、男性の多くは船と運命を共にしました。
この悲劇を題材にして、各国の国民性を皮肉るジョークがあります。いくつかのバージョンがありますが、私が聞いた中で一番エスプリが効いていると思ったのは、二十数年前に白井健策氏から聞いたものです。当時、朝日新聞のコラム「天声人語」を執筆していた白井氏は、新入社員の研修会で講演し、こんな風に語りました。

タイタニック号は沈み始めていた。けれども、救命ボートが少なくて、男性の乗客には海に飛び込んでもらうしかなかった。豪華客船の甲板で、クルーは男たちに声をかけて回った。フランス人には、少し離れたところにいる妙齢の女性を指さしながら、耳元でささやいた。「あのお嬢様が飛び込んでいただきたいとおっしゃっています」。フランス人は「ウィ」とうなずき、飛び込んだ。ドイツ人には集まってもらい、号令をかけた。「気をつけ!飛び込め!」。彼らは次々に飛び込んでいった。
アメリカ人には「正義のために飛び込んでください」と頼むだけでよかった。彼は明るく「OK」と返事してダイブした。イギリス人には、慇懃な態度で「紳士の皆様には飛び込んでいただいております」と告げた。彼は黙って飛び込んだ。日本人の番になった。乗組員は彼の耳元に手をかざしながら、小さな声でつぶやいた。「みなさん、飛び込んでいらっしゃいますよ」。周りの様子を見ながら、彼もあわてて飛び込んでいった。
* * *
研修会場はドッと沸きました。でも、会場を包んだ爆笑には、もの悲しさが混じっていた――新入社員のチューター役で参加していた私にはそう感じられました。それぞれの国民性をこんな風に描くのはかなり乱暴なことですが、特徴を見事にすくい取っている面もあります。だからこそ、みな身につまされて、笑いの中にもの悲しさが入り込んでしまったのでしょう。
安倍政権が戦後の歴代内閣の憲法解釈を変え、現在の憲法9条の下でも集団的自衛権を行使することができるとの新解釈を閣議決定しました。「国権の最高機関」である国会での審議もろくにせず、憲法と法律の解釈について最終的な判断を下す立場にある裁判所をも置き去りにして、行政府の長が事実上の憲法改正にも匹敵する判断を下してしまいました。
何のために「三権分立」という大原則があるのか。法の支配を確固たるものにするためには「法的な手続きをきちんと踏むこと」が極めて重要なのに、三権分立も法の支配をも蹴散らしての閣議決定です。一国の首相が憲法をないがしろにし、憲法の柱である大原則を踏みにじっても恬(てん)として恥じない。なのに、たいした騒動にもならず、野党から大きな抵抗も受けない――国外の人たちの目には、何とも不思議な光景に映っていることでしょう。

古巣の朝日新聞は、安倍首相の解釈改憲を阻止しようと、大キャンペーンを繰り広げました。大げさに言えば、死にもの狂いの紙面展開をしています。けれども、私にはその主張がひどく虚ろに響いて聞こえます。「安倍政権は憲法を自分たちの都合のいいように解釈している」と非難していますが、実は朝日新聞もまた長い間、自分たちに都合のいいように憲法を解釈し、それを擁護し続けてきたではないか、と思うからです。
焦点の憲法9条は戦争放棄をうたった第1項に続いて、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と規定しています。しかし、日本は朝鮮戦争をきっかけに再軍備に踏み切り(というより占領軍にそうするように命じられて再軍備し)、着々と軍備を増強して今日に至っています。日本の自衛隊はアジア有数の戦力を保持しています。いろいろと言い繕う人もいますが、素直に見れば、どう考えても自衛隊は軍隊であり、その保持している力は戦力です。この矛盾を解消するためには憲法を改正するか、自衛隊は違憲だとして解散させるか、どちらかしかありません。
今の日本で「自衛隊は違憲だから解散させるべきだ」と考える人は、ほんの一握りでしょう。私も「自衛隊は戦後の日本社会でしかるべき役割を果たしてきた」と受けとめています。解散など論外です。従って、矛盾を解消するためには憲法を改正して、自衛隊をきちんと位置づけるしかないと考えています。それほど多くの文言を入れる必要はありません。憲法第9条の第2項を「陸海空軍その他の戦力は、必要最小限度の戦力を除いて、これを保持しない」と改正すれば足りるし、それで十分なのです。あの戦争が終わって、間もなく70年。ほかの部分も、時代にそぐわなくなったところは素直に改正すればいいのです。
そのうえで、「では必要最小限度の戦力をどこまで行使するのか」「個別的自衛権に限るのか、集団的自衛権の行使まで広げるのか」を議論すればいいのです(私は「集団的自衛権を行使する必要などない」と考えています)。
けれども、朝日新聞は「今の憲法を一字一句変えてはならない」という厳格な護憲派の立場を変えず、維持しています。「自衛隊は自衛のための必要最小限度の武装組織であり、軍隊ではない」という説得力の乏しい論理を展開してきました。その論理に立って「自衛隊は違憲ではない」と主張しています。これもまた、安倍政権とは別の立場からの「解釈改憲」ではないのか。
憲法を都合よく解釈してきた者が、別な風に憲法を都合よく解釈する者を非難する――それが朝日新聞と安倍政権の対立の構図であり、だからこそ、その主張が虚ろに響くのだ、と思うのです。そして、保守派の改憲論と朝日新聞的な護憲論の対立から透けて見えてくるのは、双方とも立派なお題目を唱えてはいるが、どちらも憲法をないがしろにしているという現実ではないのか。
一番哀れなのは、日本国憲法なのかもしれません。言葉を発することができるならば、憲法は小さな声でこうつぶやくのではないか。「みなさん、私をもてあそぶのはもうやめてください。私の肩には、みなさんの未来がかかっているんですよ」
(長岡 昇)
7月26日(土)と27日(日)に予定通り、「出直し第2回最上川縦断カヌー探訪」を開催します。山形県はこの7月、昨年に続いて豪雨に襲われ、深刻な被害が出ましたが、その後、天候が回復し、最上川は穏やかな流れを取り戻しました。
2012年7月の第1回最上川縦断カヌー探訪では、1泊2日の日程で山形県長井市?朝日町?中山町の53キロを下りましたが、昨年の大会中止を踏まえて開かれる2014年カヌー探訪は、同じく1泊2日の日程で朝日町?中山町?村山市の48キロで開催します。26日(土)午前10時半、朝日町雪谷のカヌー公園を出発して午後、中山町・長崎大橋の最上川せせらぎ公園に到着。翌27日(日)は午前10時に中山町・長崎大橋を出発し、午後、村山市の碁点橋にゴールする予定です。参加者は37人(山形県内19人、県外18人)の予定です。主催はNPO「ブナの森」(事務所・朝日町、長岡昇代表)です。
2012年7月の第1回最上川縦断カヌー探訪では、1泊2日の日程で山形県長井市?朝日町?中山町の53キロを下りましたが、昨年の大会中止を踏まえて開かれる2014年カヌー探訪は、同じく1泊2日の日程で朝日町?中山町?村山市の48キロで開催します。26日(土)午前10時半、朝日町雪谷のカヌー公園を出発して午後、中山町・長崎大橋の最上川せせらぎ公園に到着。翌27日(日)は午前10時に中山町・長崎大橋を出発し、午後、村山市の碁点橋にゴールする予定です。参加者は37人(山形県内19人、県外18人)の予定です。主催はNPO「ブナの森」(事務所・朝日町、長岡昇代表)です。
*メールマガジン「小白川通信 13」2014年6月9日
涙があふれ
滂沱(ぼうだ)と流れ落ちる時
それは悲しみ
涙が一筋
頬をそっと伝う時
それは哀しみ
悲劇はこの世の闇の深さを人に伝え
哀歌は人の心にひそむ切なさを刻む
悲しき者は
過ぎ去った日々を悔やみ
哀しき者は
残された日々を慈しむ
悲しみは沈み、哀しみはたゆたう

ミヤコワスレ(都忘れ) 山形に帰郷して知った花の一つ
1980年代、駆け出しの記者だった頃、朝日新聞の国際面に「喜怒哀楽」というタイトルの付いた記事がありました。各地の特派員が1ページをほぼ全部使って、任地で起きた政変や事件、事故、あらゆることの背景と意味を随時、ゆったりと綴る欄でした。地方支局で小さな事件や事故を追いかけ、他社にスクープされた特ダネの追っかけ記事をデスクに怒られながら書いていた頃、よく読んでいました。大好きな欄でした。
なのに、外報部に配属されて自分が国際報道に携わるようになった時には「喜怒哀楽」はもう消えていました。代わりに登場したのは、物事が動いたら即刻、息せき切ってその背景を書き飛ばす「時時刻刻」や、片肘張った感じの「特派員報告」という大型解説記事でした。どちらも好きになれないタイトルでしたが、「喜怒哀楽」のようなゆったりした記事を書くことは、もう時代が許さなくなっていたのかもしれません。
さらに時が過ぎ、今の記者はより一層スピードを求められるようになりました。なにせ、インターネット用に「電子版」の記事も出稿しなければなりません。「時時刻刻」というタイトルもあまり見かけなくなりました。時計の長針と短針どころか、秒単位のスピードを求められる時代、タイトルそのものが時代にそぐわなくなってしまったからでしょうか。
それでも、かつての「喜怒哀楽」というタイトルには愛着が尽きません。この世のすべての感情と情念が込められているように感じるからです。ちっとも理性的でなく、しばしば感情をほとばしらせてしまう人間としては、「それ以外に何があると言うのか」と言いたくなってしまうのです。
この四文字熟語に接するたびに心にうずくものもあります。「どの国のことを報じる時でも、喜怒哀楽をバランス良く伝えなければならない」と頭では分かっているのに、私が書く記事はいつも「怒」と「哀」の記事ばかりでした。持ち場が血なまぐさいことの多いアジアだったということを割り引いても、人々の喜びと楽しみに目を向けることのできない記者でした。どんなに悲惨な戦地にも、普通の人々の普通の暮らしがあり、その暮らしの中で喜びを見出して生きる人がいるのに、その姿を記事にする力量を欠いていました。
「育ちが暗いから」と自分で言い訳をしてきましたが、やはりそれでは済まされないものがあります。その罪滅ぼしの気持ちもあって、「喜怒哀楽」の中で一番好きな「哀」という言葉のことをずっと考えてきました。メールマガジン「小白川通信」の再開にあたり、その罪滅ぼしの営みの断片を掲げます。
*2月のメールマガジンで小保方さんの「万能細胞」発見を激賞したら、その後、雲行きが怪しくなり、ついには「懲戒処分」が取り沙汰される事態になってしまいました。それで気落ちしたこともありますが、細かい体調不良もあって配信を休んでいました。ようやく「書く元気」を取り戻しました。また、ポツポツと書いていきます。
(長岡 昇)
◇2004年10月23日付 朝日新聞別刷りbe「ことばの旅人」
人は時に、奇妙な願望を抱く。
私の場合、それは「灼熱の砂漠に身を置いて、どれだけ耐えられるか試してみたい」というものだった。
北インドの農村で、熱風に身をさらしながら働く村人たちを見た。湾岸のクウェートでは、摂氏52度の熱波を体験した。その度に深いため息をつき、気候の穏やかな国に生まれ育った幸せをかみしめた。
同時に、これほど過酷な土地にとどまり生きてきた人々に、畏敬の念に似たものを覚えた。何という強靭さ。自分にも、そのかけらのようなものがあるのだろうか。試してみたい、と思った。
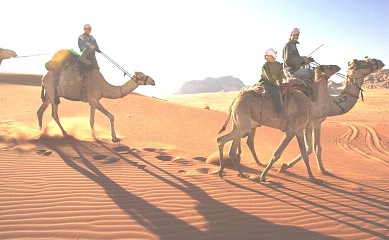
ヨルダンのワディ・ラムの砂漠を行く遊牧民の兄弟(撮影:千葉 康由)
脳裏に浮かんだのは、学生のころに見た映画「アラビアのロレンス」に出てくる、あの砂漠だった。
第1次大戦中、オスマン・トルコの支配下にあったアラビア半島で、アラブ人の反乱が起きる。トルコと戦っていた英国は、T・E・ロレンスを連絡将校としてアラブ軍に送り込み、反乱を支援した。
映画はこの史実を基に、ロレンスを「砂漠の英雄」として描いたものだ。デビッド・リーン監督、ピーター・オトゥール主演で1962年に封切られた。
遊牧の民ベドウィンのラクダ部隊に加わり、ロレンスは砂漠に繰り出す。海に面したトルコの要衝アカバを背後から衝(つ)くためだ。
砂漠を800キロ余りも踏破し、アカバまであとわずかという時、彼は部下のガシムがいなくなっていることに気付く。ラクダから落ち、砂漠に置き去りにされてしまったのだ。
助けに行こうとするロレンスを、ベドウィンたちは「引き返せば死ぬ」「ガシムは寿命が尽きたのだ」と押しとどめ、こう言う。「これは定めなのだ」
(It is written.)
ラクダを鞭打ちながら、ロレンスは言い返す。「この世に定めなどない」
(Nothing is written.)
ロレンスはガシムを救い、ベドウィンの信頼を勝ち取る。アカバを占領し、さらにダマスカスへ。映画は、西欧の理性がイスラムの宿命論を乗り越え、反乱に勝利をもたらす物語として展開する。
だが、それは実像に虚像を塗り重ねた物語だ。虚像を剥ぎ取った後に見えてくるものは、歴史の激流に翻弄(ほんろう)され、魂を引き裂かれそうになりながら苦悩した一人の人間の孤独な姿ではないか。
論説委員・長岡昇
「砂漠の英雄? とんでもない。彼は典型的な二重スパイだ」
エジプトの日刊紙アルワフドのタラビリ編集長は、ロレンスが果たした役割を端的な言葉で表現した。
「英国は第1次大戦を中東進出の好機とみなした。ロレンスは情報将校として、ある時は母国のために、別の時にはアラブのために動いた。ユダヤ人によるイスラエル建国の手助けまでした」
当時の英国の「三枚舌外交」は、つとに有名だ。フランス、ロシア両国と密約を交わし、トルコ敗北後の領土分割を決めた。一方で、アラブ人には独立を、ユダヤ人には国家建設をそれぞれ保証した。
両立し得ない約束を交わしたのは、戦争に勝つことが至上命題だったからだ。英国の振る舞いは、中東に紛争の火種をばらまく結果になった。イラクの国境線が引かれたのはこの時だ。パレスチナ人が父祖の地を失った遠因もここにある。
だが、こうした外交を進めたのは当時の政治家や高官だ。戦場にいたロレンスにその責めを負わせるのは酷だろう。
彼自身、密約を知って苦しみ、戦後もアラブとの約束を果たすために奔走した。富も名誉もすべて拒み、名前まで変えて世捨て人のような後半生を送ったのは、それでも、自責の念をぬぐい去ることができなかったからかも知れない。
ロレンスが多くの足跡を残したヨルダンでも、厳しい声を聞いた。
歴史家のスレイマン・ムーサ氏は「ロレンス伝説は欧米メディアが作り上げたものだが、本人にも自分の役割を過大に売り込む癖があった。アカバ攻略は自分の発案、というのもその一つだ」と言う。
ヨルダン南部の砂漠ワディ・ラムを駆け抜け、トルコ軍を撃破するアカバのシーンは、映画のハイライト部分だ。ロレンスの著書にも「私の奇襲作戦」とある。
しかし、ムーサ氏は多数の証言を根拠にこれを否定する。「ロレンスがアラビア半島に来たのは、反乱が始まって半年もたってからだ。トルコを攻める戦略はすでに決まっていた。アカバ攻略を立案したのは、アウダ・アブ・ターイだ」
映画では、彼は金目当てにロレンスの部隊に合流した、がさつな族長として描かれている。ムーサ氏の言う通りなら、アウダの一族にとっては受け入れがたい扱いだろう。
アカバで、アウダの孫アキフ氏(51)に会った。建設会社を経営する孫は、やはり「祖父の描き方は不満だ」と言う。
ところが、ロレンスに対しては、先の2人とは正反対の考えを口にした。「彼はベドウィンの真の友だ。われわれのために戦い、血を流した」
チャーチル首相はロレンスを「現代に生きた最も偉大な人物」とたたえた。一方、作家のリチャード・オールディントンは「大うそつきの変質者」と切って捨てた。英国での評価は二つに割れ、その死から70年近くたっても定まらない。それはアラブから見ても同じなのだった。
有名になった後、ロレンスは知人に「忘れたい。そして忘れられたい」と語った。自分ですら自分が分からない。他人に分かるはずがないではないか−−そう叫びたかったのではないか。
アカバを去り、その東にあるワディ・ラムの砂漠に向かった。広い枯れ谷の両側に、ほぼ垂直の岩山が連なる。ロレンス伝説が広がるにつれて、世界遺産のペトラ遺跡と並ぶヨルダンの観光名所になった。
酷暑期に入ったせいで、砂漠は閑散としていた。2頭のラクダを仕立て、通訳を伴って砂漠に乗り出した。1泊2日。ラクダ使いがずっと付き添い、さらに2人のガイドがトラックで先回りして食事と泊まりの支度をしてくれる。
飲み水にも事欠いたロレンスの砂漠行とは比べようもない。それでも、照りつける太陽は変わらない。少しだけだが、「灼熱の砂漠」を体験できた。
この日は砂漠の奥からの熱風ではなく、かすかに海風が吹いていた。それが驚くほど、つらさを和らげてくれた。
夜、ラクダ使いのイブラヒム君(19)が「テントを使わないで、砂の上に寝具を敷いてそのまま寝たら」と勧める。素直に従い、満天の星を眺めながら寝入った。
かすかな風。きらめく星。小さな恵みが砂漠では大きな慰めになることを知った。ロレンスは砂漠に、どんな慰めを見いだしていたのだろうか。
****************************************
アラビアのロレンスの関係先を「訪ねる」
ヨルダン南部の砂漠ワディ・ラムまでは、首都アンマンからデザート・ハイウエー経由で車で4時間ほど。アカバからは約1時間。アンマンの旅行会社に頼めば、砂漠の旅をアレンジし
てくれる。交渉次第で、1時間の旅から1週間の旅まで可能だ。
ワディ・ラムの砂漠は砂がそれほど厚くないため、四輪駆動車でも走り回ることができる。ラクダより料金は高い。ラクダを使った今回の旅は1泊2日で1人分が310米ドル(約34
000円)だった。
暑さのピークは8月。その前後もかなり暑い。ラクダに乗ると、慣れていないこともあって体がこわばる。跳びはねるように揺れるので、尻に負担がかかる。記者は50キロほど乗った
が、最後に肛門部から出血した。
夜は冷えるので長袖を用意した方がいい。場所によっては毒蛇やサソリ、毒グモがいるので、野営する場合には注意が必要だ。ガイドによると、観光客に被害が出たことはないものの、
数年前に遊牧民が毒グモに刺されて死亡したという。
近くにローマ時代の遺跡とされるペトラ遺跡がある。
****************************************
「読む」
ロレンスの自伝的著作「知恵の七柱」は平凡社の東洋文庫から翻訳出版されている。その簡約本「砂漠の反乱」(角川文庫)は品切れ。
ロレンスをめぐる論争などを知るには牟田口義郎著「アラビアのロレンスを求めて」(中公新書)が有益。スレイマン・ムーサ著「アラブから見たアラビアのロレンス」(中公文庫)は
欧米とは違う視点からロレンスの実像に迫る。
ロレンスを日本に初めて紹介した故中野好夫の著書に「アラビアのロレンス」(岩波新書)があるが、品切れ。
****************************************
ことばの出典
トマス・エドワード(T・E)・ロレンス(1888ー1935年)は、英国貴族と駆け落ちした女性家庭教師との間に生まれた。オックスフォード大学在学中に中東を徒歩旅行し、卒論「十字軍の城砦(じょう・さい)」を執筆。卒業後はトルコとシリアの国境地帯で古代遺跡の発掘調査にあたった。
第1次大戦の勃発に伴い陸軍に入り、1916年末から2年間、アラブの反乱に加わった。米国の従軍記者ローウェル・トマスが彼を「英雄」として報じ、米英両国で記録映画を交えた講演会をしたことから一躍、有名になった。
アラブの反乱について、ロレンスは著書「知恵の七柱(なな・はしら)」で詳しく書いており、本文で紹介した「ガシム救出」のエピソードにも触れている。ただし、著書には「この世に定めなどない」という表現はない。この表現は映画「アラビアのロレンス」にあり、日本語の字幕では「運命だ」と訳している。
日本学術会議の大川玲子・特別研究員(コーラン学)によると、アラビア語の動詞「カタバ」には「書く」という意味に加え、「運命をあらかじめ定める」という意味もある。詳しくは次のページの「学ぶ」の項を参照。
写真はジェレミー・ウィルソン著「アラビアのロレンス」(新書館)から。
****************************************
「学ぶ」
大川玲子氏の新著「聖典『クルアーン』の思想」(講談社)によると、イスラム教では、全知全能の神が最初につくったものは「筆」と解釈されている。神は、その筆で天地創造から世の終末まですべての事を「天の書」に記し、次に天地創造にとりかかった、と解釈する。
神が預言者ムハンマドに下した啓示は「天の書」の内容であり、すべてはあらかじめ定められている、という宿命論につながる。”It is written.”という映画のセリフは、以上のようなイスラムの宿命論を踏まえたものと考えられる。
*メールマガジン「小白川通信 12」 2014年2月1日
こんなに驚き、かつ勇気を与えてくれるニュースに接したのは何年ぶりだろうか。理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子さんがまったく新しい方法で「万能細胞」の作製に成功したことを伝える報道は、驚愕度において新聞の1面をデカデカと飾るにふさわしく、この国に温かい風を吹き込んだという意味において社会面にもしっくりと収まるニュースだった。小保方さんの人柄に加えて、彼女が割烹着姿で研究にいそしみ、理研がそれをとがめたりしなかったことがこのニュースをより温かいものにしているように思う。

科学誌として世界一の権威を誇る英国のネイチャー誌が2年前に彼女の論文の掲載を拒んだ際、「何百年にもわたる細胞生物学の歴史を愚弄している It derides the history of cellular biology, which goes back centuries」 と評し、2度目の寄稿でやっと掲載したことも明らかになった。そう言わしめるほど生物学のこれまでの常識を突き破る成果だった、ということなのだろうが、拒否した際の表現に、私は「欧米を先導役にして進んできた近代化と現在進行中のグローバル化にひそむ傲慢さ」を感じた。
かつて札幌で勤務していた頃(1988年)、冬に十勝岳が噴火し、北海道大学の火山学者に取材を申し込んだことがあった。定年近い老教授は素人の私が素朴な質問をしても嫌な顔ひとつせず、丁寧に火山のメカニズムを教えてくれた。そして「十勝岳の噴火はとても危険なのです」と警告した。大規模な噴火が起きた場合、山に降り積もった雪が熱で瞬時に解けて泥流となって麓の集落を襲うことがある、というのだ。実際、大正15年には巨大な泥流が発生し、144人もの住民が犠牲になっていた。
取材を終えて帰りかけた時、この碩学が口にした言葉が忘れられない。「訳知り顔でいろいろと解説しましたが、火山の活動がどういう仕組みで起きるのか、実はほとんど分かっていないのです。40年近く、生涯かけて研究してきました。世界中の火山学者と一緒に。でも、分かっているのはせいぜい1割くらいでしょうか」。寂しげではあったが、誠実な人柄をしのばせる言葉だった。
彼の言葉が強く印象に残ったのは、同じ頃、原子力発電の取材で原子力工学の教授に会った際に、この教授もまったく同じことを言っていたからだろう。原発建設を推進する立場であるにもかかわらず、彼はこう言ったのだ。「原子力発電所をどう造れば、どういう風に発電できるかは分かっている。けれども、原子炉の中で中性子がどう動き、核分裂反応がどういう風に起きているのかはほとんど分かっていないのです」。脳死の取材で脳神経外科の教授に話を聴いた時もそうだった。彼は「脳の研究は今の科学の最先端の一つで、ものすごい数の研究者が取り組んでいますが、分かっているのはまだ10パーセントくらいでしょうか」と語った。
その後、科学はそれぞれの分野で前進した。しかし、大いなる自然と広大な宇宙の営み全体から見れば、人間が解き明かしたものはまだほんの一部に過ぎない。宇宙の始まりから現代までの歴史を綴った『137億年の物語』(文藝春秋)の著者、クリストファー・ロイドはエピローグに「壮大な物語に比べれば、人類の歴史は取るに足らない」と記した。古生物学者のリチャード・フォーティも『生命40億年全史』(草思社)を「たしかなのはただ、この先も変化は続くということのみである」という言葉で結んだ。
「数百年にもわたる細胞生物学の歴史」と言うが、その生物学が成立するまでに、名もない者たちが数万年、あるいは数千年にわたって小さな営みを積み重ねてきたことを忘れているのではないか。われわれの遥かかなたにある「何ものか」に対する畏敬の念があれば、ネイチャー誌が小保方さんの最初の論文の掲載を断るにしても、また別の言葉があったのではないか、と思うのである。
宇宙の歴史を持ち出すまでもなく、地球の歴史においてすら、人間の歴史はほんの短い間の出来事であり、近代以降など「刹那(せつな)」の出来事に過ぎない――そうした畏敬の念を持ち続ける者こそ、これからの時代を切り拓いていくのではないか。
(長岡 昇)
* * *
小保方晴子さんは中学2年の時にとても深い内容の読書感想文を書いています。毎日新聞主催のコンクールで千葉県教育長賞に輝きました。1月30日の毎日新聞公式ホームページに掲載された全文を以下に転載します。
* * *
「ちいさな王様が教えてくれた 大人になるということ」
−松戸市立第六中学校 2年 小保方 晴子
私は大人になりたくない。日々感じていることがあるからだ。それは、自分がだんだん小さくなっているということ。もちろん体ではない。夢や心の世界がである。現実を知れば知るほど小さくなっていくのだ。私は、そんな現実から逃げたくて、受け入れられなくて、仕方がなかった。夢を捨ててまで大人になる意味ってなんだろう。そんな問いが頭の中をかすめていた。でも、私は答えを見つけた。小さな王様が教えてくれた。私はこの本をずっとずっと探していたような気がする。
「僕」と私は、似ているなと思った。二人とも、押しつぶされそうな現実から、逃げることも、受け入れることもできずにいた。大人になるという事は、夢を捨て、現実を見つめる事だと思っていた。でも、王様は、こう言った。「おまえは、朝が来ると眠りに落ちて、自分がサラリーマンで一日中、仕事、仕事に追われている夢をみている。そして、夜ベッドに入るとおまえはようやく目を覚まし一晩中、自分の本当の姿に戻れるのだ。よっぽどいいじゃないか、そのほうが」と。私はこの時、夢があるから現実が見られるのだという事を教えられたような気がした。
小さな王様は、人間の本当の姿なのだと思う。本当はみんな王様だったのだと思う。ただ、みんな大人という仮面をかぶり、社会に適応し、現実と戦っていくうちに、忘れてしまったのだと思う。
いつか、小さな王様と「僕」がした、永遠の命の空想ごっこ。私は、永遠の命を持つことは、死よりも恐ろしい事だと思う。生きていることのすばらしさを忘れてしまうと思うからだ。それに、本当の永遠の命とは、自分の血が子供へ、またその子供へと受けつがれていくことだと思う。
王様は、人は死んだら星になり、王様は星から生まれると言っていた。私は、王様は死んでいった人々の夢であり願いであるような気がした。人間は死んだら星になり、王様になり、死んでから永遠がはじまるみたいだった。こっちの永遠は、生き続ける永遠の命より、ずっとステキな事だと思う。
「僕」は王様といっしょにいる時が、夢なのか現実なのかわからない。と言っていたけれど、きっと「僕」は、自分の中の現実の世界に小さな王様を取り入れることによって、つらい現実にゆさぶりをかけ、そこからの離脱を見い出しているのだと思う。
「僕」は王様にあこがれているように見えた。つまり、自分の子供時代に、ということになるだろう。私も、自由奔放で夢を見続けられる王様をうらやましく思う。でも、私はそう思うことが少しくやしかった。なぜなら自分の子供時代を、今の自分よりよいと思うということは、今の自分を否定することになるのではないかと思ったからだ。まだ私は、大人ではない。なのに、今から、自分を否定していては、この先どうなっていってしまうのだろうと思って恐かった。でも、また一方では、「前向きな生き方」や「プラス思考」などというものは、存在しないようにも思えた。
夢には、二面性があると思う。持ち続ける事も大切だが、捨てる事もそれと同じ位大切な事なのだと思う。どちらがいいのかは、わからない。また、私がこの先どちらの道に進むのかも。ただ、言えることは、みんなが夢ばかり追いかけていては、この世は成り立たなくなってしまうということだけなのだと思う。
私は王様の世界より、人間の世界の方がスバラシイこともあると思った。なぜなら、人間には努力で積み重ねていくものがあるからだ。子供のころから培ってきたものは、なに物にも勝る財産だと思うからだ。王様の世界では生まれた時が大人だからそれができない。
絵持ちの家に行ってから消えてしまった王様は、もう「僕」の前には現れないと思う。なぜなら、もう「僕」には王様の存在の必要がなくなったからだ。私と「僕」は答えを見つけた。「夢を捨ててまで大人になる意味」の答えを。それは、「大人になる為に、子供時代や夢がある」ということだ。最後の赤いグミベアーは、さようならのメッセージなのだと思う。
これからは「僕」も私も前を向いて生きていけると思う。王様は、まだ答えの見つからない、王様がいなくて淋しがっている人の所へ行ったのだろう。
私は本の表紙に名前を書いた。王様が教えてくれた事を大人になっても忘れないように。
王様の存在が夢か現実かはわからないが、この本を読む前の私にとっては夢であった。しかし、少なくとも、今の私の心の中で生きている王様は現実だということは紛れもない事実である。
世の中に、ちいさな王様と友達になる人が増えたら明るい未来がやってくる。そう思ってやまないのは私だけではないのであろう。
<アクセル・ハッケ著(那須田淳、木本栄共訳)「ちいさな ちいさな王様」(講談社)>
*メールマガジン「小白川通信 11」 2013年11月23日
「攻めの人」は守りが弱い、とよく言われる。攻撃することが習性になってしまい、防御のスキルが磨かれないからだろう。どうしても脇が甘くなってしまう。医療法人「徳洲会」グループから5千万円の資金提供を受けたことが明るみになり、その釈明に追われる猪瀬直樹・東京都知事の言動を見ていると、あらためて「脇が甘いなぁ」と感じる。
猪瀬氏が徳洲会から5千万円を受け取ったのは去年12月の東京都知事選の前だ。この問題が明るみに出た昨日(11月22日)の昼過ぎ、彼は報道陣に対して、徳洲会の徳田虎雄・前理事長から「資金提供の形で応援してもらうことになった」と述べ、都知事選の応援資金であったことを認めた。

険しい表情で報道陣の質問に答える猪瀬直樹東京都知事(中央)=東京都庁で11月22日午後、矢頭智剛撮影(毎日新聞ニュースサイトから)
猪瀬氏の顧問弁護士は仰天したことだろう。これが事実なら、猪瀬氏には直ちに「公職選挙法違反(虚偽記載)」の容疑がかかる。選挙運動に使った金は自己資金であれ、借入金であれ、すべて収支報告書に記載して選挙管理委員会に報告しなければならない。都知事選後に猪瀬陣営が提出した収支報告書には、そのような記載はないからだ。私が顧問弁護士なら、「5千万円は選挙とは何の関係もないことにしなければならない」と強く助言する。
実際にそのような助言があったかどうかは知らない。が、猪瀬氏はその後、一転して「選挙資金ではなく、あくまで個人としての借り入れでした」と言い始めた。「お金の目的」を変更することで追及を免れようとする作戦に切り替えたようだ。なるほど、個人の間の金の貸し借りは犯罪ではない。金額はともかく、世間ではままあることだ。
しかし、今度は別な問題が浮上する。猪瀬氏は以前から徳洲会の徳田虎雄氏と面識があったわけではなく、都知事選に出馬することが決まってから「ご挨拶」にうかがったのだという。最初のご挨拶で5千万円も「無利子で貸してくれた」徳田氏の意図は何だったのか。意図も目的もなく大金をあげたり、貸したりしてくれる人はこの世に存在しない。今度は、東京都内で病院や介護施設を経営する徳洲会グループがそれを合理的に説明しなければならなくなる・・・・。真実を隠そうとすると、このように次から次に別の問題が噴き出してきて、収拾がつかなくなるのが世の常だ。
ジャーナリストとしての猪瀬氏の仕事には、目をみはるものがあった。『天皇の影法師』や『ミカドの肖像』では、権力の周りでうごめく政治家や政商の姿を活写した。『昭和16年夏の敗戦』では、無謀な戦争に突き進んでいった東条英機をはじめとする当時の指導者たちの愚かさを赤裸々に描いた。その輝きが、政治の世界に自ら飛び込んでいってからは色あせてしまった。しどろもどろの言動を見るにつけ、ドロドロした政界の闇の深さを覗き見るような感慨にとらわれる。
5千万円という金額で思い出すことがある。私が新聞記者になって4年目の1981年1月に発覚した「千葉県知事の5千万円念書事件」である。当時の千葉県知事、川上紀一(きいち)氏が東京の不動産業者、深石鉄夫氏から知事選の資金として5千万円を受け取り、「貴下の事業の発展に全面的に協力するとともに利権等についても相談に応じます」との念書を交わしていた、という事件だ。
川上氏は念書の存在を認め、知事を辞任するに至るのだが、深石氏は千葉県だけで仕事をしていたわけではない。私の初任地の静岡でも「彼が政治家に5千万円を渡した」という情報が飛び込んできた。「調べろ」との支局長の指示を受けて、私は静岡県の伊豆半島にある大仁(おおひと)町に走った。
当時、大仁町では日産自動車が大規模な福利厚生施設を建設する計画を進めていた。が、なかなか前に進まない。深石氏は日産の依頼を受けて、計画を円滑に進めるために「静岡県の政界の実力者に接近、5千万円を提供した」というのが疑惑の粗筋だった。計画予定地の土地登記を調べ、日産の本社に出向き、深石氏の事務所の扉をたたいた。「政界の実力者とは静岡県知事であり、金を受け取った疑いが濃厚」との心証を得たが、物証は得られず、記事にする見通しは立たなかった。
一生懸命に取材したのに1行も書けないのは悔しい。で、ある晩、山本敬三郎・静岡県知事の私邸に夜回りをかけた。予約なしで、いきなり玄関口に立ち、「念書事件の深石氏から静岡の政治家にも5千万円渡っているという情報があります」と問い質した。「知事に5千万円渡っている」と口にしたら、名誉棄損になる。だから慎重に「静岡の政治家にも」と言葉を選んだのだが、うろたえたのか山本知事は「私は受け取ってないよ、私は」とむきになって否定するのだった。
知事サイドも必死だった。朝日新聞の取材がどこまで及んでいるのか、気になって仕方がなかったのだろう。その後、定例の知事会見があるたびに、会見後に「長岡君、ちょっとお茶でも飲みませんか」と知事から声がかかった。「五千万円問題」の潜行取材を知らない他社の記者や県庁の幹部はいぶかしがり、「あの記者は知事と特別な関係にあるらしい」と変なうわさまで立った。世の中の歯車はおかしな回り方をすることもある、と思ったものだ。

田中角栄元首相(Source:http://yoshio-taniguchi.net)
田中角栄元首相がロッキード事件で受託収賄の疑いで逮捕されたのは、これらの「知事5千万円受領疑惑」の5年前、1976年のことである。全日空の旅客機選定をめぐる大疑獄事件で、田中角栄氏が受け取ったとされる金は5億円だった。その記憶もまだ生々しく、政治通の間では「一国の総理に大事なことを頼むなら5億円、知事に頼むなら5千万円が相場」と言われていた。「なるほど、切りのいい金額だ」と、妙に納得したのを覚えている。
1980年代のバブルの時代、政治家への献金の相場は跳ね上がったに違いない。だが、バブルの崩壊とデフレを経て、献金の相場はまた、昔に戻ってしまったのかもしれない。都道府県の知事はさまざまな許認可の権限を握っている。こと許認可権に限れば、衆議院議員や参議院議員の及ぶところではない。
徳洲会グループはどのような意図、どのような目的をもって、東京都知事候補に5千万円を提供したのだろうか。それが資金供与だったのか、貸付だったのかは、さほど重要ではない。返済したかどうかも関係ない。収賄罪にしろ詐欺罪にしろ、受け取った時点で犯罪は成立しており、返済しても立件に影響はない。知りたいのは「その金の意味」であり、それが犯罪として立件できるのかどうかである。
1970年代、80年代の東京地検特捜部は実にまともで、強かった。報道機関も執拗に事実を追い続けた。それがこの国の民主主義をより良いものにした。検察の不祥事を乗り越えて「徳洲会グループの選挙違反事件」を摘発した特捜部がどこまで政治の闇を暴くことができるのか。日本のメディアが今、どれだけの強靭さを持っているのか。東京都知事の5千万円受領事件の帰趨は、それを教えてくれるだろう。
(長岡 昇)
*メールマガジン「小白川通信 10」 2013年11月10日
この春まで4年間、民間人校長として働いて気づいたことがある。それは、公務員の世界では「いかにして多くの予算を獲得し、使い切るか」が想像以上に大きな比重を占めていることである。そして、使い切ることを重ねているうちに、いつの間にか、その予算がそもそも何のための金なのか、本当に必要な予算なのかといったことを考えなくなってしまう。
「民間企業だって同じだ。予算獲得の代わりに売り上げ増に血道をあげているではないか」と反論する人がいるかもしれない。確かに似ている。事業部ごとに、獲得した予算を使い切る傾向もある。しかし、決定的に異なる点がある。それは、企業の場合、必要がなくなった事業に資金をつぎ込み続ければ経営が傾き、やがては倒産して消えていくことだ。「市場」という公平で冷酷な審判がいるのだ。政府や自治体にも議会や報道機関などのチェック機関があるが、それらは市場ほどには公平でも冷酷でもない。
一つの国やその中にある自治体においてすら、血税の使途を適正にするのは難しい。ましてや、それが世界レベルになると、もっと難しくなる。国連とその関係機関のことである。平和維持活動や難民の救済といった崇高な使命に携わっていることもあって、その無駄遣いや腐敗を追及する矛先はどうしても鈍くなってしまう。私が知る限りでは、気合を入れてこの問題に取り組んだことがあるのは、英国のBBC放送くらいだ。かつて、精力的な取材を通して国連の無駄遣いと腐敗を調べ上げ、告発したことがある。

パリのユネスコ本部(インターネット上の写真)
最近、ひどいと思うのはユネスコ(国連教育科学文化機関、本部・パリ)の無駄遣いである。世界自然遺産や文化遺産を登録して、その保存活動に力を入れたのは立派な仕事だと思うのだが、それが一段落して事業の拡大が望めなくなるや、ユネスコは「無形文化遺産」の登録事業に乗り出した。役人の世界でよく見られる「新規事業の創出」である。
2003年のユネスコ総会で「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択され、2006年に発効した。保護の対象になるのは「口承による伝統及び表現」「芸能」「社会的慣習、儀式及び祭礼行事」「自然及び万物に関する知識及び慣習」「伝統工芸技術」の五つだ。食文化も保護の対象とされ、和食も「無形文化遺産」として登録されることになった。食文化に関してはすでに、フランスの美食術や地中海料理、メキシコやトルコの伝統料理が登録されており、「和食もこれに匹敵する」というわけだ。
ひどい話である。どの国、どの民族、どの地域の人々にとっても、それぞれの食文化はかけがえのない価値を持つ。与えられた風土の中で生き抜くために、先人が知恵を重ね、涙と汗をまぶしながら育んできたものである。なのに、それに対して、国際公務員であるユネスコの職員が段取りを付け、政治家や学識者を集めて審査して格付けし、登録するというのだ。信じがたい傲慢、不遜な行為と言わなければならない。そんなことに我々の血税が政府を通して流され、費消されていいのか。

実は、早期退職する前年の2008年にユネスコから朝日新聞社に無形文化遺産に関して、「メディア・パートナーシップを結びませんか」という提案があった。いくぶん関係する部署にいた私は「そんな企画に加わるのはとんでもない。食い物にされるだけだ」と強硬に反対したが、すでに社の首脳が提携を決めた後であり、ごまめの歯ぎしりに終わった。「日本の新聞社と手を組むとしたら朝日新聞しか考えられません」とか何とか言われた、と聞いた。
日本の政府や政治家には厳しい姿勢を崩さないのに、こと国連となると、日本の報道機関は手の平を返したようになる。朝日新聞社も右ならえ、だ。古巣のことを悪く言いたくはないが、本当に情けない。社の上層部が決めたとなると、普通の記者は「批判する気概」をどこかに放り投げてしまうようだ。11月8日の朝刊2面に「無形文化遺産に和食が登録されるの?」という記事が掲載されたが、国連の広報記事と何ら変わらない。問題意識の「も」の字も感じさせない、いわゆるチョウチン記事である。日本政府のチョウチン記事は恥ずかしいが、「世界政府」とも言うべき国連のチョウチン記事は恥ずかしくないらしい。「メディア・パートナーシップ」という錦の御旗があるからか。
中華料理やインド料理、タイ料理やベトナム料理、中東やアフリカ諸国の料理・・・・。それらに比べて、フランスや地中海、メキシコやトルコ、日本の料理を先に「無形文化遺産」に登録する理由をどう説明するのか。どのような基準に基づいて、だれが決めたのか。少なくとも、それを俎上に載せ、言及するのが「健全な報道機関」というものだろう。
食文化に限らない。口承文化にしても芸能、祭礼行事にしても、数値化できないもの、言語では表現できないもの、見えない部分にこそ、深い価値があるのではないか。そこが世界自然遺産や文化遺産と質的に異なるところだ。無形の文化をどう扱うかは、それぞれの国や共同体に任せ、互いに尊重する。それで十分ではないか。
私に言わせれば、ユネスコの「無形文化遺産」事業そのものが、新しい予算の獲得という、役人が陥りがちな邪(よこしま)な考えから始まったものである。最初から無理なことを官僚の作文で味付けして始めた事業だから、ますますおかしな方向に突き進んでしまうのだ。世界自然遺産や文化遺産と違って、無形文化遺産ははるかに奥が深く、底なし沼のように事業費が膨らんでいく。それを承知で始めたのだろうから、役人の野望は恐ろしい。
(長岡 昇)
*メールマガジン「小白川通信 9」 2013年11月4日
山形の農村に住んでいても、新聞や雑誌の書評を読めば、読みたい本を探すことはできる。それをインターネットのアマゾンで注文すれば、数日後には手許に届く――と強がっているが、最近「やっぱり、身近なところに本屋さんがあるといいなぁ」と思う出来事があった。
夕方、山形市内である人と待ち合わせた。早く着き過ぎてしまい、20分ほどあったので、近くの本屋さんに入った。そこで文芸書のコーナーに差しかかった時である。まるで「オイ、俺を手に取ってみろよ」と声をかけられたように、英国の作家ジョセフ・コンラッドの『闇の奥 Heart of Darkness』(三交社)という本に吸い寄せられていった。

Joseph Conrad (3 December 1857-3 August 1924) Source:Wikipedia
まず、最初にある「訳者まえがき」を読んだ。「この小説は文学的にも思想的にもたいへん興味深い作品である。英文学史上屈指の名作とみなされ、世界の英語圏諸国の大学で、教材として、20世紀で最も多く使用された文学作品とも言われる」とある。ここで、心にピクンと来るところがあった。大学入学直後に味わった小さな挫折感と、そのトラウマがかすかにうずいたのである。
山形から上京した18歳の私は、すこぶる小生意気な若者だった。周りにも同種の人間がたくさんいた。そうした新入生の鼻っ柱をへし折ってやろうとしたのだろう。英語担当の助教授は教材として、コンラッドの短編『文明の前哨地点 An Outpost of Progress』を使った。19世紀末の作品なので、英語そのものが難しい。内容はもっと難しい。辞書で単語の意味は分かっても、何が書いてあるのか、何を言いたいのかほとんど分からなかった。
その助教授の試験問題がまた、難しかった。設問も英語で書いてあり、作品の意味が分からなければ答えられないものだった。当然のことながら、ボロボロの赤点。英語にはいささか自信があった田舎育ちの18歳はいたく傷ついた。そして、助教授の目的は見事に達成された。落第しないために、学生たちは彼の後期の授業に必死で取り組まざるを得なくなったからだ(後期の試験は極端に簡単で、平均すれば合格点を取れるように配慮してあった)。
そんな古傷を思い出しつつ、「訳者まえがき」に惹かれて購入し、読みふけった。ベルギーのかつての植民地、コンゴの奥地に小さな蒸気船(川船)の船員として赴いたコンラッド自身の体験に基づいて書かれた長編小説である。訳文が練れているので、日本語としては読みやすいのだが、内容は相変わらず難しい。正直に言えば、まだよく理解できないところがそこかしこにあった。けれども、途中でやめることはできず、読み通した。人の心の奥底を抉り出すようなところがある、と感じたからだ。
解説を読んで、英国人の作家と思っていたコンラッドが実は没落ポーランド貴族の末裔で、英国に帰化してからも英語を流暢にはしゃべれない、特異な作家だったこと、ベトナム戦争を題材にした映画『地獄の黙示録』がこの『闇の奥』を下敷きにしていたことを知った。人間とはどういう生きものなのか。文明とは何か。野蛮とは何か。『闇の奥』も『地獄の黙示録』も、それを透徹した目で見つめ、描いた作品だった。「18歳の若者に理解できないのも無理はない」と今にして思い、古傷が少し癒やされたような気がした。
翻訳した藤永茂(ふじなが・しげる)という人がまた面白い経歴の持ち主だった。1926年、旧満州の長春生まれ。九州大学理学部の物理学科を卒業し、1968年からカナダ・アルバータ大学教授、とあった。著書に『アメリカ・インディアン悲史』(朝日選書)とあるので、これも取り寄せて読んでみた。今年の9月にコロラドとテキサスを訪れ、かの地の開拓の歴史を少しかじり、インディアン殺戮のすさまじさを知ったばかりなので、興味津々で読み始めた。こちらは小説ではなく、アメリカ史における開拓とインディアンがたどった運命を綴ったノンフィクションである。「読みたい」と思っていた内容が書き記してあった。
1620年の秋にメイフラワー号でアメリカ大陸(マサチューセッツ州プリマス)に渡ったイギリスの移民101人は冬の厳しさに耐えられず、その半数が春を待たずに死んだこと。先住民であるインディアンたちは困窮する彼らを見捨てることなく、生きる術を教えたこと。翌年の秋、移民たちは豊かな収穫に恵まれ、インディアンと共に祝った。この時の祭りが「感謝祭(サンクス・ギビングデイ)」として定着していった、と記してあった。本のテーマは、藤永氏が記す次の一節に要約されている。
「飢えた旅人には、自らの食をさいてもてなすというインディアン古来の習慣にしたがって、彼(白人の入植地一帯を支配していたインディアンの指導者マサソイト)はピルグリムを遇した。しかし、ピルグリムたちの『感謝』は、インディアンの親切に対してではなく「天なる神」へのみ向けられていたことが、やがて痛々しいまでに明らかになる」(同書p29)
その後の叙述は、銃と馬を持つ欧州からの移民たちがいかにしてアメリカ・インディアンを古来の土地から追い払い、殺戮し、開拓を続けていったかの物語である。血みどろの戦いの末にインディアンたちは西へ西へと追い立てられていった。戦闘は女性や子どもをも巻き込み、しばしば虐殺の様相を呈した。その描写はおぞましいほどである。やがて、インディアンたちは「居留地」というゲットー(収容所)へと押し込められ、細々と生きていくしかなくなった。藤永氏は、アメリカ・インディアンの社会を次のように描く。
「(彼らは)自分たちをあくまで大自然のほんの一部と見做し、森に入れば無言の木々の誠実と愛につつまれた自分を感じ、スポーツとしての狩猟を受けいれず、奪い合うよりもわけ合うことをよろこびとし、欲望と競争心とに支えられた勤勉を知らず、何よりもまず『生きる』ことを知っていた人間たちの声がきこえて来るに違いない」(同書p252)

18世紀末から19世紀初めにかけてインディアン諸部族の連合を率いて白人と戦った指導者テクムセ(テカムセとも表記)S:Wikipedia
藤永茂氏は量子化学者である。その彼がなぜ、ジョセフ・コンラッドの作品と彼の思想にのめり込み、アメリカ・インディアンの運命にかくも深く身を寄せていったのか。それは、コンラッドがアフリカ・コンゴのジャングルの奥深くで観たものと同じものをアメリカ・インディアンがたどった歴史の中に観たからではないか。そして、藤永氏の言葉を借りれば、それは「現在、我々の直面する数々の問題と深くかかわっており、我々がそれによって生きる価値の体系の問題であり、人間がしあわせに生きるとはどういうことかという切実な関心事と深くかかわっている」(同書p3)からにほかならない。
19世紀のコンラッドの作品も、同じ時期にヨーロッパからの移民に追われ、死んでいったアメリカ・インディアンたちの物語も、少しも色あせることがない。なぜなら、21世紀を生きる私たちもまた、一人ひとりが同じ根源的な問いを突き付けられ、日々、選択を迫られながら生きていかなければならないのだから。
(長岡 昇)
《注》白人の西部開拓・入植に武力で抵抗したインディアン諸部族連合の指導者テクムセ(テカムセ)について詳しく知りたい方は、次のウィキペディアURLを参照してください。
▽日本語版 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%A0%E3%82%BB
▽英語版 http://en.wikipedia.org/wiki/Tecumseh
*1994年4月4日 朝日新聞夕刊(社会面)
太平洋戦争の末期、ビルマ(ミャンマー)駐留の日本軍がインド北東部の占領をめざして攻め込んだインパール作戦から、今年で50年。激しい戦闘と悲惨な退却行で命を落とした将兵は、2万人とも3万人ともいわれるが、その数すらはっきりしない。区切りの年とあって、この3月には170人近い遺族や戦友会関係者が、追悼のため相次いで現地を訪れ、インドの辺境で手を合わせた。
19940404.jpg)
野原に仮の祭壇を設け、異郷に眠る肉親に向かって手を合わせる遺族=1994年3月17日、インパール盆地北方で(撮影・長岡昇)
追悼に訪れたのは、政府派遣の慰霊巡拝団8人と全ビルマ戦友団体連絡協議会(西田将会長)の8グループ161人。遺族のひとり、大江ち江さん(69)=滋賀県高島郡新旭町=の兄達男さんは、インパール盆地の北カングラトンビで戦死した。「小隊長さんが兄の右腕だけをだびに付し、昭和22年3月に自宅に届けてくれはったんです。たまたま同じ日に、マニラで戦病死した次兄の遺骨も届きました。母は気丈な人でしたけど、その夜は白木の箱を両わきに抱きかかえて、声を上げて泣いとりました」
埼玉県北葛飾郡庄和町の名倉健次さん(61)の父平次さんは、ミャンマー国境に近いテグノパールで戦死した。砲兵部隊の兵士だった。一家は働き手を失い、当時12歳だった名倉さんが農業を継いだ。「日本は何不自由なく暮らせる、豊かな国になりました。皆様はその礎になられたのです」。インパール南のロッパチンに建設中の平和記念碑の前で、合同慰霊祭が営まれ、名倉さんは遺族を代表して、かすれ声で鎮魂の言葉を読み上げた。
インドとはいっても、インパール周辺はモンゴル系の少数民族が多数を占め、分離独立を求める武装闘争が続く。中央政府は外国人の立ち入りを厳しく制限しており、地元にとっては、日本と英国の旧軍関係者がほとんど唯一の外国からの訪問者になっている。しかし、現地を訪れる遺族も老いが進む。地元マニプール州の政府当局者は「日本の若い人たちはここに来てくれるでしょうか」と語っていた。(インパール〈インド〉=長岡昇)
<インパール作戦> 1944年3月から7月にかけて、日本のビルマ方面軍第15軍が実施したインド進攻作戦。敗色濃い太平洋戦争の戦局打開を狙って、約8万5600人の兵力(航空部隊を除く)を投入。インド北東部インパールの占領をめざしたが、英軍の反撃で敗退した。
*メールマガジン「小白川通信 8」 2013年10月25日
戦争が人の心に刻むものはかくも深く、重いものなのか。庄内町余目(あまるめ)の乗慶寺(じょうけいじ)にある「追慕之碑」の前に立つと、あらためてそう思い知らされる。

生き延びた将兵が建立した「佐藤幸徳将軍追慕之碑」=山形県庄内町余目の乗慶寺
第2次大戦の末期、旧日本軍は戦局の打開をめざして、ビルマ(ミャンマー)から英領インドの北東部に攻め込んだ。「インパール作戦」として知られるこの戦いで、各部隊は3週間分の食糧しか与えられず、「足りない分は敵地で確保せよ」と命じられて突進した。戦いは長引き、雨期が始まり、兵士は飢えと熱病で次々に倒れていった。退却路は「白骨街道」と化し、数万人が戦病死した。
この作戦を担った師団の一つを率いたのが余目出身の佐藤幸徳(こうとく)中将だった。彼は補給もせずに突撃を命じる軍上層部の対応に憤り、戦闘の最中に独断で師団の撤退に踏み切った。生還した佐藤師団長は「精神錯乱」の汚名を着せられ、ジャワ島に左遷された。戦後も、旧軍幹部から「この独断撤退によって戦線が崩壊し、作戦そのものも失敗に終わった」と指弾された。
だが、彼の下で戦った将兵は違った。「もともと成功の見込みのない無謀な作戦だった。師団長が撤退を決断したからこそ、われわれは生き延びることができた」と慕った。そして、戦争が終わって40年たってから「追慕之碑」を建立したのである。
「復員後も、幸徳さんに対する世間の目は厳しかったようです。長くかかりましたが、ようやくきちんと評価されるようになりました」と、余目の本家を継いだ佐藤成彦(しげひこ)さん(66)は語る。
トゲトゲしかった日英両国の元軍人たちの関係も変わった。長い時を経て、互いに手を差し伸べるようになってきた。佐藤師団長が取り持つ縁で、来月には庄内町の有志が訪英して元軍人やその家族と語り合う。
(長岡 昇)
(コラム「学びの庭から」はこれで終わります)
*10月25日付の朝日新聞山形県版に掲載されたコラム「学びの庭から 小白川発」(6)
* * *
短いコラムなので触れることができませんでしたが、実はニューデリーに駐在していた1994年に、私はインパールを訪れたことがあります。この年は悲惨な退却行で知られる「インパール作戦」から50年の節目にあたり、日本から「これが最後の機会」と思い定めた慰霊巡拝団が多数、現地入りしました。その慰霊団への同行取材でした。
インドでは取材規制がほとんどなく、原則としてどこでも自由に行けたのですが、インパールを含む北東部については当時、内務省がジャーナリストの立ち入りを厳しく制限していました。インドからの独立を求める分離派ゲリラによる武装闘争が続き、治安がかなり悪かったことに加えて、「独立派の主張を海外メディアに報道されるのは不愉快だ」という中央政府の意向もからんでいたようです。
「これを逃せば、在任中にインパールに行く機会はない」と考え、内務省の担当者のもとに「入域許可を出してほしい」と日参し、日本大使館からも「慰霊の旅を取材するのだから便宜を図ってほしい」と要請してもらって、出発前日の夕方にやっと許可を得た記憶があります。ハンコを捺す時の内務省幹部の渋面を今でも覚えています。
その時のルポ記事は、NPO「ブナの森」の「雑学の世界」にアップしてありますが、取材にあたっては事前にインパール作戦のことをかなり詳しく調べました。文献の中で最も詳しく信頼性が高いのは、防衛研修所戦史室が編纂した『戦史叢書 インパール作戦』(朝雲新聞社)でした。英国側の資料にも丹念に当たっており、バランスがいい。作戦に従軍した朝日新聞記者、丸山静雄氏が戦後40年たってから出版した『インパール作戦従軍記』(岩波新書)も深いものを感じさせる本でした。
ただ、困ったのは、これらの本を読んでも「インパール作戦ではいったい何人亡くなったのか」が分からないことでした。作戦に参加した陸上兵力は8万5600人。そのうち、3万人から4万人前後が死亡したと推定されるのですが、判然としません。明確にズバッと書いている資料もありましたが、そちらは信頼性に難がありました。
調べるうちに、なぜ死者の数が分からないのか、おぼろげながら見えてきました。もともと弱体化していた日本軍のビルマ方面軍(作戦開始時で31万6700人)は、インパール作戦の大失敗で全体がボロボロになりました。そして、態勢を立て直すいとまがないまま、反攻してきた英軍と激戦になり、その後の「イラワジ会戦」などでさらに多くの犠牲者を出してしまいました。その結果、どの戦闘で誰が死亡したのか、生存者と死者、行方不明者の把握すらできない状態に陥ってしまった、というのが真相のようです。
アジア太平洋戦争では、あちこちの戦場で部隊が玉砕しました。ガダルカナル島やフィリピンの島々のように餓死者が大量に出た戦場もあります。だが、「戦後何年たっても死者の把握すら十分にできない」という戦場はほかにないのではないか。インパール作戦は実に悲惨でみじめな戦いでした。作戦を主導した第15軍の牟田口廉也(むたぐち・れんや)司令官は、その責任を負うどころか、戦後も「あと一息で英軍を倒せたのに、第31師団の独断撤退で勝機を逸した」と自己弁護に余念がありませんでした。それが生き残った将兵の怒りを一層かき立て、戦友会の結成や運営にも影を落としたようです。
このルポ記事の執筆から19年たって、独断撤退した佐藤幸徳中将が故郷の山形県出身であることを、今回ひょんなことから知り、コラムで紹介させていただきました。きっかけについて書くと長くなりますので、「山形大学と英国の大学との留学生交換交渉の過程で知った」とだけ記しておきます。人と人とのつながりの不思議さを感じさせられた取材でした。
*メールマガジン「小白川通信 7」 2013年10月5日
山形県の内陸部にある私の故郷の朝日町では毎日、午前11時半になるとサイレンが鳴り響く。今では「もうすぐお昼ですよ」くらいの意味しかないのだが、かつてはもっと大きな役割を担っていた。
新潟県境に近い、山あいの町である。農民は山に入って杉林の下草を刈り、山腹の畑で作物を作っていた。小さな湧き水を頼りに棚田で稲作をしている農家もあった。腕時計などない時代、農民はこのサイレンで昼近くになったことを知り、山から下りて家に戻り、昼食を摂っていた。多くの村人が自宅から歩いて30分ほどかかる山の中で仕事をしていたのである。
.jpg)
棚田では稲刈りが終わり、脱穀が始まっている=山形県山辺町大蕨で(10月5日)
経済成長が終わり、農業の担い手が減るに従って、まず山仕事が続けられなくなり、山の中の畑や田んぼが放棄された。それでも、村人たちは里山のふもとにある田んぼだけは何とか耕作し続けた。数百年にわたって人々はコメによって命をつないできた。先祖伝来の田んぼは「命」そのものだったからだ。その命も全部は守れなくなり、休耕田があばたのように広がり続けているのが今の農村の姿である。
その後、みんな腕時計を付けるようになった。農作業の多くも自宅近くの田んぼか果樹園になった。午前11時半にサイレンを鳴らす必要はもうないのだが、まだサイレンを鳴らしている。朝日町だけでなく、近隣の町でも続けているところがある。サイレンの音は変わらないのだが、かつては活力に満ちていた音が今ではやけに寂しげに聞こえる。
里山を歩き回るたびに、「もったいないなぁ」としみじみ思う。広大な山々が利用されることなく荒れ果て、山の中の畑と田んぼの多くは原野に戻ってしまった。福島での原発事故の後、人々が暮らしていた町や住宅地、田んぼが雑草だらけになっている風景が映し出され、都会の人は驚いているが、日本の農村の山はかなり前から同じような状態になっていた。全国あまねく、そんな風になったので、誰も気にしなかっただけだ。
4年前に新聞社を早期退職して故郷に戻ってから、ずっと「この里山をなんとか活用できないものか」と思ってきた。そして最近、同じような思いを抱いている人が大勢いて、「里山を基盤に暮らしを立て直す試み」を始めていることを知った。日本総合研究所の藻谷(もたに)浩介氏とNHK広島取材班の共著『里山資本主義』(角川ONEテーマ21)に教えられた。この本はもちろん、「農村での自給自足を旨としていた昔に帰れ」などと呼びかけているわけではない。その訴えはもっと深い。
商人が財を蓄えて経済を引っ張る商業資本の時代から産業革命による工業化を経て、資本主義は「カネがカネを生むマネーの時代」に入って久しい。その最先端を走っているのがアメリカの資本主義である。1%の金持ちが多くの富を集め、普通の人との極端な「富の分配の格差」をなんとも思わない。それどころか、「才覚のある人間が多くの報酬を受け取るのは当然のこと。それを非難するのはただのやっかみ」と公言してはばからない。「世界経済はアメリカの基準によって再編されるべきだ」とも唱えている。社会と経済のグローバル化は避けがたい流れなのだろうが、それがこういう人たちの論理と基準で推し進められてはたまらない。
「そんな資本主義でいいのか」と問いかけ、里山を生活の基盤とする新しい生き方を提示しているのがこの本だ。都会で猛烈社員として働いていた若者が退社して山口県の周防(すおう)大島に移って無添加のジャムを作る店を出し、繁盛している。規格外として都会に出荷できなかった柑橘類も活用しているところがミソだ。
中国山地の山あいにある岡山県真庭(まにわ)市では、建築材を作るメーカーが製材の際に出る木くずをペレット(円柱状に小さく固めたもの)にして燃やし、発電や暖房に使うビジネスモデルを確立した。工場で使う電力をすべて賄えるようになり、地元の役場や小学校の暖房もボイラーでこのペレットを燃やして行う。エネルギー源を外国に頼る必要がなくなり、そのほとんどを地元にあるもので賄えるようになった。広大な山林を背負っており、持続可能な範囲で山の資源を使っているので、枯渇するおそれもない。
広島県の庄原(しょうばら)市には、ペレットに加工するなどという難しいことをしなくても、薪を効率良く燃やす「エコストーブ」を開発することで燃料費を大幅に減らすことに成功した人たちがいる。彼らはこれを「笑エネ」と呼び、年寄りは「高齢者」ではなく「光齢者」なのだと言う。与えられた条件の中で、明るく、前向きに生きる。
実は、こうした試みをずっと前から国家ぐるみで展開している国がある。オーストリアである。本では、その実情も紹介している。欧州の真ん中で何度も戦争の惨禍をくぐり抜けてきたこの国は、エネルギーを外国に頼る危うさを自覚し、原子力発電のリスクを認識して、国内に豊富にある木材資源を最大限に活用する道を選んだ。国レベルでも実行可能な選択肢なのである。
エコノミストの藻谷氏は「経済全体を里山資本主義に転換しよう」などという非現実的なことを唱えているわけではない。社会を「マネー資本主義」一色に染め上げるのではなく、こうした「里山資本主義」もサブシステムとして採用し、強欲な資本主義にのめり込むのを防ぐバランサーとして広げていこう、と呼びかけているのだ。実に説得力のある主張である。
先のメールマガジンでお伝えしたように、山形大学と留学生の交換協定を結んでいる米コロラド州立大学と話し合うために9月下旬にコロラド州のフォートコリンズを訪れた。そこでも、この里山資本主義と重なるような企業活動が始まっていた。
同州の「モーニング・フレッシュ乳業」という会社は、無農薬の牧草で育て、成長ホルモン剤などを一切使わないで飼育している乳牛から搾乳し、それを戸別配達している。有機農業の酪農版である。別の企業は紙コップをリサイクル資源で作り、「小さな選択が社会を変える」と呼びかけていた。地元の企業とコロラド州立大学の研究者たちが手を組み、次々にベンチャーを立ち上げている。マネー資本主義の本家でも「このままでいいのか」と、造反の炎が上がり始めているのだ。
現在の米国スタイルの資本主義を「強欲な資本主義 Greedy Capitalism」とするなら、里山資本主義は「穏やかな資本主義 Green Capitalism」と呼べるのではないか。「グリーン」には「(気候などが)穏やかな」という意味もある。「持続可能で環境にやさしい」というニュアンスも含む。英語のスローガンにするなら、
From Greedy Capitalism to Green Capitalism
といったところだろうか。
こうした営みが大都市の近くではなく、地方、それも過疎と高齢化に苦しむ辺縁の地で始まり、広がりつつあるのはある意味、当然のことであり、この国の希望でもあるような気がする。なぜなら、大都市に住み、アメリカに視線を注ぎながら未来を考えている人たちには自分たちの足許で何が起きているのか、分からなくなっているからである。
2020年の東京五輪開催に血道をあげ、開催が決まったことに浮かれている人たちに言いたい。関東大震災が起きたのは1923年(大正12年)、今から90年前のことである。首都の直下には大きなエネルギーがたまっており、いつ次の大地震が起きてもおかしくない状況にある。東京の防災態勢がまだまだ不十分で、巨額の投資が必要なことについて防災専門家の間で異論はなかろう。東南海、南海地震への備えも膨大な資金を必要とする。貴重な血税は地震や津波に備え、一人でも多くの命を救うためにこそ使われなければならない。お祭りに巨費を投じる余裕が、今、この国にあるのか。
(長岡 昇)
《追伸》文中でご紹介した山口県周防大島のジャムのお店は「瀬戸内ジャムズガーデン」といいます。そのホームページも、すごく楽しそうです。店名のところをクリックして、ぜひご覧になってください。
*メールマガジン「小白川通信 6」 2013年9月30日
山形県は米国の中西部にあるコロラド州と友好の盟約を結んでいる。山形には奥羽山脈、コロラドにはロッキー山脈がある。白銀の峰々が両者を結び付けた。
山形大学とも縁が深い。コロラド州立大学と留学生の交換協定を交わしており、この5年間で9人の山大生が留学した。もっとも人気のある大学の一つである。留学した学生たちはどんな暮らしをしているのか。実情を知り、州立大学の教職員との交流を深めるため、同州フォートコリンズにあるキャンパスを訪ねた。

昼食後、芝生で車座になって福祉政策を論じる大学院生たち=コロラド州立大学で
すでに朝晩は冷え込みが厳しく、構内のニレの木はうっすらと色づき始めていた。学生は約3万人。山形大学の3倍以上だ。昨年度に受け入れた留学生は1500人を上回る。受け入れ数の国別順位が興味深い。1位の中国と2位インドは予想通りだが、3位がサウジアラビア、4位ベトナム、5位韓国と続き、日本はなんと6番目だ。米国全体でも似た傾向にある。これでは、日本政府としても「留学生の大幅増を」と号令をかけたくなるだろう。声を張り上げるだけではなく、渡航費用の一部を支給するなど留学の支援態勢をぐんと強化する必要がある。
留学するのは語学に自信のある学生が多いが、それでも英語で行われる講義を理解し、参考文献を読みこなすのは容易なことではない。渡米後しばらくは、大学内の語学コースで学習に励むケースが多い。3人の山大生も会話力の向上に努めていた。
学園都市のフォートコリンズは「米国で一番暮らしやすい街」と報じられたことがある。留学担当のローラ・ソーンズさんは「気候が穏やかで、犯罪も少ないからでしょう」と語った。とはいえ、この大学にも自前の警察部隊があり、銃を携行した要員が構内を巡回している。「治安の風土と感覚」が日本とはまるで異なることを忘れてはなるまい。
(長岡 昇)
*9月27日付の朝日新聞山形県版に掲載されたコラム「学びの庭から 小白川発」(5)から。見出しは紙面とは異なります。
* * *
紙幅の関係で、コラムではコロラド州立大学への留学生の国別内訳について詳しく触れることができませんでした。昨年度ではなく、最新の2013年秋学期の留学生1506人の内訳は次の通りです(大学生と大学院生の合計。3?4週間の夏季集中講座に参加した留学生も含む)。
▽中国 443人▽インド 213人▽サウジアラビア 188人▽ベトナム 57人▽韓国 50人▽リビア 42人▽イラン 30人▽オマーン 28人▽クウェート 27人▽台湾 24人▽英国 22人▽タイ 19人▽コロンビア 18人▽オーストラリア 17人▽ブラジル 17人▽マレーシア 16人▽日本 13人
(この数字はコロラド州立大学のホームページのデータから拾ったものです。ほかの国と違って、インドの留学生はほとんどが大学院生です。日本からは学部生9人、大学院生4人)

コロラド州立大学の語学(英語)コースの授業風景
この大学に留学している山形大学の学生(3人)によると、日本人留学生の数があまりにも少ないので中国や韓国、アジア・中東の留学生は不思議がっているそうです。「日本に関心を持っている留学生が多いので、日本人と知り合いになりたがっていてモテモテです」と話していました。
テキサス大学アーリントン校(州立)への留学生3556人の国別内訳は次の通りです(2012年秋学期)。
▽インド 825人▽ネパール 387人▽中国 225人▽韓国 159人▽ベトナム 146人▽バングラデシュ 98人▽ナイジェリア 85人▽タイ 46人▽台湾 43人▽メキシコ 43人。
日本からの留学生は24人。トップ10に入っていないため、順位は不明。10数位か20数位と思われます。あとで精査してみます。なお、ネパールからの留学生が飛び抜けて多いのはテキサス大学アーリントン校の近くにネパール人のコミュニティーがあり、母国から留学生を呼び寄せているから、とのことでした。
日本からのアメリカへの留学生は東部や西海岸の大学に進むケースが多いので、米国全体の留学生国別内訳では、日本の順位はもう少し上がるようです。統計がいくつかありますが、「フルブライト・ジャパン(日米教育委員会)」の調査(2011?2012年)によると、日本の留学生数は7位です。
http://www.fulbright.jp/study/res/t1-college03.html
こうした国別順位については、さまざまな受け止め方があると思いますが、若者が異なる土地で異なる文化の下で育った人々と触れ合い、学識を深めることはとても大切なことだと考えます。「米国への留学は減っているが、よその地域への留学は増えている」ということならいいのですが、そうではなく、全体として日本の若者の留学が減り続けています。若者の資質や気力の問題だけではなく、日本の社会から留学を後押ししようとする気概と活力が失われつつあるように思います。その流れに抗することはドンキホーテ的かもしれませんが、微力を尽くすつもりです。
今回の出張で、米国の大学はますます「富める者の学び舎」になりつつあることも確認できました。州立大学でも授業料は年間100万円から百数十万円と、日本の公立大学の2倍ほどです。(山形大学の学生は留学生交換協定に基く派遣のため授業料は免除)。ハーバード大学やイェール大学などのいわゆる「アイビーリーグ」の大学はすべて私立ですから、授業料はさらに高く、州立大学の数倍です。各種の奨学金制度があるとはいえ、それを享受できる人数は限られており、米国の有力大学の実態は「特権階級の子弟のための教育機関」と言わざるを得ません。
教科書代もやたらに高く、多くの大学生が入学と同時に教育ローンを組み、アルバイトに追われながら学んでいます。勉学に真剣にならざるを得ないのです。テキサス大学アーリントン校の国際教育担当者は「アメリカの大学生は入学と同時に『奴隷状態』 the beginning of slavery になってしまうのです」と嘆いていました。
日本にしろ、アメリカにしろ、また伸び盛りの国々にせよ、次の時代を担う若者をどう教育しようとしているのかをつぶさに見れば、その社会の在りようがあぶり出されてくるような気がします。
*メールマガジン「小白川通信 5」 2013年8月30日
幸せとは何だろうか。高山良二さんがカンボジアの子どもたちと一緒にほほ笑んでいる写真を見ると、そんなことをしみじみと考えてしまう。

地雷処理をしている村の子どもたちと高山良二さん=カンボジア・バタンバン州で、ソックミエンさん撮影
カンボジアは、この半世紀で最も悲惨な歴史を刻んだ国の一つである。戦乱に次ぐ戦乱。1970年代には、ポル・ポト政権の下で大虐殺があった。平和を取り戻した後も、地雷や不発弾が多数残り、苦しみ続けている。高山さんは20年前、自衛隊員として国連の平和維持活動に加わり、この国を初めて訪れた。「強烈な体験でした。45歳で人生のスイッチが入った」と言う。
定年後、今度はNPO(非営利組織)の代表として再訪し、地雷処理に取り組んでいる。6月中旬、山形大学の市民講座の講師としてお招きし、体験をお聴きした。「地元の若者を訓練して、自分たちで地雷を処理できるようにする。私が消えても続く。それが目標です」と語った。故郷愛媛県の人たちの支援を受けて、地域おこしにも力を注ぐ。井戸を掘り、学校を建て、地元産のキャッサバで焼酎も造った。
与えるだけではない。カンボジアの農村から、今の日本の姿が見えてくることもある。貧しい暮らしながら、村ではいがみ合いや言い争いがほとんどない。5人分の料理しかないところに7人がやって来ても、ちっとも慌てない。「奪い合えば足りませんが、分け合えば余りますよ」と言い、実際、最後にはいつも少し余るのだった。
そうした姿を見て、高山さんは思う。「お金の風船がどんどん膨らんで、日本は世界で2番目の金持ちになりました。けれども、私たちの心の風船はしぼんでしまったのではないか。他人を思いやり、助け合う心を忘れてしまったのではないか。しぼんだ風船を、またみんなで膨らませたい」
もう一度、写真を見る。高山さんも、子どもたちも、なんと満ち足りた笑顔だろう。
(長岡 昇)
*7月12日付の朝日新聞山形県版に掲載されたコラム「学びの庭から 小白川発」(3)
見出しは紙面とは異なります。
*高山さんが代表を務めているNPOは「国際地雷処理・地域復興支援の会(1MCCD)」といいます。
青字のところをクリックすると、ホームページに移動できます。
*メールマガジン「小白川通信 4」 2013年8月16日
もしアメリカと戦争をしたら、どうなるのか。
近衛文麿内閣の時につくられた総力戦研究所が日米の軍事力や工業力をもとにシミュレーションをし、その結果を閣僚や軍首脳に報告したのは昭和16年の夏、開戦4ヵ月前のことである。
若手の高級官僚や将校、敏腕記者ら36人の研究生が出した結論は「日本必敗」だった。「奇襲に成功すれば緒戦は勝利が見込めるものの、いずれ長期戦になる。総合的な国力の差は明らかで、物量に劣る日本に勝機はない。戦争末期にはソ連の参戦も予想され、敗北は避けられない」
報告を聞いた東条英機陸相は「実際の戦争というものは君たちが考えているようなものではない。意外なことが勝利につながっていく」といなしたが、その顔は青ざめていたという(猪瀬直樹著『昭和16年夏の敗戦』)。
歴史に照らせば、彼らの予測は驚くほど正確だった。だが、戦争への流れを押しとどめることはできなかった。そして、後の世代は、この俊英たちですら見通せなかったものがあったことを知る。その一つが軍事力や工業力にも増して「総合的な知力の差」が大きかったことである。

小白川キャンパスで現代史の講義を聴く学生たち=山形大学提供
山形大学での現代史の講義で「第2次大戦と暗号」を扱った。日本が「鬼畜米英」とさげすみ、敵性語を排斥していた時に、相手は日本語と日本文化の研究に全力を注いだ。そして、数学者や物理学者と力を合わせて日本側の暗号を解読してしまったのである。企図が筒抜けの中で戦われた戦争。しかも、日本の暗号が解読されていた事実が公表されたのは、戦争が終わって実に30年もたってからだった。
「暗号とか情報とかに関して、今の日本の力はどうなっているんでしょうか」。授業を受けた学生の一人から質問を受けた。「もちろん、昔よりずっと良くなっている」と答えたいところだが、正直に言えば、そう答える自信はまったくない。
(長岡 昇)
*8月16日付の朝日新聞山形県版に掲載されたコラム「学びの庭から 小白川発」(4)に加筆
* * *
「第2次大戦と暗号」の授業では、日本語で「暗号」と翻訳される英語にはcypher(文字のレベルで行われる置き換え)とcode (単語や語句のレベルで行われる置き換え)の二つがあること、暗号の解読ではその言語特有の使用頻度が一つの鍵になる、といった基本的なことから説き始めた。
例えば英語の場合、もっとも多く登場する文字はe(12.7%)であり、次がt(9.1%)。使用頻度がもっとも少ないのはqとzで0.1%であることが知られている。ドイツ語や日本語にもそれぞれ特有の使用頻度がある。英米は分担、協力しながらドイツと日本の暗号解読に取り組んだ。
暗号の解読にはこうした語学や文化の研究に加えて、数学や数理解析、物理や工学の英知を総動員しなければならない。英米は電気式(リレー式)の計算機を創り出して解読に使い、戦争が始まった後には真空管を使った電子計算機を発明して活用した。戦時中の暗号解読競争が計算機の性能を飛躍的に向上させ、戦後のコンピューター技術の基礎を築いたと言っていい(大駒誠一著『コンピュータ開発史』共立出版)。
英米の知力のすごさを感じるのはむしろ、戦後である。コラムでも触れた通り、彼らは日独の暗号を解読していたことを1970年代まで隠し通した。1977年に米国の天才的な暗号解読者、ウィリアム・フリードマンの伝記が出版されるに及んで、英米当局は渋々、解読作戦の概要を公表した。それによって、日本外務省の暗号はアジア太平洋戦争が始まる前から完全に解読されていたこと、日本海軍の最高機密暗号も戦争が始まって間もなく、ほぼ解読されていたことが判明した(R・W・クラーク著『暗号の天才』新潮選書)。
戦後30年余り、日本の旧軍人たちは「我々の暗号は解読されていたのではないか」「いや、そんなはずはない」といった論争を延々と続けた。そうした記録を読むと、虚しさを通り越して激しい脱力感を覚える。その後も、個別の技術や文化の面ではともかく、総合的な知力という面での差は埋まることはなかった、と考えるしかない。
学生たちの反応で興味深かったことの一つは「ルーズベルト大統領は真珠湾攻撃を事前に知っていたが、あえて目をつぶり、米国世論の怒りをかき立てる道を選んだ」という、いわゆるルーズベルト陰謀説を信じている学生が少なくなかったことである。中には「高校の歴史の授業で先生がそう言っていた」と言う者までいた。インターネット上では、いまだにこうした陰謀論が幅を利かせている。
事実を一つひとつ掘り起こしていけば、そうした陰謀説には何の根拠もないことは明らかだ。日本の外務省の暗号をすべて解読したとしても、そこには「真珠湾攻撃」といった具体的な軍事作戦のことは全く出て来ない。当時の米側の記録によれば、彼らが想定していたのは主に「フィリピンの米軍基地への奇襲」である。真珠湾攻撃の可能性に触れた断片的な情報が事前にあったことは事実のようだが、それは数多くの雑多な情報の一つであり、信憑性を高める関連情報は何もなかった。「日本海軍に真珠湾を攻撃するような力はない」と米側が油断していたのは間違いない。
暗号の講義は1回では終わらず、2回に分けて行った。「知の蓄積」という問題を考える格好の素材と考えたからである。講義の準備をしながら、暗号解読の重要な鍵の一つである「言語の使用頻度」という着想が、中東社会のイスラム研究を通して得られたことを知って、私も驚いた。イスラム教の聖典『コーラン』や預言者ムハンマドの言行録を詳細に検討するために古いアラビア語の研究が積み重ねられ、アラビア文字の使用頻度に目が向けられたのだという(サイモン・シン著『暗号解読』新潮社、p34)。
知の世界は広く、そして限りなく深い。
地域おこしのNPO「ブナの森」(山形県朝日町)は、2013年7月27、28両日に第2回最上川縦断カヌー探訪を開催すべく、準備を重ねてきましたが、山形県内で降り続く雨のために最上川が増水し、氾濫しているので、中止することを決めました。大雨のため、最上川沿いに走る国道287号線の一部で路肩が崩れるなど、交通網や生活インフラにも被害が出ています。ご了承ください。
自然の中で行うイベントですので、自然の営みに従わざるを得ません。これにめげずに、最上川を活かした地域おこしに取り組み、次回の開催をめざします。引き続き、ご理解とご支援をたまわりますようお願い申し上げます。

自然の中で行うイベントですので、自然の営みに従わざるを得ません。これにめげずに、最上川を活かした地域おこしに取り組み、次回の開催をめざします。引き続き、ご理解とご支援をたまわりますようお願い申し上げます。

大雨のため、山形県朝日町にある上郷(かみごう)ダムは5つの水門をすべて開けて放流しています(2013年7月25日朝)
*メールマガジン「小白川通信 3」 2013年6月1日
桜前線がようやく北海道の稚内に達し、かの地でも満開を迎えたという。「やれやれ」と感じ入っていたら、この山形にも、まだ桜を鑑賞できるところがあった。
西川町の月山志津(しづ)温泉である。五色沼のほとりの宿で「峰桜(みねざくら)」が咲き誇っていた。もともと高山に生える桜らしく、ハイマツに似た姿をしている。「咲き方も変わってます。東から西へと咲いていくんです」と宿の主人が言う。確かに、東向きのところはすでに葉桜、色鮮やかなのは西側だけだった。

宿の庭先で咲き誇る峰桜=5月24日、山形県西川町の月山志津温泉で
志津温泉は県内でも有数の豪雪地帯として知られるが、この冬、温泉街の人たちの心をざわつかせる出来事があった。気象庁が「青森県の酸ヶ湯の積雪が566?になった。積雪の最深記録を更新した」と発表し、これを新聞やテレビが一斉に「国内最高」と報じたからだ。
心がざわついて当然である。志津の積雪は例年、6?前後に達する。西川町の観測によれば、40年前には8?を記録した。「5?台で、何で国内最高なんだ」と言いたくもなる。気象庁に問い合わせると、担当者は次のように釈明した。「われわれはきちんと『アメダスの観測地点で記録された最深積雪を更新した』と発表したのです」
アメダスによる自動観測体制が整ったのは1970年代である。観測地点は約1300しかない。志津に限らず、全国には酸ヶ湯温泉を上回る積雪記録はたくさんある。しかし、気象庁記者クラブの面々は、そんなことは気にも留めず「国内最高」と報じた。かくして「酸ヶ湯の積雪が日本一」となってしまったのである。
志津の人たちの間から「それなら、ここもアメダスの観測地点にしてもらおう」という声が出ている。どんな形であれ、メディアで温泉の名前が報じられるのは効果抜群だからだ。もし「観測機器の設置費用も地元で負担する」と言い出したら、気象庁よ、どうする。
(長岡 昇)
*5月28日付の朝日新聞山形県版に掲載されたコラム「学びの庭から 小白川発」
* * *
山形県には市町村が35あり、すべての自治体に温泉があるのが自慢です。どこに行っても、ゆったりと湯船につかることができます。ただし、地下深く1000?も2000?も掘って、最近になってお湯が出てきた「新興の温泉」より、やはり昔からの温泉場の方が趣は深い。
そうした老舗の温泉の中でも、志津温泉は「霊峰月山」の山懐に抱かれた「地の利」に加えて、五色沼の静かなたたずまいと湖畔のブナ林が素晴らしく、私のお気に入りの温泉の一つです。首都圏からお客様を迎える時には、迷うことなく、この温泉の旅館「つたや」をお薦めしています。
山菜や蕎麦などの料理も文句なしなのですが、悩みは冬の雪。例年、6?ほどの積雪があり、吹雪の日には辿り着くのも困難ということもあります。豪雪を活かした「雪旅籠(ゆきはたご)」のイベントや春の残雪トレッキングなどの企画を立てて奮闘していますが、やはり豪雪はハンディの一つです。
せめて「豪雪を知名度アップの材料に」と思っても、気象庁のアメダスの観測地点になっていないこともあって全国ニュースにはなりにくく、青森の酸ケ湯(すかゆ)温泉の後塵を拝しているのが現実です。「及ばずながら応援したい」との気持ちで、このコラムを書きました。ぜひ、山形まで足を延ばし、月山志津温泉を訪ねてみてください。
*この冬、酸ケ湯温泉の積雪566?が「国内最高」と報じられた背景については、今年3月4日のメールマガジン「おおや通信 101」でも詳しくお伝えしました。カヌーによる地域おこしをめざすNPO「ブナの森」のホームページに掲載していますので、ご参照ください。
*メールマガジン「小白川通信 2」 2013年5月21日
学識深く、人品いやしからざる人も、あまりに深く政府や官僚と付き合うと、我を見失い、そのお先棒担ぎに堕してしまうことがある。しばしば指摘されることではあるが、その実態が赤裸々に暴露されることは滅多にない。権謀術数にたけた官僚たちが巧みに蔽い隠し、見えなくしてしまうからである。
その意味で、5月19日付の朝日新聞朝刊1面に掲載された「経産省、民間提言に関与」のスクープは、地味な内容ながら実に小気味いい、画期的な特ダネだった。読んでいない人のためにその概要を記すと、次のような記事である。
「東大総長や文部大臣を務めた有馬朗人(あきと)氏を座長とし、経団連の元会長や電力会社のトップで作る『エネルギー・原子力政策懇談会』という民間の団体が『緊急提言』をまとめ、2月に安倍晋三首相に手渡した。その提言は原発の早期再稼働を求め、原発の輸出拡大を促すものだったが、提言の骨子や素案を作ったのは経済産業省の職員だった」
もの知りの中には「政官業の癒着は今に始まったことではない。どこがニュースなのか」といぶかる人もいるかもしれない。それはその通りなのだが、癒着ぶりを事実を以って明らかにするのは容易なことではない。このスクープが画期的なのは、動かぬ事実を以ってそれを裏打ちし、報道した点にある。記事の中で、次のような証拠を突き付けているのだ。
「朝日新聞は、提言ができるまでの『骨子』や『素案』などの段階のデータを保存したパソコン文書作成ソフトの記録ファイルを入手した。ファイルの作成者はいずれも経済産業省の職員だった」
記録ファイルを突き付けられたからだろう。経済産業省資源エネルギー庁の幹部は記者に対し、資源エネルギー庁原子力政策課の職員が提言のもとになる文書を作成したことを認めた。そのうえで、「打ち合わせのメモを作ったり、資料を提供したりすることは問題ではない」と釈明している。そう言い繕うのが精一杯だったのだろう。
経済産業省の文書作成記録ファイルを見ることができるのは、経産省の中でもコンピューターのシステムに詳しく、アクセス権限を与えられたごく一部の人たちである。そのうちの誰かが新聞記者に関係ファイルを提供したのだ。どのような心境、どのような動機で提供したのかは本人しか知り得ないことである。だが、東日本大震災と福島原発事故の後の動きを見れば、想像するのは難しいことではない。
原発事故であれだけの惨事を引き起こしたにもかかわらず、政官業の中には原発の再稼働と輸出促進を求める声が渦巻き始めている。安倍政権の発足で、渦巻はますます勢いを増しそうな気配だ。経産省の中にも「心ある官僚」はいる。「これでいいのか」と思い悩んでいる人が少なからずいるに違いない。
内部の文書作成記録ファイルを新聞記者に渡すことは、形の上では国家公務員法違反になる。いわゆる「守秘義務」違反だ。発覚すれば、懲戒の対象になる恐れがある。下手をすれば、職を失う。その危険を冒してでも「全体の奉仕者であるべき公務員が『原発推進』を唱える民間団体の提言作りを後押しするのはおかしい」と考え、告発するに至った、と考えられる。
この国で生きる限り、この国の法律は守らなければならない。しかし、人には法律よりも大切なものがある。それは、自らの良心であり、「世のため人のため」という気概である。新聞記者であれ、公務員であれ、それは変わらない。ましてや、相手が「公務員は全体の奉仕者たれ」という根本を忘れて「暴走」した場合は、それを告発することこそ、人としての務めだろう。記録ファイルをメディアに渡す決断をするまでには葛藤もあったに違いない。勇気ある告発に敬意を表したい。
告発する側は、誇張ではなく、職を賭し、人生をかけて告発に踏み切る。当然、どこに告発するかも熟慮する。その告発先が古巣の新聞だったことは、掛け値なしに嬉しい。原発事故とその後の被災者の苦しみについて、「プロメテウスの罠」という連載で粘り強く書き続けていることが告発者の胸にも届いたのだ、と信じたい。
あらためて、問題の「提言」を読み、その関連の資料にも目を通してみた。提言をした「エネルギー・原子力政策懇談会」の前身は、2011年2月(東日本大震災の直前)に発足した「原子力ルネッサンス懇談会」という団体であることを知った。この団体は、原発事故後の反原発の動きに危機感を抱き、事故の1カ月後には「原子力再興懇談会、あるいはエネルギー政策懇談会などに名称変更して提言をまとめたい」と表明していた。事故収束のめども立たず、被災者が逃げ惑っている時に、もう「再興」を唱えていたのである。
その提言の内容もお粗末なものだ。官僚の「昔の歌」をなぞっているに過ぎない(官僚が下書きしているのだから当然だが)。一番大きな問題は、原発政策を進める場合、必ず立ちはだかる「放射性廃棄物の最終処分をどうするのか」という難題にまったく触れていないことである。「未来の世代」への責任をどうやって果たすのか。それに答えるどころか、触れようともしないことに、私は「人としての退廃」を感じた。そのような提言をした団体の代表を引き受け、名を連ねた人たちに憐れみを覚える。
(長岡 昇)
*メールマガジン「小白川通信 1」 2013年5月4日
日本の近代化とその後の戦争について、学校でどのように教えるべきか。論客が入り乱れて、激しい議論が続いている。
「二度と戦争を起こしてはならない。そのためには、戦争に至った道筋とその悲惨な結末をきちんと教えなければならない」とリベラル派は説く。保守派は「あの戦争は日本が生き残るための自衛の戦争だった。自分の国をおとしめるような、自虐的な教育はもうたくさんだ」と反発する。どちらに軍配を上げるべきか。
アフガニスタン戦争をはじめとして、いくつかの戦争や紛争を現場で取材した者として、私は戦争を美化する側に与(くみ)する気にはなれない。同時に、平和を唱えるだけで国際政治の厳しさに目を向けようとしない人たちにも、げんなりする。

昼休みに技を披露する山形大学ジャグリング同好会のメンバー=山大小白川キャンパスで
そもそも、近現代史は中学や高校で「きちんと」教えられているのか。歴史の授業は礼儀正しく、旧石器時代から古代、中世へと進む。そして、入試や卒業が迫る年度末になって、ようやく現代にたどり着く。教師も生徒も気はそぞろ。ほどなく卒業、である。
「侵略戦争だったか否か」の論争ももちろん大事だが、そうしたことを考えるためには、歴史の大きな流れをバランス良く理解していなければならない。とりわけ、近現代史について、事実関係を正確に把握していなければならない。教育の現場で、そういう授業が十分に行われていないのではないか。
小学校の校長を定年退職し、この春から山形大学で「グローバル世界を考える」という講義を担当することになった。現代から過去へとさかのぼる方法で、近代までの歴史を教え始めた。
1回目の授業で「アジア太平洋戦争で日本人はどのくらい犠牲になったと思いますか」と問うてみた。「20万人くらい」とある学生が答えた。首をかしげて、別の学生に振ると、「50万人」。300万人を超える日本人が命を落としたことを認識している学生は、1人もいなかった。
責めることはできない。彼らが想像力の翼を広げようとした時、その背中を押してあげなかったのは私たちではないか。
(長岡 昇)
*5月3日付の朝日新聞山形県版に掲載されたコラム「学びの庭から 小白川発」(1)に一部加筆
* * *
この春、大学に入学してきた1年生は平成6年(1994年)前後の生まれである。国際テロ組織、アルカイダが実行した9・11テロ(2001年)の頃には小学校に入ったばかり。おぼろげに記憶している学生が多少いる程度だ。

ハイジャックされた旅客機がニューヨークの世界貿易センターに激突する状況を描いたイラスト(『テロリストの軌跡 モハメド・アタを追う』草思社から)
ベルリンの壁の崩壊に象徴されるソ連・東欧諸国の体制崩壊や冷戦の終結は、生まれる前のこと。ソ連の侵攻で燃え上がったアフガニスタン戦争もベトナム戦争も遠い過去の出来事だ。ましてや、第2次世界大戦など「記憶のはるか彼方」という状態にある。
けれども、大学を卒業して社会に出て、広い世界で働くようになれば、第2次大戦や冷戦の傷跡がいたるところに残り、今なお疼(うず)いていることに気づかされる。そうしたことを大づかみに理解していないと、いらぬ誤解や摩擦を生んで苦しむことになる。
にもかかわらず、中学でも高校でも現代史はあまり丁寧に教えられていない。コラムで指摘したように、古代から順々に教えていくため、現代史の部分は卒業が迫る年度末になり、教師も生徒も息切れしてしまうからだろう。現代史そのものが歴史として定まっていない部分が多く、教えるのが難しいという事情があるにせよ、「こんな状態でいいのか」と私はずっと思っていた。
歴史教育に携わる研究者や教科書の執筆者の間では「侵略戦争か否か」や「従軍慰安婦問題」をめぐって激論が交わされているが、そもそも、より大きな事実関係をきちんと教えていないことの方がはるかに深刻で重大な問題ではないか、と私は言いたい。
第2次大戦で何があったのか。時代の激流の中で、どれほど多くの人間が命を奪われたのか。どのようにして死んでいったのか。朝鮮戦争やベトナム戦争、アフガニスタン戦争や湾岸戦争ではどうだったのか――そうした大きな流れについてのバランスの取れた教育こそ必要であり、それができて初めて、「では、これらの事実をどう受けとめるべきか」という段階に進む。それが自然であり、望ましい教え方ではないか。
この春から、私が山形大学で担当することになったのは「グローバル・スタディーズ」という新設されたコースである。グローバル化された世界で活躍できる人材を育成するのが目的で、1人でも多くの学生を海外留学に送り出すことを目指している。私はそのコースの担当教授として期限付きで採用された。
英語力の向上は、同時に採用された英国人(山形県在住)の准教授に頼る。フランス語やドイツ語、ロシア語、中国語は専門の教員がいる。私の役回りは学生たちに「海外留学に出る前に学んでおくべきこと」を示唆すること、と心得ている。まずは、学生たちの記憶にも生々しい東日本大震災と福島の原発事故のことから授業を始めた。
タイトルは「被災者への称賛と為政者への失望」。身内を失いながら、より困窮している人たちへの心遣いを忘れなかった被災者の姿に世界は驚嘆した。同時に、首相官邸や中央官庁、東京電力の面々のぶざまな対応に愕然とした。それによって炙(あぶ)り出された日本社会の特質とは何か――それを考えることから始めた。
次は、9・11テロを実行するに至ったイスラム勢力の思想。そして、冷戦後の世界を描いた「文明の衝突」論の鋭さと危うさ、冷戦の終結と社会主義諸国の体制崩壊、アフガン戦争とベトナム戦争、米ソ冷戦の実相、朝鮮戦争、広島・長崎への原爆投下、日本軍の無残な敗走(ガダルカナル、インパール)、英米による暗号解読と電算機技術の飛躍へと、時代をさがのぼっていく予定だ。
我ながら、大それた試みだと思う。おまけに、素人なりに「日本人の美意識」についても語りたいと考えている。海外で学ぶなら、現代史を知ることに加えて、「自分たちの国のユニークさと面白さ」についても考え、自分なりに語れるようになっておくことが必須、と考えるからだ。前期の講義は15回。後期も素材を変えて「無謀な講義」に挑みたい。そういう授業があっていい、と考えるからだ。メールマガジンで折に触れて発信し、みなさまからの批判と助言を仰ぎたい。
*この3月まで、校長をしていた大谷(おおや)小学校にちなんで「おおや通信」と題するメールマガジンをお送りしていましたが、勤務先が山形大学に変わりましたので、これからは大学の所在地の山形市小白川(こじらかわ)町にあやかり、「小白川通信」と改題してお送りします。
*メールマガジン「おおや通信 104」 2013年3月18日
北国にとって、3月は雪解けの月です。降り積もった雪が春の太陽に温められ、透明な水となってほとばしります。私はこの季節が一番好きです。ほとばしる水が新しい命の息吹を感じさせてくれるからです。そして、それは新しい希望へとつながっているからです。
12人の6年生のみなさん。卒業、おめでとうございます。君たちは6年間、大谷小学校に元気に通ってくれました。そして、最後の1年間は全体の大黒柱として、この学校を支えてくれました。教職員を代表して、あらためて「ありがとう」という言葉を贈りたいと思います。
一人ひとりに、はなむけの言葉を贈ります。

この春、大谷小学校からは12人が巣立っていきました。校長も一緒に卒業しました
白田凌士(りょうじ)君
東日本大震災があった2年前の秋、津波で大きな被害を受けた宮城県七ケ浜町の小学生を迎えて、大谷小学校で交流の集いが開かれました。お互いに初対面でしたから、最初はぎこちなかったのですが、君は真っ先に相手に声をかけて、その場の雰囲気を和ませてくれました。おかげで、リンゴもぎも、その後の芋煮会もとても楽しいものになりました。本当にありがとう。最初に口火を切るというのは何事につけても大変なことです。そういう自分のいいところを大切にして、大工さんになるという目標に向かって真っすぐに進んで行ってください。
白田 実(みのり)さん
あなたはとても物静かな生徒ですが、みんなのことを実によく見てくれていました。給食の配膳の時も、掃除の時も、下級生にきめ細かく気配りをしてくれていましたね。ありがとう。書道が得意で、書き初めでよく金賞を取っていました。ピアノも習っていました。そのピアノの先生がひいている姿をみて、自分もピアノの先生になることを目標にしたのですね。一歩ずつ前に進んで、その夢を実現してください。
白田知里(ちさと)さん
町の陸上競技記録会で、あなたはリレーのアンカーとして走ってくれました。青葉の中を走る姿は輝いていました。みんなに勇気を与える走りでした。学校では鼓隊の指揮者として全体をまとめ、放送委員としてみんなを引っ張ってくれました。ありがとう。お母さんもおばあちゃんも花が大好きで、将来は花屋さんになるのが夢ですね。お店を訪ねた時に思わず笑みがこぼれる、そんな花屋さんになってください。
白田好稀(よしき)君
日光と福島に修学旅行に行った時の帰りのバスのことを思い出します。君は、「ワイルドだろう?」とスギちゃんのもの真似を連発しました。バスの中は爆笑の渦でした。スポーツ少年団でバスケットの練習に励む君の姿からは想像もできない、もう一つの意外な顔を見せてくれました。「芸は身を助ける」と言います。その才能を大切にしてください。カーレーサーになるのが夢で、そのためにちゃんと勉強しますと書いていました。夢を叶えるために、その誓いを大切にしてください。
志藤 桃さん
あなたは、ニコニコしている時が本当に多かったですね。苦しい時でも笑顔を忘れず、みんなを励ましてくれました。そのえくぼに表彰状をあげたいくらいでした。ありがとう。優しい看護師さんになって患者さんを勇気づけてあげるのが夢です。優しさは折り紙付きです。一歩一歩、その夢に向かって進んでください。
志藤周平君
君の笑顔も、時には桃ちゃんに負けないくらいでした。クラス全体、学校全体をいつも明るくしてくれて、ありがとう。スポ少のバスケットの練習も一生懸命にやっていましたね。体育館でそのドリブルのうまさを見て、感心したことを覚えています。夢は美容師になって、お客さんみんなを笑顔にすること。大丈夫です。今の笑顔を忘れずに努力すれば、きっと実現できます。
白田真子(まこ)さん
あなたは、4年前に私が大谷小学校の校長として赴任した時、最初に出会った生徒でした。始業式で3年生を代表して「がんばり発表」をすることになり、その練習のために一人で学校に来ていました。あの時は自信がなさそうでしたが、今では、みんなの前で話す時にも実に堂々としています。頼もしい限りです。将来の夢は犬や猫の世話をするトリマーですね。これからも自信を持って前に進み、その夢を叶えてください。
遠藤 翼君
君は、クラスでは勉強の面でも行事でもみんなの背中を押してあげる役割を引き受けてくれました。また、縦割り班では下級生の面倒を見る班長の役割をしっかり果たしてくれました。何でも安心して任せることができる生徒でした。本当にありがとう。将来はテニスの選手になって世界の各地を訪ねたいという夢を抱いています。中学に進んでも、これまで同様、文武両道で頑張って、その夢に挑戦してください。
白田いぶきさん
5年生の秋に田んぼで稲刈りをした時のことを思い出します。みんなが戸惑っている中で、あなたはしっかりと稲を刈り、束ねていました。宿泊学習で、木をこすり合わせて火起こしに挑戦した時も、最初に火おこしに成功したのはあなたの班でした。慣れない、大変なことをする時、クラスのみんなはいつも、あなたがどうするかを見ていました。とても頼りになる存在でした。将来の夢はマンガ家。厳しい道ですが、じっくり構えて自分を磨き、夢を叶えてください。
阿部慎吾君
君は町の陸上競技記録会でも水泳記録会でも大活躍し、みんなを引っ張ってくれました。運動会でも赤組の組頭として獅子奮迅の活躍でした。ありがとう。君にはサッカーのことをたくさん教えてもらいました。地元のチーム、モンテディオ山形のことは誰よりも詳しかったですね。夢はサッカーの強い大学に入って、プロのサッカー選手になること。高い運動能力を活かしてその夢に挑戦してください。
川村優貴乃(ゆきの)さん
大谷小の体育館で剣道の練習を始めて間もない、4年生のころでした。あなたは「いくら練習しても結果が出ない」と少し悩んでいました。けれども、その後も練習を休むことはありませんでした。精進を重ね、剣道の大会で次々に優勝カップを手にするようになりました。「努力は裏切らない」ということを身をもって知ったのではないでしょうか。「剣道日本一」という目標に向かって、これからも倦(う)まず弛(たゆ)まず、研鑽を積んでください。
川村さくらさん
あなたは、クラスで一番静かな生徒でした。でも、作文を読むと、口には出さなくてもあなたがいろいろなことを深く考えていることがよく分かりました。学校文集に、おばあちゃんと黒豆を煮てお正月料理を作ったことを書いていました。優れた作文でした。これからも自分の力を信じて、文章を書き続けてください。洋服のデザイナーになるのが目標です。新しいものを生み出すという点では、文章もデザインも共通するものがあります。コツコツと努力を積み重ねてください。
在校生のみなさん
いつもみんなをリードしてくれた6年生は、今日、大谷小学校から巣立っていきます。少し心細いかもしれませんが、4月からは新しい仲間が入ってきます。その新しい仲間と力を合わせて、また「元気で楽しい学校」をつくっていきましょう。伝統というものは、そうやって少しずつ積み上げていかれるのだと思います。私も一緒に卒業しますが、新しい先生方と新しい伝統を築いていってください。
保護者のみなさま
お子様のご卒業、まことにおめでとうございます。みなさまに手をつながれて大谷小学校の門をくぐったお子様は、今や中学校の制服に身を包み、こんなに大きくなりました。それぞれ、胸にこみ上げてくるものがあるのではないでしょうか。この6年間、お子様を元気に大谷小学校に通わせていただき、本当にありがとうございました。どの子も、豊かな感受性と多様な才能に恵まれています。大らかな目で、また温かい心で、これからもお子様たちの成長を見守ってあげてください。もちろん、わたくしたちもいつまでも応援し続けます。
ご来賓のみなさま
本日はお忙しい中、大谷小学校の卒業式にご臨席たまわり、誠にありがとうございました。校長として4年間、大谷小学校を運営してまいりましたが、朝日町と北部地区のみなさまには、あらゆる局面で最大限の支援をしていただきました。あらためて、深く感謝申し上げます。
4年間を振り返ると、与えるよりも与えられることの方が多い日々でした。教えるよりも教わることの方が多い4年間だったような気がします。感謝の言葉を重ねて、卒業式のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
*3月18日、山形県朝日町立大谷小学校の平成24年度卒業式での校長あいさつ
*メールマガジン「おおや通信 103」 2013年3月15日
東京で先月、全国結婚支援セミナーという集いがあった。若者の未婚と晩婚化が深刻な問題になる中で、私たちに何ができるのか。実践例に触れ、話し合った。
このセミナーに、福島県飯舘村の菅野典雄(かんの・のりお)村長が講師として招かれた。原発事故によって家も田畑も放射能で汚染され、全村避難を強いられた村である。菅野村長は「この災害はほかの災害とはまったく違う」と切り出した。「重い軽いで言えば、津波で身内を亡くされたところの方が重い。ですが、少なくともそこではゼロからスタートできる。それに対し、私たちはこれから長い間、汚染ゼロに向かって生きていかなければならないのです」

全国結婚支援セミナーで福島県飯舘村の実情を語る菅野典雄村長(中央)
被災した人たちの心についても語った。「ほかの災害では、再建に向かってみんなで結束できる。でも、放射能災害では、みんなの心が分断されるのです。年寄りと小さな子を持つ親では対処の仕方が違う。同じ村内でも、放射線量の高い人と低い人では賠償額が異なる。分断の連続なのです」
道は遠く、険しい。けれども、菅野村長は「私たちは必ず村に戻ります。そして、先人から受け継いだものを次の世代に引き継ぎたい」と言うのだった。
あの大震災から2年。津波の傷も癒えず、原発の事故処理のめども立たないのに、円安と株高に浮かれる人たちがいる。その中に、原発政策を推進し、「日本では過酷事故など起こり得ない」とうそぶいていた人たちがいる。懲りない面々と言うべきか。いつの間にか、この国は若者が汗を流しても報われることの少ない国になってしまった。長じても、結婚と子育てをためらう社会になってしまった。
どこを変えなければならないのか。何をなすべきなのか。小学校の校長をしながら考えてきた。今月末に定年退職し、4月からは山形大学で教壇に立つ。キャンパスでも同じことを問い続けたい。
*3月15日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(12)より。写真は紙面とは異なります。4月以降は大学のキャンパスのあれこれを、月に1回のコラムでお届けする予定です。
*メールマガジン「おおや通信 102」 2013年3月7日
月に2回発行している大谷小学校の学校便り「大谷っ子」に、4年の男の子が書いた作文「お父さんの出発の日」が掲載されました。
会社勤めをしている父親がアメリカに新しくできる工場で働くために2カ月ほど出張することになり、お母さんと一緒に山形駅まで行って父親を見送った、という内容です。男の子は「見送る時は少しさびしかったです」と結んでいました。大谷小学校のような農村にある学校でも、家族が仕事や旅行で海外に行くことは、今では珍しいことではなくなりました。世界はますます狭く、身近なものになってきました。

大谷小では毎年3月にバイキング給食があります。好きなものをお腹いっぱい食べることができます
思えば、この男の子は4年前、私が校長として赴任して間もないころ、「世界はずいぶん狭くなったなぁ」と実感させてくれた生徒の一人でした。全校朝会で講話をすることになり、私は「今日は恐竜より古い時代から生きている魚の話をします」と切り出しました。すると、当時1年生だったこの生徒は手を挙げて「分かった。シーラカンスだ!」と叫んだのです。
いきなり正解を言われて、私は内心、驚いたのですが、そんな素振りは見せず、淡々と「生きた化石」と言われるこの魚をめぐる話を語って聞かせました。何億年も前の地層から化石で見つかり、とっくの昔に絶滅したと考えられていたこの魚が70年ほど前にアフリカ沖で偶然、発見されたこと。そして、1997年に今度はインドネシアの海でも見つかった、と写真も使いながら紹介しました。
講話が終わってから、私はこの生徒にそっと「どうしてすぐに分かったの」と尋ねました。答えは「お父さんにアクアマリンふくしま(水族館)に連れて行ってもらって、見てきたばっかりなんだ」というものでした。高速道路網が整備されて、今では山形県の朝日町から福島県のいわき市まで、日帰りでドライブできるようになったのです。
この次の年には、アイスランドの噴火を言い当てられました。この時も、体育館に集まった生徒に向かって「今日はヨーロッパの人たちが困っている話をします」と言っただけなのに、またもや「分かった」という言葉が返ってきたのです。この時も1年生でした。大きな噴火でしたので、テレビのニュースでも報じられていましたが、「ヨーロッパの人たちが困っている」という切り出しで、すぐに「噴火」という言葉が出てくるとは思ってもいませんでした。そこで訳を尋ねると――。
「じいちゃんがヨーロッパ旅行に行ってたんだけど、飛行機が飛べなくなって帰るのが遅くなったんだ。帰ってきてから聞いたら『おっきい噴火があったんだよ』って言ってた」

卒業まであとわずか。5年生を中心にして在校生が「6年生を送る会」を開きました
子どもたちが大人になる頃には、世界はさらに狭くなっていることだろう。その世界が身近なだけでなく、豊かで暮らしやすいものになるように、一人の大人として力を尽くしたい。
*大谷小学校の学校文集「おおや」43号への寄稿に加筆
*メールマガジン「おおや通信 101」 2013年3月4日
北国に住む者にとって、雪は「あなどりがたいもの」である。この冬も、雪下ろし中に屋根から転落したり、排雪溝に落ちたりして犠牲になるケースが相次いだ。北海道の地吹雪はもっと怖い。身動きできなくなり、助けを求めることができなければ、命を奪われてしまう。週末にそれが現実のものになった。痛ましい事故だった。
こうした事故が相次いだこともあって、雪が降らない所では「この冬は記録的な大雪だった」という印象が広がっている。そのきっかけになったのは、2月下旬にテレビや新聞がさかんに伝えた「青森県の酸ケ湯で積雪が566センチを記録した」というニュースだったように思う。「国内最高の積雪」と報じた新聞もあった。

雪に埋もれた大谷小の校舎。積雪は1メートルあまりだが、屋根からの落雪がすごい
強い違和感を覚えた。少なくとも、東北各地の積雪は去年の大雪よりはずっと少ないからである。どうしてこのような報道がなされたのか、調べてみた。すると、日本独特の制度である「記者クラブ制度」の弊害が浮かび上がってくる。
まず、一連の報道の出発点となった気象庁の発表内容である。気象庁は2月26日に「青森県の酸ケ湯の積雪が同日午前5時の時点で566センチになった」と発表し、「アメダスの観測地点で記録された最深積雪を更新した。記録的な積雪である」と付言した。発表内容そのものはもちろん事実であり、正確である。
問題は、この発表を受けて気象庁記者クラブの記者たちがどのような記事を書くかである。怠け者の記者(あるいは「忙しい」が口癖の記者)は、この発表の範囲内で要領良く文章をまとめ、デスクに送る。きっと「過去最高の積雪」と仮見出しを付けて出稿したのだろう。この時点で、正確な事実が誤報に転じる。
もう一度、発表内容に戻ってみてほしい。気象庁は注意深く、「アメダスの観測地点で記録された積雪」と条件を付けていた。この範囲での「記録更新」なのだ。アメダス(地域気象観測システム)の運用が始まったのは1974年である。観測地点が現在の約1300になったのは、その5年後の1979年だ。つまり、これ以前には別な積雪記録があるし、現在でもアメダスの観測地点以外では別な積雪記録がある、ということである。
気象庁の広報担当に電話して、「気象庁として把握している最深積雪記録は何センチですか」と尋ねてみた。答えは「伊吹山(岐阜・滋賀県境)の測候所で1927年に記録した1182センチ(11メートル82センチ)」というものだった。今回、メディアが最高積雪と報じた酸ケ湯の2倍以上である。
そんなに昔まで遡ることもない。10メートルを超える積雪はさすがに少ないが、6メートルあるいは7メートルという積雪記録は新潟や山形、秋田の豪雪地帯ならざらにある。私が暮らしている山形県朝日町の近くにある西川町では毎年、独自に積雪記録を取っている。この冬の最高記録は「月山志津(しづ)温泉の604センチ」という。町役場の職員によれば、ほぼ平年並みだ。町の記録によれば、志津温泉の積雪は1973年の800センチが最高という。

西川町の積雪表示。2月25日の志津温泉の積雪は604センチ。
西川町の職員に「青森県酸ケ湯の積雪566センチのことをどう思うか」と聞いてみた。「うちの町では多いところで5メートルくらい降るのは当たり前だから、とくにすごいとも思いません」と言う。気象庁詰めの記者はきっと、雪国で暮らしたことがないのだろう。積雪についての実感も湧かないのだろう。そうでなければ、566センチの雪を何の条件も付けずに「過去最高」と表現したりはしない。ほんのわずかの時間を割いて補足取材をすれば、566センチの持つ意味はすぐに分かるはずだ。
悩ましいのは、補足取材をして「積雪566センチはいくつかの限定条件付きの『過去最高』である」ときちんと書くと、自分の原稿のニュース価値が下がることである。なにせ、デスクや編集者は「史上初」や「過去最高」「全国初」が大好きだからだ(自分もその一人だったから、偉そうなことは言えない)。かくして、誤報が大手を振ってまかり通る。テレビや新聞への信頼感はこうして掘り崩されていくのだ、としみじみ思う。
官庁が横書きで出してきた「報道資料」をひたすら縦書きの記事にする記者のことを、新聞業界で「タテヨコ記者」と言い、そういう報道を「タテヨコ報道」と言う。自分もそういうことをしてきた覚えがある。怠惰と堕落への道であり、これに抵抗するためには相当の覚悟と努力がいる。
引退した老人の繰り言めくので、こういう事は本当はあまり書きたくない。だが、今回の酸ケ湯の最高積雪報道については書かずにはいられなかった。こんなタテヨコ報道をいつまでも続けていると、報道への信頼はますます細る。気象庁記者クラブの面々に奮起を促したい。
*メールマガジン「おおや通信 100」 2013年2月22日
災害や紛争で犠牲者がたくさん出て、食料や水が手に入らなくなった時、人はどのような行動を取るものでしょうか。やっと届いた救援物資に群がり、奪い合う。けんかも始まる。それが普通の姿でしょう。
生き残った家族を守るために、みんな必死なのです。責めることはできません。貧しい国や地域に限ったことではありません。2005年の夏にアメリカ南部がハリケーンに襲われた時にも同じことが繰り返されました。
ところが、東日本大震災の被災者はそうではありませんでした。津波で身内を失い、家を流されながら、彼らは列を乱すことなく、静かに支援物資を受け取りました。悲しみに打ちひしがれ、寒さに震えながら、隣人に手を差し伸べることを忘れませんでした。そして、その映像が世界に流れたのです。

ひな祭りの季節。大谷小には「御殿(ごでん)飾り雛」が鎮座しています。
多くの国の人々にとって、それは「世界の常識」をくつがえす振る舞いであり、姿でした。映像でこうした姿を見た人から1通の英語のメールが発せられ、インターネットで世界に広まりました。「日本から学ぶ10のこと10 things to learn from JAPAN 」というメールです。以下のような内容です。
1. 静けさ THE CALM
胸をたたいたり、取り乱したりする映像はまったくなかった。悲しみそのものが気高いものになった。
Not a single visual of chest-beating or wild grief. Sorrow itself has been elevated.
2. 厳粛さ THE DIGNITY
水や食料を求める整然とした行列。声を荒げることも粗野な振る舞いもなく。
Disciplined queues for water and groceries. Not a rough word or a crude gesture.
3. 力量 THE ABILITY
例えば、信じがたいような建築家たち。建物は揺れたが、倒れなかった。
The incredible architects, for instance. Buildings swayed but didn’t fall.
4. 品格 THE GRACE
人々は取りあえず必要な物だけを買った。だから、みんな何がしかのものを手にすることができた。
People bought only what they needed for the present, so everybody could get something.
5. 秩序 THE ORDER
商店の略奪なし。道路には警笛を鳴らす者も追い越しをする者もいない。思慮分別があった。
No looting in shops. No honking and no overtaking on the roads. Just understanding.
6. 犠牲 THE SACRIFICE
50人の作業員が原子炉に海水を注入するためにとどまった。彼らに報いることなどできようか。
Fifty workers stayed back to pump sea water in the N-reactors. How will they ever be repaid?
7. 優しさ THE TENDERNESS
レストランは料金を下げた。ATMは警備もしていないのにそこにある。強き者が弱き者の世話をした。
Restaurants cut prices. An unguarded ATM is left alone. The strong cared for the weak.
8. 訓練 THE TRAINING
老人も子どもも、みんな何をすべきかよく分かっていた。そして、それを実行した。
The old and the children, everyone knew exactly what to do. And they did just that.
9. 報道 THE MEDIA
速報に際して、彼らはとてつもない節度を示した。愚かな記者はいない。落ち着いた報道だった。
They showed magnificent restraint in the bulletins. No silly reporters. Only calm reportage.
10. 良心 THE CONSCIENCE
店が停電になると、人々は品物を棚に戻し、静かに立ち去った。
When the power went off in a store, people put things back on the shelves and left quietly.
(http://www.facebook.com/notes/xkin/10-things-to-learn-from-japan-/202059083151692)

この冬も大谷小に「ばくだん屋さん」が来て、ポン菓子を作ってくれました
私はこのメールのことをつい最近、2月10日付の毎日新聞に掲載された西水美恵子さん(元世界銀行副総裁)のコラムで知りました。大きな組織を率いた経験を持つ人らしい、力強く明晰なコラムでした。日本語訳も付いていましたが、英文を探し出して自分で翻訳し直してみました。
「褒めすぎ」のところもあるような気がします。東北の被災地ではATM荒らしもありました。保存食品の買いだめに走った人もいます。けれども、被災者の多くが信じられないような強さと優しさを見せてくれたのは確かです。同じ国に住む者ですら、目頭が何度も熱くなりました。世界各国で多くの人が被災者の姿を驚きの目で見つめたのも、分かるような気がします。
彼らはこうしたことを当たり前のことのように、淡々と成し遂げました。東北に生まれ、東北で暮らしていることを私は今、誇らしく思う。
*大谷小のPTA便り「おおや」90号に寄稿したエッセイに加筆。
*メールマガジン「おおや通信 99」 2013年2月15日
1月から2月にかけて、NHKのBSプレミアムで放送された「北の英雄 アテルイ伝」は画期的なドラマだった。アテルイとは、古代の東北に住み、「蝦夷(えみし)」と呼ばれた人たちの指導者の名前である。奈良時代から平安時代の初めにかけて、支配地を北へ広げようとした大和朝廷に対し、蝦夷は大規模な反乱を起こした。ドラマは、その史実をベースに展開する。
ハリウッドの西部劇の定番は、勇敢な騎兵隊が野蛮なインディアンと戦い、打ち負かす物語だ。そのハリウッドがインディアンを主役にした映画を作ったようなものだ。蝦夷の英雄を主人公にしたテレビドラマは初めてだろう。

朝日町の小学校スキー記録会。町内にもアイヌ語に由来するとされる地名がある
ドラマの最終回で、桓武天皇は「この国の土地も民もすべて朕(ちん)の手の中にある」と豪語する。征夷大将軍の坂上田村麻呂は投降したアテルイの助命を願うが、天皇はこれを許さず処刑を命じる。斬首の前に、アテルイは田村麻呂に問う。「帝は我等(わあら)をなにゆえ憎む。なにゆえ殺す。同じ人ぞ。同じ人間ぞ」。深い問いである。
そもそも蝦夷とはどういう人たちだったのか。岩手大学の高橋崇(たかし)・元教授は『蝦夷(えみし)』(中公新書)で「彼らはアイヌ人か、あるいは控え目にいってアイヌ語を使う人といってよいだろう」と記した。一方、秋田大学の熊田亮介・副学長は、最近の考古学の成果も踏まえて「東北にはアイヌ系の人たちもいたし、大和政権の支配地から逃れてきた人たちもいた」と、蝦夷=アイヌ説を否定する。蝦夷の実像については諸説あり、いまだに決着がついていない。
大和朝廷と戦った蝦夷の中には捕虜になり、関西や九州、四国に移住させられた人も大勢いた。文献にも、しばしば登場する。彼らはその後どうなったのか。それも歴史の闇の中に埋もれたままである。
アテルイはその闇を照らし、私たちを歴史の深みへと誘(いざな)う。
*2月15日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(11)より
* * *
蝦夷(えみし)の実像について詳しいことを知りたい方のために、ミニ解説を試みます。
私の理解では、古代の東北地方に住み、大和朝廷の支配に屈しなかった蝦夷(時に「まつろわぬ民」と表現される)については、主に四つの説があります。
(1)蝦夷=アイヌ説
コラムで引用した元岩手大学教授の高橋崇(たかし)氏が代表的な論者。同氏の著書『蝦夷(えみし)』『蝦夷の末裔』『奥州藤原氏』(いずれも中公新書)の3部作は、この立場に立つもの。とくに、最初の『蝦夷』をお薦めします。
(2)蝦夷=辺民説
秋田大学副学長の熊田(くまた)亮介氏らの説。古代東北にはアイヌ系の人たちと大和朝廷の支配地域から逃れてきた人たち、それ以外の集団などが混住していたと主張する。最近の考古学の発掘調査などを踏まえれば、蝦夷=アイヌ説では説明できないことが多すぎることを根拠にする。参考文献『東北の歴史 再発見』(河出書房新社)。
(3)蝦夷=和人説 蝦夷は辺境に追いやられた大和民族の一部であるとの説。戦前、皇国史観に立つ学者が唱えた。
(4)蝦夷=イエッタ説(これは私が勝手に名付けたものです)
大正から昭和初期にかけて、在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)が唱えた。東北の蝦夷はアイヌ系の人たちではなく、北方から日本列島に入ってきたツングース系のイエッタ民族であるとの説。学界からは異端視され、事実上、黙殺された。近年、歴史民俗学研究者の礫川(こいしかわ)全次氏が再評価し、菊池山哉の著作『先住民族と賤民族』や『蝦夷とアイヌ』の復刻版を出しました(どちらも批評社、1995年)。
個人的な感想を記せば(3)は論外、(2)は「いろいろな民族、人間集団がいた。どれが反乱を起こしたのかは分からない」と言っているだけで、学説と言えるのか疑問です。
(1)の蝦夷=アイヌ説が一番自然で説得力があると考えていますが、日本の先住民族が一つであると考える理由はなく、(4)が主張するイエッタ民族など「第2、第3の先住民族」がいて、古代の東北で混住していた可能性は十分にあるのではないか、と考えています。
また、東北の蝦夷論とは別に、(4)の菊池山哉の研究は日本の部落差別のルーツを考えるうえでも再評価されてしかるべきだ、と受けとめています。
*メールマガジン「おおや通信 98」 2013年1月18日
雪が降りしきるある日、大谷小学校の職員室で「こういう時、地元の言葉ではどういう風に表現するか」が話題になった。朝日町生まれの私は、何の疑問も抱かず「雪(ゆぎ)がのすのす降るって言うよね」と口にした。「んだね」と同郷の教師が応じた。
ところが、寒河江出身の教師は「雪(ゆぎ)がのそのそ降る、だべっす」と異を唱えた。山形市生まれの教頭と西川町育ちの事務職員も「のそのそだよねぇ」と、顔を見合わせながら言う。全員に聞いてみると、朝日町の出身者は「のすのす」、それ以外の教職員は「のそのそ」と分かれた。意外な分かれ方だった。
方言の使い方は、朝日町の中ですら異なる。置賜に近い集落では、うらやましいことを「けなり」と言ったりするが、ほかではあまり使わない。方言の分布は複雑で、その表現は実に多彩だ。
.jpg)
大雪の中、スキーを楽しむ大谷小の生徒=茂木ゆかりさん撮影
小学校ではこれまで、5年生の国語の授業で「方言と共通語」を学んでいた。「どんな方言があるのか、おうちの人に聞いてみましょう」と呼びかけると、家族との会話も弾む。楽しい授業の一つだった。
ところが、2011年度の国語の教科書(光村図書)から、「方言と共通語」という項目が消えてしまった。文部科学省はこの年から小学校の学習指導要領を改訂し、「日本の伝統と文化」を重視する方針を打ち出した。そのあおりで、一部の教科書では方言がこぼれ落ちてしまったようだ。
「方言も日本の文化の一部なのに……」。東北大学方言研究センターの小林隆教授は嘆く。「大震災の後、被災地のあちこちで復興のスローガンに方言が使われています。人々の心に寄り添い、励ます力が方言にはあるのです」
私たちは「言葉の海」に生まれ、その中で育っていく。多くの人にとって、その海で最初に出会うのは方言である。衰退しつつあるとはいえ、その豊かさに改めて目を向ける動きもある。もっともっと、大切にされていいのではないか。
*1月18日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(10)より
? ? ?
ニューデリーで特派員として働いていた頃、インドやパキスタンでよく「いくつの言葉を話せますか?」と聞かれました。北インドの知識人の場合、地元のヒンディー語のほかに、南部のカンナダ語やタミル語などを話せる人が多い。もちろん、英語も流暢に話し、さらにもう一つの外国語を話す人も珍しくない。三つ、もしくは四つの言葉を操るのが普通なので、こういう質問も自然に出てくるのです。パキスタンやアフガニスタンでも、同じような質問を受けました。
当方は、日本語のほかは下手くそな英語くらいしか話せないのですが、それではちょっと悔しい。というわけで、「山形弁ももう一つの言葉」と自分に言い聞かせ、見栄を張って「三つ」と答えたりしていました。振り返って、我ながらいじましいと思うのですが、東京暮らしが長くなったら、頼りの山形弁があやしくなってしまいました。母親からは「お前、発音(はづおん)、おがすぐなったなぁ」と言われました。
方言は語彙も発音も、実に多彩で豊かです。ズーズー弁とさげすまれた時代を経て、1980年代あたりから、見直しと復権の時代に入ったように感じていたのですが、文部科学省とそれを支える国語の専門家たちの考えはどうも違うようです。「日本の伝統と文化」にこだわるあまり、何か大切なことを見落としているのではないでしょうか。
*メールマガジン「おおや通信 97」 2012年12月20日
今の政治家はてんでダメですが、昔の政治家は例え話がとても上手でした。傑作の一つに「新聞の社説は『床の間の天井』のようなものだ」というのがあります。
その心は?「立派に作ってあるが、だれも見ない」
社説は、論理展開も書き方もそれなりに立派だが、立派すぎて面白みに欠け、これではだれにも読んでもらえないよ、というわけです。この例えを初めて聞いたのは、2001年春に朝日新聞の論説委員になって間もない頃でした。その巧みさに、自分が当事者の一人であることも忘れて、思わず「うまい!」と唸ってしまいました。
その夏、山形の実家に帰省した時に「床の間の天井」が実際、どんな作りになっているのか、のぞいてみました。確かに、人が見るところでもないのに、高級な木材を使って立派にしつらえてありました。以来、床の間のある部屋に入ると、失礼も省みず、天井をのぞく癖が付いてしまいました。どれもこれも、実に立派に作ってありました。見えないところにも贅を尽くす、日本人らしい美意識のなせるわざなのかもしれませんが、それにしても、なんとも巧みな例えです。
感心してばかりはいられません。私は職人気質の記者ですから、「ならば、のぞいてみたくなるような社説やコラムを書いてみよう」と、むきになった記憶があります。それができたかどうか、自信はありませんが、少なくともそのための努力と工夫はしたつもりです。
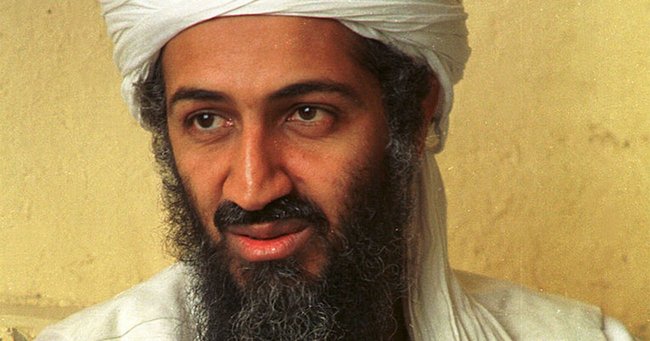
以下の文章は社説ではありません。2006年から07年にかけて、朝日新聞の論説委員室が中心になって連載した「新戦略を求めて」の一部です。9・11テロの首謀者とされるオサマ・ビンラディンのことを書くために、彼の父親の故郷を訪ね、その人脈に触れつつ、「テロとの戦いはどうあるべきか」を論じたものです。
* * *
その村は、垂直にそそり立つ岩山のふもとにあった。れんがを積み重ねた家が岩山にへばりつくように並んでいた。イエメン東部、ハドラマウト地方のルバート・バエシェン村。国際テロ組織アルカイダの首領、オサマ・ビンラディン容疑者の父親が生まれ育った村である。

「農地はなく、日雇いの暮らしだったらしい」とハッサン村長は語る。父親はこの村から石油特需に沸くサウジアラビアに出稼ぎに行き、建設会社を興して財を成した。ビンラディン容疑者は、五十数人いるとされる子どもの1人だ。古老によれば、1960年代に一族の者が村に戻って水道や道路の整備をしたことがあるが、今はだれも残っていない。父親は一度も帰省しないまま死去した。ビンラディン容疑者もこの村に来たことはないという。

インド洋の交易ルート沿いにあるハドラマウトは、昔から多くの移民を出してきた(地図参照)。ビンラディン一族のように仕事を求めて、あるいはイスラム布教のために海を渡った彼らは「ハドラミー」と呼ばれる。もっとも多くのハドラミーを抱えるのはインドネシアだ。ジャカルタにある親睦団体「アラウィー連盟」によると、300万人を上回り、イエメン本国より多い。
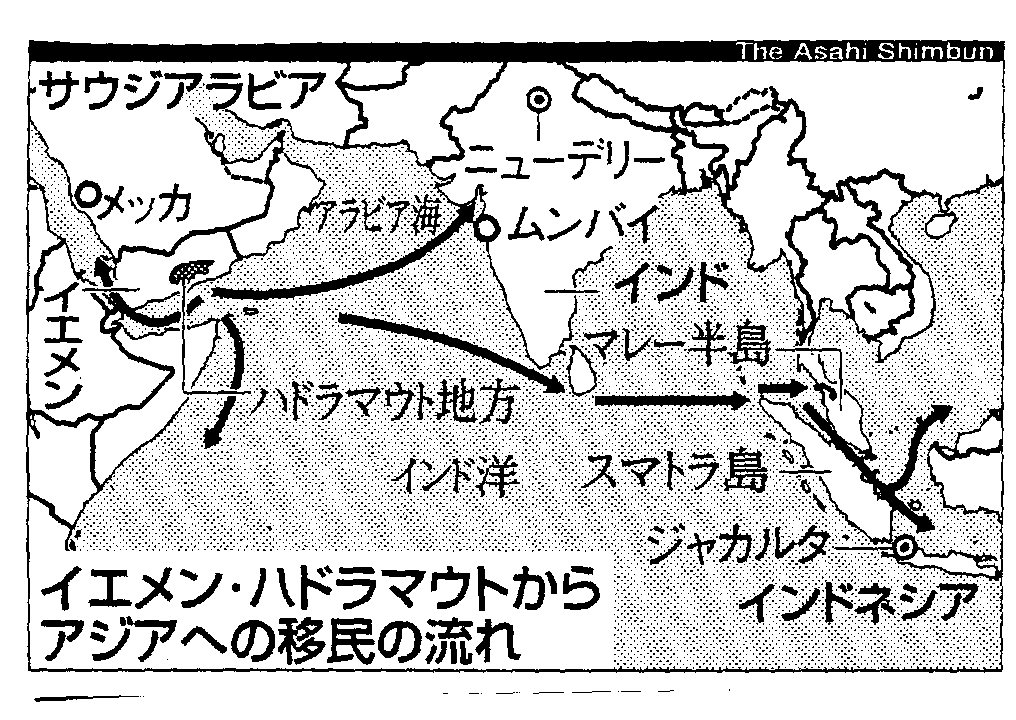
2002年のバリ島爆弾テロを皮切りに、インドネシアでは大規模なテロが続発した。これらのテロを実行した過激派「ジェマー・イスラミア」の精神的指導者、アブ・バカル・バアシル師もハドラミーである。ビンラディン容疑者と並ぶ重要人物がイエメンの同じ地方の出身者であることから、テロ対策の専門家たちはその人脈に目を向ける。
だが、過激派に立ち向かう穏健なイスラム指導者の中にも、実は多くのハドラミーがいる。インドネシアのコーラン研究の権威、クライシュ・シハブ氏もその1人だ。シハブ氏は「罪のない者を巻き込むことをいとわない無差別テロは、イスラムのいかなる教えに照らしても許されない。彼らは病める者たちだ」と断言する。
インドネシアの治安当局は、こうした穏健なイスラム指導者と連携してテロ集団の孤立化を図ってきた。同時に、オーストラリアから携帯電話の追跡装置、日本からは警察用の通信機器や交番制度のノウハウなどを提供してもらい、テロ対策に生かしてきた。
テロ対策調整官のアンシャド・ンバイ氏は「軍事的な手段でテロを封じ込めても、一時的な効果しかない。捕まえて裁判にかけ、彼らが理念の面でも誤っていることを明らかにすることが何よりも大切だ」と語る。東南アジアのテロ組織の内情に詳しい「国際危機グループ」のジャカルタ代表、シドニー・ジョーンズ氏も「法的な手続きを踏むことの重要性」を説く。インドネシアでは逮捕者の中から捜査に協力する者を獲得し、過激派の切り崩しに成功しつつあるという。
なのに、米国はキューバのグアンタナモ収容所で、多くのイスラム教徒を裁判なしで拘束し続けている。大義なき戦争を始めてイラクを内戦状態に陥れ、パレスチナ紛争を収拾するための努力も怠っている。平和を求め、イスラムの正義と理念を実現しようとする勢力を、いかに支えるか。テロとの戦いで日本に求められていることである。
*2007年1月8日付 朝日新聞朝刊 連載「新戦略を求めて」 第5章 イスラムと日本(2)から
*オサマ・ビンラディンは2011年5月2日(パキスタン時間)、パキスタン北部に潜伏していたところを米海軍特殊部隊に急襲され、殺害された。
*メールマガジン「おおや通信 96」2012年12月14日
福島県飯舘村の村民歌は「山美(うる)わしく水清らかな」で始まる。2番は「土よく肥えて人(ひと)情(なさけ)ある」と続く。この歌にある通り、うららかで美しい村だった。
その村が原発の放射能によって山も土も汚染され、全村避難に追い込まれた。村は電源立地交付金を受け取ったことも、原発の工事で潤ったこともない。難儀だけを背負い込まされた。
村内に三つあった小学校は、隣の川俣町の工場跡地に建てたプレハブの仮校舎に移転した。同じ敷地に小学校が三つもあるのは福島県ではここだけだ。校庭はテニスコート2面ほどの広さしかない。

プレハブの仮校舎で学ぶ飯舘村の子どもたち=福島県川俣町
「大変でしょうって、よく言われます。確かに、幅々とさせられないのはつらいです。でも、村の子どもたちが一緒になったからできることもある。それを生かしたいと考えています」。臼石(うすいし)小学校の二谷(ふたつや)京子校長は言う。
全村避難で村民はバラバラになった。けれども、震災前の小学生の6割、222人が福島県内の避難先からスクールバスでこの仮設の小学校に通っている。
飯舘村では汚染土などの除染作業がようやく始まったが、盗難防止のため村内を巡回している住民は浮かぬ顔で言った。
「放射線量が下がっても、村に戻るのは年寄りだけだろう。子どもがいる若い人は戻らないのではないか。このままでは、年寄りだけの村になってしまう」
村の広瀬要人(かなめ)教育長は「そうかもしれない」と認める。「それでも」と教育長は言うのである。「これだけ多くの親が覚悟を決めて『飯舘の子は飯舘の学校で育てたい』と通わせてくれている。すぐには戻れなくても、いつか、この子たちが復興の担い手になってくれるのではないか。その種をまくつもりで頑張りたい」
もっとも厳しい試練にさらされた人たちが、かくも高く希望の旗を掲げている。原発事故を防げず、右往左往した人たちよ。恥ずかしくはないのか。
*2012年12月14日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(9)
2001年3月8日の朝日新聞夕刊「らうんじ」
「都会は騒がしくて、かなわん。土をいじりながら静かに暮らしたい」
作家プラムディヤ・アナンタ・トゥールは、インドネシアのボゴール郊外の農村、ボジョン・グデに新しい家を建てた。小さな畑も付いている。近く引っ越す予定だ。
今でも1日4箱は吸うという丁字入りのたばこをくゆらせながら、老作家は「ジャワの農村で育ったから」と、土へのこだわりを口にした。2月中旬、完成間近の新居で、プラムディヤの76歳の誕生日を祝う会が開かれた。旧友らは記念に日本製の耕運機を贈った。足腰が弱って、もう自分で動かすことはできない。それでも、いとおしそうにハンドルをさすり、目を細めた。

76歳の誕生祝い。子と孫が勢ぞろいし、プラムディヤ夫妻(中央)を囲んだ/撮影・M・スルヤ氏、ボゴール郊外のボジョン・グデで
昼食後、前庭で家族の写真を撮ることになった。
傍らに白いスカーフをかぶったマイムナ夫人。夫妻を7人の娘と1人息子、孫たちが取り囲む。初めてのひ孫も長女に抱っこされて加わった。
後日、引き伸ばして手渡すと、プラムディヤはつぶやいた。
「歴史的な写真だな、これは」
すぐには意味が分からなかった。
通算16年に及ぶ投獄。釈放後も続いた当局による監視と迫害。娘のうち3人は、亡くなった前妻との子供。家族全員がそろったことは、これまで一度もなかったという。
家族が集まる。そんな当たり前のことが難しい人生だった。
* *
1965年の9月30日から10月1日にかけて、インドネシアを揺るがす大事件が起きた。共産党系の将校が部隊を率いて陸軍司令官ら6人の幹部を殺害、放送局や電話局を占拠して「革命評議会」の樹立を宣言した。
当時、陸軍戦略予備軍の司令官だったスハルト将軍はこのクーデターを鎮圧、共産党の伸長を許したスカルノ初代大統領を失脚させ、実権を握った。いわゆる「9・30事件」である。拮抗(きっこう)していた国軍と共産党の力関係は崩れ、共産党支持者に対する大虐殺が始まった。死者は、国軍の推計で45万?50万人。被害者と遺族の団体は約90万人と主張している。
プラムディヤは共産党系の文化団体の中心メンバーだった。「芸術は政治に従属すべきだ」との論陣を張り、反対勢力を激しく攻撃していた。事件後間もなく、ジャカルタの自宅で逮捕された。
「手間をかけやがって」
連行の途中、兵士はそう毒づきながら、銃床で彼の頭部を乱打した。この時から、右耳は聞こえなくなった。
刑務所を転々とした後、1969年にマルク諸島の流刑地、ブル島に送られた。荒れ地を切り開いて自分たちで収容所をつくった。食糧は自給自足。ピーク時には1万人を超える政治犯がいた。「ヘビ、ネズミ、犬……。栄養になるものは何でも食べた。必ず生き抜く、と自分に誓った」
プラムディヤは、この収容所で代表4部作を完成させた。後にタイプライターを使えるようになったが、最初のころは紙もペンもなかった。毎夕、囚人仲間に語り聞かせながら、構想をまとめていった。

流刑地ブル島の収容所でタイプライターを打つ プラムディヤ=1977年2月、当時の朝日新聞ジャカルタ支局長、増子義孝氏写す
『人間の大地』『すべての民族の子』『足跡(そくせき)』『ガラスの家』の4部作は、連続した一つの物語である。舞台は、19世紀末から20世紀初めにかけてのインドネシア。オランダの植民地支配下で苦悩するジャワ貴族出身の若者が民族意識にめざめ、独立運動に立ち上がるまでを描いている。インドネシアという国家の原型が、この時代に形成されたとみるからだ。
『人間の大地』の中で、プラムディヤはオランダによる砂糖の強制栽培の実態と農民の屈従を描いている。そして、抵抗することを忘れたジャワ人を「太陽に焼かれたミミズのような」民族と表現した。
「彼らは敗れるべく運命づけられていたのであり、その自己の運命を理解していなかったがゆえに、なおさら哀れなのです」(出版社めこん、押川典昭訳)
オランダに最後まで抵抗し続けたのはスマトラ島北部のアチェ人だった。
「彼らには守るべきもの、たんなる生や死、あるいは勝ち敗けよりもっと尊い何かがあるからです」(同)
そのアチェも武力に屈した。
人間としての誇り。それを守り抜く決意が崩れた時、人々はひれ伏し、流れに身を任せて漂い続けるしかなかった。
* *
流刑地で10年。プラムディヤは1979年末に釈放された。最初にブル島に送り込まれ、最後に釈放された政治犯の1人だった。
「逮捕の理由を説明されたことは一度もない。もちろん、裁判もなし。釈放書には『法的には9・30事件とのかかわりはない』と書いてあった。あまりの文化の低さに、怒りより哀れを覚えた」
翌年、『人間の大地』を出版した。初版は12日間で売り切れた。当時のアダム・マリク副大統領は「祖父や父がいかに植民地主義に立ち向かったかを理解するために、すべての若者が読むべきだ」と賛辞を寄せた。
ところが、スハルト政権は間もなく、この本を「マルクス・レーニン主義を広め、社会の秩序を乱そうとしている」として発禁にした。その後に出版したものもすべて発禁になった。プラムディヤは言う。
「人間を平気で踏みつけにするという点で、スハルト政権はオランダの植民地支配と何ら変わらなかった。何度発禁処分を受けようと、本を出し続けた。書き続けることが、私にとっては闘いだった」
1998年にスハルト政権が倒れ、インドネシアは民主化に踏み出した。国民はようやく、プラムディヤの本を手にすることができるようになった。だが、出版が黙認されているだけで、発禁処分そのものは解除されていない。最高検察庁の担当官は「共産主義を禁じた国民協議会の決定が撤回されていない以上、発禁を取り消すわけにはいかない」と言う。プラムディヤの闘いはまだ終わっていない。
(敬称略)
(文・長岡昇 ジャカルタ支局長)
* プラムディヤは2006年4月30日、81歳で死去。紙面では「プラムディア」と表記しましたが、より原音に近い「プラムディヤ」に改めました。このほかにも一部、加筆訂正をしました。
2001年3月9日の朝日新聞夕刊「らうんじ」
強靱な意志。強烈な個性。作家プラムディヤの生い立ちを知るため、故郷のブローラに向かった。ジャカルタから中部ジャワの州都スマランまで空路で1時間。そこから東へ車で3時間半ほど。東ジャワとの州境に近い小さな町だ。
空港から乗ったタクシーの運転手は、たまたまブローラの出身だという。道すがら「町の名物は何なの」と聞いてみた。
「サテ・アヤムがうまい」
即座に答えが返ってきた。甘辛いタレをつけて食べるインドネシア風の焼き鳥だ。どこにでもあるが、ブローラのものは地鶏の肉質がいいうえ、タレが独特なのだという。
続けて「町の出身者で有名な人はいる?」と尋ねた。しばらく考え込んでいる。「思いつかないなあ。とくにいないんじゃないの」。いろいろ水を向けてみたが、名前は出てこなかった。

プラムディヤの父親が校長をしていた中部ジャワ・ブローラの学校は、今は公立中学になっている。生徒た ちは午前7時前に登校してくる
プラムディヤはこの町で、1925年に生まれた。オランダの植民地支配は爛熟期に入っていた。その一方で、独立への胎動も始まり、運動が地方にも広がりつつあった。父親のマス・トゥールは「ブディ・ウトモ」という民族主義団体が運営する学校の校長をしていた。自ら教壇に立つかたわら、自宅で大人のための識字教室を開くなど、この地方の中心的な活動家として人望を集めていた。
「親戚の子供だけでなく、貧しい家庭の子供もうちで預かっていました。多いときには24人もいた。食事の支度だけでも大変でした」。故郷で暮らすプラムディヤの妹ウミ(70)は、母親のサイダが汗だくになりながらも誇らしげに働いていたのを覚えている。
オランダは当初、「ブディ・ウトモ」の運動を「原住民の教育水準の向上に役立つ」と推奨していた。しかし、教育運動が独立運動へと発展し始めたのに気づき、1930年代後半から弾圧に転じた。
植民地政府は親たちに転校させるよう、露骨な圧力をかけた。生徒数は激減し、運動の拠点になっていた自宅に住民が寄りつかなくなった。絶望した父は、バクチにのめり込んでいく。短編『弟の生まれたころ』で、プラムディヤは父の挫折を書いている。
「父は家に帰って来なかった。時には3日3晩も姿を見せなかった。学校にもいなかった。母は私に言った。『父さんはね、とても失望しているの。今は慰めが必要なの』」(冨尾武弘訳)
このころのことを語る時、プラムディヤの口調は重くなる。独立運動に邁進し、ジャワ文化の豊かさを教えてくれた父と、家庭を顧みなくなった父の姿が交錯し、心が乱れるのだろう。
崩れた父に代わって、家族の生活を支えたのは母だった。裕福な家庭に育ち、土をいじったこともなかった母が、田畑を耕して食糧を確保し、雑貨商をして生活費を稼いだ。「女性の隠された力はすごい」。奮闘する姿を見て、プラムディヤはそう思ったと言う。彼の人生と作品に最も大きな影響を与えたのは、この母といっていい。
小学校を卒業すると、プラムディヤはスラバヤにあるラジオ修理工の養成学校に進んだ。早く働き手になり、家族の生活を支えるためだった。在学中に第2次大戦が始まり、日本軍がジャワ島に上陸した。その3カ月後、母は10人目の子供を出産して体調を崩し、35歳で世を去った。
* *
父が校長をし、プラムディヤが通った学校の跡地は今、公立中学になっている。校門のわきには「学校の創設者」として父を顕彰する碑がある。放課後、生徒30人ほどの3年生のクラスで「故郷が生んだ作家」を知っているか尋ねた。プラムディヤのフルネームも言ってみた。みんなキョトンとしている。ひょうきんな男の子が「ルーパ(忘れた)」というと、ドッと笑いが広がった。だれ1人、知らなかった。
「彼の作品は教科書に載っていないし、文学史にも名前が出てきませんから。図書館にも1冊もないんです」。国語担当の女性教師、ワフユ・ウィナンティは気まずそうな表情をした。民主化されたはずなのに、中学の指導要領はスハルト政権時代の1994年版がそのまま使われている。政治的な混乱が続き、改訂作業は遅々として進まない。
「ブローラ生まれの生徒たちが将来、外に出て、プラムディヤの名前も知らないのではつらいのではないですか」と言うと、彼女は「授業内容について検討する職員会議で話し合ってみます」と語った。
* *
プラムディヤの生家には、弟のワルヤディ(74)が住んでいる。1965年のクーデター未遂事件の後、兄に続いて3人の弟たちも次々に逮捕された。投獄期間はそれぞれ12年、10年、5年。もう1人いる末弟だけが逃走し、逮捕を免れた。

プラムディヤの妻は夫の釈放を待ち続けたが、ワルヤディの妻はすぐに去った。流刑地のブル島から故郷に戻って以来、ずっと独りで暮らしている。医学や薬草の知識があるため、近隣の住民に治療を頼まれ、評判になったこともあったが、当局ににらまれ、だれも訪ねて来なくなった。
「兄貴には世話になった。若いころ英語の通訳になれたのも、兄貴に援助してもらったおかげだ」。かなりしっかりした英語でそう言う。だが、プラムディヤは、里帰りしても生家ではなく、妹の家に泊まる。
兄は建て替えの費用を出すと言っているのだが、弟は「このままでいい」と受け付けない。居間にかけられた両親の肖像画には、クモの巣がまとわりついていた。朽ちかけた家で、弟は世捨て人のようにして生きている。名をなした兄に、複雑な思いがあるのだろう。
ぎくしゃくしたものはある。けれども、ともかく全員生き延びた。プラムディヤ兄弟にはまだ、救いがある。この国には、理由も分からないまま殺されていった人々が数十万人もいるのだから。
(敬称略)
(文・写真 長岡昇 ジャカルタ支局長)
*メールマガジン「おおや通信 95」 2012年12月2日
人との出会いに加えて、本との出会いも、その人の歩みに重大な影響を及ぼします。私にとっては、インドネシアの作家、プラムディヤの小説『人間の大地』との出会いがそうでした。

76歳のプラムディヤ(2001年、撮影・千葉康由氏)。5年後、81歳で亡くなった
インドに続いて、1999年からインドネシアに特派員として赴任した私は、騒乱と暴動、腐敗と不正の取材に追われ、へとへとになっていました。「殺伐とした出来事だけでなく、潤いと深みを感じるものも取材したい」と願う日々。そんな時に手にしたのが大河小説『人間の大地』(押川典昭訳、出版社「めこん」)でした。
19世紀末から20世紀初めにかけて、オランダの植民地支配下で独立をめざして立ち上がり、押しつぶされていく若者たちを描いた作品です。「インドネシアのような大きな国(地域)がなぜ、オランダのような小さな国に支配されるに至ったのか」。プラムディヤは自らが抱いた根源的な疑問を解きほぐすために、政治犯の流刑地ブル島での過酷な生活に耐え、この『人間の大地』に続いて『すべての民族の子』『足跡(そくせき)』『ガラスの家』の4部作を書き上げたのだと思います。
スハルト独裁政権は、プラムディヤの作品を「マルクス・レーニン主義を広め、社会の秩序を乱す」として次々に発禁処分にしました。このため、インドネシア国内ではほとんど知られておらず、海外で翻訳出版されて広く知られるようになりました。
仕事の合間に、文字通り、むさぼるように読みました。それだけでは満足できなくなり、作家本人に会って、いろいろと聞きたくなりました。ジャカルタの旧市街にあるプラムディヤの自宅に通い、時にはボゴール郊外にある畑付きの別邸まで行って、本人がしゃべりたくないこと(共産党系の文化団体のリーダーとして他の文学グループを激しく攻撃したこと)もズケズケと聞きました。
30年あまり新聞記者として働きましたが、1人の人間にこんなに何回も長時間にわたって話を聞いたのは、プラムディヤが最初で最後になりました。そのインタビューをもとに、ジャカルタを離れる前(2001年3月)に夕刊に4回の連載記事を書きました。
連載記事(1)?(4)は、このNPO「ブナの森」の「事務局ブナの森」→「雑学の世界」というコーナーにあります。ご一読ください。
2001年3月15日の朝日新聞夕刊「らうんじ」
故郷ブローラの小学校を卒業したプラムディヤは、東ジャワのスラバヤにあるラジオ修理学校に入学した。修業期間1年半の職業訓練校だ。卒業が間近に迫った1942年12月、太平洋戦争が始まった。
「ちょうど分解修理の実習をしている時、ラジオで『日本が真珠湾を攻撃した』というニュースを聴いた。みんな茫然としていた」。戦争になれば、徴兵が始まる。生徒はそれぞれ帰郷した。プラムディヤもブローラの実家に帰った。

年を重ねて、プラムディヤの視力は落ちてきた。しかし、目には力がある(撮影/千葉康由氏、西ジャワ州ボゴール近郊のボジョン・グデで)
オランダ領東インド(現在のインドネシア)には、戦争遂行のために日本が必要とする石油があった。フィリピンとマレー半島を確保した日本軍は、インドネシア攻略を開始した。翌42年1月、まずスラウェシ島北部のマナドとボルネオ島沖のタラカン島に進出。2月にはスマトラ島南部パレンバンの油田地帯を押さえ、ティモール島を占領してオーストラリアへの退路を断った。
欧州ではこれより先に戦争が始まっており、オランダ本国はすでにドイツに占領されていた。補給が途絶えた現地軍は総崩れになる。3月1日、日本軍が三方面からジャワ島に上陸すると、オランダ軍はわずか9日で全面降伏した。

植民地支配者として、300年以上も君臨してきたオランダ人が右往左往し、逃げ惑う。しかも、攻め込んできたのは自分たちと同じような肌の色、体格の日本人。インドネシアの人々にとって、それは衝撃だった。
当時、プラムディヤは17歳。故郷でオランダの敗走と日本の進撃を目撃した。「うれしくてしょうがなかった」ことを覚えている。アジアのほかの国はともかく、少なくともインドネシアでは当初、多くの人が日本軍を「白人の植民地支配から解放してくれた」と大歓迎したのは間違いない。
だが、幻想はすぐに崩れる。日本軍歓迎の渦の中にいたプラムディヤは、行軍中の日本兵に腕時計と自転車を略奪された。「こつこつためた金で、やっと買ったものだった。何の抵抗もできない自分に、無力感を覚えた」。17歳の少年の体験は、その後の日本軍による支配がどのようなものになるかを暗示していた。
* *
「インドネシアのような広大な地域が、なぜオランダのようなちっぽけな国に支配されてしまったのか」。プラムディヤは1950年代に『ゲリラの家族』など、対オランダ独立戦争をテーマにした作品で作家としての地位を確立したが、こうした疑問にとらわれ、しばらく執筆活動をやめる。
「答えは歴史の中にある」と考え、アジア史、とくに20世紀初頭の歴史の研究に没頭した。その時、西欧列強の力に屈しなかった日本に目を向ける。
スハルト体制下での14年間の獄中生活を経て、1985年に出版した作品『足跡』の中で、プラムディヤは日本のことをこう表現した。
「北のかなたには、すっくと立ち上がり、世界の文明国から対等の存在として認められた、
輝けるアジアの民がいる。すなわち、日本人である。日本人以外に、これほど大きな名誉に浴したアジアの民はいない」(出版社めこん、押川典昭訳)
オランダの植民地支配に抵抗しようとして挫折した父。そのせいで家族は生活苦に陥り、プラムディヤは手に職を付けるため職業訓練校に進まざるを得なかった。夢の中でまどろむしかない、わが民族……。それを思う時、自立し、列強と戦う日本は「驚異の民族」だった。
日本の軍政が始まると、プラムディヤはジャカルタに出てきた。首都で、同盟通信社(共同通信社の前身)のタイピストの職を得た。働きながら中学に通い、小説を読みあさった。 「同盟通信では、マタノさんとスズキさんにお世話になった。小説で影響を受けたのは、アメリカの作家スタインベック。ストーリー展開が映画のようだと思った」
速記も習い、日本への傾斜が深まる。「日本人女性と結婚したいと思ったこともあったよ」と言う。しかし、戦局が悪化するにつれ、日本が唱える「大東亜共栄圏」の虚飾は急速にはがれ、「インドネシアは日本が戦争を続けるための資源と労働力の供給地」という本音があらわになっていく。
若い男は補助兵力として動員された。軍事施設の建設や軍需工場での労働、鉄道敷設などに住民が動員され、十分な食料も与えられないまま過酷な労働を強いられた。『日本占領下のジャワ農村の変容』(草思社、倉沢愛子著)によれば、住民の動員数は日本軍関係者の推計で257万人、インドネシア政府は戦争賠償の交渉の際、約400万人と主張した。動員による死者数は、推計すらない。

インドネシアの独立記念塔の地下にある日本占領時代のジオラマ。強制労働させられる住民の姿が描かれている=ジャカルタ市内
プラムディヤとのインタビューの通訳をしてくれた助手に、私は「日本はオランダを追い出して、独立のきっかけを作った。一方で軍政時代にひどいことをした。プラスマイナス、ゼロではないか」と聞いたことがある。
日ごろ穏やかな助手が、この時だけは顔色を変えた。「冗談じゃないですよ。じいさんは、日本の軍政はオランダの植民地支配より、ずっとひどかったって怒ってましたよ」。インドネシアで今使われている高校の歴史教科書は、より明確に表現している。
「日本はインドネシアを占領したことのある国の中で、もっとも残酷だった」(グラフィンド・メディア・プラタマ社版)
『足跡』の中で、プラムディヤは日本を「希望の星」としつつも、日本や列強による中国侵略にも触れ、侵略に抵抗する中国の民族主義者を登場させている。近く、日本軍政時代の従軍慰安婦問題をテーマにした本を出版し、日本のもう一つの顔を世に問う。
プラムディヤに冒頭の問いをしてみた。彼は「フッ」と小さく息を吹き出しただけだった。あの戦争を一言で定義しようとすること自体、愚かなこと。そう言いたかったのではないか。
(敬称略)
(長岡昇=ジャカルタ支局長)
2001年3月16日の朝日新聞夕刊「らうんじ」 連載終了
プラムディヤの両親は、2人ともジャワ人である。生まれ育ったのは中部ジャワで、家庭では当然のことながらジャワ語が使われていた。だが、彼はこの言葉が「嫌いだ」と言う。
「ジャワ語は敬語や謙譲語がものすごく複雑だ。相手が自分より目上なのか目下なのかをまず決めてから、話さなければならない。権力や秩序を固定し、維持するような機能がある」
学校教育はオランダ語で受けた。父親が校長をし、プラムディヤが通った郷里の小学校も、その後入学したスラバヤのラジオ修理学校も、授業はオランダ語だった。植民地では「支配者の言葉」が共通語になる。独立を語るにしても、職を得るにしても、共通語ができなければ話にならない。独立運動の初期、指導者たちは運動方針や組織づくりについてオランダ語で議論している。

76歳の誕生祝いの席で、初のひ孫に目を細める プラムディヤ(撮影/M・スルヤ氏、西ジャワ州ボゴール近郊のボジョン・グデで)
プラムディヤにとって、インドネシア語は第三の言語である。初めてこの言葉を教えてくれたのは、生家のお手伝いさんだった。
「彼女はジャワ人なのに、なぜかインドネシア語ができた。人間のことを『オラン』って言うんだよ、と教えてくれた。ジャワ語ではエビを『ウラン』という。幼心に『人間がエビみたい。変な言葉だなあ』と思った記憶がある」
インドネシアを代表する作家は少年時代まで、インドネシア語とほとんど無縁の生活を送っていた。
* *
インドネシア語は、マラッカ海峡の両岸で使われているマレー語(ムラユ語)がもとになっている。交易や布教のための言葉として、昔からジャワ島やスラウェシ島の港町などでも使われていた。
さまざまな民族が入り交じる中で意思疎通を図るためには、言葉は単純で明快な方がいい。マレー語には単数、複数の区別がない。過去と現在は動詞の変化ではなく、文脈で区別する。敬語はあるが、複雑ではない。
インドネシア大学文学部のクリストミー講師(言語学)によれば、オランダは自分たちの言葉と文化を植民地に広めようとしなかった。このため、マレー語はその後も交易語として広がり続けた。オランダが自国語の普及に力を入れ始めるのは、20世紀の初めに植民地政策を融和的な方向に転換してからだ。
ところが、独立運動の指導者の間ではそのころから「自分たちの言葉で民衆に独立の意義を訴えるべきだ」との機運が高まっていく。代表作の一つ『すべての民族の子』の中で、
プラムディヤは言葉をめぐる知識人の葛藤を描いている。ジャワ貴族出身の主人公ミンケはオランダ語で書くことにこだわり、マレー語は「借用語だらけの貧しい言葉だ」として使おうとしない。友人はこう言って説得する。
「あなた自身の民族の言葉で書くこと、それこそが自分の国と民族に対するあなたの愛のあかしなのです」(出版社めこん、押川典昭訳)
独立運動の指導者たちは1928年、最大の民族であるジャワ人の言葉ではなく、少数派の言葉であるマレー語を共通語にすることを決め、これをインドネシア語と名付けた。話者の数より、民族間の架け橋としての機能を重視した結果だ。少数派の言語が独立後の公用語になった珍しい例で、歴史家は「インドネシアの賢明な選択」と呼んでいる。

* *
プラムディヤがインドネシア語を日常的に使うようになったのは、日本の軍政が始まった1942年に首都ジャカルタに移ってからである。多感な17歳の若者は、インドネシア語の小説をむさぼるように読んだ。
戦時下の日本と同じように、軍政当局は「敵性語」のオランダ語や英語の使用を禁止した。インドネシア語にはオランダ語をそのまま転用した言葉がたくさんあったが、使用禁止に伴い、インドネシア語への翻訳と転換が急速に進んだ。
プラムディヤは皮肉を込めて、この時期を「インドネシア語の黄金時代」と呼ぶ。動機はどうあれ、敵性語の禁止はインドネシア語の成熟を促し、その後の発達に大きな影響を及ぼした。
1945年8月15日、日本は降伏した。インドネシアはその2日後に独立を宣言する。オランダはこれを認めず、49年までインドネシアと戦争を続けた。プラムディヤも独立戦争に加わり、反オランダ活動の容疑で逮捕され、2年間投獄された。この体験を基にした小説『ゲリラの家族』で、彼は作家としての地位を確立する。
長年投獄された反骨の作家が一度だけ、弾圧する側に回ったことがある。1950年代後半、共産党系の人民文化協会(レクラ)の中心メンバーだったころだ。共産党勢力を取り込んだスカルノ政権の下で、彼は「芸術は政治に奉仕すべきだ」との論陣を張り、「芸術は何ものからも自由であるべきだ」と主張する芸術家を排撃した。
詩人のタウフィック・イスマイルは「彼の作品には敬意を払うが、あの時の行為は許せない」と言う。「共産党の青年組織は『反共』とみなした作家の活動を妨害し、その本を焼いた。レクラは反対するどころか、それを支持した」
この話になると、プラムディヤは反論も弁明もせず、沈黙する。文壇の亀裂はいまだに修復されていない。
* *
インド洋の波を受けるスマトラ島から、南太平洋に横たわるニューギニア島中央部まで、5000キロ余り。インドネシアは米国本土よりも長く東西に広がる。そこに1万数千の島が散らばり、200とも300ともいわれる民族が隣り合って暮らす。
国家としての統一を保つのは容易なことではない。植民地として支配したオランダも、独立後のスカルノ、スハルト両政権も結局は「鉄拳」で抑え込むしかなかった。
1998年にスハルト政権が崩壊し、インドネシアは民主化に踏み出した。「力による支配」は終わった。では、複雑多様なこの国を力以外の何でまとめていくのか。
宗教でも、イデオロギーでもない、何か。
プラムディヤはそれを探し求めて、人々の営みを紡ぎ続ける。
(敬称略)
(長岡昇 ジャカルタ支局長)
*メールマガジン「おおや通信 94」2012年11月16日
「近いうち」がついにやって来て、衆議院の解散、総選挙となりました。こんなに気の乗らない選挙は記憶にありません。民主党にはあきれましたが、自民党に託す気にもなれません。かといって、巷で話題の「第三極」の看板は、あの橋下徹氏やかの石原慎太郎氏。これでは「もっと深い失望を味わうことになるだけ」と、ますます冷めた気持ちになってしまいます。
というわけで、総選挙にはあまり関心が湧いてきません。しばらく前、秋田県境にある山形県の金山町を訪ねた時につらつら考えたことをお送りします。
◇ ◇
税金をどう使ったのか。政府や自治体は納税者にきちんと説明しなければなりません。今では多くの人が「ごく当たり前のこと」と考えるようになりました。そのためにつくられた情報公開制度も、すっかり定着しました。
けれども、この制度ができるまでには、ずいぶんと時間がかかりました。政治家や官僚たちがあれこれと理由をつけて抵抗したからです。税金の中身と使い道を熟知する側は「自分たちだけの秘密の壁」をいつまでも維持しようとしたのです。
都道府県の中で、この情報公開制度を最初につくったのは神奈川県でした。1983年(昭和58年)のことです。「地方の時代」をスローガンに掲げ、革新陣営の期待の星だった当時の長洲一二(ながす・かずじ)神奈川県知事が条例づくりを主導しました。
当時、私は横浜支局の駆け出し記者でサツ回り(警察担当)をしていました。県政担当のベテラン記者や遊軍記者が情報公開の意義と役割を書きまくっているのを、まぶしい思いで脇から見ていました。長洲知事も一線の記者たちも「開かれた、新しい社会への道を切り拓くのだ」と燃えていました。
ところが、神奈川県は「日本で最初に情報公開制度をつくった自治体」にはなれませんでした。その前年の1982年に山形県の金山町が情報公開条例を制定し、「最初の自治体」になってしまったからです。なぜ、東北の小さな自治体がこういう大きな意義を持つ制度を神奈川県より先につくることができたのか。情報公開制度のことを直接、取材したことのない私は、ずっと不思議に思っていました。
この秋、金山町を訪ねて、その謎が解けました。新しいことに果敢に挑戦していた当時の岸宏一・金山町長(現在は山形県選出の参議院議員)が、学生時代の知人で朝日新聞の記者をしていた田岡俊次氏に情報公開の制度づくりを強く勧められて決断した、ということでした。田岡氏は、官僚の乱費と腐敗を追及した調査報道や軍事・防衛問題の専門記者として知られる敏腕記者ですが、情報公開条例づくりにも一役買っていたとは知りませんでした。
都道府県が公文書を開示するとなると、警察の情報をどう取り扱うかなど厄介な問題がいくつか出てきます。そうした難題に対処している間に、金山町がさっさと条例を制定してしまったのです。神奈川県は長い時間と膨大なエネルギーを費やしましたが、「日本で最初に情報公開制度をつくった自治体」として歴史に名を残すことはできませんでした。
金山町は情報公開に先鞭をつけたこと以外にも、1960年代から景観を重視した街並みづくりをしてきたことでも知られています。地元の杉を生かした、切り妻屋根と白壁、下見板の住宅づくりを奨励し、自然石を使った堰(せき)をめぐらして潤いのある街並みをつくってきました。欧州の経験から学ぶために、町民をドイツに派遣する事業も続けています。実にユニークで面白い町です。

切り妻屋根と白壁、杉の下見板が特徴の「金山住宅」
ともあれ、情報公開制度はその後、都道府県レベルでも市町村レベルでも全国に広がりました。しかし、自民党の歴代政権はなかなか情報公開に踏み切ろうとせず、国の情報公開法が施行されたのは2001年の春、森喜朗政権の末期です。金山町の条例制定から、実に19年後のことでした。
戦後日本の政治システムと官僚制度は、経済成長が続いている間はそれなりによく機能していました。しかし、成長期を過ぎ、経済が停滞し始めてから、おかしくなりました。中央の諸制度が牽引役ではなく、改革の阻害要因になり始めたのです。情報公開をめぐる動きは、それを象徴的に示すものでした。
硬直した制度が何をもたらすのか。去年の東日本大震災で、私たちはいやになるほど見せつけられました。「阻害要因としての中央」がその極に達した結果が福島の原発事故だった、と私は受けとめています。
停滞から抜け出すための「改革の風」は今、生活の現場、つまり地方から吹き始めています。金山町に限らず、時代の流れを見極め、困難な事に挑戦している自治体や地方の組織はたくさんあります。さらに成熟した社会への道を切り拓くために、地方で踏ん張る人たちの背中をもっと押していきたい。 (完)
*メールマガジン「おおや通信 93」2012年11月9日
おばあさんが孫に昔の苦労話を語って聞かせた。
「ばあちゃんが小さい頃は食べる物がなくってねぇ。お腹をすかせて、よく泣いていたよ」
孫は不思議がって、首をかしげながら尋ねたという。
「おばあちゃん、どうしてコンビニに行かなかったの?」
今の子どもたちにとって、食べ物とはお金さえあれば自由に手に入るものである。「ひもじくて泣く」という経験もしたことがない。それは幸せなことなのだが、幸せには不幸が付いて回るのが世の常だ。飽食の時代には、また別の苦しみが待っていた。

大谷小の畑で育てたサトイモで調理師さんに芋煮を作ってもらい、近くの里山で青空給食を楽しんだ
小学校の校長になって驚いたことの一つは、アトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー疾患の多さだった。卵アレルギー、そばアレルギー、パイナップルアレルギー……。自分が子どもの頃には聞いたこともないような病気で苦しんでいる子がたくさんいる。
アトピーの原因については諸説あり、いまだに解明されていない。研究者は自分の専門にこだわりすぎて、迷路に陥ってしまっている印象を受ける。私が「もっとも説得力がある」と感じたのは、高雄病院(京都市)の江部(えべ)康二医師の説明だ。江部氏は、アトピーが昭和30年代から増え始めたことに目を向ける。
経済成長に伴って、農民は農薬をジャブジャブ使うようになった。食品を流通させるために、防腐剤や添加物が惜しみなく投入された。こうした化学物質は、今や全体で数万種類に及ぶ。「もともと人間には自然治癒力があるが、それにも容量がある。それを超えた場合、さまざまな症状となって現れてくるのではないか」と江部氏は説く。
一つひとつの化学物質には使用上の規制がある。しかし、全体を見ている人間はどこにもいない。「健康には直ちに影響はない」という、原発事故の時に聞いた言葉が虚ろに響いてくるのである。
*11月9日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(8)
見出しと改行は紙面とは異なります。
*メールマガジン「おおや通信 92」 2012年10月26日
大谷小学校の5年生は毎年、地域の方から「現役の田んぼ」をお借りして米作りの勉強をしている。泥にまみれて田植えをし、実った稲穂を秋に刈り取る。
収穫した稲は天日干しして脱穀するのだが、この作業にも力を入れる。指南役の小野昇一郎さんが千歯こきと足踏み式の脱穀機、それにハーベスター(自走型脱穀機)を用意してくれるのだ。大きな櫛(くし)のような千歯こきは江戸時代、足踏み式は明治から戦後にかけて、ハーベスターは最近まで脱穀の主役だった。農機具の改良と進歩の歴史を体験しながら学ぶことができる。
修正.JPG)
「千歯こきでの脱穀は、とても力のいる仕事でした。昔の人は大変な仕事をたくさんしていたんだなぁと感じました」
生徒はそんな感想文を書いた。いつも食べているご飯に、これまでどれほど多くの人々の汗が注がれてきたことか。かすかにではあっても、感じ取ることができたのではないだろうか。本を読んだり、話を聞いたりしただけでは得られない、農村の小学校ならではの「生きた授業」の成果である。
この授業には「続編」もある。脱穀した後の稲藁(いなわら)を使って縄をない、みんなで正月用の注連(しめ)飾りを作るのだ。自分の分だけでなく、お世話になった方々の分も作ってプレゼントする。
稲藁は長い間、縄や俵など農民の生活に欠かせないものの材料として使われてきた。けれども、現代の収穫作業の主役、コンバインは刈り取りから脱穀まで一気にこなし、稲藁は裁断して田んぼにまいてしまう。稲藁にしてみれば、さぞかし寂しいことだろう。
わずかな量ではあっても、注連飾りとしてお正月の玄関を彩ることができれば、稲藁も少しは救われるのではないか。そんな思いを込めて、今年も注連飾りの縄をなうことにしよう。
*10月26日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(7)
見出しと改行、写真(遠藤秀彦さん撮影)は紙面とは異なります。
最上川をカヌーでゆったりと下る第1回最上川縦断カヌー探訪(NPO「ブナの森」主
催)は、2012年7月28日(土)、29日(日)の両日開かれ、1日目は21人が山
形県の長井市から朝日町までの24キロメートル、2日目は22人が朝日町から中山町ま
での29キロを下りました。

真夏の太陽が照りつける中での厳しい川下りになり、流れの激しい瀬での転覆もありま
したが、全員けがもなく、最上川の急流と景観を存分に楽しむことができました。1日目
のみ、あるいは2日目のみ参加した人もおり、参加者は全部で24人でした。このうち、
18人が2日間で53キロの全コースを漕ぎきりました。

《参加者》 24人(エントリー順、敬称略)
【2日間で53キロを完漕】 18人
中村圭太郎(山形県上山市)▽大泉麻紀子(山形市)▽芦野真一郎(山形市)▽長南平
(山形県酒田市)▽金井初枝(埼玉県越谷市)▽武田安英(酒田市)▽小田原紫朗(酒田
市)▽佐藤明(鶴岡市)▽市川秀(東京都中野区)▽青木誠人(天童市)▽長澤敬行(山形
市)▽城戸口徹(山形市)▽佐竹久(山形県大江町)▽小野俊博(大江町)▽崔鍾八(山形県
朝日町)▽菊地大二郎(山形市)▽林和明(東京都足立区)▽松本雅之(山形県寒河江市)
【1日目、24キロを完漕】 3人
三部義道(山形県河北町)▽渡辺不二雄(山形市)▽長岡和之(朝日町)
【2日目、29キロを完漕】 3人
勝村文直(山形市)▽佐藤雅之(酒田市)▽渡辺政幸(大江町)

《陸上サポートスタッフ》 31人(アイウエオ順、敬称略)
安藤昭郎▽安藤美智子▽安藤稔▽海野信雄▽大泉忠昭▽今野義之▽斉藤栄司▽佐久間淳▽佐竹
勝男▽佐竹久(ひさ)▽佐竹恵子▽佐藤和之▽白田金之助▽鈴木多悦▽清野千春▽高橋洋一▽長
岡里子▽長岡昇▽長岡典己▽長岡洋樹▽長岡由衣▽長岡佳子▽長岡遼子▽奈良崎美雄▽藤山純一
▽堀俊一▽渡邉和浩▽渡邉信一▽渡辺富士子▽渡邉宥▽渡辺陽子

《各ポイントの通過時刻》
*カヌー集団のほぼ中央が通過した時刻(記録:「ブナの森」斉藤栄司)
1日目 【7月28日(土)】
9:40 長井市の長井橋河川公園で開会式
10:00 長井橋河川公園を出発
11:05 白鷹〈しらたか〉町の睦橋を通過
11:56 同町の荒砥〈あらと〉橋を通過
12:15?13:10 黒滝橋の上流で昼食
13:40 白鷹町の道の駅「あゆ茶屋」を通過
14:15 朝日町の大平〈たいへい〉橋を通過
14:25 同町の大船木〈おおふなき〉橋を通過
15:25 同町の暖日〈ぬくい〉橋を通過
15:40 上郷ダム公園の右岸にゴール

2日目【7月29日(日)】
9:50 朝日町の赤釜〈あかがま〉を出発。赤釜は上郷ダムの下流の集落。
10:28 同町の五百川〈いもがわ〉橋を通過
11:15 同町の八天〈はってん〉橋を通過
11:58?12:10 同町の「タンの瀬」を通過
12:55 用〈よう〉の堰堤を通過
13:22 大江町の大江大橋を通過
13:45?14:35 同町の「おしんの筏くだりロケ地」で昼食
14:47 同町の最上橋を通過
15:05 寒河江〈さがえ〉市の簗瀬〈やなせ〉橋を通過
15:20 同市の此の木橋通過
15:30 同市の平塩〈ひらしお〉橋を通過
15:54 同市の高瀬大橋通過
16:35 中山町の長崎大橋の下流右岸にゴール
《後援団体》
国土交通省山形河川国道事務所▽山形県▽東北電力?山形支店▽長井市▽白鷹町▽朝日町
▽大江町▽西川町▽寒河江市▽中山町▽山形カヌークラブ▽大江カヌー愛好会▽山形県カヌ
ー協会▽美しい山形・最上川フォーラム
《ウェブサイト、ポスター》
▽ウェブサイト制作 コミュニティ アイ(成田賢司、成田香里、澤田毅)▽ポスター制作
ディーエムサインスタジオ(渡邉幸雄)
催)は、2012年7月28日(土)、29日(日)の両日開かれ、1日目は21人が山
形県の長井市から朝日町までの24キロメートル、2日目は22人が朝日町から中山町ま
での29キロを下りました。

真夏の太陽が照りつける中での厳しい川下りになり、流れの激しい瀬での転覆もありま
したが、全員けがもなく、最上川の急流と景観を存分に楽しむことができました。1日目
のみ、あるいは2日目のみ参加した人もおり、参加者は全部で24人でした。このうち、
18人が2日間で53キロの全コースを漕ぎきりました。

《参加者》 24人(エントリー順、敬称略)
【2日間で53キロを完漕】 18人
中村圭太郎(山形県上山市)▽大泉麻紀子(山形市)▽芦野真一郎(山形市)▽長南平
(山形県酒田市)▽金井初枝(埼玉県越谷市)▽武田安英(酒田市)▽小田原紫朗(酒田
市)▽佐藤明(鶴岡市)▽市川秀(東京都中野区)▽青木誠人(天童市)▽長澤敬行(山形
市)▽城戸口徹(山形市)▽佐竹久(山形県大江町)▽小野俊博(大江町)▽崔鍾八(山形県
朝日町)▽菊地大二郎(山形市)▽林和明(東京都足立区)▽松本雅之(山形県寒河江市)
【1日目、24キロを完漕】 3人
三部義道(山形県河北町)▽渡辺不二雄(山形市)▽長岡和之(朝日町)
【2日目、29キロを完漕】 3人
勝村文直(山形市)▽佐藤雅之(酒田市)▽渡辺政幸(大江町)

《陸上サポートスタッフ》 31人(アイウエオ順、敬称略)
安藤昭郎▽安藤美智子▽安藤稔▽海野信雄▽大泉忠昭▽今野義之▽斉藤栄司▽佐久間淳▽佐竹
勝男▽佐竹久(ひさ)▽佐竹恵子▽佐藤和之▽白田金之助▽鈴木多悦▽清野千春▽高橋洋一▽長
岡里子▽長岡昇▽長岡典己▽長岡洋樹▽長岡由衣▽長岡佳子▽長岡遼子▽奈良崎美雄▽藤山純一
▽堀俊一▽渡邉和浩▽渡邉信一▽渡辺富士子▽渡邉宥▽渡辺陽子

《各ポイントの通過時刻》
*カヌー集団のほぼ中央が通過した時刻(記録:「ブナの森」斉藤栄司)
1日目 【7月28日(土)】
9:40 長井市の長井橋河川公園で開会式
10:00 長井橋河川公園を出発
11:05 白鷹〈しらたか〉町の睦橋を通過
11:56 同町の荒砥〈あらと〉橋を通過
12:15?13:10 黒滝橋の上流で昼食
13:40 白鷹町の道の駅「あゆ茶屋」を通過
14:15 朝日町の大平〈たいへい〉橋を通過
14:25 同町の大船木〈おおふなき〉橋を通過
15:25 同町の暖日〈ぬくい〉橋を通過
15:40 上郷ダム公園の右岸にゴール

2日目【7月29日(日)】
9:50 朝日町の赤釜〈あかがま〉を出発。赤釜は上郷ダムの下流の集落。
10:28 同町の五百川〈いもがわ〉橋を通過
11:15 同町の八天〈はってん〉橋を通過
11:58?12:10 同町の「タンの瀬」を通過
12:55 用〈よう〉の堰堤を通過
13:22 大江町の大江大橋を通過
13:45?14:35 同町の「おしんの筏くだりロケ地」で昼食
14:47 同町の最上橋を通過
15:05 寒河江〈さがえ〉市の簗瀬〈やなせ〉橋を通過
15:20 同市の此の木橋通過
15:30 同市の平塩〈ひらしお〉橋を通過
15:54 同市の高瀬大橋通過
16:35 中山町の長崎大橋の下流右岸にゴール
《後援団体》
国土交通省山形河川国道事務所▽山形県▽東北電力?山形支店▽長井市▽白鷹町▽朝日町
▽大江町▽西川町▽寒河江市▽中山町▽山形カヌークラブ▽大江カヌー愛好会▽山形県カヌ
ー協会▽美しい山形・最上川フォーラム
《ウェブサイト、ポスター》
▽ウェブサイト制作 コミュニティ アイ(成田賢司、成田香里、澤田毅)▽ポスター制作
ディーエムサインスタジオ(渡邉幸雄)
2003年9月18日 朝日新聞夕刊コラム「窓/論説委員室から」
土木という言葉で思い浮かべるのは、汚職と談合。ダムにいたっては、今や「無駄な公共事業の代名詞」のようになってしまった。土木史を専門とする岡山大学の馬場俊介教授は嘆く。
教授によれば、土木の語感が変わり始めたのは昭和30年代の高度成長のころからだ。橋や道路が競うように造られ、土木全体が利権の渦にのみ込まれていった。
「それまでは材料も資金も乏しく、技術者は一つひとつ心を込めて造った。土木という仕事に誇りを持っていたのです」

実際、古い時代に造られたものには、人をひき付けてやまないものがある。写真家の西山芳一(ほういち)さんは、そうした土木構造物を撮り続けてきた。代表作を集めた個展「水辺の土木」が、東京・京橋のINAXギャラリーで開かれている。
潅漑用の小さなダムの写真がある。あふれた水が堰堤(えん・てい)の切り石にはじかれ、白いレース状の流紋を描く。右岸の擁壁は地形に合わせてしなやかに曲げられ、水が弾むように流れ落ちていく。大分県の竹田市にある白水(はくすい)ダムだ。1938年に完成し、今も地域の田畑を潤している。研究者は「日本で一番美しいダム」と呼ぶ。
軍靴の響きが高まり、物資も欠乏し始めた時代に、ここまで美しさを追い求めた技術者がいたことに驚く。この小さなダムに込められたような思いを人々が失った時、土木という言葉もまた輝きを失ってしまったのではないだろうか。〈長岡 昇〉
*メールマガジン「おおや通信 91」 2012年9月14日
この夏、伊豆半島で開かれたセミナーで、天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した天野篤(あつし)・順天堂大教授の話を聞く機会があった。
心臓の冠動脈のバイパス手術は、麻酔で心臓の動きを止め、人工心肺を使って行うことが多い。心臓が動いている状態では太さ数ミリの血管を縫い合わせるのは至難の技だからだ。天野さんはその「至難の技」に挑み続けてきた。病院で寝泊まりし、自宅にはほとんど帰らなかった。家族には「父親はいないもの、夫はいないものと思ってくれ」と言っていたという。

伊豆半島のセミナー会場の近くで出合った野生の鹿
順風満帆の人生を歩んできた人ではない。進学校に入ったものの成績は中くらい。3浪して日大医学部に合格した。病院の勤務医として現場で腕を磨き、心臓血管外科の頂点に上りつめた人だ。「偏差値エリートを集めても勝負には勝てない。知識と経験をいかにして統合するかが大事だ。この世の中では、偏差値50前後の人間が大切」と言う。
教育の世界では、いまだに偏差値が幅を利かせている。個々の生徒や学校全体の学習の到達度を測る尺度として、偏差値は重要である。だが、あくまでも「重要な尺度の一つ」でしかない。
「そんなきれい事はたくさんだ。世間は結局、有名校への進学数でしか評価してくれないではないか」と反論されそうだ。確かにそういう現実がある。だから、偏差値を片手に教育長が校長を締めあげ、校長が教師を責め立てるような自治体も出てくるのだろう。
だが、天野教授は「例外中の例外」なのだろうか。そうではあるまい。長く生きていれば、人間には偏差値に劣らないくらい重要な尺度がいくつもあることを肌で知るようになる。時代の流れが変わる時、価値の尺度もまた大きく変わる。あの大震災から1年半。流れは間違いなく、変わりつつある。
*9月14日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(6)
見出しと改行は紙面とは異なります。
*メールマガジン「おおや通信 90」 2012年9月3日
5月18日の「おおや通信82」でお伝えした通り、今年は大谷小学校の子どもたちに「いのち」をテーマにして、一連の校長講話をしています。毎月一度、わずか15分間の話ですが、1年生から6年生まで全員が分かるように話すのは容易なことではありません。もちろん、子どもだましの話でお茶を濁すわけにはいきません。
というわけで、校長として話をする前には、必ず山形県立図書館に行って本をあさり、ネットでも十分に調べることにしています。講話は4月の「いのちと地球」から5月の「いのちと太陽」、6月「いのちと水」、7月「いのちと土」と続いていますが、いつも頭から離れないのは「生命はどのようにして生まれたのか」「進化を決定づけるものは何か」という根源的な疑問です。

カナダのバージェスで発見された奇妙な動物マルレラ Marrella の復元図
これらの問題については、ハーバード大学の古生物学者、スティーヴン・ジェイ・グールド教授が1989年に出版した『ワンダフル・ライフ』(邦訳は1993年、早川書房)という本が有名です。この本は、恐竜が生きていた時代よりずっと古い時代の地層から発見された膨大な数の化石群を扱ったものです。カナディアン・ロッキーのバージェスという場所から発見されたカンブリア紀(5億4200万年前?4億8830万年前)の化石群で「バージェス頁岩(けつがん)動物群」と呼ばれています。
グールド教授は、カンブリア紀に生物の爆発的な進化が起き、現代につながる動物の先祖のすべてがすでにこの時代には登場していたこと、しかもそのうちのかなりの動物がその後、絶滅したことを指摘しました。生物の大量絶滅は地球上で何度も起きていることも力説しています。そして最後に、ナメクジのような「ピカイア」という脊索(せきさく)動物を紹介し、これが人間を含むすべての脊椎動物の先祖である可能性を示唆して世界的なセンセーションを巻き起こしました。

古生物の化石群があることで澄江は世界自然遺産に登録されました
古生物に関する私の知識は19年前に読んだこの本で止まっていたのですが、今回、小学校で話すにあたって、その後の研究の進展状況を調べてみました。その結果、中国雲南省の澄江(チェンジャン)でもカンブリア紀の動物の化石が大量に見つかり、それまでの説を覆すような発見が相次いでいることを知りました(宇佐見義之著、技術評論社『カンブリア爆発の謎』を参照)。
また、「古生物学界の教皇」と呼ばれたグールド教授に対抗するように、大英自然史博物館の古生物学者、リチャード・フォーティ氏が1997年に『ライフ』(邦題は『生命40億年全史』、2003年に草思社刊)を出版し、生命の起源に関する壮大な物語を展開していることも知りました。

英国の古生物学者リチャード・フォーティ氏 Richard Fortey
この本は、地球上に最初に誕生した生命は長さ数千分の1ミリの細菌であろうと考えられること、しかも、当時の地球の大気には酸素はなく、水素と二酸化炭素を利用して生きるメタン生成細菌と考えられる、と述べています。つまり、地球上で今生きている生物の中でこの「生命の元祖」にもっとも近いのは、光も届かず酸素もない深海の熱水鉱床の噴き出し口で生きている細菌だろうということです。
地球で生まれた小さな細菌が長い時を経て大いなる進化を遂げ、やがて人間を含む多様な生物を生み出すに至るまでの気が遠くなるような長い物語に触れ、地球と生命に関する英米の分厚い知の蓄積に圧倒される思いでした。グールド教授のベストセラー『ワンダフル・ライフ』もすごい本ですが、このフォーティ氏の『生命40億年全史』は一人の研究者の物語としても読み応えがあります。時間に余裕のある方には、ぜひ一読をお薦めします(時間が足りない方には、宇佐美義之氏のコンパクトな『カンブリア爆発の謎』がお薦めです)。
最近、NHKがドキュメンタリー番組で「生命は隕石に乗って火星から飛来した」という新説を紹介していましたが、その場合でも「では、火星のどういう環境の下で生命は誕生したのか」という疑問が残ります。そして、やはり「酸素もない環境で誕生した細菌こそ生命の起源」という物語が語られるのかもしれません。
これらの本の内容は、小学校での15分間の講話ではとても語れませんが、せめてその香りだけでも伝えたいと考えています。9月の校長講話のテーマは「土とミミズ」の予定です。ミミズの研究に40年の歳月を費やしたというチャールズ・ダーウィンのことに触れつつ、ミミズの不思議を語るつもりです。
*メールマガジン「おおや通信 89」2012年8月30日
教育現場への風当たりが強い。大津市で起きた中学生の自殺事件についての市教育長と中学校長の不誠実な対応によって、現場への非難はピークに達した感がある。
一人の人間が13歳という若さで自ら命を絶った、という事実は重い。学校で何があったのか。それが自殺とどのようにかかわっていたのか。どんなにつらくても、関係者は事実を正面から受けとめ、見つめなければならない。それは教育者というより、一人の人間としてなさねばならぬことである。報道を通して伝えられる市教育長と中学校長の言動からは、その覚悟が感じられない。命が失われたことへの「畏(おそ)れ」がうかがえない。

警察が強制捜査に乗り出したことについて「教育の問題に警察が介入するのはいかがなものか」と異論を差し挟む人がいる。おかしな論理である。「いじめ」がエスカレートすれば、ある段階からそれは暴行、傷害、恐喝といった犯罪に転じる。学校が対処できるうちは警察は控えていればいいが、その範囲を超えれば刑事事件として捜査するのは当然のことだ。
「生徒が動揺する」と言う人もいる。その通りだろう。しかし、事実を隠蔽し、あいまいにすれば動揺は収まるのか。大人たちが苦悩する姿を見せる。そして、何が起きたのか可能な限り明らかにする。激しい心の揺れを静めるためには、そうするしかないのではないか。
大きな事件が一つの小さな過ちによって起きることは、まずない。過ちに過ちが重なり、さらに重大な判断ミスが折り重なった時に、噴き出すものだ。大津市の事件もそうしたケースと考えるべきであり、今は折り重なった過ちを一つひとつはがして検証作業を進めていくしかあるまい。

新聞記者として30年余り働いた後、早期退職して故郷の山形県で民間人校長になって4年目を迎えた。教育の一線に身を置いて違和感を覚えるのは、大津市のような事件が起きると、それがすぐに「今時の学校は」と一般化され、押し寄せてくることだ。
学校はそんなにひどいのか。 実際に校長として働いてみて、「そんなことはない」と強く思う。むしろ、日本の教育にはまだ底力がある。教師の多くは誠実に自らに課せられた職務を果たしている。気骨のある教師も少なくない。
小学校の校長になって間もなく、近くのキャンプ場で2泊3日の宿泊体験学習があった。5、6年生がテントを張り、5回の食事を自分たちだけで作るハードな合宿である。マッチと古新聞、それに炊事5回分の薪(まき)と食器が班ごとに子どもたちに配られた。食材はその都度、渡される。1日目の夕食のメニューはカレーライスだった。何となく浮き浮きしていた私は、6年担任の教師にこうくぎを刺された。
「火の焚(た)き方も調理の仕方も一切、教えないでください」
それでカレーライスはできるのか。心配して尋ねると、担任は涼しい顔で言い放った。
「いいんです。失敗して、泣いて覚えればいいんです」
私が勤める小学校は農村にある。今や農村の子どもたちですら、火の焚き方を知らない。かまどにドテッと薪を置き、古新聞を丸めて火をつけている。これでは勢いよく燃え上がるわけがない。それでも、容赦なく夕食の時間になる。子どもたちは、ポロポロのご飯に生煮えの「カレースープ」をかけて食べていた。泣きべそをかいている子もいた。先生たちは別のかまどで、ちゃんとしたカレーライスを作って食べた。
よほど悔しかったのだろう。先生たちはどうやって火を焚いているのか。翌朝から、必死になってまねをし始めた。そうやって、3日目にはどの班でも、ちゃんとご飯を炊けるようになった。優しく教えるだけでは子どもは育たない。時には突き離して、追い付くのを待つ。民間人校長の私が口を出すまでもなく、実にまともな教育が行われていた。
去年の5年生の稲作の学習にもうなった。地元の人の田んぼをお借りして田植えから稲刈りまで体験した後、刈り取った稲藁(いなわら)で縄をなう学習をした。さらに、その縄でお正月用の注連(しめ)飾りを作った。身近にあるものを使いきる、優れた実践である。
山形県の高畠町には、学校給食で使う野菜の半分以上を生徒たちが自ら作っている学校がある。二井宿(にいじゅく)小学校という。野菜の有機栽培をするだけでなく、この小学校ではモチ米を育て、生徒たちが地元の独り暮らしのお年寄りに励ましの手紙を添えて配って歩く。すごい学校である。
不祥事は不祥事として厳しく追及されなければならない。任に堪えない校長や教師がいるなら、退いてもらう必要がある。だが、そうしたことにかこつけて、教育の現場全体をたたくような風潮は改められるべきだ。これでは意欲のある教師まで萎縮してしまう。
 修正版.jpg)
不祥事があるたびに、文部科学省が偉そうな通知を出してくるのも耐え難い。教育の一線に細々と口出ししてきた習性から抜け出せないのだろう。いざという時、文部科学省をはじめとする中央の官僚たちがいかに頼りにならないか。私たちは東日本大震災を通して、骨身に染みて思い知らされた。
巨費を投じて開発した放射性物質の拡散予測システムは、ほとんど役に立たなかった。震災前、原発推進の国策に沿って、文科省は「原発事故の心配はない」という副読本を全国の小中学生に配布し、事故後にすごすごと撤回した。にもかかわらず、今度は「放射線はスイセンからも出ている」という副読本を全国に配布し、除染に苦しむ人たちから猛反発を受けた。度し難い人たちである。
東京が細々と指示を出し、地方がそれに従う。そんな時代はもう終わりにしなければならない。東京は大きな、揺るぎない方針を指し示す。地方は自分たちの実情に合わせて工夫を凝らす。それを東京にフィードバックし、必要に応じて助言を受ける。互いに支え合う関係へと変えていかなければならない。
私たちは「難しい過渡期」を生きている。冷戦は終わったが、新しい国際秩序はまだ見えない。インターネットの普及が政治と経済の在り様をがらりと変え、グローバル化を加速する。豊かにはなったものの、少子高齢化が進み、かつてのような活力はない。
未来は厳しい。だが、まだ力はある。問題は、まだある力を最大限に発揮するための変革を、自分たちの力で成し遂げられるかどうかだ。新しい道へと踏み出す覚悟はあるのか。私たち一人ひとりが問われているのである。
*京都に本社がある宗教の専門紙「中外日報」(8月28日付)に掲載された小論です。
中外日報から依頼されて寄稿しました。
*メールマガジン「おおや通信 88」 2012年8月10日
本業のほかに名刺をもう1枚作ろう。そんなスローガンを掲げて、3年前に東京で小さなNPO(非営利組織)が産声を上げた。「二枚目の名刺」というNPOだ。
「仕事に精を出しつつ、社会貢献活動にも取り組もう。それが自分を変え、やがて社会をも変えていく。一歩、踏み出そう」。代表の廣(ひろ)優樹さんはそう呼びかける。仕事一筋の生き方から、複線型のゆったりとしたライフスタイルへの転換を訴えている。
小学校の校長をしながら、私も地域おこしの活動を始めた。過疎化が進む故郷が少しでも元気になる道はないのか。地域を歩き回り、周りの人たちと語り合う中で目を向けたのが最上川だった。「母なる川」という美名とは裏腹に、最上川は汚れが目立つ。地元の人たちは、大人も子供もあまり近づかなくなった。

カヌーの愛好家が「日本一の流れ」と激賞する最上川の「タンの瀬」
そんな中で、朝日町にある最上川の激流に集う人々がいた。カヌーの愛好家である。首都圏や関西から来た人たちに聞くと「ここの流れは日本一だ」と言う。一緒に最上川をカヌーで下ってみた。私はまったくの初心者。たちまち転覆し、しこたま水を飲んでしまった。だが、そこには確かに、見たこともない厳かな風景が広がっていた。
2年前に「ブナの森」というNPOを立ち上げ、カヌーで最上川を50キロほど下る企画の実現に乗り出した。速さを競うレースではなく、1泊2日で最上川の流れを楽しむイベントを目指した。資金は寄付頼みで、心もとない。昨年の大震災後は活動も停滞した。それでも、地域おこしを支援してくださる方々やカヌーの愛好家に支えられて、7月末になんとか開催に漕ぎ着けた。
イベントの名称は「最上川縦断カヌー探訪」という。これで地域が元気になるのか。定かではない。けれども、人と人とのつながりは確実に広がった
*8月10日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(5)
写真は紙面に掲載されたものとは異なります。
*メールマガジン「おおや通信 87」 2012年8月4日
故郷の山形県朝日町で地域おこしのNPO「ブナの森」を旗揚げしてから2年半。準備を重ねてきた最上川縦断カヌー探訪の第1回大会をようやく開催することができました。これまで物心両面で支えてくださった皆様に、あらためて深く感謝いたします。
 修正版.jpg)
カヌー探訪は7月28日(土)、29日(日)の両日、開かれました。真夏の太陽がギラギラと照りつける中、1日目は21人、2日目は22人が最上川の中流域(長井市?白鷹町?朝日町?大江町?寒河江市?中山町)の53?メートルをゆったりと下り、最上川の流れと景観を堪能しました。都合で1日目だけ、あるいは2日目だけ参加した方もいらっしゃいますので、実際に川下りを楽しんだ方は24人でした。これを30人余りの陸上スタッフがサポートしました。
参加者は山形県内のカヌーイストにとどまらず、東京や埼玉からも駆けつけてくださいました。朝日町の周辺には鉄道の路線がありません。「最上川のこの辺を下ってみたくても、アクセスがあまり良くないので挑戦できませんでした。今回の企画で、ようやく念願が叶って下ることができました」と言ってくださった方が何人もいらっしゃいました。
最上川の中流には、朝日町に上郷ダム(最大出力1万5000?ワット)という大きなダムがあり、カヌーで一気に下ることはできません。このため、上郷地区で一泊して2日かけて川を下るイベントになりました。上郷地区の方々には棚田米で作ったお握りや山形名物の芋煮、収穫したばかりのジャガイモやサヤエンドウを使った味噌汁などの食事を提供していただきました。「山形らしい食事」と、とても好評でした。また、ダムの下流にある赤釜(あかがま)地区の皆様にも全面的に協力していただきました。
「ブナの森」が調べた範囲では、カヌーによる50キロを超える川下りは、北海道の天塩川カヌーツーリング(150キロ)と釧路川カヌーレース(100キロ)に次ぐ、日本で3番目に距離の長いカヌーイベントとみられます。来年以降も7月末に開催して実績を積み、将来は少しずつ距離を延ばして、最上川が日本海にそそぐ酒田市になんとか到達したいと考えています。
そのためには、最上川の中流や下流のカヌー愛好者とネットワークを築いて連携する必要があります。その意味では、今回のカヌー探訪に山形市や酒田市、鶴岡市のカヌーイストが多数参加してくださったのは、心強いかぎりです。第1回の成果と課題をしっかりと総括して、来年のカヌー川下りに備えたいと考えているところです。今後とも、ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
*朝日町のホームページに、カヌー探訪の記事と写真が掲載されました。次のURLをクリックしてください。
http://www.town.asahi.yamagata.jp/
NPO「ブナの森」は、最上川縦断カヌー探訪の企画に賛同し、寄付してくださる方々の善意で
運営されています。会計報告は左の欄の「ブナの森」会計報告をご覧ください。
ご寄付は、下記の郵便振替口座でお受けしています(郵便局から振り込む場合です)。
ご支援をなにとぞよろしくお願いいたします。
口座番号: 02270―7―124933
加入者名: NPOブナの森(エヌピーオーブナノモリ)
郵便局からではなく、一般の都市銀行などから振り込まれる場合には、下記の番号をご記入ください。同じ口座ですが、都市銀行などから振り込む場合には店名や口座番号が変わります。
店名 二二九(ニニキユウ)店番(229) 口座番号 0124933
名義 NPOブナの森(エヌピーオーブナノモリ)
みなさまのご寄付に加えて、平成22年度は山形県朝日町の「志藤六郎村おこし基金・やる気と
挑戦を応援する活気づくり事業」の補助金を受けることになりました。
ホームページとポスターの作成用に30万円の支援をしていただきました。
財政基盤を強くするため、これから自治体や企業、団体など各方面に支援を要請する予定です。
寄付者一覧 (敬称略・アイウエオ順)
【2020年】
 カ行
カ行
菊地 恵里
 サ行
サ行
佐竹 久
 タ行
タ行
崔 鍾八
 ナ行
ナ行
長岡 遼子/西嶋 秀樹
 ハ行
ハ行
林 和明
【2019年】
 ア行
ア行
安藤 昭郎/市川 秀
 カ行
カ行
児玉 譲
 サ行
サ行
佐竹 久
 タ行
タ行
高成田 享/都丸 修一
 ナ行
ナ行
長岡 里子 /長岡 泰子/長岡 遼子
【2019年】 団体寄付
清野りんご園/
【2018年】
 ア行
ア行
安藤 昭郎/飯嶋 和一/市川 秀/
 サ行
サ行
佐竹 久/
 ナ行
ナ行
長岡 泰子/
【2018年】 団体寄付
清野りんご園/
【2017年】
 ア行
ア行
飯嶋 和一/市川 秀/伊藤 富子/
 カ行
カ行
小関 圭子/今野 義之/
 サ行
サ行
佐竹 久/相馬 周一郎/外岡 秀俊
 タ行
タ行
高尾 勝/高成田 享・恵
 ナ行
ナ行
長岡 泰子/
 マ行
マ行
宮田 謙一/
【2017年】 団体寄付
清野りんご園/
【2016年】
 ア行
ア行
飯嶋 和一/市川 秀/
 カ行
カ行
今野 義之/
 ナ行
ナ行
長岡 里子/長岡 泰子/長岡 遼子/
 ハ行
ハ行
萩原さち子/
【2016年】 団体寄付
清野りんご園/
【2015年】
 ア行
ア行
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/飯嶋 和一/市川 秀/伊澤 紘樹/市川 秀/伊藤 富子/井上 和久/大江 志伸/大隅 博英/大峯 伸之
 カ行
カ行
加来 由子/桂 信雄/河谷 史夫/川名 紀美/木村 宰/熊谷 功二 /熊谷 昌彦/小関 圭子/今野 義之
 サ行
サ行
齋藤 隆/斉藤 亮子/佐々木 賢介/鈴木 厚徳/鈴木 恒夫/相馬 周一郎/外岡 秀俊
 タ行
タ行
高木 高久/高成田 享/高橋 典明/玉井 厚子/冨尾 武弘/富田 裕/友部 冬子
 ナ行
ナ行
長岡 泰子/長岡 美智子/永谷 千賀子/中島 鉄郎/仁木 壮/西嶋 善昭
 ハ行
ハ行
萩原さち子/藤山 純一/古川 俊美
 マ行
マ行
松本 仁一/松本 妙子/水田 千益/宮田 謙一
 ヤ行
ヤ行
山内 定義/山本 紘三/横山 嘉太郎
 ワ行
ワ行
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2015年】 団体寄付
清野りんご園/岡山日経懇話会
【2014年】
 ア行
ア行
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/伊澤 紘樹/伊藤 富子/井上 和久/上田 誠也/大峯 伸之
 カ行
カ行
桂 信雄/河谷 史夫/川名 紀美/木村 宰/桐村 英一郎/熊谷 功二/熊谷 昌彦/小関 圭子/今野 義之
 サ行
サ行
斉藤 亮子/佐々木 賢介/澤田 猛/鈴木 恒夫/住川 治人/相馬 周一郎
 タ行
タ行
高橋 典明/玉井 厚子/友部 冬子
 ナ行
ナ行
長岡 里子/長岡 昇/長岡 美智子/長岡 泰子/仁木 壮/西嶋 善昭/野村 彰男
 ハ行
ハ行
萩原 さち子/藤山 純一/古川 俊実
 マ行
マ行
松本 仁一/松本 妙子/宮田 謙一
 ヤ行
ヤ行
山田 修/山内 定義/山本 紘三/横山 嘉太郎
 ワ行
ワ行
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2013年】
 ア行
ア行
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/安藤 昭郎/飯嶋 和一/石澤 良昭/伊藤 富子/井上 和久/入澤 ユカ/岩崎 利宏/大隅 博英/扇長 忠雄/太田 善康/大峯 伸之
 カ行
カ行
加来 由子/桂 信雄/神野 稔章/神野 峯一/川名 紀美/菊地 正明/木村 宰/桐村 英一郎/熊谷 功二/熊谷 昌彦/今野 義之
 サ行
サ行
斉藤 栄司/斉藤 亮子/相馬 周一郎/佐々木 賢介/杉山 文彦/鈴木 恒夫
 タ行
タ行
高木 高久/高橋 典明/玉井 厚子/崔 鍾八/冨尾 武弘/富田 裕/友部 冬子
 ナ行
ナ行
中島 鉄郎/長岡 里子/長岡 泰子/長岡 昇/仁木 壮/西嶋 善昭/野村 彰男
 ハ行
ハ行
萩原 さち子/藤山 純一/古川 俊実
 マ行
マ行
松本 仁一/松本 妙子/宮田 謙一
 ヤ行
ヤ行
山内 定義/山口 直/山本 紘三
 ワ行
ワ行
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2012年】
 ア行
ア行
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/飯嶋 和一/伊澤 紘樹/板垣 喜代志/市川 秀/
井上 和久/遠藤 一男/大江 志伸/大隅 博英/太田 善康/大軒 由敬/大峯 伸之/
尾形 良道
 カ行
カ行
加来 由子/片桐 茂/桂 信雄/川名 紀美/木村 宰/桐野 昌三/小菅 幸一/駒木 克彦
今野 義之
 サ行
サ行
斉藤 栄司/斉藤 長右衛門/佐々木 賢介/佐竹 久/佐藤 明/佐藤 公正/佐藤 雅之/
澤渡 紀子/三部 義道/柴田 津與志/島谷 泰彦/末吉 正憲/杉山 文彦/鈴木 恒夫/
清野 千春/関根 正男/外岡 秀俊
 タ行
タ行
平 善昭/高木 高久/高橋 典明/高間 成之/武田 安英/玉井 厚子/崔 鍾八/長南 平
冨尾 武弘/富田 裕/友部 冬子
 ナ行
ナ行
中川 隆生/中島 鉄郎/中村 圭多郎/長岡 里子/長岡 泰子/長岡 昇/長岡 典巳/
長岡 美智子/長岡 遼子/長場 馨/仁木 壮/西嶋 善昭/西山 利行/西山 征夫
 ハ行
ハ行
萩原 さち子/林 和明/藤山 純一/古川 俊実
 マ行
マ行
松本 妙子/水田 千益/宮田 謙一
 ヤ行
ヤ行
山内 定義/山本 紘三/遊快倶楽部/横山 嘉太郎
 ワ行
ワ行
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2011年】
 ア行
ア行
浅井 隆夫/浅沼 知行/足立 雅/天田 栄一/安藤 昭郎/飯嶋 和一/伊澤 紘樹/
伊澤 良治/市野 功/井上 和久/井上 智恵美/碓井 祐司/海野 和幸/遠藤 和久/
大江 志伸/大隅 博英/太田 善康/大軒 由敬/奥山 勝弘/小田 尚/大峯 伸之/
 カ行
カ行
加来 由子/片桐 茂/桂 信雄/河西 努/川名 紀美/木村 宰/桐村 英一郎/工藤 正年
熊谷 昌彦/熊谷 功二/小菅 幸一/児珠 孝童/小林 貞夫/小林 道和/今野 義之/
 サ行
サ行
斉藤 栄司/斉藤 長右衛門/齊藤 隆/齊藤 亮子/佐々木 賢介/佐竹 久/定森 大治/
佐藤 公正/沢田 猛/澤渡 紀子/斯波 成尚/柴田 ひろみ/柴田 泰子/須藤 繁/
住川 治人/杉山 文彦/鈴木 慎一/鈴木 恒夫/鈴木 利治/関根 正男/相馬 周一郎/
 タ行
タ行
高尾 勝/高木 高久/高野 正夫/高橋 典明/高橋 禮介/多田 秀人/玉井 厚子/
冨尾 武弘/富田 裕 /友部 冬子
 ナ行
ナ行
中島 鉄郎/長岡 泰子/長岡 昇/仁木 壮/西山 征夫/野村 彰男
 ハ行
ハ行
萩原 さち子/橋間 博美/広岩 邦彦/藤山 純一/古川 俊実/堀 浩一/堀 俊一/堀 幸雄
 マ行
マ行
前田 耕作/幕田 英雄/松本 仁一/松本 妙子/宮田 謙一
 ヤ行
ヤ行
矢野 秀弥/山内 定義/山口 直/山田 中正/山本 紘三
 ワ行
ワ行
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2010年】
 ア行
ア行
相本 久子/浅井 隆夫/浅沼 知行/足立 雅 / 天田 栄一/荒谷 一成/飯嶋 和一/
伊澤 紘樹/石澤 良昭/市野 功 / 井上 和久/入澤 ユカ/岩崎 利宏/上田 誠也/
碓井 祐司/宇野 秀 / 海野 和幸/遠藤 和久/遠藤 富雄/大江 ち江/大図 俊朗/
大隅 博英/ 太田 善康/大軒 由敬/大峯 伸之/岡本 浩史/奥山 勝明/小田 尚 /
小野 真哉/翁長 忠雄
 カ行
カ行
加来 由子/ 桂 信雄/河谷 史夫/川名 紀美/木村 宰 /桐村 英一郎/上坂 樹/
熊谷 功二/熊谷 昌彦/小島 宏明/小関 圭子/小林 貞夫/駒木 克彦/今野 義之/
 サ行
サ行
斉藤 栄司/斎藤 鑑三/齊藤 滋/齊藤 隆/佐々木 賢介/定森 大治/佐藤 和孝/
佐藤 公正/沢田 猛 /三部 義道/島田 博/常名 恒夫/末吉 正憲/杉山 文彦/
鈴木 慎一/鈴木 恒夫/住川 治人/関根 正男/相馬 周一郎/外岡 秀俊/
 タ行
タ行
高尾 勝/高木 高久/高野 正夫/高橋 典明/多田 秀人/玉井 厚子/冨尾 武弘/
富田 裕/友部 冬子/
 ナ行
ナ行
中川 隆生/中島 鉄郎/長岡 里子/長岡 泰子/長岡 昇/長岡 遼子/長場 馨/
成原 孝一/成原 千枝/仁木 壮/西川 幸治/野村 彰男/
 ハ行
ハ行
萩原 さち子/藤山 純一/古川 俊実/古田 博己/堀野 典久/
 マ行
マ行
前田 耕作/増子 義久/松島 日世士/松本 仁一/松本 妙子/幕田 英雄/水田 千益/
宮川 ひろ/宮城 倉次郎/宮田 謙一
 ヤ行
ヤ行
矢野 秀弥/山内 定義/山口 直/山田 修/山本 紘三
 ラ行
ラ行
 ワ行
ワ行
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
寄付団体一覧 (アイウエオ順)
【2013年】
全国地域結婚支援センター/田川地区平和センター/西村山地区歯科医師会/
ふるさと共生塾(東根市)
【2012年】
インド徳里会/ジェネシス(株)/全国地域結婚支援センター/(株)米月山/(株)マグエバー/
和歌の宿 わかまつや
【2011年】
インド徳里会/ジェネシス(株)/(株)マグエバー/和歌の宿 わかまつや/(株)米月山
【2010年】
インド徳里会/ガネーシャ会/こころのクリニック山形/ジェネシス(株)/和歌の宿 わかまつや/
(株)伊藤製作所/(株)米月山/(株)マグエバー/(株)マグナ/(株)ムラヤマ
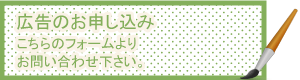
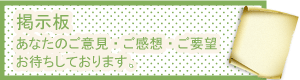
運営されています。会計報告は左の欄の「ブナの森」会計報告をご覧ください。
ご寄付は、下記の郵便振替口座でお受けしています(郵便局から振り込む場合です)。
ご支援をなにとぞよろしくお願いいたします。
口座番号: 02270―7―124933
加入者名: NPOブナの森(エヌピーオーブナノモリ)
郵便局からではなく、一般の都市銀行などから振り込まれる場合には、下記の番号をご記入ください。同じ口座ですが、都市銀行などから振り込む場合には店名や口座番号が変わります。
店名 二二九(ニニキユウ)店番(229) 口座番号 0124933
名義 NPOブナの森(エヌピーオーブナノモリ)
みなさまのご寄付に加えて、平成22年度は山形県朝日町の「志藤六郎村おこし基金・やる気と
挑戦を応援する活気づくり事業」の補助金を受けることになりました。
ホームページとポスターの作成用に30万円の支援をしていただきました。
財政基盤を強くするため、これから自治体や企業、団体など各方面に支援を要請する予定です。
寄付者一覧 (敬称略・アイウエオ順)
【2020年】
菊地 恵里
佐竹 久
崔 鍾八
長岡 遼子/西嶋 秀樹
林 和明
【2019年】
安藤 昭郎/市川 秀
児玉 譲
佐竹 久
高成田 享/都丸 修一
長岡 里子 /長岡 泰子/長岡 遼子
【2019年】 団体寄付
清野りんご園/
【2018年】
安藤 昭郎/飯嶋 和一/市川 秀/
佐竹 久/
長岡 泰子/
【2018年】 団体寄付
清野りんご園/
【2017年】
飯嶋 和一/市川 秀/伊藤 富子/
小関 圭子/今野 義之/
佐竹 久/相馬 周一郎/外岡 秀俊
高尾 勝/高成田 享・恵
長岡 泰子/
宮田 謙一/
【2017年】 団体寄付
清野りんご園/
【2016年】
飯嶋 和一/市川 秀/
今野 義之/
長岡 里子/長岡 泰子/長岡 遼子/
萩原さち子/
【2016年】 団体寄付
清野りんご園/
【2015年】
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/飯嶋 和一/市川 秀/伊澤 紘樹/市川 秀/伊藤 富子/井上 和久/大江 志伸/大隅 博英/大峯 伸之
加来 由子/桂 信雄/河谷 史夫/川名 紀美/木村 宰/熊谷 功二 /熊谷 昌彦/小関 圭子/今野 義之
齋藤 隆/斉藤 亮子/佐々木 賢介/鈴木 厚徳/鈴木 恒夫/相馬 周一郎/外岡 秀俊
高木 高久/高成田 享/高橋 典明/玉井 厚子/冨尾 武弘/富田 裕/友部 冬子
長岡 泰子/長岡 美智子/永谷 千賀子/中島 鉄郎/仁木 壮/西嶋 善昭
萩原さち子/藤山 純一/古川 俊美
松本 仁一/松本 妙子/水田 千益/宮田 謙一
山内 定義/山本 紘三/横山 嘉太郎
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2015年】 団体寄付
清野りんご園/岡山日経懇話会
【2014年】
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/伊澤 紘樹/伊藤 富子/井上 和久/上田 誠也/大峯 伸之
桂 信雄/河谷 史夫/川名 紀美/木村 宰/桐村 英一郎/熊谷 功二/熊谷 昌彦/小関 圭子/今野 義之
斉藤 亮子/佐々木 賢介/澤田 猛/鈴木 恒夫/住川 治人/相馬 周一郎
高橋 典明/玉井 厚子/友部 冬子
長岡 里子/長岡 昇/長岡 美智子/長岡 泰子/仁木 壮/西嶋 善昭/野村 彰男
萩原 さち子/藤山 純一/古川 俊実
松本 仁一/松本 妙子/宮田 謙一
山田 修/山内 定義/山本 紘三/横山 嘉太郎
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2013年】
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/安藤 昭郎/飯嶋 和一/石澤 良昭/伊藤 富子/井上 和久/入澤 ユカ/岩崎 利宏/大隅 博英/扇長 忠雄/太田 善康/大峯 伸之
加来 由子/桂 信雄/神野 稔章/神野 峯一/川名 紀美/菊地 正明/木村 宰/桐村 英一郎/熊谷 功二/熊谷 昌彦/今野 義之
斉藤 栄司/斉藤 亮子/相馬 周一郎/佐々木 賢介/杉山 文彦/鈴木 恒夫
高木 高久/高橋 典明/玉井 厚子/崔 鍾八/冨尾 武弘/富田 裕/友部 冬子
中島 鉄郎/長岡 里子/長岡 泰子/長岡 昇/仁木 壮/西嶋 善昭/野村 彰男
萩原 さち子/藤山 純一/古川 俊実
松本 仁一/松本 妙子/宮田 謙一
山内 定義/山口 直/山本 紘三
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2012年】
阿久沢 寛/浅沼 知行/足立 雅/飯嶋 和一/伊澤 紘樹/板垣 喜代志/市川 秀/
井上 和久/遠藤 一男/大江 志伸/大隅 博英/太田 善康/大軒 由敬/大峯 伸之/
尾形 良道
加来 由子/片桐 茂/桂 信雄/川名 紀美/木村 宰/桐野 昌三/小菅 幸一/駒木 克彦
今野 義之
斉藤 栄司/斉藤 長右衛門/佐々木 賢介/佐竹 久/佐藤 明/佐藤 公正/佐藤 雅之/
澤渡 紀子/三部 義道/柴田 津與志/島谷 泰彦/末吉 正憲/杉山 文彦/鈴木 恒夫/
清野 千春/関根 正男/外岡 秀俊
平 善昭/高木 高久/高橋 典明/高間 成之/武田 安英/玉井 厚子/崔 鍾八/長南 平
冨尾 武弘/富田 裕/友部 冬子
中川 隆生/中島 鉄郎/中村 圭多郎/長岡 里子/長岡 泰子/長岡 昇/長岡 典巳/
長岡 美智子/長岡 遼子/長場 馨/仁木 壮/西嶋 善昭/西山 利行/西山 征夫
萩原 さち子/林 和明/藤山 純一/古川 俊実
松本 妙子/水田 千益/宮田 謙一
山内 定義/山本 紘三/遊快倶楽部/横山 嘉太郎
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2011年】
浅井 隆夫/浅沼 知行/足立 雅/天田 栄一/安藤 昭郎/飯嶋 和一/伊澤 紘樹/
伊澤 良治/市野 功/井上 和久/井上 智恵美/碓井 祐司/海野 和幸/遠藤 和久/
大江 志伸/大隅 博英/太田 善康/大軒 由敬/奥山 勝弘/小田 尚/大峯 伸之/
加来 由子/片桐 茂/桂 信雄/河西 努/川名 紀美/木村 宰/桐村 英一郎/工藤 正年
熊谷 昌彦/熊谷 功二/小菅 幸一/児珠 孝童/小林 貞夫/小林 道和/今野 義之/
斉藤 栄司/斉藤 長右衛門/齊藤 隆/齊藤 亮子/佐々木 賢介/佐竹 久/定森 大治/
佐藤 公正/沢田 猛/澤渡 紀子/斯波 成尚/柴田 ひろみ/柴田 泰子/須藤 繁/
住川 治人/杉山 文彦/鈴木 慎一/鈴木 恒夫/鈴木 利治/関根 正男/相馬 周一郎/
高尾 勝/高木 高久/高野 正夫/高橋 典明/高橋 禮介/多田 秀人/玉井 厚子/
冨尾 武弘/富田 裕 /友部 冬子
中島 鉄郎/長岡 泰子/長岡 昇/仁木 壮/西山 征夫/野村 彰男
萩原 さち子/橋間 博美/広岩 邦彦/藤山 純一/古川 俊実/堀 浩一/堀 俊一/堀 幸雄
前田 耕作/幕田 英雄/松本 仁一/松本 妙子/宮田 謙一
矢野 秀弥/山内 定義/山口 直/山田 中正/山本 紘三
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
【2010年】
相本 久子/浅井 隆夫/浅沼 知行/足立 雅 / 天田 栄一/荒谷 一成/飯嶋 和一/
伊澤 紘樹/石澤 良昭/市野 功 / 井上 和久/入澤 ユカ/岩崎 利宏/上田 誠也/
碓井 祐司/宇野 秀 / 海野 和幸/遠藤 和久/遠藤 富雄/大江 ち江/大図 俊朗/
大隅 博英/ 太田 善康/大軒 由敬/大峯 伸之/岡本 浩史/奥山 勝明/小田 尚 /
小野 真哉/翁長 忠雄
加来 由子/ 桂 信雄/河谷 史夫/川名 紀美/木村 宰 /桐村 英一郎/上坂 樹/
熊谷 功二/熊谷 昌彦/小島 宏明/小関 圭子/小林 貞夫/駒木 克彦/今野 義之/
斉藤 栄司/斎藤 鑑三/齊藤 滋/齊藤 隆/佐々木 賢介/定森 大治/佐藤 和孝/
佐藤 公正/沢田 猛 /三部 義道/島田 博/常名 恒夫/末吉 正憲/杉山 文彦/
鈴木 慎一/鈴木 恒夫/住川 治人/関根 正男/相馬 周一郎/外岡 秀俊/
高尾 勝/高木 高久/高野 正夫/高橋 典明/多田 秀人/玉井 厚子/冨尾 武弘/
富田 裕/友部 冬子/
中川 隆生/中島 鉄郎/長岡 里子/長岡 泰子/長岡 昇/長岡 遼子/長場 馨/
成原 孝一/成原 千枝/仁木 壮/西川 幸治/野村 彰男/
萩原 さち子/藤山 純一/古川 俊実/古田 博己/堀野 典久/
前田 耕作/増子 義久/松島 日世士/松本 仁一/松本 妙子/幕田 英雄/水田 千益/
宮川 ひろ/宮城 倉次郎/宮田 謙一
矢野 秀弥/山内 定義/山口 直/山田 修/山本 紘三
鷲沢 毅/渡辺 茂樹
寄付団体一覧 (アイウエオ順)
【2013年】
全国地域結婚支援センター/田川地区平和センター/西村山地区歯科医師会/
ふるさと共生塾(東根市)
【2012年】
インド徳里会/ジェネシス(株)/全国地域結婚支援センター/(株)米月山/(株)マグエバー/
和歌の宿 わかまつや
【2011年】
インド徳里会/ジェネシス(株)/(株)マグエバー/和歌の宿 わかまつや/(株)米月山
【2010年】
インド徳里会/ガネーシャ会/こころのクリニック山形/ジェネシス(株)/和歌の宿 わかまつや/
(株)伊藤製作所/(株)米月山/(株)マグエバー/(株)マグナ/(株)ムラヤマ
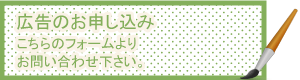
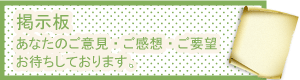
*メールマガジン「おおや通信 86」 2012年7月13日
今の子どもたちにとって、炎とは「青いもの」である。スイッチをひねれば、青いガスの炎が勢いよく噴き出してくる。長い間、人間が使いこなしてきたのは赤い炎なのだが、今やそれを目にする機会はめったにない。学校教育で「赤い炎」を教えなければならない時代になった。
修正版.jpg)
宿泊学習では、みんなでドラム缶風呂に入ります。子どもたちに大人気です
大谷小学校では、それを朝日少年自然の家(大江町)での宿泊学習で教えている。野外での2泊3日のテント生活である。
「火の焚き方も、調理の仕方も一切、教えないでください」
テントを張り終わって間もなく、私は6年担任の教師から、くぎを刺された。「それでは、まともに煮炊きできないんじゃないの」と心配する校長に、この教師は涼しい顔で言い放った。
「いいんです。失敗して、泣いて覚えればいいんです」
1日目の夕食はカレーライス。案の定、子どもたちはまともに火を焚くことができない。かまどにドテッと薪を置き、その上に古新聞をかぶせて火をつけている。これでは燃え上がるわけがない。それでも容赦なく、夕食の時間になる。ポロポロのご飯と生煮えの「カレースープ」を口にして、泣いている子もいた。
翌朝から、おいしいものを食べたい一心で、みんなが火の焚き方を必死になって覚えようとする。そうやって、3日目にはどの班でも、ちゃんとご飯を炊けるようになった。
テント場のわきのトイレは汲み取り式である。水洗トイレしか知らない子の中には「できない」と泣きベソをかく子もいる。ここでも、子どもたちは泣きながら学ぶのだ。あらゆる動物は、食べなければ生きていけない。同時に、排泄しなければ苦しみ、やがては死んでしまうことを。
保護者からは「水洗トイレにしてほしい」といった声も寄せられるという。そんな声に屈してはならない。世の中には「親の気持ち」より大切なこともある。
*7月13日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(4)
*メールマガジン「おおや通信 85」 2012年7月6日
自分の出身県ながら、このごろ「山形県は偉いなぁ」と、つくづく思います。
昨年の東日本大震災の後、ガソリンや灯油が手に入らず、みんなとても困りました。それでも、山形県内では不満を口にする人はあまりいませんでした。「まずは津波の被災地に早くガソリンを届けなければいけない。私たちは我慢しよう」。そう思い定めて、みんなで耐え忍びました。

大津波に襲われた宮城県石巻市の沿岸部の惨状(2011年4月24日)
岩手県や宮城県の被災地が膨大な量のがれきの処理に困っていると知るや、真っ先に受け入れを表明したのも山形県でした。「頑張れ!東北」などと声高に叫びながら、いざ自分の所でがれきを受け入れる段になると「放射能で汚染されている恐れがある」といった住民のクレームを理由に受け入れを渋る自治体が多い中で、その潔さは際立っていました。
福島県からは、原発事故の影響で小中学生の県外脱出が相次いでいます。その子どもたちを一番多く受け入れているのも山形県です。米沢市や山形市の奮闘ぶりには、本当に頭が下がります。
「まさかの時の友こそ真の友」という英語の格言があります。
A friend in need is a friend indeed.
高校の英語の授業で教わりました。忘れられない格言の一つです。
困っている時に手を差し伸べてくれる友人こそ本当の友人、という意味です。山形の人たちの行動こそ、その良いお手本でしょう。
こうしたことを外に向かって宣伝しないのも、山形らしいところでしょうか。正直者が馬鹿を見る貧しい社会から、正直者がきちんと報われる豊かな社会へ。難しい道かもしれませんが、そうした社会に向かって一歩ずつ進んで行きたい。
*大谷小学校のPTA便り「おおや」第88号(平成24年6月15日発行)の
連載コラム「豊かさとは何か(10)」に加筆
*メールマガジン「おおや通信 84」2012年6月15日
会議や研修会で校長が大勢集まると、休憩時間によく給食の話になる。息抜きの時間なので、本音がストレートに出てくる。「給食が飛び抜けておいしい」と評判なのは高畠町である。有機農業の里として全国に知られているだけあって、そもそも食材がいいのだろう。調理師さんたちも頑張っているからに違いない。
 修正版.jpg)
大谷小学校では学年ごとに学校の畑で野菜を栽培しています。1年生が作っているのは
ピーマン、サツマイモ、トウモロコシ、トマトの4種類。一部は給食の食材にします
ピーマン、サツマイモ、トウモロコシ、トマトの4種類。一部は給食の食材にします
その対極にあるのが山形市だ。「給食の時間がつらい」とこぼす校長が多い。私も何度か食べたが、お世辞にも「おいしい」とは言えない。ついこの間も、山形市から別のところに異動になった校長が「ホッとした」と話していた。
評判が悪くて当然である。山形市は大規模な給食センターで2万食以上をまとめて作り、51の小中学校に配送している。調理師さんがどんなに腕を振るっても、炊き立てのご飯を提供する自校給食にかなうはずがない。
どこの市町村も財政は火の車だ。人件費の削減を迫られ、給食を民営化する動きが広がっている。給食センターで一括して作れば、経費が浮くのは確かだろう。
しかし、食は学力、体力すべての基盤である。そこに金と力を注ぎ込むことを惜しんで「子どもは地域の宝です」などと言っても、誰も信用しないだろう。
「民営化しても、おいしい給食を出すことはできる」と言う人もいる。理屈はそうだが、現実はそんなに甘くはない。企業はもうけを出さなければ立ち行かない。それは逃れられない定めであり、給食の質に必ず跳ね返ってくる。
自校給食を民営化すれば、調理師さんは職員会議に出て来なくなる。子どもと接する大人たちが一体となって教育にあたるチームワークが崩れる。これはコスト論では推し量れない大きな損失である。
目に見えないもの。数字では表せないもの。それをたぐり寄せる英知こそ、今、求められているのではないか。
*6月15日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(3)
*改行個所や写真の説明は一部、新聞のコラムとは異なります。
*メールマガジン「おおや通信 83」2012年5月27日
3年前に私が校長として赴任した時、大谷小学校の生徒は89人でした。その後、90人、80人と増減し、4年目の今年は78人になりました。閉校になる心配は当面ありませんが、これからもじりじりと減り続けます。
では、明治6年の創立以来、大谷小の生徒数が一番多かったのはいつか。校長に成りたてのころ、調べたことがあります。「きっと、戦後のベビーブームのころだろう」と思いました。
男たちが戦場から続々と故郷に戻ったのは、昭和20年から23年ごろでした。厚生労働省の統計によると、日本の赤ちゃん誕生のピークは昭和24年で269万人です。ならば、小学校の生徒数のピークは昭和30年前後になるはずです。
ところが、意外なことに大谷小の生徒数のピークは昭和21年の716人でした。疑問に思いながらも「戦争が始まる前に生まれた子どもが多かったのだろう」と、漠然と考えていました。
最近、そうではなかったことを知りました。私の小学校時代の恩師(81歳)が大谷小を訪ねてきて、こんな昔話をしてくれたからです。
「女学校を出たばかりで、私はまだ16歳でした。そのころ(昭和22年)は先生が足りなくてねぇ。なんとか教壇に立ってくれないかと頼まれて、西五百川(にしいもがわ)小学校の先生になったんですよ。初めて持った学級の子どもが54人。疎開してきていた子も多くて、地元の子とよく喧嘩になっていました」
当時を知る年配の方に確認したところ、西五百川小だけでなく、町内のほかの小学校にも疎開児童がかなりいた、とのことでした。農村では、戦争による疎開が生徒数のピークを変えるほど多かったのです(私は昭和28年生まれ、小学校入学は昭和34年です)。
時はめぐり、今、「第二の疎開」とも言うべき現象が起きています。原発事故によって多くの児童生徒が福島県から逃げ出しました。文部科学省の調査によれば、その数は昨年の9月時点で1万1918人でした(幼稚園、小中学校、高校の合計)。最も多く受け入れているのは山形県です。福島県と境を接する米沢市や、県庁所在地の山形市が主な受け入れ先になっています。
子どもが追い立てられ、逃げなければならない――時代背景も理由も異なりますが、なんとも切ないことが21世紀の日本で起きています。しかも、その「第二の疎開」が原発事故から1年以上たった今の時点でもそれほど減っていないのです。
米沢市の教育委員会によると、同市に避難してきた小中学生は昨年12月の267人がピークで、徐々に福島県に戻って減る傾向にありましたが、この春になってまた増え、262人に達したそうです。「原発のある福島県の浜通りではなく、(福島市や郡山市がある)中通りからの転校生が増えているのが特徴です。とくに小学1年生がたくさん転校してきました」と市教委の担当者が説明してくれました。
政府が「原発事故の収束宣言」をし、「食品の放射能汚染はしっかり検査をしています」と言ってみても、子を持つ親は信じていません。自分で判断し、自分にできる方法でわが子を守ろうとしているのです。
この期に及んでも、原発建設を推進してきた人たちの中には「脱原発など絵空事だ」と言い張り、電力の原発依存を維持しようとする人たちがいます。その人たちに、私は問うてみたい。「あなたには、自ら福島原発の近くに住み続ける覚悟がありますか。わが子を、自分の家族を、自分の親を住まわせ続ける覚悟はありますか」と。
即座に「もちろん」と答えることができる人とならば、「原発依存をどうやって減らしていくのか」「代替エネルギーの開発をどう進めるのか」について真剣に議論をしてみたい。けれども、わが子を避難させる親たちの苦悩に思いが及ばないような人たちとは議論すら難しいだろう。謙虚な気持ちで未来を見つめようとする心がないのだから。
*メールマガジン「おおや通信 82」 2012年5月18日
校長として小学生に話をするのは、中高生や大人を相手にするのとは違った難しさがある。
1年生はひらがなを習い始めたばかりである。話の中に知らない言葉が出てくると、途端に頭がぐらつき出し、「なに言ってんのか分かんない」という顔になる。かといって、かみ砕きすぎると、6年生がそっぽを向く。こちらは大人の世界への入り口にいる。両方によく分かり、なおかつ心に残る話をするのは容易なことではない。
修正2.jpg)
大谷小学校の近くにある秋葉山に、みんなで春を探しに行きました
去年は大震災の話をした。津波はどうして起きるのか。被災地はどんな状況にあるのか。ボランティアに行って泥かきをした体験を交えながら、できるだけ分かりやすい言葉で語りかけた。
原発の仕組みと事故の話もした。この時は、子どもたちの知らない言葉も使わざるを得なかった。かつて、北海道の泊原発を取材したことがある。その際に入手した燃料棒のサンプルを示しながら、こう述べた。
「この棒はジルコニウムという金属でできています。硬いけれども、1800度くらいで溶けてしまいます。そうなったら大変なことになります」
難しい話だったに違いない。けれども、どの子も食い入るようにして聞いていた。何か、とてつもないことが起きていることを察知していたからだろう。子どもたちは、未熟ではあっても愚かではない。「これは大事だ」と感じたら、一生懸命に理解しようとする。子どもだましの話でお茶を濁してはいけない。
今年は毎月、命について話をしたいと考えている。4月のテーマは「いのちと地球」。地球が誕生したのは46億年前とされる。人間が登場したのはついこの間、子どもに大人気の恐竜ですら、生き物としては新参者である。
恐竜より古い時代に生きていた不思議な動物たちのイラストを見せたら、何人かが「オオッ」と身を乗り出してきた。
*2012年5月18日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から 朝日町発」(2)
*メールマガジン「おおや通信 81」 2012年4月13日
山形県の朝日町では、学校のグラウンドの雪がようやく消えて地面が見え始めました。
年配の方に聞いても、これほどの大雪は生まれて初めてとのことでした。
4月から月に1回(第2金曜日)、朝日新聞の山形県版に小さなコラムを書くことに
なりました。暗?い記事ばかり書いてきた元アジア担当記者としては、つとめて明るい
タッチのコラムにしたいと念じています。とっても難しいです。
? ? ?
コラム「学びの庭から 朝日町発」 子どもの目 光る時にこそ
子どもがじっとこちらを見ていたら、気をつけた方がいい。ある時、給食で同じテーブルにいた子どもの目の隅がキラリと光った。
校長「どうした?」
生徒「先生、鼻毛が白いよ」

この春、大谷小には11人の1年生が入学しました。玄関前には、除雪した雪がまだたくさん残っています。
子どもは気配りということをまだ知らない。見たこと、面白いと思ったことをズバリと言う。この子は、白髪がある大人は鼻毛も白いことをこの時、初めて「発見」したのだろう。「よく見つけたねぇ。ニャロメ!」。ここは、怒りつつ褒めるしかあるまい。
新聞記者から小学校の校長に転じて3年になる。ある人が「子どもの目には、この世の
中はとても明るく見えているのです」と言っていた。その通りだと思う。小学生にとっては、毎日が発見の連続である。自分の小さな世界がどんどん広がっていく。私たちが想像する以上に、世の中が明るく見えているに違いない。
大震災とそれに続く福島の原発事故で、この国はとても「明るい状態」とは言えない。彼らが生まれる前から、経済は右肩下がり。国の借金も、ものすごい額だ。けれども、長い歴史の中に身を置いてみれば、実はそれほど暗くなる必要もない。
明治までさかのぼるまでもなく、昭和ですら冷害で飢餓にあえぎ、娘の身売りが横行した時代があった。父祖の時代、若者は戦場に送られ、次々に死んでいった。われわれの世代で言えば、学びたくても学ぶ機会をつかめない人がたくさんいた。
それらをすべて乗り越えて、今がある。厚い蓄積の上に現在の暮らしがある。問われて
いるのは、その蓄積を次の世代にどのように伝え、どう活かしていくかだろう。
子どもの目がキラリと光った時にこそ伝えたい。この国の豊かな蓄積を、おおらかな気持ちで。
*このホームページに掲載した写真は、朝日新聞山形版に掲載されたコラムの写真とは異なります。
*メールマガジン「おおや通信 80」 2012年4月6日
東京では桜が満開のようですが、山形はまだ冬です。今日も、未明から雪が降り続きました。今年は「春まだ浅き」ではなく、「春まだ遠き」という風情です。そんな北国の農村にある小学校から、入学式の校長あいさつをお送りします。
? ? ?
いつもの年なら「春爛漫」という時節なのですが、今年の春はかなり変わっています。朝から雪がのしのしと降りました。学校のグラウンドも一面、まだ白い雪に覆われたままです。あたたかい春の風を待ちわびる中での入学式になりました。
11人の1年生のみなさん、入学おめでとうございます。
つい先日、みなさんが通っていた「あさひ保育園」で卒園式があり、私も出席させていただきました。そこで今日は、そのおさらいから始めたいと思います。卒園式では、来賓の方々からたくさん御祝いの言葉をいただきました。その中に、とっても大切な教えがありました。それは何だったでしょうか? 覚えていますか?
それは「何よりもまず、交通事故に気をつけましょう」という教えです。鈴木浩幸町長がおっしゃっていました。毎朝、学校に行く時、そして学校からおうちに帰る時、車には十分に気をつけなければなりません。ふさげて道路に飛び出したりしては、絶対にいけません。毎日、元気に学校に通って、元気におうちに帰る。まず、これをしっかりと行うことが大切です。分かりましたか?
次に大切なこと。それは、学校で自分の好きなこと、得意なことを見つけることです。本を読むのが好きなひとは、静かに本を読みましょう。駆けっこが得意な人は、雪が消えたらグラウンドを思いっ切り走りましょう。絵を描いたり、歌を歌ったりするのが好きな人は、たくさん絵を描き、たくさん歌いましょう。「元気で楽しい学校」――それが大谷小学校のスローガンです。毎日、元気に学校に通い、教室にいるのが楽しくなるような、そんな学校を一緒につくっていきましょう。
3番目は、私からのお願いです。みなさんは保育園を卒業して、きょうから小学生になりました。これまではお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんのお世話になってばかりだったかもしれませんが、これからはそれではいけません。おうちの中で自分にできることを探して、毎日、ちゃんとお手伝いをするようにしましょう。小さな事でいいのです。例えば、朝、起きたら、自分の布団は自分でたたむ。ご飯を食べる時に、みんなの茶碗を並べてあげる。そうしたことを自分で見つけて、おうちの人のお手伝いを毎日するように心がけましょう。分かりましたか。
2年生から6年生のみなさん。11人の1年生を迎えて、大谷小学校の生徒は78人になりました。去年より少し少なくなりましたが、その分、みんなで補い合って、より良い学校になるように頑張りましょう。慣れない1年生の面倒をよく見てあげてください。
保護者のみなさま。お子様のご入学、おめでとうございます。いつの時代であっても、子どもを育てるというのは容易なことではありません。お一人お一人、語り尽くせぬほどのご苦労をされたことと拝察いたします。お子様を大谷小学校に入学させていただいたことに、教職員を代表して心から御礼を申し上げます。
子どもたちは、小学校の6年間でいろいろなことを吸収し、驚くほどの成長を遂げます。保護者の皆様方と手を携えて、私たちはその成長を促し、支えるために全力を尽くすことをお誓い申し上げます。
ご来賓のみなさま。きょうは雪が降る中、大谷小学校の入学式にご臨席たまわり、誠にありがとうございました。子どもは家庭と学校に加えて、地域の力で育っていくものですが、朝日町には地域全体、町民みんなで子どもを育てていこうという、そういう気概があふれています。さまざまな場面で、学校の運営を支えていただいていることに改めて深く感謝申し上げます。
今後とも、より一層のご支援とご協力をたまわりますようお願い申し上げて、入学式のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
*メールマガジン「おおや通信 79」2012年3月18日
3月は、風光る月、とも言われます。風が光るように吹き渡る月です。日差しが強くなり、雪解け水が日ごとに勢いを増す季節になりました。多くの人が新しい場所、見知らぬ土地へと旅立つ季節でもあります。
13人の6年生も、その時を迎えました。卒業、おめでとうございます。6年間、大谷小学校に元気に通ってくれたこと、そして、この1年間は学校の大黒柱の役割を果たしてくれたことに、教職員を代表して心から「ありがとう」という言葉を贈りたいと思います。
一人ひとりに、はなむけの言葉を贈ります。

長岡龍輝(たつき)君。
君は、秋の運動会の応援合戦でミゲルに扮して、大いに沸かせてくれました。図書委員としての読み聞かせでも、人気抜群でした。折に触れて、大谷小学校を笑顔でいっぱいにしてくれて、本当にありがとう。大谷剣道スポーツ少年団でも大事な役割を果たしてくれました。目標は、人の命を助ける消防士になること。体を鍛え、よく勉強して、たくましい消防士になってください。
菅井茉衣(まい)さん。
あなたは、今年の学校文集に載った作文で東日本大震災のことを書いていました。停電で寒かったこと、テレビで津波が押し寄せる音を聞いて怖かったことを綴っていました。そのうえで「生き残ったこの命を大切にして、被災した人たちが復興できるように応援していきたい」と書いていました。思ったことを素直に綴った、とてもいい作文でした。幼稚園の先生になるのが夢ですね。優しい心を大切にして、子どもたちに慕われる先生になってください。
長岡知緩(ともひろ)君。
君とは、3学期の給食の時間によく同じテーブルになりました。食事をしながら、君は同じ班の下級生の面倒を実によくみていました。掃除の時にも、丁寧にやり方を教えてあげていましたね。見えにくいところで、気を配ってくれていました。ありがとう。中学に進んだらテニスをしたいと言っています。部活動でも細やかな気配りをして、いい雰囲気の部になるよう努めてください。
菅井芽衣(めい)さん。
左沢(あてらざわ)にある少年自然の家で宿泊体験学習をした時、みんなで木をこすり合わせて火をおこすことに挑戦しました。この時、真っ先に火をおこすことに成功したのは芽衣さんの班でした。その時の、大喜びした顔をよく覚えています。一生懸命に努力すれば、天は必ず報いてくれます。目標はやさしい美容師さんになることですね。一歩一歩進んで、夢を叶えてください。
志藤理央(りお)君。
町の水泳競技記録会で、君はリレーと背泳ぎに出場し、金メダルを3つも手にしました。見事な泳ぎでした。苦しさに耐え、何度も何度も練習した成果でした。一歩ずつ着実に進むことの大切さをみんなに教えてくれました。中学や高校に進んでも水泳を続け、いつの日か「世界の北島康介選手を超えたい」と夢見ています。高い目標ですが、志と目標は高いほどいいのです。挑戦してください。
堀 杏菜(あんな)さん。
5年生の時に、みんなで米作りの勉強をしました。その田んぼは杏菜さんのおうちの田をお借りしました。田植えの時も稲刈りの時も、お父さんをサポートしてみんなを引っ張ってくれました。夏の花笠祭りに参加した時にも、たくさん汗をかき、頑張ってくれました。ありがとう。目標は、料理研究家になって新しい料理を創り出すこと。いつか、誰も考えつかないような料理を作って、みんなを喜ばせてください。
白田匠摩(しょうま)君。
去年の文化祭のフィナーレは、カントリーロードの全校合唱でした。その冒頭で、君は独唱し、澄んだ歌声を響かせてくれました。とても魅力的な独唱でした。大工さんをしているお父さんと同じ道を歩みたい、と言っています。修行を積んで立派な大工さんになって、地震でもびくともしない家をどんどん建ててください。
畑 愛佳理(あかり)さん。
あたなは、言葉数は少ないけれども、とても豊かな感受性を持っています。学校文集の扉に「マット運動は苦手」という、あなたの詩が載っています。その詩は「くやしさと苦労の分だけ、大きな喜びが返ってくる」と結ばれていました。言葉遣いの豊かさに感心しました。小さい時から料理が好きで、お菓子を作るパティシエになるのが目標ですね。持ち前の感覚をお菓子作りに活かしてください。
阿部大悟(だいご)君。
モンテディオ山形のコーチが大谷小学校にサッカーを教えに来てくれた日のことを思い出します。コーチが「だれか手伝ってくれる人はいませんか?」と言うと、君は真っ先に「ハイ!」と手を挙げました。新しいことに果敢に挑戦する君らしい行動でした。とても大切なことです。寿司屋さんになるのが目標ですね。大人になっても、その気持ちを忘れず、新しい事にどんどん挑戦し続けてください。
武田七海(ななみ)さん。
あなたは、6年間で一番思い出に残ったこととして、大朝日岳への登山を挙げていました。つらくて、くじけそうになったけど、頂上に着いたらうれしくて、それまでのつらさが全部吹き飛んだそうですね。これからの人生でも何度か、そういう事があるかと思います。つらい思いをすれば、喜びもまた何倍にもなって返ってきます。それを忘れず、お菓子を作るパティシエになる夢を実現してください。
志藤康平(こうへい)君。
君は、大谷剣道スポーツ少年団の主将としてみんなをまとめ、数多くの優勝旗をもたらしてくれました。団体と個人の両方で山形県で1位という快挙を成し遂げました。優勝の陰には、人の何倍もの練習とたゆまぬ努力があったことは言うまでもありませんが、家族をはじめ多くの人に支えられての優勝でもありました。感謝の気持ちを忘れず、これからも剣道の技を磨いて、警察官になる夢を叶えてください。応援しています。
白田千紘(ちひろ)さん。
去年の秋、津波で大きな被害を受けた宮城県七ケ浜町の小学生を招いて、交流する会がありました。その会で、あなたは大谷小学校を代表して歓迎のあいさつをしてくれました。心のこもった、温かい、とてもいい挨拶でした。看護師さんになって、みんなを笑顔にしたいというのが目標ですね。持ち前の優しさを大切にして、周りにいる人みんなが元気になる、そんな看護師さんになってください。
堀 博道(ひろみち)君。
町の陸上競技記録会と水泳競技記録会での活躍、見事でした。歩いて一番遠い中沢から6年間、通ってくれてありがとう。ある日、君が1年生の栞汰(かんた)君と語らいながら歩いて帰る姿を目にしました。相手が1年生でも、大人を相手にするのと変わらない態度で接しているのを見て、とてもいいことだなぁ、と感心しました。その気持ちをこれからも大切にしてください。夢は、駅伝の選手になって箱根を走ることですね。厳しい道ですが、ひるまず、挑んでください。
保護者のみなさま。
お子様のご卒業、おめでとうございます。
小さな手をつないで校門をくぐった子どもたちは、今や中学校の制服に身を包み、大人の世界に足を踏み入れようとしています。どの子も豊かな可能性と大きな力を秘めています。この国の未来を担っていくのは、この子どもたちです。これからも、温かく大らかな気持ちでその成長を見守ってあげてください。私たちも、いつまでも応援し続けます。
1年生から5年生のみなさん。頼りになる6年生は今日、旅立ちます。4月からは新しい仲間を迎え入れて、あなたたちが大谷小学校の新しい歴史を刻んでいかなければなりません。お互いに支え合って、また「元気で楽しい学校」をつくっていきましょう。
ご来賓のみなさま。きょうはお忙しい中、卒業式にご臨席たまわり、誠にありがとうございました。大震災後の混乱を乗り越え、この冬の大雪にもたじろがず、この学校で学び続けることができましたのは、ひとえに皆様方の温かいご支援とご協力があったればこそです。心から感謝申し上げます。
今後とも、よりいっそうのご支援を賜りますようお願い申し上げて、卒業式のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 (完)
? ? ?
18日は、大谷小学校の卒業式でした。3月の中旬になってインフルエンザにかかる6年生が続出し、一時は卒業式を延期することも検討せざるを得なくなりましたが、前日になってようやく13人の卒業生が全員出席できる見通しになり、なんとか式を挙行することができました。
私にとっては、校長として3回目の卒業式になりました。人生訓めいた話はしたくない。紙に書いたものを読み上げることもしたくない。小さな学校にふさわしい挨拶をしたいと考えて、今年も一人ひとりにエールを送りました。
だれもが豊かな可能性を持っています。小学校の校長として、子どもたちが育つ様子を日々見ていると、きれい事ではなく、文字通りそう思います。その可能性を伸ばしてあげられるのか、それとも、その芽を摘んでしまい、善からぬ道へと追いやってしまうのか。それぞれの家庭と学校、地域で触れる大人たちが決定的な役割を果たすのだ、ということを痛切に感じます。
*メールマガジン「おおや通信 78」 2012年3月6日
なるほど、官僚たちはこうやって蜜を集めて、吸い続けるのか。民間人校長になってから、つくづく感心させられ、あきれさせられる出来事がありました。視聴覚教育をめぐる醜聞です。
話は、戦後の焼け跡時代にさかのぼります。食べる物にも事欠く時代。学校で子どもたちに映画や16?フィルムの作品を見せてあげたくても、映写機やフィルムを買うお金などあるわけがありません。GHQ(連合国軍総司令部)はこれをあわれみ、手持ちの映画や16?の作品を提供して、教育の振興を促したといいます。
「戦後の復興を担う子どもたちに少しでも良い教育を施したい」と、多くの教育者が熱い思いを抱いていた時代でした。資金が足りないなら、みんなでお金を出し合って購入して共同で利用するしかない。そうやって、各県に「視聴覚教育連盟」というものができました。山形県では昭和28年、私が生まれた年に発足しています。
戦後復興が進むにつれて、県より小さい単位の地域にも「視聴覚連盟」や「視聴覚ライブラリー」といったものが作られていきました。その全国組織が財団法人「日本視聴覚教育協会」と、この財団が事務局をつとめる全国視聴覚教育連盟という団体です。2つとも、少なくともその発足から1980年代あたりまでは、日本の教育にそれなりの役割を果たした組織でした。
問題は、映画や16?の作品が主要な教材ではなくなり、インターネットで視聴覚教材を含むさまざまな教育の素材が手軽に入手できるようになった今でも、この2つの全国組織とこれを支える地方組織が残存していることです。
私が住む朝日町も、山形県西村山地区の視聴覚教育協議会という地方組織に入っており、年に35万円の負担金を出しています。5つの市町の首長と教育長が協議会のメンバーで、平成24年度の事業計画を見ると、16?フィルムのメインテナンスや映写機操作技術講習会などというものがあります。文部省の呼びかけで始まった制度と組織が、その役割を終えたにもかかわらず、惰性でいまだに続いているのです。
その元締めである「日本視聴覚教育協会」の会長は、元文部事務次官の井上孝美氏です。1997年に文部省を退官した後、放送大学学園理事長、放送大学教育振興会理事長と渡り歩き、今も放送大学教育振興会の会長と日本視聴覚教育協会の会長を兼ねて高給を食んでいます(どちらも非常勤の会長職)。
高給を得ても、それにふさわしい仕事をしているのなら、何も文句は言いません。しかし、日本視聴覚教育協会はとっくにその役割を終えたと考えられるのに、教育映画を作る会社や教科書会社を抱え込み、いまだに視聴覚教育の地方組織に号令をかけ続けています。その事業内容を見ると、天下りした元文部官僚に給料を払い続けるための事業と言いたくなる代物が並んでいるのです。
時代遅れの視聴覚教育にエネルギーと公費が注がれる一方で、ITとインターネットを教育にどう活かすかという喫緊の課題への取り組みは遅れています。拙著『未来を生きるための教育』でも詳述しましたが、日本の公教育のIT化は置き去りにされ、2010年からようやく小中学校の教職員にパソコンが本格的に貸与され始めたばかりです。米欧諸国は言うに及ばず、韓国やシンガポールなどの国々からも、はるかに離されてしまいました。
ここで奮い立つなら、まだ救いがありますが、学校のIT化をめぐっては総務省と文部科学省が縄張り争いを繰り広げているのが実情です。電波行政を握る総務省が「フューチャースクール推進事業」なる旗印を掲げて学校へのタブレット端末の普及を図り、文科省は電子黒板や校内LANの整備に躍起になる、という有り様です。そこから見えてくるのは「省益をどう広げるか」という醜い姿であり、次世代を担う子どもをどう育てるのかという真摯さは感じられません。
そういう人たちは「生き残るためのテクニック」にも長けているので、始末が悪いのです。くだんの「日本視聴覚教育協会」も、このままでは生き残れないと考えてか「ICTを活用した教育活動を推進していきたい」と提唱し始めています。笑止千万です。とっくの昔に退官した文部事務次官を非常勤の会長に据える組織が、いまさらどのようなIT教育を推進すると言うのか。まだ良心が残っているのなら、せめて静かに退場すべきでしょう。
官僚たちが蜜を集めて、退官後も吸い続けるこうした天下り団体がいったいどのくらいあるのか。そこに血税がどのくらい注ぎ込まれているのか。根っからの楽観主義者である私ですら、それを考えると、暗い気持ちになってしまいます。
〈注〉タブレット端末:タッチパネル式のミニパソコン。総務省の事業では、研究実証校の生徒に1台ずつ貸与しています。将来、教科書が電子書籍になれば、生徒はこの端末で教科書を呼び出して読むことになり、紙の教科書はなくなります。
*メールマガジン「おおや通信73」2012年1月11日
人間であれ物事であれ、その性格や特質を理解しようとするなら、生い立ちにさかのぼって考えることが大切です。この頃、つくづくそう思います。ならば、原発はどのようにして生まれたのか――正月休みに原爆と原発の生い立ちに関する本を渉猟しました。
これまでにおびただしい数の本が出版されていますが、手にした本の中では、2005年に出版された『科学大国アメリカは原爆投下によって生まれた』(歌田明弘著、平凡社)が、着眼の鋭さといい、内容の濃密さといい、秀逸でした。
出版社「青土社」の編集者を経てフリーになった歌田氏は、米国の原爆開発計画(マンハッタン計画)で政治家と軍部、科学者と産業界をつなぐ役割を果たしたヴァニーヴァー・ブッシュ Vannevar Bush を主人公にして原爆開発の経過をたどっています。V.ブッシュは当時、米科学界の大御所でルーズベルト大統領の科学顧問でした。米議会図書館や米国立公文書館には、彼が書いた書簡や文書が大量に保管されています。歌田氏は、それらを丹念に読み解き、冷静な目で原爆開発の歴史をたどっています。

この本を読むと、第2次大戦が起きる前の世界について、二つのことに気づかされます。一つは、大戦前に圧倒的な力を持っていたのは大英帝国であり、欧州であり、米国は登り竜の勢いにあったとはいえ新興工業国であったということ。もう一つは、そうした国力を反映して、物理や化学の研究でも先端を走っていたのは欧州諸国であり、米国はそれを追う立場にあったということです。
1932年に中性子を発見したのは英国のチャドウィックであり、これを受けて核物理学の分野で目覚ましい成果を上げたのはフランスのジョリオ=キューリー夫妻やハンガリーのレオ・シラード、イタリアのエンリコ・フェルミ、デンマークのニールス・ボーアといった科学者たちでした。それが1938年、ドイツのカイザー・ウィルヘルム研究所でのウランの核分裂実験の成功へとつながりました。
核分裂に伴ってものすごいエネルギーが生まれる。それを利用すれば恐ろしい破壊力を持つ新兵器をつくることができる。それを科学が明らかにしました。時あたかも、ドイツではヒトラーが権力を握り、世界制覇への野望を膨らませ、戦争に踏み切ろうとしていました。ユダヤ人や少数民族への迫害も熾烈になっていました。
「ヒトラーが原爆を手にしたらとんでもないことになる」。欧州の科学者たちは警鐘を鳴らし、ナチスの迫害を逃れて次々に米国に亡命していきました。ドイツと対峙し、疲弊していた英国にはすでに、これらの科学者を受け入れ、原爆開発に取り組む余裕はなくなっていました。
若い力にあふれ、戦火が及ばない米国で、ボーアやフェルミ、シラードら亡命科学者たちは「ドイツよりも先に原爆を開発しなければならない」と、血眼になって研究と開発に突き進んだのでした。歌田氏の本を読むと、米国の巨大な工業生産力に加えて、こうした亡命科学者たちの協力がなければ、原爆は到底、開発し得なかったことがよく分かります。そして、ルーズベルト大統領や軍部、産業界を動かし、オッペンハイマーをはじめとする米国内の科学者と亡命した科学者による原爆の共同開発の指揮を執ったのがV.ブッシュだった、というのがこの本のエッセンスです。
米国に原爆開発を急がせたのは「ナチスに先を越されることへの恐怖」であり、開発を可能にしたのはナチスに追われ米国に亡命した科学者たちでした。その意味で、ナチス・ドイツを率いたヒトラーは、自ら意図したわけではないにしろ、原爆開発の助産師の役割を果たしたことになります(歌田氏は本の中で「助産師」という表現は使っていません。私が勝手にそう呼んでいるだけです。念のため)。
よく知られているように、米国はウラン濃縮型の原爆とプルトニウムを使った原爆の2種類を並行して開発、製造しました。理論的にはどちらも可能であるとされていましたが、どちらのタイプの原爆も、実際に製造するのは技術的にきわめて困難であり、巨額の費用とものすごい人員がかかると見込まれていました。「どちらでもいい。とにかくドイツよりも先に完成させたい」と考えて両方の開発に乗り出し、かろうじて製造に成功した、というのが実態のようです。
このうち、後者のプルトニウム型原爆をつくるために初めて大型の原子炉が造られました。プルトニウムは自然界には存在しません。原子炉内でウランに中性子をぶつけることによって人工的に生成されます。そのプルトニウムを使用済みの核燃料から抽出して原爆の材料にするために、大型の原子炉が造られたのです。その生い立ちからして、原子炉は核開発と不可分の形で結び付いていたのでした。
米国は戦後、原爆の開発を通して獲得した技術とノウハウを活かして、原子力発電の分野で世界をリードしました。歌田氏の本のタイトル『科学大国アメリカは原爆投下によって生まれた』というのは比喩ではなく、事実を散文的に表現したものと言っていいでしょう。
科学技術に関して、米国が戦争中に開発・発展させ、戦後の世界で頂点に立ったものがもう一つあります。コンピューターの製造と活用です。半導体はまだ登場しておらず、当時の電子計算機は真空管を使った巨大な装置でしたが、主にドイツや日本の暗号を解読するために使われました。ドイツでも日本でも、軍部は「われわれの暗号が解読されることは理論的にあり得ない」と考えていました。人間が持つ計算、解析能力を前提にする限りでは、それは正しかったのです。
ところが、英国と米国は電子計算機を開発して、暗号の解読に活用しました。日本やドイツが前提としていたものを乗り越えてしまったのです。この技術もまた、戦後アメリカの繁栄の柱になり、今も大きな収入源となっているのはご存じの通りです。歌田氏は本の最後のところで、このコンピューターの分野でもV.ブッシュが先駆的な役割を果たしていたことを紹介しています。こうしたことを考慮に入れれば、本のタイトルは『科学大国アメリカは戦争によって生まれた』としても良かったのかもしれません。
*米国の原爆開発の歴史を物語風に綴った『マンハッタン計画』(ステファーヌ・グルーエフ著、早川書房)もお薦めです。ただ、この本も歌田氏の本も400ページを超える厚さですので、お急ぎの方にはお薦めできません。
*メールマガジン「おおや通信77」 2012年2月16日
作家、五木寛之氏の近著『下山の思想』がベストセラーになっています。経済的繁栄のピークを過ぎ、少子高齢化がますます進む日本にとって、今は粛々と山を下り、次の高みを目指すための備えをする時だ、と説く五木氏の考えは、多くの人の心を揺さぶっています。「下山」という言葉に前向きの力を付与したところに、この本のすごさを感じます。
もはや「大きくなるパイを奪い合う」時代ではありません。「小さくなるパイをどうやって公平に分配するのか」に知恵を絞る時代です。それを考えると、就学援助をめぐる教育界の論議は時代の流れを無視しており、ピンボケではないかと感じてしまいます。「制度をもっと充実し、援助額を増やすべきだ」と論じるものが多いからです。
就学援助というのは、経済的に苦しくて勉学を続けるのが厳しい小中学生がいる家庭を支援する制度です。生活保護世帯に加えて、生活保護を申請するには至らないものの経済的に苦しい世帯(準要保護世帯)に対して、給食費や学用品代、修学旅行費などを自治体が支給するものです。

大谷小学校の給食風景(本文とは直接の関係はありません)
苦しい時には、みんなで支え合うのは当然です。制度そのものは理にかなっています。経済的に苦しい家庭の生徒は勉学や進学で不利な状況に置かれており、経済的な格差が教育の格差として固定化される傾向があることも明白です。機会均等という観点からも、就学援助制度をさらに充実させる必要がある、というところまでは賛成です。
問題は、援助の総額をさらに増やすべきかどうかです。パイが減る中で、福祉の費用も増やせ、就学援助も増やせと言い出したら、国や地方の財政はパンクします。限られた財源をどう公平に適切に配分すべきか、という観点が欠かせないのに、就学援助を論じる研究や報道にはそれが欠落しているものが多いのです。
文部科学省が公表している就学援助に関する統計(2010年度)を見ると、その運用に大きな疑問が湧いてくるのです。小中学生100人当たり、どのくらいの比率で援助がなされているのか。都道府県別の比率は、次の通りです。
大阪府 28パーセント
山口県 26パーセント
東京都 24パーセント
・・・・・・・・・・
山形県 7パーセント(6.9)
群馬県 6パーセント(6.4)
栃木県 6パーセント(6.3)
静岡県 6パーセント(5.6)
小学校の校長として制度の運用にかかわっている立場から見ると、静岡や栃木、群馬、山形のデータは納得のいく比率です。経済的に苦しくて給食費などを払うのに苦労している家庭は全体の1割弱というのが実態でしょう。なのに、大阪や東京では生徒4人に1人の割合で就学援助を受けている。大阪や東京の方が山形や静岡よりずっと貧しい家庭が多い、などということは考えられません。
では、何が起きているのか。ここからは私の推測ですが、大阪や東京では、かなりの数の保護者が「もらえるものなら、もらおう」と申請し、自治体の窓口は「断ったら面倒なので認めてしまえ」と援助を認定する、ということが起きているのではないか。もしくは援助を決める基準そのものが大甘なのではないか。そう解釈しなければ、この文科省の統計は理解できません。
大谷小学校がある地域は、決して裕福な家庭が多い地域ではありません。それでも、厳しい家計の中から教育費を捻出して、全家庭からきちんきちんと支払っていただいています。就学援助の対象家庭はゼロです。その一方で、大阪や東京では4人に1人が税金で給食費などを負担してもらっている――不平等、さらに言えば不正がまかり通っている、と考えざるを得ません。
下山の過程にあるこの国で今、大切なことは「痛みを分かち合いながら、本当に助けが必要な人をみんなで支えること」ではないでしょうか。それは、前回のおおや通信「共同除雪」で紹介した「独り暮らしのお年寄りの中でも、本当に手助けが必要な人のために雪下ろしをする」という考え方にもつながることです。きれい事の「就学援助論」ではなく、下山の時代にふさわしい、まっとうな「就学援助論」を聞きたい。
*就学援助制度については参議院企画調整室の鳫(がん)咲子氏がバランスの
取れた論文を書いており、参考になります。次のURLです。
http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/2009/20096528.pdf
*メールマガジン「おおや通信76」 2012年2月9日
月曜日(2月6日)のテレビ朝日「報道ステーション」に山形県朝日町の峯檀(みねだん)という集落が登場しました。この大雪で、北国はどこでも雪下ろしと雪かきに追われて大変です。そんな中で住民たちが共同で除雪作業をして頑張っている集落がある、というリポートで「頑張っている集落」の一つとして紹介されました。
都会と違って結束力の強い農村ならどこでも共同で除雪作業をしている、と思う人もいるかもしれませんが、決してそんな事はありません。それぞれ、自宅の屋根の雪下ろしと家の周りの雪かきで精一杯で、よその家の心配をしている余裕などないのが実情です。私も、自分が住んでいる団地の駐車場の除雪と、実家の雪かきでヘトヘトになっています。山沿いにある実家の周りの積雪は2メートル近くあります。軒先は、下ろした雪がうずたかく積もり、屋根に届きそうなほどです(写真参照)。

雪下ろしは危険を伴います。屋根から転落したり、側溝に落ちたりして死傷する事故が今年も相次いでいます。親類や友人といえども、気軽に頼めるものではありません。自分の家のことはそれぞれ自分でやる、というのが大原則なのです。
ならば、テレ朝に登場した峯檀という集落はどこが違うのか。ここは、結束力が飛び抜けて強いのです。村のお祭りにしても学校のPTA活動にしても、率先して仕事を引き受けてくださる方が何人もいて、地域の大黒柱のような地区なのです。共同で地区内の除雪をし、独り暮らしのお年寄りの家の雪下ろしもしています。
峯檀の区長さんにお聞きすると、「共同で除雪を初めて5年になりますが、やはり大変です」と苦労を語ってくれました。独り暮らしなら無条件で雪下ろしをしてあげるわけではありません。裕福で建設会社に雪下ろしを頼む余裕のある家は除きます。近くに身内がいる場合も手伝いません。本当に困っている独り暮らしの家だけ、みんなで雪下ろしをしてあげるのです。
除雪の共同作業は、その線引きをきちんとし、集落内の実態をしっかり把握していなければとてもできません。共同作業中にけがをした場合の対応も、事前に決めておく必要があります。自治体からいくらか補助金が出ているとはいえ、「かわいそうだから」などという感傷的な気持ちで始められることではないのです。
そういう難しい共同除雪をしている地区がいくつもあるのが大谷小学校のある地域です。不登校なし、給食費の不払いなし、モンスターペアレントなしの「3ない小学校」は、こういう土壌があるからこそ成り立っている、と感謝しています。山形で民間人校長になってから、都市部のある校長から「わざわざ民間から採用したのに、なんで大谷みたいな苦労の少ない学校の校長にしたんだ、とやっかんでいる人もいるよ」と教えてもらいました。確かに、都会に比べれば、苦労の少ない学校かもしれません。
その代わり、と言ってはなんですが、私は「どんな場面でも、民間で飯を食ってきた人間らしい判断をする」と決め、実行しています。去年3月の東日本大震災の後、山形県内では、ほとんどの市町村の校長会が「犠牲者に弔意を示すため、当分の間、酒席は控える」と、一斉に宴会の自粛を決めました。
私はこれに異を唱えました。「どのような形で弔意を示すかは、それぞれの学校によって異なっていい」「大津波で身内を亡くした保護者や教職員がいるなら、当然、酒を飲む気にはなれないだろう」「被害がほとんどなかった山形の学校が為すべきことは、一日でも早く日常生活を取り戻し、被災地の復興を支えることだ」と考えたからです。実際、その通りに行動しました。
この冬も、大雪の日に臨時休校にしたり、授業を早めに切り上げて生徒を一斉に下校させたりした学校がたくさんありますが、大谷小学校は猛吹雪でも普通通りに授業をし、下校時に教職員が付き添うという対応をしました。一日一日の教育を淡々と進める。それが何よりも大切だと考えるからです。
戦乱が長く続き、子どもを学校に通わせることすらできなかったアフガニスタンで、教育を施すことができないことを嘆く親の声を何度も何度も聞かされました。「普通の一日」の大切さをしみじみと感じました。だからこそ、雪国の小学校が吹雪くらいで学校を休んだり、授業を削ったりしてはいけない、と思うのです。
「普通の一日の大切さ」という観点から眺めると、東京都が進める教育改革や、大阪府の教育条例づくりにも違和感を覚えます。学校選択制を導入したり、国旗の掲揚と国歌の斉唱を迫ったり、はたまた教職員の勤務評定を厳格にしたりと、それぞれ騒いでいますが、私の目にはどちらも「制度いじりに躍起になっている」と映るのです。
率直に言って、東京でも大阪でも、多くの保護者が公立の小中学校に見切りをつけ、私立に逃げ始めています。公教育の土台そのものが大きく揺らいでいる。その揺らぎは、公教育の制度をどうにかすれば収まるような段階を過ぎているのではないか。揺らぎは企業社会の在り方ともつながっており、もっと大きな視点で取り組まなければ、対処できなくなっているのではないでしょうか。
学校がごく普通の、淡々とした一日を取り戻すために、社会のそれぞれの組織やメンバーに何ができるのか。前向きに、互いに支え合うつもりで語り合い、動く時ではないか。東京や大阪で続くヒステリックな騒動から有益な何かが生まれるとは、とても思えないのです。
*メールマガジン「おおや通信75」2012年1月31日
事実を正確に伝える。それがメディアに求められる何よりも大切なことです。誰もが自分の職務と良心に忠実であろうとしています。けれども、そうしてもなお、真実に迫るのは難しく、「事実とは何か」と思い悩むことから逃れることはできません。
そんな事をあらためて思ったのは最近、NHKディレクターの七沢潔氏が著した『原発事故を問う』(岩波新書)を読んだからです。この本は、1986年4月26日に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発事故の原因とその後の影響について、長期間の取材を踏まえて書かれ、事故から10年後の1996年に出版されました。
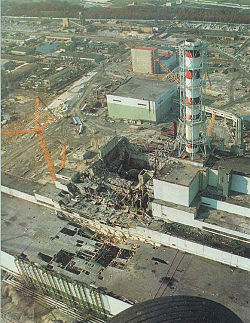
Source: Wikipedia " Chernobyl Disaster "
チェルノブイリ事故については、私にも強烈な記憶があります。事故発生のニュースが世界を駆け巡った日の夜、私は朝日新聞東京本社の整理部に在籍していて、整理部員として紙面編集のサブをしていました。事故の第一報は「スウェーデンで異常に高い放射線値が測定された。風向きを考慮すると、ソ連の原発で事故があった可能性がある」と、ごく短い文章で伝わりました。ソ連当局はずっと沈黙したままでした。一報を補う情報は、わずかしか流れてきませんでした。
これをどのくらいの大きさのニュースとして扱うのか。胃がキリキリと痛むような時間が過ぎていきました。そして、扱いを最終的に決めたのは編集局長でも編集局次長でもなく、整理部の部長代理でした。決断することを誰もがためらう中で、彼は「これは世界を揺るがす大ニュースになる」と判断し、1面のトップニュースにしたのです。翌朝、日本の全国紙の中で「1面トップ」の扱いをしたのは朝日新聞だけでした。時として、物事を決めるのは肩書でも権限でもなく、志の高い人間であることを知りました。
その次の強烈な記憶は、事故から4カ月後でした。ソ連指導部は1986年の8月、ウィーンにある国際原子力機関(IAEA)に詳細な事故報告書を提出しましたが、これを当時の朝日新聞ウィーン支局長が入手し、世界的な特ダネとして報じたのです(8月16日付の朝刊)。日本のメディアが世界を揺さぶるようなスクープを放つことはめったになく、堂々の特ダネでした。
後に外報部に配属になった時、この報告書を入手した元ウィーン支局長から取材の裏話や、ファクスで報告書を受け取った東京サイドの苦労(ロシア語の長文の報告書を読みこなし、記事にまとめるのは容易ではなかった)を聞きました。世界的なスクープを手にした時の高揚感と緊張感に触れ、「いつか自分も」と力んだことを思い出します(もちろん、そんな機会はなかったのですが)。
ソ連当局のその報告書は、チェルノブイリ原発の運転員たちが信じられないような規則違反を何重にも犯し、それが破局につながったと結論づけていました。事故による放射能汚染はそれまで公表されていたよりも、はるかに広範囲に及ぶことも明らかにしていました。
この時の紙面の印象が強烈だったからでしょう。私は当時からずっと、チェルノブイリ原発事故の主たる原因は「規則をきちんと守らなかった原発運転員たちの職務怠慢である」と思っていました。チェルノブイリ原発の原子炉が減速材として黒鉛を使う独特の原子炉であり、日米で使われている水を減速材とする軽水炉とは違って制御が難しいことは知っていましたが、「事故の主因は人的なもの」と思い込んでいました。
ところが、七沢氏はこの本の中で、事故から5年後にソ連当局が「事故の主因は人的なものではなく、黒鉛減速チャンネル型炉の構造的な欠陥である」との報告書をまとめていたことを紹介しています。ソ連国家原子力安全監視委員会の副委員長だったニコライ・シュテインベルクがまとめた、いわゆるシュテインベルク報告書(1991年)です。
黒鉛炉で核分裂を抑制するために挿入される制御棒には、挿入時に気泡を発生させる弱点があり、ある条件が重なると、制御棒を一斉に入れた際に核分裂反応が逆に急速に進む危険性があること。従って、制御棒の扱いや原子炉の運転には特段の配慮が必要であり、規則を厳格に守らなければならない、というのです。
ソ連の原発運転員たちはそうした「黒鉛炉にひそむ弱点や欠陥」について全く知らされておらず、「電源喪失時にタービンの慣性回転によって少しでも発電し、非常電源として使えないか」という難しい実験を迫られ、規則から外れて実験を続けざるを得ない立場に追い込まれていった。それが事故を引き起こしたのであり、人的なミスを事故の主たる原因とするのは間違いである、とこの報告書は指摘しているというのです。
事故原因の究明がなぜ捻じ曲げられてしまったのか。七沢氏は、その背景にも踏み込んでいます。事故直後から黒鉛炉の欠陥を指摘する意見はあったが、黒鉛炉の設計者はソ連の原爆および原発開発の功労者であり、科学界の重鎮であった。当時のゴルバチョフ書記長ですら、責任を追及できる状況にはなかった――激しい権力闘争の末に、運転員に責任をかぶせることで妥協が図られた、というのです。
事故後のこうした経緯は、チェルノブイリの事故を息長くフォーローしてきた人々にとってはよく知られていることなのかもしれません。しかし、わき目でチラチラと見てきただけの私には、ひどく衝撃的な内容でした。
ソ連の事故報告書に関する朝日新聞のスクープはもちろん立派なスクープですが、報告書そのものがソ連指導部の妥協の産物であり、真の原因が黒鉛炉の構造的な欠陥にあることを覆い隠すことを目的として作成されたのであれば、その報告書を大々的に報じることは、結果として「真実を隠すお手伝い」をしてしまったことになります。
事実を正確に押さえ、的確に報道したとしても、時としてそれが真実に迫るどころか、真実から人々の目を遠ざける結果をもたらすこともある。メディアで働くことの難しさと、真実に迫ることの困難さを今さらながら突き付けられた思いです。
この『原発事故を問う』という本がもう一つ優れていると思うのは、チェルノブイリ事故の後も原発建設に邁進し、プルトニウムを取り出して使う「核燃料サイクル」に固執した日本の特異な姿と、その背景にも鋭く切り込んでいることです。随所に、今の福島原発事故の惨状を予告するような記述もあります。出版から16年たっても、少しも色あせない作品です。
*メールマガジン「おおや通信74」 2012年1月19日
山形では、お正月に餅をたくさん食べます。種類も豊富です。クルミやゴマをすりつぶし、砂糖や醤油を加えて餅をくるみ、クルミ餅やゴマ餅として食べます。ずんだ餅というのは枝豆をすりつぶし、砂糖と塩少々を加えてまぶしたものです。

この正月にどんな餅を食べたのか。どの餅が一番好きか。大谷小学校の生徒80人にアンケートをしてみました。用紙には9種類の餅と「その他」の10項目を設け、一番好きなものには1、次に好きなものには2、3と番号を書いてもらう方式です。1位は3点、2位と3位はそれぞれ2点、1点として集計しました。結果は次の通りです。
1年 2年 3年 4年 5年 6年 全校
1位 納豆 納豆 納豆 磯辺巻き 納豆 磯辺巻き 納豆
2位 ずんだ 磯辺巻き きなこ きなこ あんこ 納豆 磯辺巻き
3位 きなこ きなこ 磯辺巻き 納豆 ずんだ あんこ きなこ
4位 ゴマ あんこ あんこ ずんだ きなこ ずんだ ずんだ
5位 クルミ 雑煮 雑煮 雑煮 磯辺巻き 雑煮 あんこ
6位 磯辺巻き ずんだ ずんだ クルミ クルミ きなこ 雑煮
前回の調査(2年前)でもそうでしたが、今回も全体では納豆餅が断トツの1位でした。山形県全体で調査しても、たぶん同じような結果になるでしょう。納豆をあまり食べない関西や中国、四国出身の人にとっては驚きの結果かもしれません。
全校集計の7?9位はゴマ餅、クルミ餅、おろし餅(大根おろしをまぶした餅)の順でした。「その他」では、なんと「何も付けない白い餅」を挙げた生徒が4人もいました。つきたての餅をそのまま食べるのがおいしい、というわけです。「砂糖醤油(さとうじょうゆ)を付けて食べるのが好き」という生徒もいました。
私にとっては、磯辺巻きが全体で2位に入ったのが驚きでした。実は、2年前の調査では「調査項目」に入れていませんでした。私が子どもの頃(50年前)には、見たこともない食べ方だったからです。初めて見たのは、東京で暮らし始めてからでした。なぜ見たこともなかったのか。年配の人の話を聞いたら、疑問はすぐに解けました。
昔の農村では、それぞれの家で臼と杵を使って自分たちで餅をつきました。一升ほどついて、それを手で小さくちぎって、納豆やきなこ、あんこを入れた器に落としてまぶし、それから食べていました。ですから、少なくとも正月に食べる餅には磯辺巻きのようなものが登場するはずがなかったのです。「昔の農村は貧しく、海苔のような値の張るものはめったに買えなかった」という見方もありました。
磯辺巻きは、切り餅を買ってきて焼いたりあぶったりして食べる、都会の食べ方だったのでしょう。それがジワジワと東北の農村に広がり、ついには伝統の納豆餅を脅かすほど人気を集めるに至った、と考えられます。実際、生徒たちに聞いてみると、自宅で臼と杵で餅をついている家庭は今や1割ほど、自動餅つき器でつくのが8割、残りの1割は最初から市販の切り餅、という結果でした。この半世紀で、餅のつき方も食べ方も大きく変わり、人気度も変わってきたことが分かります。
というわけで、今年最初の校長の話では「納豆餅と磯辺巻き」を取り上げました。餅の人気ランキングは地区の人たちに配布する学校便りでも紹介しましたが、生徒たちにあらためてこの人気ランキングを示し、納豆が世界のどの地域で食べられているかを話しました。
調べてみると、納豆は朝鮮半島の一部や中国の雲南省、タイやビルマの山岳地帯、インド北東部のインパールやコヒマ、シッキム地方、インドネシアのジャワ島など、アジアの各地で食材として使われていました。私自身、かつての激戦地インパールを訪ねて取材した時や、インドネシアの首都ジャカルタや農村でご馳走になったことがあります。インドネシアの納豆は「テンペ」といい、日本の納豆とはかなり趣の異なる食べ物でしたが。
納豆という身近な食材からも、世界にはいろいろな国や地域があることを学ぶことができます。磯辺巻きが躍進した背景には、餅つきの衰退と農村の食生活の変化という時の移ろいが映し出されています。この子たちが大人になり、親になった時、餅の人気ランキングはどうなっているでしょうか。
*メールマガジン「おおや通信72」 2011年12月9日
ある校長先生からいただいた手紙の中に「自動販売機の故障と釣り銭」の話がありました。自動販売機が故障して、釣り銭がたくさん出てしまうようになった。その自販機をよく使う子どもが故障に気づいたが、知らんぷりして使い続け、何度もたくさんの釣り銭を手にした、という話です。
これをどう考えるか。教師や保護者、地域の人たちの集まりで議論になり、「ごまかしは良くない。自販機の管理をしている人に教えてあげるべきだ」という意見と、「悪いのは自販機をきちんと管理していなかった業者だ。子どもに罪はない。むしろ、状況を理解して現実的な対応をしたその子は『生きる力』がある。偉い」という意見に分かれ、両方の意見が拮抗したのだそうです。
私は心底、驚きました。物事にはいろいろな見方や考え方があって当然です。「自販機の故障に気づいて釣り銭でもうけるなんて、はしっこい子だなぁ」という受けとめ方もあるでしょう。けれども、大人たちから「生きる力がある。偉い」という意見が出て、しかもそれが少数意見ではなく、正義派と相半ばするくらいいるとは、思いもよりませんでした。
世の中がきれい事だけで済まないことは確かです。誰しもつい、うそをつき、ごまかしをしてしまうことはあるでしょう。けれども、大人たちが「それもありだ。それこそ生きる力だ」と言ってしまっていいはずがありません。愚直に「あるべき姿」を説く。理想を語る――それが大人の役割ではないでしょうか。
正直で公平であることが尊ばれる。そういう社会こそ真に豊かな社会である、と私は信じています。
(大谷小学校PTA便り「おおや」第86号 コラム「豊かさとは何か(8)」を一部手直ししたものです)
*メールマガジン「おおや通信71」 2011年12月1日
高級ブランドとはまるで縁がない私のような人間でも、さすがにルイ・ヴィトンという名前は知っています。通勤電車の中で、LとVを組み合わせたロゴのあるバッグを肩にした女性をしばしば見かけました。「猫も杓子も同じバッグを肩にかけて、むなしくないのかね」と、ひねた目で見ていたものですが、このルイ・ヴィトンが東日本大震災で打撃を受けた宮城県の牡蠣(かき)養殖の支援に乗り出したと聞いて、驚きました。
3月下旬の「おおや通信58」で、気仙沼市の牡蠣養殖業、畠山重篤(しげあつ)さんのことを紹介しました。「おいしい牡蠣を育てるためには海が豊かでなければならない。海が豊かであるためには川が澄んでいなければならない。そのためには山が豊かでなければならない」と考え、水源地で植林を始めた人です。「森は海の恋人」と名付けた運動は国語や道徳の教科書でも紹介され、広く知れ渡りました。
その畠山さんも3月の大津波で養殖施設をすべて壊され、苦しんでいましたが、それを伝え聞いたルイ・ヴィトングループが総額6000万円の支援を申し出、最終的には2?3億円の拠出をすると約束してくれたのだそうです。
高級バッグを売る会社がなぜ、牡蠣養殖の応援をするのか。話は40数年前にさかのぼります。牡蠣はフランス料理に欠かせない食材です。フランスでも長く養殖が行われてきましたが、1970年ごろ牡蠣に伝染病が広がり、養殖事業が危機に陥りました。この時、窮状を救ったのが宮城県の漁民でした。牡蠣のタネ貝を大量に送り、フランスで牡蠣養殖が途絶えるのを防いだのです。
フランスの漁業関係者はそのことを忘れていませんでした。フランス料理のシェフたちも覚えていました。「宮城の人たちに恩返しを」との声が湧き上がり、ルイ・ヴィトンもその輪に加わったのです。創業のころ、ルイ・ヴィトンは木枠を使った旅行鞄を作り、ビジネスの基盤を固めました。そのこともあって、木や植林に関心を持っており、「森は海の恋人」運動に心を動かされたのかもしれません。
ルイ・ヴィトンの経営陣はこの夏、大震災に見舞われ、苦しんでいる畠山さんをパリに招いて被害状況や復興計画に耳を傾け、その場で支援を決めました。「助けたら、返してくれる。手を差し伸べてくれる。それは世界共通なんだなぁ、と知りました」と畠山さんは語っていました。「養殖を再開したくても資金の目途が立たず、途方に暮れていた時期だったので、助かりました。日本の政府や県からは何の支援もない時期でしたから」とも述べていました。
支援の見返りにルイ・ヴィトングループが求めたことは、たった一つだそうです。畠山さんが暮らし、仕事をしている宮城県気仙沼市の唐桑(からくわ)半島の景色のいい所にフランス料理のレストランをつくり、おいしい牡蠣料理を出すこと。そのために、元気な牡蠣をまた育てる。それだけです。
「粋(いき)だなぁ」。普段、使うこともない「粋」という言葉が思わず口をついて出てきました。
*「森は海の恋人」運動やその後の展開については、畠山さんの近著「鉄は魔法つかい 命と地球をはぐくむ『鉄』物語」(小学館)を読むことをお薦めします。
*メールマガジン「おおや通信70」 2011年11月9日
どんなにひどい事にも、少しはいい事がある。今回の東日本大震災に即して言うならば、常日頃、偉そうな顔をしている政治家や中央省庁の官僚たちがいざという時にいかに役に立たないか、広くみんなに知れ渡ったのは、数少ない「いい事」の一つでした。
今年7月の「おおや通信65」で、文部科学省が「地震があっても原子力発電所は安全です」というお粗末な副読本を作って全国の小中学校に配り、大震災の後にひっそりと自分の役所のホームページからその内容を削除していたことを紹介しました(平成の「墨塗り副読本」事件)。
その文部科学省が、今度は「放射線について考えてみよう」という小学生向けの副読本を作りました。「あれだけ恥ずかしい内容の副読本を全国にバラまいて世間のもの笑いになったのだから、今度こそ気を引き締めて、しっかりした副読本を作ったのだろう」と思って、学校に届いたサンプルに目を通しました。
一読して、フツフツと怒りが湧いてきました。農村に戻って小学校の校長になり、比較的穏やかな日々を送っているので、自分ではだいぶ温厚になったつもりでいたのですが、やはり本性はそんなに急には変わらないようです。怒りが爆発しそうになりました。
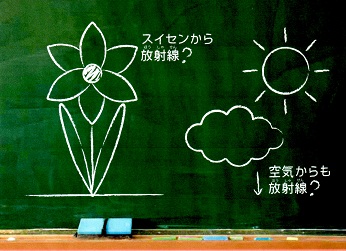
副読本の表紙からして、ふざけている。黒板にスイセンの花と雲を描き、「スイセンから放射線?」「空気からも放射線?」と書いてある。含意は明らかです。放射線は自然界にもごく普通にあるものです。怖がることはないのです――と印象づけたいのでしょう。しかし、この副読本は福島をはじめとする放射能汚染地域の小学校にも配られるのです。汚染地域に住む子どもや親たちが今、知りたいのは、そんなことではないでしょう。このような副読本を作って配ろうとする、その心根が私にはまったく理解できません。
もちろん、科学的には文句を付けられない内容になっています。放射線は、ドイツの科学者レントゲンが偶然、発見したものであること。身の回りにもごく普通にあること。エックス線撮影をはじめ医療などさまざまな分野で利用されていること。淡々と列挙し、「放射線の量と健康」のところは「一度に100ミリシーベルト以下の放射線を人体が受けた場合、放射線だけを原因としてがんなどの病気になったという明確な証拠はありません。しかし、がんなどの病気は、色々な原因が重なって起こることもあるため、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることが大切です」と結んでいます。
最後のページにある「事故が起こった時の心構え」には、嗤(わら)うしかありませんでした。「うわさなどに惑わされず、落ち着いて行動することが大切です」と、堂々と記述しているのです。
福島の原発事故が深刻さを増すにつれて政権の首脳部がパニックに陥って怒鳴り散らしたこと、事故対応の拠点になるはずだった現地のオフサイトセンターが停電と道路渋滞で機能しなかったこと、128億円もかけて開発した放射性物質の拡散予測システム(SPEEDI)のデータを国の原子力安全委員会が出し渋り、役に立たなかったこと・・・。こうした政治家と官僚の醜態は今や周知の事実です。政府がきちんとした対応をしなかったからこそ、みんながうわさに右往左往し、落ち着きを失ってしまったのではなかったか。反省の言葉もなく、よくぞ「落ち着いて」などと書けたものです。
この副読本を最後まで読んで気づいたことがあります。それは、「はじめに」という文章で福島の原発事故に触れているものの、本文では最初から最後まで「原子力発電所」という言葉も「原発」という言葉も一度も出て来ないということです。「放射線を使っている施設で事故が起こった時には」などと、最後まで一般論で表現しているのです。
この副読本を作った人たちは良心の呵責を感じないのでしょうか。過去の苦い経験から謙虚に学ぶということができないのでしょうか。あの恥ずべき原子力の副読本(「わくわく原子力ランド」と「チャレンジ!原子力ワールド」)の作成にかかわった人物のうちの何人かが、また編集委員に名を連ねているのを見つけた時には、卒倒しそうになりました。
副読本の発行は文部科学省の名前でなされています。担当部局は研究開発局の開発企画課というところです。担当者に電話して「福島の原発事故と除染などの対応について盛り込むことをなぜしなかったのですか?」と詰問しました。返ってきた返事は「当然、そういう議論もありましたが、今回はまず基礎知識を掲載して次の改訂で考えましょう、となりました」というものでした。
難しいこと、意見が分かれることは避けて、先送りする。未曾有の大震災と原発事故でこれだけ痛い目に遭い、批判にさらされているのに、官僚とそれを取り巻く人たちの保身術には、なんの影響も及ぼしていないのでした。こういう人たちが「国家百年の計」などと口にしているのかと思うと、「やはり現場がしっかりするしかない」とあらためて強く思うのです。
*注 小学生のための副読本「放射線について考えてみよう」は、文部科学省のホームページにアップされています。URLは次の通りです。
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1311072/syougakkou_jidou.pdf
*メールマガジン「おおや通信69」 2011年10月21日
今年3月までの1年間、朝日新聞アスパラクラブのウェブサイトで世田谷の高橋章子さんとコラムを連載し、この「おおや通信」でも配信させていただきましたが、コラムの内容に加筆して本として出版しました。高橋さんとの共著です。前書きのみ配信させていただきます。
京都の「かもがわ出版」が発売元で、10月22日から全国の書店やネット販売でお求めになることができます。22日の朝日新聞1面に広告も掲載される予定です。
本の収益はすべて、山形の地域おこしのために立ち上げたNPO「ブナの森」の運営資金にする予定です。「ブナの森」オフィスでも、著者割引で販売しています。メールかファクスでご注文いただければ、郵送料を当方で負担し、料金後払い(郵便振替による振り込み)で送らせていただきます。お知り合いの方、とくに教育に関心をお持ちの方にご紹介いただければ、幸いです。
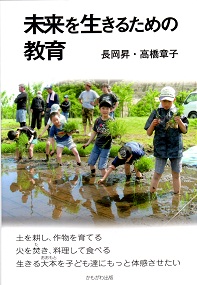
◇ ◇
新聞はいつも、哀しみと怒りに満ちている。
大震災に打ちのめされ、放射能におびえた今年は、いつにも増して深い哀しみと怒りの言葉が紙面にあふれた。命のはかなさと重さをしみじみと感じさせられた年でもあった。
新聞記者になって10年余りたった頃、私はアフガニスタン戦争を取材するため、この国を初めて訪れた。1989年の春だった。首都のカブールには連日、ロケット弾が降り注ぎ、多くの血が流れていた。
ある日、郊外にある難民キャンプを訪ねた。ハエが飛び交い、汚物の臭いが漂う中で、数万人のアフガン人が暮らしていた。ここで、真っ白なひげをたくわえ、眉間に深いしわを刻んだ老人に会った。戦闘に巻き込まれて、孫を亡くしたばかりという。
「私のような年寄りが生き残り、命を授かって間もない孫が死んでいく。耐えがたい」
そう言って、命は一つひとつが「幸運の結晶」であること、どの命もかけがえのない存在であることを訥々(とつとつ)と語るのだった。扉の詩は、この老人の言葉をほぼそのまま採録したものである。
それまでに聞いたどんな言葉よりも、その後に聞いたどんな表現よりも、胸に重く沈んで消えなかった。
ゆえあって、30年勤めた新聞社を早期退職し、2009年の4月から故郷の山形県で公募の民間人校長として働き始めた。どんな事情があったのかは本書を読んでいただくとして、にわか校長として働くことを決めた時、私は「子どもたちに贈る言葉を一つだけ選べ」と言われたら何を選ぶのだろうか、と自問した。
数日考えて、思い浮かんだのは、切なくも懐かしいアフガンの地で出会ったこの老人の言葉だった。
学校運営の指針として「いのちは『幸運の結晶』」という言葉を掲げたものの、あまりにも重い言葉であり、子どもたちの前でその意味や背景を詳しく語ったことはまだない。先生たちに押しつけるつもりもない。心の片隅にかすかにとどまり、いつか思い起こすことがあれば、それで十分ではないか、と思っている。
この本は、報道の現場から教育の一線に身を転じて感じたこと、考えたことを綴ったものである。第一部の「校長と母の放課後メール」は、2010年3月から1年間、朝日新聞アスパラクラブのウェブサイトに連載された同名のコラムをほぼそのまま収録し、一部加筆した。コラムは、世田谷在住で3児の母である高橋章子さん(投稿雑誌「ビックリハウス」の元編集長)と1週間おきに執筆したもので、往復書簡のような形式になっている。
第二部の「メールマガジン『おおや通信』」には、上記のウェブコラムの連載が始まる前に私が知り合いに配信したもの(第一話?第八話)と、コラムの連載終了後(東日本大震災の後)に配信したもの(第九話以降)の両方を載せている。
給食費の不払い、フィンランドの教育、学校のIT環境、小学校での英語教育、食農教育など、この本が扱うテーマは多岐にわたるが、もともとエッセイ的な内容であり、どこから読み始めても大丈夫な構成になっている。グラビアの写真やイラストを眺めながら、関心のあるところからお読みいただきたい。
2011年10月 長岡 昇
*メールマガジン「おおや通信68」 2011年9月26日
秋分の日の連休を利用して、久しぶりに東日本大震災の被災地に復興のお手伝いに行ってきました。行き先は宮城県の七ケ浜町。私が住む山形県の朝日町とは、「海の子山の子交流」という事業で小学生同士が行き来している間柄で、朝日町からは大勢の人がボランティアに駆けつけています。私も2回目の訪問でした。
一人でマイカーに乗って出かけたのですが、東北自動車道の仙台近郊の出口には全国からボランティアに駆けつけたバスや乗用車が長い列を作っていました。車の数が多いこともあるのですが、被災やボランティアの証明書があると高速料金が免除になるため、ほとんどの車がETCの出口ではなく普通の出口に詰めかけ、そのために渋滞しているのでした。
七ケ浜町では、海苔(のり)の養殖事業をしている星博さん宅で、「タネ貝の糸通し」という仕事をしてきました。海苔養殖では、まず牡蠣(かき)の貝殻に海苔のタネ(胞子)を植え付け、それがある程度育ってタネ貝になった段階で、2枚のタネ貝を細い麻糸でつないで、それを養殖用の魚網に播いて海苔を育てるのだそうです。

自宅裏の作業場で私たちに「タネ貝の糸通し」を教える星博さん(中央)と奥さん(左端)
一連の作業はほとんど機械化され、一人でも出来るようになっていたのですが、大津波で星さんが所有する機械や設備はすべて流されてしまいました。このため、昔やっていたように手作業でやらなければならなくなり、人手が必要になったのでボランティアの出番、となったわけです。仙台市在住の沢田さんと品田さん、茨城県から駆けつけた西尾さん、私の4人で、星さん夫妻の指導を受けながら、2000個のタネ貝の糸通しをしました。
海水に浸したタネ貝を拾って糸を通す作業を繰り返したのですが、仕事をしながらお聞きした星さんの話がとても面白かった。星さんのうちは半農半漁で、海苔の養殖と稲作で生計を立てています。職人気質の強い人で、海苔の養殖でも稲作でも工夫を重ね、独自の道を貫いている人でした。
海苔が牡蠣の貝殻である程度まで育ったら、いったんゴシゴシとブラシをかける。「ストレスを与えて、なにくそ!という気にさせるのです」と星さん。稲作の苗も、芽を出した後、何度もわざとローラーをかける。そうすると、苗は根っこをしっかり張ってはい上がろうとする。そして、丈夫に育つと言います。適度にしごきながら育てる。何やら、人の育て方を教わっているようでした。
抗生物質や農薬を使わず、EM菌という自然の素材を使って育てることにこだわり、販路も自分で開拓したのだそうです。「七ケ浜の星さんの海苔はいい」という評判があちこちの寿司職人に口コミで広がり、今ではルーマニアにある寿司店にまで海苔を販売しているとか。時代の流れを読む力のある人なんだなぁ、と感じ入りました。
一緒にボランティアとして働いた沢田さんからも、いい話をお聞きしました。「はるかのひまわり」が七ケ浜町でも収穫の時期を迎えたのだそうです。
報道でご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、このひまわりは1995年の阪神大震災で亡くなった神戸市の加藤はるかさん(当時11歳)の自宅の庭に咲いていたものです。そのひまわりから得た種が2004年の新潟中越地震の被災地に贈られ、栽培が広がりました。
そして今回。神戸から直接、あるいは新潟県の中越を経由して、さまざまなルートで南三陸町や気仙沼市、石巻市、七ケ浜町などに「はるかのひまわり」の種が届けられ、花を咲かせたのです。ひまわりには「放射能を除染する効果はなかった」と報じられました。けれども、苦難を経験した人と人をつないで、みんなを元気にしています。
6月14日の河北新報によれば、生徒の7割が津波に呑み込まれた石巻市の大川小学校にも届けられました。その後、大川小が間借りしている飯野川第一小学校の校庭でたくさん花をつけたそうです。ひまわりの種を届けることで元気の素を届ける。それが花開いて、また次に元気がつながる。参加している人たちは「はるかのひまわり」プロジェクトと呼んでいます。素敵なプロジェクトです。
これがローカルニュースにとどまっているのが、私には信じられません。もっと深く取材して、全国の読者や視聴者に届けたい。そう思う記者がなぜいないのか不思議です。

宮城県七ヶ浜町の松ヶ浜漁港。津波でがれきだらけになったが、片づけがほぼ終わり、漁業が再開されつつある
*星博さんの海苔や米について知りたい方は次のサイトへ
http://www.hoshinori.jp/rice.html
*「はるかのひまわり」プロジェクトについては次のサイトをご覧ください
http://www.season.co.jp/haruka_sunflowerFB.htm
*メールマガジン「おおや通信67」 2011年9月6日
いつもの年なら、秋は農民にとって待ちかねた、胸躍る季節です。春先から流した汗の結晶を手にする季節だからです。けれども、この秋は農民、とりわけ東北の農民にとって、今までに経験したことがないほど憂鬱な季節になってしまいました。福島の原発事故の影響で、果物や野菜の出荷価格が暴落しているからです。
暴落は8月下旬の桃から始まりました。桃の大産地である福島県には例年、桃を買い求める観光客が直売所に押し寄せるのですが、当然のことながら今年はその流れがピタッと止まってしまいました。桃の生産農家はやむなく、青果市場に出荷しましたが、これまた当然のように買いたた かれ、出荷価格は例年の半分以下、日によっては10分の1まで下がってしまった、と聞きました。
市場に桃があふれた結果、やはり桃の産地である山梨や山形の桃の出荷価格も暴落しました。山形の生産農家は「福島の農家には投げ売りのような出荷をやめて欲しい」と嘆くのですが、そうもいかない事情があります。福島の生産農家にしてみれば、実際に出荷して売上伝票を手にしなければ、東京電力に事故による損害賠償を請求する証拠が得られないからです。「暴落」を示す出荷伝票をもとに「これだけの損害を被った」と主張するしかないのです。
9月に入り、福島産の桃の出荷が終わったため、桃の値段は例年近くまで戻したそうですが、山形県の農協関係者は「これから梨の出荷が始まる。続いてブドウ、リンゴ、米の出荷も始まる。すべての作物で桃と同じことが繰り返されるのではないか。暴落がどの範囲まで広がるのか予想もつかない」と顔を曇らせています。畜産や酪農だけでなく、野菜栽培や稲作への打撃もきわめて深刻です。
憂鬱な秋が「今年限り」ならば、まだ「なんとか乗り切っていこう」という元気も出るでしょう。しかし、放射性物質による汚染の影響が何年続くのか、汚染のレベルが低くなったとしても風評被害は収まるのか、答えられる人は誰もいません。なにせ、4基もの原発がこれほど長期にわたって放射性物質をまき散らした前例はないのですから。
なんと罪深い事故であることか。原発の安全神話を唱えてきた政治家と官僚、電力業界、研究者たちの無責任さにあらためて強い怒りを覚えます。そして、自分を含めて原子力発電が持つ可能性と危険性を冷静にバランス良く伝えることができなかったメディアも、その責めから逃れることはできません。
バラ色の夢を語る者には注意せよ――昔からそう言われてきたのに、なぜ同じような過ちを繰り返してしまうのか。人はついに歴史から学ぶことができないのか。秋雲がたなびき始めた空を見上げながら、考え込んでいます。
*メールマガジン「おおや通信66」 2011年8月23日
東北の小学校の夏休みは短く、大谷小学校でもきのう(22日)から2学期が始まりました。始業式では、校長として「よく遊びよく学べ」という夏休みモードから「よく学びよく遊べ」という勉強モードに切り替えましょう、と呼びかけたうえで、子どもたちに「今年の2学期は特別な2学期になりました」という話をしました。
東京電力の原発事故で大量の放射性物質がまき散らされたため、福島県の多くの学校ではグラウンドを使えない状態が続き、親たちが不安と不満を募らせています。そして、夏休みを前に「もうこんな状態には耐えられない」と、子どもを県内外に避難させる決断をした親がたくさん出てきました。「原発疎開」に拍車がかかっているのです。
2学期から山形県内に転校した福島県の生徒は、小学生だけで280人を上回りました。夏休み前に転入した生徒を含めると、山形県内の小学校への転入者は900人を超えます。もちろん、中学生や高校生も来ています。山形県だけでなく、宮城県や茨城県、北関東や首都圏にも、ものすごい数の生徒が転校していきました。
読売新聞福島版によると、原発事故の後、福島県内でこれまでに転校した小学生と中学生は合計で1万4000人に上り、全体の1割近くに達しています。このうち、同じ福島県内の放射線レベルの低い地域に転校した生徒が4割、残りの6割は県外への疎開です。
始業式の校長あいさつで、私は「この100年間で日本の子どもたちが危ないところからたくさん逃げ出したのは2回しかありません。先のアジア太平洋戦争の時、空から爆弾が降ってくる空襲から逃れるための疎開と、今回の原発事故による疎開の2回です。危険なところから危険でないところに移ること、それを疎開と言います。3月の大震災とそれに続く原発事故によって、そうした疎開が始まり、2学期から新しい学校に移る生徒がたくさん出てしまったのです。今年の2学期は『特別な2学期』になりました。そのことを胸に刻んでおきましょう」と述べました。
続けて「多数の日本人が放射能の被害を受けるのはこれが3回目です」とも説明しました。「1回目は8月6日の広島への原爆投下、2回目は8月9日の長崎への原爆投下。そして、3回目が今回の福島の原発事故による被害です。そのことも、よく覚えておきましょう」と結びました。
2学期の始業式の校長あいさつとしては、異例の長いあいさつでしたが、生徒たちは静かに聞いていました。子どもなりに、なにかとてつもないことが起きていることを感じているのだと思います。
疎開というのは本来、都会から人の少ない田舎に移動することを表現する言葉のようですが、私はあえて「原発疎開」という言葉を使いたい。ほかの言葉が思い浮かばないからです。疎開する生徒もつらいし、残る生徒もつらい。福島県では、なんとも切ない状況が続いています。「日本の原子力発電所では大きな事故など起こり得ない。クリーンで効率的な電力源です」と唱えて原発建設を推進し、事故への備えを怠ってきた人たちの罪深さをあらためて思います。
*メールマガジン「おおや通信65」 2011年7月5日
NHKが今朝のニュースで「文部科学省は原子力に関する小中学生向けの副読本を見直すことを決めた」と報じていました。副読本は、2010年に全国の小中学校に配布ずみとのこと。いったい、どんな副読本なのか。大谷小学校にもあるかと思って探してみたのですが、卒業した生徒にすべて配ってしまったようで、予備が見つかりませんでした。
やむなく、ネットで検索してみました。副読本のタイトルは、小学生向けが「わくわく原子力ランド」、中学生向けは「チャレンジ!原子力ワールド」というものでした。東日本大震災と福島の原発事故を経験した今となっては、まるでブラックユーモアのようなタイトルです。日本は今や「びくびく原子力ランド」状態だし、政府と東京電力は先が見えないまま「原子力ワールドにチャレンジ」し続けています。
タイトルだけではありません。内容もまた、空恐ろしさを感じさせるものでした。科学的なデータを積み上げて丁寧に作られていますが、「石油はやがて枯渇する」「石炭は二酸化炭素を出す」「自然エネルギーは天候に左右される」と進み、最終的には「安全対策をほどこしながら原子力発電を推し進めるのがベスト」と誘導する構成になっています。
こんな小さな副読本でも「原子力発電を推進する」という国策に沿って、全国の教師が教え、全国の生徒が学ぶ仕組みがちゃんと整っているのです。いつの時代でも、教育はその時代の政府の意向を映し出す鏡なのだ、とあらためて痛感させられます。
スリーマイル島とチェルノブイリの原発事故にも一応触れているものの、「日本では事故が起きないように、また起こったとしても人体や環境に悪影響をおよぼさないよう、何重にも対策が取られています」と自信たっぷりに記述し、大きな地震が来ても原子炉は「自動的に止まる仕組みも備えています」といった具合です。
止まった後も、原子炉はものすごい熱を出し続けること。その熱を取り除くことができなくなれば大変なことになり、その影響が広範囲に長く続くこと。そうしたことには触れていません。地震対策と事故時の「オフサイトセンター」についてはたっぷりと書きながら、津波については全く触れていないのも、今となっては象徴的です。
この副読本の内容は、3月の大震災までは誰でも文部科学省のホームページからダウンロードすることができました。ところが、震災後、文科省はこの副読本のPDFデータをホームページから削除してしまったのだそうです。なにやら、アジア太平洋戦争に敗れた後、GHQの命令で教科書を墨で塗りつぶした史実を連想させます。やや大げさに言えば、平成の「墨塗り副読本」事件といったところでしょうか。
しかし、ネット社会が怖いのはこういう時です。文科省は削除したつもりなのでしょうが、ネット上には副読本の内容が様々な形で残っています。この副読本をもとに教師用のガイドブックを作っている会社があり、その内容をネット上にアップしたりしているからです。そのURLは下記の通りです。
それぞれの末尾には、この副読本の作成にかかわった面々の名前も記されています。天網恢恢、疎にして漏らさず、と言うべきか。
▽小学生用の原子力副読本(教師用)
http://kasai-chappuis.la.coocan.jp/NuclearPowerPlant/pdf/el_t_wakuwaku.pdf
▽中学生用の原子力副読本(同)
http://kasai-chappuis.la.coocan.jp/NuclearPowerPlant/pdf/jr_t_challenge.pdf
*メールマガジン「おおや通信64」 2011年6月14日
年に3回発行される大谷小学校のPTA便り「おおや」に「豊かさとは何か」というタイトルでコラムを書いています。去年は食にまつわる話を書きました。今年は東日本大震災を通して、豊かさとは何かを考えてみたい、と思っています。
? ? ?
大谷小PTA便り「おおや」第85号 連 載 「豊かさとは何か(7)」
津波について書かれた本を一冊だけ読みたい、という方には作家、吉村昭の「三陸海岸大津波」という本をお薦めします。今から40年も前に書かれた本ですが、明治29年と昭和8年に三陸の沿岸部を襲った大津波がどのようなものであったのかを、生々しく克明に綴っています。
執筆した当時、この地方にはまだ明治の大津波を経験したお年寄りが生きていました。吉村は村々を歩き回って、そうしたお年寄りたちから直接、話を聞いてこの本をまとめたのです。
例えば、岩手県田野畑村の中村丹蔵の証言。中村は当時10歳で、山の中腹にある家にいた。押し寄せた津波は山をはい上がり、家の中にまで流れ込んだ。その家は海面から50メートルの高さにあった――。
岩手県の釜石や田老、宮城県の気仙沼や志津川といった、今回の震災でも被災した地名が次々に出てきます。そして明治の時にも、津波は各地で20から30メートルの高さに達していたことが分かります。
今回の大津波について「千年に一度」と表現する人たちがいます。確かに、地震の規模を示すマグニチュードに着目すれば「千年に一度」と言ってもいいのかもしれませんが、三陸に押し寄せた津波は明治のものとそれほど大きな違いはありませんでした。
私たちの社会は、遠い過去の津波の傷跡を丹念に洗い出し、記録する作家を生み出すほど豊かになった。けれども、そこから教訓を汲み出し、きちんと防災に生かすだけの豊かさには達していなかった、ということなのかもしれません。
*メールマガジン「おおや通信63」 2011年6月7日
大震災の発生以来、おびただしい量のニュースが流れた。テレビはNHKが圧倒的にいい。もともと、民放とは比べ物にならないくらい取材陣が手厚く、政府の地震対策に深く組み込まれていることもあって有利な立場にあるのだろうが、それにしても今回の震災を多角的に捉え、深く伝えようとする気概を感じる。
隠居した年寄りの小言のようで気が引けるのだが、新聞各紙の報道は物足りない。現場の記者も本社の編集者も、一生懸命に目を血走らせて働いていることは分かるのだが、「映像では伝えきれないものを抉り出して活字にする」という覚悟のようなものがあまり感じられない。
原発事故が起きた時、そこにいた東電と協力会社の人たちはどう動いたのか。首相官邸や東電本社はどう対処したのか。政府が住民に避難を指示した原発周辺20キロ圏で何が起きているのか。知りたいことが十分に伝わって来ない。東京の編集幹部は「命の危険、健康を害する恐れのあるところに取材に行けとは言えない」と手綱を引き締めているのではないか。ここ十数年で次第に強まってきた傾向である。
突っ込めばいい、というものではない。が、危険を冒さなければ知りえないこともある。自らの意思で、編集幹部の制止を振り切ってでも前に進む記者がいなくなっているのではないか。経験したことのない大震災・大事故を取材するためには、発揮したことがないほどの覚悟が必要だというのに。
その覚悟を、週刊現代の一連の報道に感じるため、なおさら新聞報道への落胆が大きいのかもしれない。正直言って、新聞記者時代は「週刊誌に負けてたまるか」と上から目線で見ていたが、今回の週刊現代の震災報道、とりわけ福島原発事故の報道には目をみはるものがある。多少、「危険性をあおり過ぎ」と思われる記事もあるが、それを補って余りあるほど、優れた報道が多い。
その中でも「白眉」はノンフィクション作家、佐野眞一氏の福島原発半径20キロ圏のルポである。5月28日号と6月4日号に連載された。佐野氏は「お上の許可」など得ないで20キロ圏に入り、丹念に見て回り、人々の話にじっくりと耳を傾けて、何が起きたのか、何を考えたのかを綴っている。作家としての地位を確立している人だが、淡々としたその文章からほとばしる気概と深い洞察にうなった。
事故の第一線で働いた原発労働者の話を聞いた後、佐野氏は記す――
◇ ◇ ◇
「(原発労働者の世界は)一言で言えば、人間の労働を被曝量測定単位のシーベルトだけで評価する世界のことである。一定以上の被曝量に達した原発労働者は、使い物にならないとみなされて、この世界から即お払い箱となる。
それは、一回限りで使い捨てされる放射能防護服と同じである。マルクス的に言うなら、“疎外された労働”の極限的形態が、原発労働ということになる。
原発労働者は、産業的にはエネルギー産業従事者に分類される。だが、同じエネルギー産業に携わっていても、炭鉱労働者の世界とは根本的に違う。
炭鉱労働も過酷な労働には違いない。だが、そこから無闇に明るい「炭坑節」が生まれた。それは、死と隣あわせの辛い労働を忘れるための破れかぶれの精神から誕生したにせよ、その唄と踊りはあっという間に全国を席巻していった。(中略)
だが、原発労働からは唄も物語も生まれなかった。原発と聞くと、寒々とした印象しかもてないのは、たぶんそのせいである。原発労働者はシーベルトという単位でのみ語られ、その背後の奥行きのある物語は語られてこなかった。(中略)
原発のうすら寒い風景の向こうには、私たちの恐るべき知的怠慢が広がっている。
(週刊現代2011年5月28日号のルポ前篇から抜粋)
◇ ◇ ◇
すでに読んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、まだの方には一読をお薦めします。佐野氏のルポに加えて、6月4日号に掲載された「ある老科学者からの伝言」(NHKのETV特集のフォーロー記事)も誠実さを感じさせる記事でした。
「図書館に行って週刊現代をめくる時間がない」という人には、山形の地域おこしNPO「ブナの森」の事務局が特別にサポートサービスをします。下記のメールアドレスもしくは電話&ファクス番号に連絡して「週刊現代の記事を送ってください」と申し出てください。
NPO「ブナの森」
メール:bunanomori@plum.plala.or.jp
電話&ファクス:0237-85-0377
ウェブサイト http://bunanomori.org/
*メールマガジン「おおや通信62」 2011年5月14日
新聞社時代の友人が「チェーンソーを使えるボランティアを求む」との要請に応えて、
宮城県気仙沼市の被災地に行き、がれき撤去の手伝いをしてきました。
10日夜に仙台市のカプセルホテルに泊まり、11日に気仙沼入り。被災地で1泊して
2日間、作業をして戻ってきたそうです。以下はそのルポです。
転送の了解は得ましたが、見出しは長岡が勝手に付けました。
? ? ?
気仙沼市本吉地区で11、12の2日間、流された民家の、残された基礎部分のがれきの処理と小さな漁港に突き出た「象頭山」という、おそらく海の安全の祈りの場であろう石碑と祠のある小さな岩山周辺の片づけを手伝って、今夜自宅に戻りました。遠かった。
そもそも、(前日の10日)仙台で宿泊できる宿がない。震災で配管などがいかれてまだ再開できないところもあるうえ、あっても自治体や支援団体、インフラ系の会社の応援組に占拠されて、駅に遠いビジネスホテルもカプセルホテルも満員御礼。2時間ほどさがしてようやくカプセルホテルが1人分だけ空いたので運良く泊まれたが、個人でボランティアに行くのは、車中泊がいちばんと思う。
当の本吉地区では、まだ電気もきてなく、闇夜にランプで札幌、神戸、岐阜からきた団塊の世代、昭和17年生まれのおっさん連中と一杯飲みながら、テントや車の中で寝るのはなんだか野外キャンプの気分。定年後の自由な生き方ってのは、こういうものだと何となく思う。
魚網、泥、瓦、ガラス、電線、電柱、キティちゃん人形、袋入りのせんべいが絡み合いもつれ合って歩道に乱舞している。倒木、流木、30センチほどの厚さをもつシノ竹が、その土を抱えたままはぎとられ、そこにロープやら網がからんだまま道に放り出されているのを、人形やロープや漁網をわけながらチェーンソーで切り、運んだ。チェーンソーの歯は時々、小石や電線やビニールひもを食い千切っては折れ、2本もってきた歯もほとんど敗退した。それでも、「象頭山」は若者ら10人ほどで一日でだいたいきれいにした。地元のあばちゃんが「きれいになったねぇ」とよろこんでくれたのは、うれしかったね。しかしーー。
自然の力はすごい。人間はぜんぜんすごくない。そう思ったね。
本吉地区はちょうど三陸道の終点、登米・東和インタから南三陸町に入って国道45号線を志津川、歌津と上がって気仙沼市に入ってすぐの地区。小さな入り江の集落なので、ボランティアの手作業でもなんとか少しずつかたづけられ、復興のふの字くらいは見えますが、あの南三陸町をみると、ほとんど絶望的です。
2か月が過ぎても、あれはテレビや新聞が伝える「壊滅的な被害」なんてものではない。むしろ「がれきの海」です。人間社会をつくっていたコンクリート、自動車、鉄筋、ブロック、アスベスト断熱材、タイヤ、木材、金属の塊がもつれ合い、からみあって海となっている。そこに活動する自衛隊やボランティアや大型重機は、まるで大海にあらがうアリのようでした。人間が生産してきたものはうんこと小便とゴミだけだ。
人間のことだからきっと徐々に復興するでしょう。科学と進歩を信奉して津波にも地震にも負けない建物を作るかもしれません。「自然災害に強く、安全な原発」もまた復興させることでしょう。でも、自然を相手に戦ったら負けるにきまってます。自然に逆らったら、またこっぴどい目にあうでしょう。人間の「すごくなさ」を本当に実感しなければならないと、2か月後の現場をみてそう思いました。
*メールマガジン「おおや通信61」 2011年5月10日
ご報告するのが遅くなってしまいましたが、山形県河北町の日帰りボランティアバスに同乗して、4月24日(日)に宮城県の石巻市に復旧のお手伝いに行ってきました。
総勢26人。マイクロバスとワゴン車に分乗して朝6時に河北町役場を出発、9時すぎに石巻専修大学のキャンパスに着きました。ここに石巻市の災害ボランティアセンターがあり、各地から来たボランティアに仕事を割り振っています。私たちは、石巻漁港に近い不動町に向かうよう要請されました。宮城県出身の漫画家、石ノ森章太郎氏の記念館を右手に見ながら橋を渡ったところが八幡町、その隣が不動町でした。

ここで班分けされ、私を含む10人はお年寄り夫婦の家の家財出しと泥かきをすることになりました。おばあちゃんと手伝いに来た娘さん2人、娘さんのいとこ(男性)の4人で作業しているところに、10人の助っ人が加わったわけです。河北町の谷地高校の女子生徒、これで5回目の参加という21歳の若者、初老の夫婦など多彩な顔ぶれでした。
泥だらけになった箪笥や畳を次々に運び出し、歩道沿いに並べていきました。津波の襲来から1カ月半もたっているのに、畳はまだじっとりと濡れていました。重いものは2人では運べないほどでした。畳をはずすと、床には濃いこげ茶色の泥が1センチ近い厚さで積もっていました。これをスコップでこすり取り、土嚢に詰めていきます。
家のあらゆる場所に泥、泥、泥・・。津波が海底の泥を巻き上げて押し寄せ、残していったものです。青森から岩手、宮城、福島、茨城、千葉までのすべての沿岸部に泥を伴って押し寄せた津波。なんと巨大なエネルギーであることか。スコップで泥かきをしながら、頭がクラクラしそうでした。
こういう作業は少人数でしていたのでははかどらず、気も滅入ってくるでしょう。大勢のボランティアでワッサワッサやるのがいい。1時間ほどで家具と畳出し、家の中の泥かきが終わり、続いて物置と側溝の泥かきをしました。どういうわけか、こちらは溶かしたアスファルトのような、まっ黒な泥でした。物置に保存していた白菜や玉ねぎが腐り、泥の臭いと混じってかなり強烈です。臭いに鈍感な私でも、マスクなしでは耐えられないほどでした。
短い昼食休憩をはさんで3時間足らずの作業でしたが、後片付けはほとんど終わりました。見知らぬ人をたくさん迎えて、最初は硬い表情をしていたおばあちゃんも「こんなにきれいになって・・」と嬉しそうでした。震災当日のことを聞いたら、「(おじいさんと)2人とも逃げ遅れてしまい、避難所の小学校には行けそうもなかったので、そこのホテル(4階建て)に逃げ込んで助かりました」と話していました。
壁に残った跡から判断すると、この家は80センチほどの高さまで水に漬かったようですが、倒壊は免れました。大切なものがなんとか残っただけでもまし、と言うべきかもしれません。ここから数百メートル海寄りの八幡町は壊滅状態で、がれきの山になっていました。元の状態で残っている住宅は皆無。一部の地域では、いまだに電気も水道も復旧していませんでした。
それでも、ポツリポツリと後片付けを続ける人たちがいました。あきらめてはいません。ほんのわずかではあっても、前に進んでいました。私たちも、たった1軒だけですが、この日、きれいにすることができました。若いボランティアたちが淡々と、穏やかな表情で仕事をしている姿がなんとも頼もしく、印象的でした。
新聞社にいたころ、2004年12月にインド洋大津波に襲われたスマトラ島北部のアチェ地方を1カ月後、1年後、2年後に訪ね、取材しました。目を覆いたくなるような惨状を呈していた被災地が少しずつ片付けられ、だんだん元の街のようになっていくのを見て、「自然の力はすごいけれど、人間の力だってすごい」としみじみ思いました。
山形県からは、河北町に続いて、私の故郷の朝日町などほかの自治体からも日帰りのボランティアバスが出ることになりました。山形大学と東北芸術工科大学もボランティアバスの運行を始めました。できる範囲で、息長く。そんな活動が広がっていることに勇気づけられます。インド洋大津波後の復興にも増して、「人間だってすごい」ということを日本から発信したいし、きっとできる、と信じています。

*これからボランティアにでかける人へのワンポイントアドバイス
泥かきをすると、かなり汚れます。上下の雨具を着用することをお薦めします。
ゴム製の長靴、手袋も必需品です。泥には破傷風菌など雑菌がかなり含まれています。
*長岡昇のメールマガジン「おおや通信60」 2011年4月22日
先週末、山形県河北町(かほくちょう)の「環境を考える会」のみなさんと今回の大震災について語り合う機会がありました。山形の内陸部にある河北町は、かつて紅花の生産地として栄えた町です。その集いで、この町から宮城県石巻市の被災地に向けて、毎日ボランティアバスが出ていることを知りました。
毎朝6時、被災地での奉仕活動を希望する20人ほどの住民が河北町役場に集合。町が委託し、町社会福祉協議会が運行するバスで宮城県の石巻専修大学へ。ここで、石巻市災害ボランティアセンターからどの地区で活動するか指示を受け、夕方まで奉仕活動をして、その日のうちに町に戻る。それを4月の初めから毎日、続けているのです。
大震災後、住民の間から「自分たちも被災地に行って復旧の手伝いをしたい」という声が続々と寄せられ、それを受けて町役場と社会福祉協議会が、姉妹提携関係にある石巻市に毎日ボランティアバスを出すことを決めた、とお聞きしました。
バスを運行する経費は町が負担、派遣事務や被災地との調整は社会福祉協議会、そして汗を流すのは一人ひとりの住民――自治体と公益団体、住民がそれぞれバランス良く、自分たちが果たすべき役割を果たしています。しばしば「これからは『新しい公共』の時代」と言われますが、この河北町の被災地支援は、その「新しい公共」という考え方を行動に移すとどうなるかを分かりやすい形で示してくれているように思います。
もちろん、ボランティアバスの運行自体は、目新しいものではありません。阪神大震災の時にもあったと聞いています。また、今回の大震災でも、日本の各地から被災地に向けてボランティアバスが運行されています。
ただ、例えば長野県のある市が出しているボランティアバスの場合は「3泊4日」の日程です。これだと、参加できる人はどうしても限られてしまいます。「お手伝いしたい」という気持ちはあっても、年度初めの忙しい時期に4日間費やすのは容易なことではありません。
その点、被災地に隣接する山形県や秋田県からなら、日帰りで応援に行くことができます。そして「1日ならなんとかなる」という人はたくさんいます。実際、河北町の場合はこれまでボランティア活動をした経験がない人も多数参加していると聞きました。幅広い層が参加することを可能にした「日帰りボランティアバス」のアイディアと実践。東北の各地にこうした取り組みが広がることを願っています。
石巻市のボランティアセンターによれば、被災地ではまだまだ人手が足りません。津波が運んだドロの除去、壊れた住宅の片付けと清掃、支援物資の仕分けと運搬・・・。大勢の方が駆けつけてくれているものの、派遣要請はボランティアの数の倍というのが実情だそうです。
1日だけですが、私も河北町のボランティアバスに乗って、24日に石巻市の被災地にお手伝いに行く予定です。戻りましたら、その様子をまたご報告します。
*長岡昇のメールマガジン「おおや通信59」 2011年3月31日
大津波に襲われた時、人はどのように振る舞い、どのようにして生き延びようとしたのか。それを伝える報道に接して、何度も目頭が熱くなってしまいました。
住民に津波の襲来を知らせるため昔ながらの半鐘を乱打し続け、自分は津波にのみ込まれてしまった消防団員、押し寄せる波にのまれながら病院の衛星電話を同僚に手渡して行方不明になった職員(今はこの衛星電話が外部との唯一の連絡手段)、自分の身内も行方不明のままなのに予備自衛官の招集に応じ、泥だらけになって海辺で捜索を続けている自衛隊員・・・・。何と気高い人が多いことか。すさまじい自然の力に打ちのめされながらも、救われる思いです。
人の運命を分けるものは何なのか。それを考えざるを得ない日々でもあります。岩手県宮古市田老地区では、営々として築いてきた「世界一の防潮堤」がほとんど役に立たず、むしろ「この防潮堤があるから大丈夫」との油断を招き、被害を大きくしてしまった可能性があること。逆に、そうした防潮堤やコンクリート製の防災ビルがない「無防備な港町」の人たちは、揺れの直後にひたすら高台に逃げたために犠牲者を最小限に抑えることができたことを知りました。自然に向き合う時、人間は謙虚になるしかない、ということなのでしょう。
福島第一原発の事故は「謙虚さを失った人間集団への強烈な鉄拳」のように思えます。同じ太平洋岸にある東北電力の女川(おながわ)原発(宮城県)は、ほとんど損傷がなく、いまは原発敷地内の体育館を地元の人たちに避難所として提供し、食事も出している、と28日付の山形新聞が報じていました(共同通信の記事と思われます)。
この記事によると、東京電力が福島第一原発を建設した時に想定した津波の高さは5.7メートル。そのうえで、1?4号機は「余裕をみて」海抜10メートルの土地に建設したのだそうです(5、6号機は13メートル)。一方、東北電力の女川原発の場合は、9.1メートルの津波を想定し、海抜14.8メートルの高台に建設したとのこと。女川原発は新しい原発なので耐震基準なども違うのでしょうが、そうしたことよりも決定的だったのは、この4.8メートルの標高差です。非常用の電源設備やそれを冷やすポンプなどが津波で水をかぶるか、かぶらないか。それがこの差によって決まったからです。
専門家の助言がなかったわけではありません。古い地層から過去の津波のことを調べている古地震学者は、平安時代869年の貞観(じょうがん)地震では東京電力の想定を超える津波が襲来した可能性があることを指摘し、対策を講じるよう助言したのだそうです。2004年のインド洋大津波のことも念頭にあったはずです。東京電力は、その助言に素直に耳を傾けようとしませんでした。しぶしぶ非常用電源とポンプの壁の補強工事にとりかかったものの、終わらないうちに「3・11」を迎えてしまった、と報じられています。
自然から学ぼうとしない者たちのために、私たちは未曾有の大津波に加えて、史上2番目にひどい原発事故という二重の苦難に向き合わなければならなくなりました。「想定外だった」などと言って逃げようとする学者や官僚がいますが、事実は違います。事実は「想定しようとせず、学ぼうとしない人たちがいた」のです。
*メールマガジン「おおや通信58」 2011年3月27日
「森は海の恋人」という言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょうか。「牡蠣(カキ)を丈夫においしく育てるためには、何よりも海に注ぎ込む川が健康でなければならず、そのためには上流の森が豊かでなければならない」。そう考えた宮城県気仙沼市の漁師たちが20年ほど前に始めた運動です。漁師たちは大漁旗を抱えて山に通い、植林を重ねてきました。
この運動を提唱し、その中心になってきたのが宮城県気仙沼市の畠山重篤(しげあつ)さんです。去年の8月に畠山さんの話をお聞きする機会があり、一緒に食事をしながらお人柄も知ることができました。ユニークで、しかも深い智恵を感じさせる方です。漁師たちが始めた運動は今や、漁業と林業、環境との関係といった範囲を超え、京都大学との学際研究にまで発展しています。
その畠山さんの郷里も今回の大津波で被災したことを知り、何とか支援物資をお届けしたいと思っていたのですが、山形ではガソリンの入手もままならず、行くことができませんでした。先週末、ガソリンを譲ってくれた方がいて、自分の車を満タンにできたので、コメや飲料水、ミカンやリンゴ、インスタント食品、乾電池、トイレットペーパーなど当座必要そうなものを車に積んで、一人で気仙沼に向かいました。それぞれ20リットルほどですが、ガソリンと灯油もなんとか入手して積み込みました。
山形自動車道と東北自動車道は仮復旧していますので、高速道路で岩手県の一関インターまで走り、そこから東にある気仙沼に向かいました。港と市街は壊滅状態でした。電気はいまだに来ていません。畠山さんの自宅は、気仙沼中心部の北にある唐桑(からくわ)半島の漁村にあります。普段なら市街地から30分ほどで行けるのでしょうが、道路や橋がズタズタになっているため、ガレキの山を縫うようにして進まなければならず、山側を大きく迂回してやっと半島にたどり着きました。1時間半ほどかかりました。山形からは片道200キロ余り、5時間がかりでした。
畠山さんが住む西舞根(にしもうね)地区もほぼ全滅の状態でした。畠山さんは留守でしたが、家族によると、自宅は海抜25メートルの高台にあるのに、その玄関先まで津波が押し寄せたので、あわてて裏山によじ登って難を逃れたそうです。息子さんは「50戸ほどの住宅のうち、かろうじて残っているのは、うちを含めて4戸だけ」と言っていました。
それでも、この地区の住民は津波の襲来を予想して一斉に高台に走りました。逃げ遅れて亡くなったのは、体が不自由なお年寄りや車いすの人など数人だそうです。畠山さんの家にいた家族は全員、無事でしたが、老人ホームに入居していたおばあちゃんはベッドに横になったまま波にのまれて亡くなった、とお聞きしました。大震災から15日後のきのう(26日)、ようやく葬儀を営むことができ、畠山さん本人は一足先に葬儀場に向かったため行き違いになってしまったようです。
大変な時なので、持参した物資を手渡してすぐ、私は帰路につきました。途中、南三陸町など海沿いの地域を通りました。建物の損壊状況やプラスチック類の漂着ぶりから判断すると、津波の高さは「リアス式の海岸部で25?30メートル、平坦な海岸部で10?15メートル」と見られます。2004年12月に起きたインド洋大津波の現場(スマトラ島北部のアチェ地方)を取材して回りましたが、これに匹敵する破壊力だったと考えられます。
インド洋大津波の犠牲者は最終的に20万人前後と推定されています。ほぼ同規模の津波で、今回、犠牲者が数十万人規模にならないとすれば、日本の場合は津波が何度も起きており、「グラッと来たら高台へ」という教訓が途上国よりはるかによく浸透していたからかもしれませんが、それにしてもすさまじい災害です。
被災から2週間たち、医薬品などを除けば、現地には飲み水やインスタント・レトルト食品、毛布などの緊急支援物資が届きつつある印象を受けました。これからは日常的な生活物資、つまり普通のご飯やみそ汁、おかずを用意するのに必要な食料、新鮮な果物、ガソリンや灯油、乾電池などを被災地に届けることが求められています。つまり、被災者支援は「緊急段階」から「第2段階」へと進むべき時期に差しかかっているように思います。
駆け足で被災地とその周辺を見て回って、もう一つ感じたのは、被災の後背地への物資供給の重要性です。最初にも触れましたが、山形県内ではいまだにガソリンや灯油の入手が困難です。これと同じことが津波被災地のすぐ近く、津波の被害に遭わなかった地域で起きています。物資の流れが「とにかく被災地へ」となっているため、被災の後背地を素通りしてしまい、ガソリンや食料などの生活必需品がいまだにほとんど手に入らないのです。
これでは、すぐ近くにいる人たちが被災者に手を差し伸べたくても、できません。ガソリン一つ手に入れるのに、4時間も5時間も並ばなければならないからです。「後背地にも生活必需品を」と声を大にして叫びたい。むろん、被災者支援の後方拠点とも言うべき山形や秋田にも必要です。
福島原発の事故による放射能汚染が首都圏にも及び、大変なのは分かりますが、まず被災地、次にその後背地にもっと物資を送り込まないと、復旧と復興が大幅に遅れる恐れがあります。電気や水道、ガスの復旧作業にあたる人たちは、その後背地で寝泊まりして仕事を続けていますが、その宿泊場所にも事欠く状況になっています。
私は土曜日(26日)に気仙沼の被災地を訪れ、そのまま車で夜を明かすつもりでいたのですが、知人の助けで、たまたま宮城県の大崎市(旧古川市)のビジネスホテルに泊まることができました。そのホテルも、倒壊こそしなかったものの、あちこち壊れていました。修復工事もできないまま、なんとか宿泊と簡単な食事のサービスを提供しているのには頭が下がりました。
被災地から遠いところほどより多く節約し、少しずつリレーしていって、とにかく津波の被災地と後背地に早く物資を届けたい。
メールマガジン「おおや通信19」 2010年3月5日
?小学校や中学校では今、卒業式の予行演習がたけなわです。大谷小学校でも、11人の卒業生を温かく送り出すべく、準備に余念がありません。
練習のうち、かなり力を入れるのが歌の練習です。卒業式では校歌や別れの歌に加えて、君が代も歌います。その練習を見ているうちに「意味も分からないまま歌うのは、つらいだろうなぁ」と感じました。そこで、朝の集会で校長として「君が代の意味と歴史」について話すことにしました。次のような内容です。

今日は、卒業式でみんなで歌う日本の国歌、君が代について話します。1、2年生には少し難しいかもしれませんが、とても大事な話ですからよく聴いてください。
歌は、言葉とメロディーの2つでできています。言葉が先にできて後からメロディーが付くこともあるし、メロディーが先にできて、後で言葉が付けられることもあります。両方同時にできることもあります。
「君が代」は、言葉が先にあって、ず?っと後になってからメロディーが付けられた歌です。(黒板に古今和歌集のルビ入りの和歌を張って示しながら)これが「君が代」のもともとの歌詞です。?
? 我君は千代に八千代に
? さざれ石の巌となりて
? 苔のむすまで
? 古今和歌集(905年)から?
この和歌は1000年以上も昔に作られたものです。最近、4年生は俵万智のサラダ記念日の短歌を習いましたが、それと同じで5、7、5、7、7のリズムになっています。「さざれ石の」のところは6つの音になっています。
誰が作ったのかは分かっていません。そのため、この歌の意味についてはいろんな人がいろんな事を言っています。「恋の歌だ」と言う人もいます。
「何を言っているんだ、葬式の歌(挽歌)だ」という人もいます。ですが、和歌のことを長く研究した人の多くは「長寿を祝う歌だ」と言っています。それが素直な考え方のようです。古今和歌集の「祝い事の歌」のところに収められているからです。
意味は「わたしの大切な人が千年も万年も長生きできますように。細かい石が長い年月の間に大きくて固い岩になるくらい長く、その岩に苔がびっしり生えるまで長く」というものです。とても目出度い歌なので、その後もずっと、鎌倉時代から江戸時代まで歌い継がれてきました。「我君は」のところは、後で「君が代は」と変わり、そのまま歌の題名になりました。
ずっと人々に親しまれてきた歌ですが、江戸時代から明治へと変わった時に、この歌に今のようなメロディーが付けられました。明治13年、今から130年前のことです。この時、もともとの意味が大きく変わってしまいました。
当時、すべての力を持ち、日本を支配していたのは天皇陛下でした。今とは違う政治でした。その政治の影響で「君が代は」というところが「天皇陛下の世の中が」と読み替えられ、それが「ずっと続きますように」という風になってしまったのです。それは、もともとの「君が代」にとっては哀しいことだったでしょう。
そういう政治の下で、日本は戦争に突き進み、多くの人が亡くなりました。先の戦争で、日本では300万人以上の人が亡くなりました。中国でも1000万人以上、フィリピンでも100万人を超える人が命を失いました。ほかのアジアの国々でも多くの人が亡くなりました。
このため、「君が代を歌いたくない」という人たちがいます。それなりに理由のあることですが、私は「心が狭すぎるのではないか」と思います。逆に、「君が代を歌わないのはけしからん」と怒って、「歌わない人を罰するべきだ」という人たちもいます。私は「大人気ない人たちだなぁ」と思います。日本は自由な国です。歌わないという人たちがいても構わないでしょう。ただ、そういう人たちには、静かにしていて欲しいと思うのです。
「君が代」という歌は歴史にもまれて、哀しい時期を過ごしたこともありましたが、1000年の時を経て、もともとの穏やかな、人々の幸せと長寿を願う歌に戻ったのだと思います。戦争の後、この国の主人公は国民一人ひとりになりました。その一人ひとりの幸せを願う歌になったのだ、と考えればいいのです。
卒業式では、静かな気持ちで、みんなの幸せを願う気持ちを込めて、この歌を歌いましょう。
? ?
*主な参考文献
「日の丸・君が代の成り立ち」(暉峻康隆著、岩波ブックレット)
「君が代の歴史」(山田孝雄著、宝文館出版)
「三つの君が代」(内藤孝敏著、中央文庫)
「『君が代』の履歴書」(川口和也著、批評社)?
*古今和歌集の歌は
我君は千世に八千世に
さゝれ石の巌となりて
苔のむすまて
が正しいようですが、「我君は→君が代は」のところがポイントなので、黒板には上記のように記しました。
*メールマガジン「おおや通信18」 2010年2月26日
あるシンポジウムで教育学者の大田尭(たかし)さんの話をお聞きする機会がありました。92歳という年齢を感じさせない、かくしゃくとした話しぶりでした。冒頭、大田さんは谷川俊太郎さんの詩を引用しました。
あかんぼは歯のない口でなめる
やわらかい小さな手でさわる
なめることさわることのうちに
すでに学びがひそんでいて
あかんぼは嬉しそうに笑っている
人は、生まれ落ちたその瞬間から学ぶことを始め、学びは命が尽きるまで続く。それを手助けするのが教育である――生涯かけて「教育とは何か」を追い求めてきた碩学(せきがく)の言葉に、重いものを感じました。
大田さんは、今の日本を「無機化しつつある社会」と表現していました。昔のような共同体が壊れ、過度の市場経済主義によって個々人がバラバラに無機物のようになってしまった、と警鐘を鳴らしていました。
バラバラになっていく社会の中で、一人ひとりがどう振る舞うのか。子どもたちの学びをどう手助けしていくのか。難しい時代ですが、それはまた、仕事のやりがいがある時代ということでもあります。一人ひとりの決意が問われる時代、と言っていいかもしれません。
(*大谷小学校PTA新聞「おおや」第81号から。詩は、2009年1月1日の朝日新聞に掲載された谷川俊太郎「かすかな光へ」の一部)
メールマガジン「おおや通信15」 2009年12月22日
東北は先週から厳しい寒波に襲われ、ドカ雪になりました。郷里の山形県朝日町でもひと晩に30センチ、20センチと降り続き、このまま根雪になりそうな雲行きです。
「自宅から学校まで車で8分。なんと恵まれた環境だろう」と悦に入っていたのですが、雪降りの朝は、車に積もった雪を振り払い、駐車スペースを除雪するのに、毎回30分から1時間はかかります。雪かき30分、それから通勤の生活が春まで続くわけで、やはり「雪国暮らしは容易ではない」と思い知らされています。
「絵の詩のと 雪の五尺に住んで見よ」
朝日町在住の俳人、阿部宗一郎さんは雪国のつらさに思いが及ばない都会の人に向けて、痛烈な句を詠んだことがあります。この土地で80年余り暮らした人の感慨でしょう。
「そんな大雪なら、小学生の登下校も大変だろう」と思うかもしれませんが、さにあらず。道路はきれいに除雪され、通学バスも通学タクシーもスーイスイです。地方では、学校の統廃合が進み、通学バスではカバーしきれないので、一部の集落にはタクシーを手配して子どもを送り迎えしています。大谷小学校でも2地区、5人の生徒がタクシー通学です。経費を考えれば、その方が安上がりなことは分かっているのですが、にわか校長としては釈然としないものがあります。
きょうは大谷小学校の平成21年度2学期の終業式でした。そこで、子どもたちには「元気で年末年始の休みを楽しんでください。雪かきの手伝いも忘れずに」と述べた後、かつての焼野(やけの)という集落の人たちが続けた雪踏みのことを話しました。こんな話です。

? ? ?
大谷小学校には、かつて3つの分校がありました。その1つが大暮山(おおぐれやま)分校で、ちょうど10年前に分校としての役割を終えました。昔、この分校には90人の生徒がいました。いまの大谷小学校よりもたくさんいました。
その中に、焼野という集落から通ってくる子どもたちがいました。焼野は実は、隣りの大江町の集落なのですが、近くに学校がないので、山を越えて大暮山分校に来ていました。片道、歩いて1時間以上もかかりました。冬、雪が降ると、もっと時間がかかり、1時間半以上も歩かなければなりませんでした。
子どもたちがあんまり大変そうなので、大暮山の人たちは「冬の間だけ、子どもをこっちに預けたらどうだ」と提案しました。でも、焼野の人たちは「ありがたいけど、やっぱり一緒に暮らしたいから」と丁重に断ったのだそうです。
そして、雪が降るたびに村人たちは交代で雪踏みをして、子どもたちを先導しました。一方、大暮山の村人たちも反対側から雪踏みをし、峠のあたりで両方の雪道がつながったといいます。冬の間、雪が降るたびにそれを続けたのです。
つらくて、大変だったと思いますが、これにはいいこともありました。これだけ苦労して雪道を往復したので、焼野の子どもたちは足腰がとても強くなって、駆けっこも速かったのだそうです。
いま、大谷小学校にはタクシーで登下校している友だちもいます。便利で快適でしょうが、足腰を鍛えるのにはプラスになりません。つらいことにも、いいことがある。便利なことにも、困ったことがある。世の中には、いいことだらけ、つらいことだらけ、というものはありません。いいことにはつらいこと、つらいことにはいいことが付いて回るようになっています。そのことを忘れないでください。
? ? ?
校長として行事や朝の会であいさつする時は3分以内。説教くさい話はしない、と決めているのですが、きょうは珍しく説教くさくなり、時間も3分をオーバーしてしまいました。そのせいか、1年生が1人、話しているうちにお漏らししてしまいました。
やはり、長い話は禁物のようです。良いお年をお迎えください。?
*焼野の人たちはかなり前に離農し、いまは集落の跡地を探すのも困難です。?
*メールマガジン「おおや通信8」 2009年9月8日
東北の小学校の夏休みは短く、8月19日からすでに2学期が始まっています。
26日に校内の水泳大会があり、9月6日には秋の運動会を開きました。大きな行事は早めに終えて、あとは「勉学に集中する」という構えです。これまでの通信で、大谷小学校の生徒は89人とお伝えしましたが、きょうは保護者の職業についてご紹介します。
兄弟や姉妹で在籍している子がいますので、89人の生徒に対して保護者は71世帯です。そのうち、専業農家はわずか6世帯しかありません。あとは、公務員が9世帯(教師3、自衛隊3、地方公務員3)、自営業が7、民間企業勤務が49という内訳です。

3年生が同級生のおじいちゃんの畑でリンゴの収穫をしました
私は「農村地帯なのに、これしか専業農家がいないのか」と驚いたのですが、サクランボ農家が多い地域出身の教師は「うちの地域より多いね。リンゴだと専業農家として食べていけるんですねぇ」と感心していました。
山形の内陸部はサクランボの産地として有名ですが、この「赤いダイヤ」は収穫期間が6月の1カ月ほどしかありません。ビニールの覆いなど設備費がかかるうえに農作業が集中するため、手広く栽培することは難しく、サクランボを中心にした農業だけでは暮らしていけないのだそうです。その点、リンゴは早生(わせ)から晩生(おくて)まで様々な品種を栽培することによって、9月から11月まで3カ月近く収穫することができます。大規模に栽培することも可能で、これが「リンゴ専業農家」としての暮らしを支えているようです。
それにしても、朝日町のような農村地帯にある小学校ですら、専業農家が「71分の6」しかいないとは・・・・。日本の農業、とりわけ中山間地の農業はぎりぎりのところまで来てしまったということでしょう。かつて、朝日町では専業農家が6、7割を占めていました。いまは祖父母が田畑を耕し、若夫婦が月給取りをして生活を支える、いわば「2世代による兼業農家」が多数派になりました。サクランボ農家の多くも、このタイプです。若夫婦には農業のノウハウが乏しく、祖父母が働けなくなれば、農業はさらに廃れてしまうでしょう。
農業を再生し、農村を活性化するためには「若い人が農業で食べていけるシステム」を作るしかありません。総選挙で民主党が主張した「農業者への戸別所得補償制度」は、そのための1つの処方箋なのかもしれませんが、何を基準にどうやって補償するのか、制度作りがきわめて難しく、成果が出るまでには時間がかかりそうです。その間にも、農村の過疎は進み、人口も減り続けます。じっと待っているわけにはいきません。若者を惹きつけるためには、自分たちで動き出す必要があります。
実際、岩手県の九戸(くのへ)村では、新たに農業を始める人に、単身なら月額10万円、夫婦なら13万円、夫婦と子どもには15万円を支給する制度を始めました。年に2家族を対象に3年間支給する、という制度です。意欲的な試みですが、新たに農業を始めようとする若者に「3年間だけ生活を支える」というのでは短すぎるように思います。村の財政を考慮すれば、それが限界なのかもしれませんが、できれば、「就農して子どもが小学校に入るまでの10年間」は支えたい。
そこで私は「100人が月に1000円ずつ拠出して1人の若者を支える『農業サポーター制度』を創設しよう」と提唱しています。これなら無理がなく、なんとか10年間続けられるのではないでしょうか。税金に頼らず、ボランティアベースで新規就農者を支えるのは、「その方が支援対象者の審査や支援打ち切りの判断などが柔軟にできる」と考えるからです。自治体には、農地のあっせんや営農のアドバイス、農機具のリースなど側面から支援してもらう構想です。
むろん、この農業サポーター制度が機能するためには、支援を受ける人が収支をガラス張りにして公開することが大前提になります。昔から「所得を隠すのが当たり前」になっている農民にとって、これは意識革命を求めるものでもあります。
農業と農村はもう、崖っぷちまで追い詰められてしまいました。常識や慣習にとらわれていては、とても甦らせることはできません。文字通り、身を切る覚悟で道を切り拓くしかない、と考えています。
〈注〉 1.学校教育法などでは「小学生は児童、中学生は生徒」と区別していますが、
11歳、12歳の小学生はもう半分、大人です。「児童」という日本語を使う
のに違和感を覚えますので、あえて生徒と表現しています。
2.山形県東根市には陸上自衛隊の駐屯地があります。昔は遠くて、大谷から
通えなかったのですが、道路が整備され、いまでは通勤圏内になりました。
*メールマガジン「おおや通信7」 2009年7月22日
週刊東洋経済が2009年7月11日号で政府の補正予算について「14兆円補正の実態は省庁の“つかみ取り”」という特集を組んでいました。小学校の現場にいると、その“つかみ取り”の実態がよく分かります。
補正予算の成立に伴って、文部科学省は都道府県や市町村の教育委員会を通して全国の公立学校に「教育資器材の大盤振る舞い」に乗り出しました。大谷小学校にも「理科の実験器具はいらないか」「電子黒板はどうか」とのお達しが回ってきました。購入可能な物品のリスト付きです。理科教育設備の整備費だけで200億円もの予算がついたのだそうです。

磁石メーカーの社長さんが出前授業をしてくれました
理科担当の教師に「何か不足していて欲しいものはありますか?」と尋ねると、「だいたい足りています」との返事。私が「それなら購入希望を出すこともないね」と言うと、うなずいていました。ところが、朝日町の教育委員会から「せっかくだから要求した方がいい」と言われたようで、私の知らないうちに町教委がつくった予算要求リストに記入して出してしまっていました。
4月に校長に就任して以来初めて、大谷小の教師を大声で叱りました。「予算があるからといって、とくに必要でもないものを要求するとはどういうことか」「公立の小中学校だけで全国に3万校ある。それが全部、こういう金の使い方をしていたらどうなるのか。国が滅びるよ」。新聞社で鬼デスクと言われたころの地金が出かかりました。
とはいえ、リストはすでに大谷小学校として提出ずみです。それを掌握していなかったのは私の責任です。いまさら撤回はできません。あまりにも過大と思われるものを削って修正することしかできませんでした。結果的に、大谷小としては72万円余りになりました。要求した主な理科実験器具などは、次の通りです。いずれも「もっとあれば便利」「あれば便利」という機材で、必須のものではありませんでした。
生物顕微鏡 4台 19万2000円
野外用の軽量顕微鏡 2台 10万円
星座早見盤 25個 3万7500円
気体検知測定器 6台 10万2000円
財政赤字で国の将来が危ぶまれるのに、不要不急なことに金を使おうとしているのは文部科学省にとどまりません。農水省は、大谷小の旧校舎跡地に「ビオトープ」を作ろうと動いています。ドイツ生まれのこの構想は、川辺や草原を人工的に作って自然に親しむことをめざすものです。
都会ならいざ知らず、すぐ近くを最上川が流れ、里山に囲まれているところに何が悲しくて人工的な自然を作るのか。ただただ、農水官僚の仕事ぶりにあきれるばかりです。その最上川の岸辺に、国土交通省は「フットパス」という遊歩道を次々に作っています。地元の人たちは「だれが利用するんだか」とあきれ顔ですが、「金が下りるならイイか」という態度です。大谷小学校の周辺だけでもこの有り様なのだから、全国ではいったいどのくらい無駄金が使われていることか。暗澹たる思いです。
道路や建物、器具といった「ハード」ではなく、教育の中身と質の向上、若者の就労支援、ハンディを負った人たちへの支援といった「ソフト」にこそ、知恵を絞って資金をつぎ込まなければならない時代になっているのではないでしょうか。
この国が「なすべき事をなす方向」に進むことを切に願います。
◇メールマガジン「おおや通信5」 2009年7月1日号
しばらく前、隣町にあるキャンプ場で5年生と6年生の宿泊体験学習があり、これに同行しました。野外テントで2泊3日。まず、古代人のように木をこすり合わせて火を起こす。その火で煮焚きして、食事を作る。翌日は急な崖をロープで上り下りと、かなりハードなキャンプ生活でした。
印象に残ったのは、食事作りでした。生徒たちに与えられるのは薪と新聞紙とマッチ、それに食事の材料と調理器具だけ。引率の先生たちはあえて、火の焚き方や食事の作り方を教えません。「失敗しながら覚えればいい」と言います。

1日目の夕食のメニューはカレーライス。案の定、生徒たちは火を上手に焚くことができません。かまどに薪をドタッと置き、その上に新聞紙を重ねて火をつけたりしています。これでは勢いよく燃え上がるはずもなく、鍋で炊いたご飯はポロポロ、カレーのジャガイモや玉ねぎは生煮えでした。まずくて食べられたものではないのですが、ほかに食べるものもないので、空腹に耐えきれず、呑み込むようにして食べていました。泣きベソをかきながら食べている生徒もいました。その傍らで、私を含む教師集団はしっかりと火を焚き、普通のカレーライスをおいしくいただきました。
よほど悔しかったのでしょう。翌日の朝食づくりの際には、真剣な顔をして私がどうやって火を焚くのか、観察していました。私は、キャンプ場に落ちている枯れ枝を拾って焚きつけとして使いました。それを見て、枯れ枝を集めて使う生徒も出てきました。どのグループも次第に上手になり、5回目の食事を作るころにはそれなりのものが作れるようになりました。
考えてみれば、今や田舎でも、子どもにとって炎とは「青いもの」であり、ガスコンロのスイッチをひねれば出てくるものです。赤い炎はロウソクなどでたまに見るものでしかありません。少なくとも、暮らしで使うのは「青い炎」です。「火を焚く」という、生きるために不可欠のスキルすら、学校教育で教え込まなければならないのが現実です。
大谷小学校の生徒たちは、まだ恵まれている方です。というのは、5回も食事を作るような宿泊学習を実施している学校は、いまや山形県でも数えるほどしかないそうです。テントで1泊2日、あるいは宿泊棟のベッドで1泊するだけ、というのがほとんどと聞きました。先生方もしんどいし、親も望まない、ということのようです。
気骨のある教師たちがまだ残っていたことに感謝しています。この体験を生かすべく、秋には全校生徒で山形名物の芋煮会をする予定です。里芋とネギは学校の畑で栽培したものを使い、河原の石でのかまど作りや煮焚きは、すべて子どもたちにやらせるつもりです。芋煮会も「失敗したら泣けばいい」を貫くつもりです。

*「おおや通信」は、新聞記者から小学校長に転じた長岡昇が学校で感じたことをつづってお送りしているメールマガジンです。
*メールマガジン「おおや通信2」 2009年4月27日
新聞記者として30年間働いて、一番深く心に刻み込まれたのは、アフガニスタンの難民キャンプで出会ったパシュトゥンの老人の言葉でした。
アフガニスタン内戦を初めて取材した1989年の4月。駐留ソ連軍が完全撤退した直後で、戦闘が激しくなり、首都のカブールには連日、ロケット弾が降り注いでいました。子どもたちも巻き添えで多数犠牲になり、この老人も孫を失った一人でした。老人は、私に向かってこう言いました。
「わしのような老人が生き永らえて、孫が殺されてしまった。いくつもの命がかろうじて生き延び、やっとつないだ命なのに。いのちは幸運の結晶なのに」

カブール北方のパシュトゥン人の村で
民間人校長として働くことが決まった時、何よりも子どもたちに伝えたいと思ったのはこの老人の言葉でした。大谷(おおや)小学校の紹介冊子の冒頭に以下のような形で引用するつもりです。
◇ ◇ ◇
いのちは「幸運の結晶」
君のいのちは
お父さんとお母さんが出会って生まれた。
どちらかが病気やけがで倒れていたら
君はこの世にいなかった。
お父さんとお母さんは
おじいちゃんとおばあちゃんが出会って生まれた。
だれかが病気やけがで倒れていたら
2人はこの世にいなかった。
おじいちゃんとおばあちゃんは
ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんが出会って生まれた。
そして、ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんも
昔むかし若い2人が出会って生まれた。
たくさんの、数えきれないほどたくさんのいのちが
幸運にも生き永らえて
いのちを君につないできた。
だから、いのちは「幸運の結晶」。
ひとつひとつ、かけがえのない存在。
? アフガニスタンの古老の言葉 ?
採録:長岡 昇(大谷小学校校長)
*メールマガジン「おおや通信1」 2009年4月7日
1月末に朝日新聞社を早期退職し、3月から民間校長候補として山形県教育委員会の
研修を受けてきました。3月下旬、赴任先が郷里の朝日町にある大谷(おおや)小学校に
決まりました。山形の農村で何が起きているのか。民間校長として見たまま、感じたままを時折、「おおや通信」と題してお届けします。
 12'2'16.jpg)
きょう(4月7日)、大谷小学校の入学式がありました。
新1年生は22人、生徒は全体で89人、教職員15人のこぢんまりした小学校です。ついこの間まで新聞記者として働いていた人間が、保育園を出たばかりの子どもたちにどういう話をするものか。関心を持たれた方が何人かいらっしゃいましたので、つたない挨拶ですが、お伝えします。
なお、校舎は10年前にできたばかりで、まだピカピカです。校長室と職員室は冷暖房完備、教室と体育館は暖房つき。教職員と生徒が全員そろって昼食をとることのできる「ランチルーム」つき、という贅沢な施設です。背後には白銀の月山が見守るように鎮座しています。写真をご覧になりたい方には個別にお送りします。ご連絡ください。
? ? ?
1年生のみなさん、入学おめでとうございます。
大谷小学校の先生を代表して、歓迎の言葉を述べさせていただきます。
ことしの新入生は22人です。これで、大谷小学校の生徒は89人になりました。
去年より2人増えました。とてもうれしい事です。
これからみんなで、元気で楽しい学校をつくっていきましょう。
本を読むのが好きな人は、本をたくさん読みましょう。スポーツなら得意だよ、
という人はスポーツを楽しみましょう。音楽や絵を描く時間もあります。
好きなこと、楽しいことをたくさん見つけるようにしましょう。
わたしたちは、みなさんが元気に学校生活を送ることができるように力を尽くします。
みなさんは保育園を終えて、きょうから小学生になりました。
そこで、私から、ひとつだけお願いがあります。
それは、自分の家で毎日、なにかひとつ、お手伝いをするようにしてほしいという
ことです。小さなことでいいのです。たとえば、玄関の掃除をする。自分の洗濯ものを
たたむ。そういうお手伝いをしてほしいのです。
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんはみなさんをここまで育てるために、
たくさん汗を流してきました。これからも大変です。
ですから、うちで小さなお手伝いをして欲しいのです。
お願いします。
2年生、3年生、4年生、5年生、6年生のみなさん。1年生はみなさんの姿を見ながら大きくなっていきます。1年生と仲良くしてください。
保護者のみなさま、入学おめでとうございます。こころからお慶び申し上げます。
いつの時代でも、子どもを育てるのは大変なことです。それぞれ、語り尽くせぬ思いを胸に抱いて、きょうという日を迎えられたのではないでしょうか。
お子さんたちを大谷小学校に入学させていただいたことに、教職員一同、厚く御礼申し上げます。わたくしどもは、お子さんたちが元気に育つよう全力を尽くしますが、もとより、教育は学校だけでできるものではありません。みなさまのご協力とご支援を、こころからお願い申し上げます。
ご来賓のみなさま。きょうはお忙しい中、入学式にご臨席たまわり、誠にありがとうございました。先ほど、保護者のみなさまに学校へのご協力とご支援をお願いしましたが、教育は保護者と学校だけでできるものでもありません。
地域の皆様方のご協力なしには成り立ちません。
これまで同様、温かいご支援を賜りますよう、こころからお願い申し上げて、入学式のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
2006年11月16日 朝日新聞夕刊 コラム「窓 論説委員室から」
甲乙つけがたい提案が二つあった場合、どうするか。「じゃんけん」で決めている会社の話が経済誌に載っていた。愛知県のマスプロ電工というテレビ部品メーカーだ。「これなら、負けてもしこりが残らないから」と社長が語っていた。確かにあれこれ迷うより、いいかもしれない。会社の業績も好調らしい。

考えてみれば、じゃんけんはすごいゲームだ。グー、チョキ、パーのそれぞれが強くて弱い。哲学的ですらある。気になって、起源を調べてみた。大手出版社の百科事典は30行足らずの記述しかなくて、要領を得ない。図書館でも、いい本や資料が見当たらない。その歴史から語源まで、内容がもっとも充実していたのはインターネット上の無料百科事典「ウィキペディア」だった。
それによると、じゃんけんの誕生は意外に新しく、19世紀末の日本だという。戦後、日本が立ち直り、経済的に発展するにつれて海外に広まったようだ。 英語ではRPSという。Rock(岩)、Paper(紙)、Scissors(はさみ)の頭文字を取ったものだ。
カナダに「世界じゃんけん協会」というのがある。11年前に結成され、4年前から世界選手権大会を開いている。代表のグラハム・ウォーカーさんによると、先週末、トロントで今年の大会が開かれたが、日本からの参加者はゼロだった。「寂しい」と嘆いていた。「本家」としては、やや肩身が狭い。 〈長岡昇〉
2005年6月12日 朝日新聞の社説「児童労働」
学校に行かず、家族の生活を支えるために働く。そうした児童労働は、先進国ではほとんど見かけなくなった。けれども、アジアやアフリカ、中南米の途上国では農園や工場でいまだに多くの子どもたちが働いている。国際労働機関(ILO)の推計によれば、世界中の15歳未満の子どものうち、1億8600万人が働いている。6人に1人の割合だ。
働く姿を目にすることはなくとも、私たちの身の回りには子どもたちの手で生み出されたものがあふれている。チョコレートはその一つである。原料になるカカオ豆の多くが西アフリカの国々で栽培されている。北海道大学の石弘之教授が新著「子どもたちのアフリカ」(岩波書店)で、カカオ農園の実態を描いている。

チョコレートの原料になるカカオ豆
最大の輸出国コートジボワールでカカオ豆を摘むのは、奴隷として売られてきた少年たちだ。早朝から深夜まで棒で殴られながら働かされている。チョコレートとは、カカオ豆を炒って砂糖と牛乳、それにアフリカの子どもたちの汗と血と涙を加えたもの??地元の人たちは悲しみを込めて、そう言う。
木綿のシャツにも、子どもたちの労苦が織り込まれていることがある。南インドでは、10代前半の少女たちが綿花の授粉と綿摘みをしている。現地で調査にあたった一橋大学の黒崎卓・助教授は「安くて従順な労働力として、雇う側には好都合なのだろう」と見る。
73年に採択されたILO条約で、15歳未満の子どもを働かせることが原則として禁止された。条約を生かすための国際計画が作られ、各国でさまざまな施策が推し進められている。3年前からは、ILOが6月12日を「児童労働反対世界デー」とすることを提唱し、取り組みを強めてきた。
だが、改善の兆しはなかなか見えない。アフリカではエイズが蔓延し、社会の基盤を掘り崩しつつある。アジアには、圧政や腐敗にあえぐ国がある。それぞれの国を土台から立て直さない限り、子供たちを労働から解き放ち、学舎にもどすのは難しい。児童労働がはびこる国々で何が起きているのか。まず、それを知り、私たちに何ができるのかを考えたい。
インドの労働組合は日本のNGO「国際労働財団」の支援を受けて、石切り場で働く子どもたちを学校に通わせる活動を続ける。子どもが働くのを当たり前のように見ていた大人たちの意識が、少しずつだが変わってきた。
国際機関や国、自治体に加えて、NGOの果たす役割はますます重要になってきた。それをしっかりと支えたい。先進国の企業にとっても他人事ではない。児童労働で生まれる原料や製品をなくしていくように努める。そうした姿勢の企業を後押ししたい。
一つひとつは細い糸でも、束ねれば、太くて強い綱になる。
2000年6月3日 朝日新聞夕刊1面

「生きた化石」といわれ、アフリカ南部でしか見つかっていなかった古代魚シーラカンスが3年前、インドネシアのスラウェシ島でも発見された。サンゴがきらめく透明な海。海洋学者は「海面下の断がいにシーラカンスが好む横穴がたくさんある。生息に最適の条件がそろっている」という。経済の低迷にあえぐ地元は「シーラカンスで地域興しを」と夢見ている。
(マナド<インドネシア・スラウェシ島>=長岡昇)
●サメの網に
シーラカンスを最初に捕まえたのは、マナド沖合のマナドトゥア島に住む漁師のマクソン・ハニコさん(38)。1997年9月、サメを取るための底刺し網にかかっていた。
「うろこが硬いのにブヨブヨして、変な魚だった。長いこと漁をしているおやじも『見たことがない』と言っていた」
マナドの魚市場に運んだ。そこに、米カリフォルニア大学バークリー校の海洋学者、マーク・アードマンさん(31)が居合わせた。インドネシアでの研究が一区切りつき、バリ島で結婚式を挙げた。新婚旅行でマナドまで足を延ばし、散歩がてらに市場を訪れたところだったという。「シーラカンスみたいだが、まさか」と思い、写真を撮っただけだった。インドネシア初のシーラカンスは、3万ルピア(約400円)で仲買人に競り落とされた。
●たった100円
マクソンさんと仲間の漁師はその後、同じ魚を2匹捕まえたという。「脂っぽくてまずい」と評判が悪く、3匹目の売値はわずか8000ルピア(約100円)。買い取ったレストランの経営者は「食えそうもないので捨ててしまった」と話した。
米国に戻ったアードマンさんが専門家に写真を見せたところ「シーラカンスに間違いない」との鑑定。アードマンさんは発見場所に近いブナケン島に居を構え、本格的にシーラカンスの研究を始めた。
翌1998年7月、漁師のラメ・ソナタムさん(57)が同じマナドトゥア島沖で、シーラカンスを生きたまま捕まえた。マクソンさん同様、水深100?200メートルでサメ用の底刺し網にかかっていた。ラメさんによると、底刺し網漁を始めたのは1983年から。中華料理に使われるフカヒレが高値で取引されるようになったからだ。
この標本はジャカルタ郊外の研究所に運ばれ、論文が科学誌に掲載された。発見は海外で大きく報じられたが、インドネシアの新聞は地味な記事を載せただけだった。この年、インドネシアではスハルト政権が倒れ、国内は混乱の極みにあった。経済危機も深まるばかり。地元サムラトゥランギ大学のブルヒンポン水産学部長は「研究費を申請したが、まったく認められなかった」と嘆いた。
それでも、大学の研究者や非政府組織(NGO)が中心になって、地域興しの運動を始めた。シーラカンスをあしらったアクセサリーやハンカチが土産品として登場した。NGOの関係者は「政情不安で観光収入は激減した。隣のマルク諸島では宗教抗争がくすぶっている。シーラカンスのある水族館ができれば、足を運んでもらえる」と期待を込める。
「水中遊歩道をつくって、シーラカンスの泳いでいるところを見てもらったらどうか」「人工飼育はできないだろうか」。資金はないが、夢はどんどん広がっている。
●日本が支援
この地域興しを、日本の国際協力事業団が支援している。海洋保全の専門家として環境庁から派遣された和田茂樹さんらが、関係機関を集めて保護検討委員会を立ち上げるなど奔走した。和田さんは「アフリカでは欧米の研究者がシーラカンスを全部持っていって、地元には何も残らなかった。インドネシアでは地元が活用できるように手助けしたい」と話している。
<シーラカンス> 約4億年前の古生代デボン紀に登場し、約7000万年前(中生代白亜紀)に絶滅したと考えられていた原始的な魚。1938年、南アフリカの沖合で発見され、その後、マダガスカル島やコモロ諸島で多数捕獲された。魚から陸生動物への進化の道筋からそれて孤立した特殊な魚と考えられている。硬骨魚類の総鰭(そうき)類に属する。

【写真説明】
シーラカンスを捕まえた漁師のラメさん(右)とマクソンさん。手にしている刺し網にかかった/撮影・長岡昇=北スラウェシ州マナドトゥア島で
98年に発見され、インドネシア科学院の生物研究開発センターに保存されているシーラカンスの標本。一般には公開していない/撮影・長岡昇=ジャカルタ郊外のチビノンで
1993年1月13日付 朝日新聞国際面のコラム「特派員メモ」から
1992年末から始まった宗教暴動がインド中に広がり、世情が騒然としてきたら、1階に住む家主さんが突如、大型犬を飼い始めた。門の前ではもともと、チョキダールと呼ばれる警備員が寝ずの番をしているのだが、「それだけでは心もとない」と考えたようだ。
ところが、この犬がものすごい勢いでほえ続ける。2階に間借りしているわが家にまで、グワングワンと響いて眠れないほどだ。

「おいしいものでも食べれば、落ち着くかも」と思って、ある日の夕方、ベランダからおかずの肉ダンゴを2個投げてみた。わざわざシンガポールまで行って買ってきた上等の豚肉だ。なのに、このワンちゃんはクン、クンと二度ほどにおいをかいだきり、プイと横を向いてしまった。
次の日、家主さんに聞いたら「あの犬も、菜食主義なんです。ミルクとパンと野菜以外は受けつけません」。家主さん一家はジャイナ教徒で、全員が厳格な菜食主義者だ。考えてみれば、肉を食ったりする不埓(ふらち)な犬を飼うはずがなかった。
忠実で仕事熱心だったが、間もなく、この菜食主義犬はお役御免になった。家主さんも、うるさくて眠れなかったらしい。こちらもホッとした。家族からは「貴重な肉を無駄にした」と責められたけれど。
※古い記事なので、冒頭に「1992年末から始まった」と加筆しました。
(ニューデリー・長岡昇)
* * *
※上の写真は、銀座でワインバー「オクシトン」を経営する
小島宏明さんと初枝さんの愛犬クローカ。
彼はベジタリアンではありません。コラムとは直接の関係はありませんが、
愛らしく、また富士山のたたずまいが初春らしいので掲載させていただきました。
* * *
本日「最上川縦断カヌー探訪」
ホームページ公開しました。
全国のカヌー愛好家の集いの場として、
そして
第1回 最上川縦断カヌー探訪を盛り上げる場として、
ご活用いただけたらと思います。
ホームページ公開しました。
全国のカヌー愛好家の集いの場として、
そして
第1回 最上川縦断カヌー探訪を盛り上げる場として、
ご活用いただけたらと思います。
《「ブナの森」の役員》
・代 表 長岡 昇 プロフィールをみる
プロフィールをみる
・事務局長 崔 鍾八(チェ・ジョンパル) プロフィールをみる
プロフィールをみる
・監査役 長岡 典巳
・顧 問 佐竹 久
《「ブナの森」のメンバー》
・遠藤 大輔(だいすけ) フリーランスデザイナー(山形県朝日町在住)
・岸 浩 会社員(福島市在住)
・斉藤 栄司(えいじ) 専業農家 (山形県尾花沢市在住)
・佐竹 久 大江カヌー愛好会会長(山形県大江町在住)
・佐藤 周平 ここりり映像代表(山形市在住)
・白田金之助 白田鉄工所代表(山形県朝日町在住)
・崔 鍾八(ちぇ・じょんぱる)清野りんご園経営(同)
・長岡 昇 元新聞記者(同)
・長岡 典巳 (のりみ) 元朝日町建設水道課長(同)
*顧問弁護士(ボランティア)児玉 譲(東京・銀座、飯沼総合法律事務所所属)
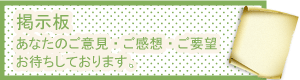
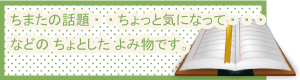
・代 表 長岡 昇
・事務局長 崔 鍾八(チェ・ジョンパル)
・監査役 長岡 典巳
・顧 問 佐竹 久
《「ブナの森」のメンバー》
・遠藤 大輔(だいすけ) フリーランスデザイナー(山形県朝日町在住)
・岸 浩 会社員(福島市在住)
・斉藤 栄司(えいじ) 専業農家 (山形県尾花沢市在住)
・佐竹 久 大江カヌー愛好会会長(山形県大江町在住)
・佐藤 周平 ここりり映像代表(山形市在住)
・白田金之助 白田鉄工所代表(山形県朝日町在住)
・崔 鍾八(ちぇ・じょんぱる)清野りんご園経営(同)
・長岡 昇 元新聞記者(同)
・長岡 典巳 (のりみ) 元朝日町建設水道課長(同)
*顧問弁護士(ボランティア)児玉 譲(東京・銀座、飯沼総合法律事務所所属)
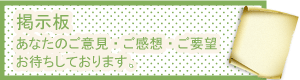
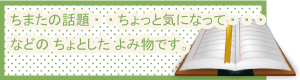
*メールマガジン「おおや通信6」 2009年7月15日
自分が子どものころには聞いたこともなかったのに、やたら多くなった病気の一つがアトピー性皮膚炎です。肌が乾いてささくれ立ち、かゆくてつらそうな病気です。
大谷小学校で生徒の健康状態を調べたところ、22人の1年生のうち、なんと半分の11人がアトピー性皮膚炎と診断されました。全校でも89人のうち21人、4人に1人近くがこの病気でした。ごく軽い症例も含めているとはいえ、これほど多いとは思っていませんでしたので驚きました。
文献を見ても、「アトピーの原因は不明」と書いてあるだけです。遺伝的要因、花粉やダニの影響、有害化学物質説、合成洗剤との関わり、ストレス説などが列挙してあるものの、それぞれについてどう考えるべきかをきちんと書いてあるものが見当たらず、戸惑うばかりでした。
そんな中で、長い間アトピー患者の治療にあたってきた高雄病院(京都市)の江部康二・副院長の講演録は、とても説得力がありました。江部氏は、原因についてはいろいろな仮説があるが、「歴史的に(はっきりしている)たった一つの事実は、高度経済成長以前は(アトピーが)少なかったし、治っておった」ことだ、と指摘しています。そしてこの時期、1960年代から、日本人の食生活が急激に変わり始めたことに言及しています(「完全米飯給食が日本を救う」〈東洋経済新報社〉第3章に講演録)。
身近で採れたものを食べていた日本人の伝統的な食生活は、この時期から激変しました。さまざまな食品が大規模な流通ルートに乗って出回るようになり、インスタント食品も次々に登場しました。それに伴い、食品添加物や防腐剤が大量に使われるようになりました。農薬の大量散布が始まったのもこの時期、合成洗剤が普及し始めたのもこの時期です。
一つひとつは健康にすぐ害があるとは言えないにしても、これらが次々に体内に入り込んだために、人間の自然治癒力では対処しきれなくなり、それが皮膚炎という形で表れたのがアトピーと考えるべきではないか、というのが江部氏の主張です。
従って、高雄病院では食生活の改善や漢方薬の服用、鍼灸を施すといった方法で人間の自然治癒力を高めることを基本的な治療方針にしているとのことです。ステロイド(副腎皮質ホルモン剤)を塗ってかゆみを止めることも患者によっては必要としながらも、ゆっくりと減らしていくという立場です。
アトピーは、単に「皮膚がかゆくてつらい」ということにとどまりません。荒れた肌は、対人関係にマイナスの影響を及ぼし、性的に成長するにつれて自然な異性関係が築かれるはずなのにそれを妨げます。われわれが想像する以上に強烈な影響を及ぼしていると考えます。
毎日、何を食べるのか。それが10年、20年と積み重なった時に体にどういう影響を及ぼすのか。現代科学の力をもってしても、それを解き明かすのは不可能ですが、さまざまな「新しい病気」という形で、われわれの体は警告を発してくれているのではないでしょうか。
(*江部康二氏の肩書は講演録が作られた当時のものです。)